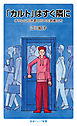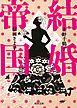検索結果
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-■■■忖度なき提言 高市首相の経済政策■■■ 河野龍太郎×松尾豊×伊藤由希子×唐鎌大輔 インフレ・消費減税・金利上昇……このままでは危ない ◎最強の参与・今井尚哉の解散戦略 赤坂太郎 ◎成田悠輔の聞かれちゃいけない話 12 黒田東彦 いまは金融も財政も引き締める時です ■■■第174回 芥川賞発表■■■ ◎「時の家」鳥山まこと 解体直前の家に三代の住人がよみがえる ◎受賞者インタビュー「人生に建築以外の軸が欲しかった」 ◎「叫び」畠山丑雄 万博から満州へ。暴走する、おかしな男 ◎受賞者インタビュー「牛のように図々しくゆっくり進んでいきたい」 ■■■特集 暴君トランプの新帝国主義――秩序破壊の世界を直視せよ■■■ ◎緊急座談会 冨田浩司×坂口安紀×山下裕貴×峯村健司 ◎世界の終わりへの航海(後編)P・ティール S・ウルフ 『ワンピース』のルフィはキリストだ ◎短期集中連載 日本に戦略的思考はあるか 2 垂秀夫 日米同盟動揺の最悪も想定せよ ■■■特集 没後30年の『この国のかたち』■■■ ◎AI時代に読むべき司馬遼太郎 磯田道史 ◎磯田道史が選んだ珠玉の3篇 「孫文と日本」「戦国の心」「秀吉」 ■■■文藝春秋ゼミナール 大人の作文術■■■ ◎文章は「飛躍」で勝負だ 阿部幸大 ◎「感想文」は全方位的な能力を養う 渡邉雅子 ◎大成建設の天皇、大いに語る 5 森功 柏崎刈羽原発「再稼働工作」の内幕 ◎K‐POPに負けるな―日本の音楽業界は変わるのか 高橋大介 ドンなき後の芸能界 ◎腰痛手術 5泊6日 体験記 山根一眞 数年来の激痛に耐え兼ね、保険適用の手術を受けてみた ◎「やってられない!」久米宏が吠えた日 早河洋 ◎遠藤(元小結)「やり切る、抗う心」を語る 北陣聖大 ◎日本の顔 インタビュー 三宅唱 映画もサッカーも監督の仕事は似ている 【連載】 ◎〔最終回〕裏読み業界地図 大西康之 半導体立国・日本は復活するのか ◎飲食バカ一代! 5 松浦達也 味坊集団 梁宝璋 ◎古風堂々82 藤原正彦 ◎日本人へ269 塩野七生 ◎ベストセラーで見る日本の近現代史150 佐藤優 ◎言霊のもちぐされ17 山田詠美 ◎ディープな地経学9 マット・ポッティンジャー ◎ゴルフ春秋13 ◎地図を持たない旅人23 大栗博司 ◎有働由美子対談86 又吉直樹(芸人・作家)……ほか
-
4.4問題を起こす人を抱え込むことは愛であったはずなのに、なぜ悪化するのだろう。DVやアルコール依存、母娘問題など、家族関係に困ったとき、「共依存」という言葉は解決のためのヒントを与えてくれる。新装版に寄せて田房永子氏が新たに解説を寄稿。
-
3.0
-
4.2
-
4.0オールドメディアはなぜ信用を失ったのか? 追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。 取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。 そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。 さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索する。 選挙、宗教、企業不祥事、そして見落とされる深刻な医療問題「HPVワクチン」騒動の実相など、混乱・錯綜する情報のなかで新聞、テレビの報道が伝えない真実、ネット配信が歪めるいまの社会の病巣を明らかにし、本当に知るべき日本の深層を明らかにする。 (目次より) 第一章 独自の取材手法 第二章 選挙取材と影響力 第三章 カルトと政界の関係を追及 第四章 もうひとつの命題 第五章 メディア出演とトラブルへの対処 第六章 会見取材 第七章 ジャーナリズムとは
-
-始まりは一通の電話からだった。子どもがオウム真理教に入信し、連絡が取れなくなったという親からの連絡を受けた著者は、知り合いの坂本堤弁護士を紹介する。「被害者の会」が結成され、サンデー毎日がオウム批判の連載を開始した直後、坂本さん一家3人が謎の失踪をとげる。そこから、著者とオウムとの長い闘いが始まった──。 教祖である麻原彰晃こと松本智津夫の生い立ちから教団設立に至る道程を追い、閉鎖環境における「神秘体験」で信者を洗脳し、御布施によって財産を奪い取る搾取構造を暴く。地下鉄サリン事件に先立つ4年前、早くもオウムの狂気に警鐘を鳴らした、江川紹子渾身のルポルタージュ第1弾! 「麻原彰晃教祖は教団の目的に「人類救済」を挙げている。もし彼が真実この目標を掲げているのなら、今こそ実践に移してほしい。空念仏ではなく、本当に人びとや地球環境や平和を守るための行動に出てもらいたいと思う。坂本弁護士一家拉致事件への協力もしてほしいと願う。しかし、これまで私が観察してきたかぎり、彼のいう「人類」とは、オウム真理教の信者、つまり自分の支配下の人間にかぎられるようだ。しかも、その信者たちも「救済」の対象というより、支配下の員数にすぎない」 2018年、麻原はじめオウム真理教元幹部13名の死刑執行により、数々の謎は二度と本人たちの口から語られることはなくなった。麻原彰晃とは? オウム真理教とは? 出版局、電子書籍編集部に復刻希望が多数よせられた江川紹子のオウム関連著書を、新たな原稿「反面教師としてのオウム」を加え、電子書籍として完全復刻する。
-
4.3「親にされたようなことを、自分の子どもにはしたくない」と感じている大人たちへ――豊富なカウンセリング経験から導き出された「愛情よりも安心感」の子育て論摂食障害、うつ病、子どものゲーム依存やネット依存、夫のDV、息子の不登校……カウンセラーとして、長年、家族に起きているさまざまな問題に対処してきた著者だからこそ見えた、「子育てでやってはいけないこと」とは?ウェブメディア「現代ビジネス」の大好評連載を書籍化。「叱り方、ほめ方」「お金の与え方」といった子どもへの接し方はもちろん、夫婦関係や祖母との関係、ママ友との関係まで、子育てをめぐるさまざまな人間関係を取り上げながら子どもに対してやってはいけないことを解説。「子どもを伸ばすほめ方とダメにするほめ方はどこが違う?」「子どもにお願いする親はなぜ問題?」「子どもの前で夫婦喧嘩をすると何が起こる?」といった具体例を示すことで、子育てで起こる問題と、対処方法がわかります。多くの人たちが、そのまた親たちから受けた育児態度やしつけ、もっと具体的に言うなら虐待に近い経験を、子どもに対して繰り返したくないと考えています。 幅広い年齢の人たちの語る生育歴、社会的に活躍しているにもかかわらず毎晩悪夢にうなされている人たちの幼いころの記憶などから逆算していくと、「これだけは子どもに対してやってはいけない」行為が浮かび上がります。そして親の立場からはなかなか見えづらい、子どもは何が苦しいか、何がつらいかということがらも見えてきます。 ―――「プロローグ」より
-
4.0愛情の押し売り地獄から、どうにも逃げられない? 臨床歴50年の第一人者が「母親が変わる」という道筋を探す実践バイブル。文庫化に伴い、新章「『DV加害者プログラム』をとおして加害者について考える」を加筆し、山崎孝明氏による解説を新たに追加した。
-
3.0高齢化する母親、娘としての団塊女性。老いることで娘を引き寄せる母に娘はどう備えればいいのか。母娘問題の第一人者による力作。文庫化に伴い、新章「高齢化する母と娘たち」を加筆し、水上文氏による解説を新たに追加した。
-
5.0著者のロングセラーが待望の文庫化。「母の愛」という幻想に傷つけられてきた娘たちが、母娘問題を「解決」することはできるのか。文庫化に伴い、新章「解決方法はあるのか」を加筆し、三宅香帆氏による解説を新たに追加した。
-
-1巻141円 (税込)政治・経済から歌舞伎、恋愛、アートや相対性理論まで、各分野で活躍中の著者28名が「これだけは言っておきたい!」ことをテーマに執筆。 次々新しい出来事が起こっても、時間は地続き。情報の波にのまれそうになったら、これら28個の視点を、前に進むとき、考えるときの指針にしてください。 【収録作品(一部)】 飯田泰之 日本経済にまず“実力通り”の力を発揮させよ 生島淳 東京オリンピックもWCラグビー日本大会もすぐにやってくる 大栗博司 まさか毎日アインシュタインのお世話になるとは 沖田×華 北陸新幹線開通でおとずれた幸せと誤算 開沼博 『福島第一原発廃炉図鑑』が埋める「空白」 國分功一郎 無人島をどう生き延びるか? コグマ部長 仕事始めにテンションの上がる読書案内 今野晴貴 本当に恐ろしい「奨学金」という時限爆弾 坂口孝則 万全のリスク管理は無理だと認める勇気を持とう 佐藤慶一 “分散型”が進むメディア業界ではWebライター/編集者の“身体性”が鍵を握る 辛酸なめ子 印象に残ったフェス10選 鈴木大介 貧困問題をオワコン化するな! 武田砂鉄 2016年に求められるのは、「五郎丸ピケティ」的な語感 中川右介 海老蔵をもっと歌舞伎座に――これにつきる 中田考 難民問題が“先進国”に突きつけたもの 中村淳彦 2015年、介護という社会保障は破綻した 速水健朗 聖子とマッチとハムスターとしての僕たち 久田将義 山口組分裂で抗争勃発?乗じて半グレがのし上がる? 北条かや 上司の方々、『タラレバ娘』にきちんと向き合って下さい。 ※本作品は「幻冬舎plus http://www.gentosha.jp/」で連載した“言っておきたい!!2016”の記事をまとめたものです。
-
4.0「学校に行きたくない」「朝、起きるのがつらい」「いじめにあっているけれど、誰にも相談できない」、 そんな「思い」を抱える子どもがたくさんいます。 学校に関する悩みや思いを抱える子どもたちや、その保護者、かつてそういった経験をしたことのある大人からの声を募集しました。 寄せられた投稿について、 3人の専門家が一緒に考えます。 学校にまつわる悩みに向き合うのは、脳と心の関係について研究・発信を続ける脳科学者の茂木健一郎、 カウンセリングを通して多くの人の声を聞き、人間関係の問題を見つめてきた、原宿カウンセリングセンター所長の信田さよ子、 いじめ問題の解決を目指し、『こども六法』(弘文堂)を制作した山崎聡一郎。 子どもたちや取り巻く大人が、不安や悩みごとをどのように捉え、どのような考え方をすればよいのかをともに考えていきます。 本書のもとになったニコニコ生放送番組『明日、学校へ行きたくない』での座談会に加え、 後日おこなわれた追加取材の内容や、専門家の知見とメッセージが詰まったコラム、 『不登校新聞』石井編集長と山崎聡一郎の対談などを特別収録。 ■目次 はじめに プロローグ漫画 1章 明日、学校へ行きたくない 2章 どこにも居場所がない 3章 将来に希望をもちたい エピローグ漫画 大人の読者に向けて おわりに
-
3.6親による虐待、発達障害、宗教2世、PTSD……多重当事者だからこそ書けた、物語形式によるアダルトチルドレンの回復メソッド。当事者研究、オープンダイアローグ的対話実践で、自分なりのメソッドを発見してください。 依存症、精神疾患、貧困、DVなど、さまざまな事情による機能不全家庭で育った人のために書かれた、回復メソッドの教科書。アダルトチルドレン(AC)の困り事は多様で、一般的な処方箋だけでは対応しきれない。多様な出方をするACの事例にあわせて、当事者自身が回復メソッドを発見する必要がある。それがメタメソッドの考え方。当事者研究とオープンダイアローグ的手法により、数多くの対話型自助グループを主宰する著者の経験知が詰まった、物語形式で語る、アダルトチルドレンの回復指南書。アダルトチルドレン関連の文学・マンガ・映画作品についてのコラムも収録。 【「はじめに」より】 「本書はアダルトチルドレン(機能不全の家庭で育った人)のために書かれています。アダルトチルドレンの困り事は多様ですから、本書では処方箋を並べていくことに合わせて、そのような処方箋を当事者の側から新たに発見する場として「対話型自助グループ」を推奨しています。その意味で本書は「メソッド」の本であると同時に、メソッドを開発するための「メタメソッド」の本でもあります。」 【目次より】 1 アダルトチルドレンに関する基本事項 入口として──ダイキの物語/1−1 心理学的観点から/1−2 医療的観点から/1−3 ふたたび心理学的観点から/出口として──ダイキの物語 2 さまざまな回復モデル 入口として──アヤカの物語/2−1 傷ついた子どもの回復/2−2 トラウマケアの観点から/2−3 対話型自助グループのすすめ/出口として──アヤカの物語 3 当事者研究とオープンダイアローグの実践 入り口として──リョウの物語/3−1 前もって理解しておくこと/3−2 自助グループでの当事者研究/3−3 自助グループでのオープンダイアローグ/出口として──リョウの物語 ☆COLUMN『くるまの娘』(宇佐見りん著)/『イグアナの娘』(萩尾望都作)/『ブラック・スワン』(ダーレン・アロノフスキー監督)/『新世紀エヴァンゲリオン』(庵野秀明監督)/『血の轍』(押見修造作)/『人間失格』(太宰治著)/
-
4.5アディクション臨床における「当事者」とは誰か? 「抵抗とともに転がる」とは何を意味するのか? 「家族の変化の起動点」はどこにあるのか? カウンセラーとクライエントの「共謀」とは何か?――医療モデルと司法モデルの境界線上で、アディクション臨床とともに走りつづける臨床家の思想遍歴と臨床美学を一挙公開! 藤岡淳子との対談を収録したアディクション・アプローチの聖典! ●長いコピー(HPに引用): アディクション臨床における「当事者」とは誰か? 「抵抗とともに転がる」とは何を意味するのか? 「家族の変化の起動点」はどこにあるのか? カウンセラーとクライエントの「共謀」とは何か? アディクション臨床は、その黎明期からつねに医療モデルと司法モデルの境界線上で揺れつづけ、当事者不在のなかで医療の無力化を、依存する当事者に苦しむ家族への支援の無効化を突きつけられてきた。しかし、ドメスティックバイオレンスや児童虐待をも視野に収める逆転の発想は、アディクション臨床における心理職の役割を確立することにもなる。アダルトチルドレン、自助グループ、治療的共同体、被害者臨床を補完する加害者臨床などのコンセプトと実践を取り込む機動力で、アディクション臨床とともに走りつづける臨床家の思想遍歴と臨床美学を一挙公開。 藤岡淳子との初対談を収録したアディクション・アプローチの聖典!
-
4.0内側からの狂信論 宗教、スピリチュアル、自己啓発、マルチ商法、 陰謀論、自然派カルト、ネトウヨ言説… 「真理」を求める人たちを、どうして軽んじられるだろうか――。 宗教2世(エホバの証人2世)として過酷な幼少期を経験し、現在、宗教2世のために自助グループの運営にも尽力する文学研究者の著者が、宗教1世(自らカルト宗教などに入信した人)と宗教2世10名にインタビュー。その証言や、幻想文学、そして自身や自身の母親の経験をもとに、「他人」としてではなく、「当事者」として、また問題に深く関心を持つ味方「共事者」として、「狂信」の内側に迫る。 自己省察を踏まえ回心と逆回心(W.ジェイムズ)を読み解く。 宗教研究・文学研究・回復ケア論の新たなアプローチ。 ――島薗進(宗教学者) 自らがなぜ踏み越えたか、振り返る。 今なお癒えぬ傷をさすって。 当事者たちの渾身の独白集。 ――荻上チキ(評論家)
-
4.0ASD/ADHDの大学教員、コロナ禍を生き、ウクライナ侵攻下のウィーン、アウシュビッツを行く。日常と非日常が交差する、はてなきインナートリップの記録。 10年ぶりにウィーンへ研究旅行に行くべく、羽田空港に赴いた著者を待っていたのは、出国許可がおりないというまさかの措置だった……。発達障害特性を持つ著者が、コロナ禍、ウクライナ侵攻の最中に、数々の苦難を乗り越え日本を出国し、ウィーンの研究者たちと交流し、ダヴォス、ベルリン、そしてアウシュヴィッツを訪問するまでの、めくるめく迷宮めぐりの記録。発達障害者には、日常もまた、非日常的な迷宮である。装丁・川名潤、装画・榎本マリコ。 「障害があるということは、ふだんから被災しながら生きているようなものだ。著名人の誰かがそのような発言をしたと思うのだが、(…)僕はこの言葉に大いに首肯できる。僕たちの日常は、災難だらけなのだから。障害者とは日常的な被災者なのだ。もとから被災していて、それだけでも大変なのに、疫病が流行し、コロナ禍の時代が出現した。(…)精神疾患の当事者がコロナ禍を生き、戦争を身近で感じた日々のちょっとだけ稀有な記録。それが本書の内容だ。」(「はじめに」より) 【目次】 はじめに──大学教員と精神疾患 第一章 コロナ禍時代の日常──京都にて 自助グループを主宰する発達障害者 基本、失敗の人生を生きている 好評を博した『みんな水の中』 「当事者研究」から「当事者批評」へ 研究の快楽 授業について 食べもののこと 「推し」に支えられて生きる 第二章 出国できませんでした──羽田空港での洗礼 いま海外って行けるんだ! 夢見心地の朝 大使館の窓口と格闘する 書類は揃ったぞ! 楽勝コースのはずだった 出国失敗 栗isうまい 第三章 中途半端な時期──ふたたび京都にて 立ちあがれ、オレよ 頭木弘樹讃 続・頭木弘樹讃 まさかの鼻血大出血、出発日前日の不眠 第四章 ウィーンとの合一──かつて帝都だった街で ウィーンを体になじませる 中心街 住居とマスク着用義務 食と障害者モード グリーンパス狂想曲 第五章 学ぶことを通じてのみ──教養体験、研究、外国語 美術とガラクタ 伝統音楽との戯れ 研究生活 「なろう系」としてのオーストリア語学習? 第六章 旅行と戦争──戦時下のアウシュヴィッツ訪問 各地への旅行(一) グラーツ、リンツ、ザルツブルク、インスブルック、クラーゲンフルト、ハルシュタット、メルク 各地への旅行(二) ダヴォスとベルリン 各地への旅行(三) ブラウナウ・アム・イン 各地への旅行(四) アウシュヴィッツ/ビルケナウ 帰国 参考文献
-
3.6
-
3.8絶え間ない緊張が続く、中東イスラーム諸国をとりまく情勢。「イスラーム原理主義」すなわち「過激」「危険思想」というイメージが再生産されるなか、本来は唯一神・アッラーの存在こそが、人間の人間による支配と国家の暴走、対立を食い止める秩序になりうると著者は説く。国境を越えて勢力を拡大する「イスラーム国」への評価も踏まえながら、ムスリムたちの死生観をわかりやすく解説する、必読の一冊。東京大学先端科学技術研究センター准教授・池内恵氏の解説付き。【目次】序章 イスラームとジハード/第一章 イスラーム法とは何か?/第二章 神/第三章 死後の世界/第四章 イスラームは政治である/第五章 カリフ制について考える/終章 「イスラーム国」と真のカリフ制再興/解説――自由主義者の「イスラーム国」論~あるいは中田考「先輩」について 池内 恵
-
3.7イスラームへの無理解と差別に根ざした欧米社会における軋轢。混迷を深める中東情勢。「文明の衝突」への憂慮から、これまで諸宗教や世俗主義者間の対話が様々な所で行なわれてきたが、現状を見る限り「対話」は残念ながら現実の紛争を止める力にはなりえなかった。イスラームと欧米の原理は、もはや「お互いを理解し合い、共約することは不可能である」という前提に立ち、これ以上の犠牲を避け、共存をめざすために「講和」を考える段階に来ているのではないか。中東研究の第一人者とイスラーム学者が、イスラーム法をふまえ、その理路と道筋を世界に先駆けて語り合う。【目次】はじめに 「文明の衝突」を超えるために 内藤正典/序章 世俗主義とイスラームの衝突/第一章 難民/第二章 新覇権主義時代の到来/第三章 講和という方法/第四章 日本がイスラーム世界と向き合うために/補遺 イスラーム法の講和規定について 中田 考/おわりに 西欧の「普遍理念」という偶像の時代の終焉 中田 考
-
-イスラーム教徒(ムスリム)が少ない日本では、その教え自体になじみが薄い。よくわからない一方で、日々の報道を通じ中東の戦争や、欧州のテロ事件、難民といった言葉でイスラームのイメージが形作られています。世界のムスリムの人口が16億人を超えると言われる今、無益な文明の衝突を減らすには、相手のロジックを知り考えることが何よりも大切なはずです。本書は、日本人イスラーム法学者が、「ムハンマド」「スンナ派」など、99のトピックでイスラームの教えと歴史をやさしく概説し、その多様性と共存への可能性へと目を開く一冊です。【目次】序 理解はできないけれども共存するために知っておくべきイスラームのこと/第一章 法の宗教/第二章 イスラームの下の暮らし/第三章 イスラーム人物伝/第四章 イスラームと現代/コラム 近代日本のイスラーム理解1 大川周明/コラム 近代日本のイスラーム理解2 井筒俊彦/あとがき/著者選 イスラームをさらに知るための文献リスト/資料 イスラーム関連年表
-
4.0
-
4.0イスラームは、穏健で寛容で民主的な、平和の宗教か? かたや男性・イスラーム法学者にしてイスラム教徒=中田考。かたや女性・イスラム思想研究者にして非イスラム教徒=飯山陽。ともにイスラームを専門としつつも、立場を異にする二者が交わす、妥協を排した書簡による対話。 IS、トルコ・クルド問題、アフガニスタン中村哲氏殺害、ハラール認証、イラン情勢、コロナ禍の影響……。同じトピックを論じても、これだけ世界の見方が違う。はたして日本人は、イスラームをどれだけ理解しているか? 神の前の自由・平等? 人が獲得した自由・平等? 誰も教えてくれなかった、イスラーム世界の真実をめぐる、火花を散らす対話の記録。 「20年以上前に初めて出会った時から今に至るまで、中田先生は私にとって、全く分かり合うことのできない異質な他者です。中田先生だけでなく、私は日本の中東イスラム研究業界に属する多くの研究者と、ほとんど全く分かり合うことができません。(…)私はこの往復書簡を通して、中田先生と分かり合おうとも、中田先生を説得しようとも全く思いませんでした。私の目的は、ひとつにはもちろん、それぞれのテーマについての分析を提示することですが、もうひとつは中田先生と私の議論が徹頭徹尾嚙み合わないことを読者の方々によくよくご覧いただき、その上で、なぜこうも嚙み合わないのかについての理由を明らかにすることです。」(飯山陽 まえがきより) 「人文社会科学の他の分野と比べても職業的専門家の絶対数が圧倒的に少なくマーケットも小さいイスラーム研究が学問の名に値するものに成長するためには、どんなにレベルが低く誤解と偏見に満ちていようとも、イスラームを理解できない人、理解しようとも思わない人にさえも広く読まれる作品ができるだけ多く生み出され、流通することが不可欠だと私は信じています。(…)本書ができるだけ多くの読者の目に留まり、読者の中からたとえ一握りほどの数であったとしても、本書に書かれたことの背後にある「誰の目も見たことがなく耳が聞いたともなく心に浮かんだこともない」(預言者ムハンマドの言葉)広大で深淵な世界を垣間見、彼らに続こうと志す者たちが現れることを願ってやみません。」(中田考 あとがきより) 【目次】 第一書簡 あるべきイスラーム理解のために 第二書簡 イスラム国をめぐって 第三書簡 トルコ、クルド問題について 第四書簡 タイのイスラーム事情 第五書簡 中村哲氏殺害事件をめぐって 第六書簡 ハラール認証の問題 第七書簡 イラン/アメリカ関係の深層 第八書簡 コロナウイルス禍がもたらしたもの 第九書簡 トルコのコロナ対応をめぐる考察 最終書簡 インシャーアッラー それぞれの結語として
-
4.0「ユダヤ教、キリスト教、イスラームの神は同じ」「戒律を重んじるユダヤ教とイスラームのコミュニティは驚くほど似ている」「千年以上にわたって中東ではユダヤ教、キリスト教がイスラームのルールに則って共存してきた」。なのに、どうして近現代史において衝突が絶えないのか?本書は、日本ではなじみが薄い一神教の基礎知識を思想家内田樹とイスラーム学者中田考がイスラームを主軸に解説。そして、イスラームと国民国家、アメリカ式のグローバリズムの間にある問題を浮き彫りにし、今後の展望を探る。【目次】序 レヴィナシアン・ウチダ、ムスリム中田先生に出会う 内田 樹/第一章 イスラームとは何か?/第二章 一神教の風土/第三章 世俗主義が生んだ怪物/第四章 混迷の中東世界をどう読むか/第五章 カワユイ(^◇^)カリフ道/補遺 中東情勢を理解するための現代史 中田 考/跋 未だ想像もできないものへの憧憬 中田 考
-
4.0なぜキリスト教徒は戦争に強いのか? なぜキリスト教圏とそこから派生した世俗国家が覇権を制しているのか? そして、西欧とイスラームの衝突の思想的な原因はどこにあるのか? 本書は、この大きな「なぜ?」に答えを提示している。西欧思想に通じた社会学者とイスラーム学者による、互いの立場に妥協せずに展開されるスリリングな対話からは、紛争の時代を見通す智慧が見えてくる。一神教とその社会、そして戦争の関係を考察する文明論の決定版。【目次】はじめに 橋爪大三郎/第一章 戦争観の違い イスラームvsキリスト教/第二章 ナショナリズムと戦争/第三章 キリスト教徒はなぜ戦争がうまいのか/第四章 ヨーロッパのシステムは普遍的なのか/第五章 核の脅威と国際社会/第六章 イスラームは国際社会と、どのように調和するのか/第七章 破滅的な核戦争を防ぐ智慧を持てるか/おわりに 中田 考
-
3.5オスマン帝国の終焉から100年 日本は「帝国」の智慧に学べ 紛争と閉塞を生む「国民国家」の限界を超えるために 第1次世界大戦後、西欧列強が「国民国家」を前提とし中東に引いた国境線。それが今なお凄惨な戦争の原因になっている。そのシステムの限界は明白だ。 トルコ共和国建国から100年。それはオスマン帝国崩壊100年を意味する。以来、世俗主義を国是とし、EU入りをめざしたトルコ。だが、エルドアン政権のもと、穏健なイスラーム主義へと回帰し、近隣国の紛争・難民など国境を超える難局に対処してきた。ウクライナ戦争での仲介外交、金融制裁で経済危機に直面しても折れない、したたかな「帝国再生」から日本が学ぶべきこととは? 政治、宗教からサブカルチャーまで。ひろびろとした今後の日本の道筋を構想する。 ◆目次◆ プロローグ 「帝国」をめぐる、新しい物語を探して 内田樹 第1章 現代トルコの戦国時代的智慧に学ぶ 第2章 国民国家を超えたオスマン的文化戦略を考える 第3章 東洋に通じるスーフィズムの精神的土壌 第4章 多極化する世界でイスラームを見つめ直す 第5章 イスラームのリーダーとしてトルコがめざすもの 第6章 日本再生のために今からできること エピローグI トルコに学ぶ新しい帝国日本の転生 中田考 エピローグII 明日もアニメの話がしたい 山本直輝
-
3.8誰もが願う「より健康に、より長く生きたい」という希望。iPS細胞による再生医療をはじめ、出生前診断、遺伝子治療やロボット技術――最新のバイオテクノロジーに根差す現代医療は、その願いを着実に実現しつつあり、「病気や老化を克服する」可能性さえも見えてきた。 ところが、従来不可能であったことが「できてしまう」ようになることで、私たちはこれまで想像もしなかった課題に直面しつつある。それはたとえば、「技術的に可能なら、人工的に人のいのちをつくり出してもよいのか?」「身体の特徴や能力、知性などを親が好きに選んで、子どもをデザインしてもよいのか?」など、今日の倫理観では対処できないようなジレンマだ。そしてそれらは、テクノロジーが発展するほどにますます複雑になっていく。人がただ望むままに進んでいくならば、私たちはやがて「いのちをつくり変える」領域に踏み込んでしまうのではないか。 本書では、バイオテクノロジーがもたらすこのような治療を超えた医療=エンハンスメントの課題と、生命科学と深く結びついた現代、そして未来の社会を生きるための新しい“いのちの倫理”を、読者とともに「哲学的」に考えていく。
-
3.8《目次》 はじめに 斎藤環 Ⅰ 傾聴/境界 【第一信】斎藤環→坂口恭平様 恭平さんの方法論は、「とんでもない」 【第二信】坂口恭平→斎藤環様 死にたい人に死なない方法を伝えているわけではないんです Ⅱ 治療/フィールドワーク 【第三信】斎藤環→坂口恭平様 どのくらい「技法」として意識していますか? 【第四信】坂口恭平→斎藤環様 苦しさや悩みには、一〇種類くらいのパターンしかありません 46 Ⅲ 脆弱さ/柔らかさ 【第五信】斎藤環→坂口恭平様 「活動処方療法」の効果を共同で研究してみたい 【第六信】坂口恭平→斎藤環様 今までの人生の中で一番マシだったことを聞いてみます Ⅳ 自己愛/承認欲求 【第七信】斎藤環→坂口恭平様 相談者とともに欲望を作り出しているようにも見えます 【第八信】坂口恭平→斎藤環様 自分の欲望ってのが、実は一番、どこにもない答えなんですよね Ⅴ 流れ/意欲 【第九信】斎藤環→坂口恭平様 「所有欲」について、どう考えていますか? 【第十信】坂口恭平→斎藤環様 創造するという行為が、至上の愛よりも強い喜びです Ⅵ 悟り/変化 【第十一信】斎藤環→坂口恭平様 恭平さんの境地は、幸福であり究極の自由であるように思います 【第十二信】坂口恭平→斎藤環様 人々もまた幸福のことを知っていると僕は確かに感じています おわりに 坂口恭平
-
3.8
-
5.0暴かれるオウムの犯罪! 麻原彰晃の呪縛から逃れようとする信者、まだマインドコントロール下に置かれている信者……彼らの「罪と罰」を法廷で冷徹にウォッチし続けた執念の記録。江川紹子の「オウム裁判記録」第一弾。 「オウム事件を巡っては、約二百人の信者・元信者が起訴されている。殺人、監禁拉致死、死体損壊、営利略取、小銃や麻薬の密造、爆弾や火炎瓶の使用、運転免許証の偽造、強盗、暴行、窃盗と、罪名も多種多様で、まるで犯罪のデパートのようだ。しかし、起訴されている被告人たちほとんどは、オウムに入るまで犯罪とは全く無縁の人々だった。いわゆるエリートと呼ばれる学歴や職歴の持ち主もかなりいる。彼らもまた、宗教を通して自己の心の研鑚を求めてオウムに集まっていったはずだ。なぜ有為の若者たちが犯罪者になっていったのか、どうして坂本弁護士一家を始めとする多くの人々が命を奪われる結果となったのか、その真相に少しでも近づきたい。そんな思いで、私は今日も法廷に足を運ぶ」 2018年、麻原はじめ元幹部13名の死刑執行により、数々の謎は二度と本人たちの口から語られることはなくなった。麻原彰晃とは? オウム真理教とは? 出版局、電子書籍編集部に復刻希望が多数よせられた江川紹子のオウム関連著書を、新たな原稿「反面教師としてのオウム」を加え電子書籍で完全復刻する。 (目次) 反面教師としてのオウム──電子版刊行に寄せて はじめに 第1章 オウムへの葛藤と闘う信者たち 第2章 裁かれる幹部信者たちの犯罪 第3章 地下鉄サリン事件の真相 第4章 麻原彰晃の妄想を解明する あとがき
-
-坂本弁護士一家殺人事件や地下鉄サリン事件など13にもおよぶ事件の罪に問われた麻原彰晃こと松本智津夫だが、法廷では怒号と不規則発言を繰り返し、証言台の元信者らを脅すとも取れる態度を示し続けた。そんな中、実行犯の証言から、新たな真実が次々と明らかになる。一審だけで257回もの公判が開かれ、延べ522人の証人が法廷に立った。そして2006年、ついに麻原の死刑は確定する──。早川紀代秀、岡崎一明、林郁夫、井上嘉浩など各実行犯の公判を追いかけることで、それぞれの人間像にも迫った、江川紹子のオウム裁判記録第3弾! 「『真実』を解明する場は、裁判所だけではない。報道や評論、小説やドラマなど、様々な分野で、いろいろな立場の人によってオウム事件は取り上げられてきた。司法にすべてを委ねるのではなく、そうしたものを参考に、一人ひとりが、真相を探っていくのが大事なのではないだろうか。本書は、私が私なりに『真実』を求めてきた記録である」 2018年、麻原はじめオウム真理教元幹部13名の死刑執行により、数々の謎は二度と本人たちの口から語られることはなくなった。麻原彰晃とは? オウム真理教とは? 出版局、電子書籍編集部に復刻希望が多数よせられた江川紹子のオウム関連著書を、新たな原稿「反面教師としてのオウム」を加え、電子書籍として完全復刻する。 【目次】 反面教師としてのオウム──電子版刊行に寄せて まえがき 第1章 教団、被害者、そして社会 第2章 坂本弁護士を殺害した者たち 第3章 サリン事件を引き起こした人々 第1部
-
3.0やあ。日本一『萌え』にくわしい精神科医だよ。 月刊ゲームラボの人気時評を書籍化 ゲーム脳、ツンデレ、青少年犯罪、3.11、妹萌え、押しかけ厨、児ポ法、ひきこもり、日常系、男の娘…… おたく愛好家の精神科医が横断する2001~2014 サブカルにも政治にも絶望したら「おたく」しかないじゃないか!? 「何も信じない」けれど「何かを欲望する」ことを可能にするのは「おたく」しかない みんなゲーム脳だった!?/「お兄ちゃん」という魔法/ミヤザキ死すとも腐女子は死せず/ツンデレ美少女の精神分析/秋葉原通り魔事件と非モテ問題/ジブリ祭りとロリコンの倫理/せんせいがモノノフになったら妻はどんな顔をするだろう/『進撃の巨人』はなぜ笑えるのか 他、ゼロ年代おたくクロニクル。
-
-親を亡くした悲しみを抱える子どもたちがその後の人生を歩んでいくためには、その死別体験とどのように向き合えばよいのか。 原著書名の“Never the Same”とは、「〔親の死を経験したあなたは、以前の〕あなたとは違う〔けれども、もうあなたは前に進む準備ができている〕」というニュアンスを意味している。親を亡くした子どもたちは、時間の経過とともにその喪失の悲しみを受け容れて成長していくと言われるが、著者は「子どもは必ずしも親の死を乗り越えてはいない」という。その上で本書では、子どもたちが親の死を無理に受容したり乗り越えたりするのではなく、「親の死の前の〈わたし〉と後の〈わたし〉は同じではない。それでも自ら前に向かって歩みを進めることができる」ように導いていくことを目指している。 アメリカのグリーフケア施設「ダギー・センター」(1982年設立)の責任者を長く務めた著者が、臨床現場での事例を紹介しながら提言する一冊。
-
3.0“世界制覇を公約に掲げて生徒会長に当選した俺の妹が「生徒会長」を「カリフ」に改称した。俺の妹がカリフなわけがない!男性であることは、カリフ有資格者の10条件の一つだ!”超グローバルエリート親子が牛耳るカースト制高校を舞台に、カリフ制再興を唱える天馬愛紗とその双子の兄・垂葉、剣術の達人衣織、理事長の御曹司・無碍、萌え心くすぐる美少女メク、謎の米国エージェント・ナオミなど、一筋縄ではいかないキャラクターたちが繰り広げる、夢と冒険の胸キュン学園ドラマ。はたしてカリフは東方の地・日本に現れるのか?『13歳からの世界征服』で悩める若者たちへのメッセージを発信した著者が、人類を領域国民国家の牢獄から解放するカリフ制の再興を説くべく書いた、前代未聞のカリフ・ライトノベル。天川まなるによる、イスラーム豆地識マンガも収録。
-
-
-
4.2
-
4.1最大の政治団体、家族と国家による暴力。 日々、私たちはそれに抵抗している。 家族は、以心伝心ではなく同床異夢。 DV、虐待、性犯罪。最も身近な「家族」ほど暴力的な存在はない。 イエは「国家のミニチュア」に陥りやすいのだ。その中で、私たちは日々格闘している。いわんや、被害の当事者は闘い続けている。 絶え間ない加害に対し、被害者がとる愛想笑いも自虐も、実はサバイバルを超えたレジスタンスなのだ。 エスケープでもサバイバルでも、レリジエンスでもない。 私たちはレジスタンスとして、加害者に後ろめたさを抱かせる――。 被害を認知することは服従ではなく抵抗だ ■家族は無法地帯である ■愛情交換という暴力 ■家族における暴力の連鎖は権力による抑圧委譲 ■報道では虐待だけが選ばれて強調される ■殴られれば、誰もがDV被害者と自覚するわけではない ■被害者は不幸の比較を犯してしまう ■父のDV目撃が息子をDV加害者に陥らせる ■被害者支援に加害者へのアプローチは必須だ ■彼らの暴力は否定するが人格は尊重する 【目次】 まえがき――母の増殖が止まらない 第一部 家族という政治 第一章 母と息子とナショナリズム 第二章 家族は再生するのか――加害・被害の果てに 第三章 DV支援と虐待支援のハレーション 第四章 面前DVという用語が生んだもの 第五章 「DV」という政治問題 第六章 家族の構造改革 第二部 家族のレジスタンス 第一章 被害者の不幸の比較をどう防ぐか 第二章 加害者と被害者が出会う意味 第三章 加害者アプローチこそ被害者支援 第四章 レジリエンスからレジスタンへ 第五章 心に砦を築きなおす あとがき 主要参考文献一覧
-
-非常事態の水面下で起きていたこととは。未来の危機において起こりうることとは。 パンデミックは、見えなかった、見ないようにしていた問題を明るみにした。 家族で最も弱い立場に置かれた女性たちは、どのように生きのびようとしたのか。 家族問題に長年たずさわる臨床心理士が、その手さぐりと再生の軌跡を見つめた。社会の変化を視野に入れ、危機の時代の家族のありようを鮮烈に描写したエッセイ。 【目次】 まえがき 第1章 KSという暗号 第2章 飛んで行ってしまった心 第3章 うしろ向きであることの意味 第4章 マスクを拒否する母 第5章 親を許せという大合唱 第6章 母への罪悪感はなぜ生まれるのか 第7章 「君を尊重するよ(正しいのはいつも俺だけど)」 第8章 私の体と母の体 第9章 語りつづけることの意味 第10章 むき出しのまま社会と対峙する時代 第11章 慣性の法則と変化の相克 ――一蓮托生を強いられる家族 第12章 現実という名の太巻きをパクっとひと口で食べる あとがき――忘れないために、そして未来のために 主要参考資料一覧 【著者】 信田さよ子 公認心理師、臨床心理士、原宿カウンセリングセンター顧問、日本公認心理師協会会長。1946年生まれ。駒木野病院勤務、嗜癖問題臨床研究所付属原宿相談室室長を経て、1995年原宿カウンセリングセンター設立。アルコール依存症、摂食障害、ひきこもりに悩む人やその家族、DV、児童虐待、性暴力、各種ハラスメントの加害者・被害者へのカウンセリングを行ってきた。著書に『母が重くてたまらない』『さよなら、お母さん』『アダルト・チルドレン』『家族と国家は共謀する』『タフ・ラブ』『共依存』他。
-
4.0悲しみから目を背けようとする社会は、実は生きることを大切にしていない社会なのではないか。共感と支え合いの中で、「悲しみの物語」は「希望の物語」へと変容していく。「グリーフケア」に希望の灯を見出した入江杏の呼びかけに、ノンフィクション作家・柳田邦男、批評家・若松英輔、小説家・星野智幸、臨床心理学者・東畑開人、小説家・平野啓一郎、宗教学者・島薗進が応え、自身の喪失体験や悲しみとの向き合い方などについて語る。悲しみを生きる力に変えていくための珠玉のメッセージ集。 【まえがき――入江杏 より】(抜粋)「世田谷事件」を覚えておられる方はどれほどいらっしゃるだろうか? 未だ解決を見ていないこの事件で、私の二歳年下の妹、宮澤泰子とそのお連れ合いのみきおさん、姪のにいなちゃんと甥の礼くんを含む妹一家四人を喪った。事件解決を願わない日はない。あの事件は私たち家族の運命を変えた。 妹一家が逝ってしまってから6年経った2006年の年末。私は「悲しみ」について思いを馳せる会を「ミシュカの森」と題して開催するようになった。(中略)犯罪や事件と直接関係のない人たちにも、それぞれに意味のある催しにしたい。そしてその思いが、共感と共生に満ちた社会につながっていけばと願ったからだ。それ以来、毎年、事件のあった12月にゲストをお招きして、集いの場を設けている。この活動を継続することができたのは、たくさんの方々との出逢いと支えのおかげだ。本書はこれまでに「ミシュカの森」にご登壇くださった方々の中から、6人の方の講演や寄稿を収録したものである。
-
4.4
-
3.9男女の違いという大テーマに斎藤環が挑む! 男と女はどう違うのか? 「性差」とは一体なんなのか? 人気の精神科医が、社会にはびこるトンデモ仮説を排し、この大テーマをさまざまな角度から分析する。(講談社現代新書)
-
-ビジネスパーソンの必須教養「哲学」「社会学」「宗教学」「西洋美術史」「国際政治学」が一冊でまとめて学べます。仕事ができるビジネスパーソンの教養として、これらを語れるようでなければ世界で通用しません。スティーブ・ジョブス、ビル・ゲイツ、ピーター・ティールなど成功するビジネスマンは皆、リベラル・アーツの素養を身につけています。パーティーに招かれたときの初対面の相手との会話や、取引先との会話でも役立つ一冊。さあ、言葉からにじみ出る教養を身につけましょう。 ※本作品は『大学4年間の哲学が10時間でざっと学べる』(貫 成人・著)、『大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる』(出口 剛司・著)、『大学4年間の宗教学が10時間でざっと学べる』(島薗 進・著)、『大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる』(池上 英洋・著)、『大学4年間の国際政治学が10時間でざっと学べる』(小原 雅博・著)の合本版です。 ※本商品は1冊に全巻を収録した合本形式での配信となります。あらかじめご了承ください。
-
4.1
-
3.7
-
3.2神道1300年の歴史は日本人の必須教養。「神道」研究の第一人者がその起源から解き明かす。ビジネスエリート必読書。 明治以降の近代化で、「国家総動員」の精神的装置となった「神道」。近年、「右傾化」とも言われる流れの中で、「日本会議」に象徴されるような「国家」の装置として「神道」を取り戻そうとする勢力も生まれている。 では、そもそも神道とは何か。 神道は古来より天皇とともにあった。神道は古代におけるその成り立ちより「宗教性」と「国家」を伴い、中心に「天皇」の存在を考えずには語れない。 しかし「神道」および日本の宗教は、その誕生以降「神仏習合」の長い歴史も持っている。いわば土着的なもの、アニミズム的なものに拡張していった。そのうえで神祇信仰が有力だった中世から、近世になると神道が自立していく傾向が目立ち、明治維新期、ついに神道はそのあり方を大きく変えていく。「国家神道」が古代律令制以来、社会にふたたび登場する。神聖天皇崇敬のシステムを社会に埋め込み、戦争へ向かっていく。 近代日本社会の精神文化形成に「神道」がいかに関わったか、現代に連なるテーマをその源流から仔細に論じる。同時に、「国家」と直接結びついた明治以降の「神道」は「異形の形態」であったことを、宗教学の権威で、神道研究の第一人者が明らかにする。
-
3.7
-
-チームで活動しているけど 実はコミュニケーションが苦手な人への処方箋 職場、家庭、サークル、近所づきあいで避けては通れないコミュニケーション。 「うまく意思疎通できない」「認識がすれ違っている」「話がかみ合わない」といった経験はないでしょうか。 この本では「コミュ障のかたまり」を自認する著者(大学教員の横道誠とYouTuberのだいまりこ)が、コミュニケーションの困難さを乗り越えるべくどのようにふるまってきたのかを実体験に即して語りあいます。 ふたりがもっているコミュニケーション困難を乗り越える技法として「言いっぱなし聞きっぱなし」「リフレクティング」「ホワイトボードに板書」などの5つを対話形式で実演しながら紹介します。 さらに「前向きに諦める」「弱さの情報公開」「自由の相互承認」といった、つらさを和らげるティップスも満載です。 コミュニケーションの困難さを自力で克服するのではなく、他者との関係性の中で共に解決していく「他力」の知恵を学べる新しいコミュニケーションスキル本です。 ・はじめてチームリーダーになった人 ・チームメンバーともう少し楽にコミュニケーションしたい人 ・話の輪に入れずに自分が少し浮いているように感じる人 ・コミュニケーションに悩むメンバーを助けたい人 ・ケア現場で活用されている技法に興味がある人 といったような方々にぜひ手にとっていただきたい一冊です。 【目次概要】 第1章 コミュニケーションって大変です――知られざる対話の技法を探る 第2章 相手がまるごとわかるようになる――「やわらかいインタビュー」の技法 第3章 悩みごとが開かれる――「言いっぱなし聞きっぱなし」の技法 第4章 課題と人を切り離す――「ホワイトボードに板書」の技法 第5章 仲間の思考が深まる――「リフレクティング」の技法 第6章 お互いがリスペクトしあえるようになる――「学術研究」の技法 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 全国の家庭に出向き、ひきこもりを外に出す実践を続けてきたタメ塾・工藤定次。診療室で治療に当たってきた精神科医・斎藤環。これまで対立していると見られる二人はこの対談で初めて出会った。そして、それぞれの“哲学”を背景に、ひきこもりの本質、ひきこもりにどう向き合うか、解決するにはどうしたらよいのか、ひきこもりの終わりとは何か、といった、ひきこもりをめぐるさまざまなテーマに対して、10時間以上にわたって激論を交わした徹底討論集。
-
4.0
-
3.31巻1,650円 (税込)「いまの日本の指導者にいる大人たちの中に、君たちの将来の幸福なんて考えている人間はほとんどいません」―内田樹 豪華講師20人が、中高生に向き合いながら、日本の問題点を語り尽くした白熱1800分! この社会の仕組みはいつまで続くのか? わたしたちはどうやって現代を生き抜くべきか? 文学・社会学・歴史・科学・芸術・政治などさまざまな分野から考えます。 豪華講師が、中高生に向き合いながら、日本の問題点を語り尽くしました。 この社会の仕組みはいつまで続くのか? 白熱1800分!
-
3.6〈「心がない」ってどういうこと?〉 ◉「自閉スペクトラム症の当事者はマンガ、小説、アニメ、映画、テレビドラマ、音楽などから〝人の心〟を理解しようとしているのではないか?」 ◉その仮説をもとに、さまざまな生い立ちを抱える当事者7人に、自身も当事者である著者が共感を込めてインタビュー。かれらが夢中になったマンガ、小説、アニメ、映画、テレビドラマ、ポップミュージックは、どのようなものだったのか。 ◉インタビューから見えてくる「それぞれの生きづらさ」。そして〝心〟の不思議が浮かび上がる、当事者の生活史にして昭和平成令和サブカル絵巻。 ********** ▶ぼく自身の人生を振りかえってみると、創作物から学んだことが非常に多いと感じるんだ。それこそ人の心の秘密も、多くを本から学んだ。 ▷自閉スペクトラム症者は非言語的コミュニケーションが不得意だって、よく言われるよね。 ▶実際ぼくは日常生活で人の心がわからなくて困惑し、その秘密をひもとくために文学作品に親しむようになったんだ。それで、ほかの「発達仲間」の場合はどうかなって思ったんだ。 ********** 【目次】 はじめに 序章 第1章 HOTASさん 第2章 まるむしさん 第3章 ナナトエリさん 第4章 ヨシさん 第5章 ぽん子さん 第6章 八坂さん 第7章 リナさん 終章 終章 おわりに **********
-
4.1友達はいないといけないのか。家族はそんなに大事なのか。働かないと負け組なのか。話し下手はダメなのか。「ひきこもり」を専門とする精神科医と、「重度のうつ」をくぐり抜けた歴史学者が、心が楽になる人間関係とコミュニケーションのあり方を提案する。
-
-21世紀の世界に浮上した「宗教と戦争」という難題。 戦後80年の日本で伸長する「右派ポピュリズム」。 私たちは信教の自由と政教分離を本当に自覚してきただろうか。 タイ、イギリス、そして日本。世界の君主制と宗教の関係から、日本がかつて歩んだ戦争への道を繰り返さないために、その実像を解き明かす。 憲法学、政治学、宗教学、思想史など第一線の研究者が結集。 現代日本に、いまだ影響を及ぼす「国家神道」と、「天皇制」の論点とは。 戦後の平和憲法下で「信教の自由」「政教分離」が保障されながらも、しばしば神道儀礼の国家的意義が問われる天皇制を、君主制の歴史という視点から捉え返す。 日本近代のあり方を、イギリスやタイなどとの比較も交え、国際的な視野で読み解く。 【目次】 序 章 近現代の君主制としての天皇制と国家神道(島薗進) 第1章 国家神道と物語論――憲法学の観点から(江藤祥平) 第2章 日本から見たイギリスの王権と宗教(梅川正美) 第3章 君主をめぐる政教関係 タイの事例から(矢野秀武) 第4章 近代の神道における儒教の影響(小島毅) 第5章 宮中祭祀から見た近現代の皇室(原武史) 第6章 天皇崇敬の広まりと軍の宗教性――尊皇の軍人・乃木希典が国家神道にもたらしたもの(島薗進) 第7章 国家神道と政教分離(駒村圭吾) 第8章 戦後立憲主義、東アジア王権と国家神道(松平徳仁) 付 章 鼎談「国家神道と政教分離」(島薗邁・駒村圭吾・松平徳仁)
-
-1巻330円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 (目次より) ●〔対談〕暴走する心のメカニズム ネガティブ感情はどこから来てどこへ行くのか 中野信子×木原祐健 ●人に迷惑をかけたくない…… 都市に沈みゆく声なき孤立者たち 石田光規 ●〔対談〕格差拡大、少子高齢化、巨額の財政赤字 分断と貧困が進む日本社会「三重苦」からの打開策は? 湯浅 誠×田中拓道 ●孤独・孤立対策担当大臣に聞く 喫緊の課題に、大胆に対応する 坂本哲志 ●関心競う経済に振り回されるメディアと私たち 「非実在型炎上」は何を示すのか 鳥海不二夫 ●「キャンセル」が飛び交う不寛容な国・アメリカ フランシス・フクヤマ/聞き手:会田弘継 ●犯人は「一人で死ね」ばいいのか? 暴発型事件の背後に横たわるもの 磯部 涼 ●〔対談〕ひきこもると意欲が低下する 「コロナうつ」と「欲望」の関係 斎藤 環×佐藤 優
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 宗教に馴染みの薄い日本の子どもたちが、宗教を中心に生きる世界の人たちと仲良くできるよう、宗教と生活との関わりをわかりやすく解説。 世界各国の人たちと交流をするときに宗教の知識が必ず役に立ちます! ---------------------------------- 宗教を知れば 世界の人たちのことがわかる! ---------------------------------- クリスマスがイエス・キリストの誕生を祝う、宗教的なお祭りであることは知っていますか。キリスト教にはもうひとつ、復活祭という大事なお祭りがあるのですが、こちらの意味を知っている人は少ないと思います。 イスラム教徒をムスリムといいますが、大勢のムスリムがサウジアラビアのメッカに巡礼に行くことは知っていますか。世界各地のイスラム教徒が多い地域にはモスクがあります。モスクで皆が礼拝をするときに向くのは、メッカがある方角です。では、メッカとはどのような場所なのでしょう。 この本では、世界の宗教のあらましを紹介しています。仏教、キリスト教、イスラム教が世界の三大宗教ですが、それだけでなく、ヒンドゥー教、ユダヤ教、神道、シク教、ゾロアスター教などにもふれています。もちろん、全部を紹介するのは無理ですが、主なものは取り上げています。 自分たちの生活のなかに、宗教と似かよったものがないかどうか考えてみてください。手を合わせる、頭を下げる、「いただきます」と言う。これらは、宗教とつながりがあるふるまいではないでしょうか。 かんたんに答えられない、たくさんの疑問がわいてくるかもしれません。でも、それが「世界の宗教を学ぶ」ことから得られるよい結果なのです。無関心ではなく、わかりたい、わかろうとする気持ちを持っていただけることを願っています。 ※本書の売上げの一部は「一般社団法人こども食堂支援機構」を通じて全国のこども食堂支援に使われます。 【もくじ】 はじめに:宗教を知れば世界の人たちのことがわかる 第1章:知らないようで知っている「宗教」のこと 第2章:日本と東アジアの宗教 第3章:いろいろな世界の宗教 第4章:宗教によって違うくらしの習慣
-
4.0現代社会の必須知識「統一教会問題」。日韓関係、宗教史、宗教と政治、人権問題と不法行為等、各分野の第一人者が解きほぐす決定版。 安倍元首相殺害事件に端を発し、旧統一教会の人権侵害と不法行為が露わになり、それを支えてきた政治家たちとの関係が問われるようになった。 多くの事実関係が明らかになっているが、このような事態が生じるに至った歴史的経過については必ずしも十分に示されてきたとは言えない。 とりわけ宗教史的な文脈のなかで統一教会の特徴、また統一教会をめぐる宗教と政治の歪な関係について問うことは十分になされていない。 いかにしてこれだけの人権侵害と悪しき「政治と宗教」の関係が生じるに至ったのか。 本書では、日々報道がなされている「旧統一教会」問題を現代社会の必須知識ととらえ、これまでの経緯とともに体系的に捉え、各分野の第一人者が歴史的・国際的文脈から多角的に論じる。
-
4.0コロナ禍という人類史上希な病理下において、人々の精神を支えるものはなにか? 人と人とが会うことが制限される状況下で、我々はどう振る舞うべきなのか? ひきこもり問題、オープンダイアローグの第一人者が綴る、コロナ禍を生き延びるためのサバイバル指南書。 感染症をキリスト教の〈原罪〉になぞらえて自粛風潮の危うさを訴えた「コロナ・ピューリタニズムの懸念」、災厄の記憶が失われていくメカニズムをトラウマ理論に結びつけて分析した「失われた『環状島』」、対面の場から生まれる根源的な暴力性を問う「人は人と出会うべきなのか」など、ネット上で大反響だったコロナ関連の論考を集大成。コロナ禍という未知の時代を生きていかなければならない我々のヒントとなる、貴重な論考集。 私は、コロナ禍がそれほど社会や人間を変えるとは思っていない。(…)おそらくコロナ禍が過ぎてしまえば、社会が驚くほど変わっていないことに人々は気付かされるだろう。(…)私が注意を向けているのは、ふだん「日常という幻想」が覆い隠しているさまざまな過程や構造が可視化される場面だ。「親密さとは何か」「不潔とはどういうことか」「人の時間意識を構成しているものは何か」「社会はどのように災厄を記憶するのか」そして「対面(臨場性)はなぜ求められるのか」。いずれもコロナ禍でなければ問われることのなかった問いばかりだ。(「あとがき」より) 【目次】 はじめに 1.〝感染〟した時間 コロナ・ピューリタニズムの懸念 失われた「環状島」 〝感染〟した時間 人は人と出会うべきなのか 会うこと、集うことの憂欝と悦び 2.コロナ・クロニクル 「医療」に何が起こったか 第3波の襲来とワクチンへの期待 コロナ・アンビバレンスとメディア コロナ禍のメンタルヘルス リモート診療の実態とリモート対話実践プログラム(RDP) リモート教育は「暴力」からの解放である コロナ禍で試される民主主義 3.健やかにひきこもるために 健やかにひきこもるために リアリティショーは「現代の剣闘士試合」か 「マイルドな優生思想」が蔓延る日本に「安楽死」は100年早い 「鬼滅の刃」の謎─あるいは超越論的炭治郎 「意思疎通できない殺人鬼」はどこにいるのか? 亡き王女(猫)のための当事者研究 あとがき カバー画像:《同じ月を見た日》 コロナ禍に孤立感を抱えている、ひきこもりを含む様々な事情を持った国内外の人々が参加するアートプロジェクト。各々の場所から月の撮影を行い、ここに居ない誰かを想像する。 企画:渡辺 篤 撮影:「アイムヒア プロジェクト」メンバー約50名 画像配置協力:紅、田中志遠
-
3.41巻850円 (税込)日本の未来はどうなるか――? 養老孟司 ユヴァル・ノア・ハラリ ジャレド・ダイアモンド 福岡伸一 ブレイディみかこ 角幡唯介 東畑開人etc. 22人の論客が示すアフターコロナの針路!朝日新聞大反響連載を書籍化新型コロナウイルスは瞬く間に地球上に広まり多くの命と日常を奪った。すべての人に平等に降りかかるこの感染症によって、社会は様変わりしてしまった。第2波の懸念も高まり、感染への恐怖が消えない中、私たちは大きく変容する世界をどう捉え、どのように考えればよいのか。現代の知性たちのパースペクティブを通し「コロナ後」を思考する糧を届ける。
-
4.3「ダメ、ゼッタイ」に代わる、有効な手立てはありうるのか? 依存は回復の始まり。 やめればいいってものじゃない!? 連載時から当事者、当事者家族、支援者・専門家を騒然とさせた 不良患者×不良医師による画期的な往復書簡がついに書籍化――。 現代人にとって最も身近な「病」である依存症――非合法のドラッグやアルコール、ギャンブルに限らず、市販薬・処方箋薬、カフェイン、ゲーム、スマホ、セックス、買い物、はたまた仕事や勉強など、その対象は多岐にわたる。 そんななか最も身近な依存物質であるアルコール依存症の治療中で、数多くの自助グループを運営する文学研究者・横道誠と、「絶対にタバコをやめるつもりはない」と豪語するニコチン依存症で、依存症治療を専門とする精神科医・松本俊彦の、一筋縄ではいかない往復書簡が始まった。最小単位、たったふたりから始まる自助グループ。 依存症の裏側にある、さらにその深淵へ! 特別鼎談「ギャンブル依存症問題を考える(ゲスト:田中紀子)」も収録。
-
3.6
-
-
-
4.1
-
4.7有史以来、無数の宗教が生まれ、そして消滅していった。そのそれぞれが独自の信条、儀礼、神話をもっていた。アフリカの狩猟民族の神話、アイヌのアニミズムやヨーロッパのシャーマニズム信仰、オーストラリアのアボリジニの神話、古代文明における宗教的儀礼もとりあげる。さらに、世界最古の宗教のひとつとされるゾロアスター教、道教・儒教などの中国の思想、日本の神道についても、図解入りでわかりやすく解説。 「五大宗教」と言われるヒンドゥー教、仏教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教については、それぞれ30~40ページにわたって詳しく解説。その起源から歴史、教義や儀礼・慣習について、教典や宗教者の言葉の引用を交えながら紹介する。いま世界で起きているさまざまな対立についての理解を助け、これから何をするべきかを考える指針を与えてくれる。 「近代・現代の宗教」「その他の宗教・宗派」「日本の新宗教」などのページで、シク教やサンテリア、モルモン教、バハーイー教、天理教、エホバの証人、ラスタファリ、統一教会、ハレー・クリシュナ、創価学会、金光教、大本といった新宗教についても触れる。世界の諸宗教について、一般の読者に向けてまんべんなく記述した、便利なガイドブックの決定版。
-
4.3西側の「色めがね」を外して現実を見よ! ここまで現実がよくわかる世界情勢の本は誰にもかけない。 プーチンの言い分が聞こえてくる恐ろしい本だ。 ―橋爪大三郎(東京工業大学名誉教授・社会学者) 「現世の話」「世俗社会」の常識は、ロシアに全く当てはまらない─。 ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、注目される世界情勢。 政治、軍事、経済、地理といった様々なレイヤーが複雑に絡み合う現実を、一般に考えられる要因だけでなく、文明・宗教を含めた多層的な観点で理解しよう、というのが本書の目的です。 西欧型の「植民地帝国」や「国民国家」を主とする従来の地政学ではなく、「宗教を基盤とする文明の中核を為す帝国」を主とする、「宗教地政学の視座」でロシア・ウクライナ情勢、世界変動の分析を試みる一冊! 【目次】 序章 宗教地政学から読み解くロシア原論 第一章 ロシアとはいったいどんな国なのか 第二章 ロシア正教会とは 第三章 宗教から見たロシアのウクライナ侵攻 第四章 世界はどのように変化するか 終章 ロシアとトルコの500年の戦いから見たロシアのウクライナ侵攻
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●〔鼎談〕日本人は何を宗教に求めているのか グリーフケア・科学・スピリチュアル 島薗 進×大谷栄一×岡本亮輔 ●宗教2世問題とは何か 当事者の立場と、研究者としての立場から 横道 誠 ●仏教・キリスト教・イスラム教 三大宗教の死生観 現代の「疎外」と古典世界への「郷愁」 中村圭志 ●御先祖様と日本人 近現代史から見た墓と弔い 問芝志保
-
3.3日本の宗教研究の第一人者が、宗教という営みの“核心”を明らかにする! アンデルセンや宮沢賢治の物語をはじめ、文学や芸術における「救い」というテーマは、昔も今も人の心を打つ。この「救い」の教えは、キリスト教、仏教、イスラームなど世界中の宗教において教義の中心となってきた(そのような宗教を「救済宗教」と言う)。なぜ、宗教では「救い」が重要とされ、普遍的な教えとなってきたのか。 一方で、先進国、特に日本では、宗教への信頼が揺らいでいる。しかし、そんな現代社会においても、従来とは形を変えながら求められる“宗教性”があるのではないか。 宗教の起源から現在にまで通じるこのような問いに、救済宗教と文明の歴史をたどることで理解と考えを深め、宗教という営みそのものの核心に迫る。 【内容】 第1章 信仰を求めない「救い」――文芸が表現する救済宗教的なもの 第2章 「救い」に導かれた人類社会――歴史のなかの救済宗教 第3章 なぜ「救い」なのか――文明史に救済宗教を位置づける 第4章 「救い」のゆくえ――「救済宗教以後」を問う
-
4.2
-
4.1ほんとうに新しいものは、いつも思いがけないところからやってくる! 仕事、結婚、家族、教育、福祉、共同体、宗教……私たちをとりまく「あたりまえ」を刷新する、新しくも懐かしい生活実践の提案。 しょぼい起業でまっとうな資本主義を再生/もののはずみで家族になる/国家が掲げる大義名分より仲間が大事/欲しいものがあればまずそれを他人に与えるところから/話はどんどん複雑にする/お金は「思いがけない使い道」に……。 世界を変えるには、まず自分の生活を変えること。熟達の武道家から若き起業家へ、世代間の隔絶を越えて渡す「生き方革命」のバトン。 何か「新しいけれど、懐かしいもの」が思いがけないところから登場してくる。それを見て、僕たちは、日本人がまったく創造性を失ったわけではないし、才能が枯渇したわけでもないと知って、ほっとする。きっとそういうことがこれから起きる。もうすぐ起きる。それが「どこ」から始まるのかは予想できないけれど、もうすぐ起きる。そういう予感が僕にはします。えらてんさんとの出会いは僕にとってそのような徴候の一つでした。 (内田樹 まえがきより) 【目次】 1章 全共闘、マルクス、そして身体 2章 しょぼいビジネス、まっとうな資本主義 3章 共同体のあたらしいあり方 4章 教育、福祉制度を考える 5章 先祖と宗教とユーチューバー 6章 日本とアジアのあるべき未来
-
4.0
-
4.5
-
4.1
-
-1巻880円 (税込)【WedgeONLINE PREMIUM】 事件・事故で振り返る平成全史 令和を生きるために知りたいこと【特別版】 月刊誌『Wedge』で2024年 5月号(4月20日発売)2024年6月号(5月20日発売)と、2号に渡って特集した「平成全史 令和の日本再生へ 今こそ知りたい平成全史」から、平成に起こった事件、事故に関する記事を集めた特別版です。 月刊誌『Wedge』の創刊は、時代が昭和から平成となった直後の1989年4月20日である。平成時代は、阪神淡路大震災と東日本大震災という「二つの震災」やオウム真理教による地下鉄サリン事件や秋葉原での通り魔事件などさまざまな出来事が発生し、日本社会における課題を表出させた。人々の記憶から忘れ去られないようにするには、正確な「記録」が必要だ。創刊35周年という節目で2号に渡る特集の中から、平成の事件・事故に関する記事を厳選した。 年表(前半) 年表と写真で振り返る 平成前期の日本と世界 年表(前半) 編集部が取材・撮影した写真で振り返る平成(後半)と令和 Part 1 「平成」を利用したオウム真理教 カルトは今もあなたの隣に(江川紹子 ジャーナリスト) Part 2 阪神大震災で進化した警察〝未災者〟の国民にできること(西岡研介 ノンフィクションライター) Part 3 正念場を迎える福島の復興 「巨大な実験場」で終わらせるな(開沼 博 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 准教授) Part 4 消えない東電の責任 1Fの今が私たちに問いかけること(Wedge編集部) Interview 1 平成の「重さ」を取り払い なりたい自分になれる社会へ(安藤優子 キャスター、ジャーナリスト) Part 5 増える不登校、変容するいじめ 対応策の〝アップデート〟を(石井光太 ノンフィクション作家) Part 6 減る暴力団、増える半グレ 不都合な真実にも目を向けよ(溝口 敦 ノンフィクション作家、ジャーナリスト) Part 7 「食の平成史」から考える 食べものの価値と商道徳のあり方 鼎談(丸岡 守 まるおか 会長 ×島村菜津 ノンフィクション作家 ×笹井清範 商い未来研究所 代表) Part 8 衰退する夜の銀座 裏面にある女性たちの「性」の自己管理(溝口 敦 ノンフィクション作家、ジャーナリスト) Part 9 平成を映すノンフィクション 私が選ぶとっておきの3冊(稲泉 連 ノンフィクション作家) Part 10 事件史で振り返る平成 「虚」から「実」への転換を 対談(與那覇 潤 評論家× 石井妙子 ノンフィクション作家)
-
4.3「自分には生きている価値がない」「ブサイクだから異性にモテない」。 極端な言葉で、自分を傷つける人が増えている。 「自分が嫌い」をこじらせてしまった人たちの、自傷行為のように見える言動。 その深層心理にひきこもり専門医である精神科医が迫る。 誰にでも何歳からでも起こり、一度おちいると出られない、徹底的な自己否定。 「ダメな自分」の思い込みを見つめ直し、健全な自己愛を取り戻す方法を探る。
-
-
-
2.0保守のコスプレ。“売国政治”の正体! 自民党の「劣化」が止まらない――。 国際競争力の低下、“反日カルト”との蜜月、いまだに迷走を続けるコロナ対策、上がらない賃金と物価高、少子高齢化に格差拡大……とあまりの無策ぶりに、多くの国民は怒りを通り越して絶望するばかりだ。 公正な自由選挙制度の下、この国ではなぜか、自民党がほぼ常に第一党となって揺るがない。 それはどうしてなのか? 彼らはいずこで日本の舵取りを誤ったのか? その「失敗の本質」に迫るべく、10人の識者を直撃した。 〇統一教会に票乞いするハレンチ 〇「グロテスクな親米派」の跋扈 〇農業消滅で「飢えるニッポン」 〇派閥=選挙互助会の体たらく 〇“情と空気”に流される防衛政策 【目次】●第一章 “空気”という妖怪に支配される防衛政策 石破 茂(自民党・衆議院議員) ●第二章 反日カルトと自民党、銃弾が撃ち抜いた半世紀の蜜月 鈴木エイト(ジャーナリスト) ●第三章 理念なき「対米従属」で権力にしがみついてきた自民党 白井聡(政治学者・京都精華大学准教授) ●第四章 永田町を跋扈する「質の悪い右翼もどき」たち 古谷経衡(作家) ●第五章 “野望”実現のために暴走し続けたアベノミクスの大罪 浜 矩子(経済学者) ●第六章 「デジタル後進国」脱却を阻む、政治家のアナログ思考 野口悠紀雄(経済学者) ●第七章 食の安全保障を完全無視の日本は「真っ先に飢える」 鈴木宣弘(経済学者・東京大学大学院農学生命科学研究科教授) ●第八章 自民党における派閥は今や“選挙互助会”に 井上寿一(歴史学者・学習院大学教授) ●第九章 小泉・竹中「新自由主義」の“罪と罰” 亀井静香(元自民党政調会長) ●特別寄稿 自民党ラジカル化計画―― 一党優位をコミューン国家へ 浅羽通明(古本ブローカー)
-
4.0総選挙で過半数割れの大惨敗! 「1強時代」がついに終焉! 自民党政治を「総括」する時が来た―― いったい誰のために「政治」はなされていたのか? もはや言い尽くされた感のある自民党による「国民不在」の政治と政策。この30年間、実質賃金が上がらないなかで国民の税負担、社会保障費負担はなぜ増加し続けたのか。なぜ巨額の利益を上げる企業に課される法人税は上がらないのか。なぜ億を超える資産を持つ富裕層は税制優遇されるのか。なぜマイナンバーカードの取得が実質的に義務化されるのか。なぜ選択的夫婦別姓制度は導入されないのか――。 宗教団体、大企業、富裕層、アメリカ、財務省、ネット右翼…… 利権と忖度で自縄自縛となった“保守政党”の正体とは?
-
4.6安倍元首相と教団、本当の関係。 メディアが統一教会と政治家の関係をタブーとするなか、教団と政治家の圧力に屈せずただひとり、問題を追及しつづけてきたジャーナリストがすべてを記録した衝撃レポート、緊急刊行! 〈事件の10か月前、この宗教団体のフロント機関が主催するオンライン集会に予め撮影したビデオメッセージでリモート登壇した安倍は基調演説の中で、教団の最高権力者への賛辞を述べていた。全世界へ配信された安倍の基調演説を見た山上は犯行を決意。この“動機”は山上の思い込みなのか、それとも一定以上の確度をもって裏付けられるものなのか。その検証は第2次安倍政権発足後、9年間、3000日以上にわたって自民党とこの宗教団体の関係性を追ってきた私だけがなし得るものだった。日本の憲政史上最も長い期間、内閣総理大臣を務めた安倍が殺害されるに至った道程を記す。〉(プロローグより) (底本 2022年9月発売作品)
-
3.9「中田先生、なぜ人を殺してはいけないのですか?」「人を殺していけない根拠などありません」壊れた社会を生きていく上で、私たちが本当に知っておくべきこと。 「中田先生、なぜ人を殺してはいけないのですか?」「人を殺していけない根拠などありません」子どもたちの抱える普遍的な悩みにイスラーム学者が答えたらこうなった。壊れた社会を生きていく上で、私たちが本当に知っておくべきこと。 【目次】 1.なぜ人を殺してはいけないのですか——人生の悩み なぜ人を殺してはいけないのですか? 普通の人間は、人を殺したりものを盗んだりしたいと思いません。それはなぜですか? なぜ自殺をしてはいけないのですか? 他 2.いじめられています——人間関係の悩み いじめる相手を殺したいほど憎い。 いじめられていますが、自分は非力なので抵抗できません。 学校に行けばいじめられるし、家にいると親にいろいろ言われます。 他 3.なぜ勉強しなくてはいけないのですか——勉強の悩み 勉強に集中できず、将来が不安です。 受験を控えているのに勉強についていけません。 なんで勉強しているのか、いくら考えてもわかりません。 他 4.夢が持てません——世界征服のススメ 夢も目標もどうやって持てばいいのかわかりません。 世界征服、具体的にどういう世界を目指せばいいんでしょう? 家出したいと考えています。 他 5.好きな人に告白できません——恋愛の悩み モテたいのですが、どうすればいいのでしょう。 容姿にコンプレックスがあります。 他 6.人は死んだ後どうなるのですか——その他の悩み やりたいことが見つかりません。 なんのために働くのかわかりません。 他 【著者】 中田考 イスラーム法学者。1960年生まれ。灘中学校、灘高等学校卒業。早稲田大学政治経済学部中退。東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。カイロ大学大学院文学部哲学科博士課程修了(Ph.D)。1983年にイスラーム入信、ムスリム名ハサン。現職は同志社大学一神教学際研究センター客員フェロー。
-
4.2在家の知恵者たちが仏の前に集結! 厳格な教えを強いる一神教とはちがい、仏教はなんでもござれの世界。どのような思想信条をもつ者に対しても、門戸が開かれ、不届き者の声にも耳を傾けてくれるありがたい宗教。そのような仏様の教えを体現し、どんな相手からもよいお話を引き出せる座談の名人・釈徹宗先生がホストとなった対談集。スポーツ、アート、文学、教育、将棋、人工知能、生命科学などの世界の第一線で活躍する著名人たちとの妥協なき16の語らいを収録。 目次 まえがき――釈徹宗 1 色即是空 打たれてもめげない「直球勝負」が大事です。――羽生善治 何かを諦めたほうが、手に入るものがある。――為末大 「物語」の力をいま取り戻せ。――いとうせいこう 「依存先」が多いほど、人は自立できる。――熊谷晋一郎 2 輪廻転生 この世界にあふれる「問題」は、互いにつながっているのです。――国谷裕子 「日本語」は人の心を優しく開かせる言葉です。――黒川伊保子 「家族」と「共同体」のために生きる。それが人生をもつということ。――山極壽一 人間の「非合理」を知っている。それが宗教の底力だ。――佐藤優 3 四苦八苦 老いも死も、万能解決策は「受け入れること」。――久坂部羊 生命の仕組みを知れば、「操作の時代」も怖くない。――仲野徹 「ヘンな日本画」には日本人の秘密がある。――山口晃 「できる」と信じれば、人は何歳からでも伸びる。――坪田信貴 4 如実知見 人間の注ぐ親鸞のまなざしを、インドの月光に見たのです。――高史明 小説が描けるものは、「断片」の中の真理なのです。――小川洋子 現代人にとっての幸福は、「集中」にヒントがある。――石川善樹 演劇や芸術には「人を育てる力」がある。――平田オリザ
-
-生命エネルギーの奔流が激突するところ、 「性愛」と「暴力」が鮮やかに描かれる。 日本における神話研究の最前線を斬新な観点から 平易に伝える<シリーズ神話叢書>、待望の第一弾! 神話が人間の本質に関わる物語であるとしたら、 性愛と暴力ほど人間が人間である所以に深く関わるテーマはないのではないだろうか。 古今東西、性愛の喜びと悲しみの詩や暴力や死に立ち向かう英雄譚は人々を魅了し続けている。 暴力の神話については「メドゥーサ」から南米の「インカリ神話」まで 性愛の神話については「お菊」譚から「ドゴン神話」まで、 互いが重なりあって存在している情景を丹念な調査と研究から明らかにする。 【目次】 1:南郷晃子「花の名を持つ女:むごく殺されるお菊、お花をめぐって」(日本) 2:斧原孝守「暴虐の巨神と原初夫婦神:中国の古典神話と民間神話の世界から」(中国) 3:川村悠人「手足で待ちかまえる女根たちと征服する男根たち」(インド) 4:石川巌「ギムポ・ニャクチクの花嫁:古代チベット土着宗教儀礼説話への招待」(チベット) 5:内海敦子「インドネシアの神話:秘するべき男女の愛、愛すべきものへの暴力」(インドネシア) 6:深谷雅嗣「『ホルスとセトの争い』:同性愛と暴力」(エジプト) 7:松村一男「メドゥーサはなぜペルセウスに殺されねばならなかったのか?」(ギリシャ) 8:横道誠「グリム兄弟の仕事:ゲルマン神話とドイツの昔話の暴力と性愛に関して」(ゲルマン) 9:木村武史「双子の妹を求めるオゴの性愛の罪を贖う供犠と再生による世界創造:マリ、ドゴン神話より」(アフリカ) 10:谷口智子「ラテンアメリカにおけるエロスと暴力:征服のトラウマとしてのインカリ神話と民衆劇」(ラテンアメリカ) 11:木村武史「ヴァギナ・デンタータとココペリ:豊穣・幸福と恐怖・病・暴力」(北米)
-
-
-
4.0
-
3.3
-
4.0移民、難民、驚異の人口増加率で2030年、22億人に なぜイスラーム教徒だけが増え続けるのか? 近代以降、世界は先進国のキリスト教文化圏の価値観で回ってきた。それが今、資本主義システムへの不信感と共に、根底から揺らいでいる。実際、ヨーロッパではクリスチャンの教会離れが深刻化し、キリスト教は衰退の兆しを見せている。そこに、ムスリムの人口増加、移民・難民流出問題が加わり、イスラームは相対的にその存在感を増している。テロや紛争、移民の労働問題に苦悩しつつも、先進国がイスラームに魅せられる理由は何か。比較宗教学の島田裕巳が、世界屈指のイスラーム学者かつムスリムの中田考と激論。日本人だけが知らないイスラームの真実と未来とは。 「Yes, イスラーム!」 世界はキリスト教の嘘と欺瞞に、もうウンザリ ■ 雪崩を打ったように欧州へ押しかけるシリア他からのムスリム移民・難民 ■ 移民に対して不満が募る一方で、ドイツ、イギリス、北欧では、教会税を払いたくないと教会を離れる人が続出 ■ イギリスでは、日曜日に教会へ通うキリスト教徒は1割以下に ■ 人手不足で、ムスリム移民労働者に頼りつつある欧米諸国 ■ ムスリムになるには「アッラー(神)以外のものに従わない」と誓うだけでいいという意外な手軽さ ■ イスラーム女性との結婚で、改宗・入信する男性が増加 ■ イスラームの魅力は、「合理的」「嘘がない」「上下関係がない」
-
4.3
-
-021年7月初めから急速に患者が拡大し、9月まで続いた新型コロナウイルスの感染拡大第5波は、それまでにない激流となって各地に押し寄せた。重症化する患者が相次ぎ、入院が必要なのに在宅での療養をよぎなくされる患者も激増。入院できないまま自宅で死亡する例も出た。もはや「医療逼迫」を超えて「医療崩壊」と言わざるをえない惨状を呈した。 東京都では、8月12日~9月14日の間、都の基準による重症者数が連日200人を超え、8月28日には過去最高の297人に達した。重症者用の病床使用率は、9月1日に96.9%となった。 救急車を呼んでも、搬送先がなかなか見つからず、長時間患者が車内で待たされるケースも増加した。救急隊が「医療機関への受入れ照会」を4回以上おこない、「現場滞在時間」30分以上に及んだ「救急搬送困難事案」を、総務省がまとめているが、東京都では7月19日から9月12日までに毎週1000件以上が報告されている。とりわけ8月9日~15日の週においては、その数は1837件にも上った(うち、コロナ疑いは870件)。 自宅療養者の死亡者も同様に増加し、9月19日付読売新聞によると、8月1日以降9月17日までの東京都で、自宅療養中に亡くなった人は44人(救急搬送後の死亡者を含む)を数えた。 そんな中、東京都墨田区のデータがひときわ目を引く。 同保健所によると6月25日~9月29日の重症者数はゼロ。大都市圏でこの時期に重症者が1人も出なかった自治体は珍しいのではないだろうか。入院待機者も8月中旬にはゼロとなり、ほかの都市部の自治体のように、本来入院が必要な患者が自宅療養をよぎなくされる、という事態はなくなった。 こうした対策が功を奏した背景には、速やかなワクチン接種や、「墨田区モデル」とも呼ばれる地域内で完結する医療体制の整備、区と医療関係者の連携、議会の対応など、いくつもの要因がある。 本書では、そうした墨田区の対策を概覧しながら、なぜワクチン接種を速く進めることができたのか、ワクチン以外にどのような対策が有効だったのかを見ていくことにする。墨田区の取り組みと知見を記録として残すことで、危機時における地方自治体のあり方を考える参考にしていただければ、と思う。
-
-侵入しない・させない関係をつくる。寂しさと共存し、穏やかに、やさしく、タフに暮らすために。 タフラブは、ベトナム戦争帰還兵のアルコール依存や暴力に苦しむ家族が「生きる術」として生み出した概念。「手放す愛」「見守る愛」などと訳されている。 東日本大震災以来、「絆」が困難を乗り越えるためのキーワードとして使われてきたが、「絆」は本来、牛馬などをつなぎとめる綱のこと。家族や世間の絆に苦しめられてきた人々のカウンセリングを長年続けてきた著者は「絆」に疑問符を投げかけ「タフラブ」という生き方を紹介する。『タフラブという快刀』(2009年)を改題し、加筆・修正・再編集した作品。 【目次】 序 章 タフラブの誕生 医療では救われない/勇気をもって手放す/戦争の落とし子/帰還兵の暴力/実体なき「人の心」 ほか 第一章 無法地帯 複雑に絡み合う現実/「崩壊」は悪いことか/「私」と「私」/「弱まる絆」論/持たざる者の希望/モテる男の証/社会の底辺で ほか 第二章 巨大なスポンジ 果てしない吸収力/性本能と母性本能/珍獣パンダ/父性と父権/正義の父/「私に任せなさい」/現代の秘境 ほか 第三章 切り分け 油と酢のように/母の愚痴を聞く娘/「切り分け」の法則/沈黙の臓器/必殺代理人/「問題」とは何か/除外される「父の問題」 ほか 第四章 覚悟と断念 寂しさとともに/結婚制度に囲い込まれ/「積みすぎた方舟」/「夫が娘を蹴ったんです」/久しぶりの深呼吸/四八パーセントの協力 ほか 終 章 関係からの解放 それは蜃気楼/控えめなリスク回避 【著者】 信田 さよ子 臨床心理士、日本公認心理師協会会長。1946年、岐阜県に生まれる。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。駒木野病院勤務、嗜癖問題臨床研究所付属原宿相談室室長を経て、1995年原宿カウンセリングセンターを設立。アルコール依存症、摂食障害、ひきこもり、DV、児童虐待に悩む人やその家族のカウンセリングを行ってきた。 著書に、『母が重くてたまらない』(春秋社)、『選ばれる男たち』(講談社現代新書)、『カウンセラーは何を見ているか』(医学書院)、『家族と国家は共謀する』(角川新書)などがある。
-
-【推薦】 今すぐ行って、見て、学びたい! 教育にユートピアはない。でも、その精髄に触れられる学校は存在する。 ──苫野一徳さん(哲学者、教育学者/『「学校」をつくり直す』著者) 「学校は変われる」 このシンプルな事実を伝えるのに本書以上のものがあるだろうか。 ──村中直人さん(臨床心理士/『〈叱る依存〉がとまらない』著者) 開学10周年を迎えた京都の公立高校には、全国から視察が相次ぐ――。 不登校や発達障害のある生徒を受けとめ、自分のペースで安心して学べる「学びアンダンテ」を掲げる清明高校。公立校の枠を超えた革新的な取り組みと理念の全貌に迫り、未来の教育の可能性を描く。