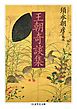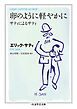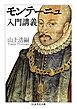筑摩書房作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-西洋と東洋、どうしたら二つの文化の融合が可能かを考え続けてきた国・トルコ。トルコの考え方を通して、異文化理解やグローバルとはどういうことかを考える。
-
-
-
-
-
-ギリシア・ローマやキリスト教と並ぶもう一つのヨーロッパの源流とされ、 日本でも根強い人気を誇るケルト文化。だが、 近年ではケルト神話やケルト音楽からイメージされるような島のケルトと歴史上のケルト人との連続性にはさまざまな異論があり、なかにはその実在を疑う「ケルト否定論」すら展開されている。では、古代ケルト人とは何者だったのか。 著名な神話を入り口に、それを考古学的・歴史学的知見と照らし合わせることで、古代ケルトの生活世界へと分け入る入門書。
-
-
-
-海岸に流れ着いた巨人、蹴鞠に精進した人のもとに現れた鞠の精、白狗の妻となった女、吉祥天女像と交わった男、天狗の幻術くらべ、安倍晴明、紫式部、花山天皇、西行法師……、『日本霊異記』『今昔物語集』『宇治拾遺物語』などの代表的な説話集から歴史書『大鏡』、紀行文『海道記』にいたる平安・鎌倉期の17作品から精選された珠玉の82編を収める。ファンタジーにユーモア、時には能芸や和歌を語る奇談の数々は、奇想天外、摩訶不思議、多情多恨、絢爛華麗、抱腹絶倒。稀代のアンソロジストが流麗な現代語訳で遺した美しくも哀れな古典幻想文学の花束をどうぞ!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-日本人に特有の「言えそうで言えない」英語表現があるようだが、なぜだろうか? ビジネスを中心に日常的な場面やSNSで使われそうな会話の中で、より適切な英語表現はどれになるかを、クイズ形式で学んでいく。文法的な誤りや単語の使い方、さらに文化的背景や物事の捉え方の違いを解説で読みながら、日本語と英語の発想の違いに気付くことで、よりシンプルで伝わる英語表現を身につけていきたい。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-「力学の原理に差はないのだから、教養課程の学生が専門課程に相当する部分まで進んでいけない理由はない。進めるだけ進め、少なくとも道は開いているほうがよい、行く先で解けるようになる面白い問題に展望があるほうがよい」。本書で提供される問題は、机上で考えられたものだけではなく、実際の自然現象に即して創られたものも多く含まれる。それらは難解な問題もあるが、話題は広く、古典力学の豊かさを余すところなく示している。経験豊富な執筆陣が、一切の妥協を排して世に送った類書のない力学演習書。練り上げられた刺激的な問題と詳細な解説で、力学の高みへといざなう。
-
-来たるべき300年後の社会を実行可能な形で構想した画期的試論、ついに文庫化! この複雑な世界を複雑なまま生きることはいかにして可能か――。これが本書の中心にある問いだ。生命の起源から説き起こし、膜と核の問題が社会制度と地続きであることが、最初に示される。社会の〈なめらかさ〉とは、膜の機能を弱め、諸物が連続的なつながりをなすネットワークへと開いていくことにほかならない。それは、情報技術の支援の下、貨幣・投票・法・軍事というコアシステムの変革によって実現される。近代のメジャーバージョンアップだ。巻末には、原著刊行後に顕在化した問題を俯瞰する新論考を付し、本書の現代性と可能性をあらためて照射する。
-
-
-
-能は退屈どころか、本当はとてつもなく面白い。700年におよぶ日本の伝統文化の蓄積があるからだ。太閤・秀吉や五代将軍綱吉は相当な能狂いだった、桃山時代までの能は今のおよそ2倍の速度で演じられていた、世阿弥の晩年はよくわからず、その著書『風姿花伝』は明治末年まで一般にはその存在すら知られていなかった――等々、能の歴史を楽しく学びつつ、日本の伝統芸能の本質も理解できる。日本人なら教養として知っておきたい、確かな史料に基づいた能楽史の入門書決定版。
-
-大阪や東京日本橋界隈の問屋、観光地の朝市、縁日、門前町の商家など、その源流をさかのぼると、多くは中世社会にまでたどり着く。そして彼らの営業形態や商売人としての思想には、中世から引き継がれたものも少なくない。いわば現代経済社会の基礎は中世の商業社会にあるといえよう。本書は長く商業史を牽引してきた著者が、中世の個々の商人像にスポットライトをあてつつ、経済全体の流れについても描いてみせた商業史入門の傑作。朝廷に仕えた供御人、大原女などの行商人、都市の定住商人、戦国の豪商等々、さまざまな商人のしたたかな営業活動が、活き活きと浮かび上がる。
-
-
-
-
-
-
-
-江戸時代の日本について、鎖国によって孤立し停滞した封建制社会であったと受け止める傾向がある。また、農民や町人は、厳しい身分制度でがんじがらめの支配を受けていたと信じられがちである。しかし村々に残る資料をみて歩くと、この時代の百姓たちは自ら所有する土地を耕しながら布や酒をつくって店をひらき、さらには寄合の協議で村の運営を動かすこともあったことなどが分かってくる。江戸時代はむしろ、元気な百姓が主役の、近代的な前期資本主義社会だったのだ。支配者史観を覆し、庶民の視点から江戸時代の歴史を読みなおす。
-
-映画は人間の認識に何をもたらしたのか。映画とともに誕生した思考とは何であるのか。こうした問題を、ほかのどの国にもまして考察しつづけ、思想的系譜として育んできたのがフランスにほかならない。本書では、ジャン・パンルヴェからジル・ドゥルーズまでを貫くその歴史を、“自動性”の概念を軸に再構成し、映画の力による世界への信と希望の可能性を考える。
-
-
-
-
-
-南宋末、フビライ率いるモンゴル軍が南下し、王朝は危殆に瀕していた。政治の中枢は腐敗と混乱のなかにあったが、ひとりの秀才が敢然と挙兵し、防禦にあたる。文天祥その人である。だが大勢に利はなく、あえなく囚われの身となり、その間に宋は三百年の歴史に幕を下ろすこととなる。天祥は、フビライから宰相就任要請があるもこれを固辞。五言古詩「正気の歌」を遺してついに刑場に果てる――。反時代的なまでに儒教道徳に忠実で、純なる人間性を貫いた生涯。それは、人間のひとつの極限をわれわれに突きつける。宋代史研究の泰斗が厚い考証を基に天祥の実像を描いた名著。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-日本の右傾化が進んでいると言われて久しい。実際、ヘイトスピーチや改憲潮流、日本会議など、それを示す事例には事欠かない。ならば日本社会は、全般的に右傾化が進んでいるのか? 本書ではその全体像を明らかにすべく、ジャーナリストから研究者まで第一級の書き手が結集。「社会」「政治と市民」「国家と教育」「家族と女性」「言論と報道」「宗教」の六分野において、それぞれ実態を明らかにしていく。いま、もっとも包括的にして最良の「右傾化」研究の書である。 ※ 著者からの申し出により、本電子書籍版に「第6章 有権者の「右傾化」を検証する」は収録されていません。
-
-
-
-琉球王国として独自の文化を形成した沖縄。1938年に初めて現地を訪れた柳宗悦は、工芸品ばかりでなく、建物や人、暮らしぶりにいたるまで、すべてが美しい島々に魅了される。以来、来島を重ね、調査・蒐集を行い、展覧会などを通じてその魅力を紹介した。しかしその夢のような美の王国は1945年の沖縄戦で灰燼に帰してしまう。本書には表題の「琉球の富」をはじめ、柳が沖縄のすばらしさや沖縄の人々への想いを綴った主な論考を収録。あわせて玉陵や識名宮、首里の町並みなど、失われてしまった美しい風景を記録した貴重な写真も多数掲載。戦前の沖縄がここに蘇る。文庫オリジナル。
-
-
-
-現在は島根県東部の一地方である「出雲」の名を冠した地名や神社が、列島各地に存在するのはなぜなのか。出雲の謎とは、この国の成り立ちにかかわる問いである。各地に広がる出雲信仰の足跡や伝承、郷土史を丹念に播き、見えづらくなった古来の地域と地域とのつながりを再構成。一つの中心から勢力を拡大していく従来の国家像や近代的な中央集権国家の観念にとらわれない、もうひとつの日本の成り立ちを鮮やかに描き出す。
-
-
-
-人体、鉱物や雪の結晶、建築の意匠、芸術・工芸作品……。対称性はミクロレベルにおいては分子構造から、マクロレベルでは特殊相対論で距離の定式化や銀河の形状に至るまであらゆるところに伏在している。ただ、この対称性のパターンは、意外にもその種類が多くない、という注目すべき事実がある。パターンを分類し、抽象し、一般化すると、そこに数学の概念“群”が現れてくる。本書の前半は“平面の結晶群”とも言うべき周期性をもった壁紙模様、モザイク模様が語られ、後半ではプラトンの正多面体の合同群についての考察がなされる。初学者のための群論的思考入門。
-
-
-
-
-
-「自由・平等・友愛」を掲げて行われたフランス革命。その革命政府によって課された重税、徴兵令や、カトリック教会への抑圧などに反発して起こったフランス西部・ヴァンデ地方の民衆蜂起は、「カトリック王党軍」という反乱軍を組織して、共和軍との数年に及ぶ内戦へと突入した。革命政府は、ヴァンデ地方での無差別の大量殺戮をもってこれを弾圧し、1793年から96年にかけて革命の名の下に数十万の民衆が犠牲となる。ヴァンデの人々はフランス革命をどう捉え、何を目的に行動したか。史料に基づいて、「後進地域の狂信的民衆による反革命蜂起」とみなされてきた戦争の実態を克明に描く。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-平成を彩った名選手から伝説の試合、球界の大事件、忘れられないバイプレイヤーや珍エピソードまで、“平成プロ野球”を総括したコラム集。文庫化に際して、とんねるず、ファミスタ、TVドラマ、女子アナなどの平成カルチャーと新世紀末プロ野球の危険な蜜月関係に迫る書下ろしコラム4編も新加入。平成の名場面を圧倒的偏愛でまとめた「球界年表」も収録する。
-
-「想定外に当たっていたね」。アインシュタインの理論を、現代の物理学者はおおむねそう評価する。実験機器と実験法の進歩につれ、ただの予想かと見えた理論が次々に実証されてきたからだ。独創の極致ともいえる理論を彼は、いったいどうやって生み出したのか? 幼少期から執筆時までの約70年間を振り返り、何をどう考えてきたのかを語り尽くす、アインシュタイン唯一の自伝。生い立ちと哲学、19世紀物理学とその批判、量子論とブラウン運動、特殊相対論、一般相対論、量子力学に疑義を呈した真意、統一場理論への思いが浮き彫りになる。貴重な写真を多数収録。達意の新訳による文庫オリジナル。
-
-高校までの数学は、問題が与えられ、定義を憶え、定理やその証明を使いこなしながら解いてゆくもので、しかも与えられた問題には必ず「正解」がある。これに対して大学では、与えられた問題を解くのではなく、「問題がどのように作られたのか」、「問題をどのように作るのか」という点に目を向けることが重要とされている。この大きな断絶を埋めるべく本書は誕生した。数学の教科書は著者によるひとつのストーリーが書かれたもので、けっしてその記述を鵜呑みにしてはいけない。数学の真の喜びは、自分自身の教科書を「再構成」したときにはじめて、「新発見」というかたちでやってくる。書き下ろし「解答」を付した大幅増補版。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-宗教戦争のさなか、通念や世間の道徳に懐疑の目を向けつつ、自然に従って生きることの喜びを説いたモンテーニュ。その著『エセー』では、自己の判断力を試し鍛えていくさまが、自由な文体によって描き出される。異文化への関心と共感、戦時における人間の狂気や暴力、性の歓び、ボルドー市長としての政治経験、旅と読書の愉楽など、扱われるテーマは実に幅広く、われわれの心を揺さぶる文章に充ちている。ストア的克己主義と節度ある快楽主義とを往還し、メメント・モリの受容から拒否へと至る過程で、独自な思想が紡がれていく。類まれな開明的人物の核心に迫る出色の講義。文庫オリジナル。
-
-医療現場、原子力発電所等、一つ間違えば大きな事故が生じうる組織において、学習はどのようになされるか――。失敗を含む「日常的実験」の繰り返しこそ、現場での学習の資源である。本書では、このリスクを伴う試行錯誤を許す空間を「学習の実験的領域」と呼び、法的・経済的諸条件に影響され、組織ごと、状況ごとに変動するその不安定なありようを明らかにする。フィールドワークや豊富な民族誌的資料をもとに、学習を社会科学のテーマとして扱い、状況的学習論といった従来の理論モデルを超える新たな枠組みを示した。事故と安全、科学技術、組織といった具体的文脈のもとでの学習を考える、数々の概念装置を与える書。
-
-建築は、一見すると哲学とも思想とも関係のない即物的なもので、定義など簡単にできそうである。ところが、建築ほど定義しづらいものはない――。20世紀末、構築的なものへの批判に晒され混乱をきわめた「建築とは何か」という問いに、著者は建築史と思想史を縒り合わせながら、真正面から立ち向かう。一本の柱が原野に立てられた太古から、ゴシック、古典主義、ポストモダニズム建築まで。建築様式の歴史的変遷の背後にはどのような思想があったのか。本書は、ひとつひとつ思考を重ねつつ、歴史的視座を与えようとした意欲的主著である。著者自身による自著解説を付した、待望の文庫版。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。