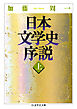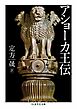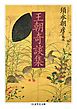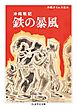ちくま学芸文庫作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
5.0剰余価値追求の終わりなき運動、資本主義。本書はそのメカニズムを精密に分析し、社会科学史に聳え立つ。『マルクス・コレクション』版を全面改訳。 貨幣の増殖を自己目的とする終わりなき運動、資本主義。なぜ等価交換に見える商品流通のなかから、富裕化する階級と貧困化する階級との絶対的対立が生じるのか。この矛盾に満ちた資本主義社会の運動法則全体を、マルクスは19世紀イギリスの産業社会を素材に解明しようとした。全4巻を構想しながら、生前に刊行されたのはこの第1巻だけだった。しかしそれは独立性の高い著作として、以後の知的・政治的世界に巨大な影響を与え続けた。上巻には、「第1篇 商品と貨幣」から「第4篇 相対的剰余価値の生産」の「第12章 分業とマニュファクチュア」までを収録。全2巻。
-
-人間を決めるのは「生まれ」か、それとも「育ち」なのか。いまだに議論の応酬がやまないこの論争に介入し、世界中で大反響を巻き起こした認知心理学者スティーブン・ピンカーの代表作。本書でピンカーは、人間の心は「空白の石版(ブランク・スレート)」であってすべては環境により決定されるという議論に対し、性差など「生まれつき」の要素を無視することはできないとして徹底的な反証を繰り広げる。現代科学の膨大な研究蓄積を武器に、「人間らしさ」の根源を問う、現代の古典というべき一冊。上巻は、人間本性の存在を否定することの危うさを論じた「第III部 四つの恐怖を克服する」まで。
-
4.6日本人の心の奥底、固有の土着的世界観とはどのようなものか、それは、外部の思想的挑戦に対していかに反応し、そして変質していったのか。従来の狭い文学概念を離れ、小説や詩歌はもとより、思想・宗教・歴史・農民一揆の檄文にいたるまでを“文学”として視野に収め、壮大なスケールのもとに日本人の精神活動のダイナミズムをとらえた、卓抜な日本文化・思想史。いまや、英・仏・独・伊・韓・中・ルーマニアなどの各国語に翻訳され、日本研究のバイブルとなっている世界的名著。◆上巻は、古事記・万葉の時代から、今昔物語・能・狂言を経て、江戸期の徂徠や俳諧まで。
-
-一般相対性理論の概念的基礎であることが判明して再び脚光をあびたリーマン幾何学は、1854年の本書収録講演に始まる。この講演にガウスは珍しく高い評価を与えたという。すでに平行線公準の否定に始まるロバチェフスキーやボヤイの非ユークリッド幾何学はあったが、リーマンは、幾何学といいながら図形からでなく、位置を表すn個の変数の組や曲線の長さから新しい幾何学を組み立てた。数式をほとんど用いない哲学的な講義内容を、ワイルがていねいに数式展開しながら注釈。また序文でも本講演の意義を、理論物理学における遠隔作用から接近作用への潮流になぞらえ熱く語っている。ミンコフスキーの論文「空間と時間」併収。解説 H.ワイル
-
-数学のアイディアは経験に由来する、というノイマンの数学観は、作用素環に関する研究にも如実に現れている。それは量子力学を数学的に記述しようとしたところから、ノイマンが数学の一分野として確立したものだ。その後、荒木不二洋、境正一郎、竹崎正道、冨田稔など日本人の著しい活動とアラン・コンヌやヴォーン・ジョーンズらの研究によりさらに発展した。本書は「作用素環について」と題された一連の論文と、終戦直後の講演「数学者」を収録。“数学はどうあるべきか”という深い洞察に裏打ちされた第一級の業績がここに。
-
3.7日本料理の基礎が出来上がった江戸時代。後期に入り経済事情が安定すると、ふだんの食事にも胃袋を満たす以上のものが求められるようになる。こうした中で生まれ、洗練されていったのがすし、天ぷら、蕎麦、うなぎだ。腕利きの料理人が現れると、食べ手にも粋人が現れる。この両者が出会い、食の世界に変革がもたらされていった。たとえば、日本橋南詰の天ぷら屋台の名店「吉兵衛」の客が、隣り合わせた屋台のかけ蕎麦に天ぷらを浮かべることを思いつく、といった具合に──。膨大な史料を読み解き、江戸四大名物食誕生の知られざる歴史に迫る、江戸食文化史の決定版!
-
4.7ウィーン出身の哲学者カール・ポパー(1902‐1994)。その思想は「批判的合理主義」として知られ、主として科学哲学や政治哲学の領域でこれまでに大きな影響を与えてきた。だが、この「知の巨人」の反証主義などの思想はたびたび誤解され、批判にもさらされてきた。本書は、ポパーを最も深く、かつ正確に理解する著者がそうした誤解を正し、ポパーの明晰さそのままに知の体系を解説するものである。『開かれた社会とその敵』の新訳も担当した著者による、いちばん信頼できる伝記として、また専門的見地に基づいたポパー哲学全体を俯瞰できる最良の入門書としても広く読まれてきた定番書、待望の改訂版。
-
3.6万葉の昔からはじまり、江戸時代に花開いた日本人の家飲み。当初健康のため、安眠のために飲まれていた「寝酒」は、灯火の発達とともにゆっくり夜を楽しむ「内呑み」へと変わっていく。飲まれていたのは濁酒や清酒、焼酎とみりんをあわせた「本直し」等。肴は枝豆から刺身、鍋と、現代と変わらぬ多彩さ。しかも、振り売りが発達していた江戸の町では、自分で支度しなくても、家に居ながらにして肴を入手することができた。さらに燗酒を売る振り売りまでいたため、家に熱源がなくても燗酒が楽しめた。驚くほど豊かだった日本人の家飲みの歴史を繙く。
-
4.2寛延年間に生まれた居酒屋は、雨後の筍のように増え続け、文化文政の頃には人口比率でほぼ現在と同じ規模の産業に成長する。食文化を豊かにし、さらには幕府の各種規制を撤廃させていく原動力ともなった居酒屋の歴史を、日記や川柳、随筆、書簡、触れ書などから丹念に掘り起こす。
-
4.5「自己」とはどのように形成され、どうすれば変えられるのだろうか。実はそれは、私たちが自分自身について「物語る」ことで産み出されているのだ。そして物語がエピソードの選択・配列を伴う限り、そこからはみ出してしまうものも存在する。自己物語はそうした「語り得ないもの」(例えばトラウマ的体験)を巧妙に隠しているのであり、この隠蔽を解除する方向へと物語を書き換えることで、異なった自己を産み出すことも可能になる──。物語論を治療に用いた家族療法(物語療法)から、社会学的自己論は何を学べるか。〈物語〉をキー概念に自己の生成・変容をあざやかに読みといた刺激的論考集。
-
-
-
-
-
-
-
4.1“近代世界を一つの巨大な生き物のように考え、近代の世界史をそうした有機体の展開過程としてとらえる見方”、それが「世界システム論」にほかならない。この見方によって、現代世界がどのような構造をもって成立したかが浮き彫りとなる。すなわち、大航海時代から始まるヨーロッパの中核性、南北問題、ヘゲモニー国家の変遷など、近代のさまざまな特徴は、世界システム内の相互影響を分析することで、はじめてその実相を露わにするのだ。同時にそれは、歴史を「国」単位で見ることからわれわれを解放する。第一人者が豊富なトピックとともに説く、知的興趣あふれる講義。
-
-
-
-驚異的な経済成長をもたらし豊かな社会を実現する一方で、格差を常態化し、深刻な不況をくり返す資本主義。その原因はどこにあるのか――。ヒュームやスミスにはじまり、マルクスそして新古典派の登場をへて、ケインズ、ハイエク、ヴェブレンまで。経済学の巨人たちは、自らが生きた時代の課題にとりくみ、その思想を形成した。本書は、そうした現実的背景に照らしながら、かれらの理論の核心を平明に説く。さらに後半では、貨幣や消費などの重要テーマごとに経済分析のあり方を問うことで、経済思想の今日的意義を浮き彫りにする。経済という人間の営みを根底からとらえなおす、決定版入門書。
-
4.2どんぶり物を生み出したのは、江戸時代に生きたある男の“食い意地”だった。出前の蒲焼が冷めないようにと、蒲焼をご飯の中に入れ込んで楽しんでいたところ、それがまわりにも広まり、日本初のどんぶり物、うな丼が誕生する。それまで白いご飯の上におかずをのせるという発想を持っていなかった江戸っ子たちは、すっかりうな丼の虜となった。だがうな丼以降、新たなどんぶり物が誕生するには時間がかかった。天ぷら蕎麦や親子とじ蕎麦は江戸時代には生まれているのに、天丼や親子丼の登場は明治になってから。その背景には何があったのか? 膨大な史料から、どんぶり物誕生の歴史をひもとく。
-
-自律性、個体性、境界の自己決定、入出力の不在。これらを特徴とし、自己を産出するネットワークを不断に再生産し続けるシステム、それがオートポイエーシス・システムである。神経生理学の研究から導き出されたこの構想は、観察者の視点からではなく、システム自身からシステムを定式化しようと試みたもので、生命のみならず認知の領域をも射程に入れる。その可能性は社会学、経済学、法学、精神医学など多分野において汲み取られ、豊かな展開を遂げた。閉鎖系のダイナミクスがもたらす開放性の新たな意味とはなにか──。第三世代のシステム論のモデルを高度な記述とともに提示した独創的著作。
-
5.0
-
4.0遠くヨーロッパ中世、市井の人びとは何を思い、どのように暮らしていたのだろうか。本書から聞こえてくるのは、たとえば石、星、橋、暦、鐘、あるいは驢馬、狼など、人びとの日常生活をとりまく具体的な“もの”との間にかわされた交感の遠いこだまである。兄弟団、賎民、ユダヤ人、煙突掃除人など被差別者へ向けられた著者の温かい眼差しを通して見えてくるのは、彼らの間の強い絆である。「民衆史を中心に据えた社会史」探究の軌跡は、私たちの社会を照らし出す鏡ともなっている。ヨーロッパ中世史研究の泰斗が遺した、珠玉の論集。
-
4.0詩を、作者の心情の直接的発露であり、それを伝える手段だとする見方は根強い。だが、詩において言葉は日常の用法とは異なる態度で取り扱われる。それゆえ、著者が「詩は表現ではない」と明言したとき、旧来の詩観は大きく揺さぶられることとなった。言葉を関係性によって捉えることが重視され、「作者─発話者─主人公」の区別に紙幅が費やされる。これらを通し、われわれは詩がどのようにして成り立つのか、その秘密に近づけるだろう。詩とはいったい何か。この問題を追究したものとして本書に並び立つ書はいまもって少ない。実作者も鑑賞者も一度は読んでおきたい詩作品入門。解説 野村喜和夫
-
4.2唐代、治世の問題を真正面から取り扱い、帝王学の指南書となった『貞観政要』。幾多の戦乱を乗り越え、太平の世を現出させた太宗(李世民)が名臣たちと交わした問答を史家・呉兢が編纂。爾来、中国のみならず日本においても為政者たちが折に触れて立ち返る古典の地位を得てきた。「指導者の条件」「人材の登用」「後継者の育成」など、およそ組織運営に関わる人間なら必ず迷い、悩むであろう問題に古人はどのように臨んできたのか。本書には汲めども尽きぬ教訓が今も満ち溢れている。本文庫は明代の通行本(戈直本)を底本とし、全篇より七十篇を精選・訳出。
-
4.0純粋な「形式性」と起源なき「名前」の流通によって現実が作られる時代。それは、いかにして生まれたのか──。19世紀中葉、一組の義兄弟が陰謀を企てる。兄の名は、ルイ=ナポレオン。フランス皇帝ナポレオン1世の甥である。かたや父親を異にする弟の名は、ド・モルニー。「私生児」にして、のちの内務大臣・立法院議長である。権力奪取の計画は首尾よく運び、ここにフランス第二帝政の幕が上がることとなる。希薄で、シニカルな相貌をまとって……。ド・モルニーが遺した二つのテクストを読解し、マルクスが見落としたものを軽やかに描く、著者最初の書き下ろし作品。
-
3.9人を納得させる議論には「型」がある。「定義」「類似」「譬え」「比較」「因果関係」──たった五つの論法さえきちんと使いこなせれば、誰だって自分の考えを的確に表現できるようになり、一見もっともらしい相手の主張の弱点も見えてくる。教育現場でディスカッションなどを指導する際の手引きとして書かれた本書には、議論に欠かせないこれらの技術の使い方と、それに対する反論の仕方といった、私たちが身につけておくべきイロハが明快に論じられている。豊富な実例を通して論証・反論の技術を磨く、確かな修辞学的知見に裏打ちされた入門書。『議論の技を学ぶ論法集』文庫版。
-
3.5考古学的な知見と、『日本書紀』『古事記』などの文献資料を織り合わせてはじめて、古代の真の姿が浮かび上がる。この考えから「古代学」を提唱する学界の重鎮が、古代の読み解き方を根本から問い直し、「土地」「年代」「人」の見方をめぐって、具体的かつ革新的な方策を提案する。「土地」の見方では変貌する河内と摂津から国生み神話の鍵などを考察。「年代」の見方では銅鏡の「年代」や「暦」を通して、古代人が時間をどう記述したかを探る。「人」の見方では、倭人=「呉の太伯」の後裔伝承の重要性などを提議。未解明の謎の数々や、古の人びとの心に想いを馳せながら、古代史を総ざらいで生きる入門書。
-
3.8恥じらいながら、生まれたばかりの透明な素肌を露にする愛の女神ヴィーナス、恍惚としてひとり横たわるマグダラのマリア、近代をとりこにした東洋の女奴隷たちの妖艶な姿態―西洋美術の世界を彩る美しいヌードが大集結。性のモラルの厳しいキリスト教社会で裸体を描くことがどうして可能だったのか? その多くが神話や聖書を題材とするのはなぜか? ボッティチェッリ描くヴィーナスのお腹が膨らんでいるわけは? いくつかの鍵を用いて読み解くと、魅惑的な姿に秘められた謎があざやかに浮かびあがる。カラー多数。200点以上の図版とともに楽しくアートの世界へ誘う極上の美術案内。
-
4.3
-
4.0力強く簡潔な文体と精彩あふれる描写で知られるタキトゥスの2つの小品を収める。『ゲルマニア』は、当時ローマ帝国に北方から脅威を与えていたゲルマニアの諸部族に関する民族誌。風土、習俗、制度などについての概説と各部族の記述からなる。野性に満ちて強力なゲルマニア人と、文明化し過ぎ頽廃・衰亡への道を歩むローマ人を対比し、警告を発する。『アグリコラ』はタキトゥスの岳父を描いた伝記。暴君のもとでの貴族の生き方を示すとともに、ブリタンニア(古代イギリス)の地理や民族を詳しく記す。
-
5.0「エディプス・コンプレックスはあらゆる社会に存在する」とフロイトは説いたが、マリノフスキーはこの仮説に対し民族誌的資料を駆使し、それが近代西欧の家父長制的社会特有の現象であると根底から相対化してみせた。近代的社会人類学の確立者として学説史に不朽の名を刻んだマリノフスキーが、性において人類の内なる自然と文化的力との相互作用のドラマを考察した古典的名著で、家族の起源、近親相姦の禁忌、父系制と母系制との関係等いまだ多くの示唆を与えてくれる。また、文化の概念をはじめ、彼の主要な理論、概念が展望でき、マリノフスキー理解の恰好な入門ともなっている。
-
4.4条件づけられた人間が環境に働きかける内発的な能力、すなわち「人間の条件」の最も基本的要素となる活動力は、《労働》《仕事》《活動》の三側面から考察することができよう。ところが《労働》の優位のもと、《仕事》《活動》が人間的意味を失った近代以降、現代世界の危機が用意されることになったのである。こうした「人間の条件」の変貌は、遠くギリシアのポリスに源を発する「公的領域」の喪失と、国民国家の規模にまで肥大化した「私的領域」の支配をもたらすだろう。本書は、全体主義の現実的基盤となった大衆社会の思想的系譜を明らかにしようした、アレントの主著のひとつである。
-
4.0
-
4.0集団への帰属の欲求とは何を意味するのか。この欲求が他者に対する恐怖や殺戮へとつながってしまうのはなぜなのか――。グローバル化の進展は、さまざまな文化の保持者たちの基盤を揺るがし、時に偏狭で排他的な帰属意識を生み出してしまう。複数の国と言語、そして文化伝統の境界で生きてきた著者は、本書のなかで新しい時代にふさわしいアイデンティティのあり方を模索する。鍵となるのは、「言語」だ。言語を自由に使う権利を守ること、言語の多様性を強固にし、生活習慣のなかに定着させること、そこに世界の調和への可能性を見る。刊行後、大きな反響を呼んだ名エッセイ、ついに邦訳。文庫オリジナル。
-
4.0アイヌ文化とはなにか、彼らはどのようなくらしを営み、どんな世界観をもっていたのか。本書では、史上初のアイヌ出身国会議員であり、その文化の保存・継承に長年尽力してきた著者が、みずからが生まれ育った二風谷(にぶたに)の四季の生活を振りかえりながら、その模様をやさしく紹介していく。食文化、住まい、儀礼、神話・伝承、習俗、自然観や死生観……。それらの記述を通して浮かび上がってくるのは、自然と調和し共に生きようとするアイヌの心である。いまなお日本人に広く知られているとはいえない先住民族アイヌの世界。その全貌を知るための基本書となる一冊。
-
-「想定外に当たっていたね」。アインシュタインの理論を、現代の物理学者はおおむねそう評価する。実験機器と実験法の進歩につれ、ただの予想かと見えた理論が次々に実証されてきたからだ。独創の極致ともいえる理論を彼は、いったいどうやって生み出したのか? 幼少期から執筆時までの約70年間を振り返り、何をどう考えてきたのかを語り尽くす、アインシュタイン唯一の自伝。生い立ちと哲学、19世紀物理学とその批判、量子論とブラウン運動、特殊相対論、一般相対論、量子力学に疑義を呈した真意、統一場理論への思いが浮き彫りになる。貴重な写真を多数収録。達意の新訳による文庫オリジナル。
-
4.3青山二郎は、小林秀雄、白洲正子の骨董の師匠としてだけでなく、河上徹太郎、中村光夫、宇野千代といった周囲の人たちにも大きな影響を与えた。その青山の信仰とは、知識に依らず、眼を頭から切り離して、純粋に眼に映ったものだけを信じるという「眼の哲学」であった。やきものから学んだ眼力によって、骨董はもちろん、人間の真贋から社会批評まで、ズバリとその本質を言い当てる。青山の文章は、独特な比喩とともに難解なところもあるが、知識ばかりが横溢する現在、もっとも辛辣な文明批評となっている。上巻は、「梅原龍三郎」「北大路魯山人」「小林秀雄と三十年」「贋物と真物について」など、美術と人物に関する文章43篇を収録。
-
4.2
-
4.7ブッダはなにを語り、どのように説いたのか。その教えを最も純粋なかたちで伝える最古層の重要な仏教経典の集成。阿含=アーガマとは伝承されてきた聖典を意味する。これらの経典群のなかには、あらゆる宗派を超えた仏教の原初のすがたがあり、その根本がある。本書は厖大な阿含経典群のなかから、よく古形を保ち、原初的な経と判定される諸経をとりあげ、パーリ語原典からの現代語訳と注解で構成。第1巻は、ブッダの悟りの内容を示す「存在の法則(縁起)に関する経典群」と、その法則に即して人間をかたちづくる要素を吟味した「人間の分析(五蘊)に関する経典群」を収録する。
-
4.0インド亜大陸のほぼすべての地を統一したマウリヤ朝第三代の王・アショーカ。ダルマ(法)による政治を行い、八万四千におよぶ塔の建立、五年大会の開催など、仏教の守護者として歴史的に名高い。本書は、その生涯をサンスクリット原典から訳出。王はいかにして熱烈な仏教徒となったのか──。家族をめぐる劇的な出来事をはじめ、伝記は興味深い逸話に満ちている。古代インドにおける仏教徒の世界観や人生観が王の行跡から垣間見えるとともに、凡夫の煩悩を持ちながら聖なる世界を希求したアショーカの姿は、現代を生きるわれわれを引きつけてやまない。巻末には本書をめぐる詳細な解説を付す。
-
3.3
-
-
-
4.0
-
3.5
-
4.3霊学研究の諸成果に関心を寄せる人々の中には、そのような人生の高次の謎を口にする者が一体どこからその知識を得たのか、という点に疑問をもたざるをえない人もいるであろう。本書はまず第一にこのような人のために役立ちたいと望んでいる。霊学は人生の高次の謎の本質に深く係わろうとする。この霊学からの発言の根底にある諸事実を吟味しようとする人は自力で超感覚的な認識を獲得しなければならない。本書はそのための道を記述しようとしている。四大主著の一冊。
-
4.5『逝きし世の面影』の著者渡辺京二は、日本近代史の考察に、生活民の意識を対置し、一石を投じてきた思想家である。その眼差しは表層のジャーナリズムが消費する言説の対極にある。本巻には、西欧的な市民社会の論理では割り切ることのできない、大衆の生活意識にわだかまる「ナショナル」なものを追求した「ナショナリズムの暗底」、明治国家への最大の抵抗者としての西郷隆盛を常識的定説から救抜する「逆説としての明治十年戦争」、北一輝と日本近代の基本的逆説の関連を問う「北一輝問題」など、日本近代史を根底から捉え返すことを試みた論考を集成する。
-
4.8位相は“近い”という日常感覚を数学的に厳密にとらえ直したもの、といってよく、現代数学において最も基本的で重要な概念の1つである。歴史的には、18世紀から19世紀末にかけて解析学が進展していくなかで、極限・収束・連続性などをめぐる議論から位相空間論が生まれ、20世紀における関数解析学の展開によって、より抽象的に定式化されていった。本書は、数学の意味・こころを語る達人である著者が、1950年代、60年代、70年代に、位相をめぐって書き綴った「位相解析入門」「位相用語集」「位相構造」という3つの文章からなる。著者の名調子に乗せられて、位相のこころを体感してみよう。
-
4.3ガウスは50桁ぐらいの計算はものともしなかった。むしろ楽しみですらあった。しかも数字に異常な記憶力があり、いちど計算したことのある数は自在に取り出すことができた。整数の研究にも熱情を注ぎ、法則の発見のために独力で大きな数表をつくった。素数の表、二次剰余・非剰余の表、1000以下の素数の逆数の表……。このように数学の神に導かれたガウスもいたし、一生を数学に生きたオイラーもいた。狂熱に引きまわされ短い生涯を駆け抜けたアーベルやガロアもいた。他にアルキメデス、ニュートン、ライプニッツなど全20人が登場。天空を舞うような彼らの高揚感を熱くつづった「数学者物語」。
-
4.3一揆といえば、虐げられた民衆が農具や竹槍を手に極悪非道な領主たちに立ち向かう、そんなイメージを抱きがちだ。しかし、それは戦後歴史学が生み出した幻想に過ぎない。史料を丹念に読み解くなかで見えてくるのは、革命や暴動といった固定観念とはほど遠い、権力者とのしたたかな折衝のあり様だ。一揆とは、暴発的な武装蜂起ではなく、既成の社会関係では対応できない危機に直面した人々が「契約」によって生みだした、新たな社会的つながりなのだ──。これまで語られてこなかった一揆の実像と、現代の社会運動にまで連なる結合の原理を、新進の中世史家が鮮やかに解き明かす。
-
-法然が登場する以前、仏教は驚くことに、一部のエリートのためだけに存在する宗教だった。漢文で書かれた難解な経典が読めること、日常生活を気にせず修行に打ち込めること、が条件だったからだ。しかし実際に苦しみ、救済を必要としたのは、文字も読めない市井の人びとに他ならない。そこで法然は、誰でも、いつでも、どこでも実践可能な「念仏」を柱とする浄土宗を打ち立てた。この『一百四十五箇条問答』は、法然の教えに惹かれながらも、従来の仏教との違いに戸惑ったり、生活を改めなければならないのかと不安に思った人びとの145の疑問に、法然がやさしく答えたもの。浄土仏教や法然その人を理解するための、またとない入門書となっている。
-
4.0
-
4.5有名芸術家の名作はもとより、版画や挿絵、広告や記念碑に至るまで、美術作品が、何のために、どのように描かれてきたか──それが「イメージの歴史」だ。ここではさまざまな学問領域を自由に往来し、ポスト・コロニアル的かつジェンダー的な視線で従来の美術史を書き換える。絵画と社会のかかわりや画像の解釈方法などの理論を踏まえ、さらに西欧文化が繰り返し描いてきたイメージにメスを入れ、その精神的・社会的な背景を明らかにする。レイプを描き続けたのはなぜか、新しい政治形態はどのような画像を生んだか──人間の想像力に新たな光を当てる美術史の誕生。
-
4.0
-
4.0
-
-
-
-
-
3.8遠くインダス文明にまでさかのぼり、異文化が交錯する要衝の地として繁栄してきたインド。そのため現在も多様な民族、言語、宗教が混在する。また古来よりカースト制が敷かれてきたことから、社会階層も多様に存在している。しかし、どの地方、どの民族のカレーを食べてもカレーとしてのカテゴリーに収まっているように、インド文化圏は多様な中にも統一性が保たれている。それはいったいなぜなのだろうか? 映画、新聞広告、絵画、物語、遺跡、陶磁器、食べものといった身近なテーマを切り口に、インドの文化と歴史を丸ごと理解する、世界的権威によるまたとない入門書。
-
-グローバル経済の起源は大航海時代にあると言われる。しかしそれよりはるか前、インド洋海域世界には二千年以上もの間、様々な民族、人種、宗教が交じり合う自由で自立した大経済圏が存在していた。季節風を利用した航海技術の確立により長距離交易が盛んに行われ、アフリカから地中海世界、西アジア、インド、東南アジア、中国にわたる広大な地域が一つに結ばれていたのだ。しかしレコンキスタ終結後、この経済網はヨーロッパ人に破壊され、奪われていく。イスラームの影響下で栄えた大経済圏・文化圏の全体像を、膨大な史料とフィールドワークをもとに描き出す、海域史研究の記念碑的名著。
-
-イングランド北部の炭鉱町ウィガン。1936年、オーウェルがこの労働者の町を訪れたとき、不景気と失業がひろがっていた。炭鉱夫たちと生活をともにしながらオーウェルは、彼らの顔貌を独特な身体感覚のもと丹念に書きとめていく。ここは、中産階級下層の彼の階級意識が決定的に試される場所となった。たとえば、「労働者階級には悪臭がする」。社会主義への支持を表明しながら、越えられない階級間の「ガラスの間仕切り」。彼はこの違和感を、あえて率直に表明する。声高に語られるドグマではなく、人間らしい生活、すでに中産階級からは失われてしまった生活様式への愛が、未来を考えるひとつの指標として提示される。20世紀ルポルタージュの嚆矢。
-
4.5アジア太平洋戦争において死没した日本兵の大半は、いわゆる「名誉の戦死」ではなく、餓死や栄養失調に起因する病死であった──。戦死者よりも戦病死者のほうが多いこと、しかもそれが戦場全体にわたって発生していたことが日本軍の特質だと著者は指摘する。インパール作戦、ガダルカナル島の戦い、ポートモレスビー攻略戦、大陸打通作戦……、戦地に赴いた日本兵の多くは、無計画・無謀きわまりない作戦や兵站的な視点の根本的欠落によって食糧難にあえぎ、次々と斃れていった。緻密な考証に基づき、「英霊」たちのあまりにも悲惨な最期を明らかにするとともに、彼らを死へと追いやった責任を鋭く問う、告発の書。
-
-「薄曇りの夜空のひろがるその下で、はるかかなたイオニア海の水平線に、金属が溶けあうように曙光がさしはじめた。よしと、一杯の紅茶とトーストのかけらを飲みこんだ」。1921年1月、作家は妻“女王蜂”を伴い、居住していたシチリアからサルデーニャに向けて旅立つ。近代化のさなかにあっていまだ野性味を残す島の自然と人々。市場の野菜。山々を行く汽車とバス。だがこの島にも第一次世界大戦後の世情が影を落とし……。作家は確かな直感と観察によって、旅の跡を活き活きと書き綴る。本文庫では原書初版で削除された箇所を復元。ロレンス文学の頂点と評される傑作旅行記を名訳で。
-
4.0スタジオ・システムという強力な支配形態のもとにおかれた、古典的ハリウッド映画産業。利潤追求を至上命令とする製作会社によって俳優・監督・脚本家他あらゆる関係者が管理されるなか、激動期のアメリカで、いかにして映画は製作されたのか。監督と撮影所の対立、陸軍による検閲、自主検閲的倫理規定ヘイズ・コード、第二次世界大戦のプロパガンダ映画、それに携わった黒人映画作家……。複雑な力学が働く映画の生成過程に、文書資料や関係者インタビューなど一次資料を用いて実証的に迫る。映画学(フィルム・スタディーズ)という研究領域を切り拓いた画期的作品。 解説 板倉史明
-
4.0なにも絵画や彫刻、音楽だけが文化なのではない。あたりまえの日常にいちばん近い部分を発達させること。それこそが文化なのだ。吉田健一は、エリザベス朝にはすでに水洗トイレがあったことを指摘し、そこに実用性を重んじるイギリス文化の本質を見る。イギリスで他の芸術に比して文学が発達したのも、文化的であろうとしたからではなく、日常の言葉へのこだわりが、自然と、詩や小説というものになっていったからなのだ──。胡瓜のサンドイッチやハムの味、酒の飲み方など、身近な話題を入口に、いつの間にか本質的な部分へと読者をいざなう、名人芸的文化論。
-
4.0『英語類義語活用辞典』『日英語表現辞典』などの編著者であり、「英語力に練達の人」としてつとに名高い最所フミ。彼女は、言語の機能とは与えられたものをcomprehend(了解)し、absorb(吸収)して、express(外面化)するプロセスの繰り返しにあるとする。そのうえで英語を学ぶ人々に、よりいっそう力を養うにはどうすればよいかを、日本人の実状を踏まえて実践的に述べる。英語と日本語の違い、効果的な「読み」、「書く」ための心構え、英会話と音読といったテーマを通し、著者一流の秘訣を一挙公開。その方法論は今も輝きを失ってはいない。
-
-類義語・同意語・反意語の正しい使い分けが、豊富な例文から理解できる定評ある辞典。思わぬ誤解や失礼をしないための使用例が、卓越した日本語と英語の語感をもつ著者により解説される。(1)意味がほとんど同じで、どちらを使っても大した違いのないもの。mistakeとerror、bigとlargeなど。(2)使い方をまちがえるとコミュニケーションに重大な齟齬を来たすもの。doubtとsuspectなど。(3)漠然と類義語だと信じられているがその実、異質な言葉。fortunateとhappyなど。「なるほど」と腑に落ちる効果的な使い方が、わかりやすく習得できる、学生や教師・英語表現の実務家の必携書。
-
-映像を表現と主体意識、存在条件との間の緊張関係から考え、真の創造を探求した至高の映画論。1950年代に始まる転換期にあって、旧来的な映画観を転覆すべく、著者は思考を尖鋭化させていく。調和を失った社会のなか、見えなくなっているものを見えるようにすることを芸術における第一義の課題としながら──。アヴァンギャルドもドキュメンタリーも、つまり内と外に分かれた意識の方向も、見えないものに迫る方法として交差し、それを通じて新たなイメージは創り出される。初刊は1963年。映画史的直感や時代との格闘から生まれた洞察はいまも色褪せてはいない。
-
4.5「それ独自の事実のフォルムと表示のなかに刻み込まれた時間――ここにこそ、私にとって芸術としての映画の第一の理念がある」。その理念が有機的統一をもって結晶する“イメージ”。『惑星ソラリス』『鏡』『サクリファイス』など、生み出された作品は、タルコフスキーの生きた世界の複雑で矛盾に満ちた感情を呼び起こす。俳優や脚本のあり方をはじめとする映画の方法は、現代において涸渇した人間存在の源泉を甦らさんとする意図とともに追求された。戦争と革命の時代である20世紀に、精神的義務への自覚を持ち続けた映画作家の思考の軌跡。
-
3.8
-
3.5
-
3.0和食の原型は江戸時代に形作られた。そう聞くと江戸の料理は素朴なものだったと思われるかもしれないが、さにあらず。魚は天然、野菜は有機、その上調理方法にも技巧が凝らされており、江戸の食文化はとても豊かだった。例えば刺身一つとってみても今はたいてい醤油を添えるが、江戸時代は魚の種類ごとに煎り酒や生姜酢などの各種調味料を使い分けていた。薬味もわさびだけでなく、からし、おろし大根、蓼など多様だ。本書ではそんな豊かな江戸の料理と食材を季節ごとに紹介し、各種行事食の由来も解き明かす。第一人者による人気連載を初書籍化。江戸時代の図版も約150点収録。
-
5.0東京は坂の街。「その名は江戸っ子気質そのままで、単純明快、即興的で要領よく、理屈がなくて、しかもしゃれっ気があふれている」。富士を眺められる坂は「富士見坂」、海を望む坂は「潮見坂」、墓地のそばの坂は「幽霊坂」、赤土の坂は「赤坂」、急な坂は「胸突坂」…。東京の坂道と、その名前を見つめると、江戸庶民の暮らしと心が浮かび上がる。東京中を隈なく歩き、古書や古地図を渉猟して、坂道に織り込まれた歴史を辿る。「坂道」研究というジャンルを確立し、いまなお坂道ファンのバイブルと親しまれる古典的名著。本書を片手に散歩すれば、いまも江戸を垣間見られる。
-
-ざっと三百年間の移り変わりを述べることに致します―。大火や幾度もの改革、風呂屋や歌舞伎の流行といった時代背景・風俗とともに語る江戸服飾史入門。明治期、学者・大槻如電が三越呉服店の依頼をうけて講談調で記した原稿に、注釈や図版を多数加え、現代人向けに編集した。金ピカの裃を着て真面目な顔でいる武士たち、ひいきの役者の紋を銀簪に彫る女たち、度重なる倹約令を経てなお新たな流行を作り出す江戸の人々の姿が活写される。当時の語りの面白さを残したユニークな書であり、着物、履物、流行りの模様、髪型、帯の締め方までを詳細に示す貴重な資料である。
-
3.9労働の発生と組織化、欲望の無制限な発露に対する禁止の体系の成立、そして死をめぐる禁忌……。エロティシズムの衝動は、それらを侵犯して、至高の生へ行き着く。人間が自己の存続を欲している限り、禁止はなくならない。しかしまた人間は、生命の過剰を抑え難く内に抱えてもいる。禁止と侵犯の終りなき相克にバタイユは人間の本質を見ていった。内的体験と普遍経済論の長い思考の渦から生まれ、1957年に刊行された本書によって、エロティシズムは最初にして決定的な光を当てられる。バタイユ新世代の明快な新訳で送る、待望の文庫版バタイユの核心。
-
-「力学の原理に差はないのだから、教養課程の学生が専門課程に相当する部分まで進んでいけない理由はない。進めるだけ進め、少なくとも道は開いているほうがよい、行く先で解けるようになる面白い問題に展望があるほうがよい」。本書で提供される問題は、机上で考えられたものだけではなく、実際の自然現象に即して創られたものも多く含まれる。それらは難解な問題もあるが、話題は広く、古典力学の豊かさを余すところなく示している。経験豊富な執筆陣が、一切の妥協を排して世に送った類書のない力学演習書。練り上げられた刺激的な問題と詳細な解説で、力学の高みへといざなう。
-
4.5海岸に流れ着いた巨人、蹴鞠に精進した人のもとに現れた鞠の精、白狗の妻となった女、吉祥天女像と交わった男、天狗の幻術くらべ、安倍晴明、紫式部、花山天皇、西行法師……、『日本霊異記』『今昔物語集』『宇治拾遺物語』などの代表的な説話集から歴史書『大鏡』、紀行文『海道記』にいたる平安・鎌倉期の17作品から精選された珠玉の82編を収める。ファンタジーにユーモア、時には能芸や和歌を語る奇談の数々は、奇想天外、摩訶不思議、多情多恨、絢爛華麗、抱腹絶倒。稀代のアンソロジストが流麗な現代語訳で遺した美しくも哀れな古典幻想文学の花束をどうぞ!
-
5.0ユダヤ系でありながら熱烈な愛国者にしてゲオルゲ派。迫害と亡命。二十世紀の矛盾そのものを生きたかのような著者の法外な学殖と情熱は、王権表象の冷徹な解剖に向けられた。王は死んでも王位や王冠、王朝は存続する。その自然的身体とは独立して存在するように見える王の政治的身体は、いかにして産出されたのか。王権の政治神学的・象徴的基盤は西欧の歴史の中で、どのように編制されたのか。本書には、問題提起とシェイクスピア『リチャード二世』論に始まり、キリスト論との類比、法学的思考の浸透とその影響、王を神秘体の頭と捉える政体有機体説に説き及ぶ、第五章までを収録する。全二巻。
-
4.2第二次世界大戦における最激戦地の一つ沖縄。軍民合わせ20万人もの尊い命が犠牲となった。本書のタイトルの「鉄の暴風」とは、1945年3月26日から3カ月間にわたり途絶えることなく続いた艦砲射撃や空爆のすさまじさを表現した言葉だ。1950年の初版刊行以降、沖縄戦を象徴する言葉として定着した。地形が変わるまで打ち込まれた砲爆弾、壕に逃げ込んだ住民を炙り出す執拗な火炎放射、そして民間人にまで及んだ自死の強制。本書は行動を軍とともにした記者たちが自らも体験したその壮絶な戦場の実態を、生存者をたずね克明に記録したもの。現代史第一級の史料を初文庫化。
-
4.2沖縄学の権威による沖縄食文化史入門。著者は『おもろそうし』などの古典文学をもとに琉球文化の源流を探る研究に取り組んできたが、最後の著書となった本書では、食を素材に、沖縄の歴史が描き出される。ヤマトとは異なる食材・料理・飲食風習を対外関係史から説明し、沖縄料理の中にある東南アジア文化、中国文化の影響を解説。そして、食の思い出とわかちがたく結びつけられた戦前・戦中の記憶をつづる。取り上げられるのはラフテーやゴーヤチャンプルーなどよく知られた料理から、今では幻となった伝統菓子にいたるまで幅広い。食が語る沖縄の歴史。
-
4.0
-
4.0
-
-
-
-
-
3.0
-
-
-
-
-
-
-
3.0天正十五年(1587)、豊臣秀吉は九州平定のため、大軍を率いて出陣。博多に凱旋し、戦勝祝いのさなか、「バテレン追放令」五カ条を発布した。日本でのキリスト教宣教に関する禁令である。キリシタン大名・高山右近を家臣団から排除したことと併せ、イエズス会士たちに強い衝撃を与えた。諸宗派間の平和共存を構想していた秀吉が転回をなすに至った背景には何があったのか。それは日本史上にいかなる反作用をもたらしたか――。イエズス会が支配する教会領長崎で起きた事件と、「バテレン追放令」を記す2つの文書の検証から、日本とヨーロッパの象徴的衝突に迫る。サントリー学芸賞受賞作の改訂増補版。
-
4.3
-
5.0