無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
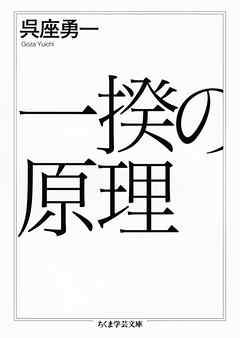
一揆といえば、虐げられた民衆が農具や竹槍を手に極悪非道な領主たちに立ち向かう、そんなイメージを抱きがちだ。しかし、それは戦後歴史学が生み出した幻想に過ぎない。史料を丹念に読み解くなかで見えてくるのは、革命や暴動といった固定観念とはほど遠い、権力者とのしたたかな折衝のあり様だ。一揆とは、暴発的な武装蜂起ではなく、既成の社会関係では対応できない危機に直面した人々が「契約」によって生みだした、新たな社会的つながりなのだ──。これまで語られてこなかった一揆の実像と、現代の社会運動にまで連なる結合の原理を、新進の中世史家が鮮やかに解き明かす。
...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。