理工作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.5生き物たちは、驚くほど人間に似ている。 ネズミは冷たい雨に濡れた仲間を助けるためにわざわざ出かけるし、シロアリは女王のためには自爆だっていとわない。カケスは雛を育てるために集団で保育園を運営しているし、ゾウは亡くなった家族のために葬儀を行う。 あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかるし、動物園の器具を壊したゴリラは怒られるのが嫌で犯人は同居している猫だと(手話で)指し示す・・・といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。 過酷な自然界において野生動物たちは生き残りをかけて日夜闘いを繰り広げている。しかし、それだけではない。野生動物たちは仲間と助け合って種をつないできた。 本書は、シドニー大学の「動物行動学」の教授であり、アフリカから南極まで世界中を旅する著者が、好奇心旺盛な視点とユーモアで、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動の数々、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。 人間もまた社会性動物であり、生き物たちは、驚くほど私たちに似ている。 動物への古い固定観念を取り払い、あなたの「世界観」が変わる瞠目のある書。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 あなたの世界が広がる! 数理モデルから学ぶ 新しいものの見方 【本書の特徴】 ●数式やアルゴリズムで世の中の現象を記述する数理モデルについて広く紹介します ●文章や図、イラストを使って、数式そのものではなく、その意味をコンパクトに伝えます ●「それが何か」「何の役に立つのか」の観点で、さまざまな数理モデルの差がわかるように配慮しています ●AIの思考回路である機械学習の数理モデルについて重点的に解説します 数理モデルは、世の中の現象を数式やアルゴリズムで記述するものです。 「難しそう」「無味乾燥」と感じる人も多いかもしれませんが、文章と同じように作り手の個性が反映される点が特徴です。 本書では、著者が半導体メーカーで培った経験をもとに、数学で世の中を表す数理モデルの世界を紹介します。 また、近年急速に発展しているAIの思考回路、つまり機械学習モデルについても重点的に解説しており、AIがどのような視点で世界を学んでいるか、その原点を学ぶことができます。 ただ、数理モデルと聞くと、大学入試のような複雑な数学を思い浮かべるかもしれません。 しかし、問題としての数学と、実際に世の中で役立っている数理モデルの数学は少し違います。 本書では、数式そのものではなく、その意味を理解することに重点を置き、文章や図、イラストを使ってコンパクトに解説します。 これにより、それぞれの数理モデルのイメージをつかむことができるでしょう。 【こんな方におすすめ】 ・数理モデルの世界に興味がある方 ・数理モデルを通して、ものの見方を学びたい方 ・AIの中身、その思考回路の原点を知りたい方 〈本書の構成〉 Chapter 01 数理モデルを理解する基礎用語18 Chapter 02 微分方程式モデル Chapter 03 最適化モデル Chapter 04 確率モデル Chapter 05 統計モデル Chapter 06 動的な相互作用モデル Chapter 07 構造を記述するモデル Chapter 08 機械学習モデル Chapter 09 数理モデルの土台となる数学 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0
-
4.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 MIT(マサチューセッツ工科大学)、ハーバード大学、スタンフォード大学などアメリカの名門大学が採用する「世界基準」の教科書! シリーズ累計30万部を突破したベストセラーの完全改訂版が、11年ぶりに登場。 第1巻 細胞生物学 2021年2月刊行 第2巻 分子遺伝学 2021年3月刊行 第3巻 生化学・分子生物学 2021年4月刊行 『カラー図解 アメリカ版 新・大学生物学の教科書』シリーズは、米国の生物学教科書『LIFE』(11 edition)から「細胞生物学」、「分子遺伝学」、「分子生物学」の3つの分野を抽出して翻訳したものである。『LIFE』のなかでも、この3つの分野は出色のできであり、その図版の素晴らしさは筆舌に尽くしがたい。図版を眺めるだけでも生物学の重要事項をおおよそ理解することができるが、その説明もまことに要領を得たもので、なおかつ奥が深い。 『LIFE』は全58章からなる教科書で、学生としての過ごし方や実験方法からエコロジーまで幅広く網羅している。世界的に名高い執筆陣を誇り、アメリカの大学教養課程における生物学の教科書として、最も信頼されていて人気が高いものである。例えばマサチューセッツ工科大学(MIT)では、一般教養科目の生物学入門の教科書に指定されており、授業はこの教科書に沿って行われているという。本シリーズを手に取る主な読者はおそらく次の三者であろう。第一は生物学を学び始めて学校の教科書だけでは満足できない高校生。彼らにとって本書は生物学のより詳細な俯瞰図を提供してくれるだろう。第二は大学で生物学・医学を専門として学び始めた学生。彼らにとっては、生物学・医学の大海に乗り出す際の良い羅針盤となるに違いない。第三は現在のバイオテクノロジーに関心を持つが、生物学を本格的に学んだことのない社会人。彼らにとっては、本書は世に氾濫するバイオテクノロジー関連の情報を整理・理解するための良い手引書になるだろう。 第1巻 細胞生物学 第1章 生命を学ぶ/第2章 生命を作る低分子とその化学/第3章 タンパク質、糖質、脂質/第4章 核酸と生命の起源/第5章 細胞:生命の機能単位/第6章 細胞膜/第7章 細胞の情報伝達と多細胞性 第2巻 分子遺伝学 第8章 細胞周期と細胞分裂/第9章 遺伝、遺伝子と染色体/第10章 DNAと遺伝におけるその役割/第11章 DNAからタンパク質へ:遺伝子発現/第12章 遺伝子変異と分子医学/第13章 遺伝子発現の制御 第3巻 分子生物学 第14章 エネルギー、酵素、代謝/? 第15章 化学エネルギーを獲得する経路/第16章 光合成:日光からのエネルギー/第17章 ゲノム/第18章 組換えDNAとバイオテクノロジー?/第19章 遺伝子、発生、進化 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アメリカの名門大学が採用する「世界基準」の教科書! 『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書』シリーズは、米国の地球学教科書『UNDERSTANDING EARTH』(8th edition)を全3巻の構成で翻訳したものである。我々の地球がどのように成り立ち、どのようなダイナミズムで進化してきたのかが、最先端の情報とともに、非常にわかりやすく解説されている。 第1巻と第2巻では、プレートテクトニクスから、マントル対流など地球内部の動き、それらによって生みだされる火山や地層、岩石変成など、地球の固体部分の大きな仕組みが手に取るように理解できるつくりになっている。 また、第3巻では、大気・海洋の大循環システムから、いまや避けられない関心事である温暖化、マクロ的視点でとらえた気候大変動など、地球の表層部分の大きなメカニズムを中心に学べるようになっている。 本シリーズは、基礎から専門的な知識までしっかりと学びたい高校生や大学生の教科書として最適であるだけでなく、さらに専門的な地球科学、惑星科学、地質学の科学書を知解するための基本知識を得ることのできる、科学に興味のある、あらゆる読者のための良質な入門書である。
-
-一人の天才の独創が生んだ相対論に対し、量子論は多数の物理学者たちの努力によって構築されてきた。その精緻化のプロセスで、彼らを最も悩ませた奇妙な現象=「量子もつれ」。因果律を破るようにみえる謎の量子状態は、どう理解されてきたのか。EPRパラドックス、隠れた変数、ベルの不等式……。当事者たちの論文や書簡、討論などを渉猟し、8年をかけて気鋭の科学ジャーナリストがリアルに再現した、物理学史上最大のドラマ。 アインシュタインが生涯信じなかった“幽霊現象”――。 最高の頭脳を翻弄した“量子の奇妙なふるまい”が、「宇宙観」に革命をもたらした! 量子力学100年の発展史を一気読み。 直観と論理の狭間で、物理学者がもがく! 一人の天才の独創によって誕生した相対論に対し、量子論は、多数の物理学者たちの努力によって構築されてきた。 数十年におよぶ精緻化のプロセスで、彼らを最も悩ませた奇妙な現象=「量子もつれ」。 たとえ100億km離れていても瞬時に情報が伝わる、すなわち、因果律を破るようにみえる謎の量子状態は、どんな論争を経て、理解されてきたのか。 EPRパラドックス、隠れた変数、ベルの不等式、局所性と非局所性、そして量子の実在をめぐる議論……。 当事者たちの論文や書簡、公の場での発言、討論などを渉猟し尽くし、8年の歳月をかけて気鋭の科学ジャーナリストがリアルに再現した、物理学史上最大のドラマ――。
-
3.7
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 冷戦、宇宙開発、新幹線、公害、ロボット、コンピューター…… 昭和100年を迎え、あの頃の未来に立って読み返す 高度経済成長期の科学誌傑作選 大正から昭和の科学史を追体験できる「子供の科学」創刊100周年記念書籍の第二弾! 1950年代から1980年代のバックナンバーの中から、科学とテクノロジーに強い現代の知の巨人、小飼弾が注目記事をピックアップして解説する。 米ソの冷戦からの宇宙開発競争、新幹線の計画から完成、いつか住めなくなると危惧された各地の公害、なくなると言われた石油、便利になる家電、マイコンとも呼ばれ日新月歩に進化したコンピューターなど、月刊誌だからこそ細かに記録された各分野の進化を体験できる一冊。当時の未来予想を答え合わせする楽しみも! ※電子版には早期購入限定電子書籍は付きません
-
-★★オープンなデータは“使ってこそ”価値がある★★ Pythonではじめる、社会を読み解くデータ分析の世界へ! 研究者・ジャーナリスト・ビジネスパーソン・公務員など、 データを活かしたいすべての人に贈るオープンデータ分析入門書の決定版! 政府統計(e-Stat)、有価証券報告書(EDINET)、米国の経済データ(FRBのFRED)、法人データ(gBizINFO)、etc...。 国内外の公的機関が提供するさまざまなデータを用い、データの取得・ハンドリング・可視化・分析の一連のプロセスを、Pythonで実践的に学びます。 「どこにデータがあるの?」 「どうやって取り出すの?」 「どう加工して、何が読み取れるの?」 そんな疑問を、豊富なコード例と実践事例からていねいに解説します。 【本書の特徴】 ・Python初学者でも安心! >データ分析の基礎(Pythonの基本操作・pandas・統計・可視化[Plotly])を詳細に解説 ・実データを用いた実践方式の分析! >e-StatやFRBのFREDなどのさまざまなAPI活用方法を具体的に紹介 ・社会・経済を読み解く力がつく! >人口、家計、金融、企業データなど、多様な統計を活用 ・すぐに実践できる! >ソースコードをすべて公開しているので、分析をそのまま再現 【実践事例も充実】 ・gBizINFOの法人データを使い、スタートアップ企業の立地を地図上で可視化 ・e-Statを活用し、ふるさと納税による地方自治体の税収の影響をパネルデータ分析 【目次】 第1章 序論 第I部 Pythonデータ分析の基礎 第2章 データハンドリングとpandas 第3章 統計の基礎 第4章 データの可視化とPlotly 第5章 オープンデータとデータ取得 第II部 オープンデータ分析の基礎 第6章 オープンデータ・経済統計・公的統計 第7章 人口データの取得・可視化・分析 第8章 家計・生活・労働データの取得・可視化・分析 第9章 金融・市場データの取得・可視化・分析 第10章 国際統計・長期経済統計データの取得・可視化・分析 第11章 法人・産業データの取得・可視化・分析 第III部 オープンデータ分析の実践 第12章 gBizINFOの法人データを用いたスタートアップ企業の分析 第13章 e-Statを用いたふるさと納税のパネルデータ分析
-
4.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ていねいな解説と授業に沿った15章立てでよくわかる。カラーなので重要なところも逃さない。例題、演習問題も充実。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆人気ブログ&YouTubeチャンネル「電気エンジニアのツボ」のわかりやすさそのままに、電気の基本、知識、技術がわかる◆ 工場、ビル、施設などの現場で電気関係の仕事を行う方に向けて書かれた本です。仕事を始めて1~3年くらいの電気エンジニアの方、電気工学・電子工学を学ぶ学生の方、転職などで新たに電気関係の仕事をすることになった方は、以下に思い当たることがないでしょうか? ★現場に配属されたばかり。基礎から学びたい ★基本的な電気作業を指示されるが、自信を持って対応できるだけの知識がない ★学校で電気工学を学んでいる。講義は理論中心で実務的な内容に触れる機会が少ない ★設備管理、設備保全などの職に就きたいが、何から学べばいいのかわからない ★現場のオペレータから設備保全の部署に異動になったばかりで困ることが多い ★「現場でどう使うのか」を実感できる教材を探しているが、そのような本が見つからない もし1つでも思い当たるなら本書はお役に立てるはずです。電気を仕事にする方々にとっての「よき先生」であるシマタケさんが、若手社員のころに「こんな内容を知っておきたかった」を1冊にまとめたのが本書です。仕事の現場で役立つ、電気の基本、知識、技術を、オールカラー+600点の図解紙面でお伝えします。 ■目次 第1章 電気の基礎知識 ──01 電源の種類 ──02 配電方式の種類 ──03 コンセントの種類と形状 ──04 導体、絶縁体、半導体 ──05 抵抗、絶縁抵抗、接地抵抗 ──06 抵抗とインピーダンス ──07 電線サイズと許容電流 ……ほか 第2章 工場やビルなどの施設にある設備 ──01 電気工作物の種類 ──02 制御盤・分電盤・配電盤・動力盤 ──03 工場における照度の基準 ──04 制御盤や分電盤でよく使用される電線・ケーブルの種類 ──05 防塵・防水仕様 ──06 防爆電気機器の種類 ──07 中央監視システムのしくみ 第3章 工場と設備の自動化 ―シーケンス制御― ──01 シーケンス制御の概要 ──02 PLC方式とリレー方式 ──03 PLCの概要 ──04 押しボタンスイッチの種類としくみ ──05 セレクタスイッチの種類 ──06 有接点リレーの概要 ──07 タイマリレーの種類 ……ほか 第4章 工具や計測機器の使用方法 ──01 過電圧カテゴリ(測定カテゴリ)と対地間電圧 ──02 テスタの使い方 ──03 機器の電流を測定 ―クランプメータ― ──04 漏れ電流値の測定 ―リーククランプメータ― ──05 ワイヤストリッパの使い方 ──06 裸端子用圧着工具の使い方 ──07 フェルール端子用圧着工具の使い方 ……ほか 第5章 図面 ──01 電気図面の種類 ──02 実体配線図の概要 ──03 シーケンス図の電気用図記号 ──04 シーケンス図の概要 ──05 シーケンス図のタイムチャート ──06 線番号の決め方 第6章 配線方法 ──01 ネジ式端子台への正しい配線接続方法 ──02 ON・OFF回路の配線方法 ──03 有接点リレーを用いたON・OFF回路 ──04 有接点リレーを用いた自己保持回路 ──05 インバータの操作部と端子台の構成 ──06 インバータの操作パネルでモータを運転するための配線方法 ──07 セレクタスイッチを用いたインバータの外部運転 ……ほか 第7章 トラブル事例とその対策 ──01 電磁開閉器のサーマルリレーがトリップしたときの対応方法 ──02 制御盤内故障診断時のテスタ活用法 ──03 制御用リレーの故障種類と原因・対策 ──04 漏電の調査方法 ■著者プロフィール シマタケ:現役の電気エンジニアとして15年以上にわたり「工場・ビル・施設」などで設備保全や生産技術に従事。生産設備の製作、改造、メンテナンス、電気設備の管理、社内基準整備、電気教育、DX推進など多岐にわたる業務を経験。「参考書では教えてくれない知識と経験」をコンセプトに、2019年よりブログ「電気エンジニアのツボ」を運営し、2020年にはYouTubeチャンネルも開設。自身が新人時代に苦労した経験を糧に、読者や視聴者の「最短・最速で知りたい情報にたどり着きたい」という思いに応えるため日々活動を続けている。
-
5.0人類最大の脅威への切り札は“ウイルス”!? 「ウイルス」と聞いてたいていの人が連想するのは「悪い」ことだろう。 人間に感染して病気を引き起こし、障害を残したり、命を失わせたりする。コロナウイルス、インフルエンザ・ウイルス、エボラ・ウイルスらは最悪の嫌われ者だ。 だが、地球には人類からすれば「善良な」ウイルスもいることをご存知だろうか。 ワクチンに使われているウイルスや、がんの腫瘍細胞だけに感染して死滅させるウイルスといったものがいる。 そして本書の主人公が、「ファージ」ことバクテリオファージだ。 彼らは細菌(バクテリア)に感染して殺すウイルスである。 細菌とウイルスの違いがよくわからないという方もいるだろう。ひと言でいえば、細菌は細胞からできている「生物」だが、ウイルスは最も簡単な場合、DNAをカプセルで包んだだけの存在で、生物とは言い切れない。 病原菌を殺してくれるウイルスがいるなら、医療に役立てられないか、と考えるのは自然なこと。20世紀初頭、ファージの発見者デレーユはこれで赤痢を治療できると示して、ファージ療法は一躍大流行したのだ。 ならばなぜ、現代ではファージ医療をほとんど誰も受けられないのか? 微妙な配合が必要なファージより簡単な治療薬として抗生物質が発見されたことが革命を起こし、西欧世界ではファージは忘れ去られたのである。 しかし、ファージ研究がわずかに続けられている場所があった。それは鉄のカーテンの向こう側、共産圏ジョージアだった……。 100年近くにわたり営々と忘れられた研究をつづけていた古めかしい研究所に、著者は足を踏み入れる! 数奇な運命をたどったファージ研究の歴史。そして今、次々現れる抗生物質耐性菌や不可解な難病への切り札として再び脚光を浴びるファージ療法の最前線、さらに科学におけるファージの絶大な貢献度まで……。 人類が避けては通れない病との戦いに不可欠な必須の知識。 そして何より、歴史に埋もれた異端の科学者たちの数奇な物語が、読み物としても抜群に面白い。 「善良なウイルス」の全貌を明かす決定版の傑作ポピュラー・サイエンス!
-
4.5
-
-「電気自動車(EV)こそが自動車の未来」と語られてきたこの10年。だが普及が進むほどに充電インフラの不足や航続距離の短さ、電池原料の偏在、寒冷地での性能劣化など理想と現実のギャップが浮き彫りになる。一方で「過去の遺物」とされたエンジンは静かに進化を続けていた。ガソリンエンジンの熱効率はいよいよ50%へと迫り、実現不可能とされたレベルに達しつつある。燃料採掘や発電などを考慮した総合的な環境性能で、地域によってはEVと遜色ないか、上回る水準になっている。 日本車メーカーはEVシフトが叫ばれる裏側でエンジン開発の歩みを止めなかった。トヨタ自動車は欧州の厳しい排ガス規制に通用する次世代エンジンを提示し、ホンダはハイブリッド車(HEV)専用エンジンを刷新した。日産は“究極の燃焼”を掲げ、SUBARUは水平対向エンジンの特性を生かしたHEVを磨き、マツダはロータリーを発電用として復活させた。HEV用エンジンから水素燃焼まで多様なアプローチを同時並行で進める日本の「マルチパスウェイ戦略」に再び世界が注目し始めた。 本書はトヨタやホンダなど7社を軸に日本勢の強みと戦略を徹底的に解説する。加えて欧州のEV偏重政策が転換を始めた背景や中国勢が40%後半の熱効率で猛追する実態などを世界の潮流変化も豊富なデータとともに示す。さらにロータリー復活の舞台裏やエンジン音の価値の行方、HEVの深化など開発現場の最新の声や周辺エピソードについても多く集めた。 EVかエンジンか――。本書を読むと二者択一ではない未来が見えてくる。エンジンが次の50年へ向けて消えることはなく、新たな進化のステージに入ったことを理解できるはずだ。
-
4.4『土 地球最後のナゾ』で河合隼雄賞受賞を受賞した著者による、書下ろし最新作! 〔前書きより〕 「土とは何なのか?」「なぜ生命や土を作ることができないのか?」という本質的な問いをあいまいなままにしておくことはできない。46億年の地球の歴史を復元し、豊かな土と生命、文明を生み出したレシピを明らかにすることがこの本の目的である。 生と死は、生物と無生物は、土でつながる。多くの陸上生物は土から命の糧を得て、やがて遺体は土の一部になる。つまり、土も変化する。土が変われば、そこで生きられる生物も変化する。40億年の相互作用の中で、地球は次の時代の主役となる生物に適した土壌を用意する。土に居場所を見つけた生物は生存権を得て、さもなければ絶滅してきた。途中でレースを降りた恐竜の化石とは違い、土はいつも陸上生物のそばで並走してきた。土は、地球の変化を見続けてきた“生き証人”としての顔を持つ。 どうだろうか。もし、足元の土が実は生命誕生や私たちヒトをも含む生命進化、今日の環境問題の根っこにまで大きく関わる46億年にわたる壮大なストーリーを教えてくれるとしたら。もう恐竜の化石にすべてを任せておくわけにはいかない。身近にありながら、普段はあまり注目されることのない土だが、私たちは土なしに繁栄していなかっただろうし、いまだに人類が人工的に作れない複雑で神秘的な力を秘めている土が未来を照らす一条の光となるにちがいない。
-
3.7常識なんてなんのその。物理に、ボンゴに、金庫やぶり、時には夜遊びも……。好奇心のおもむくまま、気の向くまま、どんなことでも本気で愉しむ。それがファインマン流の生き方。稀代のノーベル賞学者がユーモアたっぷりに語る、冒険譚のような痛快自叙伝。ベスト/ロングセラーを読みやすい文字に改版する。解説=橋本幸士
-
3.9もう人間関係、世代間ギャップ、依存症で悩まない! 脳科学者が脳卒中に学んだこと。 左脳の脳出血により、右脳の機能しかなくなったとき、脳科学者のジル・ボルト・テイラー博士は、それまでの認知機能、身体機能を失ったにもかかわらず、この上もない幸福感に包まれた。8年間のリハビリの末、すべての機能を取り戻した博士が、脳卒中の実体験と神経解剖学の科学的見地から得た新しい知見を惜しげもなく開示する。 左脳は思考、右脳は感情というステレオタイプから脱却し、脳の仕組みを知れば、考え方・感じ方の嫌なクセは変えられる。脳は、ふたつの感情、ふたつの思考、合計「4つのキャラ」のシェアハウスだ。たとえば、心と頭が別々のことを言っているときは、脳の異なるキャラ同士が争っている。キャラたちが、ひとつのチームとして協力し合えば、心穏やかな人生が手に入る。 脳は、今でも進化の途上にある。私たちは、何かことが起こったときに、感じ、考える回路を何度も使ううち、その回路だけが発達してしまい、ほかの回路を作動させることができなくなっている。けれど、それを知って、別の回路をはたらかせることができるようになれば、いつもの自分の考え方や感じ方のパターンとなっている嫌なクセを変えられるのだ。 脳科学の分野の「4つのキャラ」と、ユング心理学の「4つの元型」は符合すると、著者は言う。本書は、脳科学と心理学を融合させ、自分自身の力で、自分の「脳」を動かし、なりたい自分になる方法を教えてくれる。
-
5.0※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 物理学の醍醐味のーつは、物理法則が美しく彩られた数式の形で表されることである。本書は、「相互作用」と「対称性」に着目して、3つの相互作用(電磁相互作用、強い相互作用、弱い相互作用)を軸に、対称性を通奏低音のようなバックグラウンドにして、「素粒子の標準模型」を理解することを目標に据えた。 標準模型の基本数式を理解するためには、「テンソル解析」「群論」という数学と「場の量子論」という物理学が必要になる。これまであまり馴染みのない数式や表現に戸惑うかもしれないが、本格的な専門書や論文を読むための踏み台となるような内容と解説に心掛けたので、そのモヤモヤした気持ちをグッと堪えて、とりあえず受け入れて読み進めてほしい。その後で、気になった数式に戻って、専門書なども参考にしながら、自分で導出してみたり、その意味するところをあれこれ考えてみるとよいだろう。
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 創刊100周年を記念! 創刊から終戦までの雑誌『子供の科学』を読み直す 膨大なバックナンバーの中から、科学とテクノロジーに強い現代の知の巨人、小飼弾が、日本の科学技術発展に寄与した側面に注目して記事をピックアップ。当時の社会情勢を背景に、どんな意図で、何を解決したくてこの記事が書かれたのか、また、当時の知識人が科学の進歩をどこまで予言できているのかなどを振り返る。 特に戦争が近づいてくる様子、また戦況が厳しくなったことが読み取れる記事は必見。当時の読者の役に立とうと編集された内容は、そのまま世相を反映していることに改めて気付かされる。月刊誌だからこそ世の中の動きが細かに記録されていることにも、現代人として胸が熱くなること必至だ。 ※紙版は早期購入限定「昭和20年12月号デジタルBOOK」セットとなっております。期間内にデジタルBOOKを帯のQRコードから取得することで、戦後間もない貴重な「子供の科学」を全ページ読むことができます!(取得期限:2025年3月8日まで) 電子版では紙版ではモノクロだったページも全ページカラーで掲載(デジタルBOOK特典はありません)。
-
3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆分数の割り算なぜひっくり返す? ◆速さの問題ワケわからん! ◆食塩水まぜて楽しいか? ◆サインコサイン誰やねん ……理由を教えてもらえずに 解き方に納得していないもの、ありませんか? ◎ガチ文系なのに、入社試験で数学が必要になった! ◎ニガテ民なのに、子どもに算数を教えなきゃいけない! ◎算数につまずいたせいで、人生がうまくいかない! ……そんなあなたのための本 ニガテ総選挙No.1の速さ問題、脳が拒絶するつるかめ算や利益算、常になんとなく不安な文章問題……。疑問や不満がつもりつもって、わたしたちは算数につまずき、数学にたおれる。 何のために学び、どこにつながるのか……知っていたら、もっと頑張れたはずだった。「そういうものだから」と言い聞かせられてきた、絶妙に納得できないテーマを厳選。算数・数学に不満たらたらのケンジと、数学好きの兄貴が、対話しながらひも解いていく。 いま学んでいる生徒さんにも、子どもに算数を教えなきゃいけない保護者にも、長年のしこりを抱える大人たちにも。 ニガテ勢のかゆいところに手が届く、たくさんの「そうだったのか!」をつめこんだ画期的一書。 【目次より】 第1章 方程式 ◆何で勝手にXっておいてんだよ! 何と何をイコールでむすぶんだか、さっぱり分からねえよ! 【ポイント】 方程式 第2章 〇〇算 ◆つるかめ算 どっから来たんだ、ツルとカメ! なぜ突然、足の本数を数えだしたっ!? 【ポイント】 つるかめ算 ◆仕事算 「ある仕事を2人で協力すると何時間かかるか?」だと…… そんなの、2 人の仲の良さ次第だろうが!! ◆利益算 原価とか、定価とか、売価とか、利益とか…… いちいち言葉がむずかしいんだよ! ◆濃度算 しょっぱい水を作って混ぜ合わせて、何がしたいんだ! しょっぺえのは人生だけで十分だぜ! 【コラム】 数学って、どうして解けないと悲しくなるの? 第3章 四則計算 ◆いまだに引き算は不安だぜ! なんで数学得意な人は「あ、これは××算だな」ってすぐ分かるんだっ!? ◆繰り下がりたくても、その位、0なんだよ! 0なのに、どうやって借りてくるんだ!! ◆割り算、ややこしいんだよっ! 割り切れない思いを抱えてこそ、大人ってもんだろうが! ◆かけ算が先で、足し算が後ぉ? 後回しにしたら、足し算がかわいそうじゃねーか!! ◆□×0=0だよな? だったら、□÷0 をしたら、答えは0 になるはずだろうが! 【ポイント】 0のルール 【コラム】 文章問題の公式の意味が分からない 第4章 分数 ◆分数とか、この世にいらねえだろうがっ! ◆足すだけなのに、ややこしすぎんだよ、分数! 通分ってのは、どこの校則だ!? ◆分数のかけ算、「斜めに約分」って、なんなんだっ! ◆分数の割り算…… 「とにかくひっくり返せばいいんだよ」って、なんだそれ!? 【コラム】 家庭内で、算数や数学に慣れ親しむ 第5章 小数 ◆小数の計算、ああしろこうしろって細かく言われたけど、 俺は何も納得してねぇぜ! 【ポイント】 小数の文章題 【コラム】 桁を理解する 第6章 マイナス ◆「とにかく覚えろ」と言われたマイナスの計算。 僕たーち、私たちはー……納得していません! ◆(マイナス)×(マイナス)がプラスになるとか ポジティブにもほどがあるだろ!! 【コラム】 文章問題が苦手 第7章 比 ◆なんなんだよ、比って!? そんなん使ったら、かえってややこしくなるだろうが!! 【ポイント】 比の文章問題 第8章 速さ ◆目に見えねぇんだよ、速さなんて! 見えないものを、どうやって解けってんだ! ◆2人同時に動くなよ! 片方を計算してる間にもう片方も動き出しちまうじゃねえか! ◆おい兄と弟、一緒に池の周りをまわってやれよ! お互い、たった一人のきょうだいじゃねぇか。 ◆出る前に、忘れ物がないか確かめとけよ? 余裕をもって家を出れば、追いかけないで済むんだぜ。 【ポイント】 速さの文章問題 第9章 その他 ◆動点Pはなぜ動くのか!? 落ち着け、点P! 頼むから、じっとしてろ。え……点Qも!? ◆サイン・コサイン・タンジェント、日常生活で使ったことないぜ、コノヤロー。 この知識、ほんとに役に立ってんのか!? 【コラム】 新しい単元との出会い まとめ: 一度にぜんぶ理解しようとしなくてもいいらしいぜ!
-
4.0チャールズ・ダーウィンの『種の起源』は、生物の進化がなぜ起こるのかを自然淘汰で説明し「神が天地創造の際にすべての生き物を完璧な姿でつくった」というキリスト教の世界観を覆した。コペルニクスの地動説と並び、人類に知的革命を起こした大名著である。 しかし、『種の起源』はかなりわかりにくいので、内容がきちんと理解されていない。「ダーウィンは『種の起源』で、人間の進化については一切述べていない」とか「『種の起源』によって神を否定した」など、もし読んでいればすぐに間違いだとわかるコメントが、後を絶たない。 日本でいえば江戸時代に書かれた本なので、現在からみれば間違いがたくさんある。けれど、専門的な知識がないと、どこが正しくてどこが間違いかを判断するのは難しい。これが、小説や哲学などの古典と科学書の古典を読む際の大きな違いだ。 本書は、そんな『種の起源』の重要なポイントを押さえながら、最新の生物学の知見も身につく本。 主な特徴は以下の5つ。 1)『種の起源』より薄くて、短い時間で読める。 2)現在の科学からみて、正しいか正しくないかを明記する。 3)最新の進化学の知見も、読み物として楽しく解説する。 4)『種の起源』を読んだ人の記憶に残るであろう部分は、科学的に間違っていても省略しない(もちろん間違いであることは明記する)。 5)『種の起源』を読んだときに記憶に残らないであろう部分は省略する。 つまり、読者の頭の中に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じ記憶が残るような本、一言でいえば、『種の起源』を読んだふりができる本を目指す。
-
4.1
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 太陽系の外に広がる広大な宇宙の謎を探る旅へようこそ。星団・星雲、銀河、ブラックホール、そして宇宙の果てへ。旅の主役は500枚以上におよぶ圧倒的に美しい写真と想像図。新発見の太陽系外惑星から膨張宇宙、星団や銀河が作る大規模構造、星の形成、恒星での元素合成、惑星や生命の起源まで最先端の情報が満載。地上の大型天体望遠鏡や宇宙望遠鏡の発展によって「ヴィジュアルサイエンス」へと進化した深宇宙天文学の集大成。
-
-
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 実践的な意思決定力を身につける! Pythonと因果推論でデータ分析の壁を乗り越える! 本書では因果推論の活用を通じて、効果検証や相関と因果関係の違いといった、データ分析の現場でよくある問題を解決する方法を紹介します。 さらに、因果推論の基礎から、機械学習や時系列解析との組み合わせ、さらに因果探索まで学習することにより、因果推論を軸として幅広い問題に対応可能になります。これにより、データ活用の価値を高められます。 本書では、具体的な事例や豊富な図を用いて、因果推論の基本的な概念や手法を分かりやすく解説します。また、Pythonコードを用いた実装を通じて、因果推論を実務に応用するスキルを身につけることができます。 本書の特徴 ・実践的な学習と活用 因果推論の基礎だけでなく、ビジネスケースでの活用方法まで、分析手法や企業での活用例の解説をし、Pythonコードを用いた実装を通じてデータ分析のスキルを深めます。 ・直感的な理解のための全体像の把握と図解 因果推論、機械学習、時系列解析を図で構造的に解説します。 ・意思決定のためのガイドライン 最適な分析を行い、より良い意思決定に導くための具体的なガイドラインを提供し、データドリブンな意思決定を支援します。 はじめに 第1章 因果の探求から社会実装 第2章 因果推論の基礎 第3章 基本的な因果推論手法 第4章 因果推論高度化のための機械学習 第5章 因果推論と機械学習の融合 第6章 感度分析 第7章 因果推論のための時系列解析 第8章 因果構造をデータから推定する因果探索
-
4.0数十トンもある雲が落ちてこないのはなぜ? 雨粒はどのようにできる? 高原は太陽に近いのになぜ涼しいの? ジェット気流って何? 高気圧や低気圧はなぜできるの? 台風はどうやって発達する? 気象にまつわる素朴な疑問から、気象と天気の複雑なしくみまで、その原理を詳しく丁寧に解説。「しくみがわかる」を重視した入門書です。気象用語の多くを網羅し、気象予報士を目指すスタートにも最適です。 たとえば、下記のような「原理(しくみ)」を解説しています。 ・「湿った空気」は重くない ・「赤外線のジャグリング」で気温が決まる ・「気圧のセオリー」でわかる低気圧と高気圧 ・「ジェット気流が低気圧・前線を発達させる 本書は、2011年3月に出版され、23刷まで増刷された『図解・気象学入門』の改訂版です。この12年の間、それまではほとんど聞くことのなかった「線状降水帯」といった気象用語が天気予報で盛んに使われるようになりました。「今までと違う」と感じられる異常気象が毎年のように現れ、気象を理解することへの関心はますます高まっているのではないでしょうか。 改訂版は、そのような変化に対応できるよう、わかりやすいと好評であった内容はそのままに、新しい気象用語を加えました。さらにわかりやすくするための修正や補充を行った最新完全版となっています。 1章 雲のしくみ 2章 雨と雲のしくみ 3章 気温のしくみ 4章 風のしくみ 5章 低気圧・高気圧と前線のしくみ 6章 台風のしくみ 7章 天気予報のしくみ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 天文年鑑2026年版は、2026年に起こる天文現象の予報と解説(全国8都市における日の出入り・月の出入りの時刻や月の出・月の入りの時刻をはじめ、毎月(12ヵ月)の星空、日食や月食などの食現象、各惑星の動き、準惑星や小惑星の動き、彗星の出現予報、流星群の予報など)や、2024年夏~2025年夏に起こった天文現象の観測結果を収録しています。 2026年版の巻頭口絵では、2025年9月8日に3年ぶりに見られた皆既月食の様子をはじめ、8月20日に出現した太陽の巨大プロミネンスなどの貴重な画像を掲載しています。 2026年に起こる天文現象として注目したい現象は,まず年初の 1月4日のしぶんぎ座流星群の極大です。年始の澄みきった空の元で流星群が楽しめます。 さらに3月3日の宵には皆既月食が起こります。皆既食の継続時間が約1時間23分で、日本全国で楽しめる月食です。ぜひ見ておきたい現象です。 また、 8月13日のペルセウス座流星群の極大日には、アイスランドやスペインで皆既日食が起こります。 そのほか、レグルス食、プレセペ星団食、プレヤデス星団食、ふたご座流星群など、2026年も様々な天文現象が起こり目が離せません。天文年鑑を手に、星空や天体観測を楽しみましょう。 ●2026年の注目の天文現象 1月 4日:しぶんぎ座流星群が極大 1月 7日:レグルス食 3月 2日:レグルス食 3月 3日:皆既月食 6月20日:プレセペ星団に金星が侵入 8月13日:皆既日食(アイスランド,スペイン) 8月13日:ペルセウス座流星群が極大 10月11日:プレセペ星団に火星が侵入 11月 2日:プレセペ星団食 11月24日:プレヤデス星団食 12月14日:ふたご座流星群が極大
-
5.0★基礎知識から構築、評価、改善まで! 実践に使える本格派の一冊★ AIエージェントの開発に初期から取り組み、実務で使ってきた著者陣がおくる、 「現場」で使える、プロになるための一冊。 ヘルプデスク、データ分析、情報収集、マーケティングの具体的なAIエージェントの構築方法に加え、 AIエージェントの評価や改善までを網羅的に学べます。 電通総研、Algomatic、ジェネラティブエージェンツの各社の取り組みの紹介も! 「第1部 AIエージェントを知る」は、AIエージェントを作り、現場で活用するための知識をまとめています。1章ではAIエージェントの定義や重要な性質、ビジネス状況、活用例を説明します。2章は技術観点でAIエージェントを構成する各技術要素の説明と実装上で気をつけることを説明しています。 「第2部 AIエージェントを作る」では、AIエージェントを開発していきます。まずは3章で、AIエージェントの開発に必要な共通技術を解説します。4章では、ヘルプデスクの質問応答を題材にPlan-and-Execute型エージェントの実装をおこないます。5章では、データドリブンな意思決定業務を題材にデータ分析からレポート作成まで行うエージェントを実装します。6章では、情報収集業務を題材にarXiv上の論文を探索しレポートするエージェントを実装します。7章では、マーケティング業務を題材にロールプレイングによる意思決定支援やマルチエージェントによる会話型推薦エージェントを実装します。読者がすぐに実装を再現でき、読者の環境に合わせて改変して精度を高め、業務利用できることを意識しています。 「第3部 AIエージェントを現場で使う」では、実際にAIエージェントのプロジェクトを進めるうえで、避けては通れない課題について広く解説します。評価方法、エラー分析、UX、セキュリティ、モニタリング、継続的な精度改善方法を紹介します。10章ではAIエージェントの実用化に向けた著者陣の各社の取り組みを解説します。 【おもな内容】 第1部 AIエージェントを知る - 第1章 AIエージェントの概要 - 第2章 AIエージェントの構成 第2部 AIエージェントを作る - 第3章 AIエージェントの開発準備 - 第4章 ヘルプデスク担当者を支援する - 第5章 データ分析者を支援する - 第6章 情報収集者を支援する - 第7章 マーケティングを支援する 第3部 AIエージェントを現場で使う - 第8章 AIエージェントの評価 - 第9章 AIエージェントの活用 - 第10章 各社のAIエージェントの実用化に向けた取り組み
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【目次】 Ⅰ 建築基準法 1 総則 1.1 法の目的 1.2 法の構成 1.3 用語の定義 1.4 法の適用除外 1.5 既存建築物に対する制限の緩和 例題(解答と解説) 1.6 面積・高さ等の算定方法 例題(解答と解説) 1.7 建築手続 例題(解答と解説) 2 一般構造 2.1 敷地の衛生及び安全 2.2 大規模の建築物の主要構造部等 2.3 採光・換気 2.4 天井高,床高,遮音構造 2.5 階段 2.6 便所 例題(解答と解説) 3 構造規定 3.1 構造耐力・計算に関する規定 3.2 構造部材の耐久性に関する規定 例題(解答と解説) 4 耐火構造,防火構造,防火区画等 4.1 耐火構造と耐火建築物 4.2 準耐火構造と準耐火建築物 4.3 防火構造 4.4 準防火性能を有する外壁の構造 4.5 特定防火設備と五つの防火設備 4.6 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 4.7 防火区画等 4.8 界壁,防火上主要な間仕切壁,小屋裏隔壁 4.9 自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物 例題(解答と解説) 5 避難 5.1 適用される建築物 5.2 廊下の設計基準 5.3 直通階段の設計基準 5.4 避難階段・特別避難階段を設けるべき階の区別 5.5 内装制限 5.6 避難上の安全の検証と避難規定の適用除外 例題(解答と解説) 6 建築設備等 6.1 給水,排水その他の配管設備の設置及び構造 6.2 電気・避雷設備の設置及び構造 6.3 エレベーター,エスカレーターの構造 例題(解答と解説) 7 道路 7.1 道路の定義 7.2 私道の築造基準 7.3 道路と敷地 7.4 道路内の建築制限 7.5 私道の変更又は廃止の制限 7.6 壁面線の指定 例題(解答と解説) 8 用途地域 8.1 用途地域及び地区の種類 8.2 用途地域の種別 8.3 用途地域別主要用途の制限一覧 8.4 特別用途地区等 8.5 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置 例題(解答と解説) 9 建築物の形態規制 9.1 容積率の制限 9.2 建率の制限 9.3 第一種,第二種低層住居専用地域・田園住居地域の外壁の後退距離 9.4 建築物の敷地面積 9.5 高さ制限 9.6 日影による中高層の建築物の高さの限度 9.7 高度地区,高度利用地区,特定街区,地区計画等 9.8 防火地域又は準防火地域内の建築物 9.9 敷地内の空地及び敷地面積の規模(総合設計制度) 9.10 一定の複数建築物に対する制限の特例 例題(解答と解説) 10 その他 10.1 建築協定 10.2 建築審査会 10.3 仮設建築物に対する制限の緩和 10.4 工作物に対する準用 10.5 工事現場の危害防止 10.6 建築物の敷地が区域,地域,地区の内外にわたる場合の措置 10.7 罰則 10.8 雑則 例題(解答と解説) 複合問題 Ⅱ 建築士法 1 総則 2 建築士の業務 3 免許及び登録 4 罰則 例題(解答と解説) Ⅲ 都市計画法 例題(解答と解説) Ⅳ 建設業法 例題(解答と解説) Ⅴ 消防法 例題(解答と解説) Ⅵ 住宅の品確法 例題(解答と解説) Ⅶ バリアフリー法 例題(解答と解説) Ⅷ耐震改修促進法 例題(解答と解説) Ⅸ 景観法 例題(解答と解説) Ⅹ 建築物省エネ法 例題(解答と解説) その他の法令 例題(解答と解説) 重要語句
-
-
-
-法改正にも完全対応! 1級建築士・学科試験なら、要点解説と問題がセットになったこの1冊! 学科試験に合格するには、基本的な知識を効率的に身につけ たくさんの問題を解いてさらに理解を深めつつ、問題に慣れることが重要です。 本書は【要点解説】と【問題】を1冊にまとめて学科試験をサポートします。 【要点解説】では、学科試験で知っておくべき内容を簡潔に解説。 効率的に知識を得ることができます。 【問題】では、これまで何度も試験に出てきた重要ポイントから 最近の試験の傾向を反映した様々な問題を掲載。 重要なポイントや分かりにくい問題には、詳しい解説が載っているので 正解や解答を導き出すポイントが分かります。 独学で試験を受けようとしている方にも 問題数も2000以上あるので、とにかく問題を解きたいという方にもお勧めです。
-
4.2「直観力」「やる気」「リスク評価」…… 感情や情動は生命の進化がもたらした究極の能力だ! 最先端の「感情神経科学」が明らかにした、 感情や情動の驚くべき世界。 今、「感情神経科学」は大革命のさなかにある。 そして、かつては「的確な判断の邪魔をするもの」とされてきた感情や情動は、 進化がもたらした生存のための最強の能力であることが明らかとなっているのだ。 自分の情動状態を知り、感情を手なずけ、活用するための、 最先端科学の知見が満載の書。 ★本書で得られる知見★ ・感情や情動は、進化がもたした生存のための卓越した能力である ・人は情動がなければ何も行動を起こせない ・あなたの意思決定は、ポジティブな状態か、ネガティブな状態かという 「コア・アフェクト」に大きく影響される ・やる気も鉄の意志も情動によってもたらされるが、 それらは睡眠不足や加齢によって衰えてしまう。 ・喜びやポジティブな情動は人を創造的にし、リスクを取るように促す。 ・悲しい気持ちのときは、より現実的で正確な判断を下せる。 ・空腹感は(食べ物に限らず)ものを手に入れることを促し、 嫌悪感はものを手放すことを促す。 ・「欲しい(欲求)」と「好き(嗜好)」は脳の別の回路によるものである (「好きではないのに欲しい」という衝動も生じうる)。 ・情動は伝染する。幸せな人に囲まれていると幸せになれる。 ・社会的な成功を収めている人は、他人の感情を理解したり、 自分の情動をコントロールできるなど情動的知能が高い。 ・自分の情動プロファイルを知れば、感情を手なずけていつでも役立たせられる …… 「情動状態のダイナミクスを意識することは、人生の成功に欠かせない要素の一つである。 やる気を出したり、衝動を抑えて気分を整えたり、他人に適切に対応したり上で役に立つのだ」 (「第2章 情動の目的」より)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 建築設備士試験対策の決定版 建築設備士試験対策用のテキストです。 「建築知識一般」「建築法規」「建築設備」の3課目を収録。 節の終わりには一問一答を掲載。インプットした知識の定着を行うことができます。 2次試験対策として、設計製図の基本知識も収録。 巻末には模擬試験を収録し、試験前の総仕上げを行うことができます。 【目次】 1章 建築一般知識 2章 建築法規 3章 建築設備 4章 第二次試験対策 5章 模擬試験 【アプリ版】 本書収録の一問一答と模擬試験を収録した学習アプリです。 通勤・移動・昼休みなどのスキマ時間を使い、 反復学習や試験直前期の総仕上げなどを行うことができます。 本書と併せて活用することで、合格力をさらに高めることができます。 ]ぜひご利用ください。 *アプリは本書とは別売です。 *Google PlayまたはApp Storeからダウンロードすることができます。
-
3.8皮膚はさまざまな能力を併せ持った「スーパー臓器」です。有害な化学物質や病原体の侵入を防ぐ物理的バリアであるともに、人体最大の免疫器官であり、無数のセンサーが埋め込まれた感覚器官です。 皮膚組織の分子レベルが解明が進んだことで、これまでからだを覆う「薄皮」のように思われてきた皮膚には、生命活動にかかわるさまざまな精緻なしくみが備わっていることがわかってきました。21世紀に入ってからの皮膚医学の進展は目覚ましく、毎年のように教科書を書き換えるような発見が相次いでいます。本書は、人体最強の臓器と呼ばれる皮膚の謎に、最新の科学的知見を元に迫ります。 ここまでわかった万能の臓器「皮膚」の謎 ・人が温度を体感できる「からくり」がわかった ・皮膚をかくと、かゆみが静まる驚きの理由 ・ヒトが「裸のサル」になった必然的理由とは? ・アトピー性皮膚炎の原因遺伝子がわかった ・いかに皮膚は老化するのか? ・喘息などのアレルギー発症も、アレルゲンの皮膚侵入が引き金になる ・AIの診断能力はすでに一流の皮膚専門医をしのぎうる (本書の内容) はじめに 第1章 そもそも皮膚とはなにか? 第2章 皮膚がなければ、人は死ぬ ―生体防御器官としての皮膚 第3章 なぜ「かゆく」なるのか? 感覚器官としての皮膚 ―感覚器官としての皮膚 第4章 動物の皮膚とヒトの皮膚 109 ―生き物が変われば皮膚も変わる 第5章 皮膚の病気を考える ―どんな病気があるのか? 第6章 アトピー性皮膚炎の科学 ―現代人を悩ます皮膚の難病 第7章 皮膚は衰える ―皮膚の老化とアンチエイジング 第8章 未来の皮膚医療はどう変わる? 239 番外編 研究者になるための体験的・人生ガイド
-
-
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 海の近くに行けば、比較的容易に出会うことのできるカモメですが、その観察は簡単だと思われがちです。 しかし、実際はカモメの観察はとても難しいのです。 カモメの成鳥は、夏と冬で大きく外見が異なりますが、その識別はそれほど難しくはありません。 難しいのは、同じ種でも、成長過程(おおよそ1~4年)で刻々と姿が変わり、その姿が成鳥とまったく異なる点になります。 実際の観察では、同一種の群れで中でも群れの中で複数の外見があり、さらに他の種が混じると判別が極端に難しくなります。 そのためカモメの観察は、バードウオッチャーの間では、とても難しく奥が深いとされています。 本書では、カモメの観察方法を解説した上で、初心者の方がカモメの識別方法が分かるよう、カモメの大きさや各部位の色彩や形の違いをチャートにした検索図を用います。 さらに、カモメを観察をする上で難しいとされる識別のポイントを、各年齢における差異、類似種の見極めのポイントなど、詳しく解説します。 このほかカモメの種ごとのページ以外にも、「雑種」や「世界のカモメ」「カモメ類の雌雄差」「大型カモメ類の換羽状態の見方」などの項目も設け解説しました。 カモメの観察の難しさを分かりやすくしてくれるるのが、この「日本のカモメ観察図鑑」です。 カモメに興味があり、じっくり観察したい人、バードウオッチの深い世界に入り込みたい人に、おすすめです。
-
-すでに半世紀以上、生物学は「情報」すなわち遺伝子を中心に回り、遺伝情報がエネルギーと物質の流れを形作るという生命観を奉じてきた。本書はその関係を転倒させる。20年前、ミトコンドリアの重要性とその進化的な意義を、ほとんど予言的とも言える慧眼で指摘した著者が、このテーマの最深部に分け入り、またもや斬新な生命像を引き出した。「クレブス回路」について予備知識のある人は、一般には少ないだろう。それは半世紀以上もの間、学術的にも退屈な、単なる糖代謝の経路と目されてきた。だが最近はこの回路の可逆性や可変性に着目した研究が進んでいる。本書はこの回路を、生成的で可逆的でもある代謝の中枢として捉えなおす。回路の起源は生命誕生の時にまでさかのぼり、その見過ごされてきたダイナミクスが、かつては複雑な動物の進化の鍵となり、いまも身体の生死を握っているというのだ。私たちにとってのクレブス回路の意味を一変させる第4章、がんの動態と代謝を結ぶ第5章はとくに読み逃せない。著者は異能の科学者たちによる発見の物語もふんだんに織り交ぜながら、読者を超ミクロの世界へと導いている。生化学は込み入っているが、大づかみにでも読み進めてみてほしい。生命の起源、進化、がん、老化の理解を更新する驚きの生命論だ。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、オンプレミスやクラウドでシステム構築に携わってきたエンジニアが、「Microsoft Azure」を使って設計、構築を進める上で知っておくべき「アーキテクチャ設計の考え方」を体系的に整理したものです。 Azureならではのアーキテクチャのポイントを、実践の場で役立つ「設計書」という形でまとめました。Azureが初めてでも読み進められるように、基本概念からアーキテクチャの原則、サービス選定の理由、運用設計のポイントまで、順を追って解説しています。 Azureでは数百を超えるサービスが提供されており、その数は今も増え続けています。どのサービスを選択し、どのように組み合わせればよいのか。アクセンチュアのクラウドソリューションを支えるメンバーが、自身の経験とノウハウを踏まえて、具体的に分かりやすく解説します。
-
-★★データベースの未来を見据える、絶好の一冊!★★ RDBの堅牢な信頼性と、NoSQLの圧倒的なスケーラビリティ ――その両方を兼ね備えた次世代データベース、それが「NewSQL」です。 いったい何が「新しい」のか? その革新的なしくみとは何か? NewSQLを支える要素技術や、最大の特長である分散データベースの動作を、データベースのプロが徹底解説! ビッグベンダーが次々と参入する代表的なNewSQL製品の特長を深掘りします。 本書で扱う主なNewSQL製品:Google Cloud Spanner、TiDB、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Aurora DSQL 世界中の企業で、いまNewSQLの導入が急速に進んでいます。 NetFlix、Pinterest、eBay、SpaceX、LinkdIn、レバテック、DMM.com、みんなの銀行、楽天などがすでに活用中。 ◎実際のユースケースを通じて、NewSQLの「使いどころ」が見えてきます!◎ 【目次】 第1章 序論 ――なぜいまNewSQLが注目されているのか 第2章 アーキテクチャから見るNewSQLへの進化 第3章 NewSQL製品ごとのアーキテクチャと機能 第4章 NewSQLの要素技術 第5章 NewSQLにおける分散トランザクション 第6章 NewSQLの標準SQLへの対応状況 第7章 NewSQLのユースケース
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 量子力学の初学者向けテキスト決定版! はじめて量子力学を学ぶ人がつまづくことのないように、一歩一歩ていねいに解説。 必要な前提知識は大学1年生レベルの数学と物理のみです。 物理を専門としない学生向けの講義を担当した著者の経験から、「波動力学」のみを用いて容易に原子の話題(5章)までたどり着けるようにしました。 その後、6章で線形代数の基礎を学び、「行列力学」へと学びを進めます。 また、物質科学では、レーザー光や超伝導、磁性などの「量子力学らしい」魅力的な現象があります。 これらの現象の本質的な理解を目指して、第二量子化や相対論的量子力学、量子もつれなど、一段上のレベルの入り口までをていねいに解説します。 量子力学の本格的な勉強に進む前の足慣らしとしても最適な一冊です。 【目次】 第1章 序論 第2章 波動と波動方程式 第3章 波動関数の一般的性質 第4章 1次元におけるシュレディンガー方程式 第5章 3次元におけるシュレディンガー方程式 第6章 線形変換 第7章 行列と量子力学 第8章 ハイゼンベルグの運動方程式 第9章 角運動量とスピン 第10章 摂動論 第11章 フォノンとフォトン 第12章 多粒子系の波動関数 第13章 第二量子化 第14章 相対論的量子力学 第15章 量子もつれ ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.4著者のピダハン研究を、認知科学者S・ピンカーは「パーティーに投げ込まれた爆弾」と評した。ピダハンはアマゾンの奥地に暮らす少数民族。400人を割るという彼らの文化が、チョムスキー以来の言語学のパラダイムである「言語本能」論を揺るがす論争を巻き起こしたという。本書はピダハンの言語とユニークな認知世界を描きだす科学ノンフィクション。それを30年がかりで調べた著者自身の奮闘ぶりも交え、ユーモアたっぷりに語られる。驚きあり笑いありで読み進むうち、私たち自身に巣食う西欧的な普遍幻想が根底から崩れはじめる。とにかく驚きは言語だけではないのだ。ピダハンの文化には「右と左」や、数の概念、色の名前さえも存在しない。神も、創世神話もない。この文化が何百年にもわたって文明の影響に抵抗できた理由、そしてピダハンの生活と言語の特徴すべての源でもある、彼らの堅固な哲学とは……? 著者はもともと福音派の献身的な伝道師としてピダハンの村に赴いた。それがピダハンの世界観に衝撃を受け、逆に無神論へと導かれてしまう。ピダハンを知ってから言語学者としても主流のアプローチとは袂を分かち、本書でも普遍文法への批判を正面から展開している。
-
5.0「「リボソーム」という言葉を出すと、科学者でさえたいてい、ぽかんとした顔になる」(本文より)リボソーム、それはヒトだけでなく、動植物や細菌にいたるまであらゆる生命のタンパク質をつくり、生命活動を支える重要な分子機械である。人間の眼には見えないこの小さなマシンは、どんな形状をしていて、どんな風に動いているのか。その構造と機能を解明した功績で2009年にノーベル化学賞を受賞したインド出身の生物学者が、秘密解明までの日々を、200名を超える科学者たちの貢献を交えて語る。インドから米国へ、さらに分子生物学のメッカ、英国ケンブリッジのMRC-LMBへ。物理学で博士号を取得し、経験もコネもなかった著者が生物学の道に進路変更して、第一人者となるまでにはどんな苦労があったのか。鍵となった研究手法の解説から、キャリア選択の迷い、ライバル研究者との競争や政治的な駆け引きまで、繊細なユーモアあふれる文体でこのうえなく誠実に綴った、自伝的科学エッセイの傑作。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、統計学の基礎を「読むだけで理解する」のではなく、Excel操作を通して「体験的に身につける」ことを目的とした入門書です。 統計学を初めて学ぶ大学生や初心者を主な対象とし、予備知識がなくても進められるようExcelの操作を丁寧に解説。各章は例題から始まり、関数やグラフを用いた操作を重ねることで段階的に内容を理解できる構成となっています。 難しい概念をわかりやすく簡潔に説明し、作業を通して考え方を実感できるよう工夫しているだけでなく、例題直後の問題で自分の理解度を確認しながら進めることができます。また各節の最後には、Excelを使わずに考える確認テストを設け、思考力の定着を図っています。 正規分布や中心極限定理、推定、検定まで、統計学の基礎を無理なく学べる一冊です。
-
4.0【岡野原大輔氏 推薦!!】 これまでのロボットには困難だったタスクにどう挑むのか。 「フィジカルAI時代」の中核技術を理解するための指針となる一冊。 ★★生成AIによる大変革、次の主役はロボット!★★ ■ロボットを知らなくても読める! この大変革の流れを知らずして、AI・情報科学の未来は語れません。 AIに関心のある研究者、エンジニア、マネージャー、起業家―― 技術の潮目をつかみたいすべての人に贈ります。 ■AIが“世界に接する”時代へ! 生成AIは、いまや言語や画像にとどまりません。 LLMを超え、より大規模でマルチモーダルなモデルが「基盤モデル」です。 それがロボットと結びつき、世界に接するAIが生まれています。 ・「あれ取ってきて」という指示に応答するロボット ・みずからコードを書いて自分を制御するロボット ・未知の環境でも、試行錯誤して成果を出すロボット かつてできなかったことが、基盤モデルの力で実現しています。 ■語り尽くすのは、最前線を走る若きツートップの研究者! 「そもそも、基盤モデルとは何なのか?」 「基盤モデルでロボットの何が変わるのか?」 「基盤モデルをロボットにどう使うのか?」 技術の本質を捉えたい人に向けて、深く・わかりやすく語り尽くします。 【目次】 第1章 基盤モデルとロボット 第2章 基盤モデルでロボットの何が変わるのか 第3章 これまでのロボット 第4章 基盤モデルができること 第5章 基盤モデルをロボットにどう使うか 第6章 ロボット基盤モデル 第7章 今後の展開
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 とっつきにくい熱力学を多くの事例でわかりやすく解説。数式の途中経過はできるだけ省略せず丁寧に記述。 本書は、初等熱力学について述べた第 1 部と統計熱力学について記述した第 2 部から構成されている。 第 1 部では、第 1 章から第 4 章までが純物質(1 成分系)を、第 5 章から第 8 章までが多成分系を扱い、第 4 章の後半では具体的な純物質の相平衡現象に、第 7 章と第 8 章では具体的な多成分系の相平衡と化学平衡現象にそれぞれ熱力学を応用している。 また、第 2 部では、単純な統計学を利用して、気体・固体・液体状態にある様々な分子の集合体を考察している。一般的な教科書では、古典力学(解析力学)と量子力学から出発して統計熱力学を体系的に説明しているものが多い。しかしながら、非常に多数の分子がかかわる古典力学・量子力学になじみのない化学系の学生さんの多くは、その出発点で挫折することが多いことを鑑みて、本書では統計熱力学の体系的な記述をあえて避けた。 本書の第 1 部は、大阪大学の理学部 1 年生に提供していた熱力学の講義がベースとなっている。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★書いてみえる! 解いてわかる!!★ 「抽象的で難しい」と敬遠されがちな位相空間。でも、この本でまなぶと──。 集合や写像は数学を深く理解するために必須の言語であり、集合に開集合系を定めてできる位相空間は極限操作や連続性を考察するために欠かせない概念である。現代数学は位相空間という舞台装置の上に成り立っているといっても過言ではない。 理解を助けるための図が多く、自習用の詳細解答付き。さあ、ペンをもって、手を動かしてみよう。集合・位相の実践大全! 【本書の特徴】 ●全体のあらすじが見渡せるよう、冒頭に「全体の地図」を設けた。 ●写像や同値関係について丁寧に示すとともに、well-definednessについても具体例を挙げて詳しく述べた。 ●位相空間に重点を置き、その基礎的事項について平易にまとめた。 ●位相空間の良い例であるユークリッド空間やベクトル空間について、例題や節末問題でくり返し登場させた。 ●位相空間の位相的性質(連結性・コンパクト性・ハウスドルフ性など)やコンパクト化、距離空間の完備化などについての記述を充実させた。 ●数学の専門書でしばしば登場するドイツ文字について「ドイツ文字の一覧」(フラクトゥーア体と筆記体)を見返しに掲載した。
-
-
-
3.0ビッグバン、星の進化、超新星、太陽系の誕生――ロマンがあって、果てしなく謎に包まれていて、実はどこかで繋がっているという不思議。謎解きのように辿れば実はとても奥が深い! 本書は、最先端の研究から導き出していく考察系科学論です。 ***「宇宙はビッグバンから始まった」「夜空は暗い」「太陽には寿命がある」どれも、科学がたどり着いた「事実」です。でも、それがどのように発見され、なぜそう考えられるようになったのか、知っていますか? 本書を通して、知識に奥行きが生まれることで、夜空に広がる宇宙が、ただ“知っている”だけの場所ではなく、思わず「夜空を見上げてしまうほどワクワクする」――そんな小さな高揚の入り口になれば幸いです。――著者より*** “わかったふり”をアップデートさせれば、ただの教養がもっと深くなっていきます。過去・現在・未来、そして物質の起源から宇宙空間への、神秘的な「知の旅」へご案内します!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 4科目一体型テキストの決定版! 【概要詳細】 大人気試験対策講座がギュギュッと1冊に! 本書は、電験三種(電気主任技術者第三種)の試験対策テキストです。試験対策の指導者として高い人気と実績を誇る著者が試験内容を徹底的に分析し、「合格するための知識とテクニックの習得」にこだわって解説しました。 「理論」「機械」「電力」「法規」の全科目に対応、かつ電験三種に必要な「数学」まで網羅しています。必要なポイントのみを解説しているので、広範な試験範囲を無駄なく効率よく学べます。 また、「2抵抗の並列合成抵抗といえば和分の積」のように、「○○といえば□□」という形式で解説していますので、難解な項目もイメージしやすく、初学者でも学習しやすいつくりとなっています。 「効率よく学習し、限られた時間で合格ラインに到達したい」という方におすすめの書籍です。 【本書の特徴】 「○○といえば□□」方式でおぼえやすい! 合格率の低い科目から学習することで得点力アップ! テーマ別練習問題&過去問題が充実! 【目次】 第1部 理論 第2部 機械 第3部 電力 第4部 法規 第5部 電験三種に必要な数学 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.7
-
4.1「宇宙論」は、ここ100年で非常に目覚ましい発展をとげています。これら直近100年の宇宙論の歩みを、最先端の発展までを含め、宇宙論や素粒子論、量子重力理論などを専門とする著者が、徹底解説。はじめての「宇宙論」として本格的な、そして現代的な宇宙論を知ることができるような1冊になっています。 人間の宇宙への興味は、古来より尽きることはありませんでした。実際、古代エジプトからインド、ギリシャに至るまで、様々な「宇宙論」が考えられ、それらに基づいた神話や哲学が発展してきました。にもかかわらず、現代の宇宙論につながる「観測に基づいた系統的な世界観の構築」が始まったのは、かなり最近、ここ400年あまりのことなのです。 理論物理学の最前線では、私たちの宇宙を超えた、その外側や生まれる以前などについても議論できるようになってきています。これらの驚くべき成果は、主に20世紀に入って起こった爆発的な物理科学の発展によってもたらされたものであり、それはアルベルト・アインシュタインをはじめとする多くの科学者の長年における仕事の結果として得られたものです。 現代の宇宙論で科学的に調べることができる、私たちの宇宙が誕生してから約10のマイナス30乗秒後といった宇宙の「超初期」について紹介したり、恒星や銀河、銀河団といった現在私たちが見る構造の起源が、このような宇宙の超初期にどのようにして作られたのか、理論的な説明や、それを確認するための観測についても触れていきます。 よく耳にする「ビッグバン宇宙」や「インフレーション宇宙」といった言葉についても理解が進むように詳しく解説しています。 さらに、近年理論物理学者の間で急速に受け入れられつつある描像である「マルチバース理論」を紹介します。この最新の描像によれば、私たちが全宇宙だと思っていたものは無数にある「宇宙たち」の一つにすぎず、それら多くの宇宙においては素粒子の種類、性質およびそれを支配する法則、さらには空間の次元に至るまで、多くのことが私たちの宇宙とは異なっているとされるのです。 私たちのこの宇宙が始まる前から寿命について、またこの宇宙の外側まで、壮大なスケールで語られる、わかりやすい最先端の宇宙論です。
-
4.0鉱物ってこんなにおもしろい! かわいいキャラクターときれいな写真で 楽しく読める鉱物と宝石の図鑑。 鉱物や宝石をテーマにした、小学生向けの図鑑です。 うさぎのようにフワフワした石や、湿度が高いと溶けてしまう石など 約55種の鉱物のおもしろいところやスゴイ特徴を、 テキスト、鉱物をキャラクター化したイラスト、写真で具体的に紹介しています。 鉱物1種につき2ページ完結なので読みやすく、知識がなくても楽しめます。 〈内容例〉 ・石なのにふわっふわ! オーケン石(オケナイト) ・恐竜の卵みたいな石 亀甲石(セプタリア) ・金色に輝く星たちが集まった 白雲母(マスコバイト) ・石なのにぐにゃぐにゃする 砂質片岩(イタコルマイト) ・湿度が高いと溶けてしまう石 岩塩(ハライト) ・ルビーとサファイアは、じつは同じ鉱物 鋼玉(コランダム) ・工場の煙突で生まれる石 紅亜鉛鉱(ジンサイト) ほか 【対象年齢】小学4年生頃から 【著】さとうかよこ 鉱物標本やオリジナル理科雑貨のショップ「きらら舎」オーナー。小学生向けの鉱物ワークショップなども行っている。おもな著書に『世界一楽しい遊べる鉱物図鑑』(東京書店)、『美しい実験図鑑』(新星出版社)などがある。
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1986年の初版刊行以来、多くの読者から高い評価を得てきた『数学シリーズ 集合と位相』が、信頼の内容はそのままに、装いを新たに登場。 集合と位相は、概念そのものが現代数学のあらゆる分野に深く浸透し活用されている。本書は、数理系の学生を対象に、集合と位相の基礎的な内容をまとめた入門書である。はじめの3章で集合を、残りの6章で位相を扱う。 「集合」では、最初に集合と写像の概念およびその演算について述べ、続いてカントールの対角線論法やベルンシュタインの定理などを考察し、また選択公理と整列可能定理が互いに同等であることを証明する。「位相」では、ユークリッド空間への位相の導入、距離空間への位相の導入へと次第に抽象化して、一般の位相空間へと導いている。 このたびの増補新装版では、旧版には一部しか掲載されていなかった「解答とヒント」を大幅に増補・充実させて、すべての問題に対する解答を収めた。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 受験数学界にその名を轟かせた人気講師が、最重要ポイントを光速で伝授。 全国の大学生に支持された超ベストセラー待望の改訂版! ページ数、演習問題を大幅に増加。 予備校生に人気の実力派講師・齋藤寛靖先生が、大学生のために特別講義! 洗練された説明と厳選された問題で、単位の取得を強力にバックアップするよ。 それにとってもわかりやすいから、高校で勉強をしていなくてもバッチリOK。 試験対策にもノート代わりにも使える。 一石三鳥な本なので、欲張りなアナタにピッタリです。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 とってもわかりやすい物理数学の本。微分方程式、ベクトル解析、フーリエ解析などこれ1冊で大丈夫!物理学に関連づけて解説! (本書のまえがき) 物理を学んだり,物理学の研究を進めるうえで,『物理数学』は欠かせないものですが,大学に授業についていけずに苦しんでいる学生のみなさんも多いことかと思います。 本書は,基礎的な内容を基本から解説することで,数学がやや苦手なみなさんに,大学での授業が理解できるように支援することを目的にしています。この目的のため,少々の厳密を犠牲にする面もありましたが,本書で数学の垣根を取り払って,物理学を楽しく学んでもらえればと願っています。 物理学的考察を行う際に,少なくとも数式をツールとして扱えるようになれば,徐々にですが数式の意味もわかってくるようになってきます。そうなれば,みなさんの前に,物理学の素晴らしい世界が広がってくることでしょう。 第1章 微分学 第2章 微分と積分の関係 第3章 微分方程式 第4章 偏微分方程式 第5章 線積分・面積分・体積分 第6章 ベクトル解析 第7章 線形代数 第8章 複素関数 第9章 解析力学 第10章 ベクトル空間 第11章 フーリエ変換とラプラス変換 第12章 特殊関数 付録A 物理学と測定 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
5.0大人気の願望実現×量子力学YouTuber、ゆさの初書籍! 願いがすべて叶う「最高のパラレル」に移るための 最強メソッドがここに! あなたさえ望めば、現実はいま、この瞬間にも切り替わります。 仕事でなかなか結果を出せない。 いつもお金の不安で頭がいっぱい。 人間関係のストレスが絶えない。 大好きな人に振り向いてもらえない――。 こんなふうに、今、さまざまなことで頭を悩ませていたり、 辛い想いを抱えていたりしませんか? 思うようにならない現実に苦しんでいるのは、 運が悪いからでも、 ましてやあなたの能力や魅力が足りないからでもありません。 その理由は、ただ一つ。 知らず知らずのうちに、 あなたが「うまくいかない世界線」を選んでいたから。 ただそれだけのことなのです。 実は生きる世界線は、自分でいくらでも選ぶことができます。 本書は、わかりやすい動画が大好評の 願望実現×量子力学YouTuber、ゆさの初書籍。 一冊を通じ、「素粒子(フォトン)」と「宇宙の仕組み」を 丁寧に紐解きながら、「最高のパラレルシフト(世界線移行)」を 叶えるための方法を、 ロジカルに、それでいて、とにかくやさしくお伝えします。 大切なのは、「観測=自分への定義づけ」を しっかり行うこと、 そして自分が発するエネルギーに日々気を配り、調整すること。 この二つを意識すれば、一瞬で世界線を移ることだって、 あっさり叶います。 あなたが「自分はこういう世界線を生きる!」と観測した瞬間、 その現実は確定します。 現状はまったく関係ないのです! この世界の創造主は、ほかの誰でもなく、あなたです。 さあ、一緒に行きませんか? 心がうち震えるような、「自分史上最高のパラレル」へ。 【構成】 第1章 生きる世界線は、今、この瞬間にもシフトできる! 第2章 フォトンを調整して、理想の世界線と共振する 第3章 宇宙はいつでもギフトを贈ってくれている! 第4章 感情に寄り添って、「叶わない」の壁を超えていく 第5章 現実化を加速させるための、「密度」と「頻度」の高め方 巻末に、「本音をあぶり出す内観ワーク」つき!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 熱力学、統計力学、量子統計までを通して学ぶテキスト。例題や補足説明も充実。初学者に最適の1冊。 第1部 熱力学 第1章 熱力学の基礎 第2章 気体分子運動論 第3章 熱力学第1法則 第4章 熱力学第2法則 第5章 エントロピー増大の原理 第6章 熱力学関数 第7章 相転移 第2部 統計力学 第8章 統計力学の基礎 第9章 状態数とエントロピー 第10章 小正準集合 第11章 正準集合 第12章 大正準集合 第13章 エントロピー再考 第14章 ゆらぎと感受率 第3部 量子統計力学 第15章 量子力学の基礎 第16章 格子振動 第17章 空洞放射 第18章 量子気体 第19章 転送行列と密度行列 第20章 スピン系 第21章 相転移 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0待望の日本語版新版(原著第IV版、50周年記念版の全訳)。科学とは何か、知識の進歩とは何かについての固定観念を抜本的に塗り替え、「20世紀の最も影響力の偉大な本」に数えられる名著である。新版は半世紀ぶりの〈新訳〉であり、クーンの論述が細部まで丹念に掬い上げられた。また、新しい読者への案内としてI・ハッキングによる「序説━━五十周年記念版に寄せて」が巻頭に加わっている。「通常科学」から「危機」へ、そして新しい「パラダイム」へ──世界観の変わり方をダイナミックかつ周到に語って世界を変えたクーンのヴィジョンが、21世紀的な解像度の訳文でよみがえる。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界的研究者が最新研究にもとづいて、多様で複雑な現象(地震)を語り尽くす。スロー地震から巨大地震まで、また、地震動(揺れ)だけでなく、震源で起こる岩石の破壊現象、確率的な過程としての地震活動もカバーする。これが、地震学の最前線! 【おもな内容】 第1部 イントロダクション 第1章 地震とは?/第2章 弾性体力学の基礎 第2部 破壊すべりと震源波動場 第3章 表現定理とグリーン関数/第4章 モーメントテンソルによる震源の表現/第5章 現実的な震源:点震源/第6章 現実的な震源:面的なモデル/第7章 現実的な震源:複雑なモデル 第3章 震源近傍の物理学 第8章 巨視的な破壊と摩擦/第9章 クラックの破壊/第10章 破壊すべりの動的進展/第11章 全地震プロセスのモデル化 第4部 地震現象の総合的理解 第12章 地震活動のモデル化/第13章 地震の固有性/第14章 スロー地震とファスト地震/第15章 地震の予測 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 多くの人がつまづく積分。それを入門編、中級編、上級編の3編に分け、読むだけで段階的に理解できる一冊にまとめました。まずは、「積分」とは何か? その考え方を数学の歴史にも触れながら、わかりやすく解説していきます。入門編は、まさに読み物としての面白さがあり、タイトルの通り、「読むだけ」で積分の考え方、成り立ち、積分の基本がわかります。中級編は、定積分の数学的な証明から置換積分、部分積分などの応用的な積分を解説。「なぜそうなるのか」を順を追って解説していくので、基本がより深く理解できます。「入門編」で理解したことをさらに深めることができます。そして上級編は、量子力学の「波動関数」から「フーリエ変換」「ガンマ関数」「重積分」「ガウス積分」まで。天気予報から、CG制作、CTスキャンの解析など、日常のあらゆるところに潜んでいる「積分」を身近なものになる一冊です。 主な内容 初級編 ・積分とは何か? ・面積と定積分 ・微積分学の基本定理とは? ・微積分学の基本定理の実践 中級編 ・面積の「新定義」を確かめる ・微積分学の基本定理 ・積分テクニック(1)置換積分 ・積分テクニック(2)部分積分 上級編 ・微積分学の基本定理の証明 ・「ガンマ関数」とは何か? ・「重積分」とは何か? ・ガウス積分
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 好評教科書を全面カラー化! 旧版の美点(重要ポイントに絞った記述、単純な部品を使った解説、加工や設計を意識した実践的内容、取り組みやすい練習問題など)を強化した。もちろん最新の JIS に準拠。製図を学ぶなら、まずこの一冊から。 【おもな目次】 Part 1 製図 三面図(第三角法・第一角法)/断面図/寸法記入/寸法公差/幾何公差/表面粗さ/立体図 など Part 2 機械部品 ねじ/歯車/軸受/キー結合/止め輪/ばね/金属材料と樹脂材料 Part 3 設計 加工方法と組立精度を考えた設計/機械材料の性質/軸受の支持設計/構想図 Part 4 CAD CADの活用/モデリング/アセンブリ/ドラフティング 付録 これが使ってよい表記法だ! ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.9いまだそのほとんどが解明されていない宇宙。私たちが思っているよりももっとたくさんの謎が存在していて、現時点でわかっていることは、たった5%だといいます。「わからない」からこそ、私たちは長い間、宇宙に魅了され続けているのでしょう。 世の物理学者たちは、そんな謎につつまれた宇宙と向き合い、解明しようと研究を重ねています。それでもなお、いまだに「わかっていない95%」の宇宙とは、一体なんなのでしょう? そこで本書では、現時点で解明されていない宇宙の謎を紹介。また、宇宙を語るにはずせない「素粒子」「量子力学」「時間」「量子重力」における謎についても紹介し、さらなる謎に潜っていきます。そして、謎に対してどのような仮説が出ているのか、その仮説の反証には何が挙げられているのか、この謎のポイントはどこかなどを、気鋭の物理学者が解説します。ぜひ一緒に、「95%の宇宙の謎」について考えてみてください。 謎が解明されたら新たな謎が生まれる――この宇宙の浪漫に、ワクワクが止まらなくなるはず! 宇宙が好きな人はもちろん、社会人だけでなく、物理学を学びはじめた学生でもわかる“宇宙一面白くてわかりやすい”宇宙入門書です! ※カバー画像が異なる場合があります。
-
4.4すべての人が知っておきたい、 日本列島・地球・宇宙の教養が身につく! 人間をとりまく、あらゆる自然現象を扱う学問《地球科学》。 高校地学は、そのエッセンスがつまった「最高の教養」だ。 日本列島の地学的特徴、地震や噴火のメカニズム、 地球46億年の歴史、宇宙の成り立ちと進化…… 「こんなに楽しい高校地学、もっと多くの人に学んでほしい!」 想いを共にした地球科学の第一人者とカリスマ地学講師が、 「誰もが読んで楽しめる教科書を」と作ったのが本書である。 地球科学の必須知識をマスターしたいすべての人に! 《目次》 序章 日本列島と巨大災害 なぜ日本列島には地震が多い?/南海トラフ巨大地震のメカニズム/誘発される「富士山噴火」/「次の大震災」の被害予測/盲点だった日本海側の防災対策 ほか 第1章 地球の姿としくみ 地球はどんな形をしているか/地球の中身はどうなっている?/地球内部で何が起きているか/地磁気とはなにか/プレートテクトニクス革命/プレートが覆う地球/地震と断層/地震はどこで起きるか/火山のはたらき ほか 第2章 46億年の地球史 地層のなりたち/地層からたどる地球の歴史/地球と生命の誕生/生物の陸上進出/陸上生物の繁栄/地質からみた日本列島/日本列島の歴史 ほか 第3章 地球をめぐる大気と海洋 大気圏/雲はなぜできるのか?/大気の状態はどのように決まるか/地球をとりまくエネルギー/風の吹き方/大気の大循環/日本の天気/気候変動はなぜ起きる?/地球を揺るがす環境問題 ほか 第4章 はてしなき宇宙の構造 太陽系の天体/地球の自転と公転/惑星の運動/太陽/恒星までの距離はどう測る?/なぜ恒星はカラフルなのか/星団/銀河系/宇宙はどのように誕生した? おわりに 高校地学のエッセンス
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 本書は、専門学校や他の教育機関で長年教鞭を執ってきた著者が、そのノウハウを惜しみなく結集した合格対策テキストです。1冊に学科、実地の両試験の対策を収録しています。 「よく出るところだけを」というリクエストに応え、短時間で効率よく学習できるよう、必須の知識にポイントを絞ってコンパクトにまとめています。 学生や専門職の方など、総合的な実務経験のない方、幅広い知識が足りない方でも経験記述がむりなく解答例、やさしい用語解説、解答のコツを豊富に掲載しています。 ●1冊で合格を目指す ●範囲を絞った要点整理 ●経験不足を補う用語解説 ●覚えて使える経験記述 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は中学数学レベルからスタートし、集合、関数、微分、積分、行列、確率といった、AI・データサイエンスに不可欠な数学の基礎を丁寧に解説します。 豊富な練習問題やポイント・補足によるアドバイス、Excel演習などの充実したサポート内容によって、数学が苦手な方でも安心して学習を進められます。 数理・データサイエンス・AI(応用基礎レベル)モデルカリキュラム「1-6.数学基礎」に準拠した、統計確率・線形代数・微分積分の土台となる数学的知識を無理なく習得できる “いちばんやさしい“ 教科書。
-
4.0回し車の中で走るハムスターを見てこんなことを思ったことはないだろうか.「めっちゃ上手に走るなぁ」「走っていて楽しいのかしら」「なんで走っているの?」――.でも回し車で走るのはハムスターだけではない.ラットもマウスもニワトリもゴキブリも走っている.なぜ走るのか,その素朴な疑問に真正面から挑む.
-
4.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 本書は河川マニアの6人で執筆している。 土木技術者または環境技術者を志しているにも関わらず川に関心が無い。これはゆゆしきことである。 この問題に数年前に気づいた。レジャーで多くの人が海や山に行くが,川に行くことは少ない。 もっと川を身近に感じてもらいたい。もっと川を知ってもらいたい。もっと川を語ってもらいたい。 この強い思いが本書の執筆の動機である。 そのため,一般的な河川工学の教科書と少し違う。河川工学入門の手引書のような位置づけである。 興味を持ってもらえるように文より写真や図面を豊富にするように心がけた。 本書で読んだもの,見たものは,ぜひ,実際に川に足を運んで見て欲しい。 この本が河川に行くきっかけになれば幸いである。 【著者紹介】 編著:風間 聡(かざま そう) 東北大学大学院工学研究科 教授 著:峠 嘉哉(とうげ よしや) 東北大学大学院工学研究科 助教 著:渡辺 一也(わたなべ かずや) 秋田大学大学院理工学研究科 准教授 著:小森 大輔(こもり だいすけ) 東北大学大学院工学研究科 准教授 著:横尾 善之(よこお よしゆき) 福島大学理工学群共生システム理工学類 准教授 著:糠澤 桂(ぬかざわ けい) 宮崎大学工学部 助教 【目次】 第1章 河川について 第2章 河川の水理 2.1 降水 2.2 水理学の基礎 2.3 開水 2.4 地下水 2.5 数値解析法 2.6 計測手法 第3章 土砂の水理 3.1 はじめに 3.2 河床材料 3.3 砂の運動と移動 3.4 掃流砂 3.5 浮遊砂 3.6 ウォッシュロード 3.7 土砂の拡散 3.8 河床変動計算 3.9 河川地形 3.10 治山と砂防 3.11 砂州と河口 第4章 治水 4.1 はじめに 4.2 主な治水工法 4.3 近代における水害の歴史 4.4 水害に対する河川計画 4.5 水防と治水 第5章 河川工作物 5.1 河川工作物 5.2 堤防 5.3 護岸、護床 5.4 水制 5.5 堰とダム 5.6 水門 5.7 魚道 5.8 その他の工作物 第6章 利水 6.1 河川水の利用 6.2 ダムと堰 第7章 河川環境 7.1 はじめに 7.2 河川の水質 7.3 河川の生態系 7.4 私たちの暮らしと河川環境 7.5 河川環境評価 第8章 親水 8.1 親水とは 8.2 親水整備 8.3 親水の問題 8.4 親水の評価
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アイザック・ニュートンの代表作『プリンシピア 自然哲学の数学的原理』の全訳を復刊(全3巻)合本版。出版当時から難解と言われた「プリンシピア」を、現代の科学者が「内容そのものの解明理解を目的」として翻訳。巻末注には、微積分の定理を使った別証明、原典では省略された証明の内容、現在の視点から見た物理的概念の解説がまとめられている。“中世紀”を通じて多くの思想家たちは、地上の現象と天空の現象との間に、何らかの神秘的な原因を付加することによって、はっきりとした区別を設けていた。ニュートンはこの思想を最も力強く打破したのである。彼は言う。「自然の物事の原因としては、それらの諸現象を真にかつ十分に説明するもの以外のものを認めるべきではない(中略)」と。こうして人間は、天にあるものは完全なもの、地にあるものは不完全なものとの永い間の信仰から解放され、すべての自然現象は合理的な因果律の同じ支配のもとにあることをしらされるのである。(「訳者解説」より)「プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第1編 物体の運動」「プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第2編 抵抗を及ぼす媒質内での物体の運動」「プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第3編 世界体系」3冊の合本版です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 重点事項がすぐにわかる! 数学検定試験の重要ポイントで解説したテキストに、過去問題(5回分)を掲載した「参考書+問題集」型の受検対策書です。 準1級は高校3年生から大学初年度の数学となり、一般の人には難しく感じますが、現場技術者には最低限必要なものです。準1級の受検者はもちろんのこと、技術書が難しく感じる方の数学のおさらいとしておすすめの1冊です。 はじめに(監修の言葉) 受験案内 準1級の試験範囲 第1部 問題解説編 第1章 高次方程式 第2章 図形と方程式 第3章 三角関数 第4章 指数と対数 第5章 ベクトル 第6章 数列 第7章 複素数平面 コラム 1 のn 乗根と正多角形 コラム 複素数の難しさ 第8章 式と曲線 第9章 関数 第10章 極限 第11章 微分 第12章 積分 第13章 行列 第1部 練習問題解答 第2部 過去問題 第1回 1次 2次 第2回 1次 2次 第3回 1次 2次 第4回 1次 2次 第5回 1次 2次 第2部 過去問題解答
-
-
-
-タリアセン・ウェストやグッゲンハイム美術館などのアメリカにある有名建築をはじめ、帝国ホテルや明日館など日本にある建築を含めた75件を各1~2頁で紹介するライトの建築ガイド。ライト建築を気軽に概括的に知ることができると好評を博した一冊が新装改訂版で登場。見学・公開情報を更新し、ライトめぐりの旅にも必携です。 ・移築や改修などを経て、近年新たに公開された建物を多数収録 ・見学ツアーの有無やアクセス情報なども掲載 ・ライトの建物が集中している6エリアのおすすめ見学コースを提案 ・全米におけるライト作品の分布MAP付き
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 累計18万部突破! 「読む元素事典」の決定版が、〈国際標準の最新元素周期表〉に完全対応! 元素とはなにか──? ・各元素の性質の違いはどう決まる? ・周期性があるのはなぜ? ・天然の元素と人工元素の違いとは? ・元素の数はどこまで増える? ・元素発見ランキングの第1位は誰? ・原子量などの重要データはなぜ変動する? ……ほか、元素番号1番「水素」から118番「オガネソン」まで、「万物の根源」をなす全元素を徹底詳説! 本書が支持される4大理由とは? 1:「元素の本質」をいきいきと描き出す。 事典的要素が充実していることはもちろん、読み物としても面白い。具体的なエピソード満載で、各元素の個性を紹介。 2:全118元素の特性や用途など、重要ポイントが一目瞭然。 化合物や現象の列挙にとどまらず、その原因やメカニズムを掘り下げて解説。 3:生命と元素の関わりがよくわかる。 生命活動に必須の元素から、いまだその存在が謎に包まれている元素まで、健康や病気にどう影響するかを詳述。意外な元素に、生命との関係があった。 4:充実した元素データ。 同位体の種類や存在比、半減期から電子配置、原子量まで。元素に関する最新数値を網羅。
-
4.0この本は、先に訳出した同じ著者の本「コンサルタントの秘密」の姉妹編であって、両編合わせて著者ワインバーグ氏のこれまでの仕事の集大成ともいえるものである。著者ワインバーグ氏は、序文において「成功したシステムと不成功に終わったシステムを比べてみて、じきわれわれは成功のほとんどすべてが小数の傑出した技術労働者の働きに依存している、ということに気づいた。」と述べている。 人はスーパーエンジニアというと、技術をよく知っていてどんどんすごいことを思いつく人、といったものばかりを思い浮かべるかもしれない。そしてそういう技術革新能力も貴重である。だが、スーパーエンジニアが本当に「スーパー」であるためには、技術革新の力だけでなく、動機づけと組織化の能力を併せ持っていることも必要だ。この本の用語を借りていえば、「問題解決型のリーダーシップ」を身につけていなければならないのだ。 [訳者まえがき]より
-
5.0★話題の天才宇宙物理学者、待望の一般書デビュー! ★世界27カ国語で刊行決定の最新宇宙論! ★「ニューヨークタイムズ」ベストセラーリスト入り! ★Amazon.com エディターたちによる「ベスト・ノンフィクション」選定図書 ★並はずれた一般向け科学書に与えられる2024年度「コスモス図書賞」受賞 ★宇宙物理学の重鎮がこぞって絶賛 ・なぜこの宇宙はこれほど絶妙に「生命にやさしく」できているのか? ・「物理法則」は永久不変ではなく、生物と同じく「進化」する? ・多元宇宙(マルチバース)は無限ではなく有限? ・時間は「存在しない」? 本書の著者トマス・ハートッホは、車いすの宇宙物理学者スティーヴン・ホーキング(2018年没)の20年来の愛弟子であり、「ホーキング最終論文」の共著者でもある天才物理学者。師からの「最後の宿題」に応えるべく、未完に終わった研究を引き継ぎ、究極のビッグ・クエスチョンに挑む。今世界で話題沸騰中の、最高にエキサイティングで感動的な最新宇宙論! 【目次】 第1章 この宇宙はなぜ「生命に適している」のか 第2章 宇宙に「始まり」はあったのか 第3章 「宇宙誕生の瞬間」は存在しない 第4章 永遠に、無限に「増殖」しつづける宇宙? 第5章 多元宇宙で途方に暮れる 第6章 私たちの「観測」がこの宇宙をつくる 第7章 時間は存在しない 第8章 「最後の理論」の先にあるもの 装幀:水戸部 功 「なぜ私たちの宇宙はこのような姿をしているのか? すべてはどのように始まったのか? そして、どのように終わるのか? 著者のハートッホは、スティーヴン・ホーキングと二人三脚でこの壮大な謎を探求してきた物理学者であり、身体と発話の不自由なホーキングが晩年も並はずれた頭脳を持っていた事実の目撃者だ。本書は本当にすばらしい。本書を読めば、宇宙に関して今どこまで分かっているのか、さらに創造的な思考法とはどういうものかがよくわかる」 ーーマーティン・リース(ケンブリッジ大学名誉教授。王立協会元会長。宇宙物理学者) 「師であり共同研究者だったホーキングと同様、著者ハートッホは新説を打ち立てる野心をむき出しにしている。すべてを詰めこんだこの本は、宇宙について現在分かっていることと、未知の領域に踏み出す大胆なアイデアの両方を、わかりやすく解説してくれる。それだけでなく、今後登場するであろうさらに壮大な理論をも垣間見せてくれるのだ」 ーーショーン・キャロル(ジョンズ・ホプキンズ大学教授。量子物理学者) 「ホーキングとハートッホは"トップダウン宇宙論"によって物理学の新たな哲学を打ち立てつつある。本書はあなたの思考の枠を大きく押し広げてくれる。 極めて価値ある1冊だ」 ーー ルイス・ダートネル(宇宙生物学者。『この世界が消えたあとの 科学文明のつくりかた』)
-
4.2エッシャーの代表作である《物見の塔》《滝》《上昇と下降》などのだまし絵。これらの作品は、一見しただけではそこに錯視図形があるとわからないほど自然に見える。しかし、少しの間をおいて「これはありえない立体だ」と気付いた瞬間、鑑賞者に大きな驚きをもたらす。この劇的な鑑賞体験はどのようにして作られたのか。エッシャーはまず、絵のあちこちに鑑賞者を誘導するトリックを仕掛け、さらにそれらを手品師さながらに覆い隠していった。そしてトリックの存在を生涯隠し通し、決して語らなかったのだ。本書は100点を超える図版でだまし絵の制作過程を分解し、エッシャーがかつて5つの作品に仕掛けた視覚のトリックを明らかにしている。エッシャーが制作中に何に悩み、何を大切にしていたかにまで踏み込んでいく。謎解きの楽しさに満ちた1冊。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本で見られる1260種のウミウシを収録した図鑑です。 特徴がひと目でわかる各種ウミウシの図解入り。 ウミウシ・ファンの裾野を広げるべく、同定の決め手となるポイントを全てイラストで解説したウミウシ図鑑です。 ウミウシを美しく撮影するテクニックや、ウミウシを上手に探すコツなど、実践で使える実用書であり、かつ、美しいウミウシの魅力が伝わる写真の数々や歴史的な絵画も紹介。 慶良間諸島と八丈島をメインに北海道、本州、沖縄まで日本で見られるウミウシ、変異、spなどを含め1260種を収録した決定版の書籍です。 ・掲載種は国内での撮影種のみに限定 ・特徴や識別ポイントがひと目でわかる、各種ウミウシのイラスト解説付き ・初心者からでも始められる、ウミウシ撮影術 ・短時間で上手にウミウシを見つける方法を紹介 ・本邦初の新しいウミウシも掲載! ・1900年代初期の和洋の絵画に見る「ウミウシの美」
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 透徹した論理のもとに「熱」の現代的描像を説き明かす、至高の雄編。熱力学と統計力学を統一的に論じ、豊富な演習で理解を深める。 ◇主な目次◇ 第 I 部 熱力学 第 1 章 熱力学とは 第 2 章 熱力学系と熱力学的状態 第 3 章 熱力学の法則 第 4 章 熱機関と Carnot の定理 第 5 章 エントロピー 第 6 章 熱力学関数の微分形式 第 7 章 変分原理と熱力学関数 第 8 章 相転移 第 9 章 熱力学の応用 第 II 部 統計力学の基礎 第 10 章 統計力学とは 第 11 章 確率論 第 12 章 熱平衡状態 第 13 章 ミクロカノニカル分布 第 14 章 カノニカル分布 第 15 章 基本的な例 第 16 章 古典統計力学 第 17 章 情報とエントロピー 第 III 部 統計力学の応用 第 18 章 相互作用のある系 第 19 章 Ising 模型 第 20 章 格子振動 第 21 章 空洞放射 第 IV 部 量子統計 第 22 章 グランドカノニカル分布 第 23 章 同種粒子 第 24 章 Fermi 分布と Bose 分布 第 25 章 Fermi 粒子系の性質 第 26 章 Bose 粒子系の性質 第 V 部 相転移と臨界現象 第 27 章 相転移の統計力学 第 28 章 平均場理論 第 29 章 臨界現象 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 多くの人がつまづく微分。それを入門編、中級編、上級編の3編に分け、読むだけで段階的に理解できる一冊にまとめました。まずは、「微分」とは何か? その考え方を数学の歴史にも触れながら、わかりやすく解説していきます。入門編は、まさに読み物としての面白さがあり、タイトルの通り、「読むだけ」で微分の考え方、微分の基本がわかります。中級編は、その数学的な証明から三角関数、指数関数、対数関数などの応用的な微分を解説。「なぜそうなるのか」を順を追って解説していくので、基本がより深く理解できます。「入門編」で理解したことをさらに深めることができます。そして上級編は、「テイラー展開」から「オイラーの公式」まで。大学数学の入り口まで到達します。難しい内容も、ひとつひとつの概念をかみくだいて、丁寧に解き明かしていきます。 主な内容 初級編 ・関数とは何か? ・関数とグラフ ・人類は接線をどのように考えてきたのか? ・いよいよ微分入門 ・三角関数とは何か? ・指数関数・対数関数とは何か? 中級編 ・微分係数 ・Xn乗の導関数とその導出 ・2回微分とグラフの凸凹 ・積と商の微分公式 ・合成関数とその微分 ・三角関数 ・指数関数・対数関数 上級編 ・「連続」とは? ・「極限」について(ε-δ論法) ・「近似」とは何か? ・これがテイラー展開だ ・オイラーの公式を導く
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ピンポイント解説&問題演習で、ストレートに合格へたどり着ける最適の一冊 本書は、技術士第一次試験 基礎科目・適性科目それぞれの過去10年間の出題傾向を分析したうえでこれを内容構成に徹底的に反映し、合格に直結する「出るとこだけ」をポイント解説。また、関連した過去問の問題演習で理解度を確認しながら学習を進められる構成としてまとめています。 第1章 技術士第一次試験受験の手引き 第2章 出題傾向と分析・対策 第3章 基礎科目の研究 1群 設計・計画 2群 情報・論理 3群 解析 4群 化学・材料・バイオ 5群 環境・エネルギー・技術 第4章 適性科目の研究 付録 関連法令
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■これから電気回路を学ぶ人のためにこれから電気回路を学びたいと考えている学生の方、また、仕事で電気回路の知識が必要になった社会人の方に向けて書かれた本が本書です。電気回路に関する知識を再確認したい技術者の方にも役立つ一冊です。 ■電気回路の基本を見やすく、わかりやすく解説 「電気と回路の基礎」「直流回路」「回路素子」「交流回路」「三相交流回路」に関し、それぞれをわかりやすく、しかも詳しく解説しています。見やすいオールカラーの紙面に図版類を多用するなど、理解を促す工夫がたくさんです。 ■数学が苦手な人でも大丈夫 数学が苦手という人のために「微分・積分」は使っていません。三平方の定理、三角関数、複素数を知っていれば理解できるように配慮しました。三角関数と複素数に関しては本書の中で解説しています。 ■素子の動作原理を物理的、電磁気学的に解説 電気回路を解析するには、物理や電磁気学の知識がなくても公式さえ覚えれば、答えを導くことができますが、それ以上先には進めません。原理を知った上で公式や定理がどのような意味を持つのかを深く理解することで、複雑な回路の解析にも対応できるようになるはずです。
-
4.0
-
-★まさにバイブル!★ 転移学習は、従来の機械学習の方法では解決することが困難な要請や課題をうまく取り扱うための方法です。深層学習の登場以降、事前学習済みモデルの利用が容易になり、転移学習が広く用いられるようになってきた。 本書では、転移学習の基本概念から、ドメイン適応、事前学習済みモデル、知識蒸留、マルチタスク学習、メタ学習、継続学習などをていねいに解説。この一冊から始めよう! 【主な内容】 第1部 転移学習への導入 第1章 機械学習から転移学習へ 第2章 転移学習の基本概念 第2部 転移学習の基礎 第3章 ドメイン適応の理論 第4章 データに基づくドメイン適応の基礎 第5章 モデルに基づくドメイン適応の展開 第6章 事前学習済みモデル 第3部 転移学習の展開 第7章 知識蒸留 第8章 マルチタスク学習 第9章 メタ学習 第10章 少数ショット学習 第11章 ドメイン汎化 第12章 継続学習 第13章 強化学習における転移学習 付録A 深層ニューラルネットワークと生成モデルの基礎
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シーケンス制御の基礎がマンガでばっちりわかる! はじめて学ぶ人のために、シーケンス制御の基礎をわかりやすく解説している。記号表記はなるべく必要なものにおさえ、シーケンスの基本はきちんと解説。様々な電子部品の組み合わせで機械を制御していく仕組みを、マンガと文章によって理解することができる。 目次 プロローグ ひきこもりとおせっかい 第1章 制御 手動制御と自動制御 電気回路と制御回路 接点の働き 接点の種類 フォローアップ 自動制御とは 制御回路の基本 接点の基本形とその働き 第2章 シーケンス制御 シーケンス制御 フィードバック制御で動く機器 フォローアップ 全自動洗濯機に見るシーケンス制御 エアコンとフィードバック制御 第3章 制御に使う様々な機器 押しボタンスイッチ トグルスイッチ セレクタスイッチ マイクロスイッチ 電磁リレーとは タイマとは フォローアップ 命令用機器 検出用機器 制御操作用機器 表示用機器と警報用機器 第4章 シーケンス図の描き方 縦描きと横描き 機器を表す文字記号 接続箇所の表し方と実際の接続 シーケンス図を読みやすくする フォローアップ シーケンス図の描き方の基本 シーケンス図と文字記号 制御機器端子記号 シーケンス図の位置参照方式 シーケンス図の読み方 シーケンス回路の故障原因の見つけ方 第5章 接点と論理回路 デジタルとは 論理回路とは フォローアップ 2値信号 基本的な論理回路 論理回路を表す図記号 NAND回路からAND、OR、NOT回路を作る 第6章 リレーシーケンスの基本回路 表示灯を消す回路 回答者が2人の場合 回答者が3人の場合 タイムチャートとは 実際に配線してみる エレベーターの基本回路 フォローアップ 基本回路とタイムチャート タイマを使った時限動作回路 順序動作回路 モータの運転停止回路 エピローグ 索引 著者略歴
-
3.5※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “やさしく学べる”シリーズの続刊テキスト。コンピュータサイエンスの基礎をなす“離散数学”を、著者一流のやさしく具体的な解説により、数多くの例題、演習問題を解きつつ、「なるほど」と実感しながら身に付けることができる。本文の随所に、イラストによる注意事項、ワンポイント解説を配して、読者の理解を助ける工夫を凝らし、数式の展開も丁寧に行い、計算力も同時に高めることもできる。もちろん、詳細な演習問題解答もこれまでどおり掲載しているので、自習書としても使える。
-
4.0ウーバーも参戦する空のMaaS市場、巨大産業を支配するのは? 「空飛ぶクルマ」に乗って渋滞に巻き込まれずに目的地までひとっ飛び――。SF映画などで見られた光景が、当たり前になるかもしれない。「空飛ぶクルマ」とは、航空機と自動車が融合した新しいモビリティー(移動手段)だ。巨大市場に急成長する可能性を秘め、新興企業から大手企業までが主導権を握ろうと世界中で競争が激化している。 エアバスやボーイングなどの航空機メーカー、トヨタやダイムラーなどの自動車メーカー、シーメンスなどの部品メーカーがこぞって注目している。 さらに、配車サービス大手の米ウーバーは、空のライドシェア「uberAIR」を発表し、空飛ぶクルマの動きを世界でリードしている。 日本の産業界も参戦し、経済産業省は「空飛ぶクルマを日本の新産業に育てよう」と動いている。 空飛ぶクルマを巡る一連の動きをまとめた本書を通じて、巨大産業の産声を感じてほしい。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 宝石を楽しんで学び、理科好きな子どもを育てる図鑑の決定版!・宝石のひみつが、写真とイラスト図解でわかる本。誕生や結晶、輝きのひみつ、歴史など、学びに役立つ子ども向け学習図鑑。・圧倒的に美しい宝石写真、色引き図鑑なので分かりやすい。・監修者は、斯界の第一人者である宮脇律郎先生(国立科学博物館 地学研究部部長、日本鉱物科学会会長)。※特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」開催。国立科学博物館(2022.2.19~6.19) 名古屋市科学館(2022.7.2~9.19)。キラキラした宝石の、誕生や結晶、耀きのひみつ・ふしぎには、地球科学から物理、歴史文化まで、幅広い内容を含まれています。お子様の興味に合わせて、読み進めることができ、「科学する力」「探求する力」が身につく、男女問わず、親子で楽しめる図鑑です。
-
-船瀬俊介渾身の調査! 埋もれた名著『船瀬俊介の民間茶薬効事典』の完全復刻改訂版! この1冊で今日からあなたも健康茶マスターになれます! ◎ がん、動脈硬化を防ぐには、「明日葉茶」 ◎ 糖尿病、胃炎、便秘には「アロエ茶」 ◎ 精力増進、不妊改善には「イカリソウ茶」 ◎ アレルギーには「イチョウ茶」などなど… 今あなたに必要なお茶がすぐわかる「民間茶別効能表」(巻末)付き! 日本古来から伝わる健康茶には、驚きの薬効がつまっていた! 代表的な健康茶29種の効能、臨床データ、作り方までを完全公開! それでもあなたはまだクスリを飲み続けますか?
-
-一般相対性理論の概念的基礎であることが判明して再び脚光をあびたリーマン幾何学は、1854年の本書収録講演に始まる。この講演にガウスは珍しく高い評価を与えたという。すでに平行線公準の否定に始まるロバチェフスキーやボヤイの非ユークリッド幾何学はあったが、リーマンは、幾何学といいながら図形からでなく、位置を表すn個の変数の組や曲線の長さから新しい幾何学を組み立てた。数式をほとんど用いない哲学的な講義内容を、ワイルがていねいに数式展開しながら注釈。また序文でも本講演の意義を、理論物理学における遠隔作用から接近作用への潮流になぞらえ熱く語っている。ミンコフスキーの論文「空間と時間」併収。解説 H.ワイル
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 数学は“13種類”の考え方にまとめられる! シリーズ累計18万部突破「新体系・〇〇数学の教科書」シリーズに、新たなラインナップが登場 数学の問題を解く中でも重要なことが、なぜその解法を思いつくのか?という疑問です。 そこに注目し『新体系・高校数学の教科書』の構成をもとに、高校数学の全分野を網羅しながら、実践問題形式で解法への発想法を解説します。上下巻・同時刊行! 論理・直感・試行錯誤「体験的数学思考」をもとに、解法の発見に至るプロセスに必要な思考法や発想がみにつく! “思いつくセンス”を育てる、現代人必読の数学読本。
-
4.0


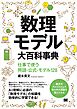





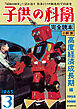




![[カラー図解]電気エンジニア1年目の教科書 ~電気系設備保全・生産技術の実務のための基本~](https://res.booklive.jp/1938422/001/thumbnail/S.jpg)















![これ1冊で最短合格 電気通信主任技術者 要点解説テキスト&問題集[伝送交換主任技術者編]](https://res.booklive.jp/1663001/001/thumbnail/S.jpg)














































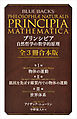














![統計学が最強の学問である[数学編]―――データ分析と機械学習のための新しい教科書](https://res.booklive.jp/480726/001/thumbnail/S.jpg)








