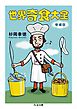ちくま文庫作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.5
-
4.4
-
4.2
-
4.0
-
4.0平成を彩った名選手から伝説の試合、球界の大事件、忘れられないバイプレイヤーや珍エピソードまで、“平成プロ野球”を総括したコラム集。文庫化に際して、とんねるず、ファミスタ、TVドラマ、女子アナなどの平成カルチャーと新世紀末プロ野球の危険な蜜月関係に迫る書下ろしコラム4編も新加入。平成の名場面を圧倒的偏愛でまとめた「球界年表」も収録する。
-
4.0
-
4.0「トキさん」は1906年、十勝の入植者の子どもとして生まれ、口減らしのため、生後すぐにアイヌの家族へ養女として引き取られた。和人として生まれたが、アイヌの娘として育った彼女が、大切に覚えてきたアイヌの言葉、暮らし。明治末から大正・昭和の戦前戦後を、鋭い感覚と強い自立心でアイヌの人々と共に生き抜いてきた女性の人生を描く優れた聞き書き。
-
5.0
-
3.5知らない土地で、ちょっとドキドキしながら、居酒屋の暖簾をくぐるときの期待と不安は何とも言えない旅の楽しみである。地元の人に混じり人情に触れるもよし、静かに酒と料理を味わうもよし。酒場を求めて、山、海、温泉……。観光地や路地裏まで日本各地を旅しながら見つけた、あの店この店。全国24か所を旅した、酒場ルポの傑作。文庫オリジナル。
-
4.3クマと遭遇したとき、人間は生き延びるために何をすればいいのか。死んだふり、木に登る、リュックを置いて逃げるといった、巷に流れる俗説は有効なのか? 「クマは師匠」と言うアイヌ民族最後の狩人が、アイヌの知恵と自身の経験から導き出した、超実践的クマ対処法を伝授。クマの本当の姿を知ることで、人間とクマの目指すべき共存の形が見えてくる。
-
4.0
-
3.9
-
5.0
-
4.0武器運び、馬の世話、土木作業、衣類・食糧運び、戦が始まれば最前線で敵と向き合い、集団で槍、鉄砲を扱う。そんな戦場の現場人の役割ごとの声を収録し、多くの武士が戦場心得の参考とした『雑兵物語』。江戸前期に成立し後期の1846年に刊行され一般にも流布した古典を、わかりやすい現代語訳とリアルな挿画で送る。現在の最前線ではたらく人々も切実に読める一冊。
-
3.7
-
4.1
-
4.4ハルラント聖王国の最西端“西ノ庄”の少女エヤアルは幼少のとき、魔法を暴走させて災厄を招き、“炎の鳥”に魔法を奪われた。成長した彼女は労働力として砦に連行されるが、そのとき、あらゆる物事を記憶する力に突如目覚める。彼女の力をめぐって動き出す陰謀と過酷な運命。エヤアルがもたらすのは平和か破滅か……。日本ファンタジーの旗手の新境地。
-
3.8
-
3.9昭和初期の渋谷では牛が普通に歩いてた? いつから漫画家の先生にはげましのおたよりを出してたの? 戦前の新聞の一面には広告しか載ってなかった? 昭和30年代にクールビズ論争が? 大正時代のダイエットブーム? 戦国と幕末だけが歴史じゃない。忘れられた名もなき庶民の身近な歴史・文化史を史料から丁寧に洗い直せば、日本の歴史はこんなに意外でおもしろい!
-
3.4
-
4.0
-
3.9
-
-
-
3.9もしも借金が返せないのならば、約束通り貴方のその体から1ポンドの肉を切りとらせろ――。ユダヤ人の金貸しシャイロックがアントーニオに要求した証文が現実となった。それに対してヴェニスの法廷が下した驚くべき判決とは? そして裁判官の正体は? 商業都市ヴェニスとロマンティックな愛の町ベルモントを舞台に、お金とセックスの隠喩をちりばめて繰り広げられる、世界で一番有名な喜劇を鮮やかな最新訳でどうぞ。
-
5.0
-
3.8東京オリンピックを翌年にひかえた1963年、東京の下町・入谷で起きた幼児誘拐、吉展ちゃん事件は、警察の失態による犯人取逃がしと被害者の死亡によって世間の注目を集めた。迷宮入りと思われながらも、刑事たちの執念により結着を見た。犯人を凶行に走らせた背景とは? 貧困と高度成長が交錯する都会の片隅に生きた人間の姿を描いたノンフィクションの最高傑作。
-
3.7
-
3.5
-
4.0
-
4.5
-
3.0
-
4.4
-
3.8「安全への逃避」をはじめとするベトナム戦争の写真報道でピュリツァー賞にかがやき、一躍世界に名を知られ、やがて34歳の若さで戦場に散った“日本のキャパ”沢田教一。情熱と野望に満ちたその人生の軌跡を、ベトナム、アメリカ、ロンドン、香港に訪ね取材し、浮かび上がらせたノンフィクション。ベトナム戦争のある一面を知ることができる貴重な記録でもある。
-
3.0
-
4.3「何を読めばいいんですか?」と聞かれるたびに困った。「読むべき本」が多すぎる! だから「実は読まなくてもいい本」を決めればいいのでは、と考えた。「知のパラダイム変換」が起きた今、複雑系、進化論、ゲーム理論、脳科学、ICT(情報通信技術)の分野で「読むべき本」が浮かび上がる驚きの読書術。文庫版書下し「リベラル化する世界の分断」を加えパワーアップして再登場!
-
4.0謎のイタリア人パオロ氏がはじめたお店は立ち食いそば屋兼古本屋! 「お金もちになるための方法は?」「体罰は必要?」「のらネコと共存するには?」──ご近所の主婦が持ち込む数々の難題を、おすすめ本でズバッと解決。鮮やかなツッコミも冴えわたる知的エンタメ読書ガイド! 「自殺予防に民主主義」「頭か、腹か」「日記に書かれた戦前・戦中」の文庫版おまけ三本を追加。
-
4.5
-
4.3誰にも文句を言われず好きなだけ寝ていられる。時間を気にせず好きなことができる。10万円で小屋を作ってベーシックに暮らす(Bライフ)までの試行錯誤。雑木林に土地を買い、手工具で小屋を建て、水や電気、トイレ等の生活設備を整える。地元の人の反応や野生動物との出会いも。文庫化にあたり薪ストーブの楽しみについても追記。小屋ブームの一端を担った本。
-
3.2
-
4.2
-
3.8iPadやキンドルの登場により日本でも電子書籍の時代が始まると騒がれている。しかし、このブームは定着するのだろうか? 紙のメディアは生き残れるのか? 不透明な先行きに冷静かつ確かな展望をもつためのポイントを、グーグル、アップル、アマゾンらの動向と、日本の出版社・新聞社の試みとを丹念に取材・分析する。
-
-
-
4.4老王リアは退位にあたり、三人の娘に領土を分配する決意を固める。二人の姉は巧みな言葉で父を喜ばせるが、末娘コーディリアの率直な言葉にリアは激怒し、彼女を勘当、二人の姉にすべての権力・財産を譲ってしまう。ここから老王の悲劇は始まった。シェイクスピア四大悲劇の最高峰を第一人者による流麗の技で訳出。詳細を極めた脚注を付す。
-
3.7連合艦隊が勝利した最大の要因は軍事技術の合理的で正確な運用にあった。日本は近代砲術の基礎となる「斉射法」を世界に先駆けて用いただけでなく、独自の砲術計算によって精度を高めていったのである。その後の海上決戦の範となった日本海海戦の全貌を検証し再現する。『坂の上の雲』では分からない日本海海戦の真実!
-
-「泣きながら一気にページをめくったあの日を忘れることはできません」。 ひとりの読者の感想から広がり、子育てに悩む女性たちの間で話題に。 子は、親が大好きだ。 かつて子どもだったあなたへ、子育て中のあなたへ。 どの子も親が大好きで、「自分が役に立っているだろうか」「必要とされているだろうか」と考えている。しかし思春期になり、親から逃れようとする心と、従おうとする心の葛藤に悩み「心の病」になってしまう。真の解決は、親が子を救い出すのではなく、子に親が救われるのだと分かった時に訪れる。「引きこもり」や「拒食症」で悩む多くの子どもたちに向き合い、心の声に耳を傾けてきた著者が綴る、あなたの子どもと、かつて子どもだった親を救う本。
-
4.3
-
5.0
-
4.4
-
4.0
-
4.3
-
4.2
-
3.0
-
4.3「若年性レビー小体型認知症」本人による、世界初となる自己観察と思索の記録。認知症、脳の病気とは一体何なのかを根本から問い、人間とは何か、生きるとはどういうことかを考えさせる。周りに理解されないための孤独と絶望の中にありながら、幻覚(幻視、幻聴など)、嗅覚障害、自律神経症状など自分に起きたことを日記形式で淡々と観察し、卓越した文章力で表現した希望の書。
-
3.0
-
3.0日本映画の黄金期を支えた、巨匠と名優たち。小津安二郎と原節子、溝口健二と田中絹代、木下惠介と高峰秀子、黒澤明と三船敏郎。ゴールデンコンビによる数々の名作。その誕生の裏に隠された壮絶な人間ドラマとは? NHK第2「カルチャーラジオ」で好評を得た「日本映画の黄金期を支えた監督とスターたち」を大幅に改稿した、文庫オリジナル。
-
4.32004年京都市左京区に開店。2015年にホホホ座へと発展してきたガケ書房。インパクトある外観と独自の品揃え、店内ライブなどで唯一無二の存在となり、全国の読者や作家、ミュージシャンに愛されてきた。筆談で過ごした子供時代、様々な仕事の体験、開業後の資金繰り、セレクトというモノの売り方への違和感などを本音で綴った青春記。
-
4.0ラクダのこぶ、サソリ、ウマのたてがみから、土のスープ、樹液、みかんご飯、甘口イチゴスパ、そして紙、蚊の目玉のスープまで。伝統食品あり幻の珍グルメあり。「奇食とは、人間世界の謎を開ける鍵なのだ」という著者の、悶絶必至、味の大冒険。人間の業の深さを実感する珍グルメ全集。文庫化にあたり、パンカツ、トド、イソギンチャク、蘇など8品を増補。全56品。
-
4.0古くは“バレばなし”とよばれてきた“艶笑落語”。いいかえれば、セクシー落語、ピンク落語、ポルノ落語でもある。品よく形容するならば、好色落語、お色気落語、風流落語ということになる。本書は、江戸時代から今日まで、“お座敷ばなし”として、ひそかに語りつがれて来た何百という艶笑小咄の中から精選し、バラエティ豊かに編んだ正統な小咄傑作集。
-
3.6
-
-親子三人競演の『びんぼう自慢』出版記念会、りん夫人の涙、洋服嫌い、最後の改名、志ん生のネタ帳……古今亭志ん生に信頼され、名著『びんぼう自慢』の聞き手&構成者として、長年、志ん生とその家族と交流を続けてきた著者が『びんぼう自慢』に収録しきれなかったエピソードや志ん生への愛情あふれる思い出をつづる。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

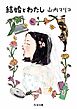

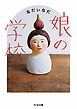

















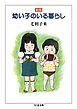





















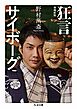

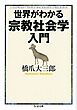
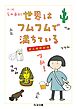

![ぼくたちは習慣で、できている。[増補版]](https://res.booklive.jp/1067299/001/thumbnail/S.jpg)