サブカルチャー・雑学作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「大きさ」「重さ」「速さ」「強さ」「賢さ」などトコトンくらべたら、新発見が続々! 歴史的事実と科学的根拠をもとに作った新タイプの空想科学図鑑! 本書では、「もしも現代に恐竜がいたら……」そんなありえない夢にこたえ、さまざまな研究によってみえてきた恐竜たちの生態を、恐竜どうしや現在の動物たちとくらべています。「恐竜」とひとくくりにしても、その姿や生態は実にさまざま。30mを超える超大型恐竜もいれば、小型犬ほどの恐竜もいます。大きさ、重さや速さから、頭の幅や歯の形、嗅覚や賢さまで……。あらゆる視点でくらべてみると、改めて恐竜たちのすごさを実感して、わくわくすることでしょう。【もくじ】◆プロローグ漫画 ケラトふたたび!◆第1章 恐竜のいろいろをくらべる全長、体重(重さ、軽さ)、高さ、嗅覚、賢さ、頭部の“武装”、短距離走、歯…など◆第2章 恐竜ワールドカップ アジア、アフリカ、オセアニア・南極大陸、南アメリカ、北アメリカ、ヨーロッパ…など◆第3章 古生物のいろいろをくらべる陸上動物の大きさ、水棲生物の大きさ、どこまで潜れた?、飛行距離…など◆エピローグ漫画 また会う日まで「大きさ」「重さ」「速さ」「強さ」「賢さ」などトコトンくらべたら、新発見が続々!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 旅行ガイドブックには載らないような奈良の「隠れ名所」を厳選紹介。その地に残る、日本史の意外な謎に迫る!「三島由紀夫が感嘆した『ゆりまつり』を支える人々」「最中の文様に残る江戸時代の脳トレブーム」「奈良の景観に合わせた和風のキリスト教会」「石段に彫られた『盃状穴』の謎」「悲劇の大津皇子の本当の墓?」「神話の世界!先住民族『土蜘蛛』の足跡を訪ねて」など、奈良に住んでいる人も奈良通の人も知らない、深掘りしたネタ満載。歴史ロマンあふれる奈良の意外な魅力を凝縮した一冊!
-
4.02016年は不倫元年といっていいほど、著名人の不倫の話題が尽きない1年でした。 ベッキーの「ゲス不倫」からはじまり、ファンキー加藤、乙武洋匡、中村橋之助、石井竜也、三遊亭円楽、桂文枝、 とにかく明るい安村、宮崎謙介元議員、武豊など、芸能人から文化人、政治家、スポーツ選手まで……。 なぜ人はこれほど不倫に陥りやすいのでしょう? いけないとわかっていながら、また、リスクが高いという認識がありながら倫理を超えてしまう本能とは? そこからわかる男女の違いは? など、本書では、最新心理学で人間の本質が浮き彫りになります。 そのように、いまどきの不倫を分析することは男女関係/人間関係の「裏」真理の理解につながります。 不倫をしている人にもしていない人にも、不倫を超えて役立つオモシロ心理学本! ●ベッキー型●ファンキー加藤型●石井竜也型●宮崎元議員型●とにかく明るい安村型など、いまどき不倫のタイプもズバッと分析!
-
4.0今までの恋愛セオリーは全部勘違い!? 書籍発売と同日に入籍を発表し、これまでつき合ってきた男性からもプロポーズされ率100%を誇る著者がセキララに語る、絶対に「彼」を落とせる昼と夜の新テクニック! 『新型ぶりっ子』になれば、欲しい恋も結婚もすべて手に入る! チュートリアル徳井氏推薦! 【新型ぶりっ子とは?】 ・計算ずくの思いやりを駆使(くし)する ・ぶりっ子にはみえないぶりっ子 ・男性はバカではない、という前提でふるまう ・同性に嫌われずに、男性にかわいいと思わせる ・「この子以外とはエッチしたくない」と思わせるエロさ 電子限定特典!書籍用に撮り下ろした未公開カットを多数収録!
-
4.0「おっさんがアイドルを好きであることを、みっともないと思う必要はない。 いや、むしろ胸を張ってもいい趣味だと思う。でも、本当に胸を張るのはどうなのか? 周囲に『俺、アイドルが大好き』とカミングアウトすることですら、いささか躊躇してしまうのが現実で、 ましてや、履歴書の趣味・特技の欄に『アイドル鑑賞』と書きこむ勇気は、なかなかないだろう。 でも、それでいいのだ。心のどこかに“恥じらい”や“うしろめたさ”を抱いていたほうが、 間違いなくアイドルを楽しめるのだから! これは子供や若者には味わえない、おっさんならではの特権であり、 ある意味“醍醐味”でもある。うしろめたさはドキドキを加速させ、恥じらいはワクワクを拡大させる。 だからこそ、大人がアイドルを追いかけることは、途方もなく楽しいし、 まさに究極の『大人の嗜み』と言ってもいいのではないか?」(序章より) 中年のおっさんであり、夫であり、アイドルオタクであり、 同時にフリーライターとして週末になるとさまざまなアイドルの取材に出かけている著者が、 めいっぱい自分の恥を晒しつつ、アイドルを“たしなむ”ことの素晴らしさと、そこに生じる苦しみや悲しみを、 たっぷりと綴る。著者が追い続けた元AKB48 平嶋夏海との対談も掲載! 【著者情報】 小島和宏(こじま・かずひろ) 1968年、茨城県出身。 1981年、テレビの歌番組で観た伊藤つかさの『少女人形』がきっかけでアイドルにハマる。 以後、断続的にアイドルを追いかけてきたが、2004年の結婚を機に完全他界。 しかし、雑誌編集者に口説き落とされ、2009年ごろからアイドル関連の記事を執筆するようになり、アイドル熱が再発。 2011年にももいろクローバーと出会って以降、取材の軸足を完全にアイドルに移す。 『Quick Japan』(太田出版)では、毎号100ページを超えるももクロ特集&メンバー個別特集をほぼ1人で執筆。 現在はももクロを中心に、HKT48、Negiccoらの取材に奔走し、雑誌やムックで幅広く執筆中。 ももクロのイベントやトークショーでは、メンバーと一緒にステージに立つことも多い。 2015年末からは、Negiccoの13年間の足跡を追った長期ドキュメント『Negicco~Road to Budokan』を『BUBKA』(白夜書房)にて連載中。 主なアイドル関連書籍に『AKB裏ヒストリー ファン公式読本』『ももクロ活字録』『活字アイドル論』(白夜書房)、 『3・11とアイドル』(コア新書)、『ももクロ見聞録』(SDP)がある。
-
4.0単行本『生きがいの創造』が、まったく新しいタイプの人生の案内書として話題を呼んでから、本書の親本であり、続編となる、単行本『生きがいの創造II』が世に出るまでに、実に9年の歳月が過ぎていた。そして、その本の冒頭には、「このことを公開すべき時がようやく、やってきました」とある。つまり、『生きがいの創造II』とは、『生きがいの創造』を発表するにいたった経緯を、著者自身が綴った告白の書と言ってよい。内容は、「そんなこと絶対にあり得ない」と言いたくなったり、「これは空想的な物語だろう」と評価する読者がいるかもしれない。しかし、ここに書かれていることは、まぎれもなく、著者自身の体験なのである。直観力が鋭くなくても、「心の眼」を大きく開いて読めば、そういう世界が存在しても不思議ではないと、理解できるはずだ。その時、読者は歴史が変る証人になっているはずだ。なぜ生きなければいけないか、その理由がわかる本。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本刀と歴史人物とのエピソードや名刀にまつわる「物語」「噂と謎」「製作者」「使い手」を紹介
-
4.0AVやエロ本などで得られる間違った知識に捕らわれているみなさん。それらはファンタジーであり、リアルではありません。いったんそれらを白紙に戻す必要があります。最近本当に気持ちのいいセックスをしたのはいつですか? パートナーと通じ合って、二人が感じ合えるセックスをしていますか? 本当にきもちのいいセックスを知ることは豊かな生き方を知ることです。今こそ性欲とセックスについて正しく知り、性と生について学び直してみませんか?
-
4.0「愛している」という言葉は、恋愛小説やドラマなどでは陳腐なぐらいよく使われるフレーズである。実際生活においても、私たちはこの言葉を、便利なものとして、さまざまな場合において使っているのではないだろうか? しかし、突き詰めて考えてみれば、「愛」とは、いったいどういうものなのか? このことは、古今東西の哲学者や作家たちが、それこそ大まじめに追及してきた、「人生における究極のテーマ」なのだ。私たちは、物事の価値観が揺れ動いている現代において、このテーマについていかなる考察をしておかなければならないのか。このような問題意識にたって書かれたのが、本書である。「男女の愛」から、より広い意味での「人間愛」にいたるまで、さまざまな角度から深く検証と考察を行い、読者の人生観や恋愛観、価値観にまで大きな揺さぶりをかけて行く。魅力にあふれた人生論である。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 きのこ検定とは、きのこの楽しさと魅力を伝えるのに役立つ知識の習得度をはかる検定試験。おいしい料理、体にいい健康食品、野遊びで見つける楽しさなど。様々な角度からきのこを知れば知るほど、奥深いきのこの世界が広がります! 本書はその公式テキストで、きのこ図鑑150種、おいしくヘルシーにいただくレシピ集など、新たなテーマを増補した改訂版です。 【第1章 きのこの食文化と栄養学】きのこレシピ、きのこを食べて美しくなる、菌のパワーを食生活に生かす、きのこ別の効能、きのこの味と香り、きのこと料理、きのこの薬用利用 【第2章 きのこ図鑑】全150種のカラーガイド、きのこを記録する、きのこの切手、きのこのグッズ、きのことエンターテイメント 【第3章 きのこ生物学】きのこは菌類、きのこの構造特徴見分け方、きのこのライフサイクル、きのこの生育環境、身近にあるきのこ、きのこ狩りの注意点、採取したキノコの保存方法、毒キノコの対処法 【第4章 日本のきのこ】日本のきのこの歴史、日本における人工栽培の歴史、きのこの語源と方言、日本の消費状況、きのこ栽培にチャレンジ、きのこの大規模生産 【第5章 世界のきのこ】世界のきのこの歴史、世界のキノコ栽培、各国語できのこ、世界の消費状況、きのこの文学、きのこと地球環境、フェアリーリングとは? 【きのこ検定とは・級別模擬問題】
-
4.0民俗学の祖として知られる柳田国男。しかしその学問は狭義の民俗学にとどまらぬ「柳田学」として、日本近代史上に燦然と輝いている。それは近代化に立ち後れた日本社会が、今後いかにあるべきかを構想し、翻ってその社会の基層にあるものが何かを考え尽くした知の体系だった。農政官僚、新聞人、そして民俗学者としてフィールドワークを積み重ねるなかで、その思想をいかに展開していったのか。その政治・経済・社会構想と氏神信仰論を中心としつつ、その知の全貌を再検討する。
-
4.0「しゃらくせえ」「おととい来やがれ!」――ユーモアたっぷりのセリフから、「都会人・江戸っ子」の暮らしぶりとオモシロ気質を読みとく。【主な内容】「こちとらちゃきちゃきの江戸っ子でい」―江戸っ子の決めゼリフ/「火事と喧嘩は江戸の華」―揉めごとに効く啖呵/「浅葱裏は野暮天の看板」―勤番侍や江戸庶民の服装/「月も朧に白魚の……」―隅田川と江戸っ子の食生活/「椀と箸を持って来やれと壁をぶち」―長屋の日常生活/「現銀安売掛値なし」―新しい商法の売り文句/「嬶アを質に入れても初鰹を食う」―初物に美学を感じる江戸っ子哲学/「二本差しが怖くて目刺しが食えるか」―武士なにするものぞの心意気/「何くわぬ顔で男にけつまづき」―男と女の出会い/「田舎者でござい、冷えものでござい」―江戸のしきたり/「知らざあ言って聞かせやしょう」―歌舞伎、川柳など町人文化/「花の雲鐘は上野か浅草か」―俳句や川柳に描かれた盛り場
-
4.0米を主食としてきた日本で、空前の「パンブーム」が起きている。日本人お得意の「和洋折衷」力で世界をうならせるほど一大進化を遂げたパン文化。SNSに料理写真が躍り、食マニアが増えた現代だからこそ、百五十年の歴史が生み出した到達点を振り返ることに大きな意味があるだろう。おなかがすくこと必至!パンだけでなく、「食」にまつわる現代の動きがわかる一冊である。 ・日本人のためのパン、はじまりはあんパンから ・パン文化の礎を築いた外国人戦争捕虜たち ・パン好きは特に関西に多い ・「ふわふわ」「モチモチ」は日本独特の好み ・在日外国人が口をそろえて「日本のフランスパンはおいしい」 *電子版は文中写真がすべてカラーとなっております。
-
4.0律令国家の時代にいた、「陰陽師(おんみょうじ)」を知っていますか? 陰陽師は、天文学、方位学、暦学、易学にもとづいて、都市計画や年中行事の作成に携わる一方、 吉凶占いやお祓い、祈祷といった呪術的な側面もあわせもつ官職でした。 その陰陽師の末裔として、四国の四万十川のほとりで代々、陰陽師由来の陰陽の教えを受け継ぎながら、 鑑定師の道を歩み、これまで5万人以上の人々の人生を好転させてきた。それが、この本の著者、幸輝氏です。 運気を上げるために、どんな考え方に立ち、どう行動をすればいいのか。 この本では、運気をあやつる鑑定師といえる幸輝氏が、一日中、あなたのそばにいたとしたら、どんなアドバイスをするか、という視点で、 陰陽の考え方に基づいた効果絶大の開運方法を伝授します。 本書巻頭には、効果絶大と評判の陰陽霊符(れいふ)つき。 よき流れとご縁がもたらされるよう、渾身のエネルギーを込めてお届けする一冊です。 *目次より 【朝の暗示】 ●「改札」は陰陽の世界のさかいめ、空間の変化を意識しなさい 【昼の暗示】 ●相手の右目を見るか、左目を見るか、私が話す内容で変えている理由 【夜の暗示】 ●トイレに長居して運気を逃がすな 【男女関係がうまくいく陰陽術】 ●復縁がかなうか、すでに終わっているかがわかる「赤い糸の秘儀」 【お金に好かれる陰陽術】 ●小銭は常に「5円玉を9枚」財布に入れておきなさい
-
4.0現代の女子と同じように、恋に悩み、おしゃれを楽しみ、将来を真剣に考えていた平安時代の女子たち。その喜怒哀楽を一緒に味わいながら、住まいやファッション、恋愛と結婚、身分や進路など、古典常識を楽しく身につけましょう♪ メールテクや夢の探し方など、いまも役立つ情報が満載。美しい挿絵もいっぱいの、一番わかりやすい古典入門です。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 知って得する! 今のあなたにピッタリな神様がきっと見つかる! 古来の神様は女子にうれしいご利益がいっぱい! 日本には「八百万(やおよろず)の神」といわれるように、たくさんの神さまがいます。 そして、神さまによって“ご利益”がそれぞれちがいます。 本書は、どの神さまがどんなご利益、どんな個性をもっているかをかわいいイラストと共に紹介する“神さまのカタログ”です。 恋愛、お仕事、夢、健康などなど。 女子の欲張りな願いをかなえたいとき、困ったときにどの神さまに何をお願いすれば良いのかがわかります。 「女子力アップに、この神さま」 ・美人の神さま…宗像三女神 ・若返りの神さま…月読命 ・ダイエットの神さま…天手力男命 「恋愛・結婚に効く、この神さま」 ・縁結びの神さま…大国さま(大国主命) ・浮気防止の神さま…スセリヒメノミコト など。
-
4.0「この人の作るものが見たい!」と思わせる作り手が最近、少ない。そんな時代に異質な輝きを放ち、今、もっとも注目を集める演出家・プロデューサーの一人の、TBSプロデューサーの藤井健太郎が、企画の立て方、細部へのこだわり、お笑い論を通して、「熱狂的なファン」を生み出すコンテンツの作り方、仕事の手法を初めて明かします。 ※本書の電子書籍化に際し、コラムと対談のそれぞれ数ページとオマケQRコードの収録を見送らせていただきました。あらかじめご了承ください。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 なるほど納得! SEXテク60★これで今晩イキまくり!!★裏モノJAPAN まんがでわかる! 60通りのセックステクニック ★清楚なお嬢様も! ★ナマイキGALも! ★不感症の奥様も! ●アソコの正しい攻め方 ●下手な女はこう仕込め ●飽きた女が新鮮に! ●感じまくるNEW体位 ●羞恥プレイてんこ盛り ●あの性感帯を知ってたか ・どうせ乳首やクリ攻めでしょと思わせておいてキスをしまくる ・脱ぎかけのシャツを口にくわえさせれば凌辱感たっぷり ・抜いて拭いて舐める。この繰り返しでマン汁ペニスも無抵抗に ・下手くそフェラがティッシュ1枚で唾液じゅぼじゅぼに ・ごぶさた系の人妻は顔全体で硬いチンコを味わい尽くす ・ブスのは舐めたくない・・・。ラップ越しのクンニが結構イイんですって ・湿布のプニプニがクンニの代用になるなんてありがたや ・イキそうな気配を察したときに手マンのスピードを上げていないか? ・繊細さを愛するレズたちはアソコをいじるときに小指を使う ・指曲げ! 回転! 浣腸フォームでヒダヒダを刺激せよ 他50項目 編集部より★本誌掲載記事の中には真似をすると法律に触れるものも含まれています。悪用は厳禁です。
-
4.0夢とロマンにあふれたツチノコ探索記の傑作が、40年以上のときを経て、大人気「黒本」シリーズ(「黒部の山賊」「山怪」等)の装丁を纏い、待望の復刊! 昭和40年代に日本中の話題をさらった幻の珍獣ツチノコ。 ツチノコはきっといると信じる著者・山本素石が、同志たちを引き連れ日本津々浦々を駆けめぐる様子を描く、ユーモアたっぷりの怪蛇探索記。 巻頭には、素石率いるノータリンクラブの活動をモチーフに小説『すべってころんで』(朝日新聞連載)を執筆した田辺聖子氏がツチノコ愛にあふれた一文を寄せる。 また、黒本版復刻に際し、月刊『ムー』編集長の三上丈晴氏が特別に解説文を執筆している。
-
4.0目には見えないが、そこに確かに存在する何か。日本ではこれを妖怪と呼ぶが、その正体を明らかにする研究こそが「妖怪人類学」である。自ら設立した世界妖怪協会で、この研究活動を晩年のライフワークとした水木しげるは、日本と世界を旅して各地の〈目に見えない存在〉の渉猟に励んだ。その研究成果の粋を集めた本書には、各誌で掲載されたフルカラーの妖怪絵79点と解説編を収録。水木ファン必携の1冊。
-
4.0ポケモンGOよりクセになる? 珍樹ハント! 「珍樹ハント」とは、樹木の幹や枝などに現れる、動物やキャラクター、はたまた有名人にそっくりな模様や形を見つけること。 この奇天烈な遊びに魅せられて珍樹ハンターとなった、この道十年以上の著者が、二千点を超えるコレクションの中から、えりすぐりの写真を大公開! 健康にいい、脳が活性化する、お金がかからない。そして病みつきに! 子どもからお年寄りまで楽しめる樹木のワンダーランドへご招待します。
-
4.0平安時代に活躍した大陰陽師・安倍晴明の末裔たち六家系が、1000年以上もその術や叡智を継承し、歴史の裏舞台で今もなお日本を支え守り続けているという。 その六家系のうちのひとつ、水の家系第27代の安倍成道氏が、自ら正統・陰陽師の知られざる歴史、過酷を極める修行、1080にもなる術の数々などについて、初めて語った一冊。 1000年以上という長きに渡り、陰陽師の血脈がいかにして継承されてきたのか? 陰陽師の修行とは、どのようなものなのか? そして、そもそも陰陽師とは、何者であるのか……? 繰り返される歴史の荒波を避けるように表舞台から姿を消し、極めて限られた人のみを守り支えてきた陰陽師の中にあって、その連絡先を公表し、一般の鑑定も受け付ける稀有な活動を行っている成道氏。先読みの術、結界、そして除霊など、水の家系が得意とする術の数々について、実際の体験談も含めて紹介。
-
4.0世界中から日夜、不気味な事件や現象が報告されている。 世界中の人々の夢に現れる謎の男「THIS MAN」、南米のサッカー場に現れた伝説の怪人「シャドーマン」、NASAが撮影した未知の人工衛星「黒騎士の衛星」、UFOが映った「バナナTVのUFO」、古代の遺跡から発見された謎の数字「ニネヴェ定数」、そして世界中から報告が相次いでいる“地球の終末を告げる音”「アポカリプティック・サウンド」…。 果たしてそれらは本当なのか?『謎解き超常現象』シリーズで数々のオカルト事件を解明してきたASIOSが、ネットで話題の最新怪奇現象の謎解きに挑戦! 41の真相を解き明かす!
-
4.0世界中の歴史遺産に刻まれた謎の文字群がなぜ日本の神代文字と言霊で意味を成すのか。Welcome To Ryohten’s KARA World。
-
4.0覚醒した宇宙人の魂サアラが、宇宙セントラルのマスター・メータックスから聞いた情報をもとに、今一番伝えるべき大切なことを完全セレクション。
-
4.02020年、大学入試が激変する! 大学・高校ランキングも変わる! 2020年に大学入試センター試験が廃止された後、大学入試はどうなるのか? さらに企業の採用の変化まで含め、これからの子どもの進路選びを考えるために必読の一冊!
-
4.0故障なし、放射能漏れなし、廃棄物なし、燃料交換も運転員も送電線もなくていい―脱原発を現実的に可能にする夢の超技術(カプセル型発電機ネイチャー・セル10)の全貌を世界で初めて一般に公開。
-
4.0「聖書の暗号」と「日月神示」に「真実・未来・正しい対処法」がある―よい世の中はわれわれで創れる。その道しるべ。
-
4.0誰もが目的をもって生まれてくる。自分のミッションがわかれば、宇宙は味方し、出会いは引き寄せられ、人生は輝き出す! 古代マヤ文明の儀式で使われた「ツォルキン暦」から「人生の目的」「幸せへの道筋」を読み解く方法を紹介します。この本の主な内容/プロローグ 人生に奇跡を起こす「マヤの叡智」/第1部 「マヤ暦」が告げる、あなたの「生まれてきた目的」/第2部 「マヤ暦」でわかる、「ソウルメイト」の引き寄せ方/第3部 「マヤ暦」が指し示す、「人間関係」の築き方 第1部では、太陽の紋章ごとの「覚醒ポイント」と「マヤの叡智」を紹介。第2部では、体表の紋章ごとの「人を魅了する方法」と「各紋章をもつ人へのアプローチのコツ」、第3部では「感覚がお互いに似ている太陽の紋章」、「背中合わせの関係の紋章」などをご紹介。巻末に「西暦とマヤ暦の対照表」があるので、簡単に自分や相手の「太陽の紋章」を割り出せます。
-
4.0パリ、ミラノ、東京のファッション・ショーを、各メゾンのショーで流れる音楽=「ウォーキング・ミュージック」の観点から構造分析する、まったく新しいファッション批評。パリコレ以後を増補。
-
4.0敵と街角や店で出くわす。「いい話」につられて、面倒を押し付けられる。実績を上げて妬みを買う……。一流ヤクザほど、そんな危機のタネを鋭く察知して未然に防ぎ、もしコトが起こっても賢く逃げる。常にリスクに晒されながら生きる者たちに学ぶ、トラブルを無傷で切り抜け、かつ得を取る最強の自己防衛術。危機回避は常在戦場のプロが知っている。
-
4.0【知識ではなく、行動を共有しよう】あなたは「レディ」として扱われていますか? 「紳士は、すべての人に平等に接しますが、きちんと区別しています(本文より)」言葉遣い、立ち居振る舞い、心遣い……「紳士」と行動を共有し、レディとしての嗜みを身につけましょう! [レディに生まれ変わる習慣一例]・ゴキゲンなボキャブラリーを、増やそう。・一つの成功で、勝ち組と勘違いしない。・「一番になれない所」に行こう。・違いを、楽しもう。・わざと失敗して学ぼう。・「知ってる」よりも「もっとしたい」を楽しもう。
-
4.0東日本大震災を予言し、見事に的中させた松原照子が自らの超常能力を語る。幼いころから彼女だけに見えていた「不思議な世界の住人」から教えてもらった本当の歴史、そして近未来に起こるであろう世界と日本の事件と災害などをあますところなく大公開する。
-
4.0現存する最古の歌集『万葉集』には、日本と日本人の夜明けの姿がいきいきと描かれている。とくに東歌・防人の歌では庶民の作が多く、奈良朝の貴族でない人々の心象に分け入ることができる。本書は、若き日に和歌に傾倒した「歴史探偵」が、万葉の世界を現代感覚で読み解く。「雑学・名もなき人の歌」「長安の山上憶良」の二部構成で、思わず耽読してしまう滋味深い随想集。
-
4.08年前に『彼と復縁したい貴女へ』という女性の復縁本を、 織田先生にお描きいただき刊行しました。 多くの男性から「男性版は出ないのか」「ぜひ、出してほしい」と 問い合わせをいただき、驚いた経験があります。 一度終わった恋愛を復活させて幸せになれるのか? と思う人もいるかもしれません。 ですが、私の周りは、復縁(復活愛)で幸せになった友人等が多数います。 一度離れたことで、彼や彼女の良さに気づくことができた。今度こそ、この関係を大切にしたい。そう思ったことでお互いを大事にし、いい関係を築くことができているようです。 ぜひ本書を読んで、今度こそ、大事な彼女と幸せな関係を築き上げてください。 ■目次 ・1 必要なのは「覚悟」 ・2 彼女の心を取り戻すステップ1 距離を置く ・3 彼女の心を取り戻すステップ2 弱みをなくす ・4 彼女の心を取り戻すステップ3 強さと安定感を手に入れる ・5 彼女の心を取り戻すステップ4 見た目で彼女を虜にする ・6 彼女の心を取り戻すステップ5 今度こそ、彼女にとって必要な存在になる ・7 彼女に連絡を取る ・8 彼女との再会、そして復縁へ ■著者 織田隼人
-
4.0一度終わった恋愛を復活させて幸せになれるのか? と、思う人もいるかもしれません。 ですが、私の周りは、復縁(復活愛)で幸せになった友人等が多数います。 一度離れたことで、彼や彼女の良さに気づくことができた。 今度こそ、この関係を大切にしたい。そう思ったことでお互いを大事にし、 いい関係を築くことができているようです。 でもだからといって、ただ復縁すればいいわけではありません。 やはり一度は終わってしまった関係、心が離れてしまった関係をやりなおすのには、 それなりに変わらなければならない、と著者の織田氏はおっしゃっています。 ぜひ本書を読んで、大好きな彼と幸せな関係を築き上げていただきたいと思います。 貴女の復縁をこの本が手助けします。 ■目次 ●1 キーワードは「半年」 ●2 半年間で貴女がすべき3つのこと ●3 復縁の最大の敵を克服する ●4 幸せな将来のための反省の仕方 ●5 復縁したい女性が悩んでいること ~よくある質問10への回答~ ●6 復縁を成功させるための彼へのアプローチ法 ●7 彼に「復縁したい」と思ってもらうために ●8 すべては復縁が成功したときから始まる ■著者 織田隼人(おだ・はやと)
-
4.0「ドラえもん」「怪物くん」ほか多くの名作を生み出した「二人で一人のマンガ家」は八七年末にコンビを解消、新たなまんが道を歩み始める。この二つの才能の秘密を解き明かす、唯一の本格的藤子論。
-
4.0地名をみれば、地形の変遷や歴史がわかる。 東京23区内にある416の地名のルーツを解説した由来本。著者自ら、実際に各地に足を運んで地形を確かめ、その歴史を研究した記録です。そもそも、地名は自然地形をもとにしてつけられていました。たとえば、葦(あし)が生えていたから「足立区」、古墳のある高い所だから「竹の塚」、川が造った島・陸地だから「島根」、一日に千駄も薪を伐り出したということから「千駄木」など。このように、名付け方はいたってシンプルですが、このように由来がわかれば、過去の地形やその土地にまつわる歴史まで知ることができるのです。東京23区の散歩のおともにもなるハンディサイズの手軽な地名本。各区の地図付きです。
-
4.0古来より、日本人は花鳥風月に象徴される美しく豊かな自然のもとで、歴史を築き文化を育んできた。文学や美術においても花鳥風月の心が宿り続けている。自然を通し、日本人の精神文化にせまる感動の名著!
-
4.0いいかげんな女、それはつまり「良いさじ加減の女」。・「100点満点の自分」を目指さないで、「いいかげんな50点の自分」にOKを出す・「イタリアンが好き」とオシャレぶるのではなく、「ラーメンが好き」と言う・「黒歴史」を封印するのはやめて、正直に「黒歴史」を武器に変える など、崖っぷちから這い上がり、プチリッチ婚を掴んだからこそわかる、上っ面な関係で終わらせない恋愛術。著者紹介ひろん 恋愛コンサルタント&ファイナンシャルプランナー。28歳で億万長者とのセレブ婚を果たしたものの、あえなく離婚。31歳、バツイチ、家なし、仕事なし、美貌なし、知性なしという婚活偏差値35で再婚活に挑む。泥臭い努力の末、「いいかげんな女」が愛されると実感。たった一年後にプチリッチで優しい男性と再婚を果たす。 現在、「1人でも多くの女性を幸せにしたい」と活動中。ブログ:http://ameblo.jp/hiron-blog/
-
4.0料理の卓を通して人との絆や温かさを感じるほのぼの料理漫画「クッキングパパ」。なかでも主人公の荒岩一味を中心とした妻虹子、長男まこと、長女みゆきの荒岩家の個性豊かな4人はもはや国民的認知度高いハッピー家族と言っても過言ではないだろう。そんな明るく、幸せなイメージの「クッキングパパ」一家と登場人物の知らざれる謎を紹介。
-
4.0累計100万部を突破し今夏、3Dアニメ映画として公開決定した児童文学『ルドルフとイッパイアッテナ』の原作者が"童話を書く秘訣"を伝授!「独創的物語を目指すな」、「テーマは後、先にプロット」といった童話創作の極意から、物語を思いつく方法、動物を上手く書く方法、新人賞に応募する人へのアドバイスなどの具体的なハウツーまでユーモアにあふれる筆致で語られます。児童書業界のさまざまな裏事情も紹介。
-
4.0現代以上に豊富かつイマジネーションに富む江戸の性技巧の数々―。風俗、季節とも密接な関係のある性生活の実相を多彩な春画で解説。
-
4.0恋愛は、人生に関わる大きなトピック。人気ライターの著者は、「別れた男を忘れられない」「長期間、恋愛経験がなく、焦っている」「いつも恋愛が短期間で終わり続かない」「異常な奥手」「“本当の自分”を愛してくれる女性を求め続ける」というように、恋愛において対等なパートナーシップを作ることができず、長期的に苦しむことを「恋愛障害」と名付ける。これらの問題を解決・克服を目指すためのエクササイズを紹介する。
-
4.0人間の不思議な性(さが)を生物学から解き明かす! 同じ人間なのに、お互いの心がなかなか理解できない男と女。同じように進化してきたはずなのに、なぜこんなに違うのだろう。男はなぜ戦争をするのか、女の浮気はなぜバレないのか、ヒトはなぜ一種なのか――本書は、男女とヒトの素朴な疑問を生物学の視点から解説しつつ、動物の人間臭い行動や虫の面白い習性などを紹介するもの。【内容例】●男はなぜ察することができないのか●男はなぜストーカーになるのか●男の体はなぜ女より大きいのか●女はなぜ男より長生きなのか●女はなぜハイヒールを履くのか●女はなぜ手土産にこだわるのか●ヒトの親離れはなぜ遅くなったのか●ヒトはなぜ裸なのか●ヒトはなぜ世界中に広がったのか▼人間はとてつもなくヘンな生き物だ!
-
4.0衝撃のデビュー「ソルジェニーツィン試論」、ポストモダン社会と来るべき世界を語る「郵便的不安たち」など、初期の主要な仕事を収録。思想、批評、サブカルを郵便的に横断する闘いは、ここから始まる!
-
4.0ネイティブハワイアンの伝統的な問題解決法「ホ・オポノポノ」。 これを、ハワイ伝統医療のスペシャリストであり「ハワイの人間州宝」(1983)の故モーナ女史が、 現代社会で活用できるようアレンジしたのが「セルフアイデンティティ スルー ホ・オポノポノ(SITH)」です。 それを世界に広めた第一人者ヒューレン博士と、モーナ女史の一番弟子として活躍するKR女史のおふたりが、 ホ・オポノポノのなかでも最も大切な潜在意識「ウニヒピリ」について、じっくり語ってくれたのが本書。 「ホ・オポノポノ」を正しく実践するためにも、必ず知っておきたい究極の真理です。 *目次より 1 ありがとう、ウニヒピリ。 最愛のカウンセラー もう一人の自分 声を聞く 今のウニヒピリはどんな状態? 正直であるということ 話しかけてみる 2 ごめんなさい、ウニヒピリ。 迷い、傷 苦しみ からだとウニヒピリ(1) からだとウニヒピリ(2) 3 ゆるしてね、ウニヒピリ。 クリーニング 役割 図書館 共同作業 クリーニングツール お手伝いの頼み方 4 愛しています、ウニヒピリ。 いろいろな“声” “なぜ”何も変わらないの? 自分が変わればほかも変わる 事前のクリーニング 5 ゼロ・コード 大切なのはわかろうとしないこと ゼロになるということ 平和は自分から始まる 手放すということ
-
4.0日本政府が3・11地震兵器攻撃を認めないのは、戦争回避のためだった!? 独自の情報源を持つ著者らが、3・11人工地震テロをはじめ、この世を真に動かしている陰謀世界のダークサイドについて語り合う。
-
4.0勉強がイヤで仕方のなかった著者が、「なるべく最小限の労力で成果を出す方法」を考え続けた結果、現役で東大に受かり、仕事についてからもフル活用している「暗記のコツ」をつかむ。勉強=暗記ではないが、少なからず必要とされること。その具体的な方法を余さず公開する。楽に覚えて、かつ地道な努力を続けるヒケツがわかる。 いかに論理的に、能率を上げて問題を解決するか?「そもそも何のために覚えるのか」「覚えなければいけないことは一体何なのか」「覚えたことをどう活用するのか」というステップに注目し、最低限の量を効果的に暗記する方法と、すぐに実行できる「力技と裏技」を紹介します。
-
4.0証拠の残らない“クリーン”な超テクノロジーはシークレット・ガバメントの世界支配手段―3・11東日本大震災でも人類最終兵器「プラズナー」が使われていた!フィラデルフィア実験、ミステリーサークル、エリア51、9・11、インド・スマトラ沖地震、開洋丸、富士山攻撃、琉球タブレット、太秦=イエス・キリスト、多次元同時存在の法則、秦氏、三種の神器=三位一体、平安京ヒト型構造―驚愕の飛鳥情報。
-
4.0(1)われわれの肉体は、本質である霊魂の容れ物です。(2)「この世」と「あの世」の役割は?(3)「この世」での正しい生き方は?これらを分かりやすく書きました。ぜひ正しく理解してください。
-
4.0なぜ昔から、人は「人生を変えたい」と思った時に、神社にお参りしたのか?神社参拝は、あなたの魂の中に眠る神話をめざめさせる儀式だった。神社で、どのように運命が変わるのか、その秘密を公開。
-
4.0ガンジス河の源流、標高4000メートル以上のヒマラヤで140年も修行している伝説の聖者と出会い、ヨーガの奥義を学び霊的導きを受けた日々――。「ヨーガ行者の王」の称号をもつ著者が、自らの体験を物語形式で綴る。
-
4.0陸海空、世界のいたるところに実在する未確認生物たち。飛鳥昭雄が長年収集し続けてきた極秘UMA情報を一挙に大公開。
-
4.0「なぜいつも自分を不幸にするダメな男性ばかり好きになってしまうの?」「つき合っても、いつもプロポーズされない」「いつも片思いばかり」「どうしてどうでもいい人にばかり好かれるの?」など、もしもあなたがいつもうまくいかない恋愛に悩んでいるなら、このメンタルブロックに原因があります。本書では、あなたにかけられたメンタルブロック(=心の制限)を外し、あなたが「愛されて当然だ」と思えるようになるための、「自分をがんじがらめの不幸から救うやり方」と、「自分を幸せに許可するやり方」をご紹介します。氏のアドバイスによって、「突然、男性からちやほやされ出した」「片想いの彼が勝手に近づいてきた」「運命のパートナーに出会えた」等感動の声も続々!! 大人気マリアージュカウンセラーが明かす最高の愛を引き寄せる方法を一挙公開。大好きな人に大切にされる幸せを、あなたも味わってみませんか?
-
4.0A.三十五歳。三十路も半ばだ。B.三十歳六カ月。三十路も半ばだ。正しい使い方はどちらでしょう? 答えは、Bの三十歳六カ月。「みそじ」とは、三十代ではなく三十歳の一年間のみを表すことばです。Aの意味で使っていた方も多いのではないでしょうか。本書では、日本語のプロである新聞の校閲者が、ふだんから間違えやすいことば、意味を取り違えやすいことば、実は勘違いしている慣用句などを200余り取り上げ、クイズ形式でわかりやすく解説します。語源や言葉の変遷なども織り交ぜながら、楽しんで読めて、日々の暮らしにすぐに役立つ一冊です。「足かけ」ってどこからどこまで?/「御の字」の満足度は?/「小春日和」っていつの天気?/一同に会する? 一堂に会する?/快心の作? 会心の作?/けんもほろろは、どんな「けん」?/雪辱を果たす? 晴らす?/「募金」と「寄付」ってどう違う?/「かすみ」と「おぼろ」はどう違う? など
-
4.0文章を書くというのはどういうことか。現代における文章とはどのようなものか、また、その望ましい姿とは。――森鴎外・夏目漱石など明治の作家から、安部公房・大江健三郎・井上ひさしら現代作家まで、豊富な文例をあげながら、近代百年の口語文の歴史のあとを辿る。文章を素材にした近代日本文学史であると同時に、文章表現の心構えを分りやすく説いた、万人のための文章講座。
-
4.0日本語はスリリングな情報と知られざる歴史の宝庫である。漢字は何字覚えればよいか? 「四」が嫌われる本当のワケは? 生前の「藤原不比等」が「プディパラ(の)プピチョ」? 母は「パパ」と呼ばれていた? 遣唐使やザビエルの通訳は誰? 「ら抜き言葉」を使った文豪は? 知るほどに日本語が面白くなる。漢字、発音、文法、歴史について、思わず他人に話したくなる薀蓄(うんちく)を凝縮。読者を「日本語通」への道に誘(いざな)う一冊。
-
4.0厳しさを増すこの時代を生き抜くには、実直に頑張るだけでなく、ときには「ズルさ」を発揮することも必要だ──。社会全体が敵になるような大きな困難を乗り越えてきた著者が、「人と比べない」、「嫌われることを恐れない」、「問題から目をそむけない」などの誰でも直面する11のテーマを解き明かしていく。2014年新書年間ベストセラー『人に強くなる極意』待望の第二弾。
-
4.0脳科学的な見地からすると、恋愛に必ず終わりが訪れるのは極めて正しい反応。しかし、生涯を共に生きる恋愛を超えた愛を手にするにはどうしたら良いのか。まさに目からウロコなアイデアが詰まった一冊。
-
4.0【ご購入の前に】本電子書籍には、紙版に収録されている「カタカムナウタヒ80種」は掲載されておりません。 日本語の源流である「カタカムナ」に秘められた宇宙のしくみ、原理原則を読み解く決定版! 著者はセミナー等で大人気の「ヒフミ48声音の思念読み」の第一人者。カタカムナ文字を分析し、世界中の言葉や現代語に共通した言霊の法則があることを発見。48声音に秘められた内的なエネルギーの法則「カタカムナ48声音の思念」を使うと、言葉の本質的な意味がわかり、夢が実現しやすくなります。精神科医・越智啓子先生、大推薦!
-
4.0「願いを叶えたい」「運命の人に出会いたい」「天職で輝きたい」なら余計なことをやめること! Amebaランキング各種部門第1位! 超人気ブログのメソッドが一冊に! 幸運に導く「最強の味方」とつながる方法【目次】宇宙におまかせ ステップ1 やらなくてもいいことをやめ、制限をはずす/宇宙におまかせ ステップ2 自分を大切に扱い、「受け取ること」に慣れる/宇宙におまかせ ステップ3 よけいな思考を手放し、宇宙に同調する/宇宙におまかせ ステップ4 チラッと思ったことを、実現させる/宇宙におまかせ ステップ5 魂の声を聴き、自動的に奇跡を起こす【著者紹介】大木ゆきの 学校教師、コピーライター等を経て、スピリチュアルの世界で仕事を始め、ワークショップや連続コースを全国で開催。インドの聖地で学び、怖れや執着から自由になる「認識を変える光」を流せるようになる。
-
4.0【さあ、「禁断の方法」をあなたに】お金がないのは、願う強さがまだ足りないから? 必死にがんばっているのになぜ? 「引き寄せ」は結局、特別な人だけに起こることなの? ……いいえ、必死に願わなくても、がんばらなくても、「引き寄せの公式(R)」なら誰でも「引き寄せの達人」になれます。あなたにも「幸せなお金」が無限に流れ込むようになるのです。「50歳、リストラ、借金4千万円、所持金2万円」からの超V字回復!! 2ヶ月で月収5倍、3年で年収10倍の“大逆転劇”を成し遂げた著者の真実。奇跡はあなたにも起こる!
-
4.0雑誌『旅』の名編集長として知られた岡田喜秋氏が、全国の有名無名(当時)の山村を訪ね歩いた紀行文32編を収録。 好評のヤマケイ文庫『定本 日本の秘境』『旅に出る日』に次ぐ、文庫化第3弾。 第一部 山村の組曲 秩父、阿武隈山地、栗山郷、足和田、奥只見ほか。 第二部 アルプスの見える村 日本アルプス山麓の各所 第三部 推理する山旅 祖谷渓、秋葉街道筋、白神ほか。 1974年(昭和49)に河出書房新社より刊行した単行本の文庫化です。 底本は、1981年(昭和54)刊行の河出文庫版。
-
4.0天皇のために造られた地下世界、松代大本営。ファンタジーさながらの地下の大神殿、大谷資料館。地下にあったマーケットの痕跡、昭和炭鉱隧道マーケット。特攻隊が潜んでいた洞窟、震洋隊特攻基地鵜原火薬庫。世界遺産になった資源争いの現場、石見銀山。地下だからできた最先端科学の大実験場、スーパーカミオカンデ。 日常生活の中ではあまり意識することはないが、じつは私たちの足の下には多彩な別世界が広がっている。泥だらけになり、野生動物に攻撃され、時には立入禁止の柵の向こうに足を踏み入れつつ著者が見てきたアナザーワールドを、豊富な写真とともに紹介。 本書を読めば、地上の「常識」が変わる!
-
4.0途方もないモノとヒトが集まる、世界有数のメガシティ「東京」。この街には、母国を離れて暮らすアジアの人々のコミュニティーが存在している。 タイマッサージ店やタイ料理屋が密集する“リトル・バンコク”墨田区錦糸町、弾圧を逃れて日本にわたった人々が暮らす“リトル・ヤンゴン”新宿区高田馬場、通りを歩けばスパイスの香りが漂う“リトル・デリー”江戸川区西葛西……。 東京のアジア人街はいかにして生まれたのか。また、人々はその街でどのような暮らしをしているのか。 地元の人々が集まるディープなスポットを訪ね歩き、東京のアジア人街のいまに迫る!
-
4.0古来より日本では様々な拷問が行われてきた。 斬首刑、釜茹で、火炙り、獄門など、よく知られたものから、釣責め、三段切り、瓢箪責め、塩責め、海老責めなど、にわかには想像しがたい処刑も数多く存在した。 果たして、どの時代から、どのような罪に対して、かくも過酷な拷問が行われてきたのだろうか…? その歴史を明らかにしつつ、実際に行われていた過酷な拷問・処刑の数々を徹底解説!
-
4.0風呂敷を使う、万葉集の和歌を覚える、美しいお辞儀をする、思いやりの心を持つ。 「和」の文化が100歳まで脳を伸ばし続ける! 和菓子を食べる、着物を着る。下駄をはく、茶道を習う。 日本文化が最強の脳トレである。 現代人の脳はゆがんでいる。 スマホ、パソコン、ネットに頼った生活は脳を局所的にしか使わなく、若いうちから脳を劣化させてしまい、最悪「IT型認知症」を引き起こす可能性がある。 そこで大事なのが、日本文化に根差した生活習慣をすること。 電化製品に頼らず家事をしてみる、風呂敷を使う。 神社にお参りにいく、祭りに参加する。 最近ではやらなくなってしまった、昔ながらの日本習慣を実践するだけで脳をまんべんなく鍛えることができ、100歳まで伸び続ける脳をつくることができるのだ。 日本人が忘れてしまった日本文化を取り戻すことで、健康脳が手に入る。 第1章 「和」の文化が脳の劣化を予防する 第2章 日本人がもっている「五大脳力」 第3章 「五大脳力」を鍛える「和」のトレーニング 第4章 日本人脳の弱点を知って、強くする
-
4.0「キリスト教を知らずに西洋は分からない」は本当か? 日本人に宇宙船アポロは作れただろうか? なぜ日本人はマネジメントが下手なのか? 英語は本当にグローバルな言語か? 3ヵ月でギリシャ語を学ぶ「草野球式習得法」とは?――仕事に効く「大人の教養」集中講義、すべてのビジネスパーソン必読!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 気持ち悪い!! 恐竜以前の世界にいた、ありえない生物たち! 人類の歴史がはじまる遥か昔、恐竜すらいなかった地球を支配していた「古生物」たち。絶滅してしまったそんな生物たちが、もしも現代にいたら…もしもペットにできたなら……、そんなありえない設定で、太古の生物の魅力と神秘をひもとく、新感覚の空想科学図鑑です。「体の大きさ」「どんな地域や環境で生活していたか」「何を食べていたか」などの基準で、総合的に飼いやすさを判定し、星の数でランク付け!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 もしも、ノミやクモなどの身近な生物の力が強力になったら…? そんなありえない設定を入り口に、野山や海だけでなく身のまわりにいる“実は”危険な生物を紹介する新感覚の図鑑。現代は、身近な危険生物を殺虫剤で駆除できたり、ケガを負っても消毒薬で対処できたりする時代です。そんな技術が発達する一方で、人間は動物としての抵抗力を失っています。本書は、わが身を守る方法もまじめに科学して、生きる知恵も学べる図鑑です。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 宇宙旅行が可能になった近未来。その時代の子どもたちが、宇宙人を探す旅をしながら、太陽系、銀河系、そして宇宙について学ぶ空想科学図鑑となっている本書。「空想」といえども、解説している内容は、しっかりとした科学的根拠にもとづくもの。ありえない設定だからこそ、宇宙の魅力やふしぎがよくわかるようになっています。
-
4.0お宝はどこに眠っている? 「開運! なんでも鑑定団」だけではわからない本物の見分け方、掘り出し物の見つけ方、骨董の楽しみ方を教えます。 本物を見分ける目筋を磨きなさい ■ ファースト・インスピレーションで勝負しろ ■ 儲けようという欲の心を捨て去れ ■ 掘り出し物は値段より伝来で探す ■ 大切なのはどうしても欲しいという純粋な熱意 ■ 約束にかなっていればすべて本物とは限らない ■ 時間をかけて本物をたくさん見なさい ■ 自分の好みのジャンルを極めなさい
-
4.0UFO、UMA、超能力、心霊写真、ピラミッドパワー、ムー大陸……。本書ではオカルトブームの発祥をたどり、日本で“オカルト”と呼ばれているものの実態に迫る。そこからみえてくるのは、社会現象としてのオカルトブームに映し出される戦後日本や僕らの姿なのだ。ネット時代の今、個人はオカルトの自由とでもいえる状況を謳歌している。混迷する21世紀を生き抜くためにも、オカルト好きをカミングアウトしよう!
-
4.01066年、いわゆる「ノルマンの征服」によって、王や貴族、上級聖職者などイングランド王国の支配者層はことごとく、アングロサクソン人から仏語を母語とする「フランス人」に代わった。顧みれば、その僅か142年前にアングロサクソン諸王国を統一し誕生したこの王国の短い治世は、北欧世界から襲来する侵略者との戦いの歴史だった。だが、それは戦場に斃れたアングロサクソン人たちのヒロイックな生き様と共に、ひときわ眩しい光彩を放った時代として、今なおイギリス人の心に深く刻み込まれている。本書は、歴史の狭間に消えゆく故国に命を賭した、誇り高き、最後のアングロサクソン戦士たちの史録である。【目次】イングランド王系図/ウィリアム征服王系図/エゼルレッド無策王とクヌートの子供たち/プロローグ ある日の国連安全保障理事会/第一章 襲い来るデーン/第二章 勇者たち/第三章 終焉への足音/第四章 最後のアングロサクソン戦士/エピローグ 現代イギリス人のルーツたち/附録 モルドンの戦い
-
4.0日本の古代史上、最大の謎とされる邪馬台国。その女王、卑弥呼が中国の皇帝から贈られた「親魏倭王」の金印はいったいどこにあるのか。陵墓に、いっしょに埋葬されているのか。実はある秘密組織が卑弥呼の金印を継承しているという。衝撃の事実を大公開する。
-
4.0敬語は3つだけ! 迷いが消えるハギノ式敬語論 敬語にはたった3種類しかなく、 しかもそのひとつ「丁寧語」は「です・ます・ございます」だけで、おしまいにくっつければいいだけの話ですから少しも難しくない。あとのふたつ「尊敬語」と「謙譲語」だって「ハギノ式敬語のしくみ図」で処理すれば少しも複雑ではありません(本文より) ――これ一冊で敬語の迷いがすっかり解消! 誰でも達人になれる「ハギノ式敬語論」。 問題:次のようなとき、何と言いますか? ● 先生に「貸した本は読み終えたか」と尋ねる ● 部長に「新築の家はできたか」と尋ねる ● 先輩に「ここは鴎外が住んでいたところだ」と言う → 答えは「ハギノ式敬語スタジアムIウォームアップ編」で!
-
4.0私たちは本来、光の存在であり、人生は輝くためにある。どうしたら自分が輝けるのか、何度も生まれ変わった私たちは、いま人生のハイライトを迎えつつあること、地球のハイライト、アセンションを迎えてなど、私たちの生き方と宇宙の未来を説く。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 明治・大正期の作家たちの描いた「山怪」作品を斯界の雄・東雅夫の選で集成。 山の裏側を垣間見るかつてないアンソロジー。 われわれ日本人にとって、最も身近な「異界」である山々は、山神や山人、鬼や天狗、狐狸や木精といった魑魅魍魎のふるさとであると同時に、 日本の怪談文芸や幻想文学の豊饒なるふるさと、原風景でもある。 近代の文豪から現代の人気作家まで。 数多くの作家が、深山幽谷を舞台とする神秘と怪異の物語を手がけてきた。 本書は、山を愛し読書を愛する人々にとって必読の名作佳品を集大成した史上初のアンソロジー企画。 収録作品: 火野葦平「千軒岳にて」 田中貢太郎「山の怪」 岡本綺堂「くろん坊」 宮沢賢治「河原坊」 本堂平四郎「虚空に嘲るもの 秋葉長光」 菊池寛「百鬼夜行」 村山槐多「鉄の童子」 平山蘆江「鈴鹿峠の雨」 泉鏡花「薬草取」 太宰治「魚服記」 中勘助「夢の日記から」 柳田國男「山人外伝資料」 編者解説(東雅夫) ほか。
-
4.0魔術、占星術、錬金術、さらには「聖書にならなかった聖書」まで、ヨーロッパにはあまたの「秘された書」が伝わる。その中から特に重要な書をピックアップ。一冊一冊の内容を豊富な図版と分かりやすい文章でダイジェストする。『東洋魔術書大全』の姉妹版。
-
4.0李光洙は韓国の夏目漱石である。近代文学の祖とされ、知らぬ者はいない。韓国併合前後に明治学院、早大で学び、文筆活動を始めた李は、3・1独立運動に積極関与するが挫折。『東亜日報』編集局長などを務め、多くの小説を著した。だが日中戦争下、治安維持法で逮捕。以後「香山光郎」と創氏改名し日本語小説を発表。終戦後は、「親日」と糾弾を受け、朝鮮戦争で北に連行され消息を絶つ。本書は、過去の日本を見つめつつ、彼の生涯を辿る。
-
4.030日間で、心をほどよくスリムでパワフルに! アドラー流心理学の教えを具体的に実生活に生かしながら、心のダイエットを始めましょう。たとえば…◆自分がつぶやく言葉を「よくやったね」に変える ◆できないことを頼まれたら心を込めて「ノー」という ◆食事に誘われたら、とにかく行ってみる…など、自分を大好きになる60のレッスン。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【カラー版:電子版は本文中の付録画像を全てカラーで収録しました!】『りぼん』創刊60周年企画公式本。●これはすごい! 60年分の全ふろくリスト ●伝説の別冊まんが「カラーシリーズ」全78巻紹介 ●特別インタビュー:一条ゆかり先生、吉住渉先生、水野英子先生ほか……など、創刊以来60年の間についた約3700点の付録を、あらゆる角度から分析。ファン必携の永久保存版!! 【もくじ】カラー口絵 ふろくコレクション/はじめに/りぼんのふろく同窓会 開会のことば/第1章 ドキドキの歴代ふろくベスト10/第2章 わくわくの全ふろくリスト1/第3章 金・銀・カラーの別冊まんがたち/第4章 キラキラの全ふろくリスト2/りぼんのふろく同窓会 閉会のことば/おわりに
-
4.0第1弾「人生のしくみ」では、自分の一生や運命がいかにして決められるかを明らかにし、第2弾「人生の癒し」では心が倦み疲れている人、悩みが頭から消え去らない人たちへの処方箋を提示、第3弾「人生の創造」では、人生をいかに自分の思い通りに作っていくかを説いた。そして今回は、人生を喜びでいっぱいにして、喜びの視点であらためて人生を見つめ直すことを提示。自分が何をしているときに喜びを感じるのかを投げかけ、自分をもっと知るきっかけになる本に。
-
4.0天文学の最先端が、SFの世界観に近づいてきた! 1995年の系外惑星(太陽系の外の惑星)発見以降、惑星学のフィールドは太陽系から銀河系へとドラスティックに変化し続けている。太陽系と系外惑星の異なる点や、惑星や惑星系の生まれ方といった基本的知識から、系外惑星探査の最前線まで、惑星科学分野の泰斗である著者が易しく網羅的に描く、驚きと興奮に満ちた一冊。 [内容] はじめに──惑星の謎を解けば宇宙がわかる 第1章 SFに追いついた天文学──惑星探査の現状 第2章 人と惑星──コペルニクス的転換が起こるまで 第3章 太陽系の誕生 第4章 惑星系はこうして生まれる 第5章 惑星の新しい定義とは 第6章 銀河系惑星学を拓いた二大発見 第7章 生命を宿す星はあるのか おわりに
-
4.0“本当の自由”を手に入れませんか――? 自然とまわりが好きな人ばかりになってくる、嫌なあの人が気にならなくなる、夢のような出会いに恵まれる。難しく考えずに、「本来の自分」を表現するだけですべてはうまく回り出すのです。
-
4.0人生、いまいちパッとしない……原因は、あなたの「セルフイメージ」にあったのです。なぜか人から大事にされてしまう「セルフイメージ」改革レッスン。(内容)序章さあ、チェンジ・スイッチを押しましょう! (著者紹介)中野裕弓 人事コンサルタント、ソーシャルファシリテーター。世界銀行本部よりヘッドハントされ、日本人として初めて人事カウンセラーとして勤務。帰国後、企業でのマネジメントコンサルティングや研修、コミュニケーションカウンセリング、執筆、全国各地での講演など幅広く活躍。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あなたの身も危ない! 被害者続出! 復讐・嫌がらせの手口 裏モノJAPAN 2015年12月号★特集 ・自宅の外からこんな細工をされればお手上げだ ・最近、郵便物がてんで届かないようならこの手口を疑え ・郵便受けが分厚い冊子だらけでドエライことに! ・磁石ひとつでガスを止めてしまう事件続発中 ・電気を勝手に止められれば冷蔵庫の中身が腐ってしまう! ・一晩で室内がゴキブリだらけになる恐ろしい手口 ・立つことが不可能なスッテンコロリン液体 ・雨の日だけ卑猥な言葉がブロック塀に浮かび上がる ・出会い目的の男やゲイが次々と自宅にやってくる恐怖 ・チカン願望の女になりすまし、実際の服装まで伝える鬼畜 ・〈レイプ願望あります〉決してそんな書き込みを信じてはいけない ・あくまで被害者を装う狡猾なリベンジポルノ ・エンコー女性、要注意! 小さな機器で自宅がバレるかもしれません ・画像を見れば最後、スマホの通信速度がメチャ遅に ・たったこれだけのことでLINEが使えなくなる! ・これぞ呪いのメッセージ! ラインを開こうとしたら強制再起動に ・女のシャワーシーンに見入っていたら急に死体写真が! ・ラインをブロックされても確実に罵詈雑言を伝える方法 ・ターゲットの位置情報が本人に気づかれないまま半永久的に届く ・ネット上には我々のスマホやパソコンをぶっ壊す連中がおります ・中古車屋から早朝も夜中も電話を鳴らされればノイローゼ必至 ・着信拒否も意味なし! 「ハァハァ」電話が10秒おきに殺到 ・大量メールが止まらない 迷惑千万なイタズラ ・ママ友イジメに用いられるカルト宗教団体への資料請求 ・フェイスブック友達全員に、風俗に行ったことにされてしまう ・アパートの隣人やカフェの連中のネットを遮断してしまう ・違法駐車の車やバイクにこんな制裁を与える者が! ・こんなにある! 迷惑自転車への嫌がらせ ・キャンキャンうるさい犬の飼い主は要注意 ・ちょっと待った! そのトイレットペーパー、肛門がヤケドするかも ・まさかイヤホンからうるしにかぶれるなんて ・自転車サドルへの嫌がらせはただ濡れるだけでは済まない ・恐怖! 歩くだけで靴が燃え上がるなんて! ・大量の毛髪が抜け落ちる恐るべき除毛剤はどこに混入される? ・無味無臭だけにいくら盛られても気づかず飲んでしまう下剤 ・寄生虫を使って七転八倒の苦しみを与える輩 ・女性に飲ませてガマンできない尿意を… ・タバスコの500倍の辛さでファミレスが阿鼻叫喚 ・タバコに香水をかけられたら呼吸困難になることも! ・シルバーのクロムハーツが数秒で真っ黒に ・もし運転中ならゾッとする…。夜になると急に視界がぼやけてしまう ・100均の磁石を束にすればクレジットカードが即オシャカ ・触られた形跡もなくこっそりスマホを破壊されてしまう恐怖
-
4.0人口減少、経済停滞を迎える日本。そういったなか、復活のカギをにぎるのは「文化」である。すでにヨーロッパでは、国家規模で文化芸術の推進に取り組んでおり、その成果は様々なところに散見される。また、日本でも地域に根差した文化による地方再生が実践されている。そういった現状を分析しつつ、人間国宝といった形のない伝統や、世界遺産に登録されるような景観を活かすだけではなく、私たちの身近にある小さな文化に注目し、そこから日本人がよりよく生きていくための姿を探る。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 みなもと太郎、とり・みき両氏推薦!! マンガの構造やマンガ家それぞれの流儀を愛してやまないマンガ家の上野顕太郎が、めくるめく「マンガの描き方本」の世界へあなたを誘う!!
-
4.0ナンバーワン舞妓としてエリザベス女王などのお座敷にもあがり、20年以上も祇園で活躍してきた著者による「おもてなし」の神髄を語った一冊。会話、ふるまい、身なりなど、祇園の一流の人が徹底している基本がわかる!
-
4.0ミステリー最前線で活躍する作家43人が惜しげもなく披露する、極秘の執筆作法。作家志望者、ミステリーファン必読の書。 日本推理作家協会 編著 赤川次郎/東直己/阿刀田高/我孫子武丸/綾辻行人/有栖川有栖/五十嵐貴久/伊坂幸太郎/石田衣良/岩井志麻子/逢坂剛/大沢在昌/乙一/折原一/恩田陸/垣根涼介/香納諒一/神崎京介/貴志祐介/北方謙三/北村薫/北森鴻/黒川博行/小池真理子/今野敏/柴田よしき/朱川湊人/真保裕一/柄刀一/天童荒太/二階堂黎人/楡周平/野沢尚/法月綸太郎/馳星周/花村萬月/東野圭吾/福井晴敏/船戸与一/宮部みゆき/森村誠一/山田正紀/横山秀夫
-
4.0時代劇、時代小説が100倍楽しめることウケあいの超うんちく話が満載! 明治以来の近代日本には、300年もの徳川幕府の太平が先立ち、日本は300の藩に分かれていた。本書では、全国47都道府県別に分け、戦国時代から幕末までの流れ――300藩の成り立ちから藩主の統治ぶり、さらにいまなお残る名所旧跡まで、すべてを網羅! お城や城下町好きのための観光ガイドとしても最適! これぞ「コンパクト藩史物語」!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 超人気ブログ「暇な女子大生が馬鹿なことをやってみるブログ」が書籍化! 暇な女子大生が「30代男性を逆ナン」「女子大生2人でバイブバーに突撃」「誕生日に元カレに電話」「タイでゴーゴーバーに潜入」など、男と女にまつわるアレコレを、「暇だから」という屈託のない理由で体当たりルポします。 イラスト&写真満載で思わず笑ってしまう面白エッセイ。 ※渾身の書き下ろし8本に加え、全ての記事に「後日談」付き!
-
4.0非力なヒトはなぜ厳しい自然選択を生き残れたのか。走る能力の意外な重要性とは何か。脂肪が健康を害するなら、なぜヒトの体は脂肪が溜まりやすくできているのか。2型糖尿病など、現代人特有の病はそもそもどうして現れたのか……。人類進化の歴史をさかのぼることは、不可解な病がどこから来たのかを教え、ヒトの未来を占うことにもつながる。「裸足で走ることへの回帰」を唱えて名を馳せた進化生物学者リーバーマンが満を持して世に問う、人類進化史の決定版。
-
4.0地理的な空間をどう認識するかは時代によって異なる。その違いを象徴するのが「地図」である。大きくみれば、江戸時代は日本の「かたち」が地図上で整えられた時代であった。前期は、中世的な感覚にあふれ、観念的に日本の「かたち」が表現された。後期になると、政治や社会の変化にあわせて日本がとらえられるようになる。本書では、江戸時代の日本地図の変遷をたどり、現代の日本の「かたち」がいかにつくられたかを探る。近世史の知られざる側面を照射し、歴史地理学の世界へ読者を招待する一冊。
-
4.0からだが疲れる、疲れがとれない、それは血液に代表される体液や気の「流れ」が悪くなるからです。精神的な疲れも、ムダ、無理、コミュニケーションなどの問題から、物事の「流れ」が悪くなるからです。血液を流し、呼吸を流し、ムダなものを流す。そうしてすべてがスムーズに流れれば、からだや心の疲れも流れ去ります。毎日忙しい中で、疲れを「流す」技を身につけようというのが本書の狙いです。
-
4.0「難関中学に合格する家庭」の年間スケジュールがよくわかる! 2008年に刊行され「息子の偏差値が上がった!」「役に立つ内容ばかりで、本がフセンだらけになった」と大好評だった『受験手帳』。本書はその大好評ロングセラーの改訂版。小学6年生からグングン伸びる子、ガクっと落ちる子の違い……それは「親子の12カ月の過ごし方」にあった。勉強法のカリスマ、合格請負人が教える中学受験のためのバイブル!
-
4.0戦国時代、各地に割拠する武将たちは、敵・味方のあいだに流れる微妙な情報を取捨選択し、的確な状況判断を下さねばならなかった。情誼と誠意の仮面の下で知謀の限りを尽くし、山陰・山陽十カ国、豊前・筑前の九州二カ国を合併し、名実ともに中国地方の覇王となった毛利元就の戦いぶりとは? 元就と同時代を生きた武将たちの野望とは? 自らの生き残りを賭けて躍った男たちを描く戦国史話集。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。










![[改訂版] きのこ検定 公式テキスト](https://res.booklive.jp/411313/001/thumbnail/S.jpg)







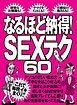




































![[超保存版]UMA完全ファイル](https://res.booklive.jp/50002895/001/thumbnail/S.jpg)











































![受験手帳[改訂版]](https://res.booklive.jp/332148/001/thumbnail/S.jpg)
