無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
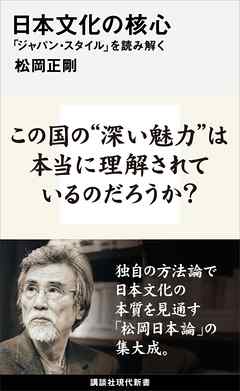
「わび・さび」「数寄」「まねび」……この国の<深い魅力>を解読する!
独自の方法論で日本文化の本質を見通す「松岡日本論」の集大成!
お米のこと、客神、仮名の役割、神仏習合の秘密、「すさび」や「粋」の感覚のこと、「まねび」と日本の教育……断言しますが、日本文化は廃コンテキストで、一見、わかりにくいと見える文脈や表現にこそ真骨頂があるのです。(「はじめに」より)
<本書のおもな内容>
・なぜ日本はヤマトと呼ばれるのか
・神さまをカミと呼ぶようになった理由
・日本人のコメ信仰にひそむ背景
・日本人が「都落ち」にダンディズムを感じる理由
・日本人が七五調の拍子を好むわけ
・世阿弥が必要と考えた「物学」の心
・今の時代に求められる「バサラ」と「かぶき者」
・「伊達」「粋」「通」はなぜ生まれたのか ほか
<本書の構成>
第一講:柱を立てる
第二講:和漢の境をまたぐ
第三講:イノリとミノリ
第四講:神と仏の習合
第五講:和する/荒ぶる
第六講:漂泊と辺境
第七講:型・間・拍子
第八講:小さきもの
第九講:まねび/まなび
第一〇講:或るおおもと
第一一講:かぶいて候
第一二講:市と庭
第一三講:ナリフリかまう
第一四講:ニュースとお笑い
第一五講:経世済民
第一六講:面影を編集する
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。