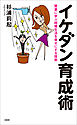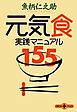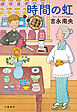文藝春秋作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
3.6暴力団は壊滅できる! 警察官人生を通じ暴力団対策とりわけ凶暴として知られた工藤會対策に従事した刑事が明かす、暴力団との戦いのこれまでとこれから。 福岡県警と工藤會との戦いを通して、暴力団と日本社会がどう向き合うべきかが見えてくるのではないか。きれい事で飾った「ヤクザ」ではなく真の暴力団の姿を、そして暴力団壊滅のために何が必要なのか、多くの市民に知ってほしい。(「はじめに」より抜粋) 【目次より】 第一部 工藤會VS福岡県警 一 取締りあるのみ、の時代 二 工藤會壊滅を目指して 三 市民と共闘の時代へ 四 工藤會頂上作戦 第二部 暴力団VS市民 一 暴力団は今も脅威か 二 市民が暴力団に狙われたら? 三 令和の暴力団との戦い 四 ヤクザと刑事
-
3.8健康診断はこんなに危険! 欧米に健診はない! 日本人の多くは「健康」のため職場健診や人間ドックを受診していますが、欧米には存在しません。 「より健康になる」とか「寿命をのばす」という効果を証明するデータがないからです。 著者の近藤誠さん本人も、慶大病院で在職した40年間、執行部から強い圧力がありながらも、一度も受けませんでした。検診は有効というデータがないからです。 にもかかわらず、日本では、医学的な根拠がないままに健診が義務化されています。 健診は危険がいっぱいです。CTや胃エックス線撮影には放射性被ばくによる発がんリスク、子宮がん検診には流産や不妊症のリスクなどがあります。 異常値が見つかった後に行なわれる肺や前立腺の「生検」も極めて危険です。手術後に「がんではなかった、おめでとう」と平然と述べる医者もいます。 さらに危険なのは、「過剰な検診」が、過剰な薬の処方や手術など「過剰な治療」につながるからです。 人間ドックには「早く見つけるほど、早く死にやすい」という逆説があります。 実際、中村勘三郎さんや川島なお美さんは、人間ドックで「がんを早期発見され、早期に亡くなってしまった」のです。 「検査値より自分のからだを信じる」こそ、健康の秘訣です。健康なときに健診など受けるものではありません。 本書は、さまざまなデータや論文に基づき、「健康診断が有害無益である」ことを徹底的に明らかにします。
-
3.0靴ひもをほどかず、そのまま靴に足を入れる。 スポッとかかとが抜ける靴を履く。 靴ベラを使わず、かかとを踏みつぶすようにして革靴を履く。 「歩きやすいから」と、大きめの靴を履く。 これらはすべて、やってはいけないNG行為。健康に悪影響を及ぼす可能性のある、危険な靴の履き方、選び方なのです。 靴の選び方を誤り、合わない靴――きつい靴はもちろん、大きめの靴もNG――をはいていると、足の骨格の崩れを招き、外反母趾や巻き爪など、足のトラブルにつながります。足はからだ全体を支える土台なので、足ばかりか腰痛、膝痛、肩こりを招いてしまいます。 そして年をとり筋力が衰えてくると、歩行や日常生活にも支障が出て、最悪の場合、寝たきりの引き金になってしまうのです。 では、みなさん、正しい靴を選ぶために、自分の足の正しいサイズを知っていますか? 長さだけではありません。ワイズと呼ばれる足の幅や、太さも重要なのです。 ではサイズを測れば問題解決! というわけにはいきません。なぜなら、靴売り場には限られたサイズしか売られていないため。「自分にぴったりの靴」「ラクに歩ける靴」を探しているのに、そのニーズが満たされないのはなぜか。そこには靴メーカーの事情が見え隠れ。 その結果、「幅広でゆったり、歩きやすい靴」という、健康面からはとんでもない宣伝がとびかうことになるのです。 交通事故による股関節の手術とリハビリを経て、足と靴の健康に目覚めた著者が、「足病学」の知見を取り入れ、間違いだらけの靴選びと、自分に合った靴を見つけられない現状に警鐘をならします!
-
4.0剣道三段、抜刀道五段の著者が描く武人の魂。 歴史に名を刻んだ剣豪、現代に生きる伝説的な武人の壮絶な技と人生を通じて日本人の武とは何かを考える、著者最後の一冊。 歴史に名を刻んだ名剣士と、現代に生きる各流派の伝説的な武人。 その壮絶な技量と圧倒的な人生を通して、日本人の武を考え抜く。 著者の津本陽氏は、日本を代表する歴史、時代作家であるだけでなく、自ら剣道三段、抜刀道五段の腕前であり、武芸への造詣も大変深い作家。 本書には、津本氏本人の剣術修行の様子も詳細に描かれ、氏の「体験的武道入門」ともいえる内容である。 われわれの先人がいかに武を磨き、乱世を生き抜いてきたのか。 津本氏は、戦中、戦後直後の殺伐とした空気のなかで、日本人の攻撃性は維持されたという。 いま、テロに代表されるような「暴力の時代」が、再び訪れようとする予兆がある。 武の心得とは何か、と問うときに、本書の持つ意味は大きいはず。 [目次] 第一話 近藤勇と比肩した男 第二話 永倉新八の竜尾の剣 第三話 明治政府の剣豪 第四話 江戸幕府最後の侍と明治維新 第五話 薩摩隼人と示現流 第六話 龍馬暗殺現場の試斬 第七話 見事の死にざま 第八話 柳生新陰流の極意 第九話 大東流・佐川先生の俤 第十話 夜半の素振り
-
3.7結婚満足度が高い女性はこんなワザを使っていた! 3人に1人が離婚する時代、ダンナに満足し幸せな結婚生活を送るための秘訣とは? 既婚女性2000人以上を対象にした調査を元に、マーケッターが分析。 ダンナを育てるちょっとしたコツを教えます。 プロローグ 結婚して幸せになれる人、なれない人 第一章 史上初! 幸せ結婚調査から見えてきた賢妻たちのプロフィールと結婚生活 第二章 賢妻に学ぶ、基本のイケダン育成術 第三章 こんなに変わった! 家事ダン&育メン育成の秘訣 第四章 結婚後もラブラブが続くために 第五章 気になる賢妻たちのセックス事情 第六章 夫を成功へと導く「アゲマンの術」 第七章 性格の不一致は不幸の原因? 第八章 ケンカの種をどう乗り越える? 第九章 結婚ビジョンをつくろう 第十章 もっともっと! 幸せ時間の増やし方
-
3.8今も影響を残す史上最長政権の功罪 アベノミクス、選挙での圧勝、戦後70年談話、さまざまなスキャンダル、憲法改正をめぐる騒動、TPP……。7年8カ月という例をみない長期政権の評価は、いまも定まっていない。この間、日本の政治をとりまく見方は「反安倍」か、さもなくば「親安倍」かに二分された。この政権は、結局、何をやろうとし、何を残したのか? 『新型コロナ対応民間臨時調査会』『福島原発事故10年検証委員会』など、話題のレポートを次々発表しているシンクタンクが、政権当事者に対する徹底インタビューを軸として、その政権の内幕に迫る。
-
4.1
-
4.1
-
3.8
-
-戦後日本で、かつてなく改憲の可能性が高まるいま、「知ってるようで知らない」憲法について本質を理解するための決定本。 長谷部恭男、片山杜秀、石川健治、森達也、国谷裕子、原武史――憲法を巡る各テーマを豪華ゲストらと共に徹底的に考えた、高橋源一郎の白熱講座へ、ようこそ! ・憲法は条文がすべてではない!? ・9条は意味論と語用論に分けて考えよう ・立憲主義は民主主義と対立し得るもの? ・大正デモクラシーから国家総動員体制にいたった流れ ・天皇の「おことば」が突きつけた問題とは? 社会の「分断」を越えた対話のために――土台となる決定本がここに。
-
3.5
-
4.2誰が一番偉いのか? 何故みんなが従うのか?? なぜトップが責任をとらないのか??? この国を動かす権力のリアルに迫る! 将軍よりも執権よりも「家長」が強かった鎌倉幕府。上皇が複数い たら誰が一番偉いのか? 実力で抜擢すると貴族の人事は荒れる? 日本史の出世と人事をつぶさに見ると、そこには意外な法則が! 人気歴史学者が解き明かす「この国の権力のかたち」。 出世と人事は何で決まってきたのか? ・上皇、女性天皇を生んだ「権力抗争」 ・戦国大名の家柄をチェックすると ・「令和」がなぜいけないのか? ・貴族が悔しがる「超越」とは? ・僧侶の世界も家柄次第 ・父が強すぎる武家の論理 ・明治維新は特異な「実力主義」革命だった ほか ※この電子書籍は、2010年に文春新書から刊行された『天皇はなぜ万世一系なのか』を大幅増補し、再構成した新版を底本としています。「天皇と上皇どちらが偉いのか」「女性天皇を日本史から考える」「令和という年号への違和感」を新章として書き下ろしました。
-
3.8孤独な男女が出会う時、何かが起きる ウーバーイーツの配達員をしているK。TikTokerをしている女子大生のICO(イコ)。巨大な「システム」の中に生きる二人の人生が交錯する時、何かが動きはじめる。実力派作家がデビュー10周年に放つ、渾身作。 ラランド ニシダさん、金原ひとみさん、窪美澄さん絶賛! 「まだ見ぬ誰かとの数奇な巡り合わせはインターネットに操られる。ITは我々を孤独にさせてくれない」(ラランド ニシダさん) 「上田岳弘は、こんなにも抽象の世界から、具体の力を行使する」(金原ひとみさん) 「うんざりするような世界でも、私は誰かと繋がっていたい。そんな欲望を肯定してくれたこの小説は、限りなくせつなく、そしてやさしい」(窪美澄さん)
-
4.0気鋭の現代美術家が描く、美大青春物語! カオス化した美大の学園祭で、田舎出の藝大志望の青年は浪人生活を振り返る。心を打つ表現とは。揺れ動く青年期を鮮明に描いた傑作。 佐渡出身で藝大志望の僕は多摩美の学園祭を訪れ、カオス化した打ち上げに参加する。酒を飲み、芸術論を戦わせる中、僕は浪人生活を見つめ直す。表面的なテクニック重視の受験絵画は、個性や自由といった芸術の理想とはかけ離れていた。真に人の心を揺さぶる表現とは。気鋭の現代美術家が、揺れ動く青年期を鮮明に描いた傑作小説。 ※この電子書籍は2020年8月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
4.0年間500軒のレストランを食べ歩くという芸能界でも屈指のグルメ、渡部建。TV番組のアンケートで「美味しい店を知っている芸能人」の1位に選ばれた彼が、デート、合コン、深夜飯、一人ご飯など目的別に自信を持ってすすめる77軒をセレクト。お店との付き合い方や食べても太らない方法といったコラムも収録した、著者初のグルメガイド!
-
-「芸能界のアテンド王が教える最強の店77軒」に続く、アンジャッシュ渡部建のグルメ本第2弾! 前作はシチュエーション別にお店をチョイスしたが、今回は、東京にあるレストランで著者が何度でも食べに行きたくなる究極のメニュー100皿をセレクト! 一本100円の串からコースの中の一皿まで! 見ているだけでお腹がすいてくること間違いなし。1,000円以下の安旨グルメも豊富に紹介! インバウンド向けに料理名英訳付き。
-
3.6なぜ四季のセリフは聞きやすいのか――。創立60周年を迎えた日本を代表する劇団「劇団四季」は、他の新劇と比べてセリフの聞き取りやすさに定評があります。その秘密は「母音法」「呼吸法」「フレージング法」という独自のメソッド。言葉に対する探求の積み重ねが生んだ賜物といえるでしょう。それを会得することは、一般の人々にとっても、対人関係やビジネスの現場において第一印象がよくなり、思っていることを正確に伝えられるといったメリットがあります。そしてある種の健康法としても。創設者・浅利慶太氏が、そのメソッドを余すところなく初公開します!
-
5.0約50年の歴史を持つアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』。現在放送中の第6期では、ねこ娘がモデル体型の美少女となり、“ツンデレ”なキャラクターと合わせて多くの視聴者の支持を集めました。本電子書籍では、その第6期ねこ娘を中心に、設定画&名場面集、声優・スタッフインタビューなどで歴代のねこ娘の魅力を徹底解説。さらに描き下ろしのねこ娘イラストを5種収録しました。『ゲゲゲの鬼太郎』ファン、ねこ娘ファン必読の内容となっています。 ■おもな目次 【妖怪復活! 第6期『ゲゲゲの鬼太郎』】 ・豪華描き下ろしねこ娘イラスト5種 ・鬼太郎ファミリーとねこ娘の活躍を総まとめ! 第1~26話ハイライト集 ・INTERVIEW 庄司宇芽香(ねこ娘役)/永富大地(プロデューサー)/小川孝治(シリーズディレクター)/清水空翔(キャラクターデザイン・総作画監督) 【名場面&秘蔵資料で振り返る 猫娘の歴史】 ・第1期~第5期猫娘 設定画&名場面集 ・三田ゆう子(第3期ネコ娘役)に3つの質問/西村ちなみ(第4期ねこ娘役)に3つの質問 ・Interview今野宏美(第5期ネコ娘役) 【『ゲゲゲの鬼太郎』が50年愛される理由】 第3期編集・第4期プロデューサー 清水慎治
-
-大人気アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の名脇役・ねずみ男のキャラクターブックが電子書籍で登場! お金と権力が大好きな俗物なのに、どこか憎めない性格でファンも多いこのキャラクターを徹底解説。 アニメ第6期を中心に、歴代のアニメシリーズから原作までカバーした充実の一冊。 ■おもな目次 【2年目もノンストップ! 第6期『ゲゲゲの鬼太郎』】 ・ねずみ男劇場開幕! 描き下ろしイラスト2種 ・第1話~第75話 ダイジェスト&長編プレイバック ・クスッと笑えてときにドキッ ねずみ男名言集 ・Interview 古川登志夫(ねずみ男役) 「歴代のねずみ男は演技巧者ばかり。プレッシャーは半端ないですよ」 大野木寛(シリーズ構成) 「ねずみ男と名無しは裏返しの存在なんです」 ・Special Talk 庄司宇芽香(ねこ娘役)&藤井ゆきよ(犬山まな役)&古川登志夫 「ねずみ男の本当の良さは大人になったら分かります」 ・Column ゲゲゲのアフレコ見学記~妖怪いやみ編~ 【ねずみ男なくして語れない! 『ゲゲゲの鬼太郎』の50年】 ・アニメ第1期~第5期 ねずみ男の歴史 ・原作『墓場鬼太郎』『ゲゲゲの鬼太郎』 ねずみ男活躍エピソードBEST7 ・Special Column 水木しげるが語るねずみ男 ・Special Interview 池上遼一(漫画家) 「ねずみ男は水木しげる先生自身かもしれません」
-
3.9第二十回松本清張賞受賞。スキャンダルを逆手にとり人気画家にのしあがった財閥令嬢・八島多江子。謀略渦巻く戦時下の上海で、多江子が愛する運命の男たち。 昭和17年10月、八島財閥令嬢にして当代の人気画家・八島多江子は、戦時統制化の日本を離れ、上海にやってきた。そこで、招聘元である中日文化協会に潜入していた憲兵大尉・槙庸平から、民族資本家・夏方震に接近し、重慶に逃れた蒋介石政権と通じている証拠を探すように強要される。 「協力を断れば、8年前の事件の真相をマスコミに公表する」 8年前、多江子が夫・瑠偉とその愛人によって殺されかける有名な事件が起きた。愛人は取り調べ中に自殺し、瑠偉は証拠不十分で釈放されたものの、親元の伯爵家から除籍され、満州へ追われた。そして奇跡的に一命を取り留めた多江子は、スキャンダルを武器に人気画家へのし上がった。だが、その真相は、愛人と外地へ駆け落ちしようとした瑠偉を許せなかった多江子が、他殺に見せかけて自殺を図ったのだった。槙は何故か、その秘密を嗅ぎつけていた――。
-
3.0佐藤優×片山杜秀 コロナで変わる世界史 ■コロナ不況から暮らしを守る 玉木雄一郎 補正予算200兆円のまやかし 対策はもっと大きく、早く、簡素に! 神谷秀樹 トランプバブル崩壊 株、債券、土地はこうなる 荻原博子 アフターコロナの「生活防衛術」 小柳津篤 働き方は変わる もう元には戻らない ■激変する世界と中国の闇 黒田勝弘 韓国・文在寅政権を救った挙国一致の“コロナ自慢” アイ・フェン 中国政府に口封じされた 武漢・中国人女性医師の手記 中野剛志 グローバリゼーションが終わりを迎える 峯村健司 米中コロナ戦争 CIAと武漢病毒研究所の暗闘 山中伸弥×橋下徹 緊急事態を超えて ウイルスvs.日本人 磯田道史 「感染症の日本史」~答えは歴史の中にある 続・感染症の日本史 第二波は襲来する 養老孟司 人生は本来 不要不急 ■私とコロナの日々 阿川佐和子/福岡伸一/野村萬斎/ブラックマヨネーズ吉田敬/宮本亞門/落合陽一/古谷経衡/尾木直樹/林伸次/古市憲寿 ■暴かれた日本の不都合な真実 橘玲 「狡猾なウイルス」に試されている 赤坂太郎 ポスト安倍で官邸分裂 コロナ禍は人災だ 保阪正康 自粛警察とファシズム 能町みね子 無駄な原稿を書かせてほしい 中村淳彦 誰も助けてくれない「貧困女子」の地獄 後藤逸郎 東京オリンピックはもう無理だ 石橋正道 ベテラン開業医も困惑「コロナ感染記」 女子部JAPAN 「コロナ婚」へ急ぐ女子たちの本 三浦瑠麗 コロナ給付金10万円 使い途でわかった日本人の新しい絆
-
3.5「漫画家になって、全員を見返すんだ!」 地方の底辺高校に通うさえない男子2人がコンビを組み、プロ漫画家を目指す物語。 ボンクラの長谷川が原作を考え、不登校の竹夫が作画を担当。級友をモデルにしたゾンビ漫画を投稿したところ、新人賞に入選してしまう──。青春の〈夢と現実〉、創作の〈喜びと苦悩〉が交錯する、これぞ令和の『まんが道』。「漫画家漫画」の最新問題作、爆誕! 『ブラックジャックによろしく』佐藤秀峰氏、推薦! 「才能に執着せず凡人を生きる男。 才能を信じ凡人を受け入れられない男。 それぞれの終着駅。 身につまされろ。」 『これ描いて死ね』とよ田みのる氏、絶賛! 「凄かった。 いや、本当こうなるだろうなって展開の上をゆく展開で 読み終えた後どんな感情になっていいのか分からず数分驚いたり戸惑ったりした後に ようやく飲み込めて凄すぎて笑うしかなくすげー!と言いつつ爆笑してしまいました。 作中の『生まれて初めて何かに頑張ってるんだ』て台詞に落涙しました。 僕も漫画を描き始めた時そうだったから。 古泉先生大好きです。」
-
3.7いろんなダイエット法を試してきたけれど、何度も挫折してリバウンド! そんなふうに感じているすべての人への最終回答が、のべ7万人を治療し、断食指導をしてきた鍼灸界のカリスマ・関口賢先生が提唱する「月曜断食」。 週1日、月曜日に何も食べず、〈良食→美食→断食〉のサイクルを繰り返すという、誰でもコスト0ですぐに取り組める超簡単な体質改善プログラムです。 食べ過ぎでバカになった胃腸が本来の機能を取り戻し、睡眠の質が向上すると、面白いように痩せていきます。多くの実践者が1ヶ月間で5~7kg痩せて、脂質異常症や生理不順、むくみ、肌荒れがあっという間に解消。取り組み期間中のお酒もOKで、しかもリバウンドしにくいのが特徴です。 月曜断食5つの効用 ■食べないだけのシンプルな方法なので、かかるお金は0円! 過食も間食も自然に減ってお財布にやさしい ■過食でダメージを受けていた胃腸の機能が回復するので代謝がよくなり、睡眠の質が劇的に高まる ■内蔵から綺麗になるので、美肌効果が高い ■単に体重が減るだけでなく、脂肪の燃焼しやすい体へと体質改善できるのでリハウンドしにくい ■PMS(月経前症候群)や生理不順のみならず、不妊、子宮筋腫の改善の声も
-
4.2シリーズ累計20万部の『月曜断食』の進化版が初のビジュアルブックになって登場。 多彩なイラストでわかりやすく解説するとともに、とくに成否の分かれ目となる回復食の摂り方や、 前著の反響として寄せられたさまざまな疑問点に丁寧に答えた決定本です。 本書では、100万人超のフォロワーをもつ大人気料理研究家リュウジ氏とのスペシャルコラボレーションが実現! 回復食、良食、筋肉を落とさない美食の3カテゴリーで、「手早くつくれて最高にうまい!」37レシピを提案します。 「僕史上最高にヘルシーなレシビ」とリュウジ氏が太鼓判を押す料理で、月断の効果も倍増すること間違いなし! 他にもカツヤマケイコ氏の抱腹絶倒コミックエッセイや、 TVでお馴染みのダイエット外来ドクター・工藤孝文氏との対談なども収録。 「綺麗に、健康にやせたい」すべての人に贈る体質改善プログラムの決定版!
-
3.5◆考古学ではわからなかった「世界史」の最先端◆ ヒトゲノム計画以降、急速な進化を遂げたDNA解読技術によって、 私たちは数万年前の人類のゲノムも抽出・分析できるようになった。 それにより、遺骨や遺跡の存在が不可欠だった従来の歴史学は一変。 ゲノムの痕跡を辿ることで、骨さえ見つかっていない太古の人類から 現在の私たちへと繋がる、祖先の知られざる物語が解き明かされた―― ・ホモ・サピエンスはネアンデルタール人と何度も交配していた ・DNAにのみ痕跡を残す、知られざる「幻の人類」が発見された ・狩猟から農耕への移行を加速させたのは、二つの突然変異の出現だった ・現存する全人類の共通祖先は、わずか三五〇〇年前、アジアにいた ・ヨーロッパを二度襲ったペスト菌はどちらも中国からやってきた 【目次】 ■序 章 人類の歴史はDNAに刻まれている ■第一章 ネアンデルタール人との交配 ■第二章 農業革命と突然変異 ■第三章 近親相姦の中世史 ■第四章 人種が消滅する日 ■第五章 遺伝学は病気を根絶できるか? ■第六章 犯罪遺伝子プロジェクト ■第七章 ホモ・サピエンスの未来 ■解 説 ゲノムで辿る日本人のルーツ 篠田謙一(国立科学博物館人類研究部長)
-
4.0いまだ世界的な感染収束が見通せない新型コロナウイルス感染症。変異を繰り返して感染力を増すウイルスと戦うためには何が必要なのか。生物やウイルスの設計図である「ゲノム」の視点から、ウイルスとワクチンに関する最先端の知見をわかりやすく解説する。 目次 はじめに 第一章 すべてはゲノムが教えてくれる 第二章 新型コロナウィルスのすべて 第三章 検証・科学なき国の感染対策 何が間違ってどこがおかしかったのか 第四章 ウイルス 宿主に寄生し増殖する「無生物」 第五章 ウイルスvs人体 戦う細胞・免疫 第六章 ワクチン 感染症から人類を守る救世主 第七章 「万能型」新型コロナウイルスワクチンの可能性 おわりに
-
-話題の「声優×二次元芸人」プロジェクト! 発売即完売の1stLIVEを完全ノベル化。舞台では演じられなかった幻のエンディングも収録。 お笑いにかける青春 俺の相方が世界で一番面白い! 『俺ガイル』の渡航が描く、お笑いにかけた3組のコンビの涙と笑いと葛藤の青春物語! 東京は神田神保町のお笑い養成所SSS(スーパースタースクール)で、青春をお笑いにかける3組のコンビ。 日々学びオーディションを受け、バイトとネタ作りに追われている。コンビ間の衝突やライバルへの嫉妬など、きらびやかな世界の裏側に翻弄されながら、日本一、世界一のお笑い芸人を目指す青春ストーリーだ。 登場するのは―― 共感系幼馴染コンビ「スターダスト」上原淳也(cv:花江夏樹)・東沢楓(cv:西山宏太朗) ちぐはぐ凸凹コンビ「菊一文字」町田瀬那(cv:豊永利行)・大野虎之助(cv;石川界人) イマドキ関東芸人「6‐シックス‐」狛江一馬(cv:熊谷健太郎)・喜多見蓮(cv:阿座上洋平) LIVEは実際に3組がネタを演じ、会場の観客の投票でその後の展開が決まるマルチエンディング方式だった。本書もその形を踏襲しており、LIVEでは演じられなかったエンディングも収録されている。 イラストレーションは、由良が担当。書き下ろし表紙イラストと、挿絵3点を寄せている。 ※購入特典のキャストの手書きコメント付特製ポストカードは電子版には付いておりません。紙版のみの収録となりますので、ご注意ください。
-
4.0
-
3.32019年5月1日、今上陛下の「生前退位」が決定し、年内にも新元号(歴史的には「年号」が正しい)が発表される見通しです。 しかし、そもそも元号とは、どのように決まるものなのでしょうか? 元号・皇室研究の第一人者である所功先生が、新書の読者に、その歴史から現在、そして今回の決定の予想されるプロセスまで、わかりやすく解説した決定版が本書です。 元号の歴史は、驚きに満ち溢れています。とくに、ひとつの元号が何度も候補になっては消え、候補になっては消えて、最終的にやっと採用されるなど、ひとつひとつの元号のドラマがあることもわかります。 たとえば、「平成」は幕末にも候補に挙がっていました。また、「明治」は十回目、「大正」は五回目でやっと採用されています。 さらに、天皇と元号の関係、藤原道長、足利義満、織田信長、徳川家康ら、時の権力者と元号のかかわりなどは、歴史のダイナミズムをよく表しています。 さらに、かつては震災、大火、戦乱なども理由として改元が行われたため、元号そのものが「歴史の節目」となっているのです。 昭和から平成への「元号決定」のドラマや、「安延」から「和暦」まで、歴代の「未採用年号」一覧も付けた、まさに決定版ならではの内容をお楽しみください。 【目次】 第一章 漢字文化圏の暦と年号 第二章 律令国家の成立と年号 第三章 平安期史の展開と年号 第四章 中世年号に見る正統争い 第五章 近世年号の見る公武合体 第六章 近代に確立した「一世一元」 第七章 戦後史上の「元号問題」 第八章 「平成」改元と新元号 付録1 日本年号の出典と考案者一覧 付録2 日本年号・干支・西暦の対比表
-
3.3島田荘司作品中、初めて映画化された青春ミステリーの傑作! 病院で目覚めた医大生・糸永遥は自分の名前さえ思い出せず、思い出せたのは恋人の雅人の名前だけ。交通事故を起こして大怪我をし、ERに運び込まれた遥は、一過性全健忘によりほとんどの記憶を失ったのだった。 治療の結果、徐々に記憶は回復していくが、事故当時の状況だけがどうしても思い出せない。車に同乗していたはずの雅人の安否もわからず、不安と焦燥で遥はうつ病を発症し自殺未遂を起こす。うつ病の治療のためTMS(経頭蓋磁気刺激法)を受けるが、治療直後から雅人の幻を見るようになる。幻の恋人とデートを重ねる遥は、やがてTMSなしではいられなくなっていく……。 男女のナイーヴな恋愛感情が織りなすミステリー。小説版は映画版とは男女の役どころが入れ替わっている。
-
4.420年以上『週刊文春』の巻頭カラーを飾る「原色美女図鑑」。2006年の登場以来、幾度となく登場してきた綾瀬はるかの姿を、1冊にまとめた写真集。雪山でのロケ、水中を泳ぐ美しい姿はここでしか見ることができない貴重なカット。さらに、未公開の秘蔵カットも満載。最新の撮りおろしを含め、綾瀬はるかの21歳から27歳の成長を感じる完全永久保存版です。
-
5.0今、テレビ業界で確実に視聴率を持ち、消費活動に直結するのは、美人女性キャスターたちである。小林麻央、小林麻耶、皆藤愛子、山岸舞彩、高樹千佳子、長野美郷、八田亜矢子etc.ニュース、お天気、バラエティ番組で活躍し、写真集やカレンダーを発売すれば確実な売り上げが。週刊文春グラビア頁で、15年にわたり撮ってきた、美人女性キャスターグラビアを集大成。新たな撮り下ろしとインタビューを加えた、話題騒然スペシャルムック!
-
3.0現役女子大生、グラビアで注目etc. 次世代注目キャスター16名出演の豪華写真集を、2017.3.3ひな祭りに発売! 美人キャスターたちの貴重なグラビアが満載の「原色美人キャスター大図鑑」。 シリーズ第3弾は、フレッシュな若手に焦点をあてました。 「めざましテレビ」お天気キャスター・阿部華也子、「NEWS ZERO」お天気キャスター・良原安美、井上清華、「週刊プレイボーイ」水着グラビアが話題の伊東紗冶子など、 次世代を担う注目キャスター16名をピックアップ。写真はすべて撮り下ろし。彼女たちの爽やかな笑顔に癒やされること間違いなし。 巻末には、永遠のアイドルアナ・皆藤愛子の貴重な未公開カットも収録しています。
-
4.5世界最古の大恋愛小説のストーリーを追いながら、個性あふれる王朝の女性たちのキャラクターを分析した、源氏物語の入門書。 1997年4月から6月の3カ月間、NHK教育テレビ「人間大学」で「源氏物語の女性たち」という番組を書籍化した作品です。この番組は寂聴さんが毎回、源氏物語ゆかりの地に出かけていき、語るという内容。作者の紫式部をはじめ、光源氏が最も愛した紫の上、男を虜にした魔性の女・夕顔、誇り高くインテリ女性・六条御息所、情熱的で官能的な朧月夜など、光源氏を取り巻く女たちをわかりやすく解説しています。 「紫式部は仏教に帰依してもなお物語を書きつづけたことで、救われていたのではないでしょうか。『源氏物語』の底には、女人成仏の悲願がかく流れているように私には思われてなりません」 といった具合に、寂聴さん独自の見解が満載です。
-
4.2中国に、美女は多いが「悪女」も多い……。中国で悪女と呼ばれるには4つの条件があります。1、美女であること。2、才媛であること。3、世間を驚愕させる事件を起こすこと。4、政治権力とかかわりがあること。つまり美人で、頭も良くなければ悪女になれません。 彼女らは、なぜ悪女になったのでしょうか? 悪女にならずには生きていけなかったからです。薄煕来の妻・谷開来、“公共情婦”李薇、ネット上の露悪女、そして江青、葉群。中国を陰で動かした悪女たちそれぞれの人生には、恐ろしいけれど、どこか物悲しさ、痛ましさを覚えます。彼女らの素顔を通じて、現代中国の本質に迫ります。
-
3.0バカとは知識がないことではありません。価値判断ができないことです。 豊富な知識と立派な肩書きをもつバカは大勢います。 いつの時代でも一番強いのはバカなのです。「非学者論に負けず」という 言葉があるように、バカは論破できないから。批判する側は疲弊し、バカをみるのです。 バカにバカと言ったところで、奴らが反省するわけでもないし、無駄な反発をかうだけだし、徒労である。 しかし世の中には言ってもムダかもしれないけど、言わなければならないことがあります。 バカが圧倒的な権力を握るようになってしまった今の時代、国を滅ぼすバカには、 やはりバカと言うしかありません。 週刊文春の好評連載「今週のバカ」を再構成。 主な登場人物は、石原慎太郎、橋下徹、安倍晋三、みのもんた、朴槿恵、秋元康、朝日新聞、ネトウヨ、松本人志・・・。
-
4.4【ヒロイン達のお色気増し増しの描き下ろし漫画12p付き電子限定版!!】 「また俺、ヤっちゃいました…」系勇者様は今日も旅立てない!! 異世界に転生した主人公は勇者となり、魔王討伐の任を受ける。 転生者として受け入れてくれたこの世界に報いるため、旅立とうとするのだが…。 ある時は女賢者、また別の日は幼なじみ魔法使い、そして今日は女遊び人…などなど 魅力的なヒロインたちに誘惑されまくりで最初の村から一向に旅立てない主人公!! 「また俺、ヤっちゃいました…」系勇者誕生! ※電子限定特典:描き下ろし漫画12ページ収録 ※本編の内容は通常版と同じです
-
4.7広島平和記念公園の片隅に、土饅頭と呼ばれる原爆供養塔がある。かつて、いつも黒い服を着て清掃する「ヒロシマの大母さん」と呼ばれる佐伯敏子の姿があった。なぜ、佐伯は供養塔の守り人となったのか。また、供養塔にまつられている被爆者の遺骨は名前や住所が判明していながら、なぜ無縁仏なのか。「知ってしまった人間として、知らんふりはできんのよ」佐伯敏子の言葉を胸に取材を丹念に重ねるうちに、埋もれていた重大な新事実が判明していく──。引き取り手なき遺骨の謎を追う、もう一つのヒロシマの物語。 第47回(2016年)大宅壮一ノンフィクション賞、第15回早稲田ジャーナリズム大賞受賞作がついに文庫化! 解説・平松洋子
-
4.5「漣さんは〈役者〉として輝いたまま旅立った。俺がこうありたいと思う生き方がここにある」――ビートたけし 若き日に全てをかけた劇団・転形劇場の解散から、ピンク映画で初めて知った映像の世界、北野武監督との出会い、名監督たちと独自の世界を作り上げていった過程まで――。24時間営業俳優が語る俳優観と撮影秘話は深い余韻を残す。 大杉漣が残した未発表ノートをもとに、もう一つの顔を浮き彫りにする大杉弘美氏の特別寄稿付き。 現場で生ききった唯一無二の俳優の軌跡がここに。
-
4.1福島第一原発事故で、日本は「あの戦争」と同じ失敗を繰り返した――。『カウントダウン・メルトダウン』(大宅賞受賞)で福島第一原発事故を克明に描いた船橋氏が、福島の失敗の原因を徹底検証。 船橋氏の方針は、「文化論」を極力避けること。「文化決定論」は無責任と敗北主義をもたらし、「日本人だからダメなのだ」という居直りとあきらめをもたらすだけだからです。そこで氏は組織論、リーダーシップ論、ガバナンス論の視点から、どのような状況におかれた意思決定者が、どのような人間関係や指揮系統のなかで、どのように決断や命令を下したのかを具体的に検証。その結果あぶり出されたのは、戦力の逐次投入、「最悪のシナリオ」を考えることの放棄、インテリジェンスの軽視、タコツボ的な指揮系統、大局を見ない組織間抗争……。まさに、太平洋戦争論において散々指摘されてきたものと酷似した、数々の問題点でした。今度こそ同じ失敗を繰り返さないために、船橋氏はいかなる処方箋を見出すのか? 半藤一利氏らとの特別対談を収録。
-
4.0
-
4.2石油の価格は、いったい誰が決めるのか? 「今でも石油の価格は、OPECとセブンシスターズ(欧米の巨大石油資本企業)が裏で話し合って決めているのでしょう?」 私たちの生活に大きな影響を与える石油価格。しかし今でもこうした誤解がはびこっている。 商社に入社以来、40年以上にわたってエネルギー関連事業にたずさわり、現在はエネルギーアナリストとして活躍する著者が、石油価格のメカニズムをビジネスマン向けに徹底解説。また、エネルギーに関する海外のオピニオンを紹介しつつ、いまエネルギー事業が直面している構造変化と、それがもたらすであろう国際情勢の変化を論じる。 <おもな目次> ●第一章 原油大暴落の真相 波瀾万丈の2016年が明けた/資源を「爆買い」した中国/シェールオイルの「強靭性」 など ●第二章 今回が初めてではない 資金ショートか、大油田発見か/強欲独占、ロックフェラー/非OPEC原油が勢いづく など ●第三章 石油価格は誰が決めているか OPECとセブンシスターズが裏取引?/市場を動かす「先物取引」/中国勢の価格操作疑惑 など ●第四章 石油の時代は終わるのか 石油が枯渇する心配はない/シェール革命の何が「革命」だったのか/石油は「西から東へ」の時代に など ●第五章 原油価格はどうなる? 長期、短期の需要予測/隠された余剰生産能力/エクソンはなぜ読み違えたのか など
-
4.3
-
3.8NHKドラマ化もされた大人気「まんまこと」ワールド第2弾! 町名主の跡取り・麻之助は、ついに祝言をあげることに。けれど花嫁を迎えに出ようとしたその時、悪友・清十郎の父が卒中で倒れてしまう。堅物の父・源兵衛から「かつて訳ありだった二人のおなごの境遇を確かめて欲しい」と頼まれた清十郎は仰天し――。 町名主名代ぶりも板につきながら、淡い想いの行方は皆目見当つかぬ麻之助。両国の危ないおニイさんたちも活躍する、江戸情緒溢れる6つの短編集。 解説・細谷正充 ※この電子書籍は2009年3月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
5.0「実は一途なゴキブリ系女子」「本命以外はとことん利用するホタル系女子」、「振られて逆切れアメンボ系男子」、「束縛俺様ギフチョウ系男子」……。 昆虫をこよなく愛する“現役慶應ガール”の著者が、イマドキの若者の恋愛模様を、昆虫の驚くべき恋愛戦略や交尾方法に例えて分類。ちょっと困った“ムシ系男女”の生息地・対処方法を細かく分析し、風刺をきかせて紹介します。この一冊で、恋も虫も丸わかり! テレビにも出演している「クイズ・クイーン」でもある著者が出題する「ムシクイズ」、昆虫をおいしく料理する「ムシレシピ」、あなたが何ムシ系かわかるチャートなど、おまけページも充実。第10回「出版甲子園」グランプリ受賞企画の書籍化。 各話に挿入されるヒトコマ漫画と昆虫のイラスト&カバーは、漫画家の谷口菜津子が担当。
-
4.0
-
4.1「小泉家って親子の会話もワンフレーズなんですか?」(福田) 「そりゃね、ワンフレーズじゃ済まないよね」(小泉) 自民党若手政治家の中でもっとも期待される2人、小泉進次郎氏と福田達夫氏の対談本が実現しました。総理だった父のこと、世襲政治家の家のこと、そして自分の夢のすべてを、初めて語り合った衝撃的な1冊です。 2人は2017年の農政(全農)改革で、自民党の農林部会長と部会長代理という立場で、初めてタッグを組み、大仕事を成し遂げました。その過程で、お互いを知り、認め合い、まるで昔からの親友のような関係になったのです。 「うちの親父(小泉純一郎元首相)は、政治家になると友だちなんかできないと言ってた。それが政治の世界だと」(小泉) 「確かに友だちはいなかったかもしれなかったけど、お父様には仲間がいた。うちの親父(福田康夫元首相)とか森喜朗首相は兄弟だった」(福田) 2人は驚くほど素直に意見をぶつけ合います。農政改革の現場では、敵陣に真っ先に攻め込んで暴れまわる騎兵隊長が小泉氏なら、そのあとを粛々と占領していく歩兵隊長が福田氏。個性は違うけれどもぴったりと息のあったコンビは、小泉純一郎総理―福田康夫官房長官時代を彷彿とさせます。 司会はテレビの政治解説でもおなじみの、時事通信特別解説委員の田崎史郎さん。2人の本音をどんどん引き出していきます。 日本の未来を担う2人の本当の姿が見えてきます。
-
4.3小泉純一郎はいま、どんなことを考えているのか? 政界引退後もなお、その記憶が語り継がれ、人気の衰えも知らぬ元総理。 総理官邸を後にして10年、初めてロングインタビューに応じ、 ノンフィクションライターと向かい合った4時間半。 安倍政権、野党再編、原発ゼロ、闘争の作法、盟友との決別、息子・孝太郎と進次郎、我が「余生」……。 「小泉純一郎にオフレコなし」 一年生議員の頃から永田町界隈の記者たちの間でそう謳われただけあって、ロマンスグレーの男はざっくばらんに語った。 小泉純一郎は過去をどう総括し、どんなニッポンの未来を構想しているのだろうか──。 ●「原発は安全、安い、クリーン。これ全部ウソだ」 ●「選挙に弱い政治家は圧力に弱いんだよ」 ●「酒と女は二ゴウまでって(笑)」 ●「小沢一郎は橋本龍太郎より面白かったな」 ●「俺なら原発ゼロを総選挙の争点にする」 ●「安倍さんは全部強引、先急いでいるね」 ●「議員やめてから靖国に一度も行ってないよ」 ●「自民党は総理に何言おうが自由だった」 ●「進次郎の結婚は四十過ぎでいいよ」 ●「政界っていうのは敵味方がすぐ変わるんだよ」 ●「『女性遍歴を書いてください』って言われる(笑)」
-
-安倍長期政権が続く中、自民党にあってその存在感をますますましている小泉進次郎。そんな小泉が党内で信頼を寄せているのが、福田康夫元首相の長男で、2012年当選の福田達夫だという。農業問題にかかわり持ったことで、意気投合したという二人はお互いをどう見ているのか。政治記者・田崎史郎氏はそんな二人の対談を企画、『小泉進次郎と福田達夫』(文春新書)としてまとめた。本書では、新書には書ききれなかったエピソードやなぜ二人が親しくなったのかその裏側を明かした。(※文藝春秋2017年12月号掲載記事を再編集)
-
4.2友達だけど、違う生き物 夏休み、俺は片想い中のサブレと夜行バスの旅に出た。彼女が口にした、ちょっと風変わりな目的のために――見知らぬ町で一緒に過ごすうち、そして会話を重ねる度に、サブレをもっと深く知った俺の中に名前のない感情たちが溢れ出てきて……。特別な夏の4日間が教えてくれた、恋だけじゃない、世界の「あと全部」を巡る物語。 『君の膵臓をたべたい』から10年―― 住野よる史上、最も不器用で愛おしい恋の物語 言葉にする前の、 この瞬間だけが 永遠ならいいのに。 【登場人物】 めえめえ(瀬戸洋平) サブレに片想いし、彼女と旅に出る高校生 サブレ(鳩代司) 命のエネルギーに惹かれる、ちょっと気にしすぎな同級生 夏休み、夜行バスに揺られ、僕らは世界の輪郭と、言葉にできない想いの行方をなぞっていく。 単行本 2023年2月 文藝春秋刊 文庫版 2025年9月 文春文庫刊 この電子書籍は文春文庫版を底本としています。
-
4.2島田荘司推理小説賞史上最高傑作と大評判! 聡明な盲目の少年がインターポール捜査員とともに、凄惨な〈幼児目潰し事件〉の真相に迫る! 中国の孤児院で育ち、裕福なドイツ人夫婦の養子となった盲目の少年、阿大(ドイツ名ベンヤミン)。 彼は、黄土高原で発生した六歳児が木の枝で両目をくり抜かれる“男児眼球摘出事件”に強い関心を持つ。凄惨な事件のなぜ起こったのか? 犯人は? お目付け役のインターポール捜査員・温幼蝶と母国へ旅立ったベンヤミンがたどり着いた真相とは――。 「この作ほどこちらに多くを考えさせ、また創作執筆時にも劣らない、さまざまなストーリーをこちらの脳裏に想起させた候補作は過去になかった」(島田荘司)と激賞された新たな探偵ミステリーがここに誕生! <島田荘司推理小説賞> 2009年に創立された中国語で書かれた未発表の本格ミステリー長篇を募る文学賞。応募作は台湾、香港、中国、マレーシア、イタリアなど世界各国から寄せられる。
-
4.02019年5月1日、日本の歴史が変わります。 「高齢譲位」(政府は「生前退位」と称しますが、内容は「高齢」を理由とした「譲位」にほかなりません)によって、皇位継承が行われた先例はありません。 2月末に、退位と即位に伴う儀式の概要が発表されましたが、それは正統的なものになっているのでしょうか? さらに、今上陛下のご譲位によって、いよいよ皇位継承者は皇太子殿下、秋篠宮殿下(皇太子殿下の即位後は「皇嗣」殿下となられる)、そして悠仁親王殿下のお三方になってしまわれます。皇位継承権利のある成年皇族しか参列できないとされてきた即位の礼は、まことにさびしいことになってしまうのではないでしょうか? 皇位継承の歴史と未来、そして、今直面する危機についての決定版が本書です。 本書は1998年、文春新書創刊の第一号として世に出たものです。以来、ベストセラーとして版を重ねてきました。 そこに、最新の情勢を踏まえて大幅に加筆。増補改訂版として生まれ変わりました。 代替わりのすべてが、本書でわかります。
-
-幕末のテロリストが、愛される経営者に! 横浜焼き打ちを決行しようとした青年は、パリ万博で幕府の瓦解を知る。「一万円札の顔」になった日本最強の経営者、その数奇な運命。 色好みだけど、ケチではなかった。「史上最強の経営者」「日本資本主義の父」など、多くの異名を持つ渋沢栄一の生涯。幕末にテロを決行しようとした青年が、パリ万博で幕府の瓦解を知り、激動の明治には日本一愛される経営になるまで。「一万円札の顔」の数奇な運命を歴史小説の第一人者が描いたエネルギーあふれる人生録決定版! 単行本 2021年1月 文藝春秋刊 『むさぼらなかった男 渋沢栄一「士魂洋才」の人生秘録』 文庫版 2024年12月 文春文庫刊 文庫化にあたり増補・改題 この電子書籍は文春文庫版を底本としています。
-
4.3四半期決算を廃止せよ! 長期保有株主を優遇せよ! 日本が新しい経済ルールをつくる! 日本が率先して「21世紀の新しい資本主義=公益資本主義」を世界に示すべきだ――確信をもってこう断言するのは、「理論や理想ばかりを説く経済学者」でも、「資本主義に反対する社会主義者」でも、「海外を知らない国粋主義者」でもありません。最も競争の激しいビジネスの本場、米国シリコンバレーで、数々の成功を収めてきた「最強のベンチャー事業投資家」です。 著者の原丈人さんは、考古学研究の資金稼ぎのため米国のビジネススクールに通い、さらに先端工学も学んで起業。大成を収めました。その資金をもとに新技術を創出する数々の企業の起業・経営に参画し、シリコンバレーを代表するベンチャーキャピタリストとして活躍しました。 そんな経験から、米国流ビジネスの限界と問題点を身をもって知っているのです。 株主優先、四半期決算、時価会計、社外取締役制度など、「会社は株主のもの」とみなす「米国流の株主資本主義」の導入が「改革」と称されていますが、むしろ弊害を生んでいます。「会社は株主のもの」という考えでは、投資や経営が、短期利益重視となり、新技術開発にまわすべき中長期資金や、真にリスクをとる投資が不足してしまいます。 税制や金融のルールを改めることで、マネーゲームに回っている資金を中長期投資へと導くことこそ、「公益資本主義」が目指す「成長戦略」です。中長期経営を重視する日本型経営こそ、「公益資本主義」の雛形。米国を反面教師にし、今こそ日本が新しい資本主義のルールを示すべきなのです。
-
3.3「人間の直感はなぜ間違うか?」。その命題を突き詰めてあらゆる学問の常識を覆したのは、2人の天才心理学者だった。 生い立ちも性格も全く違うカーネマンとトヴェルスキーの共同研究は、やがて経済学の分野にも革命を齎(もたら)すのだが……。 『マネー・ボール』で著者が見落としていた先に隠されていた、感動のヒューマン・ドラマ。解説・阿部重夫 「ぼくらは友だちだ。きみがどう思っていようと」 不合理な人間モデルを前提とした行動経済学を生み、世界を永遠に変えた、2人の天才科学者の友情と別れ 世界的ベストセラー『ファスト&スロー』著者にして、 ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマン。 華やかに見える彼の人生には、決して欠かすことのできない共同研究者がいた。 彼の名はエイモス・トヴェルスキー。 カーネマンはこの悲運の天才を愛し、そして激しく嫉妬した――。 ※この電子書籍は2017年10月に文藝春秋より刊行された単行本『かくて行動経済学は生まれり』を改題した文庫版を底本としています。
-
4.0「高偏差値エリート」はなぜ転落したのか? 高学歴、高偏差値なのに…… 使えない・空気を読めない・ミスを連発 するのはなぜなのか? 難関校に合格するも休みがちに、大学で周囲から孤立、職場ではまったく評価されない。 将来を約束されたエリートたちは、なぜ“転落”してしまったのか――。 精神科教授として発達障害の患者に長年向き合ってきた岩波明氏によると、ここ10年あまり、これまでとは違うタイプの患者が目立って増えてきたという。 高学歴で知的レベルが高く、有名校や一流企業に所属している。 ところが些細なことがきっかけとなって、それまでの「人生経路」からドロップアウトしてしまう。 彼らに共通しているのは、発達障害を抱えているということ。 20世紀末から社会の「管理化」「デジタル化」が強力に進行し、規格からはずれた個人が簡単にあぶり出されるようになったのだ。 数々の症例に接してきた精神科医である著者が、高学歴発達障害の人々の現状を浮き彫りにし、いかにして回復して社会復帰するか、“再生”に至るまでの道のりを提示する。
-
3.0独自の見地からがん治療に対する見解を発信し続け、2012年に菊池寛賞を受賞した近藤誠医師の抗がん剤論決定版! 肺がんや胃がんなど、固形がんの標準治療とされる抗がん剤。だが、実は延命効果は認められない。認可取得を狙い、関係者が臨床試験データを改変する手口の数々を徹底論証する。抗がん剤が殺細胞薬として開発された以上、命を縮める毒性は免れない。それより、本当に必要ながん治療を自分で選ぶ力を身に付けよう! 本書は2011年に刊行された『抗がん剤は効かない』に最新の知見を加え、タイトルを改めたものです。
-
4.3健康長寿のカギは「食べる力」にあり! 医療は日々進歩し、日本人の平均寿命はどんどん延びている。ところが医療の現場で犠牲になっているものがある。 それは「食べること」だ。 多くの専門医は自分の分野を優先するので、「食べること」は時として治療の邪魔になる。そのため専門分野の治療を優先する医師が、患者に「食べさせない」選択をしてしまうのだ。食べることが少しでも危険だと判断されると、食事はほとんどが流動食、点滴。ひどい場合は、経鼻経管栄養や胃ろうにされてしまう。なぜ、こんなことが起こるのだろうか? 実はいまの医師は教育課程において「食べること」を勉強する機会がない。 そもそも食支援に重要な役割を果たす「口腔機能」の専門家がいない。「口腔」とは口の中から喉までの器官。人間の体の中で、口と歯だけは医科でなく、歯科が担当する。口腔内のがんやできものは歯科の口腔外科が担う。ところが口腔の外科医はいても、機能の低下や障がいを治療・改善する内科の専門家が全くの不在なのだ。 医療から見放されている「口腔機能」だが、人間が生活していく上で、このうえなく重要な器官なのだ。「食べる」「喋る」「笑う」という、人間の健康にとって最も重要な行為を支えているからである。 本書では「食べる力」の重要性を、実例を交えて紹介するとともに、健康に老後を過ごすために必要な対処法や、自宅で簡単にできる「口の力」リハビリ法もイラスト入りで紹介します!
-
4.1『精霊の守り人』『獣の奏者』『鹿の王』…世界中で愛される著者の最新作! 人並外れた嗅覚を持ち、植物や昆虫の声を香りで聞く少女アイシャ。旧藩王の末裔ゆえ、命を狙われ、ウマール帝国へ行くことになる。遙か昔、神郷よりもたらされたというオアレ稲によって繁栄を極めるこの国には、香りで万象を知る〈香君〉という活神がいた。アイシャは、匿われた先で香君と出会い……。壮大な物語が今開幕! ※この電子書籍は2022年3月に文藝春秋より単行本上下巻で刊行された作品の、文庫版を底本としています。文庫版は4巻構成となります。 単行本『香君 上 西から来た少女』 → 文庫版『香君1 西から来た少女』『香君2 西から来た少女(ともに2024年9月発売) 単行本『香君 下 遙かな道』 → 文庫版『香君3 遙かな道』(2024年11月発売予定)『香君4 遙かな道』(2024年12月発売予定)
-
-日本独自の伝統医学として誕生した“漢方医学”。西洋医学によって「どこか怪しげな医療」として片隅に追いやられていた時期もあったが、最近、その位置づけに大きな変化が起きているという。「漢方の科学化」が進んだことによって、その有用性が注目されるようになってきたのである。医療の現場でどのように漢方が使用されているのか、その最新事情を高血圧、糖尿病、アトピーなどに適する漢方薬リストと合わせて紹介!
-
3.8心の痛みに効く、とびっきりのカフェご飯! 東京の出版社をやめ、百合が原高原にカフェを開業した奈穂。 かつてペンションブームに沸いたが、今はやや寂びれ気味の高原にやってきたのは、離婚を承諾しないモラハラの夫に耐えかね、自分の生活を変えるためだった。 そんな背水の陣ではじめた奈穂のカフェには、さまざまな人が訪れる──。 離れた娘を思う父、農家の嫁に疲れた女性、昔の恋に思いを残した経済アドバイザー……。 「ひよこ牧場」のバターやソーセージ、「あおぞらベーカリー」の天然酵母のパンや地元の有機野菜など、滋味溢れる食材で作られた美味しいご飯は、そんな人々に、悩みや痛みに立ち向かう力を与えてくれる。 奈穂のご飯が奇跡を起こす6つの物語。 ジューシーなチキンのコンフィとモミジイチゴをのせたベビーリーフサラダ/ 高原野菜と鶏肉のチーズクリームシチュー/特製さくさくベーコンサンド/ “男前な口どけ”のイチゴ入り泡雪羹/5種類のお豆のカレー/ 蕪と水菜と胡桃のサラダ/百合根のポタージュ/薔薇のシロップに漬けたくずきり…etc. 女性を主人公に多くのベストセラーを輩出してきた著者が、自らレシピを試して「絶対においしいものだけ」がぎっしり詰まった連作集は、読者に栄養をたっぷり届けます。 解説は漫画家の野間美由紀さん。 ──人間の心の機微の中にはいつも謎が隠れている。そんな謎を優しい目線で描いたこの小説も、紛れもなく上質なミステリーなのである。(解説より) 料理研究家の高山かづえさんが作る高原カフェレシピも特別収録!
-
-前身の大会から含め、「夏の甲子園」が始まって100年目となる2015年に刊行。 江川卓、太田幸司、清原和博、桑田真澄、松坂大輔、田中将大、斎藤佑樹……ヒーローたちの鮮烈な記憶をたどる第一部。 池田高・蔦文也、横浜高・渡辺元智、星稜・山下智茂、常総学院・木内幸男ら、名将たちの横顔を描いた第二部。 歴代優勝決勝戦の一覧、47都道府県の出場校記録など、記録をまとめた第三部。 高校野球がつむいできた物語を、あらゆる角度から迫った完全保存版。
-
4.0甲子園には魔物が棲む──。 応援には魔曲がある! 高校野球が100倍面白くなる、世界初の甲子園「ブラバン応援」研究本! 吹奏楽名門校出身の著者が、高校球児と吹奏楽少女の恋を描く少女マンガ『青空エール』(河原和音作)監修をつとめるうち、すっかり応援マニアに。 「サウスポー」「狙いうち」なぜ応援は懐メロばかり? 日本一有名な応援曲は○○高校オリジナルだった! 打線爆発する魔曲「ジョックロック」とは? ……などなど、完全ブラバン目線で名門高校顧問やOBに直接取材を重ねた、トリビア満載&マニア垂涎の一冊。 夏の甲子園100回大会にあわせ、新ネタ大増量で文庫化しました!
-
3.7結婚は「始まり」に過ぎない。今も昔も―― 「好きでもない女と結婚するのは絶対に嫌だ」「自分たちは宮家に生まれて、あれこれ苦労した」「あの女王さまでは、子どもをお産みになることは出来ないでしょう」――。 さまざまな立場に葛藤する皇族を描いた5つの短編には、読む者を圧倒する”心の内”が綴られる。これまで描かれたことのない、衝撃の短編集。 * 妹の友人に恋焦がれ、ようやく結婚目前まで漕ぎつけた久邇宮朝融王は、彼女にまつわる“ある噂”を耳にし、強引に婚約を破談にした。その後、別の宮家の子女と結婚したものの……(「綸言汗の如し」) 徳川家の若き未亡人・実枝子は、喧嘩の絶えなかった夫・慶久が妾との間に遺した子に愛情を注げず苦悶していた。思い起こせば、あの頃は本当に幸せだったのに。(「徳川慶喜家の嫁」) まもなく結婚の沙汰が下るのではないかというある日、久邇宮家の息子たちは声を潜めて話していた。「内親王はご免こうむりたい」――(「兄弟の花嫁たち」) 九条家の子女・節子は15歳の時に嫁いだ。のちの大正天皇の后(貞明皇后)である。夫は妻を顧みないにもかかわらず子ばかりが生まれ、節子は悲しみに歯を食いしばる。(「皇后は闘うことにした」) 貞明皇后の秘蔵っ子・秩父宮に嫁いだ勢津子もまた、皇后によって選び抜かれた秘蔵の嫁だった。だが、2人の間に子はできず、秩父宮も病を得てしまう。(「母より」)
-
4.0痛みを知るから勁くなれる――令和の新皇后、雅子さま。その皇太子妃としての道のりは決して平坦ではなかった。ご成婚パレードでの笑顔はなぜ失われたのか? お世継ぎ問題、「適応障害」の真相は何だったのか? 長年にわたり雅子さまの実像を追う唯一のジャーナリストが描く、新皇后の素顔とは。半生を網羅した決定版! 【目次より】 序章 幸せの黄色いワンピース 第1章 帰国子女の憂鬱 第2章 「根無し草にはなりたくない」 第3章 新人外交官の悩み お妃候補への戸惑い 第4章 皇太子妃選定「極秘プロジェクト」 第5章 ご成婚──雅子さんのいちばん長い日 第6章 「新皇太子妃」に差す影 第7章 長官が尋ねた「お身体のこと」 第8章 愛子さまご誕生までの全舞台裏 第9章 涙が止まらない 第10章 「人格否定発言」初めて語られる真相 第11章 ようやく治療がはじまった 第12章 悠仁さまご誕生──急転する皇室の運命 第13章 愛子さまが学校に行けなくなった日 第14章 ご成婚二十年──雅子妃はお幸せだったのか 終章 令和の皇后として ※この電子書籍は、2015年1月に文藝春秋より刊行された単行本『ザ・プリンセス 雅子妃物語』を改題、新章を増補した文庫版を底本としています。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。