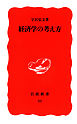岩波書店作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.5
-
3.4
-
4.3柳田国男・渋沢敬三の指導下に、生涯旅する人として、日本各地の民間伝承を克明に調査した著者(一九〇七―八一)が、文字を持つ人々の作る歴史から忘れ去られた日本人の暮しを掘り起し、「民話」を生み出し伝承する共同体の有様を愛情深く描きだす。「土佐源氏」「女の世間」等十三篇からなる宮本民俗学の代表作。 (解説 網野善彦)
-
3.7サーカスの団長になり、おなじみの動物たちをひきつれてキャラバンの旅をつづけていたドリトル先生は、ある日、ついに世紀の名歌手カナリアのピピネラに出会いました。やがて世界ではじめての鳥たちによる公演がロンドンで大成功をおさめ、先生と動物たちの名は一躍各国になりひびき、売上金をもとに数々の事業をはじめます。
-
3.5兼六園の雪釣り、泉鏡花、鈴木大拙、西田幾多郎など日本を代表する文豪や思想家、友禅や金箔、和菓子づくりなど代々受け継がれてきた職人技術、そして金沢21世紀美術館など新たな文化の発信地……。金沢で生まれ育ち、まちづくりに長年携わってきた著者が、金沢のまち、歴史、文化を歩きながら、その奥深い魅力を余すところなく伝える。
-
4.2
-
4.2すぐれた民藝品を求めて日本全国を歩いた民藝運動の創始者・柳宗悦(1889―1961)が、各地に残る美しい手仕事を紹介しながら、日本にとって手仕事がいかに大切なものであるかを訴え、日本がすばらしい手仕事の国であることへの認識を呼びかけたユニークな民藝案内書。秀逸な小間絵(芹沢けい介)を多数収録。(解説 熊倉功夫)
-
4.0
-
4.5
-
4.5
-
5.0
-
4.3
-
3.7「自分の育った地域なんてたいしたことないですよ」と言い捨ててしまう若者は多い.本当にそうなのだろうか? どの地域にも固有の歴史や文化があり,人々の営みがある.それらを知っていくことで,自分や社会,そして未来が見えてくると著者は説く.調査実習の手法や体験をふまえ,時間と空間を往来しながら,地域学の魅力を伝える.
-
3.9
-
4.5
-
-
-
4.5
-
4.5
-
4.1強者が押しつける「正しさ」と暴力や分断がはびこる現代社会.そこで置き去りにされているのは,尊厳を踏みにじられた人々が紡ぐ〈小さな物語〉――恐ろしい怪物の物語として知られる『フランケンシュタイン』を,10のテーマを通して多様な作品群と縫い合わせ,読む者をケアの本質へと誘う.想像力を解き放つ文学論.
-
4.2
-
4.0
-
-
-
4.0
-
5.0
-
5.0本書は「政治的中立性」という曖昧な概念によって人々の言論活動を制限することの危険性を説くものである.公務員や放送への要求であるこの言葉は,いつしか独り歩きし,自由であるはずの私たちの言論空間が委縮して久しい.「何となく,これを言ったらまずいのではないか」という空気は,この国のそこら中に漂っている.
-
4.2
-
4.2
-
-1938年の創刊から、岩波新書は、赤版(1938-1946年)、青版(1949-1977年)、黄版(1977-1987年)を経て、1988年から現在の新赤版となり、およそ3500点が刊行されている。 創刊80年を期に刊行された『岩波新書解説総目録1938-2019』を増補して、2023年12月までのラインナップを収めた電子書籍オリジナル版としておくる。創刊以降のすべての書目を、刊行順に配列して、内容解説文を付す。書名・著訳編者名を網羅しての索引検索機能に加えて、電子書籍の有無も表示される。時代の中で培われてきた「現代人の現代的教養」の全貌を提示する、知のアーカイブである。
-
4.0
-
3.6
-
4.4われわれは生きて戻れるのか? ――原発が爆発・暴走するなか,地震・津波被害者の救助や避難誘導,さらには原発構内での給水活動や火災対応にもあたった福島県双葉消防本部一二五名の消防士たち.他県消防の応援も得られず,不眠不休で続けられた地元消防の活動と葛藤を,一人ひとりへの丹念な取材にもとづき描き出す.講談社 本田靖春ノンフィクション賞ほか受賞の迫力作.
-
3.9フレーゲからラッセル,そしてウィトゲンシュタインへ――二十世紀初頭,言葉についての問いと答えが重なりあい,つながりあっていった.天才たちの挑戦は言語哲学の源流を形作っていく.その問いを引き受け,著者も根本に向かって一歩一歩考え続ける.読めばきっとあなたも一緒に考えたくなる.とびきり楽しい言葉の哲学.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
4.6
-
4.6
-
4.0
-
4.3「父には,弱いといえるところが一つもないんですの」完璧な父を敬愛する,内向的で平凡な容姿のキャサリン.彼女の前に現れた,美貌で言葉たくみな求婚者――19世紀半ばのニューヨークを舞台に,鋭く繊細な会話と描写が,人間心理の交錯と陰影を映し出す.『ある婦人の肖像』とならぶ,ジェイムズ(1843-1916)初期の佳作.
-
3.5中世の写字生,グーテンベルクをはじめとする印刷術の立役者,あるいは蒐集家,偽作者,伝統を守ろうとした改革者たち…….いつの時代にも,書物を愛し,あたかも書物に愛されて生きているような人々がいた.巻物から冊子へ,音読から朗読へ,書物と人が織りなす世界を楽しみながら,壮大な迷宮を旅する.カラー口絵四ページ.
-
3.5ウィーンはいかにして「音楽の都」になったのか.十八世紀後半のウィーンでは,宮廷や教会などによる支援,劇場の発展,音楽教育の普及と聴衆の拡大,演奏会や舞踏会の展開など,多彩な要素が相互に作用しながら,音楽文化が重層的かつ豊かに形成されていった.膨大な同時代の史資料を駆使して描かれる「音楽の都」の実像.
-
4.5
-
4.6
-
4.3このままだと日本は必ず没落する…….1999年に刊行された本書は,2050年を見据えて書かれているが,驚くほど現在の日本の現実を予見している.なぜそうなるのか,日本人の精神性と日本の金融,産業,教育の荒廃状況を舌鋒鋭く指摘し,その救済案「東北アジア共同体構想」を示し,救済案への障害となるものをも示す.(解説=中村達也)
-
-福島第一原発事故から一〇年が過ぎた.多額の復興予算は,当事者不在の公共事業や検証なく繰り返される除染などに費やされ,さらに原発事故の傷跡を覆い隠す「復興五輪」が強行された.地元住民を置き去りにする偽りの「復興」は福島に何をもたらしているのか.住民らの苦悩と闘いをカラー写真とルポで描く好評シリーズ第4弾.
-
3.4
-
3.9
-
4.0
-
3.7
-
4.0
-
3.0
-
4.3「アイドルとして自分たちの出来ることをやろう!」。AKB48グループの被災地訪問活動は2011年5月から現在まで、毎月1回、一度も欠かすことなく続けられている。即席のステージで行われるミニライブや握手会に参加したメンバーの数はのべ450人以上…。彼女達はそこで何を感じたのか? アイドルの知られざる活動の記録。[カラー写真多数]
-
4.0
-
3.7
-
4.0
-
3.8
-
4.2
-
3.6遠い昔、日本民族の祖先たちはいかなる経路をたどってこの列島に移り住んだか。彼らは稲作技術を携えて遥か南方から「海上の道」を北上し、沖縄の島づたいに渡来したのだ……。ヤシの実の漂着・宝貝の分布・ネズミの移住など一見小さな事実を手掛りに、最晩年の柳田が生涯の蓄積を傾けて構想した雄大な仮説。 (解説 大江健三郎)
-
4.6鎌倉幕府の滅亡に始まる南北朝の動乱.北条一族の終焉,楠正成らの知勇が支える後醍醐天皇の新政権,足利尊氏の離反と南朝北朝の分離,室町幕府の成立…….数十年にわたって列島を揺るがした巨大な戦乱を記す『太平記』全四十巻.後世に深甚な影響を与えた書の古態を伝える室町初期の「西源院本」に,初の校注を加える.(第一─八巻を収録)※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。


















































![[電子書籍オリジナル版] 岩波新書解説総目録 1938-2023](https://res.booklive.jp/1511236/001/thumbnail/S.jpg)