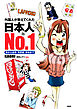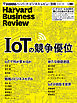社会学作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-150年繰り返された韓国の裏切り! 「マトモな国になってくれ!」日本人の願いと善意を踏みにじってきた韓国・朝鮮人。輸出を見直し、ホワイト国から除外した、いまこそ「新・征韓論」を! 最終的かつ不可逆的な解決を合意した慰安婦問題を、政権交代後の文在寅大統領は勝手に再燃させた。日本大使館前の慰安婦像は撤去せず、今も新たに日本に謝罪を求め続けている。両国の最高機関での公式な合意であったものを自分の都合で破棄することは、自らに責任遂行能力が全くないことを認めたことを意味する。そういう国を信頼する必要はない。まさに日本が河野談話を破棄する好機ではないか。(本文より)
-
-直言、辛言、暴言ですが! ・悪夢をもたらした民主党の残党が未だに跋扈 ・『サンデーモーニング』を私物化したテレビ屋 ・君は何サマのつもりか、歌手・タレント・芸人よ ・児童虐待する親は私人による「現行犯逮捕」を認めろ ・いい加減にしろ沖縄、甘ったれるな沖縄 ・暴力否定の流れで、鍛練まで否定する愚 ・スポーツ界のトンチンカンたちを叱責する 「日本トンチンカン悪者」列伝 貴乃花、小平奈緒、白鵬、福山哲郎、辻元清美、蓮舫、関口宏、寺島実郎、張本勲、田中優子、桑田佳祐、東山紀之、北大路欣也、春風亭昇太、林家三平、吉永小百合、加藤登紀子、鳩山由紀夫、奥田瑛二、爆笑問題、古舘伊知郎、久米宏、宮根誠司、なかにし礼、大竹まこと、村上春樹、坂本龍一、立木義浩、前澤友作、テリー伊藤、高田純次……ほか多数登場! ベストセラー『日本アホバカ勘違い列伝』に続く第二弾! 「トンチンカン」とは── (鍛冶屋の相槌は交互に打ち、音が揃わないところから。「頓珍漢」とも当てる) (1)物事がゆきちがい前後すること。つじつまの合わないこと。 「──なことを言う」 (2)とんまなこと。また、そういう人。 ──『広辞苑(第七版)』より。
-
5.0ビジネスで成功するためにどうすべきか。中国・韓国の理不尽な対日攻撃にどう反撃するか 朝日新聞論説委員に読ませたい一冊です! (編集部より)→本書は、渡部昇一氏と谷沢永一氏が、『孫子』の説くさまざまな訓話を、現代の日本の状況と照合しつつ論じ合った本です。その教えは21世紀を生きるビジネスパーソンにも参考になる内容です。また、『孫子』と関連して「宋襄(そうじょう)の仁(じん)」を取り上げます。これは、昨今の日韓関係などにもピタリと当てはまる教訓です。「宋襄の仁」とは、宋と楚との戦いの際、宋の公子・目夷が楚の布陣しないうちに攻撃しようと進言したが、襄公は君子は人の困っているときに苦しめてはいけないといって攻めず、楚に敗れたという故事によるものです。本書エピローグ等でお二人はこう指摘します。 「『孫子』は、儒学の反対です。『宋襄の仁』になるなということを教えている。襄公のようにはなってはいけない、ということです」(渡部) 「『孫子』のもっとも重要なエッセンスは『宋襄の仁』になるなであり、『ええかっこしい』ではいけないことに尽きます」(谷沢) 韓国の慰安婦・徴用工・レーダー照射等々の理不尽の対日攻撃に際して、ささやかな反撃(戦略物資の対韓輸出規制)をしたとたん、「報復の応酬に陥りかねない」「即時撤回せよ」と居丈高に一方的に日本政府を批判する社説(2019・7・3)を書く朝日新聞論説委員にも本書を読んでもらいたいものです。 ※本書は、2013年に小社より刊行した単行本『孫子の兵法 勝つために何をすべきか』を改題し、WAC BUNKO化したものです。
-
-本書は、二〇〇〇年一月にPHP研究所より出版された『人生は論語に窮まる』を改題して二〇一二年にワックより刊行した『いま、論語を学ぶ』を『だから、論語を学ぶ』と再度改題したWAC BUNKO版です。 こんなに読みやすく、よく分かる! 「知の巨人」の二人の結論 人生で大切なことはみんな論語が教えてくれた! 「この本は読後感が大変さわやかで、心が洗われるような気がする。自信を失って浮遊状態にある日本人にとって、孔子の『論語』と、渡部・谷沢両先生の本書の教えは最高の人生指南だと思う」(日下公人「解説」より) ●社会生活をきちんとしていれば教養は自ずからつく ●友だちになろうと思われる人間になれ ●自分より劣った者を友にする人は成長しない ●人生とは八割以上が待つことである ●偽善のメッキは必ず剥げる ●「信」がなければ何事もなし得ない ●賭博の借金は必ず返すのが紳士の条件 ●これだけは許せないという基準を持つ ●露骨な批判を嫌う日本社会の雰囲気 ●実力があれば隠れたままで終わることは考えられない
-
5.0こんなによく分かる! そして面白い! 日本人なら知っておきたい日本の歴史・神話の故郷 編纂1300年を超える古事記の謎を解く! 本書は三十五年以上も前に書いたもの、つまり一種の「若書き」である。しかし今回、丁寧に読み直してみたが、内容を変える必要のあるところはなかった。この本が最初に出た時の週刊誌の書評に、「危険な本だ」という主旨のものがあったことを覚えている。その頃はソ連瓦解以前であり、国連を批判したり、憲法を批判したり、南京大虐殺説を批判したりすると、議員や大臣も罷免されたものだった。たった三十数年前の話だが、今昔の感に堪えない。その頃に書いたものでいまも変える必要がないのだから、今後も変える必要がないのではないかと自分の「若書き」を読み返した次第である。
-
4.0
-
3.0夢見る「平和ボケ」と「情報弱者」を煽るマスコミを一喝する 門田隆将 今の日本は、左右対立の時代ではなくて、夢見る「ドリーマー(D)」と、「リアリスト(R)」との「DR戦争」の時代。そんな時代に「ドリーマー」向けの雑誌を作ったら絶対にダメ。ところが、新潮社や文藝春秋まで、「ドリーマー」向けに編集するようになった── 高橋洋一 アマゾンでワンちゃんの「ペット用のトイレシート」を買うと、同じ日付の新品同様の朝日新聞が送られてきた。これはいわゆる「押し紙」のリサイクル活用なのか? もはや、日本の新聞やテレビなどは、「情報弱者」にしか相手にされない「ミニコミ」に成り下がった──
-
-川村二郎 日本型リベラルの正体とは……良く言えば現実離れをした空理空論を弄ぶ子供、悪く言えば無責任でいざとなると逃げ隠れする卑怯者。 タテマエは子供のもの、ホンネは大人の世界:何でもかんでも平等を求めるのが子供なら、文化遺産が権力者の遺物で、人間が平等なのは、法の前だけであることを知っているのが大人である。 竹内久美子 平等とは……モテない自分にも女を平等に分け与えよという意味、貧富の差がないとは、稼ぎのいい男が妬ましいから格差をなくせという意味。 長年にわたり学界に巣くい、腹立ち、呆れ、うんざりし続けている連中の正体:科学的事実の前に思想があり、思想のためなら捏造、改竄、隠蔽もいとわない、時には研究妨害をもする。
-
-フェイクニュースといえば――朝日だけではない、いまNHKが酷い! 誤報しても謝らない朝日。新聞の体裁をとった怪文書でしかない。 安倍総理のことは何もかもすべて気にくわないのが左のメディアと政党。 高山正之 ジャーナリスト トランプ叩きの差別的報道に明け暮れる米国にはまともなジャーナリズムは存在していないかに見える。日本の新聞も同じ症状を示している。中でも朝日はひどい……。 和田政宗 参議院議員・元NHKアナウンサー 「NHKスペシャル」の「731部隊の真実~エリート医学者と人体実験~」などは、結論ありきのバイアスがかかった放送だった。自虐史観的な「史実を歪める」報道は大河ドラマにも見られます。
-
3.0本書で論難されている「勘違い人間」とは──こんな面々! (1) 生まれながらの特権・利権をもった世襲人間(政治家・医者・歌舞伎役者等々) (2) 能力がないのに有名になり図に乗っている人間(テレビタレント・芸人等々) (3) 能力がないのに、自分を偉いと錯覚し、価値観を押しつける人間(作家・弁護士・評論家・キャスター等々) (4) 国民の血税をすすっている人間(天下り官僚・補助金漬けの農民・漁師等々) (5)勘違いしている組織やテレビ局の人間(日本相撲協会・日本弁護士連合会・「サンデーモーニング」等々)---のことである。 「暴言」というなら云え! ・国会の世襲議員が150名? 先進国ではありえない ・芸能人・漫才師・歌舞伎役者己の専門に徹しろ ・TVに出てくる大学教授・記者・弁護士は厚顔無恥 ・某映画監督よ、権力が嫌いなら助成金を返せ ・偉そうに屁理屈こねるスポーツ選手に媚びるな ・たいした小説も書けずに作家を名乗るバカ ・警官のネズミ盗り・スピード違反摘発は詐欺だ (主要登場人物) 池上彰、是枝裕和、小泉進次郎、辻元清美、蓮舫、関口宏、羽生結弦、ビートたけし、阿川佐和子、谷岡郁子、タモリ、太田光、大竹まこと、安室奈美恵、尾木直樹、田中英寿、中田英寿、白鵬、原晋、安藤優子、テリー伊藤、佐藤優、下重暁子、寺島実郎、青木理、八代英輝 ……ほか多数登場!
-
5.0
-
4.2いまからでも遅くない? あなたも「神童」になり、「数学バカ」「理系バカ」になれる!? 小学・中学・高校時代、教科書をもらった初日にその内容を全て理解できた――そう豪語する「神童」だった著者による画期的なAI型知的生 活実践記です。 激烈な競争社会を生き抜くためのノウハウも満載。そして、「専門バカ」と言われるような人材こそが、明日の日本の国難を救うと結語。渡部昇一さんの『知的生活の方法』とは一味違った新しい知的生活の方法も提唱。そのポイントは「数学バカ」になれるかなれないか――です。そのためには…どうすべきか? 先ず、「新聞・テレビ」に不要に接しないこと! そして、この本に書かれている「AI型知的生活」を実践してみては。そうすれば、読者のみなさんは「文系バカ」にならず「数学バカ」や、なんらかの「専門バカ」となり、官界やマスコミや会社や地域社会で注目され活躍の場を得て、日本を救うことができるかも……。 いまからでも遅くありません。会社を定年で辞めたあと、海外の大学に留学して博士号を取る人もいます。なせばなるのです! ! それにつけても、ひっかかったのかどうかは別にしてセクハラ騒動を巻き起こすような「何の専門性もない」財務官僚の多くは「ただのバカ」。そして、モリ・カケ報道など、些細な問題を追及する記事ばかりを書いている「文系のマスコミ記者」こそ「本当のバカ」。その点、著者のような「数学バカ」は「専門バカ」とバカにされがちですが、そういう「専門バカ」こそが、日本の国難を救うのです。日本のために役立つ「専門バカ」はどんなバカなのか、本書を読んで読者のみなさんも是非考えてみてください。
-
3.0「慰安婦虚報と同じ過ちを繰り返す朝日は、ニュースの軽重を判断できなくなり、もはやただの紙切れで新聞ではない! 」 ──『崩壊 朝日新聞』『こんな朝日新聞に誰がした?』の著者(元朝日記者)の長谷川煕が再び朝日を直撃! 「日本罪悪史観」を克服しようとする安倍首相を打倒すべき仇敵とみなし、そのために『印象操作』『流言飛語』による虚報を延々と続けた朝日新聞は、あまりにも「恥多き新聞」ではないのか! 朝日が火を付けたこの大騒動、多くのメディアや野党は安倍政権追及に血眼になりましたが、収賄の疑いはもちろん、 何らかの不当介入のようなことを安倍氏がした事実は浮上せず、逆に今治市に加計学園が獣医学部を新設する経緯に安倍氏は何の関係もないことが私の取材でも明確になってきています──(著者) 長谷川氏が本書で言及もしている小川栄太郎さんの『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪』を、朝日新聞社は「本社には一切取材もないまま、根拠もなく、虚報、捏造、報道犯罪などと決めつけている。 事実に反した誹謗中傷による名誉毀損の程度はあまりにひどく、言論の自由の限度を超えている」と批判し訴訟まで起こしました。 しかし、長谷川さんは、元OBとして正式に取材申込みをしたものの拒絶されました。 本書に関して「本社には一切取材もないまま」とは、朝日には言わせません! そこで、長谷川さんは「玄関からある家(朝日)に(どのように疑惑が作られていくかの取材)に入ろうとしたのですが、作戦を変えて裏の勝手口から同家(朝日)にお邪魔(何が報道されていないかを追求)することにしました」。 「無断で裏の勝手口から入ったのです」「そうしたら、そこには汚い洗濯物が籠にいっぱい入っていたり、食べ残しの茶碗類が汚れたテーブルの上にあったり、棚には埃が溜まっていたり、まあ同家の日常の有様が裏からそこそこ観察できました」とのこと(本書22頁~)。 朝日の内部文書解読や徹底取材で明らかになったモリ・カケ事件をめぐる「虚偽報道」の実態、とくとご覧ください。──(編集部) 衝撃の書下しノンフィクション!! (商品内容) 第一部 「文科省内部文書」による「空中楼閣」に嵌まった朝日新聞 安倍疑惑事件は冤罪である! 「フェイクニュース」を見分ける 築地(朝日)の報道の初歩から遊離した空気 安倍首相は「報道被害者」だ 朝日は私の取材申込みを断った 「総理のご意向」“スクープ”に見る重大な疑い 朝日の隠蔽報道 小川本に関する朝日の申入書は破綻している 私がデスクなら紙面掲載は許さなかった 「夜郎自大」の「自画自賛」 陥穽に嵌まった朝日記者の盲点 「スクープ前夜」の総合判断の欠如に唖然 朝日記者の“徹底取材”は思考麻痺によるもの 「吉田調書」虚報と同じ構図 朝日キャンペーン報道の歪曲性 社内翼賛体制の自己賞賛・自己催眠 朝日の「報道しない自由」に異議あり 朝日はもはやただの紙切れで、新聞ではない 第二部 獣医師界と癒着した官庁行政の欠陥を黙殺した朝日新聞 悪玉と善玉をアベコベにした加計報道 腐敗だらけだった農政 斬り捨てゴメンの斬妖状を突きつけられた学者 永久不変の「国公私立十六校体制」 「印象操作による報道」への反論 知的能力が著しく低下した朝日記者 BSE事件が明るみにした獣医師のレベルの低さ BSEの隠蔽工作を謀った農水省・獣医師会 捏造に加担した獣医師たち 獣医学界の「村社会」の秩序維持のために手玉に取られた朝日 決定的だった加戸守行前愛媛県知事の国会証言 朝日は加戸証言をほぼ黙殺 安倍首相の失態 朝日・坪井コラムの欠落部分 疑惑の矛先は獣医師側に向かわず 日本獣医師連盟の「政界工作」の実態 策謀工作で汚れきっていた日本獣医師会 補遺 「流言飛語」と「報道しない自由」を謳歌する朝日新聞 朝日発の「流言飛語」に同調する野党政治家とメディア 恥多き居丈高・傲岸不遜な態度 続発する朝日虚報に見られる特徴とは 安倍首相「関与疑惑」ではなく朝日「不報道疑惑」が決定的に重要 「カケ報道」関連参考資料──(編集部編)
-
5.0朝日新聞記者、高級官僚、エリート議員── 学歴のあるバカが国を滅ぼす! 元『週刊朝日』編集長が「学バカ」を斬りまくる! 「学歴のあるバカ」ほど始末におえないものはない。取扱いのむずかしい「学バカ」はマスコミや国会、政財界にかぎらず、どこにでもいる。読者諸兄姉の上司がそうでないことを祈るばかりである。 私は朝日の社内だけでなく、他の会社や官庁、大学で、学はあってもバカはバカを沢山見てきた。テレビを見ていると、こういうバカは増える一方のようである。バカがはこびらないようにするには、偏差値の物差しをなくすことが第一歩である。──「あとがき」より
-
4.5「近未来の衝撃──激変する社会」に どう対応するかを考えるための必読の書。 これは“予測”ではない。すでに見ている現実だ! AI、IT問題の専門家が縦横に語り合う──人類の進化速度がますます加速化されるシンギュラリティ(技術的特異点)がやってくる近未来(2025年~2045年)の日本、世界はこうなる!? 「これは予測ではない。すでに見ている現実だ!」 ・寿命は120歳まで延びて、還暦は人生の折り返し点になる? ・AI兵器によって、人が死なずに戦争ができるようになる? ・AI作家が芥川賞を受賞し、編集者の仕事はなくなる? ・政治家、裁判官、検事、弁護士、外科医、会計士、税理士のほとんどは失職する? ・人間そっくりで会話もアレも可能なセックスロボット誕生で性産業は衰退し売春婦、アダルト女優は消滅! そして人は結婚しなくなる?……
-
3.5遊牧文化のモンゴルに先輩・後輩の序列はなく、“力”がすべての社会! トップは法をつくる人であって、守る人ではない! 白鵬が我がもの顔で振る舞う理由 まえがき 第1章 モンゴル力士は、なぜ強いのか? 遊牧騎馬民の、男子たるものの必要条件 モンゴル相撲に求められるのは、平衡感覚と敏捷性 モンゴル力士は君主のボディガードだった 『日本書紀』に見られる相撲の起源 宮中の「三度節」とナーダムの三種の競技は起源が同じ 厳密にいえば、相撲は国技ではない 日本のマスコミは、異文化に対する想像力に欠ける 「いじめ」が成立するのは日本文化の特徴 日本の「隣百姓」とはまったく正反対の生き方 「まわりに合わせる」という考え方のないモンゴル文化 モンゴルには「長幼の序」はない 世代を厳しく区別する「輩行」という考え方 モンゴルでは末子が親の面倒を見る 第2章 モンゴル女性秘話 朝青龍と白鵬の母親は、モンゴル国立大学卒のインテリ モンゴル人にとってのいい男、いい女 遊牧生活を維持するため、男と女の役割分担は明確だった 夫婦喧嘩をすると、「出て行け」ではなく「オレは出て行く」 モンゴル草原東端の遊牧民「烏丸と鮮卑」 「男は女の家の労役に服し、その後、女の家から財産の分与を受ける」 二千年前でも二十世紀の内モンゴルでも、女に財産権があった チンギス・ハーンの賢母、ホエルン ホエルンは自分の部下と軍隊を持っていた 征服戦争に従軍したチンギス・ハーンの娘 中華思想は、遊牧民に敗北したことから始まった「負け惜しみの思想」 孫娘を第三夫人にしたアルタン・ハーン 夫、義理の息子、その息子、その孫と四度結婚して権勢をふるった女 女をほめないイスラム教徒の知識人が絶賛したソルコクタニ妃 フビライ・ハーンの正皇后チャブイ・ハトン チャブイこそが、元朝皇帝と帝国の政治機構の接点だった 中央アジアとインド洋を旅して二十五歳で死去したコカチン姫 遊牧民の族外婚は、安全保障のため チンギス・ハーンの五百人の妃妾は本当か? チンギス・ハーンのすべての財産を管理していた四人の后妃 第3章 モンゴル帝国を知っていますか? 明朝は、モンゴル帝国の宗主国・元朝の唯一の継承者か 「韃靼」とは、漢人のモンゴル人への“侮辱語”だ 征服された側の人たちが書いた歴史 遊牧騎馬民が世界史を変えた時代の終焉 なぜ、遊牧帝国と呼ぶのか? モンゴル帝国時代のモンゴル人とは 姿や名前は変わったが、世界各地でふたたび支配者となって生き残った 元朝の「行中書省」が、現在の中国の省の起源 明朝も清朝も元朝の継承国家だった 四百年かけてモンゴル帝国の西半分と北方すべてを獲得したロシア 満洲国・興安省の境界が、そのまま中国内蒙古自治区の境界となった 清朝に課せられた莫大な賠償金が、モンゴル人に劇的な変化を与えた 戦前、日本人はなぜ「満蒙」といったのか 内モンゴルも外モンゴルも、同じことばを話す同じモンゴル人だった 中国に留まったのが「内モンゴル」、離れたのが「外モンゴル」 「玉子はぜったい食べないでね、中国人が作っているから」 北の遊牧民は南の農耕民をばかにしていた モンゴル人が中国人を嫌いな最大の理由 モンゴルとチベットは同盟関係にあった 「ダライ・ラマ」の誕生 チベット仏教徒になった遊牧民が、モンゴル民族と呼ばれている カザフ人もモンゴル人と同じモンゴル帝国の子孫たち モンゴルとカザフスタンはもはや違う文化の国 第4章 日本にとってモンゴルは大切な国 蒙古襲来と日本の幸運 「義経は死なずに北方に逃げた」 末松謙澄こそが“義経伝説”の生みの親 チンギス・ハーンが源義経であったことを証明しようとした男 日本人はなぜ“義経伝説”が好きなのか 伊藤博文に見込まれた末松謙澄 「チンギス・ハーンは源義経だった」の英語論文は愛国心から 「モンゴロイド」ということば 「蒙古斑」は日本の赤ん坊で初めて発見された 「民族」とは、十九世紀末から二十世紀初めに誕生した政治的な呼び方 「人種」の区分も「言語」の区分も、政治的動機から生まれた 民族も人種も言語もみなフィクションか これだけ違う日本人の美意識とモンゴル人の美意識 モンゴルを知れば、生きるのが楽になる 二大国の狭間で、今日まで独立を保ってきたモンゴル外交の巧みさ 中露との等距離・中立外交、アメリカとの積極的な協調外交 上海協力機構には加盟せず、オブザーバーを選択する 国連を舞台に、一銭も使わず大きな貸しを日本につくったモンゴル外交 日本の「文化」から、世界の「文明」になった相撲 横綱の品格を問うマスコミに品格はあるのか モンゴル国は、日本にとって大切な国になる
-
3.0出井伸之と社長レースを争ったこともある(?)、 NHK「プロジェクトX」にも登場した元ソニー役員が傘寿(80歳)を超えて、 まだ働くのはなぜか── シルバー世代(後期高齢者)による 画期的な「就活・終活・仕事」論 20代、30代よ、人生後半戦は楽しいよ! 40代、50代よ、定年なんか怖くないよ! 60代、70代よ、君たちはまだ若いよ! ──と言いたい! 「この本は、後半戦にチャレンジしていくことになる後輩たちへのエールのつもりだが、前半戦をいま戦っている人たちにも是非読んでいただきたい。マラソンは折り返し地点で終りではない。人生の勝負はゴールで決まる」 定年後やってはいけない十戒 1学校に行く2資格を取る3語学の勉強をする4ジムに行く5葬式に行く6本を書く7勲章を貰う8NPOに参加9会社を創る10勝負事をする。 さて、定年後やるべきことは……(本書をお読みください) 「古稀」「還暦」どころか「傘寿」を超えて「米寿」「白寿」「百寿」まで働くために――誰も気付かなかった人生哲学の書── ビジネスマンの人生は、20代から定年(60歳)までの40年と、定年後の60代から百歳(少なくとも九十歳) までの40年とに分けられる。前半(表)と後半(裏)の人生、どちらも「勝ち戦」にするにはどう働くべきか───。
-
3.0
-
4.0米国籍・米国人の私が、 袋叩きにあおうとも真実を語ろう! 先の大戦は「自衛の戦争だった」と、 マッカーサーも最後は変わった! アメリカ人が教わった「日米戦争」は嘘だらけ 「真珠湾・南京事件・慰安婦」の嘘を撃破しよう!
-
3.0利権と占いの大統領「朴槿惠よ、お前もか」 かつて『醜い韓国人』の刊行に関与し、韓国の文化・政治にも詳しい加瀬英明さんと、韓国生まれで、日本の大学に学び、日韓文化の違いを身をもって体験し、『攘夷の韓国開国の日本』で山本七平賞を受賞している呉善花さん。そんな二人が、スキャンダルまみれで朴槿恵大統領が辞任する背景にある、韓国の歴史・文化の根深い恥部・後進性を徹底解剖。 呉善花 「韓国は表面上は日本のようだけれども、消費社会の皮を一枚剥がすと北朝鮮そっくり。朴槿恵は百年以上昔の閔妃の再来のようなもの」 加瀬英明 「『反日』を愛国心のシンボルにするしか生きていけない韓国は、まるでアンデルセンの『裸の王様』みたいな国。滑稽というしかない」 はじめに──占い政治で韓国を愚弄した朴槿惠………………………呉 善花
-
-二人はいずれも朝日新聞OB。それぞれ『崩壊朝日新聞』(長谷川氏)と『ブンヤ暮らし三十六年 回想の朝日新聞』(永栄氏)という著作がある。この二人が、慰安婦報道などに見られた、誤報虚報だらけの「朝日新聞」にメスを入れる。こんな堕落した言論機関になった諸悪の根源、ガン細胞は、歴代社長・幹部社員たちの「平和ボケ」「左翼リベラル」「反知性主義」にありと、古巣をめった斬りにして論駁する。抱腹絶倒&一読賛嘆の「朝日新聞血風録! 」 『崩壊 朝日新聞』を出して、朝日関係者から「晩節を汚さないでください」と言われたり、 「ゴロツキ」視されても、全く辛くない。「ゴロツキ」、光栄じゃないか…(長谷川熙) 朝日にはタテマエ優先というか、現実にはありえないユートピア、青い鳥を追いかけるような記者がやはり多い。 だから知識人といわれる人から支持される…(永栄潔) はじめに エリック・ホッファーと長谷川さん 永栄潔
-
5.0マスコミ報道では絶対に分らない沖縄の真実! 「在日米軍の73.8%が沖縄に集中している」── これは、テレビや新聞が沖縄を伝える一つの常套句だが、これはデタラメである。 つまり、73.8%という数字を算出する際の分母に、三沢、佐世保、横田、岩国、横須賀など 自衛隊との共有の在日米軍基地は含まれていない。 三沢の米軍基地などは、自衛隊の所有部分はわずか3%だが、 これも共有施設として73.8%の分母には入っていないのである。 要するに、73.8%とは、米軍専用施設のことをいうのだ。 このように、本書は、マスコミ報道では絶対に分らない「沖縄の核心」に、 政治、経済、社会、歴史など様々な角度から迫った著者渾身のレポートである。
-
3.0来日して34年あまり。 新たな日韓の架け橋たらんと欲した私だが…… 韓国はもはや、誰が大統領になっても 「反日・親北」の呪縛から逃れられない ・ 金正男暗殺でも、「親北」感情は広がる ・ 慰安婦像は日韓関係の棘 ・ 韓国の「親北」の心理 ・ 朴槿惠の転向と「反日・親北」姿勢 ・ 甦る盧武鉉の亡霊 ・「国民情緒法」に則った「過去清算」 ・ 韓国女性はシャーマンや占いに依存……ほか はじめに──金正男暗殺でも目覚めない韓国 第1章 朴槿惠体制はいかにして死滅したか 大統領弾劾訴追案の可決 崔順實の疑惑 朴槿惠のイメージが裏切られた 韓国のシャーマン文化と朴槿惠 現代でも韓国女性はシャーマンや占いに依存している 崔順實の父・崔太敏は母親を利用して近づいた 崔親子の手慣れた錬金術 崔太敏との関係を深め、父・朴正熙の暗殺まで招く 金載圭は朴正煕暗殺の動機に「朴槿惠と崔太敏の行状」を挙げていた 孤独な朴槿惠の心をつかんだ 崔順實との関係のはじまり 一九八〇年以後も朴槿惠を支え利益を得てきた 朴槿惠の謎の金脈 鄭允会が陰の実力者だった? 第2章 政治家・朴槿惠の「光と闇」 死んでから両親に正々堂々と会うために活動再開 一九九八年、政治家として踏み出す 北朝鮮への甘い認識で金正日と和解 報われなかった金大中への謝罪 大統領選出馬による転向と「反日・親北」姿勢 二〇一二年大統領選で、保守陣営が朴槿惠支持に流れた事情 朴槿惠に求められたのは「反共反日・富強国家」再生だったが…… セウォル号事故対応から凋落がはじまった 『産経新聞』加藤記者の名誉棄損事件の内幕 「反日」の拳を下せなくなった ノーベル平和賞を狙った? 朴槿惠政権の足跡 第3章 歴代大統領の末路と「反日・親北」姿勢の歴史 歴代大統領の末路 戦後韓国の出発は日本の残したものから 反日政策の一方での有能な人材としての親日派の活用 戦後韓国は日本の経済援助によって復活した 韓国の「親北」の心理 金大中時代の「南北首脳会談」で北朝鮮の「悪印象」を覆した 南北統一への韓国、北朝鮮の姿勢 第4章 盧武鉉の「罪と罰」 「東北アジアの時代」をアピール 盧武鉉の「反日・親北」政策の推進 「親北」政策による韓国経済の悪化 盧武鉉政権になってはっきりしてきた「国民情緒法」 「国民情緒法」に則った「過去清算」 北朝鮮に肯定的な教科書の登場 盧武鉉の「過去清算」という暴挙 「親北=反日=民主」イデオロギーの確立 韓国では、司法も「国民情緒」によって判断される 「人類の普遍的な倫理」を振りかざす盧武鉉の対日強硬策 第5章 韓国にとって「慰安婦」問題とは何か 慰安婦問題にかかわるアメリカの対日非難決議の背景 「クマラスワミ報告書」の真偽 国連が慰安婦問題を取り上げるように働きかけたのは日本人弁護士 慰安婦像は日韓関係の棘 「韓国挺身隊問題対策協議会」とはどのような組織か エピローグ 韓国崩壊への道 金正男暗殺でも、若者たちの間に「親北」はさらに広がっている 甦る盧武鉉 ポスト・朴槿惠は北朝鮮寄りの政権になる 誰が大統領になっても、韓国は「反日・親北」で滅びの道に 大統領弾劾の行方
-
4.1
-
-2014年、三人の少女からなる日本のメタルアイドルグループ「BABYMETAL」が世界の音楽シーンに登場し、またたく間に大人気となった。その神懸かり的な音楽パフォーマンスをもって欧米の大人達を熱狂させて急速に世界進出した光景は、「BABYMETAL現象」と称されている。この現象を描写し、さらに日本文化史の観点から解説する。BABYMETALの音楽スタイルはあくまで特殊日本的な形態であり、本来は日本の音楽業界以外では人気を得ないものであるはずだった。ところが世界の音楽シーン席巻という、本来起こり得ないはずの出来事が起こってしまった。その成功した背景を象徴するキーワードとは、「大人文化と子供文化の合体」。BABYMETALの音楽スタイルの実態とは、滅びかけている日本古来の大人文化の残骸の上に乗り、戦後に伝統文化が廃れ形骸化するに同期して発生した子供文化の衣をかぶり、欧米の音楽形態を借りて成り立っているのである。追随する者のいない所以である。BABYMETALの音楽パフォーマンスの裏付け・背景となっているものを広範多岐にわたる側面から解剖して解説し、BABYMETAL現象と日本文化の未来における展望を描く。
-
3.8
-
3.8アメリカのアポロ計画が終了してから40年余――その間、人類は月に行っていません。人々のあいだにはいつしか「いまさら月になど行く必要はない」という認識さえ広まってきています。しかし、それは月での優位を独占しようとするアメリカの広報戦略にはまっているにすぎません。じつは世界ではいま、アメリカ、中国、ロシアなどを中心に、月の探査・開発をめぐって激しい競争が水面下で始まっています。30~40年後には、月面基地が完成するともみられているのです。世界はなぜ月をめざすのか? その答えが、本書にはあります。(ブルーバックス・2014年8月刊)
-
-
-
3.9
-
3.7「管理者たち」が牛耳る官僚機構、「説明責任」なき行政システム――。日本社会を蝕む病根とはなにか? 政権交代や大震災を経てなお変わらない、日本社会の本質を突く衝撃作。書き下ろしを加えた最新改訂版!
-
4.1自己責任ではない! その貧困は「働けない脳」のせいなのだ。 ベストセラー『最貧困女子』ではあえて書かなかった貧困当事者の真の姿 約束を破る、遅刻する、だらしない――著者が長年取材してきた貧困の当事者には、共通する特徴があった。世間はそれを「サボり」「甘え」と非難する。だが著者は、病気で「高次脳機能障害」になり、どんなに頑張ってもやるべきことが思うようにできないという「生き地獄」を味わう。そして初めて気がついた。彼らもそんな「働けない脳」に苦しみ、貧困に陥っていたのではないかと――。「働けない脳=不自由な脳」の存在に斬り込み、当事者の自責・自罰からの解放と、周囲による支援を訴える。今こそ自己責任論に終止符を!
-
5.0「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。 病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」 自分と世界、身体と心、正常と異常…… 目に映る景色をガラリと変える一冊! 【本書で考える問い】 ●病気はどう「発明」されるのか? ●新しい病気が生まれるのは、いいこと? ●ゲームのやりすぎやごみ屋敷は病気のせい? ●生きづらさは連鎖する? ●どこまでが医学で、どこからがビジネス? ●命の優先順位はあるのか?……ほか 「私は以前から、「病や障害はマイナスなもの、できるだけ避けるべきもの」という医学での「ふつう」の考え方に、どこか違和感をもっていました。 しかし、もちろん、医学を否定しているわけではありません。頭が痛いときは薬を飲みますし、必要なワクチンもきちんと受けます。先日も、持病が悪化して入院し、治療を受けました。医学がたくさんの命を救っていることも、よく知っています。 医学は、病や障害をなくすことを目指しています。それは悪いことではありません。 でも、人間は生き物ですから、死を完全に避けることはできませんし、同じように、病や障害を完全になくすこともできません。病や障害とともに生きていくことを肯定することも必要です。そのときには、「ふつう」を見直す文系の考え方が、大きなヒントになると思うのです」――「はじめに」より
-
4.0なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか? お金も人も足りない……打つ手はあるのか? 見て見ぬフリはもうできない! 道路、鉄道、水道、インフラ、橋…… この国は崩れ去ってしまうのか? 全国民当事者! 私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を 豊富なデータと事例から解き明かす! 「インフラは、どのように造るかだけでなく、どう維持していくかが非常に大事なのです。言葉にするとシンプルですが、簡単なことではありません。 そのことを端的に示しているのが、40年ほど前にベストセラーになった『荒廃するアメリカ』の内容です。アメリカでは1930年代に集中整備されたインフラに対し、その後のメンテナンスに十分な予算を割かなかった。その結果、老朽化が進行し、50年後の1980年代の経済に大きなダメージを与えました。 景気がいい時代に大量のインフラを建設して、多くの人の生活を便利にしたのはいいものの、うまくメンテナンスをしないと、朽ち果ててしまう、あるいは八潮の事故のように崩壊してしまう。 これがインフラの抱える“危機の本質”なのです」――「はじめに」より 【目次】 第1章 日本のインフラはどうなっているのか? 第2章 インフラはどのように劣化するのか? 第3章 「良いインフラ」をどう造るか? 第4章 「今あるインフラ」を長持ちさせるには? 第5章 地域のインフラはみんなで守る 第6章 インフラの「残された課題」
-
3.3■他の動物とは違う“ヒトの本性”がわかる! ヒトは美しくもあり、また残酷な生き物だ。赤子のときは利他的な行動を取るのに、なぜ大人になるにつれて利己的になってしまうのか。「人の能力を決めるのは遺伝か環境か」という論争はなぜ不毛なのか。チンパンジーにヒトのような言語能力はあるのか。魚にも自意識はあるのか――。遺伝子、言語、自意識という3つの謎を進化生物学の知見から読み解き、“人間の正体”に迫る。 ■本書の要点 ●ドーキンスの『利己的な遺伝子』は誤解されている ●チンパンジーは言語の意味を理解できない ●魚にも自意識がある!? ●ヒトは本来、他者に優しい生き物 ●潔癖、肥満、運動不足という「現代病」 ■目次 ●第1章:生き物の世界 ●第2章:ヒトに固有の特徴は何か ●第3章:「遺伝か環境か」論争の不毛 ●第4章:ヒトは本来「利他的」なのになぜ争うのか ●第5章:「現代病」に陥る人類 ●第6章:ヒトを育てる、人を育てる
-
3.9
-
3.8■長年の学歴論争に一石を投じる! 学歴不要論など侃侃諤諤の議論がなされるのに、なぜ学歴社会はなくならないのか。誰のために存在するのか。背景にあるのは、「頑張れる人」を求める企業と、その要望に応えようとする学校の“共犯関係”だった!? 人の「能力」を測ることに悩む人事担当者、学歴がすべてではないとわかっていてもつい学歴を気にしてしまうあなたへ。教育社会学を修め、企業の論理も熟知する組織開発の専門家が、学歴社会の謎に迫る。 ■本書の要点 ●学歴は努力の度合いを測るものとして機能してきた ●ひろゆき氏の学歴論は本質を捉えている!? ●日本の学歴主義の背景にあるメンバーシップ型雇用 ●仕事は個人の「能力」ではなくチームで回っている ●「シン・学歴社会」への第一歩は職務要件の明確化 ■目次 ●第1章:何のための学歴か? ●第2章:「学歴あるある」の現在地 ●第3章:学歴論争の暗黙の前提 ●第4章:学歴論争の突破口 ●第5章:これからの「学歴論」――競争から共創へ
-
-
-
4.2【だから若い女性はホストにハマるのか!】なぜ若い女性がパパ活、風俗、立ちんぼで稼いでまで、ホストクラブで大金を使うのか? 背景には、担当ホストの魅力だけではなく、歌舞伎町特有の論理がある。感情労働・肉体労働・アイデンティティ労働のすべてを兼ね備えたホストの仕事から、女性客の深層心理、そしていまの若者の価値観・消費行動まで丸わかり。Z世代ライターが、愛憎渦巻く夜の世界の「搾取と依存の構造」を解き明かす。 【“歌舞伎町の病”は他人事ではない】●病1 売上至上主義:金や売上がすべて、結果さえ出せばいい ●病2 外見至上主義:ルッキズムの対象は一般の男性会社員にも波及 ●病3 自己資本主義:自らの見た目、プライベートまで切り売りする ●病4 承認至上主義:自分を見てくれないと特別感を得られない ●病5 推し万能主義:身近な人まで、誰でも“推し”と呼ぶ 【目次】●第1章:歌舞伎町・ホストクラブとはどんな場所か ●第2章:ホストは究極の感情労働 ●第3章:ホストはアイドル化しているのか? ●第4章:なぜ若い女性がホストにハマるのか ●第5章:売掛問題解決のための緊急提言 ●第6章:歌舞伎町は若者の価値観の最前線
-
3.0
-
-
-
5.0
-
3.5
-
-
-
3.5●威圧的、話を聞かない、権力に従順――自覚症状ナシ! ●男女問わず日本全国に蔓延する「おっさん思考」の正体とは? ●5人の識者と語り合う「男社会の価値観」の行方 「おっさんは、私だった」。かつてアナウンサーとして活躍し、現在はエッセイストとして活動する著者は、ある経験を契機に、これまで忌み嫌っていた「おっさん的な感性」――独善的で想像力に欠け、ハラスメントや差別に無自覚である性質――が自分の中にも深く刻まれていることに気づく。この“おっさん性”は、男女問わず多くの人々に深く染みついているのではないか――。本書はそんな日本社会に染みついた“おっさん性”について考察した、著者と5人の識者との対話集である。ハラスメント、同調圧力――男も女も生きづらさを抱え、心を殺さねば生き延びられない“おっさん社会”から脱却するためのヒントがここにある。
-
3.9仕事がうまくいかない、会社が変わらない、人生の先が見えない……。その原因はすべて「マーケティング」が足りないからだ! 本書はカリスママーケターが厳選した「35のマーケティング技術」を用いて、自分を、会社を、そして社会を変えるための方法論を説くもの。世界の共通認識となりつつあるSDGs17の目標をベースに、どのようにマーケティングを用いて成果を出していくかを実践的に紹介していく。例えば、●「逆転ポジショニング」による価格付けで優良な顧客を集める ●ジェンダー平等実現は「センターピン集中戦略」で一点突破 ●ダッシュボードで若手もベテランも公平に働ける会社を作る ●逆算思考で難問に思いもよらなかった解決策を ●ビジコンで外部の優秀な人材とつながる など、極めて実践的なノウハウを紹介する。これから訪れる未来と、そこで活躍するための条件がわかる、まさに神田流マーケティングの集大成。
-
-パンデミック、大国間競争の本格化、地球環境問題の深刻化など、人類は大きな曲がり角、いわば「転形期」の只中にいる。単なる過渡期というだけにとどまらず、矛盾や対立も併存する緊張状態にあるといえよう。この局面を乗り越えるための視座とビジョンを、各界の第一人者が提示する。 【本書に登場する識者と論考のテーマ】柳井正「サステナビリティと経営」/小林喜光「生き残る企業」/マルクス・ガブリエル「倫理国家・日本」/養老孟司「情報処理に偏重する現代人」/宇野重規「直接民主主義」/レベッカ・ヘンダーソン「環境問題を解決する資本主義」/御立尚資&ヤマザキマリ「現代のルネサンス」/仲野徹&宮沢孝幸「新興ウイルス」/安宅和人「人類の危機」/森田真生「弱さの自覚」/村上陽一郎「科学の可能性と限界」/岩井克人「変貌する会社と雇用」/中西寛「文明の二重転換」/村山斉「基礎学問の重要性」/谷口功一「『夜の街』の憲法論」/兼原信克「経済安全保障の強化」
-
5.0「夫 死んで欲しい」「夫 嫌い」。検索サイトのグーグルで「夫」の後にスペースキーを打ち込むと、衝撃的な単語がズラリと並びます。これは「サジェスト検索」と呼ばれ「そのワード(単語)とセットで頻繁に検索されるワード」を案内してくれる機能です。つまり、サジェスト検索は「他人がどのようなことを考えているかを知る」という楽しみ方もできるわけです。様々な検索ワードを探してみると「えっ、そんなこと考えてたの!?」という驚きのオンパレード。「しりとり 必勝法」「おばさん 定義」「行きたくない 飲み会」「芸能人 身長」「後輩 タメ口」「ドタキャン 彼女」「仕事中 暇つぶし」「既婚者 好きになった」「老人 性生活」「呪い 方法」……。みんな、人には相談できない悩み・おかしなことを検索しています。くすくすと笑えて「ニッポンのリアルな実態」が手に取るように分かる検索ワードの世界へようこそ!
-
3.7日本は世界第二位の経済大国である。一方で、長く続いた不況や昨今の「格差社会論」の影響で気持ちがネガティブになり、「豊かさを実感できない」「恩恵に与っているのは一部の金持ちだけ」などと口走る人が出てきている。それをまた煽るかのように、有力メディアが「非正社員やワーキングプアが溢れている日本は、若者にとって夢も希望もない国」と報じる。だが、それは本当か。台湾出身で在日40年にもなる著者は言う。「日本は、世界各国の食が結集する豊かな社会で、あらゆる情報が安い値段で手に入る」「多くの日本人は生き方の選択肢が無限に存在し、努力と行動で必ず頭角を現せる環境にある」著者自身、いまどころではない就職難の時代に来日し、数々のアルバイトを必死でこなしてきた「究極のフリーター」である。その著者が声を大にして言う。「幸運=チャンスの女神はあなたたちの目の前を通っています。日本は世界で一番夢も希望もある国です!」
-
4.0
-
5.0地方を救うため、まず最初に行なうべきは、地方に仕事をつくること。「地方創生」はこの方針を掲げさまざまな取り組みを行っているが、地方にはすでに仕事がある。しかもそれは第一次産業や建設業など、日本人の日々の暮らしに必要不可欠のものだ。問題はそうした仕事の「職業威信」が低いことである。田舎の仕事は威信が低く、都会の仕事は威信が高い。そうした価値観は、いかにして醸成されてきたのか。さらに三つの「都市の正義」――「選択と集中」「競争と淘汰」「『自分は排除の対象にはならない』という冷たい客観主義」がはらむ罠を、地域社会学者が鋭く指摘する。北海道ニセコ町、山形県飯豊町などの「地方の声」も掲載。 ●「子どもを産めるのは女性だけ」をどう直視するか ●霞が関の影のタスクフォース ●人口密度が高い地域ほど、出生率は低下する ●高齢世代ほど、威信の低い仕事に就く ●国に依存する都市の住民 ●観光で本当に儲けるのは誰か ●首都圏における東京一極集中の内実 ●北海道ニセコ町――地方創生トップの町を脅かす海外資本の乱開発 ●朝日新聞――“小さな拠点”をめぐる「誤報」 ●全国で進む学校統廃合 ●人口減少を改善するための地方創生とは
-
4.5反響を呼んだ朝日新聞連載「パラダイス文書を歩く」の書籍化。バミューダ諸島、アフリカのブルキナファソなど現場を歩いて浮かび上がったタックスヘイブンの実態、日本の大企業の関わりを示す新たな取材成果など、さらなる税逃れの闇を描く。池上彰氏が解説。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「日本人が気づかない日本の良さ」を爆笑コミックエッセイで紹介! 日本に住む外国人たちが目にした日本生活での驚きの数々。そこには、われわれが見落としていた、日本人の暮らしの中でのあらゆる工夫が詰まっていた。内容例を挙げると、◎狭い家だからこそできるエコライフ、そして揚句の果てには彼女もできてしまう日本の家とは? ◎呑み会にはまった外国人。おしゃく文化で異国生活のさびしさもどこへやら ◎缶コーヒー、フルーツサンドイッチ、具だくさんピザなど驚きのアレンジ力 ◎エステ、ネイル、化粧など女性の美的センス ◎超先進的な恋愛観 ◎日本語の擬音の多様な表現力 ◎日本人の必殺奥義「以心伝心」 等々 日本をネガティブに見ていた著者が、なぜか外国人たちの視点を通じて日本文化、日本人をポジティブにとらえるようになっていく。日本を再発見して日本を好きになる、世界地図を広げて、他の国をもっと知り外国人と異文化交流したくなる一冊である。
-
3.5「あのころの未来」を、私たちは生きている。 伝説のマーケティング雑誌「アクロス」元編集長の時代を読み解く視点 1980年代を知れば、2030年が見えてくる! ■「シンプルな消費者」と「クールな支配者」の時代 平成時代はバブル時代との対比で語られることが多い。だが私にいわせれば、バブル時代は非常に特殊な時代であって、一九八〇年代の前半には、平成時代につながる価値観、生活文化の芽生えがあったと思う。私が一九八二年から一九九〇年まで編集部に在籍していた雑誌『アクロス』が一九八〇年代を象徴する雑誌であること、時代の三歩先を予測する雑誌であったことは自他共に認めるものであり、一九八〇年代という時代を知る上では、最も効率的な資料である。そこから平成三〇年を経た現代につながるテーマを見つけ、近未来を予測していく、というのが本書のつくりである。(「はじめに」より) 【目次】 第一章 記号の消費から交換の消費へ 第二章 豊かな社会から小さな幸福へ 第三章 格差社会に破れた人々の反動化 第四章 一夫一婦制の終わり 第五章 街は屋台と市場になる 第六章 虚構化する都市と縄文回帰 第七章 知性からの逃走と呪術への解放 第八章 柔らかい全体主義
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 刊行趣旨)児玉誉士夫、瀬島龍三、白洲次郎、五島慶太、土光敏夫……。日本史の教科書にはほとんど出てこないが、隠然たる力で日本を動かした男たちがいた。海外諜報機関のスパイ説や、暴力とカネの匂いをまとった彼らに、政財界の大物がひれ伏した。昭和という時代は、清濁併せのむ怪物が生きられた最後の時代だった。豊富な写真と証言で14人の怪物たちの人と仕事に迫る。内容)特別対談1 保阪正康×田﨑史朗 フィクサーたちの昭和史日本の黒幕 児玉誉士夫とは何者だったのか石原莞爾はなぜ、いまだ人気があるのか五島慶太 別名「強盗ケイタ」渋谷と東急を作った王白洲次郎の正体 昭和史の黒子正力松太郎 原子力とジャイアンツ吉田茂 日本の戦後を作った男山口組三代目・田岡一雄と芸能界岸信介 妖怪と呼ばれた男特別対談 保阪正康×半藤一利「開戦2日前、東條英機はなぜ寝室で号泣したのか」瀬島龍三 大本営作戦参謀はロシアのスパイだったのか1974~1989 角影政権の時代ロッキード事件が残したもの フィクサーと角栄とピーナッツ三島由紀夫は、なぜ死なねばならなかったのかメザシの土光さん 土光敏夫という生き方情と理 後藤田正晴という男がいた頃※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.0清和会(現・清和政策研究会)は、安倍晋三首相が後継者であることを自認する祖父・岸信介元首相の十日会(岸派)を源流とし、大蔵省主計局長出身の当時の自民党の領袖・福田赳夫を中心に一九七九年に結成された。 一九七二年、田中角栄と福田がポスト佐藤栄作を争う激しい派閥抗争いわゆる「角福戦争」が勃発した。闇将軍・田中角栄から竹下派(経世会)による政治的差配が、一九七〇年代前半から一九九〇年代にかけて長く続き、清和会は傍流に追いやられる。 しかし、二〇〇〇年に森喜朗が政権の座に就くと、その後、同派閥出身の小泉純一郎が圧倒的支持を集めて小泉旋風を巻き起こす。郵政民営化に象徴される「聖域なき小泉改革」のその実は、経世会の利権潰しにあった。その後継に安倍晋三、福田康夫が政権の座に就き、四代続けて総理を輩出し、自民党最大派閥となる。 民主党からの政権奪取を経て、人相までも祖父・岸信介に似てきたと言われる安倍首相が目指すのは、安保改定とその先にある自主憲法制定である。皮肉なことに、日米安保改定をなした岸元首相が退陣に追い込まれたのは、怒れる若者たちが安保改定阻止に胎動した「六〇年安保闘争」に起因する。半世紀以上の時を経て、国会前に集まる「怒れる若者たち」の空気と行動は酷似している。 五人の総理・総裁を輩出した現代の自民党最大派閥「清和会」の深層に、森喜朗、小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫の総理経験者をはじめ自民党最高幹部の証言インタビューから迫る、政界ノンフィクション!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 │特集│ IoTの競争優位 第1部 IoTで何が変わるか 次なる産業革命はすでに始まっている 「閉じたIoT」から「オープンなIoT」へ IoTの次に訪れるIoAの時代 第2部 戦略とビジネスモデル 「成果」を売る戦略:顧客価値からつくるビジネスモデル インダストリアル・インターネット:GEが描く未来 仕組みが先、ITは後 IoTは問題解決の手段にすぎない デジタルが生み出す5つのビジネスモデル 第3部 新たな価値創造 サービス・ドミナント・ロジック:IoT時代の新たな価値づくり カーシェアリングは顧客の視点から生まれた ベンチャーの機動力が大企業の力を引き出す ドイツはインダストリー4.0で何を目指すのか アナリティクス3.0 第4部 IoTが目指す世界 ハイアールアジアが取り組む家電革命 ウェアラブル・コンピューティングの可能性 IoTで組織の境界線は変わる
-
-ナショナリズムは悪なのか?第二次安倍政権の誕生以降、中国・韓国政府をはじめ、国内の「既成左翼」勢力からも、「アベは右翼だ」との批判が巻き起こっている。安保法制の国会論議におよぶ現在もそうした声が後を絶たない。だが本当にそうなのか? 「右傾化」批判は戦後七〇年を迎える今日まで、焦土と化した敗戦以降、一度の戦火も交えることなく平和国家として成熟した民主主義と市民社会を構築してきた努力を無に帰するものではないのか? 日本を「右傾化」批判する国々がどれだけ、戦争をしてきたのか! アジア情勢と世代論から読み解く間違いだらけの戦後イデオロギーの正体!
-
4.0
-
-更生を望んでも、許さない 自己責任社会の代償とは――? ヤクザや暴力団は街から一掃されたかに見えたが、「もっと悪い奴」がやって来た。 本当に安心で安全な社会はどうしたら実現できるのか。 黒いスーツにサングラス、肩で風切るヤクザは、もういない。しかし、今の「クリーンな社会」では、お年寄りが悪質な犯罪に巻き込まれ、若者が闇バイトに手を染めている。姿の見えない悪人が増加してしまったのだ。暴力団排除条例によって、反社会勢力は社会から一掃されたかに見えたが、不寛容な社会が、更生を望む人々の社会復帰を妨げている。彼らを裏社会に還流させ、表社会から悪人を排除し続けていれば、本当に「安心」が実現するのか。行き過ぎた自己責任社会を問いなおす。
-
4.0コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか? この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言! アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層! 「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」 (本文より) 農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス(兵站)を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。 国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ! (目次) はじめに 日本を襲った四つの衝撃 序 章 「令和のコメ騒動」序曲 第一章 減反政策という桎梏 第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領 第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン 第四章 農業は国防 第五章 日本農業 希望の灯 おわりに
-
4.0
-
3.5親や自分のお墓をどうする? 死後の手続きには何が必要なの? 国内外メディアから取材殺到! 第一人者がすべての悩みに答える!! 【推薦、続々!】 樋口恵子氏 「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける! みんなが安心できる本です」 高橋源一郎氏 「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって? どんなふうに? ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」 【本書のおもな内容】 ・ひとりで死んだらどうなるか? ・「骨」は歩いて墓に入れない ・家と墓はどう変化してきたか? ・死亡届の「届出人」は誰がなる? ・任意後見契約、いつすればいい? ・「友人に頼んである」では、ダメ ・連帯保証人以外の選択肢 ・配偶者喪失感を癒す墓参り ・親族に頼むか、第三者に頼むか ・明治時代に制定の法律が大活躍 「本書執筆の原点となったのは、「墓の継承問題」と「身寄りのない人の死後の担い手問題」であった。 ……本書では、市民団体の活動も踏まえつつ、転換期のダイナミズムを捉えていく。その中には、近年、新たに支持されている「樹木葬」について、同じ自然志向の墓が増えている西欧のイギリスや、東アジアの韓国と比較し、日本の墓における「自然の正体は何か」についても迫ることになる。 さらに、ますます顕著になる「人口減少社会」や「ひとり世帯が4割を超えていく社会」にあって、家族機能の弱体化を補う「身寄りのない人」へのサポートや、「事後福祉」の必要性を説明する」――「はじめに」より
-
5.0「難波橋筋に難波橋はない?」「道頓堀のゴールインマークは何代目?」大阪という街を知りつくした著者が、謎に満ちたその歴史、デザイン、建築……を縦横無尽に解説。貴重な図版も多数。 大阪という街はこういうふうにできている! これが大阪イズム! 「難波橋筋に難波橋はない?」 「道頓堀のゴールインマークは何代目?」 「食品サンプルは大阪発祥か?」 「誰が大阪城復興天守閣を発案したのか?」 「大阪に世界一のプールがあった?」 関西の都市政策や都市文化を研究し、大阪府と大阪市の特別顧問も務める、まさに大阪という街を知りつくした著書が、謎に満ちたその歴史、デザイン、建築……を縦横無尽に解説する。貴重な図版も多数掲載。
-
3.9いま日本で謎の死が増えている――。 有名人の「がん」による死が後を絶たない。 無意味な医療、効かないワクチンを政府・霞が関・医療界が国民に勧めるのはなぜか? 背景にある「医療ムラ」のおかしな現実を地域医療で奮闘する在野の医師が明らかにする! 目次 第一章「がん死亡数急増」の謎 第二章 謎の大量死 第三章 なぜ「突然死」が増えているのか 第四章 なぜ医師はワクチンを打たないのか 第五章 医療利権 第六章 メディアはなぜ騙されたのか 第七章 医療は本当に必要なのか 「はじめに」より そもそも私は医師ではありませんでした。大学は東京で経済学部に通っていたのです。その時は医師になろうとも思っていませんでした。それがヒョンなことから医師を志し、三〇歳を過ぎてようやく医師になりました。 そんな経歴ですのでそもそも医療業界に忖度する義理もありません。医師として勤務しながら自由に医療業界を見て回り、医療経済的な視点を基礎に総合的に俯瞰的に医療業界という特殊な世界を評価したいと常々思っていました。
-
-
-
3.9学力格差や体験格差が深刻化する日本の教育。そんな中、入試難易度や威信という点においてトップに君臨しつづける東京大学に進学するのはどんな人たちなのか。学歴エリートはどこからきてどこへ行くのか。中高一貫男子校出身者の多さや地方女性の少なさの実態、親の学歴、家庭環境や文化経験、卒業後の職業・年収・役職、結婚や子育て、そして社会意識や価値観まで。東大卒業生を対象に行われた大規模な独自調査のデータから明かされる、学歴エリートの生態と格差社会のリアル。 【独自調査から徹底検証! データから読みとく学歴エリートの実態】こんなに多い!中間一貫男子校出身者/幼少時の読者や文化経験は?/地方女性という困難/親の学歴はどう影響している?/就職・年収・役職/「東大女性は結婚できない」は本当?/学歴エリートの偏った社会意識……
-
3.7
-
4.1
-
3.7◎ベストセラー、待望の文庫化! ◎この本から「正義中毒」への問題提起が広まりました ◎「怒りに振り回されることが減った」「脳の仕組みから克服のヒントまでわかりやすい」「気持ちが楽になった」など、大反響! 誹謗中傷、炎上、不倫叩き、不謹慎狩り、ハラスメント… 「間違っている人を徹底的に罰しなければならない」 「自分と異なる意見は悪である」 世の中に渦巻く「許せない」感情の暴走は、 脳の構造が引き起こしていた! 人の脳は、裏切り者や社会のルールから外れた人など、 わかりやすい攻撃対象を見つけ、 罰することに快感を覚えるようにできています。 この快楽にはまってしまうと簡単には抜け出せなくなり、 罰する対象を常に探し求め、 決して人を許せないようになってしまいます。 著者は、この状態を正義に溺れてしまった中毒状態、 「正義中毒」と呼んでいます。 これは、脳に備わっている仕組みであるため、 誰しもが陥ってしまう可能性があるのです。 他人の過ちを糾弾し、 ひとときの快楽を得られたとしても、 日々誰かの言動にイライラし、 必要以上の怒りや憎しみを感じながら生きるのは、 苦しいことです。 また、軽い気持ちで発信したことが 誰かの心を深く傷つけ、 取り返しのつかない結果を 招いてしまうという悲しい事象は、 数えきれないほど起きています。 本書では、「人を許せない」という感情が どのように生まれるのか、 その発露の仕組みを 脳科学の観点から紐解いていきます。 「なぜ私は、私の脳は、許せないと思ってしまうのか」を 知ることにより、自分や自分と異なる他者を理解し、 心穏やかに生きるヒントを探っていきます。 ※本書は2020 年1 月に弊社より刊行された『人は、なぜ他人を許せないのか?』を改題し、加筆修正したものです。
-
4.0シリーズ累計13万部突破! もうガマンしない! [見た目][介護][夫][うつ][お金]の不安がぜ~んぶ吹き飛ぶ! ●第1章 60歳以降が女性の「本当の人生」 「本当の自分」が出しづらい日本/「第2の人生」のスタートに最適な60歳 女性こそ60歳から「やりたい放題」に生きられる/男性ホルモンが増大する更年期以降の女性 やる気が減退する「男性更年期」とは?/本音を言えない相手に嫌われても問題なし 60代は新しい友人をつくりやすい/年齢を気にせず「やりたいこと」を楽しもう 新しいことへの挑戦が脳を若返らせる/おしゃれに定年はない シニアのプチ整形は決して悪くない/見た目にこだわり続けたほうがいい理由とは? 「推し活」はおしゃれ心も刺激してくれる ●第2章 親や夫のしがらみにとらわれない 「第2の人生」を阻む介護問題/親孝行は親が元気なうちに 「介護施設に入れる=かわいそう」は思い込み/家族を介護するとストレスをためやすい 若い女性ばかりを見るフェミニスト/「親の介護は当たり前」という思い込み 定年後の夫ほどやっかいなものはない/第2の人生でも夫と一緒にいたいか? 二人だけの生活がもたらすストレス/楽しくないなら夫の世話なんてしなくていい 熟年離婚という決断があってもいい/法律は熟年離婚した女性の味方 シニアが働ける場所はいくらでもある/お金以外の目的が持てる仕事を選ぼう 仕事ができなくなっても心配はいらない/生活保護を受けるのは恥でも悪でもない セーフティネットは手をあげた人だけに機能する/60代以降の女性にはモテ期がやってくる ●第3章 無理に痩せると命が縮む!? 小太りくらいがもっとも長生きできる/太りすぎより痩せすぎのほうがリスクは高い 高齢者の「食べないダイエット」は命を縮める/栄養不足に悲鳴をあげるシニアの体 栄養不足の原因「フードファディズム」とは?/栄養不足解消にコンビニを活用しよう ラーメンほど体に良いものはない!?/高血糖より危険な低血糖 若い頃の1・2倍のたんぱく質を目標に ●第4章 医者の言いなりにならないで 医者の言うことにもウソがある!?/コレステロールを制限するメリットはない コレステロール不足で生じるデメリットとは?/がんやうつのリスクまで高まってしまう 悪玉コレステロールが嫌われる理由/多くの医者は「総合的に考える」習慣を持たない 専門分化はコロナ対策にも弊害をもたらした/高齢者はあっという間に薬漬けになる 薬漬け医療に拍車がかかる理由/まったく意味のない日本の健康診断 血圧や血糖値を下げるデメリットとは?/骨粗鬆症の薬でかえって骨折しやすくなる!? 薬の多量摂取で転倒リスクが倍に/薬の相談に乗らない医者は切り捨てよう ●第5章 知らないと怖い「うつ」のリスクとは? ●第6章 前頭葉の活性化で「第2の人生」を楽しむ ●第7章 「やりたい放題」生きるのが長寿の秘訣!
-
3.8話題の生成AI、どこまでなにができる? AIって結局、どんなしくみで動いているの? 最新テクノロジーで私たちの仕事は奪われる? AIで働き方や生活がどう変わるのか知りたい… ChatGPT、Bing、Claude、Midjourney、Stable Diffusion、Adobe Firefly、Google Bard…今世紀最大ともいえる変革を全世界にもたらした、生成AI。 この時代を生きるわたしたちにとって、人工知能をはじめとする最新テクノロジー、そしてそれに伴う技術革新は、ビジネス、社会生活、娯楽など、多様な側面で個々人の人生に影響を及ぼす存在となっています。 ただでさえ変化スピードが速く、情報のキャッチアップに苦戦するテクノロジー領域。数か月後には今の状況ががらりと変わってる可能性が非常に高い…そのような状況下で、今私たちは生きています。 ホットな話題でいえば、「クリエイターはみなAIに取って代わられるのでは?」「人間にしかできない価値創造ってなに?」など、これまで当たり前だと信じて疑わなかった「労働」「お金」「日常生活」などのパラダイムシフトが起こっています。 そんな今、まさにみなさんに手に取っていただきたいのがこの1冊です。 この時代を生きる多くの方が抱いているであろう不安や疑問、そして未来への興味関心に、本書はお応えします。 本書では、AI研究の第一人者である東京大学教授・内閣府AI戦略会議座長を務める松尾豊氏の研究室所属の今井翔太氏が、生成AIで激変する世界を大予測! 激動の時代を生きるすべての人にとって、これから到来する未来を生き抜くヒントと正しい技術的知識を提供します。 ※カバー画像が異なる場合があります。
-
3.3ChatGPTを代表格とする文章生成AI、ミッドジャーニーやステーブル・ディフュージョンに代表される画像生成AIなど、各ジャンルで高機能のAI技術が続々と誕生している今。 あらゆるビジネスパーソンはそれらの概要を理解し、使いこなせなければ生き残れない時代が到来しているといえます。 さらには、最新のテクノロジーツールを自在に操れたうえで、自らのプレゼンスを高めるために、「己の付加価値をどうビジネスで生み出すか」が問われ始めてもいます。 そんななか、多くの働く人の頭にあることは、「テクノロジーによって自分の仕事が奪われるのではないか」「共生していくにしても、太刀打ちできる気がしない…」という危機感でしょう。 数年前は、「どんなに技術が進歩しても、ヒトにしかできない仕事やクリエイティビティはある」と信じて疑わなかった人々でさえ、この現実を目の前にして「いよいよ本格的に多くの人が失業するのでは?」と考えを一転させているはずです。 本書は、かねてよりAIやメタバース、テクノロジーと雇用の関係性について、先見的な意見を述べてきた経済学者・井上氏が、この大変革期に「人工知能が私たちの雇用や日本経済に与える影響」についてやさしく語る1冊です。 ※カバー画像が異なる場合があります。
-
-
-
3.6
-
3.9
-
4.2
-
-日本のヤクザの資金源・シャブの韓国、台湾ルート、最凶地帯メキシコ・コロンビア、最大の生産地ゴールデン・トライアングルとアフガニスタン(ゴールデン・クレセント)、そして浸食される「病める巨大マーケット」アメリカーー。 禁断の世界麻薬マーケットの暗部と、世界の反社がどうつながっているのか? 伝説のマトリだから書ける「人類、欲望の裏面史」! ナルコスとは―― 「感覚を失わせる」という意味のギリシャ語のナルコン「narkoun」に由来する英語「narcotics」から派生したスラングで、海外ではドラッグとともに麻薬を意味するものとして認知されている。 第一章 アメリカの戦争に翻弄された戦後日本のナルコス汚染 第二章 マトリの私が体験した山口組のナルコスビジネス 第三章 日本に覚醒剤を供給してきた「闇の韓国・台湾ルート」 第四章 世界最凶のナルコス地帯「メキシコ・コロンビア」とアメリカの影 第五章 オウム、ロシア 薬物テロがもたらす惨劇 第六章 世界最大の麻薬地帯「ゴールデン・トライアングル」とその先にある新たな脅威
-
3.7「どこまで書く気やねん」(ガーシー) 社会に混乱と破壊をもたらしながら真の悪を斬る「闇の仕事人」か、あるいはただの時代の「あぶく」として消え去るのか―― ガーシーとその黒幕、そして相棒たち。日本に遺恨を持つ「手負いの者たち」の正体と本音とは。 日本の政治、経済、芸能、メディアの歪がつくりあげた爆弾男……彼らの本当の狙いとは何か、当事者本人が次々と実名で語る! 目次 すべてを失い、ドバイにやってきた男 ガーシーとの出会い 秘密のドバイ配信 急展開の示談成立 幻のインタビュー 「自分は悪党」 参院選出馬 FC2創業者 朝日新聞の事なかれ主義 元ネオヒルズ族 ガーシー議員の誕生 黒幕A 元大阪府警の動画制作者 元バンドマンの議員秘書 ワンピースと水滸伝 「悪党」と「正義」 嵐のバースデー モーニングルーティン 年商30億の男 王族をつなぐ元赤軍派 痛恨のドバイ総領事館事件 近親者の証言
-
4.0数々の大胆な改革を実行してきた異端児・橋下徹が初めて語る、 「誰に投票しても変わらない日本」を一新するオンリープラン。 僕は2008年から2015年まで、大阪府知事、大阪市長、そして大阪維新の会代表、日本維新の会の代表を務めました。一から政党を立ち上げ、政権交代可能な二大政党制をつくり上げようとがむしゃらに走ってきました。うまくいったこともあれば、失敗したこともある。そんな実体験を山ほど踏まえてきたことで、これまで誰もが語ったことのない「日本再起動」の具体的な方法が見えてきたのです(「はじめに」より)。この国の閉塞感を打破する、戦略的グランドデザイン! ※カバー画像が異なる場合があります。
-
3.8
-
3.8
-
4.4なぜ分裂したのか? どこまで分裂したのか? この分裂はどこに向かっているのか? 日本人の知らないアメリカのリアル! ・レイプより中絶のほうが重罪に ・南部の投票所が次々と消滅!? ・最高裁が自由と平等の国をちゃぶ台返し! ・武装集団は最高の愛国者? ・「痛み止め」で毎日100人が死亡! 銃、中絶、選挙、政教分離、最高裁……。「自由の国」アメリカはいつの間に、ここまで分裂してしまったのか? 超人気番組、BS朝日「町山智浩のアメリカの今を知るTV」待望の書籍化! 現地取材で集めた生の声が語る、知らないではすまされないアメリカのリアル。 ※カバー画像が異なる場合があります。
-
3.0「ネトウヨ」と罵られても私は挫けない! ネット全盛で「天下の朝日と池上彰」の権威は消滅 学校の「いじめ」はYouTube教育で解消できる さぁ、保守派の狼煙をあげよう!衝撃のノンフィクション(書下し) 私は、幼稚園児の頃にはリニアの運転手になりたいと思っていた。しかし、大人になると、アカデミズムの世界では嫌われる「保守系」の大学教員になってしまった。そしてYouTubeを馬鹿にしていた私が、いつのまにか教員を辞めて、なんとYouTube(岩田温チャンネル)を開局してしまった! それは何故か? YouTubeは全体主義と闘うための道具だと知ったからだ。そこで、私は大学教員を辞めて「独立型知識人」を目指して「YouTuber」になったのだ。 象牙の塔の中で、現実をいっさい知らない政治学者が政治を語るバカバカしさを変えよう。 序 章 「独立型知識人」を目指して「ユーチューバー」になってみた! 第一章 「夫唱婦随」「二人三脚」「二足の草鞋」でYouTube開始 第二章 YouTubeのリスクマネジメントを考えてみた 第三章 「テレサヨ」に「ネトウヨ」と罵られても私は挫けない 第四章 ネット全盛で終焉を迎える「朝日新聞」と「池上彰」の時代 第五章 学校の「いじめ」はYouTube教育で解消できる おわりに──保守派の狼煙をあげよう! 「ネトウヨ」と罵られても私は挫けない! ネット全盛で「天下の朝日と池上彰」の権威は消滅 学校の「いじめ」はYouTube教育で解消できる さぁ、保守派の狼煙をあげよう!衝撃のノンフィクション(書下し) 私は、幼稚園児の頃にはリニアの運転手になりたいと思っていた。しかし、大人になると、アカデミズムの世界では嫌われる「保守系」の大学教員になってしまった。そしてYouTubeを馬鹿にしていた私が、いつのまにか教員を辞めて、なんとYouTube(岩田温チャンネル)を開局してしまった! それは何故か? YouTubeは全体主義と闘うための道具だと知ったからだ。そこで、私は大学教員を辞めて「独立型知識人」を目指して「YouTuber」になったのだ。 象牙の塔の中で、現実をいっさい知らない政治学者が政治を語るバカバカしさを変えよう。 序 章 「独立型知識人」を目指して「ユーチューバー」になってみた! 第一章 「夫唱婦随」「二人三脚」「二足の草鞋」でYouTube開始 第二章 YouTubeのリスクマネジメントを考えてみた 第三章 「テレサヨ」に「ネトウヨ」と罵られても私は挫けない 第四章 ネット全盛で終焉を迎える「朝日新聞」と「池上彰」の時代 第五章 学校の「いじめ」はYouTube教育で解消できる おわりに──保守派の狼のろし 煙をあげよう!
-
3.5人口が急減する日本。なぜ出生率も幸福度も低いのか。日本、アメリカ、スウェーデンの子育て世代へのインタビュー調査と、国際比較データをあわせて分析することで、「規範」に縛られる日本の若い男女の姿が見えてきた。日本人は家族を大切にしているのか、男性はなぜ育児休業をとらないのか、職場にどんな問題があるのか、アメリカやスウェーデンに学べることは――。アメリカを代表する日本専門家による書き下ろし。
-
-韓国現代史「最大のタブー」に迫る! 韓国最大の歴史的タブーといわれる問題に迫った衝撃作です。 韓国では今、ベトナム戦争時の韓国軍による「ベトナム人虐殺事件」を解明しようとする動きが出ています。かつて、この事件について報じた韓国メディアは韓国軍の退役軍人らに襲撃されるなど、長くタブーとされてきた問題です。 経済的に強く結びついた韓国・ベトナム両政府は、この問題に蓋をして、真実を闇に葬り去ろうとしてきました。 筆者は、ベトナムにおいてこの事件の被害者や遺族の証言を得たことをきっかけに、ベトナム、韓国への取材を積み重ね、真実に迫ります。 戦争の悲劇、そして、政府や軍に翻弄される無辜の人々の姿。 日本の現代史を考える上でも貴重な作品です。 第28回小学館ノンフィクション大賞最終候補作。
-
3.0ポリティカル・コレクトネス(PC)をぶっ飛ばせ! 社会的常識より生物学的常識で人間の行動や社会を斬ります! 前著『ウエストがくびれた女は、男心をお見通し』は、櫻井よしこさんから絶賛されました。 「『なんとイヤらしいタイトルか』と思ってみたら著者は竹内久美子さん。彼女の記事は切り抜いて保存している私である。もしも私に目が三つあったら、3本の記事を同時に読みたいくらい面白い本だ」(「週刊新潮」2021・5・20号) 引き続き、竹内節炸裂の一冊がでました。 動物行動学で語る“男と女"、そして皇室や社会問題まで……。ぜひご一読ください。 ●ポリコレという名の妖怪が徘徊しているのでご注意を! ●「血液型性格」の違いをバカにすると結婚できない? ●「赤」を見たら、男は必ずコーフンする? ●自信満々の美女は早死にする…かも? ●彼氏のいる女ほど男の匂いに敏感になる! ●ハゲは女に嫌われるが胃がんには強い! ●河野太郎はニホンザルのリーダーを見習え! ●ポリコレに毒された日本の皇統・政界・論壇 ●どうした文藝春秋よ! 皇室を滅ぼしたいのか ●野村監督が連勝時にパンツを変えない合理性! ●精子を増やせ! アダルトビデオは少子化を救う! ●コロナ・伝染病に負けずに長生きする人生戦略とは ●男の猜疑心がつくりあげる処女信仰 ●「一夫多妻」があるなら「一妻多夫」もある? ●「不妊女性」のおかげで「子沢山」になる理由とは ●長身の阿部寛と大谷翔平の違いはアゴにあり ●ジャニーズ系羽生クンはネアンデルタール人の子孫だから人気者 ●なぜ二歳児は親を手こずらせるのか……
-
3.8
-
5.0歴史的な厄災が私たちに突き付けた「問い」とは? 医療崩壊、排外主義、コロナ貧困、自殺者の増加……。新型コロナウイルスの感染爆発は、全世界に社会的混乱と不安をもたらした。誰一人として先行きが見通せない状況で、私たちはパンデミックをどう生き抜くべきか。そして、先人たちはパンデミックとどう向き合ったのか。4人の論者が自身でセレクトした名著を持ち寄り、いま我々が直面している問題に即して解題し、感染症が暴いた人間の本質に迫る。大好評を博した「100分deパンデミック論」(2022年1月3日放送)の内容をさらに充実させた一冊! 【目次】 1 斎藤幸平:グローバル資本主義の限界(ジジェク『パンデミック』を読む) 2 小川公代:パンデミックとケア(ウルフ『ダロウェイ夫人』を読む) 3 栗原康:奴隷根性を打ち砕け!(大杉栄『大杉栄評論集』を読む) 4 高橋源一郎:露わになる社会の本質(サラマーゴ『白の闇』を読む)
-
-「失われた30年」を取り戻し、財政悪化、少子高齢化を最小限の痛みで乗り切り、 この国の未来を切り開くための具体的TODOリスト25! 人口減少、貧困化、低成長……現代日本の厳しい現実を打破するために 国家がやるべき「たったこれだけ」の改革 ・デジタル政府で適正かつ迅速な再分配を ・高齢者向けベーシックインカムを新設 ・膨張が続く医療財政を微調整で安定化 ・教育改革で人的資本を拡充 ・奇策「価値が減っていくデジタル通貨」を有効活用せよ 序 章 「日本病」の正体 「日本はオワコン」か/なぜ日本は変われないのか 第一章 日本を変える「三つの哲学」 コロナで傷ついた日本経済/「日米金利差」の悪夢/中国・韓国に追い越される/絶望の「高齢貧困」問題/介護難民があふれる「二〇二五年問題」/日本を蝕む「人口減少」「貧困化」「低成長」 第二章 デジタル政府で何ができるのか 高所得者ほど税金が安い?/「デジタル政府先進国」スウェーデンの凄さ/「働き方の多様化」に対応できない 第三章 本当に必要な社会保障改革 日本の不都合な真実「世代間格差」/「高齢者の四人に一人が貧困転落」の衝撃/基礎年金を「高齢者向けベーシックインカム」に/「老後二〇〇〇万円」に不可欠な「年金ダッシュボード」/「病床数が多いのに医療難民が発生した本当の理由/公的保険の「不透明なお金の流れ」 第四章 日本はまだまだ成長できる 地方活性化の切り札「地方庁」/「ケア・コンパクトシティ」構想/「情報銀行」で競争力を取り戻す/「データ証券化」で遅れを挽回する/教育格差を解消する「所得連動型ローン」 終 章 「財政の安定化」から逃げてはならない 「インフレで赤字解消」は本当か/「価値が減っていく通貨」が赤字を解消?/日本経済の真の実力
-
4.0







![[新装版]私はなぜ「中国」を捨てたのか](https://res.booklive.jp/20021177/001/thumbnail/S.jpg)