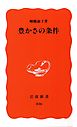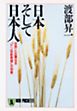社会学作品一覧
-
3.7
-
3.9
-
3.5
-
3.9このままでは、日本は没落してしまう! それほど日本の大学生は、海外の大学生と比べて勉強していません。 これは、東大・慶應・早稲田などの一流大学も例外ではありません。 実は日本では、大学生・大学の先生・企業の採用担当者のそれぞれが 自分の利益を最大化した結果として、「勉強しない大学生」が量産されています。 だから、「もっと頑張れ!」とか、「若いうちは勉強しなきゃダメだ!」といった 精神論では、問題は解決しません。 それぞれが自分の利益を最大化した結果、大学生が勉強する「システム」を作る。 本書では、そんな現実的な解決策を紹介します。 東大・慶應・早稲田など、9大学28学部の、「授業ミシュラン」付き。
-
3.0「ニコニコ動画」の登録者数、3185万人。その数もさることながら、おそらく、これほど“オジサンたち”の注目や支持を集めないまま、若年層に圧倒的な支持を受けて普及したサービスは存在しない。それゆえに、現在ビジネスの中心で活躍する「非ニコニコ世代」には、ニコニコ動画の何がすごいのかが見えづらい。 しかし10年後、消費・ビジネスの両面で中心となって活躍するのは、現在10代、20代の「ニコニコ世代」だ。彼らはなぜ、ニコニコ動画を熱狂的に支持するのか? その答えを知ることは、5年、10年後のビジネスを構築する上で非常に有益なはずだ。 本書では、日本最強のコンテンツ集団を支えるカルチャーを、ドワンゴ会長川上量生氏と同執行役員CCO横澤大輔氏への取材から克明に炙り出す。
-
3.0欧米では古くから「LGBT」という人たち向けに大きな消費市場が存在しています。 LGBTとは「レズビアン(女性に惹かれる女性)」、「ゲイ(男性に惹かれる男性)」、 「バイ・セクシャル(両性愛者)」、「トランスジェンダー(性同一性障害)」 の頭文字を取り、性的少数者の総称として使われる言葉です。 LGBTは人口の約5%の規模で存在するといわれています。 LGBTに関する商品やサービスの市場は、米国では77兆円、英国は7兆円にもなり、 企業は無視できず、情報感度が高く可処分所得も多いLGBTへの対応を誤ると 業績に大きく影響する可能性もあります。 そして、日本でも市場は5兆7000億円という調査結果もあります。 ようやく日本で注目され始めたLGBT市場とどう向き合うのか。 週刊ダイヤモンド(2012年7月14日号)では第二特集「国内市場5.7兆円 LGBT市場を攻略せよ!」を掲載。 本特集はレズビアン&ゲイカルチャー、LGBTコミュニティに貢献した人に贈られる 「Tokyo SuperStar Awards2012」のメディア賞を受賞しました。 この度、その特集を電子化しました。 雑誌のほかのコンテンツは含まれず、特集だけを電子化したため、お求めやすい価格となっています。 【掲載内容】 ・第1部 業績を左右する77兆円市場 米国企業が意識する“視線” ・第2部 10の事例から将来像を読み解く 日本におけるLGBT最新事情 日本IBM/シスコシステムズ/ゴールドマン・サックス/プルデンシャル生命保険/ ソフトバンク/ディズニーとパークハイアット/TOOT/LAUXES/アルファロメオ ・職場におけるカムアウト問題 周囲の理解と配慮は不可欠 ・Column 中年期を迎えるゲイ1期生 直面する「老後」という課題
-
4.0平成22年「くまもとサプライズ」キャラクターとして登場したくまモン。 商品売上は1年で293億円、熊本のブランド価値向上への貢献は計り知れない。 ゆるキャラ・くまモンを「売るキャラ」に育て上げたのは、PRもキャラクタービジネスも経験ゼロの、しがない地方公務員集団・チームくまモン。 くまモン失踪事件などの物語戦略、利用料フリーで経済を活性化させる楽市楽座戦略等々、公務員の常識を打ち破る自由な活動を展開し、自治体史上例のない成功を遂げた奇跡のプロジェクトの全貌。
-
3.4
-
4.0和より競争、平等より格差、長期的視点より目先の利益、情より公正さ、規制より自由、従業員より株主…… それらのアメリカ的価値観は、はたして日本人に適したものなのだろうか? 大多数の日本人を幸福にする社会にふさわしいのだろうか? グローバリゼーションのなか、改革という勇ましい掛け声によって、日本社会の根本がアメリカ文化で脅かされている。 その歪みが現在の金融危機によって露呈した今、精神的アメリカ離れの声も聞かれるものの、アメリカ追従の基本的な流れは変わらない。 しかし、アメリカ人とアメリカ社会にとって良い仕組みが、必ずしも日本人と日本社会にとっても良いとは限らない。 元通産官僚でもあった著者が、アメリカ人と日本人の価値観の違いを定性的定量的に示しつつ、21世紀の世界の幸福にも寄与する日本的価値観の再評価と、それに基づく社会の仕組みの再構築、そのための政策を大胆に提案する。 はたして、あなたはどう思うか? 反対意見も含めて、建設的かつ本質的な議論が本書から始まることを期待したい。
-
3.0
-
-
-
3.7
-
4.0【スポーツで、ビジネスで、世界での闘いは“ルール作り”からはじまる】 スキージャンプ、F1、柔道などの「国際スポーツ」で、半導体、自動車、大型二輪車などの「国際ビジネス」で、日本が勝つとルールを変えられるのはなぜ? 日本人と欧米人とのルールに対する考え方の違いとその理由を解き明かし、日本人がルール作りへ参画するにあたって持つべきプリンシプルと、失ってはいけない美徳を語る。 スポーツ、ビジネス、行政関係者など、さまざまな分野のプロフェッショナルから反響を呼び、「国際感覚が磨かれる」「日本的な考え方の良し悪しが分かる」と多数の読者からご好評をいただいた『ずるい!? なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか』(2009年12月刊行)に大幅加筆した増補改訂版。
-
-ITとは、「個人の志の実現」をかつてない速度と規模で加速してくれるツールです。 大きな資本を持たない個人でも実現可能なことが飛躍的に増えました。また、インターネット上の様々な「無料」のサービスにより、境遇による「チャンスの格差」が是正されつつあります。たとえ途上国に生まれたとしても、優秀な人材であれば瞬く間に世界トップレベルのステージに立つことができる。あるいは個人のアイデアが世界中にシェアされることで、従来では考えられないほど大きな影響力を及ぼすこともあります。 この新しい世界で、あなたにできることはなんでしょう? 自分を諦めるのはまだ早い。誰かに期待するより自分を信じて行動してみる。そんなタイミングが来ていると思います。【読了時間 約38分】
-
4.3
-
4.0
-
3.6
-
4.0
-
4.0
-
3.6
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1位は長野、2位は東京、3位は福井 その差はどこに? 地域の幸福を考えるのに、客観的な状況把握は欠かせない。 この本では55の指標を用意して、それに基づくランクづけをして、各県の状況を的確に把握する。 世界の幸福度ランキングも参照しつつ、これからの地域づくりに欠かせない基本的な視座を提供する。
-
3.9
-
3.9
-
4.2
-
3.5「管理者たち」が牛耳る官僚機構、「説明責任」なき行政システム――。日本社会を蝕む病根とはなにか? 政権交代や大震災を経てなお変わらない、日本社会の本質を突く衝撃作。書き下ろしを加えた最新改訂版!
-
4.5増税せずとも復興はできる! 未曾有の大震災により、市場経済も市民生活も大打撃を受けているにもかかわらず、政府は“復興”という名目で様々な増税政策を推し進めようとしている。政治家や経済評論家たちは毎日のように「財政難」を訴え、「日本は借金漬け」と繰り返す。果たしてそれは真実なのか? 「市民税10%減税の恒久化」「議員報酬半減の恒久化」をマニフェストに掲げる名古屋市長河村たかしは「増税せずとも復興できる」と断言する! 本当に増税は不要なのか? その根拠はどこにあるのか? 増税以外の選択肢で日本を再生させるには? その答えがここにある!
-
5.0フジテレビ系ドラマ「結婚しない」から考える 30代、40代女子が結婚できないほんとうの理由 人生には「結婚する」という選択肢と「結婚しない」という選択肢があります。が、プロポーズもされないのに、「結婚しない」とは言えません。それは「結婚できない」ということ。「いつか白馬の王子様が来るはず」「30代はモテ期がくるらしい」といった幻想を抱くのは危険です。白馬の王子様が永遠に現れませんし、モテ期なんて、とっくに終了しているからです。また、現在同棲中、あるいは長くつきあっている彼氏がいるという方も、まだプロポーズされていなければ要注意。なぜなら、つきあいが長くなればなるほど、結婚は遠のいていくからです。 では、結婚するには、どうしたらいいのでしょうか? 30代、40代の女性が結婚したいなら、短期決戦。効率的に結婚まで持ち込む必要があります。もう、20代の恋愛戦略は通じないことを肝に銘じてください。 本書では、2012年10~12月毎週木曜夜10時から放送されているフジテレビ系ドラマ「結婚しない」を例に、結婚するためにはどうしたらいいかをお教えします。
-
3.7副知事になった作家、3年に及ぶ格闘の記録 2007年6月、石原慎太郎・東京都知事からの「特命」は突然だった。 東京が国との間に抱える様々な問題を解決すべく、突破口となる役割を託された作家は、都庁の中で、何を見て何を感じ、どう動いてきたか。 作家の想像力が行政に与えた影響とは? 都庁で考えた「この国のゆくえ」とは? 就任から3年、永田町・霞が関との戦いから都職員との触れ合い、東京発の政策提言に至るまで、縦横無尽に綴る。 「東京都は昔から伏魔殿と呼ばれた。そんな形容詞でいかにもおどろおどろしく語るだけなら、何も説明したことにはならない」(プロローグより)
-
4.0
-
3.5
-
3.7
-
3.4
-
4.0元警察庁長官・國松孝次氏推薦!「もうこんな本は2冊と出ない」―― 闇夜を駆け、密かに忍び込み、大金をせしめて逃げる。「賊」とは、日本がまだ江戸と呼ばれた次代の暗闇を蝙蝠のごとく飛翔した大泥棒であり、いまはもう小説やテレビの中でしか存在しえない滅亡した人物たちだと思われてきた。自らを「賊」と呼び、「泥棒」「こそ泥」とは一線を画し、孤高の自尊心と賊として生涯を終える固い信念を抱き、江戸時代から伝承された技を磨き続けた賊が昭和から平成の時代にも実在していた。 自らを「賊」と呼び、ベテランの警察関係者からは「最後の賊ではないか」といわれ、「首相官邸でもやっただろう」とされる実在した伝説の大泥棒が、1988年から1993年の6年間の獄中で書き遺し、自ら「賊」とサインした6冊の「獄中日記」があった。 日記を譲り受けた犯罪学の権威がもう1人の大泥棒とともに読み解いた、「犯罪行動生態学」の研究にして「日本の裏の文化史」。誰も真摯に書き留めようとはしなかった、裏の世界に生きた者たちから表の世界に住む私たちへのメッセージ集。
-
3.9高い防波堤が津波の被害を大きくした?! 低タール・低ニコチンの「軽い」たばここそ、危険である。鉄道やバスの事故、医療事故、原発事故、津波と地震、温泉施設での火事など……事故が起きるたびに、関係者の責任が問われ、規制が強まり、対策がとられる。だが、果たして安全対策によって「安全・安心」は高まったと言えるのだろうか。事故や病気や失敗のリスクを減らすはずの対策や訓練が、往々にしてリスクを増やすことになるのはなぜなのか、考える。著者は、道路幅が広がればスピードを出す運転手がいるように、立派な防波堤を信頼したがために津波警報でも逃げなかった例をあげ、人間の心理を考えない安全対策では心もとないことに警鐘を発する。内外の豊富な実例をあげながら、人間の心理とリスク行動の謎に光を当て、いかにしてリスクと向き合うべきか、リスク・マネジメントの課題にまで踏みこんでいく。
-
4.0アメリカは穀物を覇権維持のための最有力の投資手段だとみなしている。「世界支配の近道は、世界の人々の胃袋を支配することである」がゆえに、農業大国でありながらもアメリカでは農業補助金が穀物農家に支出され続けている。 アメリカはすでに、トウモロコシ、大豆、小麦の世界3大穀物のすべてにおいて世界最大の輸出国となっている。世界2位の経済大国となった中国が覇権を狙うとき、アメリカは穀物価格値上げという牙をむく そのとき、先進国のなかでも食料自給率が極端に低い日本では、円安と穀物価格の上昇で、牛丼1杯が1000円になる日が来る ヘッジファンドマネージャーが、世界のマネーの動きをつぶさに見ながら、世界最大の穀物輸出国のアメリカが仕掛ける戦略を読み解き、来るべき危機を予見するとともに、日本のとるべき道を示唆した1冊。
-
3.0医師の世代間格差、収入格差、機会不平等の実態に迫ります! 医師不足や過酷な勤務状況下で、40代以下の疲弊した勤務医は、開業するにも不安がつきまとい、自分の子も医師になって欲しいという願望は強くありません。一方、年配の開業医はある程度時間に余裕があり、半数以上が男の子を医師にしたいと考えています。 このように年代や勤務形態で格差が広がりつつある中、医師たちはどのような医療システムが望ましいと考えているのでしょうか。財源の公私分担をどのようにすべきか、どんな医療技術を保険適用すべきか、限られた医療資源をどのような患者に優先すべきかなどのテーマをどのように考えているのでしょうか。 本書では、「開業医はやはり息子に跡を継がせたいのか」「開業医と勤務医はどれくらい年収が違うのか」「医局制度とはどんなものなのか」といった素朴な疑問をはじめ、過酷な勤務医の実態、地方の医師不足、医師自身の考え方の違いなどについてアンケート調査を行ったうえでデータに基づいて経済学的分析を行いました。日本の医師の置かれている実態や今後の医療制度を考えるうえで有用な1冊です。
-
4.0
-
-
-
3.9
-
-いま団塊の世代が、大量に“高齢者”の仲間入りをさせられている。定年後も成功した人の美談が盛んに取り上げられる一方で、「冗談じゃないよ。人生そんなに甘くないよ」と文句を言いたくなる人も多いのが現実。本書は、大ベストセラー『気くばりのすすめ』で一世を風靡した元NHKの国民的アナウンサーが、「老人は浪人である――74歳までは自分の『食い扶持』を稼ごう」「ローンでロンリーになるな――『定年までに何とかなるさ』は卒業」「その場で『忘れたこと』をメモに取れ――永遠に脳から消えてしまう前に」「他人の暮らしを羨むなかれ――明日も今日のようであれば十分」「いつも人の輪の中心に――『三角形の頂点』にいる年代は終わった」「遺言を結い言に――今の自分をあらしめて下さった方々に感謝」など、人生の有終の美を飾るための心構えを、独特の語り口を交えて当意即妙に語る。人生諦めは禁物である。定年を諦念としない秘訣とは何か?
-
3.5
-
3.0
-
3.7
-
3.8『20歳のときに知っておきたかったこと』の著者ティナ・シーリグによる待望の第2弾! 私たちはみな、自分自身の未来を発明する役割を担っています。 そして、発明の核心にあるのがクリエイティビティなのです。 ――<はじめにより> クリエイティビティというと、一握りの人だけがもっている特殊な才能だと誤解されやすいですが、実は誰もが内に秘めている力なのです。そしてその力は、解放されるのを待っているのです。 本書には、創造性を豊かにするためのさまざまなヒントが詰まっています。 言葉ひとつ、モノひとつ、アイデアひとつが、創造性を発揮する機会になることに目を見張るでしょう。 人生をチャンスに変えたいすべての人に贈る1冊。
-
4.3
-
3.8
-
4.1
-
3.4
-
4.0ニッポンの性と生を変える! 東京大学文学部在学中に、上野千鶴子ゼミに所属した著者・坂爪真吾氏は、新宿・歌舞伎町などで性風俗産業に関わる人々を取材。関わった人すべてを不幸にする風俗業界の惨状と問題点を明らかにした研究論文「機械仕掛けの『歌舞伎町の女王』」を発表した。 大学を卒業後、誰もが安全な性サービスを受けられるインフラ作り――新しい「性の公共」を求めて、障害者への射精介助を行なう非営利組織「ホワイトハンズ」を起業する。物議を醸した「処女童貞卒業合宿」などをめぐって警察や行政と激しいバトルを繰り広げながら、それでもなお精力的に活動を続ける理由とは何か――。 現在、全国18都道府県でケアサービスを提供している1981年生まれの著者が、その尋常ならざる情熱を初めて綴った奮闘記。
-
3.6
-
4.0
-
3.3
-
3.8世界は今、「お金とテクノロジー」に支配されきってしまった感がある。そんな中で、著者の省察では、「日本は、誰も経験したことがない時代」に突入した。どういうことかというと、まず、人口が減少を始めた。このことは、経済という観点から見れば、右肩上がりの経済成長は見込めないということを示し、したがって、日本としては、「経済成長のない未来」を考える必要に迫られた。また、その経済成長にともなって運営される筈の、民主主義ということにも、見直しをせざるを得なくなった。さらには、いつになったら解決するのかわからない、「フクシマ」という問題を抱え込んだ。これらはいずれも、「解き難い問題」であり、それを含んだ未来を我々はいかにして肯定的に考えてゆくべきなのか。これまでの著者の問題意識を総覧した、「平川克美への入門書」というべき一冊である。
-
4.0スウェーデン、フィンランドなど北欧諸国を抑えて「子どもの幸福度」1位に輝くオランダ。400年の交流がありながら、日本人はこの小国をあまり意識してこなかった。ところが震災を経て混迷を深めるいま、1000年に及ぶ洪水との死闘を乗り越え、欧州屈指の低失業率で経済的にも安定を続けるオランダが一躍注目されている。自由闊達な対話を認め、問題解決に向け協力し合う関係性豊かな社会。日本人にもっとも欠けている「不確実性に強い知的弾力性」はどこからくるのか? <オランダ的思考>の強さの秘密。【オランダから何を学べるか?】◎対話を続けるオランダの災害対策「デルタプラン」 ◎「ポルダー」が地域連携の文化を生み出した ◎オランダでワークシェアリングが成功した理由 ◎1時間当たりのGDPが世界でもっとも高いオランダ ◎世界最大の「農業ビジネス国」 ◎知の交流を促進する新しい「場」のサービス ◎「仕事=会社に来ること」ではない……
-
3.4
-
4.0
-
3.5
-
3.8一九七〇年代から現在に至るまで、巨大な潮流をつくってきた少女漫画の歴史を、<純粋少女>をキーワードに読み解く。とくに“二十四年組”を中心に花開いた<少女漫画>の魅力とその高度な達成について――大島弓子の『バナナブレッドのプディング』、萩尾望都の『トーマの心臓』、そして岡崎京子の『ヘルタースケルター』を主な手がかりに――戦後文化論として読み解く。少女漫画のヒロインたちが抱える繊細な“怯え”は、大人の論理が強要する安易な成熟の拒否であり、無意識の抵抗だったのではないか。今日に至るまで連綿と受け継がれてきた“震え”や“怯え”の伝達装置としての<純粋少女>たちに、高度消費社会の諸矛盾を、戦後民主主義の限界を乗りこえる可能性をみる。「少女漫画の名作一覧」も収録。
-
-本書では、日本で起きた、もうひとつの幕末を取り上げてみました。鎌倉幕府の幕末です。江戸時代の幕末維新は「点と線」を上下左右に結んで動き立体的な改革劇でした。点と点を結ぶ線を引いたり、引き直したりして倒幕運動を推進していきました。一方で時代はさかのぼりますが、鎌倉幕府を討った倒幕運動は「面の関係」で読み取れます。鎌倉幕府の幕末にあるのは、面の世界です。改革という面をスライドさせたり、剥がしたりの倒幕運動でした。そこには危うさが見えてくるのです。そういった「面の関係」の動きが、実は、現代の日本にもあるのではないか、と。面の表を一皮むけば、ガラリと姿を変えた日本の底が見え隠れするような、そんなスリリングなストーリーが、内側に隠されているかもしれません。鎌倉幕府にあった倒幕運動に、私たちは、二十一世紀の日本と奇妙な符号を読み取ることができます。
-
-
-
-
-
4.2近年、世界のオンラインゲーマーのコミュニティは数億人に達し、莫大な時間と労力がヴァーチャルな世界で費やされている。これは現実に不満を持つ人々による「大脱出」にほかならない。 なぜ人々は「ゲーム」に惹かれるのか? それは現実があまりに不完全なせいだ。現実においては、ルールやゴールがわかりづらく、成功への希望は膨らまず、人々のやる気はますますそがれていく。 そんな現実を修復すべく、ゲームデザイナーの著者は、「ゲーム」のポジティブな利用と最先端ゲームデザイン技術の現実への応用を説く。コミュニケーション、教育、政治、環境破壊、資源枯渇などの諸問題は、「ゲーム」の手法で解決できるのだ
-
-「……歴史的に確定した定義を多くの人が理解しないために問題化してしまうニュースもある。さまざまに表出する「表現の自由」に対する制限は「表現の自由を保障してこそ民主主義は成熟する」という長い間かかって確立した常識が忘れがちになっているから幅をきかせる。「国家の役割とは国民の生命と財産を守ることだ」という不朽の定義さえ投げ捨てられると外国で人質になった国民に「自己責任」を問うような逆立ちした論理がまかり通る。」(「はじめに」より)ニュースの裏にある歴史を知ることで、今ある情報についての理解がふくらむ。ニュースを見る目を10倍深めるための、元新聞記者がおくる一冊。
-
3.7
-
-行政でもない、企業でもない第三の勢力・NPO。非営利の市民活動による社会的起業、コミュニティ再建、共生・参加型まちづくり、新事業・雇用創出などのノウハウとマネジメント戦略を、先駆的な米国の事例とともに紹介する。
-
-労働時間の短縮や長寿化によって、不況下でも人びとの余暇は増大している。 この自由時間を使って、個人と地域の知的資産の増強を図り、みんなで“いい世の中”ができないだろうか。 そのための自分おこし・人づくりのノウハウと戦略・ビジョンを探る。
-
3.3
-
3.5
-
-
-
3.5
-
3.8
-
-
-
-
-
3.9「おにぎり食べたい」――日記にそう書き残して孤独死した男性は、数カ月前まで「生活保護」の対象者だった。北九州市で続発する餓死事件。役所が繰り広げる水際作戦。一方で、「怠け者が生活保護を食い物にしている」という報道も後を絶たない。明らかにされるワーキングプアとの根深い関係――。「生活保護年収四〇〇万円相当(四人世帯)>ワーキングプア」という衝撃の事実からあぶり出される真実とは? 三五〇〇件以上の相談に応じてきた専門家が、生活保護の現場から格差是正の処方箋を示す。◎若者に広がる貧困、◎自業自得、自己責任?◎九八年に社会が変わった、◎不正受給額は計72億円、◎水際作戦と受給者バッシング、◎若者が生活保護を受ける、◎額面20万円のサラリーマンと同じ、◎人生何度でもやり直しができる、◎プチ生活保護のすすめ、◎放置したときのコスト、◎入りやすく出やすい制度へ、◎支援の芽を育てるために
-
3.6なぜ日本人は戦前を否定するのか? なぜ「歴史」を社会科で教えるのか? 日本人に天皇は必要なのか? ――六〇年前の敗戦をきっかけに、明治も江戸も古代までも全否定する奇妙な歴史観が、この国を支配してきた。しかし、近現代世界はいま大きく変動している。戦争の真実を物語る史料も公開されはじめた。「この国のかたち」を描くために、私たちはいま何をすべきか。まず第一に、日本を考えるにあたってすべての「結節点」である「あの戦争」の意味を考えないわけにはゆかない。次に、「終戦」という嘘、「自主憲法」という嘘、「憲法九条が平和を守った」という嘘、「戦後の民主化が高度成長を促した」という嘘、「国際化」という嘘……積み重ねられた「戦後の嘘」を打ち捨てなければならない。さらに、「天皇」と「心」を日本文明の核心として捉えることで、日本人のアイデンティティを、真正面から問いなおさなければならないのである。