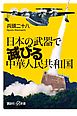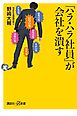社会・政治作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
3.7
-
3.0
-
4.0
-
-
-
3.8「日本について学べば学ぶほど、 『アメリカの見方がおかしい』と思うようになった」 なぜ日本だけが謝罪を求められるのか? 先の大戦において、米航空母艦の乗組員であった祖父から 「国の為に自分の命を捧げる日本の特攻隊員の潔さ」を 教えられたのをきっかけに日本研究の道を志した 気鋭のアメリカ人歴史学者が、偏見に満ちた「対日歴史観」を正す!
-
3.0
-
3.5
-
3.8
-
-
-
-電力自由化をきっかけに各家庭へのスマートメーター導入が開始され、電力産業、電力関連ビジネスは一気にデジタル化の道を歩み始めました。本書では、IoTとも密接な関係を持つ電力とエネルギーの未来を、ワイヤレス給電、EV(電気自動車)、ドローン、ビッグデータ、蓄電池、エネルギーハーベスティング、VPPといった最新テクノロジーの話題とからめながら解説します。また、近い将来「電気をシェアする時代」が訪れる、という著者独自の未来予測をもとに、これからの時代に求められる新しい価値観と発想のヒントを与えてくれます。
-
-東京オリンピック、築地市場移転問題、東京都知事選、小池都知事の登場、都議会など、昨今、東京都の行政にかかわるニュースは枚挙に暇がありません。 しかしその一方で、我々はあまりにも東京の行政のことを理解していません。そもそも、14兆円という国家規模並みの予算を持ちながら、誰が決定にOKを出し、誰がその執行を行っているのかもほとんど知られていません。 東京の行政とはどういったしくみで行われていて、それを執り行っている都知事と議決する議会の権限はどうなっているのでしょうか? 本書では、都庁、都議会、都知事も含め、行政を中心に「東京」について基本からわかりやすく解説しながら、現状について知識を得ることができるとともに、今後の都政のあり方と関わり方について、学んでもらうことができます。
-
-ロッキード事件発覚から40年。異常なほど角さん人気が盛り上がり、角さんの言動を紹介する「角栄本」が相次いで出版されています。 角さんは日中国交正常化交渉を成し遂げるなど「功」も多い政治家です。しかし、角栄本のほとんどは角さんの虚像と神話に基づくものが多く、人心を惑わすものだということが私の意見です。 長年、角さんの問題に密着取材したマスコミ記者として、角さんの実像と「角栄本」の正しい読み方のお手伝いをしたいと思います。 (まえがきより抜粋)
-
3.0京都府北部、人口35,000弱の地方都市が〈地方創生〉の観点から注目されている。 『里山資本主義』の藻谷浩介氏も絶賛する、その理由とは? 綾部の魅力、潜在力を、『1』行政の取り組み(水源の里条例や世界連邦都市宣言など)『2』綾部発祥、グンゼの創業者・波多野鶴吉の人づくり『3』やはり綾部発祥、日東精工の地域貢献(絆経営)4新しいライフスタイル「半農半X」といった視点から取り上げ、地方創生――人づくり、モノづくり、街づくり――という点で、綾部から学べるものを紹介する。 『里山資本主義』や『デフレの正体』などのベストセラーを著した藻谷浩介氏も、「綾部は世界のどこに出しても胸を張れる全国でも数少ない街。ここに日本と世界の先端があります」と推薦している。人口35,000にも満たない小さな都市が、なぜここまで元気なのか――3世帯四人しか暮らさない集落に年間3,000人以上が訪れる理由。四つある綾部市の第三セクターすべてが10年以上黒字基調の健全経営、グンゼと日東精工、東証一部上場企業がなぜ今も綾部に本社をおいているのか――といったことを掘り下げていく。
-
4.3トランプ、習近平、プーチン…… 見えざる力を暴く、 佐藤優の集大成! 大統領選後のアメリカはどうなるか? イギリス離脱後のEUのゆくえは? プーチンのユーラシア主義の本質とは? 英米からロシア、中東から中国まで。新旧政治家の比較考察から、各国に特有の論理を読み解く歴史的アプローチ。地理をふまえて各国の戦略に迫るアプローチ。双方の合わせ技で国際情勢の本質を一気に把握する。「分析家・佐藤優」の集大成! [内容] 序 章 国際情勢への二つのアプローチ 第一章 英米を動かす掟─「トランプ現象」と「英国EU離脱」の共通点 第二章 ドイツを動かす掟─「生存圏」から「EU帝国」へ 第三章 ロシアを動かす掟─スターリンとプーチンの「ユーラシア主義」 第四章 中東を動かす掟─「サイクス・ピコ協定」から「IS」まで 第五章 中国を動かす掟─「海」と「陸」の二兎を追えるか 終 章 「歴史×地理」で考える日本の課題
-
3.5日本の「戦後70年」とは平和の時代であった。しかし今日「戦後レジームからの脱却」へ歩を進める政権によって、かつてないほど不安で希望の見えない時代が迫りつつある。果たして私たちに「戦後80年」は到来するのだろうか。比較敗戦論、論壇と出版、集団的自衛権と憲法、歴史学による戦前・戦後論、少子化問題、中央銀行の破綻……。日本の知の最前線に立つ講師陣が「戦後とは何か」を論じつつ、この先10年、日本が歩むべき道を提言する。朝日新聞社と集英社による連続講座シリーズ「本と新聞の大学」第4期の書籍化である。【目次】まえがき 姜尚中/第一回 基調講演 一色 清×姜尚中/第二回 比較敗戦論 敗戦国の物語について 内田 樹/第三回 本と新聞と大学は生き残れるか 東 浩紀/第四回 集団的自衛権問題とは何だったのか 憲法学からの分析 木村草太/第五回 戦後が戦前に転じるとき 顧みて明日を考える 山室信一/第六回 戦後日本の下半身 そして子どもが生まれなくなった 上野千鶴子/第七回 この国の財政・経済のこれから 河村小百合/第八回 総括講演 姜尚中×一色 清/あとがき 一色 清
-
3.52016年7月の10日に投開票された第24回参議院議員通常選挙で、 有権者は誕生したばかりの民進党に厳しい審判をくだした。 野党(民進、共産、社民、生活)が鳥越俊太郎氏を推薦した東京都知事選の結果など最新情報を交えながら、 国民の期待を裏切り続けるツッコミどころ満載の新党を断罪する。 また、民進党のだらしなさによってもたらされた「自民党1強」体制にも、ひとりの経営者として、 日本を愛する者として、伝説の保守政治家・赤尾敏の姪として物申す。 【著者情報】 一円用円形など、日本品質の製品を作り続けるアカオアルミ株式会社の代表取締役。 元衆議院議員、大日本愛国党初代総裁を務め、日本を代表する保守政治家として今なお高い人気を誇る赤尾敏の姪。 共著に『国防女子が行く』(ビジネス社)があり、ひとりの国民として、また経営者として、 “日本人らしさ”を大切にしている。
-
5.0
-
5.0「中国は謀略をもって、経済・文化・資源・政治・メディアなど多面的にジワジワと 日本と台湾に侵出しているのを台湾国民の多くが気づいている。 一方、日本国民の大半はその迫りくる危機に気づいていないのが実情なのだ」(本文より)。 前著『台湾人から見た日本と韓国、病んでいるのはどっち?』において、 中立的な目線で日韓を7つの分野から徹底比較して大きな話題を呼んだ李 久惟(リ・ジョーウェイ)氏。 15ヶ国語以上を操り、世界中を飛び回り、さまざまな分野で語学講師・セミナー講師として活躍するなど、 積極的に国際交流や言論活動を行ってきた台湾人著者が、 本書では経済、政治、軍事、領土、資源、社会、文化・思想・宗教、歴史、メディア・言論、教育など、 さまざまな分野から、中国の真の姿と狙いをより浮かび上がらせていく。
-
4.3
-
4.0
-
4.1
-
4.7
-
3.8「NO」しか言わないオキナワのままでいいのか? 誤解だらけの基地問題、政権交代とトモダチ作戦の裏側、偏向するメディア――政治的思惑と感情論ばかりが支配する空気に抗い、事実に基づいて日・米・沖のあるべき姿を探究し続けた二十年。歴史研究者として、海兵隊の政治顧問として、情熱を傾けてきた著者が沖縄問題の虚実を解き明かす。沖縄も政府も米軍も、傾聴すべき直言が満載の刺激的論考。
-
4.015ヶ国語以上を操る台湾人・李久惟(リ ジョーウェイ)氏。 李氏は東京外国語大学を卒業後、世界中を飛び回り、 さまざまな分野で語学講師・セミナー講師として活躍するなど、 積極的に国際交流や言論活動を行なってきた。 また通訳としても台湾新幹線プロジェクト、野球の国際大会(オリンピック予選、WBC)、 サッカー国際大会(アジア予選、東アジア選手権)などで輝かしい実績を残している。 そんなグローバルな活動を展開する李氏には、緊張状態が続く日本と韓国の関係はどのように映っているのか? 「歴史」「政治」「文化」「社会」「教育」「経済」「スポーツ」という7つの分野から、 多角的かつ客観的に綴ってもらった一冊。 台湾人から見て、病んでいるのは日本と韓国、果たしてどっち?
-
3.0「日本、ヤバイんじゃね? そう思った時に、何ができるかと考えたら、漫画で周知だった。 日本が好きで、ちっぽけなイチ日本人として何かしたくて、漫画を描いている。 これからも書いていくだろう」(本文より) --2015年5月15日、富田安紀子が世に送り出した漫画『日之丸街宣女子』は発売前から大きな話題となり、 ベストセラーへの階段を一気に駆け上がる。 しかしその裏では、著書とその周辺への過剰なまでの“弾圧”が行われていた! ……それでも「日本が好きでなぜ悪い?」。 初の新書で著者が当たり前のことを当たり前に綴る!! 第1章…『日之丸街宣女子』にまつわるエトセトラ 第2章…『日之丸街宣女子』発売日周辺一カ月記 第3章…漫画家という職業 第4章…私と「新保守」のヒストリー 第5章…私が漫画家としてできること 第6章…拝啓、『日之丸街宣女子』から思いを込めて
-
3.8
-
3.0東京裁判から、中国、韓国、靖国問題まで――。 左派から保守派へ大転換した元・日本共産党NO.4である著者が、 「日本共産党」を軸に近現代史をひもとく。 【プロフィール】 筆坂秀世(ふでさか ひでよ) 1948年、兵庫県生まれ。高校卒業後、三和銀行に入行。 18歳で日本共産党に入党、25歳で銀行を退職し、専従活動家となる。 国会議員秘書を経て参議院議員に当選。 共産党ナンバー4の政策委員長を務めるとともに、党屈指の論客として活躍。 2003年に議員辞職。05年に離党後、政治評論家として活動。 主な著書に『日本共産党』(新潮新書)、『論戦力』(祥伝社新書)など。
-
4.3乗り物の側から見た移動でなく、人の側から、人と環境に配慮した移動。今、富山ではこうした考え方にもとづく、公共交通を軸にしたまちづくりが着々と進められている。日本列島の一地方に過ぎないこの地で、世界的な潮流となっている先進的公共交通政策がなぜ、どのように可能になっているのか。本書は、地元富山の行政機関や多数の交通関係者に取材し、その秘密を解き明かす。富山の試みは、果たして例外なのだろうか。 森口将之(もりぐちまさゆき) モビリティジャーナリスト、モータージャーナリスト。株式会社モビリシティ代表取締役。1962年東京都生まれ。早稲田大学卒業後、出版社編集部を経て、1993年に独立。国内外の交通事情を精力的に取材・視察し、地球環境や高齢化社会等、問題が山積した現代社会における理想のモビリティの探求・提案を続けている。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。日本デザイン機構理事。日本自動車ジャーナリスト協会会員、日仏メディア交流協会会員。著作に「最速伝説―20世紀の挑戦者たち」(交通新聞社)、「パリ流環境社会への挑戦」(鹿島出版会)、「マイナスのデザイン」(共著・ライフデザインブックス)ほか。 ※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。
-
-世界最高の軍事戦略家であるクラウゼヴィッツ。彼が遺した不朽の名著である『戦争論』は、非常に“哲学的”で難解なことで知られる。しかし、それは後世の読者が、クラウゼヴィッツの主義主張の背後にたぎり立つ“ロマン主義的な情熱”を汲み取ることに失敗しているからなのだ――。クラウゼヴィッツは、なぜ終始一貫「精神」の威力を強調したのか? なぜ政治の変革を訴えたのか? フランス革命後のナポレオン戦争で、完膚なきまでに叩きのめされた祖国プロイセンを蘇らせるべく、稀代の戦略家が伝えたかった本当の核心を、現代日本の軍学者が“超訳”で読み解く。「軍事的天才」「戦略の要素としての精神力」「マニュアルはどこまで可能か?」「熟慮と断行のけじめ」「今日では決戦は強要しうる」「国民にガッツがあると、外国も助けてくれる」「時代ごとに制約があり、可能性がある」――決断とリーダーシップの神髄がここにある! 『[新訳]戦争論』を改題。
-
-おそれるな、つかいこなせ! ――安倍政権下で2015年10月まで社会保障と税一体改革担当副大臣をつとめた西村康稔衆議院議員が、 マイナンバー法の立案・制度の導入等を担当した経験から、マイナンバーをどこよりもわかりやすく解説。 制度の概要からマイナンバー・マイポータルの活用法、 今後のIT展開と東京オリンピックへ向けての可能性、 電子政府の未来まで、マイナンバーを最大限つかいこなす方法を論じた一冊。 1 番号とは何か 2 マイナンバー制度の概要 3 小さく生んで、大きく育てる 4 日本のIT戦略 5 マイナンバー制度と電子政府が日本を変える 6 東京オリンピックに向けて
-
4.1役所や学校、地域も見逃していた 虐待の衝撃的事実! 18歳まで自宅監禁されていた少女、車内に放置されミイラ化していた男の子─。虐待、貧困、保護者の精神疾患等によって監禁や路上・車上生活を余儀なくされ社会から「消えた」子どもたち。全国初の大規模アンケート調査で明らかになった千人超の実態を伝えると共に、当事者23人の証言から悲劇を防ぐ方途を探る。2014年12月に放送され大きな反響を呼んだ番組取材をもとに、大幅に加筆。 [内容] はじめに──なぜ「消えた子どもたち」は放置されるのか 第一章 一八歳まで監禁されていた少女 第二章 「消えた子ども」一〇〇〇人超の衝撃 第三章 貧困のせいで子どもがホームレス、犯罪に 第四章 精神疾患の親を世話して 第五章 消えた子どもたちの「その後」 第六章 自ら命を絶った「元少女」 第七章 「消えた子ども」の親の告白 エピローグ もう一度、前を向いて おわりに──「消えていた」子どもたちが問いかけたもの 虐待が疑われる事案の通報先
-
3.5
-
-私たちが抱く、「なんで 原発再稼働なの?」。Q&Aの元祖OKWAVE社と連携し、web上の『みんなのQ&A』で一般のユーザーの方から総数116の『疑問・質問』を出していただき、10の『素朴な疑問』にまとめ、直接それを国・行政の担当者にぶつけました。そして「国が再稼働という『結論』に至った理由」を明らかにしたのが本書なのです。 過去、日本が原発導入に至った経緯から海外での原発事故、その後の福島第1原発の事故で行政はどう変わったのか。行政は電力事業者と癒着しているのではないか。地元に対策費としてお金をばら撒いているのではないか。さらに、原発ゼロで持ち堪えているのに、どうして再稼働するのか、今後の電力供給ビジョンを含め回答してもらいました。そして、廃炉費用を加算した原発の発電コストは本当に安いのか。規制員会の安全基準は海外に比べ、世界で最も厳しいものなのか。原発依存度を限りなく削減する具体策はどうなっているのか。廃棄物処理はどうするのか。私たちが抱えている疑問とそれに対しての回答をまとめました。 日本には商業用原子炉が46基あります。新規制基準への適合性確認を15原発25基が申請し、すでに九州電力川内原発1号機と2号機は運転を再開しています。今後、各地で再稼働に向けた動きが出てくることが予測されます。賛否を考える際に、「再稼働する理由」を知ることはとても重要なのではないでしょうか。
-
5.0田母神俊雄、待望の新党「太陽の党」結成! どのような日本を目指すのか、自身の考えを語りつくした1冊。 さらに既存の党や政治家について鋭く切り込みながら、 自身の今後の政治活動の指針を明らかにします。
-
-盤石なのか、そうでないのか? 第一人者が冷静に分析 中国の伝統的思想を踏まえ、独特の政治体制から現指導者の人脈まで、第一人者が持てる知見を総動員して中国共産党「支配の構造」を分析。経済の急減速、高まる民衆の批判、止まない腐敗・汚職など、共産党に吹くかつてない逆風を、習近平はいかに克服しようとしているのか。安易な中国崩壊論、民主化楽観論を排し、巨大国家の行く末を冷静かつ堅実に見通す著者渾身の一冊。 [内容] 序 章 習近平の危惧 第一章 なぜ中国人は共産党を支持するのか 第二章 中国政治を動かす「人脈」の実態 第三章 揺れる中国──変わる社会と変わりにくい体制 第四章 「中国の夢」と「新常態」のジレンマ 第五章 「中国型民主主義」の可能性
-
4.0現場から、渾身の提言! 憲法第9条の下、専守防衛の軍として戦後、一発も実戦で撃たなかった自衛隊。集団的自衛権行使と国連PKOでの武器使用拡大路線で、自衛隊の役割はどう変わるのか。日米同盟と憲法のはざまで、悩みながら海外派兵の実務を仕切ってきた元防衛官僚が、発足以来60年の矛盾に向き合い、拙速な法改正に異を唱える。どんな大義のために殺し殺されるリスクを負わせるのか、国民の覚悟を問う一書。 [内容] 第一章 自衛隊を取り巻く矛盾 1 自衛隊と「国民」をつなぐ 2 変わりゆく時代のなかで 3 矛盾の限界 第二章 鼎談・前線からの問題提起 1 政治の論理と現場の乖離 2 好戦的に変わったPKOと、自衛隊員のリスク 3 憲法と集団的自衛権 4 誰が責任をとるのか 5 日本はどう貢献するのか 第三章 いまこそ自衛隊から平和を問い直す 1 国民の期待と自衛隊内の不満 2 リスクを理解しているか 3 日米同盟を考え直す 4 イラク派遣の成果 5 海外派遣の課題 6 政治と自衛隊、憲法の論点
-
3.0
-
3.8反米/親米を超えて変わりゆく大国の素顔をとらえる 「貧困大国」等々のアメリカ衰退論は、どこまで的を射ているのか。これからの対アジア政策、中東政策、日米関係はどうなるのか。そして“ポストオバマ”のアメリカはどこへ向かうのか――。戦後70年を機に、気鋭の文化人類学者が、「歴史認識」「政治」「社会」「外交」から、アメリカ社会の実相とダイナミズムを鮮やかに描きだす。 ※写真の一部をカラーで収載しています。 [内容] 第一章 アメリカの「歴史認識」──日本像から見る (1) 不可解な日本の「保守」 (2) なぜ右派が警戒されるのか (3) 更新される「歴史認識」 (4) 「ディスカウント・ジャパン」への反応 第二章 アメリカの「戦後」──保守とリベラルの相克 (1) 「自由社会の盟主」はいかにつくられたか (2) 「黄金の五〇年代」を起点とするアメリカ現代史 第三章 戦後社会の変質──自由大国のジレンマ (1) 「個人化」する社会 (2) 保守化する経済、拡大する格差 (3) 超資本主義化する政治 (4) 新自由主義的「自治」の加速 (5) 社会のリベラル化 第四章 オバマ外交の現実──「世界の警察官」からの退却 (1) アメリカ再建への要請 (2) アジアへの「リバランス」 (3) 転機を迎える日米関係 (4) 中東をめぐる混迷 第五章 「アメリカの世紀」は終わったのか──親米/反米を超えて (1) アメリカ衰退論を検証する (2) アメリカの自画像 (3) アメリカへのまなざし
-
3.7
-
3.5《もはや中国は堕ちるところまで堕ちた!》●数万人の「法輪功学習者」の臓器を生きたまま摘出●「厳打」による百万人以上の逮捕と二万人以上の処刑●金を払わなければ強制的に堕胎させる「一人っ子政策」●内モンゴルの草原を砂漠に変えた徹底的な環境破壊・「泥棒を乗せて走っている」が大げさではない列車・毎日15時間労働、月当150円、休めば拷問…「馬三家労働教養所」での迫害・日本へ輸出される「割り箸」で患部を掻く感染症の作業者・1962年から公然と行われてきた「身体の再利用」「革命化処理」・世界の臓器移植の85%を占める中国では、いまや人間が「輸出品」・「築七年の家」半分以上、砂漠に埋もれている・人の思想を「政治審査」で「赤」「黒」「白」と色分けする・偽政治、偽裁判、偽食品、偽結婚…「偽物」なら何でも揃う国・中共は「無産階級」ではなく、世界有数の「資産階級」
-
-平成25年8月4日に、自治体法務検定の第3回「基本法務」及び第4回「政策法務」の一般受検を実施。本書は、この一般受検で出題された「基本法務」及び「政策法務」の問題とその解答及び解説を完全収録した、自冶体法務検定委員会公認の唯一の問題集である。
-
-平成24年7月29日に、自治体法務検定の第2回「基本法務」及び第3回「政策法務」の一般受検を実施。本書は、この一般受検で出題された「基本法務」及び「政策法務」の問題とその解答及び解説を完全収録した、自冶体法務検定委員会公認の唯一の問題集である。
-
-平成23年7月10日に、自治体法務検定の第1回「基本法務」及び第2回「政策法務」の一般受検を実施。本書は、この一般受検で出題された「基本法務」及び「政策法務」の問題とその解答及び解説を完全収録した、自冶体法務検定委員会公認の唯一の問題集である。
-
5.0小泉ポピュリズム政治の限界が露呈しはじめた。漂流する日本の舵取りは、いったい誰に託すべきか。二大政党制、政界再編へのシナリオはいかに。戦後政治の現場をつぶさに見てきた稀代の政治家が、議員バッジをはずしてもなお、国を憂い、真に自立した国家のヴィジョンを語る。著者は、戦前と今日の政治状況が奇妙に符合していることを指摘する。1936年の「二・二六事件」から大東亜戦争で敗戦を迎えるまでの間と、90年代のバブル崩壊後の10年あまりのことである。ともにこの間、10人近くの総理大臣が登場しては消え、政治リーダーが国家の基本政策をないがしろにしていた。その先にあるのは、崩壊の一途である。今こそ取り組むべきは、憲法、教育基本法の改正、安全保障、東アジア外交における骨太の政策ではないのか。自らの政権を回想し、「政治家は歴史法廷の被告席に立たされている」と説く。政治から歴史観、人生観まで中曽根哲学の真髄を結集した書である。
-
3.0もしかしたら、嫌われているかもしれない……うまくいっているはずの人間関係が、無性に怖くなることはないですか? 友人や同僚が携帯電話を手に笑っている。近寄ると「何でもないよ」と煙に巻かれる……。インターネットの普及によって、知らないところで自分の悪口が囁かれているかもしれないと疑心暗鬼になる私たち。「気にするな」と言われても、だれが何を書き込んでいるか不安で、サイトやメールを見ずにはいられない。周りの視線、笑い声、着信音。「たかがウワサ」のはずなのに胃が痛い……。いじめや誹謗中傷などの攻撃手段と化し、心を蝕むウワサの真の恐怖。学校と職場の事例から子ども・大人それぞれの人間心理を読み解く。心を病まないための対策マニュアルも紹介する。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2014年10月20日、80歳の誕生日を迎えられた皇后美智子さま。本書はそんな節目の年に美智子さまが天皇陛下とともに歩まれた足跡を多数の写真とともに振り返ります。「皇室は祈りでありたい」――そのお言葉どおり、美智子さまは自然災害が起こるたびに現地へ赴き、被災者を慰め、犠牲者を弔われてきました。その「祈りの旅」や、半世紀前に国民を魅了した、懐かしいミッチースマイルのお写真の数々、渡辺みどりさん、喜多洋子さんによる特別寄稿など、皇室報道で実績のある「週刊女性」ならではの永久保存版です。※電子版には「特別付録 天皇・皇后両陛下2015年カレンダー」は付属しません。
-
3.6
-
3.9
-
3.9
-
4.0いま韓国は瀬戸際に立たされている。北朝鮮に対する警戒感を喪失してしまったからだ。北朝鮮の南進武力統一政策はまったく変わっていないのに、韓国は同じ民族という幻想に引きずられている。いたずらに反日、反米に走り、敵と味方とを取り違えている。政界、財界、マスコミの中枢に北朝鮮の手先が忍び込み、世論を意図的に北寄りに操作している。誇りを忘れた韓国人は、独裁的な途上国でしかない北朝鮮に完全に屈服してしまった――。盧武鉉政権誕生以来、東アジアの平和をなし崩し的に脅かす韓国の変節を糾明する。北朝鮮の核開発はどこまで進んでいるのか? 韓国にとって主敵はいったいどこなのか? このままだと韓国が内部から自壊するという恐怖のシナリオとは? 反共国家韓国 左傾化、北朝鮮化する韓国 盧政権はなぜ反米になったのか 反日を続ける韓国 北朝鮮は何を狙っているのか 韓国と北朝鮮―軍事バランス 日本はどう対処すべきか。
-
4.0
-
3.0
-
4.0
-
3.7
-
3.6
-
3.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「我々は、どのような未来を目指して研究を行っているのか?高校生や、大学生に、我々は明るい未来を目指すために研究を行っていることを伝えたい。」という考えのもと、渡辺仁史・研究室出身の教員・研究室在籍生が、これからの明るい未来を描いた。全ての研究には、発足以来のキーワードである「人間-空間-時間系」のコンセプトが浸透し、人間と空間との関わりだけではなく、時間という他の研究室にはないオリジナリティのある視点が含まれている。本書を通して、30年間の渡辺研究室の膨大な研究成果は、これからの明るい未来を描くためにあるということを、広く世の中に知ってもらいたい。 本書は「教員が描く未来」「学生が描く未来」の2つの章で構成されている。Chapter 1 では、渡辺仁史と渡辺仁史研究室出身の教員が自身の研究や思想をもとに未来を描いている。まず概要が語られ、その後いくつかの詳細を語るテーマによって構成されている。また、各教員の研究や思想を表すダイアグラムや写真、図を用いている。Chapter 2 では、渡辺仁史研究室所属の卒修論生(2010年度渡辺仁史研究室在籍)が、今まで研究室で行われてきた研究や論文をもとに未来を描いている。見開き2ページで一つの未来像の提案となっており、左ページでは現代における問題点や時代背景を提起し、提案する未来像に関連する研究を3つ紹介している。そして、右ページで具体的な未来像を提示し、その説明文を記載している。学生4人が1グループとなり、7グループ計28人が描いた未来であるので、各々の個性や考え方を反映した提案となっている。
-
-
-
4.0
-
3.9
-
3.7本書は、安全保障や危機管理を主題とした国際情勢の最新レポートである。世界唯一の超大国アメリカの首都・ワシントンからの視点は、日本のマスメディアに今なおはびこる戦後の「平和主義」が、いかに非現実的、非国際的であるかを浮き彫りにする。例えば、アメリカでは靖国参拝反対論は意外なほど少なく、むしろ中国側を批判しているのだ。真の平和を保つためには軍事や安全保障を遠ざけてはならない――これが世界の現実認識である。日本が戦後の呪縛をみずから解くときがきたのである。日本の外交は、もっと「凛」とした態度をとってしかるべき。そのためには、民主主義や人権尊重という普遍的な価値観の重要性を堂々と説くべきである。例えば、中国に対してひたすら譲る「友好恭順」外交が破綻したいま、こうした普遍的な主張によって、中国における民主主義の不在や人権抑圧を批判すること。それが「正常な国」へと大きく前進するプロセスとなるのである。
-
3.0日本人は中韓と、政治・経済・文化においてアメリカなどへの対立軸となりうる「東アジア共同体」を設立しうるのか? 協調の前に認め合わねばならない日中韓の「差異」について考察を深め、あるべき姿を提案する。
-
3.0
-
3.5
-
-
-
3.8
-
5.0新事実続出!現地写真253点で隣国の謎を解明。万景峰(マンギョンボン)号、美女応援団、絶叫女性アナの真相! メディア初公開! いまだ冷戦を続ける特異国家が持つ「もう1つの素顔」。
-
-
-
3.5
-
-
-
4.0
-
4.0
-
4.0
-
3.9
-
4.0
-
3.9
-
3.8
-
3.9
-
3.8