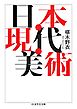筑摩書房作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-
-
-
-
-
-
-前近代的な土着性をはらんだ「日本の前衛」、〈つくらないこと〉の呪縛としての「もの派」、岡本太郎の「爆発」、赤瀬川原平の紙幣「模造」、読売アンデパンダン、森村泰昌、村上隆、会田誠……。世界史から切り離され、忘却と堂々めぐりを繰り返す「閉じられた円環」である「悪い場所」日本において、美術の歴史は成立しているのか? 1945年=敗戦以降の美術の動向と批評の堆積を遡行し、歴史的・政治的なコンテクストに位置づける。戦後日本の精神を浮き彫りにし高く評価された、卓越した日本文化論にして著者の主著! 解説 安藤礼二
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-湾岸戦争をアメリカのTV放送だけで追ってみる、という試みから始まった本書は、アメリカを突き動かす英語という言葉の解明へと焦点を移していく。母国語によって人は規定され、社会は言葉によって成立する。たえず外部を取りこみ攻撃し提案していく動詞中心の英語に対し、日本語とは自分を中心とした利害の調整にかまける言葉だと著者は結論付ける。言語にはそれぞれ美点と歪みがある。日本語のなかで生きる私たちは日本語という「歪み」を通してしか考えられない。「戦後」という時空間は、実はその「歪み」そのものなのだ。ではその歪みから自由になることはできるのだろうか。「歪み」を熟知したうえで「歪み」を駆使すれば、日本語の外へでていくことはできる、と著者は書く。英語と日本語への熟考が、やがて読み手を世界の認識の根源まで導く鮮やかな思考の書。 1997年は加藤典洋の『敗戦後論』と片岡義男のこの本の出現で画期的な年として記憶されることになるだろうと思った。(高橋源一郎『退屈な読書』より)
-
-私たちは、私たちの文化と言語とを形成してきた永い歴史を受けて、その流れの中で、感じ、思い、考えている。では、過去にどのようなことがあったために、いま私たちはこのように感じ、思い、考えるのか。そして、その過去に気づくことによって私たちは何を得られるのか――そうした日本思想史と現在の関わりについての問題を研究してきた著者が、これまでに様々な機会に発表してきた短い考察を集成。碩学による「日本」をめぐる長年の思想史探究を集成した、驚きと刺戟に満ちた珠玉の小文集。 【目次】はじめに/I その通念に異議を唱える/II 日本思想史で考える/III 面白い本をお勧めする/IV 思想史を楽しむ/V 丸山眞男を紹介する/VI 挨拶と宣伝/索引
-
-
-
-
-
-
-
-日本を農業中心社会とみなす、長年常識とされてきた社会像は、近年つくられた虚像だった──ベストセラー『日本の歴史をよみなおす(全)』で、このことを明らかにした網野史学。この一貫した視点から、本書では「百姓」=「農民」という定説を覆し、実際にはその大きな部分を占めていた「海民」たちの活躍を読み解く。漁業、製塩業に従事するのみならず、広く遠洋交易を営み、企業家的な活動すら行った海民たちは、いかに日本の社会を彩り、形作ってきたのか。史料を駆使してその豊かな世界を掘りおこし、日本史に新たな地平を切り開いた快著。
-
-大阪や東京日本橋界隈の問屋、観光地の朝市、縁日、門前町の商家など、その源流をさかのぼると、多くは中世社会にまでたどり着く。そして彼らの営業形態や商売人としての思想には、中世から引き継がれたものも少なくない。いわば現代経済社会の基礎は中世の商業社会にあるといえよう。本書は長く商業史を牽引してきた著者が、中世の個々の商人像にスポットライトをあてつつ、経済全体の流れについても描いてみせた商業史入門の傑作。朝廷に仕えた供御人、大原女などの行商人、都市の定住商人、戦国の豪商等々、さまざまな商人のしたたかな営業活動が、活き活きと浮かび上がる。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-日本の浮世絵はなぜ遠近法をもたなかったのか。浮世絵に限らず、日本の美術は中国やヨーロッパの影響によるものを除き、独自の遠近法をもたなかった。しかし、写実の範囲を超えた造型方法である「視点の移動」が見られる。そこには日本人の伝統的なものの見方が反映されているのではないだろうか。遠近法を突破口に、浮世絵、歌舞伎、宗教から浮き彫りにされる個と全体との関係を論じた日本文化論。
-
-
-
-
-
-現代の私たちは日本の伝統文化をあまりにも知らない。それは明治時代に西洋の知識や技術を取り入れるためにつくられた学校教育や近代の学問が、日本の文学や歴史を私たちの心から切り離して論じてきたからだ。伝統的な日本人の心のあり方や死生観はどのようなものだったのか。いま私たちが伝統的と思っているものの多くが、いかにして明治に入ってからつくりだされてきたのか。民俗学や宗教学、倫理学等の観点から近代以降に日本人が見誤り、見失ってきたものを掘り起こす。
-
-
-
-
-
-「たぶん」の意味で“maybe”を使うと誤解される? 「フレッシュサンド」「ペットボトル」は英語じゃない? 日本語を直訳して変な表現をしていたり、あまり使われない古臭い表現を多用していたり、全然通じないカタカナ語を使っていたり、日本人の英語は勘違いだらけ! 長年日本人の英語に接してきた著者が、日本では意外と知られていない英語の常識を伝授します。ベストセラー『日本人の9割が間違える英語表現100』シリーズ待望の第2弾。
-
-知ってるつもりの英単語でも、ネイティブが多用しながら日本人にはあまり知られていない「使える」意味、用法がある。本書は、高校英語までにおよそ出あう単語の中から、意外な・面白い意味を持つ100の英単語を集めた単語解説集です。これらを知っていれば、英語文献や英語記事、英語の動画などもすらすら理解できるはず! あなたはいくつ知っているか?!
-
5.0See you again.は、永遠の別れのときだけに使う? 「ドンマイ」「ハイテンション」「ファイト!」は全然通じない? 教科書に載っていても実は通じない英語、何気なく使っている和製英語など、日本人が身につけている英語には勘違いがたくさん! 長年日本人の英語に接してきた著者だからこそわかる、日本人が間違えやすいポイントと、その正しい言い方を伝授。これを読めば、しっかり伝わる英語表現が身につきます!
-
-
-
-「膝」と言えば、ピンポイントの膝頭ではなく太ももの前側全体を指し、「肩」と言えば、肩峰のみならず、首肩まわりの「界隈」を指す……おおざっぱであり曖昧であり、細かいことは気にしなかったはずの日本人の身体観。ところが、現代の身体に関する志向性はこれに逆行している。人間同士の境界も環境との境界も曖昧であったがゆえに、他人や自然と共鳴できていた日本人の身体観を、古今東西の文献や文学、また能の詞章を検証しつつ振り返ることで、「カラダ」と「ココロ」に分裂し、内向きになっている現代の身体観を、打開する端緒としたい。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-平安時代には父親などの「経済的庇護者」、中世には「主従制の主人」との関わりで使われた「頼む」という言葉。また、頼み頼まれる社会関係は近世に「義理」概念を生む基盤となるなど、日本史のなかで意味を変化させてきた。その変化は人と人の結びつきの変化を表している。『万葉集』『源氏物語』から「一揆契約書」「頼み証文」まで、様々な史料に現れる「頼む」の変遷を丹念に読み込み、日本人の社会的結合を描く、まったく新しい社会心性史の試み。
-
-
-
-「日本人は無宗教だ」とする言説は明治初期から、しかもreligionの訳語としての「宗教」という言葉が定着する前から存在していた。「日本人は無宗教だから、大切な○○が欠けている」という“欠落説”が主だったのが、1960年代になると「日本人は実は無宗教ではない」「無宗教だと思っていたものは“日本教”のことだった」「自然と共生する独自の宗教伝統があるのだ」との説が拡大。言説分析の手法により、宗教をめぐる日本人のアイデンティティ意識の変遷を解明する、裏側から見た近現代宗教史。 【目次】はじめに 藤原聖子/第一章 無宗教だと文明化に影響?――幕末~明治期 木村悠之介/第二章 無宗教だと国力低下?――大正~昭和初期 坪井俊樹/第三章 無宗教だと残虐に?――終戦直後~1950年代 藤原聖子/第四章 実は無宗教ではない?――1960~70年代 木村悠之介/第五章 「無宗教じゃないなら何?」から「私、宗教には関係ありません」に――1980~90年代 和田理恵/第六章 「無宗教の方が平和」から「無宗教川柳」まで――2000~2020年 稲村めぐみ/おわりに 藤原聖子
-
-
-
-
-
-
-
-1945年の敗戦後、主体性をもたず権力や多数者にいとも簡単につき従う日本人の傾向をどう克服するか、が大きな課題として論じられた。だが、今もこの問題はなんら解決されていない。これほど根深く、空気のようにわれわれの精神を規定しているものは何なのか―それこそが、日本の「自然宗教」である。われわれの心性の背景をなす「自然宗教」とは、どのように生まれ、いかなる特徴をもつものか? なにゆえそれは、この国に「普遍的思想」が根づくことを阻害するのか? 民俗学、歴史学、宗教史、思想史など幅広い知見を渉猟してその淵源を探り、克服へのかすかな道筋を問う。渾身の書き下ろし。
-
4.0機能不全に陥った日本政治。いまや自公は少数与党となり、一方で野党はまとまることができず、右派ポピュリスト政党が存在感を増している。こうしたなかで、わが国の政治を立て直すには何が必要か。「平成の政治改革」から現在まで、野党再編、政権構想、選挙制度改革、ジェンダー平等、西欧の右派ポピュリスト政党、2025年参院選など複数の視点から検証。現在地を浮かび上がらせるとともに、来るべき日本政治を展望した、必読の論集! 【目次】はじめに(山口二郎)/第一章 日本政治の失われた三〇年と野党の蹉跌――なぜオルタナティブは生まれなかったか(山口二郎)/第二章 平成の政治改革と「二党制の神話」――なぜ小選挙区比例代表並立制は機能しなかったのか (中北浩爾)/第三章 ジェンダー政治の三〇年――平等で包摂的な社会に向けた成果と課題(辻由希)/第四章 政党政治の危機状況――西欧の混迷から考える(古賀光生)/終章 二〇二五参議院選挙と政党政治の再編(山口二郎)/あとがき (中北浩爾)
-
-太平洋戦争時、帝都防衛の任をおびていた陸軍飛行第五十三戦隊。その整備兵であった著者は、日本全土への空襲が本格化する昭和19年11月から翌年の敗戦に至るまで、手許にあった文庫本の余白にひそかに日記を書き綴っていた──。苛烈をきわめる各地への空襲とその被害の経過を定点観測のように詳細に記録しつつ、そこに疲弊していく兵士の日常や傍観者たらざるを得ない自身へのやるせなさ、膨らんでいく戦争・国家への疑念、荒廃していく国土や次々と斃れていく戦友への痛切な思いが、随所に差し挟まれていく。等身大の兵士の視点から本土空襲の全貌を綴った貴重な記録。
-
-日本地図を鑑賞しよう。「ムカツク」地名や人名にしか読めない地名、不思議な飛び地や奇妙な県境など楽しい発見の宝庫だ。その由来を探れば、地形や歴史、あるいは地図制作者の意図が見えてくる。地図の見方や古地図の味わいなど、マニアならではの目のつけどころを、初心者にもわかりやすく紹介する。「机上旅行」を楽しむ地図鑑賞入門。
-
-
-
-ふとした時に表れる日本人独特の感覚。自分の湯呑みを他人に使われてしまった時の気まずさなどはその一例といえるだろう。高取によればこの感覚は、自己の範囲を所有するモノや所属する集団にまで広げて認識していた近代以前の名残だという。また祖先としての神、他所から来る神という二種の神観念があるのも、定住だけでなく漂泊もまた少なくなかった前近代の暮らし方に由来するという。本書はそうしたわれわれの感覚や習慣を形作ってきたさまざまな事例を挙げ、近代的な自我と無意識下の前近代が交錯する日本人の精神構造を明らかにする。民俗学の傑作にして恰好の入門書。
-
-西洋哲学の概念や思考法のみが純粋なものであるという特権的な意識は、いまや世界的に大きな批判に晒されている。西洋独占主義的な哲学観を輸入した日本が、「日本哲学」を再び検討すべき時期がやってきた。アメリカ、日本、ドイツでハイデガーの哲学、現象学・解釈学から仏教思想・京都学派までを幅広く研究し、日本の哲学史を専攻の一つとしてきた著者が、日本哲学とは何かを、定義・内容から深く問い直し、世界規模の対話に開かれた日本哲学がもつ可能性を総合的に考察する。 【目次】まえがき/序 章 日本哲学の定義と範囲を再考する/第一章 日本・哲学・とは何か/第二章 西洋独占主義的な哲学観を問い直す/第三章 日本哲学の定義を問い直す/第四章 日本哲学の内容を問い直す/終章 世界における日本哲学、日本における世界哲学/参考文献/解説 世界の思考資源としての日本哲学 中島隆博
-
-全国の企業1000社にどんな福利厚生をしているかアンケートをし、社員とその家族を幸せにしている100の事例を紹介する。それは業績にも確実に効果を及ぼしているという分析もあわせて明らかにする。第3子誕生時に100万円支給する。最もながめのいいところに社員のカフェがある。社員が株のほとんどを持っている。等々それぞれどのように導入し、効果はどうかなどを紹介する。中小企業が工夫をしたユニークな事例ばかりで、参考にしやすいはずだ。
-
-
-
-
-
-双六、丁半、花札、富くじ……。賭博は古代より日本社会に存在し、貴族の社交の嗜みとして、武士の陣中の慰みとして、また庶民のエネルギー発散のはけ口として、あらゆる階層の人々を虜にしてきた。本書では、現在もなお残る定番の賭け事から、忘れ去られた昔の流行物、果てはイカサマの技術に至るまでの数々を紙上に再現。権力による禁圧の裏で新たな賭博が次々と生み出されてきた様を、豊富な図版とともに活写する。賭博という人間存在を語るうえで不可欠な現象に着目することで、時代の性格や民衆の感情の新たな側面が見えてくる。類書のないギャンブル日本史。解説 檜垣立哉
-
-ひとは、生まれてから死ぬまで他人とのかかわりにおいて生きている。しかしそれが時にはわずらわしくもあり、また時には人恋しくもなる。並はずれた才能を持ちながら世を疎み、心の葛藤を自然を愛でることと孤独に耐えることで癒しながら生きた中世以来の隠遁者たち、西行法師、鴨長明、吉田兼好、松尾芭蕉、種田山頭火、尾崎放哉らの研ぎ澄まされた感性の表現から、われわれ現代人は何を感じとり、受け継ぐことができるのか。日本人の心の系譜を読み解く力作。
-
5.0昨今、メディアや識者からは、日本の教育に否定的な意見ばかりが目立つ。その結果として、教育現場の実態とはかけ離れた教育政策にすがりついてしまう。しかし巷間言われるように、日本の教育は本当にダメなのだろうか? 国際比較データを駆使して新しい姿を描き出す。思い込みを解きほぐし、不安や疑問に答え、未来に向けて提言をする。専門分野も国籍も異なる気鋭の研究者2名が、教育をめぐる議論に新しい視点を提供する。
-
-統制とは、市場の価格機構に何らかの方法で干渉し、その機能を制限することである。日本における経済統制は、世界恐慌による危機的状況への企業の自主対応から生まれた。やがて、日中戦争(日華事変)の勃発、太平洋戦争への突入と戦争が全面化するにつれ、性格を変貌させていく。国家による軍需生産への集中とそれ以外の生産物への介入拡大という、統制が統制を呼ぶ事態のなか、破局へと突き進む日本―。昭和12年(1937)から昭和25年(1950)までの国家統制時代を中心に、名著『昭和史』の著者が経済の動きについて全体像を提示する。戦後の出発を決定づけた戦時中の経験とは何であり、現代に何を教えるのか。
-
5.0
-
-私たちはいつ、病気で働けなくなったり、障害を負ったり、会社が倒産して仕事を失ったりするかわからない。個人の努力ではどうしようもない場面に遭遇した時にも健康で文化的な最低限度の生活が維持できるように憲法の生存権を保障する仕組みが社会保障だ。自分の力や家族や地域での支えあいではどうにもならないことが多いからこそ、この仕組みが必要である。では、法律と運用はどうなっているか。生活保護、年金、医療、公衆衛生、介護保険と高齢者福祉、労災保険と雇用保険、子育て支援、障害者福祉、社会保障財源としての消費税など、その仕組みと財政の最新事情から課題まで網羅する一冊。
-
-日本の深層文化を探ること―それは、かつての日本人たちの豊穣な意味の世界を生きなおすことだ。「稲作文化」の常識に反して、かつて穀物の一方の雄であった粟の意義。田とは異なる豊かさを提供してくれた各地の「野」。食用だけでなく道具や衣類そして儀式の象徴となる鹿。さらには「大きな魚」としてのクジラ…。思い込みを排すれば、史料と遺跡はこんなにも新しい姿を見せてくれる。
-
-古代日本においては、統治の正統性を確立するために、征服した部族が、征服された側の神話を、自らの神話に取り込んだ。そうして出来上がったのが天皇家の神話、記紀神話である。記紀神話の成立にあたっては、天皇家に征服された伊勢の豪族、度会氏、宇治土公氏がすすんで協力した。その結果、伊勢地方の太陽神であったアマテラスが万世一系の祖先神となる。しかしなぜ単なる一地方神が皇祖神に選ばれたのか?それはアマテラスが、日本人にとって最も当たり前で受け入れやすいタイプの神だったからだ。国家統治のために創り上げられた神話を元の地方神話に解体し、日本の神の原初の姿を取り出して見せた、画期的な研究。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-「日本独自の文化・伝統」はどのようにして生まれたのか。天皇のもと稲作中心に営まれた古代日本社会に、中国大陸から仏教が伝来して以降、さまざまな文化との交流、混淆、対立が繰り返される。大嘗祭、祇園祭り、盆踊り、元寇、ねぶた祭り、南蛮貿易、寺請制度、かくれキリシタン。古代から現代まで、数々の外来の文化の影響を受けて変容し形成された日本の民俗宗教を、歴史上の政治状況、制度の変遷とともに多角的に読み解く。
-
-幕末に来日した外国人たちがこぞって驚くほど、日本には裸が溢れていた。理想化されない自然な身体イメージを享受してきた日本人は、江戸末期に初めて西洋の理想的身体であるヌードに出会い、近代化の過程で葛藤と苦難を体験する。本書は生人形や淫靡な錦絵を生んだ幕末の驚くべき想像力、日本という環境で日本女性を描こうとした洋画家たちの苦悩、戦後日本中に乱立したヌードの公共彫刻、海外で高く評価される日本独自の身体芸術・刺青など、さまざまなテーマを横断し、裸体への視線と表現の近代化をたどる異色の美術史。文庫化に際し大幅な加筆を行った増補版。
-
3.0
-
-
-
-
-
-
-
-情報化の進行は、二〇世紀的な旧来の文化論を過去のものにした――。本書は情報化と日本的想像力の生む「新たな人間像」を紐解きながら、日本の今とこれからを描きだす。私たちは今、何を欲望し、何に魅せられ、何を想像/創造しているのか。私たちの文化と社会はこれからどこへ向かうのか。ポップカルチャーの分析から、人間と情報、人間と記号、そして人間と社会との新しい関係を説く、渾身の現代文化論。
-
-日本人、あるいは日本文化とは何か。民族の個性は、いつどのようにして形成されたのだろうか――文化人類学の明晰な方法論を用いて、西洋世界の社会・文化と対比しながら、日本人の思考様式・生活意識を規定する日本文化の特質を解き明かす。日本の文化人類学を確立した著者が積年のテーマを結実させた名著。
-
-
-
-中国スペシャリストとして、戦前の対中外交を率いた陸軍「支那通」。その代表的人物・佐々木到一は、孫文はじめ中国国民党の要人と深い親交を結び、第二次北伐に際しては国民革命軍にも従軍した。しかし、その後、支那事変(日中戦争)では南京攻略戦に参加して、いわゆる南京「虐殺」の当事者となり、戦後、激しい批判にさらされることになる。革命に共感を寄せ、日中提携を夢見た彼らが、結果としてなぜ泥沼の支那事変へと両国を導くことになったのか。われわれは、どこで道を誤ってしまったのか? 「支那通」の思想と行動を通して、戦前の日中関係の深層に迫る。
-
-
-
-