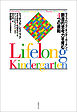ビジネス・実用 - 日経BP作品一覧
-
4.0☆なぜ国会審議は無意味に見えるのか、なぜ能力の低い議員が量産されるのか、出たい人より、出したい人を選ぶには、どうすればいいのか……。 ☆「政治の劣化」が叫ばれて久しい。原因は政治家の質、日本人の「民度」だけでは語れない。そこには、政治機能に歪みをもたらす制度的な問題があったのだ。国民が当事者意識、参加意識を高め、改革を進めなければ道は開けない。 ☆政治制度の分析を専門とする研究者が、日本の政治に埋め込まれた矛盾、問題点を鋭く突き、真に機能する制度とは何かを考える。これからの国、地方の進むべき道を考えるうえで必読の書。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ゲーム製作で分かる パーツの動かし方入門30 Google工作キット2種で画像学習とサーボ制御 「マインスイーパー」「旗揚げゲーム」「モグラ叩き」。 特集1ではラズパイでゲーム工作をしながら、多様な電子パーツを制御する基本を学びましょう。 LED点灯などの基本から、割り込みの設定、ディスプレイのスクロール制御など、電子工作で頻出する制御法を網羅的に紹介します。 特集2は、「画像認識AIカメラ」と「新版AIスピーカー」のGoogle工作キット2種のさらなる活用法を紹介します。 AIカメラでは、グー、チョキ、パーの画像をディープラーニングで学習し、AIカメラとじゃんけん対決します。 AIスピーカーではサーボを音声で制御し、“歌って踊れるAIスピーカー"に仕立てます。 このほかラズパイ以外の工作ボードとして、ソニーの新製品「SPRESENSE」も活用。ボタン操作でビートを刻めるビートボックスを作ります。
-
4.0バフェット、マンガー、ダリオ、ガーリー、ガンドラック、アイカーンら、著名投資家が推薦! マクロ情勢の予測はするな サイクルに耳を傾けよ ■投資において、たった一つの最も重要なことなど存在しない。前著『投資で一番大切な20の教え』で論じた20の要素一つひとつが、成功を願う投資家にとって絶対に欠かせないものなのである。 ■だが、最重要項目にまちがいなく一番近い要素は、市場サイクルを理解することだ。これまで私が知り合ったすぐれた投資家の大半は、サイクルの一般的な動き方と、「今、サイクルのどこに位置しているのか」を察知する類まれな感覚を身につけている。 ■残念なことに、サイクルの根本的な性質について書かれた文献はほとんど存在しない。そこで私は、サイクルとは何かというテーマに的を絞った本を書く決意をした。 ■投資家はサイクルを認識し、評価し、どうすべきかをそこから読み取り、それが示すとおりに動く術を身につけなければならない。サイクルに耳を傾ける投資家は、サイクルが引き起こす大混乱を理解し、それに乗じて著しいアウトパフォーマンスを得られるだろう。 ■オークツリー・キャピタル・マネジメント共同会長兼共同創業者が、勝率を高める王道の投資哲学を説く。
-
4.0本書は『Mastering Windows Server 2016 Hyper-V』(Sybex、2016年)の翻訳書です。Hyper-Vの普及が進むにつれ、現場の実務に携わる技術者向けの解説書が永らく待たれてきました。 本書はそのようなニーズに応えるもので、Hyper-Vを広く深く解説する初の本格的な解説書です。仮想化技術の基礎から始まり、Hyper-Vの導入・設計・運用・管理を実践的に解説します。 SCVMM(System Center Virtual Machine Manager)やAzureのIaaS機能、コンテナーとDockerといった注目の分野、RDS(リモートデスクトップサービス)などの周辺技術についても取り上げています。 本書で、オンプレミス環境を超える、Azureを支える技術としてのHyper-Vについて理解を深めることができます。日本語版では、原書発行後の最新情報をできる限り補足するよう努めました。
-
4.0モノが溢れる時代に「新しい価値」を発見するには 良質なアイデアを生み出し続ける必要があった。 「ひらめき」だけでは語れない、思考のサイクルを創るための技術を伝授する! ◆モノが溢れる時代の企業や商品の競争力は、「アイデア」で差がつく。しかし、「アイデア」を形にするためのデザインとビジネス、双方に通じる知識を持つ人はとても少ない。こうした、ビジネスとデザインの橋渡しをする能力を持った人のことを「クリエイティブ・ディレクター」という。「クリエイティブ・ディレクター」は、限られた領域だけでなく、ありとあらゆる組織に必要となってきている。言い換えると「経営がわかるセンスのいい人間」のことだ。美しくてかっこよくて、使いやすくてわかりやすい、みんなが親しみを持てる企業や製品、広告をデザインできる人のこと。代表的なのはスティーブ・ジョブズ。 ◆本書では、クリエイティブ・ディレクターに必要な「アイデアの生み出し方」と「人を巻き込みアイデアを形にする」二つの能力のうち「アイデアの生み出し方」に焦点を置く。より良質なアイデアはどのように生み出すのか? 業界の最前線で活躍している水野学氏、小西利行氏、嶋浩一郎氏、菅付雅信氏、夏野剛氏、水野祐氏らが語る。 ◆本書は、2015年にスタートした「六本木未来大学」の講義録をベースに構成する。「六本木未来大学」とは、2012年に六本木の美術館やギャラリー、地域の人々と手を取り合い、街全体で六本木の新たな価値を見出すべくはじまった「六本木未来会議」で、「クリエイティブ・ディレクション」を学ぶための学校として、水野学氏の提案で開講した。
-
4.0対話ボットから翻訳、自動運転、未来予測まで、「第3次ブーム」と言われる人工知能(AI)の技術革新は、衰えるどころかますます加速している。その結果、AIを使いこなせる人材、いわゆる「AI人材」の争奪戦は激しさを増している。 AI人材の獲得競争が世界規模で拡大し、AI人材の給与は高騰している。GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)やBAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)といった米中IT大手はAIの研究開発にケタ違いの資金を投じ、優れた人材をかき集めている。 本ムックは、AIを主軸にITの研究開発の最前線を紹介すると共に、各社のAI人材育成・採用・活用戦略を読み解く。企業の経営者、企画担当者、開発担当者などを対象に、3~5年先の未来を見据えるために不可欠な情報を提供する。 まず第1章と第2章で世界の動向を解説。ファンドを通じて10兆円をAIに投じる孫正義氏の世界戦略と、中国のAI開発戦略について、それぞれ現地取材に基づく最新のレポートをお届けする。続いて第3章で日本企業を中心とするAI人材戦略を解説する。 第4章はAI技術開発の最先端、第5章はAIがもたらすリスクとその回避策、第6章は量子コンピュータやブロックチェーンなどAIを支えるITインフラの技術革新を取りあげる。 未来を見通し、AIビジネスでライバルに差を付ける必携の一冊だ。
-
4.0
-
4.0
-
4.0プロマネが現場で使える書籍、遂に登場! システム開発の全フェーズを完全網羅 プロジェクトマネジメントに関する勉強本は多数出版されていますが、それらを勉強するだけではシステム開発プロジェクトを成功には導きません。特に経験の浅いプロジェクトマネジャー(プロマネ、PM)の場合、実際のプロジェクトの現場で「何をすればよいのか」と手探り状態になることが数多く発生します。結局は、個々のプロマネの力量次第で成功確率に差が出ているのが現状ではないでしょうか。 本書はそうしたプロジェクトマネジメントの勉強本ではありません。実際のシステム開発プロジェクトを成功させるために、プロジェクトマネジャー(プロマネ、PM)やメンバーの誰が、いつ、何をやればよいかを詳細に解説したプロジェクト実行ガイドです。プロマネになったばかりの人でも、プロジェクトがどのフェーズにあっても、本書は即座に活用でき、プロジェクトを成功へと導きます。 具体的には、システム構築プロジェクトの全フェーズを23群に分け、各フェーズの定義、標準タスクフロー、推奨するアクションで構成しました。プロマネが取り組むべきタスク、そしてメンバーが取り組むタスクと、それに対して推奨されるPMの取り組みが一目で分かります。各フェーズの計画書の作成例や成果物のイメージも豊富に収録しており、プロマネが常に手元に置くべき一冊です。
-
4.0あの人はいい性格だ、うちのワンちゃんはおとなしい性格……。 日常的によく使う「性格」という言葉。しかし「では、性格とは何ですか?」と 聞かれると、実はうまく説明できない。 本書は、性格を科学するパーソナリティ心理学の専門家が、 最新の研究成果を踏まえて、5つの性格特性(ビッグファイブ)の組み合わせから、 人間の性格は、どうすればうまく表現できるのかをわかりやすく説明します。 サイコパス、グリット、神経症傾向……。よく話題にのぼる「性格用語」も 具体的に解説され、広くて深い人間の「性格の宇宙」への旅に招待します。
-
4.0マイケル・ポーター『競争の戦略』が刊行されたのは30年以上も昔のことだ。いまや企業にとって戦略は必要不可欠なものとなった。 戦略を持たない企業はないといえる。ところが、一時ブームとなった「ブルーオーシャン戦略」は、他社との差別化の道は容易には見つからない という厳しい現実を前に、あっという間に廃れてしまった。どの企業も同じような戦略を立て、差別化が困難という状況が続いている。 どの企業も頭のいい人が集まって立派な「成長戦略」を掲げているのに勝者、敗者に分かれるのは、戦略の本質を理解した「実行」が決め手に なっているから。企業の業績は戦略と実行の掛け算であり、戦略立案=トップの役割、実行=現場の役割といった二分法ではうまくいかない。 戦略とは分析、ロジックであり、実行は組織における人間の気持ち、やる気である。本書は、戦略実行における問題点、失敗事例を挙げながら、 実行の要となる「組織におけるコミュニケーション」を深堀りする。
-
4.0なぜ、ディズニー映画は炎上しないのか? 似たような発信内容でも、女性の反感を買う、ズレてる会社と愛される会社がある。その成否をわけるのは――。ジェンダー(男女の役割)規範に詳しい著者が、ディズニープリンセス映画の変遷や国内外企業による「女性像」の発信の成功・失敗事例から、企業ブランド戦略、マーケ活動に活かせる情報発信の新ルールを指南する。誰もが発信する時代だからこそ、広報や経営企画担当者から企業経営者までが知っておくべき、新しいビジネス知識が学べる一冊。 <本書のポイント> ★CM、SNSでの「女性像」の見せ方は、一歩間違うと大きな炎上リスクに → 具体的な炎上CMから炎上ポイントと回避策を解説! ★海外でもジェンダー表現の拙さからの炎上はあり、ジェンダー対応力が世界共通語に → ジェンダー対応は、グローバル企業としての存在感と連動することを紹介! ★お手本はディズニー。シンデレラから中性的なプリンセスへの進化 → 具体的なプリンセス映画の変遷から先進企業のジェンダー対応力をたどる! ★日本企業は女性の役割の変化に配慮せよ!
-
4.0建設産業の生産性向上に火が付いた! 建設と最新テクノロジーが融合する「建設テック」を丸ごと解説 国交省が打ち出した政策「i-Construction」を引き金に、アナログな建設産業が、AI(人工知能)やロボティクスなどの最新テクノロジーを取り入れて生まれ変わろうとしています。覚醒を始めた70兆円市場への参入をもくろむのは、大手IT企業から創業間もないスタートアップまで多種多様。新たな技術やサービスが次々に産声を上げつつあるのです。 飛躍的な生産性向上に挑む建設業界と、建設産業の変革をビジネスチャンスととらえた異業種の企業、彼らを政策面で後押しする国交省。三者の動きが織りなす「建設テック革命」の熱気を、豊富な事例と当事者への綿密な取材を基に描きます。 【主な内容】 プロローグ 人手不足がもたらす建設テック革命 第1章 建設業界でドローンが大ヒットしたワケ 第2章 三次元データが現場にやってきた 第3章 自動運転・ロボットで建設現場が「工場」に 第4章 AIが救うインフラ維持管理 第5章 新たな主役はスタートアップ
-
4.0意思決定とは未来に対する賭け(=BET)である。 ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット、バラク・オバマ、クリスティアーノ・ロナウド……超一流の成功者はみんな身につけている! ポーカーが教えてくれる「思考の技術」とは――。 意思決定の達人であるプロのポーカープレーヤーが、不完全な情報のなかで最善の結果に到達するための「思考と判断の技術」を伝授します。 意思決定を「正解」と「間違い」のどちらかにしか当てはめられない世界から去ったとき、私たちは両極のあいだを行き来できるようになる。より良い決定を下すということは、白か黒かという考えをやめ、あいだのグレーに色調の目盛りをつけることである。 [第1章 人生はチェスではなく、ポーカーだ]より
-
4.0激化する米中対立。制裁関税の連鎖から通貨摩擦、金融リスクの拡大……。 超円高など日本経済を巻き込む最悪のシナリオに備えよ。 トランプ大統領は米朝会談の直後、中国に対して2000億ドルにのぼる追加関税を課すと警告。関税の報復合戦がエスカレートしている。米中貿易戦争の核心は、先端産業の覇権を巡る争いであり、産業の高度化を目指した「中国製造2025」などの戦略プランを掲げる習近平国家主席としては、簡単には譲歩できない。貿易戦争の激化は通貨摩擦を呼び込むとともに、中国の金融システムの脆弱性を突き、金融危機の引き金となる可能性も否定できない。また、米中の争いには早晩、日本も巻き込まれ、厳しい日米FTA交渉が始まる。 挑発的なツイートを目にしても、いまだ多くの人が「そんな酷いことにはならないだろう」と等閑視している日本。しかし、この危機は長期化の様相を示している。超円高を含めた最悪のシナリオを直視しなければならない。日銀審議委員を務めた著者が貿易戦争の本質とその深刻なリスクをわかりやすく解説する。
-
4.0セキュリティ、拡張性、可用性、保守性を高める! AWSでの基盤構築・改善法を構成図で解説 業務システムにAWSを本格導入するうえで必要な知識は多岐にわたります。どこから学んだらいいか分からない、AWSを触っているが体系的に理解したという手応えがない、といった悩みを抱える方が多いようです。 そこで本書では、オンプレミス(自社所有)環境のシステムの開発・運用に携わってきたがクラウドについては知識も経験もまだ乏しいというエンジニアの方を対象に、AWSを基本から解説します。業務システムで必要なAWSの主要サービスの知識と、それを使ったインフラ設計について体系的に学びます。 さらに、知識が身に付いたかどうかをチェックできるように問題を出します。「AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト」というミドルレベルのAWS認定資格を想定した問題なので、試験対策になります。本書を読むことで、この資格を取得するベースの知識が身に付くことを目標の一つとします。 本書は単なる、AWSのサービスの解説書ではありません。AWSを実務で使いこなせるように、コーポレートサイトのシステムを題材にして、アーキテクチャー設計と基盤構築の実践的なノウハウも解説します。 ロードバランサーと仮想マシン2台というシンプルな構成から始め、AWSの様々なサービスを使ってこのインフラを改修し、可用性、拡張性、セキュリティ、保守性を段階的に高めていきます。AWSの主要サービスを具体的にどのように活用するのかについて、コーポレートサイトのシステム改善を通じて学びます。
-
4.0自動車業界で話題の「CASE」そして「100年に一度の大変革」。 その本当の意味は何か。ビジネスはどう変化していくのか。 気鋭の若手アナリストが読み解く! 【自動車の「スマホ化」とは?】 ガラケーからスマホに変わった時代。 デバイス(端末)メーカーは主役の座を奪われた。 新たな勝者は、SNSなどのアプリ開発者(フェイスブック、ツイッター)、 そしてアップルやグーグルなどのプラットフォーマーたち。 「エコシステム」を発展させ、「データ」を制するものが「勝ち組」となった。 自動車業界でも同じ現象が起きる。 「自動車」というモノが主役の時代から、 エコシステムとデータが主役の時代へ。 旧来の発想とはまったく異なる パラダイム転換のメカニズムを解き明かすのが本書だ。 【モビリティ2.0とは?】 モビリティ1.0時代 -内燃機関(エンジン)によって走る自動車が「人やモノ」を運ぶ -「自動車産業」という枠組みの中で、車両の生産台数を競う -モノの汎用化が加速し、コスト削減競争で消耗する「衰退産業」 モビリティ2.0時代 -「データを運ぶ手段」という新しい「意味」が加わる -都市を中心としたエコシステムを活性化させる重要な媒体へ -サービスとしてのモビリティ=「MaaS(Mobility as a Service)」という新ビジネス -世界中で都市化が進む中、超成長産業として拡大 この流れはもう止められない! 新時代にビジネスチャンスをつかむためのヒントが本書にある!
-
4.0砂上の飽食ニッポン、「三人に一人が餓死」の明日 三つのキーワードから読み解く「異端の農業再興論」 【小泉進次郎】「負けて勝つ」農政改革の真相 【植物工場3.0】「赤字六割の悪夢」越え、大躍進へ 【異企業参入】「お試し」の苦い教訓と成功の要件 本書は、これまでの農業関係の本では真正面から取り上げられることの少なかった三つにテーマを絞り込んだ。 「小泉進次郎」「植物工場」「企業の農業参入」。これらをめぐり、意見は分かれている。 ある人びとからすれば、小泉は農業改革の旗手であり、植物工場は未来の食料生産を支える希望の技術で、企業は遅れた日本の農業を再建する立役者となる。一方、別の人たちに言わせれば、小泉は農業のことをよく知らず、植物工場と企業参入は失敗だらけ。 収益性の低さにさらされながらも、これまで黙々と農業を続けてきた農家の努力にこそ未来を託すべきだ、となる。 前者の意見は農業を専門としない人たちに多く、後者は農業のことを長年、地道に観察してきた人たちに多い。そのどちらにも正解はないというのが本書の立場だ。 どっちつかずの議論にするのが目的ではない。まずは先入観を排除し、問題を浮かびあがらせる。植物工場と企業参入は失敗例を詳しく伝え、小泉の農政改革に関しては残された課題を詳述した。そのうえで、過小評価されがちな三者の可能性に光を当てた。 農業に関する本としては、本書は「異端」に類するのかもしれない。だが、将来の食料問題を見据え、農業の課題を点検するためには、農業ジャーナリズムもこれまでの境界を越えてテーマを広げるべきだと思っている。 (本書「はじめに」より)
-
4.0日本テレビの夕方の報道番組「news every.」に出演するキャスター兼解説委員の小西美穂氏。 本書では、彼女が歩んできたこれまでのデコボコ人生を、あますことなく書き下ろしています。 30~40代の女性は、いつも人生の選択に迫られているのではないでしょうか。 キャリアはどうする?結婚・出産は? 立場が異なる女友達との付き合い方は?年を重ねる親とはどう向き合う? 誰もが真剣に悩み、そして決断を下していかなくてはなりません。 小西さんも、同じように迷い、そして決断を下してきました。 もちろん、選んだ先で失敗をすることもありました。 けれど本書を通して、小西さんは「何度転んだって大丈夫」というメッセージを送っています。 キャリアで迷った時の扉の開き方から、チームの力を引き出す方法、 自分の成長をうながすノート術、そして43歳で11歳年下の男性と ゴールインに至った婚活術や、親の闘病と仕事の両立まで。 小西さんがデコボコ人生を通して導き出した、笑って前を向くための数々の知恵を、みなさんもご覧ください。
-
4.0開発期間15年、 日本初のシワに効く薬用化粧品はいかにして生まれたのか。 66万人が使う大ヒット化粧品の誕生秘話 なぜ、これまで「シワを改善する」と明確にうたえる化粧品が作れなかったのか? なぜ、化粧品業界でポーラが「一番」になれたのか? そもそもなぜ、シワはできるのか? そしてなぜ、リンクルショット メディカル セラムで改善できるのか? 日本初のシワに効く薬用化粧品(=医薬部外品)として、 2017年1月に発売されたポーラの「リンクルショット メディカル セラム」。 発売から1年半の売り上げは売上179億円、これまでに66万人が購入という メガヒットとなった。 この商品を15年、15憶円をかけて開発したのが、現在、ポーラ・オルビス ホールディングス執行役員の末延則子さんだ。35歳から50歳まで何度も 大きな困難に見舞われながら世界で初のシワ改善メカニズムを発見、 独自の有効成分を見つけ出し、日本初の「シワを改善する医薬部外品」として 厚生労働省の承認を取得した。 自称「怖がりで心配性」という彼女が、 周囲から何度も「リスクが大きすぎる」「あきらめろ」と言われながら なぜ、それを成し遂げることができたのか。 末延さんと、研究を共に推進してきたスタッフ、化粧品業界に精通する アナリストや化粧品ジャーナリストへの取材を行い、 波乱万丈の開発ストーリーに迫る。
-
4.0ファーストリテイリング 柳井正氏 推薦! ! ファッション・ビジネスの概念を日本にもちこみ、ハーバード・ビジネススクール・ウーマン・オブザイヤーを受賞。数々の社外取締役などを勤めた著者が、人生の中で直面する壁の乗り越え方を伝授する! ◎著者の提唱する「主体的なキャリア創り」とは、仕事で成功するだけではありません。人生の質を考えること、自己のアイデンティティを確立することも含まれます。不確実性の高い現代社会で働く人々は、偶然の出来事で人生が大きく変わりやすいです。本書では、就職、子育て、転勤、定年など人生の各ステージで直面する課題の解決策を提唱します。 多くのハードルを突破してきた著者だからこそ語れる、長い人生で目標を達成しながら働き続けるための仕事術を伝授します。
-
4.0
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 AIモデルの精度向上を実現する手法、熟練者がやさしく伝授 今、IoT(Internet of Things)の分野でAI(人工知能)の活用が急速に広まっています。ただし、実業務において成果を得るまでに到達できる企業はごくわずかでしょう。その主な原因は、AIにおける学習モデルの精度にあります。AIにとってデータの良しあしが最も重要な点はよく知られていますが、現実にはAIに適したデータを収集するのは容易ではありません。 ではどのようにデータを収集すればよいでしょうか。その答えは、「データの前処理」にあります。本書は、日立産業制御ソリューションズ AI&ビッグデータソリューションセンタが取り組んできた、IoTで生まれるビッグデータをAIに与えるためのデータの前処理に関する実践的なノウハウを事例に基づいてまとめたものです。 本書前半の1章、2章では、データ利活用におけるデータ前処理の重要性について紹介します。後半の第3章以降では、IoTやAIにおけるデータ活用プロセスについて、より実践的に解説します。各章では、データ分析ツールを用いた実践方法を掲載しています。プログラミングの知識なしに、データ前処理を体験できます。 本書の読者は、IoT、AI、ビッグデータ解析の導入に興味を持っている、あるいは、すでに導入されている企業の経営層、CIOをはじめ、情報システム部門や企画部門といった関連する方々、実務的なデータ活用プロセスを学びたい学生を対象としています。特に、IoT、AI,ビッグデータ解析を導入する意欲がありながら、技術面・費用面で踏み切れないでいる中堅・中小企業の方々に読んでいただきたいと思います。
-
4.0AIに選別される危機 法と権利の問題を、気鋭の研究者が論じる 『AIと憲法』。 「憲法論とは9条論だ」と考えている方、憲法にいかめしい「改憲・護憲論」をイメージしている方にとっては何とも意外な組み合わせに聞こえるかもしれない。 しかし、SF映画によく出てくる主題、つまり、全く善良な市民がAI(Artificial Intelligence)に「あなたは潜在的犯罪者だ」などと予測・分類され、社会的に排除されるような世界は、今やフィクションからノンフィクションへと変わりつつある。 実際、米国の警察や裁判所では、犯罪者予測にAIプロファイリングが使われ、それによる排除や差別が問題になっている。中国では、信用情報機関のAIが算出した個人の信用スコアが社会の至る所で利用され、スコアの低い人が差別を受ける事例が増えてきている。 日本でも、企業の採用活動や金融機関の与信の場面でAIのスコアリングが多く使われ始めているが、そのような人生の重要局面で、もしAIに「あなたはダメなやつだ」とレッテルを貼られたら、あなたの人生はいったいどうなっていくのだろうか。 こうしたAIの事前予測に基づく個人の効率的な「分類」(仕分け)と、それによる差別や社会的排除は、「個人の尊重」(日本国憲法13条)や「平等原則」(14条)を規定する憲法上の論点そのものと言える。 日本人がある一方向にぐんぐん進んでいって良い結果が得られた試しはない(先の戦争や原発問題を想起していただければそれで十分だろう)。そうであるなら、今まさに、「個人の尊重」や「民主主義」といった「青臭い」憲法原理に思いを巡らせ、AIが本当に我々一人ひとりを幸せにするのかをじっくり考えてみる必要があるのではないのか。 それは、近年、米国で沸き起こっているような「反AI」運動を開始せよ、というのではない。AIは、うまく実装すれば憲法原理のより良い実現に資する。これはおそらく疑いのないことである。したがってポイントは、経済合理性や効率性の論理だけにとらわれない、憲法と調和的なAI社会の実現にある。 本書は、こうした「両眼主義」(福澤諭吉)を日本においても浸透させるべく編まれたのである。「AI、AIって言うけど、それって本当に大丈夫なの?」と漠然とした不安をお持ちの方は、ぜひ本書を手に取っていただきたい。その「不安」の根源がおわかりいただけると思う。 ――「はじめに」より
-
4.0ビジネスパーソンこそ、正しい練習が必要だ! 面接、営業、プレゼンテーションなど、 ビジネスで自分の強みを生かし、成功を収めるには、 計画と実行のあいだに「練習」が必要だ。 マイケル・ジョーダン、リオネル・メッシ、ロジャー・フェデラー…… 世界のトッププロは、練習の真の価値を知っている。 数学でも、音楽でも、スポーツでも、人材管理でも、 どのようなスキルを伸ばすときにも、 課題は同じなのだ。 その最初の一歩は、「上達すること」に上達することである。 むやみに練習しても、上達はない。 全米ベストセラーで話題のカリスマ教師が 仕事にすぐ生かせる練習の極意を解説。
-
4.0★ノーベル経済学賞が複数受賞可能なら何本受賞してもおかしくない、質量とも世界最高峰の業績を誇るティロール先生が、初めて一般向けに書き下ろした経済書! 良い社会をつくるために経済学はどう役立つのか、現実感覚に富んだスーパー経済学者が万人向けにわかりやすく解説します。 ★なぜ、経済学が社会の問題を解決するのに活用できるのか、というそもそも論から、社会の制度、環境や雇用・失業、金融危機などのマクロ的な経済問題、競争政策や産業政策、イノベーション、規制など、幅広いテーマを取り上げます。ティロール先生がこれまで積み重ねてきた知見が凝縮されている本であり、自らの学者としての生活を交え、一般の読者向けに解説します。数式は一切なく、経済学を知らない人でも読みこなせる。質が高く、広く長く読まれる良書です。 ★ティロール経済学の特色は、完全市場や完全情報などを前提とする従来の経済学とは異なり、不完全市場や経済的インセンティブだけで人は動かないなど、より現実的な前提をおいて、企業や個人、政府の行動を説明し、望ましい行動を促すための制度設計を提案する点にあります。「現実に使える経済学」「社会を良くするための経済学」です。 ★ジャン・ティロール教授は2014年ノーベル経済学賞を受賞した、「スターの中のスター」といわれる「知の巨人」。ゲーム理論を応用した産業組織論、金融論、バブル論など、広範なフィールドにわたってきわめて優れた研究を相次いで発表。ノーベル経済学賞は「市場支配力と規制」に関するテーマで受賞したが、他の分野での受賞も取り沙汰されたほど研究領域は多岐にわたります。また、優れた理論家であると同時に現実感覚に秀でた研究者と評されています。
-
4.0多様化する人材、様々な課題に、 「多面思考」で対応する! 人材育成を立て直し、加速するためにはどうすればよいか。必要なのは、「多面思考」を取り入れ、人材の多様化に即した人材育成の打ち手を考え、一人ひとりの個性が活きる人材育成を実践していくことに他ならない。 本書では、“人材育成の原理原則”を体系的に押さえ、組織成果の最大化へ向け、“効果的な人材育成のための多面思考のあり方”を提示。 同時に、人材育成上の課題をとりあげ、どのように多面思考力を活用し、日常の部下指導や組織運営の取り組みを通じた人材育成を進め、こうした課題を克服していくか、具体的な実践方法を示す。 ポイントとなる概念、理論、フレームワークについて、図表を活用してわかりやすく解説。読者が振り返りを行えるよう、テーマごとに押さえるべき要点のまとめ/チェックリスト等を挿入する。
-
4.0○サイバー攻撃、スパイ活動、情報操作、国家による機密・個人情報奪取、フェイクニュース、そしてグーグルを筆頭とするGAFAに象徴される巨大IT企業の台頭――。われわれの日常生活や世界の出来事はほとんどがサイバー空間がらみになっています。サイバー空間はいまや国家戦略、国家運営から産業・企業活動、個人の生活にまで、従来では考えられなかったレベルで大きな影響を及ぼしつつあります。 ○サイバー空間では、国家も企業も、集団も、個人もプレイヤーとなる。その影響力はそれぞれの地理的位置、物理的な規模とは一致しない。そして、経済やビジネスでもデータがパワーをもつ領域が広がっていますが、その規模はGDPでは測れません。 〇本書は、これほど重要になっているのに、実態が不透明なサイバー空間を定量・定性的に初めて包括的にとらえ、サイバー空間の行方を決める支配的な要素を突き止めるものです。果たして、そこから見えてくるものは何か? 日本はサイバー空間で存在感を発揮できるのか? ○執筆には、三菱総合研究所で進めているサイバー空間分析プロジェクト・メンバーと、サイバー研究で知られる慶応義塾大学の土屋大洋教授が入り、骨太の分析と展望を展開します。
-
4.0正社員の7割が、自分を“負け組”だと思っている?? なかなか思うように進まない日本の女性活躍推進。 その原因と処方箋を働く女性たちの声からあぶり出す、日経編集委員渾身のルポルタージュ。 「うちの女性課長、何とかしてください! 」――男性社員から起こる悲痛な声 「みんな残業しているのに、ママ友とカラオケ? ありえないです」――子アリ子ナシの溝 「夫がイクメンなら今頃私は管理職なのに・・・・・・」――一筋縄でいかない家庭とキャリアの両立 「同じ『働く母』とはいえ、実家が近いあの人とは違います」――ワーキングマザーの環境差 「今はパート主婦。活躍する元・同期と大きな差がついてしまった」――高学歴主婦の憂鬱 「女性活躍推進? 全く実感ありません。私とは別世界の話ですね」――非正規社員の本音 一体、何が彼女たちの行く手を阻んでいるのか? 「輝けない」40人の証言をもとに、職場の女性社員の力を最大限に引き出すための方法を考える。
-
4.0「イクメン」なんて、もう古い!! 次世代を担う若き経営者やプロフェッショナルたちは、どのようにわが子を育てているのか。 学校選びは? お小遣いのルールは? 夫婦の協力体制は? 将来の職業選択に、どうアドバイスをしている? そして、子育てとビジネスの相乗効果は期待できるのか――。 注目の経営者たち10人へのインタビューを通して、驚きの実態が見えてきた! ◇学校はあえて「公立」。 多様性ある環境で、リーダーシップを学ばせる ◇スマホは3歳から。 失敗も含めて、早くから体験したほうがいい ◇経済の仕組みは「メルカリ」を通してレクチャー ◇単身赴任でも、LINEを使って毎日コミュニケーション ◇スポーツはサッカーとゴルフ。サッカーで友達を増やして、ゴルフで忍耐力を養う ◇「オールA」より、B・C混じりの成績をほめる。 あえて不得意なことに挑戦! ◇「将来有望」なスキルを身につけるより、「大好きなこと」を見つけさせる ◇一緒にいられる時間が短くても、「濃く」「深く」愛していく 誰にだって、今日からすぐに実践できる! 「自分の頭で考えて動く」賢い子供の導き方が満載。
-
4.0人一倍遊び、人一倍野球に取り組み、常に逃げずに真っ向真剣勝負。 プロ野球黄金時代、“最強の敵役”としてライバル球団ファンをも魅了した伝説の左腕の苛烈な生き様。 中学では「やんちゃな少年同士の決闘が日常茶飯事」で、高校からは「弱い球団で巨人など強い者を倒すことを生きがい」にし、「三振か四球か」ノーコンでカーブもほうれぬままドラフト1位で阪神入団。契約金は「800万円の札束を見てみたかった」と一括現金でもらい、プロに入ると「勝っては繁華街に繰り出し、毎晩お祭り騒ぎ」「もらったらもらった分使って、人よりいいものを食べ、いい服を着て、いい女性と付き合う。これぞプロ野球選手ではないか」。奪三振記録は「取るなら王(貞治)さんしかない」と実行し、甲子園伝統の一戦、巨人・阪神戦では逃げずに真っ向勝負。縦ジマのエースは“最強の敵役”として巨人ファンをも魅了した。南海移籍後は、野村克也監督に「野球界にいっぺん、革命を起こしてみろよ」と言われ、意気に感じてストッパーに転向、これが広島移籍後にあの「江夏の21球」につながったのか。日本ハム移籍後は、複雑な家庭環境で育ったがゆえに大沢啓二監督に「父」を見て奮闘。最後は大リーグに挑戦し引退。個性派が影を潜め、選手が平均的になってしまった現在の管理野球に苛立ちながら、今も野球解説の現場に立つ――野球のロマンを追い求め、独得の美学をつらぬき通す男の履歴書。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 非常食か保存食、程度の地味な存在だったサバ缶が、水産缶詰商品の主役に躍り出た。 その生産量はツナ缶を抜き、第1位に。 昨年末にテレビ番組で「ダイエットにいい」「意外においしい」と取り上げられて以降、 スーパーでは品薄状態だ。 長年、魚油の研究を続けてきた早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構の矢澤一良さんは、 「旬の、最も脂が乗った状態のサバを缶に封じ込めることによって、青背魚にたっぷり含まれる EPA、DHAといった“いい油”を安価に手軽にとることができる」とサバ缶のメリットを説明する。 サバ缶の健康パワーを担うのが、EPAやDHAといったオメガ3脂肪酸。 脳の機能を高め、血液をサラサラにし、ぽっこりおなかや動脈硬化、心筋梗こう塞そくの原因となる 中性脂肪値を下げるなど、さまざまな効果が認められている。 本書ではサバ缶の美味しくて健康効果を最大限に引き出す食べ方をご紹介します。
-
4.0
-
4.0コーポレートガバナンス=株主重視経営 では、株主の向こうにある社会がきちんと見えていますか? ◆株主との接し方に悩む多くの経営者 コーポレートガバナンス時代、会社と株主との関係が大きく変わりつつあります。「株主とどう接すればいいか」「総会で何をすればいいのか」……経営者たちの意識が従来の「総会の乗り切り方」から大きく変化、多くが「株主との対話」のあり方に悩んでいます。 一方、ほとんどの投資家(株主)は、ESGなど社会性・社会的正義を大事な視点に置きながら、企業が正しく利益を上げ成長していくことを望んでいます。コーポレートガバナンスとは「株主重視経営」のこと。その株主の向こうには社会がある。つまり、株主=世論なのです。世論の動向に即した経営ができるか。いま企業に問われているのは、そうした「良い経営」の実践であり、ガバナンスコードは、それを集大成したものにすぎません。 ◆良い株主を味方につけることが経営を良くする 本書は、企業法務の第一人者が、ガバナンス時代の株主との対話の在り方を、新しい流れに沿って提言するもの。企業不祥事などが起こるたびに筆者が主張してきたのは、まさに、「企業が社会と正しく向き合っているか」ということでした。そうした基本認識のもと、株主と企業との関係を整理し、いかに「株主と対話」していくべきか、株主が重視しているポイントごとに解説します。著者は、多くの著名企業にアドバイスを行うとともに、日経新聞や「商事法務」などの媒体を通じ、様々な提言を行ってきた人気弁護士。今回は、まさにそのど真ん中のフィールドでの提言書であり、特に上場企業にとって、株主対応のマニュアル本となるものです。
-
4.0AI(人工知能)やIoT(インターネット・オブ・シングズ)を活用すると、2030年の日本のGDP(国内総生産)は従来予測より132兆円高まる――。これは総務省による2017年の予測です。新技術の活用が企業の成否を左右するなか、多くの企業でAIやIoTへの取り組みが始まっています。 その陰でAIをだまして人や自動運転の判断を誤らせるサイバー攻撃や、IoTのセキュリティの甘さを突く大規模攻撃が次第に増えてきているのをご存知でしょうか。次の金融インフラの一翼を担うと期待が集まる仮想通貨にもサイバー攻撃が殺到し、2018年1月には580億円相当の仮想通貨が流出したのは記憶に新しいところです。 我々がビジネスで使わざるを得ない業務メールにも詐欺の手が迫っていて、既に4割の国内大企業がだまされている事態も調査で判明しています。個人情報や機密情報を掠め取ろうとするサイバー攻撃も巧妙さが増すばかりです。 彼を知り己を知れば百戦して殆(あや)うからず――。最新技術の活用なしにデジタル社会を勝ち抜けない今、最新技術が直面するサイバーリスクを知り、それに備える重要さは言うまでもありません。 本ムックはサイバー攻撃者が照準を合わせている「AI」「IoT」「仮想通貨」「ビジネスメール」「個人情報」の5大分野について、最新の攻撃トレンドを掲載し、その対策を分かりやすく解説します。 今やサイバーリスクは経営リスクになりました。現場担当者のみならず、経営者やマネジメント層まで必要な知識が全て学べる1冊です。
-
4.0「老後貧乏」はこうして避ける! リタイア後をにらんだ資産運用の安心手法 「リタイア後の生活を支える」ために、資産形成の考え方から、 退職資産を守り、生かしていく方法までを具体的に紹介。 -人的資本(=働いて稼ぐ力)という大きな資産を最大限に生かすには -自分の資産をヘッジするには -リタイア特有のリスクとは -投信、年金保険、ローンなどをいかにうまく組み合わせて使うか…… 人生の「ゴール」が見えてきた世代には、切実なノウハウが 本書にはたくさん入っている。 長年リタイアメントやそれを支える保険商品などを研究してきた学者が、 理論的な裏付けをもってわかりやすく説明。 日米の制度のちがいについては、野村證券の専門家が解説でフォローする。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 経済ってそういうことだったのか! シリーズ累計40万部。『池上彰のやさしい経済学』、ついにマンガ化。 「世の中の経済は、真面目に考え出すと、不思議に満ちています。そんな不思議を解き明かし、 経済について詳しくなりたい。そんなあなたの思いに応えようと、この本が つくられました。 頼りない二人の新入社員の仕事の駄目さ加減を描いたマンガを笑ってみているうちに、 私たちの身の回りの経済を学んでいく構成になっています。(中略) 需要と供給という経済の基礎から始め、アダム・スミスやカール・マルクス、ケインズ、フリードマン など経済学者の学説を知ることで、あなたの経済への見方は大きく変化することでしょう。 まずは基礎から始め、段階を追うにつれ、あなたはいずれ新聞の経済面も理解できるようになるでしょう。 マンガの二人と共に、あなたも成長できるのです。あなたの成長に期待します。 ジャーナリスト 池上 彰(前書きより) ◇『池上彰のやさしい経済学1 しくみがわかる』をマンガ化しました。 ◇基になっている単行本は、実際に大学で行われた経済学の基礎講座をベースにしており、経済学とは縁遠い学生にも理解できるようにやさしく解説しています。マンガ版では、この講義のエッセンスを紹介しながら、オリジナルストーリーのマンガを展開しています。
-
4.0つみたてNISA、iDeCoにも最適。 100年人生時代、一生お金で困らないためのノウハウを満載! 『ウォール街のランダム・ウォーカー』のバートン・マルキールと 『敗者のゲーム』のチャールズ・エリス、 2人のカリスマによる「長期投資のバイブル」を全面改訂。 本書では「Keep it Simple」を合言葉に、その投資手法をKISS Investingと名づけ、 5つのルールをあげている。 -できるだけ若い時から計画的に貯蓄に励む -政府や企業の貯蓄優遇や課税軽減制度を最大限に活用する -インデックスファンドで広範な分散投資を図る -リバランスを通じて資産配分を守り続ける -市場価格の変動に惑わされない このシンプルな投資を実践するための手順を様々な事例やエピソード、 最新のデータを駆使して解説する。 第2版では、データを最新のものにアップデート。 さらに、この投資手法がリーマン・ショックなどの異常事態でも 有効に機能することを検証した。
-
4.0なぜ「アパレル不況」と呼ばれる中でも、ユニクロとZARAは売上をのばすのか? 世界一のファッションチェーンを目指すユニクロと王座に君臨するZARA。 巨大アパレル2社の強さの秘密を徹底解剖! ◆本書は、2014年11月に刊行された「ユニクロ対ZARA」を文庫化にあたり加筆・改訂したものです。単行本発売当時から現在に至るまでのユニクロやZARAの戦略の変化など、両社の最近の動向や他のファストファッションの最新事情も盛り込みます。 ◆フリマアプリ、エアークローゼット、ZOZOSUIT・・・・・・。新サービスの登場で、大手百貨店をはじめ、アパレル産業はますます変化を求められています。中でも、日本と世界の代表的企業、ユニクロとZARAは注目企業です。 ユニクロを展開する、ファーストリテイリングは2017年9~11月期連結決算の純利益が前年同期比13%増の785億円と好調です。一方、売上高3兆円に迫るアパレル世界最大手、インディテックスもトップの座に君臨しています。本書では、両社の特徴や思想、企業文化、成長戦略などを比較してそれぞれの強さの秘密を読み解きます。 ◆若い世代のファストファッションの中でも、「ユニクロ」と「ZARA」は特に人気です。しかし、ベーシック商品を中心に据えるユニクロと、流行をいち早く取り入れるZARAの商品戦略の違いが影響し、消費者も堅実派と積極派におおむね二分されています。こうした消費者の嗜好の違いは、対照的な両社の戦略に大きく紐付いており、本書で解説します。2社を軸に、「H&M」「Forever21」をはじめとした有力アパレルの動向も盛り込み、この一冊で業界全体が俯瞰できます。 ◆著者はファッション流通コンサルタントの齋藤孝浩氏。日経ビジネスや日経MJでも、アパレル分野で頻繁に取材を受けているほか、繊研新聞や業界紙への寄稿も多く、近年は明治大学、青山大学等でファッションビジネスに関する講義も受け持っています。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 これで「ダマシ」を回避! テクニカル指標にはそれぞれ強みと弱みがあります。 あるひとつの指標に頼ったのでは、 売買判断にも限界が出てしまうのです。 だからこそ「組み合わせ」が重要です。 指標を組み合わせ、 弱点を補い合うことで「ダマシ」の回避につながります。 本書は、 ●テクニカル分析の基本的考え方 ●トレンド系指標・オシレーター系指標の強みと弱み ●局面・トレードスタイル・銘柄規模別の最適な組み合わせ術 ……を豊富な事例とともに説明していきます。 □主力株の急騰時・急落時には「移動平均線×MACD」 □中期投資には「移動平均線×ストキャスティクス」 □新興市場銘柄には「ボリンジャーバンド×MACD」 ……など、ぜひ本書を通じて、 ご自身の「最強の組み合わせ術」を発見してください。
-
4.0「人生っていうのは一度きり。どうせなら一国一城の主に なってみたいと、誰もが心の底で思っているんじゃないだろうか。 でもさ、それって難しいことじゃないんだよね。 大会社の社長になるなんていうのはムリでも、小さな店の主だったら誰にでもなれる。 それで、一生楽しく商売続けられる」(「はじめに」より) 繁盛店をつくる武器は、 本当においしい料理が三品あれば十分。 誰もが好きな定番のメニューに力を集中し、 「あきず」に「やめず」に「変わらず」続ければ、 街で一番の繁盛店には誰でもなれるのです。 一国一城の主になれる繁盛店づくりの基本。 店づくり、接客、人材育成から商品づくりまで、 コーヒー屋、「汁べゑ」をはじめとする居酒屋など外食業一筋50年の 楽コーポレーション 宇野隆史社長が語る 背伸びせずに続けられる小さな商売のコツ。 『トマトが切れれば、メシ屋はできる 栓が抜ければ、飲み屋ができる』 『笑う店には客来たる 楽しむ人には福が舞う』(いずれも日経BP社) に続く、“居酒屋の神様”宇野社長による5年ぶりの新著。 前著2冊は、韓国語などの翻訳版も出版され、 韓国語版は2冊の累計で16万部超の大ヒットを記録。 大企業を退社して第二の人生を歩み出す多くの開業者に勇気を与えました。 SNS(交流サイト)などの口コミや写真のきれいさで 飲食店のはやりすたりが決まるといわれる今の時代でも、 長く続く小さな商売に一番大事なのは、どれだけお客さんに楽しんでもらえるか。 宇野氏が考える繁盛店の基本は、時代にも地域によらず大事なことばかりです。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、これからデジタル化を担うエンジニアが知っておきたい基礎から応用までを、4分野で解説します。マイクロサービスアーキテクチャーなど最新のアプリ開発手法を学ぶ「アプリ開発の最新手法」、AIやIoT活用の勘所がわかる「AI&IoT活用の最前線」、クラウドの選択、活用スキルが身につく「最新クラウド活用術」、プロジェクト管理手法の最前線を知る「デジタル化で変わるプロジェクト管理」に分けて学びます。
-
4.0『100年に一度の変化』は、脅威ではなく好機 日本の自動車産業は何に注力すべきか、2030年に向けた 成功への道筋を明らかに 「日本の自動車産業の強み・弱みを正確に把握し、 欧米中の打ち手を理解し、この大きな変化に適応することができれば、 日本の自動車産業は新しい発展を遂げることができると確信している。」 (第5章本文より) 【主な内容】 プロローグ 100年に一度の変化にどう対応するか 第1章 パワートレーンの電動化 製造・販売に変革を迫る 第2章 自動運転 無人化のその先へ 第3章 シェアリング 世界で急拡大する「所有から利用へ」 第4章 コネクテッド化 新たなビジネス機会を生み出す 第5章 2030年の競争軸とは EV・自動運転の開発競争を超えて
-
4.0「他にやりたいことがあるので…」 「留学します」 「家庭の事情で」 ――退職する社員が会社に本音を告げる事は少ない。 だからこそ、「優秀な若手が辞めてしまう」という悩みを持つ企業は、本質的な解決に至ることがなく、同じ事をくりかえします。 ただでさえ人手不足のいま、企業の競争力を大きく削ぐことになりかねません。 そこで本書では、 「入社当初からいずれ転職するつもりだった」 「将来が見えない、『こんな風になりたい』という先輩がいない」 「労働と給料が見合わない」…… など、会社を辞めた若者の本音を聞き出しながら、 どうすれば、優秀な社員を定着させる事ができるか、リテンション(定着)マネジメントのポイントを示します。
-
4.0衝撃の監督交代、日本代表はどうなるのか! 緊急対談も盛り込み、サッカーを知的に、深く語り尽くす。 ロシアW杯の行方はどうなるのか。各国の戦力、戦術分析、組み合わせの妙などを交え徹底分析! 日本代表の監督交代を受け、緊急対談も実施。どうすれば日本は世界の頂点に立てるのか。タブーを排し語り尽くす。 VAR(ビデオアシスタントレフェリー)など、新たなテクノロジーがサッカーをどう変えるのか。未来も分析。 準優勝した99年ナイジェリア・ユースで「勝てた理由」は、実は食事にあった!? コーチとして参加した当事者がいま明かす真実なども交えながら、ピッチの外、チーム運営の環境が試合結果にもたらす影響なども深く突っ込んで語られます。 W杯では、なぜ自国監督が有利なのか。ドイツなど、継続的に強い国、チームは何をやっているのかなども多角的に分析。日本がW杯で頂点を目指すために必要な取り組みも知的に解説します。 強くて、上手い選手が、献身的にチームプレーに徹するようになったブラジルなど、最新情勢も分析。世界のサッカーの潮流が分かりやすく説かれ、サッカー観戦が今以上に楽しくなります。
-
4.0■クリステンセン教授など大物が大絶賛! 「大企業になっても成功しつづけるにはどうすればいいのかを研究してきたが、まさしくその実践的ガイドとなるのが本書だ」 クレイトン・クリステンセン(『イノベーションのジレンマ』著者、ハーバード・ビジネス・スクール、キム・B・クラーク記念講座教授) 「最先端を行きたいと考えるリーダーなら、この本の内容をじっくり身につけなければならない。 本書は、大企業から家族経営の零細企業や非営利組織にいたるまで、先進的な組織にとって、今後何十年も必須の道しるべとなるだろう」 ローレンス・サマーズ(チャールズ・W・エリオット記念講座教授、元米国財務長官) 「大企業がスタートアップのようになるにはどうすればいいのか……いや、その企業が生まれた当時の集中力や熱気を取りもどすには どうすればいいのかと言うべきか。そのやり方を示すのが本書である」 マーク・アンドリーセン(アンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者兼パートナー) ■GE、トヨタなど大企業、ドロップボックスやエアビーアンドビーなど豊富な事例 GEやトヨタがいかに「スタートアップ・ウェイ」で組織を生まれ変わらせたのか? 「俺たちが作っているのは、すぐに修正できるようなソフトウェアと違うんだ」 当初は大企業の社員、役員に大きな反発を受けながらも、著者エリック・リースは組織、社員の思考、人事制度も変革していく。 その生々しい事例とともに、スタートアップ・ウェイの実行方法が手にとるように理解できます。
-
4.0○日本の債務はついに1,000兆円の大台を突破。いまや、財政破綻は「起きるか、起きないか」ではなく、「起きたらどうなるのか」「どう危機をしのぐのか」を考えるべき時に来ている。デフレが終わり、金利が上昇期を迎えれば、財政赤字問題が一気に悪化する懸念があるからだ。「財政破綻」が実際に起こったら日本経済は一体どうなるのか? どのような危機対応策をとるべきなのか。 ○本書は、「財政危機時のトリアージ」、財政破綻後の「日本銀行の出口戦略」「公的医療と介護・福祉」「長期の財政再構築」「経済成長と新しい社会契約」といった重要課題を取り上げ、日本経済・財政の再生への道を探る。 〇切迫した状況のもとで、国家の運営に支障を来さないように何をするのか、何を守り、どう再生するのか。政策の優先順位が厳しく問われるが、そのシナリオ分析は、財政破綻そのものを回避するための方策を考える上でもヒントを提供する。 ○編著者の小林慶一郎氏はじめ、小黒一正(法政大学教授、財政・公共政策)、左三川郁子(日経センター主任研究員、金融政策論)、小林庸平(三菱UFJリーサーチ&コンサルティング経済政策部主任研究員、公共経済学)、佐藤主光(一橋大学教授、財政)、松山幸弘(キヤノングローバル戦略研究所研究主幹、社会保障)、森田朗(津田塾大学教授、行政学)と、経済・財政・社会保障の専門家が執筆。
-
4.0改めて知る、6つの事件 自らの経営体験からまとめた 必ず身につけ、実行すべき日々の心得集 リーダーの条件として、宮内氏が書き留めてきた10カ条を初めて公開し、 その内容を詳しくまとめました。 大企業に勤めていて、いずれは経営陣を目指す管理職や若手社員、 またベンチャー企業の経営者や起業家らに向けて、イノベーションを起こす経営、 持続的に発展する組織とはどのようなものかを10カ条を基に詳しく解説します。 ≪主な内容≫ 【はじめに】 リーダー論をまとめた10 カ条 【第1条】 鼓舞・激励し総力で 【第2条】 熟考する 【第3条】 照準を絞り注力する 【第4条】 代表する 【第5条】 経営者としての自覚を常に持つ 【第6条】 人材育成・活用 【第7条】 存続と継続 【第8条】 グランドデザインを描く 【第9条】 マクロ観を身に付ける 【第10条】 向上心を持つ
-
4.0「M&Aは総合格闘技」 「M&Aは売りから入れ。買いはマイナスからのスタートだから」 日本のM&Aが本格化した1990年代から2000年代半ばにかけて、主要プレーヤーとしてM&Aをリードしたゴールドマン・サックスの辣腕アドバイザーの著者が、 自らが手がけた多くのM&A案件の内実を初めて明かした稀有のノンフィクション。日本のM&A20年史でもある。 ゴールドマン・サックスのニューヨーク修行時代から、内外の大物経営者との出会い、社内でのカネ・政治・出世競争などの知られざるエピソードを数多く描く。 日産自動車、三菱自動車、ダイムラー・クライスラー、日立製作所、DDI、KDDなど数多くの企業が登場。M&Aアドバイザーからみた日本経営論にもなっている。 著者が手がけた大型案件の代表的なものは以下の通り。 ●DDI・IDO・KDD社合併 ●ロッシュによる中外製薬買収 ●NKK・川崎製鉄経営統合 ●GEキャピタルの日本リースのリース事業買収 ●ダイムラー・クライスラーの三菱自動車への資本参加 ●日立製作所によるIBMのHDD事業買収 ●三菱商事のローソンへの資本参加など。
-
4.0Googleが提供するクラウドサービス AWSとの違いを軸に徹底解説 「Google Cloud Platform」(GCP)は、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureと同じく、企業向けのクラウドサービスとして提供されている。後発であることは否めないが、後発であるからこその特徴を備えている。 一般的な用途では「マネージドサービス」の充実が特徴と言える。そのほか、今注目の「機械学習」「ビッグデータ」関連のサービスが特に充実しており、AI関連のシステム基盤として要注目であることは間違いない。 本書では、「コンピューティング」「ストレージ」「ネットワーキング」「ビッグデータ」「機械学習」「アカウント管理」「運用監視」という7つのカテゴリーに分類し、GCPの特徴を、AWSとの違いを軸に解説している。 また、GCPのサービスを解説するほか、エンタープライズ用途のユースケースに基づいて、GCPを用いた設計ガイドをまとめている。技術力に定評のあるGoogleのクラウドサービスを検討するのに最適な1冊である。
-
4.0Googleが知ってる“あなた”は誰? 検索履歴やスマホの位置情報から自動的に生成され、 刻々と変貌しながらデジタル空間をさまよう「データの幽霊」 (=デジタル・アイデンティティー)の正体に迫る! アルゴリズム解析を前にすると、「私たちが何者なのか?」という問いは、「コンピューターは私たちを何者だと言っているか?」という問いに等しくなる。アルゴリズムによって「セレブリティー」とされたり「信用できない」とされたりするのと同じように、生身の個人としての自分を無視された私たちは、自らの生をコントロールできなくなる……。[序章より] ……著者は述べる。「私たちは、私たちの実在がもっぱらデータである世界に生きているわけではなく、私たちの実在がデータによって拡張される世界に生きている。つまり、私たちはすでにデータでできている。…テクノロジー派未来主義者の言うシンギュラリティーは決して訪れない。なぜなら、すでにここにあるからだ。」 肉体の死を超えて、自我や意識がサイバー空間の中で「生き続ける」というファンタジーは、すでにデータとなって漂流している私たち自身の迷妄である。ひとつだけ確かなことは、私たちが実在の死を迎えても、私たちの個人データはサイバー空間を漂い続けるということだ。[武邑光裕氏・解説より]
-
4.0人工知能(AI)やIoT、ビッグデータにまつわる技術の進歩はとどまるところを知らず、「当社でもAIを使って何かやらねば時代に取り残される」と焦ってしまいがちですが、AIであろうとIoTであろうと、テクノロジーをただ導入しただけで何かすごいことが起きるわけではありません。技術の進歩を企業経営に活かすという点ではっきりしていることは、「テクノロジーに振り回されてしまう企業」と「テクノロジーをしたたかに使いこなす企業」に大きく分かれるということです。 本書の筆者はITコンサルタントとして30年の経験があり、「IT」が経営の現場でどのように使われてきたのかをつぶさに見てきました。その経験から、「振り回され社長」はいかにして振り回され社長となり、「したたか社長」はいかにしてしたたか社長になったのかを、わかりやすく解説しています。ITで起きたことは、AI・IoTでも繰り返されるでしょう。 筆者は「多くの会社でテクノロジーを経営に活かしてほしい」と願っています。そのために、ITでの経験を踏まえた、テクノロジーを活かす経営メソッドを本書で詳しく解説しています。それは企業規模によらず実践でき、どのような企業にも参考になります。 ポイントは、結果が出てから「次はどうする」とフィードバックするのではなく、結果が出る前に、結果に影響を与える先行データに着目し、そのデータを基に現場に働きかけるのです。それを「フィードフォワード」と呼びます。「過去」(=確定した業績)は変えられないですが、「未来」(=今期の業績)は変えられます。テクノロジーの使いどころも見えてきます
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 戦前に建てられた「プレモダン(モダニズム以前)」の名建築50件をイラスト・写真・文章でリポートします。 建築の知識があってもなくても楽しめる、建築に出会う旅に誘う1冊です。 特別対談:井上章一(国際日本文化研究センター教授)×磯達雄(建築ジャーナリスト) 「隈、妹島はコンドルの上に花開いた」 戦後建築を理解するために知っておくべき明治~終戦の建築家10人 ■主な内容 PART1:明治期 富岡製糸場(オーギュスト・バスティアン)/旧済生館本館[現・山形市郷土館](筒井明俊)/旧札幌農学校演武場[現・札幌市時計台](開拓使工業局・安達喜幸)/手宮機関車庫3号(平井晴二郎)/道後温泉本館(坂本又八郎)/京都国立博物館(片山東熊)/旧岩崎久彌邸(ジョサイア・コンドル)ほか PART2:大正期 東京駅丸の内駅舎(辰野金吾)/梅小路機関車庫[現・京都鉄道博物館](鉄道院・渡辺節)/旧秋田商会(秋田寅之助)/函館ハリストス正教会(河村伊蔵)/名和昆虫博物館(武田五一)/旧京都中央電話局西陣分局舎[現・NTT西日本西陣別館](逓信省・岩元禄)/自由学園明日館(フランク・ロイド・ライト)ほか PART3:昭和期 一橋大学兼松講堂(伊東忠太)/聴竹居(藤井厚二)/イタリア大使館別荘(アントニン・レーモンド)/甲子園ホテル[現・武庫川女子大学甲子園会館](遠藤新)/綿業会館(渡辺建築事務所/渡辺節、村野藤吾)/東京中央郵便局(逓信省/吉田鉄郎)/横浜市大倉山記念館(長野宇平治)ほか
-
4.0今、何を学び、どう生きるのか 時代を理解し、本質を見極めるために。 あなたがあなたらしく生きるための、「学び方」・「働き方」・「生き方」 池上先生と一緒に考えてみませんか。 「高校では知識を覚えることばかり……これで教養は身につくの?」 「受験勉強や部活に追われ、心の豊かさを見失っている」 「池上先生のように多くのテーマを考え話せるようになるには、どのようにアンテナを張ればいい?」 「最近は論文しか読んでいないんです……」 「大学を出てからも勉強したい」 「アメリカという国をどのように理解すればよいのでしょうか」 「日本企業の不祥事が相次いでいますが、経営は大丈夫?」 いま、国内外で不穏な空気と不透明感が広がる出来事が多く起こり、 私たちの未来への不安は増えていく一方のように感じられます。 本書では、世界・日本で「いま何が起こっているのか」を若者たちの質問を交えてわかりやすく解説しながら、 私たちはどうすればよいのか、時代を理解し物事の本質を見極めるための「学び方、働き方、生き方」を 池上先生が一緒に考え、伝えていきます。 ジャーナリストと教育者、筆者が持つ2つの顔がうまく溶け合った 悩める若者たち、未来を生きていく私たちへ贈る、池上彰の「生き方」講座。 池上氏の温かなまなざしとメッセージが一冊に詰まった、 日本経済新聞の朝刊・電子版の連載コラム「池上彰の大岡山通信 若者たちへ」の書籍化第4弾。
-
4.01回の営業で成約! お客さまの心をつかんで、 YESと言ってもらえる 伝説の“即決アプローチ”を初公開! 著者ならではの軽やかな文章で、 「売れる営業」の本質がわかる! 「新人時代とやっていることが変わっていないのでは?」 と悩んでいる営業担当者におすすめ! 【著者からひとこと ~「はじめに」より】 別に出し惜しみをしてきたわけではないのですが(苦笑)、 この必殺技はどちらかというと テクニックやノウハウを超えた要素が多いので、 文字にして説明してもわかりにくいのでないか? と懸念し、 なかなか書けなかったわけなのです。 (~中略~) とにかく この「YESの9割」が決まるという フロントトークを使えるようになれば、 もっと楽しくお客様に感謝されながら 結果を出すことができるようになります。
-
4.0子どもたちを真のデジタルネイティブである「クリエイティブ・シンカー」(創造的思考力・発想力を身に付けた人)に育てるにはどうしたらよいのか――。 そのために、大人たちはどのように振る舞えばよいのか――。 プログラミング言語「Scratch(スクラッチ)」の開発者が世に問う、人生100年時代の新しい教育論。 世界が、子供だけでなくすべての人にとっての創造的な思考と学びの大切さについて理解し始めるにつれ、メディアラボにおけるミッチの役割とライフロング・キンダーガーテン・グループの取り組みは、ますます重要になっています (中略) ミッチが掲げる4つのPの原則(Projects, Passion, Peers, Play)は、メディアラボの大学院生の教育プログラムはもとより、世界中で数百万の子供たちが利用しているプログラミング環境(言語でありコミュニティでもある)スクラッチ(Scratch)の基盤となる考え方です。 (中略) 私の願いは、この本が「急速に変貌する世界で生き残るためのコンパス」としての役割を果たすことです。 ――日本語版序文より この本は、子供、学び、創造性を気にかける人たち、子供たちのために玩具やアクティビティを選ぼうとしている保護者たち、生徒が学ぶ新しい方法を探している教育者たち、新しい教育体制を取り込もうとしている学校管理者たち、子供のための新しい製品やアクティビティを生み出そうとしている開発者たち、あるいは単純に子供、学び、そして創造性に興味を持つ人たちに向けて書かれています。 ――第1章 創造的な学びより
-
4.0ソフトバンク、アマゾン、ベネッセ、HIS…… 「生き残る会社」は、時代にあわせて稼ぐ事業を変えていた。 決算書で見抜くあの企業が儲かる理由! ◆決算書は企業戦略を写す鏡。本書は、経営環境の激変を受けて、自らの姿を変え続ける企業を分析するための「決算書の読み方」について解説。なぜ、その事業を選んだのか、そのビジネスでどう稼ぐのか。リスクや将来性を見通すには……実際の決算書を使いながら、ポイントを押さえてわかりやすく説明します。 ◆ソフト流通からブロードバンド・携帯、そして投資会社へと変わり続けるソフトバンク。先行投資で赤字のEコマース事業をクラウドで支えるアマゾン。少子化で減収に悩む教育産業から介護へと軸足を移すベネッセ。ネット時代に、あえて「変なホテル」「ハウステンボス」などのリアルで稼ぐHIS。本書で取り上げるのは、最近話題の企業・ケースがメインです。興味深く読み進めながら、安全性・成長性分析、時系列・業種間比較、業界特有の指標といった、ひととおりの経営分析の基本知識を身に付けることができます。 ◆初心者でもわかるよう、実際の決算書のデータを使いながら、注目のポイントや見方を解説。前作の『ヤバい決算書』のように丁寧な解説をこころがけます。 本書で取り上げる企業・・・・・・アマゾン、楽天、ソフトバンク、富士フイルム、日立造船、HIS、ベネッセHD、サッポロHD、イオン、ライン、クックパッド、フジ・メディアなど。
-
4.0■昔のほうが、生活は豊かだった。社会の中間層には経済的活力があり、社会インフラはきちんとメンテナンスされていた。だが、その後何十年にもわたって経済成長率は大きく鈍り、中間層の時間当たり賃金は減少する一方で、CEOの賃金は10倍になった。富の格差は広がる一方だ。 ■「経済学の父」とされるアダム・スミスは、自由な市場はすべての人にとっての最善を生み出すと考えた。だが、現実世界を見回すとスミスの「見えざる手」が機能していないように思える。むしろ、ダーウィンが観察したように、個々の動物の利益と、種としての大きな利益は深刻に対立している。 ■このダーウィンの観察を、経済に応用したら、どんな世界が見えるだろうか。個人の利益と、社会全体の利益は、どうやってバランスさせればよいのだろうか。格差、教育、公共投資、貧困といった諸問題に対し、人気経済学者が解決策を提示する。
-
4.0民は国の本 吏は民の雇 武士の時代の終わりを見通し、財政・藩政の立て直しと近代化に生涯を捧げた男。 「幕末の風雲児」のもう一つの顔に迫る。 ◆越後の英雄のもう一つの素顔 河井継之助というと、戊辰戦争で新政府軍相手に善戦しつつも非業の死を遂げた悲劇の武士というイメージが強い。司馬遼太郎の歴史小説『峠』で好漢として描かれたことにより今なお人気も高い人物であり、彼を取り上げたノンフィクション、フィクションも数多出版されている。しかし実は、戊辰戦争に至るまでのその人生はほとんど知られていない。 河井は「維新の三傑」西郷・大久保・木戸のように、京都を舞台に政治活動に奔走したわけでも、坂本龍馬のように、脱藩して活動の場を広げることもなかった。権力闘争に狂奔する中央政界の動向からは距離を置き、あくまでも長岡藩にとどまったうえで、欧米列強を模範にその富国強兵に邁進した。一言で言うと近代化である。 ◆未来を見越し近代化に尽くしたその生涯を描く 継之助の人生は、いわば長岡藩の官僚として財政そして藩政を立て直すことに捧げられた。来るべき近代日本を見通し、その魁の役割を長岡藩に担わせようとした。西洋の事情に通じた開明派藩士で、明治政府の近代化政策を先取りした人物だった。 本書は、幕末の解説で定評ある筆者が、明治維新、つまり河井継之助没後150年を迎えるに際し、戊辰戦争と結び付けられがちな河井の生涯を読み直すことで、その歴史的役割を解き明かすもの。時代の変わり目、財政の立て直し、官と民のあり方など、その目指したものは、今日の日本にとっても大いに参考にすべきものがある。
-
4.0企業が被るサイバー犯罪の被害総額は世界で推計47兆~63兆円。 デジタルビジネスに取り組む中で、経営者はサイバーリスクとどう向き合い、どうマネジメントしていくべきか――。 100%の防御が不可能となった今、身代金を要求するランサムウエア「WannaCry」をはじめ、大量の情報漏洩を企む標的型攻撃、一瞬にして数億円を横取りするビジネスメール詐欺など、様々なサイバー脅威が企業を襲っている。 一方で、サイバーセキュリティは新旧・複数の技術に横断するだけでなく、政治や犯罪、国内外での企業の連携など様々な要素が複雑に絡み合っている。 結果として、サイバーセキュリティは多くの経営者にとって、とっつきにくいテーマになっている。 政府が「サイバーセキュリティは経営リスク」と叫んでも、実態として新しいリスクのコントロールは難題のまま横たわっている。 本書はサイバーセキュリティに問題意識を持ちながら、複雑さゆえにとっつきにくさを感じている経営者に向けた「経営書」である。 筆者の横浜氏は通商産業省(現経済産業省)からマッキンゼー日本支社に転じ、現在はNTT持株会社でサイバーセキュリティのスポークスパーソンを務めている。 18年間に及ぶマッキンゼー時代のコンサルティング経験と、現職での国内外のサイバーセキュリティ関連カンファレンスでのパネリストなどを通じた幅広い見識とを組み合わせ、筆者は様々なサイバーセキュリティの課題を経営者目線で解説する。 サイバーセキュリティでマネージすべきリスクはデジタル化したコーポレートリスクである。新たなリスクに向き合う経営者にぜひ読んでいただきたい。
-
4.02010年6月に河出書房新社から刊行された『ワインの歴史』を改題、改訂し、文庫化しました。 ワインはメソポタミアに始まり、 エジプト、ギリシャ、ローマを経て、 欧州、世界へどのように広がったのか? 旧約聖書と新約聖書のワイン記述の違い 130種類以上のワインがあった古代ギリシャ ワインはローマ軍の必需装備だった ブルゴーニュワインはシトー派修道院が源流 ナポレオン三世が「格付け」を作らせた --等々、ワインのことをあまり知らない読者も 楽しく読むことができる歴史読み物です。 文庫化にあたっては第10章を改訂し、文庫あとがきを加えました。
-
4.0■OKRとは? OKRは、Objectives and Key Resultsの略。目標の「O」(Objectives)と主な結果の「KR」(Key Results)を設定する最も注目されているフレームワーク。大きな目標「O」と具体的な数値目標「KR」を組合せることで、目先の数字に振り回されず、やる気が出て、生産性が断然上がります。 ■前半は物語、後半はノウハウですんなりわかる! 本書の構成 <前半>シリコンバレーのスタートアップの物語 高級レストランなどに高品質の茶葉を販売するスタートアップ「ティービー」が舞台。資金調達は成功したものの、売上が伸びず、創業者同士がぶつかり、社員の不満が募る。そのときにエンジェル投資家の勧めで、ティービーに導入されたのがOKRだ。OKRの設定や運営でつまづきまくるが、やがて社内の全員が変わってくる――。 <後半> OKRの設定から運営まですべてのノウハウを紹介。成功の法則、よくあるOKRの失敗例も紹介。 ■OKR「成功の法則」 ・目標「O」はひとつ、主な結果「KR」は3つくらいにする ・KRは「難しいが不可能ではないもの」にする。簡単すぎると意味がない、不可能ではやる気がなくなる ・OKRはポジティブな表現にする。チームを脅してはダメ。 ・3カ月単位で運用、でも毎週の振り返りは必ず! ・月曜日に進捗をチェックしてコミットしよう ・金曜日の「ウィン・セッション」で成果を見せ合えば、ほかの人の仕事も理解できるし、来週のやる気にもつながる!
-
4.0☆地名、歴史、鉄道、食べ物…日頃見過ごしがちな、さまざまな謎に迫り、好評を博している日経電子版の好評企画、「東京ふしぎ探検隊」より人気の鉄道テーマを中心に、地理、五輪などにも話題を広げ、待望の書籍化。 ☆「新幹線、幻の東北・東海道直通計画」「池袋駅、東は西武で西、東武のナゾ」「東京と千葉の領土問題とは何か」「吉祥寺駅と町田駅は、かつて神奈川県だった」「大塚の北にある南大塚のナゾ」など、大きな反響が寄せられた鉄板ネタを厳選、大幅な加筆、連載記事ではかけなかった秘話なども交えて詳しく、楽しく解説します。 ☆図版や写真、イラストも満載。コンパクトな新書サイズなので、旅のお供に最適の書籍です。
-
4.0〇情報通信技術は世界の姿を一変させ、さらにグローバル化は進む。保護主義は時代錯誤だ。貿易ではなく、知識のフローの変化こそが重要なのだ。いまこそグローバル化の真実に目覚める時だ――。本格派国際経済学者が放つ話題の書。 〇人類史上のグローバル化の歴史を整理し、産業革命以前を「グローバル化前史」、産業革命以降、1990年以前を「オールド・グローバリゼーション」、90年代以降を「ニュー・グローバリゼーション」と名づける。産業革命以降のグローバル化により、先進国と新興国という「大いなる分岐」が進んだ。しかし、90年代以降のコミュニケーション技術の進歩により、モノ、アイデアの移動の制約が著しくなくなり、グローバル・バリューチェーン革命により、グローバル化の質が大きく変化、世界の富の分布が変わり、G7諸国と一握りの新興国との経済は収斂しつつあると論じる。そして、さらなる情報テクノロジーの進歩により、ヒトの移動さえ制約が解消されるグローバル化の未来を大胆に展望します。 〇最新の国際経済学の研究をもとに、収斂が進むグローバル化のリアルな姿を、豊富なデータ、日本をはじめとする各国の経験をもとに説得力豊かに描き出します。また、従来の比較優位理論や貿易政策・産業政策はもはや有効ではない、と説きます。世界の現実を理解するうえで欠かせない必読書です。
-
4.0“マクロン大統領誕生”を2年前に予測。 フランス文化の強さと弱さを解剖する。 学校・家庭での「人の育て方」と「成熟したオトナ文化(センシュアリティ)」の土壌づくり。 教育無償化、少子化対策、グローバル人材育成など、日本が直面する喫緊の課題へのヒントが満載。 ミシェル・ウエルベック『服従』が描く近未来とは異なるフランスの実相。 ◆「試験に選択問題はない」「100点満点ではなく20点満点」「鉛筆を使わずボールペンと万年筆」「数学の答案に“技術点”」「給食も収入によって値段が変わる」「子どもには残り物を! 」--日本とまったく違うフランスの教育と子育て。芸術や文化、学術などで、いまなお世界をリードする人材はどこから生まれるのか。 ◆在仏20年、パリで3人の男の子を育てた皮膚科医が、フランスのエリート教育や子育てをエピソードを交えて紹介する。日本の親にとっても、子どもを一流の人物に育てる上で、参考になる点がふんだんにある。フランス流の成熟したオトナ文化に関心を持つ多くの読者への示唆にも富む。
-
4.0流産して知った、妻の気持ち。 絶対に産むと決めていた、夫の子ども。 矢沢心・魔裟斗夫妻が、自らの経験とともに語る これから治療に臨む人へ伝えたい想い 4年にわたる山あり谷ありの不妊治療を夫婦で乗り越え、 2児の母となった女優・矢沢心さんと、 夫で格闘家・タレントの魔裟斗さんが 自らの経験を語りながら、これから治療を始める人、 現在治療中の人にエールを送ります。 治療を進めるなかで孤独感や不安を抱えることも多い不妊治療。 でも、夫婦で静かに寄り添い合い、気持ちを共有することで 乗り越えられた経験があるからこそ、同じ立場にいる人を応援したい。 そんな二人の想いがこもった1冊です。 ------------------------------------------- 「私たち夫婦は、不妊治療に一縷の望みをかけ、共に歩んできました。 出口の見えないトンネルを、長い間さまよっていました。 今振り返ると、こうして無事子どもを授かることができたのは、 奇跡のような道のりだったと感じます。 今も、授からなくて悩んでいる人はたくさんおられると思います。 そんな人たちに、不妊治療へ臨むことに抵抗や不安を感じて、 足踏みするようなことはしてほしくありません。 勇気を持って、前へ一歩、踏み出してほしいのです。」 (「あとがき」より抜粋) -------------------------------------------
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スマートフォン(スマホ)の高性能化・多機能化が加速していますが、 初期設定のままでは不要な設定やアプリが満載。 設定の変更やムダの削除、本当に必要なアプリの導入といったカスタマイズをしないと、 せっかくのスマホも使いやすくはなりません。 そこで本書では、最新の初期設定変更方法やお薦めのアプリを一挙に紹介。 ほかにもパソコンとスマホを連携させて便利に使う方法など、 仕事にも趣味にも役立つスマホの最新情報を1冊にまとめました。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 定評ある「ひと目でわかるHyper-V」に2016版が登場!Windows Server 2016版Hyper-Vの導入・管理の基本操作をステップバイステップ形式でわかりやすく解説します。2016の新機能である「Nested Hyper-V(Hyper-Vの入れ子)」と「Nano Server」もしっかりカバー。Hyper-Vを評価したい情シス担当者、サーバー管理者、SE、営業担当者などの皆様にお勧めします。
-
4.0未来予測に定評のある 野村総研のアナリストが 先端テクノロジーが与えるインパクトを先読み! 【本書で取り上げられる主なテーマ】 ・AI(人工知能)はホワイトカラー業務をこなせるか? ・自動運転で激変するバリューチェーンと自動車関連ビジネスの未来 ・進化する音声操作、「ボイス・ファースト」の時代がやってくる ・チャットボットがポータル、検索エンジンの次のウェブの玄関になる ・VR/AR/MRはキャズムを越え「ポスト・スマホ」になれるか ・バイオメトリクス認証は生活をどう変えるのか ・センシングはモノから人へ。「究極のおもてなし」は実現するか ・ブロックチェーンの「使いどころ」を考える
-
4.02030年の自動車産業はこうなる! 進化の方向性を新たな視点で提示 現在、自動車産業は100年に1度の大変革期にある。世界の自動車産業は今後、どのように進化するのか。進化のけん引役になるのは、「自動運転」と「次世代型モビリティーサービス」である。将来の無人運転を視野に入れた自動運転技術と、カーシェアリングやライドシェアリングなどの次世代型モビリティーサービスが融合することで、自動車産業の姿は大きく変わる。 それは、クルマの価値が「所有」から「使用」にシフトするという使い方の変化にとどまらない。クルマを開発・生産することで利益を得るという現在のビジネスモデルが、根本から崩れる可能性を秘めている。 日本の自動車産業は、不連続で急激な変化への対応が苦手であると言われる。しかし今後は、自動運転や次世代型モビリティーサービスの動向に注意深く目を凝らし、その変化に備えることが求められる。 2030年の自動車産業の姿を予測するのは非常に難しい。言い換えれば前提条件の置き方によって、自動車産業の将来像はどのようにでも描ける。本書では、自動運転技術と次世代モビリティーサービスに焦点を当て、それらの普及シナリオの描出と、既存事業へのインパクトの評価を試みた。 具体的には、各国における前提条件をできる限り多面的に考察し、その違いを踏まえた形で、新たに生まれるサービスの普及シナリオを骨太、かつできる限り詳細に描いた。さらに現在の自動車産業へのインパクトを評価し、変化への対応策を提言した。自動車産業に携わる方にとって必携の一冊である。
-
4.0Uber(ウーバー)とAirbnb(エアビーアンドビー)――とんでもない破壊者たちの闘争と熱狂の全軌跡! ベストセラー『ジェフ・ベゾス 果てなき野望』著者、ブラッド・ストーンの最新作 2社ともまだ創業から10年未満。しかし、2社合わせた会社評価額は10兆円とシリコンバレーでもまれにみるような成長を遂げている。 UberとAirbnbはいかにして、成功をつかんだのか? 世界各国、各都市での規制との戦い、既得権益を握る企業との闘争、次から次へと現れるライバルたちとの競争、そしてユーザーやコミュニティの熱狂、さらにはUberのカラニックCEO解任。 アメリカのテクノロジー記者として圧倒的な取材力を誇る著者が、その全真相を描く。 ■UPSTARTとは? UPSTART(アップスタート)とは、成功を収めた人物で、経験豊富な年長者や確立された手法をあまり尊重しない者のこと。そう、シリコンバレーの破壊者たちのことだ。 彼らは製品をめちゃくちゃ磨きあげ、大勢のユーザーを味方につける。そしてどんどん成長する。 時として冷徹に。場合によっては倫理を若干犠牲にしながら。 規則を守って慎重になりすぎたら、ライバルに負けてしまうのだ。 ■創業者たちのことば ブライアン・チェスキー(Airbnb創業者兼CEO) 「とにかく早く成長すること。レーダーに引っかからないくらい小さいか、制度として認められなくてはいけないくらい大きいかのどちらかでいたい」 トラビス・カラニック(Uber創業者兼前CEO) 「実際に成功するまでは成功しているふりをするんだ」
-
4.0
-
4.0自ら動き、考えるITエンジニアが巨大なWebサービスを支える そんなリクルートテクノロジーズの内幕を当事者が語ります 国内最大級のリクルートのWebサービスを支えるテクノロジー企業、リクルートテクノロジーズ。そんな同社で活躍するITエンジニアは、自ら動き、自ら考えることで、自走する組織を作り上げています。同社に所属する、あるいは新天地に向けて卒業した約30人に上るITエンジニアのリアルな活躍を、同社の執行役員CTO(最高技術責任者)である米谷修氏が筆致軽やかに描き上げたのが本書です。 同社のエンジニアの活躍を、(1)強い当事者意識を持ってチャンスをつかみ取り、成長するエンジニアの軌跡を追った「挑む」、(2)テクノロジーの力を信じて限界を突破するエンジニアの活躍に迫る「創る」、(3)時には触媒となって異分野を繋げ、融合する。そんなエンジニアのチーム力の根幹を見る「繋ぐ」、(4)自走する方向を見失わず、時に軌道修正できるバランスを生み出すエンジニアのセンスを知る「調える」――の4章に分けてエンジニアの活躍を紹介します。 さらに本文に登場したエンジニアの一部が実名でインタビューに登場。当時を振り返り、ITエンジニアの仕事について本音で語ってもらいます。ITエンジニアの実態や活躍を知りたいビジネスパーソン、ITエンジニアを希望する学生にとって、必ずや参考になる一冊です。
-
4.0AIアプリ開発は簡単だ! Azureでの実践法を基本から徹底ガイド ディープラーニング(深層学習)という技術が登場したことにより、見る・聞く・理解する・考える・話すといった人のような認知機能を備えるAI(人工知能)がコンピュータで実現できるようになりました。ディープラーニングは機械学習と呼ばれる技術の一種で、認知機能の精度・性能を向上させるには、正解とみなせる入出力データのセットである教師データを用意して学習させることが必要です。 そこで有用なのが、Microsoft Cognitive Services。学習済みのAI部品が29種類、クラウドサービスとして提供されており、自前で教師データを用意したり学習させたりする手間が最小限で済みます。Microsoft Cognitive Servicesを使えば、認知機能を備えるAIを簡単に開発できます。 本書では、AIの基礎知識やMicrosoft Cognitive Servicesのサービス内容について解説したうえで、ピザ注文受付ボットやFAQ(よくある質問)回答ボットを題材として具体的な開発方法をステップバイステップで示します。 システムエンジニアやプログラマにとって、認知機能を備えるAIの開発を経験するうえで最適な1冊です。本書でAI開発の第一歩を踏み出してください。
-
4.0☆日本企業の最後の大量採用世代、「バブル入社組」も、はや50代に差し掛かり、人生の岐路に立っている。根っから楽観的と評される彼らは、多くの企業でどのように見られているのか。就職氷河期世代との対立、役職不足、保証されない将来……。バブル世代が置かれた現状と将来について、豊富な事例から人材コンサルタントが鋭く分析する。 ☆大企業では、業種によってバラつきはあるが、実に社員の5人に1人は「バブル入社組」が占める、と言われている。会社の大きな人材の塊と言われているが、他の世代からは、「根拠なく楽観的」「ポータブル・スキルが欠けている」「分析的ではない」などと言われ、手堅い意識を持つ、すぐ下の「氷河期世代」と鋭く対立することも。 ☆そんなバブル世代が、今後も戦力となって会社に貢献し、生き残りを図るには、弱点ともとらえられる「根拠なき楽観」を武器にすればよいのではないか。自身もバブル世代の真ん中である人材コンサルタントの著者が、さまざまな業種の多くの企業、さらに同世代の声なども織り交ぜながら語る、まったく新しいバブル世代論。
-
4.0IBMディープ・ブルー戦から20年 伝説のチェス・プレイヤーが 「機械との競争」から学んだ“創造”の本質。 「洞察に満ちた一冊。一気に読み終えてしまった。」(解説・羽生善治) 機械が人間の仕事をどれだけ多くこなせるようになっても、私たちは機械と競争しているのではない。新たな課題を生みだし、自分の能力を伸ばし、生活を向上させるために自分自身と競争しているのだ。……もし私たちが、自分たちの生みだしたテクノロジーに対抗できなくなったと感じているなら、それは目標や夢の実現に向けた努力や意欲が足りないからにほかならない。私たちは「機械ができること」ではなく「機械がまだできないこと」にもっと頭を悩ませるべきだろう。(本書より)
-
4.0クラウドサービスが当たり前のものとなり、AIやIoTなど最新のデジタル技術が相次いで登場する中、多くの日本企業が新たなデジタルビジネスの立ち上げ、あるいは既存のビジネスのデジタル化に取り組むようになりました。なかにはシリコンバレーにオフィスを構え、米国のITベンチャーとの連携を目指す企業も登場しています。 ところが日本企業のデジタル戦略は今、大きな壁にぶつかっています。「デジタル組織を設置したものの、肝心のビジネスが立ち上がらない」といった経営者の嘆きも聞こえてきます。日本企業が立ち止まっている間に、米国のITベンチャーなどが次々と新たなデジタルビジネスを興し、既存の産業のディスラプション(破壊)が進みつつあります。 日本企業は一刻も早くデジタルへの取り組みを通じて事業構造の変革、いわゆる「デジタルトランスフォーメーション」を実現しなくては、ディスラプションのえじきとなるでしょう。 本書では、日本でいち早く「デジタルトランスフォーメーション」の必要性を説いたベイカレント・コンサルティングが、日本企業や米国企業の事例を徹底分析し、日本企業のデジタル戦略の問題点を具体的に提示しました。その上で、日本企業が即座に実践できるデジタル戦略として「3ステップで実現するデジタルトランスフォーメーション」を提案しています。 デジタル戦略を具体化する際に経営面、マーケティング面、技術面などで考慮すべき9のアプローチも詳細に解説するなど、類書にはない具体的で、すぐに役立つ施策の宝庫です。
-
4.0全米で累計100万部超のロングセラー 『敗者のゲーム』著者による入門書の決定版! 「アクティブ運用での一攫千金を夢見るのはやめて、地道にインデックスファンドで資産運用しよう」―― チャールズ・エリスの主張は、いつもシンプルだ。 コンピュータによる超高速取引が浸透すると、ますます個々のファンドマネジャーの能力は平準化されてしまう。 いまや、一般の投資家が連戦連勝するファンドマネジャーを見つけて資産を託すというのは、 ほとんど不可能に近い。 本書は、「夢見る投資初心者」たちにその現実を伝え、インデックス投資のメリットを説く入門書だ。 エリス自身が「アクティブ運用信者」からインデックス投資へ「宗旨替え」するストーリー、 そして簡潔にまとめられたポイント解説は、予備知識のない読者にも非常に読みやすい。 プロ・アマ問わず、投資家必見の1冊だ。
-
4.0帰りの電車で寝ている人は、人生損している!? それどころか、死亡リスクが高まるかもしれない!! 今すぐ身に付けるべき「疲労回復スキル」を余すことなく伝授 超多忙で眠れない日本人に贈る一冊! 良い休息をとることは良い仕事につながる。 「睡眠」が重要なビジネススキルとなった今、それでも多くの人が、 「ぐっすり眠れない」「翌朝体が重い」「生産性が上がらない」と不調を訴える。 実は、よかれと思ってカラダと脳にダメージを与える習慣を続けてしまっているのだ。 ×帰りの電車で席に座って寝る ×ベッドの上で寝る前に本を読む ×まだ眠くないのにベッドに入る ×休日にいつまでも寝ている 1つでも当てはまれば、即刻生活を改めよう。 睡眠不足は、仕事の生産性を下げ、致命的なミスの原因となるだけでなく、 肥満や高血圧、糖尿病、心筋梗塞など、命に関わる病気のリスクを上げてしまう。 本書では、第一線で活躍する24人の医師と専門家に話を聞き、 最新の科学エビデンスに基づいた疲労回復スキルについてまとめた。 日本人の睡眠の問題を知り尽くしたプロフェッショナルが あなたの「眠りの悩み」を解決する!
-
4.02018年1月スタートのつみたてNISAにも完全対応! これで、老後不安にさよならできる! 現役世代も、リタイア組も必ず役立つ、 積立投信を活用した長期投資の実践術。 コツコツ、ゆったり、争わない、ハラハラしない。 でも、しっかり儲かる投資術を、 プロが平易に指南します。 ●人生100年時代、始めるのに遅すぎることはない! ●投資に対する5つの誤解を解く ●肉食系の投信業界。あなたが投資信託で損をしてきた理由 ●「草食系投資」をどの投信で実践する? ●肉食業界にいた僕らがらくちん投資に導かれたワケ ●三者三様ホンネでバトル! あなたに合ったらくちん投資 ●長期投資がつくる日本の未来
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 真の安藤忠雄が浮かび上がる! 「50人の証言」で徹底検証 建築も生き方も、その存在すべてが人々の心をつかんで離さない。安藤忠雄が社会に与えた影響とは?設計活動50年の真実を、50の建築と50の真実であぶり出す。作品集であったりインタビュー集であったりと、社会や建築界に対する安藤氏の挑戦を多角的な視点から位置付けたものは見当たらない。数ある安藤本のなかでも「集大成」といえる1冊。オールカラー版。 <主な内容> ◆PART1:1960~70年代「安藤忠雄の原点を探る」 ◆PART2:1980-90年代「環境問題や公共性を追求」 ◆レビュー:空から見た安藤建築(80~90年代) ◆PART3:2000年代「街や人との関係を深める」 ◆PART4:次代につなぐ「人間力と人工知能のはざまへ」
-
4.0躍進企業16社が自ら語る! 新サービス立ち上げをねらう新興企業も、既存の大手金融機関も注目するフィンテック。 ただの「流行り言葉」から、いよいよ本格的なビジネス展開が始まった。 いま、話題の企業は、何をしてきたのか。どんな展開を狙っているのか? これまでの金融サービスの成功法則と、どこがちがうのか? 金融革命を担う経営者たちが自ら語る。 ◆本書に登場する主な企業◆ 【ロボアドバイザー】 ウェルスナビ 【自動家計簿・クラウド会計】 マネーフォワード 【貯金アプリ】 インフキュリオン・グループ 【クラウドファンディング】 ミュージックセキュリティーズ 【決済】 BASE 【決済】 エクスチェンジコーポレーション 【決済】 Origami 【決済】 Liquid 【仮想通貨】 QUOINE 【ブロックチェーン】 SBI Ripple Asia 【ブロックチェーン】 R3 【ビッグデータ】 Treasure Data 【ビッグデータ】 ギックス 【AI・ビッグデータ】 ゼネリックソリューション 【クラウド会計】 freee 【UX/UI】 グッドパッチ
-
4.0行き着く先はインフレタックスという究極の増税策! ? 総選挙を経て、再び安倍内閣に託したこの国の経済。 その処方箋が間違っているとすれば、最後にツケを払うのは、われわれ国民なのかもしれない。 ◆異次元緩和は間違った処方箋 5年目に入った「アベノミクス」だが、デフレ脱却には至っていない。それは、アベノミクスの目標及び処方箋が間違っているからではないか? 実は、金融政策依存は、政治的には非常に都合がよい。極論すれば、日銀が物価目標を明示しマネーの供給量を増やすだけで、政治は何もしなくてよいからだ。しかし人口減・高齢化が進む社会では、経済規模は必然的に萎まざるを得ない。量的・質的緩和では、本当の日本経済の構造問題に対処することは不可能なのである。 ◆このままでは金融資産がどんどん目減りする! 人口減対策と雇用制度改革を避けるアベノミクスは、実は意図せざる究極の増税策、すなわち「インフレタックス」である。そして、その潜在的な納税者は、金融資産を保有する企業や高齢者なのだ。 異次元緩和で膨れ上がる日銀の資産と増え続ける国家債務は、いずれ国債の価値下落を通じ日本経済をインフレに導く。その時、国家債務の実質負担は収縮する一方で、企業や国民が持つ金融資産の価値は目減りする。実は、戦前、高橋是清は、世界恐慌からの脱却を図るに当たり、日銀による国債保有を悪性インフレの原因になるとして許さなかった。アベノミクスを高橋財政と同一視し肯定するのは、全くの間違いなのである。 本書は、こうした視点をベースに日本経済の近未来を分析、蓋然性のあるシナリオを提示。インフレタックスが現実となれば、高齢者や企業は蓄積した金融資産の購買力を失い、中若年層は、親もしくは祖父母世代の経済力に依存できなくなる。そうしたリスクに備えるうえで、読者に知っておいてほしい知識を提供する。
-
4.0データサイエンティストを目指す人、社内でデータ分析組織に携わる人、 これから同じような組織を作りたい人、イノベーションや業務改革を成功させたい人に! 日経情報ストラテジーが選ぶ「データサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー」の初代受賞者である、大阪ガスの河本薫氏による待望の2冊目となる本。同氏が所長を務めるデータ分析組織「ビジネスアナリシスセンター」の生い立ちから数々の失敗、乗り越えてきた壁、そして分析組織のリーダーに求められる信念と行動を初告白します。 社内外の誰からも注目されていなかった無名のチームが、いかにして日本一有名なデータ分析組織に生まれ変われたのか。チームを率いる著者がこれまで語ることがなかった苦悩や挫折、そして、ある日突然有名になってからの状況の変化などを、余すところなく赤裸々につづった一冊です。 本書はデータ分析の手法の紹介にはフォーカスしていません。なぜなら著者は「データ分析は業務改革やイノベーションを実現するための手段の1つに過ぎない」と考えているからです。むしろ、チームのメンバーとデータ分析でイノベーションを起こすという「ミッション」を共有し、問題を解くことではなく会社に役立つことに価値を置く「カルチャー」を育み、社内の事業部門から「信頼(レピュテーション)」を勝ち取ってイノベーションを達成することがデータ分析組織の役割であり、責任範囲であるという持論を展開します。そのために必要なノウハウや社内での話の進め方、人の巻き込み方などの経験談をふんだんに盛り込みました。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 最新版は、マーケターが確実に押さえておく必要のある「技術キーワード」の解説や、同一カテゴリーのアプリを比較しながらマーケティングへの活用法を解説する「アプリカテゴリー解説」といったページも新たに掲載いたします。最後に、トレンド分析として「Nintendo Switchはどれほど期待されているか」「物流ラストワンマイル問題解決の処方箋」「テレビCMの投下とネイティブアプリゲームのプレー(アクティブプレーヤーの数)にどのような関係があるのか」などにもフォーカスします。 本誌はデジタルマーケターが日頃、疑問に思っているテーマを取り上げるとともに、最新のデジタルマーケティングの内容が満載の一冊になります。
-
4.02020年東京五輪・パラリンピックは日本経済、最大の起爆剤! 自動車、電機、通信、物流、医療、小売り、警備、観光、エンタメ、 外食、ホテル、不動産、ロボット、AI(人工知能)、ドローン…… 全産業のビジネスチャンスを総ざらい!!! 東京では現在、2020年の東京五輪・パラリンピックの開催に向けて、 あらゆる場所で大型の都市再開発プロジェクトが進んでいます。 けれど、その内容には大きな懸念があります。 というのも、このままでは東京が、"つまらない未来都市"に、なりかねないからです。 安全で、清潔で、居心地はいいけれど、あまり面白くない。 そんな国際都市に、世界第一線の優れた企業や優れた人材は、なかなか集まりません。 本来、東京は、もっと個性豊かで、魅力的で、多様な特徴がつまった、 とてもユニークな都市です。現在の強みをさらに磨けば、東京は世界で唯一無二の、 最強の国際都市に生まれ変わるはずです。 そこで多様な分野の一線で活躍するキーパーソンが結集。 未来の東京、すなわち「NEXTOKYO」のあるべき姿と、 全産業のビジネスチャンスを徹底解説しました。 ≪NEXTOKYOプロジェクトのメンバー一覧≫ A.T.カーニー 梅澤高明/ABBALab 小笠原 治/カフェ・カンパニー 楠本修二郎/ ライゾマティクス 斎藤精一/弁護士 斎藤貴弘/アーティスト、東京大学 スプツニ子!/ Takram 田川欣哉/元陸上競技選手 為末 大/ロフトワーク 林 千晶/タイムアウト東京 伏谷博之/ 建築家、東京藝術大学 藤村龍至/建築家、米ハーバード大学大学院 森 俊子
-
4.0システム開発を成功に導く要件定義の進め方が分かる 事例を基にした演習を解きながら極意を学ぶ 要件定義は、システム開発プロジェクトを成功させるための最も重要な工程の一つです。要件定義に失敗すると、必要な要件が抜け漏れたり、不要な要件が定義されたりします。そうなると、設計以降の工程で手戻りが発生し、納期の遅延やコストの増大を招きます。 それでは、どうすれば要件定義を成功させることができるのでしょうか――。 本書では、要件定義の担当者身に付けておくべき代表的な知識・スキルを、「進め方」「コミュニケーションスキル」「ツール」の大きく三つに分けて解説します。 進め方は、要件定義の手順、成果物、運営方法のことです。「方針と実施計画の立案」「現行業務と問題の把握」「問題分析と課題の設定」「課題解決策の立案」「システム要件の整理」という五つのステップからなる要件定義の具体的な進め方を分かりやすく解説します。 コミュニケーションスキルでは、欲しい情報を効率良く集める「ヒアリングスキル」、会議体での意見交換をスムーズに行う「ミーティングスキル」、検討した内容を関係者に効果的に伝える「プレゼンテーションスキル」を紹介します。 さらに、要件定義の各場面で必要な情報を集めたり、集めた情報を整理したりする際に役立つツールとその作成方法を具体的に説明します。 本書では全編にわたって、筆者の実際の経験を基に作成した架空の事例を使って解説します。演習問題を数多く盛り込み、それらを解きながら読み進めることで、確実に知識やスキルを身に付けることができます。要件定義を担当するすべての人に必携の一冊です。
-
4.0五郎さんが生きた、あの時代。 集団就職、東京への人口移動、農業の衰退、バブル崩壊、交通事情の変化、恋愛の変遷、受験戦争、ゴミ問題――名作ドラマが映した社会の激動を描きとる。 「北の国から」ファン必読の1冊!! フジテレビで1981年から2002年にわたって放映され、国民的な人気ドラマとなった「北の国から」。単なるヒューマンドラマにとどまらず、戦後間もないころから現代までの日本の社会のあり様とその変化を描いた秀作でもある。 ドラマがリアルタイムで描いた1980年代から2002年まではもちろんのこと、戦後の富良野で黒板五郎が成長し、東京で家族を持つまでの時代をも物語の背景として取り込み、ドラマは1人の男の生涯を描いたものとなっている。 本書では、そうした黒板五郎を中心としたドラマの登場人物たちの人間模様を取り上げ、その背景にある社会の変化に注目し、改めて戦後日本のあり様を見直す。ドラマ内の名場面を多数引用しながら、日本社会の変遷を振り返る意欲作。
-
4.01巻2,200円 (税込)破壊された市場の「空隙」をねらえ! あらゆる業界をのみ込む「破壊の力学」と、 それを支える「デジタル・ビジネスモデル」を解明。 勝ち残りをかけた既存企業の戦い方を明らかにする。 ITとは無縁だと思われていたタクシー業界やホテル業界。デジタル・ディスラプター(破壊的イノベーター)が現れ、業界の競争基盤を破壊してしまうと、いったい誰が予想しただろうか。いまや「デジタル・ディスラプション」は、あらゆる業界をのみ込もうとしている。 既存企業は、デジタル化がもたらす破壊の力学にどう対応すればよいのか。本書は、既存企業の視点からこの問題について網羅的に論じ、自らディスラプターとなる(ディスラプトされるのではなく、どうすればディスラプトできるかを考える)ための実践的なロードマップを示す。 カギは「バリューチェーン」ではなく「バリュー」そのもの デジタル・ディスラプションが起こるのは、「市場や社会のなかにある、満たされていないニーズ」を満たす「新たな価値提案」がデジタル技術によって可能となるため。デジタル・ディスラプターは、既存ビジネスと同じバリューチェーンをつくらなくても、デジタル技術を用いて容易に既存ビジネスと同じかそれ以上の価値を提供する。それを支える「デジタル・ビジネスモデル(デジタル技術の進展によって可能になった新しいビジネスモデル)」を明らかにし、既存企業が採るべき「4つの対応戦略」を詳説する。 ・既存企業は、なぜ、どのようにして苦戦を強いられるのか? ・デジタルがもたらす「新たな価値提案」とは? ・ディスラプターは、どのような「デジタル・ビジネスモデル」で攻めてくるか? ・破壊された市場で、既存企業が利益を享受できる「価値の空白地帯」とは? ・既存企業が採るべき「4つの対応戦略」とは? ・反撃に打って出るために不可欠な「3つの組織能力」とは?
-
4.0リーン・スタートアップの次の段階である「成長」に向けての6つのステップを詳述した経営戦略の解説書です。 ベストセラー『リーン・スタートアップ』の著者エリック・リースがシリーズ・エディターをつとめたオライリーの「The Lean Series」第1弾『Running LEAN』の著者による続編です。 エリック・リースは本書の推薦に当たり、「関心ある企業に組み込むための実践的なアプローチ」と評しています。120点近い2色刷の図によって、理解しやすい図解の構成になっています。 本書の6ステップを、著者はGO-LEAN(Goal→Observe and Orient→Learn, Leverage, or Lift→Experiment→Analyze→Next Actions)[目標→観察と方向付け→学習・利用・強化→実験→分析→次のアクション]と名づけています。 本書では、うまく成長できないのは「局所最適化の罠」であると位置づけ、ゴールドラットの制約理論を引用しながら、全体最適化の方向へと読者を導きます。 また、本書では拡大の規模の目安となる「10倍ルール」を設定し、ステージごとの目標値を定めています。これがもう1つの新しいツールとなる「トラクションモデル」です。 これらのツールなどを使い、リーンの「継続的改善」を用いながら、「目の前のニーズに完璧に応えつつ、グローバルな拡大を実現する」ことを目指すのが、本書です。
-
4.0見える化、働き方改革、フェアネス・・・ 業界の異端から主流へ! 知られざる先進企業の全貌!! 設計、施工の請負業態が一般的になっている日本の建設業界。その建設業界では、形のない仕事に報酬を払う「フィービジネス」は、なかなか定着しにくい風土があります。そこにITを駆使する独自の経営方針で切り込んだのが、明豊ファシリティワークス。発注者側に立ち、建築プロジェクトの遂行を支援するコンストラクションマネジメント(CM)業務を開拓してきました。 「“効率良く”は目標にするが、“要領良く儲ける”はタブー」を企業の指針とし、CMビジネスの市場で勝ち抜いてきた、明豊ファシリティワークス。知られざる先進企業の強さの秘密に迫ります。 ■目次 序 章 高まるCM導入の機運 第1章 品質・工期・コストの管理を支援 第2章 フェアネスと透明性を旗印に顧客主義を貫く 第3章 「明朗会計」を打ち出し、異端から主流へ 第4章 発注者支援業務をフィービジネスとして確立 第5章 「見える化」でサービス品質と生産性を上げる 第6章 ワクワク感で優秀な人材を呼び込む 第7章 社会へ定着させる道筋 終 章 代表取締役社長・大貫美氏に聞く
-
4.010年裁判の末、逆転無罪となった長銀・日債銀粉飾決算事件、著者が冤罪と見るライブドア事件、10年にわたる長期の粉飾決算事件であるオリンパス事件、現在進行中のウエスチングハウス買収後の東芝巨額粉飾決算――5大粉飾事件の深層を解明! 「想起すれば、21 世紀は粉飾決算とともにやって来た。本書で分析の対象となっている巨大粉飾決算事件はすべて20 世紀末から世紀を跨いで事件が発生し、21 世紀初頭の司法により決着が図られている。 21 世紀は時価会計の時代でもある。人類は、ベネチアのルカ・パチオリ以来、500 年間という長い年月をかけて、複式簿記による経済活動の測定及び報告の歴史を積み上げてきた。 この500 年に及ぶ企業会計は、一貫して投下資本の回収計算を目的とする取得主義会計により行われてきた。それが前世紀末頃から時価会計が出てくると、時価会計はあっという間に世界の会計制度を席巻してしまった。 (中略) 本書で分析の対象となっている粉飾決算事件は、時代が取得原価会計から時価会計に移行していく過程で事件化し、時価会計が主力となった時代に粉飾決算事件として決着している。 粉飾決算を引き起こした経営者は指弾されてしかるべきであるが、私は事件の背景に、時価会計が経営者の倫理観を毀損していった側面が見えてならなかった。時価会計導入以来すでに20 年近い年月が流れた。 人類史における時価会計導入の功罪が検討されるべき時期に来ている。私はVS シリーズ3 部作の完成版を書きたいと思うに至った。」(本書「はしがきに代えて」より)
-
4.0
-
4.0爆買い、おカネの亡者、パクリ天国――。こんな「中国人」像はもう古い!? 日本のそれを遙かに超えるスピードで激変する中国社会。街中ではシェア自転車が走りまわり、現金を持つ人・使う人もめっきり少なくなった。 中国、そして中国社会の何が成熟し、また旧態依然のまま停滞するのはどんな部分なのか。数カ月単位で変貌する中国最新事情を豊富なエピソードから紹介する。 「中国でも人気の『半沢直樹』から、彼らは何を学んでいるのか」「レンタル彼女と帰省し、実家の親を安心させようとする」「シェア自転車にいたずらすると、なぜか婚活に悪影響!?」……。本書で示される、数多くの興味深い事例を読めば、中国に暮らす人々の等身大の姿がくっきり浮かび上がる。 彼らの思考、行動様式を知れば、日本に住む私たちと同じ希望、不安、苦悩を持つことが理解できる。いまの中国、そしてこれからの中国の行方を見すえる上で必読の良質なルポルタージュである。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 仕事もプライベートもうまくいく 「時間のルール」がまんがで身につく! 仕事が遅く、毎日がうまくいかない事務職の明日美。 ある出会いをきっかけに、時間の使い方にルールがあることを知り、成長していく…。 読むだけで、あなたの仕事とプライベートが充実するストーリー! ◆ 探し物ゼロ! デスクの片づけ ◆ 発見! 最強のTO DOリスト ◆ 仕事を抱えない! 上手な断り方 ◆ 朝スッキリ! 睡眠&起床テク ◆ 心とカラダ、最高の休ませ方 ◆ 時間のムダがなくなるデスクの片づけ、3つのルール ◆ メール&検索 もっと効率化! ワザ ◆ 生産性を上げる“ やめる勇気”&上手な断り方 ◆ 早起きが苦手な人のための睡眠&起床テク ◆ マインドフルネスで脳を休める ◆ 自分に自信がつく! 週末前向き勉強術
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “今どき トラブル”の全貌が明らかに! ●セオリー無視が「重大事故」生む! ●「軒ゼロ住宅」は危険がいっぱい! ●間違いだらけの「クレーム対応」! 住宅実務者にとって、雨漏りは最大の関心事。住宅トラブル件数の約85%を、雨漏り事故が占めています。最近は、屋根の庇を十分に出さない「軒ゼロ住宅」や「パラペット住宅」で雨漏り事故が多発。本書では、雨漏りが発生しやすい部位の納め方を、基礎から易しく解説するとともに、軒ゼロやパラペットなど、雨漏り事故が増えている部位の対策も詳説します。雨漏り対策の決定版です。 ●主な内容 第1章 まずは基本!雨漏り頻発部位はココだ 第2章 ピンチ脱出!雨漏り再発時の対処法 第3章 設計者必見!デザインが呼ぶ雨漏り 第4章 それでもやる?危険だらけの軒ゼロ住宅 第5章 間違いだらけ!パラペットの納め方 第6章 潜むトラブル!壁内の雨漏り&結露 第7章 建て逃げ許さじ!雨漏り欠陥責任は20年 第8章 これで安心!雨漏りクレームの対処法













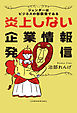


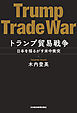























![投資の大原則[第2版] 人生を豊かにするためのヒント](https://res.booklive.jp/533127/001/thumbnail/S.jpg)