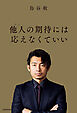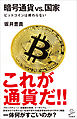経済作品一覧
-
4.1
-
3.8
-
3.7
-
3.5
-
3.5
-
4.3どんな権威やロジックも吹き飛ばして正解を導き出す「統計学」。「ビッグデータ」が重宝される風潮からも分かるとおり、その影響は、現代社会で強まる一方。そうした社会的な趨勢で、私たちの未来に立ちふさがる少子高齢化や貧困などの諸問題に統計学ブームの火付け役の西内氏が立ち向かう! この本は東京大学政策ビジョン研究センターの研究成果をまとめたもので、日本の未来における喫緊の課題に対して、その通説・俗説を統計学的にくつがえしていく切れ味は抜群。『統計学が最強の学問である』の第三弾が今秋刊行予定と、再び見込まれる統計学ブームのなか、話題になること間違いなし!
-
-待望の電子書籍化! 電子版発行に当たり、電子書籍版「まえがき」でアベノミクスを総括するとともに、新アベノミクス成功の鍵にも言及。日銀の本質を理解するための必読書! 日銀が邪魔さえしなければ日本経済は必ず復活する! 我々が日頃、毎日使っているお金は日本政府ではなく「私企業」である日本銀行が発行している。そして僅か9人の人間がファッショ的に日本経済を牛耳っているのである。この不可解に斬り込んだ。 著者プロフィール 栗原茂男(くりはら・しげお) 1949年東京生まれ。早稲田高等学校・中央大学商学部卒業。丹羽経済塾幹事。中央大学出身の経済人団体である南甲倶楽部会員。世界経済研究協会とも交流があり、政党等に招かれて経済の講義なども行う。英国王立国際問題研究所・ロンドン大学LSEフォーラム会長の宇田信一郎氏とは丹羽経済塾や『あてな倶楽部』で親しく情報交換を続けている。 現在は食品卸店としてコンビニエンスストアを経営しながら市井の経済研究家として独自人脈やインターネットを通じて提言を行っている。また各界から日本文化を尊重する人たちが集う『あてな倶楽部』の代表を務める。
-
3.7
-
3.3
-
4.0
-
3.8
-
3.3
-
3.3
-
4.0
-
4.1「社会が高齢化するから日本は衰える」は誤っている! 原価0円からの経済再生、コミュニティ復活を果たし、安全保障と地域経済の自立をもたらす究極のバックアップシステムを、日本経済の新しい原理として示す!!
-
4.0
-
4.0小説を書いたり、囲碁で世界的な強豪を負かしたりと、AIが目覚しい発展を遂げています。このまま技術開発が進んでいくとどうなるか……。 著者は「2030年には人間並みの知性を持ったAIが登場する可能性がある」と指摘。そうなるとホワイトカラー事務職は真っ先に職を奪われ、医者も弁護士も失業の危機に瀕するでしょう。「最大で人口の9割が失業する可能性もある」と著者は推定しています。 では、一部の資本家以外は飢えて死ぬしかないのでしょうか? AIによって奪われた労働は、BI(ベーシックインカム)で補完しよう! それが著者の提言です。AIの発達が人類の幸福へつながるためにはどうすればいいのか。気鋭の経済学者の大胆予測。 【目次】 第1章 人類 vs. 機械 「ターミネーター」は現実化するのか?/よみがえる技術的失業/なくなる職業 など 第2章 人工知能はどのように進化するか? ディープラーニングによるブレイクスルー/ロボットの身体感覚/AIは将棋盤をひっくり返すか? など 第3章 イノベーション・経済成長・技術的失業 日本は衰退する運命にあるのか/第二次産業革命の終わりとポストモダン/AIは雇用を奪うか? など 第4章 第二の大分岐――第四次産業革命後の経済―― 第四次産業革命をめぐる覇権争い/全人口の1割しか働かない未来/全ての労働者は飢えて死ぬ など 第5章 なぜ人工知能にベーシックインカムが必要なのか? 生活保護は労働者を救うか?/ベーシックインカムとは何か/財源が問題ではない理由 など
-
4.2石油の価格は、いったい誰が決めるのか? 「今でも石油の価格は、OPECとセブンシスターズ(欧米の巨大石油資本企業)が裏で話し合って決めているのでしょう?」 私たちの生活に大きな影響を与える石油価格。しかし今でもこうした誤解がはびこっている。 商社に入社以来、40年以上にわたってエネルギー関連事業にたずさわり、現在はエネルギーアナリストとして活躍する著者が、石油価格のメカニズムをビジネスマン向けに徹底解説。また、エネルギーに関する海外のオピニオンを紹介しつつ、いまエネルギー事業が直面している構造変化と、それがもたらすであろう国際情勢の変化を論じる。 <おもな目次> ●第一章 原油大暴落の真相 波瀾万丈の2016年が明けた/資源を「爆買い」した中国/シェールオイルの「強靭性」 など ●第二章 今回が初めてではない 資金ショートか、大油田発見か/強欲独占、ロックフェラー/非OPEC原油が勢いづく など ●第三章 石油価格は誰が決めているか OPECとセブンシスターズが裏取引?/市場を動かす「先物取引」/中国勢の価格操作疑惑 など ●第四章 石油の時代は終わるのか 石油が枯渇する心配はない/シェール革命の何が「革命」だったのか/石油は「西から東へ」の時代に など ●第五章 原油価格はどうなる? 長期、短期の需要予測/隠された余剰生産能力/エクソンはなぜ読み違えたのか など
-
3.3「ピケティが示した不平等の歴史的な展開を、さらに歴史的に俯瞰する。格差論の未来のために!」 ――『21世紀の資本』共訳者・山形浩生氏 推薦 フランスの経済学者トマ・ピケティによる大著『21世紀の資本』が公刊されたのは2013年。その後、ノーベル経済学受賞者のスティグリッツやクルーグマンらの推薦もあって英訳から火がつき、またたく間に世界的にベストセラーになりました。 どうして大ブームになったのでしょうか? 実は下地ができていました。高度成長を終えた先進国のなかで、ピケティしかり、日本の「格差社会」「大衆的貧困」ブームしかり、明らかに「不平等ルネサンス」とでもいうべき学問的潮流が起きていたのでした。 それでは一体いつ、経済学者たちの「不平等との闘い」は始まったのでしょうか? 本書では、ピケティ的な意味での「市場経済の中での不平等(所得や資産の格差)」に焦点を絞り、その歴史を紐解きます。 18世紀にフランス革命の思想的後ろ盾となった、ジャン=ジャック・ルソーと、そして“神の見えざる手”で知られるアダム・スミスから議論を始め、マルクス経済学、近代経済学、不平等論議の新しいステージ「不平等ルネサンス」、そして現代のピケティにいたるまでの学問的軌跡を追っていきます。
-
3.9■■■■■■■■■■■■■■■■ 経済安全保障の最優先課題 「量子コンピュータ」について わかりやすく解説した入門書! ■■■■■■■■■■■■■■■■ 自動車・金融・化学・製薬・物流 メタバース・AI…… 量子コンピュータは 世界をどう変えるのか? ■■■■■■■■■■■■■■■■ いま世界各国では、既存のスーパーコンピュータを 遥かに凌ぐとされる「量子コンピュータ」の 大規模な開発プロジェクトが進み始めている。 本書はそれを無条件に肯定したり、あるいは 逆に頭ごなしに否定するといった内容ではない。 量子コンピュータの基本的な原理から産業的側面、 さらには社会・政治的インパクトに至るまで、 多面的な事実を積み上げ考察を加えることにより、 その際どい実現可能性を検証していくのが 本当の狙いである。 はたして「夢の超高速計算機」は 本当に実現するのかーー。 ■■■■■■■■■■■■■■■■ IBM,グーグル、 マイクロソフト、アマゾン…… ビッグテック参入のウラで 報じられていない実態とは? ■■■■■■■■■■■■■■■■ ・・・本書のおもな内容・・・ 第1章 巨額の投資対象に変貌した「科学の楽園」 ――量子コンピュータとは何か 「経済安全保障」の最優先課題 これから高まる“量子人材”の必要性 2023年が実用化へのターニングポイント グーグルvs.IBMの激しい応酬 別路線を歩むマイクロソフトの意図 猛追するアマゾンの焦り ほか 第2章 現実離れした「量子コンピュータ」のしくみ ーー謎の超高速計算機はどう動いているのか 量子力学の基本法則 全知全能の神ですらわからない「真の不確実性」 量子ビットの作り方 量子コンピュータ開発の技術的難題 量子コンピュータ=汎用性が高いとは言えない理由 巡回セールスマン問題、NP困難問題は解けるのか? ほか 第3章 量子コンピュータは世界をどう変えるのか 【自動車】渋滞を解消しサプライチェーンの最適化 【金融】投資ビジネスの競争優位性を高める 【化学】最適な組み合わせを見つけバッテリー開発に活かす 【製薬】創薬にかかる膨大な時間とコストを圧縮 【物流】配達ルートや輸送手段の効率化 【メタバース】巨大な仮想経済圏を難なく支える超並列コンピューティング 暗号破りコンテストの結果と次世代暗号導入を急ぐ理由 暗号をめぐる中国と米国の駆け引き ほか
-
3.8どうして日本の国力は 30年以上も低下し続けているのか? 低所得・低物価・低金利・低成長の 「4低」=「日本病」に喘ぐニッポンを、 気鋭のエコノミストが分析! <本書の主な内容> ・「4低」現象は「日本化(Japanification)」と呼ばれ、世界で研究対象に ・今や日本の賃金は、アメリカの半分強、韓国の約9割 ・失業率が高い国ほど、賃金上昇率も高い不思議 ・「物価上昇率がマイナス」は、OECD諸国で日本だけ ・異次元の金融緩和でも、物価が上がらない理由 ・日本は家計も企業も過剰貯蓄、はびこるデフレマインド ・アメリカはリーマン・ショック後、すごい勢いで量的緩和と利下げを行い、「日本化」回避に成功 ・日本の政府債務の増加ペースはG7の中で最低、財政赤字を気にしすぎ ・ここ30年で、アメリカのGDPは2倍、日本は1.2倍 ・日本では、年収200万円未満の世帯が増加、年収1500万円以上の世帯は減少⇒1億総貧困化へ ・「日本の年金・社会保障制度は危機的状況」の間違い ・大きな可能性を秘めている日本の第一次産業
-
-
-
3.6仕事の面白さと深みをたっぷり味わい、 感動や興奮を仕事仲間や取引先と共有する――。 部長のやりがいは、会社人生最大のものです。 ■■■部長ほど面白い職業はない!■■■ とはいえ、成功ばかりの人生などありえません。 著者が課長時代に直面した「事件」、 部長時代に経験した手痛い失敗とは? 働き盛りのみなさんに贈る 「人生の勝負どき」を乗り切るためのヒント。 ・・・ ■ 豆腐屋でにわか見習い ■ 成果ゼロの飛び込み営業で得た教訓 ■ 課長時代に直面した「事件」 ■ 部長時代の手痛い失敗 ■「やられた!」と思ったこと ■ 昇進の目前に現れる「卑しい本性」 ■ 他人のことはいえない「酒をめぐる失敗」 ■ 反面教師としていた部長 ■ 取引先のトップと会うための早道 ■ 議論で負けないコツ ■ 働き盛りに取り組んだこと ■ 人間関係を築く基本 ■アイデアがひらめくヒント ■ 部長として成功する秘訣 ■ 上に立つ人間がすべきこと ■ 自分の後任を意識的に教育する ■ 部下の才能をいかに引き出すか ■ 優秀な社員ほど厳しい職場に送り込む ■ 会社を真に変えるには ■ 社内の反発をどう抑えたか ■ 会社のルールをぶっ壊せ ■ 参加者唖然の「ビール事件」 ■ 灰皿が飛ぶ職場 ・・・ 本書では、新しいビジネスを創造した事例とともに、 いま思い返しても赤面するほどの失敗した事例も 包み隠さず書きました。 成功ばかりの人生などありえません。 喜びや感動とともに苦悩や無念を味わうのが リアルな部長の姿です。 ポストコロナ時代、「グレートリセット」と呼ばれる 価値観の大転換期を迎えるなかで、 会社から離れた自宅などで仕事をする テレワークが一気に普及するなど、 私たちの働き方も大きく変わろうとしています。 しかしどんなに働き方が変わっても、 仕事の本質は変わりません。 大企業であろうが中小企業であろうが、 部長のあなたでなければできない仕事は多く、 それが会社の進む方向を動かし、 あなたの人生をも動かすのです。 ・・・ 【本書のおもな内容】 第1章 仕事・読書・人が自分を磨く 第2章 部長時代の手痛い失敗 第3章 会社のルールをぶっ壊せ 第4章 上に立つ人間がすべきこと 第5章 なぜあなたは働くのか
-
4.3気鋭の財政社会学者・井手英策が、新自由主義がなぜ先進国で必要とされ、広がり、影響力を持つことができたのか、歴史をつぶさに振り返り、スリリングに解き明かしていく。そして経済と財政の本来の意味を確認し、経済成長がなくても、何か起きても安心して暮らせる財政改革を提言。閉塞感を打破し、人間らしい自由な生き方ができる未来にするための必読の書! 市場原理を絶対視し、政府の介入を少なくすれば、富と複利が増大する、という新自由主義の考えは、80年代にレーガンとサッチャーによって実行され、米・英は好景気を迎える。日本では、外圧や、政財界の思惑と駆け引き、都市と地方の分断などの要因から新自由主義が浸透。経済のグローバル化も起こり、格差が広がる。勤労が美徳とされる「勤労国家」で、教育も医療も老後も、個人の貯金でまかなう「自己責任国家」、日本。財政が保障することは限られ、不安がつきまとう。本来お金儲けではなく、共同体の「秩序」と深く結びついていた経済。共通利益をみんなで満たしあう財政への具体策を示し、基本的サービスを税で担う「頼り合える社会」を提言。貯金ゼロでも不安ゼロ、老後におびえなくてすむ社会に!
-
4.2
-
3.7
-
4.2
-
-「できるだけ話さないですませたい…!」 これは、忙しい人、コミュニケーションが苦手な人、教える側・質問する側……ビジネスパーソンの共通の願いではないでしょうか? 関係をよくするための雑談は別として、仕事に関するやりとりはできるだけ簡潔に、要領よく、最低限ですませられるのが理想なはず。 そこで本書では、「紙1枚」シリーズを中心に累計50万部突破のベストセラー著者が、言いたいことが最短で伝わるようになる「紙1枚」の下書き術を伝授します。 企画提案やプレゼンの前、あるいは人に何かを依頼したり回答する前に、どんな準備をすれば一発で「伝わる」のか。 本書では、具体的な考え方や下書きの作り方を、微に入り細に入り解説します。 事例には効率のいい「自己紹介の作り方」なども入っていますので、難しく考えず楽しく取り組み、身につけることができます。 著者はトヨタ自動車でキャリアをスタートし、そこで学んだ「紙1枚」の極意を自分なりに応用・発展させてきました。 そして今では書籍や講演会等「伝えること」で大活躍していますが、実はもともとはいわゆる「コミュ障」に悩んでいたと言います。 「できるだけ話さずにすませたい…!」 ――これは、他でもない著者の切なる願いだったのです。 そんな著者が自分のキャリアを通じて編み出し、積み上げてきた「伝える前の事前準備」は、とにかく実践的で、明日からすぐに使える内容ばかりです。 伝えるのが苦手な人は、「伝える前」の準備が絶対的に足りていない――逆に言うと、適切な事前準備さえすれば、話すのが苦手な人でも一発で伝えられるようになるのです。 伝えることが苦手な人、もっとうまく伝えられるようになりたい人は、4色ボールペンと紙を用意して、ぜひ本書を読んでみてください!
-
4.0「カッコイイほうを選べ」 「空気を読むな、自己主義で行こう!」 18年にわたるプロ野球人生で培った、自己肯定感を高める35のメソッド! プロ野球の阪神タイガース、千葉ロッテマリーンズで活躍した著者が 現役時代のエピソードを踏まえて説く「人生訓」が詰まった一冊! 強く・かっこよく・自分らしく生きるロジックを学べば 自然と自己肯定感が高まり、生きる活力が湧き出す! 【目次】 はじめに 「常識」を疑い、「普通」を問い直す 第1章 自分か、それとも他人か? 第2章 「他人の目」を利用して考える 第3章 成功とはなにか? 失敗とはなにか? 第4章 物事は常に逆算して考える 第5章 幸せな人生を歩むために おわりに 新しい刺激が生まれると、新しい感覚が生まれる
-
-TwitterでバズったExcelショートカット一覧やわかりやすい図解をふんだんに使った、Excel参考書の決定版! 見るだけですぐにExcelが使えるようになるテクニックが満載です。 基本操作、関数、並べ替え・抽出&データベース分析、グラフ作成など、基礎から応用まで完全網羅。 オートフィルターやピボットテーブルを使ったデータベース分析、表組見本に沿って理解する関数、わかりやすいグラフ作成方法まで、実践的なExcelスキルが身に付きます。 <著者コメント> Excelはまったく難しくありません。むしろ楽しいものです。 Excelが見るだけでわかるようになる、丁寧でカンタンな図解解説と、 ショートカット一覧で、楽しくExcelを使いこなしましょう! <目次> 第1章 Excel基本操作の見るだけ図解 第2章 Excelステップアップ操作の見るだけ図解 第3章 表組見本付き! 関数の見るだけ図解 第4章 並べ替え・抽出とデータベース分析の見るだけ図解 第5章 わかりやすいグラフ作成の見るだけ図解 第6章 実践編 売上台帳&採用管理シートを作ってみよう
-
4.4メンタリストDaiGo推薦! 習得スキルを絞り込めば、「キャリアの選択肢」が広がる! ライフシフト専門家と国際金融のプロが総力提言。 序 章 DXより重要な「戦略的学び直し」 第1章 世界の変化と立ち遅れる日本 第2章 ビジネスパーソンのレジリエンスを高める 第3章 「シナリオ」を身につける~不透明な未来を見通す力~ 第4章 「スピード」を身につける~世界に通用する速さを生む決断力~ 第5章 「サイエンス」を身につける~決断を支える合理的思考力~ 第6章 「セキュリティ」を身につける~自分の土俵を創り、守る力~ 第7章 人生100年時代を生き抜くために~世代別のリスキリング方法
-
3.7●世界インフレ、日本の円安・物価高、ウクライナ危機…… ●加速・複雑化する現代経済の要点を整理し、平易に解説! ●“安い日本”に負けない「日本の勝機」が見えてくる! 経済学者の伊藤元重氏は、既存の常識では予測できない現代の社会情勢を「事実は小説より奇なり」と表現し、物価も賃金も上がらなかった「停滞と安定」の時代から、「変化と不確実性」の時代へと移行していると説く。だが同時に「予測不可能な未来を見通すためには、経済学の力が必要だ」とも語る。そこで本書ではさまざまな経済学の視点から、これら「難問」の解明に挑む。読めば加速・複雑化する社会情勢が理解でき、日本再興の「勝機」が見えてくる!
-
-コロナパンデミック以来、資源価格の高騰、ロシアによるウクライナ侵攻など、世界は激動の時代に突入した。20世紀の二つの世界大戦を経験し、インフレ、大量失業、国際通貨危機などの問題と格闘したケインズ。その知恵を今こそ学びたい。
-
4.0コロナ禍で人流が減り、鉄道はビジネスモデルの変革を迫られた。 乗客はいったいどれくらい減ったのか。 主要路線、地方鉄道の乗客の推移を追うとともに、駅ごとの利用者数の増減を把握。 JR東日本が運輸収入46.8%減にまで落ち込むなど、各社危機的な売上減にあえぐ中、鉄道会社の戦略の肝となるダイヤの改正から、新たな収益を得るための戦略を豊富なデータとともに網羅していく。 公共交通機関として巨額のコストを負担しながら、利益を獲得すために鉄道会社は どのような戦略を導き出したのか――。
-
-経営者、起業を考えている方、 会社で経営に携わる管理職の方、 必読の1冊です! 企業経営においては、組織づくりに関する さまざまな課題があります。 離職率を下げるにはどうしたらいいか。 新卒社員を育てるにはどうしたらいいか。 社内のコミュニケーションを 円滑にするにはどうしたらいいか。 情報共有を実現するにはどうしたらいいか。 デジタル化を進めるにはどうしたらいいか。 すなわち、強い組織をつくるにはどうしたらいいか。 これらを解消するには、しくみをつくって、 そのしくみに人材を貼り付けるのが得策です。 しくみをつくることで、特定の社員の資質に 依存しない経営が実現し、組織が強くなります。 ただ、どれほど優秀なしくみをつくっても、 社長と社員の価値観が揃っていなければ、 機能しません。 そのため、中小企業経営者が 最初にすべきことは、 「会社の土台を固めること」 「経営の柱を太く大きく育てること」 です。 では、どうすれば、土台を固めることが できるのでしょうか。 経営の柱を育てることができるのでしょうか。 どのように社員を教育すれば、 会社のルールが実行されるのでしょうか。 その答えのひとつが、本書です。 「何があっても潰れない組織」 「どんな状況にも対応できる組織」 をつくるためのノウハウを、実例と図解を 交えてわかりやすく紹介します。 中小企業の経営者はもちろん、 起業を考えている方、 会社で経営に携わる管理職の方も 必読! 強い組織をつくることは決して難しくありません。 750社超を指導してきたカリスマ経営者が 今日から使える超実践的ノウハウを伝授します!
-
4.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 No1週間経済誌「日経ビジネス」が2023年を徹底予測 日経ビジネス専門記者が解説 2023年の30業種を大胆予測 自動車・半導体・商社・機械… 円安・コスト高の影響 消費の行方は? 10大トピックス&スケジュール コロナ対策/ウクライナ侵攻/ポスト黒田 ほか 米・欧・中・日の賢人が予測 ! 日本と世界の経済はどうなる? 今ここにある米中の危機 台湾有事に備えよ 人生100年時代の見方、生き方、働き方 「絶望物価」「経済安保」「低年金サバイバル」 社会を変える注目の新技術11 Web3・空飛ぶクルマ・給電道路・空中ディスプレー ミトコンドリア治療薬・次世代原子炉…ほか ≪目次≫ ●徹底予測 2023 の見どころ 戦争、疫病、インフレ…… 先が見えない時代を生きる ●混迷の近未来を読み解く 世界の4賢人 特別インタビュー イアン・ブレマー氏、ビル・エモット氏、柯 隆氏、小林 俊介氏 ●高まる米中の緊張 「台湾有事」は起こるのか ●時代の大きな転換を示す 10大トピックス&スケジュール ●専門記者が2023年を読む 主要30業種予測 ●世界を変えるテクノロジー 情報・インフラ・医療を変える注目技術11 ●不透明な時代を乗り切る 人生100年時代の見方、生き方、働き方
-
4.5【こんな人におすすめ】 ・副業を始めたい会社員 ・ブログでちょっとお金を稼いでみたい人 ・寝ている間に収入が得られる仕組みを作りたい人 ・1年以内に本気で脱会社員を目指している人 ・すでにブログを始めているけどなかなか稼げていない人 ・Webライターでのクライアントワークにヘトヘトな人 【この本のポイント】 ・「サイト設計テンプレート」(エクセルやスプシで作成)に書き込んでコツコツ実行するだけで「稼げるブログ」が作れる ・Web用語は日本語でやさしく解説しているので文系さんにもおすすめ ・読むだけでSEOの知識が自然と身につく ・豊富な図解やチェックリストでやることが明確化していて分かりやすい 【SEOのプロ・著者のしかまるってこんな人(前書きより)】 サラリーマン時代の僕は人生に絶望していた。やりたくもない仕事、尊敬できない上司に笑顔で対応する日々。「なんのために働いているんだろう?」と葛藤を感じながらサラリーマン生活をしていた。そんなある日、僕はたまたま「ブログで稼ぐ」という方法と出会った。当時の僕はもちろん、ブログを開設するための知識やライティングスキルは全く持ち合わせていない。でも、幼い頃からやっていたバレーボールと筋トレについての記事を10記事ほど書いてみたところ、ある日の朝起きてスマホを見ると3円の報酬が発生していた。僕は衝撃を受けた。寝てる間にお金が増えている。たった3円と思うかもしれないが、何もしていないのにお金が自動的に増えたことは衝撃的だった。そこから僕はブログに文章を書いて稼ぐというゲームに魅了された。それから4年後。僕は会社員をしながらブログで月100万円以上稼ぎ、法人を設立して独立。法人1期目で年商1・5億の社長となった。
-
-【3,000以上のアカウント】と 【2,000万以上のフォロワー】を分析してわかった Instagramで売上とフォロワーを増やす方法。 3COINS(スリーコインズ)、BEAMS(ビームス)、atmos(アトモス)、WEGO(ウィゴー)、LOWRYS FARM(ローリーズファーム)、GLOBAL WORK(グローバルワーク)、mystic(ミスティック)......など 影の仕掛人の最新ノウハウを全公開! ー------------------------ センス、時間、予算がなくても大丈夫! ×映える写真だけ ×運用テクニックだけ この本を読めば、だれでも「Instagramの仕組み」が理解でき、 「時短で」高品質なコンテンツが作れるようになります。 ~目次~ 【基本】 ●アルゴリズムの理解がInstagram成功の最短ルート ●Instagramを成功させる7つの心得 ほか 【アカウント】 ●プロフィールはあなたのことを簡潔に伝える場所 ●アカウントの世界観を作る ●世界観の作り方 NG例とGOOD例 ほか 【写真】 ●スマホ撮りの基本は「垂直水平!!」 ●加工とは「誇張」ではなく「リアルの再現」 ほか 【動画】 ●1動画で数千フォロワー獲得も夢じゃない ●日常のできごとを切り取る ほか 【発信】 ●フォロワーが減らないストーリーズとは? ●ネタ切れ対策法 ほか 【分析】 ●「バズる投稿」はこうやって生まれる ●投稿データ一覧シートを作る ほか
-
3.6
-
4.5物語を通して楽しく学べる「ビジネス」と「生き抜く力」! (あらすじ) 中学校の図書室に忘れ置かれた不思議な『みんなの経営の教科書』と出会い、 ヒロトは仲間と共に社会の課題に向き合う――。 “人は誰でも自分の人生を経営している。だから、すべての人にとって経営は必要不可欠” という強い思いから、中学生から社会人までが楽しめる物語形式で書き下ろされた、 これからの時代に必要なビジネス素養が身に付く本。 ※本書は前から物語、後ろから“教科書”を読むことができます 【目次】 第一章 不思議な教科書 第二章 ぼくたちの放課後ビジネス 第三章 私たち、株式会社はじめます 第四章 俺たちの合言葉は「なんでも、どこでも!」 第五章 ワタシたち「ゴミ買います!」 放課後株式会社の奇策 第六章 放課後株式会社、乗っ取りの危機 第七章 伝説の経営者登場 あとがき 『みんなの経営の教科書』 基礎編 中級編 応用編 この物語はフィクションであり、登場人物、団体名等は架空のものです。
-
3.02020年からのコロナ禍によって、都市部でも地方でも、鉄道の通勤・通学需要や観光需要が激減し、鉄道会社の経営は大打撃を受けた。コロナ禍が終息しても、少子高齢化が続く限り、通勤・通学需要は減る一方だ。すでにローカル線の経営状況はかなり厳しく、バスへの転換も進んでいる。しかし、バスへの転換は、交通弱者の外出の機会を減らしたり、自家用車の利用を増やして環境への負荷が増えたりするなど、デメリットも多い。一方、成田・羽田・関空といった国際空港へのアクセス線の新設や西九州新幹線の開業、北海道新幹線や北陸新幹線の延伸、リニア中央新幹線の建設をはじめ、路線の新設・延伸の計画も数多くある。ローカル線はどうすれば維持できるのか? あらたな路線は日本経済の起爆剤となるのか? また、鉄道を活用したあらたなビジネスに、各社はどのように取り組んでいるのか? さまざまな視点から考える。
-
4.0
-
4.6ニュースにはたくさんの数字が出てくる。新型コロナウイルス感染症のパンデミックが世界を席巻してからは、なおさらだ。感染者数、陽性者数、再生産数、陽性率……。しかしその数字は、ニュースに出てくる時点で選択されており、記事のストーリーに沿うかたちで提示されている。因果関係は本当にあるのか。その数字は本当に「大きい」のか。増えた、減ったの判断の基準は本当に正しいのか。じつは数字によるミスリードにはパターンがあり、それを知っていれば大きな間違いは避けられる。具体的な例を使い、ユーモラスな語り口でその方法を伝授する。
-
-入門書を読んでも、実際チャレンジしようとすると続出してくる「あれ、この場合はどうするの?」の数々。 なんとなく、概要を理解して満足しただけでは、身にならない。 でも、いざ、やってみると、いろいろ迷ってしまい、わからないことだらけ……。 投資未経験の超初心の編集者が、FXカリスマブロガーの羊飼い氏のもと、自らFXに挑戦。 そこで、噴出してきた、入門書を読んでも、わからない数々の「?」を抽出し、より詳しく解説してもらった! 実際の口座開設から、初のFXトレードまでの流れも詳しく紹介。 そのままマネるだけで、超初心者からでもFXトレードができるようになる入門書の決定版! また、FX上級者にとってもうれしい、「羊飼いのFXトレードシート」も掲載。 初心者から上級者までお役立ち度満載、満足度満点の一冊。
-
4.3
-
4.0
-
4.2「人新世」(人類の経済活動が地球を破壊する時代)というウソがまことしやかに唱えられている。彼らは「脱成長」を唱え、「環境危機の時代を克服するには、資本主義による経済成長を諦めるべきだ」という。この一見、倫理的に思える脱成長論は、じつは社会主義・共産主義の復活を目論むレトリック、仮面である。経済成長を止めて全体のパイを減らし、弱者をよりいっそう貧しくさせる「罠」なのだ。資本主義よりも共産主義のほうが環境破壊を生むことは、かつてのソ連や現代の中国を見れば明らかだろう。また、気象関連災害による死者は経済成長とともに大幅に減少してきた。「人類はかつて自然と調和した素晴らしい生活を送っていたのに、資本主義と経済成長のせいで自然に復讐されている」という物語は、事実に反する。社会主義の大失敗と資本主義が人類を救ってきた歴史、自由な生活と経済成長がコロナ禍と貧困・格差、地球環境問題を解決できることを示した一冊。
-
4.0
-
4.4株価は上がっていても、自分の給料は上がっていない気がする人はいませんか? それ、自分自身の努力の問題ではなく、ぜんぶ国と日銀の政策が原因なんです。 菅内閣で内閣官房参与を務めた著者が、イチから日銀と国民の関係性を解説した上で、なぜ私たち一般庶民の給料が上がらない気がしているのかを解き明かします。 ・日本人の給料は30年前から上がっていない ・物価がやたら高く感じる ・アベノミクスって結局どうだったの? 本書はこれらの疑問をすべて解決します。
-
3.4少子高齢化による人口減少に加えて、コロナ対策で遅れをとった日本に逆転のシナリオはあるのか? 企業も個人もコロナ禍を生き抜くには、今までの常識を一切捨てて「戦略的に縮む」しかない。 累計88万部『未来の年表』シリーズの著者が、きわめて具体的な方法を提示する。 【目次】 第1章 先進国脱落ニッポンの逆転戦略 第2章 日本企業は「高品質・低価格」を捨てよう 第3章 コロナ後に勝つビジネスパーソンの働き方 第4章 縮小ニッポンの新しい生活様式と街づくり 第5章 「人生の未来年表」で戦略的に生き抜く 巻末データ集「平成の30年間で日本はこう変わった」
-
3.5脱炭素社会の基礎知識 次のビジネスはこの知識が武器になる。 カーボンニュートラルに世界の投資マネーが殺到! 第一人者による決定版! いまや環境問題は大きな経済問題として認識されるようになった。金融界も「カーボンニュートラル」を意識するようになり、株価や金融政策にまで影響を及ぼすようになった。この言葉が持つ「破壊力」を理解しなければ、まともな事業計画を立てることも、経済政策を議論することも、さらには良い就職先を選ぶことも、良い投資することも、これからはできなくなる。 状況の展開が急すぎて、何が起きているかを飲み込めずにいる人がなくないかもしれない。だが、菅政権が「2050年カーボンニュートラル」を不意に打ち出した背景には、世界規模での経済競争や地政学観点による事情があった。菅政権はそれを自ら打ち出したのではなく、本経済を守るために打ち出さざるをえなかったのだ。 わたしたちは今、とてつもなく大きな時代の転換点にいる。それに早く気づいた者だけが、これからの時代をリードしていくことができる。あなたはこの動きを追い風にできるか、それとも追い込まれてしまうのか? ◆担当編集者より 管総理の宣言で「カーボンニュートラル」は国策となった。経団連もこれを無視はできず、今までは懐疑的に見られていた「気候変動対策が次の経済成長のエンジンになる」という認識が広まりつつある。 今、この変化を追い風にできる会社と、逆に追い込まれる会社に、くっきり分かれつつある。二酸化炭素排出量が多い火力発電はもちろん、取引先を含む製造過程での排出量が多い製造業から、気候変動で投資先が製造ライン崩壊やサプライチェーン寸断など予測できない損失にあうリスクを抱える金融機関まで、カーボンニュートラルを目指した事業構成にしないと生き残れない。あの日本製鉄でさえ、高炉依存を脱却して電炉にも投資するなど大きな事業再編を強いられている。 一方で、環境技術やEV分野の技術で世界に先行する日本企業は数多く、重厚長大産業といわれてきた分野でも事業を切り替えて成長している会社が多い。スタートアップにもチャンスが巡ってきている。 このように、これからのビジネスパーソンは、カーボンニュートラルに対する基本的な知識なしには、先進的なビジネスに携わることはおろか、事業を継続することもできなくなってきた。本書はこの分野の第一人者が、カーボンニュートラルとは何かから始まって、気候変動が与える経済へのリスク、産業界の動向、そして新たに生まれた地政学的リスクをわかりやすく解説した入門書。
-
4.0
-
3.8
-
3.0
-
3.9
-
4.5気鋭の在中国・金融アナリストが読み解く! 貿易、IT、金融・・・ますますエスカレートする米中対立! 米トランプ大統領の対中攻撃は貿易、IT、そして金融の分野まで拡大し、「米中冷戦」「米国経済圏と中国経済圏のデカップリング(分離)」が、新型コロナウイルス感染症に苦闘する世界経済の新たな「重石」になりそうです。 対する中国も、騒乱の続く香港に「国家安全維持法」を制定。また、中印国境紛争や南シナ海、尖閣諸島などでの軍事行動を活発化させるなど、反撃に出ています。 特にアジア一の金融都市・香港をめぐる争いは「実際の戦争の一歩手前」ともいえる金融戦争の様相を呈してきており、今後も予断を許しません。 そんな米中対立を、日本と中国でグローバル企業向けに為替リスク管理の支援を実施し、中国本土、香港などの第一線で活躍してきた若き気鋭の金融アナリストでもある戸田裕大氏が徹底解明! 本書は、今後の日本、アジア、世界はどうなるのか? 米中対立の狭間にいる日本にはどんなチャンスがあるのか? などがすべて網羅された「中国観、世界観」を解説。そして対立の深層を鋭く分析。 世界を相手にする日本の企業戦士、中国IT企業やソフトバンクGなど中国経済の発展から利益を得ている日本企業へ投資を行っている投資家、中国人民元やドルなど外国為替市場に関係するみなさんにぜひご一読を進めたい一冊です。 米中対立がこれから5年、10年と、世界を覆う「暗雲」になることは間違いない以上、この1冊は不透明な情勢を読み解くためのヒント満載! 第一章 貿易、ITに続いて、ついに米中金融戦争が始まった! 第二章 中国の悲願・人民元国際化と通貨覇権争いの行方 第三章 国家安全維持法と香港が中国の繁栄に果たした役割 第四章 SWIFTかCIPSか? 通貨送金を巡る米中覇権争い 第五章 為替市場の仕組みと人民元レートの変遷 第六章 中国を為替操作国に認定した米国の真の狙いとは? 第七章 国家安全維持法施行後の香港と米中金融戦争の行く末
-
3.5カリスマYouTuber黒川敦彦氏の好評第二弾! 黒川氏が「予言」していた金融危機は、2020年3月、コロナショックという形で現実のものになった。 世界の株価は急減し、巨大な投資企業に変貌していたソフトバンクは1兆4000億円もの巨額の赤字を計上、農林中金、ゆうちょ銀行が保有する巨額のCLOの価格が暴落、日本銀行・金融庁が警告を発するなど、前著の指摘はことごとく現実のものになった。 アメリカ、EU、日本など各国の巨額の財政出動、金融緩和によって株式市場は持ち直したが、本当の超巨大金融危機はこれから訪れる。 リーマン・ショックを救ったのはチャイナマネーだった。 コロナ・ショックでは各国政府が市場を支えた。 しかし、近い将来、膨らみに膨らみ切ったバブルが破裂すれば、それを救えるものは誰もいない。 そのとき、真っ先に危機を迎えるのはどの企業か。 生保、メガバンク、航空会社、商社、ITなど、「危ない会社」を名指しし、危機を生き残る道を説く。 全国民必読の一冊。
-
3.6
-
5.0「シリコンバレー型資本主義」の本質は「失敗の肯定」にある! 「日本型組織」では、2020年代の富は生み出せない! 2000年代以降、世界のビジネスモデルは大きく変わった。 20世紀型の資本主義からシリコンバレー型の資本主義へ。 新型コロナで加速するビジネスの新潮流から日本再生の道も見えてくる。 シリコンバレーの盛衰をつぶさに見てきた著者が明らかにする 「お金とハイテクのからくり」 工場が富を生み出す時代からソフトウェアが富を生み出す時代。 そこではお金の動き方も大きく変化している。 2020年代も、その流れは変わらない。 なぜGAFAが隆盛を極めているのか? なぜ日本は低迷しているのか? 「アルゴリズムは現代の金型」「エア風呂敷」 「ソフトウェアが世界を食べる5・5世代」など わかりやすいキーワードを駆使し、その動きを解き明かす。
-
4.0還暦とはよく言ったもので、「人生100年時代」を迎えつつあるいまも、60歳は転機の年。仕事に区切りがつき、子どもは独立。そしていよいよ自分の人生の終わりも視野に入ってくる……。「50歳を境に人生をギヤチェンジしていこう」と勧めてきた著者が、いよいよ60歳を迎えるにあたり、いつかは訪れる死というものを、どのように受け入れればよいかを考えていく。「宗教家・哲学者・芸術家・文学者など古今東西の賢者たちから導きを受け、後半生をより良く過ごすために必要な「死生観」の養い方を学ぶ一冊。 第1章 自分で人生を作り出すということ 第2章 死といかに向き合うか――賢者達の死生観 第3章 この世とあの世の道理を学ぶ――宗教の教え 第4章 死の瞬間を表現する――文学と死生観 第5章 人はいかに生きて、いかに死ぬべきか――私の死生観
-
4.1現在、GAFAをはじめ、テック企業の成長を支える重要な職種として注目されるプロダクトマネジャー。 じつは、この本家本元はトヨタのチーフエンジニアである。 世界中で売れる製品を開発し続ける仕組みとは。 世界が注目するその仕組みの中心で司令塔の役割を果たすチーフエンジニアの秘密を 多くのヒット車をつくり続けた名チーフエンジニアが明かす。 トヨタはなぜ30兆円の売上と2兆円強の利益を出せるのか? もちろんよく知られた「生産方式」も強みのひとつ。 しかしどんなに生産方式が優れていても、売れるものがつくれなければ、ただの宝の持ち腐れ。 重要なのは、世界中で売れる製品を開発し続けること。 その仕組みがトヨタにはあった。 トヨタの製品開発の仕組みの中心にいて、 司令塔の役目を務めるのが「チーフエンジニア」という職種。 トヨタのイメージを変えたファンカーゴにbB、 北米市場で圧倒的人気を集めるカムリ、 商用バンのロングセラー車、プロボックス・サクシード ソニーとの協業によるコンセプトカーpod などなど、 担当した多くの新車をヒットさせ、 「試作車レス」「大部屋開発」「ユーザー対話型開発」など、 新たな開発の仕組みを考案したことでも知られる名チーフエンジニアが、 その仕事と資質・能力をつぶさに明らかにする。 自動車のみならず、 新商品開発に日夜努力するすべてのビジネスパーソン必読の書。
-
3.5
-
4.4もう「E<環境>S<社会>G<企業統治>」を知らずに仕事はできません! ワシントンポスト、CNN、エコノミストほか世界注目の第一人者による、 不況期こそ重要なESG入門決定版。 世界の巨大投資家が気づいている史上最大の破綻リスクとは何か? 世界の勝ち組企業がやっていて日本企業がやっていない唯一のことは何か? そして、新型コロナ不況をサバイブするESG思考とは? 2019年9月に開催された国連行動サミットでは、グレタ・トゥンベリの演説が注目を浴びた。欧米での積極的な反応にくらべ、日本国内では批判的な論調が強かった。しかし日本人に見えていない現実がある。世界の投資マネーはESG(環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance))に向かって怒濤の勢いで流れているのだ。その額はおよそ3000兆円! 製造業やIT系グローバル企業もぞくぞくとCO2削減目標を行動方針に掲げていることからわかるように、もはやESGとサステナビリティは世界の勝ち組企業の常識。これに対し、日本の取り組みは遅れが際立っている。 日本人が今ひとつ理解できていないESGの教科書として、ビジネスパーソン必携!
-
4.3今、日本のみならず世界中でウイスキーが大ブームとなっています。 どの蒸留所も需要が供給を上回り原酒は底をつき、新興のクラフトウイスキー蒸留所は至るところに作られる。 まさに「黄金の10年」を迎えています。 日本食ブームに乗ってジャパニーズウイスキーの存在が知られると、訪日外国人の目当ては日本酒からウイスキーに変わったり、 これまで寒冷地帯でのみ作られると思われていた中、インドや台湾といった熱い地域でも作られたり、 あるいは最高価格1本2億円で取り引きされるなどビジネス的な側面を備えたりと、 それらすべてはこれまでのウイスキーの概念を覆すものであり、それらはウイスキーの新教養とも言えます。 本書では、黎明期よりウイスキーを日本で広めてきた世界的に知られる評論家・土屋守氏が、 教養として知っておくべき「ウイスキーの歴史」「ビジネス的な側面」」「可能性を広げるクラフトウイスキー」を紹介。 ワインに迫る勢いで拡がりを増し、投資対象としても注目を浴びるウイスキー。 それはビジネスパーソンなら誰もが知っておきたい必須の教養である。
-
3.8
-
4.0インフレは投資家に対し不公正で、デフレは借り手に不公正。 ケインズの代表作を、わかりやすい訳で読む! 第一次世界大戦後、世界中で起きた急激な物価水準変動に対し、ケインズは何を考えたか。 物価安定か、為替の安定か。金本位制をどうとらえるか。 「邪悪な現実」と格闘するケインズの思考が、ここにはのこされている。 [本書の価値とぼくたちにとっての意義―訳者から] まず本書で重要なのは、インフレとデフレの相対的な被害についての明示だろう。1990年代からの20年以上にわたり、日本経済はデフレに苦しんできた。2013年に日本銀行が黒田東彦総裁の指揮下で2パーセントのインフレ目標政策をはっきり採用し、そのために大規模緩和(黒田総裁は「量的・質的金融緩和(QQE)」と呼んでいるが、あまり名称としては普及していない)を行ったことで、執筆時点ではようやくデフレの時代が終わりつつあるようだ。だが、デフレが有害だという認識が浸透するにはあまりに時間がかかりすぎた。デフレは物価が安くなるんだからいいものなんだ、という「よいデフレ」論を、高名な経済学者を含む多くの「有識者」なる人々が言いつのっていた。本書に書かれた認識―デフレは生産者に負担を与え、生産活動を控えさせ、人々を失業に追いやり、喜ぶのは既得権益を持った金持ちばかり―がもっと浸透していれば。 ここは重要なポイントだ。インフレやデフレは、実体経済に影響を与える。そして本書は、その仕組みについても簡潔に指摘している。お金の市場の状況が実体経済に影響を与え、持続的な失業を引き起こすこともある―これはケインズ『一般理論』の肝だ。本書は『一般理論』ほどきちんと定式化してはいないものの、それにつながる明確な認識がすでにある。 (中略) むろん、本書は管理通貨制度の夜明けに書かれたものだし、現在の中央銀行や金融当局ははるかに高度な理論もあり、考えるべき内容もきわめて多い。だがこの基本的な知見は、未だにかわらないものであるはずだ。 もちろん、もっと歴史的な文書として本書を読むこともできる。金本位制や、いわば「強い通貨」を主張する人々の変な議論は、現在でもいろんなところで見かけるものだ。それを見て、人間の進歩のなさを嘆く/おもしろがることもできる。さらに本書は、ケインズの一、二を争う名言が出てくる本でもある。「長期的には、われわれみんな死んでいる」というもの。経済学者は目先の問題―たとえば失業に対して、長期的にはそれが解決される、と言いたがる。できることは何もないとか、「自然に」任せるべきだとも言う。でも手をこまねいてそんなものを待つだけでは、経済学者も金融当局も存在価値がない。いまできることを考え、実行しよう!
-
5.0
-
3.5
-
4.3
-
3.8既存のマーケティングのフレームでは語られることなく説明の難しい現象が、私たちの身近で日々、起きている。 ネット上の「釣り広告」「ステマ」、リアル世界での「ホストクラブ狂い」「後妻ビジネス」、一向になくならない「振り込め詐欺」……。 こうした現象がなぜ起きるのか? 言い換えれば、「なぜ脳がハマってしまうのか」。 「悪を知らずして悪を止めることはできない」を合言葉に、2人のプロフェッショナルが「ブラックマーケティング」の解剖と対策に挑む! 悪徳商法や犯罪スレスレの商法以外にも、人々を熱狂させた「AKB商法」等のビジネスモデルまで幅広く扱うことで、ヒトの脳のだまされやすさを痛感し、自分の消費行動を振り返る! ・焦りにつけ込む「残り2点、お早めに」の効果 ・タイムセール…人は「できるのにやらなかった」ことを後悔する ・衝動買いと「考える買い物」では、脳の機能部位が違う ・出会い系アプリ、「だまされるほうが悪い」と言い切れない理由 ・ブームに乗るのは「脳の省エネ」 ・「何かに頼りたい人」と霊感商法 ・ソシャゲの罠…「タダ乗り」では楽しめないプログラム ・ギャンブル依存と浮気性の共通点 ・日本は詐欺師天国? ・「これさえあれば」と思わせる実演販売の威力 ・だまされやすい人は「カモ遺伝子」を持っている? ――私たちの脳は、無意識に「その気」にさせられて、何かが欲しくなったり、何かをしたくなったりすることが現実にたくさん起こっています。(序章/中野信子執筆 より) ――これまでのマーケティングは、キレイゴトしか扱っていない「よい子のマーケティング」ではないか。(終章/鳥山正博執筆 より)
-
3.6すべての人の心に感動を。感動にあふれた豊かな人生を。日々の暮らしにも、ビジネスにも使える、実践・感動学入門。著者独自の「STAR分析」を用いて、トヨタ/ホンダ、Yahoo!/Google、タリーズ/スターバックス、マクドナルド/モスバーガー…、『アナと雪の女王』/『千と千尋の神隠し』…が私たちにもたらす感動のタイプを解析。感動を創出する先端的な企業やプロジェクトを訪ねながら、「感動をデザインする」方法を明らかに。「感動する○○」はこうして創造せよ! * * *[本書の内容]はじめに第1章 感動の時代がやってきた第2章 これまでの感動研究第3章 感動のSTAR分析とは何か第4章 感動のSATR分析を用いた研究事例 4-1 類似会社の感動のSTAR分析 トヨタ/ホンダ、Yahoo!/Google、マクドナルド/モスバーガー、 タリーズ/スターバックス 4-2 製品・サービス・非営利の感動の比較 4-3 ストーリーのSTAR分析 アナと雪の女王、千と千尋の神隠し 4-4 STAR分析を用いたデザインの研究 ホッピー第5章 感動の実践事例集 5-1 一〇〇〇年後を見据え「美しい経営」をする「都田建設」 5-2 体験から感動が生まれる「ソウ・エクスペリエンス」 5-3 混沌の中から本当の自分を見つける「コモンビート」 5-4 自然の中、五感で感じる「森へ」 5-5 お義父さんのストーリー第6章 感動の見つけ方・高め方おわりに
-
5.0
-
-ボリス・ジョンソン英首相誕生!! 産経新聞ロンドン支局長として現地の情勢を生で体感してきた著者が、在英3年半の経験を活かし、激動の国際政治の真実を読み解く。「EU(欧州連合)からの離脱期限である10月末までに、必ず離脱を実現する」。英国のボリス・ジョンソン首相は、こう公言してはばからない。世界経済への悪影響が必至の「合意なき離脱」をなぜ進めるのか。議会制民主主義の母国である英国が陥った極度の政治的な混迷。国論は分断され、ポピュリストが民意を支配する。かつて7つの海を支配した老大国の「失敗」から、令和の日本が知っておくべき「教訓」とは――。ブレグジット(英国のEU離脱)を決めた2016年の国民投票以来、産経新聞ロンドン支局長として現地の情勢を生で体感してきた著者が、在英3年半の経験を活かし、激動の国際政治の真実を読み解く。
-
2.3
-
-見捨てられた農地や山林も新たな視点でとらえ直せば、宝の山としてよみがえる。都市・農村交流の伝道師が地域の資源を活用し、事業化する実践事例と、農村起業のかんどころを教える。 ○本書は2011年10月に刊行された同名書の大幅改訂、文庫化です。2001年にNPO法人「えがおつなげて」を立ち上げ、代表を務める著者の活動を追ったビジネス読み物。 ○活動拠点である山梨県増富地区は高齢化率60%(全国平均26.7%)、耕作放棄率も50%以上という典型的な過疎集落だったが、都会の若者、企業で働く人や外国人を巻き込む、都市農村交流を続けた。その結果、のべ5000人以上の開墾ボランティアや企業の参加者によって5ha以上の耕作放棄地が農地に蘇った。また活動を通して100人以上が移住した。 ○開墾されて出来た農地で作った酒米を原料に、日本酒や焼酎を開発、そのお酒を東京・丸の内の飲食店などで提供。マンション住民を対象にした農業体験ツアー、山梨県産の間伐材を大手マンションデベロッパーに納品するプロジェクトなど、活動は多岐に渡る。 ○「えがおつなげて」のユニークさは、内閣府、総務省、山梨県、三重県などの行政、三菱地所、味の素冷凍食品、東京海上日動などの企業、さらには大学との連携によって、様々なプロジェクトを拡大させていく手法にある。 ○こうした成果が評価され、「えがおつなげて」は、毎日新聞グリーンツーリズム大賞優秀賞、経済産業省ソーシャルビジネス55選、日経ソーシャルイニシアチブ大賞、共同通信地域再生大賞選考委員賞など各賞を受賞。活動領域は山梨中心から全国へと広がっている。
-
4.0
-
3.7「お金」「経済」「働き方」…今までの定説、常識が通用しない時代がやってきた。 従来からの「更新」「刷新」を意味する“2.0現象”は、さまざまな業界で起きている。 「電鉄」業界もその例を漏れない。 まさしく、時代の転換を迎えようとしている。 『電車に乗らなくても儲かる未来、それが私鉄3.0!』 そんな中、私鉄が目指すべきさらなる「未来=3.0」を提言しているのが、東浦亮典氏だ。 「顧客との決済やポイントを基盤とした新たなサービス」「鉄道、バスの次に来る新しいモビリティ」「ベンチャー企業支援」など、会社の未来、私鉄の未来、首都圏のまちづくりの未来を、東急電鉄の現役の執行役員という視点から大いに語る。 さらに、社名に「電鉄」の名を冠しているが、そもそも電車だけの会社ではない東急は、 なぜ、どうやって住みたい路線、駅などで常に上位にランクインされるようになったのか? なぜ、100年にわたり、高いブランドイメージを保つことができているのか? 東急の歴史を振り返りつつ、路線図には載っていない、新しい私鉄のカタチを大提言!!
-
2.52025年までに国内に開業が予定されているIR。カジノを核としつつも、その倍以上の収益が周辺のホテル、展示場、エンタテインメント施設から見込まれる。ラスベガス大手企業の日本トップが明かす最前線。
-
4.5多くの日本人は「物価が下がるのはよいことだ」と思っている。しかし、デフレで物価が下がるのはじつは悪いことずくめである。失業率が上がり、雇用が不安定な低賃金・非正規社員を増やし、企業収益率を下げ、人件費を削減させる。借金の実質負担は重くなり、実物資産投資は抑制される。自殺者が増え、社会的に有用な企業が廃業・倒産してイノベーションが滞る。「デフレなど問題ではない」と語る経済学者は、失業者や非正規社員の苦しみを理解していないのだ。欧米の経済学者と異なり、日本の経済学者はデフレの脅威に対して鈍感である。アベノミクスを実行した元日銀副総裁が、失われた二十年を「三十年」にしないためのすべてを記す。 ●デフレ脱却なくして日本経済の再生なし ●デフレはなぜ脅威なのか ●「失われた二十年」の原因とアベノミクス ●金融政策の条件と日銀財務に関する誤解 ●財政政策のリフレ・レジームへの転換が必要だ ●成長戦略の基本原則とは
-
-
-
4.0
-
3.5
-
4.3
-
3.7【世界同時株安も予見していた「投資の神様」が日本と世界の経済のゆくえを占う】ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロスと並び「世界3大投資家」と称されるジム・ロジャーズ。ソロスと設立した「クォンタム・ファンド」は、10年で2400パーセントという驚異のリターンを叩き出し、伝説となった。本書は、そんな「投資の神様」ジム・ロジャーズが、初めて日本の読者に向けて語り下ろした1冊である。伝説の投資家の目に、日本と東アジア経済の未来はどう映るのか。じつは、本書の取材を敢行した2018年夏の時点で、ロジャーズは「日米マーケットの好景気はうわべだけ。近いうちに破綻が訪れる」と断言していた。2018年12月末に、その予言はある意味現実となった。「リーマンショック級」の株安が日米のマーケットを襲ったのだ。ロジャーズはほかにも、リーマンショック、中国の台頭、トランプ当選、北朝鮮開国に至るまで、これまで数多くの「予言」を的中させてきた。名門イエール大学、オックスフォード大学で歴史学を修めたロジャーズは、「私の投資の背骨には歴史がある」と述べる。歴史から大きな「お金の流れ」を掴むことで、数々の予測を的中させてきたというのだ。このあと、お金の流れはどう動くのか? 本書では、世界史を参照しつつ、短期・長期両方の視点から、日中韓の将来を鮮やかに論じる。日本再興への道、朝鮮半島に訪れる刺激的で劇的な未来、中国のアキレス腱……「アジアの玄関口」シンガポールから世界を見つめる投資家の慧眼に映る、驚愕の未来予測。 【目次より】●序章 風はアジアから吹いている――ただし、その風には「強弱」がある ●第1章 大いなる可能性を秘めた日本 ●第2章 朝鮮半島はこれから「世界で最も刺激的な場所」になる ●第3章 中国――世界の覇権国に最も近い国 ●第4章 アジアを取り囲む大国たち――アメリカ・ロシア・インド ●第5章 大変化の波に乗り遅れるな ●第6章 未来のお金と経済の形
-
-2019年の「経済・政治・ビジネス」の動きを大前研一が特別講義! 世界と日本の動きを俯瞰し、今の問題とトレンドを解説。 世界の視点から日本をとらえ直して見えてきた次の時代とは。 2時間の講義で、2019年のビジネスと学びのための知識を身につけることができます。 *「大前研一ビジネスジャーナル」シリーズは、大前研一が主宰する企業経営層のみを対象とした経営勉強会「向研会」の講義内容を再編集しお届けしています。 本書は特別号として2018年12月に実施した講義を書籍化しました。 <トピック> ■総論―主導国なき時代へ。2019年以降の政治・経済・ビジネスの課題認識 西欧型民主主義から独裁型へ―国家モデルの主流が変遷 主導国なき時代。米ソでも米中でもない“Gマイナス1”の世界 米中ハイテク戦争でデジタル・ディスラプションが加速 アフター・トランプの世界では人材に企業・資本がついて回る ■世界経済の動向~かくして世界はGマイナス1へ 2019年の世界経済はピークアウトし減速 空前の好景気、しかし政治リスクの影に怯える日本 万博、IR―イベント誘致で栄えた例は先進国になし 「経営と屏風は広げすぎると倒れる」買収後の統合プロセスがキモ ■Gマイナス1=Me Firstの世界~民主主義は後退し自国ファーストが席巻する 貧困、ポスト・トゥルース……“トランプ問題”の背景 中国は報復ではなく米国の構造的問題を指摘すべき 国家モデルの変容~民主主義は色褪せ、独裁が支持される世界 明暗分かれるインドと中国、独裁主義の高効率 中国地方都市の成長はEUを凌ぐ“中華連邦”を生み出すか? ■新時代、人間の真価が問われる“デジタル・ディスラプション” 新興国で進むデジタルシフト、同時多発する“イノベーション都市” 自動車産業を直撃するデジタル・ディスラプションの3つの波 流通・小売業を襲う“Amazon Effect” ■次の年号/新時代、日本はどうすればよいのか? 3つの軸で世界を捉え、新時代を生き抜くべし 主権国家の終焉。道州制で日本を再編せよ
-
4.0「仮想通貨は終わった……」 相場の暴落を機に、メディアには否定的な報道があふれかえった。 しかし、ビットコインをはじめとする暗号通貨は、本当にこのまま消えてなくなっていくのだろうか。 私たちは、まだ暗号通貨の本当の可能性に気づけていないのではないだろうか。 本書は、『多数決を疑う』『マーケットデザイン』などの著作をもつ著者が、経済学の視点から暗号通貨の思想・制度設計・通貨としての役割を詳細に論じる。本書のタイトルは暗号通貨と国家を「vs」で対置させている。だが暗号通貨は「反国家」ではない。暗号通貨は「非国家」。国家に過度に集中した力を世のなかに分散させていくものだ。 暗号通貨で社会はいかに変革するか。 本書は今起きていること、これから起きることを冷静に見通すための手助けとなる1冊である。 ◎項目(抜粋) 危険なキャッシュレス 創造主(サトシ)は正体不明 通貨の本質とは何か? 徴税と暗号通貨 銀行預金のすごさ 国際送金とリップルXRP P2Pの世界通貨 すべては巨人の肩の上に立つ ビットコインとは何か マイニングの仕組み 多数決と正しい確率 ビザンチン将軍問題 管理者のいないコミュニティ ネットワーク効果――調整ゲームと協調行動 若きヴィタリクの情熱 トークンによる資金調達 ノーベル賞学者の参入
-
3.8“お金”とは何か。 私たちの財布に入っているお金には、100円、1000円、10000円などの価値がつけられています。 しかしよく考えてみると、ただの金属、紙切れにすぎないものをなぜ高価だと「信じている」のでしょうか。 貨幣や紙幣に込められた絶大な影響力――。 その謎を解く手がかりは、人類と会計の歴史のなかにあります。 先人たちの歩みを「損得」という視点で紐解きながら、「マネーの本質を知る旅」に出かけましょう。 くらしの経済メディアMONEY PLUSの大人気連載「簿記の歴史物語」待望の書籍化!! 【第1章】 偉人とお金の意外な関係 シャーロック・ホームズの“金銭感覚”/投資家として大成功したダーウィンの“目利き” ほか 【第2章】 なぜ「文字」よりも先に「簿記」が生まれたのか? 最初の簿記はメソポタミアの「駒」/ヨーロッパで起きた数字のイノベーション ほか 【第3章】 一国の運命をも翻弄する会計の力 球根1個で家が建つ!? オランダのチューリップ・バブル/フランス革命の引き金となる1冊の暴露本『国王への会計報告』 ほか 【第4章】 産業革命。そして、簿記から会計へ 産業革命は、なぜイギリスだったのか?/鉄道が生んだ公認会計士 ほか 【第5章】 これからの「おカネ」の話をしよう 財務省が消費税を上げたがるワケ/ビットコインが問いかけるマネーの本質 ほか
-
4.5経済発展は、格差の歴史 人類に“持続的な富の増大をもたらした4条件に迫る! なぜ、我々は豊かな生活を享受できるようになったか? そしてなぜ、豊かさの誕生は1800年代以降に限られているのだろうか? 近現代に持続的な経済成長をもたらした「繁栄の4条件」を、膨大な資料と、法律、歴史、哲学、天体力学、神学、政策科学、社会学、経済学の観点から探っていく。 ●条件1 私有財産権。具体的な財産に関してのみならず、知的所有権や、自分自身の身体についても、市民の自由として確立されていなくてはならない ●条件2 世界を精査・解釈する体系的な手順としての科学的合理主義の確立 ●条件3 新製品の開発や製造に対して幅広く誰でもが投資できるような近代的資本市場の成立 ●条件4 大切な情報をすばやくやりとりできる通信手段と、人や物を迅速に運べる輸送手段 格差や不平等を決定づける「豊かさ」の歴史を明快に分析した骨太の大作を文庫化。
-
4.8◆コーポレートファイナンスとは、企業の経営について財務(お金)の視点から考える学問です。 資金をどこから調達し、どうやって運用するか、経営の効率性と収益性を高め、 企業価値の向上を目指すにはどうすればよいかを考えます。 ◆「資金調達」「事業投資」「M&A」「株主への利益還元」といった企業の財務戦略を客観的に評価し、 意思決定を行うためのツールでもあります。 ◆本書は、企業経営に携わっている実務家はもちろん、初学者にも理解しやすいよう、 数式を極力排し、具体例をあげながら図表を豊富に用いて解説します。 ◆著者は大学のMBAプログラムで「企業財務」「企業金融論」などを教えるほか、 企業の経営幹部研修なども行っている、この分野の第一人者です。
-
4.0
-
3.0経済学者の浜矩子氏が、統計データや経済指標から導き出した、メディアでは報道されていない、日本経済の恐ろしい実態を暴く。日本経済の崩壊を食い止めるために、いま、全日本国民が読むべき、著者渾身の一冊。 株高、失業率の低下などにより、 「アベノミクスは成功している」という空気が世論を支配している。 ただ、一方で、日本の財政赤字が かつてないほどに膨れ上がっていることから 安倍政権に対して、なんとなく“違和感”を抱いている国民も多い。 経済学者の浜矩子氏によると、 メディアではほとんど伝えられていないが 経済学的な視点から切り込むと 現在“成功”とされている統計データもじつは、危険信号であり、 このままでは、日本経済が恐るべき副作用に襲われ、 日本経済“完全”崩壊というシナリオまで浮かび上がってくるという。 多くの日本人が抱き続けてきた アベノミクスへの“違和感”の正体がついに明らかになる! いま、日本人全員が必読の、著者渾身の一冊!
-
3.5
-
3.0月収300万円超の高級非正規雇用とは? 当初は30万~40万円した3Dプリンターはいくらになった? ドラッグストアの「脱デフレ優等生」とは? 巨峰より高い新型ブドウとは? 価格と料金のストーリーを追えば、素顔の日本経済が見えてくる。 記者が集めた面白エピソード満載! 本書で取り上げた商品・サービス シェアオフィス シェアリングビジネス プログラミング塾 仮想通貨関連サービス・商品 高級レンタカー 3Dプリンター ドローン オフィス家具 ベビーシッター ベビー用品レンタル マンション フードビジネス トラック運賃 インバウンド対応のお土産 簡易宿泊施設 LCC おもてなしサービス ワイン 日本酒 スイーツ マスク 目薬 ティッシュペーパー 教習所 有機野菜 サバ ノドグロ ペット向け商品・サービス 衣料品 クリーニング 名門小学受験塾 哺乳びん コメ 自動車関連商品・サービス 花 タオル 住みたい街 羊肉 ジビエ肉 シャインマスカット 制服 ウイッグ レアメタル 金 パラジウム ガソリン 原油 タコ ウニ 船賃 大豆 コーヒー 鶏肉