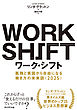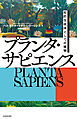教養 意味作品一覧
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●10万部超えベストセラー『今日から役に立つ! 使える「語彙力」2726』を語彙数、ページ、価格ともにUPした待望の第2弾! ●「1円で3語彙」の知識が身につく圧倒的なコストパフォーマンス! ●平成・令和で広まった新しい語彙や情報も満載! <目次> Part 1 コミュニケーション力がアップ! とっておきの言い回し Part 2 21世紀になって広まった 新語を使いこなしたい Part 3 敬語を使いこなせば 恥ずかしい思いをしない Part 4 ユニークなルーツの言葉 語源を探ってみる Part 5 読み間違え、 誤読をする人が多い漢字 Part 6 書き間違え、 誤字をする人が多い漢字 Part 7 意味を間違えて、 誤用している人が多い漢字 Part 8 古きよき日本語、 美しき日本語 Part 9 正しく使えないと残念、 誤表記したくない同音異義語 Part 10 意味が反対の対義語、 意味が似ている類義語 Part 11 ことわざ・四字熟語で 表現力をアップしよう Part 12 読めそうで読めない 難読・当て字の漢字 <電子書籍について> ※本電子書籍は同じ書名の出版物を紙版とし電子書籍化したものです。 ※本電子書籍は固定型レイアウトタイプの電子書籍です。 ※本文に記載されている内容は、印刷出版当時の情報に基づき作成されたものです。 ※印刷出版を電子書籍化するにあたり、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。また、印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。 株式会社西東社/seitosha
-
5.0◆『孫子』とは、一言でいえば戦略の本だ。自分が軍隊の将軍だったとして、ライバルの知らないような戦略やかけひきを自分だけが『孫子』から学べるなら、勝てる確率は高くなるだろう。しかし、もしお互いが同じように『孫子』を学んでいたら、こと知識の面では差がつかなくなる。 このとき、お互いの戦力も似たり寄ったりだったとしたなら、何が勝敗を決めるのだろう。指揮官の能力に焦点をあててみるなら、非常にプレッシャーの厳しい環境のなかで、人並みすぐれた洞察力や判断力、さらには学んだ戦略に対する応用力を発揮できるかどうかが、大きく問われてくるだろう。 ◆筆者は、この20年間、経営者や起業家、コンサルタント、ファンドマネージャー、弁護士、会計士、政府関係者、学者、格闘家、芸術家といった方々と、複数の中国古典の勉強会を続けてきた。また、雑誌連載や単行本執筆のために、多くの経営者にインタビューをしてきた。 彼らとの対話を繰り返すなかで、「勝負師」と呼ぶべき人々にはいくつかの共通点があることがわかってきた。幅広い知識と教養を持ち、良い意味で予想の斜め上をいく、余人には思いもつかないような発想をする人々――。本書は、そうした「勝負師」たちに共通する思考と行動を、中国古典やビジネス名著を繙きながら明らかにしていく。
-
5.0ビジネスマン&ウーマン、起業家、自営業、経営者、 そしてすべての働く人に読んで欲しい“ビジネスと生き方”の参考書! “美人社長”と“掃除の神様”の長時間に及ぶ対談を網羅! 購入者のみが見られる特典映像あり! “産廃屋”のイメージを一新した石坂産業の二代目、石坂典子社長と イエローハットの創業者で、日本を美しくする会の鍵山秀三郎相談役の 世代を超えた熱きトーク集。 「ミッションは“脱産廃屋”だと思ったんです」(石坂) 「自分のことに熱心な人は、立派な人とは言い難い」(鍵山) 「扱うものが汚い廃棄物であっても、それを扱う我々の環境が汚かったら、 それは意味が違います。だから徹底的にきれいにしようと」(石坂) 「益は無くても意味はある」(鍵山) 「“二代目は、女は、駄目でしょ”と聞かされ、心が折れそうになりました」 (石坂) 「“過去は変えられない”と言いますが、変えられるんですよ」(鍵山)
-
5.0年間200回の研修を行っている接客・接遇講師が、自らの体験をベースに、現役の奈良・薬師寺僧侶に質問をする形で、「おもてなし」の心の本質に迫ると同時に「日本人の心」について深く考察します。 【目次】 第一章 薬師寺が育んできた、「もてなしの心」 あいさつひとつにも、「もてなしの心」を込める 人を惹きつけるふるまいとは なぜトイレがきれいな店は繁盛するのでしょう? 誰に対しても気持ちのいいサービスをするために おもてなしのモチベーションを保つために 第二章 日常にできる、おもてなしのための自分磨き 毎日の仕事にこそ心を込めるのです たくさんの「ありがとう」を口に出しましょう 笑顔は何よりも美しいものです 「お辞儀」にはどういう意味があるのでしょう? 今こそ「正しいこと」の本質を見つめましょう 清らかな心をもちましょう 腹を立てず、心を穏やかに保つコツ 第三章 他人だけでなく、自分も幸せになる「もてなしの心」 勝ち負けにこだわりすぎないでください 「成功」=「幸福」だとかん違いしてはいけません 知らず知らず慢心してしまう心に 「利他」の心をもち続けましょう 周りに惑わされずに働くために お客様のために、一生、学び続けましょう 第四章 仏教もおもてなしも、人が幸せになるための智慧 マナー・接遇の背景にある仏教の心とは 縁を大切にしましょう 若い人たちに伝えていきたいこと 悪口や中傷はどう受け止めればよいのでしょう? 引き継いだものを伝えていきましょう 手を合わせましょう
-
5.0どう生きる (あさ出版電子書籍) ◆著者のコメント 「どう生きるのか」という問いに、私なら「自分の命を大切にして生きることだ」と答えるでしょう。それは親から頂いた自分のルーツを大切にすることと同時に、自分の命を大切にすることを意味します。 人生は一度しかありません。人生にリハーサルはありません。たった一度の人生をどう生きるか、真剣に考えて、その答えを毎日求め続けてください。その前向きな努力の中から、きっとあなたの答えが見つかるでしょう。 頑張ってください。(青木仁志) ◆著者はこんな人 坂本光司(さかもと・こうじ) 浜松大学教授、静岡文化芸術大学教授を経て、2008年4月より法政大学大学院政策創造研究科(地域づくり大学院)イノベーションマネジメント研究科(MBA)兼担教授法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長。全国7000社以上の企業訪問をし、「現場で中小企業研究をし、頑張る会社の応援をする」ことをモットーにしている。著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズ他、多数がある。 青木仁志(あおき・さとし)) 10代からプロセールスの世界に入り、国際教育企業ブリタニカ、国内人材開発コンサルティング企業を経て、1987年、32歳でアチーブメント株式会社を設立、代表取締役社長に就任。自ら講師を務める公開講座「頂点への道」スタンダードコースは、講座開講以来22年間で564回開催、新規受講生は26054名を数え、国内屈指の公開研修となっている。2010年から2013年まで法政大学大学院政策創造研究科客員教授。自ら実践してきた理念経営による起業家育成、経営者育成にも力を入れている。著書に『一生折れない自信のつくり方』他、多数がある。 ■目次 ●1 人として生きる幸せはどこに ●2 人として守るべきもの ●3 「前」へと進むために ■著者 坂本光司 青木仁志
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ぱっと見、ちゃんとしているのに、「残念な資料」「伝わらない資料」はそこら中に転がっている。 本書は、年齢、役職、業種を問わず、様々な資料を添削してきたコンサルタントが、その原因と対策について詳細に記す。 自分の手で「ロジカルな伝わる資料」に進化させる方法を説いた、画期的な1冊だ。 【残念な資料の3つのパターン】 1 何のために書いた資料なのかの目的が曖昧……無秩序な箇条書き、ムダな情報の詰め込み、意味のないフレームワーク活用 など 2 結論が書かれていない……そもそも結論が必要だと思っていない、抽象的すぎてよくわからない など 3 結論の根拠が書かれていない……整理軸はあるが軸に不足がある、絵でごまかしている、矢印がいっぱいあって混乱している など →自ら資料の完成度を診断し、欠点がわかるようになる! 【ロジカル資料への4つのステップ】 ステップ1 結論を明確にする ステップ2 目的をあぶり出す ステップ3 結論を具体化する ステップ4 根拠を作り直す
-
5.0【「答えのない」禅問答で考える力(発想力・新たな視点・思考の持久力)が磨ける】 禅問答とは、禅の修行で弟子の固定観念を打破し、悟りへと導くための手段として用いられる、禅者の言動や問答などのこと。際立った思考を求め、常識では理解困難だったり解決不可能だったりします。 ただ、「非常識的」ではあるが、「非論理的」ではないのがおもしろいところ。この「ちぐはぐで分かりにくい問答」を、あえて「考える」ためのエクササイズとして読み解くのが本書です。 【読み進めるうちに考えることが楽しくなってくる「深すぎる」話】 答えという結果ばかりを求めると、どうしても不安におちいります。そして結果を出すプロセスを省略したくなり、様々なものを味わい、おもしろがることができなくなってしまうのです。 意味不明な問答について、解説を読みながら何とか理解するヒントを探していると、どんどんおもしろくなってきます。わかりそうで納得できないところも、これまた絶妙におもしろい。 これを繰り返しながら、わからない不安がおもしろさに変わっていく本です。 【禅問答の一番おいしいところが一冊で楽しめる】 本書であつかうのは、「語録の王」と称される『臨済録』におさめられた禅問答。これは、唐の時代の中国で活躍した臨済義玄という僧のおこなった説法や問答などをあつめたものです。その名を冠した語録が編まれるのはたいへんな大物だという証で、臨済は中国禅宗史にあって屈指のビッグ・ネームです。 その臨済が残した問答のなかから、選りすぐりのものを解説しています。 【イラストと丁寧な解説でわかりやすく、飽きない】 禅問答の難しさの理由の一つに、非常にハイコンテクストだということが挙げられます。それぞれの問答をじっくり味わえるよう、背景が理解できるイラストを入れています。また、優しい語り口と丁寧な解説で、当時の僧たちが何を考え、行動し、どう生きたのかひもときます。
-
5.0新元号「令和」をタイトルにつけた日本最初の単行本! ベストセラー『仕事消滅』の著者によるAI君臨時代に必要な3つのスキルとは!? 学校では絶対に教えてくれない“本当に大切な話”。 ◎なぜ、ユーチューバーやキャバ嬢の仕事を知るべきなの? ◎AIは、仕事を奪うもの? 与えてくれるもの? ◎日本ってどうして幸福度が低いの? ◎20代から「お金にお金を稼がせる」なんて、本当にできるの? ◎「年収180万円でも幸せに生きられる」ってどういうこと? 「君はいま、スマホとユニクロとコンビニがあれば生活は成り立つだろう。それで幸せなら、令和の時代はマックジョブを生業とする「新下流層」として生きていける。 そんな人生は面白くない、潤いのある人生を送りたいと思うなら、君自身を新時代にアップデートすることだ! 変化の時代はチャンスの時代でもある。 本書は、本格的なAI時代に、若い人たちがどうすれば人生をもっと楽しく、冒険に富んで、意味のあるものにできるのか、その手がかりを得るために書き下ろした。君の人生の海図を描く一助になると確信している」(著者) ──脳みそに、シャワーをかけろ!──
-
5.0本書は、他を圧倒する収録語数で人気のベストセラー「大人の語彙力」シリーズ最新刊。 今回は、日本語の「語源」の世界に分け入り、知っておきたいことばのいわれや成り立ちを厳選してお届けした。悲願 この「悲」は悲しみという意味ではない! いぎたない「いじきたない」とはどこがどう違うのか 五月晴れ いまと昔では全くニュアンスが違うことば けれん味がない「けれん味」って一体どんな味?ご挨拶に代えさせていただきます 挨拶したのになぜ「代える」なのか「読む」「書く」「話す」ときに迷いがなくなる、目からウロコの方法を満載!
-
5.0世の中で「一流」と言われる人には共通点がある。 ──それは、ご先祖さまを大切にすること。 たとえば、成功している企業経営者には、会社の中に神社や仏壇をつくって、社員にもそれをしっかりお奉りするよう指導している人が少なくない。 私生活でも、毎日きちんと仏壇に線香やお水を上げたり、仏壇はなくても自分なりのやり方で、先人への感謝を表現したりしている人が多くいる。 自分と血のつながっている直接のご先祖さまに限らず、日本人全体のご先祖さまという意味で、さまざまな先人への感謝の儀式にも一流の人は意識を払う。 ──それはなぜなのか? 日本人の宗教意識や倫理観についての言論活動を続けてきた、作家・一条真也が解きほぐす心の読み物。
-
4.7デジタル化が進む小学校で定年間近の昭和ティーチャーが学びを深めつつ子どもを伸ばす教師の本来の力を発揮 1人1台時代に突入した小学校を舞台に、前向きな初任者やEdTechに強い教師、ICTが苦手な教師など多彩な顔触れ。子どもたちと共に情報端末に触れ、様々な問題に直面しつつそれを乗り越えて教師も子どもも成長していきます。その背景には、デジタル社会になっても変わらず受け継がれる教師のあり方が描かれています。 「誰だって苦手なことはある。少しずつでも変わっていけばいい」など名言も随所に、教育の根本を考える機会も得られます。 最新情報満載のコラム「デジタル社会の教育を考える教養書」も必見。 【目次】 第1章 授業改善を共通の目的にする──子どもたちの資質・能力を育成する 第2章 情報の意味を理解する──テキストとコンテキスト 第3章 自ら学ぶ力を育てる──人とつながりながら学ぶ力を高める 第4章 学習者の視点に立つ──昭和二二年度の学習指導要領 第5章 批判的思考力を高める──子どもたちが学びとる授業へ 第6章 教師も学び手として成長する──授業研究会も変化させる 第7章 スキルとモラルの両方を向上させる──保護者と一緒に考えるルール 第8章 人間としての心と力を育てる──十年後の未来 【著者】 前田康裕 1962 年、熊本県生まれ。熊本大学教育学部美術科卒業。 岐阜大学教育学部大学院教育学研究科修了。公立小中学校教諭、熊本大学教育学部附属小学校教諭、熊本市教育センター指導主事、熊本市立向山小学校教頭、熊本大学教職大学院准教授、2021 年4月より熊本市教育センター主任指導主事。『まんがで知る 教師の学び』『まんがで知る 未来への学び』シリーズ(さくら社)他著書多数。
-
4.7よくわからないまま働き始めた君へ、「働き方のモヤモヤ」に答えを出す! 『ビジネス書図鑑』『世界「倒産」図鑑』著者が物語で贈る、「幸せ」と「仕事」を巡る12の講義 News Picks取締役 佐々木紀彦氏推薦 「すべての20代、30代に読んでほしい」 新人社員サカモトは自分が働く意味を見出せずにいた。 「このまま今の会社にいていいのか?」 「自分の価値とは何なのか?」 そんなサカモトや同期たち、新人社員の前に 伝説の人事部長「石川さん」が姿を現した――。 寓話から仕事や働き方に光を見出す 新感覚ビジネス小説!
-
4.5
-
4.5「はっきり言って、いまの学校はオワコンです」 年間1万人が学校説明会に来る校長先生が教えるミライの授業 「日本で一番学校説明会に人が集まる」とも言われる千代田国際中学校校長・日野田直彦。 定員割れで予備校が出す偏差値が「判定不能」、9年で5人も校長が交代する倒産寸前の状態からV字回復し、学校説明会には毎年のべ1万人以上もの親子が参加している。 「塾なし、海外経験なし、経済力なし」の生徒を海外大学に多数進学させ、海外の有名大学が「日野田の教え子が欲しい」とわざわざ駆けつけるほど。 そんな学校の生徒は「言わなくても勝手に勉強する」「授業にダメ出しする」さらには「学校説明会をジャック」……!? 偏差値50のごく普通の学校から、そして偏差値「判定不能」にまで陥った経営不振の高校から多くの海外進学者を出した、年間1万人が学校説明会に来る、いま注目すべき校長先生が日々子どもたちに伝えている、そして「2050年」を生き抜くためのミライの授業。 【本文より(抜粋)】 いまの学校は限界にきているということです。はっきりいって「オワコン」です。 それは、日本一の難関大学である東京大学や、その東大に多くの生徒が進学する御三家とよばれる中高一貫の名門校、さらには受験戦争を乗り越えるために日々奮闘している予備校や進学塾も例外ではありません。(中略) ぼくが教育に携わっているのは、日本を変えるためには一番効果的だからです。(中略) 成績が上がらない、あまり学校や先生が好きじゃない、どうしてこんな勉強しなきゃいけないんだろう、なぜ、大学に行かなきゃいけないんだろう、どうせ自分なんて……と思い悩んでいる人にこそ、この本を読んでほしいと思います。 その悩みや違和感はまちがいではありません。ぼくもタイから帰ってきてそう思いました。 でも、少しだけ視点を変えてみてください。すると、世界はちがって見えてきます。(中略) 中学生や高校生のお子さんをもつお父さんやお母さんがたにも読んでほしいと思います。(中略) ぼくは教育で社会を変えたいと思っています。そのためには仲間が必要です。一緒にワクワクする社会をつくりましょう。 【目次(抜粋)】 第1章 学校はオワコンだ 世界はものすごいスピードで変化している/学校はなんのためにあるのか/「いえない」「いわない」「いわせない」/高度成長を支えた学校/日本は課題先進国/日本よりバンコクの方がイケてる!?/犯人探しはもうやめよう/日本と世界のいいとこ取りが最適解 第2章 ぼくがつくっている「ミライの学校」 足りないのは英会話力じゃなくて思考力/世界のクレイジーに会いにボストンへ/たった2万9800円でハーバード短期留学?/校則を変えたかったら企画書を持ってきなさい/学校説明会を生徒がジャック/コロナ禍で企画書が飛び交う学校 第3章 帰国生、校長になる 関西人、タイで暮らす/監督の話で気づかされたオーナーシップの意味/恩師に「苦手なことや嫌いなことを選べば幅が広がる」といわれ教育の道に/進学塾で気づいた日本の教育の本質 第4章 ミライの勇者へ コロンブスは夢見るプータロー/英検2級に落ちるほど英語が苦手でも海外へ/大切なのはオーナーシップ/失敗できるヤツが一番偉い/「あんただれやねん?」に答えられるか?/「振り返りは「反省」ではない/留年寸前から世界150位の大学へ/教養とは自由になるための技術/アウェー体験があれば強くなれる/日本の強さは「まあまあ力」/人生は逆張り 第5章 Go Abroad ! ―海外進学の道 海外進学のポイント/さまざまな英語試験/アメリカの大学は3種類/インターナショナルスクール生が使う裏技/いまがチャンス ……ほか 【電子書籍版ご購入に際しての注意事項】 ●本書は、同名の紙媒体の出版物(紙書籍版)を底本として作成しているため、内容は、原則、紙書籍版印刷当時のものとなります。 ●紙書籍版とは色見が異なる可能性があります。ご購入前に、必ず、電子書籍版のサンプルにて表示状態をご確認ください。
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 誰でも楽しみながら知識が身につく、教養としての建築学! 日本には約1300年前に建立された世界最古の木造建築である法隆寺をはじめ、古い時代に建てられた建築が数多く残っています。それなのに建築を知らないままではあまりにもったいない! この本は、古代から現代までの約1300年間につくられた日本建築から主要なものをキーワード(用語)とともに選び出し、その意味や成り立ち・歴史を楽しみながら学ぶことができる、大人の図鑑です。 1300年の建築の歴史を総ざらい! ビジネスシーンで役に立つ、武器になる知的教養。 ●主要目次 【古代】 【中世】 【近世】 【近代】 【現代】
-
4.5仲間とは? 家族とは? 人間とは? 学びとは? 人生とは? そして日本人が世界に誇る特性、信義、誠実、勤勉、礼儀正しさの本質とは何なのか? 論語に通じている人や組織は、強くしなやかである。 それは人間の本性をストレートに理解しているからだ。 読むたびに気づきを得る“東洋の大古典”論語の世界。 ただ読み流すのではなく、各項の本質をつかみたい。 そこで、本書では全文の現代語訳、書き下し文、原文に加え、覚えやすい【一文超訳】を掲載。 テーマは何か、主旨は何かが一目で把握でき、格言のように心に刻まれるので、論語の理解が飛躍的に向上する。 また、主要な人名や日本人に馴染みのない語句には注釈を入れた、現代の論語完全版。 【一文超訳の一例】 「口がうまく、つくり笑いをするような人間に本物は少ない」 「人と誠実につき合い、余力があれば教養を高めよ」 「上に立つ人は、重厚で威厳ある人がいい」 「父に学び、死後3年はやり方をかえるべきではない」 「親しき仲にも礼儀あり。いつも礼と和の調和をはかること」 「約束は道理で判断し、人づき合いは礼に気を付ける」 「子は健康であることが一番の孝行である」 「温故知新ができてはじめて人の師となれる」 「専門バカになるな」 「よく学ぶ人には、仕事と給料が向こうからやってくる」 「過去の歴史を学べば、未来も読める」 「儀式にはもともと意味があるはずで、無駄に思えることでも安易に否定してはいけない」
-
4.5本書は、外資系企業に30年間勤務し、ビジネスの現場で戦略構築と実践をしてきた著者が著す、実務で役立てるための戦略の実践書である。著者の現場での経験を主体に、マーケティング理論や経営理論に基づいて書かれている。いかに理論に基づいてきれいな戦略や企画を立てても、それだけでは意味はない。戦略や企画は、実行され成果を上げて、はじめて価値を生み出す。そのためには、日本企業の強みである「徹底した現場主義」で「顧客中心主義」を推進することが必要だ。しかし現代の日本では、「顧客中心主義」はいつの間にか顧客の言いなりになる「顧客絶対主義」に置き換わり、「徹底した現場主義」は「戦略なき迷走」に陥っているのが現実だ。そこで本書はビジネスパーソンの目線で、「顧客中心主義」に基づいた戦略力を身につけ、日々の現場で実践していくための考え方を紹介している。一人一人が主体的に戦略を考え、現場が「顧客中心主義」で戦略的に動けば、ビジネスは大きく成長する。本書は、戦略を考え、現場を動かし、成果を出そうと日々苦闘している全てのビジネスパーソンに役立つ本だ。
-
4.5お金を稼げる人・稼げない人の差は能力ではありません。マインド(思考)です。なのに、多くの人が「学歴がないから」「能力がないから」「元手がないから」という理由で収入アップをあきらめてしまっています。実にもったいない話です。しかも20代、30代といった若い人に、決して多くない収入に甘んじてしまっている人が多い。そこで、もう一度はっきり言います。マインドを変えれば、あなたも必ず稼げるようになります。本書は、高校中退、20歳そこそこで300万円もの借金があったにも関わらず、今では年収1億円になった著者の成功法則をまとめたものです。「時間」のみを最大の価値にしている/成功者を徹底的に真似する/リスクを自ら作る/お金を払ってお礼を言う/人に批判されることをやる/変化しないほうがリスクと考える……億を稼ぐマインドを身に付け、自由な時間と大きな収入、本当の意味での幸せを手に入れるための本。
-
4.5
-
4.5<自衛隊に学ぶ「逆境に負けない」技術> 元自衛隊幹部が教える自衛隊式のセルフコントロール。危険地帯や災害現場など、緊迫する場面でも、落ち着いて安全に活動できる自衛隊の能力の根底には、徹底した「自己管理術」があります。本書は、自衛隊で鍛え上げられたノウハウを、わたしたちの日常生活でも応用できるように紹介します。 <自衛隊式トレーニング> 自衛隊では、まず身体のぜい肉を削ぎ落し、戦闘行動に耐えられる筋肉を持つ身体へと鍛え上げられます。それと同時に叩き込まれるのが、集団行動を支える躾(しつけ)とルールです。これらの作業は、いわばパソコンのハード(身体)とOS(考え方、意識)を、自衛官用の新しいシステムに更新することを意味します。本書では、自衛隊式の考え方、意識の持ち方、手順やルールをベースに、私たちが日常生活や職場など、さまざまな場面で活用できる「セルフコントロール」のメソッドを紹介します。絶体絶命の場面でも、冷静に「最善手」を打てるよう、あなたも自衛隊流の技術を取り入れましょう。 【目次】 ●Chapter01 自衛隊生活が始まる時から徹底されること 躾(しつけ)編 ●Chapter02 セルフコントロール 回復・解除編 ●Chapter03 セルフコントロール 強化編 ●Chapter04 セルフコントロール 予防編 ●Chapter05 敵を知る ●Chapter06 日常生活における習慣化 ●Chapter07 ビジネスに役立つ自己コントロール
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、リース業界に入社したばかりの新人や採用を目指す学生、リース業界と関わりを持つパートナー企業やクライアントを対象に、リース業界の儲けの仕組みと業界の全体像、具体的な仕事の内容を1冊にまとめた書籍です。リースというと、一般には複合機のようなオフィス機器が思い浮かびますが、実は、建設機器や飛行機、医療機器など、幅広い業種を対象にリース業務は行われています。顧客に資金を貸す代わりに、物件を購入してそれを貸し出すリースのビジネスモデルは、いわば一種の金融業であるともいえます。こうしたリース業界は、現在、激変のときを迎えています。リース取引に対する会計基準が変更され、これまで資産としてみられなかった船舶、飛行機、倉庫などにも、バランスシートへの記載が義務づけられようとしているのです。そうなれば、リースの会計上のメリット、事務効率のメリットが薄れ、業界に大きな損失を生む可能性があります。本書は、いろいろな意味で注目を集めるリース業界の現在と将来を、1冊で見通せる教科書です。
-
4.5累計22万部突破の問題地図シリーズ最新作! 「能力がないクセに、担当先がいいから高評価、不公平だ!」 「担当窓口と信頼関係を作ったはずなのに、他社に負けた……」 「営業する時間を削ってまで会議して、結局なんか意味あったっけ?」 「足を使うより頭を使って効率的……って、成果出てないんですけど」 「がんばって日報を書いてもフィードバックが全然ない、意味あるの?」 「マネジメントに専念? 出来の悪い奴ばかりなのに、無理でしょ!」 「人によって営業スタイルが違いすぎ! 何が正解なの?」 前を見ても横を見ても問題だらけの営業部、どう変えていけばいいのか? 数多くの営業コンサルティング実績を誇り、17万部突破の『御社の営業がダメな理由』をはじめ数多くの著書で定評ある著者が、生産性の高い営業に変える方法を教えます。
-
4.5【内容紹介】 SBIホールディングス北尾吉孝社長が、自身の経験談を交えて、安岡の教えを現代風に解説を加えた。 ビジネスの現場で、数々の試練を乗り越えるために必要な教え、人間力の高め方が身につくはずだ。 【目次抜粋】 はじめに I 人間の基礎を固める為に必要なこと 人としての土台をつくる為に人間学を学ぶ 生きる力は片言隻句によってこそ表現される 本によって人間としての基礎をつくる 自分が主体になって学ばないと意味がない 良き師と巡り合うことが人間的成長を促す なぜ『英雄伝』『偉人伝』を読むと良いのか II 世の中に漕ぎ出る前に知っておきたいこと 「天」と共に生きる心強さ 良い縁が良い運を引き寄せる 人生の岐路に立って考える 天職を見つけるとはどういうことか 人間が備えるべき3つの識 黄金の奴隷になるな 本当のグローバル人材になる為に必要なもの III 一流の仕事人になる為に身につけるべきこと 自らを知って初めて大きな仕事が出来る 仕事とは「世の為人の為」に働くこと 権力は志の実現の為に使わなくてはならない 若いときの苦労は買ってでもしろ ハードな交渉にも動じない肚をつくる 上司に評価される社員に必ず備わっている資質とは何か 組織で自分の価値を発揮する為にどう考えるか IV 上に立つ者が絶対に知っておくべきリーダーの心得 リーダーに求められる4つの要素 人を見るときの6つのポイント 何が事業の成功をもたらすのか 努力しても伸びない部下をどう処遇するべきか 同志的結合がチームを強くする 事業を成功させる為には「機」を逃してはいけない V 人生の成熟期を迎えたときに考えておくべきこと 健康であってこそ仕事も人生も面白くなる 年を取っても若々しい精神を保つ為の3つの心がけ 出処進退のあり方がその人の人生を決める いかに終わりを全うするか 全ては自分次第 あとがき
-
4.5この世に、くだらないものなんて、ない。僕がミドリムシと歩んできたこの10年のストーリーで伝えたいことは、このことだけなんです――。2012年12月に東証マザーズ上場を果たす、東大発のバイオベンチャー、ユーグレナ。その創業者である出雲充氏が、起業までの7年間と、起業してからの7年間を、初めて語る!■ミドリムシに秘められた可能性――世界初の快挙「ミドリムシの屋外大量培養」は、なぜ夢の技術なのか?「ミドリムシ(学名ユーグレナ)」。この動物と植物の両方の特徴を併せ持つ「ハイブリッド」ともいうべきこの微生物は、なんと59種類もの栄養素を生み出し、光合成により二酸化炭素を吸収し、しかも「バイオ燃料」を取り出すこともできます。つまり、「食糧・栄養問題」「地球温暖化問題」そして「エネルギー問題」という世界を悩ませる大問題を一気に解決する生物なのだ。そんなミドリムシの大量培養を世界で初めて確立したのが、東大発のバイオベンチャー、ユーグレナなんです。■初めて語られる起業ストーリー――全世界注目の起業家が乗り越えてきた試練とは?2012年、出雲氏は、世界経済フォーラム(ダボス会議)で「ヤンググローバルリーダーズ」、ジャパンベンチャーアワード「経済産業大臣賞」を受賞するなど、全世界から注目を集める起業家のひとり。バングラデシュで栄養問題に出会ってしまうところから始まる本書では、ミドリムシ、そして頼れる仲間との出会い、迷いのなか起業に踏み切ったこと、テクノロジーを継承しブレイクスルーしたこと、次から次へと現れる巨大な試練にどうやって立ち向かったか……など、今まで語られることのなかった起業ストーリーが明らかにされます。■だから、くだらないものなんて、ない。――いま目の前にある小さな可能性に目を向けよう!ミドリムシという小さな生物の可能性を何とか引き出して、世界中に伝えよう――。10年にわたって向き合ってきた出雲氏であればこその、「いま自分が取り組んでいる小さな仕事に、世界を変える大きな意味がある」というメッセージに、心震えます。ミドリムシから取り出したジェット燃料で、飛行機が飛ぶ日がもうすぐやってくるかもしれません。
-
4.4「経験と勘と口伝」で積み上げられたものと思われがちなマネジメントには、実は学問的な裏付けがある! マネジメント理論の巨匠18人を選び、彼らの提唱した理論からクイズ形式で効率的に根幹を学べる一冊。 後輩ができたらぜひ、課長を目指すなら絶対おさえておきたいマネジメントの基礎理論。 【著者紹介】 海老原嗣生(えびはら・つぐお) 雇用ジャーナリスト。1964年生まれ。 大手メーカーを経てリクルート人材センター(現リクルートキャリア)入社。 以後20年以上、リクルートグループで雇用に関する取材、研究、提言を行なってきた。 現在リクルートキャリア社の第1号フェロー【特別研究員】として同社発行の人事・経営誌『HRmics』の編集長を務める。 経済産業研究所制度改革プロジェクトメンバー。広島県雇用推進アドバイザー。 『雇用の常識「本当に見えるウソ」』『面接の10分前、1日前、1週間前にやるべきこと』『2社で迷ったらぜひ、5社落ちたら絶対読むべき就活本』(プレジデント社)、 『なぜ7割のエントリーシートは読まずに捨てられるのか?』『もっと本気でグローバル経営』(東洋経済新報社)、『女子のキャリア』(ちくまプリマ―新書)など、著書多数。 【目次より】 ◆第1章 なぜ企業は社員のやる気を大切にするのか ◆第2章 難しいのは機会の与え方と支援 ◆第3章 組織をイキイキとさせる古典的理論 ◆第4章 指令や判断の根源がコア・コンピタンス ◆第5章 見栄えのいいメソッドよりも錆びない基礎理論を
-
4.4もし、あなたが「明日、死ぬ」と宣告されたら、今日という一日を、どのように生きるだろうか? あなたは、二度と戻らぬこの一日を、精一杯に生き切っているだろうか? 本書は、働くことの意味を、生死の深みにおいて深く静かに語った、著者渾身の一冊です。すべての働く人々へ問いかける魂の名講義! (目次紹介)◎なぜ、仕事に「思想」が求められるのか/現実の荒波 ◎いかに「思想」を身につけるべきか/三つの原点 ◎「生死」という深みにおいて観る/死生観 ◎「想像力」の極みで死と対峙する/極限 ◎「砂時計」の砂の音に耳を傾ける/一瞬 ◎「世界」という広さにおいて観る/世界観 ◎「歴史」という流れにおいて観る/歴史観 ◎「世界」と「歴史」の中で、どう生きるか/覚悟 ◎現実に流されないための「錨」/思想 ◎真の「知性」とは何か/生涯の問い
-
4.4■現代の大富豪に「お金持ちになる方法」を聞いてみた 竹田和平さんをご存じでしょうか。 ・「タマゴボーロ」「麦ふぁ~」などのお菓子で有名な竹田製菓の会長 ・100社以上の上場企業の個人大株主 ・所有株式の時価総額は100億円以上 など まさに「現代日本の大富豪」といえる人物です。 ラッキーなことに 竹田和平さんとひょんな縁から500回以上寝食をともにし 和平哲学をマンツーマンで学ぶチャンスを得た人物がいます。 それが本書の著者・・・本田晃一(通称・コーチャン)。 ■和平さんが教えてくれた「幸せになる生き方」 本田さんはインターネット黎明期に ネットマーケティングで大成功を収めますが 20代のころから、成功者と呼ばれる人々や 幸せに生きている人たちに出会うチャンスに恵まれ、 たくさんのことを学んでいました。 そのなかでも 教えがひときわ輝いていたのが竹田和平さんでした。 本書はそんな「和平さんの教え」を 「出会い」「お金」「愛」「豊かさ」「成功」「人生の極意」 の6つのテーマに分けてあなたにシェアします。 ■本書の構成 序章 出会い 理想の師匠に最短でアクセスする方法 第1章 お金 和平さん、どうしたら「幸せなお金持ち」になれますか? 第2章 愛 和平さん、「お金は愛」ってどういう意味ですか? 第3章 豊かさ 自分のなかに秘められた豊かさに気づく 第4章 成功 ぶっちゃけ、成功するにはどうしたらいいんですか? 第5章 人生の極意 いつも希望をもって生きるために
-
4.4何かを変えたいけれど、 どうすればいいのかわからない…… 新人から中堅、ベテランまで全てのビジネスパーソンへ。 ワクワクする働き方が見つかる、 想像以上の自分に出会える。 新しいキャリアデザインの方法論。 事例も満載。 副業、社内起業、転職、 パラレルキャリア、独立……働き方は1つじゃない! 「1つの会社、1つの専門性を追い、管理職へステップアップ」といった “これまでの当たり前”の目標が消えたり、 目標が無意味になるほどの想定外が起こったりするのが今の時代です。 しかし、見方を変えれば、目標を失った先にいる、 自分が想像すらしなかった新しい自分と出会えるチャンスでもあります。 そのチャンスを活かすには、新たな目標を生み出す方法論が必要。 本書は「4つのステップ」という手法を使い、 時代を切り拓く新しいキャリアデザインを伝えていきます。 講師のセミナーを聞き、 ワークショップを受けるようなイメージで読み・実践できる1冊。
-
4.4ややこしいデジタルの用語が イラストつきでスッキリわかる! 【本書のポイント】 ・デジタルマーケティングの頻出単語をシンプルに解説 ・イラストを見るだけでもイメージがつかめる ・似た単語の意味の違いや、使い分け方もフォロー ・索引つきで単語や同義語を探しやすい ・英語表記もあるので、海外サイトを読むときや出張にも便利 【こんな人におすすめ】 ・広告・マーケティング業界の新人~若手 ・マーケティングの会話がわかるようになりたい異業種の人 ・マーケティングの知識をアップデートしたい中堅~経営層 【内容紹介】 「略語やカタカナ語だらけでわかりにくい……」 本書は、デジタルマーケティングの世界に触れた人なら 誰もが感じる「言葉の壁」を解消するための単語帳です。 すべての単語はイラストとセットでわかりやすく解説。 ビジネス現場で使いやすいよう、索引も充実させました。 デジタル時代に手元に置いてソンはない一冊です。 【本書に登場する単語の一部】 KGI、KPI、A/Bテスト、運用型広告、リターゲティング、CPC、CPM、ARPPU、RPM、PV数、セッション数、GDPR、ITP、ヘッダービディング、ビューアビリティ、アドフラウド、アドクラッター、PMP、DMP、CDP、1stパーティーデータ、1stパーティーティCookie、インフォマティブデータ、VAST、パーチェスファネル、D2C、B2B、CRM、MA、リードジェネレーション、チャーンレート、デシル分析、O2O、OMO、UX/UI、ジオフェンシング、SaaS、MaaS etc. ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.4「ハーバードの大学院でデザインを学んでいて気づいたこと。それは日本人だけが突出して、“デザイン”という言葉の本来の意味を誤解していること」 電通のコピーライターとして活躍してきた一方、ハーバード大学デザイン大学院にて都市デザイン学修士を修めた建築家でもあるという異色の経歴を持つ著者の視点から、日本人が抱えてきた“デザイン”という言葉への誤解を紐解くとともに、デザイン思考の先を行く新たな手法の秘訣を紹介します。 “デザイン思考”が日本に輸入されて以来、「ゼロイチ」や「イノベーション」という文脈で、数え切れないほど多くの書籍が出版され、現在でもイベントやワークショップが至る所で開催されています。しかし“デザイン思考”とは既存のプロダクトを「改善」していく手法としては最高のフレームワークである一方、必ずしも、革新的なビジネスの「はじまり」に寄与するとは限りません。 これからの事業創造に求められることは、「未来はどうなるか」という受け身の予測的態度ではなく「(あなたは)未来をどうしたいか」という能動的な個人の欲求であると著者は言う。 ハーバード・デザインスクールの授業で著者は、創造力に必要な二つの力の存在を学んできました。ひとつはあらゆるアイデアの源泉であり、個性と専門性が求められる【個人の見立てる力】。そしてもうひとつは、自ら創造した未来から逆に現在のあるべき姿を描く【未来からの逆算力(バックキャスティング)】。 このふたつを原動力として生み出された5つのビジネスやデザインの実例を元に、誰もが革新的な発想を生み出せる4種類のメソッドをご紹介します。 ///目次/// 第0章 見立てる力 The power of likening 第1章 デザインの誤解 The misconception of design 第2章 デザイン思考の誤解 The misconception of design thinking 第3章 0→1 Zero to one 第4章 0→1の実践 0→1 Practice 第5章 社会実装 Social Deployment
-
4.3ドイツの哲学者、フリードリヒ・ニーチェ。 「神が死んだ」「ニヒリズム」「超人」「ルサンチマン」……。 私たちがいま当然のこととして見なしている考えの多くが、実はニーチェに由来しています。 ニーチェを一度も読んだことがなくても、知らず知らずのうちにニーチェ的にものごとを考えています。 意識するかどうかにかかわらず、私たちはニーチェの掌の上で踊らされているのです。 「どう生きていくのか」という問いが、ニーチェの生涯の最初から最後まで貫いていました。 彼の思索は、すべての人に何かしらのヒントを与えてくれます。 現在の生きづらい世の中で、ニーチェを読んでみてはいかがでしょうか。 序 章 ニーチェって、どうして人気なの? 第1章 ニーチェを知ると、何が変わるか? 第2章 神が死んで、どうなるか?―「神は死んだ」 第3章 生きる意味なんてない―「ニヒリズム」 第4章 真実はひとつではない―「パースペクティブ主義」 第5章 妬みが道徳を生み出した―「ルサンチマン」 第6章 人間の向こうに何があるか―「超人」 第7章 遊び、そしてパロディ―「永遠回帰」を生きるヒント
-
4.31巻2,200円 (税込)今日の世界は、かつてないほど急速な変化を遂げている。 資本主義はその限界を露呈し、人工知能は人間の仕事を奪い始め、誰もが100歳まで生きる人生100年時代が到来しつつある。 旧来の価値観が通用しなくなっていくなかで、「これから」をよりよく生きるためには、現在進行形のリベラル・アーツ(教養)が欠かせない。 思想から経済、デザインにアートまで、各界のフロントランナー11人が、 各分野の「これまで」と「これから」を紐解きながら、「これからの教養」を語り尽くす。 ◎目次 1.これからの思想――東浩紀 2.これからの生命――池上高志 3.これからの健康――石川善樹 4.これからの建築――伊東豊雄 5.これからの経済――水野和夫 6.これからのメディア――佐々木紀彦 7.これからのデザイン――原研哉 8.これからのプロダクト――深澤直人 9.これからの文学――平野啓一郎 10.これからのアート――松井みどり 11.これからの人類――山極寿一 ◎未来の創り手11人が考える、変わりゆく世界の「これから」 「僕たちは偶然性=弱いつながりを意図的に回復しなくてはいけない」(東) 「人間も機械も『人工生命化』していく」(池上) 「人生100年時代には『大きな問い』が必要になる」(石川) 「新しいコミュニケーションやコミュニティをどう居心地よく造るかが問われている」(伊東) 「近代社会の原理から脱し、『よりゆっくり、より近く、より寛容に』」(水野) 「いまはまたゼロからビジネスをつくらなければならない時代」(佐々木) 「これからはものではなく価値を作っていく時代」(原) 「デザインをする部分が本質的になってきた」(深澤) 「『個人』という概念が社会システムを考えていく上で限界に来ている」(平野) 「スペクタクルの蔓延の中で見失われている『個人の独自性』を取り戻す」(松井) 「人間はデータから脱出しなければならない」(山極) ◎「はじめに」より 爆発的に増える情報量とそれらを瞬時に検索するネット環境、 ビッグデータを駆使するコンピュータの発展にともなって、 僕らは「既になんでも知っている」かのようなイメージがあるが、果たしてそうだろうか。 逆に、より受動的で、自分の関心領域だけに閉じこもる人が多くなっているのではないか。 さらに、世界で何が起きているかよりも、国内の事象や 文化にだけ関心を向けている人も多いように思う。 そうした精神ならびに知性の不自由さから解き放たれるためにも、 異なる分野や言語を学ぶことには意味がある。 教養はリベラル・アーツの訳語だが、人が自由(リベラル)であるためには 技術と知恵(アーツ)がいる。異なるものを知らないと、人は自由になれない。 本書は「これから」をより良く生きるための現在進行形のリベラル・アーツ(教養)の 端緒に触れられるものになれればと意図している。
-
4.3住まい、健康、ふるまい、人間関係…… 人生を心地よく整えるたった一つのものさし 何が心地よく、何が美しいことなのか。 自分の美意識を持つことは、不確かな時代を生きる私たちの必修教養といえるでしょう。 美しい生活は、身体の疲れをとり、心を癒やして明日の自分を美しくします。 つまり、「美しければすべて良し」なわけです。 『お嬢さまことば』『気品のルール』『自分を躾ける』…etc 著作累計100万部超 加藤ゑみ子の集大成 <目次> 第1章 上質生活に必要な習慣 上質生活の習慣 第2章 上質生活は創造的思考で組み立てる 創造的思考の組み立て方 第3章 美と健康をつくる生活習慣 美と健康の視点 第4章 美しさを独占する色彩の意味 色彩の意味 第5章 感情的な知性を育てる美しい生活 感情的な知性の育て方 第6章 安心感は自分の美意識から 美意識と安心感 第7章 気品を心肝に持てば無敵 気品の育て方
-
4.3◎世界23か国で刊行、累計400万部突破! ◎これが、数々の不況を乗りこえ、子どもから大人まで世界で読まれ続ける「お金」の入門書。 ・小説形式だから、おどろくほど分かりやすくておもしろい! ・先ゆき不透明な人生100年時代、「お金のリテラシー」は生きのびるための必須教養! ・「お金の意義」「働くことの意味」「人は何にお金を払うのか」「投資と資産形成の基本」「信用の大切さと築きかた」 …… いつの時代も変わらない「お金と人生の大原則」を、大人もこれ1冊で一気に学び直せる! 「ねえキーラ、このままだと君は将来、両親みたいにお金に苦労する大人になってしまうよ」 少女キーラのもとにあらわれた、人間のことばをしゃべる不思議な犬、マネー。 マネーはキーラに、お金と世の中、そして人生の「しくみ」をわかりやすく説いていきます。 子どもから大人まで全世界400万人以上の人々に愛され続ける、一度は読むべき不滅のロングセラー。 ◎何のためにお金をかせぐの? ◎お金がほしいと願うのは悪いこと? ◎夢をかなえるにはどうすればいい? ◎「仕事」は不愉快でつらいもの? ◎株ってなに? 資産形成ってなに? 【本書の目次】 監修者まえがき 1章:白いラブラドール犬、マネー 2章:自分の目標を決める 3章:誰かが喜んでお金を払ってくれるのはどんなとき? 4章:好きなことを仕事にしよう 5章:決めたことは72時間以内にやる 6章:借金があるときはどうすればいい? 7章:なんのために貯金するの? 8章:努力していれば助けてくれる人がかならず現れる 9章:自分のためにお金に働いてもらおう 10章:お金を「汚い」と思っているうちはお金は貯まらない 11章:「幸運」とは、準備と努力の結果のこと 12章:お金は人間を映しだす「鏡」 13章:お金があれば、困っている人を助けられる 14章:株ってなに? 投資ってなに? 15章:自分に自信を持つには? 16章:投資信託ってなに? 17章:市場が暴落したらどうするの? 18章:冒険の終わり 大人の読者のみなさんへ――作者あとがき 「お金の話はとても大切なのに、 学校では教えてくれないし、家族でも話しにくい。 だから日本の子どもたちには、この本が必要だと思う」 ――村上世彰(投資家)
-
4.3正しく「考え」、正しく「伝える」ことで、「良い提案」が生まれる。現代ビジネスパーソン必修の「提案の技術」を明解なステップと臨場感あるストーリーで解説し、発売以来熱く支持され続けるロングセラー。「現場で使える」論理思考とプレゼンの技法がここにある。 「日本人の若手ビジネスマンが書いた、日本の企業社会を動かすための論理思考の本」。それが本書のコンセプトである。 昨今、色んな場面で「論理思考」の重要性が説かれているが、「欧米コンセプトの受け売り」の域を出た書籍を私は見たことが無い。「まずピラミッドで考える」「ロジックツリーを作る」「MECEを作る」…手を変え品を変え、だいたいどの書籍も書いてあることは同じだ。 外資系の戦略コンサルティング会社で働いていた私にとって、欧米流の論理思考も十分に理解は出来る。しかし日本に生まれ育った私には、やはり「日本的な論理思考」とでも言おうか、「欧米流ではない」物の考え方の方が、日本の会社にはしっくり来る気がしてならない。そして現在、事業会社の経営企画部員としてビジネスの現場で働く中で、日々それを実感している。 「ロジカル・プレゼンテーション」という横文字のタイトルを付けたが、内容は極めて和風である。それは私自身が、多くの日本企業をコンサルティングする中で考えた内容を体系化して書いたからだ。元のコンセプトは、サブタイトルにある「戦略コンサルタントの提案の技術」である。「ロジカル」とは「考える」という意味であり、「プレゼンテーション」とは「伝える」という意味だ。「きちんと考えて、伝えて、初めてビジネスは動く」。これが「提案の技術」であり、本書の根底に流れる考え方だ。「ロジカル・シンキング」ではない。伝えて、ビジネスが動いて、ナンボなのだ。 30歳の1人のビジネスマンが書いた書籍である。しかし、だからこそ「ビジネスの実践現場」の感覚を忘れず具体的に書き上げられたとの自負がある。皆様にお伝えしたいのは、「とにかくビジネスをうまく行かせたい」、それによって「社会を良くしていきたい」、そう考えて私自身は本書を執筆したということだ。 共感して頂ける皆様に、ご一読頂ければ幸いである。(本文より)
-
4.3元博報堂制作部長の著者が徹底的に解説する、“五感”のトレーニング方法。今は、ネットワークの進化でみな横一線の情報持ちになり、モノも同様、ハイレベルなものが溢れています。そんな現代において、“発想力”は、クリエイターだけに必要なものではなくなりました。現代の競争社会を勝ち抜くには、「創造しかない」。モノもアイデアも、いくら高性能だって「好き」と言わせなければ意味がないのです。――そこで。40数年を広告業界で過ごした著者が、着実に・確実にクリエイティブ体質をつくるトレーニングを伝授します。キーワードは“ウォッチング”。数時間実行するだけで、変わります。おもしろくて、よく身に付く。一度身に付いたら消えないクリエイティブ体質を、あなたの武器にしてください。
-
4.3ゼロから立ち上げたソフトバンクを3兆円企業に育て上げた、稀代の起業家・孫正義。その成功の原動力となったのが、「孫の二乗の法則」である。これは、孫が20代の頃に自ら考案し、以来常に人生・経営の指針としてきたもの。不朽の兵法書『孫子』からピックアップした14文字に、独自に考え出した11文字を組み合わせた「25文字」の文字盤で表されている。孫子の“孫”と自らの“孫”を“掛け合わせる”という意味から、“孫の二乗”の法則と命名された。これを片時も忘れないことで、孫はこれまで幾多の苦難を乗り越えてきた。さらに今、後継者候補にも継承すべく、自ら講義を行なっている。では、私たちが自分の仕事や人生に活用するにはどうすればいいか。その秘訣を本書では伝授。「孫の二乗の法則」を本格的に解説した唯一の書、待望の文庫化!道天地将法頂情略七闘一流攻守群智信仁勇厳風林火山海この25文字の中に、あなたの人生を変える「運命の1文字」がきっとある!
-
4.3
-
4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 テレワーク、サスティナビリティ、サブスクリブション、シンギュラリティ、フィンテック、ローンチ、PDCAサイクル、パラダイムシフト……etc。近年、このようなカタカナ用語やIT・AI関連用語が多く使われるようなりました。でも、実は用語の意味をきちんと理解していないまま使用されていることも多々あるのが現状です。本書ではビジネスパーソン必携のワードをイラスト入りでわかりやすく解説。社会人一年目から定年まで、働くすべての人が読んで見て楽しく学べる内容です。また、人事総務、経営、IT&AI、営業、製造、コンサルと分野別になっているので、知りたい用語をすぐに見つけられます。
-
4.3本書は、ディズニーランドを舞台に、カストーディアル・キャスト(清掃員)たちによって繰り広げられる感動物語。 物語の舞台は、ディズニーの清掃部門、カストーディアル。そこで働くキャストたちの4つの人間ドラマで構成されている。本書に収録されているのは、「夢の国の落とし物」「月夜のエンターティナー」「魔法のポケット」「夢の、その先」の4つの物語。どれも感動的で、ディズニーの魔法に満ちあふれた物語だ。 そして、この4つの物語すべてに貫かれているのが、初代アメリカディズニーランドのカストーディアル・マネジャーで、ウォルト・ディズニーの信頼厚く、ディズニーの世界で「そうじの神様」と称えられる、チャック・ボヤージン氏の教え。 なぜ、ディズニーランドには夢と希望が満ちあふれているのか? なぜ、私たちはディズニーランドに引き寄せられるのか? その秘密を知っているのが、ディズニーの“そうじの神様”だった。 物語を通して、夢と感動で満ちあふれ、多くの顧客を魅了してやまないディズニーランドの秘密が明らかになると共に、「働くとは?」「夢とは?」「人生とは?」など「働くことの本当の意味」を問いかける。 ※カバー画像が異なる場合があります。
-
4.3データサイエンティストはどのように考えるのか? 本書は、紙と鉛筆で学ぶというコンセプトのもと、 PythonやRなどのプログラミング言語を使わずに データサイエンティストの思考過程を体験できます。 データサイエンティストがどのような思考回路でデータと向き合っているのか、 本書掲載の40問のクイズを解きながら体験してみてください。 本書掲載のクイズは複雑な計算やExcelなども不要で、 紙と鉛筆さえあれば解くことができますので、ぜひチャレンジしてみてください。 【こんな方におすすめ!】 ・デジタル時代を生き抜くためにデータを読み解くスキルを身につけたい人 ・「データを使って論理的に考えろ」と言われるが、 データのどこを見ればよいのかわからない人 ・大学時代に政府が提唱するデータリテラシーを学ぶことができなかった人 ・大学でデータリテラシーを身につけた新入社員を受け入れる部署の管理職 ・社会でデータリテラシーがどう活用されているか知りたい人 ・データサイエンティストと仕事をすることになったが、 どのような思考回路の専門家なのか知りたい人 【本書を読むことで得られる知識/できるようになること】 ・データを活用するプロであるデータサイエンティストが どのような思考回路でデータに向き合っているかわかる ・データサイエンティストの思考過程を知る(なぞる)ことによって、 自分自身でデータを正しく読み解くことができるようになる ・データを読み解く際の勘所(着眼点)がわかる ・与えられたデータの意味を適切に読み解き、 他者に対して正しくデータを説明できるようになる ・恣意的に誇張されたグラフや不適切に切り取られたデータに騙されなくなる ・データ分析の考え方、留意事項がわかる ・データを分類する方法、データから法則を見つけ出す方法、予測する方法がわかる ・データを基に論理的に意思決定できるようになる 【目次】 第1章 デジタル時代に必要なデータリテラシー 第2章 データを読む力を身につける 第3章 データを説明する力を身につける 第4章 データを分類する力を身につける 第5章 データから法則を見つける力を身につける 第6章 データから予測する力を身につける 第7章 仕事でデータリテラシーを活用する ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.3「まず基本を身につけよう」この言葉に呪縛されて、どれだけ多くの才能が芽を吹かずに枯れていったか――下手がやみくもに基本練習を繰り返しても、かえって下手を植え付け「未知への対応力」を鈍らせてしまう。そして、基本の「意味」を認識し、「意義」を体現できている指導者が壊滅状態にある今、他人に基本をひたすら繰り返させるのは、本来恐ろしい行為である。だが、世間では「基本が大事」と言って止まない。「基本信仰」こそ思考停止社会の元凶である。武術の探求者・甲野善紀の武術には「基本」がない。学ぶ側は、やみくもに頑張るのではなく、その瞬間瞬間の対応を迫られる。わかることに意味はなく、創造しできるようになる工夫をし続ける。本書では、甲野を観察し一から独自の理論と稽古法を構築して一流の格闘家からも驚かれる技を身につけた方条遼雨のユニークな上達論と、それをめぐる二人の対論で「上達の原理」を解き明かす。
-
4.3※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書で言う「データ視覚化」(ビジュアライゼーション)とは、単に手元にあるデータをグラフにすることではありません。いくらデータを視覚化しても、その中から人間が重要な情報を読み取れないのなら、データ視覚化をする意味がないからです。あくまで、そのデータが指し示す意味を明確にすること、そしてより多くの人たち(オーディエンス)に興味を持って見てももらえることがデータ視覚化の目的です。 本書では、日本人女性唯一のTableau ZEN MASTERである筆者が長年にわたって培ってきたデータ視覚化のノウハウ、ベストプラクティス、アンチパターン等を整理分類してエッセンスを抽出し、具体的な事例をあげながら、できるかぎり丁寧に解説しました。また、セミナーなどの現場でよくされる質問に対する答えをまとめたものでもあるので、ある意味、“FAQ”でもあります。
-
4.3【内容紹介】 インドを理解する最高の教科書。 グルチャラン・ダス。インドの作家、戯曲家、歴史家、哲学者、教育者でありハーバード大卒のビジネスマン。「インドの福澤諭吉」と呼ばれる氏が今後のインド人との働き方、稼ぎ方、付き合い方を明かす。 1983年にインドに進出したスズキ。現在のシェアは50%となり、インド国民13・5億人の乗るクルマの半分はスズキ車になっている。その「インドシフト」で独走するスズキの“カリスマ”も納得のインド入門の教科書の内容とは? 【著者紹介】 [著]グルチャラン・ダス(Gurcharan Das) 著述家、経営コンサルタント(特に企業のグローバル戦略)。「タイムズ・オブ・インディア」に定期的にコラムを執筆。「ウォールストリート・ジャーナル」、「フィナンシャル・タイムズ」などに随時寄稿する世界知識人の一人。ハーバード大学哲学・政治学科卒業、ハーバード・ビジネス・スクールで学ぶ。リチャードソン・ヒンドスタンの会長兼最高経営責任者(CEO)、プロクター&ギャンブル(P&G)インディアのCEO、P&G本部の経営幹部(戦略企画担当)を務めた。小説『A Fine Family』(ペンギン)、劇作集『Three English Plays』(オックスフォード大学出版局)、エッセー集『The Elephant Paradigm』(ペンギン)などがある。ニューデリー在住。 [取材・構成]野地秩嘉(Tsuneyoshi Noji) 1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、ビジネス、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『企画書は1行』『なぜ、人は「餃子の王将」の行列に並ぶのか?』『高倉健インタヴューズ』『高倉健ラストインタヴューズ』『トヨタ物語』『トヨタ現場のオヤジたち』『スバル ヒコーキ野郎が作ったクルマ』ほか著書多数。 【目次抜粋】 巻頭解説 インド人の心は変わらない 鈴木修 第一章 私にとってのインド 第二章 インドはこんな国 第三章 インドの経済改革 第四章 カーストの意味と役割 第五章 日本人とインド人 第六章 インドで成功する日本企業 第七章 インドの日本人ビジネスマン 第八章 これからの日本とインド
-
4.3人工知能は脅威か? 救世主か? 「人類とは何か」が分からないまま、AIを理解することはできない。 火、言語、農業、都市……人類の歴史をひも解きながら、AIの本質にせまる。 ロボット。仕事。自動化。人工知能。意識をもつコンピュータ。スーパーインテリジェンス。 豊かさ。仕事のない未来。「役に立たない」人間たち。「不足」の終焉。創造するコンピュータ。無限の富。仕事の終焉。永遠なる下層階級。 インターネットの記事で、こういう類の言葉が踊るニュースを目にしたことはないだろうか。 その筋書きは、未来への希望に満ちたポジティブな場合と、恐怖に満ちた暗い場合がある。 なぜこのような両極端な話になってしまうのだろうか。 様々な分野の、豊富な知識を持つ優秀な専門家たちの未来予測は、ちょっとどころじゃなく大幅に異なり、ときに真っ向から対立する。 なぜビル・ゲイツやスティーブン・ホーキングやイーロン・マスクは人工知能(AI)を恐れ、 近い将来、人類の生存を脅かす存在になると警告するのだろうか? そしてなぜ、同じように大物のマーク・ザッカーバーグ、アンドリュー・エン、ペドロ・ドミンゴスらは、 そういった主張がばかげていて反論するまでもないと一蹴するのだろうか? この論争の全てに根気よく付き合ったとしても、そこから得られるのは、混乱とフラストレーションくらいだろう。 この状態を脱することはできるだろうか? 私は、きっとできると考えている。 まず、専門家の意見が大きく食い違うのは、それぞれが知っていることが違うのではなく、信じていることが違うためであることを理解しよう。 ただし、この本は、私自身の意見を声高に述べるものでは全くない。 読者がこの本を読み進めるとき、私の意見がどうであるかにはたいした意味はないだろう。 私のゴールは、この本を読み終えたあなたが、この本で取り上げる問いにあなた自身の信条がどういう答えを導くか十分に理解できていることだ。 さて、この旅はどこから始まるだろう? 実は、はるか昔、言語が発明された頃まで遡る必要がある。 私たちがこの本で取り組む問題はトランジスタやニューロンやアルゴリズムではない。 現実、人間性、心の本質に関する問いなのだ。「人間とは何か?」と問う前に 「ロボットはどの仕事を人間から奪うのか?」と問うから、おかしなことになる。 最初の質問に答えられない限り、二つ目の問いに意味のある答えを出すことはできない。 そこで、私はあなたを、10万年にわたる人類史を眺める旅に招待し、旅の途中で様々な問いについて論じながら、来るべき未来について思いをはせようと思う。 この本は、旅そのものだ。あなたが私と共に旅をしてくれることをうれしく思う。
-
4.3本書は、いまヨーロッパで注目されている経営戦略「意味のイノベーション」について本格的に解説する書籍です。 「モノが売れない時代に、どう売ればいいのか?」 この答えとして、いま欧州で注目されている経営戦略「意味のイノベーション」。 イタリア発のこの考え方は、極端に言えば「商品やパッケージはそのままでイノベーションを起こす方法」です。 ミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ教授の著書『デザイン・ドリブン・イノベーション』で提唱されたこの概念。 これは、2010年発表のEUの10年計画の中にも組み込まれ、欧州の最前線で使われているアプローチなのです。 デザイナーの考え方をビジネスの問題解決に活かす方法として、少し前にアメリカ発の「デザイン思考」が広く知られるようになりました。 ただ、デザイン思考は万能のツールではありません。 その長所や弱点を押さえつつ、別のアプローチから商品やサービスを革新することができるのが、本書で解説する「意味のイノベーション」なのです。 「問題解決」だけでなく、「意味」を変えることで、商品の価値を飛躍的に高める。 中堅・中小企業が、自社の資源を活かしつつ、他社と差別化を図り、長期的に売上を伸ばせる画期的な経営戦略。 特に「雑貨や家具・照明器具」といった非テクノロジー分野で効果の高いこの考え方ですが、残念ながら日本ではまだあまり知られていません。 そこで本書では、この「意味のイノベーション」の要諦を、イタリアを拠点に活躍するビジネスプランナーとデザインマネジメント専門家の二人のエキスパートが解説します。
-
4.310人以上の会社組織になったら、本当の意味での人事部をつくることが企業の反映に直結します。 現場の社員の本音を聞き出す「現場志向コミュニケーション」ができる人事部の設立が、あなたの会社の将来を大きく変えるのです。 多くの企業をこの手法によって、業績と組織のモチベーションアップに導いた著者がノウハウのすべてをお教えします。 はじめに はじめに:「総務部人事係」では会社は伸びない 第1章 なぜ中小企業には人事部がないのか? 第2章 人事部をつくると、社員がやる気になる、辞めなくなる、会社が成長する 第3章 成果の出せる人事部はこうしてつくれ! 第4章 社長の好き嫌いで社員の給料を決めるな! 第5章 「良い社員」より「合う社員」を採用しろ! 第6章 ダメな会社のOJT「教えない」「ジャマくさい」「テキトーにやれ」 第7章 人事部も利益を生み出すことができる
-
4.2『忘れられた日本人』で知られる民俗学者・宮本常一とは何者だったのか。その民俗学の底流にある「思想」とは? 「大きな歴史」から零れ落ちる「庶民の歴史」。日本列島のすみずみまで歩き、聞き集めた小さな歴史の束から、世間や民主主義、多様な価値、さらには「日本」という国のかたちをも問いなおす。傍流として、主流が見落としてきた無名の人びとの「語りの力」を信じて――。 【本書のおもな内容】 ●「庶民」が主役の歴史を構想 ●盲目の「」乞食の自分語りに見出した意味 ●村をよくするために尽くした「世間師」 ●釣り糸を変えると豊かになる ●「寄り合い民主主義」の可能性 ●日常生活に潜む「深い心のかげり」に着目 ●「ふるさと」を起点として広い世界を見る ●旅に学ぶ――父の10ヵ条 ●男性による女性支配の「東西での違い」 ●人が人を信じることで人間全体が幸福になる 「宮本の民俗学は、私たちの生活が『大きな歴史』に絡みとられようとしている現在、見直されるべき重要な仕事だと私は考える。これほど生活に密着し、生活の変遷を追った仕事は、日本の近代でほかにはみられないからだ。宮本は庶民の歴史を探求するなかで、村落共同体が決して共同性に囚われてきただけではなく、『世間』という外側と絶えず行き来し流動的な生活文化をつくってきたことも明らかにする。そしてそれは、公共性への道が開かれていたと解釈することができるのだ。また近代を基準にみたとき、さまざまな面で遅れているとされてきた共同体の生活、あるいは慣習のなかに、民主主義的な取り決めをはじめ、民俗的な合理性があったことも裏づける」――「はじめに」より ■■■■■■■■■■ 100ページで教養をイッキ読み! 現代新書の新シリーズ「現代新書100(ハンドレッド)」刊行開始!! 1:それは、どんな思想なのか(概論) 2:なぜ、その思想が生まれたのか(時代背景) 3:なぜ、その思想が今こそ読まれるべきなのか(現在への応用) テーマを上記の3点に絞り、本文100ページ+αでコンパクトにまとめた、 「一気に読める教養新書」です! ■■■■■■■■■■
-
4.2※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 〇内容紹介 百人一首は、学校で大会があったりマンガの題材になったり、目にする機会も多いけど、 100個もあるし、昔の言葉でどういう意味なのかわかりにくいし、覚えるのが大変……。 そんな百人一首を、現代風に、くすりと笑える「5文字」にしてみました……! とっても楽しくわかりやすい、新たな百人一首の教養本! 元の歌→訳→意訳→五文字 の四段階の訳+直感的にわかるイラストで、うたの意味を想像しつつ、 かわいいネコちゃんが、歌の内容を、話したくなる豆知識とともにゆる~く解説! 歌の詠まれた場所マップ、改めて理解する機会がなかなかない「枕詞」「序詞」「掛詞」のちがいや、昔使われていた月や時間帯を一覧にした知識コラムもあって、「序詞ってなに?」「どこで詠まれた歌なんだろう?」「有明の月ってなんだったっけ?」「歌を詠んでいる人同士の関係性は?」といった疑問も一挙解決! *たとえば、あの有名な「ちはやふる~」の百人一首を5文字であらわすと……? →「空前の紅葉」 ※元の歌「17.ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは」→訳「神々の時代の話としても聞いたことがありません。竜田川の水が唐紅色にくくり染めされるなんて」→意訳「こんな見事な紅葉は、今まで無かった」→「空前の紅葉」 ネコちゃん解説 <神様の時代にもなかったぐらい、竜田川が紅葉でいっぱいになったという歌。紅葉の屏風絵の前で想像で詠んだもの。 「ちはやぶる」は「神」にかかる枕詞。「水くくる」の意味は、「水を絞り染めにする」と、「水が紅葉の下を潜る」の二つの説がある。とにかくすごい紅葉だ。「紅葉」と言わずにそれを表現しており、聞く人の想像力を試される歌でもある。落語やマンガのタイトルになったりして、百人一首の中でも何かと有名。 作者の在原業平は、歌が上手ですごくもてた。物語の主人公のモデルにもなった。> ほかにも…… 「2.春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天の香具山」→「洗濯日和だ」 「12.天つ風 雲の通ひ路 吹きとぢよ 乙女の姿 しばしとどめむ」→「アンコール」 「21.今来むと いひしばかりに 長月の 有明けの月を 待ち出でつるかな」→「この嘘つき」 「33.ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ」→「桜散るの早」 「60.大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立」→「不正は無い」 「78.淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に いく夜寝ざめぬ 須磨の関守 」→「鳥うるさい」 『ちはやと覚える百人一首』著者あんの秀子氏 解説
-
4.2課題先進国ニッポンとあなたの未来 ◆もう先送りできない! 適切な問題解決のその先に、個人も国も成長がある! 少子高齢化、財政再建など課題が山積する現在の状況から日本は適切な道を選び、歩んでいけるのか? 今や「数字・ファクト・ロジック」を駆使して自分の頭で考え、判断することが何より大切な時代になった。 こうした混迷の時代でも、自分の半径5mの世界から変えていくことが結局は早く世界を変えることにつながる。 あなたの今後の人生や仕事を下支えする力を養う! ◆日本でしか通用しない価値は意味がなくなる! ◆少子化、老老介護、孤独死、待機児童問題など 数多くの難題を抱え、「課題先進国」となってしまった日本――。 歴史は自分の立ち位置を測る格好のモノサシだが、日本はいま世界でどんなポジショニングにあるのか、 そしていま日本、さらには東京の競争力をあげることがなぜ大事なのか、 ボーダーレスの本当の意味を知ることになる子、孫世代はどうやって働き、生きていくべきなのか――不透明な時代の先を見通す ◆適切な問題解決のその先に、個人も国も成長がある! 「この世界をどう理解し、どこを変えたいと思い、自分に何が出来るか考え、行動することが、人間が生きる意味であり、仕事をする理由でもある」(出口氏)
-
4.2最近、タイムマネジメントの技術が、様々取り上げられている。しかし、本当にこれらの技術で、自分自身の「時への悔い」はなくすことができるのだろうか。なにか大切な視点が抜け落ちてはいないだろうか? 著者はこの視点から、大局的な視点に立った時間論を展開する。まず示唆されるのは、時間は決して「平等」な資源ではない、ということである。時間を真に生かす人とそうでない人の差は、それほどまでに大きい。そして、時間を生かすために不可欠な視点として、時間、集中、智恵、経験、反省、人間、自分、関係、成長、成功という十のキーワードが提示される。ある意味で本書は単なる時間論の枠を越えて、人生論的な側面を強く持つ書となっている。それは、著者が語るように、「なぜ時間を生かせないのか」という問いは、究極「いかに生きるか」という問いへと逢着するからである。自分自身の時間を生ききるために必読の、時の本質に切り込む渾身の一冊。
-
4.2本書は、「超MBA式」という考えに基づいた「論理的な問題解決法」入門である。では、その「超MBA式」とは何か? 著者はそれを、「マインド」「ツール」「情報」の三つのキーワードで解説する。「マインド」とは、日本人に最も欠けている「結論志向」のことであり、この前提がないとどんな知識も活きてこないと著者は主張する。続く「ツール」については、ロジックツリーなどの既存のツールをその本質的な意味から捉えなおすことで、本当の知恵を醸成する手段を教える。そして「情報」。スピードが重視されるビジネス社会では、どう情報を集めるのかが重要となる。ケーススタディではわからない「情報の収集」について解説する。以上のことから分かるように、本書はただの「お勉強」本ではなく、「本当にビジネスの現場で使うためのMBA」入門である。本書を読むか読まないかで、MBAに関する理解が格段に違ってくる、と断言できる一冊。
-
4.2
-
4.2「飛行機の実現までには百万年から一千万年はかかるだろう」 ニューヨーク・タイムズがこの記事を掲載してわずか数週間後、ライト兄弟は人類で初めて空を飛び、この予測を覆しました。 一流紙でジャーナリストを務めるほどのエリートが、なぜそんなことを自信満々に書けたのだろうと、当時の人々は笑いました。 しかし、彼らもまた、こう考えていました。 「宇宙船? そんなものは夢のまた夢だ」 現代を生きる私たちも、未来を見誤るという意味では、宇宙船を夢と考えた人たちを笑うことはできません。 現在日本で2800万(2017年9月)を超えるユーザー数を誇るFacebook ですが、「実名登録なんて日本でははやらない」と言われていたのは、ほんの数年前のことです。 今では多くの人が使っているiPhone にしても、発売当初は「おサイフケータイが使えない」「赤外線がないなんてありえない」などの理由から、はやらないという意見が多数派でした。 これから私たちの社会がどう変化していくのかは、今の社会を真剣に眺めるだけではわかりません。巷にあふれる未来予測本を読んでも、わかることはないでしょう。私たちはいつも未来を予測し、そして外し続けてきました。人間は本来、未来を見誤るものなのです。 私たちの多くは、今目の前で起きていることからしか将来のことを考えることができません。しかし、現在の景色という「点」だけから行う未来予測は、だいたいにおいて外れます。 なぜなら、その一点においてでさえ、現実世界は膨大な要素にあふれているからです。それらが互いに複雑に影響し合って社会を発展させているのですが、それらをすべて把握することは、人間の脳というハードウェアの性能では、まず不可能なのです。 一方で、驚くほどの先見性を発揮して大きなリターンを得る人が稀にいます。 たとえば、スティーブ・ジョブズは1980年代、当時30代だったころから、すでに個人がスマートフォンを持つ未来を予言し、それを自分の手で実現させることを決めていました。 彼らはどのようにして「線」を見ているのだろうか。その思考法を汎用性のあるロジックとして整理できれば、ビジネスを進めるうえで大きなメリットになる。そう考えて、これまで自分なりに探究を続けてきました。 本書では、そこで見出すことができた技法をお伝えしたいと思います。 ※ 本書は、2015年に小社より刊行された『未来に先回りする思考法』を再編集・改定したものです。
-
4.2「本を読んでも、すぐに内容を忘れてしまう」 あなたも、こんなふうに思っていませんか? こんな、記憶に残らない「読んだつもり」の読書は、 ザルで水をすくうようなもので、時間の無駄です。 読書とは、その内容を忘れずに自分の知識として定着させて、 自己成長に結びつけてこそ、はじめて意味が出てくるものなのです。 本書では、精神科医である著者が、 脳科学的な裏付けのある「読んだら忘れない読書術」を公開します。 また、「SNSの超プロ」としての立場からも、ソーシャルメディアを使いこなし、 読書で得た知識をアウトプットする方法、人とシェアする方法などを明かします。 ぜひ、「読んだら忘れない読書術」を手に入れ、 さまざまな本で学んだ内容を仕事や生活の場で実践してください。 その前にまずは、本書を「記憶に残る読書術」で読み進めてみてください! *目次より 第1章 なぜ、読書は必要なのか? 読書によって得られる8つのこと 第2章「読んだら忘れない」精神科医の読書術 3つの基本 第3章「読んだら忘れない」精神科医の読書術 2つのキーワード 第4章「読んだら忘れない」精神科医の読書術 超実践編 第5章「読んだら忘れない」精神科医の本の選択術 第6章 早く、安く、たくさん読める究極の電子書籍読書術 第7章「読んだら忘れない」精神科医の本の買い方 第8章 精神科医がお勧めする珠玉の31冊
-
4.2なぜ、我々は働くのか。この深い問いに対しては、あくまでも、私たち自身が、その人生と思索を通じて、答えを見つけていかなければなりません。本書は、その思索を深めるために、仕事の真の報酬とは何か、を始めとする様々なテーマについて、著者の体験的なエピソードを交え、語っていきます。仕事を通じていかに成長していくか。成長のために夢や目標はいかなる意味を持つのか。なぜ顧客は成長の鏡となるのか。顧客との共感ということの本当の意味は何か。人間学を学び、人間力を身につけていくための唯一の方法は何か。なぜ、人間との格闘が大切なのか。働く人間にとって地位とは何か。生涯、会うことのない友人が、なぜ、我々の支えとなるのか。仕事の本当の作品とは何か。職場の仲間とは何か。仕事において、未来とは何か。そして、なぜ、仕事に思想が求められるのか。それらのテーマを深く考えることを通じ、読者一人ひとりに、生き方と働き方を問う本です。
-
4.1メディアが報じない「不都合な真実」 ――「新型コロナウイルス」と「季節性インフルエンザ」の感染者数と死者数 第1章 新型インフルエンザの顛末 第2章 日本ではコロナは恐くない 第3章 抑圧策から緩和策へ転じよ 第4章 データを無視する専門家 第5章 岡田晴恵・玉川徹は恐怖の伝道師 第6章 スウェーデンは成功している 第7章 5密会談 第8章 東京の抗体保有率0.1% 第9章 スウェーデンの死生観 第10章 お辞儀と清潔感の驚異 第11章 世界各国のコロナ対策事情 第12章 ウィルスとは進化の鍵だ 第13章 インカ帝国の滅亡 第14章 グローバリズムの失敗と権威主義 第15章 自由よりお上に従う日本人 第16章 経済のほうが命より重い 特別対談 木村盛世氏(元厚労省医系技官・医師)×小林よしのり 幸運にも「抑圧政策」を実行中にワクチンが開発されたとしても、 その間に社会や経済や文化がボロボロになってしまえば意味がない 特別講義 金塚彩乃氏(弁護士=第二東京弁護士会・フランス共和国弁護士=パリ弁護士会) 新型コロナウイルスとフランスの緊急事態法 ~日本の「緊急事態宣言」とは何だったのか?
-
4.1【内容紹介】 日本ではDX(デジタル・トランスフォーメーション)の文字を見ない日はありませんが、ここ数年、もう一つ、「X」のつく用語として、「カスタマー・エクスペリエンス(Customer Experience、略してCX)」という概念が日本にも入ってきて、注目が集まっています。 CXは「顧客体験」もしくは「顧客体験価値」と訳されます。「商品・サービスの購入、利用における顧客としての体験」および「体験をとおして得られる感覚的・心理的価値」を意味するようです。 ヒト(お客様)は、モノをとおしてコトを体験することで価値を感じ、満足感を得る。モノの価値に対して、コトの価値とは、お客様が体験することで得られる価値、すなわち、顧客体験価値といえるでしょう。 カスタマー・エクスペリエンスの概念は二〇〇〇年代に入ってから注目されるようになったようですが、セブン‐イレブンでは、一九七〇年代の創業当時から、仮説・検証を実践することで、お客様に満足していただける顧客体験を提供し続けてきたのです。 ★★★セブン‐イレブン流・「これが欲しかった!」をつくり出す・真の【お客さま目線】とは? コンビニおにぎり、セブン銀行、100円コーヒー……。 数々のヒットを生み、日本の新しいライフスタイルをつくってきた鈴木敏文氏。 彼が約50年前からただ一人見抜いていた、潜在ニーズを拾いあげる「ストーリーづくり」の真髄は、創業以来セブンが徹底している「CX=カスタマー・エクスペリエンス(顧客体験)」にあった! ◎「お腹いっぱい」の人は何を食べるか ◎半分にカットした割高の大根が売れる理由 ◎おにぎりの販売は「新しい習慣」を生み出した ◎Francfrancには、なぜ、便座カバーが置いてないのか ◎動物園を「お客様の立場で」を見直して気づいた衝撃の事実 ◎花の売り手が花をもらって初めて問題点に気づく ◎横を見ずに目の前にいる顧客に目を向ける ◎「過去の延長線上」ではなく「未来の可能性」に目を向ける 「お客さまだけを見てください、ほかは見なくてけっこうです」 【著者紹介】 [著]鈴木 敏文(すずき・としふみ) セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問 1932年長野県生まれ。中央大学経済学部卒業後、東京出版販売(現トーハン)を経て63年イトーヨーカ堂入社。73年セブン‐イレブン・ジャパンを創設し78年社長に就任。92年イトーヨーカ堂社長、2003年イトーヨーカ堂およびセブン‐イレブン・ジャパン会長兼CEOに就任。05年セブン&アイ・ホールディングスを設立し、会長兼CEOに就任。16年から現職。著書『わがセブン秘録』など多数。 [取材・構成]勝見 明(かつみ・あきら) ジャーナリスト。1952年、神奈川県生まれ。東京大学教養学部中退後、フリージャーナリストとして経済・経営分野を中心に執筆を続ける。著書に『鈴木敏文の「統計心理学」』ほか、『共感経営』(野中郁次郎氏との共著)など。 【目次抜粋】 イントロのようなまえがき モノ消費からコト消費の時代へ なぜ、セブン‐イレブンの日販は他チェーンより一五万円も高いのか 「カスタマー・エクスペリエンス」とはコト消費 「仮説・検証」によりコト的な価値を提供する 「真冬の冷やし中華」が売れるわけ 第1章モノではなく、コト(体験価値)を売る時代へ 1 コロナ禍で顧客体験がより重要性を増した 2 メリハリ消費、ごほうび消費は典型的なCX型消費 3 同じものごとでも提示の仕方で売れ方が変わる ほか 第2章CX経営にはどんな発想法が必要なのか 1 常に顧客を起点に発想する 2 顧客起点の発想はあらゆる分野で求められる 3 「川モデル」ではなく、「井戸モデル」で考える ほか 第3章顧客の求める体験価値をどのように生み出すのか 1 予定調和を壊す 2 「上質さ」×「手軽さ」の空白地帯を見つける 3 仮説力を鍛える① ~疑問を発することが出発点 ほか 第4章カスタマージャーニーに沿った戦略を考える 1 仮説を立てるとはカスタマージャーニーを想定すること 2 売り場という「舞台(ステージ)」で「物語」を生み出す 3 キュレーション戦略~選択と絞り込みで新しい価値を生み出す ほか 構成担当者によるあとがき
-
4.1思いを言葉化する、教養の超アウトプット法。 例えば、エレベーターで社長と一緒になったが、 気の利いたことが何も言えない… 飲みの席で、ふられた話題に「知らない」と答えたら場がしらけた… ――こんな経験はありませんか? 「言葉にできない」 「うまく(言葉で)伝えられない」 こんな悩みをもつ人は多いのではないでしょうか。 「言葉にできる」とは、相手を納得させられることが言えること、を指します。 「言葉にできない人」は、往々にして相手から 「考えていないな」と思われたり、場を気まずくしてしまいがちです。 この会話のもどかしさを解消するのが本書です。 意味のあるコンパクトなコメントを駆使し、どんな会話も盛り上げ、 いつも話題の中心にいるのが「言葉にできる人」。 日々のアウトプット(言葉化)を鍛えれば、誰でも必ずなれます。 齋藤先生が教える、教養の超アウトプット法、 知らない話題でも切り抜ける「間に合う会話力」、 15秒で伝えきる知的会話術を伝授します。
-
4.1110万部を突破したベストセラー『超訳 ニーチェの言葉』。 今までになかった、現代に生きるわたしたちを勇気づけるニーチェの名言集を生み出した白取春彦が、机上の空論あるいは単なる教養としての哲学ではなく「生きるための哲学」としてのニーチェの思想を語る。 〈本書の一部〉 「哲学は論理の正しさがどうのこうのというものではないし、そもそも哲学は学問ですらない」とニーチェは考えたのだ。 ニーチェは、哲学は人間が今ここに生きるべき生の本質だと考えた。生き方が哲学だと思っていた。真理がどうのこうのではなく、まず生き方をニーチェは重要視する。 だから、論理が正しいから真理だという考え方はしない。 この生き方が人間としてまっとうかどうかということを問題にする。このまっとうさとは、社会的、倫理的、宗教的な真摯さの意味ではない。人間本来のまっとうさを具現化しているかということだ。
-
4.1これまで書籍や雑誌、テレビで皇室から日本文化、外交問題までを語ってきた竹田さん。テレビ出演のときに共演者から「どうしてそんなにいろいろなことを知っているのですか」とも聞かれるそうですが、本書では竹田さんが初めて自らの勉強法を明らかにします。そもそも竹田さん自身、小さいころには勉強ができず、人前で話すこともできない少年だったとか。一時期は自己啓発書を読み漁ったこともあったそうですが、なかなかイメージどおりに成功できない。いま同じ悩みを抱えている人も少なくないでしょう。しかし日本文化の神髄を学んでいくうちに、竹田さんは気づいたそうです。そもそも日本と根本の価値観が異なる「西洋式成功哲学」に基づく勉強法でうまくいくはずがない……。そこで編み出したのが「日本式成功哲学」を前提にした勉強法でした。あくまで「自分」が主語になる西洋式と「日本式成功哲学」は正反対。本書でまず竹田さんが語るのは「重要なのは『生き方』ではなく『死に方』」「夢を持つデメリット」「プラス思考よりもマイナス思考」など、巷の自己啓発書とは全く逆の話です。では、「他者」のために生きる日本人が勉強をする意味はどこにあるのでしょう。「勉強の本質」から竹田式・情報収集の実践メソッド、講演の達人が誇るコミュニケーション術、人脈のつくり方までを、自らの体験や時事的な話題も盛り込みながら大公開します。ビジネスパーソンにとっても、学生にとっても、日本人なら人生の指針となり、一生使えるどこにもないビジネス書の誕生です。
-
4.1「これは読んだほうがいいです。いや、読まないとこの先の人生やばいと感じます」「今まで日本で起きつつある固有の問題と思っていたことが、グローバルレベルで起きていることに驚いています」「もし自分に子どもがいたら絶対に読ませたい本です」(読者の声より) テクノロジーの進化に伴い、ゆとりある生活を送れるかと思いきや、時間に追われ、家族や友人と過ごすこともままならない孤独な日々。こんな働き方がさらにエスカレートするのでは?未来に対する漠然した不安の正体が、2025年の「悪夢」と「希望」のストーリーによって解き明かされる。新聞、ビジネス誌の書評への連続掲載、『ワーク・シフト』を題材にした読書会が日本各地やネット上で開催されるという現象も発生。あなたもぜひ家族、仲間と一緒にシフト体験を! 【内容】 ≪下流民か、自由民か。地球規模で人生は二極分化する≫ ロンドン・ビジネススクールを中心とした「働き方コンソーシアム」による、世界規模の研究が生々しく描き出す2025年に働く人の日常。「漫然と迎える未来」には孤独で貧困な人生が待ち受け、「主体的に築く未来」には自由で創造的な人生がある。どちらの人生になるかは、〈ワーク・シフト〉できるか否かにかかっている。「食えるだけの仕事」から意味を感じる仕事へ、忙しいだけの仕事から価値ある経験としての仕事へ、勝つための仕事からともに生きるための仕事へ。覚悟を持って選べば、未来は変えられる。 著者のリンダ・グラットンは、ロンドン・ビジネススクール教授。経営組織論の世界的権威で、英タイムズ紙の選ぶ「世界のトップビジネス思想家15人」のひとり。フィナンシャルタイムズでは「今後10年で未来に最もインパクトを与えるビジネス理論家」と賞され、英エコノミスト誌の「仕事の未来を予測する識者トップ200人」に選ばれている。組織におけるイノベーションを促進するスポッツムーブメントの創始者。『HotSpots』『Glow』など7冊の著作は、計20ヶ国語以上に翻訳されている。人事、組織活性化のエキスパートとしてグローバル企業に対してアドバイスを行う。現在、シンガポール政府のヒューマンキャピタルアドバイザリーボードメンバー。TEDスピーカー。二人の息子の母親。
-
4.1あなたは、何のために働くのですか? こんな問い掛けに、あなたならどのように答えるだろうか。生活をしていくお金を稼ぐため。しかるべき地位に就きたいから。こんな答えが返ってきそうだ。しかし著者はいう。「何のために働くのか」という、この問い掛けと、その答えにこそ、今後の長い人生を左右するような、大きな意味が込められていると。給料や収入、役職や地位は、たしかに働いた結果得られる「報酬」に違いない。ところがこれらは、使ってしまえば無くなる報酬であり、その仕事を離れれば失ってしまう報酬である。しかし著者は、目には見えないが、一生失うことのない「最高の報酬」がある、と説く。それは、仕事という作品の創造を通して得られる、技術の熟練、人との出会いと学び、完成の喜び、その結果としての「人間的成長」であるというのだ。『なぜ、働くのか』に続く、好評の書籍講話第二弾は、人生を深く静かに見据えた新人生論である。
-
4.1※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 技術者は日常的に技術用語を使って考え、問題を解決しています。技術用語の中には、技術者が長年培ってきたアイディアやグッドプラクティス、それに問題解決のエッセンスが凝縮されています。 たとえば、技術用語としての「バッファ」は、データを生産するプロセスと、データを使用するプロセスの間に置かれた緩衝領域を意味します。この技術用語の発想を日常生活に適用するなら、私たちが使っている「財布」はバッファとしての役割を持っていることがわかります。さらに、いったん蓄積させることで価値を生み出すプリペイドカードにもバッファの発想が生きていることがわかります。 また、技術用語としての「ボトルネック」は、システム全体のパフォーマンスを決定するポイントを意味します。システム全体のパフォーマンスを上げるためには、やみくもに改善するのではなく最初にボトルネックを見つける必要があります。会社の承認プロセスで、特定の人物が意志決定のボトルネックになることはよくあります。ボトルネックになっている人物の承認速度を上げなければ、全体のパフォーマンスは上がりません。 本書で取り上げる技術用語はプログラミング全般、アルゴリズム、セキュリティ、マルチスレッドなど多岐にわたります。このような技術用語の意味を知り、それを用いた技術者の発想を日常生活に適用させることで、業務の改善や学業の効率化、創造力の育成などに生かすことができるでしょう。 技術者の発想に関心をもっている学生から社会人、発想力や創造力を高めたいと思っているビジネスマン、組織をうまく動かしたいと思っているリーダーなど、現代を生きるすべての読者にとって最適の読み物です。 なお、本書は『Software Design』(技術評論社)の連載を加筆修正して書籍化したものです。
-
4.1「速読はバカの早食いと同じ! 」 ロクでもない情報を遮断し 人類の「知の遺産」を味わい尽くせ! ショウペンハウエル、ヴィーコ、三島由紀夫、 ヤスパース、三木清、ニーチェ、 大江健三郎、ヘッセ、小林秀雄、ゲーテ……。 彼らはどのように本を読んだのか! 「速読はバカの早食いのようなものである。 単に腹を満たすのが目的ならマクドナルドのハンバーガーでいい。 一流のレストランに大金を払って「栄養」を求めるバカはいない。 そのレストランが提供する技術に、魂が突き動かされていく。 その過程・時間にこそ、意味がある。 古典を読むのは、過去に存在した偉大なレストランで食事をするようなものだ。 これ以上の贅沢はない。 では具体的になにを読めばいいのか? 過去を振り返れば、すでに道は示されている。 本書では先人の知恵に学びながら、再びそれを示していく。 大事なことは、真っ当な世界に連なる意志をもつことだ。」(「まえがき」より) 「人間として生き延びるには、 自己啓発本とはまったく別の意味における「スキル」が必要になる。 それは、自分を救えるのは自分ではないと気づくことだ。 自分の力などたかがしれていると思い知ることだ。 偉大なもの、崇高なものは、それを教えてくれる。 本書では人類が到達した場所と、 そこに至る「思考回路」を振り返らないと未来はないという事実を示した。 くだらないものと距離を置き、価値あるものに触れ続けなければ、 家畜として死ぬだけだ。」(「あとがき」より) <著者プロフィール> 適菜 収(てきな・おさむ) 1975年山梨県生まれ。作家。哲学者。 ニーチェの代表作『アンチ・クリスト』を現代語訳にした『キリスト教は邪教です!』、 『ゲーテの警告 日本を滅ぼす「B層」の正体』、『ニーチェの警鐘 日本を蝕む「B層」の害毒』、 『ミシマの警告 保守を偽装するB層の害毒』(以上、講談社+α新書)、 『日本をダメにしたB層の研究』(講談社+α文庫)、『日本を救うC層の研究』、 呉智英との共著『愚民文明の暴走』(以上、講談社)、 『なぜ世界は不幸になったのか』(角川春樹事務所)、 『平成を愚民の時代にした30人のバカ』(宝島社)、『死ぬ前に後悔しない読書術』、 『安倍でもわかる政治思想入門』、『安倍でもわかる保守思想入門』、 『安倍政権とは何だったのか』、『おい、小池! 女ファシストの正体』、 『問題は右でも左でもなく下である』(以上、KKベストセラーズ)、 近著に『小林秀雄の警告 近代はなぜ暴走したのか?』(講談社+α新書)など著書多数。
-
4.1どうすれば社員はもっと主体的に動けるのか? 変質とスピードの時代、勝敗を決めるのは社員一人ひとりのアカウンタビリティの育成だ。 米国で最もポピュラーな童話のひとつ『オズの魔法使い』をもとに説く、21世紀の経営の神髄。 本書の原書であるThe Oz Principleは1994年にアメリカで出版され、50万部を超えるベストセラーとなっています。 すべての経営者と管理職にとって、「主体的に動く」社員をどうしたら育てられるのかは切実な問題です。 本書の著者は、そういった社員を育て、結果を出す組織をつくるために、「アカウンタビリティ」を高めることが必要だと説きます。 「アカウンタビリティ」とは「被害者意識」の反対で、「自分が問題の当事者であると考え、自分の意志で主体的に行動しようとする意識」を意味します。 現在、日本においては、「アカウンタビリティ(accountability)」という言葉は会計用語と受け取られることが多く、その場合「会計責任」「説明責任」などと訳されます。 英語としてはもう少し意味の範囲が広く、単に「責任」「義務」と訳せることもあるようですが、アメリカでもビジネスの場では、日本同様に会計用語として使われるのが普通でした。 ところが本書の出版後は、本書の中に述べられているような意味で使われることが多くなっているようです。本書の影響の大きさがよくわかります。 著者は、アメリカで最もポピュラーな童話である『オズの魔法使い』のテーマは 「登場人物たちが被害者意識から脱し、自分の持っている能力に気づく」 ことだと言います。 そして、『オズ』の物語や登場人物になぞらえながら、個人と組織がアカウンタビリティを高めていく方法を解説していきます。
-
4.1「学習の方法を学ぶことは、専門家が言うところの「究極のサバイバルツール」、つまり、現代において最も重要な能力の一つであり、あらゆるスキルの前提となるスキルである。」(イントロダクションより) 深い学びを得るにはいったい何が必要なのか? 子どものころに学習困難を抱えていた著者が、多くの実証研究調査と、学びの専門家への取材を通して辿り着いた、小手先のテクニックではない本質的な「学び方」。 米Amazon 2017年ベスト・サイエンス書 「読者の声」 「学ぶ」という冒険に出るための「地図」みたいな本。 何かを学ぼうとする時に、1度は読んだほうが良いと思います。 ――人材派遣業、40代女性 読むことで自分にとっての学ぶ意味をより具体化できた。 ――教育関係、30代男性 本を読む<以前>と<以後>では、 まるで違う世界を生きているような感覚です。 「学び」に関わるすべての人におすすめします。 ――ファシリテーター、20代男性 「学びのデザイン」をするために不可欠な内容が詰まっていました。 ――人材開発コンサルティング、30代男性 目次 イントロダクション ダーツの実験/「究極のサバイバルツール」/体系的アプローチ 第一章 価値を見いだす 意味を自ら発見する/学びを自ら「作り上げる」/探索する種/「知的努力には伝染性がある」/意味とは学ぶこと/言語の摩滅/マインドセットの大切さ/MET研究 第二章 目標を決める 短期記憶の容量の小ささ/知識は学習の土台/学習にコンフォートゾーンはない/思考の質を上げる/思考についての思考―そして情動/感情管理の必要性/自己効力感/学習は難しくて当たり前 第三章 能力を伸ばす モニタリング/外部からのフィードバック/苦労の本質と反復/「検索練習」/脳の可塑性/間違いの心理 第四章 発展させる マイルス・デイヴィスの傑作/学習の発展としての議論/応用の必要性/「ハイテック・ハイ」/人に教えるという学習方法/不確実性の価値/「多様性は人を賢くする」/疑問の大切さ 第五章 関係づける システム思考/「最大の認知上の障害」/仮定思考/ハッキング/視覚的アプローチ/アナロジーの価値/問題解決のスキル 第六章 再考する 過信/直感型思考と熟慮型思考/評価する必要性/自分に分かっていないことを知る/分散学習/内省の必要性/静かな時間/「こぶし」実験/無限のプロセス エピローグ ツールキット
-
4.0市場規模は1兆ドル時代へ―― 社会インフラの中枢を支え 世界各国が奪い合う国際戦略物資となった半導体。 言葉は知っていてもその意味や役割は知らないビジネスパーソンに向けて、日本の半導体流通を牽引する著者が徹底解説 ---------------------------------------------------------------------- スマートフォンやパソコンをはじめとした電子機器、自動車や電車、 インターネット通信を代表とする社会インフラなど、 半導体は今、私たちの身の回りであらゆるものに使われており、 生活は半導体によって支えられているといっても過言ではありません。 近年世界的な需要の拡大が続き、日本国内の生産高だけでも年間約5兆円、 世界全体では約72兆円にもなる巨大市場となっています。 さらに、5GやEVの普及、DXによる効率化、メタバースの発展など、 応用機器や応用システムの進化とさらなる需要拡大によって、 半導体への追い風はまだまだ続くことが予想されています。 しかし、そのような世界経済の中心的な存在である半導体について、 「なにやら重要そうなもの」というイメージをもっていても、 どういうものか詳しく理解していない人が多いのが現実です。 本書では、国内外で30万人以上に利用されている電子部品、半導体の通販サイト運営を行う著者が、 半導体とはそもそも何か、世の中に欠かせないものになるまでの進化の歴史、 半導体を巡る世界の動きなどを解説します。 時事問題を語る場やビジネスシーンなどで知らないと恥をかく 大人の教養としての「半導体」の知識が身につく一冊です。
-
4.0本書は、天皇制の成立以前にまで遡って、日本史における女性天皇およびそれに準ずる女性君主の歴史を解明していくものです。 皇位継承問題などで様々な議論が起こるたびに、女性天皇、女系天皇が話題になりますが。 未来における皇室の在り方を考えていくためには、かつての時代について学ぶ必要があるでしょう。 古代日本から江戸時代まで、女性天皇が統治者として果たしてきた責務について学んでみませんか? 推古天皇、持統天皇といった8人10代の女性天皇の責務だけでなく、女王卑弥呼、神功皇后などの歴史的な位置づけなどについても解説します。 なお、女性天皇と女系天皇が混同されがちな傾向がありますが、その両者は別物です。 女性天皇は文字通り女性の天皇を意味するもので、本書では過去8人10代存在した女性天皇を中心に解説します。 第1章 伝説の女王・女皇たち 第2章 推古天皇 第3章 皇極・斉明天皇 第4章 持統天皇 第5章 元明天皇と元正天皇 第6章 光明皇后と孝謙・称徳天皇 第7章 「古代の再来」……明正天皇と後桜町天皇
-
4.0「一度読んだら永遠に忘れない」極上の説法。少欲知足、利他、縁起、供養、四宝印、出家……「諸行無常の(正解がない)時代」を生き抜く知恵と心構え。佐藤優氏(作家・元外務省主任分析官)推薦! 「仏教は抜群に面白いしビジネスに役立つ」「なんだか毎朝会社に行くのが疲れた」「ポスト争いでいがみ合う組織の雰囲気が重い」「定年後、自分はどうしたらいいのかわからない」など、仕事やビジネスに関する悩みは尽きない。そんな悩みを解決してくれるのが、仏教である。歴史に裏打ちされた合理的・科学的な真理は、長年日本人の倫理・道徳観の拠りどころとなってきた。その意味で、お釈迦さまや宗祖の言葉・教えから学べることは多い。そこで本書では、元経済系記者で現在は浄土宗僧侶の著者が、難解な用語や解説は極力避け、現代のビジネスシーンに置き換えながら、仏教を「再翻訳」。六道輪廻や八正道などイメージしづらい教えもすいすい頭に入る。ビジネスパーソン必読の“世界一わかりやすい仏教本”。
-
4.0ざっくり読むだけで、脳に“しみ込んでる感”200%! GDP、TPP、LGBT、IoT、・・・テレビや新聞、ビジネスシーンで目にする 英略語(=頭字語)を、小難しい言葉を使わずに、シンプルに解説。 高校生程度の読解力があれば、英語が苦手でも関係ありません。 たとえばGDPは 「Gross Domestic Product」の略で、 正式名称は「国内 総 生産」 これだけを読んで理解できないこともありませんが、 もっとシンプルに言うと 「国内で生み出された“もうけ”の合計」となります。 「あの略語ってどういう意味だっけ?」 と聞かれたときにササっと答えることができれば、 周りから「できる!」と思われること間違いなし! 「GDP」と「GNP」の違いや、「UNESCO」と「UNICEF」の違いも、 “一瞬”で理解でき、かつ、“一生”忘れません。 1日1ページずつ読んでもいいし、 まとめて一気に読んでもぐんぐん身になり語彙力アップ! 必ず覚えておきたい「基礎」編から、「IT」「ビジネス」「経済」「国際」「軍事」「医療」「生活」 「スポーツ」「科学」「芸能」など全11ジャンルを網羅しています。 ワンランク上を目指すビジネスマン必読。 雑談力も向上するため、就活生や会話でビクビクしたくない人にもオススメの1冊です。
-
4.0世界は、教養なくして語れない。 朽ちない教養をこの手に!! 「二時間でわかる哲学」などは、あり得ない。 現実は、思想が未だ動かしている。 いま世界で起きているのは、すでに克服され、古いものになったはずの民族問題であり、宗教問題の再発である。 歴史とは何か? ヒューマニズムとは何か? 近代<モダン>とは何か? 冷戦後、終わったことにされた近代<モダン>こそが未だに世界では影響力を持っている。 古今の書物に脈々と流れる論理の構造を掴み、解き明かすことで、危機の時代を生き抜く思考法を身に付ける。 ■陰謀論は間違えたかたちで危機を克服する方法 ■陰謀史観に対抗できるのは、健全なユーモアと笑いだ ■前衛思想はビジネスに使われている ■天才に対抗する発想は、預言者 ■類比とは、別のものの中で共通構造を見ていくこと ■ヘブライ的な発想とギリシャ的な発想 ■力で物事を理解するのは、新自由主義の市場の発想だ ■行為とは、不可能の可能性に挑むこと ■宗教の力は、本質的に関係のないものを結びつける ■時間論なき経済論に意味はない ■我々はボランティアのことを翼賛と言っていた ■ヒューマニズムは個人主義でも合理主義でも生命至上主義でもない ■キリスト教はアンチヒューマニズム ■思想は基本的に解釈、あるいは再解釈である ■世界史は、物語をつくる暴力的な力を持つ人にしかつくれない ■日本が露骨な帝国主義国になっていく可能性は高い etc. 「知性によって裏付けられたユーモア、ときにはアイロニー(皮肉)を用いることによって、我々一人ひとりが社会的にどのような位置にいるかを知る」 ※本書は『危機を克服する教養』(角川書店、2015年)を新書版として改題し、加筆修正したものです。
-
4.0お金持ちになるには、「お金の教養」を身につけるのがもっとも手っ取り早い。お金に関する具体的なノウハウがあっても、それを正しく評価して、有機的に結びつけ、具体的な行動に落とし込む「教養」がないと、お金持ちになれないのです。富裕層と公私にわたり交流し、億単位の資産を運用する個人投資家になった著者が、お金の本質的な意味、お金持ちの思考パターン、お金と密接に関係している時間・数学・ITの知識、お金の教養を生かした賢い生き方など、ノウハウよりも大切なお金の教養について解説します。人生を後悔しないためのお金の知恵が身につく1冊です。【以下、目次から】お金を生み出す資産に手をつけてはいけない/ムダな人脈はムダな支出を増やす/稼いだお金を消費することは借金することと同じ/嫌いでも苦手でもいいから数字には強くなれ/将来のために、今ガマンする人はお金持ちにならない/お金持ちは「複利」を常に考えている……ほか。
-
4.0★新しい昭和史の見方を伝える! 山川出版社の『日本史B 高校日本史』(81 山川 日B308)における戦前昭和史を、「教養」として読み直す! 実際の教科書と対比しながら、「大事なのに触れられていないこと」「さらっと記述があるだけだが、実は背景にこんなことが」という解説で、歴史の本質がつかめる! 「そんなに簡単に平和な世の中から戦争の時代へとシフトするのだろうか?」といった疑問。それは、個々の事実をつなぐ様々な出来事が教科書では端折られてしまっているから。本書では、そうした隙間を埋め、かつ簡素な記述の裏にある今日的な意味に光を当てながら昭和史を振り返る。 ・戦前昭和の歴史を学ぶことに今日的な意味が見出せない、そんな人こそ目からウロコの内容 ・いま以上に先行きが不透明な時代に、先人はどのように行動し、それがどのような結果をもたらしたのか? ・二大政党制の機能不全ないし限界についても、戦前と比較して考えることができる! ・当時の国民目線になって考えるという意味で、現代を生きる私たちが戦前昭和を身近に感じられる点。それは、当時の日本も格差社会であったこと。 ・当時の国民だとしたら? 新聞やラジオが戦争熱を煽っていくなかで、あなたは「それはおかしい」といえるのか。あるいは「おかしい」と発言すること自体、英雄的な、正しい行為だといえるのか。
-
4.0
-
4.0
-
4.0【野中郁次郎一橋大学名誉教授推薦!】 上司が代わって職場の雰囲気が、良かれ悪しかれ一変するとき、 なぜそうなるのか、答えが出るまでとことん考え抜いたことが あるだろうか? 「人の話を聴いてくれる人」と「聞く耳をもたない人」との違いは いったいどこからくるのだろうか? 好きな仕事に向かってお互いの積極性が活かされる共創的職場の実現には、このような問いに直面し本当の原因を突き詰めようとする態度が必須となる。 本書は、経営学者と現象学者が学問領域の境界を越え、具体的な職場の事例に即しつつこれらの疑問に対し、読者と共に思索を重ねる。 現象学は、上司と部下、同僚同士といった職場での人間関係での悩みの真の原因を、各自のそれまでの経験の積み重ねに求めようとする哲学である。といっても精神分析をするわけではなく、各自がそれまでに身につけてきた「人々と共に生きることの意味と価値の形成」をたどろうとするものである。 こうして「共に働くことの意味」が、具体的な4つの職場を例にしてどのように身をもって実感されるのか、分かりやすい言葉で丁寧に説明され、どこの職場でも起こり人々が日々頭を悩ませ、心を砕いている職場での「人間関係」や、創造的な職場のあり方について、普遍的な理解が得られる。 露木氏は大学院で野中郁次郎氏に師事、山口氏は野中氏と共著の『直観の経営』(KADOKAWA)のヒットが記憶に新しいところである。 本書では、経営に直接携わらない方にも身近な、日々の仕事に密着し充実した議論がなされている。
-
4.0本書の書名中の「酔古堂」とは、中国・明時代末の教養人・陸紹コウの雅号で、世の中の名利など眼中になく、悠々たる生き方を追い求めた人物のこと。「剣掃(けんすい)」とは、彼が愛読した『史記』や『漢書』をはじめとする、五十種以上に及ぶ古典から選び出した名言・嘉言を、剣(心)で世間の邪気を掃(は)らい味わう、という意味である。この『酔古堂剣掃』を愛読し、その名言・嘉言をどう味わうかを、陽明学者の泰斗・安岡正篤師が「講話」というかたちで解説したものが、本書である。内容は、「足るを知る虚無観」「好煩悩と百忍百耐」「生活・自然・風流」「山居・幽居の楽しみ」など、人格よりも経済力を、過程よりも結果を重視しがちな現代人に、自然と共生して生きる喜びを味わえと訴える、警鐘の書ともいえる内容である。本書は「現代活学講話選集」(全七巻)の五巻目。今、結果のみを重視し、急ぎすぎる日本人に心の滋養となる一冊である。
-
4.0必携!社会人・大人の新教養コトバ辞典! 即!役立つ、 コトバ、言い回しを500以上収録! 就活にも、新人教育にも、今さら訊けない上長にも! たとえば・・・ 【読めない!】(書けなくてもOKだが…) *俯瞰 *瑕疵 *職人気質・・・ 【訊けない】 *アサイン *アジェンダ …カタカナ言葉 *リスケ *ブレスト *キャパ …やたら多いカタカナ略語 *ASAP *CS *NR *MTG …頭文字並べ、辞書でもわからない 【勘違い&どっちかな?】 *姑息な手段→<誤>卑怯なやり方 *うがった見方→<誤>偏見 *うる覚え?うろ覚え? *要件?用件? *好意?厚意? 【フツーの意味ではなく、カイシャ語ならではの言い方】 *うちが持ちます:モノを持つわけではありません *一枚かんでよ:ガムをかむわけではない 【重ねコトバ】 ほぼほぼ/いっぱい いっぱい/おいおい/こみこみ 社長の朝礼で耳にする言い回しの解読法や、 会議での切り返し方、 社会人なら知っておきたいお礼の仕方、 社交辞令の言い回し・・・・ 知っていると役立つ、知らなきゃ恥ずかしい。 そんな「カイシャ語」の辞典です。
-
4.0植物が「下等生物」などではなく、「知的生命体」だと知ったら、あなたの世界の見方は一変するだろう。 植物が驚くほど高い知性を持ち、自分が置かれた状況を把握して、未来を予測し、他の生物とコミュニケーションすら取っていると知ったら――どうだろうか? 気味が悪い? 伐採したり、食べたりするのが可哀想? 人間は彼らとどう付き合うか考え直すべき……? そうしたすべての反応を引き出し、考えるヒントを提供するのが本書、『プランタ・サピエンス 知的生命体としての植物』だ。 世界で唯一植物の知性を専門に研究する「MINT研究所(ミニマル・インテリジェンス・ラボ)」の代表研究者、科学哲学教授の著者が描き出す植物の知性についての先端研究内容は、ページごとに私たちを驚かせる。植物研究の成果にとどまらず、植物を他の動物やコンピュータ、人間の脳構造などと比較することで、植物のイメージを「声なき背景である下等生物」から「プランタ・サピエンス(賢い植物)」に引き上げていく。 植物は脳を持たず、人間や動物のように動き回ることもできないが、人間とは異なる驚くべき内面世界があることが今、明らかになりつつある。 植物は計画を立て、学習し、仲間を認識し、リスクを評価し、決断を下すことができる。そして本書の導入部分で明らかにされているように、植物を「眠らせる」こともできる。 我々が思うよりもはるかに、植物は活発に、規則正しく、そして「知的に」生きているのだ。 人間が「動物中心主義」の古い考えを脱し、本当の意味で持続可能な社会を実現するために、植物という「知的生命体」を見直し、理解し、協力関係を築くことを大胆に提案した本書は、人類にとって初めての「教養としての植物本」である。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 苦手な人も多く、学生時代には避けてきた人も少なくない数学。 「数学って何の役に立っているの?」と 学ぶ意義を見い出せなかった人もいるでしょう。 しかし、私たちが知らないだけで数学の考え方や公式は、 日常生活のあらゆる物や事象に使われています。 ●論理的思考力と柔軟な発想力が鍛えられる! 本書では身の回りの物や事象に数学がどのように取り入れられているかを解説することで、 数学の奥深さや楽しさを紹介します。 ●AI、データサイエンスなど、これから必要な知識が身につく 本来は数学の生命線ともいえる「厳密さ」を棚上げして、 ざっくりしたイメージや具体例を用いて解説しているので、 文系出身の人も楽しく学ぶことができる1冊です! ●数式が少ないから、数学が苦手な人も安心 前職では、防衛省 海上自衛隊で航空学生に数学を教えていました。 授業で心掛けていたことは、 生徒が「知っている」「わかっている」「できる」ことから授業を始めることです。 基礎的な内容から教えることで、数学に苦手意識がある人でも 楽しめるようにしたいと思ったためです。 「知っている」「わかっている」「できる」が増えていけば、 苦手な意識が徐々になくなっていき、自然と楽しくなっていくものです。 実際、そのようにして数学の苦手意識を克服できた学生を見てきました。 それぞれの項目は独立しているため、第1章から読む必要性はありません。 興味がある項目からぜひ読み始めてください。 ■目次 ●第1章 身の回りで役立っている数学・算数 ・1 簡単な割り算が原因であわや「命」に関わる重大事故に ・2 「プレミアム付商品券」は本当にお得なのか? ・3 ウイルス検査の結果はどれほど信じてよい? ・4 香辛料の量を2倍にしてもカレーは2倍の辛さにならない ・5 これからの時代に必須となるAIとデータサイエンスとは? ・6 社会人も知っておきたい偏差値の意味とその仕組み ●第2章 「なぜ?」がわかると面白い数学の世界 ●第3章 柔軟な発想力を鍛える珠玉の謎解き問題 ●第4章 世界を変えた偉大な数学者たち ●第5章 意外と身近な数学の定理 ■著者 佐々木淳(ささきじゅん) 下関市立大学教養教職機構准教授。 1980年、宮城県仙台市生まれ。東京理科大学理学部第一部数学科を卒業後、 東北大学大学院理学研究科数学専攻を修了。代々木ゼミナールの数学科講師、 防衛省海上自衛隊の数学教官を経て、2022 年4 月より現職。 海上自衛隊では、パイロット候補生の教育に大きく尽力した功績が認められて、 事務官職 では異例ともいえる第3級賞詞(職務遂行にあたり、著しい功績があった者や技術上、 優秀な発明をした者などに授与される)を受賞する。 著書に『AI 実装検定公式テキストA 級』(大学教育出版)、 『公務員試験最 初でつまずかない数的推理』(実務教育出版)、 『身近なアレを数学で説明し てみる』(SB クリエイティブ)などがある。
-
4.0※本書はリフロー型の電子書籍です。 【世界の宗教地図はどのように塗り替えられてきたのか?】 ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥ―教、仏教─── 世界5大宗教の歴史からロシア正教、神道、新宗教まで、その歴史を紐解く。 宗教は、なぜ全世界に広がっていったのでしょうか。 その理由、原因はどこにあるのでしょうか。 宗教は、どういった手立てを講じることによって信者を増やしていったのでしょうか。 本書で取り上げようとするのは、まさにそうした問題です。 それを地理ということと結びつけて考えていきたいと思います。 信仰は個人のこころのなかに宿るものではありますが、その個人が置かれた地理的な環境ということが極めて重要な意味を持ちます。 異なる地域に生まれれば、それぞれの地域で支配的な宗教の影響を受け、個人の信仰もそのなかで確立されていくことになるからです。 現代においては、さらに重要なってきた視点があります。 それが、宗教のネットワークです。 さまざまな宗教対立、宗教の衝突がくり返され、歴史を経るなかで、宗教の地政学は大きく変わってきました。 宗教はそのように直接、物理的にぶつかり合うこともありますが、信者はネットワークで結ばれ、そのネットワークを広げることで、それぞれの宗教は確固とした基盤を持つようになりました。 そして現代における宗教は、そうしたネットワークという点においても急速にそのあり方を変えようとしています。 宗教の地政学はますます重要になっているのです。 では、さっそく宗教の地政学という新しい試みをはじめることにしましょう。 〈本書の内容〉 ◆宗教と地理はどう関係するのか? ◆ネットワークというユダヤ教の地政学 ◆キリスト教の地政学的な成功 ◆いったん浸透すると強力なイスラム教 ◆仏教が抱える地政学上の長所と弱点 ◆宗教対立と国家の存亡 〈著者プロフィール〉 島田裕巳(しまだ・ひろみ) 1953年東京生まれ。宗教学者、作家。 76年東京大学文学部宗教学科卒業。同大学大学院人文科学研究科修士課程修了。84年同博士課程修了(宗教学専攻)。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を経て、東京女子大学非常勤講師。著書に『性と宗教』(講談社現代新書)、『日本人の神道』(ちくま新書)、『宗教対立がわかると「世界史」がかわる』(晶文社)、『教養としての世界宗教史』(宝島社)、『創価学会』『世界の宗教がざっくりわかる』(以上、新潮新書)、『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』『葬式は、要らない』 (以上、幻冬舎新書))、『宗教消滅』(SB新書)、『0葬』(集英社文庫)、『戦後日本の宗教史』(筑摩選書)などがある。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 〇内容紹介 四字熟語をすべて5文字にしてみたら……!? とっても楽しくわかりやすい、新たな四字熟語の教養本! 四字熟語は、ニュースで出てくることもあるし、使いこなせればカッコイイけれど、 難しい漢字を使っているし、なんとなくの雰囲気で口にしてしまうことも多くて、イチイチ調べるのも大変……。 そんな四字熟語を、現代風に、くすりと笑える「5文字」にしてみました……! 四字熟語→5文字に変換!+例文+直感的にわかるイラストで、四字熟語の意味を想像しつつ、 かわいいネコちゃんが、四字熟語の内容や由来を、話したくなる豆知識とともにゆる~く解説! 気がついたら四字熟語を使いこなせていることまちがいなし! 「故事成語」と「四字熟語」のちがいを説明するなどの知識コラムもあって、今まで聞けなかった疑問も一挙解決! *たとえば、よく耳にする四字熟語を5文字であらわすと……? 音信不通→「死んだかも」 意気消沈→「もうダメだ」 紆余曲折→「色々あった」 危機一髪→「超あぶない」 言語道断→「話にならん」 阿鼻叫喚→「うわひどい」 閑話休題→「おいといて」 お父さんお母さんが使っている四字熟語も、5文字におきかえれば意味がすんなり頭に入ってくるよ! 爆笑まちがいなしの5文字で、キミも四字熟語マスターになろう!! ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 孫子から学ぶ必勝の戦術、混沌の時代を生き残る智恵。 時代を超えて読み継がれ、歴史を左右してきた“戦争”の書、『孫子』。ビジネスや人生において“戦争・競争”という一面も見逃せないとすれば、その智恵は現代にも十分生きるはずです。本書は、忙しいビジネスマンにも本物の智恵を、簡単に、わかりやすく速習できるように、一つのテーマについて1.読み下し文(原文)、2.現代語訳、3.解説、4.図解の4つの視点で、簡単に、複合的に学べるように構成してあります。“人を動かす”といったすぐ役立つ智恵から、“人生に勝つ”ことの本当の意味まで、現代ビジネスマンの教養として必携の1冊です。
-
4.0
-
4.020年間に渡るアメリカによるアフガニスタンの支配は終焉を迎えた。タリバンの復権は何を意味するのか? 日本にはどんな影響があるのか? そして大きな歴史の流れのなかでアメリカの終焉を決定づけるきっかけになったと語るのが、イスラーム法学者の世界的第一人者・中田考氏。中田氏は現在のタリバン指導部との親交も深く、世界でも稀に見るタリバンの思想と政治組織に精通した人物。はじめて語られる「タリバン復権の真実」に読者は驚愕と衝撃を受けるにちがいない。今後の国際情勢を見極める上で必須の教養書の一冊。
-
4.0ジョブ型人事制度のもとでの課長の役割と仕事とは何か、これまでとは何が違うのか、何を為すべきかについて、人材育成の専門家が体系的に整理したことで本書は次のような行動を喚起します。 ・経営からの待ちの姿勢ではなく、顧客起点から機会と脅威を探り、最適なビジネスを自律的に展開する。 ・問題の発見と解決のための自発的な目標管理プロセスを運営する。 ・プロジェクトをリードしていく。 ・メンバーとの協同力が高まる。 ・人の育成と同等に、自分のキャリアを開発する。 【目次】 第1章 これから課長がやるべき3つのこと 1 ジョブの意味を正しく理解する 2 ジョブの価値を向上させる 3 ジョブを実践する原則を知る 第2章 5つのマインドセットを変える 1 マインドセットの変革1 「競争に勝つ」から脱却する 2 マインドセットの変革2 戦略的思考の定義を変える 3 マインドセットの変革3 管理者から支援者に変わる 4 マインドセットの変革4 部下ではなくパートナーとして接する 5 マインドセットの変革5 中間管理職から中核管理職に変わる 第3章 チームの目標管理 1 自律的な仕事環境をつくる 2 作業の棚卸しをする 3 目標達成に必要なスキルを確認する 4 ジョブディスクリプションを運用する 5 チームの目標管理を行う 第4章 チーム運営に必要なスキル 1 リーダーシップ 2 共感を生むコミュニケーション力 3 問題解決のための思考力 第5章 課長のマネジメント課題 1 コンプライアンス問題への対応 2 リスクマネジメントへの対応 3 ダイバーシティへの対応 4 SDGsへの対応 5 組織づくりへの対応 6 顧客起点の行動 第6章 課長の自己成長 1 内省の習慣 2 継続的な学習習慣 3 定期的なフィードバックの習慣 4 プロジェクトをつくる習慣 5 教養を身につける習慣 6 キャリアビジョンを考える習慣
-
4.0【美しい、楽しい、面白い、大切に守りたい「和の習慣」から日本の心の豊かさに気づく】 下駄を履いてみよう 抹茶を立ててみよう ほうきで掃除をしてみよう 浴衣を着てみよう 俳句を詠んでみよう 熱燗を飲んでみよう 歌舞伎を観てみよう 歴史や意味、よさを知ったら、きっと始めたくなる 和の習慣を70個紹介します。 〈「はじめに」より〉 今の私たちのライフスタイルは決して昔ながらの「ザ・和風」ではありません。 が、よりどころとなる「芯」は、日本人ならではの和の習慣の中にあり、そこには心の持ち方、心の伝え方、モノの扱い方、人を思いやる気持ち、感謝の表し方など、自分は「何を大切にするのか」へのヒントがたくさん散りばめられているように思うのです。 ここにご紹介したのは、あらためて私が美しい、楽しい、面白い、そして大切に守りたいと思う70の和の習慣です。 この本を開いてくれたあなたが、この中の一つでも、楽しく続けていける和の習慣を見つけ、心の中の豊かさに気づいてくれたらうれしいです。 〈こんな方にオススメ〉 ・和のお稽古ごとに興味のある人 ・教養として和の作法などを知りたい人 ・新しい習慣を始めたい人 ・家時間を充実させたい人 〈本書の内容〉 リユース可能 サステナブルな着物の魅力 お太鼓だけではない 半幅帯でもっと自由に 扇子の風は袖口から 気遣いの所作の美しさ 正座は体幹を鍛え 加圧効果もあるのです 朝のお茶、夜のお茶 どんな時にどんなお茶? おいしいお茶を淹れるにはお水と温度が肝心です 自分のために点てたい 心を切り替える一服 心を軽く 写経は心のデトックス 御朱印は修行の証と心得ましょう 昔は湯上がり 今の進化する夏の浴衣たち 指先に力を入れて歩く下駄が足と身体によい理由 足が痛くならないための下駄とのつきあい方 身体にも環境にも優しい和菓子はビーガン こす、拭く、切る 晒しもめんの使い方 万能な手ぬぐいは防災グッズの必須アイテムです 思い出したい心遣い 心を包むのが風呂敷です 風鈴の音色を楽しむ感性は日本人ならではのものです 水にも火にも強い桐が日本の風土に合っているわけ 鰹節を削る音と香りを食卓に 和食の配膳は左優位と右利き文化なのです 大げさに包むほどではないけれど“ほんの気持ち”の表し方 いつもの一言 美しい和語は大人の響き お正月に、贈り物に水引で華やかに心を込める 座布団の表裏、前後ろ 日本人の本音と建前 ハンコで気軽に思いつくまま季節の一句 歌舞伎は「かべす」から楽しみましょう ふすまを3回に分けて開けるのはノック代わりの心遣いです 若々しい人はみな艶髪 つげ櫛が髪によい理由…etc. 〈著者プロフィール〉 君野倫子(きみのりんこ) 文筆家、日本文化キュレーター、着物スタイリスト。着物、和雑貨、歌舞伎などをおもなテーマに執筆。2010年に拠点をアメリカに移し、日本文化を海外へ紹介する活動を続けている。近著に『歌舞伎はじめて案内手帖』(松本幸四郎氏監修・二見書房)、日英バイリンガル『日本人の暮らしを彩る 和雑貨』(IBCパブリッシング)など。その他著書多数。 オフィシャルサイト:rinkokimino.com/
-
4.0平成から令和へと時代が変わり、皇位継承問題、特に女性天皇への関心が高まるなか、「愛子さまが天皇になれないのはおかしい」と思っている人は多い。世論調査では、「女性天皇」に賛成する人が70~80%。一方で、「女系天皇」の意味がよくわからないという声は90%を超える。賛成、反対を議論する前に、まずは最低限知っておきたい「女性天皇」と「女系天皇」の違い。そして、現在議論となっている「女系天皇」と「女性宮家」にはどのような反対意見があり、なにが問題となるのか。明治天皇の玄孫にあたる作家・竹田恒泰氏と、政治哲学が専門の評論家・谷田川惣氏――本書では、両者による対談と谷田川氏による論考の2部構成で、議論のポイントをわかりやすく解き明かす。今後の皇位継承について、日本人の教養として読んでおきたい必読書。
-
4.0心が豊かになる、考えが深まる、日本人がよくわかる。 万葉集研究の第一人者が挑戦、目から鱗の日本語練習帳 「言葉を鍛えるということは、心を磨くということと一体である」と著者は語ります。本書では『万葉集』に使われている、美しい「万葉ことば」を数多く紹介している、日本語練習帳です。日本語が持つ言葉の深みや、伝統にひたる楽しみを味わってみてはいかがでしょうか。 【もくじ】 第一章 ずっと伝えていきたい美しいことば 紹介している言葉……「はつはな」「ちはやぶる」 ほか 第二章 ことばに表れる万葉びとの心もよう 紹介している言葉……「うつろひ」「うつしごころ」 ほか 第三章 ほんのり、わくわく、万葉ことばで遊ぶ 紹介している言葉……「さやけし」「たまきはる」 ほか 第四章 ことばから古の暮らしがありありと 紹介している言葉……「ひねもす」「はろはろに」 ほか 第五章 本来の意味を知り、ことばに親しむ 紹介している言葉……「うつらうつら」「いとふ」 ほか 第六章 ひと言に深い思いが隠されている 紹介している言葉……「みやび」「あしび」 ほか 第七章 「ことば比べ」で微妙な違いを楽しむ 紹介している言葉……「鳴神」「明星」 ほか 第八章 教養として知っておきたい万葉ことば 紹介している言葉……「たらちねの」「あらたまの」 ほか
-
4.0【内容紹介】 日々起こる出来事やニュースを見聞きしたときに感じる素朴な疑問を解消するために、理解しておきたいポイントをイラストや図版をふんだんに交えてわかりやすく紹介しています。 子どもに質問されたときに、きちんと答えてあげたい親御さんや、中高生にピッタリの1冊です! 掲載されているテーマの例 「パンダはなぜ中国へ返すの?」 「日本にカジノができるというけど、問題はないのかな?」 「証人喚問をしても何もわからないのはなぜ?」 「古くなった道路やトンネル、補修されずにそのままなのはなぜ?」など、 雑誌『レタスクラブ』の人気長寿連載をまとめた1冊。 ふだん目にするニュースの「本当の意味」を知るために必要な知識や教養を、子どもにも、もちろん大人にもわかるように池上彰さんが解説します。 新学習指導要領が2020年度から変更になり、より「思考力」が問われる時代に向けて、自分のアタマで疑問を持ち、納得できるようなニュースの見方を伝えます。 テレビ、ネット、新聞、書籍などからの正しい情報の取り方についても触れています。 【目次】 第1章 日本の「今」がわかるニュース 第2章 世界の中の日本が見えるニュース 第3章 政治へのギモンがわかるニュース 第4章 未来の日本が見えてくるニュース 第5章 ニュースの送り手・メディアについて考える
-
4.0
-
4.0早送りでフィルムを再生するように歴史を読む! わかる! 世界史全体を一気に俯瞰する一冊。通史の書籍は沢山ありますが、本書は、「35のキーポイント」「歴史の読み方」「トピックス」など、歴史を理解し、腑に落ちながら読んでもらうための工夫が満載。現代とのつながりを感じながら読める人類史の本です。 〈本書の4大特長〉 ●「35の鍵」で流れがわかる! 歴史の転換点ごとに「キーポイント」を紹介。ここを見るだけで、大きな流れがつかめます。 ●「歴史の読み方」で出来事の意味がわかる! それぞれの出来事について「現代から見た意味」を解説。それが現代にどのように関係しているのか、歴史の意義・意味がわかります。 ●「トピックス」で背景がわかり、教養が高まる! 歴史の流れだけでなく、関連する話題をトピックとして沢山挿入。教養としても雑学としても知っておくべき知識が満載です。 ●やさしい語り口ですいすい読める! 大きな動きをつかむために、あえて細部をそぎ落とし、流れるように読むことができます。初めて世界史に触れる人、なんとなく知っている人はもちろん、歴史に詳しい人も新たな発見が必ずあります。
-
4.0
-
4.0「日本近代書道の父」と称される日下部鳴鶴の流れをくむ鳴鶴流第四代を継ぐ書家の著作。「字書きは文字学者でなければならない」という師匠の教えに従い、漢字の成り立ちなどについても研鑽を積み、それをまとめたのが、この一冊だ。 章立てがユニーク。「歩く文字、走る文字」「鷲づかみにされた心」「漢字でない漢字」「誠の花を学ぶ」「点は一生」の5章からなる。表意文字である漢字の意味や文字の誕生や変遷をたどり、漢字の魅力や書への思いや書聖、王羲之についても筆を進める。 書家の文字エッセーといった趣。「○(まる)」は三画で意味は四角であるなど、日ごろ接しているものだけに、改めて親しみが湧いてくる。だが、それだけではない。書の修行では「横棒三年、縦棒十年、点は一生」という。「先生になるにはその上にきちんとしたまるが書けなければならない」と、「○」の難しさも強調する。 文字と人間のかかわりは深く、歴史的にはたくさんの言語や文字が発生しては時代とともに消滅したり、大きく変化してきた。そうした中で、漢字だけが生き長らえているのは、漢字が表意文字であるという強みを持ち、書体は変わりながらも本質的には意味が変わらなかったことが大きいという。 それゆえに、中国では何千年も前の詩や文献を現代でも同じように読むことができ、それが古典的教養となって根付いている。漢字には、何千年と受け継がれてきた人類の知恵が秘められているということなのだ。 「意味を持つこと」が漢字の命であるという著者の指摘は新鮮に響く。読みやすく、手軽な漢字の入門書といえ、「漢字が嫌いだ」という人でも楽しく読める。
-
4.0トヨタの強さの真の理由は、世界中で学ばれ続ける「時間の使い方」にある。本書は、トヨタ式の普及で知られたカルマン株式会社顧問として、トヨタ式の実践現場や大野耐一直系のトヨタマンたちを幅広く取材、トヨタ式の書籍やテキストなどの制作を多数主導した著者が、トヨタの時間哲学をまとめあげた意欲作だ。「生産のリードタイム(所要時間)を10日から3日に短縮したと誇る経営者に、あるトヨタマンが助言した言葉です。『3日ではなく、72時間と考えてみてはどうですか』。それは『時間の単位を変える』という意味でした。10日を3日にした後、さらに1日を削るのはさすがにプレッシャーでしょう。でも、『24時間を23時間に』『60分を59分に』と考えれば、また新しい知恵が出てくるのではないでしょうか。どれほど長い年月も『1分1秒の積み重ね』だと見て改善を続ければ、人はかなりのことを成し遂げられるのです」(はじめにより抜粋)
-
4.0「契約書なんかなくても、信頼関係があれば大丈夫」「契約書をつくるなんてめんどうくさい」……このように思っているとしたら、その考えは危険だ。なぜなら、口頭で決めた約束だけでは、「言った言わない」や解釈の違いが起こりやすいからだ。こうしたトラブルが起きると解決のために多大な時間と労力を費やすことになってしまう。そこでトラブルを未然に防ぐためにもっとも効果的なのが、契約を文書におきかえるという作業なのだ。本書は、契約書の基本的な知識から「とき」と「場合」の意味の違いは? というような用語の使い分けまでわかりやすく解説する。契約書の作成に役立つ基本書式もついているので、常に手元に置いておきたい1冊!


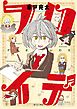




























































![ニーチェ[超]入門 生きるための哲学](https://res.booklive.jp/198748/001/thumbnail/S.jpg)