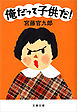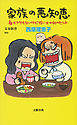エッセイ・紀行 - 文藝春秋作品一覧
-
-その出会いが僕の人生を変えた。 相撲部屋に生まれた身長192センチのイケメン青年が出会ったのは、あの「木久ちゃん」こと林家木久扇師匠だった! ほとんど何も知らずに落語の世界に飛びこんだ青年が驚いた、木久扇師匠の様々な教えとは? 著者は、林家木久扇の弟子で二ツ目の落語家。 秋田県出身の元大関・清國(元・伊勢ケ濱親方)の長男として生まれた。192センチの長身、爽やかな容貌で、「イケメン落語家」としても人気がある。 高校時代に林家木久扇の「学校寄席」を聞き、落語に目覚め、大学時代に弟子入りした。13年に二ツ目昇進。入門して9年、「落語家としての生き方も人としての生き方も、すべて師匠から教わった」。 何も知らないままに落語界に飛び込んだ著者がつづる、辛くて可笑しい修業の日々。テレビからはうかがい知れない木久扇師匠の素顔と、教えの数々。様々な師匠方との出会いと別れ。次第に分かってきた落語の面白さ……。ときに爆笑、ときにしんみりの青春落語物語。 【目次】 第一章 落語家入門 それは木久蔵ラーメンから始まった 第二章 寄席での修業 ポンコツ前座、本日も多忙なり 第三章 二ツ目昇進と我が一門 昇進披露での出来事 第四章 相撲部屋の少年 僕の家には土俵があった 第五章 木久扇伝説 うちの師匠ってこんな人 第六章 落語家の日々 思い出の師匠方 新作落語「どす恋」 特別師弟対談 林家木りん×林家木久扇
-
3.4第158回直木賞(平成29年下半期) 受賞後第一作! 著者が長年創作のテーマとして考えてきた「歴史と日本人」をこの一冊に。 ――戦前の日本は、お人よしだな。 そう思うことがある。植民地のために人をやり、金をついやし、わざわざ政治的、軍事的困難に足をつっこむ。 そうして台湾のみならず東北アジア地域そのもののなかで出る杭になった末に、あの領土の奪い合いでもない、人民革命ののろしでもない、何だか理由はよくわからないがとにかく日本の膨張が一因らしい対米戦争へずるずる入って行ってしまった。 (「お人よしの台湾統治」より) 新直木賞作家が平成の終わりに考えた「この国のかたち」。 ・元号は平ったく言えば天変地異の占いの道具だった ・植民地経営に乗り出した戦前の日本はお人よしだった? ・宮沢賢治と夏目漱石の文体の「秘密」 ・「艦これ」の隆盛を司馬遼太郎が予言していた!? ・新聞はほろびたという議論は明治時代からあった ・刀は物体、剣は精神である ・女工哀史は本当に「哀」なのか ・人口減少で「邪悪な正義」も減る ほか、 全50篇。 フェイクでもヘイトでもない。この国の豊かな歴史にふれる渾身の歴史エッセイ集。
-
4.3仏像を訪ねる『見仏記』シリーズ、武道館公演や映画化もされた大人気トークイベント『ザ・スライドショー』、展覧会の「仏像大使」活動などでおなじみのいとうせいこう&みうらじゅん。 旅に出るときの新幹線の車中でもずーっとしゃべりっぱなしの仲良し名コンビが、2016年1月から2017年5月まで放送していたラジオ番組「いとうせいこう×みうらじゅん ザツダン!」(文化放送)の中から、とくに面白かった雑談を選り抜いて書籍化。 乾電池の「単」とは何なのか? ♂♀マークの意味するものは? 新幹線で時刻通りに通過されてしまう三河安城駅って? お風呂でメガネは外すのか? 手にメモを取るのにふさわしい内容とは? 新婚さんにふさわしい間取りは? みうらじゅんの美髪の秘密とは? 三途の川は何級河川なのか? 理想の葬式とは? 死ぬときに言いたい最期の言葉は?……などなど、くだらなくて笑ってしまう雑談から「なるほど!」と感心する雑談まで、怒涛の74本を収録。 笑いの中に真理あり! 読めば身につく雑談力! 雑談上手になれる「雑談藝の極意十箇条」や、新幹線車内で隠しどりした「本気雑談」も収録。転がり続けるおしゃべりは誰にも止められない! ザッツ・トーキング・ロール!
-
3.8★パリジェンヌはねこに似てる――!? 両者の「シンプルなのに素敵」を大解剖 ・「何もしないでボーっとする」のはまるで瞑想タイム ・「水分補給は迷わず水」だからいつも頭も体もすっきり ・「野性のカン=ときめき」を大切にすれば、恋愛スキルがアップ ・「体の曲線をいかす着こなし」は柔らかな魅力を生む ……などなど、パリジェンヌの中の「ねこっぽさ」を取り入れると、毎日がいいことづくし。 Contents Partie 1 ねことパリジェンヌのマル秘リラックス術 Partie 2 愛されるコツ? ナチュラル&ワイルドな生態 Partie 3 ひとり(ソロ)活動って楽しい! Partie 4 着こなしと身だしなみのヒント Partie 5 食事と生活のヒント Partie 6 パリジェンヌ的リラックスシックな週末 1章では、シンプルに見えて哲学的な「リラックス術」 2章では、気ままなのに愛される「自然体でワイルドな生態図鑑」 3章では、「ひとり行動」だからこその、楽しく幸せな過ごし方 4章では、洗練された見た目を生む「ファッションとビューティ」 5章では、シンプルで健康的な「食生活と暮らし」を紹介。 6章には、ねこ的パリジェンヌが粋に週末を過ごすストーリーマンガを収録。 どうしたらあんな風に自由にのびのび生きられるのか? 外見から本能的な部分まで、自分のどこからどこまでを 人にさらけ出して良いのか? キーワードは「リラックスした内面、シックな外見」。 心に寛ぎを生み、魅力ある人になる秘訣を ねことパリジェンヌから学んじゃいましょう。 (「はじめに」より)
-
3.6もしかして、東京を「大都会」だと思っていませんか……? 気鋭の社会学者が、地上2.3メートルの “ちょっとだけ上から目線”で綴る、東京=日本論。 バスの窓から見つけた、東京の秘密100。 小池百合子都知事との対談も収録 【東京には、こんな秘密が隠されていた!】 六本木はまるでスラム街/セーラームーンの舞台は、麻布十番/スカイツリーにはお墓が似合う/ポケモンGOが伝える悲惨な東京史/池袋は埼玉の植民地である/浅草も千住も「下町」ではなかった/高齢者だけが使える秘密の都バス年間パスポートがある/地方出身者が西東京に住む理由/新宿はかつて上野にバカにされていた/心霊を気にしていたら東京には住めない/東京の街の色は、ほとんどが看板の色だった/等 僕は数々の都バスに乗ることで、東京を「ちょっとだけ上から目線」で堪能してきた。その記録が、本書ということになる。(中略)結果、たどり着いたのが「東京のほとんどが田舎である」という仮説だ。「田舎」というのには二つの意味がある。一つは、見た目としての「田舎」。二つ目は気質や制度とし ての「田舎」だ。 (はじめにより) ◯著者プロフィール 1985年東京都生まれ。専攻は社会学。日本学術振興会「育志賞」受賞。慶應義塾大学SFC研究所上席所員。内閣官房「クールジャパン推進会議」メンバー、朝日新聞信頼回復と再生のための委員会外部委員などを歴任。著書に『希望難民ご一行様』(光文社新書)、『絶望の国の幸福な若者たち』『誰も戦争を教えられない』(講談社)、『だから日本はズレている』(新潮新書)、『保育園義務教育化』(小学館)など多数。
-
3.0「仲の良い男友達を好きになってしまった」「彼のことは好きですが、彼のお母さんが苦手です」「10年以上も前に別れた彼を忘れられない」…。 真面目な女性ほど、恋愛の悩みは深い? 真面目だからこそ不倫してしまう、働き者だからこそ出会いがない…恋愛相談に、親や友人は意外とあてになりません。 「東京ラブストーリー」「同級生」など、作品がドラマ化されて社会現象ともなり、恋愛の教祖ともカリスマとも言われる柴門さん。「出会う」「落とす」から、「つきあう」「不倫」「結婚まで」さらに、「飽きる」「別れる」まで、サイモンさんがずばずば解決! 全章、描き下ろしの4コマ漫画つき。
-
4.5パリ暮らしが15年を超えた雨宮塔子さんにとって、この数年は「人生の大転換期」でした。パティシエ青木定治氏との離婚後、思春期前の子供たちを連れて雨宮さんは新居へ引っ越します。そして2016年には、TBS「NEWS23」のキャスターという仕事のオファーを引き受けることに。新しいキャリアへの挑戦を前に、いっしょに暮らすフランス人のパートナーはどんなアドバイスをくれたのか。パリの家や暮らしを描くエッセイで、女性として、母としての転機に、何を感じ、どう行動したのかを赤裸々に告白します。パリ暮らし16年で迎えた転機。.2014年に結婚を解消してから、TBS「NEWS23」のキャスターを引き受けるまで。“家には物語がある” 雨宮塔子の住まいと人生を巡るエッセイ。
-
4.4かつて『ファウスト』を手に取りながらも、途中で挫折したあなた! 読み通せなかったのは、あなたのせいではないのです。 投げ出してしまったのは、これまでの重々しく格調の高い“古典文学的な”翻訳と、「人格形成を目指して努力する人間の物語」と日本で勝手に神格化されてしまったから。 そもそも『ファウスト』はお芝居なので、字面を追っても本当の面白さは伝わりません。そこで演劇にも通じたドイツ文学者が、演じられる情景が目に浮かぶような訳文と、ていねいな解説をまじえながら原作を一気に紹介。 悪魔メフィストと契約して二十歳そこそこの青年に若返った老博士ファウストが、ギリシャ神話の古代から未来まで時空を超え、美男美女、神や魔物が入り乱れる世界で、欲望のままに少女をだまして捨てさったり、人を殺したりと自由奔放に活動する--歌あり踊りあり、マジック、サーカス、ストリップ、お笑い、剣劇を織り交ぜた最高のエンターテインメント『ファウスト』をついに読み通せます。
-
5.0賞味期限切れのソースで運試し。 新聞を読んでいると、つい求人欄に目がいってしまう。 ショックなことがあると、食事もせずにひたすら眠る。 風呂上りのアイスだけが仕事の励み。 トイレットペーパー8ロール入りが豊富にあれば気分が高揚・・・。 現代日本を生き抜く30代女子の日常をしなやかな文でつづり、同世代から圧倒的な支持を得た「壇蜜日記」。 シリーズ2冊に加え、週刊文春グラビア「原色美女図鑑」、阿川佐和子さんや作家・桜木紫乃さんとの対談などを収録した『壇蜜日記0(ゼロ)』を加えて、1冊にまとめた完全版。 「想像に任せるなんてイケてる芸能人みたいな事は言わないでおく。抱かれた」(本文より)
-
5.0あの欽ちゃんが、73歳にして大学生に! 舞台の仕事をやめた萩本欽一さんは考えた。認知症と戦うために、脳に新しいことを覚えさせよう。そうだ、大学へ行こう。 休まず講義に出たり、孫のような年の同級生と交流したり、駅伝チームの「スペシャル・サポーター」を務めたり・・・楽しくも、波乱万丈なキャンパスライフを語りつつ、半世紀以上におよぶ芸人生活でつちかわれた人生哲学を披露する。「週刊文春」好評連載が一冊に。 認知症と食事をテーマにした白澤卓二医師との対談、駒澤大学陸上部の大八木弘明監督との対談も収録。 歳をとってからでも挑戦は出来る。苦労も楽しむことが出来る。欽ちゃんの前向きな姿から、よりよい人生を送るためのヒントが豊富に得られます。
-
4.3
-
3.9「受験」「英語」「資格」「暗記」すべてに対応! いつでもどこでも誰でもできる! 現役東大生が明かす、スマホを駆使した超効率的なシン・独学術。 学習に特化した厳選勉強アプリ20を徹底紹介&解説! 〈スタディサプリ〉〈anki〉〈YouTube〉〈Studyplus〉 〈目標達成タイマー〉〈モノグサ〉〈reminDO〉〈abceed〉 ● 人工知能が「暗記」を超効率化! ●「世界一わかりやすい授業」が自宅で見れる ● 成績上位者の「勉強データ」が見れる ● 無理せずに勉強が続けられる 「塾や予備校に頼らず、独力で試験に合格したい」 そう考える人は、受験生にもビジネスマンにも多いと思いますが、実際にはかなりハードルが高いのも事実です。 全部一人でやると時間もかかるし、何が正しいかもわからない。集中力も続かない。 独学がうまくいかないのは、「独り」による弊害を乗り越えられないからです。 しかし、スマホを上手に活用すれば、その弊害をクリアして独学で成績をあげるために必要な「5つの力」が簡単に手に入るのです。 本書では、その自身の経験や周囲の東大生たちからの最新情報も踏まえ、誰でも簡単に無理せず独学し、そして成績を上げるためのノウハウを紹介します。 ――スマホは、勉強の「味方」だ。
-
3.7いきなり「人生百年時代」と言われても……。立ちすくむ老人予備軍に、ベストセラー『暴走老人!』の著者が、「暴走老人化」せずに孤独と向かい合う術を伝授する。 序章は、現代の神話化した「人生100年」の実像と平均寿命のカラクリについて。 第1章は、ネットやスマホとの距離を保つということについて。 第2章は、コミュニケーションのとり方、生き方の正しい方法について。 第3章は、世の中に流布する「孤独観」を整理して、そのなかで老人が陥りやすい孤立と孤独について。 第4章は、老人を取り巻く社会の眼差し、同調圧力に影響されない生き方について。 第5章は、セカンドライフのための意識の大転換に必要な「リボーン・ノート」について。 第6章は、価値ある「暮らし」を再構築するということについて。 芥川賞作家が教える、「生きがいのある老後の過ごし方」。
-
4.3松本人志の出した3つのお題に吉本若手芸人86人が挑戦した。 爆笑・失笑・珍作・怪作・傑作・・・選りすぐりの123編! 〈後輩の芸人たちに僕からお題を出して、原稿用紙一枚程度、文章を書いてもらいました。言ってみれば、文学的な大喜利です。まずタイトルを決めて、そこに向かって書いていくとどうなるか、縛りがある分、逆に個性がよく出てくるんじゃないか。〉(まえがきより) ダウンタウンの松本人志が、後輩の若手芸人たちにお題を出した。 「火星人の殺し方」 「ゴリラへの詫び状」 「日本人はなぜうんこが好きなのか」 芸人の中には舞台で輝かなくても、トークが下手でも、文章なら意外な才能を発揮する人が埋もれているかもしれない。それを見出すべく自由に発想してもらった、いわば文学的大喜利である。 集まった数百の回答は、わずか数行のものから原稿用紙数枚のものも。一発ギャグがあればショートショートもあり、まさに多彩かつ多才だった。 そこから120篇を精選。さらに各お題につき一人を選び、あらためて長めのものを書き下ろしてまとめたのが本書である。 回答例 火星人の殺し方 〈小学生の時にまずひょんなことから火星人と出会います。そこから一緒の学校に通うことになり、中学、高校、大学と一緒に過ごし互いを親友と呼ぶ間柄になります。大学卒業後は別々の人生を歩むことにします。そして大学卒業の別れの日に「これからも親友で居てくれるよな」と握手を求めて近づいて来たところを、鋭利な武器でズバッといきます。〉(ウエスP) なぜ日本人はうんこが好きなのか 〈日本人にはジャイアント馬場(大きいうんこ)が深く心に刻まれてるから。〉(吉本新喜劇・前園健太)
-
5.0
-
-別府君は「子どもが書いてる」んではなくて、作家だけどまだ子ども--吉本ばなな 新潟県在住の別府倫太郎君は十四歳。五歳のときに円形脱毛症により全身の毛が抜けてしまった。さらに七歳で小児ネフローゼを発症。ステロイド治療のためムーンフェイスとなる。小学校2年生のとき、学校に行かないことを選択した。 その後、インターネット新聞『別府新聞』を開設。別府新聞社の社長として、地域の話題の取材にでかけたり、自分のことや周囲のことをエッセイとして発表するようになった。次第にそのみずみずしい文章の魅力が評判を呼び、知られるようになった。 本書は『別府新聞』で発表した文章と、『別府新聞』を休止して以後に発行する個人雑誌『文藝雪月花』などに掲載したエッセイ、日記、小説、詩のほか、別府君の文章が大好きだという吉本ばなな氏との対談も収録。
-
4.2“ことばあそび”の世界へようこそ! 気鋭の歌人、山田航さんは、実は回文(上から読んでも、下から読んでも同じ文)作りの達人でもありました。ひとつ紹介しましょう。 「眠たいが眠ると太る、胸が痛むね」(ねむたいがねむるとふとるむねがいたむね) 回文以外にも、辞書1冊あれば、いえいえ、満員電車で吊り広告を見上げるしかない数分間にも、ことばあそびの入り口は無限に開かれています。アナグラム、パングラム、アクロスティック(折句)、しりとり、なぞなぞ、早口言葉など、シンプルで奥が深い“ことばあそび”の魅力へいざなうエッセイ。和田ラヂヲさんのシュールなイラストも魅力。
-
3.8
-
4.0エッセイ×マンガでたどる7年間の「修行映画」鑑賞の記録を一冊に! 映画館は僕にとって日常からの逃避の場であり、道場でもある。 「自分に向いていない映画」を求めて劇場に通い、「つまらな……」が出そうになった瞬間「そこがいいんじゃない!」と唱えれば、あらゆる映画に「マイ価値観」が生まれる! 『007』や『ミッション:インポッシブル』など人気シリーズ作品、『若おかみは小学生!』『君の名は。』などアニメ作品、『シン・ゴジラ』『ゴジラvsコング』など怪獣もの、『先生!、、、好きになってもいいですか?』『俺物語!!』などマンガが原作の青春もの、『クロール―凶暴領域―』『THE POOL ザ・プール』などワニ系パニック映画、『科捜研の女―劇場版―』『劇場版おっさんずラブ?LOVE or DEAD?』などテレビドラマの劇場版……ほか、恋愛映画からホラー映画、大メジャー作からマニアックな作品まで、軽妙なエッセイと絶妙な似顔絵が楽しすぎるマンガで紹介。 雑誌「映画秘宝」人気長期連載を一気読み!
-
5.0
-
4.5まわり道しなければ、たどり着けない場所がある――。 若き日の著者の、人生を決めた旅立ちの物語。読んだ人に深い感動と変化をもたらした話題の書。 第七回梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞作。 大学4年のある日、オオカミの夢を見た。自然写真家を目指していた著者は、導かれるように1冊のオオカミの写真集と出会う。「ダメもとくらいの挑戦をしないと、人生は面白くない」と語る著者は、その世界的な写真家ジム・ブランデンバーグに弟子入りを直接志願するため、単身アメリカに旅立つ。 ミネソタ州北部に広がる森と湖の世界「ノースウッズ」の入り口へたどり着き、ジムの家がその先にあると突き止めると、カヤックにキャンプ道具を積み込み、水上の旅へ。深い北国の森と無数の湖、様々な野生動物との出会い。8日間の旅の末にたどり着いた場所で、ついにジムとの対面を果たすが――。 臨場感あふれる自然描写、不安に揺れ動く心情を正直に素直に描く、著者のかざらない姿に、いつしか共感し励まされる。自分の足で歩き、自分の目で見て、人と出会うことの大切さを教えてくれる、人生の羅針盤となりうる一冊。 著者による「文庫版あとがき」追補。 解説:松家仁之(小説家)
-
5.02017-2018冬 私はあさましく品がないが幸福者だ 2018春 欲望は抑えると、脇から形を変えてはみ出てくる。 2018夏 仕事の趣は必ず顔や考え方に出てくると思っている。 2018秋 独りで生きることしかできない体に着々と仕上がっている。 勝手に別れた男のことを勝手に思い出し勝手に浸り、学生時代に好きだったプライドの高いクールな女の夢を見る。美人女優の中で自分は華やかな熱帯魚の水槽に出汁をとったあとの煮干しのようだと思い、水泳にヨガにサウナに行っても体脂肪は変わらず、ナマケモノを飼ってナマケモノのために働く理不尽な生活をしたくなる……。 壇蜜のあるがままの日々。今日もまた“自分いじり”に磨きがかかる。 ●著者自ら撮影の写真収録。
-
3.0『奥田民生になりたいボーイ 出会う男すべて狂わせるガール』作者の魅力全開! 漫画家・コラムニストとして、サブカル界で独自の道を進んできた著者の、6年ぶりのコラム本がついに刊行。 「とても」の丸みボディ(字のことです)をいつくしみ、「中指」の可哀想さを世間に喚起し、「お湯」のセルフプロデュースの高さに着目し……。森羅万象の「そこ!?」というものに過剰に思いをはせた、44本のコラム集です。 巻末には渋谷直角が「かわいい」と認めたものたちが大集合した「かわいい王国図鑑」31ページを収録。(自動販売機の横のごみ箱、TSUTAYAのバッグ、センサー式の蛇口など20本!) 【目次】 とても/ぶどう酒/まみむめも/つもり/おこげ お湯/中指/雑/くぐる/クロワッサン/打ち合わせ/イチゴ/なまこ/み/しいたけ/あわよく/ビショビショのサンドウィッチ/それもいい/味/丸まった靴下 ……ほか、絵やマンガが渾然一体となったコラム44本。 〈巻末付録〉 お寿司/バス/あぶらあげ/小石/うずらのたまご/フタ/自動販売機の横のゴミ箱/TSUTAYAのバッグ/センサー式の蛇口 ……ほか、かわいいものばかりを集めた32ページ「かわいい王国図鑑」付き。
-
3.5長く付き合っていて結婚すると思っていた彼氏とまさかのアラサー破局した ずっと恋愛をしていたけれどなぜかいつも短期恋愛で終わってしまう 好きな人はいつもいるけどいつも付き合えずにセカンド・不倫で終わってしまう フツーに恋愛すると思っていたらさっぱり恋愛に縁がなかった……などなど 「なんで幸せな恋愛につながらないの? 夢見ていた結婚に結びつかないの?」 と、心で叫んでいませんか? 理想が叶わないのは、私たちが妖怪女子だから! 本書は「恋愛に悩む男性と女性に向けた女性生態の観察」です。 「妖怪女子18種類の生態観察」「妖怪女子になる理由と構造」「妖怪女子コースから離脱する方法」という3つのパートで構成。 冒頭のフローチャートでは妖怪女子を大きく5つに分類。自分がどの分類のどの妖怪女子にあてはまるのか、試してみてから読むのもよし、最初から妖怪女子の生態を追ってみるもよし。 ただ一度しかない自分の人生を、「こうすればよかった」「ああすればよかった」「こんなんじゃなかった」と後悔して、失望と怒りと不満ですごさないために、間違った自己認識=妖怪マインドを全力でお焚き上げ!! ●妖怪女子18種 1恋愛相談マニア女子 2察してちゃん女子 3ピンとくる信仰女子 4でもでもだって女子 5ハイスペ限定女子 6港区女子 7恋心の搾取モテ女子 8ときめき至上主義女子 9すぐ幻滅女子 10尊敬できる男じゃないとダメ女子 11束縛ネトスト女子 12自称モテ女子 13私をもてなせ女子 14ずっと片思い女子 15ずっとセカンド女子 16私はあなたの信者女子 17私が彼を救う女子 18それはモテじゃないカモだ女子
-
4.2
-
-総合月刊誌「文藝春秋」の創刊85周年を機に実施された読者アンケートの結果をもとに、人気記事をセレクトして特別編集。 スペシャルコンテンツとして、歴代編集長による座談会や、「社中日記」特別版まで収録しました。時代の寵児たちの告白から、世間を揺るがせたスクープまで、この一冊に戦後日本の姿が凝縮されています。 【本書に収録されている主な記事】 ・天皇陛下大いに笑う (辰野隆 徳川夢聲 サトウ・ハチロー) ・日曜日の食卓にて (白洲次郎) ・バタバタ暮しのアロハ社長 (本田宗一郎) ・明日は明日の風が吹く (石原裕次郎) ・わたしの放浪記 (森光子) ・タダ酒を飲むな (山口瞳) ・わが日本一の借金王時代 (松下幸之助) ・ゼロ歳教育のすすめ (井深大) ・田中角栄研究 (立花隆) ・大殺界・細木数子の正体 (佐野眞一) ・犠牲 (柳田邦男) ・妻と私 (江藤淳) など ※本書は、「文藝春秋」定期購読者向け「もう一度読みたい あの記事あのエッセイ 『文藝春秋』昭和・平成 傑作選」(非売品ムック)の内容をもとに構成されています。 ※2016年7月12日に限定販売された、「Amazonオリジナル 創刊九十三年 たった一日だけ販売される 月刊文藝春秋ベストセレクション」を電子書籍化したものです。
-
3.3「やまとなでしこ」「ハケンの品格」「花子とアン」・・・大ヒット連発の人気脚本家は、ダメOLにして占い師だった! 「最初に白状してしまおう。私は、ぐーたらなダメ人間である」 学生の頃は勉強で挫折。就職活動に失敗し、大学卒業後にコネでOLになるも失敗ばかり。根っからの恋愛大好き、遊ぶの大好きな怠け者、しかも大酒飲み。 こう語る著者が脚本家として成功できたのはなぜか。世の中でもまれ、仕事と恋に鍛えられた半生を初公開。人生に迷い、悩みを抱えている人に贈る一冊。 【おもな目次】 ■第1章 負のパワーは、全開に燃やせ!■ 「ものを書く」と退職して叱られる/けっこう稼いだ四柱推命の占い師時代/二十六歳、失恋のパワーで脚本家を目指す など ■第2章 運気は他人の分まで使え!■ どこまで共感して話を聞けるか/お酒の力も借りるべし/誰に乗るか、それが問題だ など ■第3章 負けが続いたら、きっと次は勝つ■ 頭から煙が出るまで考える/悪い流れは「持っている人」に払ってもらう/天中殺には人生の修業を など ■第4章 崖っぷちに立て!■ 迷ったときは、未来の自分をイメージしてみる/女の甘えは根こそぎ捨てる/向いていない仕事をやってみる など ■第5章 「できること」はたった一つしかない 脚本家を選んだ理由/ほめられた経験を探せ など ■第6章 恋愛こそ、わが命 自慢だったラブラブの両親/恋愛は全員が加害者だ など ■付録 私を救った一言■ 美輪明宏/黒柳徹子/伊東四朗/林真理子
-
4.3東進ハイスクール講師・安河内哲也氏推薦! 「人間なんていつだって変われる。ゼロからでもやればできる!」 ――その日私は髪を切り、スマホをガラケーに替えた。 アイドルグループSKE48の五期生に合格したのは中学三年生の秋だった。 小学生時代から習ったダンスの実力が功を奏し、同期で最初に選抜メンバーいり。 紅白出場も果たして充実した毎日だった。 しかし……忙しくて学校にはほとんどいけない。 悩んだ末に大学進学を決意し、高2の冬にSKEを卒業した。 だが、進級さえ危ぶまれた成績は壊滅的。 髪をバッサリ切り、スマホをガラケーに変え、一日十数時間の怒涛の受験勉強が始まった! だが、高3の6月、模試の数学は0点だった……。 そして迎えたセンター試験。 受験は、青春だ! カバー・扉などに撮り下ろしフォトを収録。 アイドル時代の自撮り写真など貴重なプライベートショットや、テスト成績表も掲載!
-
3.8ついに「週刊新潮」山口瞳氏の記録を抜いて、前人未到の32年目に突入! 「週刊文春」連載エッセイ第29弾。 林さんの近頃の関心事は、若い人達にどうやって本を読んでもらうかということ。林さん自身、美味しいものや美しいものへの好奇心は、本から吸収してきたという気持ちがあるから。特に、川崎の中学一年生の男子生徒が殺害された事件について書いた「お母さん、お願い」の回は、批判を含め、様々な議論を呼びました。 「批判されても、思ったことははっきりと言う。それが社会に対する私の責任だと思う。書かなきゃただのおばさんですから」。 飽くなき好奇心と覚悟に裏打ちされた、切れ味鋭いエッセイ最新刊!
-
3.5
-
4.2黒木奈々、31歳。NHK BS1「国際報道2014」のメインキャスターに抜擢され、その前途は輝かしいものに思われていた。 そんなある日、友人との食事中に突然の胃痛に襲われる。救急車で運ばれ、胃せん孔との診断で入院。しかし、それは、たんなる胃潰瘍ではなくステージ3の胃がんだった……。 セカンドオピニオンを得て、胃の全摘出を決意。同時に、自らの病名を公表し、病と戦うことを宣言する。 キャスターという立場を生かし、同年代の働く女性たちが、がんに襲われたとき、何か力になれるのではないかという信念のもとに、がん宣告のあとの心境を綴った手記が本書である。 あくまで明るく、前向きに病と闘いつつも、32歳の女性ならではの悩みはつきない。 容姿が取りざたされる職業で、果たして自分は仕事に戻れるのか。 これまでキャリアを優先してきたけれど、もう一度、誰かと恋ができるのだろうか。 結婚は? 子どもを持つことは? 何も「あきらめない」ことを目標とする今の女性たち。その中でがむしゃらに先頭を走ってきたキャスターが突然の病に襲われたとき、何を選び、何をあきらめるのか。 揺れ動く気持ちを素直に書き記した闘病記。
-
5.0巻頭に「新妻」がテーマの撮りおろし写真集を収録! 結婚なんてゴールではない。 新婚早々見舞われたコロナ禍の中、マスクを作り、サウナに通い、ペットを愛でる。 祖母、ナマケモノとの別れ、そして新しい出会い――。 未曾有の一年を彼女は夫、たくさんの動物たちとどう過ごしたのか。 ほろ苦くて甘い蜜、のリアルな日々。 目次 スペシャルグラビア 2020年 冬 結婚なんてゴールではない。 2020年 春 どうにもならないことにやきもきし、目に見えない恐怖に怯える。 2020年 夏 年一しか会えなくてもそれを励みに生きていけるなら、生き甲斐になっていい人生かもしれない。 2020年 秋 小さいころから厳しくも大事にされた。だから今がある。
-
3.3「天声」にはパブリックなイメージがあり、ある種の客観をよそおっている。それに対して「人声」はプライベートであり、あくまで個人的な声。だから「人声天語」とは、要するに、反射神経による思考(発言)のことである。 2003(平成15)年から、2008(平成20)年にかけて起きた様々な事象の、おかしさ、うさんくささ、不思議さを、紋切り型ではない「人声」でとらえた世相コラム集。 収録された主な出来事は―― ネット心中/自衛隊イラク派遣議論/「週刊文春」出版差し止め問題/イラク日本人人質事件/国民年金未払い問題/佐世保小六女子殺人事件/ギリシア五輪/プロ野球リーグ再編問題/靖国問題/ライブドア事件/秋田小学生殺害事件/昭和天皇「富田メモ」報道/ハンカチ王子ブーム/朝青龍問題/安倍総理辞任/時津風部屋暴行死事件/「大阪名物くいだおれ」閉店/秋葉原通り魔事件/地下鉄副都心線開通 など
-
3.7毎日の生活の中には知的好奇心を刺激する素材があふれている。 テロのニュースを聞き、その背後によこたわる歴史を考える。 自然災害の報をうけて、火山国、地震国という日本の宿命を改めて問い直す。 オリンピックをみながら、あの戦争を思い起こす。 横綱誕生のニュースから、トランプ大統領の今後を想像する。 バーの店主だった時代を回想し、いまのジャーナリズムに檄を飛ばす。 そして、みずからの病から、人間の生と死へ思いをはせる。 日々、接するニュースや、足を運んだ展覧会、取材であった科学者の言葉などから、思考の材料を取り出す。そんな「知の巨人」のあざやかな手腕が味わえるエッセイ集。 〈目次〉 第1章 生と死に学ぶ 第2章 歴史と語らう 第3章 科学を究める 第4章 戦争から考える 第5章 政治と対峙する ●特別講義● ・最先端技術と10年後の「日本」 ・ノーベル賞興国論
-
3.9騒然とした日々の出来事から、普遍の教訓を抜き出す珠玉のエッセイ集。 「イスラム国」が引き起こした戦争とテロが世界を震撼させる一方で、EUは揺らぎつづけ、ついにイギリスが離脱。その間も難民の流入は止まることがない。アメリカではトランプ大統領が誕生し、その発言が物議をかもす。そして日本はいまだ不況から抜け出せず……まるでローマ帝国の滅亡を思わせる激動の時代に、私たちは生きている。 古代ギリシア、ローマ帝国、ルネサンス時代の歴史との対話を、およそ半世紀にわたってつづけてきた著者は、移りゆく日々の情勢を扱いながら、そこから歴史の教訓を抜き出す。 「宗教は、人間が自信を失った時代に肥大化する」 「民主政が危機に陥るのは、独裁者が台頭してきたからではない。民主主義そのものに内包されていた欠陥が、表面に出てきたときなのである」 「歴史を経ることで人間は進歩するとは思っていない」 世界情勢だけではなく、祖国日本への愛にあふれた提言や、先達として後輩女性への率直なアドバイスもつづられる。 月刊「文藝春秋」で好評連載中の「日本人へ」をまとめた第4弾!
-
4.2
-
3.5230万部突破「聞く力」シリーズ最新刊 日本人だからこその会話の妙や楽しみ方はあるはず――。 初対面の相手との会話から、認知症の親の介護や家庭円満の秘訣、 会議や会食まで。インタビュアーを三十年以上続けている アガワが披露するとっておきのエピソードとコミュニケーション術。 【目次より】 ◎自分が話したいことを見つける ◎話すべきことは相手の話の中にある ◎会話とは“しりとり話題合戦” ◎沈黙を怖れない ◎相手の話に共感し反応する ◎助け船を出すことを心がける ◎相手との距離感をつかむ ◎モテる男は、聞き上手 ◎距離と時間をおくことも必要 ◎時にはKYも有用だ ◎会合では一番下っ端に喋らせる ◎皇室の会話術に学ぶ ◎絶妙な突っ込みは会話の妙 ◎どんな接続語で始めるか ◎話題に窮したら病気自慢 ◎占いや心理テストはいいネタになる ◎小話を頭の抽斗に入れておく ◎シモネタの効用 ◎日本語の一人称は変幻自在 ◎日本語は相手の出方によって自分の発言を変えられる ◎語り手をノセる合いの手 ◎男女で差が出る会話と人間関係 ◎初対面での会話術 ◎スマホ依存は言葉を忘れさせる ◎一人で入った飲食店で何を喋る ◎アウェイの場所でどうするか ◎初めて会った人への対し方 ◎末っ子の処世術 ◎オジサン上司の心をつかむには ◎私が最も話上手と思った人 ◎専門用語で逃げるな ◎父が教えた正しい日本語と下品な日本語 ◎物語性は対話にとって大事 ◎話の使い回しは落語と同じ ◎ダジャレを嫌がらないで ◎不幸な体験は宝物 ◎認知症の母と話す ◎大惨事になる前に、笑うところを見つける
-
4.0
-
3.8
-
-「愛されるオヤジ」と「愛されないオヤジ」の境界線はここにあり! 人気漫画家・瀧波ユカリが「愛されるオヤジ」になるための46のメソッドを教えます。 「エッチがうまいと言わないで」、「『妻と不仲』と言うべからず」、「友達になりたいと思わせて!」、「ファザコンよりも老け専を狙え!」、 「ヘアスタイルで無茶はしないでね」、「ムッツリスケベもアリですよ」、「優しさと優しいふりは違います」……。 「最近女子からちやほやされなくなったな~」とお嘆きのオヤジ様たちに、『臨死!! 江古田ちゃん』『モトカレマニア』の著者であり、 「マウンティング女子」の名付け親である瀧波ユカリが「愛されオヤジ」になれる46のメソッドを、実例をあげながらかるた形式で明快にレクチャー! 「こんなおじさん、いるいる~」と女性読者から共感の嵐! 「週刊文春」人気連載の単行本化。 描き下ろし四コマ漫画付き。
-
3.4その言動やしぐさは、面白く、ときにためになることもある。 おじさんはリアルな人生の参考書だ! 大人気『おじさん図鑑』の著者が、今度は一緒に飲みに行ったり、 仕事場を訪れたり、おじさんのもつ魅力により深く迫ります。 登場するのは個性派揃いの24人。元祖フリーターのおじさん、 金魚すくいに熱を上げる寿司職人のおじさん、女装が趣味のおじさん、 そして、自民党・石破幹事長(当時)まで!! ひと癖もふた癖もある、それでいてどこか愛らしさも感じられるおじさんばかりです。 おじさん特有の言動やしぐさのおかしみにあふれ、ときにはためになる言葉も。 おじさんの世界ってなんだか楽しげで、不思議で、奥が深い……。 おじさん愛にあふれた絵と文が楽しいイラストエッセイです。
-
3.4ファミリーレストランで、近所の公園で、人生の瞬間と現代を鋭く見すえる――。『転がる香港に苔は生えない』で大宅賞、『コンニャク屋漂流記』で読売文学賞を受賞した星野博美。本好き達に激賞された、短篇小説のようなエッセイ集が電子版で登場! すべてを忘れて、私たちは幸せに近づいたのだろうか……。 吉祥寺と、戸越銀座。著者はさまざまな猫たちとの出会いと別れを経験し、生と死、そして忘れえぬ過去の記憶へと思いをめぐらせていく。 さりげない日常からつむぎ出される短篇小説のようなエッセイのひとつひとつに、現代への警鐘と内省がにじむ。 解説・角田光代 ※電子書籍化にあたり、新章「地中に埋まっている部分」を収録。
-
3.8「新春漫語」「綿菓子」「古本の街のいまむかし」「学生時代の私の読書」といった身辺雑記から「自作発見『竜馬がゆく』」「『翔ぶが如く』について」自作について、「文化と文明について」「日韓断想」「バスクへの尽きぬ回想」といった地域、歴史への想いなど、折りにふれて書かれた、厖大な量のエッセイから厳選した七十一編。森羅万象への深い知見、序文や跋文に光るユーモアとエスプリ、弔文に流れだす、人間存在へのあふれるような愛情と尊敬――。日本人の高潔さと美しさを見つめた視線の先には何があったのか。司馬遼太郎という作家の豊穣な世界に、あらためて酔う一冊。
-
3.6昭和30年、産経新聞記者時代の司馬遼太郎が、本名・福田定一で刊行した “幻の新書”を完全版として復刻刊行。 古今の典籍から格言・名言を引用、ビジネス社会に生きる人たちにエールを 送る本書は、著者の深い教養や透徹した人間観が現れているばかりでなく、 大阪人であることを終世誇りとしていた著者の、卓抜なるユーモア感覚に満ちている。 さらには、本書の2部に収録、記者時代の先輩社員を描いたとおぼしき 「二人の老サラリーマン」は、働くことと生きることの深い結びつき問う、極めつけの 名作短編小説として読むに充分である。 現代の感覚をもってしても全く古びた印象のない本書は、むしろ後年に国民作家と 呼ばれることになる著者の魅力・実力を改めて伝えてくれる。 まさに「栴檀は双葉より芳し」。ビジネス社会を生きる若い読者にも、ぜひ薦めたい一冊。
-
3.7
-
3.5大人気「ニューヨークの魔法」シリーズ、ついに完結――感動の最終章! ニューヨークは大都会なのに、ひと昔前の田舎町のような懐かしさがある。世界一お節介で、図々しくて、でも泣きたくなるほど温かい。長年、ニューヨークに住む著者が、街角や地下鉄で出会う見知らぬ人とのちょっとした心の触れ合いを、粋な英語を交えて描くエッセイ。 「人に疲れているのに人と話したくなる不思議な本」、「毎晩、1話読み、温かい気持ちで寝ます」と熱烈な支持を受け、累計約40万部。 著者が夫を撮ろうとして、たまたま写真に入ってしまった見知らぬ黒人女性。「これでいつまでも私のこと、忘れないわね。私の名前はサーシャ。で、その写真、削除しないでよ!」と叫び、自由の女神のように手をあげピースサインで颯爽と去っていく。 静かな電車で、著者の噛むガムが大きな音を立てて弾け、思わず首をすくめると、前にすわる男性が笑顔で「いいね」と親指を立てる。 美術館で好きな絵を見つめていれば、「僕もこの絵が好きなんです」と後ろに佇む異国の青年が声をかけてくる。 メトロポリタン美術館、オペラハウス、タイムズスクエア、セントラルパーク、ブルーノート、グラウンドゼロ、テレビ局のスタジオ、ブルックリン・ブリュアリー、マディソン・スクエア・ガーデン――。 ニューヨークのあちこちから、人の息づかいと会話が聞こえてくる。今日もどこかで、出会いがある。ミュージシャンの生演奏に合わせて、見知らぬ人同士が踊っている。 著者の原点ともいえるウィスコンシン留学時代の秘蔵エピソードも初公開。最終章「アメリカの家族アルバム」は涙なしには読めません。
-
4.7親しい知人だけに送った“伝説の年賀状”全記録。 真面目くさった挨拶を年賀状に書くのは億劫だ。文言代わりに私らしい写真を送れば楽でいい――そう思った結果、書くよりも何倍もメンドくさいことに! 孫・桃子相手の扮装写真は、その成長と共にトトロ、幼稚園児、コギャル、泥棒、生首となぜか過激になるばかり。やがて反抗期を迎えた孫の運命は……。 解説・阿川佐和子氏「佐藤家の孫に生まれたかった!」 汗と涙の20年を振り返る、母娘三代の座談会付き。 娘・響子 「桃子、この二十年間の記録を今、客観的に振り返ってみてどうなの?」 孫・桃子 「これを客観的には見られないよ」 娘・響子 「あんたトラウマになってるの? ひょっとして(笑)」 孫・桃子 「これに関する記憶があんまりない(笑)」 祖母・愛子「だから、いま見てどう思うのよ!」 (本文「年賀状 鼎談講評」より)
-
3.3人と接するのが怖い時も、フッと心が軽くなる。38万部の人気シリーズ著者が、そんな秘密をこっそり教えます。泣きたくなるほど愛おしい話を、英語の小粋なフレーズとともに贈る。明日へのパワーを充電できる魔法の一冊。あの『ニューヨークのとけない魔法』シリーズ、待望の第8弾! 世界一孤独な街、ニューヨーク。ひとりぼっちでも、哀しみをたくさん抱えていても、なぜ、子どもみたいに人懐こくて、お節介なのだろう――。いつもユーモアを忘れず、あったかい。だから毎日が、なんだか楽しそう。息苦しい人間関係に疲れていたら、ニューヨークの日常をちょっとのぞいてみませんか。 今回はエッセイとともに初めて、海外でも日本でもすぐ使える、とっておきのコミュニケーション術を伝授! 女優・黒木瞳さんとの対談を特別収録――「私も思い切って話しかけてみようかな」(黒木瞳) 【「ニューヨークの魔法」シリーズ(文春文庫)】――続々重版中 人とのささやかな触れ合いを、ニューヨークを舞台に描く――。NYの小粋な言葉があふれ、英語も学べるお得感。1話で完結しているから、どの本から読んでもOK! 「ベストセラーの裏側」(日本経済新聞)、「売れてる本」(朝日新聞)、「ポケットに1冊」(読売新聞)など人気書評コラムで取り上げられた話題のシリーズ。 既刊/『ニューヨークのとけない魔法』『ニューヨークの魔法は続く』『ニューヨークの魔法のことば』『ニューヨークの魔法のさんぽ』『ニューヨークの魔法のじかん』『ニューヨークの魔法をさがして』『ニューヨークの魔法の約束』
-
4.0卑弥呼や紫式部、淀君、井原西鶴、小林一茶、樋口一葉などなど、田辺さんがお気に入りの歴史上の人物たちに新たな息吹を吹き込んだ歴史エッセイ集! スサノオからはじまり、卑弥呼、持統天皇、小野小町、紫式部、後白河院、淀君、北政所、西鶴、芭蕉、一茶、歌麿、一葉、桂春団治まで、田辺さんが好きな歴史上の人物を、半分エッセイ半分小説で紹介。かわいげのある心憎いばかり人物たちを選び、まるで本人たちに会って話したことがあるかのように生き生きと描かれている。 確かな時代考証もあいまって、安心して楽しみながら、歴史上の人物たちと交遊できる。 「戦後三十年たってみれば、若者は日本の歴史や、古往の人物について、全くなんの愛着も関心も持たないではないか。彼らにあっては母国の歴史は、教科書の中の無味乾燥で煩はん瑣さ な、受験用知識にすぎないのだ。私は、それらをみて胸が痛む。古い代に生きて戦い、恋し、苦しみ、死んだ愛すべき人々が、いまの若者たちの心になんの感動をおこすことなく、打ち忘れられ、かかわりをもたず、歴史に埋没してゆくのを悲しむ。受験用知識の、かわいた記号のきれっぱしとなった人々を惜しむ」(著者の「あとがき」より)。ここで取り上げた人物を通して、若い人たちが歴史へ新しい興味を持って接してもらえるようにとの願いを込めた1冊。 解説は『はいからさんが通る』や『あさきゆめみし』などで有名な漫画家の大和和紀さん。
-
3.0春の御前山で思いがけず出会った、薄紅に咲きさかるカタクリの大群落。 あまりの小ささに草地に身を伏せて、ようやく所在を確かめた早池峰のチシマコザクラ。 レブンソウとの新しい出会いに、自分の命がその花に添って伸びひろがってゆくのを感じる―― 山と花をこよなく愛し、日本中の山々を踏破した著者が、その豊富な山行の中から、四季折々の山と花の結びつきを100選び、歴史や自身の思い出とともに綴った珠玉のエッセイ。第32回読売文学賞〈随筆・紀行賞〉受賞作。 1980年に刊行以来、多くの山好き・花好きの間で読み継がれてきたロングセラー。NHK衛星第2TVで放映された「NHK 花の百名山」、山と溪谷社刊行「花の百名山 登山ガイド」などを生み出すことになった、元祖である。 「あれらの山々にはどんな木が茂り、どんな水が流れ、どんな花々が咲いているのか」という思いで、生涯山に登り、花を愛しつづけた著者のひたむきさ、純粋さ、喜びが、文章の端々から伝わってくる名作が、活字を大きくして待望の復刊。 解説・平尾隆弘(初代担当者・神戸外国語大学客員教授)
-
-日本の剣豪を網羅した決定版! 塚原卜伝、伊藤一刀斎、上泉信綱、柳生十兵衛、荒木又右衛門、宮本武蔵、堀部安兵衛、坂本龍馬、土方歳三、沖田総司、山岡鉄舟、千葉周作……。 剣術の揺籃期である戦国時代、精神性を高めた江戸の泰平期、三大道場の出身者が鎬を削った幕末期、それぞれに時代に活躍した剣豪29人の出生から終焉までを描写しました。そのすさまじき太刀筋に似た人生は痛快無比。 時代劇ファンの基礎教養の書です。 【目次】 第一章 「剣術」の誕生と「戦国」 1 飯篠長威力斎(神道流) 2 諸岡一羽(神道流) 3 塚原卜伝(卜伝流) 4 斎藤伝鬼坊(天流) 5 富田勢源(富田流) 6 伊藤一刀斎(一刀流) 7 神子上典膳(小野派一刀流) 8 上泉信綱(新陰流) 9 神後宗治(新陰流) 10 疋田豊五郎(新陰流) 第二章 「泰平の世」の存在意義 11 柳生宗矩(柳生新陰流) 12 柳生兵庫(柳生新陰流) 13 柳生連也(柳生新陰流) 14 柳生十兵衛(柳生新陰流) 15 荒木又右衛門(中条流・神道流) 16 宮本武蔵(二天一流) 17 堀部安兵衛(直心影流) 第三章 「幕末維新」血風録 18 土方歳三(天然理心流) 19 坂本龍馬(北辰一刀流) 20 沖田総司(天然理心流) 21 近藤勇(天然理心流) 22 岡田以蔵(鏡新明智流) 23 山岡鉄舟(無刀流) 24 千葉周作(北辰一刀流) 25 武市半平太(鏡新明智流) 26 斎藤弥九郎(神道無念流) 27 島田虎之助(直心影流) 28 男谷精一郎(直心影流) 29 榊原鍵吉(直心影流男谷派)
-
4.3
-
-李白、杜甫、王維、杜牧、陶淵明、白楽天、文天祥……細川元首相が幼少の頃から親しんできた漢詩・漢文の名言名句を手がかりに、それらの縁の地を訪ねた。杜甫の「国破れて山河あり」の舞台となった長安では、唐の詩人たちが活躍した往時の都を偲び、陶淵明の「帰りなん いざ」に導かれ、名勝と謳われた廬山へ。蘇東坡が「人生夢の如し」と謳った古戦場・赤壁では、『三国志』の時代に思いを馳せる――。詩人に限らず、達磨や玄奘といった僧侶や、王羲之や八大山人のような書家や画家も細川氏が「詩心」を感じた人々として登場。中国全土を巡り、四十八話をつづった細川護熙流「中国歴史紀行集」。旅愁を誘う撮り下ろし写真や、筆者自ら旅の印象を描いた絵画や書もふんだんに収録。
-
4.4
-
4.0SNSで大反響! 多様性の時代の新エッセイ集 29歳で移り住んだニューヨーク。 言葉も、これまで培ったスキルも通じない日々。 そんな中、大切な人たちと繋がらせてくれたのは 心の底にしまい込んでいた自らの美意識だった。 「本音をインターネットに置いておいて、本当に良かった」―― 世界の諸問題への視点、生活への美意識。 総フォロワー数15万人超のSNSで、独自の視点が信頼と感動を呼ぶ 文章を発信し続ける著者のデビュー作。 noteで大反響を呼んだエッセイに書き下ろし6編を加えた 新世代エッセイ集。 解説・谷川嘉浩(哲学者)。 ※この電子書籍は2021年2月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
3.3知の巨人が語り尽くす、日本への刺激的処方箋 いつの間に、日本はこんなに生きづらい、貧しい国になってしまったのか? なぜ、こんなにデタラメな政治がまかり通る世の中になってしまったのか? その答え、実は「コモン」ですべて説明できるのです。 AIによる大量失業、富の一極集中、アンチ・グローバリズム、人口減少による高齢化と過疎化…… いよいよ限界を迎え、音を立てて軋んでいる資本主義。 その背景には、昔はどこにでもあったコモン(共有地)の喪失がある。 今こそ分断を超え、新しい共同幻想を立ちあげるときだ。 絶望の果てに光を見出す希望の書。 巻末に文庫版特別付録として、東京大学大学院准教授・斎藤幸平との対談「心地よい、新しいコモンについて語ろう」収録! 21世紀の新たな「囲い込み」を警戒せよ! そこには、ディストピアしかない──。 ・西部劇「シェーン」は「コモンの消失」という悲劇を描いていた ・「貧困は自己責任」と切り捨てる心理 ・「青年」も「旦那」も消え、子どもおじさん・おじいさんが出現 ・「一罰百戒」で委縮するテレビ局や大手メディア ・ディープ・フェイクの時代を生き抜くために ※この電子書籍は2020年11月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
-自分を厚く塗り固めていた蝋を、いま溶かしたい 祝70歳! 子育てを終え、電撃復帰から7年。 今明かされる、ちょっとミーハーで とてもナチュラルな“意外な素顔” 「連絡を取るようになって、ユーミンの家にはご主人の正隆さんがいたり、(井上)陽水さんとユーミンの手料理を食べたり。私とユーミンは前世でも姉妹、いや夫婦?(笑)」(麻美) 「麻美ちゃんは『待てる女』です。『待つ』のではなくて、『待てる』。当時は家電しかなかった。だから麻美ちゃんは、絶対、家にいた。いつでも田邊さんの電話に出られるようにね。だから『待てる女』。ちなみに私は『待てない女』(笑)」(ユーミン) 「私は子どもが欲しかった。彼がどういう人生を送りたいのかというより、そこは自分を通してしまった。最後のチャンスだった」「結婚して、何の心配もなく子育てに専念し、子どものことだけを考え生きた25 年間は私の宝物」「私の取り柄はミーハーなこと! 韓国語も習いたいし、タンゴアルゼンチーノも踊ってみたい」(麻美)――本文より 松任谷由実プロデュースの名曲「雨音はショパンの調べ」で鮮烈な印象を残し、「女が女に憧れる」(byユーミン)ロールモデルを作るも、1991年に突如芸能界を完全引退した伝説のミューズ、小林麻美。25年の沈黙を経て、極秘出産、結婚、復活の舞台裏、ユーミンとの再会を語り尽くす。TOKYO FMの名プロデューサー・作家による評伝。解説・酒井順子 【この電子書籍は、2020年3月に朝日新聞出版より刊行された『小林麻美 第二幕』の、文春文庫版を底本としています。文庫化にあたって改題・加筆・再編集しました。】
-
3.6
-
3.8情報がかけめぐる現代にあって大事なのは、歴史の縦軸・横軸にそって物事を大局的に見ることだろう。 その稀有なる視点を有するのが藤原正彦氏である。 著者は『文藝春秋』誌上において、骨太な論考を寄せてきた。対国政、対コロナウイルス、対中国、対韓国について。あるいは、毎月の「巻頭随筆」においては、時機に則した軽妙なエッセイとなる。 著者に一貫して通底しているのは、「教養」と「品格」と「ユーモア」ということになろう。その言葉は、いかにも日本人の肺腑にズシンと響く。270万部売れた『国家の品格』のエッセンスは不滅なのである。 それらを一冊にまとめて、通読できる贅沢な体験ができるのがこの作品ということになる。
-
4.0著者は言う。「質問は、大事です。質問は答えより大事です。質問がないと答えが見つからない。質問があって、答えが見つからないから、その問題を考え続けることができる」 キリスト教のことを考えると、いまさら聞けない質問・疑問がいくらでも出てくる。 例えば、「神さまはいるのか」「神さまは男か、女か」「人間は罪があるのか」「天使はどんな存在か」「地獄はどんなところか」。 なかなか聞けないことばかりだ。そんな質問・疑問に、著者は明解に答えていく。というよりも、キリスト教ではそれらをどう考えるかを明らかにしてくれる。 その解答をとおして、キリスト教の理解が深まることはもちろんだが、著者は、信仰するとはどういうことか、さらには人生や死とは何なのかに分け入っていく。というのは、キリスト教は、そうした人間が考えそうな問題について全部考えてきたことになっているからだ。 それは読めばスリリングな論考である一方で、人に思考を激しく強いるものでもある。目の前がパッと開けること、請け負いだ。
-
3.8本当の脅威は、「コロナ」でも「経済」でも「中国」でもない。 「日本型家族」だ! 核武装から皇室までを語り尽くすトッドの日本論! 磯田道史氏、本郷和人氏とも対談。 若者の生活を犠牲にして老人のコロナ死亡率を抑えた日本だが、社会の存続に重要なのは高齢者の死亡率より出生率だ。 「家族」が日本社会の基礎だが、「家族」の過剰な重視は「非婚化」「少子化」を招き、かえって「家族」を殺す。 (目次) 日本の読者へ――同盟は不可欠でも「米国の危うさ」に注意せよ I 老人支配と日本の危機 1 コロナで犠牲になったのは誰か 2 日本は核を持つべきだ 3 「日本人になりたい外国人」は受け入れよ II アングロサクソンのダイナミクス 4 トランプ以後の世界史を語ろう 5 それでも米国が世界史をリードする 6 それでも私はトランプ再選を望んでいた 7 それでもトランプは歴史的大統領だった III 「ドイツ帝国」と化したEU 8 ユーロが欧州のデモクラシーを破壊する 9 トッドが読む、ピケティ『21世紀の資本』 IV 「家族」という日本の病 10 「直系家族病」としての少子化(磯田道史氏との対談) 11 トッドが語る、日本の天皇・女性・歴史(本郷和人氏との対談)
-
4.0
-
3.0コンプレックスが文化を形成してきたのでは????という仮説を立て、これまで熟考されることのなかった「天パ」「背が低い」「下戸」など10のコンプレックスをとりあげ、数々の文献をひも解きながらカルチャーを考察する。劣等感を武器にして作品を生み出してきた表現者たちへのインタビューも収録。 文庫特典対談:ジェーン・スー×武田砂鉄「東京育ちコンプレックスが抱く“上京”への憧れ」 「天然パーマ」 インタビュー:ミュージシャン 有馬和樹(おとぎ話) 「下戸」 インタビュー:ミュージシャン 澤部渡(スカート) 「解雇」 インタビュー:ハイパー・メディア・フリーター 黒田勇樹 「一重」 インタビュー:アイドル 朝倉みずほ(BELLRING少女ハート) 「親が金持ち」 インタビュー:いきもの&クイズ好きミステリーハンター 篠原かをり 「セーラー服」 インタビュー:イラストレーター 中村佑介 「遅刻」 インタビュー:デザイナー・ソラミミスト 安齋肇 「実家暮らし」 インタビュー:現代美術家 泰平 「背が低い」 インタビュー:ミュージシャン 鈴木圭介(フラワーカンパニーズ) 「ハゲ」 インタビュー:臨床心理士 矢幡洋 ※この電子書籍は2017年8月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
-「男おひとりさま」の友情――22篇の人生 じきに百歳、老友二人の日常、回想、心情 旧制北野中学(北野高校)の同級生、ともに妻を亡くした91歳の二人が綴る日常、過去と現在の往還、淡い恋心。「男おひとり様」のリアルがここに。 目次 執筆のプロセス 土井荘平 真の英国紳士 徳岡孝夫 ひとり正月 土井荘平 人事の賽の目 徳岡孝夫 K女との電話 土井荘平 セカンドキャリア 徳岡孝夫 ハーレム・ノクターン 土井荘平 陽気な神父さん 徳岡孝夫 ステイホーム 土井荘平 気高い行為 徳岡孝夫 何れ菖蒲か杜若 土井荘平 夢の浮橋 土井荘平 政治家が死んだ時 徳岡孝夫 夢かうつつか 土井荘平 動機が行動を浄めるか 徳岡孝夫 白い人々の病院 徳岡孝夫 眼鏡が見つからない 土井荘平 政治家の表と裏 徳岡孝夫 「孤独ということ」 土井荘平 三島由紀夫のこと 徳岡孝夫 会者定離 土井荘平 ショウグンザクラ あとがきに代えて 徳岡孝夫
-
4.3『家康、江戸を建てる』『東京、はじまる』など、江戸・東京に深い造詣をみせる筆者が、東京の21の地域について過去と現在とを結び、東京の「謎」を解き明かす。 はじめに なぜ東京を「とうきょう」と読んではいけないのか 第一章 東京以前 第一回 なぜ源頼朝は橋のない隅田川を渡ったのか 第二回 なぜ大久保長安は青梅の山を掘ったのか 第三回 なぜ麹町は地図の聖地になったのか 第四回 なぜ浅草は東京の奈良なのか (新書のための書き下ろし) 第五回 なぜ勝海舟はあっさり江戸城を明け渡したのか 第二章 東京誕生(明治以後) 第六回 なぜ銀座は一時ベッドタウンになったか 第七回 なぜ三菱・岩崎弥太郎は巣鴨を買ったのか 第八回 なぜ早矢仕有的は丸善を日本橋にひらいたのか 第九回 なぜヱビスビールは目黒だったのか 第十回 なぜ「東京駅」は大正時代まで反対されたか 第十一回 なぜ野間清治は講談社を音羽に移したのか 第三章 関東大震災 第十二回 なぜ後藤新平は震災復興に失敗したのか(新書のための書き下ろし) 第十三回 なぜ日比谷は一等地の便利屋なのか 第十四回 なぜ新宿に紀伊國屋書店があるのか 第十五回 なぜ五島慶太は別荘地・渋谷に目をつけたのか 第十六回 なぜ堤康次郎は西武池袋線を買ったのか 第十七回 なぜ羽田には空港があるのか 第四章 戦後 第十八回 なぜトットちゃんには自由が丘がぴったりだったか 第十九回 なぜ寅さんは葛飾柴又に帰って来たのか 第二十回 なぜピカチュウは町田で生まれたのか 第二十一回 なぜ代々木の新国立競技場は案外おとなしいのか むすび なぜ江戸は首都になったのか
-
4.0
-
3.8
-
3.0
-
3.9芝居の達人、人生の達人──。2018年、惜しくも世を去った名女優・樹木希林が、生と死、演技、男と女について語ったことばの数々を収録。それはユーモアと洞察に満ちた、樹木流生き方のエッセンスです。 〇モノを持たない、買わないという生活は、いいですよ 〇人の人生に、人の命にどれだけ自分が多く添えるか 〇欲や執着があると、それが弱みになって、人がつけこみやすくなる 〇子供は飾りの材料にしないほうがいい 〇アンチエイジングというのもどうかと思います 〇人間でも一回、ダメになった人が好き 〇もう人生、上等じゃないって、いつも思っている 〇女は強くていいんです 〇つつましくて色っぽいというのが女の最高の色気 〇最期は娘に上出来! と言ってもらいたい 【目次】 はじめに 第1章 生きること 第2章 家族のこと 第3章 病のこと、カラダのこと 第4章 仕事のこと 第5章 女のこと、男のこと 第6章 出演作品のこと 喪主代理の挨拶 内田也哉子 樹木希林年譜 出典記事一覧
-
4.3糸井重里さんも絶賛。「おもしろいから読め。評論家よりOBより俺たちの声。」 今最もホットなモンスターブロガーによる痛快野球エッセイ! 誰が言ったか、プロ野球人気の凋落。 たしかに、地上波のテレビ局もバックレた。 時の流れは残酷だ。 俺たちのプロ野球、終わっちゃったのかなあ……。 バカヤローまだ始まっちゃいねえよ。 プロ野球は永久に終わらない連続ドラマだ。 ブログを始めた当初は化粧品会社デザイナーで野球界に何のコネもない素人。 それが人気ブロガーとなり、野球コラム企画で日本一に。 糸井重里×入江眞子×中溝康隆の座談会と、えのきどいちろうの解説も収録。 <目次から> 【読売ゴジラ遊戯】限りなく透明に近い「巨人軍・松井監督プラン」 【読売監督遊戯】高橋由伸「困った時のヨシノブさん」 【読売劇画遊戯】江川卓vs西本聖「いつも、お前が憎かった」 【読売移籍遊戯】今、山口俊にこれだけは伝えたいこと 【神宮狂乱遊戯】バレンティン新記録!「王貞治の55本塁打が過去になった日」 【天才渡米遊戯】大谷翔平「僕らが二刀流を支持する理由」 【読売絶対遊戯】古すぎて新しい男・菅野智之は過去の大エースを超えていく 【最優秀死亡遊戯】村田修一「超芸術的ゲッツーを打つ男」 【広島天才遊戯】巨人ファンが広島ファンに嫉妬した夜 【プロ野球未来遊戯】あの夜、横浜スタジアムで筒香嘉智のホームランを見た少年へ
-
4.0ベストセラー『生きる悪知恵 正しくないけど役に立つ60のヒント』につづく、漫画家・西原理恵子さんの人生相談の第二弾! タイトルが示す通り、今回は「家族の問題」についてサイバラ節が炸裂! 第1章「困った夫&妻」編では、こんな回答が。 相談「普段はいい人なのに、酒が入ると怒鳴りカラむダンナと離婚すべきか」 → 回答「子供に全部ちゃんと話して、夫のことは捨ててください」 相談「ブランド品を次々に買ってしまう妻の浪費癖を何とかしたい!」 → 「強硬手段に出るべきです。離婚届けにハンコを押して、『これ以上使ったら……』って、カードも取り上げましょう」 つづく第2章「子育て」編、第3章「家族もいろいろ」編、第4章「人生の選択」編、第5章「親兄弟が面倒くさい」編でも、悩める母親、娘、息子たちの相談へ、ときに親身に、ときに突き放して、サイバラ流の解決策を伝授します。 最終章はファン必見、西原さんと、息子さん、娘さんの座談会を収録。フツーじゃない家庭ならではの母子のやり取りもお楽しみいただけます。
-
3.8
-
4.3
-
4.3世界は牡蠣でつながっている! 美味しい話が満載。 気仙沼で牡蠣養殖業を営み、「森は海の恋人」をスローガンに植林運動を進める畠山さんは、エッセイの名手としても知られています。その氏が地元・宮城産の牡蠣を求めて世界オイスターロードを旅します。アメリカで辿った「日本の牡蠣養殖の父」の足跡、「森は海の恋人」のきっかけとなったフランスの旅路……。世界の牡蠣はこんなに日本とつながっていたのか、という驚きに満ちたエピソードが次々に飛び出します。また、牡蠣はなぜ日本でこんなに食べられているのか? おいしい牡蠣の食べ方って? などなど、牡蠣を食べるとき、ぐっとおいしくなるウンチクもたっぷり!
-
4.0自宅前で航空券を拾ったら、なぜかモデル事務所に拾われた。 フラれること13回、借金は膨らみ、オーディションには落ちてばかり。 それでも男は人との縁を繋ぎ、やがて本当の恋をし、大役を射止める。 そんな折、アメリカから一本の電話がかかってきて……。 俳優・松尾諭の笑いと涙のシンデレラ(!?)ストーリー。巻末に俳優・高橋一生による「松尾くんの自伝に寄せる文」掲載! 自称・本格派俳優の自伝“風”エッセイ ディズニープラスで2022年6月下旬配信開始予定 ドラマ化決定! 主演 仲野太賀 『拾われた男』を読んで、(中略) 彼に出会うずっと前から、拾われた男は 僕の友人だったのではないかと錯覚すらするほど、 益々気を許してしまう人になってしまった。 ――高橋一生(拾われた男の友人の役者) ※この電子書籍は2020年6月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
4.3
-
3.7映画化もされた大ヒット漫画『テルマエ・ロマエ』の作者が、古今東西の「いい男」たちの魅力を語り尽くす! 古代ローマ、ルネサンス、そして現代。先進的な文明や数々の芸術作品を生んだエネルギッシュな時代には、いつも知的好奇心あふれる熱き男たちがいました。ハドリアヌス、プリニウス、フェデリーコ2世(フリードリヒ2世)、ラファエロ、そしてスティーブ・ジョブズ、安部公房。共通するのは、既存のあり方に捉われず、新たな次元を切り拓いたボーダレスな男たちであるということです。彼らの魅力を語るうち浮かび上がるのは、負けず劣らずボーダレスに生きてきたヤマザキさん自身の半生。次なるルネサンスの種をまき、時代を切り拓くためのヒントが詰まったパワフルな一冊です。ヤマザキさん直筆イラストも多数収録!
-
4.0
-
4.3
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。