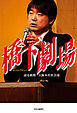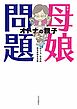ビジネス・実用 - 中央公論新社作品一覧
-
4.1
-
3.5子どもたちの「やる気スイッチ」がONになる! 人気テレビ番組で取りあげられて話題になった「ダンシング掃除」や、好奇心をくすぐる「内閣制度」など、斬新でユニークな指導法を打ち出し続け、いま最も脚光を浴びている小学校教師「ぬまっち」。アクティブ・ラーニングを先駆けた教育実践のノウハウと、その根底にある考え方を明かす。 (以下、本文より引用) 「えっ、そんな質問が出るの?」という意外性が生まれて、 立ち止まり、そのことについてみんなで考えてみる。 そんな新鮮な発見がたくさんある授業の方が、 ワクワクして楽しいし、学べることも多いと思うんです。 「全員平等」「機会均等」なんてお題目は、 ボクの教室にはありません。 火のつきやすいところから火をつけよう。 「やりたい」という気持ちをぐんぐん伸ばしていこう。 得意な力を、もっと発揮しよう。 目次 はじめに 第1章 やる気スイッチがONになる! (コラム)ぬまっちがメディアから注目された理由 第2章 ぬまっちのクラスでは、何が巻き起こっているの? 第3章 ボクが教師になった理由 第4章 ぬまっちにズバッと聞きたい17の疑問 第5章 ぬまっち語録
-
3.6ネットメディア興隆の昨今、どこでもスマホでニュースをチェック、というスタイルが当たり前に。しかし「WELQ」問題に象徴的だが、PV数や快適さを追及した結果、ネットには盗用や事実誤認を起こした「劣化」情報があふれ、もはや実害をもたらしかねないレベルに達した。その惨状を前に「ネットメディアの進化は終わった」と元新聞記者でヤフーのウェブメディア「THEPAGE」の奥村編集長は言う。氏は近年「ニュース」や「コンテンツ」という言葉の意味が変わり、「金儲け」の側面が強まったこと、多くが「コミュニケーション」というレベルにとどまっていることが問題と指摘する。それでは輪郭を失いつつある「ニュース」が広がることでどんな事態が起こるのか? 「ネコ動画」のような強いコンテンツにメディアは飲み込まれてしまうのか? 自らメディアを横断した著者が書く、新時代のメディア論刊行!
-
3.5
-
4.3はじめに 第1章◉脳とAI 脳から見た問題解決のメカニズム――酒井邦嘉 数理工学の方法論――合原一幸 次の一手を決めるプロセス――羽生善治 鼎 談――酒井邦嘉/合原一幸/羽生善治 人間とAIの棲み分けと融合 「詰み」とレーサーの感覚の共通点 AIは大局観を持てるか 文脈と共感 機能の理解が課題 解 説――自然と人間――酒井邦嘉 第2章◉AIは人間の脳を超えられるか 座談―酒井邦嘉/辻子美保子/鶴岡慶雅/福井直樹 これまでのAIブーム 自己組織化する脳とコンピュータの進歩 生成文法とAI 第二次AIブームと言語学 AIと言語学の乖離 人間が持つ生得的能力 脳のプリプログラム 自然言語処理研究の現状 学習するゲームソフト AIのクリエイティビティ シンギュラリティのその先 タAIを人間が手放さないこと 解説――想像力と創造力(酒井邦嘉) 第3章◉チョムスキーと脳科学 対 談――福井直樹/酒井邦嘉 神経科学と言語学の接点 チョムスキーの生い立ちと人となり チョムスキーと物理学 生成文法理論の誕生前夜 構造主義との決別 『統辞構造論』の思想的背景 反戦運動と生成意味論の時代 生成音韻論と理論物理学 「規則系としての文法」から原理とパラメータのアプローチへ 次の科学革命 解説――言語と思考(酒井邦嘉) おわりに
-
3.5
-
4.2
-
3.9
-
3.9
-
4.3
-
3.8
-
3.6
-
-
-
3.0
-
4.0
-
4.5発火、料理、消毒、肥料、発酵、製紙、染料、陶芸のほか香道や茶道にも道具や材料として、灰は日本人の生活を支えてきた。また童話の中には「灰かぶり姫(シンデレラ姫)」に似た話が世界にあることを見出す。食生活、社会、風俗、宗教、芸術に分け入り、身近な生活必需品=灰の科学と神秘性を解き明かす。灰の負のイメージを払拭する画期的な作品。 目次 Ⅰ 灰の生いたち 灰の誕生と埋火(うずみび)のこと 灰の成分と用途、そして灰屋のこと Ⅱ 灰と食 食べものと灰 酒と灰 醤油・味噌と木灰 海藻と灰 料理と灰汁(あく) Ⅲ 灰の恵み 和紙・織物と木灰 染料・染色と木灰 やきものと灰 Ⅳ 灰の効能 薬と灰 「秘術伝書」と灰 Ⅴ 灰の恐怖 火山と灰 死の灰 Ⅵ 灰と高貴 茶道・香道と木灰 習俗・宗教と灰 文学と灰
-
-
-
3.7
-
3.9
-
3.3断言と極論は実弾、民意が盾の戦闘マシーン橋下徹。彼は真の改革者か、それとも民衆を扇動するポピュリストなのか、その真実にせまる渾身のノンフィクション。
-
3.7
-
4.1二千六百年前、釈尊の教えから始まった仏教は、インドから中央アジア、中国、朝鮮、日本へ伝搬するうちに思想を変化させながら発達した。エリートのための仏教から、民衆のための仏教に変貌した過程を豊富な図版により解説する。 301ページ
-
4.0【本文より一部紹介】 「シニアこそ、デジタルと仲良くなりましょう」 そうお話しすると、「アナログ世代ですから無理です」「もう古稀も過ぎたし……」とおっしゃる方が大勢います。 おっしゃるとおり、私たちは生まれたときからデジタルのある世代とは正反対の“アナログ・ネイティブ”。私も米寿です。でもね、年齢は単なる数字だと思っています。 年を重ねると、どうしたって失うもののほうが多くなりますよね。視力が落ちる、髪が抜ける、想い出の場所がなくなる、親しい人が旅だってしまう。そんな喪失体験の多いシニアの強い味方こそ、デジタルです。 デジタルは不自由になった体の機能を助け、暮らしの不便さを補い、今まで知らなかった世界の扉を目の前に開いてくれます。 そう、シニアとデジタルは、とっても相性がよいのです。 人生100年時代ですから、何歳からのスタートでも十分に間に合います。「便利かもしれない」「ちょっとやってみようかな」で、いいんです。マーチャンなど、58歳でパソコン、81歳でプログラミングに挑戦したのですから。 人生で、今日という日が一番若いのです。自分自身を時代に合わせてアップデートするために、一歩を踏み出してみましょうよ。 シニアの皆さんや、デジタルにちょっぴり苦手意識のある方たちの悩みに寄り添いながら、私マーチャン流のデジタルの楽しみ方と、心の持ちようをお伝えします。 ご一緒にデジタルともっと仲良くなりましょう。 【目次より】 第1章 さあ、ご一緒にはじめましょう 第2章〈AIスピーカー、エクセルで描いた柄のブラウス……〉 マーチャン88歳、日々の暮らしにヒントがいっぱい 第3章 なぜ、テクノロジーが親友に? 第4章〈17のヒント集〉老いの苦手も、デジタルが補ってくれます 第5章〈お悩み相談〉小さなつまずき、一緒に解決しましょう 第6章 シニアはひとりじゃない。世代の強みを今こそいかそう
-
-噺家・八代目林家正蔵(後の彦六)が残した膨大な日記より、昭和一六年一二月一日から二〇年八月三一日の記述を摘録。清貧に徹した長屋での暮らしぶり、謹厳実直で「トンガリ」とあだ名された反骨精神がにじむ活き活きとした筆致に、蝶花楼馬楽時代の名人の素顔が窺える。戦時下における東京下町の日常を伝える貴重な一級資料でもある。 目 次 おぼろげな父の記憶 花柳衛彦 優しかった父 藤沢多加子 昭和十六年(十二月一日から) 昭和十七年 昭和十八年 昭和十九年 昭和二十年(八月三十一日まで) 巻末エッセイ 林家正雀 他人様を思って生きた師匠 戦い抜いた師匠 文庫版刊行に寄せて 編者解説 瀧口雅仁 馬楽時代の戦中日記をまとめて 正蔵が確かな目で見続けたもの 文庫版のためのあとがき 登場人物・登場日付索引
-
3.6
-
-南北朝の激しい抗争の余韻が尾を曳き、不安定な世相が続いた室町時代。 大和猿楽座に生まれた世阿弥は、父・観阿弥が洗練させた能を受け継ぎ、辛苦を重ねて大成させた。 逃れられない“血”の宿命を背負い、「能」とだけ向き合って芸の道を究め、後世に残る真の芸術の粋へ高めた世阿弥の感動の生涯を描く傑作歴史小説。〈解説〉澤田瞳子
-
3.8母が嫌いだった。わたしの脳内は母の固定観念で支配され、わたしはわたしが嫌いだった。母から逃げるように飛び出した東京、タバコとパチンコに溺れた日々、愛想もお金も無いわたしを雇ってくれた水商売&雀荘、ひと時の夢を見せてくれたオトコ、“笑い”で幸せを運んでくれた先輩たち、そして、自分より大事な存在となった娘……。自分のことが嫌いだったオンナ・青木さやかが、こじれた人生を一つ一つほどいていく。生きることの意味を追い求めるヒューマンストーリー。 母との確執やギャンブル依存症など、自身の経験を赤裸々に綴った「婦人公論.jp」で話題沸騰中の「47歳、おんな、今日のところは○○として」に、書籍だけのオリジナル原稿を加筆。
-
4.0
-
4.7読売新聞朝刊で連載中の好評連載「オトナの親子」の拡大版コミックエッセイ第2弾。 “毒親"の言葉も浸透しつつある昨今、長生きがもたらしたオトナの親子関係の確執はとても深く、多くの人が悩み苦しんでいます。前半では、1巻で登場した親子のその後を描いています。ついに実家を離れてひとり暮らしをはじめた娘、母に自身の心の悩みを打ち明けた娘、それぞれのジツボはどんな想いを抱え、どう娘と対峙するのが良いのか悩み、一方の娘たちも、ジツボとの向き合い方、程よい距離感を悩みながらも模索していきます。1巻同様、専門家の方々のアドバイスを含めた解説も掲載しています。後半では「著名人の実体験」と「発言小町に寄せられたリアルな声」を加え、より多彩な例を知っていただける内容となっています。本書が、親子関係を見つめ直し、少しでも心を軽くすることに役立てば幸いです。
-
3.7
-
3.82019年春、パワハラに関する法律を改正する法案が提出されました。こういった話題を聞くと、世の中では、「え、ふだんの会話もなくなっちゃうよ。もう女性とは話せないな」「もうなんでもハラスメント、ハラスメントって、嫌になっちゃうよね!」「広告や発言もすぐ炎上するし、言葉狩りじゃない?」「上司が萎縮して適切な指導ができない」などといった声があがります。本書は、そうした環境を是正し、個人のキャリアや企業の新しいリスクマネジメント、生産性が高く働きやすい職場づくりのために欠かせない「セクハラ、パワハラの意識と行動のアップデート」を促す本です。「働き方改革実現会議」の一員として、法改正などの議論の渦中にいる著者の実態調査と最新対策事情。今現在働く男女や、企業の法務担当として活躍する弁護士へのインタビュー、ITでできる最新ハラスメント対策など、“これからの働きやすい会社のかたち”を提案します。ハラスメント対策が問われる時代。雇用する側される側の正しい未来像とはなんなのでしょう。「どうすればハラスメントの加害者・被害者にならずに済むのか」を知りたい人必読の1冊です。 【本書構成】 第1章 ハラスメントを気にする男たち 第2章 女性から見たハラスメント 第3章 財務省セクハラ事件とは何だったのか? 第4章 企業の懲戒はどう決まるのか? 第5章 #MeToo以降のハラスメント対策最新事情 第6章 同質性のリスクは組織のリスク
-
4.2
-
3.7
-
3.9
-
4.1
-
3.0人はなぜ「生」に執着し「色」に執着するのか。幼少時代の誦読と棚経を回想、一休和尚や正眼国師(盤珪禅師)の訳や解釈を学び直し、原点から人間の性を見つめ直す。色と欲に煩悶した日々を顧み、生き身のありがたさ、女性は弥勒菩薩など独自の境地に辿り着く。愚かさを見すえ、人間の真実に迫る水上版「色即是空」。<解説>高橋孝次 「般若心経」全文 序 章 「まかはんにゃはらみたしんぎょう」 第一章 漢字「般若心経」にめぐりあう 第二章 正眼国師の『心経抄』と私 第三章 一切は「空」である 第四章 私版「色即是空」の世界 第五章 一休における「色即是空」の世界 第六章 死して百日紅や椿の花となる 第七章 不浄を美しいと思うときもある 第八章 六根・六塵の本体は無である 第九章 無明とは何か 第十章 四苦八苦を成敗するには 第十一章 のたうちまわって生きるしかない
-
4.2
-
4.0ハーフは皆「かわいい」「バイリンガル」「お金持ち」と思っているあなた。それは妄想です。実際には、不美人・日本語しか話せない・貧乏なハーフも大勢いる。日・独ハーフ(三十路、独身)が、日本社会でハーフが巻き込まれる「怒るに怒れない話」を多数挙げ、おもしろおかしく、時に真面目に「純ジャパ」との共生を考える。
-
3.6
-
3.6
-
4.0
-
4.0
-
3.0
-
4.0
-
4.0東京は、幕末史のテーマパークだ。道端や空き地にも、ときには堂々と、ときにはひっそりと過去のドラマが息づいている。桜田門、坂下門など頻発するテロの現場、新選組のふるさと、彰義隊の落武者にまつわる怪談……。本書はペリー来航から西南戦争までの四半世紀に繰り広げられた有名無名のさまざまな事件の跡をたどる、「足で読む幕末通史」である。巻末に幕末維新関係者千名の詳細な墓地所在地リストを付す。
-
3.7
-
3.8
-
-
-
5.0
-
-
-
3.8
-
3.8
-
4.2バレエはルネサンス期イタリアで誕生し、今なお進化を続けるダンスの一種だ。当初、王侯貴族が自ら踊り楽しんだが、舞台芸術へと転換。観客も貴族からブルジョワジー、市民へと拡大する。十九世紀の西欧とロシアで成熟し、世界へ広がった。ダ・ヴィンチ制作の舞台装置、ルイ十四世が舞った「太陽」役、チャイコフスキーの三大バレエ、シャネルやピカソが参加したバレエ・リュス、そして日本へ――六百年の歴史を通観する。
-
3.0
-
-
-
4.1バーの重い扉の向こうには、非日常の空間が待っている。そこは、酒だけを売っている場所ではない。客のひとりひとりが、バーテンダーと対面し、一期一会の時間を購い、空間に戯れる町の“秘境”である。そこには、シキタリもあれば、オキテもある。しかしそれらは、居心地をよくするものでこそあれ、がんじがらめの規則ではない。これから出かける人の背中をそっと押し、行き慣れた人をさらなる一軒へ向かわせる、体験的バー案内。
-
3.0好き嫌いがキッパリ分かれるパクチーの爆発的なブームとともに、 いま日本には第二のアジア飯ブームが到来している。 ガパオ、パッタイ、カオマンガイ……。 いつから日本人はこれほどまでにスパイスとハーブの香りの虜になったのか。 『Hanako』『きょうの料理』『オレンジページ』『dancyu』など時代を鮮やかに映しだしてきた雑誌や、アジアを舞台にした映画、小説、日本に急増する移民が広めた食文化を丹念に紐解きながら、日本人をとりこにしたパクチーとアジア飯の喜びの謎に迫る。 のびゆくアジア、どこか懐かしいアジアを愛し、旅し、食べ歩いている すべてのニッポンの女子に贈る。アジア飯の魅力の源泉をさぐる一冊。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 5匹の猫と暮らす、パグの「お茶目」。飼い主の漫画家・ひぐちにちほが、パグと猫たちとのゆかいな日常をお届けします。表情豊かで愛おしいお茶目の5年間をとらえた写真&エッセイ&イラスト集。 生後2ヵ月でひぐち家に来て、猫たちに囲まれて育ったお茶目は、自分を猫だと思っている様子。猫のようにジャンプしたがり、猫と遊んで、猫と寝る。飼い主が漫画の締め切りに追われると、お茶目も猫たちもくっついてきて、仕事がなかなか進まない! お茶目の散歩仲間は、フレンチブルドッグの「もー君」。春夏秋冬、のどかな風景の中で一緒に遊びます。桜満開の公園、色づいたイチョウ並木、真っ白な雪の中、いつでもずんずん歩くお茶目。キャベツやジャガイモの畑で大ハッスルしたりも。 大好きな梨やスイカを前にすると大きな目はさらに大きくまん丸に。飼い主に「待て」と言われると鼻をぷくぷくさせながら「よし」がかかるのを待つ姿もキュート。 子犬のころから元気いっぱいのお茶目と、ゆったりつきあう仲間たち。陽気で幸せな生活をお楽しみください。
-
-
-
4.0フランスが世界に誇る「花の都」パリ、そしてヴェルサイユ宮殿。これらを形作ったのは、ルイ十四世の治世に花開いた「グランド・デザイン」の思想だった。当時のフランスは、世界を席巻していたバロックに背を向け、徹底した計画志向の下でニュータウンを建設し、パリの街並みを整備し、ついにはヴェルサイユ宮殿を造営した。駆け引きに満ちた宮廷政治と、個性豊かな建築家たちの物語を通して、近代都市の源流に迫る。
-
4.0フランス革命直後からパリに陸続と生まれたガラス天井の通り抜けを、「パサージュ」という。オペラ座、パノラマ、グラン・ブールヴァール……時代ごとの街の名所に、パリ市民を導いてきた。夢と欲望が吹き抜けたパサージュの歴史は、パリ近代化の歴史でもある。現存する19のパサージュを、フォトグラファー鹿島直の写真で辿る新しいパリガイド。 【目次】 まえがきに代えて Ⅰ パサージュへ時間旅行の手引き パサージュの定義 パサージュガイド19の散歩路 01 ギャルリ・ヴェロ=ドダ 02 ギャルリ・ヴィヴィエンヌ 03 ギャルリ・コルベール 04 パサージュ・ショワズール 05 パサージュ・デ・パノラマ 06 パサージュ・ジュフロワ 07 パサージュ・ヴェルドー 08 パサージュ・デ・プランス 09 ギャルリ・ド・ラ・マドレーヌ 10 パサージュ・ピュトー 11 パサージュ・デュ・アーヴル 12 パサージュ・ヴァンドーム 13 パサージュ・デュ・グラン=セール 14 パサージュ・ブール・ラベ 15 パサージュ・デュ・ケール 16 パサージュ・デュ・ポンソー 17 パサージュ・デュ・プラド 18 パサージュ・ブラディ 19 アルカード・デ・シャン=ゼリゼ パサージュの歴史 Ⅱ パサージュ文学全集 失われたパサージュを求めて ギャルリ・ド・ボワ ギャルリ・ドルレアン パサージュ・ド・ロペラ(オペラ・パサージュ) パサージュ・デュ・ポン=ヌフ パサージュ・デュ・ソモン パサージュを読む パサージュ・デ・パノラマ パサージュ・ショワズール あとがきに代えて 文庫版のためのあとがき
-
4.2
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 佐々木常夫氏「聞くが8割、話すが2割和やかに勝利する組織を作る」、岡田康子氏「パワハラ命名者が教える職場のNG集」、菊地正憲氏のルポ「円滑な職場関係はどこで狂ってしまったのか」、ラグビーの中竹竜二氏、柔道の山口香氏、そして日本人初のNBAプレイヤー・田臥勇太氏による鼎談「“ド根性”監督では2020年東京五輪で勝てない」収録。
-
3.0
-
3.5
-
-
-
4.0貧乏なのに、紙幣の顔。生まれは裕福、晩年は借金三昧。いくら稼ぎ、いくら借り、何を買い、何を思ったのか?金銭事情で読み解く、日本初の女性職業作家の新しい姿。
-
3.9
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 (目次より) ●〔対談〕コロナ禍で3・11の反省は生かせたか 「権力行使という難問」に挑む民主国のリーダーたち 遠藤 乾×三浦瑠麗 ●〔対談〕カエサルの大局観、大久保利通の独裁力…… 古今東西の偉人に学ぶ危機突破の要諦 御厨 貴×本村凌二 ●「感染防止至上主義」の有権者が政権に求めるもの 世論調査に見るコロナ下の理想のリーダー像 遠藤晶久×三村憲弘×山﨑 新 ●ポスト工業社会と「賢い財政」 二重の危機における明日を切り拓く 神野直彦 ●文明危機の今こそグランドデザインを AIが示唆する「分散型」と超長期視点にみる「定常化」 広井良典 ●民意の把握と迅速な政策立案というジレンマ 熊本県知事は「緑の流域治水」を「球磨川モデル」になしうるか 今井亮佑 ●民主党政権の原発事故対応から学んだ政治家の役割 国家の危機に命を懸けるのは誰なのか 細野豪志
-
4.0
-
3.8
-
3.5
-
3.5
-
4.5日本人の美的世界・倫理的世界を善意な眼差しで概観しながらも、「慇懃と粗暴」「礼儀正しさとモラル破壊」「思慮深さと見栄っ張り」「同情心と冷淡」「慎み深さと思い上がり」といった相反する要素が両立する謎について、言語・風土・社会的要因から解明する。一九七〇年代にベストセラーとなった稀有な日本人論を初文庫化。
-
3.3
-
3.7世界が認める巨匠がおくる7つの幸福論。ネットが隆盛し、フェイクニュースが世界を覆う時代、何が虚構で何が真実か、その境界線は曖昧である。こういう時代だからこそ、与えられた情報をひとまず信じずに、自らの頭で考えることの重要さを著者は説く。幸せになるために成すべきこと、社会の中でポジションを得て生き抜く方法、現代日本が抱える問題についても論じた、押井哲学の集大成とも言える一冊。
-
4.1
-
4.1
-
4.4
-
4.5
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 (目次より) ●カギはプロの介護、世帯分離、人づきあい 気楽で悩みもなし おひとりさまの大往生 上野千鶴子 ●「人生の意味」の短い歴史 一人を生きるときに頭をもたげる問い 村山達也 ●独身の強みと他人と共にいること 僕が結婚しない理由 ヒロシ ●人生の終わりに向けて 終活は誰のためにするのか 木村由香 ●弔いの現場から見えるもの 超高齢社会の「孤独死」と葬儀を問う 佐藤信顕
-
-
-
3.5
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●〔対談〕膨張する与党、棄権する有権者…… 野党再生に足りないイズムと強さ 宇野重規×中北浩爾 ●1993年体制と「3・2・1の法則」 政治的選択肢の健全な拮抗のために 大井赤亥 ●〔対談〕いま、『資本論』をひもとく意味 資本主義が倒れるか、先に地球が潰れるか 斎藤幸平×佐藤 優 ●欧州の社会民主主義勢力が直面する課題 四つの圧力、二つのジレンマ 近藤康史 ●2000年代ラテンアメリカの政治潮流 「ピンクタイド」は今どこへ 宮地隆廣 ●平成世代が描く左翼像 エンパワーメントによる新しい連帯のかたち 小峰ひずみ
-
3.5卑弥呼はヤマト王権の初代大王、その王都は奈良盆地東南部の纒向(まきむく)にあった! 盟主不在の「倭国乱」ののち、3世紀初めの「卑弥呼共立」によって「新生倭国」=ヤマト王権は誕生した。考古学の成果と中国史書の精読から導き出された、この国の国家形成史の新しい枠組み。 ◆纒向遺跡はいつ出現し、どのような特徴をもった特別な遺跡なのか? 詳細に解説 ◆王権はのちに畿内と呼ばれる地域の勢力から誕生したのか? 新しいストーリーを提示 ◆卑弥呼はそもそも「邪馬台国の女王」だったのか? 彼女はどこに眠っているのか? 箸墓古墳の被葬者はいったい誰なのか? 最新の研究成果にもとづいて推理 本書の構成(目次) 第一章 纒向遺跡論/第二章 日本国家の起源を求めて/第三章 王権誕生への道/第四章 王権の系譜と継承/第五章 卑弥呼共立事情――私の邪馬台国論/第六章 卑弥呼とその後
-
-今日という日はいつも新しくこれからの人生の始まり。でも、けっして孤独ではありません。まわりの人々に支えられて、自宅の小さな菜園で野菜作りを楽しむ。しかも、新聞や雑誌の特集を持ち、社会的な意義を持つ会合には出席するという行動力を維持している生き方には、中高年読者に勇気を与えてくれています。本書におさめられている一編一編のエッセイによって、毎日の小さな喜びを大事にする生き方が、いかに心を明るく前向きにし、周囲にも良い感化を及ぼすかも納得できます。いま望むのは、悔いの残らない毎日を過ごすこと。病気や病院とどうつきあっていくか?日々大事にしていることは? 101歳の吉沢さんが教えてくれた人生の知恵。
-
-
-
4.0
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。















![ノーベル賞の100年 自然科学三賞でたどる科学史 [増補版]](https://res.booklive.jp/245844/001/thumbnail/S.jpg)