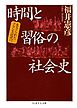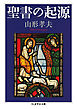学術・語学 - 筑摩書房作品一覧
-
4.6
-
3.7
-
3.7
-
-
-
4.6
-
-
-
-
-
4.0建築は、一見すると哲学とも思想とも関係のない即物的なもので、定義など簡単にできそうである。ところが、建築ほど定義しづらいものはない――。20世紀末、構築的なものへの批判に晒され混乱をきわめた「建築とは何か」という問いに、著者は建築史と思想史を縒り合わせながら、真正面から立ち向かう。一本の柱が原野に立てられた太古から、ゴシック、古典主義、ポストモダニズム建築まで。建築様式の歴史的変遷の背後にはどのような思想があったのか。本書は、ひとつひとつ思考を重ねつつ、歴史的視座を与えようとした意欲的主著である。著者自身による自著解説を付した、待望の文庫版。
-
3.0
-
4.5
-
4.0
-
4.0
-
3.3
-
5.0
-
4.0「理想」という語は、明治の時代、プラトンの「イデア」の訳語として造られ、定着した。そしてプラトンの最高傑作『ポリテイア』(『国家』)が『理想国』の標題で出版され、近代国家建設をめざす多くの日本人の希望の拠りどころとなる。だが、新たな理想社会を創らんとするその熱情は、やがて全体主義に利用される運命を辿った――。かくも激しく人々の魂を突き動かしたプラトンの理想主義哲学とは、果たしていかなるものか。『ポリテイア』の核心を読み解くことで、哲学という営みが切りひらく最良の地平を描き出す。初学者への案内として「プラトン『ポリテイア』を読むために」を付した決定版。
-
5.0
-
4.5日本人に特有の「言えそうで言えない」英語表現があるようだが、なぜだろうか? ビジネスを中心に日常的な場面やSNSで使われそうな会話の中で、より適切な英語表現はどれになるかを、クイズ形式で学んでいく。文法的な誤りや単語の使い方、さらに文化的背景や物事の捉え方の違いを解説で読みながら、日本語と英語の発想の違いに気付くことで、よりシンプルで伝わる英語表現を身につけていきたい。
-
5.0
-
4.0
-
-親鸞が、もっとも信頼する人びとや、最愛の弟子たちと交わした、胸を打つ手紙の集成。その現存する手紙全42通の現代語訳と解説で親鸞の心中に迫る。最新の親鸞研究の成果にもとづき、全書簡を書かれた順に構成。これにより、子息善鸞の義絶事件などの人間的苦悩と、煩悩具足の凡夫であることの自覚から、ひたすら阿弥陀仏の本願(専修念仏)に帰命する姿が、より鮮明に立ち現れる。それは、仏教を貴族や支配階級のもとから解放し、真に民衆のものとして、多くの衆生を獨世から救おうとする姿にほかならない。現代にも脈々と生きる、親鸞の力強い実践思想へのこのうえない入門書。
-
-親鸞はいかなる人物か。その思想はどのような今日的意義をもっているのか。親鸞に親しむほどに既成教団を否定せざるをえず、浄土真宗の末寺に生まれながらあえて寺院を離れた著者が、一市民として全存在をかけて親鸞の求道に分け入る。自己の無力を知り弥陀の本願に依ることでどのような者も救われるという「絶対他力」の教えは、ケガレを忌み、占い、苦行や作善、祖先崇拝に救いを求めた中世人に、いかばかりの衝撃をもたらしたか。中世の「聖なる世界」の構造をトータルに把握し、そのなかで親鸞が切り開いた「絶対他力」という「普遍への回路」を明らかにする、渾身の著。
-
3.3
-
3.8
-
-
-
4.0
-
-
-
4.0
-
3.0
-
5.0精神の病態を一時的な疾患としてではなく人生全体の示す歴史的な歩みとして位置づけ、独自の思想を重ねてきた著者の代表的論考のかずかず。自己と他者の「あいだ」の病態として捉えられてきた分裂病を、「時間」の病態として、現象学的な思索を展開する。とりわけ鬱病者の“あとのまつり”的体制に対し、分裂病者が“前夜祭”的な時間体制をもつという新しい構図は世界的に大きな波紋を広げた。他者や世界との「あいだ」、自己自身との「あいだ」の歴史性における患者の生のあり方を追究した本書は、精神病理学と哲学を自由に横断する独創的な学問的達成であるといえよう。
-
-従来の東京裁判論は、主に政治・外交史を基調とし、また「日本無罪論」で知られるインド代表判事パルやオランダ代表判事レーリンクによる個別反対意見をもっぱら話題とし、本来の東京判決での多数意見を軽視してきた。本書は、東京裁判の事実認定がいかになされ、責任がどう問われたのかを実証的に解明。法廷で適用された責任論や、各被告人に対する判定の根拠を体系的に分析する。判決七五周年に向けて、東京裁判を国際刑事裁判史にどう位置づけて評価すべきか、その功績と問題点とを明らかにする。【目次】まえがき/第一章 裁判の歴史的文脈と枠組み/第二章 平和に対する犯罪の争点/第三章 日本政府組織論/第四章 戦争犯罪の争点/第五章 「東京判決」――多数派判事による判決/終章 今日の国際刑事裁判にみる責任論
-
-
-
4.0
-
4.3
-
4.0戦争は、誰によっておこされ、どのように展開したか――。本書では、1931年の柳条湖事件の謀略に始まり、45年ポツダム宣言受諾と降伏文書調印によって終わった一連の戦争を「十五年戦争」と呼び、その曲折に満ちた過程と全体像を克明に描く。アジア覇権主義を掲げる日本軍部と対米英協調路線の宮中グループとのせめぎ合い、マスコミの報道によって国内で急速に高まる排外主義、アジア太平洋戦争へと向かう御前会議のありよう………。満州事変、華北分離、日中戦争、アジア太平洋戦争で構成される各部には年表、関係地図を付し、制度や組織の変遷、人事の系統図なども適宜配した。長年読み継がれてきた画期的通史。
-
3.0十字軍と言えば、もっぱら運動としての面が注目され、十字軍士たちが各地に建設した諸国家、すなわち十字軍国家の全体像が語られることはなかった。だが、1098年のエデッサ伯国建国から、1798年のナポレオンによるマルタ島攻撃までの実に700年にもわたり十字軍国家は存続していた。ローマ教会、ビザンツ帝国、神聖ローマ皇帝、イスラーム勢力や地中海の諸商業都市、傭兵団、さらには来襲するモンゴル勢など、多種多様な勢力が複雑に絡み合う興亡の歴史を、第一人者が活写する。 【目次】序 十字軍国家とは何か/I ラテン・シリア/第1章 ラテン・シリアの誕生(1097-1099年)/第2章 ラテン・シリアの形成(1098-1118年)/第3章 ラテン・シリアの成長(1118-1146年)/第4章 ラテン・シリアの発展と分断(1146-1192年)/第5章 ラテン・シリアの回復と再分断(1192-1243年)/第6章 ラテン・シリアの混乱と滅亡(1243-1291年)/II キプロス王国/第7章 キプロス王国の形成と発展(1191-1369年)/第8章 キプロス王国の混乱と消滅(1369-1489年)/補章1 ヴェネツィア領キプロス(1489-1573年)/補章2 キリキアのアルメニア王国(1198-1375年)/III ラテン・ギリシア/第9章 ラテン帝国(1204-1261年)/第10章 フランク人支配下のモレア(1)(1204-1311年)/第11章 フランク人支配下のモレア(2)(1311-1460年)/補章3 カタルーニャ傭兵団とアッチャイオーリ家(1311-1462年)/IV 騎士修道会国家/第12章 ドイツ騎士修道会国家(1225-1561年)/第13章 ロドス期の聖ヨハネ修道会国家(1310-1523年)/第14章 マルタ期の聖ヨハネ修道会国家(1523-1798年)/あとがき/主要参考文献/十字軍国家支配者一覧
-
4.6
-
3.5
-
4.4「重力」に似たものから、どうして免れればよいのか? ――ただ「恩寵」によって、である。「恩寵は満たすものである。だが、恩寵をむかえ入れる真空のあるところにしか入っていけない」「そのまえに、すべてをもぎ取られることが必要である。何かしら絶望的なことが生じなければならない」。真空状態にまで、すべてをはぎとられて神を待つ。苛烈な自己無化の意思に貫かれた独自の思索と、自らに妥協をゆるさぬ実践行為で知られる著者が第二次大戦下に流浪の地で書きとめた断想集。歿後に刊行され、世界に大反響を巻き起こした処女作。
-
5.0
-
3.0
-
-
-
4.8ヴィクトリア女王、エリザベス2世、そしてチャールズ3世まで、イギリスの歴代君主に仕えた君主秘書官たち。多くは君主の青年時代からの側近であった彼らは、国内外の様々な問題を君主に報告し、時に助言も行い、有事に際しては公正中立な立場から君主と政権をつなぐ重要な架け橋でもあった。本書では、彼らが登場した歴史的経緯を踏まえつつ、手紙や日記などの史料を交えて秘書官と君主との物語を描く。貴族政治から大衆民主政治への転換、二度の大戦、王室のスキャンダル……。激動の時代を経てなぜ今も君主制が存続するか。その謎に迫るユニークなイギリス近現代政治史。
-
3.8
-
3.7
-
3.0古代の人々の生活や信仰、祭りの中から神社は各地で発生した。では彼らはどのような神々を祀ってきたのだろうか。明治以降の国家神道の影響を受ける以前の“祭祀の原像”を求めて、主要な神社の成り立ちや特徴を解説する。取り上げられる神社は大神(おおみわ)神社、伊勢神宮、宗像大社、住吉大社、石上(いそのかみ)神宮、鹿島神宮、香取神宮などで、それらは大和王権の国家運営が進むに従い、それぞれに役割を付与され性格づけられて、律令体制下の神社制度として確立していくことになった。日本古代史における神社の起源と変遷をていねいに辿り、その存在意義を考察する。
-
4.2
-
5.0事物が存在するということは、それが知覚されているということである──。ジョン・ロックの経験論哲学の批判的継承者たるジョージ・バークリー(1685-1753)は本書『人知原理論』において、こう断言する。それは裏返せば、知覚されないものは存在しない、つまり私たちの心から切り離された「物質」なるものなど存在しない、ということだ。様々な批判にさらされながらも、ヒュームやカント、ドイツ観念論など後の哲学思想に多大な影響を与えたバークリーの思想とはいかなるものか。その透徹した論理にひめられた核心が、平明このうえない訳文と懇切丁寧な注釈により明らかになる。主著、待望の新訳。
-
-
-
3.7
-
3.8数学基礎論──それは20世紀とともに始まった、新しい数学の分野である。その黎明期には、カントルやラッセルによって相次いで見出された集合論のパラドックス、そして、ゲーデルの不完全性定理など、数学の根幹を揺るがす発見が続いた。しかし数学基礎論は、決して数学の息の根を止めてしまったのではない。「ミレニアム懸賞問題」として知られるP=NP問題(P≠NP予想)やファジー論理、さらには人工知能との関わりなど、数学の最先端を切り開く分野でもあるのだ。日本を代表する数学基礎論の大家がその歴史、および現代的なトピックについて平易に解説した入門書。
-
4.0
-
3.5「公式は覚えるだけでいい」「女子は数学が苦手でも構わない」など、数学嫌いを生む言葉はあふれています。でも本当は、それぞれのペースで楽しむもののはず! 70歳を超えた数学者が贈る、数学の本当の面白さ。 *全国の「富士見町」から本当に富士山は見えるのか!? *あみだくじの結果を自由自在にあやつる仕組み!? *1000mlの牛乳パックの体積は955平方cmしかない!? ……etc. 【目次】まえがき/第1章 数学が嫌いになるとき/第2章 数学が好きになるとき/第3章 「仕組み」から興味をもつ/第4章 「図形」から興味をもつ/第5章 「変化」から興味をもつ/第6章 「データや確率」から興味をもつ/第7章 数学教育の歴史とこれからの未来/あとがき
-
3.0
-
4.4論文・レポートの執筆、教科書・プリントの作成など、数式や数学用語を用いた文章を書く機会は案外多い。しかし、数式の表す内容にあいまいさがないからといって、その文章自体がわかりやすいとは限らない。“読者のことを考える”という原則に立って書くなら、もっと明解でもっとよく伝わる文章になるかもしれない。『数学ガール』シリーズを執筆し、文章の読みやすさに定評のある著者が自らの経験で培ったノウハウを伝授。本書「基礎編」では文章の順序、数式・命題の書き方、わかりやすい例の作り方、目次・索引の作り方などについて、豊富な具体例をもとに解説する。
-
4.4
-
3.5
-
5.0
-
3.0
-
-なにかにつけて「説明責任」が問われる昨今、では翻訳については? 「意味わかんない」「へんな日本語!」「なんでこんな訳になるの?」と読者が思っても、翻訳者は「原文がそうなんだから」とまるで他人事、説明責任などどこ吹く風、だった。歯に衣着せずに欠陥翻訳と戦ってきた闘士・ベック先生、そこでまたも立ち上がった。この訳のどこがダメか、どうすればスッキリいい訳になるのか、懇切に説明。実践篇では中学レベルから上級まで、レベルに応じてさまざまなタイプの課題文を出題、悪訳と良訳を並べ、原文理解と翻訳のポイントを具体的にレクチャーする。
-
4.5
-
3.7キリスト教の正典、「聖書」──その奥にひそむのは、古代オリエントやギリシアのあらゆる神々の姿が織り込まれ、ユダヤ民族悠久の歴史が幾重にも積み重ねられた、多文化的な空間であった。異教のバァール神話の死と復活のドラマ。ギリシア神話のアドニスとアフロディテの出会いと別れの物語。エーゲ海であがめられた治療の神アスクレピオス。治癒神イエス登場の背後には、これら異端の神々の系譜を透かし見ることができる。従来の宗教学的解釈では光をあてられることのなかったこの歴史を、宗教人類学の視線から掘り起こし、のちの聖書の読みを決定づけた古典的名著。
-
3.5感覚的経験という最も身近な段階から、数知れぬ弁証法的過程を経て、最高次の「絶対知」へと至るまで──。精神のこの遍歴を壮大なスケールで描き出し、哲学史上、この上なく難解かつ極めて重要な書物として、不動の地位を築いてきた『精神現象学』。我が国でも数多くの翻訳がなされてきたが、本書は、流麗ながら、かつてない平明な訳文により、ヘーゲルの晦渋な世界へと読者をやさしく誘う。同時に、主要な版すべてを照合しつつ訳出された本書は、それら四つの原典との頁対応も示し、原文を参照する一助となす。今後のヘーゲル読解に必携の画期的翻訳、文庫オリジナルでついに刊行。【※本電子書籍版には、紙書籍版本文の上欄、下欄に付した4つの原典(グロックナー版全集第二巻、ホフマイスター版、ズールカンプ版全集第三巻および大全集版〔アカデミー版〕)とのページ対応は含まれません。】
-
-20世紀フランスを代表する思想家モーリス・メルロ=ポンティ(1908-61)が死の前年にまとめた論集『シーニュ』。同書には、言語学、絵画論、人類学への言及や、フッサール論、ベルクソン論、マキアヴェッリ論など、おもに中期から晩年にかけて執筆された多彩な論考が収録されており、その多中心的な思想を一望するうえで欠かせない一冊となっている。本書ではそのなかから、ニザンとサルトルとの関わりが美しく綴られた序文のほか、「間接的言語と沈黙の声」「哲学者とその影」など重要論考6本をセレクトし、新訳。清新な訳文と懇切丁寧な注釈・解説により、その真価が明らかとなる。
-
-仏教は死後の救済のためのものだと思われたり、思想として知的に享受するものだと理解されることが多い。しかしそれは誤りだ。仏教はこの世を生きるための教えであり、その教えは念仏などの「行」を行うことで初めて意味を持つ。異国アメリカに仏教を広めた京極逸蔵は、仏教国でありながら仏教が根付かない日本に向け、彼の地から一つの提案をした。それが本書で説かれる「六波羅蜜」の実践だ。六波羅蜜は仏教徒の倫理規範というだけでなく、それを実践することが宗教的な目覚めへの近道ともなるからだ。専門用語に丁寧な説明をルビで付した、心底わかる仏教入門。