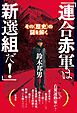右翼作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 週刊紙や議事録などを駆使して、自由主義神学者トレルチの思想に出会い、彼の思想が、どのような歴史的な背景の中で深められていったかを考察する論文集。彼の著作や発言の深意を時代の中で浮彫りにし、その全体像を初めて描く。 目次 略記号 序論 研究史と本書のねらい 第一部 トレルチの神学的課題 第一章 教授資格請求論文(一八九一) 第二章 自然主義との対決 ヘッケル『世界の謎』(一八九九)を中心に 第三章 近代の歴史的思考と神学 第二部 ヴィルヘルム二世時代の社会・学校・教会とトレルチ 第一章 社会問題(一八九〇─一九〇四) 第二章 学校と教会(一九〇四─七) 第三章 教理論争(一九〇七─一一) 伝統的信条と近代 第三部 トレルチと第一次世界大戦 トラウプとの対比 第一章 「城内平和」と両極化の兆し(一九一四─一六) 第二章 「祖国党」と「自由と祖国のための国民同盟」(一九一七─一八) 第四部 ヴァイマル共和国期のトレルチ 革命と反革命 第一章 プロイセン革命政権の学校令(一九一八)とその波紋 第二章 ドレスデン教会大会(一九一九) 福音主義教会の再編成と保守主義 第三章 「学問の革命」 シュペングラー『西洋の没落』をめぐって(一九一九─二二) 第四章 右翼急進主義(一九二〇─二二) カップ一揆からラーテナウ暗殺事件へ 結び あとがき 註 参考文献 独文概要 独文目次 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 佐藤 真一 1948年生まれ。西洋史家。国立音大名誉教授。早稲田大学文学部史学科卒業、同大学院史学研究科修了。文学博士。専門は、ドイツ近代史。 著書に、『教養としてのバッハ』(共著)『ヨーロッパ史学史 探究の軌跡』 『トレルチとその時代』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 哲学的神学を作り上げるために、啓示と理性、神学と哲学、主観と客観を超える新しい「哲学的神学」を提唱する重要な作品。 【目次より】 序説 第一部 神学の閉鎖性と非閉鎖性 第一章 近代神学の閉鎖性 古い史的イエスの探究 一 合理主義 二 古自由主義神学 三 新自由主義神学 四 歴史理解について 第二章 弁証法神学の閉鎖性 一 カール・バルト 二 ポール・ティリッヒ 三 ルドルフ・ブルトマン 第三章 非閉鎖的キリスト理解の試み 新しい史的イエスの探究 一 新しい史的イエス探究への右翼的接近と左翼的接近 二 ブルトマン後時代の神学者たち (イ) エルンスト・ケーゼマン (ロ) エルンスト・フックス (ハ) ギュンター・ボルンカム (ニ) ヘルベルト・ブラウン (ホ) ハンス・コンツェルマン (ヘ) J・M・ロビンソン (ト) ゲルハルト・エーベリンク (ト) 八木誠一 三 批判に対するブルトマンの答え 第二部 解釈学的神学 第四章 解釈学と神学 一 下から上への解釈学 シュライエルマッハー、ディルタイ、ブルトマン 二 上から下への解釈学 前期のハイデッガー、バルト、パンネンベルク 三 出来事としての解釈学 ハイデッガーの言葉理解 一 前期のハイデッガーに於ける言葉 二 ハイデッガーの転回 三 後期のハイデッガーに於ける言葉 (イ) 存在と解釈学 (ロ) 存在の呼び声としての言葉 (ハ) 非本来的言葉と言葉の体験 第五章 解釈学的キリスト論 一 言葉の出来事としてのイエスの譬え 一 イエスの信仰と言葉の出来事 (イ) 言葉の出来事とは何か (ロ) イエスと言葉の出来事 (ハ) ブルトマンと言葉の出来事 二 イエスの譬え (イ) 譬えの文体論的分析 (ロ) 譬えの呼びかけ 二 非閉鎖的キリスト論 一 イエスとキリスト 二 イエスと「私自身」 第六章 解釈学的神学と神 一 問題の所在 二 方法論 存在と神 三 種々の試み 四 神と無 結語 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小田垣 雅也 1929年生まれ。青山学院大学、ドルー大学卒。日本基督教団補教師、国立音楽大学元教授。哲学博士。著書に『解釈学的神学』『知られざる神に』『哲学的神学』『現代思想の中の神』『神学散歩』『ロマンティシズムと現代神学』『四季のパンセ』、学術文庫に『現代のキリスト教』など多数。訳書に『神への誠実』『文化史の中のイエス』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 <愛の宗教>であるキリスト教が大きな影響力をもっていたナチス支配下のドイツにおいて,なぜ,想像を絶する「ユダヤ人大量虐殺」,「障害者安楽死計画」,「侵略戦争」が遂行されえたのだろうか.本書は「政治と宗教」,「戦争批判と平和の創造」,「人間の尊厳」という問題意識を根底に据え,キリスト教会とナチス政権の複雑な関係を解明し,<第三帝国>崩壊後の「ドイツ教会闘争」の総括、「シュトゥットガルト罪責宣言」の成立過程を鮮やかに描き出した渾身の書。 【目次より】 まえがき 第一章 独裁国家と教会 ナチス政権初期の福音主義教会 一 ドイツ近現代史とキリスト教会 二 ヒトラーの政権掌握とナチス教会政策 三 教会闘争のはじまりと告白教会の形成 四 告白教会のヒトラーあて建白書 五 教会闘争と抵抗の問題 補遺1 マルティン・ニーメラー 右翼民族主義から実践的平和主義へ 補遺2 神学の諸潮流と支持政党 創造秩序の神学・自由主義神学・弁証法神学 第二章 ナチスのユダヤ人迫害とプロテスタント教会 はじめに ヒトラーの反ユダヤ主義 一 ナチスの政権掌握とユダヤ人迫害の開始 二 外国教会からの抗議 三 ユダヤ人問題に対するプロテスタント教会の基本姿勢 四 ナチス政権初期のユダヤ人迫害に対するプロテスタント教会の対応 五 ディートリヒ・ボンヘッファーとユダヤ人問題 六 アーリア条項の導入問題 七 「水晶の夜」とプロテスタント教会 八 グリューバー事務所のユダヤ人救援活動 九 古プロイセン合同告白教会の抗議表明 おわりに プロテスタント教会の光と影 第三章 ナチス安楽死作戦と内国伝道 ドイツ・キリスト教社会福祉の試練 はじめに 一 内国伝道の歴史 二 「生きるに値しない生命」の抹殺構想と内国伝道 三 ナチス安楽死作戦と内国伝道 むすびにかえて 第四章 テオフィール・ヴルム監督の抵抗 戦時下ドイツ教会闘争の一齣 はじめに 一 テオフィール・ヴルムのプロフィール 二 ナチ「安楽死作戦」との闘い 三 ユダヤ人迫害に対する抗議 おわりに 第五章 戦争末期の古プロイセン合同告白教会 序 ドイツ教会闘争と古プロイセン合同告白教会 一 シュレジエン教区告白会議 二 ブレスラウ告白会議 三 バルメン宣言一〇周年声明 おわりに 第六章 シュトゥットガルト罪責宣言への道 ドイツ教会闘争の終幕 はじめに 一 シュトゥットガルト罪責宣言の前史 二 シュトゥットガルト罪責宣言の成立 三 シュトゥットガルト罪責宣言の意義 むすびにかえて 補遺 ドイツで体験した教会生活 ボーフムの福音ルター教会 総括 あとがき ドイツ福音主義領邦教会地図 年表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 河島 幸夫 1942年生まれ。政治学者、西南学院大学名誉教授。東北大学法学部卒業後、神戸大学大学院で学ぶ。博士(法学)。専門は、ドイツ政治、戦争と平和。 著書に、『戦争・ナチズム・教会』『政治と信仰の間で』『ナチスと教会』など、 訳書に、W・フーバー/H・E・テート『人権の思想』D・ゼンクハース『ヨーロッパ2000年』などがある。
-
5.0保守的・愛国的な信条を背景に、その言動でしばしば他者を排撃する「ネット右派」。彼らはどのように生まれ、いかに日本社会を侵食していったのか。その真の意図とは何だったのか。 前史にあたる1990年代の雑誌論壇と草創期のネット論壇、55年体制の崩壊から現政権の成立までの政治状況、マンガ・アニメや「2ちゃんねる」などの文化状況、歴史教科書問題や外国人労働者問題、日本会議・在特会・極右組織などの団体の動向――。 日本社会に全面展開するネット右派の2000年代までを、嫌韓・反リベラル市民・歴史修正主義・排外主義・反マスメディアという5つのアジェンダ(論題)と、サブカル保守・バックラッシュ保守・ネオナチ極右・ビジネス保守という4つのクラスタ(担い手)からあざやかに分析する。 圧巻の情報量で「ネット右派の現代史」と「平成のアンダーグラウンド」を描き出す「ネット/右翼」研究の決定版。
-
-謎の京都皇統の舎人がもたらした極秘情報! 現代史の伏流にある世界を動かす正体とは? 帳に包まれた秘所に踏み入り禁を破って公開する ・京都皇統による秘密の伝授 ・『高松宮日記』をめぐる有象無象の策謀 ・ハープ(HAARP)の威力を知る皇室の情報力 ・石井紘基議員の刺殺事件の謎 ・不透明な総裁人事の日銀を蝕む満州人脈の亡霊 ・自衛隊を七面鳥にする自民党と公明党の犯罪 ・宮内庁と外務省の皇室イジメと小泉内閣の対米盲従の悲劇 ・異常気象の謎とカミオカンデの爆裂 ・満蒙を源流にする右翼の動きと大阿闍梨の持つ影響力の源泉 ※本書は同名書籍の電子版『皇室の秘密を食い荒らしたゾンビ政体』に序文、付録などを加え、加筆した書籍版です。
-
-なぜ日本人は、あのバカげたとしかいいようがない戦争を行ったのか。 日本が大破局への道を歩き始めた昭和戦前期、日本の歴史の大転換を中心的に動かしたのは、天皇という存在だった。 その大転換が起きた主たる舞台は東大だった。 天皇イデオロギーと反天皇イデオロギーとの相克が最も激しく起きた舞台も東大だった。 「東大という覗き窓」を通して、近代国家成立の前史から、大日本帝国の終わりまでを見渡した著者、畢生の大作が一冊に! <主な内容> 東大は勝海舟が作った/慶応は東大より偉かった/早大の自立精神、東大の点数主義/「不敬事件」内村鑑三を脅した一高生/日露開戦を煽った七博士/元白虎隊総長・山川健次郎の奔走/東大経済は一橋にかなわない/大逆事件と森戸辰男/大正デモクラシーの旗手・吉野作造/“右翼イデオローグ”上杉慎吉と大物元老/東大新右翼のホープ・岸信介/新人会きっての武闘派・田中清玄/河上肇とスパイM/血盟団と安岡正篤/血盟団事件 幻の“紀元節テロ計画”/共産党「赤化運動」激化と「一人一殺」/日本中を右傾化させた五・一五事件と神兵隊事件/狂信右翼・蓑田胸喜と滝川事件/美濃部達吉、統帥権干犯問題を撃つ/ゾルゲ・昭和天皇・平沼騏一郎/天皇機関説論争が招いた二・二六事件/昭和天皇と満州事変/東条が心酔した平泉澄の皇国史観/「太った豚」による矢内原忠雄追放劇/「大逆」と攻撃された津田左右吉の受難/戦時経済の寵児・土方成美 絶頂からの転落/粛学の立役者、田中耕太郎の四面楚歌/反ファッショ人民戦線と河合栄治郎/平賀東大 戦時体制下の大繁栄/南原繁総長と昭和天皇退位論/天皇に達した東大七教授の終戦工作
-
-右も左もあるものか! 戦前は武装共産党の委員長として警官を襲撃し、逮捕。 獄中、母の諌死を契機に転向すると、戦後は学生やごろつきを集めて共産党を襲撃。 なんとも振れ幅の大きな前半生から、やがて国際的な資源外交を裏で操るフィクサーへ。 資本主義の真っただ中で暗躍しながらも、学生運動に援助を続けるなど、 普通では理解しがたい人生を送った男。 「俺は法螺は吹くが嘘はつかない!」。 その言葉は、出鱈目だけどどこか痛快。こんな男が昭和にはいたのである。 昭和天皇にも拝謁し、その藩屏となることを誓ったというが、どこまで本当なのか……。 筆者は、終戦直後から田中の死まで秘書を務めた人物に出会い、その素顔を知る。 また、英国外務省の機密文書から、田中の国際的な活動の実態、 そしてヨーロッパの貴族を巻き込んで情報を収集し、 それを昭和天皇に届けていたという事実を知る。 東京タイガー。海外の諜報機関では田中のことをそう呼んでいた。 田中清玄は自伝を残しているが、その内容は虚実入り乱れ、本当の姿を伝えていない。 筆者によって、昭和の怪物の姿が初めて明らかになる。 田中の葬儀には、時の総理大臣から右翼、左翼の大物、そして暴力団大幹部の姿もあった。 その人脈こそが、彼の起伏に富んだ人生を表していた。 令和の現代では絶対にお目にかかれない、昭和の快男児の生涯!
-
3.01967年、10・8羽田闘争。同胞・山﨑博昭の死を背負った14人は、その後の時代をどう生きたのか? 全共闘世代の証言と、遅れてきた世代の映画監督の個人史が交差する、口承ドキュメンタリー完全版。 1967年10月8日、佐藤栄作首相の南ベトナム訪問阻止を図る全学連が、羽田・弁天橋で機動隊と激突、当時18歳だった京大生・山﨑博昭さんが死亡した10・8羽田闘争。この〈伝説の学生運動〉に関わった若者たちのその後を描いた長編ドキュメンタリー映画『きみが死んだあとで』を書籍化。 山本義隆(元東大全共闘議長)、三田誠広(作家)、佐々木幹郎(詩人)をはじめ、当時の関係者への延べ90時間に及ぶ取材メモをもとにした、映画未収録インタビューを含む口承ドキュメンタリー完全版。「しらけ世代」の代島監督がいちばん憧れた「全共闘世代」のヒーロー、秋田明大(元日大全共闘議長)に迫る書き下し原稿も掲載! 若者は「10.8後」をどう生きたのか。あの時代の貴重な証言がここに。 【目次】 はじめに 「よく見比べてから判断したいので、いまは入りません」とお断りしました。──向千衣子さんの話 映画『きみが死んだあとで』を撮るにいたった動機 捕虜を撃ち殺す写真を見たのは大きかった。──北本修二さんの話 内ゲバは厭やね。だけど指令があれば、いや、わからないな……。──山﨑建夫さんの話 ぼくの話 1 だから「襟裳岬」をふと耳にするだけで胸がジンとする。──三田誠広さんの話 もうちょっとで山﨑の一周忌やなあと思ったんですけど、その前にやめました。──岩脇正人さんの話 ぼくの話 2 何の役にも立たない老人に、何の意味があるんだと思うでしょうけど。──佐々木幹郎さんの話 49歳ではじめて没頭したんです、いまの仕事に。──赤松英一さんの話 ぼくの話 3 大学では剣道部。もともとは右翼ちっくな少年だったんですが。──島元健作さんの話 わが子に「命」が何なのかを教えてもらいました。──田谷幸雄さんの話 ぼくの話 4 高校時代は何にでもなれると思ってたけど、何にもなれなかったっていうような人生ですね。──黒瀬準さんの話 エイッて、機動隊に追われてホームから線路に飛び降りたんですよ。──島元恵子さんの話 ぼくの話 5 私の救援の原点は、じつは子どもたちなんですよね。──水戸喜世子さんの話 ぼくの話 6 護送車のバックミラーに映った顔を見たら憑かれた顔で「これがハタチの俺なんやなあ」って。──岡龍二さんの話 ぼくの話 7 俺いなくなったら、絶対集まらないから待ってるしかない。だから、ひとりで待っているんだよ。──山本義隆さんの話 ぼくの話 8 終章 あとがき 登場人物紹介 本書に登場する用語の簡易解説 参考・引用文献 関連年表
-
-良質な保守思想、現実的な軍事思想、平和を求めるリアリズムを体現した岡田の生涯を詳解。 海軍軍人(最終階級は海軍大将)、連合艦隊司令長官、海軍大臣、逓信大臣、拓務大臣、内閣総理大臣(在1934‐36年)を歴任した岡田啓介(1868‐1952)。現福井市に生まれ、海軍軍人として日清・日露戦争に従軍。首相在任中の天皇機関説事件では美濃部説支持を示したことで軍や右翼から攻撃される。二・二六事件で義弟が殺害され、事件後には被害者である岡田のほうが引責辞任。退任後は重臣として日米開戦回避に尽力、開戦後は東條打倒を画策し、鈴木貫太郎と協力しながら和平を実現した男であった。 【目次】 岡田、松尾、迫水関係 二・二六事件系譜 まえがき 第一章 襲撃 第二章 総理官邸 第三章 脱出 第四章 海軍 第五章 戦争 第六章 軍縮 第七章 大命降下 第八章 対決 あとがき 引用および参考文献 岡田啓介年表 【著者】 山田邦紀 1945年、福井県敦賀市生まれ。早稲田大学文学部仏文卒。夕刊紙『日刊ゲンダイ』編集部記者として三十年に亘って活躍。現在はフリー。著書に『ポーランド孤児・「桜咲く国」がつないだ765人の命』『軍が警察に勝った日』『岡田啓介』(いずれも現代書館)、共著に『東の太陽、西の新月─日本・トルコ友好秘話「エルトゥールル号」事件』『明治の快男児トルコへ跳ぶ─山田寅次郎伝』(いずれも現代書館)他。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 中国、インド、ベトナム、カンボジア、ミャンマー等々、アジア11カ国への進出を考えるビジネスマン必携の一冊。各国の投資環境から労働事情、リスク管理、そして生活事情まで必要な情報を満載。 【主な内容】 第1章 中国:課題を抱えつつも、引き続き成長が見込める巨大市場 第2章 インド:内需主導型の経済成長、潜在力ナンバーワンの巨大市場 第3章 インドネシア:存在感を増すアセアンの大国 第4章 マレーシア:バランスのよさで“ナンバーワン”の国 第5章 フィリピン:再評価される若い労働力 第6章 シンガポール:地域統括の条件が揃い、良好なビジネス環境 第7章 韓国:韓国グローバル企業とともに世界へ打って出る 第8章 タイ:アセアン製造業の中心国 第9章 ベトナム:チャイナプラスワンの最右翼 第10章 カンボジア:タイ・ベトナムの成長とともに発展 第11章 ミャンマー:アセアン最後の潜在投資大国への期待と課題 付録 アジア各国の基本情報、アジア各国の経済:基礎データ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 追悼復刊!「国家が暴走する時代をどう生きるか!」 反体制運動の常識を変えた鈴木邦男、原点の書!時代と同時進行する貴重な運動史! 「…恥多き、運動の歴史でもある。楽しかったし、誇らしくもあった。と同時に、恥ずかしくて思い出したくない過去もある。何であんなことをしたんだろうと思うことも多い。でも、それら全てを抱きしめて、愛しいと思う。これは愛国心と似ている。失敗も反省も含めて、その全てを抱きしめ、愛しいと思う。その気持が愛国心で、同じように運動に対する「愛」が、この本だ。」(「『右翼』との決別」より)
-
4.0ノーベル経済学賞最右翼! 行動経済学ここに極まる! 「この50年で最大のイノベーションだ!」(『ヤバい経済学』著者レヴィット教授) 対象は教育・ビジネスから途上国支援まで 子どもの成績を上げるには? ワインをたくさん売るには? 保育園のお迎えの遅刻をなくすには? 娘の競争力を高めるには? お得に買い物をするには? 恵まれない子に寄付してもらうには? 社員の生産性を上げるには? 「人はインセンティヴで動く」は当たり前! 大事なのは、誰にいつどのように仕向けるか。 子どもの成績を上げたいとき、あなたならどうするだろうか? 実は、ご褒美をあげるだけでは不十分。ご褒美を渡すタイミングや種類によって、結果は全然違ってくる。 本書では、『フォーブス』誌で「世界で最も影響力のある経済学者」に選ばれた最先端の行動経済学者が、実地実験という最強の武器で、人をやる気にさせるものは何か、人はインセンティヴにどう反応するかを解き明かす。意思決定の奥深くをあぶり出し、ビジネスの現場にも差別や格差という大問題にも解決策を出す画期的な一冊! 【主な内容】 はじめに 思い込みの向こうへ [人がやってることって、どうしてそんなこと人はやってるんだろう?] 第1章 人にやってほしいことをやらせるには? [インセンティヴが働く(働かない)のはどんなときか、そしてそれはなぜか] 第2章 女が男ほど稼げないのはなぜか、クレイグズリスト、迷路、それにボールとバケツでわかること [キリマンジャロのふもとの平原にて] 第3章 母系社会は女性と競争について何を教えてくれるだろう? [カーシ族を訪ねる] 第4章 惜しくも銀のメダリストと大健闘で銅のメダリストが成績格差を埋めてくれる、とは? [公的教育:6270億ドルの問題] 第5章 貧しい子がお金持ちの子にほんの数ヵ月でどうすれば追いつける? [保育園への旅] 第6章 いまどきの差別を終わらせるカンタンな一言とは? [君が嫌いってわけじゃないんだ、ただお金が愛しいってだけさ] 第7章 なにか選ぶときにはご用心。選んだものがあだになるかも [差別の隠れた動機] 第8章 ぼくたちをぼくたち自身から守るには? [実地実験を使って生きるか死ぬかの状況を学ぶ] 第9章 人に寄付をさせるのは本当はなんだろう? [心に訴えてもだめ、見栄に訴えろ] 第10章 割れた唇と「これっきり」のチェック欄から、人が寄付をする理由についてわかること [おたがいさまというすばらしい現象] 第11章 管理職は絶滅の危機? [職場に実験の文化を作るには] おわりに 世界を変えるには……まあ、少なくとも得をするには [この世は実験室]
-
-国家のエリート養成機関として設立された「東大」。最高学府の一極集中に対し、昂然と反旗を翻した教育者・思想家がいた。慶應義塾、早稲田、京大、一橋、同志社、法律学校や大正自由教育を源流とする私立大学、さらには労働運動家、右翼まで……彼らが掲げた「反・東大」の論理とは? 「学力」とは何かを問う異形の思想史。
-
4.0■戦時下は特務機関の頭領、戦後は実業人として、昭和を駆け抜けた男の軌跡。歴史の「闇」に埋もれた“怪物”がいま浮上する。保阪正康氏推薦! 日本一の柔道家をめざして福岡から上京するが、嘉納治五郎に講道館を破門され、右翼学生活動家として2・26事件で北一輝のボディガードを務める。軍人・長勇と義兄弟の契りを結び、戦時下の上海・ハノイで100名の特務機関員を率いて地下活動に携わる。戦後は、銀座で一大歓楽郷「東京温泉」を開業、クレー射撃でメルボルン・オリンピックにも出場した、昭和の“怪物”がいま、歴史の闇から浮上する。 [目次] 序 章 「許斐機関」との遭遇 第一章 許斐氏利の終戦 第ニ章 博多の暴れん坊 第三章 テロとクーデターの時代 第四章 大化会と二・二六事件 第五章 中国大陸へ 第六章 上海許斐機関 第七章 日本陸軍の阿片工作 第八章 「大東亜戦争」とハノイ許斐機関 第九章 大歓楽郷「東京温泉」 終 章 風淅瀝として流水寒し <著者略歴> 牧 久(まき・ひさし) ジャーナリスト。一九四一年、大分県生れ。六四年、早稲田大学第一政治経済学部政治学科卒業。同年、日本経済新聞社に入社。東京本社編集局社会部に配属。サイゴン・シンガポール特派員。名古屋支社報道部次長、東京本社社会部次長を経て、八九年、東京・社会部長。その後、人事局長、取締役総務局長、常務労務・総務・製作担当。専務取締役、代表取締役副社長を経て二〇〇五年、テレビ大阪会長。〇七~〇九年、日本経済新聞社顧問。著書に『サイゴンの火焰樹――もうひとつのベトナム戦争』(小社刊)がある。 ※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『特務機関長 許斐氏利――風淅瀝として流水寒し』(2010年10月28日 第1刷)に基づいて制作されました。 ※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
-
-「血盟団事件」「五・一五事件」「二・二六事件」当事者と接した2人が明かす革命家群像 保阪氏と鈴木氏の初顔合わせ対談。昭和史には、全人類史が経験したすべての出来事が詰まっているという。貧困・飢餓・戦争・クーデター・占領、そして平和と繁栄……。日本人の罪と過ち、知恵と勇気を映し出す歴史の大舞台で、日本人は何のために互いを「敵」と見做し、テロの果てに血を流したのか? 国家改革を求めた青年将校や憂国者の心理から現代日本の希望と挫折、その課題を浮き彫りにする。 【目次】 第1章 国家改造運動の群像 第2章 五・一五事件と農本主義 第3章 軍事学なき〈軍人大国〉 第4章 未完の国家改造運動と日米開戦 第5章 戦後の革命家たち 第6章 国家改造運動の残したもの 【著者】 保阪正康 1939(昭和14)年、札幌市生まれ。同志社大学文学部社会学科卒業。「昭和史を語り継ぐ会」主宰。昭和史の実証的研究のために、これまでに延べ四千人に聞き書き調査を行い、独自の執筆活動を続けている。2004年、個人誌『昭和史講座』刊行などの功績で第52回菊池寛賞受賞。著書に『東條英機と天皇の時代』『後藤田正晴』(ともにちくま文庫)、『瀬島龍三』(文春文庫)、『昭和史 七つの謎』(講談社文庫)、『昭和陸軍の研究』(上下、朝日文庫)、『あの戦争は何だったのか』(新潮新書)他多数。 鈴木邦男 1943(昭和18)年、福島県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。同大学大学院政治学専攻中退。サンケイ新聞を経て元一水会代表。「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」共同代表。著書に『公安警察の手口』『右翼は言論の敵か』(ともにちくま新書)、『愛国と米国』(平凡社新書)、『愛国と憂国と売国』(集英社新書)、『愛国者は信用できるか』(講談社現代新書)、『〈愛国心〉に気をつけろ!』(岩波ブックレット)、『失敗の愛国心』(イースト・プレス)、『ヤマトタケル』(現代書館)他多数。
-
-葦津が神道ジャーナリストとして神社新報を中心に筆を振るった戦後から昭和50年代にかけて、海外ではソ連・中共、国内に於いては共産党や社会党の勢力が拡大した。その象徴的な事件が、「60年安保」、「70年安保」であり、日米安全保障条約に反対する国内左翼勢力が労働者や学生などの一般市民と共に日本史上空前の反政府、反米運動を繰り広げた。 葦津は、「日本土民の感情思考を蔑視したのは、白人ばかりでなかった。日本人の中にも外人的な思考、感情を身につけなければ、民主的、文化的になれないと思いこんで、日本人の心情を非難し嘲笑した者が多かった。それは占領中ばかりではなく、今でも日本のマスコミは、それらの外人文化礼賛者に占領されているかの感がある。(中略)しかし私は、日本の土民であることに誇りを感ずる。」と本書で語っている。本書『土民のことば』とは、戦後、占領軍とのかけ引きで米国担当者の神道に対する「未開野蛮な土人の文化」との潜在意識を感じ取り、日本精神の吐露として、大東亜戦争敗戦から占領以降、米国の洗脳状態にある日本国家とその指導者たちへの強い叫びが、結実した書籍であると云える。 ■キーワード(目次の構成) ▲はしがき ▲非合理なるものへの憧れ ▲信頼と忠誠との情理 神苑の決意 ▲政治とテロとの宿縁 集団暴力の理論 ▲全学連と安保闘争 ▲民主主義と暴力 ▲神道と日本の皇室 ▲自衛隊に名誉を ▲土民のことば 民主主義と人間不信の思想 ▲民主制度と専門官僚 ▲日本土着の民権思想 ▲右翼の先蹤(維新と革命) ▲右翼ハイ・ティーン ▲スターリン歿後のソ連共産主義 ▲社会主義的情熱の冷却 ▲ニュー・フロンティアの外交 ▲とくに中国と台湾の問題について ▲台湾民族の歴史 ▲参考資料 ▲王位継承法(英国) ▲佐賀の乱、決戦之議 ▲大久保利通斬姦状 ▲大西洋憲章
-
-「フットボール批評」の人気連載が待望の書籍化! 世界的な戦術研究の第一人者である著者が 日本のサッカーファンのために書いた、サッカー戦術本の決定版。 戦術とは何か。「ゲーム(勝負事)」を、どこまで支配し得るものなのか。 洋の東西を問わず、この種の議論がますます盛んになってきている。 戦術論が普及すればするほど、根源的な問いかけがなされるようになってきたのは、 フットボールという競技自体の進化にとって、極めて好ましい兆候だろう。 3-4-2-1やプレッシングといったコンセプトを生み出してきたのは、予測不可能性を極小化し、 自らのイデア(理想)を具現化しようとする情熱であり、ひたむきな使命感でもあるからだ。 その事実を理解して初めて、ピッチ上に描かれる魔法陣の秘密は解き明かせるといってもいい。 本書はイギリス人の戦術史家、ジョナサン・ウィルソンとの共作になるが、僕たちが一貫して目指してきたのも、 歴史的な文脈をしっかりと踏まえたうえで、時代の最先端を行く戦術論の見取り図を、読者のみなさんに提示することだった。 とはいえ、ジョナサンと戦術論の本を出版するのは実に不思議な気がする。 彼は戦術論の大著を以前にも上梓しているが、もともとフットボールのジャーナリストを志していたわけではない。 さらに言うなら、戦術分析が専門だったわけでもなかった。 (「はじめに」より一部抜粋) 【目次】 Episode.1 戦術トレンド概論 プレッシングか、ポゼッションか、それが問題だ。 Episode.2 60年ぶりに戻ってきた3バック Episode.3 アンチカウンター理論としてのゲーゲンプレス Episode.4 ゼロトップはどこへ消えたのか Episode.5 ベンゲルと4-2-3-1の行方 Episode.6 10番/トップ下論 エジルが象徴するクリエイティビティのジレンマ Episode.7 ゾーン・ディフェンスがカバーする領域 Episode.8 アンチ・フットボールの誘惑と憂鬱 Episode.9 レスターと4-4-2に未来はあるか Episode.10 ポチェッティーノが受け継ぐ、ビエルサイズムとは Episode.11 アンチェロッティ式、「ハイブリッドマネージメント」のススメ Episode.12 モウリーニョが抱えるスペシャルな懊悩 Episode.13 ウイング論 左翼と右翼のウインガー Episode.14 理想主義者、ペップ・グアルディオラの挟持 Episode.15 GK、100年の孤独 Episode.16 ディープ・ライイング・プレーメイカーの誕生 column.1 共産主義思想としてのプレッシング column.2 コレクティブカウンターの衝撃
-
-差別にまみれた感染症との果てしない戦い。 「右翼の大物」「日本のドン」と差別された笹川良一の三男として生まれ、晩年の彼を支えた笹川陽平(現・日本財団会長)のライフワークが、父の遺志を継いだハンセン病制圧活動だ。 彼は約40年にわたって、「業病」と恐れられてきたこの病気に戦いを挑んできた。世界各地のハンセン病患者の施設に自ら赴き、薬を届け、差別や偏見の撤廃を説く。「制圧」(有病率が1万人あたり1人未満)を達成するための施策を各国の元首と話し合い、実行に導く。こうした活動の継続によって、1980年代から現在までに1600万人を超える人々が治癒し、未制圧国はブラジルを残すのみとなった。 著者は約7年にわたって陽平の「戦い」に密着した。アフリカのジャングルから西太平洋の島国まで、ハンセン病患者や回復者たちが暮らす土地には、深い絶望と、かすかな希望が広がっていた。父の復讐を果たすかのように邁進する陽平の姿を、著者は「いま彼が実現しようとしているのは、ハンセン病差別の撤廃、人間としての権利・尊厳の獲得運動なのである。彼は暗黒の人類史に革命を起こそうとしている」と看破する。 日本人が知らない世界の現実、人間の真実を知るための一冊。
-
-おもしろうてやがて哀しき編集者」初めて書かれた大手出版社への挽歌。 本書には、平成史を彩った数多のスター、政治家 などが次から次へと登場する。オウム真理教事件 をはじめ日本社会を震撼させた大事件を描く際 の臨場感も圧巻。また、編集長として戦友のよう に付き合った名物記者たちを活写する筆致は深 い感動を呼ぶ。著者にとっては、「有名無名」より、 「人間」一人ひとりに焦点を絞ることが何よりも 大事なのだ。同時代を生きてきた誰もが自らの来 し方を想起できる点も本書の大きな魅力である。 【目次】 プロローグ 引っ込み思案だった高校時代とバーテンダー稼業 第1章 講談社の黄金時代 第2章 フライデー編集長「平時に乱を起こす」 第3章 週刊現代編集長「スクープのためなら塀の内側に落ちても」 第4章 ばら撒かれた怪文書と右翼の街宣、そして左遷 第5章 もしも、もう一度逢えるなら エピローグ 愛すべき名物記者たちへの挽歌 あとがき 【著者】 元木昌彦 1945年新潟県生まれ。早稲田大学商学部卒。1970年講談社入社。「月刊現代」、「婦人倶楽部」、「週刊現代」を経て、1990年「FRIDAY」編集長。1992年から1997年まで「週刊現代」編集長・第一編集局長、1999年オンラインマガジン「Web現代」創刊編集長。2006年講談社を退社し、「オーマイニュース日本版」編集長・代表取締役を経て、現在は出版プロデューサー。「週刊現代」編集長時代には週刊誌5位に低迷していた売上を、創刊以来最大発行部数150万部、当時の週刊誌トップにまで伸ばした。
-
-米中対立激化の時代に求められる「男のナショナリズム」を関西右翼会の重鎮が解説! コロナ禍での五輪開催、「一億総中流」から「一億総下層」へ、中国による東シナ海侵攻国難の時代になぜ「国粋精神」が必要なのか――「極道史」「極道組織論」というこれまでにない視点でアカされる、戦後日本のフィクサーたちの真実。この時代を乗り越えるため、関西右翼は大同団結しなければならない! ・笹川良一の甥が明かす児玉誉士夫との関係の真相 ・美空ひばりとその家族は、田中清玄と児玉の暗闘で犠牲になった ・労働組合を積極的に作った田岡一雄組長の思想はリベラルだったのか、国粋的だったのか ・サイパンで壮絶な最期を迎えた白神組長の元に集まった右翼集団「三曜会」の正体 ・戦時に必要とされるヤクザにしかできない裏外交
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 企業、組織・団体をはじめ、エンタメ、芸事、スポーツ、歴史、宗教、学術まで、オールジャンルの離合集散を完全網羅!! 合併と分離をくり返す「世の中のチャート」をなぞっていけば、それぞれの趨勢が浮かび上がってくる――。 はじめに ■part.1 文化・娯楽 プロ野球チーム/Jリーグ/フットボール/日本プロバスケットボールリーグ/男子プロレス団体/ボクシング団体/拳法/空手/柔道・柔術/陰流(剣術流派)/茶道/華道/日本舞踊/歌舞伎/能/狂言/落語/源氏物語/忠臣蔵/短歌・俳句/小説・文芸誌/近代文学/ライトノベルのジャンル/トキワ荘/西洋絵画/ロックン・ロール/映画ジャンル/米(食用)/麺類/ラーメン/お好み焼き/和牛/コーヒー/犬/猫/金魚/鯉(観賞用)/サラブレッド/サンデーサイレンス系/バラ/『スターウォーズ』シリーズ/アベンジャーズ/スーパーマリオシリーズ/『キン肉マン』の超人属性/北斗神拳の系譜/ガンダムの勢力(宇宙世紀) ■part.2 制度・組織 廃藩置県/平成の大合併/東京都の区/中央官庁/国鉄の民営分割/郵政事業の再編/政党/自民党の派閥/三大財閥/四大銀行/自動車メーカー/オートバイメーカー/鉄道路線(私鉄)/航空会社/海運会社/電力会社/石油会社/鉄鋼メーカー/食品メーカー(パン、麺類、菓子、乳製品)/食品メーカー(調味料、肉・水産加工品)/飲料メーカー/パソコンメーカー/コンテンツ産業/ゲーム会社/映画会社/全国紙(日刊)/デパート(百貨店)/名門大学/神社/労働組合/政治団体(左翼)/政治団体(右翼)/指定暴力団/イスラーム武装勢力/アメリカの軍隊/自衛隊 ■part.3 教養・雑学 戦国七雄/三国時代/モンゴル帝国/イギリス/アメリカ合衆国/インド/ソビエト連邦/UAE(アラブ首長国連邦)/ユーゴスラビア連邦/EU(欧州連合)/NATO(北大西洋条約機構)/藤原四家/源氏/平氏/南北朝/鎌倉公方/江戸幕府の将軍/ユダヤ教/世界の仏教/日本の仏教/キリスト教/イスラーム教/日本の新宗教/生物の分類階級/超大陸パンゲア/生物の進化(ドメイン編)/生物の進化(脊椎動物編)/人類の進化/日本人/ゲルマン人/インド・ヨーロッパ言語(東方)/インド・ヨーロッパ言語(西方)/利根川水系/淀川水系
-
3.5民族派右翼活動家から三代目山口組北山組に渡世入り。 四代目山口組分裂を一和会きっての武闘派として生き抜き、 あの石川裕雄に 「もっとも影響を与えた」 と警察資料に書かれた「矢野康生」。 中野会副長として引退して17年経った今、 自らの半生に別れを告げるべく全てを明かす。 山一抗争の真実とは――。 近畿大学に在学中、空手道部で主将を務めた私は、ある事件をきっかけに民族派の右翼活動家になる。その後、あるトラブルをきっかけに三代目山口組北山組内森組に若頭として渡世入りした。ヤクザの世界から右翼活動家になる者は多いが、その逆は極めて珍しい。心奥にあったのは、任俠と民族派の合流だ。 修羅の世界にあって、私は武人としての義と礼に従って喧嘩に明け暮れる。当時のヤクザは、喧嘩の強い者こそ上に行くという、わかりやすい構造ということもあって、29歳で北山組直参に昇格。だが、ほどなく三代目山口組・田岡一雄組長による「右翼団体所有禁止」の通達が出る。 任俠と民族派の道は、狭いものとなり、私には暴力の世界が残された。 山一抗争において、北山組は一和会に参加。悟道連合会・石川裕雄(やすお)会長の後に私は北山組若頭となった。穏健派とされる北山組にあって、私は行動隊長として最前線で戦い、矢野組と矢野康生(やすお)の名前が知れ渡ることになる。 四代目山口組・竹中正久組長暗殺の首謀者として知られる石川会長との関係を「ライバル」のように扱うメディアは多かったが、実際は肝胆相照らす兄弟分の関係だ。大阪府警などの資料には 「石川裕雄に一番影響を与えたのは、矢野康生である」 と書かれていた。そうした仲であるにもかかわらず、石川会長については、取材で問われても長く口を閉ざしてきた。本稿では伝説と化してしまった石川会長を「等身大」に戻すことを試みた。それは、竹中組・竹中武組長と交わした約束があってのことだ。 北山組解散とともに、益田組傘下として山口組に戻った私は、五代目山口組跡目問題から始まる激震の時代を経験した。宅見若頭射殺事件によって中野会は絶縁されたが、事件の首謀者の一人、中野会・弘田憲二副会長とは一和会時代の兄弟分だった。02年に弘田副会長は沖縄で射殺されるが、葬儀に出席したことで、私も五代目山口組から絶縁される。その後、独立組織となった中野会に副会長として迎え入れられ、02年に引退する。 一本独鈷となった中野会に移籍したことや、すぐに引退したことなどは「謎」とされているが、その真相も明かしたい。 私自身は引退し渡世を去ったつもりでも、周囲は認めていなかったということだ。本書は「武闘派ヤクザ 矢野康生」への別れの表明である。「矢野康生」に対する惜別の気持ちは一つもない。 (本文より抜粋)
-
4.0愛国的・排外的な思考をもち、差別的な言説を流布させるネット右翼。その書き込みを目にするのは日常生活の一部になった。しかし、ネット右翼の実態はわかっておらず、断片的な情報やイメージに基づく議論も多い。 ネット右翼とは何か、誰がネット右翼的な活動家を支持しているのか――80,000人規模の世論調査、「Facebook」、botの仕組みなどを実証的に分析し、インターネット文化の変容と右翼的言説の関係もあぶり出す。 ネット右翼の実態を多角的に解明して、手触り感があるネット右翼像を浮かび上がらせる。
-
4.0メディアにヘイトスピーチやフェイク・ニュースがあふれ、「右傾化」が懸念される現代日本。「歴史修正主義(歴史否定論)」の言説に対する批判は、なぜそれを支持する人たちに届かないのか。 歴史修正主義を支持する人たちの「知の枠組み」を問うために、歴史を否定する言説の「内容」ではなく、「どこで・どのように語られたのか」という「形式」に着目する。現代の「原画」としての1990年代の保守言説を、アマチュアリズムと参加型文化の視点からあぶり出す。 「論破」の源流にある歴史ディベートと自己啓発書、読者を巻き込んだ保守論壇誌、「慰安婦」問題とマンガ、〈性奴隷〉と朝日新聞社バッシング――コンテンツと消費者の循環によって形成される歴史修正主義の文化と、それを支えるサブカルチャーやメディアの関係に斬り込む社会学の成果。 ****************** 酒井隆史さん(大阪府立大学)、推薦! なぜ、かくも荒唐無稽、かくも反事実的、かくも不誠実にみえるのに、歴史修正主義は猛威をふるうのか? いま、事実とはなんなのか? 真理とはなんなのか? 真理や事実の意味変容と右傾化がどう関係しているのか? 「バカ」といって相手をおとしめれば状況は変わるという「反知性主義」批判を超えて、本書は、現代日本の右翼イデオロギーを知性の形式として分析するよう呼びかける。キーはサブカルチャーである。わたしたちは、本書によってはじめて、この現代を席巻する異様なイデオロギーの核心をつかみかけている。この本は、ついに現代によみがえった一級の「日本イデオロギー論」である。
-
-明治維新は正しかったのか? 戦前史にこそ、現代日本の難問を解く鍵がある! ハト派の元エリート官僚と、行動右翼の戦前史をめぐる憂国歴史対談。明るいはずの明治時代の破綻ギリギリの頑張り、大国との連戦でもたらされた明治の変質、大正時代に迎えた知られざる近代日本の分かれ道、昭和時代の複雑な右翼思想の乱立状況について、この二人でしか明らかにできなかった〈歴史の読み方〉〈国がヘンになったときの危機管理術〉など白熱の議論を展開! 【目次】 序 章 同じ年に生まれて 第一章 明治維新再考 第二章 大正・一等国の隘路と煩悶 第三章 対米開戦の日本人 第四章 戦前史から何を学ぶべきか 【著者】 孫崎享 1943年、旧満州国鞍山生まれ。1966年東京大学法学部中退。外務省入省。英国、ソ連、米国(ハーバード大学国際問題研究所研究員)、イラク、カナダでの勤務を経て、駐ウズベキスタン大使、国際情報局長、駐イラン大使を歴任。2002〜2009年まで防衛大学校教授。 鈴木邦男 1943年、福島県生まれ。67年、早稲田大学政治経済学部卒業。全国学生自治体連絡協議会初代委員長を務める。卒業後、70~74年、産経新聞社勤務。「楯の会」事件を契機に72年、新右翼団体「一水会」を結成。99年まで代表を務め、現在、顧問。
-
-闇社会を牛耳った凄すぎる首領たちの激闘! 戦後、敗戦日本は一時、警察権力も崩壊して、無法勢力が跋扈。そこで、博徒、侠客、ヤクザが一定の存在感を持ち秩序を担った時期がある。 本書では、東の稲川会・稲川聖城、石井隆匡、西の山口組・田岡一雄、戦前からの右翼闘士・児玉誉士夫、新宿・渋谷の特攻崩れの安藤組・安藤昇、「仁義なき戦い」の広島・共政会・山田久を取り上げている。著者の大下英治氏はほとんどのドンとは長時間の直接インタビューを実現しているので、リアル感が飛びぬけており、ドンたちの文字通りの血と弾丸に明け暮れた、凄ましい生と死を活写している!
-
5.0今、世界中で「ポピュリスト旋風」が吹き荒れています。 2016年11月に実施されるアメリカの大統領選挙における共和党のドナルド・トランプ候補、 民主党から出馬したサンダース元候補、フランスの右派政党「国民戦線」の党首である マリーヌ・ルペン、前大統領のサルコジ。さらにEU離脱の旗振り役だった「連合王国独立党」の 元党首ナイジェル・ファラージ、元首相のブレア、サッチャー、ギリシア左派政権の指導者ツィプラス、 南米ベネズエラの左派政党を率いた前大統領のチャベス、日本では元首相の小泉純一郎など…… 数えればきりがないほどポピュリストが溢れています。なぜ、元々はマイナーな存在だった ポピュリストたちが今、支持を拡大し始めているのでしょうか。 一体、ポピュリズムはどのようにして起こったのか、ポピュリストとはどのような人たちなのか、 ポピュリストとどのようにつきあっていくべきなのか。 朝日新聞GLOBE編集長が、この世界的なテーマに挑みます。 【目次より】 ◆第1章◆なぜポピュリストが世界で跋扈するのか ◆第2章◆冷戦後の新秩序はまだ固まっていない ◆第3章◆着ぐるみ民主主義の時代 ◆第4章◆トランプが大統領になる日 ◆第5章◆サンダースの謎を探る ◆第6章◆国民投票の罠に落ちた英国 ◆第7章◆右翼が守る欧州文明 ◆第8章◆プーチンはなぜ80%の支持を得るのか ◆第9章◆ポピュリストが政権を握る時
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「国家が暴走する時代をどう生きるか!」 反体制運動の常識を変えた鈴木邦男の原点の書! 〈 同時進行の貴重な運動史〉手に取りやすいソフトカバーになって再登場! 「…恥多き、運動の歴史でもある。楽しかったし、誇らしくもあった。と同時に、恥ずかしくて思い出したくない過去もある。何であんなことをしたんだろうと思うことも多い。でも、それら全てを抱きしめて、愛しいと思う。これは愛国心と似ている。失敗も反省も含めて、その全てを抱きしめ、愛しいと思う。その気持が愛国心で、同じように運動に対する「愛」が、この本だ。」(「『右翼』との決別」より)
-
4.0この一冊で最新の「ネット炎上」傾向と、ケース別の対策がわかる ネットに関わる業務をしている方、危機管理担当者、必読! あなたの会社の「防火対策」は十分ですか? ペヤングやマクドナルドの異物混入騒ぎ、ルミネの動画広告、飲食店のいわゆる「バイトテロ」など、企業がターゲットとなる「ネット炎上」事件が絶えません。本書は、企業でウェブに携わる方、リスクマネジメントを担う方に向けて、最近の炎上トレンドから、必要な準備・対策、炎上した際の対応までをまとめた“炎上対策の教科書”です。 組織として必要な準備・対策編では、SNSガイドラインのサンプルを収録し、社員研修の進め方を説明しています。有事の対応については「事実無根の場合」「誤解があった場合」「自社に非がある場合」「反論する場合」「ネット右翼対応」などケース別に事例を基に対応策をまとめました。一方、「攻めのSNS活用」も成功事例10社を厳選して掲載しています。企業、学校、自治体などあらゆる組織で役立つ、炎上対策の決定版です。
-
-2023年1月に他界した鈴木邦男さんの最後の新刊。月刊『創』(つくる)の連載「言論の覚悟」の2016年から著者が闘病生活に入って執筆ができなくなった2020年までを収録。2018年からの闘病の様子も書かれている。新右翼からリベラルに変わったと言われる著者がこの数年間、どういう立場で何を語っていたか、憲法や死刑問題などについての思いがつづられている。著者の連載「言論の覚悟」を書籍化したものは既に「言論の覚悟」「新・言論の覚悟」「言論の覚悟 脱右翼篇」と創出版から刊行されており、今回の新刊が4冊目。日本全体の思想の座標軸が右へぶれたせいで相対的な立ち位置が変わったと言われる著者だが、約30年間、一貫して変わらなかったのは「言論の覚悟」で、前作までは自分の言論に責任を持つとして、全ての著書に自宅の住所と電話番号を明記していた。「言論の覚悟」は、著者の生き方を象徴するキーワードだ。亡くなってから『創』4月号の追悼特集に掲載された佐高信、武田砂鉄、森達也、雨宮処凛、椎野礼仁、金平茂紀、山本直樹、松本麗華さんらの追悼記のほか、約30年間つきあった『創』編集長による鈴木さんの活動の報告や、鈴木さんの活動年譜なども掲載されている。
-
-なぜ右翼運動家が? 「連合赤軍は新選組だ!」といい続ける鈴木邦男は、左翼運動の壊滅後、連合赤軍問題を現在まで検証し続けてきた唯一の人物なのだ。 「五〇年後には連合赤軍は新選組になるでしょう」と僕は植垣康博さんに言った。僕らが子どもの頃は、新選組は悪の象徴だった。それが子母澤寛や司馬遼太郎の小説によって見直され、新選組ブームさえ起った。連合赤軍も今は「悪の象徴」だ。でも、必ず見直されるし、NHKの大河ドラマにもなるだろう。隊規が厳しく、小さなことでも次々と切腹させた新選組。武士出身ではなかったが故に、かえって「武士道」にこだわった新選組。連合赤軍も似ている。(「まえがき」より)
-
3.0――日本人が、今も共産主義を恐がり、イヤがるのには深い理由がある。 中国とロシアの、血塗られた残虐な革命の歴史を肯定することはできない。 あれらは、やってはいけなかった人類史の実験だったのだ。 案の定、大失敗した。 今、アラブ世界で起きているIS「イスラム国」という過激派たちの出現の問題もよく似ている。 私たちは、それでもなお、日本に迫り来る共産・中国の巨大な力を、 正確に測定して感情に走ることなく、冷静に対策を立てなければいけない。 属国日本論で論壇に登場した著者が、今また「日本は中国の属国になるだろう」論をぶち上げる。 反共主義一点張りの右翼言論人と、共産主義の悪をごまかした左翼リベラルの両者に鉄槌を下す。
-
4.1安保法制、憲法改正、歴史問題、朝日新聞問題・・・真のリベラルは、今いかに考えるべきか。 リベラリズム論の第一人者、「怒りの法哲学者」井上達夫東大教授が、右旋回する安倍政権と、欺瞞を深める胡散臭い「リベラル」の両方を、理性の力でブッタ斬る! 【本書の内容から】 「自由主義」にあらず/「憲法九条」削除論/「護憲派」の欺瞞/「平和主義」の論理的破綻/安倍政権「集団的自衛権」の愚/リベラルからの「徴兵制」提言/「悪法」も法か/「主権国家」の必要/「白熱教室」の功罪/「世界正義論」への道/「哲学」の死 【著者「あとがき」より】 いま、「一強多弱」と言われる自民党の圧倒的優位の下で、安倍政権による政治の右旋回が急速に進む一方、野党勢力は民主党も他の諸党も党派間・党派内で右から左まで分裂し、リベラルな対抗軸は結集されていない。 それどころか、慰安婦報道問題等での不祥事を契機とする朝日新聞へのバッシングに象徴されるように、「リベラル嫌い」が、「右翼」や「ネトウヨ」の枠を超えて、一般の人々の間にも広がっている。しかし人々に迷いもある。たしかにリベラル派を気取るメディアや知識人は胡散臭い。でも強引に右旋回する安倍政権とそのシンパにも危うさがあり不安だ、と。 リベラリズムの哲学的基礎を解明し、その観点から法と政治の問題を考察してきた私には、まさにいま、この状況下でこそ、リベラリズムの原理とは何かを一般社会に対して説明し擁護する知的・実践的な責任があるのではないか。いつやるのか。いまでしょう。(中略)本書は、現下の政治状況に対する応答を動機としているが、単なる時局論ではない。時局的問題にも論及しているが、主たる狙いは、時局的問題を読者が自ら筋道を立てて原理的に考察するための哲学的視座を提供することである。
-
4.5ポップ史観で60年代を辿る自伝的エッセイ。 1960年、12歳。坂本九の「悲しき60才」でポップスに目覚めた亀和田少年は、ビートルズの登場で、それまで全盛だった和製ポップスが懐メロ化してしまったと嘆く。渋谷道玄坂で、毎月1がつく日に開催され、プロ作家も参加したSF好きの「一の日会」に通い、東京オリンピック開会式の日は、お祭り騒ぎに興味がなくて、ひとり千鳥ヶ淵でボートを漕いだ。吉祥寺の私大で右翼学生と渡り合い、デモで別セクトにいた美少女に恋をする。そして、童貞少年が夢中になった吉行淳之介の性小説、新宿のジャズ喫茶、映画館など、多感な少年時代をポップに生きた著者の痛快ネタ満載。「ビートルズとバリケードが俺の青春だ」なんて嘘っぱちだ。卓越した記憶力で、既成の60年代史観をくつがえす、名コラムニストの会心の作。
-
-
-
3.0右翼から左翼、文学者や哲学者まで、近代以降の論客がその魅力や影響を語り続けてきた国民的高僧・親鸞。「懺悔の達人」「反権力の象徴」「宗教の解体者」など、それぞれの親鸞論を読み解き、「絶対他力」「自然法爾」といった思想の核心に迫る。日本人の“知的源泉”に親鸞あり――。気鋭の研究者による、親鸞論の決定版!
-
-「日本と言えば世界にその名を知られる超大国であるが、ある日私は、現在の日本がどのようにして発展していったかということを知りたくなった」――日本再興の背景となった、アメリカをはじめとした「海外在住国民国家」の凋落、ヨーロッパに誕生した右翼政党「ワンボイス」騒動、中国共産党政権の崩壊……。知識人18人が2041年の世界情勢を徹底分析。分岐点となったのは、2015年。現代日本が今後どのように進むべきかを真摯に問いかける、圧巻の近未来小説。
-
4.4これは反韓ではない。日韓、未来のために! 反日種族主義の象徴「慰安婦」のすべてがわかる! 第1章 「反日」が原理の国 第2章 おそるべき慰安婦問題の反響 第3章 心からの謝罪の無意味 第4章 老若男女・慰安婦問題、大論争 第5章 戦場の性欲とフェミニズム 第6章 弱者という聖域に居る権力者 第7章 43団体の言論封殺にわしは屈せぬ 第8章 朝ナマで見た凶暴な善意のファシズム 第9章 わしは広義の強制連行による漫奴隷だった! 第10章 右翼のレッテル貼をする女性に感謝 第11章 ゴー宣版・従軍慰安婦資料集 第12章 「従軍慰安婦」の真実 第13章 慰安婦問題の歴史 第14章 慰安婦問題の歴史2 第15章 過去を裁く現代人の奢り 第16章 慰安婦問題の歴史3 第17章 20世紀の女性の人権侵害とは「性奴隷」である
-
-
-
-
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1966年に起きたマルヨ無線強盗殺人事件の尾田信夫から、 2015年に大阪府寝屋川市の中学1年生男女2人を殺害した山田浩二まで 2022年6月現在、全国7ヶ所の拘置所に収監されている死刑囚107人を刑確定順に列挙。 事件の顛末、公判の争点、確定後の動きに加え、 死刑適用の具体的基準、執行当日の手続き、 死刑存廃問題など死刑に関する基礎知識も徹底解説。 ■極刑をもって臨むほかない 裁判長が断罪した、身勝手な動機、強固な殺意、 残忍極まる手口、更生不可能な人命軽視の思考 死刑。 強盗殺人や無差別殺人など凶悪な犯罪を起こし、 裁判で死刑が確定した者の生命を奪い去る刑罰である。 日本においてその執行手段は絞首刑。 刑場において、首にロープをかけられ縊死するまで吊るされることになる。 すでに記憶にない無名因まで全てを網羅し、 さらに死刑が適用される具体的基準、刑確定から執行までの流れ、 死刑制度の存廃問題など死刑に関する基礎知識も解説した。 死刑囚それぞれの事情、裁判長の決断、被害者の無念、遺族の苦悩があることを。 死刑は決して遠い世界の話ではない。 ■目次 ●第1章 1970年代~1990年代確定 ・大濱松三 ピアノ騒音殺人事件 ・片岡利明 三菱重工爆破事件 ・藤井政安 「殺し屋」連続殺人事件 ・大森勝久 北海道庁爆破事件 ・山野静二郎 大阪不動産会社連続殺人事件 他 ●第2章 2000年代確定 ・間中博巳 同級生殺人事件 ・上田宜範 大阪愛犬家連続殺人事件 ・田中毅彦 右翼幹部連続殺人事件 ・豊田義己 静岡、愛知2女性殺害事件 ・菅峰夫 架空建設計画連続殺人事件 他 ●第3章 2010年代以降確定 ・小林竜司 東大阪集団リンチ殺人事件 ・高柳和也 姫路2女性バラバラ殺人事件 ・加藤鞆大 秋葉原無差別殺傷事件 ・渡邉剛 銀座資産家夫婦強盗殺人事件 ・植松聖 相模原障碍者施設殺傷事件 他 ●死刑をめぐる基礎知識 ・「永山基準」が示す死刑と無期懲役の境界線 ・刑確定から執行までの一部始終 ・死刑を存置すべきか廃止すべきか。それぞれの主張と反論 ■著者 鉄人ノンフィクション編集部
-
2.5中国や北朝鮮によって 現実化した国防危機…… いまの日本に、伝えたいこと。 そして私たちが知るべきこと。 三島の「散る美学」に隠された問題点 川端康成が到達した「枯淡の境地」 日本が世界に誇る文学者 2人の霊言の対比から、 浮かびあがってくる真実。 <三島由紀夫> ◇1970年の衝撃の自決、その真相を本人が激白 ◇「憲法改正」「自衛隊の決起」を促した当時の真意とは ◇戦後日本を無力化した「唯物論」と「平和教」 ◇いまだ変わらぬ国論に対する苛立ち <川端康成> ◇三島の過激な思想の限界を鋭く指摘 ◇習近平の焦りが中国の敗北を招く ◇日本神道の特徴と欠けている観点とは ■■ 三島由紀夫の人物紹介 ■■ 1925~1970年。日本の小説家、劇作家。東京生まれ。東京大学法学部卒。代表作は『潮騒』『金閣寺』『憂国』『豊饒の海』など。晩年、民兵組織「楯の会」を結成し、右翼的政治活動を行う。1970年11月25日、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地において自衛隊員にクーデターを呼びかけるが果たせず、割腹自殺した。 ■■ 川端康成の人物紹介 ■■ 1899~1972年。小説家。大阪府生まれ。東京帝国大学(現・東京大学)文学部国文学科卒。卒業後、横光利一らと「文藝時代」を創刊。一高時代の伊豆旅行の体験をもとにした『伊豆の踊子』などを発表し、新感覚派の代表作家として活躍した。日本的美意識を追究し続け、1968年、日本人初のノーベル文学賞を受賞。代表作に『雪国』『山の音』『眠れる美女』『古都』などがある。 目次 まえがき 第1章 三島由紀夫の霊言 ―没後五十年、日本の体たらくを叱る― 1 三島由紀夫が語る「日本への憂い」 2 自決を通して三島由紀夫は何をしたかったのか 3 三島由紀夫の価値観に潜む問題点 4 明らかになる三島由紀夫の「魂の本質」とは 第2章 川端康成の霊言 ―「三島由紀夫の限界」と「日本の国防」を語る― 1 川端康成と三島由紀夫の「美学」の違いとは 2 川端康成から見た三島由紀夫像を語る あとがき
-
4.5日本の大手新聞社の記者・眉村梓はフランス大統領選挙取材のためパリに出張してきた。仕事も兼ねて、久しぶりに子どもにも会える。かつて夫と別れる時、離婚騒ぎの修羅場から避難させるために小学生の一人息子をパリ郊外の寄宿学校に預けていたのだ。しかし、パリに着いたその日から事件に巻き込まれてしまう。息子のパリでの後見人になってくれていた大学時代の親友・夏緒がフォンテーヌブローの森で死体で発見されたのだ。そして息子は何者かに拉致されて行方不明に……。夏緒が生前に漏らした「ナポレオンの秘宝」という一言。その「秘宝」を巡って暗躍する謎の政治組織。ナポレオンの末裔を担ぎ出す右翼政治家。ルーヴル美術館の奥に秘められた謎。フランス政界と歴史の深い闇。梓は、偶然知り合った若き鑑定医シャルルに窮地を救われ、ともに事件の解決と息子の奪還のためにパリを駆けぬける。一気読み必至のノンストップ・サスペンス、〈鑑定医シャルル・シリーズ〉最新作。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1947年の憲法施行以来、70年余にして「改憲」をテーマに国会で議論が始まる。日本国憲法の制定においては、国内国外の様々な政治的、社会的な力が働き、その成立過程は複雑である。ポツダム宣言を受諾して日本は連合国の占領下となるが、その結果、封建主義的な日本の国家体制の根本にある大日本帝国憲法(明治憲法)を民主的なものに変革する必然性があった。そして、その変革の過程は、日本側で考えた憲法改正案がGHQに提出される第一段階と、その提出案を完全却下してGHQが独自に作成した草案に日本側の要望を取り入れて作成した第二段階に分けることがができる。本書では、この作成過程を史実に照らし合わせて忠実に再現しながら、また、今なお完全に解明されていない歴史上の謎を解き明かしながら、マンガとコラムでわかりやすく解説した。右翼、左翼といったイデオロギー的な歴史観にとらわれない視点で多くの文献を基に編集されており、高校生から大人まで楽しめる。
-
5.0
-
-新右翼を代表する論客、鈴木邦男の本音がいま明かされる! 左翼の提灯持ち、と揶揄される著者が 積年の真情を吐露する。 甘ったれた読者には、目に毒かもしれない! 鈴木邦男は進化したのか、それとも初心に戻ったのか……。 あなたは鈴木邦男を自分に都合のいいように 誤解してはいませんか?
-
-予想を裏切って、ドナルド・トランプ氏が次期アメリカ大統領に選出されてから早1カ月。 アメリカを良く知る人々はなぜ、選挙結果を読み間違ったのか。 『アメリカ人の本音』の著者、マックス・フォン・シュラー氏が、誰がトランプ氏を支持したのか、明快に解説している。それは、絶対優位が崩れ去り、自分たちの知る良きアメリカが失われていくことに危機感を抱いたアメリカ白人層だった。マイノリティを守る名目で国家を破壊していく偽善者の白人左翼、自分たちと違う者は徹底排除するキリスト教原理主義者の白人右翼、いまだ虐げられていると恨む黒人コミュニティ…。 アメリカ社会の奥底に渦巻く憎悪と我欲が、一触即発でアメリカを内戦へと引きずり込むと著者は言う。 本書を読むと、日本人がアメリカに対して抱いている自由の国、すべての人にチャンスがある国というイメージはガラガラと崩れ去るだろう。 意外なことに、日米関係は、クリントン氏が大統領になるより良かったという著者。ただし、日本側も変わることが要求される。日本はどうあるべきか。日米両国をよく知る著者からの提言! 著者紹介 マックス・フォン・シュラー(Max von Schuler) 牧師。歴史研究家。親日家。 1956年2月22日生まれ。父はドイツ系、母はスウェーデン系のアメリカ人。1974年岩国基地に米軍海兵隊員として来日。その後、日本 、韓国で活動。退役後、国際基督教大学で政治学を学ぶ。役者、コメンテーターとしても日本で活動。「日出処から」代表講師。日米両方を知る立場から、日本人にアメリカ人の本音を知らせることを、自らの使命の一つとしている。
-
3.5私は性格的に学問的にも保守思想(すなわち近代的理念・理想・理性・合理主義に対する懐疑的な姿勢)に馴染んできたので、 右翼や左翼、要するに理想主義者とは相容れないところがある。 未来にせよ過去にせよ、理想郷を設定するのが不可能な時代に生きているということを自覚できない時点で、やはりそれは弱者の思想だと思う。 その前提の上で、半ば自嘲気味に、あるいは戦略的に右や左を演じている人々は面白いし、場合によっては知的な刺激を受けることもある。 本書で扱うのは彼らではない。 「下」である。 右翼の底辺「右下」もあれば、左翼の下層「左下」もある。 橋下という政治家もいた。
-
-
-
5.0かつて右翼と左翼は明確に異なっていたが、現在はその違いも曖昧になりつつある。日本共産党が皇室の存在を認めるなか、恥ずかしげもなく「天皇制度の廃棄」という言葉を持ち出す自称保守論者もいる。そもそも保守は右翼であろうか。皇室を慮り、神社を大切にする者は果たして右翼なのか。否、私は保守こそ「中道」だと思っている。なぜなら、保守が保守するものとは「天皇」であり「皇統」にほかならないからだ。かつて三島由紀夫は、日本人が最後に守らなければいけないのは「三種の神器」と言った。それこそ正論であろう。歴史的に天皇は日本の中心であり続け、今もそのことに変わりはない。皇統を保守する立場は右でも左でもなく、中道というべきではないか。無益なレッテル貼りはもう終わりにして、日本人としてのあるべき姿を取り戻し、将来の日本のあり方を真剣に考えたい。それが本書のテーマとなる「皇統保守」である。(「はじめに」より抜粋)
-
4.5誰よりも本人に詳しいインタビュアーが知られざる半生を掘り下げる!ラッパー、アイドル、漫画家、オタク、前科者...全員人生濃厚。『帰ってきた人間コク宝』 Zeebra「藤子不二雄と名のつくものは全部ぐらい読んだ」 森下恵理「中森明菜さんが絡んできた後半2年はキツかったですね」 すぎむらしんいち「…最近、毎日飲むようになっちゃってマズいな。身内に死んだヤツいますから」 漢a.k.a.GAMI「リアルは暴力だけじゃない」 小林清美「反対車線に停まってても事故らないのは、UFOを見たあの日以来なんです」 UZI「(祖父の許斐氏利は)アヘンのルートをゲトッて、それでだいぶ財を築いたっぽいです」 テレンス・リー「女性問題の次はどの線がいいかな」 絵恋ちゃん「ガチ恋にするのが仕事だぐらいに思ってたら、一時期ちょっとヤバいお客さんばかりになっちゃった」 姫乃たま「私はもともと鬱傾向なのと、人間関係を積み上げていくのが苦手」 茜さや「いろいろあって、グラビアってこんな業界なんだってちょっとわかってきた」 小田原ドラゴン「ロリコンっていうか、おっぱい大きくて若い子が好き」 相原コージ「みんなもっとオナニーのこと描けよ!」 西田藍「ふつうがよかったなっていまでも思います」 伊藤麻希「伊藤は俳優とは絶対付き合わないです!」 畑中葉子「いまのAV業界のことを聞くと、(第一プロ時代と)同じじゃんこれって」 FUCK ON THE BEACH・ツヨッシー「俺、アイドルのマ●コ見たことありますよ」 呂布カルマ「やっぱり青山ひかるがぶっちぎりで篠崎愛を抜いたら、あとは紺野栞、鈴木ふみ奈、片岡沙耶、和地つかさ、平嶋夏海、桐山瑠衣」 戦慄かなの「少年院送りが決まった時点でパニックになって倒れた(笑)」 MC仁義 a.k.a. GERU-C閣下「僕らが一番手で、帰れコールでビール飛んできて、チャーミーとS×O×Bのトッツァンがバーッと出てきて、『おまえら何してんや!』みたいな」 ギュウゾウ「応援団もおもしろかったですね 右翼団体も楽しかったんですよ」 浅野いにお「デリヘルは楽しかった」 泰葉「中村勘三郎さんが生前、『日本で初めてテレビでラップやったのは泰葉だよ』って」 あとがきにかえて 吉田豪逆インタビュー 聞き手・構成/姫乃たま 吉田豪(ヨシダゴウ) 1970年、東京生まれ。プロインタビュアーにしてプロ書評家。専門高校卒業後、編集プロダクションを経て、今はなき『紙のプロレス』に参加。そこでのインタビューのまとめ記事などが評判となり、多方面で執筆を開始する。タレント本収集家としても有名で、インタビューは資料を駆使した徹底的な事前取材のもとに行われる。雑誌・新聞などの活字媒体に限らず、テレビ、ラジオ、ネットから各種イベントまで多彩な活動を続けている。共著書、監修本も多数。
-
-愛国者が売国奴を礼賛する摩訶不思議。 「ナショナリズム」という言葉を聞くと反射的に「右翼」「軍国主義」と認識し、毛嫌いするきらいがある。しかし、本来の意味は違う。簡単に言えば、歴史や共同体を大切にし、安定的、文化的で保守的なものだ。ところが、日本の政治は日本人の利益を破壊してきた。一例を挙げれば、雇用市場を不安定化させ、格差を拡大させてきた。移民政策を拡大させ、さらに水道の民営化で海外企業に売却が噂されるなど、かつてならば「国賊」「売国奴」と罵られてきたはずの政治家が「自称保守」を自認する人々に支持されてきた。安倍晋三前総理大臣だ。 安倍氏の後を継いだ菅義偉総理も大した差はない。“政商”竹中平蔵氏、「中小企業の再編」を菅総理に吹き込んだ元ゴールドマン・サックスのデービッド・アトキンソン氏を「成長戦略会議」のメンバーに入れたくらいだ。 おそらく日本の富が海外(特にアメリカ)に流出し続け、日本の貧国化はさらに進む。いつの時代も泣きを見るのは、一般庶民だ。まずは国家とは何かを理解する必要がある。ナショナリズムと近代とは深い関係がある。近代国家について考えるときは、まずはナショナリズムを理解する必要があるのだ。
-
5.0
-
-昭和45年11月25日、東京・市ヶ谷の自衛隊駐屯地において、作家の三島由紀夫が自決した。当時僕は八歳だった。ひどくショックを受けた記憶だけが残っている――。(本文より) 学生運動華やかなりし頃、ゲバ棒を持って活動する人々はエネルギーに満ちあふれていた。 必死になる対象がある、言いかえれば「生きがいがある時代」ということはできるだろうか。 そんな彼らを見て育った青年・小松憲一は、昭和後期の春、「大日本愛国党」赤尾敏総裁の側近として、導かれるように右翼活動に身を捧げていく。それは愚かな選択か、あるいは天命ともいうべき導きか。 党の活動に情熱を注ぎ、すべてを注ぎ込むその生き様を通して、外側からは見えづらかった「右翼活動」の本質が浮かび上がる。 国粋主義運動の第一線を命がけで生き抜いた著者が、かつての記憶を振り返り、思想と行動を記した回顧録。 【目次】 目次 第一章 思想の目覚め 軍歌/三島由紀夫との〝再会〟/政治活動の構想/赤尾敏を知る/札幌のアパートで/アルバイトで味わったこと/市ヶ谷駐屯地/赤尾敏との対話/自衛隊入隊に向けて/僕の少年時代/入隊/自衛隊での生活/自衛隊に対する諦観/危険思想/除隊/自衛隊との対立/愛国党書記長との会話/政治運動の障害 第二章 右翼活動時代 自衛隊の神経質/東京都知事選/朝日新聞阪神支局襲撃事件/右翼とは何か!/三島由紀夫の〝赤尾評〟/愛国党での生活/愛国運動の基本/警察の過剰反応と愛国党の対応/運動に対する姿勢/ハードだった一週間/思い出深い田中角栄糾弾の演説/忘れられない「小名浜論争」/反ソデー/自衛隊観閲式/「山口烈士に申し訳ない」/『憂国忌』への不満/政治運動とは/同志の除名とそれによる緊張感/二・二六事件の解釈/新右翼との対話/不審者/初めての赤尾総裁からの叱責/愛国党を離れる/昭和天皇崩御/筆保同志の除名/赤尾総裁の死 第三章 人生における重要思想 赤尾敏先生の虚像と実像/実存主義―――「死」を考える/愛国党分裂/反新右翼/精神主義研究会/先祖信仰/儒教への思い入れと懐疑/警察をどう見るか/警察はここまでやる!/筆保同志との懐かしい再会 そして……/筆保同志のお母さん/道子さんの性格/夫人派と家族派の確執/奇妙な縁?/偉大なる活動家の死/津山への再訪/同志的結合と離反の条件/農本主義と都会への嫌悪/マラソンと精神主義/精神主義の誤解/「死」の考察/鹿児島・桜島と西郷隆盛/老荘思想/≪補記≫この七年を振り返って 【著者紹介】 小松憲一(こまつ・けんいち) 昭和37年北海道紋別市生 大学在学中に右翼民族主義に関心を抱き、昭和61年5月自衛隊武山駐屯地第一教育団入隊。在隊中政治思想を有していることが発覚し、規約違反の示威活動を画策していると悪推され、また隊員に多大なる影響を与えたとして強制退職処分を受ける。昭和62年3月大日本愛国党にて赤尾敏総裁の下で活動。東京都内において精力的な街宣活動を展開。その後、執筆活動を中心に独自の運動を展開。その一方で精神を鍛える目的から「走ること」を始め、≪精神主義ランニング≫と名づけ、全国の100kmマラソン大会に出場、二十数回の完走を数える。精神主義、農本主義から老荘思想に入り、そこに人間の理想を見出し、生活に反映させ現代に至っている。
-
4.3
-
-1987年4月にスタートした「朝まで生テレビ!」。著者は、ときに強引すぎるとの批判を受けつつも、その独特の司会ぶりで、原発、天皇、右翼など“日本のタブー”に挑み、30年間にわたって番組を牽引してきた。野坂昭如氏、大島渚氏など放送開始時から存在感を示した出演者から、堀江貴文氏ら最近の若手論客まで、多彩なパネリストたちによる“論戦”を一挙に振り返る。 目次 第一章 「公平でない」「発言しすぎる」は、私にとっての褒め言葉 第二章 手応えを感じた原発論争 反対派と推進派が直接対決 第三章 自粛ムードの中、あえて天皇と天皇制を論じる 第四章 野坂昭如抜きには成り立たなかった差別問題論争 第五章 野村秋介との対話で確信、右翼とも議論はできる 第六章 ときには同志、ときには好敵手 野坂、大島、西部……素顔の論客たち 第七章 本物っぽく見えた麻原彰晃 宗教を扱う難しさを実感 第八章 対米従属か、自立か 安全保障をめぐり意見は真っ二つ 第九章 これからは彼らが主役 若手論客に教えられること
-
-
-
4.4東条内閣を生み、「聖断」を演出した昭和史のキーパーソン、初の本格的評伝! なぜ日本政治は軍部に引きずられたのか? 昭和史最大の謎を解く鍵を握る人物が木戸幸一だ。 昭和日本の運命を決する重大な岐路には、必ず彼の姿があった。 開戦時から終戦時まで内大臣をつとめ、東条内閣の生みの親。 木戸孝允の子孫、昭和天皇最側近のひとりにして、 昭和史の基本文献として知られる『木戸日記』を書いた木戸だが、 彼がいかなる政治認識を持ち、重要な局面で何を行ったか、 正面から論じた著作は少ない。 満州事変、二・二六事件から終戦まで、昭和の岐路に立ち続けた木戸を通して、 昭和前期、日本が直面した難局が浮かび上がる。 ロングセラー『昭和陸軍全史』をはじめ、永田鉄山、石原莞爾、浜口雄幸などの評伝で 定評がある著者が描く昭和史のキーパーソン初の本格的評伝。 【内容】 満州事変 内大臣秘書官としていち早く陸軍情報を入手 陸軍最高の戦略家・永田鉄山との交流 二・二六事件 反乱軍鎮圧を上申 日中戦争 トラウトマン工作に反対 「軍部と右翼に厳しすぎる」昭和天皇に抱いた不満 三国同盟と日米諒解案は両立できると考えていた 独ソ開戦という大誤算 日米戦回避のためにあえて東条英機を首相に 「聖断」の演出者として ほか
-
3.6沈黙、破る。 <かつて「一世を風靡した」舛添要一が、落ちぶれてライオンに食われかけている。こん面白い見世物はない。都職員、都庁記者、国会議員、都議、右翼、左翼、カジノ推進派、石原シンパなど雑多な人たちがライオンをけしかけた>――本文より 舛添バッシングから1年――。 石原都政、東京五輪、豊洲移転。 何があったか、どこで誤ったか。 自ら綴った反省と後悔と、そして小池知事への伝言。 <目次> 第1章 誰が私を刺したのか 第2章 都庁は「不思議の国」だった 第3章 韓国訪問とヘイトスピーチ 第4章 ファーストクラスは「悪」なのか 第5章 見果てぬ東京 第6章 五輪と敗戦 第7章 小池知事へ ――カジノ・豊洲・広尾病院
-
3.9
-
4.01960年代後半、左翼学生運動の高まりのなか、対抗すべく生まれた新右翼。彼らは既成右翼が掲げた「親米反共」「日米安全保障条約堅持」に反発し、「反米反共」を標榜、同条約と北方領土問題をもたらした「ヤルタ・ポツダム体制」の打破をめざした。新右翼の誕生から現在までを追った闘争史である本書には。その活動家として、いま脚光を浴びている日本会議の中枢メンバーが多数登場。言わば日本会議の源流がここにある。近年、右傾化現象が叫ばれるが、その流れを歴史として知ることができる貴重な記録であり、真の保守とは何かを考えさせる一冊。
-
-
-
4.0
-
4.5この国を真剣に問わなければならない今、右翼も左翼もない。イデオロギーを超えて闘ったアナーキスト・竹中労の言動を現代に響かせる体験的評伝。没後20年を経て再生する無頼の闘争。
-
-「左翼も右翼も日本語を学べ!」 言葉から思想の面白さが見えてくる。ポリコレ時代の今、言葉狩りを誘発する社会の真相とは? リベラル左翼もネトウヨも日本語の教養が全くないことをこの本を知ることができます。国語力とは論理力。この本質を知ることで言葉と論理を基礎から学ぶことができます!
-
3.0
-
-日本は「右傾化」しているといわれている。ネット右翼、憲法改正論、中国や韓国との軋轢、さらには「美しい国」ニッポンという自画自賛など、たしかにその兆しはあるようにも思える。 しかし、はたしてこれらは本当に右翼の台頭を示すものなのだろうか? 右翼による社会改革はありえるのか? 本書は、日本に蔓延する「右翼的」な雰囲気の正体を、国内の経済衰退と自信の喪失、日米中韓の関係性の変化から読み解き、右傾社会の実体を明らかにしていく。さらに、政治家や官僚などエリートが右傾化することに警鐘を鳴らしつつ、厳しさを増す国際環境をサバイブできる合理的な「中道・右翼政権」の出現を期待する。
-
4.1第15回(2011年)司馬遼太郎賞受賞作。 日本の命運を若くして背負わざるをえなかった君主はいかに歩んだのか。昭和天皇の苦悩と試行錯誤、そして円熟の日々――。我々は後年の円熟味を増した姿で昭和天皇についてイメージし語ってしまいがちだが、昭和天皇が即位したのは25歳。世間では天皇の神聖さが説かれていても、右翼や保守派の重臣たちは天皇をかなり手厳しく見ていた。本書は側近や実力者たちが残した膨大な日記など、一級の史料を丁寧に掘り起こし、生真面目で気負いのある若かりし頃から晩年にいたるまでの多面的な昭和天皇の姿を描く。「昭和」という時代を理解するために必読の評伝!
-
3.8
-
4.0「一億総懺悔」を説いた宮さま宰相は、いかなる人だったのか――。 太平洋戦争を終戦に導いた鈴木貫太郎の次の内閣を引き受けたのが誰か、ご記憶でしょうか。わずか50日間ですが、重責を担ったのが皇族の東久邇宮でした。日米開戦直前の昭和16年秋、総辞職した近衛内閣のあと、東條英機の対抗馬と目されたのも実はこの宮さま。日本の危機に「切り札」として期待された宮さまの実像は、しかしあまり伝えられていません。著者の浅見さんが新史料を駆使して明かすのは、波乱万丈の生涯、痛快無比の個性、勝手放題の実力者ぶり。臣籍降下騒動、女性問題、右翼との危険な関係などなど、興味津々の破天荒人生が初公開されます。
-
-ナショナリズムは悪なのか?第二次安倍政権の誕生以降、中国・韓国政府をはじめ、国内の「既成左翼」勢力からも、「アベは右翼だ」との批判が巻き起こっている。安保法制の国会論議におよぶ現在もそうした声が後を絶たない。だが本当にそうなのか? 「右傾化」批判は戦後七〇年を迎える今日まで、焦土と化した敗戦以降、一度の戦火も交えることなく平和国家として成熟した民主主義と市民社会を構築してきた努力を無に帰するものではないのか? 日本を「右傾化」批判する国々がどれだけ、戦争をしてきたのか! アジア情勢と世代論から読み解く間違いだらけの戦後イデオロギーの正体!
-
4.3久しぶりに実家に帰ると、穏健だった親が急に政治に目覚め、YouTubeで右傾的番組の視聴者になり、保守系論壇誌の定期購読者になっていた――。こんな事例があなたの隣りで起きているかもしれない。中にはネット上でのヘイトが昂じて逮捕・裁判の事例が頻発している。そのほとんどが50歳以上の「シニア右翼」なのである。若者を導くべきシニア像は今は昔だ。これは決して一過性の社会現象ではなく、戦前・戦後史が生みだした「鬼っ子」と呼ぶべきものであることが、歴史に通暁した著者の手により明らかにされる。 そして、導火線に一気に火を付けたのは、ネット動画という一撃である。シニア層はネットへの接触歴がこれまで未熟だったことから、リテラシーがきわめて低く、デマや陰謀論に騙されやすい。そんな実態を近年のネット技術史から読み解く。 かつて右翼と「同じ釜の飯を食っていた」鬼才の著者だからこそ、内側から見た右翼の実像をまじえながら論じる。
-
2.3
-
1.0保守のコスプレ。“売国政治”の正体! 自民党の「劣化」が止まらない――。 国際競争力の低下、“反日カルト”との蜜月、いまだに迷走を続けるコロナ対策、上がらない賃金と物価高、少子高齢化に格差拡大……とあまりの無策ぶりに、多くの国民は怒りを通り越して絶望するばかりだ。 公正な自由選挙制度の下、この国ではなぜか、自民党がほぼ常に第一党となって揺るがない。 それはどうしてなのか? 彼らはいずこで日本の舵取りを誤ったのか? その「失敗の本質」に迫るべく、10人の識者を直撃した。 〇統一教会に票乞いするハレンチ 〇「グロテスクな親米派」の跋扈 〇農業消滅で「飢えるニッポン」 〇派閥=選挙互助会の体たらく 〇“情と空気”に流される防衛政策 【目次】●第一章 “空気”という妖怪に支配される防衛政策 石破 茂(自民党・衆議院議員) ●第二章 反日カルトと自民党、銃弾が撃ち抜いた半世紀の蜜月 鈴木エイト(ジャーナリスト) ●第三章 理念なき「対米従属」で権力にしがみついてきた自民党 白井聡(政治学者・京都精華大学准教授) ●第四章 永田町を跋扈する「質の悪い右翼もどき」たち 古谷経衡(作家) ●第五章 “野望”実現のために暴走し続けたアベノミクスの大罪 浜 矩子(経済学者) ●第六章 「デジタル後進国」脱却を阻む、政治家のアナログ思考 野口悠紀雄(経済学者) ●第七章 食の安全保障を完全無視の日本は「真っ先に飢える」 鈴木宣弘(経済学者・東京大学大学院農学生命科学研究科教授) ●第八章 自民党における派閥は今や“選挙互助会”に 井上寿一(歴史学者・学習院大学教授) ●第九章 小泉・竹中「新自由主義」の“罪と罰” 亀井静香(元自民党政調会長) ●特別寄稿 自民党ラジカル化計画―― 一党優位をコミューン国家へ 浅羽通明(古本ブローカー)
-
-科学的事実を歪曲した地球温暖化の人為的影響や健康診断、きれいごとばかりのSDGsや学校制度改革――世界は徐々に破滅にむかって進んでいるけれど、人々はよほど騙されるのが好きに違いない。騙され続ける日本(人)に、有効な処方箋はありやなしや!? 老い先短い気楽さで物申す、バカバカしくも深くてためになる、秀逸なエッセイ。 妄想はどこから来るのか/人生は計画通りにいかないから面白い/コロナ禍は老化を加速する/温暖化阻止は美味しい商売だ/平等原理主義という病/アホな科学政策が加速させる頭脳流出/ほんとうのSDGs/ブルシット・ジョブ(無駄仕事)に精を出すデジタル庁/右翼、左翼、保守、革新、リベラル/ペットの寿命と自分の余命/専門家は信用できるのか ほか
-
3.8
-
-戦後日本社会のスーパースター、ノーベル文学賞候補にもなっていた天才はなぜセンセーショナルな最期を迎えたのか? 従来、作品に三島の天稟を認め心酔する読者も、1960年代からの彼が見せていた右翼的行動とその劇的な自決に対しては評価を保留する傾向――いわば作品と作家(思想)を分離する傾向があった。しかしもうこの分離は必要ない。彼の「言葉」が「行動」を求めたのは必然だったのだ。本書は、三島自身が「これがわかれば僕の全部がわかる」とした作品論『太陽と鉄』に基づいて作家履歴を3つに分けて読み解き、天才少年が肉体右翼として自決に至るまでを必然的な1本の筋道として描く、万人向けの入門書である。
-
3.0階級を生んだ松方デフレ、大逆事件の衝撃、白熱のアナ・ボル論争、弾圧と知識人の「転向」。 日本左翼の原点とは何だったのか? シリーズ累計15万部の「左翼史」シリーズ、社会運動の源泉を探る【戦前編】。 【本書の内容】 ・右翼と左翼が未分化だった戦前 ・絶大な存在感を示した大本教 ・資本主義を確立させた「松方デフレ」 ・太宰治が悩まされた「後ろめたさ」の正体 ・近代史上最大の農民蜂起「秩父事件」 ・キリスト者・内村鑑三と足尾鉱毒事件 ・「平民新聞」が打ち出した非戦論 ・無政府主義が日本で「ウケた」理由 ・幸徳秋水と「アナルコ・サンディカリズム」 ・社会主義者に打撃を与えた「赤旗事件」 ・高畠素之が見抜いたロシア革命の本質 ・「22年テーゼ」と第一次共産党弾圧 ・第二次共産党の再建と「福本イズム」 ・エンタメ性抜群のプロレタリア文学 ・佐野・鍋山転向声明の衝撃 ・疑心暗鬼を募らせた共産党と小畑達夫の死 ・転向者が出た講座派、出なかった労農派 ……ほか 【本書の目次】 序章 「戦前左翼史」とは何か 第一章 「松方デフレ」と自由民権運動 第二章 社会主義運動と「大逆事件」 第三章 ロシア革命と「アナ・ボル論争」 第四章 日本共産党の結成と「転向」の問題
-
4.2ロシア革命が成功したあと、レーニンは世界革命を遂行すべく、「コミンテルン(共産主義インターナショナル)」をつくる。それは恐るべき思想と悪魔的手法に裏打ちされた組織であった。そして大日本帝国は、やすやすとその謀略に乗せられ、第二次大戦に追い込まれていく。なぜ、そうなってしまったのか? 実は、その背後には、日本の「自滅的」な大失敗があった。リヒャルト・ゾルゲ、尾崎秀実らが暗躍していたことは、よく知られたことだろうが、彼ら以外にも、軍や政府内部に入り込み、ソ連・コミンテルンの都合の良いように動く人々がいたのである。どうして当時の日本のエリートたちは共産主義にシンパシーを覚えたのか? ソ連型の共産主義社会をめざす「左翼全体主義者」と、天皇を戴きながら社会主義的統制国家をめざす「右翼全体主義者」は、いかにして日本を席巻したのか? そして左右の全体主義の危険性に気づき、その勢力に敢然と立ち向かった保守自由主義者たちの姿とは――? コミンテルンの戦略を詳述しつつ、日本国内の動きの謎を解き、隠された「歴史の真実」を明らかにする刮目の書。 【目次より】●はじめに コミンテルンの謀略をタブー視するな ●第1章 ロシア革命とコミンテルンの謀略――戦前の日本もスパイ天国だった ●第2章 「二つに断裂した日本」と無用な敵を作り出した言論弾圧 ●第3章 日本の軍部に対するコミンテルンの浸透工作 ●第4章 昭和の「国家革新」運動を背後から操ったコミンテルン ●第5章 「保守自由主義」VS「右翼全体主義」「左翼全体主義」 ●第6章 尾崎・ゾルゲの対日工作と、政府への浸透 ●おわりに 近衛文麿という謎
-
3.0
-
3.8ヘイトスラングを口にする父 テレビの報道番組に毒づき続ける父 右傾したYouTubeチャンネルを垂れ流す父 老いて右傾化した父と、子どもたちの分断 「現代の家族病」に融和の道はあるか? ルポライターの長男が挑んだ、家族再生の道程! <本書の内容> 社会的弱者に自己責任論をかざし、 嫌韓嫌中ワードを使うようになった父。 息子は言葉を失い、心を閉ざしてしまう。 父はいつから、なぜ、ネット右翼になってしまったのか? 父は本当にネット右翼だったのか? そもそもネトウヨの定義とは何か? 保守とは何か? 対話の回復を拒んだまま、 末期がんの父を看取ってしまった息子は、苦悩し、煩悶する。 父と家族の間にできた分断は不可避だったのか? 解消は不可能なのか? コミュニケーション不全に陥った親子に贈る、 失望と落胆、のち愛と希望の家族論!
-
4.0日本の左翼は何を達成し、なぜ失敗したのか? ――忘れられた近現代史をたどり、未来の分岐点に求められる「左翼の思考」を検証する壮大なプロジェクト。 深刻化する貧困と格差、忍び寄る戦争の危機、アメリカで叫ばれるソーシャリズムの波。 これらはすべて、【左翼の論点】そのものである! 激怒の時代を生き抜くために、今こそ「左の教養」を再検討するべき時が来た――。 ◇◇◇◇◇ 戦後復興期に、共産党や社会党が国民に支持された時代があったことは、今や忘れられようとしている。 学生運動や過激化する新左翼の内ゲバは、左翼の危険性を歴史に刻印した。 そしてソ連崩壊後、左翼の思考そのものが歴史の遺物として葬り去られようとしている。 しかし、これだけ格差が深刻化している今、必ず左翼が論じてきた問題が再浮上してくる。 今こそ日本近現代史から忘れられた「左翼史」を検証しなければならない。 「日本の近現代史を通じて登場した様々な左翼政党やそれに関わった人たちの行い、思想について整理する作業を誰かがやっておかなければ日本の左翼の実像が後世に正確な形で伝わらなくなってしまう。私や池上さんは、その作業を行うことができる最後の世代だと思います。」(佐藤優) 【本書の構成】 ◇日本共産党の本質は今も「革命政党」 ◇社会党栄光と凋落の背景 ◇アメリカで社会主義が支持を集める理由 ◇野坂参三「愛される共産党」の意図 ◇宮本顕治はなぜ非転向を貫けたか ◇テロが歴史を変えた「風流夢譚事件」 ◇労農派・向坂逸郎の抵抗の方法論 ◇「共産党的弁証法」という欺瞞 ◇労働歌と軍歌の奇妙な共通点 ◇共産党の分裂を招いた「所感派」と「労農派」 ◇毛沢東を模倣した「山村工作隊」 ◇知識人を驚愕させた「スターリン批判」 ◇天才兄弟と称された上田耕一郎と不破哲三 ◇黒田寛一と「人間革命」の共通点 ◇現在の社民党は「右翼社民」
-
-
-
-事件記者になりたい一心で産経新聞に入社した著者は、現場での同業者たちに違和感を抱くようになる。なぜ彼らは特定の勢力や団体に甘いのか。左派メディアは、事実よりもイデオロギーを優先していないか。ある時は警察と大喧嘩をし、ある時は誤報に冷や汗をかき、ある時は記者クラブで顰蹙を買い、そしてある時は「産経は右翼」という偏見と闘い……現場を這いずり回った一人の記者の可笑しくも生々しい受難の記録。
-
4.3戦前右翼、反米から親米への転換、政治や暴力組織との融合、新右翼、宗教右派、そしてネット右翼・・・。戦後右翼の変遷をたどる。
-
3.0
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。












![岡田啓介 開戦に抗し、終戦を実現させた海軍大将のリアリズム [電子改訂版]](https://res.booklive.jp/20030434/001/thumbnail/S.jpg)