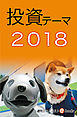構造改革作品一覧
-
4.5
-
-2002(平成14)年4月―。構造改革を唱える小泉健太郎総理が靖国神社で突如、行方不明になった!?極秘に捜索が進められるが、一人息子、小泉夏彦のもとに2020年の日本から来たという理化学研究所員・寺崎保が訪れる。彼が言うには小泉総理は1941年12月にタイムスリップしてしまったのだという…。1941年12月4日。真珠湾奇襲を画策する連合艦隊司令長官・山本五十六は、季節外れの台風のため足止めを余儀なくされていた。憲兵隊の用意してくれた車で旗艦『長門』に向かう山本を、アメリカ領事館の刺客が襲う。長官の運命は!?一方、在フィリピンの極東軍司令官マッカーサーは、ルーズベルト大統領に日本本土の奇襲を提案する。将軍たちは反対したが、ルーズベルトは、日本海軍の脅威を重大視して呉軍港の奇襲を許可する。お互いに奇襲を狙う日米は、どちらが先手をとるのか!?ロマンの復活を目ざす草薙圭一郎が活写する、胸躍らされる超弩級スペクタクル架空戦記シリーズ第三弾、いよいよ開始。
-
3.6
-
4.3
-
3.2公務員の給与は依然手厚く、時間外労働などについても高額な水準が維持され続けている。日本の政治が構造改革の名のもとに変化を迫られているなか、なぜ公務員制度だけは変革が進まないのか? その元凶を斬る!
-
3.02022年に向けて、ICT・メディア市場で何が起こるのか? AI(人工知能)、IoTで日本企業はチャンスを活かせるか? IT市場の成熟、構造変化の先を徹底予測! 携帯電話業界の構造改革の行方は? 巨大SNSプラットフォームの勢力図はどうなるのか? AI(人工知能)の発展と日本企業が進むべき道は? VR(仮想現実)が描く新たな現実とは? 本書では、「デバイス」「ネットワーク」「プラットフォーム」「コンテンツ配信」「ソリューション」など、従来の市場領域の発展と統合、境界が曖昧になっていることを鑑みて、2016年以降を見越した構造変化を予想している。 IT市場は、成長と衰退が目まぐるしく入れ替わる。成長機会も大きいが同時に事業リスクも大きな事業環境である。加えて、海外市場や社会インフラ連携などの新たなフロンティアをかたち作るための具体的な行動が求められている。 IT市場の主要分野を対象とした市場予測を行う本書は、市場の見極めや事業戦略の立案に必読の一冊。
-
3.5
-
3.0安倍総理は本当に憲法改正に向うのか? 改憲議論前の必読書! 憲法改正は、安倍総理が「DNAをしっかり受け継いでゆく」と公言する祖父・岸信介の悲願でもあった。 しかし、あの戦争を始めた指導者の一人であった岸の思想は、本当に受け継いでゆくべきものなのか。 岸・安倍ファミリーの悲願は、われわれ国民を幸せにするのだろうか。 安倍総理を支えているのは「保守」層である。しかし、一口で「保守」といってもいろいろある。 安倍総理が「脱却」すべきものとする「戦後レジーム」を築いた戦後の指導者たちも、また「戦後保守」と呼ばれる「保守」政治家なのである。 吉田茂、池田勇人、佐藤栄作、田中角栄……平和で豊かな戦後日本を作り上げた「戦後保守」から、どうしてわざわざ脱却する必要があるのか。 岸の思想の根幹は、「エリート主義」と「戦後体制の否定」である。そして、特攻の悲劇を美しい日本人の物語として賛美する。このような思想を、現代に蘇らせる必要はあるのか。 戦後の保守政治家たちの思想と行動を検証しつつ、私たちの目の前にある危機を徹底的に考えた本書は、憲法改正議論前の必読書だ! <おもな目次> ●第一章 岸信介の保守● 反米/真の独立/反大衆 など ●第二章 戦後保守● 大衆とエリート/大衆化のシンボル 田中角栄 など ●第三章 岸的「保守」の断絶● 岸の後継者 福田赳夫/青嵐会/戦後政治の総決算 など ●第四章 異端児たちの挑戦● 中曽根行革/コンセンサス政治の崩壊 など ●第五章 迷走する戦後保守● 小泉構造改革/戦後体制脱却の可能性/安倍「保守」の正体 など
-
4.0日本の官僚システムに大きく切り込んだ記念碑的作品。道路公団改革の原点。 収録作の「構造改革とはなにか」は、日本の官僚システムに大きく切り込んだ記念碑的作品。著者は、日本政治の構造欠陥を見抜き、本書がきっかけとなって道路公団改革に深く関わっていく。 本書前半は書籍『日本国の研究』(1997年3月文藝春秋刊行)。後半には後に執筆された「増補 公益法人の研究」を収録した。附録に、著者による「日本道路公団分割民営化案」。 巻末の「解題」には、「小泉純一郎との対話」(『文藝春秋』1997年2月号初出)を収録。対談時、第二次橋本内閣の厚生大臣であった小泉氏と、官僚機構の問題点と行革について論じている。ほかに、小泉内閣で経済財政・金融担当大臣を務めた竹中平蔵氏が『日本国の研究』文庫版(文春文庫1993年刊)に寄稿した解説文。猪瀬自身がのちに発表した関連記事「小泉『新』首相に期待すること」(『週刊文春』2001年6月21日号初出)、「官僚『複合腐敗』は五十年周期で来る」(『文藝春秋』2000年5月号初出)。さらに、著作集編集委員の一人である鹿島茂氏との対談「知の“十種競技”選手として」など、多くの関連原稿や、雑誌・新聞に掲載された書評などを多数収録。
-
-英語のことわざを使いこなせば、英会話力アップにつながる! “ことわざ”と言われて、すぐに思いつくものは何ですか? 石の上にも三年? 犬も歩けば棒に当たる? ことわざと言っても、日本語なら日本語の、 英語なら英語のことわざといったように、表現の仕方は各国さまざま。 ことわざというものは、庶民の暮らしの中から生まれた知恵を 短く、的確にしたものなので、違う国でも驚くほど似ているものもあれば、 自国の常識や習慣とはまったく異なることわざも存在します。 英語のことわざだと、一番有名なものは「郷に入っては郷に従え」でしょうか。 さて、英語で言えますか? 自分の生まれ育った社会のことわざを勉強するのも楽しいですが、 英会話力アップを視野に入れて、英語のことわざにも目を向けてみましょう。 ほかの国のことわざを覚えるということは、言葉だけでなく、 その国の社会や文化、考え方や歴史などをさらに深く理解することにもつながります。 本書では、暗記するだけでなく、実際に使用することを目的として、 具体的な例文をたくさん挙げながら、その解説を行っています。 英語のことわざを実際に使いこなせるようになれば、 英語表現のバリエーションも確実に広がることでしょう! ▼目次 第1章 物事を後回しにするな 第2章 中身で判断・理解せよ 第3章 諦めない・後悔しない 第4章 コツコツと努力しなさい 第5章 行動で示しなさい 第6章 勇気づける・励ます・静観する 第7章 生活習慣・態度に気をつけなさい 第8章 忠告・アドバイスする 第9章 その他のことわざ ▼著者紹介 ジリアン・ヨーク (Jillian Yorke) 英国出身、滞日歴32年。経済産業省の英文校閲、 「ニューズウィーク日本版」の和文校閲、日本経済交流財団編集員を務める。 翻訳、編集、文筆、コンサルタントなど、幅広く活躍。 訳書に『構造改革の真実竹中平蔵大臣日誌』の英語版、 共著に『英語で文通しませんか』(きこ書房)、『グローバル・エリート』(IBCパブリッシング)など。
-
3.0800円 (税込)〔週刊エコノミスト臨時増刊目次〕4月8日号 2 〔マーケットと投資〕株価が上がるこれだけの理由 上がった株、上がる株(その1)=和島英樹/株価が上がるこれだけの理由 上がった株、上がる株(その2止)=和島英樹 5 株価見通し/1 TOPIXは年内に1100ポイントへ(日経平均換算で1万3000円)=キャシー・松井 13 株価見通し/2 次のステージは構造改革の成否が焦点に=丸山俊 14 株価見通し/3 6月がピーク 1万4000円も=菊池真 15 発掘! 中小型株 5期連続増益企業80社の実力=伊藤歩 16 Q&A 信用取引 入門と応用 株高の一因に=大山弘子 24 最近の注目投信 オプションを組み込んだ複雑な商品も=篠田尚子 30 2012年に人気だった投信 資金流入額は大幅減=篠田尚子 33 優待+配当の利回りに注目! おトク度チェック=大山弘子 36 誌上匿名座談会 企業業績がついてこなければ期待は裏切られる 40 証券税制 税率20%に引き上げ 日本版ISA導入=横山渉 44 為替見通し/1 夏場に円高に振れた後、年内100円超=塚田常雅 47 為替見通し/2 政策期待による円安から景気回復による円安へ=亀岡裕次 48 為替見通し/3 いったんは調整するが、その後円安が続く3つの理由=斎藤裕司 49 賢い外貨投資 ここを見れば「行き過ぎた円安・円高」がわかる=竹中正治 50 REIT 高値づかみを避けるためには=関大介 54 地価見通し/1 東京都心部で10~20%程度の上昇地点も=石澤卓志 58 地価見通し/2 2年間は上昇、消費税引き上げ終了後は下落=望月政広 59 〔円安、株高いつまで〕インタビュー 嘉悦大学教授・高橋洋一 80兆円金融緩和で2%インフレ可能(その1)/インタビュー 嘉悦大学教授・高橋洋一 80兆円金融緩和で2%インフレ可能(その2止) 60 新日銀総裁・副総裁のデフレ脱却本気度を探る=片岡剛士 68 「日銀は変わった」そう思わせればデフレ脱却できる=安達誠司 71 なぜ、日本株の回復は遅いのか 長期上昇のための処方箋=藤戸則弘 74 国内機関投資家が動かない理由 動き出す条件=櫻井祐記 77 「通貨競争は近隣窮乏化をもたらす」という大いなる誤解=若田部昌澄 80 世界景気/1 米国 住宅市場回復、シェール革命だが、楽観は禁物=小野亮 84 世界景気/2 中国 失速免れ、今年は8%台成長へ=李雪連 87 世界景気/3 欧州 成長は鈍いが最悪シナリオは免れた=伊藤さゆり 90 〔デフレ不況〕乗り切った高橋是清蔵相のリフレ政策=中村宗悦 94 IT革新がもたらす構造変化に既存のマクロ政策は無力=室田泰弘 100 〔女性と投信〕女性が投資を始める時 6人の体験談=大山弘子 104 〔インフレ局面の借金&投資〕金利上昇時代に住宅ローンで気をつけること=竹下さくら 108 最新マンション価格動向 新築、中古とも高止まり=中山登志朗 114 金利は本当に上がるのか アベノミクスでも低下=佐野一彦 117 上手な資産運用 インフレに強い金融商品=服部哲也 120 2%インフレで何が起こる? 家計へのアドバイス=竹中正治
-
3.7「残業しなくても儲かる」理由 SCSK「働き方改革」の舞台裏 長時間労働が常態化しているIT業界において、大手システム開発会社のSCSKは「働き方改革」の先進企業として知られる。2011年6月に中堅の住商情報システム(SCS)とCSKの中堅2社が経営統合して誕生した同社は月平均残業時間が20時間以下を達成。しかも発足以来5期連続増収増益を記録。直近の2016年度(2017年3月期)には、本業の儲けを示す営業利益率が優良企業の目安とされる10%を超えるなど、M&A(合併・買収)の失敗例が多いIT業界では数少ない例外となっている。 SCSKの高い利益率を支えているのは、赤字案件を減らすための各種施策であり、そのための構造改革・意識改革である。赤字案件を撲滅するためには、仕事の「質」、すなわち「業務クオリティ」を高めるしかないとの信念に基づき、仕事のやり方や社員の意識を徹底的に変革した。業務クオリティを向上させるために、標準化や見える化をはじめとする様々な仕組みを整備すると共に、経営からライン職、現場に至る全社員の意識改革に取り組んだ。しかも、その取り組みを6年間、粘り強く愚直に継続した。 SCSKの「働き方改革」の舞台裏にあった、知られざる業務クオリティ向上への取り組みを追った。
-
3.7経営共創基盤 代表取締役CEO 冨山和彦氏 推薦 「電力システム改革は、電力業界の構造改革に留まらない。業界の枠を超えた新たな産業創出と次世代エネルギービジネスに関心を持つあらゆる人にとって必読者となる一冊。電力システム改革の近未来像がここにある」 エネルギー問題に関心がある読者向けに専門情報をコンパクトにまとめました。 業界第一線の専門家がタッグを組み電力自由化の先を見すえ、エネルギー問題を取り巻く外的要因から最新技術の動向を踏まえて、2050年のエネルギーのあり方を予測。 人口減少や電力自由化、デジタル化、分散型発電などが進むことで、電力はどのように変わるのかを利用者側、事業者側の双方の観点から解説しており、今後の原子力発電のあり方についても言及しています。 エネルギー関連の研究者や実務家には役立つ最新情報が含まれるほか、エネルギーを軸に新たなビジネスや起業の機会をうかがう読者にも企画立案の参考にもなる一冊です。
-
-言語や民族が異なる28の巨大な連合体「EU」(欧州連合)。GDP全体では米国をしのぐ世界最大の経済圏でありながら、経済は低空飛行を続けている。ギリシャ問題は当面の危機をしのいだものの、独・英・仏のリーダー3国もそれぞれの国内事情を抱えている。ましてやギリシャ、スペイン、イタリア、ポルトガルといった南欧諸国との格差は、EU協調にどのような影響を及ぼすのか。 また、経済だけでなく15年1月に起こった、フランスの週刊新聞「シャルリー・エブド」へのテロ事件も記憶に新しい。宗教や民族間の共存は可能なのか。逆に混迷を深めるのか。 本誌では現地ルポを交え、欧州の今を読み解く。 ・経済優等生のドイツですら、国民の20.3%が貧困状態。 ・フランス企業の競争力を阻害し、若者の4人に1人が職に就けない現実の背景とは。 ・英国の政治家・知識人の主張と国民感情との間に大きな隔たり ・フィンランド/ノキアの経営失速の衝撃をきっかけに始まった世界最大級のベンチャーイベントとは 本誌は『週刊東洋経済』2015年3月7日号掲載の46ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【フランス現地報告】革命の精神はどこへ・揺らぐ「自由・平等・博愛」 【INTERVIEW】 同志社大学教授 内藤正典 PART1(基本編) 世界一よくわかる欧州事情 細野真宏氏が解説 欧州で何が起こっているの? 図解 一目でわかるEU PART2(国別編) 欧州各国それぞれの危機 【ドイツ】EU優等生の孤独と苦悩 歴史的好況に沸く優等生の内憂外患 【INTERVIEW】ダイムラー会長 ディーター・ツェッチェ 構造改革の光と影 5人に1人が貧困 【フランス】問われる構造改革の本気度 【INTERVIEW】 フランスは「ヨーロッパの病人」ですか? アクサグループ チーフエコノミスト・エリック・シャネイ フランス国立統計経済研究所 景気分析部門ヘッド・ローラン・クラベル (特別寄稿)EUに見た夢は遠くなりにけり 北海道大学教授 遠藤 乾 【英国】 選挙後、「EU離脱」シナリオの現実味 【スコットランド】 独立できなくても自治は進む PART3(テーマ編) 明日の欧州を読み解く 【南北格差】南欧諸国は復活するのか 【ギリシャ】 反緊縮で挙国一致 【スペイン】 危機に終止符も反緊縮政党が台頭 【アイルランド】危機早期克服も緊縮不満は増加中 【ポルトガル】 14年に支援卒業・汚職、脱税は深刻 【イタリア】 不況克服は道半ば 【北欧】小国フィンランドで芽吹く起業家精神 【INTERVIEW】駐日フィンランド大使 マヌ・ヴィルタモ 【相場展望インタビュー】どうなる為替、株、債券 為替 シティバンク銀行 尾河眞樹 債権 みずほ証券 金子良介 株式 UBS証券 中窪文男 【金融】ギリシャ危機は日欧銀行に飛び火 【INTERVIEW】欧州ブリューゲル研究所 ニコラ・ヴェロン 【メディア】襲撃事件に震撼!? 欧州メディアの今 (コラム)フリーペーパーに押される仏日刊紙
-
3.0大相撲の制度を経済学的視点から解き、これらの制度が揺らいできている点を指摘。不足する年寄株、転職に悩む力士など、日本経済が抱える問題の縮図がそこにある。 【主な内容】 序 章 大相撲を経済学の視点で眺めること 第1章 力士は会社人間 第2章 力士は能力給か 第3章 年寄株は年金証書 第4章 力士をやめたら何になる? 第5章 相撲部屋の経済学 第6章 いわゆる「八百長」について 第7章 一代年寄は得か損か 第8章 外国人力士の問題 第9章 横綱審議会の謎 第10章 特殊なチケット販売制度 第11章 角界の構造改革 第12章 大相撲から見る日本経済
-
4.0コンビニのお弁当づくりに世界一の情熱を捧げるファミマの専務が、 セブン‐イレブン・ジャパンを経て、コリアセブンを大改革、 ローソンを買収して、まったくおにぎりを食べる文化のなかった 韓国人のライフスタイルを変えてしまった! 【著者紹介】 本多 利範 (ほんだとしのり) 1949年神奈川県生まれ。明治大学政治経済学部卒業。1977年(株)セブン‐イレブン・ジャパン入社。 1998年ロッテグループ専務取締役として、経営危機にあった韓国セブン‐イレブンの再建に招かれ、 2001年に黒字化、店舗数を130店から1500店まで増やす。2003年(株)スギ薬局専務取締役。 2005年ラオックス(株)代表取締役社長兼営業本部長。 2008年(株)エーエム・ピーエム・ジャパン副社長執行役員、2009年同社代表取締役社長。 赤字体質からの脱却を目標に収益改善をし、ファミリーマートへの売却の道筋をつける。 2010年(株)ファミリーマート常務執行役員、2015年同社取締役専務執行役員・商品本部長(兼) 物流・品質管理本部長。中食構造改革委員長としてフードのリニューアルを手掛けると同時に、 コンビニエンスストアと薬局、スーパーマーケットなど、異業種との一体型店舗などをつくりあげる。 【目次】 第一章◆コリアセブン 第二章◆フードを美味しくせよ 第三章◆おにぎり革命 第四章◆ローソン買収 第五章◆新スーパー、ロッテレモンの誕生 第六章◆食文化とコンビニエンスストア 第七章◆韓国流通に吹く風 第八章◆仕事をするということ
-
-611円 (税込)トヨタ“歴史的”勝利の全貌 Photo Clipping from 24 Hours of Le Mans 2018 目次 中嶋一貴 呪縛からの解放─ LMP1 TOYOTA “責め”て拓いた栄光への道 Data & Analysis Privateers “無理ゲー”の内幕。 Engineer’s Eye このレースの未来はどこだ? WEC富士にル・マンウイナー凱旋! TOYOTA TS050 HYBRID 17→18年技術ハイライト サルトの新皇帝。 LMP1プライベーターマシン解剖 デザイナーの“構造改革特区” LMGTE Pro Race Analysis Duel, Duel, Duel!! [LMGTE]開発トレンド&ディテールCHECK LMP2 Race Review 奇妙なギャップ 日本人かく闘えり! [2018年版] ル・マン・マニアックス 2018年出場全車総覧 勝手に査定! LMGTEの「ワークス度」 A.デイビッドソンが明かすトヨタ6人の「知られざる素顔」 機能美&個性の60ガレージ総覧 42歳からの世界制服 King of Am ポール・ダラ・ラナのポリシー ロマン・ルシノフに「24の質問」 リザルト&データ BMW TEAM MTEK Factory Tour 読者プレゼント 特別付録 両面ポスター 裏表紙
-
4.0
-
-いま大胆に変わらなければ、 日本は浮かび上がれない! ジャーナリスト田原総一郎とコーポレイトガバナンスに詳しい国際企業弁護士・牛島信による、日本再生「最終提言」! 「年功序列、終身雇用をやめるべき。日本的経営を抜本的に構造改革すべきだ」(田原) 「経団連トップ企業でも、PBR1倍未満の会社が4分の3もある。改革には相当強引な覚悟と力が必要だ」(牛島) などなど、日本再生を願う〝激しく熱い″思いが飛び交う。 【目次】 第1章 どうして日本は衰退の道をたどったのか 第2章 企業は変革できるのか 第3章 社会の「富」は会社が生み出す 第4章 会社が変わるとき、日本が蘇る
-
4.0最大の政治団体、家族と国家による暴力。 日々、私たちはそれに抵抗している。 家族は、以心伝心ではなく同床異夢。 DV、虐待、性犯罪。最も身近な「家族」ほど暴力的な存在はない。 イエは「国家のミニチュア」に陥りやすいのだ。その中で、私たちは日々格闘している。いわんや、被害の当事者は闘い続けている。 絶え間ない加害に対し、被害者がとる愛想笑いも自虐も、実はサバイバルを超えたレジスタンスなのだ。 エスケープでもサバイバルでも、レリジエンスでもない。 私たちはレジスタンスとして、加害者に後ろめたさを抱かせる――。 被害を認知することは服従ではなく抵抗だ ■家族は無法地帯である ■愛情交換という暴力 ■家族における暴力の連鎖は権力による抑圧委譲 ■報道では虐待だけが選ばれて強調される ■殴られれば、誰もがDV被害者と自覚するわけではない ■被害者は不幸の比較を犯してしまう ■父のDV目撃が息子をDV加害者に陥らせる ■被害者支援に加害者へのアプローチは必須だ ■彼らの暴力は否定するが人格は尊重する 【目次】 まえがき――母の増殖が止まらない 第一部 家族という政治 第一章 母と息子とナショナリズム 第二章 家族は再生するのか――加害・被害の果てに 第三章 DV支援と虐待支援のハレーション 第四章 面前DVという用語が生んだもの 第五章 「DV」という政治問題 第六章 家族の構造改革 第二部 家族のレジスタンス 第一章 被害者の不幸の比較をどう防ぐか 第二章 加害者と被害者が出会う意味 第三章 加害者アプローチこそ被害者支援 第四章 レジリエンスからレジスタンへ 第五章 心に砦を築きなおす あとがき 主要参考文献一覧
-
-「日本の近代」をテーマにセレクトした猪瀬直樹著作集全16巻を待望の電子合本化! 日本をアップデートするヒントがここにある! ノンフィクション分野で多くの優れた作品を残し、現在も精力的に執筆を続ける作家・猪瀬直樹の作品から、若き日に心血を注いできた「日本の近代」をテーマにセレクトした猪瀬直樹著作集。書籍版12巻+電子オリジナル版4巻、計16巻を待望の電子合本化。 昭和から平成へと移りゆくなかで猪瀬作品がどのように位置づけられてきたのかをあらためて概観でき、いまに続く日本の課題が見えてくる! 〈収録作品〉 第1巻 構造改革とはなにか 新篇 日本国の研究 第2巻 ペルソナ 三島由紀夫伝 第3巻 マガジン青春譜 川端康成と大宅壮一 第4巻 ピカレスク 太宰治伝 第5巻 ミカドの肖像 第6巻 土地の神話 第7巻 欲望のメディア 第8巻 日本人はなぜ戦争をしたか 昭和16年夏の敗戦 第9巻 唱歌誕生 ふるさとを創った男 第10巻 天皇の影法師 第11巻 日本凡人伝 第12巻 黒船の世紀 ガイアツと日米未来戦記 第13巻 道路の権力 第14巻 道路の決着 第15巻 二宮金次郎はなぜ薪を背負っているのか? 人口減少社会の成長戦略 第16巻 ジミーの誕生日 アメリカが天皇明仁に刻んだ「死の暗号」
-
4.3ビジネスの変化に対応する情報システムの構造改革! 昨今、アーキテクチャなき情報システム構築がビジネスの足かせとなっています。この問題を解決するためには、まず企業情報システムにおける「アーキテクチャ」とは何かを理解することが必要です。産業構造審議会報告などをはじめ、政府および産業界からも、情報アーキテクトの養成が強く要望されています。 本書は、アーキテクチャの概念の全体像を、体系的に基本から解説します。企業情報システムと、情報システムの粒度の相違からくる視点の相違を明らかにし、現在の情報システムが抱える問題をアーキテクチャの観点から解決に導きます。著者の実務経験および研究者としての経験を生かし、単なる知識のための本ではなく、現場で役立つ実務遂行能力を培います。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。 【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
4.3本気で変えたい覚悟のある経営者に捧ぐ。 企業変革(チェンジ・マネジメント)は、経営者に求められる根本的な仕事であり、このために経営者が存在するといってもよい。著者は、マッキンゼー出身で20年にわたり、多様な業界で次世代成長戦略、全社構造改革のプロジェクトにかかわってきた。現在は、ビジネススクールで教鞭をとりつつ、ファーストリテイリングや日本電産をはじめ、日本を代表する各企業のアドバイザーや、30を超える企業での次世代経営者育成にかかわっている。本書では、著者による数多くの変革の経験を踏まえ、内外企業の事例を挙げながら、変革の方法を説いた、著者の仕事の集大成ともいえる一冊。今、なぜ変革なのか(Why)、という意識作りに始まり、企業変革の代表的モデルの解説(What)、変革へのアプローチ(How)、そして、変革者(チェンジリリーダー)になるための条件(Who)を説いていく。V字回復やカリスマ依存ではない、企業の体質改善と、持続的な成長エンジンを組み込むことが最終目標である。
-
-新興市場が急騰。新政権の誕生で、経済のデジタル化や構造改革への期待が高まっている。 ※2020年11月10日号の特集「急伸!中小型株」を電子書籍にしたものです。
-
4.1
-
5.0大学入試で日本史を選択する受験生、必読! 「大学入試の日本史は、教科書改訂時の新記述、加筆部分から出題されるケースが非常に多い」。その分析の元、東大合格請負人、カリスマ日本史講師の野島博之が教科書『詳説日本史B』(山川出版社)の改訂時の新記述、加筆部分を徹底研究。37個のキーワードを抽出し、解説しています。難関大学入試突破の武器になる、最強のデジタル参考書。入試には、絶対ここが出る! 大人の学び直しの教養書としても! 【目次】はじめに/総論/この本の使い方/【1】大王宮/【2】藤原京/【3】遣唐使の廃止/【4】郡司と受領/【5】鎌倉時代の裁判/【6】年紀法/【7】建武式目/【8】荘園などの代官/【9】一揆/【10】徳政一揆/【11】中世の貨幣・商業・流通/【12】貫高制/【13】家康の外交的意図/【14】江戸幕府が形成した外交秩序/【15】朝鮮使節/【16】享保の改革/【17】寛政の改革/【18】内憂外患/【19】朝廷権威の浮上/【20】幕末の科学技術と文化/【21】大正政変/【22】明治憲法体制の特質/【23】総力戦の影響/【24】二十一カ条の要求/【25】山東省旧ドイツ権益問題/【26】在華紡/【27】大隈伯後援会・小選挙区制/【28】パリ講和会議/【29】関東大震災/【30】市民文化/【31】石橋湛山/【32】日本資本主義論争/【33】朝鮮戦争/【34】ブレトン=ウッズ体制/【35】企業集団/【36】ブレトン=ウッズ体制の崩壊/【37】小泉構造改革
-
-横並びで単純な量的拡大競争に集中するような銀行のビジネスモデルは限界に近づいている。高成長時代はとうの昔。経済が成熟して資金需要が低迷する一方、銀行には依然として預金が流入し続けている。同時に、日銀の金融緩和は出口が見えず、市場金利はズルズルと低下。少子高齢化で人口が減少し、企業数も減り続ける。デジタル化対応も喫緊の課題だ。こうした銀行業界が直面する難題へ構造改革は避けて通れない。人事面でも、もはや年功主義は限界に達し、早期登用、一般職廃止、副業解禁などが動き出している。銀行はどう戦っていくのか。それは銀行員たちが岐路に立たされていることも意味する。苦闘する銀行、そして銀行員の未来を検証する。 本誌は『週刊東洋経済』2019年6月22日号掲載の27ページ分を電子化したものです。
-
4.0日本の銀行業界は、「収益減少トレンド」に歯止めが掛からず、大きな岐路に立たされている。メガバンクは大規模な人員削減を発表し、デジタライゼーションを進めて事業構造改革に乗り出すとしているが、いまだ未来は見通せない。エリートだった銀行員は、今や過剰なノルマに呻吟している。 それはメガバンクに限ったことではない。地銀はさらに苦しい状況に追い込まれ、現場では、行員たちの転職希望者が続出している。 果たして、日本の銀行は生き残っていけるのか。 そして、40万人以上といわれる銀行員たちはどうなっていくのか。 カギは、異動を減らし、地域密着で経営難から立ち直り、りそな銀行以上の利益を上げているスウェーデンの銀行にある。 本書は、緻密な取材を重ねている筆者が、現場の実情を踏まえたうえで、今後、日本の銀行業界が向かうべき道筋を提言する1冊である。
-
5.0パックス・トクガワーナ(徳川の平和)は、なぜ二五〇年の長きにわたり続いたのか。江戸開府前史から黒船来航前夜まで、江戸への造詣の深さでは人後に落ちぬ二人が、世界史的視野から縦横に語り合う。従来の江戸時代観を一新する刺激に満ちた対論。『江戸の構造改革』改題。
-
3.0垂直統合型から水平分業型へ。専用品から汎用品へ――。グローバル競争が激化する半導体業界において、ドラスチックな構造改革が起こっています。半導体産業の未来は明るい。ただし、その勝者になるためには、新たな時代の価値観への対応が急務です。半導体産業の地殻変動に対峙するには何をなすべきなのでしょうか。電子部品の流通革命を起こしたチップワンストップ代表・高乗正行が半導体産業の未来図を描きます。 【主な特長】 ◆半導体業界の構造変化から、電子部品流通に問われる抜本的な変革まで、半導体の将来像を描く渾身の書き下ろし! ◆「デジタルライフ」「半導体産業」「半導体流通」「顧客視点」の4つの観点から、データも含めてグローバリゼーションを詳説! ◆ニッポンのモノづくりを支えてきた“ミスター半導体”牧本次生氏、ザインエレクトロニクスの飯塚哲哉氏、元ソニー副会長の森尾稔氏、ミスミ創業者の田口弘氏の4 名の功労者による「未来展望」も特別収録!
-
4.2格差拡大、雇用不安、デフレ、グローバリズムの停滞……。「構造改革」以降、実感なき好景気と乱高下する日本経済。過剰な貨幣発行がもたらす問題、「複雑な“経済現象”」と「理論重視の“経済学”」の乖離など、現代資本主義が直面する困難を徹底的に検証。 アダム・スミスから金融理論、リーマンショックからアベノミクスまで、経済学の限界と誤謬を提示する。 内容抜粋 「経済学」がひとつの思想でありイデオロギーであるとすれば、今日の支配的な経済学の考え方とは異なった「経済」についての見方はできないか。「稀少な資源の配分をめぐる科学」というような経済学の典型的な思考方法ではない、別の思考様式はないのか、ということだ。―――学術文庫版「はじめに」より 目次 学術文庫版「はじめに」 第1章 失われた二〇年――構造改革はなぜ失敗したのか 学術文庫付論 第2章 グローバル資本主義の危機――リーマン・ショックからEU危機へ 学術文庫付論 第3章 変容する資本主義――リスクを管理できない金融経済 第4章 「経済学」の犯罪――グローバル危機をもたらした市場中心主義 第5章 アダム・スミスを再考する――市場主義の源流にあるもの 第6章 「国力」をめぐる経済学の争い――金融グローバリズムをめぐって 第7章 ケインズ経済学の真の意味――「貨幣」の経済学へ向けて 第8章 「貨幣」という過剰なるもの――「稀少性」の経済から「過剰性」の経済へ 第9章 「脱成長主義」へ向けて――現代文明の転換の試み あとがき――ひとつの回想 学術文庫版あとがき 2012年刊行、講談社現代新書『経済学の犯罪』を改題、 大幅加筆修正したものです
-
-日本はいかに「外圧」と対峙してきたのか。発掘、日米交渉秘史、日米戦後史の真実!自身も交渉官として日米交渉の最前線に立った著者が、大戦後の日米の経済交渉の歴史をひも解きながら、超大国・アメリカの思惑と日本の外交戦略を解説。水面下で繰り広げられる日米両国のせめぎ合い、そこに日米関係の真の姿が見えてくる!第1章 戦後日本の形を決めたアメリカの占領政策とは 第2章 日本独立、変動相場制に至る日米交渉の内幕 第3章 オイルショックへの世界と日本の対応 第4章 戦後初、日米二国間の経済交渉がもたらした自由化への波 第5章 市場介入に舵を切ったアメリカとのプラザ合意、ルーブル合意 第6章 日本の構造改革を要求しはじめたアメリカとのせめぎ合い 第7章 最後まで日本の首相が「ノー」と言った日米包括協議 第8章 円高・ドル安是正へ向けた日米協調介入の舞台裏 第9章 アジア通貨危機における「IMF・アメリカ」対「日本」のかけひき 第10章 アジア通貨基金構想をめぐるアメリカとの攻防 第11章 イラク戦争から異次元緩和まで、円ドルレートに対する日米の動き 第12章 独立国・日本の「在日米軍」という矛盾 第13章 アメリカの変質と新しい日米関係をつくるチャンス
-
-日本経済の完全復活のためには、生産性を高めるための構造改革が不可欠です。小泉政権下でも、さまざまな「構造改革」がなされましたが、安定成長の軌道に乗るためには、さらなる改革の継続が必要です。本書では、日本経済がこれからも成長を続けてるために必要な、労働市場改革、社会保障改革、教育改革を具体的に解説し、さらに、改革後の日本は、アメリカ型でもスウェーデン型でもなく、カナダ型の「健全な市場社会」をめざすべきであると提言します。著者の八代尚宏教授は、これまでにも規制改革・社会保障の分野で積極的に政策提言をしており、これらの分野では第一人者といってもよいでしょう。2006年秋からは、経済財政諮問会議議員に就任し、安倍政権のブレーンとして、経済政策の舵取りを行っていました。
-
4.0日本再生のカギは芸術文化立国をめざすところにある! 著者は人気劇作家・演出家として日本各地をまわり、また芸術文化行政について活発に発言する論客として知られる。精神の健康、経済再生、教育等の面から、日本人に今、いかに芸術が必要か、文化予算はどう使われるべきかを、体験とデータをもとに緻密に論証する。真に実効性のある芸術文化政策を提言する画期的なヴィジョンの書。これは芸術の観点から考えた構造改革だ! 第7回AICT(国際演劇評論家協会)演劇評論賞受賞作。【目次】まえがき/序章 芸術の公共性とは何か/第一章 地域における芸術文化行政/第二章 経済的側面から見た芸術文化行政/第三章 教育と芸術文化行政/第四章 文化権の確立/第五章 文化行政の未来/終章 芸術の未来/あとがき
-
-プロレスおたくの仲間のために披露宴でリングをつくって試合をしちゃう職場って…。 人がやめない会社はみ~んな大家族主義経営だった! 「人がいない!」 少し前は、「人がいても人財がいない」という意味でしたが、 今は日本全国で、「人そのものがいない」という悲鳴が聞こえます。 離職率が高い企業は、人手不足倒産の危機を迎えています。 社員がやめてしまうと、次の人をなかなか採用できないのです。 こう言うと、「では、採用をうまくいかせるためにはどうしたらいいのか?」 という議論になりがちです。しかし当たり前の話ですが、重要なのは 「採用をうまくいかせること」ではなく、「人のやめない職場をつくること」です。 やめなければ、補充採用の必要はありません。 しかも人がやめない職場には一体感があり、組織全体に高いモチベーションがあります。 では、どんな職場であれば、人がやめないのか。 ■目次 ・第1部 温かくて泣ける19の職場の物語 家族の絆は切っても切れない縁 おせっかいは愛“シンコーメタリコン” 人は変われます 受け止めてくれる仲間がいれば“ヒーリング・ハンド” ダメな人間はいない、ダメな指導者がいるだけだ モノもヒトも再生します!“こんの” ほか ・第2部 月ワク企業のつくり方 「大家族主義経営」実現の9カ条 ぬくもり朝礼と6SS活動を実施する 理念型採用と理念型評価制度を行う 自己開示と意思決定尊重の風土をつくる 「めだかの学校」を採用する ESアンケートを定期的に取る ほか ■著者 角田識之 臥龍。1956年愛媛県・松山市生まれ。大手コンサルティング会社で経営コンサルタントの経験を積み、1987年独立。 1989年(株)ハイネット設立、1997年(株)ハイネット・コンサルティング、2010年(株)角田識之事務所に社名変更。 同社の代表として、構造改革という環境変化に的確に対応した数々の「第二創業の実現」を指導し、大好評を博している。 また「文明800年周期説」に基づく東洋ルネッサンスの旗手の一人として、「人本主義」による “感動経営”及び“セーブ&エンジェイ”を共通の指針とした事業家ネットワーク「APRA」による、 アジア太平洋各国との架け橋創りとしても東奔西走している (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
3.7
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 マクロ経済学はその姿を一変させ、今や新古典派理論の全盛となり、アメリカを中心とする学界もそれを「進歩」として支持する。著者はこれに断固として反対し、過去二五年間のマクロ経済学を批判的に検討し、理論の基礎をケインズの天才が見抜いた需要不足(=有効需要)に据えて、新しいマクロ経済学を試みる。中級レベルの学習のための道先案内を務める本書を通して、読者は実際的で豊かな可能性に満ちたマクロ経済学を見出すに違いない。 【目次より】 まえがき 図表一覧 序論 1 マクロ経済学の「新古典派化」 2 「新しい」ケインズ経済学 3 新しいマクロ経済学を求めて 景気循環の理論 1 Ramseyモデル 2 リアル・ピジネス・サイクル理論 3 ケインズ的アプローチ 4 金融政策と景気循環 経済成長論 1 Old Growth Theory 2 New Growth Theory 内生的成長モデル 3 経済格差の縮小 新しいマクロ経済学 1 価格と数量 2 生産要素の「不完全雇用」と生産性の部門間不均等 3 ルイス・モデル 4 需要と経済成長 5 残された課題 オープン・エンド TFPと技術進歩の需要創出効果 技術進歩はいかにして生み出されるのか 技術進歩と不完全雇用 4章付論 文献表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 吉川 洋 1951年生まれ。経済学者。東京大学名誉教授、立正大学学長。東京大学経済学部経済学科卒業、米国イェール大学にて同大学より博士号 (Ph.D.) 取得。専門は、マクロ経済学、日本経済論。 著書に、『マクロ経済学研究』『日本経済とマクロ経済学』『ケインズ 時代と経済学』『マクロ経済学』『高度成長 日本を変えた6000日』『転換期の日本経済』『現代マクロ経済学』 『構造改革と日本経済』『いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ』『デフレーション “日本の慢性病”の全貌を解明する』『人口と日本経済 長寿、イノベーション、経済成長』など多数ある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 小泉政権では、官邸主導で経済政策が決められた、という通説がある。本書では、不良債権処理、予算編成、税制改正の政策決定過程を分析し、この通説を批判的に検討するとともに、小泉・竹中両氏が、自らの理念に沿った経済政策をどの程度実現しえたかを検証する研究書。 【主な内容】 第1章 小泉改革は揺らぐことなく進んだのか――構造改革と官邸主導の政策決定 第2章 不良債権問題はいかにして解決されたのか――金融行政の政治学(1)政策過程 第3章 不良債権問題はいかにして解決されたのか――金融行政の政治学(2)分析 第4章 官邸主導の予算編成はどこまで実現したのか――予算編成の政治学 第5章 経済財諮問会議はなぜ税制改革に失敗したのか――税制改正の政治学 など。
-
4.0小泉家四代にわたる「血と骨」。「小泉純一郎はある時に化けた。進次郎は最初から化けている」。小泉構造改革とは何であったのか――。さまざまな論考が小泉政権当時から現在まである。その評価は歴史がなす。間違いなく言えることは、「郵政解散」に象徴される小泉純一郎総理の決然とした態度は、国民大衆が熱狂し望んだ絶対的宰相の姿である。現在、安倍政権に異議をなす「原発ゼロ」を生涯最後の仕事と意気軒昂に活動する小泉純一郎が触発されたのは、3・11後に精力的に毎月欠かさず被災地を訪れ、現場の声を復興策に盛り込もうとする次男・進次郎の政治家としての姿からではなかったのか。政界総力取材から浮き彫りにする小泉革命の深層。「オレの最後の仕事は、反原発だ! これに尽きる」 小泉純一郎「オヤジがやらなかったことを、わたしはする」 小泉進次郎
-
3.5日本の「失われた30年」は主流派経済学の処方箋を素直に実施した結果である。新古典派経済学による構造改革は低賃金の非正規労働者を増やし、ケインズ経済学による財政・金融およびリフレ政策は1000兆円を超える借金地獄をつくった。原因は貨幣システムの欠陥にある。主流派経済学やMMTの誤りを指摘し、現在の「債務貨幣」にかわる新たな貨幣システム「公共貨幣」を提唱。「公共貨幣」を取り戻せば「ゼロ成長」から脱却でき、新しい未来が開けることを論証する。
-
-本書は、1人1時間あたりの付加価値生産性を高めて、「高収益化」と「高賃金化」を一気に達成する方法を教える本です。 ▼ キーエンスの付加価値経営から学んだ、稼ぐ人と儲かる組織のつくり方 「世界的に見て、日本人の給与は低過ぎる」 「日本では、ここ30年間ほとんど賃金が上がっていない」 とよく言われますが、これは、今の日本社会における非常に深刻な問題と言わざるをえません。 その問題の原因は、いったいどこにあるのでしょうか? 結論から言うと、大きな原因の一つとして、日本の会社は「1人1時間あたりの付加価値生産性」が低いことが挙げられます。 給与を上げるには、最終的に「1人1時間あたりの付加価値生産性」を高め、会社として収益をアップさせることが必須条件となります。 しかし、それは容易なことではありません。 なぜなら、そのためには個々の社員、幹部クラスの人たち、そして経営者がそれぞれの立場で考え行動し、全社一丸となって取り組まなくてはならないからです。 決して個々の社員のみが、または経営者だけが頑張って実現できることではないのです。 そこで本書では、「1人1時間あたりの付加価値生産性」を高めるために何をしたらいいのかを、 ・個人やチームとして取り組むべきこと ・組織として構造改革しなければならないこと という両面から考えていきます。 「経営者の方々」にとっては、会社の高収益化と高賃金化の両方を達成するコンセプトと仕組みを学んでいただき、社員も自分自身も幸せになるために。 「会社で働くあなた」にとっては、もっと多くの給与をもらって、経済的にも精神的にも豊かな人生を送れるようになるために。 ぜひ、本書を役立てていただけたら幸いです。
-
3.3構造改革、財政再建=「病気のお年寄りは早く死んでください」!? 医療と介護の分断をただちに止めよ! 施行直後から大混乱が生じている後期高齢者医療制度。見直しの目途がいまだ立たないなか、財政再建の名の下に、今度は療養病床の大幅削減がひそかに実施されようとしている。十分なケアを受けられないまま行き場をなくす11万人の“医療難民”。まるで「病気のお年寄りは、無駄な医療費を使わずに早く死んでください」と言っているかのように……。いったいなぜなのか? 高齢者医療の難問に立ち向かってきた現場の医師と、医療制度改革に携わった元官僚が、「医療崩壊」が叫ばれる危機的な状況に一石を投じる。 【項目例】1章 「介護療養病床の廃止」問題とは何か/2章 「介護療養病床の廃止」になぜ反対なのか/3章 「医療・介護難民」を生じさせないために/4章 療養病床23万床削減決定の舞台裏/5章 後期高齢者医療制度の問題点etc.
-
-営業総力戦時代を迎えたいま、「営業の構造改革」を遂げ、収益を上げる企業に成長していくにはどうすればよいか、ズバリ指摘。営業総力戦の準備はできたか!
-
-
-
3.0トランプ大統領の米国、景気はどうなる? 中国「サプライサイドの構造改革」とは? 日銀・FRBの金融政策の行方は? Brexitと欧州経済の政治リスクとは? 世界経済を覆う「長期停滞」とは? FinTechは金融イノベーションにつながる? 2016年11月の米国大統領選挙でトランプ氏が当選したとき、東京市場では、大幅な円高・ドル安が進行し、日経平均株価は1000円を超す下落となった。その後は円安、株高となったとはいえ、「世界経済」がわが国に及ぼす影響の大きさを垣間見た瞬間だった。 このように、私たちの日常生活には、「世界経済」に関するニュースがあふれ、世界経済の動向が、ビジネスだけでなく個人の生活にも大きな影響を及ぼす。しかし、世界の状況はめまぐるしく変わり、複雑な要素が絡み合っていてニュースを見たり新聞を読んだりするだけではすぐには理解できないことが多い。 本書では、気鋭のエコノミストたちが、世界経済を理解するうえで必要な基礎知識をわかりやすく解説する。そして、これらの基礎知識を踏まえて、世界経済の展望を多面的に考察する。この1冊さえ読めば、世界経済に関する基礎知識を習得すると同時に、世界経済の展望が開けてくる。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●中国産業(20業種)のこれから5年の動きと日本企業へのインパクトを解明 2桁成長が終焉した中国、これから5年の実質GDP成長は6.5%が予測され、潜在成長力のさらなる低下、少子高齢化が一段と進むことが想定されます。そのなかで、中国政府はゾンビ企業整理、供給過剰削減、製造業高度化、国民生活向上といったサプライサイド構造改革に踏み切ることを公表しました。 本書では、中国の構造改革が日本企業に及ぼすインパクトとして、 (1)過剰生産(競争激化)、(2)資源需要拡大(競争激化)、(3)個人消費拡大、高度化(好機)、(4)医療・介護、省エネなど新たな活動領域の拡大(好機)、(5)中国企業の台頭(競争激化)の5点を指摘し、それぞれについて各産業での戦況を明らかにします。また、各項目は(1)産業の強みと弱み、(2)構造改革のインパクト、(3)日本企業に必要な対応から構成されます。 鉄鋼は供給過剰削減から高度化に進み日本企業との競争は激化する可能性大、化学産業はM&Aで一挙に機能化化学品にシフト、自動車市場には新エネ車の投入が必要など、その構造改革によって起きる変化を20産業を対象に解明し、その変化に日本企業はどう対応すべきかシナリオを示します。 日本企業の目線で中国のミクロ分析をする類書のない内容であり、豊富なデータを駆使したビジュアルな内容は資料としても価値がある。
-
4.5記者の視点を先取り! どこに着目するかで、世界の見え方が変わる。 日本経済新聞社を代表する編集委員・コメンテーターら、ベテランの専門記者が、日本と世界を取り巻くさまざまな論点と向き合い、大胆な予測を提示する。 2024年版は生成AI、グローバルサウス、相次ぐ重要選挙を特集テーマに、企業、日本経済、世界の未来について23の論点で解説。 【特集】 2024年を予測する3つのキーワード 論点1 生成AIが社会・経済に革命をもたらす 重大リスクへの対応が求められる 論点2 グローバルサウスの怒りが世界を揺らす ~米中新冷戦の勝敗も左右~ 論点3 相次ぐ重要選挙 民主主義に真の危機が迫るか Chapter 1 日本は豊かになれるのか ・日本の株式市場 日経平均株価のバブル超えあるか ・岸田財政は火の車 ~膨らむ支出、定まらぬ財源~ ・大幅拡充の新NISA 積極活用か尻込みかで資産の二極化が鮮明に ほか Chapter 2 世界企業の新常識とは ・ESGブームは去り成熟のときへ ・人手不足が迫る持続的な賃上げと構造改革 ・ビッグテックの覇権はまだ続くのか? 新スター台頭のチャンスは? ほか Chapter 3 対立深まる世界のゆくえ ・切迫する台湾有事 最悪の事態直視し、重層的備えを ・習政権に米欧から「覇権主義国家」の烙印、「2035戦略」に黄信号 ・終わり見えぬウクライナ侵攻 カギ握るプーチン体制の行方 ほか
-
4.2伝統的な商慣習を崩し、過剰なまでに構造改革を推し進め、TPP参加表明を始め様々な分野でアメリカの意向に迎合する日本人に対して警鐘を鳴らす、保守学者による国士的論考。
-
3.01巻550円 (税込)【WedgeONLINE PREMIUM】 最後の暗黒大陸・物流 「2024年問題」に光を灯せ【特別版】 トラック運送業界における残業規制強化に向けて1年を切った。「2024年問題」と呼ばれる。 しかし、トラック運送業界からは、必ずしも歓迎の声が聞こえてくるわけではない。 安い運賃を押し付けられたまま仕事量が減れば、その分収益も減るからだ。 われわれの生活を支える物流の「本丸」で、今何が起きているのか── 月刊誌『Wedge』2023年5月号(4月20日発売)の特集「最後の暗黒大陸・物流 「2024年問題」に光を灯せ」に同誌20年7月号(6月20日発売)の「DIGITAL TRANSFORMATION」(産業IT イノベーション事業本部産業デジタル企画部主席研究員・藤野 直明氏、コーポレートイノベーションコンサルティング部上級コンサルタント・梶野 真弘氏の記事を加えた特別版です。 PART 1 残業規制の導入で物流業界の体質改善はなるのか? 中西 享 ジャーナリスト PART 2 「お願いだから分かってほしい」 運送事業者の社長が激白 中西 享 ジャーナリスト 編集部 Interview 1 進み始めた荷主の意識変化 見えてきた「適正運賃への是正」 小寺康久 西濃運輸 代表取締役社長 ILLUSTRATION 私たちの生活に欠かせない物流 編集部 Interview 2 デジタル技術で課題解決 物流界のプラットフォーマー 佐々木太郎 Hacobu 代表取締役社長執行役員 CEO Interview 3 トラック物流に必要な構造改革とは何か? 矢野裕児 流通経済大学流通情報学部 教授 column 1 深刻なドライバー不足 それでも「明日届く」は必要なのか 関谷次博 神戸学院大学経済学部 教授 PART 3 物流の一翼担う倉庫 「結節点」で見たその実態 編集部 column 2 「当たり前」の舞台裏 水産卸売の現場を歩く 編集部 PART 4 荷役の負荷軽減へ 今度こそパレットの本格普及を 編集部 PART 5 宅配ドライバーの本音 働き方改革は「形骸化」するは 刈屋大輔 ジャーナリスト column 3 国の盛衰と物流は表裏一体 日本はイタリアの歴史に学べ 玉木俊明 京都産業大学経済学部 教授 PART 6 矛盾を内包した法体系を直視しドライバーの権利保護を 首藤若菜 立教大学経済学部 教授 REPORT DIGITAL TRANSFORMATION(藤野直明、梶野真弘、編集部) PART1 DXは目的ではなく手段 新しいビジネスモデルを描け PART2 「カイゼン」が遅らせたDX 製造業が問われるサービス作り
-
-
-
4.2
-
4.4
-
4.0維持・管理から活用・創造へ 収益性の高いビジネスを生む公共投資の形を提案する 高度成長期に整備された道路や建物などインフラ(社会資本・社会基盤)は今後、急速に老朽化が進む。適切に維持、修繕・補修、更新が行われないと、このままでは大きな事故につながる可能性も高い。 現に先進国のドイツでも老朽化した図書館が崩壊し、多数の負傷者が出たことがあるくらいなのだ。ところが、東日本大震災や原発事故の影響で、今の日本は、この問題に対処する体力がさらになくなってきている。 本書では今後インフラの更新とあわせて日本の国家戦略を担うインフラの構造改革(再構築・創造的破壊)をどう進めるべきかを提案する。また大震災を契機に、今後の公共投資のあり方についても一石を投じ、インフラ構造改革による市場・ビジネスに与える影響を明らかにしていく。
-
-高橋体制に移行してから2年。 「再生と成長」を掲げた中期経営計画は、 大幅赤字によって早くも雲散霧消した。 収益の短期的な改善に目を奪われ、 抜本的な構造改革を先送りしてきた経営の大罪が、 組織解体というかたちでシャープに降り掛かろうとしている。 『週刊ダイヤモンド』(2015年4月25日号)の 第2特集を電子化したものです。 雑誌のほかのコンテンツは含まれません。
-
5.02016年、かつて「液晶の雄」と呼ばれるも、液晶事業改革の失敗などにより債務超過に陥っていたシャープに、経営再建の任を受けてやってきた人物がいた。台湾の電子機器受託大手、鴻海(ホンハイ)精密工業の副総裁であった戴正呉である。 創業者・郭台銘とともに、鴻海を電子機器受託生産で世界最大規模の企業に成長させてきた戴は、シャープの社長就任後、わずか1年4カ月で東証1部へのスピード復帰を実現する。彼は何を思い、どのような経営手法でシャープ再生を実現してきたのか。 生い立ちと日本駐在、大同・鴻海での日々、鴻海がシャープへの出資を決めた理由、産業革新機構との出資争い、構造改革への挑戦、悲願の東証1部復帰、「ミスターコスト」の誕生秘話からM&Aの大原則、中国の資源をどう生かすか、そして日本の産業への展望まで。シャープ再建の立役者がいま初めて明かす、自伝的経営哲学。
-
3.5問題が起こると知りつつ何もしない。そもそも本気で変わろうとしていない。過去の成功体験にしがみつき、いつかは「神風」が吹くと根拠もなく楽観視。日本の組織に蔓延する「不作為の病」。決定力不足に悩むサッカー、人気凋落にあえぐ大相撲、既得権をめぐって混乱するプロ野球、ドタバタをくりかえすオリンピック代表選考。責任の所在はどこにあるのか。勝てるチームをつくりあげた名指導者たちの声に耳を傾け、考える。「伝統か改革か」はナンセンス! 「明日の勝者」になるために、スポーツから学ぶ組織改革の思考。 [内容紹介]日本にはびこる「不作為の病」/スポーツの「大政奉還」/「伝統」と「改革」は対立しない!/決断力と責任ある人材は生まれるか/リーダーが替われば組織は変わるのか/あるべき師弟関係とは/成功する女性リーダーの素顔/格闘技ブームはどこまで続くか/人材流出を防ぐ、人材確保を図る/日本の構造改革はスポーツから
-
4.5小泉純一郎、安倍晋三 ―― 偉業を達成できたのには「理由がある」。 日本を動かす首相を支え続ける“現代最高の知性”が 「目的達成のための最短ルート」を初めて明かす! ◎「なぜ戦うのか」という目線を忘れない ◎良質な「問い」を常に自分に投げる ◎勝つためにバルコニーに駆け上がる ◎チャンスを待て。だが決して時を待つな ◎情報源は「量」より「質」で選ぶ ◎悲観は気分。楽観は意志であると心得る ◎人生の本舞台は常に将来に在ると知る など、百戦錬磨の勝負師たちの知られざる戦術を網羅。 「外為どっとコム」超満員セミナー、完全書籍化。 【著者情報】 竹中 平蔵(たけなか へいぞう) 1951年、和歌山県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、日本開発銀行入行。大阪大学経済学部助教授、ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを経て、2001年より小泉内閣で経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣などを歴任。小泉内閣の「構造改革」を主導した。第2次安倍内閣では、「産業競争力会議」および「国家戦略特別区域諮問会議」メンバーとして活動。現在は、東洋大学グローバル・イノベーション学研究センター長・教授、慶應義塾大学名誉教授、株式会社パソナグループ 取締役会長、世界経済フォーラム(ダボス会議)理事、外為どっとコム総研首席研究理事などを兼任している。著書に『大変化 経済学が教える二〇二〇年の日本と世界』(PHP新書)、『400年の流れが2時間でざっとつかめる 教養としての日本経済史』(KADOKAWA)、『世界大変動と日本の復活 竹中教授の2020年・日本大転換プラン(講談社+α新書)』ほか多数。
-
-西暦2018年。20世紀末の構造改革に失敗した日本は経済破綻寸前で最後の巨大市場、中国東北部へ資本進出。シベリア独立への軍事支援と引き替えに大陸での利権を約束させるが……。
-
-日本人が未だかつて経験したことのない、長く深刻な不況。国民の購買意欲は冷え切り、回復の兆しさえ見えてこない。構造改革を旗印に歩み出した小泉内閣の改革はいっこうに進まないどころか、政・官・財の癒着が内閣の足元を脅かしている状態だ。一方、金融機関の不倒神話は完全に崩れ、有名企業が消費者を欺いていたことも明るみになり、国民の不信感は募るばかりだ。日本人は、なぜこのような体たらくを演じる国民になってしまったのだろうか。本書に収められている批評の多くは、昭和四十年代後半から五十年代半ばにかけて発表されたものであるが、著者は経済成長優先の反面、「日本的叡知」が失われつつあった時代にやがて現在のような事態が到来することを見事に予測していた。物質的には豊かである一方、精神的な貧困により迷走を続ける日本。今こそ著者のいう「日本的叡知」を取り戻すところに、この事態を打開する糸口が見出せるのではないだろうか。
-
4.41950年、大赤字・給料遅配・スト続きで苦しむ石川島重工業(現IHI)の社長に就任した土光氏は、「ミスター合理化」と呼ばれるほどの経営合理化で再建を果たす。その後、東京芝浦電気(現東芝)の社長に就任、さらに長年にわたり経済団体連合会会長などを務め、日本経済の発展に尽くした。また、81年、会長に就任した第二次臨時行政調査会では、国鉄の分割民営化や三公社の民営化で日本の構造改革を実現させ、「行革の鬼」との異名をとっている。しかし、その生活ぶりは質素で、潔い人生観もうかがえる。何ごとがあろうとも信念を貫き、大願を成就させた強い意志と行動力の源泉を、200篇の言葉で探る。政治や経済の仕組みが大きく変わろうとしているいま、土光氏の考え、発言は、これからの日本を考える上でも、大きな意味を持ってくるに違いない。
-
3.8不良債権処理とメガバンク再編の立役者、 知られざる真相を明かす。 100兆円規模の不良債権、銀行整理論、観光立国、 中小企業改革・・・すべて私が正しかった。 日本人が見たくない本質を突く提言をするから、 私は目の敵にされる。あらゆる論争に勝ってきた 伝説のアナリストはいったい何者か、全疑問が氷解する!
-
4.2昨今メディアを賑わせている集団安全保障、憲法改正論議には、現代日本をつくった「戦後の初発」という視点がすっぽりと抜け落ちている。日本の「戦後」とはいかにして始まったのか。実はそこには、大いなる欺瞞(ぎまん)が隠されていた。それを直視しない限り、ほんとうの憲法改正論議などできないのだ。本書では、戦後の始まりから平和憲法、構造改革からTPPに至るまで「戦後日本」を規定してきた「日米の非対称的な二重構造」を丹念に描き出す。なぜ、保守も革新も自ら進んでアメリカに追従してきたのか。なぜ、沖縄の基地はやめられないのか。なぜ、規制緩和の大合唱が起きるのか。それはわれわれが、意識している、いないにかかわらず、外交から政治・経済政策、言論に至るまで常にかの国の顔色を窺わなければならない「従属国家」だからである。だが、覇権争いとでも称すべき冷戦後の世界において、こうした「意識的/無意識的なアメリカ追従」はもはや最良の道ではなくなった。戦後70年間日本人が抱え続けてきたディレンマを鮮やかに切り取り、これから我々が進むべき方向を指し示す。現代を代表する思想家が放つ、待望の戦後論!
-
-現在の世界経済は、未曾有の低迷期に突入している。そして著者は、その低迷期間が10年の長きに及ぶと断定する。つまり、私たちは「10年不況」の世界を生きていることになる。そこでは、過去の世界恐慌やバブル崩壊の教訓は役に立たない。従来の学識や通念を捨て去り、21世紀型マネーの実態を直視し、大胆なパラダイム転換を断行しなければならない。本書は、現在の経済情勢をシビアに分析したうえで、小手先の経済政策ではなく、近未来を見据えた産業構造改革を提言する。この国を救う道は、そこにしかないのである。【目次】序章 経済学はもう役に立たない/第一章 世界はすでに「10年不況」に入った/第二章 それでもマネーは奔放に動く/第三章 「海外直接投資立国」へのパラダイム転換/おわりに
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【物流のキホンから業界が抱える課題まで、広くやさしく丁寧に解説!】 働き方改革によるドライバー不足(2024年問題)や燃料費高騰などの課題と向き合う「物流」の現場。“経済の血管”と例えられる物流事業を営む業界について、本書は儲けのしくみから、最新のビジネスモデルや課題まで幅広い情報を提供します。物流サービスを提供する企業への就転職を目指す方ばかりでなく、メーカーや小売などの事業会社で物流部門に配属された社員の方も対象としているため、「物流の入門書」としてもお読みいただけます。業界を俯瞰する客観的なデータの紹介だけでなく、物流業務に携わる者が身につけるべきキホン知識や経営戦略の視点まで、広くやさしく丁寧に解説します。 ■目次 ●Chapter 1 物流のきほん ●Chapter 2 移り変わる物流会社の役割 ●Chapter 3 物流担当者が知っておくべき基礎知識 ●Chapter 4 業態別の物流のしくみ ●Chapter 5 一歩先を行く物流業界の先進企業 ●Chapter 6 物流を支える最新技術 01 人力からITシステムへ「ロジスティクス4.0」 02 物流情報(ビッグデータ)を活用して業務改善を図る 03 物流センターの物品管理を効率化する倉庫管理システム 04 正確な配送計画の作成に役立つ輸配送管理システム 05 自動化が進む工場や倉庫での仕分け作業 06 保管効率と作業効率の向上を実現する立体自動倉庫 07 自動走行で作業者に物品を運ぶ運搬機器 08 商品管理やビッグデータ収集に活用されるIoT技術 09 人手不足が深刻化する物流業界での自動化・無人化を実現する取組み 10 次世代高速通信「5G」を超える「6G」 11 完全自動運転の実現を目指すトラック隊列走行 12 在庫管理などの無駄を無くす高精度の予測分析 13 最適な物流管理を行うAI技術 14 AI活用によるビッグデータ分析と人間の判断力の両立 15 事務作業に活用される情報システム 16 物流の効率化と高度化により装置産業化を図る 17 製造と物流が一体化した立体工業団地 18 業務の効率化や新サービスの開発にデータを一元管理して活用 19 標準化した業務をシステム化して物流の自動化や省人化につなげる ●Chapter 7 規制緩和と労働環境改善に向けた取組み 01 物流の重要項目である「輸配送」「倉庫」「労働」「環境」の法律 02 事業範囲の広い貨物運送事業の体系 03 1990年代の規制緩和による物流業界の構造改革 04 経営の厳しい貨物自動車運送事業者 05 労働環境の改善に向けた法改正と施策 06 労働時間法制の変更によって求められる物流の変革 07 荷主勧告制度は労働環境改善のための制度 08 働きやすい環境「ホワイト物流」を目指す ●Chapter 8 物流の現状の課題と将来の展望 01 産業構造の変化により物流ニーズが高度化 02 サービスは世界トップレベルだが対価の見直しが必要な日本の物流 03 人口構造の変化と業界の体質により深刻化するドライバー不足 04 宅配便の小口配送の増加とトラックへの荷積み効率の低下 05 生活を豊かにする通信販売の成長と配送技術の進化 06 物流の遠隔操作などにより働きやすい環境を実現 07 これまでの物流業務から脱却して発展性のあるビジネスを構築 08 複雑な課題を抱えるサプライチェーン・マネジメント 09 機械の判断でオペレーションを行う装置型の物流センターへ 10 生産性向上を図るための物流業務の共同化 11 社会や環境に貢献するクリーンな物流の実現 12 事故や災害などに対応して事業を継続するためのBCP策定 13 簡素で滑らかな、担い手にやさしい、強くてしなやかな物流の実現 14 将来を起点に今すべきことを考えて環境変化や技術革新を洞察した経営 15 物流業界では全体最適を目指して課題解決を図れる人材が必要 ■著者プロフィール ロジ・ソリューション株式会社:大手総合物流企業のセンコー株式会社から2008年に分社化された物流コンサルティング会社。現在は、M&Aにおけるビジネスデューデリジェンスや経営戦略策定など、経営コンサル領域へも業務を拡大。
-
3.7民主党には解けなかった5つの大問題に答えを出す。 震災復興、郵政民営化、農業の活性化、マイナンバー(共通番号)制度、財政赤字を止める制度改革、という5つの大問題が、民主党政権下では中途半端なままに放置されてきた。2009年の政権交代をきっかけに多くの政策課題への挑戦が待たれたが、この期待は満たされなかった。3・11大震災から1年数カ月を経過した今、構造改革が待たれる分野が放置されてきたツケが日に日に明らかになってくる。 21世紀の日本社会を持続可能なものとするために、政策の優先順位をどうつけるか。小泉流構造改革の必要性を訴え、民主党政権に厳しい目を向ける、田中直毅氏(国際公共政策研究センター理事長)と研究員が具体的な事実・事例を多く盛り込んで示す政策提言。
-
-長時間労働の規制、同一労働同一賃金、待機児童など、働き方に関わる諸問題が相次いで議論されている。これらの背景には、少子高齢化に伴う労働力の減少、サービス産業の時代における日本型雇用の制度疲労、という大きな問題が横たわる。本書の狙いは、そうした労働問題の全体構造を示し、体系立てて対策案を提示することである。 長年の雇用慣行や諸制度が絡み合う構造を把握しないまま各論ごとに対策を講じても、ある対策が別の問題を引き起こすといったことになりがちだった。そこで著者は「働く人を増やす」(女性や高齢者の活躍)、「働く場を整える」(地方や中小企業の活性化)、「働き方を変える」(日本型雇用の改革)という、三つの柱についてそれぞれ、現状および課題を整理し、制度設計や政策などの対策を提示している。 長年の雇用慣行を見直し、既存の制度を変えるには、問題の全体構造を踏まえつつ、一つひとつ周りから突き崩していくことになる。こうした構造改革は政治主導でないと進められない。こう考えた二人の著者は、自由民主党の中で労働問題に関心を持つ有志を集め、「多様な働き方を支援する勉強会」を開催、2年間をかけて労働問題について勉強と議論を続けてきた。その成果をまとめたものが本書である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「世界金融・債務危機の最大の教訓は何かと問われれば、それは、これまで個別に扱われる傾向があった金融政策、金融市場の規制・監督、財政政策、構造改革を相互に密接に関連した一体不可分のものとして捉える必要があるということであろう。とりわけ政策分野間の相互連関に注意が必要な分野は三つある。第一は、金融政策と金融規制・監督の連携である。第二は、金融・財政政策と構造改革の相互連関である。第三は、国内と海外の政策の連関である。」……「はじめに」より 2007年以降の世界金融危機とそれに続くユーロ圏の政府債務危機は、これまでの経済政策運営のあり方に大きな疑問を投げかけるものであった。欧米の経済学者たちや、OECD、IMFなどの国際機関のエコノミストたちは、今後、このような危機を起こさないためには、どのような政策をとるべきかについて、さかんに議論を繰り広げてきた。 本書は、グローバル金融・財政危機以降、欧米の経済学者たちがどのような議論を行ってきたかを展望し、理論的な整理を行う。一つの政策分野に偏ることなく、金融監督政策(第1章)、マクロ経済政策(第2章)、財政政策(第3章)、構造改革(第4章)について、包括的に論じる。 経済政策について論じる際に読んでおくべき専門文献が、あますところなく取り上げられ、内容が詳しく紹介されている。専門家にとっては、文献ガイドとして非常に有益な一冊である。 【主な内容】 はじめに 第1章 資産価格及び信用変動、及び国際資本移動への対応 第2章 危機時のマクロ経済政策の対応 第3章 財政の持続可能性 第4章 構造改革の役割と課題 参考文献 おわりに
-
3.4
-
-
-
-
-
-
-
4.3日本でもっとも危険な男の物語。 この国を“超格差社会”に変えてしまった中心人物はこの男だった! 「改革」の名のもと、法律を駆使しながら、社会を次々と大胆に改造してしまう。まるで政商のように利にさとく、革新官僚のごとく政治家を操る経済学者――。「フェイク(偽物)の時代」に先駆けた“革命家”の等身大の姿とは。 経済学者、国会議員、企業経営者の顔を巧みに使い分け、「日本の構造改革」を20年にわたり推し進めてきた“剛腕”竹中平蔵。猛烈な野心と虚実相半ばする人生を、徹底した取材で描き切る、大宅壮一ノンフィクション賞、新潮ドキュメント賞ダブル受賞の傑作評伝。 はじめに 「改革」のメンター 1章 和歌山から東京へ 2章 不意の転機 3章 アメリカに学ぶ 4章 仮面の野望 5章 アメリカの友人 6章 スケープゴート 7章 郵政民営化 8章 インサイド・ジョブ おわりに ホモ・エコノミカスたちの革命
-
-その姿はまさにこの国の縮図だ! いまなお「白い巨塔」なのか? それとももはや「バベルの塔」か? 構造改革の時代! ――世界に冠たる日本の医療環境。平均余命は高く、薬は豊富。しかしその一方で……。倫理からかけ離れて暴走しかねない先端治療は、国民の不信を買い、際限なく膨脹する医療費は、国家財政を揺るがす。構造改革の時代に、大学医学部は、新しい秀れた人材を社会に送り出せるのか? 豊富な取材で実像をえぐり出す。
-
4.01990年代以降の「大停滞」については、金融政策の誤りではなくて、日本が構造改革に取り組まなかったからだという説が主流である。しかし、構造論者が、いつ、どのような構造改革を怠ったから日本の実質成長率が低下したのかという問いに、まともに答えてはいない。構造問題説とは、雑多で、内容のない、誤った議論の寄せ集めなのである。本書では、むしろデフレから脱却することこそが、真の構造改革であると考え、金融政策の誤りがいかなる経路で大停滞をもたらしたのかを分析。金融政策とは金利を決める政策ではなくて、物価を決める政策であるという観点に立って金融政策の誤りを検証し、どのように金融政策の誤りをただすかを具体的に提言していく。このままでは3000兆円の日本の富が失われてしまう! すべての原因は金融政策の誤りにある。間違いだらけの日本再生論を排し、徹底した実証分析による正しい処方箋を提示する。
-
3.7
-
-
-
-中国は、生産設備などの「過剰問題」を解消するための構造改革を打ち出しましたが、思うように進んでいません。実質的に破綻している「ゾンビ企業」は増え、共産党政権内部の権力闘争は激しくなっています。中国経済混迷の原因となっている「ゾンビと政争」の実態を明らかにします。 本書は週刊エコノミスト2016年9月13日号で掲載された特集「中国 ゾンビと政争」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・構造改革は絵に描いた餅 ・インタビュー 丹羽宇一郎 ・懸念される新過剰 ・習政権の権力基盤について2人の識者が分析した。 ・中国の対欧州戦略 ・「反中」広がる香港 ・南シナ海問題 ・不良債権 ・人民元 ・銀行理財商品 ・海外進出企業が急増 【執筆者】 松本惇、藤沢壮、湯浅健司、加茂具樹、金子秀敏、羽場久美子、倉田徹、八塚正晃、神宮健、梶谷懐、梅原直樹、矢作大祐、週刊エコノミスト編集部 【インタビュー】 丹羽宇一郎
-
-1巻220円 (税込)世界経済の牽引役だった中国経済の減速が顕著だ。設備過剰、遅々として進まない国有企業改革、労働力人口の減少、貧富の格差、環境汚染など、課題を挙げたらきりがない。今後中国経済はどうなるか、またそれが世界経済にどのような影響を与えるか――を分析した。 本書は週刊エコノミスト2014年11月4日号の特集「中国大減速」を電子書籍化したものです。 主な内容 ・GDP7%割れ容認の衝撃 ・待ったなしの構造改革 山積する深刻なリスク ・習近平の実像 改革の実行が不可避な経済状態 繰り返せない「失われた10年」 ・金融バブル 民間と地方の債務圧縮に着手 景気急落はらむ綱渡りの運営 ・不動産バブル 下がり始めた不動産価格 地方政府債務と連鎖リスク ・所得格差 戸籍統一、都市化では解決不能 既得権益層に手を付けられぬ政権 ・アリババ上場 外資を引き込む中国の魔法「VIE」 株主権を弱める複雑怪奇な仕組み ・上海─香港相互取引 個人投資家の上海A株購入を解禁 企業統治の向上につながるか ・割安感目立つ香港株 値上がり期待高い有名企業銘柄」 ・続く社会運動弾圧 習近平が強化する言論規制 西側の価値観を拒否 ・香港デモと中国政府 「断固譲歩しない」姿勢が表面化 中国版カラー革命を警戒する政府 ・歴史から学ぶ 日中は常に「政冷経熱」だった ・日中首脳会談 大国意識強める指導部 早期の関係修復は困難
-
-赤字5.5億円からの奇跡の回復はなぜ可能だったのか?経営方針書、ハッピー体操、サンクスカード、定年制廃止、障がい者雇用。社員と日本を幸せにする「愛と感動」のノウハウを一挙公開!中小企業は手っ取り早くベンチマーク!――「2000年に東証一部上場」を旗印にワンマン経営を行っていた著者は、大赤字転落を機に、リッツカールトンをはじめとする優良企業を徹底的にベンチマークして、社内の業務改革、構造改革、環境整備を断行。さらにES(従業員満足)向上を最優先し、“社員が幸せになる会社”の実現のために大奮闘。「愛と感動」を理念に、定年制廃止、障がい者雇用などでグループ内の連帯感を高め、倒産寸前の危機に陥ったフォーマルウエア・メーカーを業界3位にまで回復・躍進させた経営手法、逆境克服の成功法則を紹介。
-
-
-
3.0これからの企業・組織の盛衰は「デジタル人材」が握っている! 「with コロナ」を生き抜く人事戦略の決定版、待望の刊行 SAP、サイバーエージェント、コニカミノルタ、大日本印刷など主要企業の事例を紹介 日本企業は経営・事業のグローバル化や低成長経済下における事業構造改革の各局面において、抜本的な人材マネジメントモデル変革を先送りしてきた。その結果、IT やデジタルに限らず優秀人材の獲得・リテンションについては、グローバルIT プラットフォーマーや魅力的な仕事を提供する国内スタートアップ企業に対しても大きく劣後する結果となってしまった。 本書は、デジタル時代を迎え、日本企業が立ち向かうべき、人事・人材マネジメントの変革を先進企業の取り組み事例を交えながら紹介をしていく。日本型人材マネジメントモデルを維持してきた日本企業が、今後デジタル化を進める上でどのように人事・人材マネジメントモデル変革を進めていくのかを、コンサルティングの経験も交えて示していきたい。 20 ~30 年間その会社でキャリアを重ねないと一人前と見なされない、といったような日本型マネジメントモデルはあらゆる業種・業界におけるグローバル競争において苦戦を強いられている日本企業の状況と無縁ではない。逆に言えば、デジタル時代の到来はこれまで日本企業が何度も挑戦し跳ね返されて来た日本型人材マネジメントモデル変革の絶好の機会となる。今こそ、人事・人材問題を先送りした過去の経営からは決別すべきである。(序章より抜粋)
-
-経済も産業も転換点を迎えている。株式市場も2018年は新たなステージに入るかもしれない。投資テーマは色とりどりだ。 本書は週刊エコノミスト2017年12月19日号で掲載された特集「投資テーマ2018」の記事を電子書籍にしたものです。 ・成長の四天王と家電ドミノと新元号吾/戌年は戦後4勝1敗 ・ソニーサプライズ 自動運転で画像センサー期待 ニッポン電機復活が本格化へ ・人工知能(AI)が選ぶ!年末年始の投資テーマ25 ・半導体素材・化学 業種別指数は過去最高値を更新中 ・EV・自動車部品 外資傘下の自動車部品メーカー 収益改善で「大化け」期待 ・生産性・人づくり革命 AI使い、生産性向上 従業員の「やる気」高める ・銀行の構造改革 メガバンク3行の収益改善 金融政策見直しの恩恵大きく ・小売り革命 給与増加でEC企業に恩恵 ドラッグストア、コンビニも ・外食産業の構造変化 「シェアリング」席巻 ・電力・ガス自由化 市場価格高騰で淘汰の波が一層強めに ・「鉄冷え」の鉄鋼業界 中国しだいのニッポンの鉄 カギは現場立て直しにあり 【執筆者】 井出 真、小川 佳紀、広木 隆、坂本 慎太郎、藤本 誠之、平川 昇二、鮫島 誠一郎、南野 彰、真田 明
-
4.3通史で読み解くからこそ、見えてくるものがある 家康から綱吉の時代は戦後の高度経済成長、新井白石の「正徳の治」は平成のバブル崩壊といったように、江戸時代の経済変動は現代と似ている点が多い。デフレからの脱却に繋がった、吉宗による「享保の改革」の功罪とは。田沼意次の構造改革が成功しなかったのはなぜか……。徳川幕府の経済政策の成功(光)と失敗(影)に学ぶ。 ●第一章 家康の経済戦略“エドノミクス” ●第二章 幕府を揺るがした政治危機と大災害 ●第三章 “元禄バブル”の実相 ●第四章 正徳の治――“バブル”崩壊でデフレ突入 ●第五章 吉宗の「享保の改革」――元祖・リフレ政策 ●第六章 田沼時代の真実――成長戦略と構造改革の試み ●第七章 「寛政の改革」――超緊縮で危機の乗り切りを図るが…… ●第八章 「化政バブル」――“最後の好景気” ●第九章 「天保の改革」――“最後の改革”だったが…… ●第十章 幕府崩壊と近代化の足音
-
-トヨタが生産現場の改革を終え、 凍結していた工場新設を再開する。 と同時に、新たな設計ルール 「TNGA(Toyota New Global Architecture)」の準備も整い、 2015年中にTNGA第1弾として4代目「プリウス」を投入する。 この新たな設計手法によって 魅力ある車の機動的な投入を可能にし、 世界の主要市場をくまなく攻略できるか──。 “意志ある踊り場”の間に進めてきた、 知られざる構造改革の本質と、その成否を占う。 『週刊ダイヤモンド』(2015年5月30日号)の 第3特集を電子化したものです。 雑誌のほかのコンテンツは含まれません。
-
4.0カジノや風俗などが合法となった、構造改革特別区の海上都市・"海上都市(アクア・エデン)"。 主人公・佑斗はこの地に、"脱童貞"を叫ぶ友人に連れられてただ遊びにきたはずが――気がつけば人間を辞めるハメになり……!? ゆずソフトが贈る大ヒットADV『DRACU-RIOT! -ドラクリオット-』で、作中屈指のチビッ娘キャラ布良梓と恋仲になったその後を描く物語。 カバー描き下ろしや加筆修正はもちろん、単行本だけのオリジナルエピソードも追加したファン待望の1冊。 最初から最後までイチャラブしまくりです!!
-
-
-
-
-
-ファミリーレストランが堅調だ。 長く低迷が続き、ファミレス不要論まで浮上したが、構造改革と原点回帰による基本の徹底で、再び消費者の支持を集めている。 一方で、回復の足取りが見えない居酒屋。 外食業界でなぜ明暗が分かれたのか。 『週刊ダイヤモンド』(2014年9月6日号)の第2特集を電子化したものです。 雑誌のほかのコンテンツは含まれません。
-
-
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。











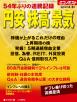














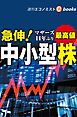







































![[新装版]土光敏夫 信念の言葉](https://res.booklive.jp/204414/001/thumbnail/S.jpg)



![図解即戦力 物流業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]](https://res.booklive.jp/1508746/001/thumbnail/S.jpg)