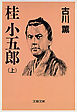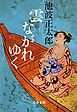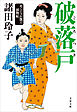歴史・時代小説 - 文藝春秋 - 文春文庫作品一覧
-
-明の海賊と日本人の間に生まれた少年は海へ――。 「国性爺合戦(こくせいやかっせん)」のモデル・鄭成功を描く 闘いと冒険の物語。 鎖国時代の平戸。孤独な少年・福松を迎えに来た母は、 台湾を根城にする大海賊の頭だった―― 明に渡った福松はやがて鄭成功となり、清と闘う道を選ぶ。 日本と中国の血を持つ男が台湾の民族的英雄に、 後に「国性爺合戦」主人公として江戸の人々を熱狂させる。 生きる場所を求め闘う魂を描く大スペクタクル長編! 解説=仲野徹 ※この電子書籍は2021年6月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
-悪は必ずしも悪ならず。 思いがけない事件の結末が胸を打つ! 消息を絶っていた盗賊「桐山の藤兵衛一味」。 再び動き始めたのはなぜか。 時代に翻弄される人々への、十兵衛の深い眼差しが胸を打つ。 ドラマ化もされたヒットシリーズ『八州廻り桑山十兵衛』。 松戸近辺に住む強欲な百姓一家殺害事件で、 十兵衛は、一時期世間を騒がした盗賊たちが再び動き始めたのではないかと疑い始める。 十兵衛の前に現れては捜査を攪乱する謎の美女、 さらに事件の背景には盗賊たちの人生を変えたある悲劇。 時代に翻弄される女と男に対する十兵衛の深い目線が胸にささる、 人気シリーズ第10弾にして最後の作品! ※この電子書籍は2017年7月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
3.9【第97回(1987年)直木賞受賞作】 ときは戦国。海と船への憧れを抱いて対馬で育った少年笛太郎は、航海中、瀬戸内海を根城とする村上水軍の海賊衆に捕まり、その手下となって、やがて“海の狼”へと成長していく。日本の海賊の生態をいきいきと描いた、夢とロマンが香る海洋冒険時代小説の最高傑作。「海を舞台にした小説は外国には多い。海洋冒険小説という一つのジャンルが確立しているほどである。四面環海の日本にそれがないというのは、ふしぎな現象だ。(略)日本の海洋小説の一里塚を築けたとすれば、私としては本当にうれしい」(「著者のことば」より)
-
4.1
-
3.7水谷豊主演でドラマ化された話題作、待望の文庫化! 礼金と引き替えに世の悪党どもを退治する殺し屋・月影。追う北町奉行筆頭与力・仙波一之進は、事件現場に倒れていた娘を救う。が、娘は記憶を失っていた。仙波は平賀源内に依頼し、エレキテルで娘の記憶を呼び起こそうとする。施療のあと、娘の口をついて出た言葉は「おっとつぁんは歌麿」。 滞在していた房総から呼び戻され、歌麿は娘と涙の顔合わせを果たす。ところが、殺人現場を見られたかもしれないと考えた月影が娘を誘拐した。娘を取り返すべく、月影の呼び出しに応じる歌麿だが…。表題作など3編収録。
-
-
-
3.3
-
-「鬼役」の坂岡真、渾身の新シリーズ発進! 火盗改の駆け出し侍が、個性豊かでアクの強い仲間たちと江戸の巨悪に敢然と立ち向かう。 九代将軍徳川家重の治世。越後新発田藩の浪人の息子・伊刈運四郎は、直参旗本・坂巻讃岐守に中小姓として召かかえられるが、出仕初日から御先手筒(鉄砲)組二十四番の手伝いを命じられる。 筒組二十四番は火付盗賊改の助役代理を命じられていて、運四郎も火盗改の見習いになってしまったのだった。 初仕事は、口から鯖の尾鰭が飛び出した血腥い屍骸の検分――。 火盗改本役の弓組二番は優秀な人材が集められたエリート集団。 かたや、筒組二十四番は出世とは無縁な外れ者ばかり。 博打にのめり込んでいる者、金勘定にやたら細かい者、記憶力だけは抜群に良い者、変装に長けた者などなど、個性的でアクの強い連中がいがみ合うが、顔に大きな刀傷がある供頭・杉腰小平太がまとめ上げて、難事件に立ち向かう。
-
3.9
-
3.8ベストセラー「まんまこと」シリーズ第7弾! 町名主のお気楽跡取り息子・麻之助が、幼なじみの色男・清十郎と堅物の同心・吉五郎とともに、さまざまな謎と揉め事の解決に挑みます。 「きみならずして」「まちがい探し」「麻之助が捕まった」「はたらきもの」「娘四人」「かわたれどき」の6篇を収録。 清十郎に子が生まれ、縁戚のおこ乃の縁談がまとまるなど、麻之助の周りで祝い事が続くものの、自分自身には揉め事ばかり。 特に親しい料理屋の娘・お雪には何かと振り回される日々だ。 ある時、野分けと呼ばれる大嵐が起こり、お雪が洪水に流される。 間一髪助かるが、何やら一大事が……!? 解説は「まんまこと」シリーズの装画を手掛けるイラストレーターの南伸坊さんです。 ※この電子書籍は2019年2月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
3.6昭和ホームドラマの原点・復刊! 東京・原宿にある蕎麦屋「大正庵」の女主人・大正五三子は、太っ腹で、世話好きで、涙もろいお人好し。 くわえて体重もずっしり横綱級で、ひと呼んで「肝っ玉かあさん」。 この原宿の三大名物の一つともいわれる「肝っ玉かあさん」を主人公に、大正庵をめぐる人間模様を軽妙に描きつつ、ほろりとくる作品。 1968年4月から1972年1月まで全117回、3シリーズにわたって放送されたテレビドラマ「肝っ玉かあさん」。 視聴率30%を誇り、その後「ありがとう」へと続く人気路線の先駆けとなった。 その脚本を担当した平岩弓枝が、ドラマを小説に書き直したのではなく、同じテーマで作者の思いを込めて小説にした。 それが本書、『肝っ玉かあさん』である。 巻末の「四十六年後のあとがき」に、ドラマ「肝っ玉かあさん」役の京塚昌子との思い出が綴られている。 【目次】 序章 雨の日曜日 幼馴染 三三子の縁談 夫婦 邪魔っけ 夏の日 運動会 女盛り ちいさな秋 あとがき 四十六年後のあとがき
-
4.0武田、北条、佐々……仕えた家が軒並み絶家! 厄神と呼ばれた男・御宿勘兵衛の生涯。 武田の遺臣として、数多の主家を渡り歩いた御宿勘兵衛(みしゅくかんべえ)は、何を求めて大坂城へ入ったのか? 武田家滅亡から、大坂の陣まで――仕えた家が次々と滅びることから、その武勇に反して「厄神」と忌み嫌われた御宿勘兵衛。 そして、時代に迎合することなく己の夢と覚悟を貫いた依田信蕃や久世但馬など、勘兵衛と関わった度し難い男たち。 「天正壬午の乱」「さらさら越え」「小田原征伐」「越前騒動」「大坂の陣」など勝者の側ではなく滅び行く者たちからみた戦を描く。 気鋭の著者が腕をふるった、時代に選ばれなかった曲者たちの物語。 解説・縄田一男
-
3.7
-
3.8NHKドラマ化もされた大人気「まんまこと」ワールド第2弾! 町名主の跡取り・麻之助は、ついに祝言をあげることに。けれど花嫁を迎えに出ようとしたその時、悪友・清十郎の父が卒中で倒れてしまう。堅物の父・源兵衛から「かつて訳ありだった二人のおなごの境遇を確かめて欲しい」と頼まれた清十郎は仰天し――。 町名主名代ぶりも板につきながら、淡い想いの行方は皆目見当つかぬ麻之助。両国の危ないおニイさんたちも活躍する、江戸情緒溢れる6つの短編集。 解説・細谷正充 ※この電子書籍は2009年3月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
5.0
-
4.0
-
4.3妻を想う男、父を信じる娘。誇りをかけた闘いの結末は!? 藩を追われ、貧乏長屋で暮らす柳田格之進。悲劇の真実を知った彼は、仇討ちを決意し……。草なぎ剛主演映画の小説を脚本家が自ら執筆。 映画『碁盤斬り』は、落語の演目として長く親しまれてきた「柳田格之進」を題材に、『日本沈没』『クライマーズ・ハイ』『凪待ち』などを手掛けてきた脚本家の加藤正人さんが、3年半の月日をかけて書き上げたストーリー。 この映画の世界を、加藤さん自身が小説として書き下ろしました。 登場人物の細かな心情の描写はもちろん、映画では描き切れなかった若き日の格之進の姿、また映画のラストの「その後」がしっかりと描かれており、小説好きの読者も十分に楽しめる作品です。 【あらすじ】 娘の絹とふたり、江戸の貧乏長屋で暮らす柳田格之進。 彼は、身に覚えのない罪をきせられた上に妻も喪い、故郷の彦根藩を追われた身だった。 しかし、かねてから嗜む囲碁にはその実直な人柄が表れ、江戸で多くの知己を得る。 ある日、旧知の藩士により、彦根藩での悲劇の真相を知らされた格之進と絹は、復讐を決意する。 絹は仇討ち決行のために、自らが犠牲になる道を選び……。 父と娘の、誇りをかけた闘いが始まる!
-
-
-
-
-
4.2
-
3.8花を生ける、人を生かす。 まだ悲しみも喜びも知らぬ少年僧の、四季折々の花に彩られた成長物語。 物語の舞台は文政13(1830)年の京都。 年若くして活花の名手と評判の高い少年僧・胤舜(いんしゅん)は、ある理由から父母と別れ、大覚寺で修行に励む。 「昔を忘れる花を活けてほしい」 「亡くなった弟のような花を」 「闇の中で花を活けよ」 次から次へと出される難題に、胤舜は、少年のまっすぐな心で挑んでいく。 繊細な感受性を持つ少年僧が、母を想い、父と対決していくうちに成長をとげていく、美しい物語。 解説・澤田瞳子 ※この電子書籍は2017年7月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
3.4
-
3.0
-
4.3
-
3.0
-
4.5後漢という時代は、ひとの美質のなかで、「孝心(親孝行)」を至上とした。 能力よりも徳を重視し、頭脳よりも心を尊重する国家がつくられた。 184年に始まった「黄巾の乱」により、王朝の礎が揺らぐ中、 後漢の理想を体現する名臣たちが輩出する。 大将軍の何進、 劉備の師である盧植、 曹操を支えた荀彧など7人を描く、宮城谷昌光の「三国志」シリーズ。 解説・湯川豊 目次 何進(かしん) 朱儁(しゅしゅん) 王允(おういん) 慮植(ろしょく) 孔融(こうゆう) 皇甫嵩(こうほすう) 荀彧(じゅんいく) ※この電子書籍は2018年2月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
3.4「いつの世でも、人が生きてゆくということは、むずかしいものである」(序より) 正史にもとづいた大作『三国志』全12巻を書き上げた著者が、時代の潮流の外にいながらも忘れがたい12人の生涯をたどった。 『三国志』をあらわした陳寿(ちんじゅ)、輝ける倫理観と志望をもっていた太史慈(たいしじ)、魏の名臣・王粲(おうさん)・・・。 ある者は、権力者や政治の中心に近づきながら、遠ざかることを余儀なくされた。その苦難をどのようにしのいだのか。曹操、孫権、劉備、関羽といった英傑たちとはことなり、歴史の中で一瞬だけ輝いた人生。その輝きが愛惜の念とともに描かれる。 著者による後漢・三国年表つき。
-
3.0歴史はふりかえってみるものではない。すすんでいって、みるものである。「特別随想 ふりかえること」より 『三国志』をはじめ長年、中国歴史小説を書き続ける著者が、みずからの歴史観、世界観、小説観をあますところなく開陳した。 自作解説や作家、経済人、学者など多彩なメンバーとの対談などを収録。 <目次> 【ロングインタビュー】私の「歴史小説」 【自作解説】三国志の世界 ・『三国志』の沃野に挑む--大歴史絵巻の豊穣なる世界 ・曹操と劉備、三国志の世界--正史からみえてくる英雄たちの素顔 ・『三国志』の可能性--歴史は多面体だからこそおもしろい ・『三国志』歴史に何を学ぶのか--構想十年、執筆十二年の大長編を終えて 【対談】歴史小説を語る ・水上勉--歴史と小説が出会うところ ・井上ひさし--歴史小説の沃野 時代小説の滋味 ・宮部みゆき--「言葉」の生まれる場所 ・吉川晃司--我々が中国史に辿り着くまで ・江夏豊--司馬遼太郎真剣勝負 ・五木寛之--乱世を生きるということ 【講義&対談】中国古代史の魅力 ・中国古代史入門--どこから学べばいいのか ・白川静--日本人が忘れたもうひとつの教養 ・平岩外四--逆風の中の指導者論 ・藤原正彦--英語より『論語』を ・秋山駿--春秋時代から戦国時代へ ・マイケル・レドモンド--碁盤上に宇宙が見える ・項羽と劉邦、激動の時代--ふたりを動かした英雄たちと歴史的必然 ・『三国志』をより深く楽しむための本 ・宮城谷昌光 中国歴史作品の年代一覧 ・特別随想 ふりかえること ・宮城谷昌光 出版年譜
-
4.0町会所から千両箱が消えた! 前代未聞の事件は幕閣の醜聞に発展する。 捕縛したものを取り調べる仮牢兼調所「大番屋」の元締を勤める鏡三郎が今回遭遇する事件は、町会所の押し込み強盗。 町会所とは幕府が貧困や災害時の救恤のため民間に設けさせた機関で、そこから二万両が奪われたという。 鏡三郎らは犯人の行方を追うが、事件は幕閣が震撼するスキャンダルへと意外な展開を見せて……。 殺される証人、予測不能な展開。狡猾な事件の黒幕に迫れるか。 冷酷非道な悪に立ち向かう同心の決死の闘い。 ※この電子書籍は2016年3月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
4.0
-
4.0
-
3.6
-
3.5
-
4.0
-
3.5
-
4.0
-
3.7始皇帝は“暴君”ではなく“名君”だった!? 『キングダム』で話題のえい政=始皇帝のすべてがわかる必読の書! 世界で初めて政治力学を意識し、中華帝国を創り上げた男。その人物像に深く迫りつつ、現代にも通じる政治・経営学を解きあかす。 自らを「始皇帝」と名乗るに至った男、えい政。乱世に終止符を打ち、中華帝国を統一した男は暴君なのか、それとも英雄なのか? 3歳まで人質として過ごした幼少期、兄との熾烈な玉座争い、家臣との相克――。天賦の才覚と不屈の精神力で過酷な運命のもとに勝ち上がった男の真実を浮き彫りにする、不朽の名著。 「崇高な争い」は感動的で、しかも美しい。 だから「歴史」でそういう場面に出会うと、夜なら眠れない程に興奮する。 ――著者「文庫版あとがき」より 解説・冨谷至 ※この電子書籍は1995年9月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を新装版として刊行したものを底本としています。
-
3.3表の顔は腕の良い仕立職人、裏の顔は達人に仕込まれた剣術で悪を成敗する「地獄への案内人」。仕立屋お竜の活躍を描く痛快時代小説開幕! 第一話は、いたいけな少女・おしんがお竜と名を変えて「地獄への案内人」の道を歩むまでが描かれます。幼い頃に父からDVを受けてきたおしんは、母と家を逃げ出すが、その母も過労で亡くなり天涯孤独の身に。母親の薬代のためにつくった借金を抱えたおしんだが、親切顔で近づいてきたやくざの林助に騙され、盗品の運び屋や、美人局の片棒を担がされるなど、悪の道にひきづりこまれてしまいます。 とあることがきっかけで、武芸の達人・北条佐兵衛に助けられて自由の身となったおしんは、天賦の才があったのか、達人から教えてもらった武術を乾いた砂が水を吸うようにわがものにしてゆきます。「お前の才能は、お前のように困っている女性のために使うのだ」という師匠の言葉を胸に、師匠の紹介で仕立屋「鶴屋」から仕事をもらうようになります。そしてお竜と名を変えて、女をいたぶる悪人を退治することを決意。そんなある日、因縁の男と再会することになって……。 お竜の庇護者となる仕立屋の主・鶴屋孫兵衛、鶴屋の碁敵で謎のご隠居・文左衛門、そして鶴屋の用心棒で、ちょっととぼけた吉岡流剣術の使い手・井出勝之助など、お竜の脇を固める登場人物たちも魅力たっぷり。そして何よりの読みどころは、お竜の艶やかさと痛快アクションシーンです!