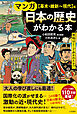徳川作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 全国の合戦の戦術や背景をわかりやすく解説。 ★ 時間経過や戦の影響など、 時代の象徴である戦いを見てみよう。 ★ 名将、勇将、智将……。 群雄割拠を駆け抜けた各将を、 活躍年表や人物関係などから詳しく紹介。 ★ 時代の成り立ち、 暮らしと文化、武将検定など、 もっと深めるための情報も掲載。 ◆◇◆ 著者からのコメント ◆◇◆ 戦国時代って、案外好き嫌いがあって、 大好きな人はキャラクターが豊富でおもしろいというし、 嫌いという人は登場人物が多過ぎて覚えるのが大変といいます。 日本史をふり返ると、幕末の人間群像に興味をひかれる人が多いし、 坂本龍馬、高杉晋作、西郷隆盛、勝海舟、大久保利通など、 キラ星のような魅力一杯の人たちが、 数多く日本史の舞台に登場します。 と同様に調べていくと戦国時代も幕末に劣らずというか、 むしろそれ以上に登場する人たちが多く、 そのひとりひとりの人生をひもといていくと 魅力一杯の人たちが実に多くいることに気づかされます。 戦国武将というと、 どうしても勇猛果敢に戦場へ赴いた武将たちに心を奪われがちですが、 たとえば名言が残されている武将、 城下町作りや文化面で貢献した武将、 勇猛果敢な有名武将のちょっとしたエピソード、 ある出来事をなした武将、 あまり有名ではないけど、 ファンの多い武将というように、 まさに十人十色といってもいいほど、 魅力あふれる武将が数多くます。 それぞれが、あの重そうな鎧に身を包み、 家族を思い、一族を後世に残すために 知恵や知略をめぐらせています。 勿論、武士である以上は、涙をのみ、 そして耐えて御頭様のいわれるままに命を捧げ、 赴きたくない戦場へ出陣しなければなりません。 この本は、歴史に学ぶビジネスノウハウ本ではありません。 あくまでも、戦国武将が数多く登場する本ですから、 やはりそれぞれの武将の人となりが知れて、 その武将の魅力が感じられる一冊になることを願い 私たちは制作にあたりました。 確かに、信長、秀吉、家康には魅力があります。 でも、まだまだ魅力いっぱいの戦国武将が たくさんいることも知ってもらいたいし、 この本が、そうした武将たちの再発見の一冊であったり、 道しるべの一冊になることを願っております。 両洋歴史研究会 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆第一章 戦国大名と戦国武将 * 明智光秀 * 浅井長政 * 足利義昭 * 安国寺恵瓊 * 石田三成 * 今川義元 * 上杉謙信 * 大内義興 * 大谷吉継 * 片倉景綱 ・・・など ☆第二章 天下統一へ * 織田信長 「誕生」「桶狭間の戦い」 * 豊臣秀吉 「誕生」「長浜城」 * 徳川家康 「誕生」「秀吉から家康へ」 ・・・など ☆ 第三章 戦国の合戦 ≪東北・北陸地方の主な戦い≫ * 第4次川中島の戦い ≪関東・東海地方の主な戦い≫ * 桶狭間の戦い * 関ヶ原の戦い * 小田原城の戦い ≪近畿・中国地方の主な戦い≫ * 姉川の戦い * 賤ヶ岳の戦い * 本能寺の変 ≪四国・九州地方の主な戦い≫ * 耳川の戦い ・・・など ☆第四章 戦国時代とは ≪戦国時代以前≫ * 承久の乱(鎌倉幕府と朝廷の対立) * 建武の新政(鎌倉幕府の滅亡) * 室町幕府の成立(足利尊氏から足利義満) ≪東日本の主な武将たち≫ ≪西日本の主な武将たち≫ ・・・など ☆第五章 戦国時代の暮らしと文化 * 地方都市の発展(商工業の発展と文化の普及) * 茶の湯と千利休 * 水墨画と雪舟 * 味噌と醤油の誕生 ・・・など ※ 本書は2010年発行『戦国時代』の内容の確認と一部必要な修正を行い、書名・装丁を変更し再発行したものです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 中学までに必ずおさえておきたい 「年代ごとのできごと」や「重要人物」も 年表や図解ですっきり整理! ★ 激動の日本の歴史を いっしょにかけぬけよう! ◆◇◆ 本書について ◆◇◆ 「歴史」という言葉を聞いただけで、 むずかしいと感じてしまうのはなぜでしょうか。 その理由の一つには 「昔の日本のことや昔の人に興味なんか持てない」 ということがあるのでしょう。 自分の親が自分の年齢のときには、 どんな時代だったのか、 考えてみることからはじめればいいのです。 さらに両親の親、つまりおじいちゃんや おばあちゃんの時代は…。 その祖父母の両親が生きていた時代はどうだったのだろう。 それをずーっとさかのぼってゆくと、 豊臣秀吉や平清盛や 卑弥呼の時代になります。 教科書的な歴史の勉強では、 なぜそれが起きたのか、 なぜその人はそのような行動をしたのか、 という大切なことを忘れがちです。 とはいえ、自分たちの行動に すべて理由があるわけではないのと同じで、 歴史的人物の行動でさえ、 すべて理由があるわけではないはずです。 「この人ってどういう人だったの」 という素朴な気持ちにこたえたいというのが本書です。 まんがであるからこそ、 歴史的人物といわれる人が 生の言葉で私たちに話しかけてきます。 「この人、おもしろい」とか 「この人、どこかズレている」とか、 感じるままに判断していただければ、 歴史への興味もきっと高まることでしょう。 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ 第1章 古代から邪馬台国 * 縄文時代と弥生時代の違いと特徴 * 邪馬台国の女王卑弥呼 * 古墳時代 古墳の分布 * 大化の改新・大宝律令 ・・・など ☆ 第2章 古墳時代から平安時代 * 聖徳太子と法隆寺 * 平城京と奈良時代 * 平安京と紫式部 * 平清盛と壇ノ浦の戦い ・・・など ☆ 第3章 武士の政権から江戸幕府 * 源頼朝と鎌倉幕府 * 応仁の乱と戦国大名 * 織田信長の天下布武 * 豊臣秀吉の天下統一 * 徳川家康と江戸幕府 ・・・など ☆ 第4章 明治維新から戦後の日本まで * 明治維新と西郷隆盛 *伊藤博文と犬養毅 * 太平洋戦争への道 * 戦後の日本と平和国家 ・・・など ※ 本書は2009年発行の 『マンガで学ぶ! 「日本の歴史」がよくわかる本』 を元に、加筆・修正を行った新版です。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 御朱印でめぐる古寺シリーズでは、鎌倉・京都・奈良・江戸といった古都の御朱印を紹介してきました。しかし、地域が合わない、掲載趣旨、格式などの理由で日の目を見なかった、わざわざ訪れてでもいただきたくなる御朱印はあまた存在します。今回は、凄い御朱印そのものを紹介しています。墨書きが凄い! 達筆すぎて凄い! もはやアート!天狗が凄い! 『どんぶらこ、どんぶらこ』あの、おとぎばなしの主人公が祀られている。一年に一回、数年に一回しかいただけない限定もの。織田信長、徳川家康、真田の六文銭、お相撲さん、気象予報士のための神社、空旅の安全祈願! とにかく読み出すと現地まで行って絶対に頂きたくなる御朱印を一挙公開! ※本商品は過去にダイヤモンド社から発行されていた商品になります。収録内容に変更はありませんので、重複購入にご注意ください。
-
-日本史上最大の戦いとして知らぬ者のない「関ヶ原の戦い」。東軍・徳川家康が、石田三成を中心とする西軍を圧倒的勢いで撃破、江戸幕府樹立を確実にしたものとして、小説や映画・ドラマなどでもおなじみの決戦だ。しかし、伝えられているイメージやエピソードとは裏腹に、史実として見る「関ヶ原」からは、戦いを前に焦りまくる家康や、思うようにならない軍略に不満ばかり述べ立てる三成の姿が浮かび上がってくる。その他の諸将にしても、裏切りあり、内応あり、様子見ありの、勝負の行方はどちらへ転んでもおかしくない戦いでもあったのだ。「れきしクン」としてテレビでもおなじみの著者が、天下分け目の決戦の舞台裏で繰り広げられた武将たちの右往左往ぶりを、軽妙なタッチで描く歴史読み物!
-
4.0【電子書籍特典11城追加版】 第一級の歴史作家が読み解く、関東甲信の隠れた名城46のガイド お城ブームを反映して、城に関する書籍が多数出版されている。安土桃山期以降の豪華絢爛な天守閣を擁する城を中心に取り上げた書籍もあれば、戦国期の軍事色が強い古城を扱った書籍まで百花繚乱である。 本書は、気鋭の歴史作家として注目される伊東潤氏が、これまでの多くの作品で舞台としてきた関東甲信の名城を紹介するもの。多くはこの地域の覇権を競った北条氏、武田氏、真田氏、徳川氏にまつわる城である。 単なる名城ガイドや探訪記ではなく、歴史作家である伊東氏が綴る各城にまつわる物語や縄張り(城の基本設計)の解説が本書の特徴。読めば必ず現地を訪れたくなるし、一度行った城でもまた行きたくなる。 特典付電子版は紙の書籍ではお伝えしきれなかった11城を新たに加えました。 この本は、ディープな城ファンや伊東潤ファンはもちろん、これから関東甲信の城めぐりを始めたい方々にもおすすめです。 【目次より】*特典付電子版のみ 序章 城の基礎知識 第1章 東京都(滝山城、石神井城、江戸城、*浄福寺城) 第2章 神奈川県(小田原城、玉縄城、津久井城、三崎城、*石垣山城、*小机城) 第3章 埼玉県(武州松山城、菅谷城、杉山城、*忍城、*岩付城) 第4章 千葉県(国府台城、佐倉城、臼井城、本佐倉城、*関宿城) 第5章 群馬県(岩櫃城、太田金山城、松井田城、沼田城) 第6章 栃木県(唐沢山城、祇園城、宇都宮城、*足利氏館) 第7章 茨城県(逆井城、額田城、小幡城、*石神城) 第8章 山梨県(新府城、躑躅ヶ崎館、岩殿城、*若神子城) 第9章 長野県(高遠城、上田城、大島城、旭山城、*戸石城) 第10章 静岡県(諏訪原城、下田城、興国寺城、丸子城、*田中城)
-
-●日経電子版「ライフ」(現NIKKEI STYLE)に連載された人気コラムの単行本化です。 ●古今東西の古典に描かれた老人像や、江戸時代としては長生きした徳川家康や『養生訓』で知られる貝原益軒らの生き方哲学に触れながら、老いは決して、忌避されるものではなく、人生の後半をこそ楽しむのが豊かな生き方であると著者は強調します。 ●「老いるほど豊かに」の例として、最終的に豊かな死を迎えることを目的とした日本ならではの長寿祝いや、お盆参りや墓参などの老いにまつわるセレモニーの重要性と意義についても詳しく触れられています。 ●老いや死のネガティブなイメージを払拭するべく、ヨーロッパの隣人祭りや、中国の死亡体験館など、日本ではあまり知られていないユニークな取り組みも交えて、誰もが心の奥底に抱く孤独に人生を終えることへの恐怖を和らげるヒントを提示しています。 ●巻末には書誌情報をまとめたブックガイドをつけました。豊かな老いぐらしのために、それらの書物をさらにひもとき、さらに人生を深めていくという楽しみも与えてくれる一冊。
-
4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★★歴史の流れがよくわかる!★★ 85人の戦国武将を、カッコいいイラストで紹介しました。さらに大迫力のCGを使って、合戦場面もリアルに再現! 甲冑や城跡写真などの歴史的資料も満載です。この一冊で戦国時代がまるわかり。歴史人物好き必携の1冊!! 【目次】 1章 戦国時代のはじまり 2章 織田信長の時代 3章 豊臣秀吉の時代 4章 徳川家康の時代 5章 戦国時代の終わり 戦国時代の国名マップ 「戦国武将大辞典」年表 <電子書籍について> ※本電子書籍は同じ書名の出版物を底本とし電子書籍化したものです。 ※本電子書籍は固定型レイアウトタイプの電子書籍です。 ※目次ページでは、該当ページの数字部分をタップしていただくと、すぐのそのページに移動することができます。なお、さくいん並びに本文中に参照ページがある場合及び【立ち読み版】からは移動できませんので、ご注意ください。また閲覧するEPUBビューアによっては正常に動作しない場合があります。 ※本文に記載されている内容は、印刷出版当時の情報に基づき作成されたものです。 ※印刷出版を電子書籍化するにあたり、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。また、印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。 株式会社西東社/seitosha
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 国会議事堂は、もと誰の家? --井伊直弼の上屋敷の一部だった。本書は、東京に残る江戸の面影を、切絵図と切絵図に重ねた現代地図、アクセス情報、豊富な写真とともに詳しく紹介。 江戸城本丸(皇居東御苑)、鬼平が設立した人足寄場(石川島公園・高級マンション)、徳川将軍家の庭(浜離宮恩賜庭園)、南町奉行所(有楽町駅前広場)、江戸の観光地(愛宕神社)、江戸幕府の最高学府・昌平坂学問所(湯島聖堂)、江戸のアウトレット(日本橋富沢町)など、著者自身が実際に歩き、江戸の息吹が感じられるおすすめの個所を厳選。 ベストセラー『東京今昔江戸散歩』(中経の文庫)に、新たに小石川谷中本郷絵図、麹町永田町外桜田絵図の2つの切絵図と、根津神社などの4項目を加え、単行本サイズに大きく見やすくなった待望の増補版! オールカラー! ※本書は2011年12月に中経出版から刊行された『東京今昔江戸散歩』(中経の文庫)を基にし、新たに「麹町永田町 外桜田絵図」「小石川谷中 本郷絵図」の切絵図と「桜田門外の変の舞台~桜田門」「加賀藩上屋敷の赤門~東京大学赤門」「江戸幕府の最高学府~湯島聖堂」「甲府宰相綱豊の屋敷~根津神社本殿」の四項目を加え、大幅に加筆・修正のうえ、改題して単行本化したものが底本です。
-
4.0明智憲三郎著『本能寺の変431年目の真実』(文芸社文庫)が、30万部を越えるベストセラーになっている。この「明智本」で示された、本能寺の変の実像分析に、副島隆彦氏が大いに刺激を受けたことが、本書執筆の動機となった。かねて、副島氏は、「徳川家康摩り替り説」(八切止夫氏の説)を支持しつつ、その実態を調査研究していたが、「明智本」の本能寺の変から考えることが、すべての伏線を一つにつなぐことを直感し、一年の間、沈思黙考を重ねてきた。そして、本書では、従来の日本史学者が語らない、「キリスト教の脅威」というものを、論考の中心に据えつけて、「なぜ信長は消されねばならなかったのか?」「秀吉・家康と続く、支配者たちは、何に気付いていたのか?」「関ヶ原合戦の結果は、なぜ家康軍の勝利に終わったのか?」などの重大な謎を、驚異の思考で説き明かしてゆく。戦国時代の英雄たちの真の姿が、著者の力技で現代に蘇る、力作書下し。
-
-ハーバードに学び、イェール大学で教鞭を執る新進気鋭の歴史学者が、明治維新を「水戸」の視点から読み解く! 江戸幕府を倒し、近代日本を創り上げたのは「薩長土肥」と言われるが、水戸藩なくして、維新は成し遂げられなかったといっても過言ではない。それは、水戸脱藩浪士らが桜田門外の変で、幕末への扉を開いただけではない。維新回天を成した志士たちは「水戸学」を学び、倒幕活動へ邁進している。長州の吉田松陰も、薩摩の西郷隆盛も、水戸学の影響を受けていたのだ。では、水戸学とはいかなるものだったのか――。それを知るには、江戸時代前半、水戸黄門として知られる徳川光圀が始めた、『大日本史』編纂に遡らなければならない。本書では、徳川光圀、立原翠軒、会沢正志斎、藤田東湖、徳川斉昭、徳川慶喜の、水戸藩を代表する六人を取り上げ、水戸学が如何に生まれ、育まれ、政治に活かされていったのかを解説していく。そして、彼らが水戸藩において行なったことは、近代日本が創られる際のロールモデルとなっていくだけでなく、渋沢栄一、松下幸之助ら財界人や、新渡戸稲造、内村鑑三ら海外でも活躍する人びとにも、大きな影響を与えていった……。「この国を変えた」水戸藩の六人を軸に見ていくことで、明治維新、そして近代日本誕生の実相がよくわかる一冊。――環境問題が深刻化し、強大国のパワーバランスが崩れ、感染症が襲い……と、世界は現在、多くの問題を抱えている。それらを解消するには、世界は、そしてそこに生きるわれわれも変わらなくてはならないだろう。だが、世界を本当の意味で変えるのは、「力」ではない。それは、日本を変革する原動力となった水戸が証明している。世界を変えるのは、人の想いであり、それが昇華した思想であるはずだ。(本文より)
-
-
-
4.5☆☆共感の声がたくさん届いています☆☆ 歴史が嫌いだった私でも読みやすかったです。(40代会社員) 江戸時代の徳川家を現代に変えて、わかりやすく書かれていたので読みやすかったです。(20代学生) 超口語で書かれていて、漫才を聞いてるように頭に入ってきて面白かった。 子供のために買いましたが親子で楽しんで読んでいます。(40代自営業) 中学受験予定の子どもといっしょに読んで、歴史を好きになりました(40代専業主婦/夫) (以上、読者アンケートから) 振り回し、振り回されながら懸命に生きた徳川将軍の壮絶で痛快な奮闘記! 初代家康から15代慶喜まで、15人の徳川将軍が生きた時代が楽しく学べて、どんな人でも歴史が大好きになる本です。家康はピンチを家臣団と乗り越えた! 綱吉は”命を大切にする”現代の倫理観を構築! 家定は激動の幕末に料理に没頭!? 家臣からあだ名をつけられても、うまくいかなくても精一杯やりきった、人間味あふれる将軍たちの生きざまが明らかに。260年以上続いた徳川幕府の時代を面白おかしくスルスル読める一冊。
-
4.0ゴミは、「なげる」? 「ほかす」? 「うっちゃる」?「明後日の次の日」、あなたの町では「やのあさって」?「しあさって」?全国2400箇所の調査記録をもとにした「お国言葉」の一大パノラマ。さまざまな方言が列島に広がるさまを地図に表すと、そこから日本語の豊穣な世界が見えてくる!辞典としても使えて方言の基礎知識も満載!国立国語研究所が総力を傾けて製作した『日本方言地図』をもとに、言葉がいかに伝播し、姿を変え、生成していくのかを描き出す。懐かしい言葉の記録でもあり、日本の長い歴史の探究でもあり、あたらな言葉の動態を探る探究でもある、無二の地図帳。「方言は日本人の心のふるさとであると同時に、日本語に新たな活力を与えるエネルギー源でもある。共通語は周囲の方言を吸収しつつ成長を続けてきた」(本書より)【本書の内容】第I部 自然/第II部 人間と生活/第III部 動植物音韻編 方言の基礎知識
-
-薄いけれども本格派。 文響社が放つ、新教養シリーズ第1弾 戦国時代の花形ともいえる30人の武将に焦点をあて、1日につき1人の武将について読み進めることで、戦国時代(室町時代後期)から江戸時代初期についての理解が進む一冊です。 武勇でその名を天下に轟かせた猛者、その智謀で味方を勝利に導いた知将、主家の存続のために知恵を振り絞った苦労人、戦いに敗れてもなお、その忠義によって歴史に名を残した悲劇の将。バラエティに富む魅力的な人物たちの解説に読む手が止まらない……。 ・天下をほぼ手中にした“風雲児”――織田信長 ・誤解に満ちた東海道の英傑――今川義元 ・秀吉に天下をとらせた名軍師――黒田如水 ・傷ひとつ負わなかった徳川軍団最強の将――本多忠勝 ・幕府の高官だった“最初の戦国大名”――北条早雲 ・他者のための戦に明け暮れた“軍神”――上杉謙信 など、最新の研究をできるだけ盛り込むとともに、武将個人のエピソードにもふれることで、彼らがどのような人物だったかが伝わるよう“戦国通”の方であっても飽きさせない内容になっています。
-
-
-
5.0徳川の世が揺らぎはじめた元治元年(1864年)、一人の青年が蘭方医学の私塾で学ぶため、安房国(現在の千葉県)から江戸にやってきた。その青年こそが後の資生堂を創業する福原有信(ふくはらありのぶ)だ。 有信は、窮乏する福原家を再興するという使命を帯びて、勉学に励む。当初は医師を目指していたが、ある時、1冊の本と出合う。その本はワートルの『薬性論』。この本が有信の後の人生を大きく変えていくのであった。 有信の真摯に学ぶ姿に、多くの人が感化され、そして有信を支えていく。そして当時の日本ではまだ受け入れられなかった「医薬分業」に取り組み、明治5年(1872年)西洋薬舗会社「資生堂」を創業する。これが2012年に創業140周年を迎えた、あの化粧品会社「資生堂」として羽ばたいてゆくのである。 本書は数々の苦難を乗り越え、自らの意思を貫いた薬師であり実業家である福原有信の人生を描く著者渾身の評伝小説である。
-
-【頭のいい人は歴史に学ぶ!】 ●歴史人物26人の 「成功と失敗」の教訓 【人】【モノ】【お金】 【情報】【目標】【健康】 ●部下を持つアナタに贈る34の教え 「強い上司ほど部下の気持ちを想像すべきであったか」織田信長 「天下をとりたければ、ちょっとでも早く動くことだ」豊臣秀吉 「大きな目標を実現したければ、歳をとっても体を動かし続けろ」徳川家康 ●リーダーの悩みは 歴史人物の言葉で9割解決する! リーダーに必要な人間の大きさ、部下がついていきたくなる圧倒的な存在感をどう得たらいいのか。 失敗をしながらも偉業を成し遂げ、歴史になお残した偉人たちの些細にして心を揺さぶる言葉が、 リーダーが抱える問題・悩みを解決しれくれる。 リーダーシップは歴史に学んで掴みとれ! ●リーダーシップが身につく偉人の言葉 「その人の長所を活かすことが、名リーダーというものだ」(北条氏綱) 「実績をあげて出世する者ほど、上の者に気をつかうべき」(伊達政宗) 「天下をとりたければ、ちょっとでも早く動くことだ」(豊臣秀吉) 「基本ストイックですが、酒だけはやめられませんでした」(上杉謙信の反省) 【行動力】【決断力】 【統率力】【育成力】【コミュ力】 ●歴史の賢者に学ぶリーダーシップの知恵 本書は、経営の4大資源といわれる 「人」「モノ」「金」「情報」に 「目標」「健康」を加えた6つの経営資源で章立てして、 歴史上のリーダーたちが残した経験や考え方を紹介していきます。 各見出しの冒頭では、現代のリーダーも抱えそうな問題に対する歴史上のリーダーの言葉を提示しています。 これは実際に歴史上のリーダーが語ったものではなく、 歴史上のリーダーがとった対応を踏まえると、 このように答えたのではないかと、わかりやすく表現したものです。 リーダーの立場にある人、またこれからリーダーとなる人には、ぜひ歴史に学んでいただきたい。 そして、ただ歴史を学ぶだけでなく、それをリーダーとして活かしてほしいという思いを込めた一冊です。 ●目次 第1章 【人】を動かすリーダー力 第2章 【モノ】は知恵で活かされる 第3章 【お金】は後からついてくる 第4章 【情報】を活かした者が勝負を制する 第5章 【目標】は言葉に表して、実現に向けて動くのみ 第6章 【健康】を優先にしない者に優れたリーダーはいない
-
-誰もが知る日本の歴史人物の足跡を、地図とともに読む。 いつ、どこで、何を成し遂げたのか。そこに至るまでにどんな道筋やドラマがあったのか。 地図とともにたどることで、お馴染みの歴史人たちの輪郭がより鮮明に、より臨場感を持って浮き上がる。 本書に登場する人物…聖徳太子、源義経、武田信玄、上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、忠臣蔵、伊能忠敬、新選組、西郷隆盛、坂本龍馬、渋沢栄一、津田梅子 大河ドラマ監修などでお馴染みの小和田哲男はじめ、各人物研究のエキスパートが執筆。
-
3.3【内容紹介】 『史記』『孫子』『貞観政要』・・・古典でありながら現代でも不朽の名作として知られ、特に『孫子』と『貞観政要』はビジネス界の著名人らも愛読していることで知られています。 千年以上前に著された書物が今に通じることにも驚きですが、実はこれらの価値について数百年前に重要視し、後世に遺そうとしたある読書家がいました。その名は徳川家康――戦国武将として天下を統一し、260余年も続く泰平の日本を打ち立てた英傑です。 ただ、彼については「織田がつき 羽柴がこねし 天下餅 座りしままに 食うは家康」と詠われているように、織田信長や豊臣秀吉と比べ、大して苦労せずに天下人となった印象を持たれがちです。しかし、そこに至るまでには数々の挫折や苦難、そしてそれらを乗り越えていくという波瀾の生涯を送っています。間違いなく家康は多くの努力によって大成功を収めたのです。そんな彼が大切にしていたのが「本を読んで学ぶこと」でした。 本書は徳川家康の生涯についてマンガを交えたストーリーで追いながら、人生における決断の背景などを解説し、そしてそれらを支えた古典の名著を紹介していきます。家康の成功について、現代に生きる人々にも、参考になる要素や学びとなる書物について知ることができます。 2023年大河ドラマ『どうする家康』も、また違った視点で楽しめる1冊です。 【目次】 はじめに 第1章 「人質」からはじまった天下取り 第2章 戦国大名としての挫折と苦労 第3章 信長の死で芽生えた大志 第4章 大望の実現に向けた事業展開 第5章 待って仕掛けた天下への道 第6章 江戸時代260余年の礎を築く あとがき 読書の「才能」を日本人に広めた家康
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本刀の歴史を軸に、日本の歴史を振り返る。刀剣からみた新しい日本史の見方を提示する、トリビア風のコラムを約40本所収。日本の歴史を動かした事件や人物たちと日本 刀の関わりを紹介する。 【主な内容】 1章 古代~室町時代 神話時代の日本刀/蝦夷征伐(坂上田村麻呂の刀)/一条天皇と三条宗近/平将門の乱/源平合戦(薄緑丸)/承久の乱と後鳥羽上皇/蒙古襲来と相州伝の勃興/ほか 2章 戦国時代~江戸時代 川中島合戦/桶狭間の戦い/姉川合戦/中国攻め/長篠合戦/本能寺の変/小田原征伐/朝鮮の役/関ケ原合戦/徳川幕府誕生/明暦の大火/赤穂事件/享保の改 革/池田屋事件/寺田屋事件 ほか
-
-現代においても様々な経営者や各界のリーダーが座右の書として掲げる帝王学の最高傑作を読みやすい現代語訳と解説でわかりやすくお届けします。 源頼朝や徳川家康、明治天皇なども政治を司るうえで参考にしたとされている、これまでの中国史上でもっとも安定した時代とされる「貞観の治」を成した名君と家臣が交わした「対話」から、上に立つ者の「あるべき姿」を追い求めた名著がいよいよ本シリーズに登場します。 ・君主が取るべき道とは、何よりも人民を大切にすることだ。 ・君子が身を破滅させるとすれば、その原因は外からやってくる要因によるものではない。 ・木を高く伸ばそうとする人は、必ず根本をしっかりと固める。 ・病気は治ったかなと思ったときこそ、より慎重に養生をしなければならない。 ・君主は舟、人民は水である。水は舟を浮かべて運ぶものであるけれど、いっぽうでまた、舟を転覆させる。 ・天下を治めるうえで要となるのは、基本をしっかりと全うできるよう努力することに尽きる。 ・聡明な君子は短所があることを自覚し、臣下の忠言もよく聞いて努力をするから、ますます善良となってゆく。 ・太平の時代には、才能だけではだめで、必ず徳行を兼ね備えた人材を登用しなければなりません。 ・天は特定の人に親しくしようとするのではない。ただ、徳のある者を助ける。 ・臣下の忠誠を期待するのなら、それ相応の礼儀をもって彼らを遇しなければなりません。 ・言っても行われないのは、言葉に信用がないから。命令しても従わないのは、命令に誠実さがないから。 ・君子が発する一言は、計り知れない影響力を持つ。 ・人は学問をしなければ、ぼんやりと壁の前に立っているようなもの。 ・小臣には国政の大事を委任してはならず、大臣には小さい実務の罪を責めてはなりません。 ・禍福とはお互い隣り合わせの存在です。 ・ひと言によって国を興すことができるし、ひと言によって国を滅ぼすこともできる。 ・君も臣も他人の思惑ばかり気にするようになれば、国はいつ滅んでもおかしくありません。 <目次> 第1部 名著『貞観政要』とは 1.今読みなおされるべき名著 2.貞観政要が生まれた背景 3.現代に息づく『貞観政要』の世界 第2部 現代語抄訳で読む『貞観政要』 第3部 現代に生きる『貞観政要』の言葉 1.真のリーダーとは 2.諌言を受け止める度量 3.人材を見いだす心がけ 4.新しい世代を育てる 5.人材を徹底して活かす 6.感動をもたらすトップ 7.引き際の美学
-
3.0家康謀略史観に疑問を持つ事で見えてきた、浪人やキリシタン、商人の存在。武将の活躍の陰で、彼らもまた生き残りを賭け参戦した。軍功書、首取状などの豊富な史料を提示しつつ、大坂の陣を鮮明に描写する。 〈目次〉 はじめに 第一章 関ヶ原合戦と江戸幕府の成立──徳川公儀の確立 1 関ヶ原合戦後の戦後処理と諸勢力の動向 2 江戸幕府の成立と徳川権力の進展 第二章 大坂冬の陣勃発──仕組まれた戦い 1 方広寺鐘銘事件起こる 2 大坂冬の陣前夜 3 大坂冬の陣開戦する 第三章 和平交渉から大坂夏の陣へ──豊臣家の滅亡 1 和睦交渉の経過 2 大坂夏の陣への道 3 大坂夏の陣と豊臣氏の滅亡 第四章 大坂の陣のその後──戦国終焉の舞台 1 徳川方と豊臣方の扱い 2 落人・浪人たちのその後 3 キリシタンたちのその後 4 戦国の終焉 主要参考文献 おわりに
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 置碁の上達エッセンスを凝縮した一冊 大橋拓文七段による置碁の解説書です。 プロ対アマのガチンコ置碁やAIの置碁を題材に、序盤から中盤の戦術を伝授します。 「優勢の時はどう打てば勝てるか」「どういうところで逆転しているのか」具体的かつ丁寧に解説しています。 置き石の働かせ方や、白番の劣勢時の手段は必ず互先でも役立ちます。 大橋拓文七段による置碁の解説書です。 プロ対アマのガチンコ置碁やAIの置碁を題材に、序盤から中盤の戦術を伝授します。 「優勢の時はどう打てば勝てるか」「どういうところで逆転しているのか」具体的かつ丁寧に解説しています。 置き石の働かせ方や、白番の劣勢時の手段は必ず互先でも役立ちます。 また、特別編として徳川慶喜の五子局も収録しています。楽しみながら上達できる一冊です。 第1章 ガチンコ置碁、四~六子編 第2章 アマ強豪との二子局 第3章 AIの置碁 第4章 特別編 徳川慶喜の五子局 大橋拓文(おおはし・ひろふみ) 昭和59年生まれ。東京都出身。菊池康郎氏に師事。 平成14年入段。令和3年七段。 29年東京工業大学非常勤講師。 著書に『爽快!勝ち筋さがし』『囲碁AI時代の新布石法』『究極の上達ツール アルファ碁Teach完全ガイド』『万里一空 大橋拓文詰碁集』(マイナビ出版)、『よくわかる 囲碁AI大全』(日本棋院)など多数。 囲碁AIに関して造詣が深いことで知られている。詰碁作家としても有名。
-
3.0鎌倉殿・源頼朝、徳川三代将軍、歴代総理……大復活の裏に神社あり! リュウ博士による「歴史×科学×見えない世界」の授業 いじめ、敗北、離婚・失恋、親ガチャはずれ…… じつは、神社に祀られている神々は、 大きな失敗や挫折をしています。 たとえば、日本で一番尊い神様「アマテラス」は、 天岩戸にお隠れになるという、 日本最古の引きこもり。 日本最古の夫婦でもあるイザナミ・イザナギの「イザナギ」は、 黄泉の国まで行きながらも約束を破り、盛大な夫婦喧嘩。 ですが、アマテラスは、天岩戸開きを通じて、 他の神々の能力を引き出しました。 イザナギは、もっとも尊い三柱の神である 三貴神(アマテラス・スサノオ・ツキヨミ)を生みます。 「他者から助けられて成長し、他者を助けて成長する」 「最悪なときこそ、チャンスが訪れる」 「悪いことがあったら、良いことが起こる」 という神様が教えてくれる知恵は、じつは科学的にも証明されています。 そんな神様を祀っている 神社こそ、日本古来の大どんでん返しができる「システム」だったのです。 誰もが知っている「天下人」「成功者」は、そのシステムを活用してきました。 「鎌倉殿」の源頼朝も、 島流し20年の罪人から天下人になりました。 徳川三代将軍も全員大きなしくじりをしていますが、 260年続く平和な世を築き上げました。 武将、歴代総理大臣、名経営者が しくじりから大復活した秘訣「神社参拝」を徹底解説。 また、『古事記』『日本書紀』といった日本神話から 統計データ、科学論文まで用いてさまざまな角度から 「しくじりから復活する方法」を紐解きます! もちろん、お金、人間関係、ビジネス……といった 「しくじり別」おすすめ神社紹介も充実。イラスト満載で楽しく学べます。
-
3.0
-
-
-
-令和の日本に、徳川家康がいる−− その男、現代の日本に神出鬼没にあらわれては、ストレスを抱える人々を解決に導いていくという。 あるときは、タクシー運転手となり、仕事に疲れた乗客の女性モデルに、アロマと温泉による癒しの効果を伝え、またあるときはスーパーの店員となり、主婦に旬の食材を用いた晩ご飯の献立を提案するーー 食事、運動、休養、人間関係、ワーク・ライフ・バランス、マインドフルネス・・・ 天下をとった徳川家康の生き方を、実践しやすい形で示した、小説+健康のエンターテイメント。 目次 プロローグ 蘇る家康 第1章 家康の医学 上京する家康、薬で子供を救う編 第2章 家康の食事 ①主婦、旬の食材を食べる編 ②粗食じゃないよ素食だよ編 ③ソロキャンプで、いくさめし編 第3章 家康の運動 ①ゴルフ場で鷹狩編 ②居酒屋で運動指南編 ③馬? いや、時代はBMXだ編 第4章 家康の休養 ①モデルの癒し編 ②忍者の鍼灸編 ③夜は早く寝るから編 第5章 家康の教育 ①近頃の子育てにもの申すも……編 ②部下は優しく育てる編 ③課金より質素倹約編 第6章 家康のワーク・ライフ・バランス ①リモートワーク闖入編 ②趣味って何だろう編 ③家康、街コンに繰り出す編 第7章 家康のマインドフルネス ①売れないお笑い芸人、今日も耐え忍ぶ編 ②VRゴーグルで瞑想編 ③終活を考え始める編 エピローグ 人として生きる家康
-
4.0
-
-大名家の補佐役=No.2が“名家老”と呼ばれるには一つの明確な条件があった。 それは、“解決しなければならない危機的な状況を乗り越えた”ということである。 “家老”という立場に立たされた者たちは、生き残りを賭けての戦い、財政破綻、家督相続の内訌、派閥抗争より大きな権力との確執など、もはや弥縫策をもってしては解決できない、危機的な課題を解決しなければならなかった。 本書では、【徳川家】本多正信・正純、【仙台藩】片倉小十郎、【土佐藩】野中兼山、【小田原藩】二宮尊徳、【備中松山藩】山田方谷、【米沢藩】直江兼続、【田原藩】渡辺崋山など、動乱の時代を生き抜いた30名の名家老たちの、危機の戦略戦術の秘策を公開。現代の組織における、補佐役に必要な条件も学べる。
-
4.0
-
5.0わずか約2500の軍勢で3万8000の徳川大軍を翻弄し退けた知謀の男とは何者だったのか!? 名著者たちの論考でその実態に迫る、「日本一のつわもの」を読み解くためのアンソロジー。 【著者紹介】 江坂彰 (えさか・あきら) 一九三六年、京都府生まれ。京都大学文学部卒業。東急エージェンシー関西支社社長等を経て、八四年に独立し『冬の火花―ある管理職の左遷録』で作家としてデビュー。 白石一郎 (しらいし・いちろう) 一九三一年、釜山生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。五七年『雑兵』で第十回講談社倶楽部賞を受賞して文筆生活に入る。八七年『海狼伝』で第十七回直木賞を受賞。 百瀬明治 (ももせ・めいじ) 一九四一年、長野県生まれ。京都大学文学部卒業。『表象』同人、季刊『歴史と文学』編集長を経て、歴史を主対象とした著述業へ。 土門周平 (どもん・しゅうへい) 一九二〇年、東京都生まれ。陸軍士官学校卒業(第五十五期)。戦車師団中隊長で終戦。防衛研究所戦史編さん官等を経て、著述業へ。 南原幹雄(なんばら・みきお) 一九三八年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。日活に勤務。七五年退社し、作家生活に入る。七三年『女絵地獄』で小説現代新人賞受賞。 滝口康彦 (たきぐち・やすひこ) 一九二四年、長崎県生まれ。高等小学校卒業。以後独学。郵便局集配員、運送会社事務員、兵役約一カ年、炭鉱鉱員などを経て、ラジオドラマ小説の懸賞当選を機に文筆業となる。 新井英生(あらい・ひでを) 一九三三年、大阪府生まれ。早稲田大学文学部中退。文芸通信社記者を経て、文筆活動に入る。 【目次より】 序◆功名心を捨てよ。人はそこについてくる――江坂彰 第一章◆「日本一のつわもの」真田幸村――白石一郎 第二章◆「戦争芸術家」の悲愴なる闘い――百瀬明治 第三章◆「大坂夏の陣」一点集中突破の威力――土門周平 第四章◆「不惜身命」六連銭の気概――南原幹雄 第五章◆「表裏比興の雄」真田昌幸――滝口康彦 第六章◆上田城守備戦と「詭計」「謀略」――新井英生
-
3.8【目次】 はじめに--日本人は特殊か 序章 「空気」が原発を止めた 首相からの突然の「お願い」/玄海原発の失敗/「空気」が法律より重い国 第一章 日本人論の系譜 罪の文化と恥の文化/講座派と労農派/敗戦と悔恨共同体/文明の生態史観 唯物史観と「水利社会」/タテ社会とヨコ社会/人と人の間/安心社会と信頼社会 「水社会」の同調圧力/灌漑農業のボトムアップ構造 日本人の肖像--福沢諭吉 第二章 「空気」の支配 「日本教」の特殊性/自転する組織/日本軍を動かした「空気」/公害反対運動と臨在感 アニミズムから一神教へ/一揆と下克上/動機の純粋性 日本人の肖像--北一輝 第三章 日本人の「古層」 超国家主義の構造/無責任の体系/国体という空気/フィクションとしての制度 つぎつぎになりゆくいきほひ/永遠の今と「世間」/キヨキココロの倫理 「まつりごと」の構造/天皇制というデモクラシー/全員一致とアンチコモンズ ボトムアップの意思決定/「古層」とポストモダン/近代化なき成長の終わり 日本人の肖像--南方熊楠 第四章 武士のエートス 日本のコモンロー/徳川の平和/自然から作為へ/尊王攘夷の起源/開国のインパクト 惑溺と自尊 日本人の肖像--岸信介 第五章 日本軍の「失敗の本質」 目的なき組織/曖昧な戦略/短期決戦と補給の軽視/縦割りで属人的な組織 心情が戦略に先立つ/心やさしき独裁者/両論併記と非決定/大日本帝国の密教と顕教 日本人の肖像--石原莞爾 第六章 日本的経営の神話 外国人の見た日本企業/日本的経営の黄金時代/勤勉革命の伝統/日本的労使関係の起源 日本企業は町工場の集合体/協力と長期的関係/共有知識としての「空気」/村から会社へ 日本的雇用がデフレを生んだ/年功序列の終焉/グローバル資本主義の試練 日本人の肖像--中内功 第七章 平和のテクノロジー 殺し合う人間/集団淘汰と平等主義/偏狭な利他主義/戦争が国家を生んだ 「無縁」とノマド/飛礫の暴力性/古層と最古層/なぜ「古層」は変わらないのか 日本人の肖像--昭和天皇 第八章 日本型デモクラシーの終わり 空虚な中心/多頭一身の怪物/霞が関のスパゲティ/「政治主導」の幻想 日本型経営者資本主義の挫折/約束を破るメカニズム/セーフティ・ネットが檻になるとき 閉じた社会から開かれた社会へ 注 人名索引
-
4.7「京都という街は、タイムカプセルのようだ」と著者は言う。オフィス街の真ん中に聖徳太子創建と伝えられるお寺があったり、京都きっての繁華街に、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された地の石碑がひっそりと立っていたり。そこには人々の日常があり、みなが変わりない暮らしを続けている。そんな石碑になど目を留めない人もたくさんいるはずだ。 それでも著者は、そんな場所に出会う度に、タイムカプセルを開けたような気持ちになるのだという。幕末の争乱期の京都へ、平安遷都する以前の京都へ、近代化が急速に進んだ明治・大正時代の京都へ……。さまざまな時代の“時”のカケラが、街のそこかしこに埋まっている。この場所で徳川慶喜は何を思ったのだろう。平家全盛のころの六波羅は、どんな景色だったのだろう。安倍晴明はここで何を見たのだろう。その“時”のカケラは、一瞬の時間旅行へと誘ってくれる。 日本美術研究者として活動する著者が、京都の通り界隈にまつわる逸話から、神社仏閣の歴史、地元の人々の季節折々の暮らし、街歩きでの目のつけどころや楽しみどころ、京都人の気質までを生活者の視点から紹介する。さらに、自身のご家族のこと、京都府警と側衛の方たちとのやり取りなどの日常生活の一端を、親しみやすい文体でつづる。6年以上、著者が京都に暮らす中で感じ、経験した京都の魅力が存分に語られており、「京都」という街の奥深さと、「京都」の楽しみ方を知る手がかりとなる。 新聞連載の24作品に、書き下ろし3作品を加えて刊行。京都の街歩きに役立つ「ちょっと寄り道」情報や地図も掲載。
-
-関ケ原の戦いに勝利した徳川家康が、江戸に幕府を開いてから約260年。徳川家の強固な支配体制のもと、日本にはかつてないほど平和な時代が訪れた。 時代劇や時代小説の影響もあってか、現代における江戸のイメージはすこぶる良い。「タイムマシーンがあったら、いってみたい」などと思っている人もいることだろう。 だが、本当に江戸時代はいい時代だったのか。江戸の人々は太平の世を漫喫していたのだろうか。 残念ながら、江戸の現実はそれほど甘くはない。 劣悪な衛生環境、病気になったら最後の低い医療レベル、度重なる飢饉に大火事、地震、火山の噴火……街には通り魔やスリがウヨウヨおり、人権完全無視の犯罪捜査や裁判が横行していた。 その過酷さは、「ご先祖さまはよくぞ、こんな時代を生き抜いた」と思わず手を合わせて拝みたくなるほど。 とにかく、ハチャメチャだった江戸時代。そのダークサイドに迫る!
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 逃げる、泣きつく、人まかせ…がんばらなかったのに何とかなった、日本史人物25人の「逆偉人伝」。読めば気持ちが楽になる! ・がんばって歴史に名を残した人の業績をたたえるのが偉人伝。でも、がんばらなかったことで有名な歴史人物も。本書はそういった日本史人物25人の所業を集めた「逆偉人伝」。あの人もこの人も、実はがんばっていなかったり、力を抜いて生きていた!? ・逃げる(木戸孝允)、泣きつく(足利尊氏)、人まかせ(徳川家綱)、スルーする(和泉式部)、世間を気にしない(前田慶次)、投げ出す(上杉謙信)、がまんしない(坂本龍馬)、こだわらない(徳川家康)、嫌われ上等(石田三成)、日常生活を放棄(葛飾北斎)、趣味に生きる(徳川慶喜)、本業やる気なし(足利義政)…など、いろいろなパターンの「がんばらなさ」を発揮した25人を収録。 ・人気イラストレーターねこまきが、各人物をその特徴からおもしろ動物キャラ化。イラスト&マンガも満載で、見るだけで楽しい! ・がんばらなくても、それぞれの生き方をした人たちの多様な生き方を楽しく読みつつ、「こんな生き方もアリ」「がんばるだけが人生じゃない」「立派じゃなくてもいい」「生きるっていとおしい」と思えてくる、新しい日本史人物図鑑です。 ・がんばりすぎた結果として、成功しなかった、過労死した、不運に終わったといった人物のコラムも。 加来 耕三(カクコウゾウ):歴史家・作家。奈良大学文学部史学科を卒業。同大学文学部研究員などを経て、著作活動に入る。テレビ・ラジオ番組への出演、歴史書の監修、マンガ・アニメの原作、大学講師、企業での講演など、幅広く活躍。著書に『徳川家康の勉強法』(プレジデント社)、『歴史の失敗学 25人の英雄に学ぶ教訓』(日経BP)など多数。 ミューズワーク(ねこまき)(ミューズワークネコマキ):2002年より、名古屋を拠点にイラストレーターとして活動を開始。コミックエッセイをはじめ、ねこや犬のゆるキャラマンガ、広告イラスト、アニメなどを手がける。著作に『ねこマンガ 在宅医たんぽぽ先生物語 さいごはおうちで』『ねこマンガ 在宅医たんぽぽ先生物語 おうちに帰ろう』(いずれも主婦の友社)、『ねことじいちゃん』(KADOKAWA)、『トラとミケ』(小学館)など多数。
-
-1000年後のこの世は みんな神様だらけ! ◆来世のご利益いま先取り! イラストレーター/キャラクターデザイナー/エッセイ漫画家として活躍する著者が、「西暦3000年の神様」を大胆予想! かつては一人の武士に過ぎなかった徳川家康が日光東照宮で祀られているように、 未来の世界では、現代では当たり前の人やモノが神様になっている可能性があると著者は予想します。 例えば、ギャルやホスト、陰キャ、港区女子、ヤンキー、意識高い系、ゆるキャラ、満員電車など、 現代では当たり前のものでも未来の世界では神様になっているかもしれないのです。 本書では、コミカルなイラストとともに、さまざまな未来の神様とそのご神徳を紹介。 読めば、今から未来の運気を先取りできるかも??
-
4.0
-
3.0江戸城は、日本最高峰の技術とマンパワーが集結して築かれた日本一の城です。 現在皇居になっている西の丸や山里丸、皇居東御苑として一般開放されている本丸・二の丸・三の丸の一部、北の丸公園になっている北の丸や大手前などが「内郭」と呼ばれる中枢部にあたり、内郭の外側を「外郭」と呼ばれるエリアが囲みます。神田川が隅田川に注ぐ両国橋脇の柳橋あたりが外濠の東側で、そこから浅草橋、御茶ノ水、小石川、市ヶ谷、四谷、虎ノ門と続き、数寄屋橋、梶橋、常盤橋、雉子橋まで。東が隅田川、永代橋や両国橋の手前までが城域です。外郭の総延長は14キロメートルもあります。秀吉が築いた大阪城の総構は約7.8キロメートルとされますから、それを凌駕するとてつもない大きさだったのです。 本書では、巨大城郭・江戸城の秀逸な構造と築城秘話を紹介します。徳川家康が豊臣秀吉の命で入った江戸は、ひどい荒地でした。しかし家康は、不毛の地・江戸を「理想の国家をゼロから構築できる新天地にしよう」と思考転換したのです。 江戸城を築くときに家康が見据えたのは、江戸幕府の盤石な体制づくり。そのため、強靭な軍事力のある城でありながら、政治・経済・商業の中心地となる国家の中枢として機能する城であり、徳川家の威厳と権威をこれでもかと見せつける存在感が求められました。 本書ではこのような築かれた時代背景、立地や地形、設計などの特徴はもちろん、城の変遷、天守や御殿の構造や装飾、石垣の積み方や石材の採石法、さらには江戸の町づくりや幕府のしくみまで、さまざまな視点から江戸城の全貌と魅力に迫っています。 実際の城歩きにも役立つ内郭及び外郭の見どころも紹介。大都市・東京に、江戸城の片鱗は今も力強く残っていることがわかります。
-
4.0【内容紹介】 組織を「安定軌道」に乗せるにはどうすべきか? 歴代天皇、徳川家康、北条政子ほかが愛読した「帝王学の教科書」をやさしく解説。 ロングセラー『「貞観政要」のリーダー学』がわかりやすく読める! 中国古典の大きな柱となっている帝王学のテキストとして使われた『書経』とならぶ古典が『貞観政要』です。 ここには唐王朝の二代目太宗李世民にまつわる話が収められています。 李世民は長い中国の歴史の中でも屈指の名君と知られ、平和で安定した社会を築くことに成功しました。 その後、『貞観政要』は多くのリーダーたちに読み次がれてきましたが、あまりに膨大な書のため、読み解くことが難しい。 そこで中国文学者・守屋洋氏がプレジデント社から上梓した『「貞観政要」のリーダー学』をさらに読みやすく編集したのが本書です。 【著者紹介】 守屋洋(もりや・ひろし) 著述業(中国文学者)。1932年宮城県生まれ。東京都立大学中国文学科修士課程修了。 『孫子、呉子』、『六韜・三略』『司馬法・尉繚子・李衛公問対』(いずれも守屋淳との共著)、『菜根譚の人間学』『論語の人間学』(いずれもプレジデント社)ほか著書多数。【目次抜粋】 はじめに 序章 創業か守成かを問う 第一章 安きに居して危うきを思う 第二章 率先垂範、わが身を正す 第三章 臣下の諫言に耳を傾ける 第四章 人材を育成し、登用し、活用する 第五章 明君と暗君を分かつもの 第六章 初心、忘るべからず 第七章 有終の美を飾らん 解題 唐の太宗と補佐役たち 人物評伝 本書に登場する才人・異人たち
-
5.0時は1899年。いまだ倒れぬ徳川幕府と薩長同盟はともに性急なる近代化と軍備増強に余念なし。一方、強化アーク灯の光届かぬ荒野には未だ魑魅魍魎が跋扈する。この暗黒の時代、人知れず妖怪狩りを続ける男がいた。男の武器はウインチェスターM1876Z式ライフル銃。コルト社製アンブローズ・ビアス・スペシャル。そして鋼の信念。大公儀魑魅魍魎改方の最後の生き残り。不吉なる妖怪猟兵の装束を纏いて、黒の軍馬シャドウウィングを駆る偉丈夫。その男の名は……小泉八雲。
-
-明治維新はテロリストの政権奪取にあった! 幕末の京都、徳川幕府を守ろうとする京都守護職の会津藩と、討幕を目論む長州藩。兵力で劣る長州藩は、闇討ち、奇襲といったテロ行為、ゲリラ戦法で局面打開を図り、ついには「尊王」を掲げているにも関わらず御所に向けて砲弾を放つ。幕府弱体の情勢の中で孤軍奮闘の会津藩主・松平容保は必死に応戦し勝利していくも、長州の力を完全には抑えることができない。やがて薩摩と手を組んだ長州はスコットランドの武器商人から最新兵器を入手し、形勢は逆転。「会津藩とはいったい何なのか」――。 時代の変化を理解しない孝明天皇、一橋慶喜ら権力者に対して、悲しいまでの忠誠を尽くす容保の苦悩と彼を取り巻く人間の様相を描きつつ、戊辰戦争、明治維新の真相に迫る。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 歴史ロマンの宝庫である、城。 巻頭では天下とりに挑んだ戦国大名たちの城を、ビジュアルでダイナミックにご案内します。 安土城(織田信長)をはじめ、駿府城(今川義元)、武田氏館(武田信玄)、春日山城(上杉謙信)、広島城(毛利輝元)、 岐阜城(斎藤道三)、仙台城(伊達政宗)、岡豊城(長宗我部元親)、小田原城(北条早雲)、大坂城(豊臣秀吉)、江戸城(徳川家康)。 また築城当時の天守が現存する12の城(姫路城、松本城、彦根城、犬山城、弘前城、丸岡城、丸亀城、松山城、備中松山城、松江城、宇和島城、高知城)や、一生に一度は訪れたい名城、約80城を紹介。 コラム「姫君と城」では、岩村城の女城主・お直の方、二度の落城を経験した信長の妹・お市の方など女性のドラマも。 築城で高名な三大大名(加藤清正、藤堂高虎、黒田如水)、映画「火天の城」でも話題の岡部又右衛門などの築城名人紹介、 プロによる城の見方・歩き方ガイド、東西の違いがわかる築城マップなどで城めぐりがもっと楽しくなります!
-
3.02017年NHK大河ドラマ決定! ! 浜松、彦根、井伊家1000年の歴史がわかる。 徳川家康だけでなく、豊臣秀吉からも高い能力を認められた徳川四天王の一人だった井伊直政。その直政を育てたのが、2017 年NHK 大河ドラマの主人公である養母の井伊直虎だった。 幕末の大老で桜田門外の変で暗殺される井伊直弼に続く名門井伊家は、どのように形づくられたのか。彦根市出身で、彦根藩の元藩校だった彦根東高校卒業の田原総一朗氏が「井伊家」の歴史に大胆に迫る! 【著者紹介】 田原総一朗(たはら・そういちろう) 1934年、滋賀県彦根市生まれ。県立彦根東高校卒。60年に早稲田大学卒業後、岩波映画製作所、テレビ東京を経て、77年フリーに。 98年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又一賞を受賞。現在、テレビ朝日系『朝まで生テレビ!』など幅広いメディアで活動中のほか、早稲田大学特命教授、「大隈塾」塾頭も務める。 著書に『日本の戦争』(小学館)、『堀の上を走れ 田原総一朗自伝』(講談社)、『誰もが書かなかった日本の戦争』(ポプラ社)など多数。 【目次より】 ◆はじめに ◆第1章 「井伊家」から私たちが学べること ◆第2章 「井伊家」千年の歴史 ◆第3章 直虎と直政のきずな ◆第4章 譜代筆頭・大老家として生きる ◆第5章 幕末、主家を想い、日本を想う。そして、死を恐れない
-
4.0大坂冬・夏の陣も過去となった江戸時代。徳川幕府体制の下、人々は泰平の世を謳歌していた。しかし、敢えて平穏な生活に背を向ける数多の人間たちがいた! 「人間の剣」完結編
-
-【ご注意】※この電子書籍は紙の本のイメージで作成されており、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 遺愛品が雄弁に物語る徳川家康75年の生涯。 松本潤主演の2023年大河ドラマ『どうする家康』は、1983年の『徳川家康』以来40年ぶりに徳川家康が主人公となることで話題を集める。静岡市の久能山東照宮は、家康が75年の生涯を閉じる際、自らの亡骸を久能山に葬るように遺言した地に鎮座し、家康が着用した具足、普段づかいの日用品など多くの遺品が蔵されている。本企画は、久能山東照宮が所蔵する徳川家康遺品の数々を紹介しながら、戦国時代を終焉させ、わが国に平和をもたらした不世出の英雄の生涯を振り返る写真集。「金陀美具足」や関ケ原合戦時に着用した「歯朶具足」などの甲冑類から、馬標、太刀、目器、鉛筆、日常的に使用した道具類も多数掲載。若き日の家康を描いたという「徳川家康像」や東照大権現像も登場。『家康』の著書もある歴史作家の安部龍太郎氏と久能山東照宮名誉宮司、宮司との鼎談も掲載。かつては、武田信玄が築城した山城跡に鎮座する境内も案内。 ※この作品はカラーです。
-
3.0本書は、戦国を中心とした名将たちの戦略・思考に迫りながら、強い組織をつくり、生き残るための方法を解き明かす一冊です。 桶狭間の戦い、本能寺の変、小田原征伐、関ヶ原の戦い、大坂冬の陣・夏の陣……。 戦国末期から江戸にかけての時代は、まさに数年先さえ見えない「混迷の時代」。 勝者がふとしたことから敗者へと転落し、一方で新興勢力がいきなりトップに上り詰めます。 ひるがえって現代。 電機や自動車、外食などで、かつて業界をリードした大企業が次々と凋落。 そうかと思えば、設立十数年の新興IT企業が破竹の勢いで伸長しています。 このように、現代と戦国・江戸初期は、「先の見えない時代」という意味では実はとても似ています。 だからこそ今、この時代を生き抜いた名将=名リーダーたちの戦略を知ることは、大きな意味を持つのです。 本書は、ロングセラー『軍師の戦略』の著者で、プロ経営者・歴史研究家として活躍する皆木和義氏が、それら名将たちに迫ります。 激動の時代を最後まであきらめずに生きた武将たちの戦略や決断、思考は、どのようなものだったのか。 彼らは、どのように人の心をつかみ、動かし、生き残ることができたのか。 それぞれの登場人物の戦略・決断の明暗を通して、ビジネスで学ぶべき教訓を解きほぐしていきます。 主に取り上げるのは、大河ドラマ『真田丸』の主人公である真田信繁(幸村)や信幸・昌幸のほか、徳川家康、上杉鷹山など。 そのパートの内容に関連する、あるいは端的に表す古今東西の名言も随所に挿入しています。 本書で、混迷の時代を見通す名将たちの戦略に、ぜひ触れてみてください。
-
4.0不滅の「帝王学の教科書」を、新たなスタイルでわかりやすく読み解いた、すべてのリーダーにとって必読の一冊が、ついに誕生しました。『貞観政要』は、中国史上、最善の政治を行なったといわれる唐の太宗と、それを取り巻く名家臣たちの言行録であり、北条政子や徳川家康なども座右の銘としてきた書です。太宗がどんな問題に直面し、どう行動したかについて、『論語』など中国古典の叡智をふんだんに交えつつ、紹介していきます。まさに、マネジメントの実際と中国古典の叡智を合わせて学べる、リーダーにとっての生きたヒントの宝庫なのです。しかし、中国古典であるために、現代の日本人には、なかなか手を伸ばしにくいのも事実です。そこで本書では、社長とその先輩の対話形式で『貞観政要』を読み解いていきます。現代の企業事例も引きながら、『貞観政要』のエッセンスが明解、かつ具体的に語られていくのは圧巻。ぜひ、手元に置きたい一冊です。
-
-プレゼン、会議、商談など、相手を動かさなければならない場面は数多い。どうすれば、相手を自分が思うように動かせるのか? それを教えてくれるのが、歴史上の偉人たちだ。交渉の場面で、彼らがどのように勝利を得てきたのかを知れば、仕事力が格段に上がる! 〈目次より〉第1章 交渉はテーブルにつく前に決まっている ●勝海舟の事前準備力 ●豊臣秀吉のシナリオ構築力 ●伊達政宗の臨機応変力 第2章 流れを一気に変える言葉とタイミング ●徳川家康の状況形成力 ●徳川家康の女性人材活用力 ●北条政子のプレゼンテーション力 ●北条早雲の忍耐力 第3章 人間力で勝った偉人たち ●黒田官兵衛の実直力 ●直江兼続の忠義力 ●林大学頭復斎の冷静沈着力 ●西郷隆盛の無私の力 第4章 あきらめたら負け ●大久保利通の堪忍力 ●大石内蔵助の巻き返し力 ●島津義弘の負けっぷり力 第5章 失敗から学ぶ交渉の要諦 ●明智光秀の引き際力不足 ●安国寺恵瓊の野心力過剰 ●徳川慶喜の覚悟力不足
-
4.0明智光秀を討った秀吉が、信長の重臣であった柴田勝家を破って後継者になった――教科書によく載っている記述ですが、ここにはとても重要な事実が抜け落ちています。それは、本能寺の変で信長の血筋が絶えたわけではなく、信長の血を受け継いだ織田家の人間が複数いたにもかかわらず、家臣の秀吉が権力を受け継いだ理由です。天下分け目の「関ヶ原の戦い」は、たった1日で終わった――誰もが知る事実ですが、なぜ「1日」で終わってしまったかの理由はあまり知られていません。大河ドラマなどで何度も扱われているにもかかわらず、日本人は意外に戦国のことを知らないのです。本書では、「中国大返しはなぜ成功したのか」「なぜ関ヶ原の戦いは1日で終わったのか」「豊臣秀吉と徳川家康は、いかにして天下を奪い取ったのか」「三英傑が目指した天下人とは?」など、知っているようで実は知らない戦国史を井沢元彦独自の視点で見直します。
-
4.3
-
3.8
-
5.0九州統一戦の見事な勝利の数々、明軍相手の大勝利、関ヶ原の戦いでの敵中突破、西軍唯一の本領安堵――。「戦国最強」として世に名高い島津氏。しかし、通俗のイメージと学界のイメージが、これほど乖離している大名はいない。実は歴史学者の間では、満足に家臣を統率することもできない、「弱い」大名として理解されてきた。 家の存続という目的は同じながら、異なる道を選び、譲らぬ兄と弟。言うことの聞かぬ家臣、内政干渉する豊臣政権、関ヶ原での敗北を乗り越えながら、いかにして薩摩藩を築き上げたのか。戦国島津氏研究の第一人者による、圧巻の評伝! 【目次】 第一部 戦国期の義久・義弘兄弟―ふたりが目指したもの― 第一章 島津氏の源流と戦国大名島津氏 第二章 義久・義弘兄弟の三州統一戦 第三章 戦国島津氏権力のイメージと実態 第四章 義久・義弘兄弟にとっての九州統一戦 第二部 豊臣政権との関係―義久・義弘兄弟の反目― 第一章 降伏直後の島津領国―混乱と領国経営破綻― 第二章 義弘の「豊臣大名」化と島津久保の家督継承内定 第三章 義久・義弘兄弟の対立表面化と「唐入り」準備 第四章 「日本一之遅陣」と島津歳久成敗 第五章 島津忠恒の世嗣承認と文禄の「太閤検地」 第六章 慶長の役と秀吉の死、朝鮮からの撤退 第三部 庄内の乱と関ヶ原の戦い―晩年の義久・義弘兄弟― 第一章 忠恒の家督継承と伊集院忠棟誅殺 第二章 庄内の乱 第三章 関ヶ原の戦い―義弘が寡兵だったのはなぜか?― 第四章 関ヶ原の戦後処理―徳川家康との和平交渉― 第五章 琉球侵攻とふたりの晩年 おわりに―島津義久・義弘の人物像―
-
3.3
-
4.0秀吉は、旧織田家臣や旧戦国大名に羽柴名字を与えることで「御一家」と位置づけた。羽柴家の論理による秩序化である。全く新しい武家の政治序列の方法を創り出した、秀吉の野望と類い希な政治手腕を描き出す。 ◆第一章 羽柴名字と公家成大名 ◆第二章 秀吉の一門大名 羽柴秀長・秀保/羽柴秀次/羽柴(小吉)秀勝/羽柴秀俊(小早川秀秋) ◆第三章 秀吉の親類大名 宇喜多秀家/結城秀康/前田利家・利長(利勝)利政/徳川家康・秀忠/京極高次/京極高知(生双)/木下勝俊/某 秀弘/青木重吉/福島正則・正長・忠清(忠勝) ◆第四章 織田家の人々 織田秀信/織田秀雄/織田信兼/織田長益・頼長/織田信秀/織田信高/織田信吉 ◆第五章 旧織田家臣の人々 堀秀政・秀治・秀隆(忠俊)/堀秀家(秀成・親良)/滝川雄利・正利/丹羽長重/長岡(細川)忠興・忠隆/蒲生氏郷・秀隆(秀行)/蜂屋頼隆/毛利秀頼/稲葉貞通・典通/津川(斯波)義康/長谷川秀一・秀康/前田秀以・茂勝/佐々成政/筒井定次/池田照政(輝政)・照直(利隆)/森忠政 ◆第六章 旧戦国大名の人々 上杉景勝/大友吉統(義統)/長宗我部元親・盛親/島津義弘・忠恒(家久)/立花統虎(親成・宗茂)/龍造寺政家/毛利輝元・秀元/小早川隆景・秀包(秀直)/吉川広家/宗吉智(義智)・義成/佐竹義宣/最上義光・義康/伊達政宗/里見義康/宇都宮国綱 ◆第七章 羽柴名字の消滅
-
3.5
-
4.2内閣全員、英雄――。 2020年。 新型コロナの初期対応を誤った日本の首相官邸でクラスターが発生。 あろうことか総理が感染し、死亡する。 国民は政府を何も信頼しなくなり、日本はかつてないほどの混乱の極みに陥った。 そこで政府はかねてから画策していたAIとホログラムにより偉人たちを復活させ最強内閣をつくる計画を実行する。 AIにより総理大臣に選ばれたのは、江戸幕府の創始者である徳川家康。 経済産業大臣には織田信長、財務大臣に豊臣秀吉、厚生労働大臣に徳川綱吉、法務大臣に北条政子、外務大臣に足利義満など錚々そうそうたるメンバーの中で、 皮肉にも総理大臣の補佐役である官房長官に選ばれたのは、江戸幕府を終わらせた男・坂本龍馬だった。 そんな歴史に名を刻む面々で組閣された最強内閣は、迅速な意思決定で、 東京ロックダウン、50万円給付金、リモート国会、令和版楽市楽座、リモート万博など、大胆な政策を次々と実行していく。 最初は「過去の人間に政治ができるのか」と半信半疑だった国民も、偉人たちのえげつない決断力と実行力に次第に歓喜し、酔いしれていくが……。 時代を超えたオールスターは未曾有の危機にどう立ち向かうのか!? そして、ミッションを果たした先に待ち受けていたものとは……!? ビジネス、歴史、政治、ミステリー、 あらゆるジャンルと時代の垣根を超えた教養溢れる 新感覚エンターテインメント!!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 劇画ありギャグありBLあり実録モノありの漫画で、笑いながら一気読み! 授業ではとても覚えきれなかった「日本史」、 本書にある大事なことだけつかめば簡単に理解できて、こんなにも面白い! 日本史に燦然と輝く英傑や将軍たち、お姫様たちの実像から、権門体制論や東国国家論などの歴史学論争まで、これさえ押さえておけば古代~幕末の日本史重要事項がざっくり頭の中に入ります。 ◆第1章 英雄の真実 織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・源頼朝 ◆第2章 毒武将列伝 北条義時・足利尊氏・毛利元就・斎藤道三・松永久秀・宇喜多直家 ◆第3章 貴族と武将の恋愛劇。そして愚かなる殿さま 細川忠興・北条政子・藤原頼長・奥平昌能・吉良上野介・徳川家斉・足利義政 ◆第4章 正直、過大評価されているかもしれない人々 伊達政宗・足利義昭・上杉謙信・真田幸村・後醍醐天皇・福島正則・平将門・崇徳天皇・菅原道真・鍋島勝茂 ◆第5章 歴史に残るやらかし 平清盛・直江兼続・鳥居元忠・井伊直弼 ◆第6章 踏み込むのが恐ろしいむ日本史、闇の禁忌 持統天皇・孝謙天皇・光厳天皇・淀殿・孝明天皇 ◆まんがでわかる歴史学 古代律令国家・権門体制論・東国国家論と二つの王権論・幕藩体制と大政委任論 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 作家、読書人など多くの人から愛される 希代の名著『人間臨終図巻』がまさかの漫画化! 戦後日本を代表する大衆小説の大家・山田風太郎が、 著名人(英雄、武将、政治家、作家、芸術家など)、 923人の死に様を切り取った『人間臨終図巻』。 本書ではその中から、紀元前~昭和まで、 出生順に120人を厳選して漫画化した。 歴史上の人物の意外な死に方に、 あなたは何を思うか? 【主な収録人物】 ◎ピタゴラス 豆を踏めなくて市民に殺された ◎アレキサンダー大王 「何だかつまらない遺言」の内容とは ◎平清盛 平家物語に書かれた死に際が劇的すぎる ◎一休 七十代後半でも夜はお盛んだった ◎徳川家康 鯛の天ぷらを食べすぎて食あたり ◎勝海舟 最後の言葉の中の最大傑作「コレデオシマイ」 ◎夏目漱石 「早くここへ水をぶっかけてくれ。死ぬと困るから」 ◎小津安二郎 「何かいってないとたまらないんだ。ナンマイダ」
-
3.8※電子書籍版にはグラビアページ、特典はありません※ 乃木坂46・山崎怜奈さんの書籍の発売が決定いたしました。 歴史やクイズなど、本人の幅広い興味を軸に、様々なフィールドで活躍を続ける山崎怜奈さんの初めての書籍は、2019年までひかりTV・dTVチャンネルで放送されていた「乃木坂46山崎怜奈 歴史のじかん」を基にした歴史本です。 全50回の放送から、山崎さんが選んだ14回を厳選して掲載しています。専門家の先生2名と山崎さんによる解説パートと、その内容から山崎さんが考えたことを綴るコラムパートの2本立てとなっています。 自らも歴史に詳しい山崎さんならではの視点で深堀りされているので、わかりやすいのに奥深い考察が満載。歴史好きな方もそうでない方も楽しめること間違いなしです。 【山崎怜奈コメント】 この度、歴史本を出版させていただくことになりました。 好きなことを本で表現できる機会をいただき、大変嬉しく思います。 また、ゲストでお越しくださった先生方の愛ある解説にも注目です。改めて御礼申し上げます。 この時代を生きやすくなるようなヒントを、先人たちの生き方から得られる一冊です。 読み終えた後、歴史の授業で感じていたモヤモヤが少しでも晴れますように! 【取り上げたテーマ】 応仁の乱/戦国の合戦/千利休/明智光秀/蒲生氏郷/真田幸村/忠臣蔵/伊能忠敬/塙保己一/安政の大獄/徳川将軍家/岩﨑弥太郎/渋沢栄一/太宰治 【この本に登場してくださった先生方】 一坂太郎、伊東潤、井上潤、冲方丁、小和田哲男、河合敦、木村綾子、黒田基樹、呉座勇一、齊藤幸一、乃至政彦、橋場日月、堀口茉純、本郷和人、宮下玄覇、母利美和、安田清人、山口俊雄、山本博文(敬称略)
-
4.3
-
3.8
-
3.5大名から御家人まで、江戸時代の元武士たちが明治維新後に語った回顧談。江戸時代の生活・習俗・規則などの話題から、薩英戦争や大政奉還のような大事件まで、当事者として居合わせた人々だからこそできる貴重な話を、江戸学の祖・三田村鳶魚の著作に携わった柴田宵曲が編む。親本は青蛙房から刊行された『幕末の武家』。文庫化にあたり新たな注釈を加えた。江戸時代を知るための必読の書。 解説・高尾善希 【内容(一部)】 ・江戸城の開門・閉門のしきたり ・米公使を言い負かした弁舌の立つ老中 ・苛烈を極めた旧幕臣の静岡への移住 ・薩英戦争真っ只中のイギリス軍艦に乗り合わせた日本人 ・軍艦開陽丸を受け取りに行く途中インドネシアで難破した話 【目次】 解題 柴田宵曲 大名の日常生活 浅野長勲 大奥秘記 村山鎮 時の御太鼓 桂園 高家の話 大沢基輔 御船手の話 向井秋村 御朱印道中・御目付 桂園 御徒士物語 鈍我羅漢 勤番者 内藤鳴雪 お伽役の話 伊藤景直 廻り方の話 今泉雄作 雲助 宮崎三昧 幕末の話 梶金八、飯島半十郎、江原素六、柴太一郎、立花種恭、竹斎、六十匁道人、相陽道人、松本蘭疇、流行歌 明治元年 塚原渋柿 外国使臣の謁見 江連堯則 明治以前の支那貿易 山口挙直 幕末外交瑣談 田辺太一 目撃した薩英戦争 清水卯三郎 日蘭交渉の一片 長岡護美 徳川民部公子の渡仏 呉陽散士 和蘭留学の話 あられのや主人 幕府軍艦開陽丸の終始 沢太郎左衛門
-
3.0日本の独立と繁栄を実現した運命の将軍! 江戸幕府を開いた徳川家康の人生は危機の連続だった。いつ殺されてもおかしくない人質だった幼少期、今川から独立し信長と同盟を結び命を張って信玄上洛を阻止、本能寺の変後の命からがらの遁走、天下分け目となった関ヶ原の戦い。さまざまな危機の中でもこれまであまり語られてこなかったのがキリシタン勢力の日本征服計画である。 信長・秀吉・家康の時代は、まさに大航海時代(15世紀初~17世紀初)の真っただ中。スペインによるインカ帝国滅亡など、西欧列強が世界征服事業を進めていた時期だった。とくにポルトガル・スペインは布教と海外征服がセットになっており、実際に日本人が奴隷として海外に輸出されてもいた。宣教師と本国の間では日本征服計画が語られ、植民地化の危機が迫っていた。 危険な宗教をどう扱うか。すでに三河や長島の一向一揆の激しさで、宗教問題の難しさは家康もよくわかっていた。「商教分離」だった徳川幕府は、鎖国へと大きく舵を切り、「徳川の平和(パックス・トクガワーナ)」が成立したのである。戦国の世を生き抜き、日本の独立と江戸250年の泰平の礎を築いた徳川家康、その知略と激動を描く!令和5年NHK大河ドラマ化。
-
4.0江戸時代の武家社会で最も権威のある存在――それが、征夷大将軍である。武士のトップに立つ将軍ともなれば、さぞ、自分の思うままに采配を振り、大勢を従えながら、人生を謳歌したのだろうと思うかもしれない。 しかし、現実の将軍はそんなイメージとはかけ離れている。上司の豊臣秀頼との付き合いに苦心する初代家康、強権すぎて幕臣が暴走を止められなかった5代綱吉、支持者に忖度しまくっていた8代吉宗など、将軍たちの素顔はかなり人間くさい。 そんな将軍たちの人間くさい面――将軍を取り巻く悩みや願望――に注目して、時代のターニングポイントを読み解くことが本書の目的である。好き放題振舞っているように見えた徳川将軍たちもまた、わずらわしい人間関係に頭を悩ませて、日々戦っていた。そうした人間関係が歴史の流れにどう影響したのか、本書では考えてみたい。
-
-名君か、暗君か!?知られざる実像に迫る! 動乱の幕末期、壊れかかった江戸幕府の復権を果たすべく、最後の切り札として立ち上がった第15代将軍・徳川慶喜。結局、討幕を目指す薩長の勢いには勝てず、いきなり大政奉還し、徳川の世に終止符を打った。しかし、薩長への対抗策や、幕府に命を懸けていた会津藩をはじめとする幕府勢力へのケアなど、その終わらせ方には、いまだ多くの批判と疑問がある。 徳川家康の生まれ変わりと称されるほど切れ者だったという話もあれば、二心殿と呼ばれ、方針や言動がすぐに変わり、家臣を激しく混乱させたという話もある。果たして、徳川慶喜とはいかなる人物だったのか。日本の歴史の大きなターニングポイントとなる明治維新のキーマンにして、最後の将軍である慶喜の実像に迫る。
-
3.3豊かな財政を誇った徳川幕府も、資金繰りには悩まされていた。 将軍の浪費、インフラ整備、相次ぐ災害、鉱山経営の停滞……。時代を経るにつれて歳入は頭打ちになるも、支出の増大の止まらない。将軍や歴代の財政当局は支出を減らし、あの手この手で歳入を増やそうと知恵を絞るも……。 財政難を背景に幕府が資金繰りに奔走した歴史を、五つの時代に分けて解明。財政からみた徳川幕府の歴史、そして江戸時代の真実に迫る。
-
4.0活動写真の弁士を皮切りに、子役時代の高峰秀子らと映画で共演するなど昭和を代表する芸能人であり、文筆家としても知られた著者が、真珠湾攻撃から東京大空襲にいたる約三年半の日々を克明に綴った記録。終戦までの四ヵ月を収録した既刊『夢声戦争日記 抄 敗戦の記』の姉妹篇。 〈解説〉濱田研吾
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 激動の歴史に翻弄されながらも行き抜いた猛者たち 江戸時代に各地を治めていた藩主は、明治4年の廃藩置県によって国元から切り離されて強制的に東京住まいとなった。戊辰戦争で勝った大名も負けた大名も一緒くたに、領地は没収され、家臣は解散させられた。 島津家や毛利家など、元大名は華族として「鹿鳴館」で開かれる舞踏会場で華やかに踊っていたというイメージでとられがちである。外交官となって世界各地を飛び回る元殿様や、実業家として成功した元殿様もいる。が、実際には極貧生活にあえぐ元殿様もいれば、宮司となって世間の片隅でひっそりと生きた元殿様、函館戦争後ずっと隠遁生活を送った元殿様もいた。 一方で、大名や公家のお姫様たちのその後は、もっと知られていない。 有栖川宮家から水戸家に嫁ぎ、最後の将軍慶喜の母となった徳川吉子、徳川家の最後を見届けた篤姫と和宮のその後とは……? 戊辰戦争で命をかけて逃げざるを得なかった二本松藩正室の丹羽久子や、北海道にわたり辛苦をなめ「開拓の母」と呼ばれるようになった亘理伊達家の伊達保子など、知られざるお姫様たちの生き様は大変興味深い。 こうした元殿様・お姫様の知られざる幕末・明治の生き様を、テレビなどでお馴染みの河合敦先生が紹介する。 ◆もくじより抜粋 巻頭特集 時系列で追う幕末事件簿/幕末維新時の三〇〇藩勢力図 第一章 家柄に翻弄された徳川の殿様とお姫様 (最後の将軍・徳川慶喜/紀州藩主・徳川茂承/尾張藩主・徳川慶勝/16代徳川宗家・徳川家達/13代将軍正室・篤姫/14代将軍正室・和宮など) 第二章 落日の徳川幕府を支えんとした殿様とお姫様 (会津藩主・松平容保/岩城平藩主・安藤信正/唐津藩主・小笠原長行/川越藩正室・貢姫/二本松藩正室・丹羽久子など) 第三章 維新後の社会を動かした殿様とお姫様 (土佐藩主・山内容堂/鳥取藩主・池田慶徳/米沢藩主・上杉茂憲/広島藩主・浅野長勲/亘理伊達家正室・伊達保子など) ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
-
3.0戦国合戦とはいかなるものだったのか。 史料に重きをおいた客観的視点、当時の人物に想いを馳せる主観的視点を行き来しながら、その実像に迫っていく。 桶狭間合戦、関ヶ原合戦と、いまだ謎多き戦国合戦。 合戦に至るまでの経緯や兵法、その合戦の周縁でなにがあったのか。 『戦国の陣形』『謙信越山』で話題を集めた著者・乃至政彦が最新研究と独自の考察で解き明かす。 大河ドラマで再び注目を集める徳川家康や織田信長、上杉謙信、武田信玄など人気武将の合戦も掲載。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◎国際化の波が迫る…激動の近・現代史!坂本龍馬が、西郷隆盛が、大久保利通が走る!時代はやがて、明治維新から軍国主義、戦後の復興、そして高度経済成長へ・・・・・・◎歴史の歯車が、再び大きく回転しはじめた!――幕末・維新から明治、大正、昭和史まで▼徳川幕府崩壊!――その最大の理由とは?▼長州藩、薩摩藩の台頭――なぜ尊王攘夷が討幕運動に変わったのか?▼大久保利通と西郷隆盛の確執――なぜ西南戦争が勃発したのか?▼大正デモクラシーは何を生み出したのか?▼日中戦争から太平洋戦争へ――日本が泥沼の戦いに踏み出したのはなぜ?▼軍国主義から民主主義への大転換で生まれた歴史のひずみとは? ・・・他シリーズ累計110万部突破!《大人の学び直しにも最適! この3冊で、日本の歴史がつかめる!》
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 豊臣秀吉、豊臣秀頼、直江兼続をはじめとする大物武将たちに(敵となった徳川家康にも)とても好かれた真田幸村。 また、地元の猟師たちや浪人たちにも「この人と生死をともにしたい」と思わせるほどの人望があった。 その人望は、“義”を貫くところから生まれたものだったのだ。 自分のまわりの人を幸せにすることを第一に考え、それを実現していくという心に生きた真田幸村の、現代ビジネスパーソンも学ぶべき真実とは? 吉田松陰研究を追求する中で、日本人に引き継がれたDNAの系譜をたどると、そこには真田幸村がいたという著者が読み解く、真田幸村のすべて。
-
-天下人の徳川家康。天ぷら食べて無念の死、と思ったのも束の間、気づけば20歳の肉体で見知らぬ世界に転生していた!? しかもエルフの王女セラフィナを人間の暴漢から救ったことで、滅亡寸前のエルフ族が籠城する『エッダの森』の大将軍に任命されてしまう。 小心者で節約家、敵が死ぬまで戦わずして待てばいい。およそ勇者らしからぬ思考の家康は、心配性ゆえ役に立ちそうな人材を『エッダの森』に集め始める。守銭奴のダークエルフには資金集めを。穴を掘りまくるドワーフには治水工事と抜け路作りを。果ては情報戦を制するため暗殺者一族まで起用。『エッダの森』を徳川幕府並みに改革していく家康だったがーー? 家康が狸爺のイメージの時代は終わった!? 天下人の経験を持った、超チートな若き家康×天真爛漫なエルフの王女が贈る、異世界統一ストーリー。
-
3.5日本を世界レベルに引き上げた男の刮目の人生! 2021年のNHK大河ドラマの主人公、2024年の新一万円札の顔として注目を集める渋沢栄一の評価はここにきて高まる一方だ。 1840年、武蔵国血洗島(現在の埼玉県深谷市)の豪農の家に生まれた栄一。利発な青年は倒幕の志士を目指したのにまるで正反対の幕臣に。明治維新直前、徳川慶喜の命で、パリ万国博覧会へ参加することになった栄一は、欧州の文明・民主主義の最先端に触れる。このことで栄一の世界は一気に広がる。 幕府が滅び、明治政府となっても栄一はその才能を大蔵省から求められ、やがては官僚を離れ、実業の道へ。500もの企業の設立にかかわり、“近代日本経済の父”と呼ばれるほどの人物となった栄一だが、その人生は徳川慶喜との関係を抜きに語れなかった――。
-
-■「本能寺の変」勃発――明智光秀は将軍宣下を受けていた!? 2020年度NHK大河ドラマ「麒麟がくる」関連本。 時代を問わず、組織が存在する以上、そこには人望、血統、派閥、出世、讒言、不運、誤算などさまざま思惑が渦巻いています。本書では、武家の最高位である「征夷大将軍」の座を逃した歴史上の人物が多数登場。 そのツワモノたちの生き方を通し、先行き不透明な組織に生きる現代人に役立つ歴史上の教訓が多数盛り込まれています。大河ドラマ時代考証で有名な著者による異色の人物日本史。 [目次] 〈はじめに〉明智光秀は将軍宣下を受けていたのか [第1章] 武家の棟梁“将軍”になり損ねた平安末期・鎌倉時代の人物 [第2章] 乱世に“将軍”になり損ねた室町・戦国時代の人物 [第3章] 太平の世に“将軍”になり損ねた江戸時代の人物 [第4章] 将軍に替わる“トップ”になり損ねた幕末維新の人物 【主な登場人物】 ◎源頼朝に警戒され源氏第三勢力に甘んじた「武田信義」 ◎四代将軍への野心を疑われるも拒んだ「鎌倉法印貞暁」 ◎畿内を実効支配するも将軍宣下が降りなかった「足利義維」 ◎将軍よりも関白の権威を利用し天下を治めた「豊臣秀吉」 ◎両親の溺愛を受け次期将軍とされるも自滅した「徳川忠長」 ◎田沼の妨害で将軍になれなかったと恨んだ「松平定信」 ◎幼くして徳川宗家を継承した幻の十六代将軍「徳川家達」etc <著者略歴> 二木謙一(ふたき・けんいち) 1940年東京都生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。専門は有職故実・日本中世史。國學院大學教授・文学部長、豊島岡女子学園中学高等学校校長・理事長を歴任。現在は、國學院大學名誉教授、豊島岡女子学園学園長。1985年『中世武家儀礼の研究』(吉川弘文館)でサントリー学芸賞(思想・歴史部門)を受賞。NHK大河ドラマの風俗・時代考証は「花の乱」から「軍師 官兵衛」まで14作品を担当。主な著書に『関ヶ原合戦』(中公新書)、『徳川家康』(ちくま新書)など多数。 ※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『征夷大将軍になり損ねた男たち―トップの座を逃した人物に学ぶ教訓の日本史』(2019年12月17日 第1刷)に基づいて制作されました。 ※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 史実は小説より奇なり! 戦い方がズル過ぎる源義経、センター向いてないのに抜擢されちゃった明智光秀、じつは戦に弱かった織田信長、 そんなに暴れん坊じゃなかった徳川吉宗、西郷隆盛像と傍らにいるイヌのツンの作者は別人だった、 お金に縁遠い福沢諭吉、樋口一葉、野口英世など、意外と知らない「笑える日本史」を、スタディサプリの人気講師・伊藤賀一が紹介。 武田信玄が重臣に宛てたガチ恋ラブレター現代語訳(全文)や、 暗記に役立つ徳川十五代将軍、内閣総理大臣の特徴をひと言でざっくり紹介、 本当にあった日本史試験の難問・珍問・珍回答など あらゆる角度から日本史を斬っていきます。 明日誰かに話したくなる日本史の話、そして教養もしっかり身に付き、 ちょっと試験にも役立っちゃう話が満載です。
-
-豊臣秀吉の天正禁令に始まる日本のキリシタン迫害史は、そのまま殉教史でもあった。 徳川幕府に引き継がれたキリシタン政策は、三代将軍家光の時代に苛烈さを増し、取り締まりと処刑による殉教が本州各地で引き起こされていく。 その弾圧の刃に追われて北へと逃れ、信者たちは津軽海峡を越えて松前へと渡った。 砂金採取に湧き金掘り鉱夫に寛大な松前で、穏やかな信仰生活を得たかにみえた信者たちを待ち受けていたのは、1639(寛永16)年夏、強まる迫害の中で起きた松前藩による信者106人の斬首だった。 幕末から近代にかけての北海道を見つめてきた著者が徳川幕府初期に挑んだ、キリシタン殉教略史。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★★戦国時代の流れをつかめ!!★★戦国時代の三大天下人、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康のライバルや、乱世を駆け抜けた日本各地の英雄たちが14人! 怒涛の乱世をキラ星の如く駆け抜けた武将たちのストーリーをマンガで詳しく紹介します!! マンガの後には、合戦の詳細や宝物、鎧など、一人ひとりに焦点を当てた解説を掲載。戦国武将にもっと詳しくなれる必携の1冊です!! 【登場人物】 織田信長/豊臣秀吉/徳川家康/今川義元/明智光秀/信玄&謙信/石田三成/真田幸村/北条早雲/毛利元就/長宗我部元親/島津義弘/伊達政宗 【目次】 【1章】 三大天下人 織田信長 豊臣秀吉 徳川家康 【2章】 天下人のライバルたち 今川義元 明智光秀 武田信玄&上杉謙信 石田三成 真田幸村 【3章】 日本各地の英雄たち 北条早雲 毛利元就 長宗我部元親 島津義弘 伊達政宗 <電子書籍について> ※本電子書籍は同じ書名の出版物を紙版とし電子書籍化したものです。 ※本電子書籍は固定型レイアウトタイプの電子書籍です。 ※本文に記載されている内容は、印刷出版当時の情報に基づき作成されたものです。 ※印刷出版を電子書籍化するにあたり、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。また、印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。 株式会社西東社/seitosha
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 生死をかけて戦う、「怖い」「近寄りがたい」と言われている武将たち。 でも心やさしく、人間味にあふれているんです。 そんな武将たちの“キャラ”を、人気イラストレーターのいとうみつる氏がゆる~く、かわいく描きました。 武将の力の採点表、得意ワザ、活躍した戦い、含蓄のあることばなど時代背景と共に、どの武将も楽しく読めます。 大人も子ども楽しめる戦国歴史図鑑です。 【内容】 PART1|武将の誕生!平安・鎌倉・室町時代 平将門/平清盛/源頼朝/源義経/足利尊氏 PART2|武将が大活躍!戦国時代から大坂夏の陣まで 北条早雲/毛利元就/北条氏康/今川義元/武田信玄/上杉謙信/武田勝頼/上杉景勝/織田信長/浅井長政/朝倉義景/柴田勝家/明智光秀 豊臣秀吉/前田利家/長宗我部元親/伊達政宗/徳川家康/石田三成/島津義弘/宇喜多秀家/大谷吉継/本多忠勝/井伊直政 加藤清正/後藤又兵衛/真田幸村/真田昌幸/真田信之 [歴史を変えた戦い] 源平合戦/桶狭間の戦い/川中島の戦い/長篠・設楽原の戦い/本能寺の変/関ヶ原の戦い/大坂冬の陣、大坂夏の陣 戦国武将年表 [その他の登場キャラクター] 北条政子/山本勘助/お市の方/おね、淀殿/島津義久、歳久、家久/武蔵坊弁慶/直江兼続/半兵衛、官兵衛/島左近 【著者紹介】 イラストレーター:いとうみつる 東京都生まれ。広告デザイナーを経て、イラストレーターに転身。“ゆるくコミカル”なキャラクターデザインを得意としている。 2014年に出版された「栄養素キャラクター図鑑」シリーズ(日本図書センター)が大人気。 監修:小和田哲男(おわだ てつお) 1944年、静岡市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。静岡大学名誉教授。専門は戦国時代史。 近著に「戦国武将の実力 111人の通信簿」(中公新書)など多数。趣味は城めぐり。
-
-徳川軍20万 vs. 真田隊5000――圧倒的な戦力差がありながら、なぜ、真田信繁(幸村)は、徳川軍を撃退できたのか?その秘密は、信繁が築いた要塞「真田丸」にあった。本書は、最新研究をもとに、従来の認識とまったく異なる「真田丸の実像」、「真田一族」の強さの謎……に鋭く迫る!◆豊臣が頼り、徳川が恐れた知謀の「真田三代」◆その名は「信繁」か「幸村」か?◆戦国最強の出城「真田丸」◆狙うは“家康の首”ただひとつ!権力にもひるまず、乱世を力強く駆け抜けた真田の男たち。信繁の人生と真田三代の歴史から、変化の激しい“現代を生きる指針”が見えてくる!
-
-
-
4.5偉人教室とは、古今東西の偉人たちによる特別な講演会。人間の人生に起きるさまざまな課題、その解決方法を偉人がじかに伝えてくれます。たとえば、 「本物の自信のつくり方」・・・ナポレオン 「私がノーベル賞を取れなかった理由」・・・野口英世 「『努力すれば夢は叶う』はウソ」・・・エジソン 「何歳になっても第一線で活躍する方法」・・・徳川家康 「仕事ってかったるい、と思ったら」・・・ミケランジェロ 「絶望からの立ち上がり方」・・・ベートーヴェン 「本当に大切なものを見つめてみる」・・・一休宗純 ……etc などなど、それぞれの人生を振り返り、希望や反省の思いを込めながら、今を生きる私たちにアドバイスをくれます。 人生には、いいことも悪いことも起きます。その中で、偉人たちはなぜ人生を全力で駆け抜けることができたのか? 人生を前向きに生きるヒントをもらえる1冊です。
-
3.8
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 道徳的にせよ政治的にせよ,正しいこと,正義を広め実現していくには,社会の運動法則をきちんと見極めてかからないと,とんでもない逆効果をおこしかねない。世界で最初のもっとも徹底した動物愛護の法令を定めたのは徳川将軍・綱吉だった。俗説と異なる理想主義を検証し,道徳や政治の問題を社会の法則とからめながら考えることができる。〈生類憐みの令〉の実態を初めて明らかにした本。 ★★ もくじ ★★ 第1部 〈生類憐みの令〉の範囲 第2部 〈生類憐みの令〉の成果 ……犬の場合 第3部 〈生類憐みの令〉の起源とその継続と廃止 第4部 〈生類憐みの令〉年表 ……本文にもれた話 付 録 授業書〈生類憐みの令〉
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 第1特集は「大江戸刀剣地図散歩」と題して江戸の刀剣の魅力に迫る。 徳川家康の江戸幕府とともにその歴史が始まったといえる江戸の刀剣。 刀の歴史としては浅いが刀剣の魅力は深く、古刀に対して新刀と呼ばれ人気を博した。 家康をはじめ歴代将軍に献上された各地の名刀が集まるなど新しい時代を迎えた江戸の刀剣事情や刀剣文化を紹介。 史跡や名所など刀剣・刀工ゆかりの地などを歴史地図でめぐる。その他企画に原寸大名刀賞翫・合作刀などを予定。 目次 「大江戸刀剣地図散歩」~花のお江戸は“刀剣の里" 江戸はどうして日本刀の“聖地"となったのか? 大江戸刀剣江戸の刀工たち 名工たちの息吹と鎚音を探して 源清麿「一期一腰」/「刀 銘 和泉守藤原兼重」金象嵌截断銘あり 「萬世御江戸絵図」の刀工たち 武州八王子・下坂鍛冶の故郷を巡る 東京の刀剣史跡を歩こう! 静かに時を刻み続ける名工たちの足跡 東京は刀剣の一大集散地 大名家・財閥・刀剣コレクターの刀たち ・江戸の刀工 在世年表│名工たちの時代を通観 ・原寸大・名品賞翫 古刀の格調・新刀の輝き 延吉・吉房・信房・国貞・勝光宗光 ・光忠の鍛えは同人説を裏づける│国宝 太刀 銘 光忠│写真家・松本啓之亮 ・匠の技を結集した│名工たちの合作刀 ・刀装具の宝箱│後藤乗真作 十二支図目貫・土屋安親作 飾り替え図縁頭│ ・刀剣小説三昧│柴田錬三郎の刀剣小説を読む│「虎徹」
-
-日本は自然災害列島です。天候異変の大飢饉に襲われた天明・天保時代はとても悲惨でした。 信濃のあづみ野は荒れ果てた山野でした。 資金も土木技術もない農民たちが手を取り、巨大な農水路「拾ヶ堰」などを開削し、日本随一の緑豊かな田園地帯に変えました。 そのうえ、米不足で苦しむ飛騨国へ、あづみ野から常念山脈、上高地を経由し、飛騨山脈の2座を越えた「米の道」をつくりました。 幕藩体制の枠組みが敵になり味方になり、数十年の歳月を要しました。 若い男女、夫婦愛、郷土愛、山岳信仰など人間愛に満ちた、こころに響く作品です。 上高地はウエストンの時代に拓かれたものと思われている方が多いなか、天保時代に「米の道」の飛州新道の中継地、槍ヶ岳登拝基地として開かれたことも知っていただきつつ、播隆上人による槍ヶ岳開山にかかわるエピソードなども絡め、天明大飢饉から続く歴史的事実を、ぜひ小説で味わっていただきたい。 時代の流れに翻弄される安曇野の農民たち、徳川幕府の思惑、そして上高地の開拓の歴史を描いた長編歴史小説。 <あらすじ> 天明3(1783)年、浅間山の噴火が引き金となって天明大飢饉が起きた。 常念山脈の山麓・安曇平の農民たちは水不足で飢餓状態に陥るが、大庄屋、等々力孫一郎は奈良井川から15キロに及ぶ巨大な「拾ケ堰」の開削を計画、多々の悪条件を乗り越えて農水路を完成させる。 新田開発が進み豊かな安曇平になったが、一方では過剰生産による米価の暴落が起きる。 そこで米の販路を飛騨国へもとめるために、常念山脈(大滝山・蝶ヶ岳)、上高地、飛騨山脈(焼岳)を越える「米の道」の開削が進められる。 安曇平の庄屋・岩岡伴次郎は私財を投げ打ち、上高地までの「伴次郎新道」を開削。 上高地の湯屋(宿屋)の経営に乗り出し、娘の志由(13歳)に宿をまかせる。 このころ播隆上人による槍ヶ岳の開山が行なわれ、上高地は飛州新道の中継地、槍ヶ岳登拝基地として期待されるようになるが、天保の大飢饉が発生。 松本平から飛騨国へ米を運びたくても幕府直轄領の飛騨国は街道の開通を認めようとせず、湯屋は経営の危機に陥る。 飛州新道が開通し、上高地が栄える日は果たして来るのか…。 ※長野県中信地方(松本市、塩尻市、大町市など)の地方紙「市民タイムス」に連載中の人気小説「燃える山脈」を単行本化。
-
4.0徳川宗家第十八代当主であり、WWF(世界自然保護基金)ジャパン会長も務める著者が日本文明のルーツを探る一冊。縄文時代一万年の間、自然の恵みの中でゆっくり文化を進化させたことが、日本人の生き方、考え方の根底にある、と著者は記す。「東京のやるべきことは江戸時代に戻って出来る限り森に満ち、都市の中に縦横に水路の通っている都市をつくること」。その江戸時代、日本は平成と同じく大自然災害に見舞われた。元禄大地震(一七〇三年)の発生、宝永元年(一七〇四年)に浅間山が噴火し、宝永四年(一七〇七年)にはマグニチュード推定八・四の大地震が起き、さらに富士山が大噴火を起こした。その後も混乱と衰退が続き、ついに八大将軍・吉宗公は「花の元禄バブル」を捨て、質素・倹約を旨とする新しい日本文明を築き上げた。平成日本の政治経済、社会文化に、いま江戸期に匹敵するような大転換が迫られているのではないか。文明の根本を問う意欲作。
-
3.0徳川時代の管理体制に独り挑んだ宮本武蔵。その思考法が私達に明示する、混沌に満ちた現代を勝ち抜くための叡智とは何か。戦国末期から江戸時代初期にかけて活躍した剣豪・武蔵。彼が晩年に二天一流と称する自らの剣術と兵法について解説したのが『五輪書』である。その考え方は、形だけにこだわった他の剣術書とは異なり、あくまでも「勝つこと」を目指した非常に合理的なものだったのである。武蔵が剣に託して兵法の道を極めたのは、日本全体に出現しつつあった巨大な管理社会に対する抵抗である。しかし、武蔵は負けることを承知しながら、その巨大な管理社会に立ち向かったわけではなく、緻密な計算と合理的な闘争方法によって、自分のできる範囲から管理社会に挑戦し、そして本当の人間のあるべき生き方を求めた。本書は、武蔵の『五輪書』を解説しつつ、現代社会においていかに武蔵の考え方が活用でき、また応用できるかを考察する一冊である。
-
-生きるか死ぬか! 自らの決断が、自身ばかりか、一族・家来の生死を決めるという時代のなかで、究極の選択を迫られつづけた戦国武将たちは、いかにしてその迷いを断ち切り、意を決したのだろうか? 歴史を動かした男たちの生死の場面・ドラマを事例としてあげ、その成功と失敗に、現代の企業リーダーが学ぶべき法則を見出す。[構成]は(1)すべてはトップで決まる…部下がよろこぶトップダウンとは…(2)いまこそ人事に集中せよ…部下の長所を見出した抜擢人事…(3)情報の選択を誤るな…リーダー・信長が下したもう一つの決断…(4)覚悟を決めろ…「厳島の戦い」にみるリーダーとしての毛利元就…(5)危機を好機に変える力…既成概念にとらわれなかったリーダーたち…(6)撤退を怖れるな…撤退で成功したリーダー・失敗したリーダー…(7)継承してこそ価値がある…後継者対策が抜群だった徳川家康…以上7つの側面から、厳しい時代を生き抜くリーダーに求められる生き様を探る。
-
-「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」の日本一短い手紙で知られる戦国武将・本多作左衛門。徳川家という組織社会の中で、「いつも主君の立場に立ち、主君にとって一番いいと思うことをやり抜く」という信念を頑なに守り続け、幕府の礎を築くのに貢献した“頑固者”作左衛門の生き方から私たちは何を学ぶのか。作左衛門が生きた末期は、武士が戦国精神の牙を抜かれ、「ききわけのいい武士」に意識を変えられた時代であった。口のうまい、ソロバン勘定の達者な新しい武士が肩で風切って歩く。それが作左衛門には我慢できない。作左衛門の考える忠誠心とは、「主人が悪いときは命がけで諌める」というものだ。「主人が悪くてもだまって従え」などという規範には抵抗する。そのため次第に主人の徳川家康に冷遇され、不遇に死ぬ。本書は、家康のためにあえて“汚れ役”に徹し、左遷されながらも信念を貫いた男・本多作左衛門の生き様を描く一冊である。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

































![[新装版]真田幸村―「弱者」の必勝戦術ここにあり](https://res.booklive.jp/354350/001/thumbnail/S.jpg)