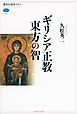学術・語学 - 講談社選書メチエ作品一覧
-
4.0フロイトが創始した精神分析を刷新し続けた不世出の存在、ジャック・ラカン(1901-81年)。1953年から最晩年の1980年まで続けられたセミネールでは何が起きていたのか? 主著『エクリ』をも読み解きつつ、セミネールの全展開を時系列順に通観していく本書は、ラカンを「哲学」として読むことによって前人未到の眺望を獲得していく。気鋭の哲学者が渾身の力をそそいで完成した、平易にして画期的な本格的概説書!※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.0
-
4.0
-
5.0
-
-
-
3.8
-
-
-
4.0
-
4.0
-
-
-
4.02次元=平面世界(フラットランド)の住人に、3次元=空間世界(スペースランド)はどう映るのか? 4次元以上の世界は、どう想像できるのか?「次元」の本質をとらえた古典的名著、待望の新訳!アイドゥン・ブユクタシによる3次元の外へ誘う写真シリーズ《フラットランド》 特別収録
-
5.0
-
3.0
-
4.7
-
5.0
-
3.9
-
-
-
4.5
-
3.8
-
-
-
3.0
-
3.7
-
3.0
-
-
-
5.0
-
4.0
-
-
-
3.0
-
3.8
-
-
-
4.0
-
4.0
-
5.0
-
4.0
-
-
-
4.0
-
3.0
-
-
-
3.5皇帝と天子 中華と夷狄「大一統」。中国史を貫く"統治と権力"の思想構造。儒教が「国教」となったのはいつか。皇帝と天子は同じものか。曹操はなぜ文学を称揚したか。諸葛亮は何を守ろうとしたのか。「竹林の七賢」は何に抵抗したか。国家の正統性を主張し、統治制度や世界観の裏づけとなる「正統思想」の位置に儒教が上り、その思想内容が変転していく様を、体系性と神秘思想の鄭玄、合理性と現実主義の王粛、光武帝、王もう、曹操や諸葛亮など、多彩な人物を軸にして、「漢」の成立と衰退、三国、魏晉時代の歴史を交えながら描き出す。(講談社選書メチエ)
-
5.0
-
-わたしが話す。あなたが自分の体にふれる。このとき、何が交されているのか? わたしたちが会話をしているとき、そこではことばだけが交わされているのではない。どんなに些細な、他愛のないおしゃべりであっても、自分の体にさわったり、身ぶりをしたり、ごく短い間があったり、ときには何かを演じたり、身体まるごとつかったコミュニケーションが繰りひろげられている。ブッシュマンの家族、日本の大学生、民俗芸能という多様な会話の現場を、徹底的にミクロに観察することで、コミュニケーションとは何か、社会とは何かという大いなる問いに挑む。現象学、社会システム理論、言語行為論などを参照しながら、徹底的に「身体」に根ざして考える"唯身論"人類学の試み。(講談社選書メチエ)
-
-
-
4.5
-
4.0
-
4.5
-
4.0
-
3.5
-
3.0
-
4.0
-
4.0
-
-
-
4.7超難解な思考をあざやかに解説! ホワイトヘッドの世紀は来るか!? 本書は、ホワイトヘッドという哲学者のひじょうに偏った入門書である。読者の方々が、ホワイトヘッド自身の本を手にとってみようか、という気になられることだけを目指した。他意(?)はない。わかりやすさを重視したので、かなり強引なところもあると思う。特に入門篇は、こちらの興味にぐっとひきつけて書いた。淡々と説明だけをするというのは、どうしても性にあわない。それぞれが、1話完結のエッセイとしても読めるように工夫したつもりだ。上手くいったかどうかは、保証の限りではない。もちろん全体として一貫した流れはある。いってみれば、本書全体が、ホワイトヘッドが考えたこの宇宙とおなじあり方、つまり「非連続の連続」になっているといえる……といいのだが。――〈[まえがき]より〉(講談社選書メチエ)
-
4.0
-
4.0
-
4.0
-
4.0
-
3.0
-
4.5選書日本中世史 第3弾! 公家政権と武家政権と寺社勢力……室町幕府の傑出した統治構造とは!? 室町幕府にできて、鎌倉幕府にはできなかったこと。それは、「太平の世」前夜の、動乱の続く地方に対して中央政権として安定的に君臨することである。そのために室町幕府が考え出した統治構造とは? 自明のものとされてきた将軍の主従性的支配権に一石を投じ、天皇・公家の持つ力の本質を検証することで、明らかになった将軍権力とは、いったいどんなものだったのか? 「わかりにくい中世をどうわかりやすくするか」の大問題に真っ向から挑む、刺激に満ちた1冊。(講談社選書メチエ)
-
4.0
-
3.3
-
3.0
-
3.0
-
-
-
-
-
3.2
-
-
-
5.0
-
5.0
-
3.0
-
3.3アガンベン、ネグリ、カッチャーリ……生政治、帝国、ゾーエー/ビオス……いまなぜイタリアなのか? ジョルジョ・アガンベン、ウンベルト・エーコ、アントニオ・ネグリ、マッシモ・カッチャーリ……。いまや世界の現代思想のシーンは、イタリアの思想家たちを抜きにしては語れない。ジル・ドゥルーズやジャック・デリダらフランスの巨星たちがあいついでこの世を去ったあと、なぜ、イタリア思想の重要性に注目が集まるのか。現代思想の最尖端で、いま何が問題なのか、そしてどのような可能性があるのか。哲学、美学、政治学、社会学、宗教学、女性学など幅広い分野での彼らの刺激的な仕事を、明快な筆致で紹介する。(講談社選書メチエ)
-
3.0
-
4.0
-
4.0
-
-
-
4.0日英同盟の是非、開戦論vs.非戦論、「露探」問題、日比谷焼打……新聞がいちばん面白かった時代。日露戦争の時代、新聞界は黄金期を迎えていた。福澤諭吉創刊の『時事新報』、陸羯南主筆『日本』といった高級紙から伊東巳代治による『東京日日新聞』、徳富蘇峰『国民新聞』や『東京朝日新聞』など時の政府に近いもの、政治家の女性問題のようなゴシップから政府・大企業批判、リベラルな主張までを載せる『萬朝報』『二六新報』。知識人から下層階級、政府支持から社会主義者まで、多様な読者に向けた無数で雑多な新聞が、大国との戦争へと向かう日本と世界をいかに語り、論争をしたか。膨大な史料を掘り起こし、新聞が大企業化する以前の、粗野で豊かだった時代を活写する、メディア史研究の試み! (講談社選書メチエ)
-
4.5
-
-
-
3.8
-
3.7脳科学が明かす日本語の構造。英語で"I love you."とは言っても、日本人は決して「私はあなたを愛している」などとは言わない。「雨が降る」を英語で言うと、"It rains."のように「仮主語」が必要になる。――これはどうしてか? 人工知能研究と脳科学の立場から、言語について実験と分析を重ねてきた著者が発見した新事実。それは、日本語の音声がもつ特徴と、主語を必要としない脳の構造とが、非常に密接な関係にあることだった。斬新な視点による分析と、工夫をこらした実験、先行研究への広範な検討を重ねて、主語をめぐる長年の論争に大きな一石を投じる、衝撃の書! (講談社選書メチエ)
-
4.3
-
4.5
-
3.0
-
4.0
-
4.5
-
3.7