軸作品一覧
-
-【内容紹介】 元味の素アセアン地域統括社マーケティングマネージャーによる「超実務視点」で伝えるグローバルマーケティング(【ブランド創造 × 事業運営 × グローバル】)の極意。 ●「日本式」マーケティング 日本人でありながら、国境の概念をあまり意識せずに活動していくような考え方・やり方がこれからの日本企業のグローバルマーケティングに役立つ。「おかげさま」「ありがとう」をいつも心のどこかに感じながら生きている日本人が、日本社会のなかで様々な経験をし確立することができた「型」を、「社会共有知」的なノウハウとして体系化・構造化していくことが大切。 ●「ヒットの法則15原則」 味の素マーケティング学校で習ったマーケティングの基本に、現場でのやり方で実践を重ね、自分なりのやり方を加えて1つのノウハウとして昇華させた「ヒットの法則」。その15原則に具体的な事例紹介も含めて、実務家だからこそ書ける細部まで、要素をできる限り因数分解して、「ヒット商品」を開発して世界中の顧客にお届けするためのプロセスやコツを埋め込むように工夫。 【目次】 はじめに 第1章 2050年はアジアの時代-華人の価値観― 第2章 新事業・新バリューチェーンの創造 第3章 マーケター力=思考力×対人力×人間力・マーケターのスキル 第4章 はじまりはいつも仮説 第5章 ヒットの法則15原則―成功の5軸×3原則― 【成功の軸1】コンセプトが生活者に受け入れられる 原則1:ネーミングのキレと理解しやすさ 原則2:手に取っても良いと思える値頃感=コストパフォーマンス 原則3:中身の良さが伝わる外見・デザイン 【成功の軸2】アイデアを具現化できる仕掛けがある 原則4:戦略は細部に宿る 原則5:頭を使って、気を遣う 原則6:消費者の期待を裏切る驚きを 【成功の軸3】その他大勢の中から選ばれるだけの魅力がある 原則7:唯一無二の独自のポジショニング 原則8:自社ならでは、かつお客様の為になる独自価値 原則9:三本の矢が築けるか?(良い商品・手に届く・伝わる価値) 【成功の軸4】儲かる仕組みが構造化されている 原則10: 売上高を要素分解、潜在需要を特定 原則11: Gross Profit構造を強固に 原則12: 販売費・一般管理費を賄えるPL構造 【成功の軸5】社会全体に共感を生む価値がある 原則13:志が明確かつ、それを言えるだけの理由がある 原則14:事業がシンプルである(誰にでも分かり易い) 原則15:不変の真理(Universal truth)に沿っている 第6章 ブランドと社会価値・存在意義 第7章 事件は現場で起こっている-C A P Dの薦め- ・PDCAサイクル=最初にP(Plan)から始めるのでなく、 ・「現場では何か課題が起こっているはずだ」という懐疑的な発想を持ち、 ・C(Chcek)から始める。 第8章 イノベーター理論の実験場―中国市場― おわりに
-
-【あなたのWebサイト、ちゃんと“働いて”ますか? ケーススタディと動画で学ぶGoogleアナリティクス!】 Webでビジネスを進めるうえで、「どのようなユーザーがサイトに来ているか」、「どのようなコンテンツに人気があるか」、「ユーザーがどのように行動しているか」といったデータを正しく把握することは大切です。現状のWebサイトの問題を見誤っていれば、改善策も見当外れなものになり、大きな成果にはつながりません。 Googleアナリティクスを使いこなして、より成果の上がるWebサイトに育てていくには、たんに操作手順を覚えるだけでなく、“どう使うか”という実践への落とし込みが重要です。そこで本書では、これだけは押さえておきたいという基礎の解説に加えて、Googleが用意しているデモアカウントを利用したケーススタディを設けています。 書籍と同じデータを見ながら、順を追って手元で解析を進めていけるので、初心者の方でもGoogleアナリティクスの各機能の使い方を実践を通して身につけられます。さらに、ケーススタディではYouTubeの動画解説も用意しているため、操作ミスなどでつまずくこともありません。まずは基礎をきちんと身に付けたい方、実際にどう使われているのかを具体的に体得したいという方にぴったりの一冊です。 〈こんな方におすすめ〉 ・自分のGoogleアナリティクスの使い方が正しいかどうかお悩みの方 ・Googleアナリティクスを実践を通じて身に付けたい方 ・Webサイトで成果が上がらず困っている方 〈本書の内容〉 CHAPTER1 分析指標はこれだけ覚えておけば大丈夫 CHAPTER2 Googleアナリティクスの管理画面と分析機能 CHAPTER3 ユーザー軸・集客軸で分析するケーススタディ CHAPTER4 行動軸で分析するケーススタディ CHAPTER5 Googleアナリティクスのさまざまな設定
-
4.0〈電子書籍版に関する注意事項〉 本書は固定レイアウト型の電子書籍です。 【ハンズオンと動画で学ぶ、最新のGoogleアナリティクス4!】 Googleアナリティクス4(2020年10月リリース)は、指標やイベント、レポートの構成等が従来のユニバーサルアナリティクスから大きく変わりました。本書は、この最新バージョンのGoogleアナリティクス4に対応した初学者向けの解説書です。 Googleアナリティクス4の基本機能、分析に使用する指標、ユニバーサルアナリティクスとの違いといった基礎的な知識や操作がしっかり身につきます。また、Googleアナリティクスの分析を実際にWebサイトの改善へつなげるためには、たんに指標や操作を覚えるだけでなく、“どう使うか”という実践への落とし込みが重要です。そこで本書では、Googleが用意しているデモアカウントを利用したケーススタディを設けています。 書籍と同じデータを見ながら、順を追って手元で解析を進められるので、初心者の方でもGoogleアナリティクス4の使い方とデータの見方を実践を通して身につけられます。さらに、ケーススタディではYouTubeの動画解説も用意しているため、操作ミスなどでつまずくこともありません。現場のGoogleアナリティクス4を体得したい方にぴったりの一冊です。 〈こんな方にオススメ〉 ・自分のGoogleアナリティクス4の使い方が正しいかどうかお悩みの方 ・Googleアナリティクス4を実践を通じて身に付けたい方 ・Webサイトの成果が上がらず困っている方 〈本書の内容〉 ■CHAPTER1 分析指標はこれだけ覚えておけば大丈夫 ■CHAPTER2 Googleアナリティクス4の管理画面と分析機能 ■CHAPTER3 ユーザー軸・集客軸で分析するケーススタディ ■CHAPTER4 行動軸で分析するケーススタディ ■CHAPTER5 Googleアナリティクス4のさまざまな設定 〈本書の特長〉 ・最新のGoogleアナリティクス4に対応! ・「実際によく使う」機能がしっかりわかる! ・デモアカウントを利用した実践的なケーススタディ! 〈著者プロフィール〉 山野 勉(やまの・つとむ) 株式会社ラグランジュポイント 取締役 2006年に法政大学都市環境デザイン工学科を卒業後、インターネット広告代理店である株式会社オプトにてアクセス解析事業部を立上げ、事業責任者として従事。延べ500社以上のサイトを分析・改善を行う。2012年に独立。独立後は、企業のアクセス解析のアドバイザーや、分析責任者を任される一方、研修講師やOJTを通してアクセス解析人材の育成を行う。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■超かんたんなICTスキルで、ハッピーな学級経営を今スグ実現しましょう! 今や「グローバル・スタンダード」と言ってもよいICT。 しかし、これまで問題なく仕事をしてきたのに、なぜ急にやり方を変える必要があるのか、なかなか足を踏みだせない教師も少なくないようです。 もちろんICTを使わなくても、教師の仕事はできます。 でも、ちょっとこれまでの学級経営を想像してみてください。 どんなに力のある教師でも、忙しい朝に欠席の理由を電話で聞き取る余裕がない、学級目標がなかなか浸透しない、子どもの忘れ物が減らないなどといった、ちょっとした「ストレス」を抱えてきたはずです。 そして、「こんなことできればなあ」という願いを抱えながらも、多忙で実現する方法を考える余裕もなく、仕方なくこれまで通りのやり方を続けてきたという人も多いのではないでしょうか。 実は、そんな教師の願いを「超かんたん」にかなえる方法があります。 それは、Googleのアプリ(正確には「Google Workspace for Education」)を使うことです。 Google Workspace for Educationは、今やGoogle社以外の端末でも使われるほど、世界中の教育現場で浸透しています。 なぜ、これほど浸透したのでしょうか。私は、この理由について、「協働」ができるからではないかと考えています。Googleのアプリの最大のメリットは、導入すると「子どもと子ども」、「子どもと先生」、「先生と先生」、そして「学校と保護者」が、端末さえあればどこででもつながることができるようになるのです。 この本では、そんなGoogleのアプリを使って、学級経営における悩みを解決し、教師も子どもも、そして保護者もハッピーになるICTの「超かんたん」スキルを紹介します。どれも、初歩的ではありながらも積み重ねることで、子どもの学習効果を高め、教師の時間節約につながるものばかりです。 スキルを紹介するのは、世界共通認定資格である「Google for Education 認定トレーナー」をもつ教師8人の教師たち。まったく使い方が分からない先生方はもちろん、少し活用してきた先生方でも、手に取っていただければ、「こんなアイデアがあったのか」と、思わずニヤリとするスキルがいくつもあるはずです。 いろんなGoogleのアプリを使いますが、特に「Google Classroom」を軸にした学級経営に注目してください。このアプリを軸に、ほかのアプリを連携・統合して運用することで、学級経営は劇的に変わり、教師人生そのものも、もっと充実したものになるはずです。学級経営とGoogleアプリコラボレーションの極意を楽しんでもらえれば幸いです。
-
-モバイルファーストからAI(人工知能)ファーストへ──。 2016年、米グーグルのサンダー・ピチャイCEO(最高経営責任者)はこう宣言し、 AIを軸とした戦略にかじを切った。 グーグルのAIは世界で最も難しいゲームとされる囲碁を攻略し、 現実社会でも活躍の場を広げている。 『週刊ダイヤモンド』(2017年6月24日号)の第3特集を電子化したものです。 雑誌のほかのコンテンツは含まれません。 *本誌の電子版も販売しています(最新号は毎週月曜日配信)。 詳しくは「週刊ダイヤモンド」で検索ください。
-
4.0Googleが提供するクラウドサービス AWSとの違いを軸に徹底解説 「Google Cloud Platform」(GCP)は、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureと同じく、企業向けのクラウドサービスとして提供されている。後発であることは否めないが、後発であるからこその特徴を備えている。 一般的な用途では「マネージドサービス」の充実が特徴と言える。そのほか、今注目の「機械学習」「ビッグデータ」関連のサービスが特に充実しており、AI関連のシステム基盤として要注目であることは間違いない。 本書では、「コンピューティング」「ストレージ」「ネットワーキング」「ビッグデータ」「機械学習」「アカウント管理」「運用監視」という7つのカテゴリーに分類し、GCPの特徴を、AWSとの違いを軸に解説している。 また、GCPのサービスを解説するほか、エンタープライズ用途のユースケースに基づいて、GCPを用いた設計ガイドをまとめている。技術力に定評のあるGoogleのクラウドサービスを検討するのに最適な1冊である。
-
3.7経営参謀とは、会社の未来像に基づいて戦略を立案し、プログラムを構築してそれを遂行できる人材のこと。企業を取り巻く環境が激変する現代において、その役割はとりわけ重要視されている。しかし一方で、企業が目先の人材に対する即戦力化を優先し、物事を一つ上の視点から考える人材を育てきれていないのも事実。本書は、経営参謀のために必要な三つの要素、「戦略立案」「組織変革」「リーダーシップ」を軸に、大競争時代を勝ち抜くためのコンサルタント頭脳の鍛え方を紹介したものだ。「軍事モデルと経営モデルの違いを考える」「自社の戦略の理解・確認の仕方」「解決策の検討方法」「課題の把握の仕方」「リーダーシップの型を考える」などについて具体事例を豊富に盛り込み、図表で平易に解説しているので、理解しやすい内容になっている。「戦略思考・手法の基礎知識がみるみる身についた!」とビジネスマンに評判の実践的テキスト!
-
4.0【スノーピークの強さの理由を、社長自らが語り尽くします】 スノーピークをアウトドアメーカーと思っている人は多いでしょう。ですが今や、16期にわたる増収を続ける絶好調企業にして、「アパレル」「飲食」「住宅デベロッパー」「コンサルティング」と事業領域を急速に拡大している総合メーカーへと変貌を遂げつつあります。事業領域として「衣・食・住・働・遊・学」を掲げるのは、服飾デザイナーから3代目社長に就任した山井梨沙氏。その中心には、常に「野遊び」を軸にしたスノーピーク独自の経営論があります。 ここ最近、「ビジョン経営」「パーパス経営」「デザイン経営」といった、経営手法がもてはやされています。スノーピークは1988年からビジョン経営、デザイン経営を続けるお手本のような企業です。 ですが、山井社長は、「自分たちがデザイン経営をしていると意識したことは一度もありませんでした」と言います。企業が目指すべき方向性を言語化し、全従業員を目標へと導く経営はどのように行われているのか。本書では、その要諦を明らかにしていきます。 【スノーピークはもはやアウトドアメーカーではありません】 キャンプで育った30代社長は、人として、経営者として何を大事にしているのか。また、今後どんな展望を持っているのか。企業価値の源泉となる焚き火のように熱い経営とは。第1章ではデザイン経営について、第2章では、業績好調の理由、第3章ではキャンプで育った経営者について、第4章では、事業を支える社員たちを紹介します。
-
-企業経営における「人事部門」の重要性に注目し、経営視点での人事「戦略」と現場視点での人事「戦略」のシナジーを『戦略人事』として、これからの時代に求められる人事の姿を考える一冊です。 これまでの『強い統制型の人事』から、「働き方改革」「多様性」「ワークとノンワークとのバランス」の尊重などを踏まえた『しなやかで開かれた人事(ライン部門や従業員個々も参画しながら全体を作り上げる人事)』を目指します。 また本書では、あえて「人事管理」に対応する言葉として「HRM(Human Resource Management:人的資源管理)」を使い、新しい人事=戦略人事のあり方を提示していきます。 これからは、「環境変化を主体的に察知して企業活動の競争優位性を高める経営(人事)戦略を打ち出し、社会・従業員などステークホルダーすべての満足を創りあげる人事」という能動的な「戦略人事」の姿勢を改めて強調しなければならないと考えます。 そして、それを司る人事担当者は、今までになく「経営を強くする」、すなわち「経営資源としてのヒト」を軸として「モノを創造すること」「カネを生み出すこと」「情報を活用しきること(新たに生み出すこと)」「時間(トキ)を稼ぎ出すこと」ができる人材を、市場から獲得し、活用し、社会に輩出していく一連のプロセスを戦略的に思考し、実践することを求められています。 このような考えから、労務管理・給与管理・勤怠管理などの日常の管理にかかわる実務の解説などは最小限にとどめ、「自社なりのメッセージ性のある『人事戦略』を立案したり、実践するためのプロセス」に的を絞っています。 ぜひとも本書を、「戦略人事」を実現するための「考える」ツールとして活かしてください。
-
-経営戦略を語る上で、最低限知っておくべき言葉、コンセプトがある。たとえば競争優位性やバリューチェーンなどは、それを知らないで経営戦略の議論をすることはできない。 KSF(Key Success Factors)もそのような言葉の一つと言えるだろう。実際、経営戦略の重要用語として、企業経営者やコンサルタントなどの間でも非常によく使われる言葉だ。筆者が教鞭をとるグロービス経営大学院の様々なクラスのスライドにも頻繁に用いられている。 KSFは一般には、事業の「成功のカギ」という意味合いで用いられ、その意味合いからしても、その概念を正しく理解しておくことは戦略立案上大切である。ただ、その「正しい理解」がなかなか難しいのがこのKSFという概念である。戦略論の書籍は多数あるが、意外とこの言葉について丁寧に解説した書籍は多くない。 また、KSFという言葉はバズワード(一見、説得力があるようで、明確な合意や定義のない言葉)であると主張する向きも少なくない。 本書では、よく使われる言葉の割に正しく理解されていないこのKSFという言葉について、事例を交えながら説明するとともに、他の重要コンセプトとの関連や、よくある質問例などを紹介している。また、KSFを軸としながら、戦略論だけではなく、組織運営のあり方についても議論している点がユニークである。
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 「敬語の基本的なことを知りたい」「若いときに覚えた敬語の知識を間違って覚えていないか心配」という人にぴったり! 「敬語の基本的なことを知りたい」「若いときに覚えた敬語の知識を間違って覚えていないか心配」という人にぴったり! ”1時間あれば復習できる”というコンセプトの敬語本です。 敬語がきちんと使える人は『この人、しっかりしていて信用できる』と思われることは間違いありません。 シーン別の敬語の使い方に加えて、メール・手紙の文例も収録。 目次より パート1 基本の敬語 パート2 ビジネスの敬語(外出・退社のあいさつ、名刺を交換する、上司に報告する、理不尽な要求にこたえる、欠勤を伝えるなど) パート3 電話&メールの敬語(電話をかける、電話を取り次ぐ、ビジネスメールの基本、メール文面集) パート4 言いにくいことを伝える敬語(謝る、お願いごとをする、催促をするなど) パート5 おつきあいの敬語(自己紹介、お祝いを伝えるなど) パート6 敬語を使って会話をしよう パート7 手紙の敬語 福田 健(フクダタケシ):1961年、中央大学法学部卒業後、大和運輸(ヤマト運輸)に入社。 1967年、言論科学研究所入所。指導部長、理事を歴任。1983年、(株)話し方研究所設立、同研究所所長に就任。 2004年、会長。コミュニケーションを軸にした講演、講座に出講。また、話し方研究所主催のセミナーでも直接指導にあたる。
-
3.3
-
-
-
-1巻330円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ~目次~ 【経営】 ●企業と人の新陳代謝を進めよ 需要喚起のアベノミクスから企業活性化のスガノミクスへ 新浪剛史×伊藤元重 ●日本コカ・コーラ、タカラトミー、新日本プロレス、そして…… 日本企業が“3カウント”を取られないための経営術 ハロルド・ジョージ・メイ×伊藤元重 【雇用・労働】 ●アベノミクス総括から見える雇用政策の課題 「最低賃金引き上げ」策の狙いと負のシナリオ 玄田有史 ●〔対談〕 連合会長に「リベラル保守」の論客が迫る 野党が「乗り移れる船」になるための対抗軸 神津里季生×中島岳志 【ルポ】 ●「地方創生」でも人口減少に歯止めかからず 菅首相の郷里・湯沢市秋ノ宮に見る地方の苦境 葉上太郎 ●存続、廃業、M&A…… コロナ禍に揺れる中小企業 高橋 徹 【財政・経済政策】 ●日本経済のアルゼンチン化を回避せよ コロナ不況と巨額財政赤字の行方 佐藤主光 ●無形の資源を守る有事の経済政策 菅政権に求められる財政支出の規模と中身 飯田泰之 ●〔時評2020〕 コロナ後は「低金利の罠」からの脱却を 土居丈朗 【規制改革 担当大臣に迫る】 ●仮想通貨、電波オークション、ドラッグラグ……。規制改革で暮らしを豊かに 「脱ハンコ」から始まる日本経済再生 河野太郎×聞き手:坂井豊貴
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 『経典釈文』「論語音義」は、何晏『論語集解』を軸として、『論語集解』諸本、『論語鄭玄注』など異本間の字句の異同、難解字への音釈、漢魏六朝間の論語説家の注釈を集成し、より正しいテキストと字音を示す目的で、六朝末に陸徳明(550-630)によって撰述された。中国では唐・開成2年(837)に建立された開成石経以後、論語本文はすべて開成石経に従うようになり、その結果、「論語音義」の記述とずれが生じ、「論語音義」修改の遠因となった。一方、日本には開成石経以前の論語古写本が伝存し、しかもそれら古写本には現在通行する「論語音義」に見えない多くの条目が書き入れられている。本書は、日本に伝わる鎌倉時代の論語古写本と開成石経系統の論語テキスト、さらに論語古写本から輯佚した「論語音義」と通行本「論語音義」を対比検討して、「論語音義」に関わる諸問題を解明する。日本古代における中国古典の学び方を知る上でも、多くの示唆を与える画期的業績。 【目次より】 凡例 序章 『経典釈文』「論語音義」研究の試み 一 陸徳明と『経典釈文』 二 『経典釈文』「論語音義」研究の目的と本書の構成 第一章 『経典釈文』「論語音義」の成書 一 「序録」に見える「論語』注釈書についての疑問 二 「序録」に見える『論語』注釈書の検討 三 「論語音義」の依拠した『論語』注釈書 四 「論語音義」所引の論語説と皇侃『論語義疏』 第二章 『経典釈文』「論語音義」を通じてみた『論語鄭玄注』 一 鄭玄による「魯論読正」記事 二 「論語音義」所引の『論語鄭玄注』 第三章 『経典釈文』「論語音義」を通じてみた『論語集解』 一 「論語音義」所引『論語集解』と『論語』諸本比校 二 「論語音義」が依拠した『論語集解』の分析 第四章 『経典釈文』「論語音義」の修改 一 「論語音義」に見える「本今作(無)」「今本」「今注」と『論語』諸本との比校 二 「論語音義」に見える「本今」とは 三 集解に「本今」が用いられる場合と用いられない場合 四 経に「本今」が用いられる場合と用いられない場合 五 「論語音義」の所引句が依拠した底本の解明 六 古抄本『論語集解』書き人れの「論語音義」より「本今」を考える 第五章 日本における経書研究と『経典釈文』の受容 (一) 藤原頼長の経書研究 (二)『経典釈文』と『全経大意』 (三) 鎌倉時代写『論語集解』断簡とその書き入れ 附論一 定州漢墓竹簡『論語』試探 附論二 『論語鄭玄注』は日本に伝来したのか まとめ あとがき 初出一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 高橋 均 1936年生まれ。中国文献学者。東京外国語大学名誉教授。 東京教育大学文学部漢文学科卒業、同大学院文学研究科博士課程単位取得退学。文学博士。 著書に、 『中国語解釈の基礎』『論語義疏の研究(東洋学叢書) 』『経典釈文論語音義の研究(東洋学叢書)』など、 訳書に、趙紀彬『論語新探 論語とその時代』温端政『諺語のはなし 中国のことわざ』 (共編訳)などがある。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 習慣が変われば、収支が変わる!! 少ない労力で最大限の効果をもたらす習慣とは!? 雑誌「競馬王」や競馬王関連書籍からのテーマ別オムニバスの第五弾(語り下ろし、書き下ろしも増量)。 勝てる人と勝てない人の差は、習慣(予想ルーティン)に表れます。 どの情報を見るか、どういうレースに参加するか、どういう馬を追いかけるか? どの券種を買うか? 儲けるためには何を優先すべきか? もし負けているのに、これら考えずにいつもと同じように馬券を買っていたら危険です。 負のループを断ち切るためには、習慣から見直す必要があるのです。 【収録内容】 勝ち続けるための必勝ルーティン ●TARO 危険な1番人気がいるレースだけに参加する! ●亀谷敬正×藤代三郎×双馬毅×馬場虎太郎 荒れるレースだけを買い続けることが回収率100%超え達成の近道! ●大谷清文 プラス収支を目指す上で絶対にやってはいけないこと ●馬券裁判男卍 負けないための年間スケジュール ●たくちん&メシ馬 気弱な傷病兵に勝てれば競馬は勝てます ●市原克也&吉冨隆安 「短縮ローテ」の正しい狙い方、見切り方 ●今井雅宏×亀谷敬正×双馬毅 最強の前走不利パターン 前走先行&展開不利 ●双馬毅 馬場読みの習慣で儲かるレースを見抜く ●馬場虎太郎 『ダ界地図』で見えたダートコースの上げ下げ ●半笑い その日の傾向を把握することが勝利のルーティン! ●古澤秀和 コース傾向を意識した軸馬選びの習慣 ●競馬王編集部 競馬における不美人銘柄 ●山崎エリカ×山崎元 2歳未勝利戦は多点買いの大穴狙いで一発逆転! ●久保和功 「馬券の買い方」の習慣 ●米田幸憲×山本昌 盤石データと軟弱データで1番人気の取捨を完璧に! ●奥野憲一 ローリスクハイリターンな3連複2頭軸流しのススメ ●六本木一彦 投資的観点から考える騎手で勝利に近付く方法 ●馬券裁判男卍 コース別 冬のダート 騎手の大全奥義! 全買いデータ ●伊吹雅也 障害馬券師ウオトモ直伝 障害こそ騎手が大事! ●ウオトモ 常勝競馬を叶えるための5つの秘策 ●キムラヨウヘイ 複勝コロがしの新習慣 複コロ先生の方法とは? ●魚谷智也
-
4.5桁違いの成果をあげるための、思考の新地平を学べる1冊。 マッキンゼーとBCG、世界2大コンサルティングファームで活躍してきた知の巨人が圧倒的なクオリティと重厚感で語る、思考法の最前線! 【10X思考(テンエックス思考)とは?】 21世紀、デジタルの世界では「旧来の延長線上にある成長」から「異次元の成長」へ移行が進んだ。 言葉のとおり、「桁違い」すなわち10倍化の成長だ。 この10倍化を生み出すための思考が、「10X思考」である。 飛躍的に進化する時代においては、ロジカル・シンキング、デザイン・シンキングといった既存の枠組みを踏まえたうえで、その限界を突破するための考え方、すなわち10X思考が必要となる。 10X思考を実践するための手引書として書かれた本書は、 目標達成の方法を教える安易なマニュアル本ではない。 しかし本書を読むことで、本物の思考力を身につけ、確かな自信を手に入れて、 問題を解決し成果を出し続ける「10X人材」へと歩みを進めることができるだろう。 【こんな方におすすめ】 ・知の最先端や次世代の働き方・生き方に関心がある ・高い目標と現実のギャップに悩んでいる ・成長することが自分の価値を高めることだと考えている ・何かしたいけれど、現状を打破する方法が分からない ・激動の時代において勝ち抜くヒントがほしい 【本書を読むことで得られるメリット】 ・この1冊で、様々な思考法の基本特性が分かる ・仕事で結果を出す思考法を習得できる ・課題に対する小手先の対処法ではなく、抜本的な能力開発が見込める ・複数の思考法やフレームワークを体系的に理解し、それらをうまく活用して新しい考え方を生み出せるようになる 【目次】 第1部 思考法の進化 第1章 ロジカル・シンキングの限界 第2章 デザイン・シンキングの罠 第3章 システム・シンキングの可能性 第2部 異次元へのワープ 第4章 3つのマクロトレンド 第5章 5つのパラダイム・シフト(PS:軸ずらし) 第3部 組織と仕事の未来 第6章 進化する組織 第7章 ライフ・シフト、ワーク・シフト 第4部 異次元思考への道 第8章 思考の新しい地平 第9章 目指せ、10X人財 【「はじめに」より一部抜粋】 20世紀後半は、ロジカル・シンキングのような問題解決型の垂直思考が幅をきかせていた。その担い手として活躍したのが、コンサルタントたちだ。21世紀にはいると、デザイン・シンキングのような機会発見型の水平思考に注目が集まるようになった。 (中略) 一方、そのような表層的な流行の底流で、世界を複雑系としてとらえるシステム・シンキングが進化し続けていった。 (中略)そして21世紀に入り、デジタルパワーは長足の進歩を遂げ始めた。 世界では「旧来の延長線上にある成長」から「異次元の成長」へと移行が進んでいる。「10X(テンエックス)」と呼ばれる現象である。10倍化、すなわち、桁違いの成長を意味する。 この10X化を生み出すのが、「10X思考」である。 ロジカル・シンキングなど、これまでのフレームワークの限界を超え、劇的進化を遂げる思考法だ。 この本は、新時代のビジネスパーソンに贈る、異次元の成長を楽しみ続け、「10X人財」となるための思考のイノベーションを導く手引書である。
-
3.0~大手人事採用担当者の、「ところで、その方は結婚していますか?」には理由があった~ ★どんなに仕事をがんばっても、独身だと伸びない! ★「結婚」すれば「ビジネスがもっとうまくいく」という法則があった! ★結婚はビジネスで最も大切な「他者からの信用」を得られる! この本は、「結婚」すると「ビジネスがもっとうまくいく」という法則を書いた本です。 その法則の軸は、ずばり、結婚するとビジネスで最も大切な「他者からの信用」を得ることです。 本書は、忙しいビジネスパーソンのために「結婚のススメ」を、論理的かつ、わかりやすく書いています。 本書をサラッと読むだけで、結婚への迷いや不安が消え、結婚で得た「他者からの信用」が、ビジネスの成功へとつながるプロセスを理解できます。 (【はじめに】より) こんな人にオススメします! ●結婚して、さらにビジネスでも成長したい人 ●「一生独身の、仕事人生でもいい」と人には強がっているが、本心では結婚したい人 ●結婚を通じて、自分自身の人生とキャリアを見つめ直したい人 ●ビジネスにおける結婚の活かし方を知りたい人 業界トップクラスの成婚率を誇る結婚コンサルタントが贈る ビジネスで成功するための結婚術! いわゆる「恋愛・モテ本」といわれるジャンルは山ほどありますが、結婚をしてさらにビジネス力も高める方法について書いてある本は本書だけです。 結婚して、さらに仕事もできるようになりたいと思っていたら、「ビジネス」か「恋愛・結婚」かの両極端の本を探し、別々に学ぶことになってしまうため、両方を同時に、そして効率的に学ぶことはできません。 素敵な結婚をしてビジネス力も向上させたい、そう思ったらぜひ本書を手に取ってみてください。
-
3.3立つ・歩く・座るなど身体の基本動作トレーニングから ペットボトルを使った温灸まで、 人気鍼灸師の健康法のすべてがつまった一冊 治療よりも養生が大切。不健康な生活でからだを壊してしまう前に、 東洋医学と古武術をベースにした12ヵ月のメソッドで健康を保とう! 現在、初診予約が受け付けられないほどの人気鍼灸師が、 自ら編み出した独自の健康法を、立つ・歩く・呼吸するなど 身体の基本動作トレーニングと、季節ごとの食養生レシピ、 さらにペットボトル温灸や爪楊枝鍼など〈からだの手当て〉の3本立てで紹介。 続けていけば少しずつからだの痛みや不具合が消えていく、 食とからだと手当てのレシピ。 2013年に刊行し好評を博した『からだの教養12ヵ月』の大幅増補決定版。 「わかってるんです、わかってるんです。立ち方、座り方、食べ方、 呼吸の仕方、温め方。はい、お酒は控えめに。 でも、でも、つい忘れちゃうんです。 だから何度もこの本をめくり直して復習しないとだめなんです! 」 ──坂本龍一さん推薦 ■からだ稽古編 ゼロ地点 ラジオ体操ができないところから 1ヵ月目 正しい姿勢って何なんだろう? 2ヵ月目 無駄な力って、どれ? 3ヵ月目 ゆらぐ体を感じよう 4ヵ月目 「軸」を知る 5ヵ月目 無理なく座る 6ヵ月目 楽に立つ 7ヵ月目 上半身を固めず動かす(1) 8ヵ月目 上半身を固めず動かす(2) 9ヵ月目 歩く 10ヵ月目 なんであちこち痛くなるのか? 11ヵ月目 呼吸と声 12ヵ月目 動くための解剖学 ■食と養生編 季節に合わせる、その前に 食こそ養生のかなめ 東洋医学の身体観・自然観 春 梅雨 夏 長雨 秋 冬 常に食べる食材の性質 ■手当て編 ペットボトル温灸 爪楊枝鍼 風邪の漢方の使い方 テーピング法(通称「リサット」)
-
3.0本書「はじめに」より抜粋 良いコーチングとは、次のように、正しい答えが見つからない、曖昧な状況に身を預けることを認識していて、受け止め、必要に応じて適切な判断を下すことを意味します。 ・ 人に対する好奇心を持ちながら、その好奇心が自分に向かっているのか、クライアントに眼差しを向けているのか常に見極める。 ・ 人の心を理解する優れた直感力を、時には適宜調整しながら相手と向き合う。 ・ 場合によっては、アドバイスを行いたくても控え、その一方でここぞというときにアドバイスする判断力がある。 ・ コーチは自分を押し付けないと同時に、クライアントに最大の意識を向けて、その人のための真の存在でいる。 ・ 人に興味を持ちながら、自分が好かれたいという欲求を自制する。なぜなら軸をぶらさず、妥協せずに相手に向き合わなくてはならないから。 ・ コーチングは真剣なやり取りだが、コーチング・ルームからは、時には騒々しいほどの笑い声も聞こえる。 本書では、コーチング・テクニックについて解説していきますが、最高のコーチングとは実はテクニックを超越するものです。それは、シームレスな対話ともいえるほどに自然体です。この状況を本のなかで理解するには、実例を示すのが最善だと思い、本書にもいくつかケーススタディを紹介しています。 【目次】 第1章 コーチングとは何か 第2章 信頼関係を築くための基本と実践 第3章 コーチとクライアントとの関係性 第4章 脳科学とコーチング 第5章 コーチングにおける言葉の重要性 第6章 課題の共有 第7章 目標設定 第8章 行動変容の支援 第9章 支援とチャレンジ 第10章 情報提供とアドバイス 第11章 涙、トラウマ、そして心理療法 第12章 より良いセッションにするアイデア 第13章 プロコーチが知っておくべきこと 第14章 テクニックを超える
-
4.0肩甲骨を自由自在に操れる者こそスポーツを制す! スピード・パワーが爆発的にアップ 眠っていた潜在能力を引き出し、ハイパフォーマンスを発揮できる身体に変わる トップアスリートの共通点は“肩甲骨”の使い方にあり 『立甲』の提唱者が理論に基づく 「歩く」「走る」「投げる」「打つ」「蹴る」 の力を引き出すメニューを紹介 ------------------------------------------------------------------------------------ すべてのアスリート、指導者、整体関係者、必読! スポーツ界で注目の「立甲」がはじめて書籍に! 肩甲骨を立てる=「立甲」ができるようになると 上半身を使う運動のパフォーマンスが飛躍的に向上し、ケガ予防にもなることが実証されています。 健康書としての「肩甲骨はがし」は立甲のさわりの部分です。 さらに肩甲骨を柔らかくし、使い方を習得すると肩甲骨を立てることができます。 「ゆる体操」で一世を風靡し、身体意識や古武術などに精通し、 10年以上前から肩甲骨と立甲の重要性を説いてきた第一人者・高岡英夫氏がわかりやすく解説します。 ------------------------------------------------------------------------------------ 立甲とは、スポーツパフォーマンス向上のためのエンジンです。 以下の効果が期待できます。 1肩甲骨の自由度が増して、腕をしなやかに、力強く使えるようになる! 2体幹が安定して、身体に「軸」が通り、ブレなくなる! 3下半身・脚部の機能まで高まる、向上する! 4身体への余計な負荷が減り、怪我のリスクが大きく減少! ≪目次≫ 序 章 「立甲」とは何か 第1章 「立甲」はすべてのパフォーマンスを高める 第2章 「立甲」の正確な方法 第3章 「立甲」でパワーアップする 第4章 立甲と甲腕回旋力で「歩力・走力」を高める 第5章 立甲と甲腕回旋力で「投力」を高める 第6章 立甲と甲腕回旋力で「打力」を高める 第7章 立甲と甲腕回旋力で「蹴力」を高める
-
4.0現代人が課せられる「まともな人間の条件」の背後にあるもの。 生活を快適にし、高度に発展した都市を成り立たせ、 前時代の不自由から解放した社会通念は、同時に私たちを疎外しつつある。 メンタルヘルス・健康・少子化・清潔・空間設計・コミュニケーションを軸に、 令和時代ならではの「生きづらさ」を読み解く。 社会の進歩により当然のものとなった通念は私たちに「自由」を与えた一方で、 個人の認識や行動を紋切型にはめこみ、「束縛」をもたらしているのではないだろうか。 あらゆる領域における資本主義・個人主義・社会契約思想の浸透とともにうつろう秩序の軌跡と、私たちの背負う課題を描き出す。 かつてないほど清潔で、健康で、不道徳の少ない秩序が実現したなかで、 その清潔や健康や道徳に私たちは囚われるようにもなった。 昭和時代の人々が気にも留めなかったことにまで私たちは神経をつかうようになり、 羞恥心や罪悪感、劣等感を覚えるようにもなっている。 そうした結果、私たちはより敏感に、より不安に、より不寛容になってしまったのではないだろうか? 清潔で、健康で、安心できる街並みを実現させると同時に、 そうした秩序にふさわしくない振る舞いや人物に眉をひそめ、 厳しい視線を向けるようになったのが私たちのもうひとつの側面ではなかったか?(「はじめに」より) 【著者略歴】 熊代亨(くましろ・とおる) 1975年生まれ。信州大学医学部卒業。精神科医。 ブログ『シロクマの屑籠』にて現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信し続けている。 著書に『ロスジェネ心理学』『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(ともに花伝社)、 『「若作りうつ」社会』(講談社現代新書)、『認められたい』(ヴィレッジブックス)、 『「若者」をやめて、「大人」を始める』(イースト・プレス)がある。 【目次】 第一章 快適な社会の新たな不自由 第二章 精神医療とマネジメントを望む社会 第三章 健康という“普遍的価値” 第四章 リスクとしての子育て、少子化という帰結 第五章 秩序としての清潔 第六章 アーキテクチャとコミュニケーション 第七章 資本主義、個人主義、社会契約
-
4.0「ダイエットにはプールが最適」「のどが乾いたらスポーツドリンクがいい」「漢方薬に副作用はない」――こういった日々メディアで流される健康知識に興味がない人は少ないだろう。しかし、そういった情報が、最新の研究論文によると実は間違いだったり、最悪の場合、寿命を縮めたり、突然死の原因になるとしたらどうだろうか? 巷で信じられている健康知識には、メディアが一部の研究結果を切り取ったり、意図的にねじ曲げられたものが多々存在するのである。医学博士で、実際に現場の最前線に立ち続ける医師でもある石原藤樹が、日常生活、食事、健康食品、子供の医療などを軸に、健康の新常識である27項目を紹介。健康で長生きしたい人に贈る、本当の医学知識書!【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
-かかと? つま先? あなたの軸はどこにある? 4スタンス理論で身体の歪みを矯正する。 腰痛、肩こり、ひざの痛み、身体のメンテナンスから、瞬発力、跳躍力、スポーツパフォーマンスまで――ノウハウ満載。 立って生まれてこない人間が、なぜ立って生きるのか。足裏を使わずに生まれ、足裏を使い続けて生きる。 健康に生きることと足裏とは深い関係性があるのではないか、という思いから足裏の研究を続けた著者は、つちふまずの定義、そして人が二足で立つということの意味にたどり着いた。 「4スタンス理論」で知られる著者による、足裏に根ざしたまったく新しい身体理論。 本書を参考に、健康的に立ち、しっかりと動き、安らかに休みましょう。つちふまずからはじめる身体改善法。
-
3.0
-
3.8今も影響を残す史上最長政権の功罪 アベノミクス、選挙での圧勝、戦後70年談話、さまざまなスキャンダル、憲法改正をめぐる騒動、TPP……。7年8カ月という例をみない長期政権の評価は、いまも定まっていない。この間、日本の政治をとりまく見方は「反安倍」か、さもなくば「親安倍」かに二分された。この政権は、結局、何をやろうとし、何を残したのか? 『新型コロナ対応民間臨時調査会』『福島原発事故10年検証委員会』など、話題のレポートを次々発表しているシンクタンクが、政権当事者に対する徹底インタビューを軸として、その政権の内幕に迫る。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 建築・土木に関わるすべての方必携!! 「震度7の連鎖」がもたらした教訓とは? 4月14日夜の「前震」、16日未明の「本震」と、2度の大地震が熊本を襲った。震度7クラスの揺れが短期間に連発するという“想定外”の現象により、木造住宅やマンションは崩れ、交通インフラやライフラインも分断された。 市民を守るはずの庁舎や学校なども多くが使用不能となった。 「本震」を現地で体験した3人の記者のリポートを軸に、日経グループの専門3誌のネットワークで地震や建築の専門家を取材。 阪神大震災や東日本大震災など、過去の大地震との比較を交えつつ、前例のない「波状的地震」が突き付けた都市と建築の課題を明らかにする。 写真で見る街の傷跡 建築編 あえなく機能停止した災害拠点 住宅編 「新耐震基準」以降でも明暗分かれる 土木編 阿蘇大橋はなぜ落ちたのか? 今こそ過去の大地震に学べ! 阪神・淡路大震災(1995)、新潟県中越地震(2004)、福岡県西方沖地震(2005)、東日本大震災(2011)、台湾集集地震(1999)、台湾南部地震(2016)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 多くの大学で支持される教科書に待望の新章追加! 本書では、鋼材の特徴から構造力学で学んだ解析法によって骨組みの応力や変形を理解し、構造力学と構造設計の結びつきをしっかり学べます。 さらに、設計の上で特に問題となる座屈現象や柱材と梁材の接合部の特性、接合法をマスターすることで、鉄骨構造設計の基礎を実務に則した形で身に付けることができます。また改訂にあたり、3版の内容をアップデートするとともに13章「ラーメン設計」を新たに追加し、ラーメン構造についてもくわしくカバーしました。 理論式や関連知識、専門用語などは側注等を使ってわかりやすく解説し、章末に演習問題も豊富に盛り込みました。最新知見や最新基準に則し、より一層学びやすい表現に改めています。 初版はしがき 大学・高専の建築系の学生および初等・中等の建築技術者を対象として,建築構造学の基礎を学ぶことに重点を置いた教科書シリーズが企画された.大学における建築構造学の教科は,構造力学が中心になっており,さらに各種構造の中から,わが国の主要な構造方法である鉄骨構,鉄筋コンクリート構造を採り入れているのが普通である. (中略) 本シリーズの特徴は,実務における設計のすべての領域を詳述するのではなく,設計の基礎となる原理および理論,建物の構造性能を支配する各種の破壊現象,外力の作用の下での建物の変形挙動と破壊性状,設計のえ方などその構造の本質が理解できるように,できるだけ内容を限定して平易に説明していることである. (中略) 鉄骨構造は,わが国で毎年着工される建物の床面積の35?40% を占めている主要な構造であり,建築系学生が将来どのような建築の専門分野で仕事をする場合でも,この構造の特性を理解しておくことが望まれる.鉄骨構造は使用材料である鋼材の特徴から,構造力学で学んだ解析法によって,骨組の応力や変形が精度よく予測できるので,構造力学と構造設計の結びつきが理解しやすい構造である.しかし,設計においては,部材の抵抗力を低下させる座屈現象や柱材と梁材の接合部など各種の接合部の性能を支配する構成法や接合法など鉄骨構造の特徴を理解する上で学ぶべきことは多い. 本書は建築鉄骨構造の要,構造計画,鋼材,ボルト接合法,溶接接合法,座屈理論,塑性解析法,軸力材,梁材,柱材,接合部,骨組に関する12 章で構成されており(注:改訂4版では「ラーメンの設計」を加え全13章),それぞれ専門分野の研究者に執筆を担当していただいた. (中略) 改訂4版にあたって 日本建築学会の「鋼構造設計規準(2005)」が版を改めて,「鋼構造許容応力度設計規準(2019)」として刊行された.内容に大きな変更はないが,本書の各章にある引用はこの規準に合わせるようにした.同学会の「鋼構造塑性設計指針(2017)」の改訂に合わせて,9 章の梁の耐力評価式,10章の柱の耐力評価式を新しい式に入れ替えた. この改訂では,新たに13 章「ラーメンの設計」を加えた.2 層1 スパンの純ラーメンの簡単な骨組であるが,1 章から12 章までの内容,それに設計の流れを具体的な計算で学べるよう,「許容応力度設計」と「保有水平耐力の確認」の手順を示した.上部構造は鉄骨でも,基礎および基礎梁は一般に鉄筋コンクリート構造になる.ここでは本書の範囲外であるが,建築学会の「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2018)」による計算手順も示した. その他の改訂について,1 章の1・3「構造特性と特徴」で各章の対象内容とそれらの繋がりが分かるようにした.1・4「新構法と展望」の内容を再整理し,制振(震)・免震構造と鋼コンクリート合成構造の概要,環境問題の最近の状況も加えた.1 章,3 章,4 章の側注を充実させた. 本書が建築を学ぶ学生・技術者にとって,建築鉄骨構造の基本と本質への理解を深めることに役立てば幸いである." 第1章 建築鉄骨構造 第2章 構造計画と設計法 第3章 鋼材の性質 第4章 ボルト接合法 第5章 溶接接合法 第6章 座屈理論の基礎 第7章 塑性解析法 第8章 軸方向力を受ける部材 第9章 曲げモーメントとせん断力を受ける梁材 第10章 軸方向力と曲げモーメントを受ける柱材 第11章 接合部 第12章 骨組 第13章 ラーメンの設計 付録1 鉄骨構造の地震と強風と積雪の被害 付録2 建築鉄骨の製作技術と品質管理 付録3 形鋼と鋼管の形状寸法と断面特性 索引
-
3.0いかに無駄なく、時間を効率的に使いながら、 描いた完成図に到達するか! 偏差値30台・勉強嫌いのナマケモノだった著者が ケンブリッジで学んだ行動習慣 段取りとは、自分の強みを最大限に発揮するための仕事術なのです。 これにより、限られた時間で最大の成果を生むことができます。 会社よりも人に信用が集まる時代。 人と人のつながりの中で仕事が生まれていく時代においては信用が全て。 新社会人になった方、異動で新しい職場になった方。 心機一転、段取りよく仕事をこなして結果を出していきたいですね! 本書では、1分程度で読めて、一生使える50のメソッドを紹介していますので、「これは!」 と思うものから、まず実行してみてください。きっと何かが変わっていきます。 「段取り」とは、自分の強みを最大限に発揮するための仕事術なのです。 良い段取りで、相手の期待を上回るパフォーマンスを示すことができれば、信用を高めることができる。 本書は、読者がその効果をすぐに感じられるよう、ケンブリッジで学んだ心理学の知見を交えて、 段取り力を劇的に高める方法を解説します。 ■目次 ●第1章 ゴールまでの道のりを描こう ・ゴールの向こう側の景色をイメージする ・「そもそも」でブレない軸を作る ・10倍思考でブレイクスルーを探る ・期限は自分で決める ・サティスファイサーを目指す ・意思決定にも期限を設ける ・断る勇気で、クオリティを高める ・逆算と積み上げの両方で考えてみる ・いかに努力しなくていいかを考える ・想定外を想定しておく ●第2章 頭の中をスッキリと整理しよう ・頭の中をできるだけ空っぽにする ・「一言で言うと?」を問いかける ・それは自分がすべきことなのか考える ・頭ではなく、手を動かす ・「ここだけの話」で情報の質を高める ・やることを二つに分類する ・PDCAはとにかく回転率を高める ・パターン化でメッシになる ・ちょっと悲観的なプランをベースに考える ・リソースを把握して、活用する ●第3章 コミュニケーションで段取りを加速させよう ・相手の頭の中にある言葉をイメージする ・メールは短く、短く、そして早く ・一歩先をスケジュール化しておく ・こまめな確認で信頼を高める ・知らないことは知らないと言う ・いい質問で理解を深める ・聞くに徹して、相手を理解する ・具体的な言葉で信頼を勝ち取る ・数値化して客観的に判断する ●第4章 集中できる環境をつくろう ●第5章 段取り力を高める習慣 ■著者 塚本亮
-
4.0管理会計は、将来の利益を生むための基本として、意思決定や投資の評価などのように、企業経営において欠かせない大事なナレッジです。予算管理、価格決定、受注可否判断、コストダウンなど、活用は多岐の分野で活用されますが、そのレベルの差がそのまま業績の差となって表れます。経理部など専門部門が担う「財務会計」とは異なり、技術部門、製造部門、生産管理、営業部門、情報部門、管理部門の第一線のマネジャーなどのすべての人が知っておくべきビジネス・ツールです。 本書は、「製品別採算管理」「事業ポートフォリオ管理」「投資案件管理」について、ケースをもとに企業の担当者に向けて実務的にまとめました。 【もくじ】 序章 管理会計とは何か 1.ケース:大手総合食品メーカーCEOの1日 2.経営ダッシュボード 3.将来の予測情報に基づく投資意思決定 4.管理会計とは何か? 第1章 製品別採算管理 1.製造業における製品別P/L管理 2.採算管理における販管費の取扱いと多軸管理の考え方 3.社内取引と仕切り価格 4.多品種変量生産での標準原価設定 5.多品種変量生産での原価差異分析 6.多品種変量生産での原価低減 7.製造・調達リードタイムが長い製品の採算管理 8.需給変動が大きい場合の採算管理 9.製品別採算管理によるPB製品の受注可否判断 10.サービス別採算管理 第2章 連結製品別採算管理 1.連結原価計算と連結製品採算管理 第3章 資本コストを意識した事業業績管理 1.事業とは 2.資本コストを意識した事業業績管理の基礎 3.投下資本の時価と簿価―事業別に資本コスト率を設定するか― 第4章 管理会計の基礎 1.P/L・B/S・C/Fとは何を表現しているのか 2.経営管理のための検討ポイント 第5章 投資管理(前編) 1.投資管理の全体像 2.投資計画作成―CGU― 3.投資計画作成―キャッシュフロー計画― 4.投資計画作成―投資判断― 第6章 投資管理 後編 1.投資実行のモニタリング 2.投資計画作成―2期にわたる投資― 3.実行後フォロー 終 章 P/L・B/S・C/Fとは何を表現しているのか 1.利益とは何を示しているのか 2.売上高とは何を示しているのか 3.営業キャッシュフローとは何を示しているか 4.フリーキャッシュフローとは何を示しているのか 5.B/S(貸借対照表)は何を表しているか
-
4.0パーパスとは何か。なぜ必要なのか。どうやってつくるのか。 いま知りたい疑問に答えます! 「パーパス(揺らぐことのない社会的な存在価値)」が注目を集めている。 日本企業でも、パーパスの策定に取り組み始めたところは多いが、 何から手を付ければいいのかわからない、という声もよく聞かれる。 パーパスと社是、ミッション、ビジョンは何がちがうのか。 本当に経営やビジネスの役に立つのか。 どうすればうまくいくのか。どこで失敗するのか。 どんな手順で進めていけばいいのか。 本書では、そうした素朴な疑問に答えながら、 パーパスの定義や考え方をかみくだいて説明し、 実際にどのように策定すればよいのかを、 先進企業の事例を用いて解説する。 【本書で取り上げる主なケース】 -ソニーグループ:「感動」と「人」を軸とした長期視点での経営を目指す -オムロン:企業理念「実践」経営により、企業価値向上を目指す -ネスレ:創業150周年のタイミングで存在意義を再確認し、言語化 -イケア・ジャパン:多様なステークホルダーとビジョンを共有し、社会にポジティブな変化をもたらす など
-
-かつて世界に名を轟かせたイギリス海軍戦艦部隊。だが、太平洋戦争に至り戦局は航空戦力の運用に軸が移りつつあった。戦艦か航空機か。当時の世界最新鋭の戦艦に帝国海軍航空隊が必死の意気で挑んだマレー沖海戦。戦術の分水嶺となった歴史的激闘を描く!!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 リーダー、管理職に不可欠なマネジメントで迷わないための「管理会計」がわかる! さまざまなビジネスシーンでカギを握るのが管理会計。最低限必要な「決算書」の読み方を学び、会社を活かすための「意思決定」のコツをつかみ、経営コンサルタントとも対等に話せる思考を身につけられる。コスト削減と合理的な意思決定を行うことから価格や目標販売数の設定や損益分岐点の分析・活用、そして、撤退のタイミングと限界利益の把握まで管理会計の知識がすんなりと身につく経営ストーリーを軸に学んでいく。また、管理会計で大切な「原価管理」の手法を理解し、利益をアップさせるための計画から実行へと結びつけ現場や経営者の視点から意思決定のノウハウがわかる1冊。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。
-
4.0近年の研究で、高血圧は塩分とともに摂取する糖分の増大で起こることが分かってきました。 減塩だけしていても高血圧は治りません。 根本的に血圧を改善するためには、「減糖」が必要です。 どうすれば血圧をさげることができるのか新しい「減糖」というテーマを軸に解説します。 1章では、何故「減糖」が身体にいいのかエビデンスをもとに解説します。 2章では、高血圧に効く10の法則を解説します。減糖だけでなく、座り方、水の飲み方なども解説し、身体にいい、法則を紹介します。 3章では、高血圧だけでなく、健康にもいい食材を紹介します。 管理栄養士だから提案できる、高血圧に効く新しい常識を是非ご覧ください。
-
3.83.11で原子力の平和利用神話は崩れた。人間の叡智は原子力に抗し得なかった。哲学もまた然り。しかし、哲学者でただ一人、原子力の本質的な危険性を早くから指摘していた人物がいる。それがマルティン・ハイデッガー。並み居る知識人たちが原子力の平和利用に傾いていくなかで、なぜハイデッガーだけが原子力の危険性を指摘できたのか。その洞察の秘密はどこにあったのか。ハイデッガーの知られざるテキスト「放下」を軸に、ハンナ・アレントからギリシア哲学まで、壮大なスケールで展開される、技術と自然をめぐる哲学講義録。3.11に対する哲学からの根源的な返答がここに。
-
4.2
-
3.3
-
-
-
4.3
-
4.0知らずに加担している、この圧倒的な不正義。 東京の路上で。灼熱のカタールで。 日常を奪われ「奴隷」とされた人たちの 想像を絶するストーリーを軸に、 世界5000万人、数十兆円規模の グローバル闇産業の驚愕の実態と いま企業・個人に求められる行動を語る。 ◎ワールドカップ開催国カタールの強制労働で世界が注目する大問題 ◎世界5000万人・数十兆円規模の“グローバル産業”「現代の奴隷制」の真実 ◎日本の事例も‥‥奴隷状態から生還した3人の驚愕のストーリー ◎ビジネスが鍵! サプライチェーンに潜む強制労働リスクにどう対処する? ◎SDGsとESGの時代、企業・個人に求められる問題解決へのアクションを示す モノのように売られ、酷使され、捨てられる―― 世界5000万人超と言われる「現代奴隷」。 それは過去でも遠い国の話でもなく、ビジネスや消費を通じて 私たちの経済・社会・暮らしにもつながっている‥‥。 アメリカで、日本で、カタールで。想像を絶する日々を経て 奴隷状態から生還したサバイバーたちのストーリー、 問題解決に取り組む人々の挑戦を丹念に取材し、 人身取引の真実と企業・個人にできることを示す。 [構成] 日本語版序文 序文――なぜ? 第1章 現代奴隷とはだれのことか 第2章 最も卑劣な犯罪――人身取引というビジネスモデル 第3章 ネパールからカタールへ――債務奴隷 第4章 心に刻まれたタトゥー――腐敗と免責 第5章 奴隷化の心理的影響 第6章 バル・アシュラムの子どもたち 第7章 人身取引加害者の胸の内 第8章 限られた選択肢 第9章 ビジネスが鍵(課題と解決策の両方で) 第10章 解決法――個人から、分野を超えた世界的な関わりへ 第11章 私のヒーローたち
-
5.0これを読まずして現代サッカーを語ってはいけない “異端のアナリスト”庄司悟はこれまでピッチ上で起こる様々な「主旋律」を、誰もが一目でわかる「一枚の絵」で表してきた。「2軸」「非対称」「皿と団子」「同期・連動」「連動→連鎖→連結→連続」「志・智・儀」といった“異端用語”を駆使しながら、ペップ・グアルディオラ、ユルゲン・クロップ、ユリアン・ナーゲルスマン、ハンス=ディーター・フリックたちが標榜する世界最先端の現代サッカーを「一枚の絵」で明らかにする。 【構成】 Ouverture〈序曲〉 はじめに Praludium〈前奏曲〉 ・起源 ・クロップ魔法陣 Op.1 〈第1楽章〉 ゲーゲンプレス2.0 〈第2楽章〉 複数で突っ走る 〈第3楽章〉 「レコード」は「データ」にあらず 〈第4楽章〉 90分のコンセプトを「一枚の絵」で表す 〈Zugabe〉 木を見て森を見ず Pause〈休憩〉 Jの主旋律 Op.2 〈第1楽章〉 皿と団子 〈第2楽章〉 有効性か効率性か 〈第3楽章〉 修正→構築→継続 〈第4楽章〉 情報≠知見 〈Zugabe.1〉 志・智・儀 〈Zugabe.2〉 ハイブリッド型0局面 Das Finale〈終曲〉 おわりに
-
-進化したWatsonでAIアプリを開発しよう! AIサービスの先駆けでもある「Watson(ワトソン)」。 近年急激な進化を遂げています。 機械学習や深層学習を利用したアプリケーション開発において 利用する開発者の方も増加してきています。 本書は、そうしたWatson の主力サービスである、 ・Watson Assistant ・Watson Discovery ・Watson Studio を軸にした開発手法を紹介する書籍です。 第1部では、Watson、Watson APIとIBM Cloudを利用した AIサービス開発の基本を紹介します。 第2部では、「Watson Assistant」「Watson Discovery」「Watson Studio」を利用した AIサービスの開発手法を紹介。 最終章では、ハタプロ社のロボット「ZUKKU(ズック)」の事例なども紹介します。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-東京電力・福島第一原子力発電所の事故発生から2年半ちかくが経過した。同原発近くの港では、海水の放射性物質の汚染濃度が原因不明のまま上昇し、事故収束のメドは一向に立たないなか、全国の原発が再稼働に向けて動き出した。 安倍政権が成長戦略の柱の1つとして推進する原発輸出政策も問題含みだ。年内をメドにエネルギー基本計画を策定するとしているが、安倍政権が原発を将来的にどう位置づけるのか、方向はまだ見えない。中小企業は電気代値上げに苦しみ、事故収束に当たる労働者の不足も懸念される。3・11後、原発に起因する問題は何一つ解決したとはいえないだろう。 7月に投開票が行われた参議院選挙の争点の一つは原発再稼働の是非だったが、残念ながら論戦が深まったとは言いがたい。5つの争点を軸に、原発と東電をめぐる問題点を徹底検証した。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12973-6)も合わせてご覧ください。 本書は,世界最先端のAI研究所の一つであるDeepMindが発表した論文を軸に,現代的なAIがどのように作られているのかをまとめた技術解説書です。 「汎用AI」「ゲームをプレイするAI」をテーマとし,おもに深層強化学習の技術を取り上げます。深層強化学習は,いまの世の中で広く使われているディープラーニングをゲームなどの領域に応用した技術です。 深層強化学習には高性能なシミュレータが必要であり,ゲームをはじめとした架空の世界を舞台として最先端の研究が進められています。 本書ではこれまでに発表されてきた論文を通して,「いま技術的に何ができて,何が難しいのか」を紐解きながら,一つ一つの技術を積み上げた先に来る,次の時代のAIについて考えていきます。
-
3.9
-
2.7同性にしか興味が持てず悩んでいた白地。小学校の教師となった今、ようやく自分と折り合いをつけ、幸せな恋をしようと前を向く。そんなとき、出会った男はどこか影があるものの白地を強く惹きつけた。恋が始まるかに見えたが、彼は自分の教え子の父親で……?悩みながらも同性の恋人を一途に愛し続ける小学校教師を軸に、彼をとりまく人々の恋愛模様をも含めて描くほろ苦いラブストーリー。電子限定おまけ付き!!
-
4.81993年、あの松井秀喜を抑えて新人王に輝いた元ヤクルトスワローズ伝説の投手・伊藤智仁。名捕手・古田敦也に「直角に曲がる」と言わしめ、名将・野村克也でさえも「私が見た中でナンバーワン」と感嘆した“高速スライダー”を武器に、プロ野球界を席巻した。そんな鮮烈デビューを果たした伊藤だが、その後はたび重なる故障に見舞われ、長期離脱を余儀なくされる。過酷なリハビリに打ち克ち、一度はカムバックを果たしたものの、伊藤の右腕は再び悲鳴を上げる・・・。その後も復活をめざし懸命なリハビリを続けたが、とうとう神宮のマウンドに戻ることはできず、03年に現役引退。世間からは「悲運のエース」と呼ばれた。しかし、伊藤智仁は「悲運」ではなかった―。三十数時間に及ぶ伊藤智仁本人へのロングインタビューを軸に、野村克也、古田敦也、岡林洋一、石井一久、館山昌平、米野智人、松谷秀幸、由規、篠塚和典、立浪和義ら当時のチームメイトや対戦相手、さらにはアマチュア時代の恩師や家族など、総勢20名以上の関係者が今まで明かされることのなかった真実を語る。今もなお、野球ファンの心に深く刻まれている伊藤智仁。その半生を、93年のデビュー戦から17年の「最後の一日」までを見届けた作家の長谷川晶一が書き下ろす、渾身のノンフィクション作品。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量15,000文字以上 20,000文字未満(20分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 生きていく上で、重要なこともそうでないことも、決断する場面は数多くあると思います。 それが人生における重要な選択の場面だと、決断するのに勇気が必要だったり、どうすればいいか悩んでしまったりすることもあるかと思います。 誰かに相談したり、いろいろと調べてみたりと、最善の選択をするためにできることもあります。 私は、自分の人生に大きな影響がある決断は全て自分で考えて行ってきました。 成功しても失敗しても悩むくらいならやってみる。そうすることで、全て自分の責任にできるからです。 もちろん失敗したこともあります。それもまた経験として後に活きてくると信じています。 慎重になることは悪いことではありません。ですが、やらずに後悔するよりはやって後悔するほうがはるかにいいと考えています。 そういった決断が苦手な人も多いのではないでしょうか。私がどういうふうに考えて、どういうふうに決断してきたのか、少しでも参考になればと思っています。 【目次抜粋】 第一部 私が自分で決断するようになったわけ 教育方針 自分の意思 自由 第二部 誰かに相談することの意味 充実した大学での一人暮らし 初めての相談 広がる選択肢、そのメリットとデメリット 第三部 大事なことほど自分で決める 結果より過程 自分で決めたこと(進学) 自分で決めたこと(仕事) 自分で決めたこと(上京) 第四部 選択肢のない決断の辛さ 潰瘍性大腸炎 何もできない日々 選択肢がある幸せ 第五部 結果論 決断したことに向かって頑張る 良い結果が全てではない 第六部 失敗だった決断 あとで気付くこともある 失敗だった決断(大学中退) 失敗だった決断(病気) 第七部 自分で決断することの意味 絶対はない 「後悔」という言葉 考え方次第 第八部 後悔しない決断をするためのコツ 常に心掛けていること 人生における大事な決断の軸 【著者紹介】 イイマトモキ 28歳のときに潰瘍性大腸炎を発症。 飲食店歴16年。 試行錯誤しながら自分にできることを模索中。 現在44歳。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 X軸とY軸が交差し、「数の組」の変化を点や線で表す座標。今では当たり前の概念ですが、デカルト以前の数学者は誰もそんなことを思いつきませんでした。デカルトはいかにして代数と幾何を結び付けたのでしょうか。「日本一わかりやすい」と絶賛される超人気予備校講師が、高校生を感動させた数学の歴史の話や、伝説の予備校講師三人の美しい「問題の解き方」を紙上再現します。 ●古代エジプト人は図形を使って2次方程式を解いた ●「解の公式」の誕生 ●実数から虚数、そして複素数へ ●アインシュタインに匹敵するデカルトの発想 ●物理学への扉を開く「モンキー・ハンティング」 ●「受験の神様」と呼ばれた渡辺次男先生の数学 ●発想の柔らかさをもった山本矩一郎先生 ●完璧な板書と解法だった根岸世雄先生
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【2022年必修化、2025年共通テスト出題予定】 情報Ⅰ学習の最初の1冊はコレ! 「情報Ⅰ」は「情報デザイン」「プログラミング」「データの活用」をツールとして活用することで、「問題を解決する能力」を身につけられる教科です。 たとえば文化祭のクラス企画でハンバーガー屋を出店することになり、出店場所に悩んだとしましょう。「データ活用」の視点を持てば、次のように考えることができます。 ①「どの場所に出店すれば売上げがよくなるだろう?」という問題を発見する。 ②過去の文化祭の出店場所と売上データの分析計画を立てる。 ③実際に分析し、出店場所と売上のデータのグラフを可視化する。 ④分析結果をもとに出店場所を決め、後日、実際の文化祭の売上げから評価する。 情報Ⅰではソフトウェアやアプリなどの操作技能の習得、情報学の知識も学びますが、それだけでは不十分。実際にそれらの技能・知識を活用し、生活の中で起こる問題解決を行って初めて、深い学びになります。その力は将来、社会に出たときも役立つはずです。 そこで本書は「問題解決」を軸にして、情報Ⅰの基礎を学べるように作りました。学んだことが実生活ですぐに役立つように、本書で取り上げる「問題解決」は、高校生にとって身近で、切実で、実行可能な題材を意識しました。 私は、教科情報の教師の仕事は、生徒が問題解決に取り組みたくなるような具体例を示すことだと考えています。本書ではそうした具体例を示しているつもりですので、ぜひ登場人物たちが問題解決に取り組む様子を楽しみながら、学んでみてください。 (「はじめに」より) 本書の7つの強み その1 新科目「情報Ⅰ」をイチから丁寧に解説! その2 本文が会話調で進むから楽しみながら学べる! その3 イラストや図が多いから想像しやすい! その4 「問題解決」が軸のストーリーだから社会で役立つ力が身につく! その5 「ここが大切!」に各項目の要点をギュッとひとまとめ! その6 各項目にふりかえり問題「確認してみよう!」を掲載! その7 「意味つき索引」があるからわかりづらい用語もこわくない!
-
3.0米国撃滅の秘策は、 超重爆撃機の製造にあり! 中島知久平 渾身の檄が飛ぶ !! 昭和16年2月、中島飛行機は群馬県の40万坪に及ぶ広大な敷地に太田飛行場を完成させ、一三試陸攻の初飛行に成功した。2日後、「大社長」中島知久平は主要技術者を前に、アメリカ本土を爆撃し得る超重爆撃機の製造を軸とする米国撃滅戦策の大綱をぶちあげ、「Z計画」がスタート。8月にはZ機を陸海軍共同開発機とすることが決まり、「富嶽」と命名された……。 12月8日、日本軍は真珠湾を攻撃し、ついに太平洋戦争へと突入。中島飛行機は東京・三鷹に総合研究所を完成させて富嶽開発の拠点とし、アメリカが底力を発揮してくる前に富嶽を完成すべく全力をそそぐ。そして翌年10月、富嶽1号機が待望の初飛行の日を迎えた……。
-
3.8
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 心理統計のエッセンスがたったの30キーワードでわかる! 初版に5つのキーワードを追加してパワーアップ。数学が苦手の学生でも基礎からしっかり学べ、しかも大学院合格に必要な知識が身につく。試験傾向分析・用語リストも充実。 目 次 例題1 心理学研究法《尺度水準 心理学の研究法 縦断研究と横断研究》 例題2 信頼性と妥当性《信頼性 妥当性》 例題3 記述統計法《度数分布表 代表値》 例題4 標準化《標準偏差と正規分布 標準化と偏差値》 例題5 2変数の関連《相関係数 相関係数と因果関係》 例題6 内的・外的妥当性《内的妥当性 外的妥当性》 例題7 統計的仮説検定《統計的仮説検定 第1種・第2種の誤り》 例題8 平均値の差の検定《 t検定 分散分析》 例題9 要因計画法《要因計画法 2要因分散分析》 例題10 因子分析《因子分析 因子軸の回転》 例題11 回帰分析《回帰分析 重回帰分析》 例題12 カイ2乗検定《カイ2乗検定 自由度》 例題13 さまざまな統計用語《点推定と区間推定 中心極限定理 さまざまな統計効果》 例題14 効果研究《ランダム化比較試験 倫理的配慮》 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0
-
-高齢者の特性から、疾患別薬物療法と支援のポイント、在宅医療、栄養サポート、嚥下障害、サルコペニア予防など、高齢者を取り巻くさまざまな視点を実例を盛り込みながら、紹介。多職種連携の視点を軸に、よりよい服薬支援のあり方が学べる一冊。薬学生・薬剤師のほか、高齢者医療に取り組む医療職・介護職向け。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-「冬の時代」を告げる凩(こがらし)が吹きすさぶ。大逆事件が迫る。――日露戦争後の明治41年、東京赤坂の陸軍歩兵第一連隊から兵卒37名が脱営した事件を軸に、軍国化の足を速めた大日本帝国と苦難の時を迎える社会主義運動の姿を、豊富な資料をもとに再構成する。史伝体と物語体の巧みな併用によって今日によみがえらせた歴史長編。1985年、第12回大仏次郎賞受賞作。
-
4.0100以上のブランドで5,000件以上の顧客体験を分析してきた著者が、顧客体験を軸にしたマーケティングの実践方法を体系的に解説した初の書籍。商品やサービスなどのブランドが顧客に価値として受け入れられるプロセスを「アクセプターモデル」として抽出。この原理原則に基づきながら、顧客の語りを「ナラティブ分析」で掘り下げ、データ化することで、ブランドが次に打つべき企画や施策のアイデアがデータドリブンな形で導き出せる。本書で仕組み化された方法を実践すれば、“天才”でなくても「売れる商品」を作れるようになる。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■国語力は一生必要な力、国語は全ての学問のベース! 国語力は一生にわたって必要な力です。「書く・読む・話す・聴く」という4つの力が国語力の軸であり、社会人に なってもコミュニケーション力と名前を変え、ついて回ります。つまり、国語力は人生において無視することが できない「力」なのです。 また、国語は全ての学問の土台となる教科です。何かを考える時は語彙力や論理的思考力が必要です。 人と会話する時にも相手の気持ちを察したり、わかりやすく伝えたりする力が要ります。実は、これらすべてが 国語力です。 人生の舵を取り、人と心を通わせて生きる為に国語力は不可欠なのです。 ■継続してはじめて実が成る力(教科)です 国語力を身に付けるには時間がかかります。だからこそ、子どものうちからコツコツと学び続ける必要が あるのです。そのため国語という教科は、まさに「継続は力なり」を地で行く教科とも言えるでしょう。 世の中には多くのテクニック本や攻略本がありますが、国語には「こう解けば必ず力が上がる」とか、「短期間で 国語力がアップする」という法則は存在しません。書く力・読む力・話す力・聴く力において、どれが今の自分に 不足しているのかを分析し、地道な努力で少しずつ伸ばしていくという、当たり前に感じる「学習を継続する」 ことが最も確実であり、付け焼き刃ではない「一生ものの国語力」を獲得するための最短ルートです。 ■本書は特に こんな方におすすめです ・お子さんの国語力にお悩みのお母さま、お父さま ・国語という教科を基本から学び直したい方 ・社会人になっても使える国語力を身に付けたいと考えている中高校生 ・コミュニケーション力に自信のない方 ■こんな方には向きません ・すぐに結果を求める方 ・テストの点数を上げることを主目的としている方※ ・受験合格がゴールだというお考えの方 ※本書は参考書や問題集ではありません ■特に効果があった学習方法の中から… 国語とはどのような教科で、何のために学ぶのか。 「書く・読む・話す・聴く」力を伸ばしていく具体的な方法とは ―札幌で「国語専門塾みがく」を主宰している筆者が、ご家庭ですぐに取り組める国語の学習法をお教えします。 30年を超える国語指導を通して、実際に生徒の力が目に見えて上がったアプローチ法を取り上げ、 教え子のエピソードやコラム、「国語専門塾みがく」でのユニークな取り組みを交えてご紹介します。 (※本書は2021/3/19に日本橋出版より発売された書籍を電子化したものです)
-
-スイフト・タットル彗星の発見、臨死体験、太古の水や炭素化炉などで知られる木内鶴彦氏と明治天皇の孫、国際問題評論家として知られる中丸薫氏との異色のコラボ。 木内氏が開発したテクノロジー「太陽光集光式発電システム」「太陽光利用炭素化装置」を軸に アセンションに向けた個々人の生き方と5次元社会のあり方を宇宙的規模で語って行く必見の書!3度の臨死体験で最良の未来と最悪の未来を目撃し、最良の未来を選択させるために過去時間に行って、出口王仁三郎や日月神示の岡本天明に光の世のヴィジョンを吹き込んでおいたという木内氏の超告白は衝撃的! エネルギーも食も農もこうして自立しよう これがミロク世の完成系ヴィジョンだ 「太陽光集光式発電システム」→原発も火力発電所も要らない 「太陽光利用炭素化装置」→ゴミ消滅・5年もつミニ電池を全家電製品に組み込み!家庭から奥様方からエネルギー革命 送電線もコードもコンセントも必要なし 地域色豊かな自立自営型農業共同体が国を超えて結び合う 《ミロク世の雛型》をここに提出します! これでお金の要らない《生態系還元型社会》が実現します! 木内: 集光レンズによる太陽光発電は同じ面積での換算値ではソーラーパネルの発電量の2乗に正比例します。同じ面積でメガソーラー(大規模太陽光発電所)の40倍。原発一基分より発電量が多いんです! 中丸: そんなすばらしいものをやらせてもらえないなんて!それが闇の世界権力によって作られたれたエゴの利権構造そのものなのよ!カネを神様にしてしまった人たちはこれから大変なことになります!太陽=アマテラスの力で光の世にグレンとひっくり返しましょう! 木内: 5年間もつボタン電池、これも太陽光集光レンズによるシステムで作れるんです。これをすべての家電製品に組み込んで行く!まさにコードレス社会の実現です!奥様方からエネルギー革命を始めてもらう! 中丸: 石油も燃料として燃やすのが20%、あとの80%は石油製品で地球はまさにゴミの山。あなたのやり方ならこの石油製品もまた石油に戻せるのよね!光の世を実体化させる具体的な方策がみえて来たわね。
-
-2軸貨車が大活躍し、一方でコンテナ化や操車場の合理化が進められていた昭和40年代。国鉄の貨物列車は種々雑多な貨車をつなぎ、小さな駅にもあった貨物ホームで解結していた。戦後の近代化の歴史と成績から、国鉄貨物の位置づけをわかりやすく解説する。 第1章 現代の鉄道貨物と国鉄貨物はここが違う あらゆるものを運んだ国鉄貨物輸送/特別急行貨物列車/急行貨物列車/地域間急行貨物列車/専用貨物列車/輸送力列車・解結貨物列車 第2章 国鉄貨物輸送の大黒柱 貨車集結輸送方式と操車場 到着時間が読めない/膨大な手間をかけて仕訳する操車場/780kmに60時間以上/操車場の近代化/地域間急行貨物列車 第3章 鉄道貨物の救世主 コンテナ輸送の歴史 コンテナ特急「たから」/救世主・フレートライナー/東海道ライナー/新規顧客の開拓に苦しむ/私有コンテナ専用ライナー/引越しとコンテナ 第4章 「公共性」の名の下に似たような制度が混在 小口扱貨物と小口混載貨物 鉄道輸送が苦手としながらも「大切な仕事」小口扱貨物/民間企業の積卸技術をいかした小口混載貨物/トラック業界が猛反対 中心駅集約輸送/新混載制度/公共性の建前で「国鉄直営」の看板だけ残される 第5章 運ぶモノの特性に合わせた輸送体勢を目指した物資別適合輸送 輸送力から輸送品質への転換/石油/セメント/化学薬品/飼料/紙製品/自動車/鉄鋼 第6章 国鉄貨物のスター的存在 鮮魚特急列車 時速10kmで所要時間を丸1日短縮/地元水産業界の猛反発にあった計画/長くは続かなかったピーク 第7章 国鉄貨物輸送と切っても切り離せない「通運」 鉄道貨物輸送の両端を担う通運事業者/許可営業制導入/独占が解かれた戦後の通運業/ライバルに変化する国鉄と通運 第8章 複雑怪奇な?国鉄貨物運賃の仕組み 最短経路で計算/生活物資は安く、贅沢品は高く/貨物等級制度/複雑な「指数」で算出した小口混載貨物/画期的だったコンテナ貨物の運賃 第9章 国鉄のもう一つの物品輸送サービス 手荷物と小荷物 全国の駅から個人が大きな荷物を発送できた/重複するサービスを整理 荷貨一元化/鉄道宅配便/鉄道郵便輸送 第10章 1790年 国鉄貨物輸送で活躍していた主な車両 終章 その後の国鉄貨物とJR貨物への移行
-
3.6戦後日本が高度成長期にあった15年間、成績はパッとしなかったが、独特の存在感でファンを魅了した球団があった。その名は、400勝投手・金田正一を擁した「国鉄スワローズ」。本書は、エース金田正一を含む国鉄スワローズ15年間の歴史を軸に、日本プロ野球創成期、隆盛期のエピソードを、新たな取材成果とともに振り返る。巻末には、歴代監督、全登録選手、15年間の全スコアを掲載。 堤 哲(つつみ さとし) 東京生まれ。早稲田大学政経学部卒。1964年毎日新聞社入社。編集委員、紙面審査委員長。社会部時代、都市対抗・選抜高校野球取材のキャップ。毎日新聞の草野球チーム「大東京竹橋野球団」名目オーナーで、正三塁手。東日印刷(株)監査役。野球文化學會会員。交通ペンクラブ事務局長。(財)日本ナショナルトラスト、(財)アジア刑政財団各評議員。「アジア刑政通信」編集長。 ※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。
-
-法律・兵器・政治……その過去から現在へ 軍隊のない独立国は、日本も含めて数ヵ国にすぎません。ところが日本の防衛予算は英・独・仏をもしのぎ、しかも1990年の湾岸戦争、1999年の周辺事態法、そして2004年の自衛隊のイラク派遣を経て、その矛盾は劇的に深化しました。にもかかわらず、防衛論争は日米安保と憲法9条の範囲にとどまっています。 本書では、法律・兵器・政治を軸に、憲法制定から近年の調達疑惑まで、日本の国防問題の全貌を解き明かします。 第1章 軍隊を持たない国 終戦とは、いつのことか 「憲法より米だ!」 憲法は「押しつけられた」のか 第九条をめぐって 第2章 「警察力」とバズーカ砲 東西冷戦 二つの中国 二つの朝鮮 朝鮮戦争への道 警察予備隊 第3章 安保体制と自衛隊 朝鮮戦争後の世界 安保条約 保安隊とはなにか 保守政治家と自衛隊 安保闘争と自衛隊 第4章 三島由紀夫はなぜ死んだか 「違憲の軍隊」 治安出動はあり得たか 「脅威」の変遷 右翼と三島 警察官僚の時代 第5章 戦後レジームとはなにか 赤城構想と三矢研究 自民党政治と自衛隊 憲法と自衛隊と裁判所 護憲派の迷走 第6章 揺らぐ「平和国家」 知られざる改憲勢力 冷戦終結への道のり 日米同盟の危機 イスラム原理主義 サダム・フセインの戦争 作られた「湾岸トラウマ」 第7章 国防の、泣ける真実 自作自演の話 戦車の話 クルマの話 兵器輸出の話 福祉と「脅威」と震災の話 ●林 信吾(はやし・しんご) 1958年、東京生まれ。神奈川大学中退。1983年より10年間、英国に滞在。この間、ジャーナリストとして活動する傍ら、『地球の歩き方・ロンドン編』の企画と執筆に参加。帰国後はフリーで執筆活動に専念している。『青山栄次郎伝 EUの礎を築いた男』(角川書店)、『超入門資本論 マルクスという生き方』(新人物往来社文庫)、『反戦軍事学』(朝日新書)、『イギリス型〈豊かさ〉の真実』(講談社現代新書)など、著書多数。
-
4.0
-
-企業法務はこんなに面白い! ビジネスを前に進める上では欠かせないにもかかわらず、その実態が見えづらい企業法務という仕事。法務パーソンとしてキャリア30年以上の著者が、その仕事の本質と全体像を分かりやすく解説し、その面白さを伝える一冊。 本書の特徴 ○対話をベースにした分かりやすさ 上司と部下の対話を軸に分かりやすく解説。著者の長年の経験に基いた現場のリアリティを追体験できる。 ○現場で求められる「マインドセット」に着目 法律の知識や英語力などだけでなく、企業法務という仕事に特有の「マインドセット」があることを提示。 目次 第1章 企業法務の実像 第2章 イシューを発見する 第3章 危険を察知する 第4章 着地点を探す 第5章 「視える化」する 第6章 視野を広げる 第7章 企業法務の未来を描く
-
-本書の内容は、 ファスティング(断食)のプロフェッショナルである、 日本ファスティングコンシェルジュ協会会長・代表講師である中嶌歩見が 「体のデトックス」と「心のデトックス」を軸に、 ・37歳にはみえない若さの秘密 ・美と健康のためにとりいれているファスティングについて ・体のメッセージを見逃さないポイント ・本当にやりたいことを見つける方法 ・どんどんやりたいことを実現させるために大切にしていること ・20代から今までの仕事や、対人関係で大切にしてきたこと ・どうやってピンチをチャンスに変えてきたか などなど自身のエピソードをふまえながら、まとめたものです。 ・夢がある人 ・もっと自分らしくありたい人 ・人生が思うように進まない ・対人関係に悩んでいる ・起業を考えている ・デトックスに興味がある ・今の自分をもっと好きになりたい ・肩の力をゆるめて楽に生きたい そんな人には必須の、夢も美貌もあきらめないデトックス的思考をぜひご一読下さい。 この電子書籍は2014年10月24日(金)にサンクチュアリ出版1階にて行われたトークイベント 『ココロとカラダのデトックス~手放すことでチャンスをつかむ!夢もキレイも叶える20の魔法~』 を電子書籍用に再構成したものです。
-
-VUCAと呼ばれる不確実な毎日の中で、世界や日本社会の将来、地球環境や持続可能性といったメタな問題から、身近な仕事・キャリア・人間関係・家族の問題まで、私たちはさまざまな問題・悩みを抱え、ストレスにさらされ続けている。 そんな日々の中で、クリアな思考をして、建設的に悩み・問題と向き合い続けることは、決して簡単なことではない。 「正直なところ、毎日が忙しくて悩む時間すらとれない」 「モヤモヤすることはあるけれど、悩んでいたら日々の仕事が終わらない」 「仕事・人生をもっと充実させたいし、このままじゃまずいのはわかっているけれど、今は将来のことを考える気力・エネルギーが残っていない」 そんな本音を抱えながら、何とか日々の生活をやり過ごしているという方は少なくはないのが現実ではないだろうか。 そんな、“ちょっとお疲れ気味”の現代のビジネスパーソンに提案したいのが、1日5分でできる“書く瞑想(ジャーナリング)”である。 書く瞑想(ジャーナリング)とは、マインドフルネスの手法の一つで、設定された「問い」について、手で文章を書いていくというシンプルなものだ。ただ、そのシンプルさにも関わらず、 ・免疫力の向上、睡眠の改善 ・不安の減少、ストレス耐性の向上 ・集中力の向上、パフォーマンスの向上 といったマインドフルネス瞑想同様の成果が報告されている。 本書では、特に仕事に直結するマインドフルネスの効果でもある「セルフ・コンパッション(自他への共感、労りの心)の醸成」と「セルフ・アウェアネス(気づきの力)の向上」を軸にしながら、“書く瞑想”のコツ・解説を行なっていく。さらに、“書く瞑想”の具体的な「問い」としては、30代以上のビジネスパーソンが日々抱える悩み(キャリア、人生の方向性、人間関係)を解消するためのものを提供する。 「書く瞑想は、人生を変えるほどの大きな力をもたらす」と著者たちは話すが、そんなパワフルな「書く」「振り返る」という「書く瞑想」の習慣を、1日5分、8週間をとおして身につけることを目指していく。 【目次】 Prologue 1日5分の“書くマインドフルネス”を始めよう Part1 セルフ・コンパッションで自信・エネルギーを取り戻す Part2 セルフ・アウェアネスを高める ~キャリア・仕事編~ Part3 セルフ・アウェアネスを高める ~ワーク・ライフ・バランス編~ Part4 セルフ・アウェアネスを高める ~人間関係・つながり編~
-
2.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 現場のプロが教える! キャラを軸にした映える背景や構図 背景画がうまく描けない人、キャラクターは描けるけどそれに合う背景をどう描けば良いか分からない人。そんな人たちに向けて、具体例を出して背景イラストの描き方を解説した本です。 まずは、基本的なテクニックや考え方を「5つのポイント」で学びます。 次に背景の作例を見ながらどの部分をどう直せば良くなるか、添削を交えて解説。修正前と修正後を並べて見ながらポイントを解説するのでとてもわかりやすいです。 3つめに「完成したキャラクターイラスト」に合った背景をどのように描いていくかを手順を追って説明します。 最後はゲーム開発のワークフローに沿って、実際の仕事現場の注意点を見せていきます。
-
3.9【内容紹介】 「個」の力が活躍の鍵! ニューノーマルを生き抜く働き方 世界中にインパクトを与えた新型コロナウイルス(covid-19)。私たちの目の前の「働き方」が大きく姿を変え、企業もその大小を問わず大打撃を受けている。 在宅勤務・リモートワークが主流となる社会では、これまで以上に「成果」が評価軸となり、「個」としての力量が問われていくことは間違いないだろう。 そんな世の中で充実して働くため、また活躍するために大切なのは、「どんな自分でありたいか」、その信念を軸にして行動することである。 もっと“自己中”に、もっと“わがまま”に――。新しい時代の「働く力」を描き出す。 【著者紹介】 [著]澤 円(さわ・まどか) 株式会社圓窓代表取締役。1969年生まれ、千葉県出身。 立教大学経済学部卒業後、生命保険会社のIT子会社を経て、1997年にマイクロソフト(現・日本マイクロソフト)に入社。 情報共有系コンサルタント、プリセールスSE、競合対策専門営業チームマネージャー、クラウドプラットフォーム営業本部長などを歴任し、2011年、マイクロソフトテクノロジーセンター・センター長に就任。 2006年には、世界中のマイクロソフト社員のなかで卓越した社員にのみ授与される、ビル・ゲイツの名を冠した賞を受賞した。 現在は、年間300回近くのプレゼンをこなすスペシャリストとしても知られる。ボイスメディア「Voicy」で配信する「澤円の深夜の福音ラジオ」も人気。 著書には、『外資系エリートのシンプルな伝え方』(KADOKAWA)、『マイクロソフト伝説マネジャーの世界No.1 プレゼン術』(ダイヤモンド社)、伊藤羊一氏との共著『未来を創るプレゼン 最高の「表現力」と「伝え方」』(プレジデント社)などがある。 【目次抜粋】 PROLOGUE 序章 Being 「ありたい自分」はどこに――自らの「本質」を知る―― 第1章 Think あたりまえを疑う――生きることは考えること―― 第2章 Transform 常にアップデートする――あなたはいつだって変わっていける―― 第3章 Collaborate 「個」として協働する――コミュニティー化が世界を救う―― EPILOGUE
-
4.8ベストセラー『オシムの言葉』の著者、木村元彦が描く「旧ユーゴサッカー戦記」シリーズの決定版。旧ユーゴスラビア7つ目の独立国として2008年に誕生したコソボ。1999年のNATOによる空爆以降、コソボで3000人以上の無辜の市民が拉致・殺害され、臓器密売の犠牲者になっていることは、ほとんど知られていない。才能あふれる旧ユーゴのサッカーを視点の軸に、「世界一の親米国家」コソボの民族紛争と殺戮、そして融和への希望を追う。サッカーは、民族の分断をエスカレートさせるのか、民族を融和に導くのか……!?
-
4.5
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「止められるなら恋じゃない」 「思い出を大切にできないやつが 今もこれからも大切にできるわけがない」 「泣いたぶんだけ強くなれるわけじゃない 泣いて頑張ったぶんだけ強くなれる」 Twitterで話題沸騰! センチメンタル研究家が綴った あなたに届けたい大切な言葉。 恋、人間関係、将来…… あなたが言えなかったこと、言って欲しかったこと。 苦しいけれど前を向ける、 切なくもあたたかい言葉たちを ぎゅっと詰めこんで1冊にしました。 【contents】 1 大好きなきみへ 2 大切なきみへ 3 頑張り屋なきみへ 4 忘れられないきみへ 【著者情報】 ハジメファンタジー センチメンタル研究家 好きな人が自分の親友と付き合うという切ない恋愛経験を軸に、イラストやポエム、トークライブ、 恋愛相談など「恋に不器用なひとたちへ」をテーマに多分野で活動。 Twitter @HAJIMEFANTASY
-
5.0英語を初めて学んだ時、文の構造の違いや動詞の活用などに戸惑われた方も多いだろう。しかし世界には、単語を入れ替えさえすれば文意が通じる言語が多数存在する。ウラル・アルタイ語族に属する朝鮮語、トルコ語、フィンランド語、ハンガリー語、モンゴル語などだ。これらの言語は、文の構造ばかりか表現方法、つまりものの感じ方までもが共通している。このことから、言語を軸に連帯をはかろうとする運動、ツラン主義が一九世紀にハンガリーで現れた。それは虐げられた民族からの異議申し立てであり、その水脈は今も生き続けている。
-
3.5
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ ポイントがわかれば楽しく教えられる! ★ 正しいフォームが身につく! ★ パパとママが上手にサポートすれば * 水が好きになる。 * 水泳が楽しくなる。 * 泳げるようになる! ★ 「水に慣れる」「もぐる時間を長くする」 「浮き方のコツ」から 「バタ足」「クロール」「息継ぎのコツ」 「キックの使い分け」まで ◆◇◆ 著者からのコメント ◆◇◆ 私は親に水泳を習いました。 両親に、代わる代わる教わったのです。 思い出せば、子どものころの水泳の授業では、 得意げになって泳いでいました。 親子で水泳大会に出たこともあり、 水泳を通じて親とのコミュニケーションが深くとれたとも思っています。 そして昔は親から教えられていたのに、 いつのまにか私が教えるようになっていました。 そんな私ですから、本書を監修することになり、 子ども時代の自分の経験と、 インストラクターとしての現在の経験を、 あますことなく伝えたいと思いました。 この本には大きな特徴がいくつかあります。 そのひとつが、家で行う水に慣れるための遊びの部分に、 ページを割いていることです。 子どもにとって、最初の経験は大切です。 水が嫌いになってしまったら、水泳はできません。 ですから、水が好きになって、 水泳が上達し、最後には 「うまく泳げる」というプログラミングになっています。 子ども対象でも、ビート板を使った練習を していないことも特徴です。 ビート板は水中での推進力を身に付けるのに 役立ちますが、顔を前に上げて息継ぎをするという、 クロールの初心者には身につけてほしくない 息継ぎの癖がつきやすいからです。 この本は小学校に入る前から、 小学校低学年までを対象にしています。 年齢幅があるので、一概に上達までの期間を 記すことはできません。年齢やお子さんの気質に合わせて、 ひとつひとつ楽しくクリアしていただきたいと思います。 水泳インストラクター 長谷 優 ◆◇◆ 本書について ◆◇◆ 「25 メートル泳げるようにさせたい」 「水泳の教え方がわからない」 子どもの水泳は初めが肝心。 水は怖くない、泳ぐのは楽しい、 と思えると子どもはぐんぐん上達できます。 パパとママと一緒に楽しく、どんどん泳げる 練習を3 つの『ツボ』で紹介します。 本書は基本は最初から読み進め、 個人のレベルによって途中から読んでもかまいません。 各テクニックが見開き完結となっており、 みなさんの知りたい習得したい項目を選んで、 読み進めることができます。 各テクニックは、それぞれ 重要な3つの『ツボ』で構成され、習得のポイントを 分かりやすく解説しています。 コツが分かるから覚えやすい。 覚えやすいから身につきやすい。 ぜひスーパーテクニック習得に役立ててください。 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆ PART1 お家でできる準備と練習 プールでいきなり練習を始める前にまずは お家で水に慣れておこう。 基本姿勢と手足の動きを身につけ、 イメージトレーニング。 * コツNo.01 水の抵抗を受けにくい軸の作り方を覚える * コツNo.02 お風呂で遊びながら呼吸を止めたり目を開けたりする。 ・・・など全6項目 ☆ PART2 遊びながら水に慣れる お家での練習が終わると、いよいよプールデビュー。 水に入る準備をしたら、まずはパパ、 ママと遊びながら徐々に水に慣れていこう。 * コツNo.07 水着、ゴーグル、キャップの選び方と3原則 * コツNo.08 練習の効率をアップ、ストレッチでケガ予防 ・・・など全14項目 ☆ PART3 クロールの体の使い方と呼吸 バタ足と腕の回転、息継ぎを練習する。 ここでフォームと軸を整えて クロールの基礎となる体の動きを覚えよう。 * コツNo.21 壁を使ったスタートの方法を練習する * コツNo.22 足全体でしなるように水を蹴る水中バタ足 ・・・など全11項目 ☆ PART4 かっこいいクロールをマスターする 基礎を覚えたら、 次は25メートル泳ぐための準備をする。 スタートのしかたや回転キック、 呼吸クロールでより、実践的な練習をやっていこう。 * コツNo.32 手を滑らせて前に進み体を伸ばしてより推進力をアップ * コツNo.33 腕の回転と体の伸びのタイミングを覚える ・・・など全10項目 ☆ PART5 クロールで25 メートル泳ぐ ターンやストロークの練習をして総仕上げに入る。 楽に25メートル泳ぐコツを踏まえて25メートルに挑戦する。 泳いだ後のケアも忘れずにやっておこう。 * コツNo.42 シンプルターンで長い距離にチャレンジ * コツNo.43 水をとらえ水の層に乗る柔らかな腕づかいをする ・・・など全9項目 ☆ コラム * コミュニケーションは笑顔が一番 * 学ぶときの特徴「なんで…」「どうして…」 * 小さいときから水泳をする利点 * パパ、ママがプールで気をつけること ※ 本書は2014年発行の 『これで25メートル泳げる!子どもに水泳を教える本』 を元に加筆・修正を行った新版です。
-
-現在、小学校の社会科では6年生で日本史を勉強します。ただ、歴史は多くの言葉が出てくるうえに、1年で歴史の流れを身につけることはむずかしいといえます。そこで小学校3年生くらいから読めて、1冊で歴史の「時間軸」を身につけることができるような本をつくりました。中学受験の準備のためにも、親がこどもいっしょにまなびなおすのにも最適な1冊となっています。イラストで理解しやすい「ざっくり年表」付!
-
4.0★ワールドカップ予選で日本を救う大活躍! "イナズマ純也"の速さの秘密! ! 現役サッカー日本代表の 快速ウイングが明かす 走るのが速くなるすごい方法! 著者は、身体能力の高い外国人選手すら 置き去りにする圧倒的なスピードで、 日本代表まで駆け上がった スピードスター、伊東純也選手。 これまでサッカー一筋だった伊東選手が、 あるお子さんの悩みを解決したことが この本のはじまりでした。 伊東選手が解決した悩み。 それは「子どもの足を速くした」ことでした。 【サッカー選手が提案する 足を速くする方法とは】 伊東選手はアドバイスをおくるために 自分の走り方を映像でチェックしました。 気づいたのは、 「ももをしっかり上げる」 「ひじを90度に曲げてふる」 昔からよくアドバイスされる 走り方の基本を守っていないのに、 速く走れていることでした。 しかもアスリートなのにからだがかたく、 思い返してみても、速く走るための練習なんて したこともありません。 そこで伊東選手は、ある考えにたどりつきます。 「走り方の勉強や練習をせずに 速くなった理由をメソッド化できたら、 もっと簡単に、どんな子でも速くなれるのではないか」 それが、子どもの足をどんどん速くする 「スピードスターメソッド」です。 【スピードスターメソッドは効果抜群】 スピードスターメソッドは、 どんな子でもできる 最強のトレーニングです。 ●運動神経が悪くても速くなる ●親の足が遅くても速くなる ●難しいフォーム練習は一切なし ●練習場所が狭くても速くなる ●成長をさまたげる筋肉はつかない ●からだの軸が安定して姿勢がよくなる ●仲間のために頑張る力が身につく ●習い事が多くて時間がない子でもできる 【体験者から驚きの結果続々! 】 実際に「スピードスターメソッド」の効果を 50メートル走で計測した体験者から 驚きの結果と声が届いています。 11.38秒 ← 12.75秒 「走るのが楽しくなった! 」(6歳男子) 6.86秒 ← 7.17秒 「手のにぎりでこんなに変わるなんて」(40歳男性) 8.94秒 ← 9.49秒 「運動会が楽しみになったのは初めて」(13歳女子) 【しかも何歳からでも速くなる】 「スピードスターメソッド」は、 簡単かつ短時間でできて、 しかもからだにかかる負担が少ないので、 運動不足の大人にも効果があります。 さらにトレーニングはふたりでやることで、 効果が上がります。 ぜひ休日、家族で楽しくトレーニングして 運動会で親子そろって活躍してください!
-
-
-
4.7スマホとゲームで眼球の形が変わる―― 調査を行った小学校6年生の約8割が近視――。スマホやタブレットの使用、ゲームのやり過ぎが、子どもたちの目を脅かしている。眼球が伸びて、形が変わってしまう「軸性近視」が、将来の白内障や緑内障のリスクを高めるほか、最新の研究によってうつ病などにもつながりうることがわかってきたのだ。科学的根拠のある治療法から、生活習慣の見直し、眼鏡・コンタクトレンズの正しい選び方まで。世界水準の防衛策を詳しく紹介した、大反響のNHKスペシャルを書籍化!
-
4.0「なんで塾に行かないの!」 「勉強しなさい!」 「ゲームばっかりして……」 親なら、一度はそうした言葉を子どもに投げかけた経験がある方も多いかもしれない。 けれど、子どもは本当に勉強していないのか。なぜ塾に行かなければいけないのか。 そもそも親自身が「~しなければならない」という考えに縛られているのではないだろうか。 時代が変われば、子どもに必要な能力も変わる。 社会が変われば、子どもの思考も変わる。 世界が身近になれば、子どもの視野も変わる。 本書は、そうした社会変化を鑑みながら、世界と日本を比較し、「~しなければならない」といったマインドブロック(思い込み)をはずし、 子どもも親も一緒に成長できる秘訣を紹介する一冊。 著者は、世界を飛び回り、現在はディリーゴ英語教室の代表を務める廣津留真理氏。 周りに振り回されない独自の子育て・家庭学習法で娘の廣津留すみれ氏はハーバード大学主席で卒業、ジュリアード音楽院を経て現在はバイオリニストとして活動。 自身も娘の大学進学を機に起業し、現在の英語塾を運営している。 そんな廣津留真理氏が、かつての経験を軸に、また現在サマースクールなどで接するハーバード生や若者などとの交流から得た知見を活かして、 これからの親が身につけるべき考え方を紹介する。 今は父親も母親も、働きながら子どもを育てなければならない、大変な時代かもしれない。 けれど、そんなときだからこそ、何かをあきらめるのではなく、子どもも自分も家族みんなで「自分らしい生き方」をすることが大切。 すぐには無理かもしれないけれど、本書を読めば、きっと幸せな未来に変わるに違いない。
-
-「国家」とは何か。富の集約と分配とは……。世界史の原理がわかれば、すべてがつながる! ブッダ、楊貴妃、ナポレオン……。世界史の本質が詰まった20名の偉人を、四谷学院、スタディサプリの人気講師が徹底解説。世界史で人物の説明を読んでも、まったく理解できないのはなぜだろうか? 参考書の文章が理解できないのか、文章は読めるけど頭に入ってこないのか。世界史の偉人たちは、時代も違えば場所も違う、異なるものが2つもかけ合わさったいわば“異質ハイブリッド”の人々。“いつ”と“どこ”がイメージできないから、人物の解説文に書いてあることはわかっても、納得のいかないうわの空な感じになってしまう。ブッダについて話すときには、前500年前後のインドの状況を知っておかないと彼の活動は理解できないし、ナポレオンを語るときには、フランス革命の流れ、そして彼がどんな影響を後世に及ぼしたかを把握しておく必要がある。本書では世界史のタテ(時間軸)とヨコ(空間軸)を丁寧に紐解いて、偉人たちに迫る。タテとヨコの土台をつくっておくと、彼らの生涯が自然と頭に入ってくる。本書では4つの時期、古代、中世、近世、近現代に分けて代表的な人物を解説する。一人ひとりが独立しているので、誰から読んでも大丈夫。本文は先生(鳩先生)と生徒(羊くん/イルカさん)の対話形式。堅苦しい内容がつづくと飽きてしまうことがあるため、また疑問が生じたときには生徒にみなさんを代弁して「それってどういうことですか?」と聞いてもらうためだ。軽妙にかけあいながらも、真面目に話を進める彼らの会話を通じて偉人の一生を楽しく学ぼう。
-
-岡山県苫田郡奥津町。 この地を守るためにとられた法的手段は悉く紙くずのように破棄されました。 唯一無二の闘う手段は「守りぬこう」とする力でした。 勝利を叫ぶ無情さ、敗北を語る優しさ。 この『琥珀』は、1992年当時にダム反対を闘い続けようとした阻止住民の聞き取りから始まります。 ダムサイト付近からダム北端へ、水没地内吉井川下から川上へ歩き進み、『琥珀』全体を読み進むうちに、現在・『今』へと向かいます。 時間軸の流れに合わせて『琥珀』という小宇宙を描き出してくれることを願っています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 私たちのまわりの機械その他の運動は,大部分の運動が回転運動です。コマの運動がわかると,多くの機械やオモチャの動く原理もわかってきます。これまでに書かれた「コマの原理」の話は,とても難しく,たいていの人がついていけないものばかりでした。でも,この本なら大丈夫。いろんな形や重さのコマを作って,実験しながらその原理を探っていきます。 サイエンスシアターシリーズって? 「芸術やスポーツを楽しむように科学を楽しもう!」と1994年から1999年,東京・早稲田大学の国際ホールを会場に行われ,大好評だった「サイエンスシアター」。その公演内容が本になりました。 ★★ もくじ ★★ 第1幕 回転力=トルクと重心 実用的な運動はたいてい回転運動/回転と力/バットの回しっこ/トルクという言葉/ニンジンを重心で切る/ドアの押しっこ 第2幕 コマで遊ぼう いろいろなコマで遊ぼう/〈ひねりゴマ〉と〈もみゴマ〉/ヒモで回すゴマ/〈ヒモ巻きゴマ〉=〈投げゴマ〉/ベイゴマの遊びかた/バネ仕掛けで回すコマ/ゼンマイ仕掛けで動くオモチャの自動車/二段ゴマと逆立ちゴマ,地球ゴマ/バネもない,心棒もないコマ/おもしろい仕掛けのついたコマ/日本人は世界一コマ好き? 第3幕 コマを作る-コマと重心 かわいい(ドングリのコマ)の性能は?/タテ長のコマと平べったいコマ/円板の高さの問題/回転する軸の位置の問題/コマの軸を重心に合わせる/円形でないコマ/不思議なボール=(へんしんボール)/回転する機械のガタつきの原因/自動車のタイヤもバランスが大切 第4幕 コマの慣性-はずみ車の科学 コマの重さと位置/よく飛ぶ紙トンボのくふう 塩野式・新型紙トンボの作り方/オモチャのオートバイの動く仕組み/〈はずみ車〉の役目/水の入ったバケツを垂直に回転させる実験/ホースから飛び出た水流は頭の真上に来ても,そのまま通りすぎる/コマはなかなか倒れない/自転車はなぜ倒れないか 力学に関する発明発見とその教育の歴史年表 〈力積〉概念の発見と運動の力学の教育改革……あとがきにかえて
-
4.0「仕方がない」から「仕方がある」へ。 ハーバード発、「社会の変え方」実践ガイド。 おかしな制度や慣習、困ったことや心配ごと…… 社会の課題に気づいたとき、私たちに何ができるだろう? 普通の人々のパワーを集めて政治・地域・組織を変える方法 「コミュニティ・オーガナイジング」をストーリーで解説。 コミュニティ・オーガナイジングとは、「仲間を集め、その輪を広げ、多くの人々が共に行動することで社会変化を起こすこと」。 ・戦略的で効果的なアクション……なんとなくデモや署名をするのとは異なり、変化につながる効果的なポイントを見つけ、戦略的に行動する。 ・ごく普通の人たちでもできる……人のつながりを徐々に広げていくことで、大きなパワーを生み出す(スノーフレーク・リーダーシップ)。 ・理論的・体系的に学べる……ハーバード大学のガンツ博士が理論化した実践的手法。バラク・オバマの大統領選キャンペーンでも活用された。 ・身近な問題から法改正まで……地域の行事、PTA、組織改革、NPOの活動、法改正など、幅広く役立つ「ほしい未来をみんなで創る」方法。 理論と実践をわかりやすく伝える ・PART I:小学生カナメたちのストーリー……ある日、昼休みがなくなった! 新たな教頭先生が始めた取り組みに違和感を覚えた5年生のカナメと仲間たち。NPOで働くユキさんのアドバイスを得ながら、みんなで力を合わせて昼休みを取り戻す活動に乗り出した――。架空のストーリーを軸に、コミュニティ・オーガナイジングの5つのステップをわかりやすく解説。 ・PART II:さまざまな実践事例……「おやじの会」や産後ケア施設の立ち上げ、若者による成人式の運営改革、著者も関わった刑法改正キャンペーン、難民支援の「6分間読書」キャンペーン等、幅広い分野における実践事例を紹介。 〈構成〉 序章「仕方がない」から「仕方がある」へ (PART I METHOD 変革の起こし方) 第1章 コミュニティ・オーガナイジングとは何か 第2章 パブリックナラティブ――ストーリーを語り、勇気を育む 第3章 関係構築――価値観でつながる 第4章 チーム構築――三つの成果、三つの条件、三つの決めごと 第5章 戦略作り――みんなの資源をパワーに変える 第6章 アクション――リーダーシップを育てる (PART II CASE 実践!コミュニティ・オーガナイジング) 第7章 人々の力を引き出す 第8章 身近なことから変化を起こす 第9章 政治を動かし、法を変える
-
3.8コメンテーターでなくても、なにかとコメントする機会が増えている時代です。ビジネスマンにしても、会議や飲み会での会話ばかりか、メールの返信に意見をプラスしたり、フェイスブックで「いいね!」にひと言添えたり、ツイッターでニュースに自分なりのコメントをつけたり、LINEの投稿を気の利いたものにしたり……。“ああ、面倒くさいったらありゃしない”と思っている人も多いのでは? そこで、複眼で物事を考える姿勢をもったうえで、コメントの内容をどう組み立てていくか。「情報は整理しない」「情報はタテ軸とヨコ軸に置いてみる」「すべてはグレーと考える」「情報はストーリーで発信する」「他人と同じことは絶対に言わない」「刺さるコメントよりも、しみ込むコメントを」「ボケる力を磨く」等々、『ニューズウィーク日本版』元編集長がマル秘ノウハウを初公開。“情報がありすぎる社会”を生き抜く必須スキル、「情報力」と「コメント力」が磨ける1冊です。
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 工房やガレージ、菜園小屋など、趣味のための小屋はもちろん、子供部屋、隠れ家、果ては終の棲家まで。 セルフビルドで小屋を建てるための軸組み構法、ツーバイ構法、丸太組み構法を徹底解説! 自分の手でわが家を作りたい方、男の隠れ家的な小屋に憧れる方、DIYファン、手づくりハウスファンのみなさまに贈る小屋作りの為の必読の書。 ※大人気の小屋(趣味の部屋、子供部屋、物置小屋など)から、自宅、別荘クラスの建築実例、そしてその作り方を徹底的にご紹介。 自分だけの小屋を手作りで!自分の手でわが家を!そんなDIY魂をがっちり受け止め応援します。 <内容紹介> ようこそ!セルフビルドの世界へ! 第1章 スモールハウスからはじめよう! 「ツーバイ構法」なら簡単! 3~10日で作る小さな家の5つの実例 第2章 「軸組み構法」でセルフビルドに挑戦! プロの大工も顔負けの技術を簡単にマスターする方法 第3章 10万円で作る12坪のマイ工房 限りなく“安く、速く”つくる「掘っ立てスタイル」のマルチ小屋 第4章 憧れのログハウスを作ってみよう 「ハンドカット」も「マシンカット」も魅力たっぷり! 第5章 100万円で作る憧れの「木の家」 軸組み構法のログハウスを家族と仲間だけで作ってみたぞ! 第6章 仕上げ工事を楽しもう! 天井、壁、床、階段、下屋の仕上げ術 第7章 関連工事マニュアル キッチン、風呂、トイレ、給排水、浄化システム、電気配線、ほか 第8章 家づくりの計画と施工管理術 土地の法律、素人でも描ける設計術、工具と部材の運び方、用語事典、ほか
-
3.3自らは43年連続黒字、 指導企業750社超で5社に1社が過去最高益を実現する、 ランチェスター戦略実践法を初公開! 26社の実践事例大公開! 「ここまで公開してしまうのか! 」と早くも大反響! 古くて新しい科学的な戦略のすべてを解説しました。 ■目次 ●第1章 弱者には弱者の戦い方がある ・ランチェスター戦略の神髄は「一点集中」 ・勝つための第一歩は「捨てる」こと ・狭い範囲に集中させると売上が伸びる ・弱者がとるべきは「差別化戦略」 ・強者になったらミート戦略に切り替える ・強者にのみ許される禁断の戦い方 ・シェアナンバーワンになったら他エリアに進出 など ●第2章 自社が戦うべき「戦場」を決める ・戦力を集中させるのは、成果が出るテリトリー ・商圏を区切り、見える化せよ ・「セグメント」も絞り込む ・「ニーズ」に注目すれば宝の山が見つかる ・攻めるべき顧客は「ABC分析」で丸わかり ・粗利益を見て顧客を入れ替える ・お客様とライバルの情報をどう収集するか など ●第3章 その「武器」でライバルに勝てますか ・高いマットが売れるのは、競合にない「武器」があるから ・社名でも競合に差をつけられる!? ・差別化のヒントになる「手軽」「商品」「密着」軸 ・自社の強みは、お客様が知っている ・客先ではライバルを褒め殺しする ・強者の差別化戦略をパクッて足下の敵を叩く ・現場見学会は、最高の差別化ツール ・値下げは差別化戦略として正しいか? など ●第4章 強い営業組織をつくる ・実行計画表で、営業活動を具体化する ・社員の訪問回数を増やす方法 ・営業力がアップするITツールの使い方 ・営業トークは台本通りに。不自然でも準備したほうが強い ・計画の実行は「対話」で確認する ・営業組織は「見つける」「捕まえる」「逃がさない」に分ける など ●第5章 ランチェスター戦略で「強者」に変身した元「弱者」たち ・ケース1 ライバルが顧客に! 寄せ集めメンバーが「科学的営業」で大きな成果! ・ケース2 究極の穴熊社長が変身! 玉砕続きのスタートにめげず大手から受注するまでに ・ケース3 しゃべりすぎる営業から、聴く営業に。売上以上に粗利益が増えた! ■著者 小山昇 株式会社武蔵野代表取締役社長
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 サイトのマルチデバイス対応に必要なノウハウとテクニックを集成! スマートフォンやタブレットが普及し、PC以外からのWebサイト閲覧が増加しています。さらに、Googleがモバイルデバイスに対応しているかどうかを検索結果のランキング要素にしたこともあり、サイトのマルチデバイス対応は必須となりつつあります。これまではマルチデバイスに対応するための明確な指標がなく、多くのページ制作者が試行錯誤を繰り返してきました。しかし、Googleが1つの指標として利用できる「モバイルガイド」をリリースし、状況は大きく変わろうとしています。 本書はGoogleの「モバイルガイド」と、ページの問題点を簡単にチェックできる2つの判定ツール「モバイルフレンドリーテスト」および「PageSpeed Insights」を軸にして、マルチデバイス対応に必要とされる知識、ノウハウ、テクニックなどを解説していきます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【はじめてでも安心! いちばんやさしいエクセル解説書です。】 Office 2021、 2019、 Microsoft365に対応した初心者向けのエクセル入門書です。 やさしく丁寧な解説で エクセルの基本操作を学習し、章末の練習問題でおさらいをします。練習ファイルと完成ファイルはサポートページからのダウンロードで配布します。この1冊でエクセルの基礎を身につけることができます 。 ■こんな方におすすめ ・時間をかけずにエクセルの基本を学びたい初心者 ■目次 Chapter 1 基本操作を身に付けよう 1-1 エクセルを起動・終了しよう 1-2 エクセルの画面の見方を知ろう 1-3 ワークシートの構成を知ろう 1-4 ブックを保存しよう 1-5 保存したブックを開こう 練習問題 Chapter 2 データを入力・編集しよう この章で学ぶこと 2-1 セルを選択しよう 2-2 データを入力しよう 2-3 データを修正しよう 2-4 データをコピーしよう 2-5 データを移動しよう 2-6 行や列を挿入しよう 2-7 行や列を削除しよう 練習問題 Chapter 3 データを見やすく整えよう この章で学ぶこと 3-1 文字の形と大きさを変えよう 3-2 色付き文字や太字にしよう 3-3 文字をセルの中央に揃えよう 3-4 3 桁区切りのカンマを表示しよう 3-5 日付の表示を変更しよう 3-6 セルの書式をコピーしよう 練習問題 Chapter 4 表の見た目を変えよう この章で学ぶこと 4-1 列幅を調整しよう 4-2 セルを結合して文字を中央に配置しよう 4-3 格子の罫線を引こう 4-4 セルの下側に二重罫線を引こう 4-5 セルに色を付けよう 練習問題 Chapter 5 計算しよう この章で学ぶこと 5-1 計算式を入力しよう 5-2 セル番地を指定して計算しよう 5-3 計算式をコピーしよう 5-4 絶対参照で計算しよう 練習問題 Chapter 6 関数を使おう この章で学ぶこと 6-1 SUM 関数を使って合計を求めよう 6-2 AVERAGE 関数を使って平均を求めよう 6-3 MAX 関数を使って最大値を求めよう 6-4 MIN 関数を使って最小値を求めよう 練習問題 Chapter 7 グラフを作ろう この章で学ぶこと 7-1 表からグラフを作ろう 7-2 グラフの大きさや位置を変えよう 7-3 グラフにタイトルを付けよう 7-4 行と列を入れ替えよう 7-5 グラフの軸に単位を表示しよう 7-6 グラフの配色やスタイルを変えよう 7-7 グラフの種類を変更しよう 練習問題 Chapter 8 表やグラフを印刷しよう この章で学ぶこと 8-1 表やグラフを印刷しよう 8-2 用紙の向きとサイズを変えよう 8-3 1 ページに収めて印刷しよう 8-4 表やグラフを用紙の中央に印刷しよう 8-5 ヘッダー・フッターを設定しよう 8-6 選択した部分だけを印刷しよう 8-7 PDF 形式で保存しよう 練習問題 Chapter 9 データを並び替え・検索しよう この章で学ぶこと 9-1 データを検索しよう 9-2 データを置換しよう 9-3 データを並べ替えよう 9-4 複数の条件でデータを並べ替えよう 9-5 条件に合ったデータを抽出しよう 9-6 データの抽出を解除しよう 練習問題
-
5.0AI・IT・DXを導入すれば、中小企業でも、 人の力を3倍、会社の力を5倍に上げられる! 実際に中小企業の現場に入ってHRテックの有効活用を指導している 人事コンサルタントだから書けた 本当に役立つHRテックの本 HR(HR:ヒューマンリソース=人事)テックとは、 簡単に言えば「人事を支えるITシステム」のこと。 ●AIで面接!? 予算ゼロから使える新システムHRテックを徹底解説 ⇒ 新卒採用の応募が殺到! ⇒ 人事評価システムが短期間で完成! ⇒ 出社不要! スマホで業務が完結! ⇒ 人事・労務の作業が大幅に削減! ⇒ 離職率が改善! 中小企業こそ、人事のIT化を進めることで、大きな効果が得られる。 全国から良い人材が集まる! 優秀な人材の定着・活用ができる! 適切な人事評価ができ、安心して社員に働いてもらえる! (心理的安全性の確保) ■目次 ・第1章 中小企業が一からはじめる簡単HRテック入門 ・第2章 予算なし人手なしの中小企業でも全国から人が集まる! HRテックによる人材の募集・採用システム ・第3章 多忙な人事担当者を強力にサポート! HRテックによる人材の定着・活用システム ・第4章 人事評価制度はHRテック頼みでは危険!? 多くの企業が陥った人事評価×HRテックの落とし穴 ・第5章 無理なく始められる HRテックの段階的な導入・ 運用方法 ■著者 森中謙介(もりなか・けんすけ) 株式会社新経営サービス人事戦略研究所マネージングコンサルタント 「人事制度を軸にした“人・組織の成長”」をモットーにしており、制度導入後も経営理念、 経営方針の浸透、あるいは評価者教育の推進など、幅広い支援を行っている。 著書に、『9割の会社が人事評価制度で失敗する理由』(あさ出版、2019)、 『社内評価の強化書~上司の“評価エラー”を逆手に取る出世の法則~』(三笠書房、2018)、 『社員300 名までの人事評価・賃金制度入門』(中央経済社、2016)などがある。 ■著者 町田耕一(まちだ・こういち) 株式会社新経営サービス人事戦略研究所コンサルタント G検定(AI活用能力)に2019 年3月合格後、E資格(AI作成能力)合格者との 限定コミュニティ(5万名以上)で活動。「NEWS+」グループのリーダー。 2022年に貢献に対する投票等で決まる最優秀賞をグループ・個人とも受賞。 英国王室公認品質協会(CQI|IRCA)から、世界80か国、 2万名以上の会員に発刊された『Quality World』誌2022年秋号のAI特集記事への寄稿にも協力。
-
4.1なんのためかわからない目標をめざして仕事をする。 「これまでこうしてきたから」で話が終わる。机上の空論だけが続く。 完璧を目指すが、成果につながらない。 「最初に立てた目標どおりであったかどうか」で評価が決まる。 マイクロマネジメントをされるほうもするほうも疲弊する。 チームや部署を越えたコミュニケーションに良くなる兆しがない。 仕事のやり方がアップデートされない。 無関心、他責、面従腹背が日常となってしまっている。 これまでのやり方では何かがおかしい。 では、どうすれば変えていけるか? 「数字だけ」から、「こうありたい」へ。 目先の効率から、本質的な問いへ。 アウトプットから、アウトカムへ。 想定どおりから、未知の可能性へ。 マイクロマネジメントから、自律へ。 縄張りから、越境へ。 1人の知識から、みんなの知識へ 思考停止から、行動へ。 変化の最前線で試行錯誤してきた著者が20年の時を重ねてたどりついた、“新しい正解”の見つけ方をあなたに。 ■目次 第1章 「数字だけ」から、「こうありたい」へ ●From 目標が次の何かに活きているか? 「数字しかない」目標になっていないか? 目標の前提に目的はあるか? 本当に目標を達成できているのか?達成したことにしていないか? 目標を予定どおり達成できることに価値があるのか? 考えてもわからないのか?考えていないためにわからないのか? ●To 自分たちの「芯」がどこにあるのか、目の前のことはいったん脇に置いて考えよう ゴールデン・サークルを用いて自分の意図を自分に気づかせよう ●From→To FromとToを別々に描こう 目標までに段階をつくって1つ1つ乗り越えていこう 第2章 目先の効率から、本質的な問いへ ●From 机上の議論が容赦なく延々と続く 表層的な理解だけ合わせて、本質的な問いが置き去りにされる 「これまでこうしてきたから」問題(圧倒的な問いの不足) 「効率性ファーストのメンタリティ」問題(正解を出さないといけない) 「失敗が次に活かされない」問題(失敗の本質は同質の失敗を繰り返すこと) ●To 問いを立てるのと同時に、その問いに答えるための「プロセス」を取り入れよう (1)問いを立てる (2)問いに答えるための仮説を立てる (3)仮説を検証するためのプランを立てる (4)検証を実施する (5)結果を確認し、理解を得る ●From→To 個別の活動に焦点を当てつつ、全体として成り立っているかに目を向けよう 全体のプランを時間軸を伴う形で可視化しよう 第3章 想定どおりから、未知の可能性へ ●From 評価の基準は「最初に立てた目標どおりであったかどうか」 「正解」からズレないことを基準に置いてきた組織が周囲からズレてしまっている ●To 「適応の時間」を明確に取るようにしよう ふりかえりをしよう むきなおりをしよう 領域を越境していこう ●From→To 探索と適応のバックログを作ろう 第4章 アウトプットから、アウトカムへ ●From 「品質が王様」という価値観 品質を高めるために、何度も幅広く検査する アウトプット自体が決められなければ3つのムダが生じる可能性がある 問うべきは「アウトカム(成果)が得られるかどうか」 ●To 早く試せるよう、価値があると思われる部分を真っ先に実現しよう 理解を正すまでの時間を短くしよう ●From→To 目的が完成品としてのアウトプットなのか、アウトカムまで狙うのかを問おう 振り子のようにアウトプットや品質の考え方を動かしていこう 第5章 マイクロマネジメントから、自律へ ●From マイクロマネジメントでは、計画の詳細さと呼応するように、細やかな報告が求められる 「予実のズレをなくすことが成果につながる」という世界観がマイクロマネジメントを生む ●To 唯一の正解がないなら、多様性を許容して「当たり」を引く可能性を高めよう 順序と時間をマネジメントしよう 自ら学び、判断し、協力しあえるチームをつくろう ●From→To これまでの「ふつう」を少しずつ変えてチームの自律性を引き出していこう 「ファイブフィンガー」「ベロシティ&リードタイム」「ワクドキ感」でチームの状態を理解しよう 第6章 1人の知識から、みんなの知識へ ●From 仕事のやり方がアップデートされてない どこにナレッジがあるかわからない ナレッジが形式知として残されていない 効率性ファーストだと共同化の機会が限られたものになってしまう ●To 1人SECIモデルを回そう 逆円錐状に学びの回転を広げよう 協働によって創発を生み出そう ●From→To 形式知のかたちを見いだしておこう ナレッジ自体のふりかえりをおこなうようにしよう 第7章 縄張りから、越境へ ●From チームや部署を越えたコミュニケーションに良くなる兆しがない 1on1やチャットでも乗り越えられない ●To 越境の2つの意味 1人から始める越境 チームでの越境 組織の越境 ●From→To 接点を作り続け、対話を進めていこう 終章 思考停止から、行動へ ●From 「自分として」考えることも、動くこともない 思考停止から無関心、他責、面従腹背につながっていく ●To 関心、チーム、リスペクト、越境でダークサイドを変えていこう ●From-to 経験とは行動を起こした人にのみ与えられる報酬
-
4.0NHKスペシャル「激震コロナショック~経済危機は回避できるか~」著者出演、大反響! 紙版発売に先がけ、電子書籍版を先行配信。 「コロナショック」を企業、個人、政府が生き残る術がここに! ▼リーマンショックを超える経済危機は、3つの時間軸で襲ってくる。 第1波 日本のGDPの7割を占めるローカル産業(飲食、小売、エンタメなど)の壊滅 第2波 自動車、電機など グローバル型大企業へ波及 第3波 金融危機の発生 ・欧米でもローカル経済圏破綻の打撃が大きい(cf.リーマンは金融圏のみ) ・中国による牽引が期待できない ・ソルベンシー問題と逆石油ショックが金融危機へ ・破産したくなければ企業は短期PLを本気で捨てよ ・手元キャッシュが全て ・最悪を想定 ・危機におけるリーダーの「べからず集」とは? ・経済のグローバル化傾向は、このまま続くのか? ・企業が、個人が、政府が、コロナショックを生き残る鍵とは?
-
4.0コロナ騒動を軸に社会の矛盾を描く痛快風刺漫画! SNSで人気の4コマ・珠玉の240作品を収録! 大人気「コロナは概念カルタ」も掲載! 「これぞまさに読むワクチン!」情報通の冨田氏が強く推奨! 「コロナ茶番には大変迷惑している」インフル先輩激怒!! 「これほどまでに我々をうまく表現した本はない」コロナ王絶賛!! 「難しい内容が、面白くわかりやすく描かれていて勉強になります!」 「誰を責めるわけでもなく、読んでいて楽しいです!」 「こんな暗い世の中で4コマにいつも癒されています。」 「これぞブラックユーモア。にやにやしてしまいます。」 「心が折れそうな状況も絵だとクスっと笑えてしまう。何度も助けられました。」 「絵も内容も大好き!ほとばしる才能を感じます!」 「コロナ王の大ファンです!これからも新作楽しみにしています。」 「ツイッターで知って、毎朝新作を読むのが日課になりました。」 「とりあえず読んで」著者が推奨!!
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。


























































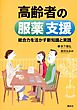





































![これからはじめる エクセルの本[Office 2021/2019/Microsoft 365対応版]](https://res.booklive.jp/1397933/001/thumbnail/S.jpg)



