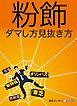社会学作品一覧
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初めて綴った感動秘話、家族だけが知る「素顔の百田尚樹」、 累計1700万部の全著書を自ら完全解説、珠玉の「私の百田尚樹論」など、 大ベストセラー作家・百田尚樹さんの全てが詰まった完全永久保存版! 初公開! わが原点『永遠の0』誕生秘話 沖縄タイムス・労組が大激怒! 沖縄で熱血大講演会 全録音 特別対談 朝日も沖縄二紙も上層部はクズばかり×我那覇真子 私が体験した沖縄偏向報道 沖縄タイムス 阿部岳記者の正体 百田家の家族が抱腹絶倒大座談会 父ちゃんは六十一年経験を積んだ子供や! 感動秘話 特攻に反対を唱えた指揮官たち 歴史の真実 日本の至宝、悲劇の戦闘機「零戦」 百田尚樹が飛んだ! 航空自衛隊「ドッグファイト」体験記 特別エッセイ 名も無き国民がつくった奇跡の国 累計1700万部! 百田尚樹、自ら全著書を完全解説 増補完全版 新・安倍晋三論 日本人初! 外国特派員協会で日本の言論弾圧を論ず ビッグ対談 櫻井よしこ 憲法改正か「カエルの楽園」か 有本香 「安倍潰し報道」はもはや犯罪だ 足立康史 左翼メディアとの最終戦争が始まった 上念司 マスコミ・左翼文化人の嘘とデタラメ 村西とおる 愛国、憂国大闘論 私の百田尚樹論 大崎洋、櫻井よしこ、松井一郎、北村晴男、高須克弥、中瀬ゆかり、石平、松本修、ケント・ギルバート、岡聡、有本香 百田尚樹の青春 秘蔵写真一挙公開28ページ 私の大好きな映画「七人の侍」 全8年の厳選ツイート集 『今こそ、韓国に謝ろう』私はこう読んだ 武藤正敏、ケント・ギルバート、杉田水脈、夏野剛、一色正春、松木国俊、西村幸祐 自筆履歴書 ニュースに一言 「防衛費は人を殺すための予算」発言 ドローンの不法飛行 自らの手は汚さない朝日新聞 くまモンよ、お前もか? 在日韓国・朝鮮人報道 ほか
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本当の自分、好きですか? 自己肯定感が低く、ずっと何かと、誰かと競争して生きてきた著者に、北欧の人々が教えてくれた幸せ習慣―― それは、「ありのままの自分でいるのを許す」ことでした。 けれどもいったい、どうやって? そのヒントは、デンマーク語で「ほっとくつろげる心地よい時間や幸福感」のことを意味する「HYGGE(ヒュッゲ)」にありました。 誰かのことをもっと知ること。 誰かと一緒に笑って楽しい時間を過ごすこと。 耳が聞こえない人の気持ちがわかるのは、そういう人がいるからだって考えること。 散歩に出かけて波の音に耳を傾けて鳥の声を聞いて、そして木々の匂いを感じること。 週末にはピカピカになるまでありとあらゆる場所を掃除することetc――。本書では、著者と発達障害の娘さんが変わるきっかけとなった出来事や言葉を通じて、北欧の人々のHYGGEな習慣を紹介していきます。 競争しなくていい。闘わなくていい。無理しなくていい。 これからのスタンダード、そして本当の自分を好きになる方法を、本書から読み取っていただけると幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 童話『ちびくろさんぼ』絶版問題と筒井康隆著『無人警察』教科書掲載問題に関わる、差別的表現を巡る論争などをとりあげ、「表現の自由」という「概念」がどのように「機能」したのかを問題にする。主に法律学の観点から論じられてきた「表現の自由」の問題を、社会学的な観点からアプローチ。マスメディアの発達した社会にあって、国家/社会/マスメディア/個人、という関連の中でこれらの問題をとらえることは、今日の政治社会そのものを考察することである。序章:「表現の自由」への新たなアプローチを目指して 第1章:「表現の自由」と人権および社会秩序 第2章:差別的表現規制と「表現の自由」の共和主義的理解について 第3章:公的領域としての思想の市場と管理社会論 第4章:知識社会学・イデオロギー研究と言説分析 第5章:アルチュセールの徴候的読解とディスクール分析 第6章:筒井康隆「無人警察」論争―「表現の自由」の空洞化 第7章:『ちびくろさんぼ』の絶版―「表現の自由」の揺らぎ 第8章:人間の複数性と「表現の自由」 第9章:「表現の自由」の保守的価値
-
3.0「人間として生きたい!」。人生を奪われた人たちの慟哭!――ハンセン病療養所。それは人が人として生きられない場所だった。「強制隔離というのは植木に巻かれた針金のようなものだ。針金はしだいに植木に食い込んでいく。気がつくと心の中までずっぽりと隔離の暮らしになじんでしまう」。そうして生きてきた元患者たちが「人間回復裁判」に立ち上がった! ● 請求金額については、同じく人生を奪われたと訴えた薬害エイズ訴訟の請求額1億円が基準となった。ただ、誰にでもわかりやすかった薬害エイズの健康被害に比べて、隔離被害は目に見えにくい。国民世論の共感は得られるのか。弁護団が悩んでいるそのとき、竪山は口を開いた。 「弁護士さんたち。1億円で私の人生と代わっていただけますか」弁護士の誰もがその問いに返す言葉をもたなかった。その被害は、狂わされた人生そのものだった。 「1億円で償える被害ではない」。しかしその重みを裁判所に正確に伝えられるのか。それがこの裁判を決する。このとき、弁護団はあらためてその課題を突きつけられたのだった。――(本文より抜粋)
-
5.0
-
3.9
-
4.2
-
-
-
-
-
4.2
-
3.4
-
3.8
-
-お金の貸し借りなど契約に関わる民法が改正された。約120年ぶりの抜本改正がビジネスや暮らしに与える影響は大きい。2020年にも施行される予定で、改正のポイントをしっかりと押さえたい。 本書は週刊エコノミスト2017年7月11日号で掲載された特集「ビジネスが変わる民法改正」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・契約のルールに大きな変化 グローバル時代に法体系刷新 ・飲み屋のツケ、病院の診療代… 時効10年に統一し、煩雑さ解消 ・労働債権の消滅時効 民法改正に合わせ長期化 ・現実に合わせ明確に定義 相手に不利な内容は無効 ・5%から3%へ「変動制」に 過払い金や損害賠償を左右 ・「公正証書」でハードル高く 事業の資金調達に影響も ・「契約不適合」の概念を導入 請負契約のシステム開発は注意 ・貸す人も、借りる人も必見 不動産実務はこう変わる! 重要7項目解説 ・我妻民法の大転換 「大陸法」から「英米法」へ 国際的潮流への対応 ・相続法の改正議論 与党に「家制度」への思い? 「法律婚だけ保護」に反対噴出 【執筆者】 桐山 友一、米江 貴史、三平 聡史、水口 洋介、小野 智彦、岩田 修一、大神 深雪、小久保 崇、吉田 修平、松尾 弘、荒木 理江
-
-
-
3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ビジネスマン必携の新教養! 毎日15秒読むだけで大丈夫。 研修では教えてもらえないサバイバル術365個を イラストレーター・ヨシタケシンスケの豪華イラスト365個付きで解説。 過酷なWebメディア業界をギリギリで生き抜いてきた デイリーポータルZ編集長・林雄司による特別コラムも必見! ●考課シートの自己評価は最高にして出す (その最高の評価がベースになって減点されていくので結果としていい数字になる) ●よその会社のかっこいい提案書、見積書は真似するために保存 ●プレゼンでは笑っている人だけを見る ●どこかに直行したことにする時は、辻褄合わせのため行き先をメモしておく ●頼まれてもいないのに新成人へのメッセージをSNSに書かない 【特別コラム】 役職早見表/海の生き物にたとえればわかる! 懲戒処分一覧/バナナボートの上座・下座/今日から使えるビジネス英会話/手土産OK・NGリスト/催促するときに使えるフレーズ/再発防止策の書き方/上司の仕事を100%断れる言い訳集/便利なメモ欄 …… 今日がしのげればそれでいい。 最強の気休め大全、刊行。
-
-日本を含む世界の先進国が、低インフレや格差の拡大、低成長など、根本的な問題に苦しんでいる。資本主義は限界か、失敗か、代替はあるのか。古くて新しいこの疑問の答えを探った。 本書は週刊エコノミスト2017年5月2日・9日合併号で掲載された特集「ビジネスマンのための資本主義入門」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・今、問い直す資本主義 経済学と哲学で説く新境地 特別対談 萱野稔人×吉川洋 ・語り継がれるドイツ小説 ベルが問うた「お金と幸福」の不都合 ・格差縮小の処方箋 「グローバル税」が再分配を促す ・【インタビュー】アンヘル・グリア(OECD事務総長) ・【インタビュー】竹田青嗣(哲学者) 「金融のゼロサムゲーム化が危機を生む」 ・お金と幸福の幻想 「利他性ある共同体」の構築必要 ・宇沢弘文と「資本主義の幻想」 よみがえる社会的共通資本 ・地球が何個も必要な資本主義 経済と自然の調和が持続社会を生む ・庶民の実践 ミニマリズムで脱・資本主義 ・AIがもたらす大失業時代 ベーシックインカム導入で理想郷に ・資本主義は国債が命 日本亡国の媚薬「シムズ理論」 【執筆者】 木本 伸、諸富 徹、大垣 昌夫、関 良基、鷲田 豊明、橋本 努、井上 智洋、米倉 茂、エコノミスト編集部 【インタビュー】 アンヘル・グリア、竹田 青嗣 【対談】 萱野 稔人、吉川 洋
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 国立新美術館をはじめとする美術館の建設ラッシュは、何を意味しているのか。明治期以降の美術館の歴史的展開をひもときながら、思想としての日本民藝館、ミュージアムパーク=上野公園の記憶と美術、近代史の矛盾を抱える遊就館、80年代文化の象徴であるセゾン美術館、地方都市の地域文化と美術館の関係性、指定管理者制度をはじめとする美術館経営などの具体的な問題群を取り上げて、文化装置としての美術館をめぐるさまざまな政治的力学を解明する。美術館という“場”を批評的に読み解き、マルチカルチュラリズムやグローバリゼーションをも議論の俎上に載せてその可能性に光を当てて、縦横無尽に美術館を語り思考するミュージアム・スタディーズの成果。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 子どもたちがいつの間にか大きくなり、少しばかり自由な時間も作れるようになる40代。また50代以降にもなれば、子育てが一段落を迎え、夫婦だけの時間が増えてきます。これまで子どもだけに意識と時間を取られてきたためか、二人きりだと居心地が悪いなど、いつの間にかお互いに微妙なズレを感じることもあるかもしれません。ビタミンママでは、そんな夫婦の子育て以外のお悩みにも注目し、人生のパートナーとのより良いセカンドステージを考えることが大切であると考え、今回「大人の夫婦」について掘り下げて考える一冊を企画しました。
-
3.8ビッグデータ、という単語を聞いたことのある人は多いかもしれない。しかし、これによっていったい何ができたり、どんなことがわかったりするのかを知らない人は、まだまだ多いのではないか?私たちが本書で示していくことは、ビッグデータが、これからのビジネスを考えるうえで、また、あなたの生活をより快適なものにするために、こんなにも役に立つのか、という驚きと発見である。今後は、すべての産業が「データ×AI化」していく。ネットとリアルは別個の世界であるどころか、切り離しえないものであり、今後ますますその連関が密接なものとなっていくことは間違いない。このような時代に生きる人々にとって、変革のカギとなるデータについての皮膚感覚的な理解が欠如していることは、致命的と言わざるを得ない。データを正しく理解する力(=データ・リテラシー)は、リアルな現実世界を生きていくうえで、もはや「常識」として身に着けておくべき必須のツールとなる。データを分析し、意思決定に役立てていく「データ・ドリブン」の思考力、分析力、情報科学の基本、データの力を解き放つ力――これらをしっかりと会得し、応用できる人だけが、これからの社会を生き抜いていけるのだ。さあ、私たちが分析した以下の新事実を読んで、データの魅力と無限の可能性を体感してみよう!第1部 ビッグデータは、「深層」を描き出す1―1 新社会人は4月に「モットーとは」、5月に「新入社員 辞めたい」、6月に「恋活」と検索する1―2 ママは、生後102日目にわが子をモデルへ応募したくなる1―3 「頭が痛い日本人」が最も多い時刻は、17時である1―4 矢沢永吉と郷ひろみは、双子レベルの「そっくりさん」1―5 日本は、「東京」と「それ以外」の2つの国からできている幕間劇1―6 音楽CDが売れる時、サバの漁獲量が増える――擬似相関とは何か?第2部 ビッグデータは、こんなに役立つ2―1 これからの「混雑ぶり」がわかり、移動のストレスが消える2―2 救援活動をスムーズに進める、「隠れ避難所」を探せ!2―3 リニアで日本はどれだけ狭くなるのかを、実際に見てみよう2―4 政治への関心が薄い日本人の注目を一挙に集めた、「令和」発表の瞬間2―5 検索量を分析すると、選挙の議席数予測は96%も的中する2―6 今の景気を予測することは、どこまで可能か?膨大なデータは見えてこそ、意味を持つ。明快にわかる、オールカラー図解版!
-
-仮想通貨のビットコインが年初から5倍近く値上がりしている。金融当局は規制を強化しつつあるが、投資、決済、資金調達と用途は広がっている。 本書は週刊エコノミスト2017年10月24日号で掲載された特集「ビットコイン入門」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・仮想通貨に集まる世界マネー 「分裂」「規制」ものともせず ・今から始めるビットコインQ&A ・資金調達バブル 賛否渦巻く「ICO」 市場急拡大、中国は全面禁止 ・ビットコイン入門 「仮想通貨の聖地」と呼ばれる飲食店 ICOで常連さんから2600万円調達 ・インタビュー 岩下直行(京都大学公共政策大学院教授、元日銀フィンテックセンター長) ・導入増えるビットコイン支払い 上昇相場で決済も増える ・規制強化 取引所登録は健全化の一歩 投資家保護、詐欺対策に課題 ・ビットコイン入門 金融庁インタビュー 佐々木清隆(金融庁総括審議官) ・分裂騒動 11月に再分裂の可能性 露呈した非中央集権の弱点 ・中国 相次ぐ規制に潜む戦略 仮想通貨の発行もくろむ ・中央銀行vs仮想通貨 価格を安定化できれば法定通貨に代わり得る ・ドラギ氏怒らせたエストニア 独自の仮想通貨構想 ・ビットコインの限界 通貨も投資も持続しない仕組みに本質的な問題 【執筆者】 田茂井治、高城泰、村田雅志、向山勇、宿輪純一、志波和幸、田代秀敏、岩村充、翁百合、中島真志 【インタビュー】 岩下直行、佐々木清隆
-
-1980年代以降、テレビ番組を録画・再生できるビデオデッキが普及したことでタイムシフト視聴が可能になり、ビデオは私たちの映像経験に大きな変容をもたらした。ビデオはどう受容され、メディアとしてどのような射程をもっていたのか。 放送技術であるビデオがニューメディアとして注目されるプロセス、教育現場での受容から家庭への普及、音楽ファンのエアチェック文化とミュージックビデオ受容の連続性、アニメファンのビデオ受容、レンタルビデオ店の成立とそれを可能にした条件――。録画・編集・流通・所有・交換・視聴・消費など、様々な視点からビデオのメディア史に光を当てて、ビデオの社会的な受容の複数性と映像経験の多層性を明らかにする。 DVDの登場や「Netflix」などの定額制の動画配信サービス、各種の動画共有サービスに目配りしながらも、ビデオというメディアの固有性とかつてあった可能性を歴史から掘り起こす。
-
3.8
-
4.0
-
4.1
-
5.0
-
4.0まやかしの数字を用いたプロパガンダ言説を、豊富な図表を用いて論破する! 「日本の借金は1000兆円以上もあり財政破綻間近である」というウソ。 「日本の人口は8800万人にまで減少し日本経済が衰退する」というウソ。 「財政再建のため、社会保障の財源が足りないから、消費増税するしかない」というウソ。 「年金制度は崩壊する」というウソ…等々。 世の中にはフェイクニュースや的外れな議論が溢れている。 思い込み、というのは人によってずいぶん違うらしいが、そもそも筆者の頭の中には思い込みというものが存在しない。 何かを論じるときは長期間のデータや海外の事例などを見るから、思い込むという感覚が正直よくわからない。 筆者は運命すらもすべて確率で考えるから、そのときの運なのか、そうでなければ何%の確率で起こったのかと考える。 大学では数学を専攻し、数量分析を使えば現状を的確に把握できるし、将来すら予測できる。 なぜなら、ある事柄について、その始まりから終わりまでの過去の経緯と、理想的にはG20、最低でもG7加盟国分の海外の具体的事例でファクトを集めれば、どの時代、どの地域にも共通する普遍的なルールが自然と見えてくるからだ。 そうすれば時間的な広がりを持つ縦軸と空間的な広がりを持つ横軸が通った、強い論考が生まれてくる。 「そんなことは当たり前だ」と思われるかもしれないが、世の中にはこの当たり前のことができる人がほとんどいないのだ。 さて、以下の問いに、あなたは正しく答えられるだろうか? 【問 世界で日本だけが貧富の差を拡大させているのか】【問 最低賃金を引き上げれば貧困問題は解決するのか】【問 就業率や賃金はどうすれば上がるのか】【問 日本はベーシックインカムを導入した方が幸せか】【問 奨学金はタダにならないのか】【問 日本の「奨学金」は英語で何と表すか】【問 国際関係とは一般的に国家間の何を指すか】【問 貿易収支が赤字になると国内景気はどうなるか】【問 日本は果たして貿易立国か】【問 対外純資産の変動は経済成長に何か影響を与えるのか】【問 消費増税は日本経済に福音をもたらすのか】【問 消費増税で苦しくなると消費税は払えなくなるか】【問 法人減税をすれば日本企業の国際競争力は高まるか】【問 将来的に日本は財政破たんするのか】【問 国家予算が増え続けると財政は危ないのか】【問 数兆円の公共投資は税金の無駄づかいか】【問 日本の高齢化率は2065年に何%になるか】【問 なぜNHK改革は与野党で長年タブー視され続けてきたのか】【問 高齢化に伴い個人金融資産残高は増え続けるのか】【問 将来的に空き家率はどのくらいまで上がるのか】【問 機械で代替できない仕事には何があるか】【問 食糧自給率が低ければ食糧難になる確率は高まるのか】【問 日本人がガンで死ぬ確率は何%か】 答えは、本書の中にある!
-
4.0
-
4.0
-
4.0
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 ファンダムエコノミーは、もはや一部の「過剰な消費者」が生み出す周縁的な経済圏ではない。それは、生産者と消費者の関係性を根底から変え、これまでとはまったく異なるビジネスを生み出す巨大な潮流だ。伝統的な経済システムと接しながら、モラルエコノミー、ソーシャルエコノミー、贈与経済がハイブリッドされた摩訶不思議な新しい経済は、来るべき政治、文化、社会さえをも変えてしまうかもしれない。ファンダム研究の第一人者からシリコンバレーのトップVC、認知科学者、中国エンタメビジネスやUXのエキスパートなどを迎え、トレッキー、デッドヘッズ、BTS Armyから、クリエイターエコノミー、Web3、NFT、メタバースまでを縦横無尽に読み解く全ビジネスパーソン必読の入門書。 【ヘンリー・ジェンキンズ/リ・ジン/岡部大介/陳暁夏代/藤井保文/ダグ・スティーブンス/ジョン・フィスク/山下正太郎/若林恵】 「ファンダムエコノミーは、伝統的な経済システムであると同時に、モラルエコノミー、ソーシャルエコノミーでもあるのです。 純粋なギフトエコノミー(贈与経済)のような状態も存在します。その背後にある欲望は単なる消費欲ではありません。欲望の対象は、対象へのアクセスなのです」──ヘンリー・ジェンキンズ 「ファンは新しいテクストの生産にとどまらず、オリジナルのテクストの構築にも参加することで、商業的な物語やパフォーマンスをポピュラーカルチャーへと変えてしまう。ファン文化は実に参加型なのだ」──ジョン・フィスク 「ファンが求める本質的な価値と効果を提供し、より的確にマネタイズを行うことができるようになることで、クリエイターはより少ないファンによって生計を立てることができるようになる。これは、クリエイターのためにユーザーがお金を払う従来の「寄付モデル」から、ユーザーが自分のためになるものに喜んでお金を払う「価値モデル」への移行を意味している」──リ・ジン 【著者紹介】 [編]コクヨ野外学習センター コクヨ野外学習センター(KOKUYO Centre for Field Research)とは? コクヨ ワークスタイル研究所とコンテンツレーベル黒鳥社がコラボレーションして展開するリサーチユニット/メディアです。ポッドキャスト番組「愛と死の人類学」「新・雑貨論Ⅱ」を制作・配信中。著書に『働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話』。Https://anchor.fm/kcfr 【目次抜粋】 #0 ファンダムは◯◯を超える 対談 山下正太郎×若林恵 #1 ファンダムエコノミー入門 ヘンリー・ジェンキンズとの対話 #2 Web3ルネッサンスとクリエイター/ファンダムの経済 リ・ジン #3 ファンダム経済は「ギブ」でまわる 岡部大介 #4 中国の音楽アプリにみるクリエイターエコノミーのつくりかた 陳暁夏代 #bookguide ファンダムを読む #5 贈与経済のためのUX 藤井保文との対話 #6 メタバースのなかのリテール ダグ・スティーブンス #7 ファンダムの文化経済 ジョン・フィスク
-
4.2
-
3.8
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人々の暮らし方と自然の関わりの結果としての風景は、瀬戸内海でどのように変遷してきただろうか。私たちの祖先は、瀬戸内海の自然をどのように認識し、その自然とどのように関わってきただろうか。そうしたことを探ることにより、どのようにすれば、どのように私たちの暮らし方を変えていけば、より良い環境、より心地よい風景を次の世代に残していけるか、考えることができるのではないだろうか。 遺跡、植生、文学、絵画など私達の祖先が残した様々な手がかりから、祖先と瀬戸内海の風景との関わり方を想像し、その変遷を辿ることにより、自然環境の荒廃が心配される現在の私達の暮らしと瀬戸内海のあるべき姿を探る。
-
3.6
-
3.5
-
3.7夫婦同姓が法律で強制されているのは今や日本のみ。本書では、夫婦別姓も可能な英国・米国・ドイツ、通称も合法化したフランス、別姓が原則の中国・韓国・ベルギーで実体験を持つ筆者達が各国の歴史や法律から姓と婚姻、家族の実情を考察し「選べる」社会のヒントを探る。そして、一向に法案審議を進めない立法、合憲判断を繰り返す司法、世界を舞台とする経済界の視点を交えて、具体的な実現のために何が必要なのかを率直に議論する。多様性を認める社会の第一歩として、より良き選択的夫婦別姓制度を設計するための必読書。
-
4.0アメリカ大統領選挙以降、フェイクニュースは国内外を問わず社会的な問題となっている。だが、国内の実態はほとんど明らかになっていない。日本国内のフェイクニュースはどのように生まれ、なぜ広がるのか。 2017年の衆議院議員総選挙、18年の沖縄県知事選挙の2つの選挙、20年の新型コロナウイルス感染症拡大時の「デマ」――各事例をもとに、ソーシャルメディアやまとめサイト、既存メディア、ポータルサイトの相互作用で、フェイクニュースが生成・拡散するプロセスを実証的に分析する。そして、フェイクニュースは、ソーシャルメディア時代において、ニュースが生成され、拡散するニュースの生態系そのものから生み出される構造問題であることを指摘する。また、フェイクニュースに対抗するために必要性が議論されているメディアリテラシーやファクトチェックについては、逆効果になりかねないと警鐘を鳴らす。 汚染の構造と複合的な要因を踏まえ、フェイクニュース生態系における汚染の連鎖を断ち切るために、プラットフォームを運営する企業、既存メディア、個人、それぞれの役割を確認する。そのうえで、多様なメディアと多様な考えの人々により構成され、相互作用が生み出す豊かなニュース生態系を実現する道筋を照らし出す。
-
3.3なぜ、ベビーカーは交通機関に乗せづらいのか? 暗い夜道を避け、遠回りして家に帰らなければならないのはどうしてか? 女性が当たり前に感じてきたこれらの困難は、じつは男性中心の都市計画のせいかもしれません。 これからの都市は、男だけでなくあらゆるジェンダーに向けて作られなければならない。 近代都市は男性による男性のための計画によって形作られてきた。多くの公共スペースは女性のために設計されておらず、母親、労働者、介護者として生活する女性たちに不自由を強いてきた。ヨーロッパでは街を歩くだけで売春婦と思われた時代があり、現代においても危険な夜道は解決されない問題として残っている。フェミニズムを建築的に展開させた本書が、世界を作り出す新しい力(パワー)になるだろう。 目次 イントロダクション:男の街 女は厄介者 都市について書いているのは誰か? 自由と恐怖 フェミニズム地理学について 一章:母の街 フラヌーズ パブリックなからだ 女性の場所 都市という難所 母親業のジェントリフィケーション 性差別のない街とは 二章:友達の街 友情に生きる ガールズ・タウン 友情と自由 クィア女性の空間 死ぬまで友達 三章:ひとりの街 パーソナルスペース おひとりさま ひとりでいる権利 公共空間の女 尾籠な話 女が場をもつこと 四章:街で声を上げること 都市への権利 安全をDIYする アクティヴィズムにおけるジェンダー アクティヴィストの旅 行動が教えてくれるもの 五章:恐怖の街 恐怖心の正体 危険の地理 恐怖のコスト 押し戻す方法 女の大胆さ 交差性と暴力 あとがき:可能性の街
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「もうフェミニズムに頼らなくても、女性だって活躍できる」 「女性差別がなくなった現代において、フェミニズムの時代はもう終わった」 と彼女は言った。 では、私やあなたの心のどこかに張りついている「女であることの不安」はいったいどこからくるのだろうか。 ――「女らしさからの自由」と「女らしさへの自由」、どちらも実現できる世界をともに目指すために。 「ポストフェミニズム」という視点から、若い世代の性別役割分業や性行動の意識調査のデータを分析。さらにSNSにおけるハッシュタグ・ムーブメントや、雑誌『Can Cam』による「めちゃモテ」ブーム、「添い寝フレンド(ソフレ)」経験者などへの調査を通じて、現代社会における「女らしさ」のゆくえを追う。
-
4.0
-
-仕事の内容で給料が決まる仕組みが日本企業にも浸透し始めている。賃金に改善の兆しが見えてきた。 本書は週刊エコノミスト2018年6月12日号で掲載された特集「増える給料」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに 【執筆者】 松本惇、小島清利、溝上憲文、原田三寛、山田久、川口大司、竹内英二、藤森克彦、黒沢敏浩、週刊エコノミスト編集部 【インタビュー】 林貴子、太田聰一
-
-「現金」に異変が起きている。スウェーデンなどキャッシュレス化が進み現金が社会から消えつつある国がある一方で、日本は現金が増え続けている。 本書は週刊エコノミスト2017年5月30日号で掲載された特集 「増える現金 減る現金」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・現金流通高対GDP比19% 突出する日本の現金依存度 ・日本 タンス預金残高43兆円 高齢単身女性の不安を反映か ・スウェーデン 民間銀行主導でキャッシュレス化 現金流通量はGDP比1% ・【インタビュー】ケネス・ロゴフ(米ハーバード大学経済学部教授)「日本は1万円札を廃止すべき」 【執筆者】 熊野 英生、白井 さゆり 【インタビュー】 ケネス・ロゴフ
-
4.2
-
3.7実家のこと、夫婦のこと、子どものこと、お金のこと… 話せていますか? ・大切なことを話せていない ・何気ない一言が尾を引く 家庭のイライラ・モヤモヤ・ギスギスが、ぜんぶ解決! 「夫婦には会話が必要」「ケンカするほど仲がいい」とはよく言われます。 でも、なかなかうまくいかない。 面倒だったり、ギスギスしたり、イラっときたり、 相手の機嫌を伺うばかりで肝心なことが言えなかったり、 つい嫌味を言ってしまって後悔したりする……。 そんなこと、ありませんか? 結局のところ、 夫婦がうまくいくとは、夫婦のコミュニケーションがうまくいくということ。 そして、コミュニケーションさえうまくいけば、二人の関係はうまくいく。 たとえば、 ・照れくさくても、「好き」「ありがとう」と言う ・「〇〇して! 」ではなく、「〇〇してくれる」?と頼む ・相談されたら、「どうしようか」?と一緒に悩む ・言いにくいことは、「キャラ」で話す ・ほめてほしいときは、「ほめて」とアピールする などなど、声かけや返事、言葉の語尾を変えるだけで、 会話はぐっとまろやかになり、夫婦の関係はぐっとよくなります。 話しにくいことも話せるようになります。 そうやっているうちに、 夫婦の会話が次第に増え、結果的に、 ・言いにくいことをがまんしてイライラすることがなくなる ・家事・育児の分担の不満がなくなる ・介護や教育費などについて話せて不安がなくなる ・相手に再び愛情を感じるようになる ・夫婦仲がよくなり、家庭に笑顔が増える といった効果が得られます。 コロナ禍の在宅勤務でイライラしてしまう二人にも、 30年先も尊敬しあえる関係でいたい二人にも、 いますぐ使えるヒントが満載の一冊です。 ◎こんな人におすすめです! □ 夫婦の会話が少なくなってきた □ 大切なことが話せていない気がする □「私ばかりやっている」と不満を感じることがある □「こんなはずじゃなかったのに」とギャップを感じる □ 愛が冷めてきたのか、優しくできない □ 今はいいけど、子どもが巣立ったあとが不安 ◎あなたはどのタイプ?円満夫婦3タイプチェックテスト付 1)恋人タイプ お互いが好き同士のラブラブ夫婦で、 独身時代のような恋愛感情でうまくいっている夫婦。 2)戦友タイプ 価値観が合っている者同士のバリバリ夫婦で、 一緒に家庭を切り盛りしていく戦友のような夫婦。 3)同居人タイプ 一緒にいてラクな相手だから結婚しているイマドキ夫婦で、 シェアハウスの同居人のような距離感の夫婦。 ◎ここが違う! ! うまくいく夫婦 うまくいかない夫婦 × 相手を家族と思う ◯ 相手を他人と思う × 以心伝心で通じ合う ◯ 報・連・相をサボらない × 二人だけでがんばる ◯ 第三者の手を借りる × それぞれスマホを見る ◯ 一緒にテレビを見る × 子どもを通じて話す ◯ 相手に直接話す × 正論を振りかざす ○ キャラで話す × セックスレスに悩む ○ スキンシップから始める × 外で相手をけなす ○ 外で相手を褒める
-
3.9
-
4.5福井の潜在パワーを知り尽くす本 カニとIT、えち鉄=メディアミックスで逆襲! 「全国体力テスト」小学5年生男女とも1位、「全国学力テスト」2位、これからの福井もやっぱり幸せな県! ★ビミョーなこともあるけどすごい「日本でいちばん幸せな都道府県」ランキング1位、都道府県別幸福度ランキング1位! 幸せの2冠王 ★福井人の主食はやきとりなのか? ★「カツレツ消費量」「フライ消費量」トップって…福井県人ってデブが多い? ★水ようかんは冬の風物詩!? ★朝倉家、柴田勝家、日本の歴史のカギは福井が握っていた!? ★「はよしね」って……「福井弁」辞典 ★「めがね」「えち鉄」「オープンデータ」ITと伝統産業のコラボで変わりつつある福井
-
4.3地方再生の知恵は、「逆境続き」の北陸にあった 共働き率と出生率で全国平均を上回る北陸三県。幸福度も世帯収入も高い。北陸ならではの協働システムや教育を取材した画期的ルポ。 世界が注目!富山市のコンパクトシティ ・道路整備率1位がアダに ・孫とおでかけ支援事業の狙い ・おでかけ定期券で健康になる ・世界中から行政視察が ・「三十年後の市民の声を聴け」 福井の幸福度はなぜ高い? ・「日本一」「世界一」の企業多数 ・「一向一揆で負けたから」 ・若者が作る「鯖江モデル」 ・女性も羽ばたく協働精神 ・教育は投資 ・教師を変えることから始める 他 解説・佐々木俊尚
-
3.4人口増加率、開業率、通勤の利便性、第1位! 福岡市=シリコンバレー?! ハリウッド?! なぜ「勝ち組」になれたのか なぜいま、福岡市なのか。 福岡について、出身者はもちろん、進学や転勤などで一時的に住んだ人も、一様に口をそろえて「住みやすいまちだ」という。 その証拠に少子高齢化が進む日本において、福岡市の人口増加率は日本一になっている。「世界で最も住みやすい二十五都市」のランキング上位の常連でもある。 だが、福岡の魅力は住みやすさだけではない。福岡はいま、イノベーションや起業で先頭を走っているうえ、成長するアジアの玄関口も担っている。 著者の牧野氏は、いまの福岡が「数十年前のアメリカ西海岸」に相当するポジションにあると分析する。アメリカ西海岸といえばアップル、グーグル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックのビックファイブが生まれた地である。 自動車産業などの凋落に見舞われたアメリカ経済を西海岸が救ったように、開業率1位「日本の西海岸」福岡が、少子高齢化で「沈みゆく日本」を救うのではないか。 実際に東京、カリフォルニア、福岡に住んだ経験のあるジャーナリストが分析する。
-
4.1
-
-■「はじめに」より この人に話して良かったと思ってもらえるようになりたい、少なくとも話したことを後悔するような職員にはならないように力をつけたいと思っています。今まで思い込みや先入観で相手を決めつけていたり、価値観や常識に囚われていたり失敗もたくさんあります。自分と向き合うこと・自分を疑ってみること、自分の感情をコントロールしていかないと、この仕事は続けていけません。 障害者の中にも、優れたスキルを持った人はいます。会社の戦力として活躍できる人がいるのに、雇用をし、給与を払っているのに、その対価に見合う労働をさせていません。 障害者を「弱者」としてとらえ、障害者を個の戦力として捉えることない社会。「弱者」であることを特に考えることなく受け入れることで、自身が「強者」になっていることに気づいていない障害者。その「常識」が、現在の日本の障害者福祉問題を停滞させています。 ■本書の内容 第1章「障害者支援について」では、特に障害者就労の支援の現場で実際に仕事として行なっている内容を解説し、障害者福祉の現状をお伝えします。続く第2章「働く障害者の理想を生むためには」、第3章「障害者福祉事業について思うこと」では、障害者雇用の理想と問題、現場から伝えたい目指すべき支援の在り方をお話します。 ■障害者支援の現場から伝えたい「福祉の未来を考える力」 福祉という仕事の特性上、どうしても「守りの仕事(利用者のリクエストに応えること)」に手が一杯になってしまうことが多いのではないでしょうか。 しかし本当に問題を解決するには、利用者を取り巻く環境を変え、未来を変えるための行動が必要です。 本書で主にご説明している障害者支援の現場においても、日々目の前の対応に多くの時間を割くことが必要とされていますが、そこでは「対症療法」ではなく、「根本治療」が求められています。 障害者支援の現場における取り組みを知っていただくことで、福祉の仕事をする方が「福祉の未来を自分たちで作る」きっかけとなれば幸いです。
-
-
-
4.6
-
4.2
-
3.6「君が代」は議論の絶えない歌である。明治早々、英国王子の来日で急遽、国歌が必要になる。しかし、時間がないため、『古今和歌集』の読み人しらずの短歌に鹿児島で愛唱されていた「蓬莱山」の節をつけて間に合わせたのが「君が代」の誕生だといわれる。以降、1999年に「国旗国歌法」で法的に国歌と認められるまで、ライバルが現れたり、戦時下には「暗すぎる」、戦後には「民主国家にふさわしくない」と批判されたり波乱が続く。最近では、教育現場での「君が代」斉唱が再び問題視される。日本人にとって「君が代」とは何なのか? 気鋭の若手研究者がその歴史をスリリングに繙く。
-
4.3
-
-
-
4.0
-
-光ファイバーの需要が急増し、半導体も新規投資が相次ぐ。一体何が起きているのか。 本書は週刊エコノミスト2018年2月13日号で掲載された特集「2ケタ成長 光ファイバー・半導体」の記事を電子書籍にしたものです。 ・中国の通信網整備がけん引 世界需要は年20%成長 ・足元は値下げ圧力なし 日本勢3社、多芯化で強み ・クラウドが需要押し上げ 技術組み合わせで性能向上 ・AI半導体 激化する新興企業の開発競争 テスラもカリスマ技術者迎え参入 ・データセンター向け半導体 王者インテルとAMD・クアルコム乱戦 ・データセンター 年5%成長で需要を支える 収益性の低下が課題 【執筆者】 松本 裕司、種市 房子、津田 建二、服部 毅、羽賀 史人
-
3.7
-
4.1出口治明 待望の復帰第一作! 「障害は不自由です。 でも落ち込む時間はありません。 人生は楽しまなければ損です!」 74歳 APU学長 完全復職。 脳卒中を発症してから1年半。 歩くことも話すことも困難な状況から、持ち前の楽観主義で落ち込むことがなく元気にリハビリ生活を送った出口さん。知的好奇心は衰えるどころか増すばかり。学長復職を目指す、講演を行う、再び本を執筆することを掲げ、自分を信じ闘病に励む稀有な姿勢と超人の思想は、私たちに生きる勇気を与えてくれる。本書には類書にない希望が満ち溢れている! [本書の主な内容] ●やっぱり大事なのは「運と適応の力」 ●流れ着いた場所でベストを尽くす ●脳卒中になっても人生観は変わらない ●74歳の僕が完全復帰を目指した理由 ●最後に悔いを残さないことが最大の幸福 ●身体が完全に元には戻らないと知ったとき ●人生は古希をすぎたら「後は神様次第」 ●リハビリで歌った『恋の予感』 ●何かを選べば何かをあきらめなくてはならない ●「病気」というピンチから得られるものもある ●ものごとにはすべたダークサイドがある ●あらゆる人が生きやすい社会づくりを ほか [本書の構成] はじめに 第一章 突然の発症から転院へ 第二章 僕が復職を目指した理由 第三章 リハビリ開始と折れない心 第四章 言葉を一から取り戻す 第五章 入院生活とリハビリの「自主トレ」 第六章 リハビリ入院の折り返し 第七章 自宅への帰還からAPU学長復職まで 第八章 チャレンジは終わらない
-
4.5増税せずとも復興はできる! 未曾有の大震災により、市場経済も市民生活も大打撃を受けているにもかかわらず、政府は“復興”という名目で様々な増税政策を推し進めようとしている。政治家や経済評論家たちは毎日のように「財政難」を訴え、「日本は借金漬け」と繰り返す。果たしてそれは真実なのか? 「市民税10%減税の恒久化」「議員報酬半減の恒久化」をマニフェストに掲げる名古屋市長河村たかしは「増税せずとも復興できる」と断言する! 本当に増税は不要なのか? その根拠はどこにあるのか? 増税以外の選択肢で日本を再生させるには? その答えがここにある!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 このくらいは「普通」のことだ-。「普通」や「常識」が規範として機能し、生活の最低限のモチベーションになっていた時代はもはや遠い過去になった。「当たり前に生きていてはダメだ」「独自であれ」「自分らしさをもつために絶えず努力しろ」などの言説の渦のなかでせきたてられるように社会制度から抜け出した途端、社会に戻ることが許されず排除される時代を私たちは生きている。独自性の獲得や社会的成功を生きる指標にするがゆえに、困難に見舞われ、むなしさを感じ、苦悩する人々の現状を、大学生の率直なコメントや若者文化、「私」語りなどの身近な事例を導きの糸にして描き出す。そして、「普通」「常識」をシニカルでニヒルな姿勢からではなく真正面からしっかりと見据えて、希望に満ちた明るい「普通」さの可能性を探る。
-
3.6
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●〔対談〕ハラスメントは減ったかもしれないが…… 職場の環境はよくなったのか? 河合 薫×常見陽平 ●令和の若者にウケるわけ 昭和レトロはどこに向かう 高野光平 ●田中角栄、山口百恵はもう現れない カリスマなき時代政治も歌もチームで勝負 枝野幸男 ●〔対談〕暴言もあれば共感もあった 令和の政治家は言葉の力を取り戻せるか 御厨 貴×東 照二
-
3.4
-
4.0
-
3.9
-
4.2テレパシー・記憶の増強・AI…… SFの世界が現実になる! 脳研究やテクノロジーの進歩により、心の仕組みと働きが劇的に解明されつつある。さらに科学の進歩がつづくならば、われわれの能力や可能性は飛躍的に高まり、驚異の未来が開けるという。 たとえば、心で考えるだけでものを動かしたり、感情や感覚をインターネットで送ったり、記憶や知能を強化することもできるようになったりするのだ。 理論物理学の権威であり、語りの名手でもあるカク博士が、自然界最大の謎といわれる「心」を題材に、壮大でワクワクする旅へと誘う知的エンターテインメント! NHK「NEXTWORLD 私たちの未来」出演の理論物理学者が綴る第一級のサイエンス・ノンフィクション。ニューヨーク・タイムズのベストセラー1位を獲得した話題の書! [内容] 第I部 心と意識 第1章 心を解き明かす 第2章 物理学者から見た「意識」 第II部 心が物を支配する 第3章 テレパシー 第4章 念力 第5章 記憶や思考のオーダーメード 第6章 天才の脳と知能強化 第III部 意識の変容 第7章 夢のなかに 第8章 心は操れるのか? 第9章 意識と精神疾患 第10章 人工知能 第11章 脳のリバースエンジニアリング 第12章 心が物を超越する 第13章 心がエネルギーそのものとなる 第14章 エイリアンの心 第15章 終わりに 補足 意識の量子論?
-
4.5
-
3.0
-
3.6家庭か仕事か――あなたはまだ悩んでいる?モーレツサラリーマンも今は昔。日本でも「組織人間」より「フリーエージェント」という働き方が確実に増えています。その結果、家庭と仕事の融合が進み、税金や社会保障といった社会ルールも着実に変化するなど、未来を見通し自分の生き方を考えるために最適の社会論がここに!
-
4.1
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 コロナ禍収束の流れとともに、一時の停滞から急速に抜け出しつつある世界。さまざまな分野での「萌芽」とも呼べる動きを多角的にピックアップし、新たなビジネスにつながる視点で、ビジネスパーソンに必要な最新情報と、社会課題解決へのヒントをまとめた。 社会の大変革へとつながるテクノロジー進化が加速する中、今回取り上げた領域は生成AIをはじめ、メタバース、リスキリング、観光による地域再生、食料安全保障、介護DX、空飛ぶクルマ、宇宙・月面ビジネス、カーボンニュートラルなど多岐にわたる。 共通するキーワードは、豊かな未来へ直結する「胎動」。イノベーションの予兆を捉えながら、本格的に始まりつつある「社会実装」の現場を取り上げた。 具体的には、三菱総合研究所の研究員たちの詳細な分析と、それぞれの分野第一線で活躍する有識者との対談やインタビュー。世界の中での日本が進んでゆく道筋を確実に捉えることのできる、読み応え十分の一冊となっている。 「フロネシス」とは…… 古代ギリシアの哲学者、アリストテレスは「実践的な知」を示す概念として、「PHRONESIS(フロネシス)」という言葉を提唱した。本書は今の社会やビジネスにつながるテーマを絞り込み、有識者のインタビューや対談、研究員たちのレポートを基に課題解決に向けた提言をまとめている。
-
3.0なくならない企業の粉飾決済。投資家の自己防衛力向上と企業風土の刷新が必要だ。 本書は週刊エコノミスト2016年12月20日号で掲載された特集「粉飾 ダマし方見抜き方」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・進む「日本企業の劣化」 経営者の悪意排除を ・インタビュー マイケル・ウッドフォード 元オリンパス社長 ・会計士が明かす手口 常道は売掛金、在庫の水増し 「のれん」の“隠れみの”に注意 ・危ない財務を見抜く ROEはROAの2倍以下! 営業キャッシュフローはプラス ・Q&Aで解説! 企業会計を知るキーワード5 ・AIで粉飾を発見・防止 ・グラフで見つける! 粉飾を見抜くエクセル活用法 散布図と回帰線で異常を把握 ・「上場ゴール」を防げ! 上場直後の大幅下方修正は直前の会計処理に“抜け穴” ・「のれん」のリスク アーム買収でソフトバンク急増 減損リスクが財務、業績に重し ・逆風の監査法人 人気職業から転落した会計士 不正会計の撲滅に不安残す ・企業風土 しがらみ断つトップ選出へ 「経営幹部の内部統制」必要 ・監査役の「覚醒」 増えるモノ言う監査役 粉飾防止の「番人」たれ ・内部通報者保護 公益通報者保護法の充実 試される財界の「本気度」 【執筆者】 稲留正英/桐山友一/金井暁子/前川修満/村井直志/村井直志/金井暁子/井端和男/磯山友幸/浜田康/山口利昭/光前幸一/エコノミスト編集部 【インタビュー】 マイケル・ウッドフォード/君和田和子/佐々木清隆/関根愛子/佐藤隆文
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 食を自分のアイデンティティやライフスタイルとして捉える人々=フーディー。その言葉や存在は、TBSドラマ『グランメゾン東京』や三越伊勢丹運営の食メディア「FOODIE」、雑誌の特集で、日本でも知られるようになった。 高級店を訪れる一方、オーガニック食品やローカルフード、「手作り」にも引かれ、郷土料理やエスニック料理も味わう。「良い食べ物」を食べて学ぶことに強い関心をもつ彼/彼女たちの実態とは、いったいどのようなものか。 現代アメリカのフーディーの生活世界、セレブシェフへの熱狂、レストラン批評やフードブログの隆盛に、雑誌記事やテレビ番組、フーディー当事者へのインタビューから多角的に迫る。そして、「食の民主化」と「エキゾチシズム・真正性への希求」という食文化の両義性と、両者の緊張関係を析出する。 フーディーをめぐる食文化から階級や人種、ジェンダーの問題系を浮き彫りにして、そこに潜む社会的な不平等や雑食的な文化資本、卓越化の戦略を明らかにする「食の社会学」。
-
3.8
-
3.5
-
4.0
-
4.0
-
4.4
-
-ブックオフから考える。 社会と都市と文化の「つながり」を。 日本全国に約800店舗を構えるブックオフは、多くの人にとって日常生活に溶け込んだ存在になっている。しかしこのような「当たり前」の存在になるまでは、ブックオフをめぐりさまざまな議論が繰り広げられてきた。あるときは出版業界の革命家として、またあるときは破壊者として、そしてまたあるときは新たなサブカル文化の創造者として……。 本書は、ブックオフが誕生した1990年代からのさまざまな「ブックオフ論」を整理し、実際に多くの店舗を観察して、「なんとなく性」という切り口から、なぜ人はブックオフに引き寄せられるのか、そして現代社会でどのような役割を果たしているのかを縦横無尽に考え尽くす。 ブックオフはどう語られてきたのか。またその語りに潜むノスタルジーとは。 チェーン店であるブックオフが都市にもたらしたある種の「豊かさ」とは。 ブックオフで「偶然」出合う本の面白さとは。 ブックオフから生まれた音楽、カルチャーとは。なぜアーティストはブックオフからの影響を語るのか。 ブックオフが生み出す公共性とは。「文化のインフラ」の内実とは何か。 チェーンストア論やテーマパーク論で注目を集める新進気鋭の著者が、出版史、都市論、建築論、社会学、政治学、路上観察学など多様な分野の知見を駆使して書き上げたいままでにないブックオフ文化論。
-
4.0
-
-「待機児童解消」が叫ばれる。だが、量拡大を至上命題とするあまり、保育の“質”低下を放置すれば、保育士不足は加速し、量の確保も遠のく。 本書は週刊エコノミスト2017年7月4日号で掲載された特集「ブラック保育園を増やすな」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・経験乏しい若手のみの修羅場 保育士に「人件費」が回らない ・親のホンネ 園児見失い告発は「風評被害」か ・保育園に「親の力」「専門家の目」 質を保つ仕組みを海外に学ぶ ・年金・医療・介護で「子育て基金」 老後を左右するのは次世代 【執筆者】 小林 美希、南野 彰、池本 美香、権丈 善一
-
5.02018年2月、美味しい米の代表とされる魚沼コシヒカリが食味ランキングで特AからAに陥落したニュースは衝撃を呼んだ。翌年、魚沼コシヒカリは無事特Aに返り咲くが、各産地が「美味しい米」の開発・生産に努め、しのぎを削る状況は激しさを増す一方だ。美味しさはもちろん、冷害耐性、豊富な栄養、収穫量など多様な目標のもと、今日も新品種の開発が続けられている。ブランド米開発の舞台裏と米作現場のさまざまな課題に迫る。 目次 ブランド米の生まれた背景――まえがき 第1章 ブランド米狂騒曲 1 コシヒカリ覇権の経緯/2 新品種はどう開発されるのか/3 あきたこまちと大潟村の挑戦/4 ブランド米の価値はどう決まるか/5 ササニシキの復権に賭ける/6 変わる食味テスト/7 日本一誉れ高いコメ――コシヒカリの味を超えるコメを/8 海外から求められる「龍の瞳」/9 収穫期をずらせるのが魅力「五百川」/10 栄養素が豊富な「金のいぶき」/11 ブランド米と小売店 第2章 ブランド米の功罪 1 味にこだわりすぎた「つや姫」/2 ブランド維持が裏目に出た「青天の霹靂」/3 美味しさの追求は諸刃の剣/4 コシヒカリの受け皿となる品種 第3章 需要に合わせてコメを作る 1 業務用米の世界/2 コメ代わり食品の登場/3 「ご飯」を食べてもらう試み/4 安くて美味しいコメが求められている/5 コメ輸出という悲願/6 耕作放棄地は増え、担い手は減る 第4章 コメの未来 1 広い面積にはドローンが有効/2 今までの限界を超えるコメ作り/3 コメの種子をめぐる大変革/4 民間のやる気を削ぐ現行システム/5 民間育種は壁を越えられるか――住友化学の挑戦/6 執念の民間育種家 コメの取引のあり方が大きく変わる――あとがき
-
3.9女子体操着であるブルマーは、ブルセラブームを契機に批判を受け、1990年代半ば以降に学校現場から急速に姿を消した。消滅の社会的背景はこれまでも断片的には語られてきたが、では、腰に密着して身体の線があらわになる服装が、なぜ60年代に一気に広がり、その後30年間も定着・継続したのだろうか。 地道な資料探索や学校体育団体、企業への聞き取り調査を通して浮かび上がってきたのは、中学校体育連盟の存在だった。そこから、中体連の資金難、企業との提携などのブルマー普及の背景を解き明かす。また、受容の文化的素地として、東京オリンピックの女子体操が与えたインパクト、戦前から続くスカートの下の2枚ばきの伝統などとの関連も検証する。 ブルマーは導入当初から性的なまなざしにさらされてきた。にもかかわらず、学校現場でブルマーが存続してきたのは、ブルマーをはく女子の身体に女子修身教育の幻を見る戦前回帰派と、美と健康を見る戦後民主主義派とが思わぬかたちで共謀していたためではないかと指摘する問題提起の一書。