ビジネス・経済 - 日経BP作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
3.3平成から令和に元号が改まり、新しい時代が始まったのは2019年(令和元年)5月1日。それから1年後の2020年(令和2年)5月の世界を誰が予想していたでしょうか。それは言うまでもなく、新型コロナウイルスの世界的な感染爆発です。 1989年に始まった平成時代の30年間は日本経済にとって激動の30年間でしたが、令和時代も波乱の滑り出しとなりました。 昭和時代の第2次世界大戦の敗戦から、戦後復興、高度成長期、2度にわたる石油危機を乗り越え、経済大国に躍進した日本。その頂点のバブル経済は、昭和から平成への時代の大きな変わり目でした。平成バブルは崩壊し、日本経済は「失われた20年」とも称される長いトンネルに入りました。平成の終わりにはようやくトンネルを抜けて、明るい日差しが注いできたのですが、令和を迎え様々な課題が浮かびあがってきています。 本書は、令和時代を迎えた日本経済の過去、現在、そして未来をわかりやすく解説することをねらっています。 これまでの日本経済の入門書は、第2次世界大戦後の日本の経済復興から始まることが多かったと思いますが、この本は平成の30年間の日本経済の歩みから始まります。平成バブルやその崩壊を実体験として知らない世代の読者を意識しているからです。 平成の30年を振り返った後は、人工知能(AI)やIoT(モノのインターネット)が生み出すデジタル革命(第2章)、地球温暖化とエネルギー問題(第3章)、急速に進む人口減少と少子・高齢化(第4章)、金融・財政政策の試練(第5章)、日本とグローバル経済(第6章)といった個別の課題を解説します。
-
3.0●名著『ゼミナール日本経済入門』を全面刷新 本書は、30年にわたって読まれてきたベストセラー・テキスト『ゼミナール日本経済入門』をより読みやすく、わかりやすく全面刷新。戦後70年を踏まえた「日本経済の今」を分析します。金融、物価、景気、産業構造といった基礎知識のほかに、貿易摩擦、財政改革、環境問題といった応用問題についても解説しています。本書一冊で日本経済についての基本から最新情報まですべてが得られます。日本が幸運にもデフレ経済からの脱却に成功したとして、その後2050年頃に向かう日本はどのような姿をたどることになるのでしょうか。日本が向き合わなければならない課題は山積しています。その中でも、少子高齢化を伴う急激な人口減少は最も深刻な問題です。終章では、課題先進国日本の「これから」に正面から取り組んでいます。 ●経済を見る目を磨く3つの読み方 本書は、序章と終章を除く各章が三部構成になっています。 (1)最新の動きを「さっと読みたい」という方は、第I部の「日本経済TODAY」だけを読んで下さい。それだけで最新の日本経済の入門書になっています。 (2)問題の背景や歴史的経過、経済理論との関係に興味のある方は、第II部の「歴史・理論を学ぶ」まで読んで下さい。応用能力が身につきます。 (3)生きた日本経済や産業構造の変化を自分で分析し、将来を予測したいと思っている方には、第III部の「統計を読む」が役に立ちます。
-
4.3高齢化・人口減少といった社会構造の変化に直面しながらも、日本経済は低迷を脱して、本来の活力を取り戻しつつある。それは、多くの企業が“失われた10年”の間に、新しいビジネス環境に適合した「事業の再設計」に成功したからだ。まさに今、日本企業の前には、巨大な可能性が広がっている―。日本的経営論の原点となった名著『日本の経営』の著者で、「終身雇用」という言葉の生みの親であるアベグレンが、日本企業の過去数十年間の歩みを分析するとともに、これから進むべき方向を提言。半世紀におよぶ日本企業研究の集大成として書き下ろされた注目作。
-
3.9日本企業は世間で言われるよりもはるかに強い。グローバルな最先端技術の領域で事業を展開する機敏で賢い数多くの企業。その顔ぶれ、昭和の経営から令和の経営への転換、イノベーターとしての競争力、見えざる技術・製品をベースとする事業戦略、タイトなカルチャーのもとでの変革マネジメントを解説する。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初心者でも安心! プロ&スゴ腕投資家たちが丁寧に指南 あなたの生涯の投資生活を一変させる新NISA。では、新NISAとは何か、攻略法やお薦め銘柄は? これらの疑問に、資産づくりの情報誌「日経マネー」でおなじみのプロ&スゴ腕投資家たちが丁寧に解説します。お得な情報が満載です! ≪目次≫ ■PART1 新NISAの改正ポイント&新戦略 ■PART2 新NISAで「攻めの投信&ETF」 ■PART3 優待・配当株投資のキホンとお薦め銘柄 ■PART4 新NISAで「目指せ!老後資金1億円」 ■PART5 スゴ腕投資家たちの新NISA活用術 ■PART6 投資のお悩み相談所 ■PART7 「数字」を正しく読む力
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2024年にNISAの恒久化が発表され、制度の仕組み自体が大きく変わることになりました。 そこで本誌では、新たなNISAの仕組みを視野に入れて、23年の投資戦略をどうすべきかについて掲載。 まず現行のNISA及びつみたてNISA枠の使い方を、新NISAに向けて見直す必要があります。 大筋の戦略を決めたうえで、仕込むべき投資先について詳述します。 株式投資、投資信託のおすすめ銘柄をアンケート調査でプロに聞き、注目テーマや企業をまとめました。 さらに23年の相場環境を予測する特別インタビューも掲載。23年の株価予想とともに注視すべき経済イベントなどをおさらいできます。 さらに、インフレ時代に投資資金をねん出するための家計を助ける買い物テクニックについても紹介します。 ≪主な内容≫ ・新NISAで老後資金のつくり方が変わる! ・新NISAの基本&最適解 ・2023年株価徹底予測 ●PART1 株式投資で増やす ●PART2 投資信託 徹底比較 ●PART3 株主優待 必勝ガイド ●PART4 最新投資術 ●PART5 家計を助ける得 ・生前贈与の新常識 ・新しいお金の稼ぎ方
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 第一線のFP、アナリストらが厳選! 注目の投信、株、ETFを多数紹介 巻頭対談に日向坂46の佐々木久美さんが登場!(岩城みずほさん[CFP(R)]との対談) 日本経済新聞社インデックス事業室が協力 ・プロ5人に聞く 新制度はこう使う ・新NISAとiDeCo(個人型確定拠出年金)のかしこい使い分け方 ・「つみたて投資枠」「成長投資枠」、それぞれの最適商品は? ・全銘柄掲載 つみたて投資枠で買える投資信託・ETF ・インデックス投資の活用法 ・日経指数を投資に活かそう
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2024年1月、投資の絶好機が到来。新しいNISA(少額投資非課税制度)が始まり、投資枠の拡大と無期限化によって、個人が取れる戦略の幅が劇的に広がります。この追い風にどう乗るかは、自由度が高いだけに難しくもあります。新NISA時代に、初心者でも稼げる投資法をまとめました。 《目次》 新NISA超入門 資産ゼロ・知識ゼロ・暇ゼロから稼ぐ! 最速資産1億円&高配当生活 MONEY SPECIAL 2024 PART 1 新NISA最強戦略 新NISAを今始めるべき3つの理由 新NISAでつくる 1億円を目指す最強の組み合わせ! 戦略1 ほったらかし投資 戦略2 コツコツ高配当株投資 戦略3 全振り高配当株投資 2024 SPECIAL INTERVIEW Zeppy社長/CEO 井村俊哉氏 今さら聞けないQ&A 初心者に立ちはだかる「3つの壁」 STEP1 制度理解 STEP2 購入準備 STEP3 運用開始 株式投資必修ワード 2024 徹底予想 特別インタビュー レオス・キャピタルワークス 運用本部 経済調査室長 三宅一弘氏 日本金融経済研究所 代表理事 馬渕磨理子氏 MONEY SPECIAL 2024 PART 2 最強日本株名鑑 新NISA時代に取るべき4戦略 MONEY SPECIAL 2024 PART 3 投資信託大賞2024 MONEY SPECIAL 2024 PART 4 株主優待最強銘柄 新旧プランはどっちが得? スマホ料金を下げる方法 Part 1 大手キャリアで最適プランを探す Part 2 ポイント還元でスマホ料金を下げる Part 3 容量別に最安プランをリサーチ 未来を作る スタートアップ大賞2023
-
3.62024年に生まれ変わるNISAと、老後資金づくりに役立つiDeCo。 今すぐ実践できる両制度の最新の使い方や上手な組み合わせ方を、 「現役世代の資産形成」に長年携わってきたプロが徹底解説。 年齢別・職業別の活用法、投資信託&株を選ぶポイントも分かる! 運用益が非課税で、資産形成の強い味方になるNISAとiDeCo。 NISAは2024年の制度リニューアルで、 生涯投資枠が最大1800万円と大幅に拡大。 非課税保有期間も無期限となり、使い勝手が大きく向上します。 iDeCoも掛け金の全額所得控除による節税メリットが大きく、 老後に向けた資産形成には欠かせません。 実はこちらも、公務員や一部の会社員にとって有利になる 拠出限度額のルール改正が2024年末に控えています。 これらの制度を利用するのとしないのとで、 10年後、20年後の資産が倍くらい違ってくることも十分にあり得ます。 資産運用を始めるのは40代からでも、50代からでも遅くありません。 新しいNISAとiDeCoを上手に活用し、長い将来に備えるためのお金、 つまり「老後資金」を効率よく増やしていきましょう。 そのための制度利用のポイントから、将来必要になるお金の知識、 実際に投資する際の投資信託や株式の銘柄の選び方、 年齢別や職業別のNISA&iDeCoの活用法までを徹底解説します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◎明暗分ける投資の新常識が見えた! 2024年に大幅拡充された新NISAが、25年1月から2年目に突入。1年目の結果・実績を振り返りつつ、NISAでの資産運用における2年目の見直し術、取り入れたい最新テクニック、老後に向けた自分年金づくりの考え方などを紹介します。 また、中長期の投資で注目される株式の銘柄や投資信託も掲載。併せて、債券や投資型クラウドファンディングなどサブ運用で押さえておきたい金融商品も解説します。 ≪目次≫ ●第1特集 投資特大号 新NISA 2年目の教科書 Part1 新NISA 2年目の戦略 Part2 日本株&米国株 Part3 投資信託大賞2025 Part4 株主優待の最強銘柄 ●第2特集 文房具ヒット大賞&予測 ●第3特集 ペット用品大賞 ●第4特集 健康グッズ大賞
-
3.8マネジメントは「管理」ではない、「創造」だ──。ドラッカーから直接教えを受けた著者が、ドラッカーが伝えたかった「本当のマネジメント」を解説する。 著者は、ドラッカーが自らの理論を伝え、また彼と思想を分かち合う教授陣が教壇に立つ米ドラッカー・スクールで学んだ。ドラッカーから直接教えを受けた最後の世代にあたる。 本書は経営の当事者として、またコンサルタントとして、著者が体験した多くの事例をとりあげながら、セルフマネジメント(自分自身のマネジメント)、マネジャーが目指すべき目的、マーケティングとイノベーション、組織とチームづくり、 会計や情報技術との向き合い方、コミュニケーションなどドラッカーのマネジメント論を学ぶ上で鍵となる7つの重要テーマについて広く、深く解説する。ドラッカーの理論全体像を学び、それらを現場で活用するための具体的なヒントを得られる構成になっている。 マネジメントは新入社員から経営層まで、さらに民間企業はもちろん自治体、非営利組織など、あらゆる組織に属する人が知っておくべき「教養」だ。 マネジメントという教養を身に着けることで、仕事に対して自ら目的を設定し、他者を生かし、日々様々なイノベーションを実践して成果をあげる創造的な働き方ができるようになる。 リモートワークをはじめ新しい働き方が広がる中、組織やチームとして最も大切な事が何かを考える上で大いに役立つ一冊。
-
4.0通算40年以上にわたりSE(システムエンジニア)という職業に関わってきた筆者が、その経験を踏まえ「しっかりしたSE」になるための鉄則50をまとめました。「SEは非常に面白く、やり甲斐のある職業」という思いが全編に詰まっています。本書を読めば、SEの仕事を面白く、やり甲斐のあるものにするための勘所をつかめます。
-
3.9SNS時代に選ばれるために! ロングセラーが全面改訂! SNSが普及したいま、お金をかけず、お客さまとゆっくり関係性を築くことが容易になりました。 これは、あなたの商品・サービス・ブランドの価値を伝えることが、よりカンタンになったってことです。 販促物、店舗運営、SNSの発信……すべてを「関係性」というキーワードで考えてみましょう。 ●商品やサービスに独自の価値はない ●時代は「つながりの経済」へと移行 ●入社したとたん800件の問い合わせがきた新卒美容師 ●関係性を築く5つの視点 ●好きなことをしているとそれが価値になる ●あなた自身が情報の「フィルター」になる ●お客さまを「かたまり」として捉えないこと ●「売ってください! 」とお客さまからいわれる存在 ●逸脱は新しい価値を生むエネルギー ……など、「つながり」の時代に、あなたの商品・サービス・ブランドを独自化し、その価値を伝える方法を徹底的に伝授します。
-
3.8ウッドショック、ウクライナ危機…日本の森林資源をどう生かす? 3本の矢を放てば、森林が数百兆円の国富となる (1)デジタル技術による国産材サプライチェーン1000カ所構築 (2)木材を廃棄せず、木質バイオマス燃料に安定供給 (3)丸太や製材ではなく、サッシ、断熱材を組み込んだ木造建築部品として輸出 <カーボンニュートラル時代、「森林列島・日本」を再生する事業プランを提示> 日本は森林面積が国土の3分の2に及ぶ森林大国。だが、これまで木材を輸入に頼ってきたため、国内林業は衰退し、木材産業や建築業、不動産業とつなぐサプライチェーン(供給網)も分断されてしまった。そうしたなか、国際的な木材の供給不安が発生、木材価格が暴騰する「ウッドショック」と呼ばれる事態を引き起こしている。直近ではウクライナ危機を受け、さらに先が見通せなくなっている。 森林大国の日本にとって、豊富な資源を生かさない手はない。本書は、森林という資源の現状とその未来を問うものである。「森林列島」を再生するために、林業や林産業ではなく森林産業を構想し、国土を有効活用する事業案を起草する。
-
3.0本書の著者である富士通執行役員副社長CROの大西俊介が2023年4月から就任した「CRO(最高収益責任者=Chief Revenue Officer)」。この役職は、IBM、SAP、セールスフォースといった世界的IT企業や急成長するスタートアップ企業が戦略的に配置し始めており、企業成長の要となる変革リーダーの職責として国際的に注目を集めています。 「単なる営業の親玉と誤解されがちですが、本質は全く異なります。顧客と企業の接点すべて―製品開発からビジネスモデル、組織体制、人材育成、顧客戦略まで―を顧客価値の最大化という視点から抜本的に変革するのがCROの使命です」と大西は話します。実際に大西は、2019年の富士通への再入社以降、時田隆仁社長CEOが主導する「時田改革」の実行役として、富士通を根本から変革する様々なプロジェクトを推進してきました。 本書は、富士通という日本を代表するグローバルIT企業が今まさに断行している変革をCROの立場で主導する著者が、その変革の舞台裏を、成功体験だけでなく直面した課題や障害、それを乗り越える処方箋も含めて明らかにし、CROという職責の役割をつまびらかにします。国内IT大手を皮切りに、外資系コンサルティング会社やインド系大手IT企業の日本代表といった多彩なキャリアを積んだ後に富士通に参加した著者だからこそ語れる、企業変革とリーダーシップのリアルな姿がそこにあります。 DX時代の経営者、事業責任者、変革推進リーダーはもちろん、顧客志向のビジネス創造に関わるすべての方々に役立つ、実践的変革バイブルです。
-
3.0決められないリーダー、決めて“夢”を叶えるリーダー リーダーの思考が会社・組織の10年後を決める! ◆リーダー(経営者)に必要なのはコンサルタントではなくコーチである コンサルタントとコーチの違いを意識しているだろうか? コンサルタントは「問題を解決してくれる人」で、新たな問題が発生するたびに相談することになる。一方のコーチは「問題の解決方法を教えてくれる人」。正しいコーチングを学べば、自力で目標を立てて問題解決していけるようになる。 そしてリーダーには、それに特化したコーチング(CEOコーチング)が必要だ。組織として問題を解決し目標を達成していく必要があり、そのためには、経営の知識や経験が欠かせないからだ。 ◆認知科学に基づく、リーダーのための最先端のコーチング手法 本書は、著者が独自に体系化した「認知科学に基づく経営者のための問題解決メソッド」をもとにしたCEOコーチング実践の書。 脳の上手な使い方を学び、「よいゴール」を設定することで、むやみにがんばらなくても、ありとあらゆることが自然に実現できるようになる――CEOコーチングは、NASA、コカ・コーラ、3M、オラクルなどで導入されたルー・タイス氏の手法と、認知科学の知見を融合させた新しい「目標実現」のメソッドである。本書は、それを具現化する「7つの力」と、その先にある「経営パフォーマンス10倍アップ」の法則を、ありがちなリーダーの過ちのケースなどを織り込みながら実践的に解説する。
-
-米国で半導体関連会社の事業立ち上げに苦闘した出来事をCEO(最高経営責任者)の視点で共有して仮想体験し、BtoBビジネスにおけるマーケティングの重要性を理解してもらう
-
-What Is IOWN? NTT's Leaders Provide the Full Story IOWN has drawn increasing attention in the media and elsewhere. But you may be wondering what exactly this advanced communications solution is that is rapidly spreading around the world. With generative AI, the metaverse, and IoT linking to all sorts of objects, the world is consuming electricity at a pace that is accelerating at astonishing speed. It is easy to imagine that these technologies will require an incredible amount of power. Our savior in this situation could be IOWN, the next-generation information platform designed with NTT's cutting-edge optical technology. Given the explosive growth in data volumes and the accompanying massive power consumption in the near future, we will need IOWN. That is because with this information platform, we have set a target of a 100-fold reduction in power consumption by the aforementioned technologies.. What kind of sustainable future will IOWN enable? In this book, NTT's leaders provide thorough explanations on topics including the technological background, the effect IOWN will have on our lifestyles and society, and specific use cases. Readers will gain a solid understanding of what IOWN is and the impact it will have on our world.
-
-経営者やビジネスリーダーを中心に、登録会員170万人のビジネスパーソンが訪れる情報サイト「日経ビジネス オンライン」。同サイトが2013年に掲載したすべてのコンテンツの中から、10万人以上のアクセス(ユニークユーザー)を集めたものを 中心に、日経ビジネス編集部の専門記者が行ったインタビュー記事をピックアップしたのが本書。いわば、日経ビジネスオンラインが2013年に生んだ「メガヒット記事」の厳選集。 京セラ創業者の稲盛和夫氏、ファーストリテイリング(ユニクロ)代表取締役会長兼社長の柳井正氏、ヤフー社長の宮坂学氏といったビジネス界のビッグネームから、NHKの朝ドラ「あまちゃん」プロデューサーの訓覇圭氏や、宮崎駿氏原作のアニメーション 「風の谷のナウシカ」に登場する小型飛行機「メーヴェ」を実際に制作して飛ばしたメディアアーティストの八谷和彦氏など、時代を彩る「時の人」22人へのインタビューを収載した。 ジャンルは企業経営からキャリア問題、日中関係、環境問題、ライフスタイルまで多岐にわたり、インタビューの切り口も多彩。そこで繰り出される識者の言葉には、ビジネスパーソンの好奇心を揺さぶる独自の視点があふれている
-
4.3サントリー、日本郵政など海外での大型企業買収が加速している。世界市場でシェアを確保できるかどうかが、企業の生死を決める。M&Aは買収後が勝負。買収後の統合作業が頓挫すれば、成功はおぼつかない。 「海外M&Aのことなら、この人に聞け」と言われるのが、JT副社長の著者だ。M&Aの担当者はJTの門を叩き、巨額M&Aを成功させた辣腕CFOに、どうやって経営統合するか、教えを請う。 JTの今日のポジションは、日本企業では珍しい二度にわたる1兆円規模の海外企業の買収によって築かれた。1998年、RJRナビスコから米国市場以外のたばこ事業を統括するRJRIを9420億円で買収、 2006年には英国のタバコ企業ギャラハーを2兆2500億円で買収した。 JTは大型M&Aで自身の組織や意識を変えながら、経営統合でも最大の効果を発揮している。2014年12月期の連結売上収益が2兆4300億円、調整後営業利益は6600億円。 このうち売上収益の55%、調整後営業利益の3分の2を海外事業が占めている。 日本と中国市場を除く世界市場をジュネーブに本拠をおくJTインターナショナルが担当している。「良い子(電電公社)、悪い子(国鉄)、普通の子(専売公社)」と言われた時代から、 たばこの世界シェア3位メーカーに大きく飛躍したJTの事業戦略を立役者の1人がはじめて明らかにした。
-
4.0すべてが変わろうとしているこの時代に、あなたがジェネレーティブAIの波に乗るための1冊 ★ 仕事の80%が変わる、未来を切り開く革新的技術へのガイドブック ★ 東京大学 松尾豊教授、パナソニック コネクトCEO 樋口 泰行氏、カーネギーメロン大学金出 武雄教授、伊藤穣一氏、杉山 恒太郎氏、Microsoft小田 健太郎氏、HIKKYさわえみか氏など、一流の専門家たちへのインタビューを収録 今、世界はジェネレーティブAIの時代へと突入し、80%の仕事が変化の波に飲まれようとしています。ビジネスの未来を決定づけるこの重大なチャンスを逃すことなく、あなたも早速この新世界に足を踏み入れてみませんか? 本書は、世界が注目する次世代のAI技術、ジェネレーティブAIについて、基本概念からビジネスへの応用、AI活用の倫理までを1冊に凝縮。ChatGPTをはじめとするジェネレーティブAIが文章だけでなく、画像や動画の生成まで可能にするこの驚異的な領域を詳細に解説。 ジェネレーティブAIとは何か、それが社会や産業にどのような影響を及ぼすのか、そしてこれからどう対応すべきなのか。AIの出現によって人間が「人間とは何か」を再認識する時代に、多面的な考察を提供します。 また、日本企業の最前線にも焦点を当て、パナソニック コネクト社が全社員にChatGPTを導入した具体的な事例や、樋口社長のインタビューも掲載。ジェネレーティブAIの実際の活用法を具体的に示し、その可能性を身近に感じていただけます。 すべてが変わろうとしているこの時代に、あなたがジェネレーティブAIの波に乗るための1冊。新世界への道しるべとなることでしょう。
-
-世界的ベストセラー『ジェフ・ベゾス 果てなき野望』著者、待望の続編発売! 止まらない発明、秘密のプロジェクト、大失敗、歴史に残る成功と急成長、 圧倒的な権力、うずまく不満と批判、不倫、離婚、再建、パンデミック、退任――。 アマゾン創業者にして、20兆円超の個人資産で世界一の富豪となったジェフ・ベゾスとアマゾンに、トップジャーナリストが鋭く切り込む! ◆なぜアマゾンは次々と発明を生み、育てられるのか? ECサイトはもちろん、キンドル、アレクサ、アマゾンゴー、AWSなどアマゾンは次々と発明をくりかえしてきた。従業員130万人を超える巨大企業になっても、大企業病にかからずに発明をつづける組織の秘密について、それぞれの開発物語を通し、表から裏まで紹介する。 ◆大失敗、歴史に残る成功と急成長 2010年末のアマゾンは売上342億ドル(約4兆円)円、従業員は3万3700人。そこから8年後には売上2328億ドル(約28兆円)と7倍に、従業員約65万人と20倍の規模で巨大化した。その後も、ぐんぐん規模を拡大し続けている。 ◆冷酷な経営者として知られるが、起業家と不倫相手には甘い人間臭さも ジェフ・ベゾスは、結果を出せない社員には厳しくあたると恐れられ、倉庫の作業員を搾取していると批判され、合理化の鬼のように言われる。その一方で本書には、若い起業家には時間を割き、評価が甘くなる側面も登場する。そして、離婚のきっかけとなった元キャスターのローレン・サンチェスとの不倫スキャンダルでは、ベゾスのそれまでとはまったく違う行動も数々見られた。人間臭いベゾスを著者が描きだす。
-
3.7時に部下を叱りつけ、ありえない目標を掲げ、けたたましく笑う。そうして小売りの巨人ウォルマート、大手書店のバーンズ&ノーブルなどとの真っ向勝負に立ち向かってきた。ベゾスのビジョンは、「世界一の書店サイト」にはとどまらない。「どんなものでも買えるお店(エブリシング・ストア)を作る」という壮大な野望に向けて、冷徹ともいえる方法で突き進んでいく。 ■急成長したアマゾンの手法がわかる! ジェフ・ベゾスとアマゾンの経営手法は独特だ。10年以上先を見据えて、必要とあれば赤字もまったくいとわない。買収したい会社があれば、相手の体力が尽きるまで価格競争を仕掛けて追い込む。投資家から批判されても、巨大な物流システムやクラウド「AWS」、電子書籍「キンドル」などの新規事業には、巨額の投資を続ける。電子書籍の普及に向けて、出版社には言わずに卸値を下回る1冊9ドル99セントで電子書籍を売りまくる。数字と情熱を重要視する合理的で冷徹な手法を解説している。 ■ベテラン記者がベゾスの許可を得て記した最高のノンフィクション 著者は、ニューズウィーク誌、ニューヨーク・タイムズ紙、ビジネスウィーク誌でジェフ・ベゾスやアマゾンの記事を書いていたベテラン記者。ジェフ・ベゾス自身はマスコミ嫌いで有名だが、長年の著者の実績から、本書に関しては、ジェフ・ベゾス自身がアマゾン幹部や親族や友人への取材を許可した。著者は本書のために、300回以上も関係者に取材。ベゾス自身が40年以上音信不通だった実の父も探し当てて話を聞いた。
-
-人生百年時代を迎え元気なシニアが増えるとともに、「老後資金2000万円問題」に象徴されるように、豊かな老後を築くための収入確保などが大きな課題となりつつあります。 もはや多くのビジネスパーソンにとって65歳まで働く、あるいは70歳を超えても働くことが当たり前になりつつあります。そこで問題になるのは「各人が自分の能力を生かして、いかにやりがいを持って働き続けられるようになるか」です。 役職定年後で肩書きを失った途端、誰でもできる簡単な仕事しか回されなくなった。定年後、再雇用されたものの職場に居場所がなく孤立している――。そんな「ああなりたくない」元上司や先輩を身近に見てきた40代、50代のビジネスパーソンにとっては、特に切実な問題でしょう。 そこで本書でご紹介するのがジェロントロジーの活用です。ジェロントロジーとは医学、生理学、社会学、心理学など様々な学術分野を横断的にカバーする学際的な学問です。エイジングに伴う生涯発達や高齢化社会における生活、人間関係、心や健康の管理、老人介護や諸制度・政策、経済などの問題を多角的な側面からとらえ総合的に研究しています。 特に注目したいのが結晶性能力です。ジェロントロジーによると人間の能力には2種類あります。比較的若い頃から衰え始める流動性能力に対して、洞察力や創造力といった結晶性能力は歳を取っても伸び続ける能力です。その結晶性能力を仕事や生活の中で鍛えていくことにより、豊かな未来が切り開けるようになります。 本書では結晶性能力を鍛える働き方、そして生き方を具体的に解説しました。すぐに試せるワークシートも多数収録しました。ぜひご活用ください。
-
4.5時給を上げる前に、時間価値の最適化を目指せ!! すきま時間を買う人・売る人、ダイナミック・プライシング、サブスクリプション――。 ほんのわずかな時間の使い方で、人生の満足度に大きな差がつく時代、になった。 気鋭の経営コンサルタントが消費行動、企業のあり方、個人の働き方まで、「時間価値」と「空間」の関係を鋭く読み解く一冊! 人々の時間へのニーズを、時短術などの「時間効率化」と創造的で豊かな時間を過ごす「時間快適化」という2軸で読み解き、「時間価値」を追求するほど、有利となる新時代の到来を「時間資本主義」という切り口で鮮やかに分析した著者の『時間資本主義の到来』を加筆修正した増補改訂版。 ダイナミック・プライシングやサブスクリプションの解説や最新事例を盛り込み、より幅広い読者に向け、わかりやすく書き直した。 ビジネスパーソンの時間の使い道は多様化し、個々人の生産性や時間価値に差が開きつつある。10分の移動時間や待ち時間というすきま時間を活用する人もいれば、長距離の通勤時間を使って本格的に副業をする人もいる。 時間で価格に差をつけるサービスも次々と登場し、「時間価値」から今後のビジネスを考えることが必須となった今、本書は、あらゆるビジネスパーソンに必読の教科書となる。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 仕事もプライベートも、 やらなくちゃいけないこと&やりたいことがいっぱいの働く女性たち。 効率よく時間を使い、ミスなく仕事を終わらせ、暮らしをフルに楽しみたい。 そんな女性たちの声に答えるべく、ディズニーやコクヨ、Googleなど 人気企業に勤める「ミスゼロ女子の仕事ワザ」から、 資格取得に役立つ勉強法、「失敗しない」服選びのコツまで。 ONにもOFFにも役立つヒントが満載の1冊です。
-
2.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 忙しくても24時間が充実している人、時間に追われずに目標や夢を 達成する人、お金を貯めている人、部屋がきちんと片付いている人… この人たちに共通するのが、手帳とノートを上手に使いこなすワザがあること。 このムックでは、そのすごいワザの数々を達人たちが日々愛用している手帳やノートを誌面で見せながら紹介します。 残業をゼロにしたい、仕事と子育てを上手に両立したい、ダラダラする時間をなくしたい…あなたのニーズにぴったり合った実例がきっと見つかります。文具ソムリエールや文房具大好き女子たちセレクトの特選文具カタログもついています。
-
4.5
-
4.1競争戦略やビジネスモデルの理論や手法をクリエイティブに使いこなすための「考える力」を磨く――。それが本書のメインテーマです。経営学を学んだことがない人でも読み進められるように、経営学が教える基本を示しながら、基本を超えていくためのヒントを提示します。わかりやすい事例を分析しながら、ビジネスモデルの設計や革新に役立つヒントをふんだんに紹介します。 ビジネスモデルは「頭の中にある理想」であって、現実は「矛盾だらけ、制約だらけ」です。経営者が思っている通りに人は動きません。あるいは経営者の言っている通りにするとうまくいかないから、現場が工夫して、経営者が意図したビジネスモデル通りではないことをしている場合もあります。そういう現実の中を進んでいくためには、ビジネスモデルに埋め込むロジックに「できの良さ」が求められます。王道を行くか、クレイジーになるか。ダントツ企業の選択を紹介します。
-
-他者が起こした失敗事例から、 廃棄物処理法と実務のポイントを学ぶ ◆前代未聞の事件、廃棄物食品横流し事件を徹底リポート ◆数々の事件から、廃棄物処理法のポイントを学べる ◆Q&Aでは業者の選び方や現地確認の方法を徹底解説 横流し、リサイクル偽装、不法投棄事件――。 本書は、数々の事件をひもときながら、廃棄物処理法の重要ポイントや現地確認などの実務ノウハウを余すことなく解説しています。 事件別に学習テーマを定めてポイントを端的に説明しているので、すべてを読めば体系的に学べる構成になっています。 実務担当者だけでなく、管理する立場の管理職や工場長、経験が浅い新任担当者にもお勧めです。
-
5.0●第一章 モンスターストライクは世界一! 開発者としての矜持 mixiパークからの撤退 mixiパークはなぜ失敗したか ほか ●第二章 ロジカルシンキング×ゲーム=モンスターストライク 『ストーリーとしての競争戦略』から学んだフレームワーク 開発キーワードは「B.B.Q.」 モンストの開発で設定した4つの戦略パス 4つの戦略パスを実践するためのクリティカル・コア モンストを超えていく組織づくり ほか ●第三章 木村弘毅社長 結局「挑戦し続ける」に行きついた半生 社長とは1つの役割である コミュニケーションの素晴らしさを唱え続けて 自分の見方を大切にする コミュニケーションとSNS ほか ●第四章 未来のコミュニケーションとミクシィ 新生ミクシィの船出 縦軸・横軸のマトリクス型組織 難しさはコミュニケーションで乗り越える スポーツをより面白く スポーツチームのエンターテインメントパートナーになる ほか
-
3.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人生100年を生き抜く「武器」を手に入れる 変化の激しい今の時代、自分の「武器」を少しでも増やすために、 仕事のかたわら勉強する人が増えています。 「皆、何を勉強しているの?」「勉強の時間はどうやって捻出しているの?」 「勉強が続くコツは?」…そんな疑問を解決すべく、働く女性たちのリアルな 勉強スタイルと学びのヒントを、この1冊にたっぷり盛り込みました。 読めばきっと自分に合った勉強スタイルが見つかり、 学びのモチベーションが高まるはずです! ◎毎日勉強を続けられている人の24時間 ◎英語力がアップした人のイマドキ勉強法 ◎脳科学で判明!40代から最強勉強メソッド ◎趣味の学びを極めたら・・・副業になっちゃいました ◎知ると人生が楽しくなる!大人の「教養」入門 ≪目次≫ ◆Part 1 人生がどんどん面白くなる!大人の勉強スタイル ◆Part 2 何歳からでも遅くない!人生逆転の勉強法 ◆Part 3 英語力がアップした人のイマドキ勉強法 ◆Part 4 一生稼げるスキルは“本業”以外で磨く! ◆Part 5 今、身に付けたい 最新・教養Lesson
-
3.0デロイトグループのグローバルな戦略コンサルティングを担うモニター デロイトでは、挑戦的な事業構造の変革と機動的な事業展開を実現するための組織再編を多数手掛けている。その中で、組織再編が成功に至ったケースと組織再編は行ったものの成果を得られなかったケースを比較分析してきた。 本書は、日本企業が組織再編を通じて変革に成功した事例を要因分析し、手法・行為としての組織再編にとどまらず、経営課題の解決と効果創出に直結する組織再編について、個別手法にとどまらず幅広い手法に関して一貫性をもって解を示していくことを目指した。組織再編の実行局面におけるコンフリクトマネジメントやコミュニケーションの難しさを踏まえた実効性の伴ったアプローチを示す良書。 著者 Strategic Reorganization グローバル化・デジタル化をはじめとした産業構造・事業環境の大きな変化と不確実性への機動的対応、持続的な 成長と企業価値の向上を実現すべく、戦略推進、成果創出のための基盤構築に向けた組織再編を支援する専門チーム。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●技術は発展すれど、便益、意義の議論は不十分。経済学的にアプローチする モビリティイノベーションの進展はめざましい勢いで進んでいる。CASE(「つながる(connected)」「自動化(autonomous)」「シェアリングとサービス(shared & service)」「電動化(electric)」)革命という言葉も登場し、「こういうことが実現できる」「こういうことが便利になる」という近未来が語られることが多くなった。 一方で、それが世の中に具体的にどのような便益を提供し、意義があるのかを理論化、モデル化した本はほとんど存在していない。本書は経済学を使ってその答えにアプローチする。 ●ゲーム理論やマーケットデザインが制度設計に有効 モビリティ革命の利便性を享受するためには、個人の情報の開示が欠かせない。オープンになったデータが増えるほど、分析力が増し、生活の利便性も大きくなる。一方で、「自分だけは情報を開示したくない」という人もいる。このとき、その人の利得(効用)はどうなるだろうか? この場合は、ナッシュ均衡に代表されるゲーム理論の考え方が有効になる。 また、シェア経済(ライドシェアなど)の進展には、マーケットデザインの考え方が欠かせない。マーケットデザインでは、自分も選ぶが、相手も選ぶことが前提になっている。「誰がどこへ行きたいのか」「誰がどこまで乗せたいのか」のマッチングが重要となる。一方で相乗りとなると対象者が複数になり、最適解も複雑になる。今後、自動運転が実現されれば、運転手がいない相乗りも可能になる。社会的に一番効用が大きいマッチングを導き出すのも、経済学の役割だ。
-
-SDGsやESGなど、企業経営にとって社会貢献が大きな課題である今「社会に資する経営手法」を解き明かす1冊 日本の経営学の権威である一橋大学名誉教授の山城章氏が創設した山城経営研究所は、日本の文化や習慣を生かしながら、豊かな社会づくりに貢献し世界で通用する経営手法「山城実践経営モデル」の普及に努めている。 同モデルが示す理想的な経営は、まず、社会のニーズを社会問題や地球環境を含む広い視点で捉え、経営リーダーが経営を通じて社会に提供すべき価値を自身の信念として持つ。その上で、経営組織を効果的に機能させるために、経営リーダーは自身の「理念」を企業全体で共有し、効果的な「ビジョン・戦略」を立て、機能的な「戦術」に落とし込み、それを効果的に遂行できる「組織」を編成。そして、それらが十分に機能していることを把握するために「パフォーマンス管理」を行う。 こうした経営手法は、SDGsやESG、ステークホルダー資本主義といった、これまで以上に社会貢献を求める現在の経営ニーズに合致している。本書では主に、「社会」「経営リーダー」「経営組織」の三つの側面から、経営者が今実践すべき経営手法を解説する。
-
-●優れたビジネスモデルの真実を解明! 環境の変化に上手く対応し、自らを変化させることが出来るようなビジネスモデルは、稼働するなかで徐々にビジネスモデルの様相が変化していく。多くの本では当初の設計ばかりに目が向き、より重要であるはずの変革し、自走し続ける仕組みの解明がなされていない。本書では、ビジネスモデルづくりのプロセスを「設計」「駆動」「変革」「自走」の4段階に分け、それぞれどんな状態なのか、実現させるためにどのような工夫がなされているのかを説明する。設計ばかりに注力し、後工程を軽視する企業のビジネスモデルは決してうまくいかない。 本書の解説に織り込まれる事例は、エフピコ、宅急便、セブン-イレブン、セブン銀行、俺のフレンチ、東レ、Amazon、テレビ通販、デル、ホンハイ、ブックオフ、グーグル、良品計画、ニトリ、サンリオ、ヒロセ電機、ミスミ、しまむら、ウォルマート、コマツ、江崎グリコ、ユニクロ、ライフネット生命、アスクル、など多岐にわたり、説得力が高い。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 SDGsがターゲットとする2030年に向けて、日本でも関連各省による広報活動などによって、企業における取り組みはもちろん、各自治体が地域の企業や住民とともに主体的に進める活動が増えています。 本書は、「SDGs 」について最低限知っておきたいトピックスを広く取り上げ、1 つのトピックを原則1 ページで簡潔にわかりやすく解説しています。SDGsとは何かに始まり、目指す未来と現状、世界や日本のアクションといった大きな動きを説明した後で、企業の経営への取り入れ方や、各個人の日々の生活でどのようなことを行えばSDGsが掲げる目標達成ができるかということを説明しています。この1 冊を読めばSDGs の全体像を把握することができます。 また、15 のワークシートを用意して、気になるキーワードを深く調べたり、関連テーマまで範囲を広げて自身で学ぶことができるため、企業研修や大学などの教育現場でのテキストとしても活用することができます。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「働き方改革」の大合唱の中、企業の現場では労働生産性の向上が至上命題に。 成果を出しながら時短を進めるためにはどうすればいいのか? 時間のマネジメント、整理、コミュニケーション、ミス防止、集中力の向上…などの視点から、著名経営者などが実践する「セルフ働き方改革」のためのテクニックを一挙公開!
-
3.9名著『道具としてのファイナンス』『ざっくり分かるファイナンス』の石野雄一氏による人気セミナーが、書籍となって登場! ! 講義調のわかりやすい解説で、難しいファイナンスがすっきりわかる。 【著者からのメッセージ】 この本は私の1日のファイナンス講義をできるだけ忠実に再現し、さらに肉づけしたものです。 この講義は、専門家ではない普通のビジネスパーソンに向けたもので、最低限これだけは知っておいていただきたい点に絞っています。数式はできるだけなくし、ファイナンスの考え方をご理解いただけることに主眼をおきました。 この本の内容をマスターすれば、ビジネスの世界では生きていけるでしょう。
-
3.0
-
3.9
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 どうする?老朽インフラ PPP/PFI成功の秘訣 ・PPP/PFI推進アクションプラン、インフラ長寿命化計画ほか、政府方針を担当官が詳説 ・先進自治体の市長にインタビュー――富山市、和光市、須崎市 ・インフラ輸出でこう稼ぐ ・日本全国PPP/PFI 9つの成功事例に学ぶ ・コンセッション(公共施設等運営権制度)の最新事情 日本全国で、インフラの老朽化が深刻な問題となっています。橋の崩落や道路の陥没、水道管の破裂といった事故が各地で起きているほか、耐震強度不足で使用できなくなる公共施設も出ています。近年相次ぐ地震や風水害など災害への備えも懸念されます。 本ムックは、老朽インフラ問題の現状を見た上で、政府が進める政策を詳しく解説。PPP/PFI推進アクションプラン、公共施設等総合管理計画、インフラ長寿命化計画など重要な施策を、各省庁の担当官が説明します。 また、コンセッション(公共施設等運営権制度)の最新事情や、PPP/PFIを活用した先進自治体の成功事例も多数紹介。 近年、注目されている海外へのインフラ輸出についても取り上げます。
-
-ウェルビーイングがホットな経営課題として注目を集めている。働く人がウェルビーイングな状態にあると、創造性が3倍、生産性が1.3倍高まる一方で、欠勤率が4割、離職率が6割、そして労働災害が7割減るという。加えて、ESGやSDGsへの取り組みと軌を一にし、企業価値の向上や優秀な人材の確保にも直結する。それだけに、経営者や管理者にとってウェルビーイングは今すぐ実践すべき最重要テーマとなっている。 では、働く人のウェルビーイングをどうやって高めたらよいのか――。実は、2022年現在で全世界から約1万1000社の企業が参加する取り組みがある。「人々の安全、健康、ウェルビーイングを第一優先にすることにより、職場におけるあらゆる事故、疾病、災害を防ぐことができる」という哲学に基づく国際的な予防活動「ビジョン・ゼロ」だ。ウェルビーイングは、安全、健康という土台を築いてこそ到達できるゴールなのである。 本書は、企業におけるウェルビーイングとは何かを解き明かし、ウェルビーイングを実践するための最強メソッドであるビジョン・ゼロを世界中で推進する専門家が実践事例や技術動向を交えて解説する。
-
3.0理論から実践まで、すべてがわかる決定版! コロナ禍によるリモートワークの広がりを受け、 「対面」が主流だった営業現場もデジタルシフトが求められている。 しかし、単純にMA・SFAを導入するといった話ではなく、 根本的に営業プロセス全体を見直す必要があるため、現場の抵抗感は強い。 本書は、そうした逆風を乗り越えて、 営業とマーケティング活動全体をデジタル化していく方法を、 具体的なケースを使いながら解説する。 ◎本書の特徴 ・デジタルシフト/DXを進めるための手順から、つまずきのポイントまでをカバー ・さまざまなステークホルダーの視点から解説。自社の導入の際に役立ちます ・リアルなケーススタディを詳細に紹介 ・システム投資を行う前に検討すべきポイントを網羅。予算の立て方から変えられます ・標準的なモデルを複数解説。幅広いビジネスモデルの企業に応用できます ◎「変革ストーリー」を詳説 【ケーススタディ1 NEC】各社のベンチマークとなったチャレンジ 【ケーススタディ2 ソフトバンク】商材が多角化する時代の営業戦略 【ケーススタディ3 JTB】コロナ禍以前に始まっていたデジタル基盤の構築
-
4.3★カスタマーサクセスの壁 ★読めば分かる疑似体験本 「カスタマーサクセス」という言葉を聞いたことはあっても、実践している人はまだまだ少ないのが実情です。本書は、「カスタマーサクセスは知っているが実践したことはない」という人に向けて書いています。 BtoBサービス企業を舞台に、上司の命令でカスタマーサクセスを担当し、最初は1人で、やがてチームをつくり、部署ができ、最後は新規事業の責任者になるまでを描いています。主人公の経験をドキュメンタリーで追い、困ったときに教えてくれる専門家の解説で実践的に知識が身に付く仕立てです。 カスタマーサクセスを実践するとどんな問題が発生し、それを乗り越えるにはどういう順番で何をすればいいのかを詳しく解説します。体験して学んだことは忘れないもの、たとえそれが疑似体験でも効果は大きいと思います。 「カスタマーサクセスに挑戦したい」と志す、ビジネスパーソンの力になってくれる1冊です。
-
-内部監査の概念を変える「価値創造監査」を紹介! コーポレート・ガバナンスの制度が整っても、なぜ企業不祥事が続くのか? あらゆる組織の統治機能をチェックし、企業価値を高める新しい経営管理手法を解説! ●2015年の会社法改正、コーポレート・ガバナンス・コードの適用から1年が経ち、新制度は急速に普及しました。しかし、その後も三菱自動車、東洋ゴムなどで不祥事が頻繁に起こっています。「コーポレート・ガバナンスの優等生」と言われた東芝は、なぜ誤ったのでしょうか。 ●組織のガバナンス(統治)を担保した強い経営=ガバナンス経営を実行するための最強ツールが、攻めの経営監査である「価値創造監査」です。これは従来、経営者の耳目であった内部監査と異なり、経営者に対するコンサルティング機能とガバナンス監視機能が十分発揮されたものです。 ●ガバナンスの効く組織の作り方、組織運営、チェック機能、リスク管理とリスクを取らせて企業価値を高めるための手法を解説します。 ●他の上場会社に先駆けて委員会設置会社に移行したパルコで、セゾングループ内でのグループ経営ガバナンスに邁進した著者による実践書。企業のみならず自治体や学校、NPOなどあらゆる組織の運営に役立ちます。
-
4.0
-
4.5次の投資戦略を 膨大なデータから掘り起こす! 本書は金融におけるデータ分析業務(資産運用、金融におけるリスク管理、金融マーケティングなど)がビッグデータの登場により、どのように変わってきたのかを概観。 さらに、これらのデータを活用することでどのような知見が得られ、どのようにビジネスに活用できるのかを豊富な具体的分析例を交えつつ解説する。金融データ分析のプロフェッショナル(データサイエンティスト)の視点から、新しいデータを活用した独自の切り口での分析結果をていねいに説明する。 【本書で取り上げる事例】 ・有価証券報告書からデータを抽出し、企業間の関係情報をビジュアル化する ・ある企業に生じたショックが関連企業の株価に与える影響の速度(タイムラグ)を分析 ・連邦公開市場委員会の文章が何を話題にしているのかを機械にテキスト分析させ、金融政策の「見通し」をスコア化する ・「政府」「中央銀行」「マスメディア」「民間エコノミスト」「市場関係者」「一般人」が発信する多種多様なデータを統合し、マクロ経済分析(経済環境のリアルタイム評価)を行う など
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆人材の価値を最大限に高め、企業価値を向上させる! 企業を構成するヒト、モノ、カネ。その根本である人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値向上につなげる人的資本経営。日本では2021年以降注目され始めました。 また、企業が持続的に成長を続けるためにも、社員の働きがいや働きやすさをどう高めるかに目を向け、企業課題と社会課題をともに解決することが重要になってきました。 投資家や就活生などに向け、人材の活躍・育成状況の情報開示を行う動きも活発化してきています。 ◆人材戦略をどう経営戦略に結び付けるか、人的資本経営の実践法を解説 しかしながら、日本における人的資本経営は始まったばかりであり、一部の先進企業を除くほとんどの企業が模索を始めた段階です。 本書は、自社の現在地の把握から先進企業の事例紹介まで、人的資本経営の実践方法を解説します。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 気鋭の公認会計士がブログサービスのnoteに連載して異例の反響を呼んだ有料記事「資本政策の感想戦」と「資本政策の定跡」を大幅に加筆修正した、スタートアップ向けファイナンス指南の決定版。 取り上げたのは、新規株式公開した以下の6社。プレイド、スペースマーケット、Gunosy、 Sansan、UUUM、ニューラルポケット。 この6社の資本政策、すなわち株式や新株予約権を最適に活用するための計画を「設立から上場までに行った全資本取引」、プレイド21回、スペースマーケット14回、Gunosy19回、Sansan30回、UUUM18回、ニューラルポケット19回、合計121回を「資本取引の影響」と「増加株式数内訳」に分けて詳細に解説している。 スタートアップ向けのファイナンス本としては、磯崎哲也著『起業のファイナンス』など良書はあるが、本書は上場までのケーススタディ集として類書が皆無の超絶ファイナンス本。
-
4.5
-
3.0Uber、Airbnb、Spotify… 従来の常識を覆す企業が続々誕生する 「破壊的イノベーション」の時代を生き抜くための処方箋 日本の企業が停滞感を打ち破り、イノベーションを起こすため、社外の知恵を取り入れるオープンイノベーションへの取り組みは待ったなしです。 本書は、ベンチャー企業の支援を中核とし、「Morning Pitch」などを通じた大企業のオープンイノベーションによる新規事業創出支援の豊富なノウハウを持つ著者が、オープンイノベーション実現の必須要素を1冊にまとめたものです。 イノベーション先進企業のインタビューを豊富に盛り込み、どうすれば社内を変え、活力ある現場を実現できるのかをリアルに紹介します。 はじめに Chapter1 日本企業のオープンイノベーションはなぜうまくいかないのか? Chapter2 オープンイノベーションを受け入れる土壌づくり Chapter3 オープンイノベーションの仕組みを構築する Chapter4 オープンイノベーションの仕組みを軌道に乗せる Chapter5 ベンチャー企業とうまく連携する Chapter6 取り組み始めた業界の現状を知る おわりに 【先進企業インタビュー】 ヤマハ/オリンパス/NTTデータ/東京放送ホールディングス ソニー/東京急行電鉄 ほか
-
-【多様性を活かした強いチームをつくる知恵が満載】 年齢、性別、国籍、文化、企業や職務上の背景などが異なるメンバーがチームに共存するダイバーシティ(多様性)。多様性の高いチームはうまく運営できれば最も革新的で効果が上がるが、その運営ノウハウはまだ日本では定着していない。本書は、チームビルディング、インクルージョン、心理的安全性、発言機会平等性、フィードバック、コンフリクト緩和、ミディエーションなど、ダイバーシティを活かすマネジメントに必要なツールやスキルを、20 年以上にわたる教育・研究実績にもとづいて日本企業目線でわかりやすく解説する実用的なテキスト。
-
4.0・顧客ニーズを起点にした高収益新商品開発の作り方を、ニーズ収集から、ビジ ネスモデル構築、新商品開発を経て発売後評価へ至る一連の流れに沿って実践的 に解説。 ・顧客ニーズをどのように収集し、それをどのように集合化し、新商品として仕 立てていくか。それをどのようにブラッシュアップし、高収益化を図っていく か。そして、それをどうやって実現させていくかといった、新商品開発のプロセ スにおける「困りごと」を事例を交えながらわかりやすく説明。 ・併せて、高収益商品を永続的に開発するための組織作りについても、仕組みと 組織の両面から解説。 ・顧客ニーズを管理する「ニーズマネジメントシステム」、「商品仕様のマネジ メント」など新しいマネジメントシステム、「困りごとの構図設計」「開発仕様 優先管理表」など実践で使えるシートも掲載。 ・キーエンスでの実務経験を、全221ページの本文と106個の図表に盛り込んだ、 新商品企画開発に携わっている人には必携のマニュアル本。
-
3.6
-
4.0
-
4.0「あのデータはどこにある?」「最新のデータが使えない」「個人情報は危なくて扱えない」――。データを活用しようにも、こんな悩みをお持ちではないでしょうか。これらの悩みは社内でデータを適切に管理できていないことに起因します。データ活用の成熟度が高い企業ほど収益力が高くなるとの調査結果があります。データ活用に不可欠なのがデータマネジメントです。変化し続ける時代はデータマネジメントをスピーディーかつ柔軟に実行できることがデータ活用を成功させる必要条件となります。いまや企業情報システムはクラウドの利用が一般的になり、データもまたクラウド上で扱われます。本書はデータマネジメントの内製支援のコンサルティングを手がける筆者が、クラウドを利用してデータマネジメントを高速化してきた実績を基に、特にクラウドを活用した取り組みに焦点を当ててデータマネジメント業務を解説します。データを活用するための人と組織の在り方から、データ活用に必要となる環境の整備、データの管理手法に至るまで、クラウド時代の実践的なデータマネジメントを知る一冊です。
-
4.0ロジカルシンキング・フレームワークは不要! どんな職場の問題も「スタート・ゴール・やり方」の三角形にあてはめるだけでスイスイ解決。超納得の問題解決手法。 現実のビジネスシーンで直面する様々な問題を解決する上で多くの社員に不足しているのは、「知識」や「経験」ではなく「考え方」である。中堅の組織を中心に足かけ10年にわたりコンサルティングや研修を手掛けてきた筆者は、適切な「考え方の考え方」がないまま場当たり的に解決しようとしたり、表面的な知識やフレームワークをビジネスの場に応用したりして、結局、問題が解決されないままでいる状況をいやというほど見てきた。 特に、現実のビジネス上の問題は「正しい答」や「一つの答」があるわけではない。様々な制約の中で最適解を導き出す道を見つけ、解決のための行動をとることが求められるのだ。そこで「考え方」の基礎を設定し、どんな問題でも一定水準の解決と行動ができるようになればよいという発想で生み出した問題解決法が「トライアングル式問題解決法」だ。 問題解決につまずく原因の多くは、実はきわめてシンプルで、「何から手を着けていいかわからない」というところにある。そこで、トライアングル解決法では、問題に対して「スタート」「ゴール」「やり方」の3つの枠組みを設定。さらに、スタートは「事実」「原因」「制約」、ゴールは「数値」「金額」「期限」、やり方は「計画」「実行」「評価」とそれぞれ3つの要素に分解することで、取り組むべき課題を「見える化」する。スタートで現状を整理し、同時に目指すべきゴールはどこかを明示することで、問題解決の考え方の「考え方」がわかるという、これまでありそうでなかった、誰にでもできる手法なのだ。 本書は、具体的な例題で、この「3×3のテーマ」にどのように取り組めばよいのか、実践的かつ簡潔に解説していく。問題解決は、ビジネス書の定番テーマ。新しい考え方として、ロジカル・シンキングなどに挫折してしまった、もしくは役に立たないと感じている人に是非、読んでほしい一冊である。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 仕事に欠かせない「数字」 自信、ありますか? ビジネスの現場は、数字を使うシーンであふれています。 「その数字に妥当性はあるのか?」 「そもそも、その数字から何が読み取れるのか?」 「その割合はどのように求めているのか?」 こんなふうに問われたとき、頼りになるのが「ビジネス数学力」です。この力を養うためにピッタリなのが、日本数学検定協会が開発した「ビジネス数学検定」です。 ビジネスパーソンに必要な数学力・数学技能を測定する検定で、ビジネスで特に必要とされる数理的な考え方を「把握力」「分析力」「選択力」「予測力」「表現力」の5つの力に分類し、さまざまなビジネスシーンを想定した問題を通して測定します。 ビジネス数学検定は3階級に分かれており、本書は新入社員や学生を対象にした「3級」試験の公式テキストになります。 ※本書は「実践!ビジネス数学検定Lite」の改訂版になります。
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ビジネスの現場は、数字を使うシーンであふれています。入社して3~5年にもなると、求められるレベルは新人のころと明らかに違ってきます。 ・利付債券の最終利回りを求める ・自己資本と当期純利益からROEを算出する ・損益分岐点売上高を求める ・単利と複利の計算を速やかに行う ・提携先企業を数字に基づいて選定する ・株価収益率に基づいて割安な株を見分ける こうしたシーンが毎日のようにやってきます。リーダーはこうした数字に強くなければなりません。 本書は、リーダークラスの人や、リーダーを目指す人たちに向けた「ビジネス数学検定2級」の公式テキストです。ビジネスパーソンに必要な数学力・数学技能を測定する検定で、ビジネスで特に必要とされる数理的な考え方を「把握力」「分析力」「選択力」「予測力」「表現力」の5つの力に分類し、さまざまなビジネスシーンを想定した問題を通して測定します。 ぜひ本書でビジネス数学力を身につけ、数字に強いリーダーになってください。 ※本書は「実践!ビジネス数学2級」の改訂版になります。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆『成功企業に学ぶ 実践フィンテック』のビジュアル版 2017年3月に発行した書籍『成功企業に学ぶ 実践フィンテック』をムック化します。書籍の原稿を大幅に編集・加筆・修正し、さらにビジュアル化することで、フィンテックの最新モデルをわかりやすく解説します。変化のスピードが速い業界であるため、ほとんどの記事は書き下ろし。書籍を購入した読者にも満足いただけます。 ◆コンテンツをパワーアップ ムック化の最大の売りは、フィンテック企業20社へのトップインタビュー。10月に上場を果たしたマネーフォワードをはじめ、ウェルスナビやfreee、Origamiといった注目企業の最新動向を浮き彫りにします。 さらに、編著者であるSBIグループのトップ北尾吉孝氏と有識者による対談や、「仮想通貨」の特集を新しく追加し、フィンテックの旬をしっかりとおさえた充実した内容になっています。
-
4.1今の人工知能(AI)を正しく理解して活用し 導入効果を最大化するAIビジネス書の決定版 AIブームはとどまるところを知らず、企業や組織はAI活用の実践フェーズに突入しつつあります。一方で、AIに関する様々な誤解がいまだに蔓延しており、深層学習(ディープラーニング)をはじめとする「今のAI」をどうすればビジネスに生かせるかの理解も進んでいません。 AIは非常に大きな可能性を秘めています。今のAIを効果的に活用すれば生産性やROI(投資対効果)の劇的な改善につながります。一方でAIは癖のある道具であり、使いこなすには正しい理解と十分なノウハウが欠かせません。 本書は30年以上にわたりAIの開発や導入・活用を手掛けてきた筆者が、AIのビジネス活用に必要なすべてを具体的に解き明かす待望の一冊です。今のAIで何がどこまでできるのかにはじまり、AI活用の進め方や評価方法、データを確保する手順、ハードやソフトの選び方、人材育成のやり方までを豊富な実例で具体的に説明します。 今がAI導入の絶好のチャンス。ここで決断しないと、国内外のライバルに後れを取ることになりかねません。自社のAI活用に取り組むIT部門や経営企画部門、業務部門、顧客企業のAI活用を支援するベンダーやコンサルタントなど、AI活用に関わる人必携の一冊です。
-
3.0DX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組むほとんどの企業が直面するのがデジタル人材、DX人材の不足だ。優秀な人材は引っ張りだこの状況で、外部からの採用は非常に難しい。今、企業がDXを成功させるために必要なのは内部の人材を再教育し、DX人材とすること。リスキリングが強く求められている。ただデジタル技術によって企業を変革させるDX人材のリスキリングは、デジタルやIT技術を教えればいいというものではない。変革の道筋を可能にする「ビジネスの仕掛け」を学ぶことがDXを成功させるリスキリングの最も重要な一歩になる。本書は、住友生命でDX推進に関わる筆者が、DXを成功させる17種類の「ビジネスの仕掛け」に加え、DXのビジネス企画のケーススタディー、リスキリングの対象人材と内容、方法と研修事例、リスキリングを成功させる「9つの学びの仕掛け」までを解説する。DXを進め、DX人材不足を解消するために必読の1冊。
-
4.3接し方を変えればうまくいく! 既に8000人のマネジャーが実感してきた、リモートでも対面でも、たった15分で部下との信頼関係を構築できる、超実践的コミュニケーション術。 自らの業務・ノルマを抱えながら部門を預かるマネジャーのほとんどは、「部下とのコミュニケーション時間が十分取れない」「考えていることが分からない」「ハラスメントが恐い」など、信頼関係の構築に悩みを抱えている。「働き方改革」の時代には最早、昭和の「飲みニケーション」も通用しない。さらにはリモートワークも定着し、これまで以上に部下とのコミュニケーション、チームのマネジメントに大いにストレスを感じているはずだ。 そこで注目されるのが1on1ミーティングである。上司と部下が定期的に1対1で対話をし、相互のコミュニケーションを高めるもの。自由に話し合うことで、部下が目指すキャリア、抱える悩みを把握し、そのサポートを通じ自立と成長を促す手法だ。 ただ、評価者である上司から部下への一方的なコミュニケーションになりがちな人事面談や目標管理面談と変わらないケースが多く、効果が出ていないのが現状といえる。 本書は、これまで8000人(2020年末時点)のマネジャー相手の研修実績を持つ筆者が、永続的な企業の発展に繋がる1on1ミーティングの本質や具体的な方法を解説するもの。理屈ややり方(技術・段取り・質問の仕方)ではなく、実践から導き出したあり方(気持ち・信頼・人間力)の問題を重視し、精神論ではなく具体的な方法論に落とし込んだ、まさに悩めるマネジャーに向けた一冊である。
-
3.8「会計=専門知識」というイメージを打破。従来の会計書ではわからない会計の本質を理解する入門書 最近では,日々の新聞や雑誌,ニュースなどで「ROE」や「キャッシュフロー」といった会計用語が頻繁に登場する。しかし,どれほどの人がこれらの会計用語を理解しているのだろうか。営業利益と経常利益の違いは,と問われたときに,その言葉の意味は理解していても,それが企業会計にとってどのような意味をもつか,答えられない人が大半であろう。筆者は,会計とは,いまや専門家が知っていればよい知識ではなく,ビジネス界の「コミュニケーション・ツール」であり,会計を学ぶことは「ビジネス・ランゲージ」を手に入れることだという。 本書は,単に貸借対照表や損益計算書とは何かを解説するのではなく,不況のトンネルから抜け出さない日本経済の問題点を指摘しつつ,企業会計の本質を平易に解説している。「日産自動車とトヨタ自動車の違い」「マクドナルド100円バーガーの成功」など身近な事例を豊富に取り入れ,全編語り口調でまとめるなど,会計の素人にとっても理解しやすい構成でまとめられた好著である。
-
4.3●最新の領域をカバー。実務を優先して記述。 本書はMBA講座にも古くから取り入れられている「経営戦略」「事業戦略」の新しい教科書。すでに類書も多く出版されているが、本書には以下の特徴がある。 1最新の戦略の議論をカバー 多くの戦略の教科書がいまだに80年~90年代の米国の学説を中心としたものであるが、本書はその後の経営戦略の議論をカバーする。デル・モデルの登場に端を発し最近のプラットフォームの議論に至るビジネスモデル論や、最近のイノベーションの議論、さらには、戦略の実現過程を扱うストーリー論に至るまで、戦略の議論には多くの教科書がカバーしない領域が増えている。これらのテーマを単独で掘り下げた書物は数多くあるが、それらが戦略論全体の体系の中に位置づけられていなかった。本書ではこれらを網羅的に解説する。 2実務領域を広くカバー 多くの戦略論の教科書は学説をベースとしたものであるが、本書は、実務を優先して記述する。大和ハウス、P&G、TBCなど、実例をあげて紹介。新興国などの市場に他社に先駆けて参入することは、インドの自動車市場へのスズキの例を挙げるまでもなく、多くの利益をもたらすものと実務では考えられているが、学説からはその重要性の指摘を聞いたことがないなど、実務と学説にはいささかのズレがある。それは、これまでの本では、戦略を導出する分析手法(フレームワーク)の解説が中心で、実際の戦略は何なのかは、よくわからずじまいだったからだ。理論上の分析は内部資源に偏ることが多いが、上記スズキの例のように、実際には、外部環境の分析から戦略は導かれることが多い。 本書は、多くの経営者や企画担当者に、実務上考えなければならない視点を提供する。
-
-
-
4.0日の丸規格の国際標準化交渉で連戦連勝だったソニーの凄腕交渉人の手記。この人がいなければ、Suicaの国際標準化はなかった。 日米欧の企業が激突する国際交渉の舞台裏を赤裸々に描いたノンフィクション。以下は、本書「まえがき」から。 本書は、ソニーに勤務していた「交渉人」の私が当事者として経験した日の丸規格の国際標準化の舞台裏を、ソニーのフェリカ(JR東日本のSuica)、デンソーのQRコード(二次元バーコード)、東京電力のUHV(1100キロボルト超高圧標準電圧)について初めて明かすノンフィクションである。 国際標準という言葉は一般には馴染みがないかもしれないが、たとえばSuicaという便利な交通用のカードは、私たちがあらゆる交渉のテクニックを駆使して反対勢力の裏をかき、多数派工作に成功していなければ、国際標準化に失敗していまほど広く普及していなかったかもしれない。 そう考えると、意外に身近に思えるのが国際標準なのだ。 誰もが知っている典型的な国際標準は、長さや重さ、時間などの計量単位の度量衡標準である。その他、ネジのサイズやピッチ、各種標識なども国際標準だ。 これらの標準がなければ、私たちの社会生活は大変不便になる。 (中略) 国際標準化という企業同士が争う戦場で力もカネも技術もない日本が勝利するのは、絶望的な状況になった。米国も欧州も中国も、すでにマイナーな日本の味方ではない。 本書で取り上げた事例は、日本にとって最後の輝きだったのかもしれない。」
-
3.4自動車産業はこれから20年間に、ガソリン車の発明以来100年以上なかった巨大な変化に見舞われる。その原動力となるのが自動運転技術だ。すでに一部の機能は実用化が始まっているが、これが広く普及することで、社会のありようは大きく変わる。「クルマを所有しないことが当たり前になり、免許のない人や高齢者でも低い料金でどこにでも移動でき、しかも交通事故も交通渋滞も激減し、駐車場も不要」という、「見たこともない社会」の実現につながる。本書では、なぜこうした変化が起こるのか、社会はどう変わるのか、自動車関連産業および周辺産業はどんな影響を受けるのか、自動運転社会はどんな道筋を通って実現するのか、自動車技術に詳しいジャーナリストが予測する。
-
-組織の生産性向上の切り札として注目されるRPA(Robotic Process Automation)。専門的なプログラミングなしに、面倒な定型業務や反復処理をコンピュータが自動実行することによって人間を定型業務から解放し、より創造的に働くことのできる時間を生み出します。 本格的なDX時代到来と共に中小企業、零細企業まで普及が進むRPA。しかし多様なRPA製品の選定の仕方や、小規模組織が挫折することなくRPA導入を成功させるための進め方については情報が非常に限られているのが現状です。 本書は中小企業を中心にした豊富な導入実績に基づいて、使ってみなければ分からないノウハウや、多数の事例を経験したからこそ分かる勘所、つまづきやすいポイントを懇切丁寧に説きます。 ITの専門知識のない人がどのようにRPAと向き合うか、RPAを出発点としたIT活用組織へのチームビルディングの手法にも詳しく触れ、経営者から現場の業務担当者まで興味を持って読み進められる必携の1冊です。
-
3.2【コロナショック後の自動車産業を徹底分析! 】 ■100年に一度の大変革に直面する世界の自動車産業は、モビリティ産業への変革を迫られている。電動化をはじめとする「CASE革命」の大激変、MaaSへの対応を進めるべく、世界の自動車産業は次々と手を打ってきた。そのさなか、新型コロナウイルスが突如として猛威を振るい、世界は一変した。本書は、業界を代表する人気アナリストが、コロナショック後の自動車産業への影響をいち早く分析し、中長期的な展望を示す注目の書。 ■ 世界の自動車市場は、コロナショック後の短期的な需要急減を乗り越え、驚くほどの急回復を見せつつある。しかし、人々の行動は地域によっては大きく変容し、ディーラーを含めた自動車産業全体に、質的にも量的にも多大な影響を及ぼしつつある。 ■本書は、ウィズコロナ時代の自動車産業における新常態(ニューノーマル)――世界の移動ニーズと消費行動、市場特性の変化を読み解き、説得力のある数字に基づいて先行きを展望する。とりわけ、2022年以降と見られるアフターコロナ時代に向けた構造変化を解説。画一的な世界ではなく、地域の特性により、より多様な状況が現出すると見通す。大きな影響を受ける部品メーカーへの影響も取り上げる。終章では、ハードウェアからソフトウェアへと価値が移行する大きなトレンドの中で、自動車産業に関わる主要産業(OEM、サプライヤー、ディーラー)への指針を示す。 ■各社の2020年第一四半期決算など最新動向を踏まえた展望は、業界関係者や投資家必読。日経ビジネス人文庫『CASE革命』との併読で、自動車産業の将来像が掴める。
-
4.3市場調査もいらない! 割引も広告もいらない! 「顧客」より「自分」が基点の 新・マーケティング論 <主な内容> 【1章】 マーケティングしないマーケティング 1 スマイルズはマーケティングをしない? 2 マーケティングの落とし穴 3 スマイルズが実践する3つのアプローチ(手法) 【2章】 スマイルズのクリエイティブ 1 シーンをイメージすることから始まったスープストックトーキョー 2 スープストックトーキョーの秘密 【3章】 課題設定力が肝 1 課題はアイデアの源泉 2 課題設定の事例 ~つまらないものを“つまる化”させる~ 【4章】 すべてはN=1から始まる ~「顧客志向<自分思考」で価値をつくる~ 1 生活者の視点に立つことがクリエイティブの大原則 2 誰かの心理的構造を捉えると“文脈”が生まれる 3 N=1からの事業の作り方 4 N=1をディープに理解するためのティップス 【5章】 関係性のブランディングの作法 ~短所でもいい。そこに特徴はあるか~ 1 関係性のブランディング 2 各社の事例に見る、関係性構築のためのヒント 3 新たな関係性を構築した2つの事例 4 順調でも関係性を検証し、時には再構築もいとわない 【6章】 スマイルズのブランディング 1 スマイルズが大切にするのは共感的関係 2 ブランドは人である 3 絶妙な距離感 4 感度のスイッチ 【7章】 実践編! N=1の発想で新規事業を生み出す ~本と出会うための本屋「文喫」の場合~ 1 文喫の開発物語~どのように顧客の文脈を作ったか 2 入場料はなぜ1500円となったのか 3 既存市場の盤面をどのように作り替えたか
-
3.3「会社に頼らない生き方をしたい! 」 でも「好きを仕事にしたい…! 」は間違い!? 1万人を超える独立・起業経験者の知恵の結晶! 副業の始め方から事業開始直後まで 各段階でやるべきこと、避けるべきことを徹底解説! 「働き方改革」で増えた自由時間を有効活用したい、 勤め先が副業を解禁した、趣味を仕事にしたい―― 会社勤め以外の働き方に興味を持つ人が増えています。 また、その多くは会社を離れても 「自分で稼ぐことができる力」を身につけたいと考えています。 本書は、副業のはじめかた、事業として継続させるためのHow to、 そして大失敗を避けるための方法について、 豊富な事例をもとに解説します。 「ベンチャー企業家の成功談」や「成功したベンチャー企業の分析」では得難い 「この次の段階では何をすべきなのか」「どのようなトラブルが起こるのか」がわかります。 事業の段階別(目次を参照)に解説しているので 既に副業を始めた人、独立した方にも役立ちます。 ◆章立て 1 「自分で稼ぐ力」を手に入れる人、逃す人【下調べ】 2 会社員から「種目」を変える【心構え】 3 空き時間でとりあえず始めてみたけれど【副業化】 4 5年後の前に今を考えよう【事業化準備】 5 売上の正体【事業開始】 6 順調なスタートダッシュへ【資金調達・手続き】 7 時間は解決してくれない【起業直後】
-
4.5「伝わらない」は、「本音」が言えていないだけ。 「本音」を言葉にすれば、人間関係はもっとラクになります。 心の奥に隠れた“本当の気持ち”を言葉にする方法がわかる本! 「自分も相手も大切にするコミュニケーション術」を、 《(1)自分の本音に気づく→(2)相手の本音を聞く→(3)自分の本音を伝える》 の3つのステップで解説。 心の奥に隠された「本当に言いたかったこと」と、 その上手な伝え方がわかります。 「つい我慢する」「気持ちが伝わらない」悩みもこれで解消。 豊富な事例と練習編で無理なく実践でき、 ビジネス・日常のあらゆるシーンで応用可能です。 ※2016年4月刊行の『本音に気づく会話術』(ポプラ社)に50ページ超の新規加筆、大幅改稿、改題して文庫化したものです。 【目次】 ●第1章:自分の本音に気づく ・「本音」とは自分が本当に大切にしたいニーズ ・グチや自慢話に隠されたもの ・「快・不快の感情」が本音を教えてくれる ・感情にいい・悪いはない ・本音に気づく7つのステップ ・ニーズに気づけば心が穏やかになる 他…… ●第2章:相手の本音を聞く ・聞きながら、頭の中でおしゃべりしていませんか ・「相手を主語」にして聞く ・本音を聞く3つのステップ ・どんな人も、大切にしたい願いは同じ ・本音から遠ざかる10の受け答え 他…… ●第3章:自分の本音を伝える(1)考え方 ・本音を伝える4つのステップ ・職場で本音を伝える ・家庭で本音を伝える 他…… ●第4章:自分の本音を伝える(2)実践 ・どんな「体験」にするかは自分次第 ・相手を責めない話し方 ・意識が変われば行動の質もパフォーマンスも向上 ・具体的に伝える、肯定語で伝える 他……
-
4.0「強欲は善」「素早く動き、破壊せよ」―― 巨大IT企業(ビッグテック)はなぜ邪悪になってしまったのか? その脅威から逃れるにはどうすればいいのか? かつては光り輝く新星とみられたIT企業が、いかにして巨大化し膨大な力を得るようになったか、それによる弊害は何か、その暗黒世界から次世代のイノベーターたちが活躍できる明るい未来を取り戻すための具体的な解決策とは――。 「ビッグテックの闇」から個人や社会に恩恵をもたらす「明るい未来」を取り戻すための方法を著名ジャーナリストが解き明かす。 ◎本書でわかること ・輝かしいIT企業が巨大かつ邪悪になる理由 ・巨大IT企業が膨大な力を得て、それを維持できる仕組み ・個人や社会に恩恵をもたらす「ネットの未来」を取り戻す方法 ◎出版社から 『Don't Be Evil How Big Tech Betrayed Its Founding Principles ― and All of Us』の翻訳がいよいよ登場。 ジョセフ・E・スティグリッツ氏(経済学者/ノーベル賞受賞者)、ショシャナ・ズボフ氏(米ハーバード・ビジネス・スクール名誉教授/『監視資本主義の時代』著者)らが絶賛。 「巨大ITへの規制強化」の流れがなぜ今来ているのかがわかります。
-
-よい意思決定の背後に何が行われていたかを描く12の物語。組織が適切な意思決定をするための重要な要因として、著者は「参加型の意思決定」「分析力」「組織の文化」「リーダーシップ」を挙げます。この四つを大枠にして、うまくいった意思決定の事例を物語ります。 世界最大級の投資信託会社のアナリストが当時人気のあったサブプライムローン債券を推奨しなかったのはなぜか? スペースシャトルの打ち上げを許可するべきか? 成長をめざして本気でホームランを狙うべきなのか?など。危機に直面してみんなが知恵を出し合い、力を合わせて困難を乗り越えてゆく、読後感のさわやかな一冊です。
-
-
-
4.1テレビショッピングでおなじみの「ジャパネットたかた」は、高田明社長が37歳のときに開いた小さなカメラ店からスタート。45歳でテレビショッピングに進出し、今では年商1500億円に達しています。豊かに暮らしたいと思っている人たちに、その願いをかなえる商品の使い方を紹介する。商品の機能よりも、その商品から得られる快適さや楽しさを分かりやすく伝える。高田社長はその名人です。それができるのは、高田社長が伝えることに対して真剣で、一切の妥協がないからです。本書は『日経トップリーダー』などのインタビュー記事を集大成。「話す」「見せる」「考える」「実行する」などビジネスの原則について、高田社長が自ら語った貴重な1冊です。
-
3.5共感の声、続々! 親父の感性、息子のロジック。 やるな、2代目。 ――【サイバーエージェント社長・藤田晋氏】 働き方改革のフロントランナー! ――【ワーク・ライフバランス代表・小室淑恵氏】 リーダーシップは技術で、 誰にでも学べると気づかせてくれる本。 ――【元陸上選手・為末大氏】 ***主な内容 なぜか愛される会社、ジャパネット。 若き2代目社長・高田旭人がロジカルに説き明かす 「アットホームでストイックな会社」のすべて。 ◎ 売れない時代になぜ売れる? ◎ カリスマ創業者が去って成長を続けるのはなぜ? ◎ 「働き方改革の旗手」とされる理由とは? 創業者・高田明の後を継ぎ、過去最高売上高更新中!
-
4.02010年の経営破綻から再生を果たし、2016年3月期には過去最高の営業利益を上げた日本航空(JAL)。再生の原動力となったのは、アメーバ経営・JALフィロソフィの導入により意識改革し「燃える集団」となった最前線の社員たちだ。 会長に就任した稲盛和夫氏の教えを採り入れ、客室や整備、空港などの現場は日々の業務を改め、採算性を改善。また、破綻で失ったブランドと信頼をゼロから再び築き上げるべく、各現場は自社のサービスを見直し、空港や客室での接客の改善や世界一の定時運航、驚きや楽しさのある新たな機内食など、サービスの向上につなげていった。 併せて破綻後のJALでは「人づくり」を重視。新入社員教育から年3回の「JALフィロソフィ教育」、客室訓練、女性活躍、働き方改革まで、JALならではの行動哲学を徹底しつつ、全社員が働きやすい環境を整えるべく取り組んでいる。 生まれ変わったJALで、組織と社員の総合力が遺憾なく発揮されたのが、2016年4月に起きた熊本地震だ。二度にわたる震度7の揺れで熊本空港の発着便がストップし、現地スタッフの1/3が避難を余儀なくされるなか、各担当者はどう動いたのか。 雑誌『日経情報ストラテジー』で大きな反響を呼んだ特集記事に大幅加筆し、稲盛和夫名誉顧問へのインタビューも収録。航空業界を長年ウオッチする専門記者が、取材期間1年以上、対象者100人超に及ぶ綿密な現場取材を基に、JAL社員たちの最前線での奮闘ぶりを追い、リアルな筆致で描写したケーススタディ&ドキュメント。
-
3.9■書籍紹介 / 著者・藤井保文よりメッセージ 「ジャーニーシフト」とは、顧客提供価値が時代によって変質したことを示した言葉です。一文で示すと以下のようになります。 顧客提供価値は、「モノや情報の提供」「瞬間的な道具としての価値」から、ありたい成功状態を実現させ、行動を可能にさせる「行動支援」に変わっている。 これは言い換えると、「ユーザにとって何かしらの行動やアクションを可能にしていなければ、企業として何の価値もない時代」になってきているということでもあります。自分の中でどれだけ受け止め、理解したり解釈したりしても、世の中に対して発信や貢献をし、社会やコミュニティーに干渉しないと、意味がない時代になってきているのです。 本書は、世界の潮流から新たな変化を読み解く本です。社会のビフォアアフターを書いたこれまでのシリーズに対し、提供価値のビフォアアフターを書いたものがこの『ジャーニーシフト デジタル社会を生き抜く前提条件』です。 DXやOMOから、SDGsやパーパス、Web3やメタバースなど、次々と現れるバズワードは、1つの大きな潮流【提供価値の行動支援化】を示しており、その中には2つの特性【利便性の進化・意味性の進化】があります。本書を通してこれらを整理し理解することが、変化の速い時代の道しるべになるのではないか、と考えています。読んでくださった方の仕事や生き方において、さまざまなバズワードに埋もれて身動きが取れなくならないよう思考しアクションしていくための、コンパスや道具になることを願っています。
-
3.8★11歳から学べる「お金の超・基本」★ お金の基本を、子どもに説明できますか? 著者累計100万部突破のFP夫婦が、 漫画と図解で、11歳の息子に教えた お金の「稼ぎ方」「使い方」「増やし方」 年収、社会保険、電子マネー、投資、NISA… 「うちの年収っていくらなの?」 ―― 子どもからそんな質問を受けて困ったという話をよく耳にします。どう答えたらいいものでしょうか。 「そんなこと、子どもは知らなくていいのっ!」などと叱りりつけて、切り捨ててしまうのも気が引けます。これからの社会を生き抜いていくうえで、お金の話は大事。学習指導要領の改訂により、2022年度からは高校の家庭科で「資産形成」の授業がスタートしました。 家庭でも、お金について正しく伝え、子どもにはしっかりとした金銭感覚を身につけてほしいもの。けれど、大人である自分自身、お金のことを正しく理解できているかというと、ちょっと心もとない気がする……。 そんなモヤモヤを解決するためにファイナンシャルプランナー(FP)夫婦がつくった、楽しくてわかりやすいお金の教科書です。大人の入門書にも好適。
-
4.0あなたの住宅ローンの借り方・返し方、実は間違っていませんか? ×「家賃がもったいないので家を急いで買う」 →買うのが遅れても損しません ×「頭金は2割以上入れるべき」 →後で繰り上げ返済に回すほうがいいのです ×「繰り上げ返済はなるべく早めにする」 →貯金がたまるまで待つほうが得策です ×「ママが仕事をセーブしても家計は何とか持つ」 →ローン返済に加えて、将来の教育費が重くのしかかります ×「節約のために家計簿は細かく付けたほうがいい」 →出費を細かく付けてもムダです ×「医療保険は入っておくべき」 →要らないので、ローン返済のために見直し対象にすべき など……。 実際の相談例を基にした、ローンの借り方・返し方の教訓が満載。 「返せるのかどうか」という不安を解消し、ご夫婦の人生をより安心なものにする1冊です。
-
3.7GAFAを規制する動きが世界に広がっている。 「個人情報を握り、独占的な支配力を持つ4社たちは、社会に悪影響を及ぼす」といった批判が噴出。 GAFAの「解体論」も浮上する中、“次の覇者”となる企業への関心が高まっている。 本書では「世界を変える」可能性を秘める次世代のイノベーター100社を一挙に紹介する。 ◆「集中砲火」を浴びるGAFA 「検索やメールサービス、SNS、電子商取引を通じて得た“個人情報”を好き放題に使って金儲けをしている」 そんな批判が強まり、世界各国の政府が規制に乗り出した。欧州連合に加えて、 米司法省や米連邦取引委員会、インドや日本の政府も4社を規制しようとする。 個人情報保護法、独占禁止法などへの違反を問われ、GAFAの「解体論」さえも現実味を帯びている。 ◆“次の覇者”になるのは誰か? 4社の勢いがそがれる中で関心が高まっているのが、GAFAの次に「世界を変える」革新を生み出すベンチャーだ。 AIやソフトウエアなどを活用した技術革新は、コミュニケーション、モビリティー、マネー、ロボット、エンターテインメントなど多様な分野で、同時多発的に発生している。 ◆「世界を変える100社」を一挙紹介 「不老不死研究」「空飛ぶクルマ」「量子コンピューター」「ビッグデータ解析」「宇宙開発」「AI」「ライドシェア」「がん治療」「RPA」。 世界を見渡せば、多様な分野でイノベーションを生み出す多様なベンチャーが強い輝きを放つ。 これからどんな企業が台頭し、GAFAに取って代わるような存在になるのか。 未踏のフロンティアはまだ多い。本書では「世界を変える100社」の実像に迫る。
-
4.0名和高司・京都先端科学大学ビジネススクール教授 推薦! あなたの会社は、10年後に生き残っていますか。 生き残っているとして、現在の主力事業は、そのまま稼ぎ続けていられるでしょうか―― これまでの企業の衰退の事例を見ると、10年前にはその芽が見られていることが多い。 変化の激しいいまだからこそ、小手先の改革ではなく、10年先の長い時間を見据えた抜本的な企業の変革に、すぐにでも着手する必要があるのだ。 本書では、長期の時間軸で強い成長力を取り戻すための戦略を、「時間軸のトランスフォーメーション戦略」と呼ぶ。 抜本的な変革を求めている企業に向けて、経営戦略の構想、シナリオ作りと実行のポイントについて解説。 成功事例を使いながら、アカデミックな理論や著者自身の実務的な経験を交えて、フレームワークとして提示する。
-
4.2●クラフトビール「よなよなエール」はなぜこんなに愛され続けるのか 「よなよなエール」で知られるヤッホーブルーイングが、クラフトビール市場で躍動している。2020年11月期には、18年連続で増収を達成。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で苦戦する大手ビールメーカーがある中、2020年12~2021年2月(第1四半期)も売上高が前年比43%増となり好調が続く。 なぜ同社は、業績を伸ばし続けられるのか。原動力になっているのは実は、ヤッホーが好きで、よなよなエールなどの個性的な同社のビールを愛飲し続けるファンの存在だ。 ヤッホーは、同社製品の世界観(ブランド)や品質、機能に加え、会社の価値観にも共感・支持する人々をファンと定義する。そう。まるで仲間や親しい友人、同志に接するかのように、すべてのコミュニケーションを組み立てているのだ。 その企業姿勢がファンの共感を呼び、さらにヤッホーの応援に熱が入るという好循環をつくり出している。 こうした考え方は、従来のマーケティング手法と比べると異質だ。 しかし消費者の嗜好が多様化し、生活様式も大きく変わり、消費者との間に密な絆を築くことが難しくなりつつある今の時代にこそ求められる、新たな企業と消費者の関係性だろう。 本書は、ヤッホーが約20年間にわたって実践してきたファンを大切にする一連の活動の全貌を紹介するものだ。 著者は、イベントなどを通じてファンづくりと向き合う専門ユニットを立ち上げ、今日ヤッホーが提供している数々のイベントを企画した中心人物である佐藤潤氏だ。次代のマーケティングはかくあるべし。本書を読めば、企業が取るべき次の一手が浮き彫りになる。
-
4.0資産を3億円に増やして40代でFIREを実現した、ろくすけさんの「ゆっくり儲ける投資法」。 「10倍株」を連発した全極意を基本から実践解説。 はじめまして。私は投資歴20 年強の個人投資家 ろくすけ と申します。もともとは会社員でしたが、3 年前、会社員の生涯年収を上回る3 億円の金融資産を確保でき、自宅もキャッシュで取得済であったこともあり、少しばかり早めのリタイアを致しました。最近は全国各地の株主総会を巡る旅を楽しんでおります。 (中略) 多くの人は早急な結果を求めるあまり、売買を頻繁に繰り返すことによって資産を増やそうとします。しかしその方法によって資金面・心理面ともに消耗してしまい、投資を途中で諦めてしまう人が後を絶ちません。 逆に、ゆったりとそれぞれの投資先と向き合い、その稼ぐ力を信じ利用することこそが、実は遠回りのようでいて、多くの人にとって近道であると私は確信しています。まさに「急がば回れ」ですね。 では、ゆったりと投資先に向き合うにはどうしたらいいでしょうか? その鍵となるのは、以下の3 つです。 (1)企業価値の分析 (2)ビジネスモデルの分析 (3)コミュニケーション つまり、「企業価値とビジネスモデルを評価・分析し、素晴らしい企業をその価値に対して大幅に下回る価格で買う」「コミュニケーションを通して自らの「仮説」の構築とその「検証」を繰り返し、自信を持って保有し続けるための拠り所とする」ということです。 本書では、私の経験をもとにそれを実践するための手ほどきをさせていただきます。 (「はじめに」より)
-
4.0もはや、一つの会社、一つの仕事だけに依存することはリスクだ。 自分の時間を未来のために投資し、「10%起業家」になろう。 今の会社をやめずに、夜や週末の時間を利用して、もう一つのキャリアを始める。 そうして得られたスキルや人脈は、誰のものでもない、自分のためのものだ。 リーマンショックですべてを失った著者が見つけた、 「10%起業家」として生きる道を、豊富な事例で解説する。 人生の時間という限られたリソースを、ただ「生きる」ために費やしてはダメだ。 僕たちの命は、現在を「生きる」だけでなく、未来へ向かって「生きていく」ためにこそある。 そう考えると、10%は「余り」ではない。むしろ10%のほうにこそ人生の本質がある。 (日本版序文より)
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ビジネス英文メールでよく使う慣用表現を10分間1レッスンのドリルで学びます。[クイズ]→[解答]→[ポイント解説]→[演習問題]の繰り返しで、英語表現の定型パターンを記憶させるユニット式の構成。ビジネス英文メールの初心者も「少しは書ける」人も、本書を読めばメールの英語に自信がついて、仕事の能率は大幅アップ。言い回しの間違いで思わぬ誤解を招いたり、失礼なメールを送ってしまったりする前に、本書の10分間レッスンで英文メール力をスキルアップしましょう!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 通勤電車の10分、昼休みの10分、寝る前の10分...。たった10分間のトレーニングで仕事のスキルを大幅アップ。ビジネスに必須の論理的な文章力を、10分間1レッスンのドリルで確実に習得できます。[クイズ]→[解答]→[ポイント解説]→[演習問題]の繰り返しで、最重要項目が体の一部に。キーポイントは「簡潔」「正確」「情報伝達力」。反復トレーニングで文章スキルを身に付けて、苦手意識を払拭しましょう!
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 仕事・人生で差をつけるために知っておきたいのが教養。 教養は「身につきにくく、即効性がない」とよく言われますが、このムックはそんな誤解を払拭できます。 ドラッカー、コトラーらによるビジネス名著のエッセンス、経済学、経営学など、成果に直結する5ジャンルのトレンドを中心に丁寧に解説します。 短時間でも理解でき、仕事の成果につながる教養です。
-
4.02030年頃にAIは、人間と同等になったり人間を超えたりはしないものの、人間の知的振る舞いをぎこちなく真似る程度には進歩している可能性があります。人間の知性に近いそのようなAIを手にしたものが、次世代の経済的覇権や政治的覇権を手にするでしょう。 それゆえ、AIの進歩の遅れている日本のような国は没落し、進んでいる中国のような国は飛躍的に経済力や軍事力を伸ばして、覇権国家となるでしょう。AI時代に世界は大きく分岐するのです。 本書は、AIが持つ暴力的なまでの巨大な力の正体と、それが一体どんな便益や害悪をもたらすのかを明らかにします。 AIは爆発的な経済成長をもたらすとともに、多くの雇用を破壊し格差を拡大させるかもしれません。 私達の生活を便利にし豊かにするとともに、私達を怠惰にして堕落させるかもしれません。 犯罪のない安全な社会とともに、人の悪口や不道徳な行い、政府批判を一切許さないような偏狭な監視社会をもたらすかもしれません。 第1章は導入で、第2章以降を読み進めるのに必要な基本的な知識を提供する役割を担っています。 第2章では、AIがどのような技術でどこまで人間の知的振る舞いを真似ることができるのかについて検討します。 第3章では、AIがどのように人々の雇用を奪ったり、格差を拡大させるのかを論じます。 第4章では、さらにそれを経済理論に基づいて議論します。AIによる爆発的な経済成長の始まりを、本書では「テイクオフ」(離陸)と言います。テイクオフの時期には、国によるばらつきが生じます。早めにテイクオフする国々と遅めにテイクオフする国々との間の経済成長に関する開きを「AI時代の大分岐」と呼びます。 第5章と第6章で説明するように、過去に「新石器時代の大分岐」と「工業化時代の大分岐」という二つの同様の開きが生じました。これらの章では歴史的にどのような国や地域が繁栄したかということについても議論します。そのうえで第7章で、「AI時代の大分岐」について論じます。 最後に第8章で、AI時代に人々が豊かになるには、国家が何をなさなければならないのかを検討します。
-
3.5どうしたら自社(自社商品)のファンになってもらえるのか。 企業の多くの人が悩んでいることでしょう。 人気の企業公式Twitterの取り組みからは、その大きなヒントが見つかります。 SNS運用者だけではありません。 マーケターや商品企画、新規事業開発、 PR、広報担当など、さまざまな企業人の参考になる 「ファンづくりの極意」がここにあります。 本書では、セガ、キングジム、タカラトミー、タニタ、東急ハンズ、井村屋の6社の「中の人」に直撃。 具体的な事例を掘り下げながら、ファンに愛される極意を明かしてもらいました。 消費はモノからコト、ヒトへとシフトしています。 企業でありながら消費者から1人の人として見られる 「中の人」はその象徴であり、つながりの接点として重要度が増しています。 企業は消費者とどうつながるべきか、新たな時代のコミュニケーションの形といえるでしょう。 各社のTwitterでの取り組みに加え、佐藤尚之(さとなお)氏と「中の人」6人との座談会の様子もまとめています。 さとなお氏は、熱狂的に支持してくれる「ファン」との関係性をベースに中長期的な売り上げや価値の向上を目指す「ファンベース」という考え方を提唱。 これからの時代になぜファンが重要なのか、企業が愛されるために何をすべきか、ファンベースの視点で「中の人」に迫ります。 今回の「中の人」6人の取り組みは、企業内の「個」の力が いかんなく発揮された好例でもあります。 6者6様の試行錯誤からは、企業の中で自分の力を どう発揮すればいいのかと悩んでいる人の参考にもなるはずです。
-
3.7産業カウンセラーである著者は見た。 メンタル不調者が多発する職場には、同じ傾向を持つ上司が闊歩していることを……。 本書は、部下を不調に追いやる危ない管理職の共通項について説く 2016年に刊行し6万部を突破した同著者の『心が折れる職場』の姉妹作とも言うべき1冊である。 危険な上司は、普段の行動からも見受けることができる。 たとえば、 ・大声で電話する、電話中に席を立っている ・机の上が異常に整頓されていたり、異常に汚かったりする ・服装や食事にまったく関心がない ・どうでもいいことに異常にこだわる こんな兆候のある上司は、危険度が高いという。 本書では、数々の実例から、職場を壊す上司の傾向を語るのみならず、 グレーな上司が君臨する職場で、部下が、あるいは経営者がどう対処すればよいかについてアドバイスを送る。
-
4.0経営目線で考える初めての介護本! 経営者、人事関係者、そして介護世代の会社員、必読。 「休んで介護」は、社員の介護離職につながる。 介護の支援制度と運用は、その会社が社員をどこまで考えているかを映す鏡。 社風改革、信頼感構築に、実は介護支援は効果あり! ワーキングケアラー(ビジネスケアラー)が急増する令和の日本。会社員人生で最大の難題の「親の介護」をどうやって乗り越えて働き続けるのか。会社による介護支援は、単なる「課題解決」ではなく、社員の心理に、ひいては社風に深く刺さる活動です。 日立製作所、大成建設、コマツ、日鉄ソリューションズ、東洋エンジニアリング、大橋運輸。規模も状況もさまざまな企業が、経営者が、HR担当者が社員のためを考えてつくりあげている支援制度を、成功・失敗の経験を含めて具体的に赤裸々に、そして熱く語ります。 会社員が自らの介護を仕事と両立するために、会社が社員の信頼を獲得するために、実際の現場で培われたノウハウ満載の、「初のビジネス目線で描かれた介護本」です。 『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』 『わたしたちの親不孝介護 「親孝行の呪い」から自由になろう』 に続く、親不孝介護シリーズ、第3弾!
-
4.6前人未到9連覇の常勝ノウハウをビジネスリーダーに初公開 2018年1月、帝京大学は全国大学ラグビー選手権で9連覇を達成しました。 大学スポーツは選手の入れ替わりのサイクルが短く、連覇が非常に難しいとされている中、帝京大学は前人未到の記録を更新し続けています。 勝ち続ける秘訣は、岩出雅之監督の「メンバーのモチベーションを最高レベルに引き上げ、どんな状況においても実力を最大限発揮させる」心理学的マネジメントにあります。 トップの指示命令がなくても、メンバー自らが学び、成長し続ける自律型組織を創り上げ、練習の苦しさを「楽しさ」に変える組織風土をつくり上げました。 岩出監督も就任当初は、学生ラグビー界の伝統校である早稲田大学、明治大学、慶應義塾大学にまったく勝てませんでした。 試行錯誤の末、自身の成功体験を捨て、「脱・体育会」など従来の常識を覆す数々の組織改革と科学をベースとしたモチベーション・マネジメントを導入して、単にラグビーの能力を上げるのではなく、創造力と人間力にあふれ自律的に動く人材が育つ組織風土・文化をつくりあげました。 その結果、帝京大学ラグビー部は常勝集団へと変貌を遂げました。 岩出監督のマネジメント手法は、ビジネスの現場でも大いに役立ちます。 本書では、ビジネスリーダーの方々に向けて、常勝集団になるための「岩出メソッド」を初めて公開します。
-
4.5「真のイノベーションを起こしたければ、まず目の前の仕事に情熱を燃やせ!」 7人の起業家が語るビジネスパーソンに求められる「共通解」である。 その真意が、起業家たちの熱い講義と、受講生との質疑応答から浮かび上がる。 早稲田大学ビジネススクールで14年間続く超人気講座の集大成をお届けする。 ◆ なぜ「情熱の仕事学」なのか 成毛 眞(早稲田大学ビジネススクール客員教授) ◆ 東大発ロボットベンチャーをグーグルに売った男 加藤 崇(加藤崇事務所代表) ◆ 「ミドリムシ」に人生を賭け、地球を救う 出雲 充(ユーグレナ社長) ◆ 「NewsPicks」と「SPEEDA」で不合理を撃つ 梅田優祐(ユーザベース共同経営者) ◆ 60代から始めるインターネット生命保険会社 出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO) ◆ 日本初のイスラム・ハラールファンドをつくる 高槻亮輔(インスパイア社長) ◆ 「未来予測」とは何か。「その先」を見通せ 田中 栄(アクアビット代表) ◆ 「WBS」は人生を変える入口だ 根来龍之(早稲田大学ビジネススクール ディレクター)
-
3.5財を得るには「道」がある! 労働価値の向上が企業の持続的な発展に結びつく。住友商事副社長、レンゴー社長を歴任した名経営者の人生哲学! ●本社の了解なく強行した、マレーシア現地スタッフの待遇改善・差別撤廃 ●業界の未来を考え、批判を承知で打ち出した「フルコスト主義」「三位一体の改革」 ●合併後、社員間の深い溝を解消した「2つの労組の統一」「賃金格差撤廃」 ●「派遣切り」「雇い止め」が社会問題になる中、派遣社員1000人を正社員化 ──逆風を恐れず、むしろ力に変え、人を活かし生産性向上につなげた名経営者の哲学を紹介!
-
4.0勝ち組だけが知っている活用法を解明! 価値を創り出し、収益を獲得し、成長するためには、カネ、ヒト、モノだけでは不充分。企業の内部そして外部に存在する情報が不可欠です。とはいえ、情報はそのままでは価値を生み出しません。価値を生み出すためには、必要な情報を企業が受信出来る状況や、必要な情報が価値創造に関わる人々に共有される状況をつくりださなければなりません。いわば、「情報の流れをつくりだす」ことが必要になるのです。 では、インターネットの発展に伴う情報量の増加と、情報の受信・発信の機会の増加は、企業にどのような変化を促しているのでしょうか。いや、受動的にではなく、成長する企業ならばそうした外部環境の変化に対して、何らかの行動を能動的にとっているに違いありません。それらを企業経営の観点から明らかにしようとするのが、本書の目的です。 【情報資源活用のために理解すべきポイント】 ・企業を取り巻く情報の流れについて、その全体像 ・情報の流れを促進し、情報を活用するための企業の取り組み ・企業成長のための情報活用の仕組み ・情報の流れとその活用を阻害する要因 ・情報の流れを活用するために、企業が取り組むべきこと






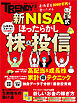
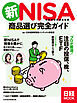

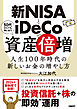
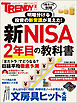





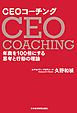

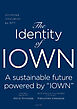






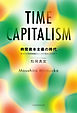





























![[実践] 超高収益商品開発ガイド 粗利80%実現7つのステップ](https://res.booklive.jp/627476/001/thumbnail/S.jpg)












































