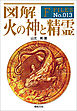伝承作品一覧
-
-【内容紹介】 こだわりを貫く、愛すべき「サービスの達人」たち タイカレーの普及に執念を燃やす食品メーカー社長、活け締め名人とのタッグで極上の鯛寿司を生み出す寿司職人、ミニスカのユニフォームで一世を風靡した理容店女性オーナー……。世間から見れば取るに足らないことに強いこだわりをもって心血を注ぎ、「最高のサービス」へと結実させる人々がいる。そんな“サービスの達人”たちの仕事と人生に迫る11のストーリー。 【著者紹介】 [著]野地 秩嘉(のじ・つねよし) 1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、ビジネス、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。『TOKYO オリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『高倉健インタヴューズ』『トヨタ物語』『スバル ヒコーキ野郎が作ったクルマ』『日本人とインド人』『京味物語』『警察庁長官 知られざる警察トップの仕事と素顔』『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』『図解 トヨタがやらない仕事、やる仕事』ほか著書多数。 【目次抜粋】 第1章 タイ馬鹿一代記 タイカレーを売る男/ヤマモリ会長 三林憲忠(三重県桑名市) 第2章 過疎と戦うジェットコースターDJ社長/シンセン 松田一伸社長(北海道札幌市) 第3章 彦寿司と活け締めの名人/彦寿司 泉明彦(福岡県福岡市) 第4章 長袖シャツの炭焼き焙煎士/ポケットファクトリー 川上敦久(愛知県名古屋市) 第5章 純ちゃんのミニスカ床屋/ニュー東京 小山純子(東京都千代田区) 第6章 モジリニアニの絵に似たアプリデザイナー/くふうカンパニー執行役 池田拓司(東京都港区) 第7章 神戸を色で表現する文房具店/ナガサワ文具センター 竹内直行(兵庫県神戸市) 第8章 津軽の伝承料理を引き継ぎ伝える会/津軽あかつきの会 工藤良子(青森県弘前市) 第9章 幸せを呼ぶリハビリの権威/ねりま健育会病院院長 酒向正春(東京都練馬区) 第10章 人気サウナのサンクチュアリ/神戸サウナ&スパ総支配人 津村浩彦(兵庫県神戸市) 第11章 眠らない握り飯の店/にぎりめし店長 本間直也(北海道札幌市)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 すべては「美味しい!」のために。自然と共に暮らす財前家の端正で前向きな日々。 NHK大分放送局が制作するローカルニュースの1コーナーが、好評を博して全国放送に。その人気番組の出版化。 ドラマや映画で活躍する財前直見さん。一児の母となり、子どもの教育のことを考えて両親が暮らす故郷の大分に移住、仕事は東京、暮らしと子育ては大分という生活を続けている。大分には、財前家に代々伝わる土地があり、そこで40種あまりの野菜と果樹を育てる両親と共に、親子三代にわたって、自然の恵みを味わい、たのしむ暮らしを営んでいる。 長年の経験をいかして様々な食材を育て、収穫する父親、それを美味しく調理・保存する母親、ふたりの勘所や技術をたのしみながら学び、息子へと伝える財前さん。だんだんと畑仕事に慣れ、要領を得ていく息子さん--。番組では、栽培・収穫から調理までのプロセスを追うと共に、家族の中で行なわれる「伝承」の様子を、鮮やかな映像で伝えている。 本書では、季節の食材を使い、財前さんが母親から受け継ぐ料理レシピ(番組で紹介しきれなかったものも!)を中心に、食材の保存法や作り方のポイントを、番組画像と財前さん手描きのイラストで詳しく紹介。「すべては美味しい!のため」と笑う家族の姿をピンナップしていく。また、田舎暮らしのよさや地元の人びととの交流、三世代同居のたのしさなどが伝わるページも収める。 ナチュラルな暮らしを志向するひとはもとより、コロナ禍によって増加した地方移住(希望)者や、それは叶わずとも、そうした暮らし方を取り入れたい都市生活者への、実用的なマニュアルでもある。「シンプルで健やかな暮らし」を切り取り、記録した、穏やかで実用的な1冊。
-
3.7第1話~第4話収録 古代の伝承が残る陸の孤島「赤目村」。都会の喧騒を嫌って赴任してきた青年医師「三沢勇人」は、赴任早々村民同士の対立に巻き込まれる。そんな中起こる事故、明らかになる村に隠された「秘密」、そして三沢自身にも秘められた「秘密」が…。「鈴木先生」武富健治が放つ恐るべき伝奇ホラー・サスペンス、ここに開演…!
-
-インドの伝承医学であるアーユルヴェーダの知恵に学ぶ、幸せなお母さんになるための「こころ」と「からだ」の整え方。妊娠前の準備から、妊娠・出産、あかちゃん・幼小児期との向き合い方、育児に関する考え方や具体的な方法まで、わかりやすく解説。あかちゃんがほしくなったら、妊娠中、産後、育児中、どんなときでもからだを整えることから始めましょう。整えることで、お母さん自身の心身が健康になり、女性が本来持つ「母性」という質がよみがえってきます。他者を育む性である女性のよさを最大限発揮できるようになります。本書では、「白湯の飲み方」「オイルマッサージ」「瞑想」「適切な食事」といった具体的な方法、「子どもの食事」「ベビーオイルマッサージ」「生活習慣」など育児についても紹介。巻末の体質チェックテストでは大人用、子ども用をそろえました。体質に合った方法で実践していけば、快適で幸せな毎日に近づいていきます!
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人類史に貴重な役割を果たしてきた塩をめぐって,発見から伝承・製造技術の発展過程にいたる総体を歴史的に描き出すとともに,その多彩な効用と味覚の秘密を解く。
-
-
-
4.0驚異的な力、奇跡の復活、無から有を生み出す能力、強力な幻、人の姿や運命まで変えてしまうほどの呪いなど、いろいろなパワーを秘めた魔法や魔法のアイテムを多数紹介した本です。神話や伝承、童話に登場する魔法や魔具を取り上げている一方で、陰陽術や錬金術など現実に存在した魔術も扱っています。この一冊を手に取って、人間の想像力が生み出した深奥なる世界へ踏み込んでみましょう。 <電子書籍について> ※本電子書籍は同じ書名の出版物を底本とし電子書籍化したものです。 ※本文に記載されている内容は、印刷出版当時の情報に基づき作成されたのものです。 ※印刷出版を電子書籍化するにあたり、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。また、印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。 株式会社西東社/seitosha
-
-人と深いかかわりをもつ「木」100種を選び、用途や特徴、伝承・伝説などを紹介した樹木の入門図鑑。 椎(しい)、樫(かし)、 (ぶな)、欅(けやき)など、名前はよく耳にしても、身近にあって毎日見ていても、また、家具や食器などとしていつも使っていても、意外と知らないのが「木」です。古くから人と深いかかわりをもってきた「木」100種を選び、その用途や特徴、伝承・伝説などを、人とのかかわりの視点から紹介した、樹木の入門図鑑。美しいカラー写真と、長年樹木の研究を続けてきた著者の興味深い解説で、図鑑としてだけでなく、おもしろい読み物としても楽しめます。紹介するのは、神事、仏事に関わりのある木、仏像になる木、家具や細工ものに使われる木、バットや木刀に使われる木など、身近なものが中心。公園や街路樹として植えられているものも多く、すぐに実物を見ることもできるので、本を読んで、実物を見て、多面的に楽しむことができます。身近な「木」の名前を知るだけで、その「木」に愛着がわき、日々の暮らしも豊かなものになるでしょう。 ■著者プロフィール ▽田中 潔(たなか きよし): 元森林総合研究所研究員。東京大学農学部林学科卒、専攻は樹木。現在、日本森林技術協会顧問。日本森林学会理事、日本農学アカデミー理事。
-
4.7「師」の多くは昭和から平成を彩った名棋士たち。「弟」は、今をときめく昇り竜の若手棋士。生まれた場所も世代も違い、なんの縁もなかった二人が「師」と「弟」として出会い、互いの人生に大きく影響を与え合う。時には勝負の場においてライバルともなる。一人の棋士が育つ過程を、師弟という関係を縦糸に、それを支える家族の物語を横糸に描く。
-
3.5異世界×神様=トーゼン最強♪ 「小説家になろう」発の大人気作品が待望の書籍化! 身体(からだ)が弱くて生きることができなかった前世。異世界へ転生したら、最強の魔法の使い手になれました!? いやいや、ただもう死ぬのはごめんだから努力していただけなんですが。 近隣の国や悪神との戦いでも毎回頑張っていると今度は背中から翼が生えてきて? 昔の伝承によるとこの翼が生える者は麗神(れいしん)テルスの生まれ変わりなんだって―― いやいやいや! 知らないうちに最強どころか神様になっちゃってるから! 気の許せる仲間と眷属(けんぞく)をお供にして異世界最強への道を突き進む神様幼女の成長録!
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ”ちがいを ちからに 変える街”。 渋谷区は1932年10月1日に誕生、今年90周年を迎えました。 「シブヤ」は今もなお、さまざまなトレンド、 カルチャーを生み続けています。 では、渋谷区の「ちがい」とは? 渋谷区の「ちから」とは? その答えを1冊に編集。 渋谷区に住む人、働く人、訪れる人、さまざまな視点で構成しました。 “ちがいを ちからに 変える街”という渋谷区のビジョンを基本に、 世界に暮らす人々の多様性を受け入れ、 渋谷区に集まる全ての人の“ちから”をまちづくりの原動力にして、 イノベーティブな取り組みを進めています。 さて「衣食住カルチャー」のすべてが楽しみな渋谷には、 時代の移り変わりが、街に人に、色濃く顕れます。 記念誌のカバーでも、渋谷90年の“過去”と“現在”が交差する様子を ホセ・フランキーさんが江戸絵巻タッチで表現しました。 渋谷区の未来について、区民を代表して中学生からの質問に、 区政、教育、文化など、まちづくりに関わるプロが答えます。 長谷部健・渋谷区長をはじめ、渋谷駅周辺の再開発に携わる内藤廣さん (建築家)、渋谷区の公共施設設計に携わる隈研吾さん(建築家)、 「渋谷区シニアデジタルデビュー大使」井上順さん(役者、エンタテイナー) たちが各々のジャンルで渋谷愛を熱く語ります。 また、伝承ホールで松本幸四郎さん(歌舞伎俳優)、LINE CUBE SHIBUYAで 草彅剛さん(俳優・アーティスト)が登場する渋谷駅周辺。 タケノコ族、ローラー族、アメカジ、裏原系、東京ファッション、 KAWAII文化…。ユースカルチャー、TOKYOスタイルを生み続ける 原宿・表参道界隈。 江戸、昭和、平成の息遣いが今も聞こえる代官山、恵比寿、広尾。 “おとなりさん”との暮らしの輪が広がる富ヶ谷、上原。 スポーツの楽しさと競技の多様性に触れられる代々木、千駄ヶ谷。 地域に密着した商店街が織りなす笹塚、幡ヶ谷、初台、本町。 個性豊かな渋谷区を6エリアに分けてレポート。 さらに道端カレンさん(モデル)、原晋さん(青山学院大学陸上競技部監督)、Taku Takahashiさん(m-flo)、観世清和さん(能楽 二十六世観世宗家)、 ヴィム・ヴェンダースさん(映画監督)、辻愛沙子さん(クリエイティブ ディレクター)ほか多数の方々がこの記念誌に参加してくれました。
-
-富田製作所――職人技の伝承で「板金世界一」へ 両備グループ――“たま駅長”の生みの親が掲げる「社員の幸せ」の方程式 伊那食品工業――トヨタも見習う、持続的成長の「年輪経営」 大企業から中小企業まで現場を知り尽くした“取材の哲人” 片山修が発掘した究極の3社には共通点があった。 社員を幸せにする会社とは、 ◎経営者の魅力にあふれた“心の経営” ◎社員と経営者の距離が近い ◎人材育成に力を入れる ◎家族的連帯組織を構築する ◎日本型経営の美点、美風を温存する 「失われた20年」。 社員の幸せは後回しにされた。 その結果はどうか。 成功したといえるのか。 社員が幸せにならなければ、企業は幸せになれない。 新しい日本型経営のかたちとは?
-
3.7
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 民俗学者・折口信夫は「古代」を知ることに全生涯をかけてきた。それは歴史という意味での古代ではなく、古来の日本人の信仰や習俗が現代までも伝承されている、時代を超えた精神性である。そんな折口が論じ続けた「古代」的な要素――千年も続く様々な信仰行事を、写真と文でたどるかつてない一冊。万葉の旅から沖縄への旅、芸能史への展開まで、彼の研究の流れに沿って、「日本人の心の原点」ともいえる写真に解説を付して収録する。
-
-ネパール、スリランカ、バリ島――様々なタイプのシャーマンを訪ね歩き、丹念なインタビューを重ねた取材の成果がここに結実! 変性意識、憑き物、呪い、プージャ、チャクラ、呪い、カーリー女神、異次元コンタクト……カルマの深層に挑む、壮大なスピリチュアル・ドキュメンタリーが完成した。 巻頭カラーページでは、各地のシャーマンによるプージャ(治癒儀式)の様子も紹介! 知られざるシャーマンの暮らし、伝承、秘術、そして多様な事例から見えてくる、大いなる変動・新たな時代のはじまり! この世は理不尽なことに満ちている。思い通りにならないことでいっぱいだ。 あらん限りの手を尽くしてもどうにもならないとき、私たちはこの世の法則を超えた何かに応援を頼む。 現在、新たにシャーマンが表に出てきたのは、これから激動の時代が始まる予兆なのではないだろうか。 ―――プロローグより
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 〈信長が、もし「文春砲」を食らったら?!〉〈戦国時代の伝承を「週刊誌の記事風」にリメイクした新感覚・歴史読本!〉信長の壮絶パワハラや家康の脱糞疑惑、上杉謙信のインサイダー取引疑惑などなど、戦国武将にまつわる史実や言い伝えを、【家臣や民からの匿名告発を受けた週刊誌がスクープ記事にした】というテイで誌面構成。スキャンダラスなゴシップネタのみならず、インタビュー、ルポ、エッセイなどあの手この手で約50ネタを掲載します。著者お得意の歴史パロディ要素を取り入れた広告ネタも随所に盛り込み、武将の性格・趣味嗜好から武士の生活文化・作法まで、楽しみながらざっくり学べる斬新な歴史本です。
-
-まえがきより 「三国志」において、呉の周瑜公瑾は人気の武将である。実際、彼が正史で成し遂げたことは、「三国志」における最大の権力者・曹操による天下統一を挫折させたことであり、ある意味最大の功績を成した人物でもある。「三国志演義」では、物語の都合上、物語の主人公である劉備に仕える軍師・諸葛亮孔明に翻弄されるが、これは史実では確認できない(魯迅が「史実を歪め過ぎている」と批判している)。 周瑜は華のある人物とされている。彼は「美周郎」「長壮にして姿貌あり」と呼ばれるほどの眉目秀麗の人物である。正史では「性格は大らかで度量があり、誰からも好かれていた」と人柄もいい。周瑜は見た目だけではなく、人柄も優れていた。妻の小喬は絶世の美女だが、民間伝承によると深い情愛で結ばれていたという。 なお、周瑜が仕えていた孫策とは義兄弟とも言える間柄であり、主君が非業の死を遂げた後も、権力に色気を見せずに孫策の弟・孫権の権力を支え続けたという。 周瑜は智謀も備えていた。主君の孫権からは「雄烈と胆略を兼ね備えている」と評され、正史の著者である陳寿も「独自の見通しを持ち、誰も思いつかない方針を提出した。実に奇才と言うべきである」と評している。 そして中国の半分を制した曹操が軍事的圧力をかけてきたときも、弱気になる主君を補佐し、圧倒的多数である曹操軍は疫病などで疲弊していることを見抜いて、赤壁の戦いに勝利する。その後、荊州と益州を取れば曹操に対抗できるとして、荊州に進軍するが、江陵攻略中に流れ矢を受け、その傷が原因となったのか、わずか36歳で急逝する。 さらには文化人でもあり、音楽にも通じていた。こうした英雄ぶりから、京劇でも必ず二枚目が演じる役である。 本書ではこのような活躍をした周瑜の業績を通じて、権力の掌握と維持について語っていきたい。というのは、周瑜の家柄は主君である孫策よりも遥かに上であり、曹操や劉備からも「周瑜は孫策や孫権に仕える人物」と見なされていなかったからだ。そうしたことを見ていくと、この時代が見えてくると思うのである。 なお、本書で書かれたことも「解釈」の一つであり、この本で書かれたことを無批判に真実だと考えてはならないのは、もちろんである。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 3歳以上の幼児とその親が対象。基本の折り紙から少し発展した折り紙まで、幼児が楽しめる動物や花、食べ物などの人気アイテムに、覚えておきたい伝承のアイテムを加えて69アイテムを紹介。著者は、長年幼稚園教育の中で折り紙を取り入れ研究している川並知子さん。①折り紙を好きにさせるための実物大イントロ ②発達心理学からのアドバイス ③創造力と想像力を養う簡単バリエーション ④折った後の遊びかバリエーション などを写真、イラストをふんだんに取り入れ、全ページカラーで編集。
-
-沖縄県発・おきなわ文庫シリーズ。 「本書は文献に見えない伝承の世界から首里城を観察し、かつて城内に生きた人間たちの息吹を伝えている。とりわけ、これまであまり知られていなかった首里城の「表」と「裏」の世界について、それぞれの特色を興味深く描き出している。またかつての城内の生活習慣を継承していた中城御殿(世子殿)において、著者自らが実験した資料を提示するなど、本書ならではの特色がみられる。また、昔日の首里城の景観についても詳細を述ベている。首里城に関する歴史、慣習、祭祀、儀礼等に関心のある人びとに一読をすすめたい書である。1989年作品紹介」 著者は真栄平房敬氏、御歳92歳。首里に生まれ戦前は城内の国民学校で教師をしてこられ、首里城復元の活動に尽力された。現在病床の身にもかかわらずご子息のご協力を得て復刊へとたどり着いた作品。ありし日の首里城の記憶を若い世代に伝え、平和への願いを込めた原稿を「遺言」として新たに追記。多くの方に読んでもらいたい内容となっている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 狩猟には古来,感謝と慰霊の祭祀がともない,人獣交渉の豊かで意味深い歴史があった。狩猟用具,巻物,儀式具,またけものたちの生態を通して語る狩猟文化の世界。
-
3.6
-
3.0■2021年、太子御遠忌1400年! 和の精神 神仏習合 憲法・冠位 対等外交…古代史のカリスマ・聖徳太子の足跡から聖者伝説の真相を明らかに。 教科書から「聖徳太子」の呼称が消えて久しいが、厩戸王こと聖徳太子は、摂政として天皇を補佐し、十七条憲法の制定、遣隋使派遣など、大陸文化の積極的な受容に努め、国家の体制づくりに尽力したことで知られる。教科書が描き、一般的にイメージされる太子像は、仏教を重んじた辣腕の政治家であり、古代史のカリスマであろう。だが、『日本書紀』などが「聖者」として太子を礼賛する一方で、太子にまつわる謎・不明な点は多い。いかにして聖徳太子は「聖者」(カリスマ)となり得たのか? 日本書紀を精読し、あえて書紀が描かなった部分を、各地の太子の足跡・伝承からも補足しながら、古代史の第一人者が謎解き風に真実に迫る歴史教養本。 [目次] 第1章 聖徳太子の生涯を知る 第2章 斑鳩と法隆寺の謎 第3章 聖徳太子ゆかりの古寺と史蹟 第4章 聖徳太子伝説の謎 <編者略歴> 瀧音能之(たきおと・よしゆき) 1953年生まれ、駒澤大学文学部歴史学科教授。研究テーマは日本古代史。特に『風土記』を基本史料とした地域史の研究を進めている。主な著書に『風土記と古代の神々』(平凡社)、『出雲古代史論攷』(岩田書院)、『古事記と日本書紀でたどる日本神話の謎』『図説 古代史の舞台裏』『古代日本の実像をひもとく出雲の謎大全』(以上、青春出版社)、『図説 古代出雲と風土記世界』(河出書房新社)、『古代出雲を知る事典』(東京堂出版)、『出雲大社の謎』(朝日新聞出版)など。監修書に『最新発掘調査でわかった「日本の神話」』(宝島社)などがある。 <執筆者略歴> 古川順弘(ふるかわ・のぶひろ) 1970年、神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。宗教・歴史分野を扱う文筆家・編集者。『人物でわかる日本書紀』(山川出版社)、『古代神宝の謎』(二見書房)、『仏像破壊の日本史』(宝島社)ほか著書多数。 ※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『聖徳太子に秘められた古寺・伝説の謎 正史に隠れた実像と信仰を探る』(2021年4月17日 第1刷)に基づいて制作されました。 ※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
-
-本書第3章に所載される『神国の民の心』は、平成19年の復刻に際して、長男泰國氏(現神社新報社社友)が冒頭「はじめに」の中で「この本は葦津の晩年になって発行された特別の本である。彼は『神国の民の心』の中で、自分の戦後を、神道の弁護士としての論に終始したと回顧している。戦後の時期は、社会一般と自分の属する神社界のことを考えて、そのための配慮を持って主張するのにつとめてきたというのである。それは彼が、戦後自分のおかれている立場を知って、その迷惑になるおそれのある独自の論は、差し控え、時にはあえて論理をさかさまにするようなこともあえてしてきたとの告白でもある。」と指摘するように、葦津珍彦個人の神道観と生き方を自ら語った著作だと云える。また第1章の『老兵始末記』も同様、神社本庁、神社新報他、葦津が関わっていた組織の役職を一切辞した際に執筆し、親しい友人や後進に限定し配布されたものである。 本書は本シリーズ前5巻とは異なり、論考としての性格も有しているが、全般を通じて自伝的要素を伴っている。葦津自身の強固な神道への信仰を背景に、天皇陛下、祖国日本、更に多くの交わった先人と後進達への敬愛の情に満ちた著作でもある。 尚、本書巻末には、泰國氏の「葦津珍彦臨終日誌」が付されている。 ■キーワード(目次の構成) ▲老兵始末記 ▲夢はただ、水泡と消ゆ ▲昭和の始めのころ ▲流血、動乱の初め ▲上海戦線で学びしこと ▲大戦前夜のころ ▲大東亜戦争の時代 ▲神道的日本民族論 ▲日本民族の世界政策私見 ▲日本神道とナチス精神 ▲神道とナチスは断じて異なる ▲神国の民の心 ▲古神道と近世国学神道 ▲祈る心と怨む心と ▲仁者無敵 ▲神国意識を高めよ ▲御在位六十年に際し切望す ▲日本国体についての一私見 ▲私も神道人の中の一人である ▲神武天皇 神道的伝承 ▲皇祖天照大御神 神道神話 ▲付録 葦津珍彦臨終日誌
-
4.2
-
4.0地理的条件、調理技術、伝統、交易の盛衰――「料理」を通してみると、歴史はますます鮮やかになる。古今東西の英雄から、時には庶民の食卓まで、興味深いエピソードと歴史的なレシピで案内する。 【目次】1 ハンムラビ 古代メソポタミア野菜の「三本柱」/2 アレクサンドロス三世 食事は質素で大酒飲み/3 ネロ 絶滅危惧種最後の一本/4 楊貴妃 茘枝は幼少期の味/5 ハールーン・アッ=ラシード 食は市場にあり/6 バシレイオス一世 古代から中世へ/7 チンギス・ハン 「赤い食べ物」「白い食べ物」/8 マルコ・ポーロ 大旅行家が観察した食事情/9 コロンブス 近世の食卓へ/10 エルナン・コルテス 「コロンブス交換」の時代/11 スレイマン一世 多様な遺産を継承するオスマン帝国/12 カトリーヌ・ド・メディシス 「伝承」の真実/13 ルイ14世 洗練されたサーヴィスの確立/14 フリードリヒ二世 コーヒーではなくビールを飲め!/15 リンカーン 感謝祭とクレオール料理/16 コナン・ドイル 大英帝国のカレー/17 夏目漱石 一生にして三食を経る/18 マクドナルド兄弟 ファストフードの誕生
-
-ホラーSF漫画『恐怖の口が目女』が大きな話題を読んだ漫画家・崇山祟(たかやまたたり)が、 今度はホラー映画『シライサン』のコミカライズに挑む! オカルト趣味だけが生きがいの、“空気"のように目立たない女子高生トリコはいつもの古書店 で一冊の本を手に取った。そこに書かれていた“目隠し村"の伝承のとりこになった彼女は翌日 、同じクラスの男女グループに伝承をベースにした怪談話を披露。すると後日、話を聞いた男女 が次々と“眼球破裂"という謎の死を遂げていく。トリコは急遽オカルト部を結成し、目隠し村 の呪いに立ち向かう。 存在を知った者を呪い、目をそらした者を死に誘う“シライサン"。それと目が合った女子高生 トリコは、もう“空気"ではいられなかった。
-
3.0世界遺産白神山地で最後の伝承マタギであり、マタギ集団のリーダー・シカリとして知られた鈴木忠勝(1990年没)との長年の交友、聞き書きを通じて、現在では失われてしまった北東北の狩猟・山村文化を記録した超力作。 狩猟と山の生活のルポに加え、伝承や歴史史料を駆使、自然と共生してきた山村の生活文化を描き出す。 2014年七つ森書館刊行の書籍の内容をより幅広く伝えるため、また内容を理解するための地図を新規掲載し、文庫化。
-
-▼第1話/蛍の宿▼第2話/原人の墓▼第3話/鬼泪(第1章/今浦島、第2章/迷子、第3章/キリサキ、第4章/赤の家、第5章/石喰い、第6章/女星が消えた) ●主な登場人物/▼蛍の宿:京子(蛍を持って海辺の旅館・磯屋を訪れた謎めいた女性)、明(磯屋旅館の一人息子)▼原人の墓:斉藤(伝承を信じ、山奥まで日本原人を探しに行く青年。天城観光ホテルに勤めている)、天城八重子(天城観光ホテルの経営者・天城重蔵の娘。斉藤と共に原人を探しに山へ向かうが…)▼鬼泪:石神栄次(27歳。東京で職を転々としていたが、5年ぶりに帰郷。故郷で働き口を探す)、磯貝松造(65歳。今も古い木製の船で海へ出る、腕のいい昔気質の漁師) ●あらすじ/上京してはみたものの、都会の空気が肌に合わず、5年ぶりに故郷へ帰ってきた石神栄次。帰郷した栄次は、浜辺で漁師の松造に出会い、その生き方に影響を受ける…。漁師、陶芸家、採石場作業員らの姿を通し、誇りを持って仕事に向かう男たちの姿と、近代化に伴う自然破壊の弊害を描いた力作(第3話)。 ●本巻の特徴/表題作の他、海辺の旅館・磯屋の家族と、謎めいた美女・京子をめぐる物語「蛍の宿」、長野の山中へ日本原人を探しに行く二人の男女の顛末を描いた「原人の墓」の全3編を収録した、異色作品集。いずれも初出は81年。 ●その他のデータ/巻末に映画評論家・門間貴志氏によるエッセイ「『鬼泪』のキャスティングを考える自分がいる」を収録。
-
4.0世界各地の伝承話をモチーフに翻案した異色作「神話伝説シリーズ」。神話伝説の持つ原始的なエネルギーを大胆な舞台設定で全開! 日常の隙間に潜む妖しくも美しい光りと影を力強いタッチで描き出している。 ▼第1話/七ツ桶の岩▼第2話/人身沼▼第3話/戦争▼第4話/野犬▼第5話/孤島の出来事▼第6話/釣▼第7話/人獣の宿 ●登場人物/草加竜之進(父母一族の仇を打つため放浪を続ける武士)。弥七(神様といわれるほどの技術を持つ漁師)。サキ(弥七の孫娘) ●あらすじ/藩主・日置弾正を父母一族の仇とねらう草加竜之進。彼はその放浪の旅の途中で老漁師・弥七とその孫娘・サキと知り合う。弥七と幻の 漁場へ漁に出た竜之進は、海に生きる男の生き様を目にして、自分の武士としての生き方をもう一度考え直す。しかし、夜中再び幻の漁場を目指して海に出た弥七は嵐に巻き込まれて……(七ツ桶の岩)。▼「天下泰平万民の幸せのため」として近隣諸国に魔の手を伸ばす戦国大名・魔壁道三。道三の言葉を信じる忍者・夜鷹は敵城主の暗殺に際して片手を失い、敵として忍び込んできた姉の首もはねた。そんな中、城のすぐそばで起こった山津波のときに夜鷹がとった手段とは……(人身沼)。 ●本巻の特徴/60年代の作品を中心としたこの短編集は、その後の白土三平とはひと味違ったスタイルの作品も収録。彼の作品世界の広がりを理解するためにも見逃せない。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 都市伝説とは、実際にはなかった出来事がさも「本当に起きたかのように語られる話」だ。 「友達の友達から聞いた」というお決まりの前置きが付く この手の“実話“は昔は口伝えで、現在はネットを通じて拡散し、 その過程で様々に形を変える。 本書は、 これを広く定義し、旧くから伝わる迷信・呪い・怪談、暗殺説・別人説、 アニメや映画にまつわる不気味な噂を含む126本の都市伝説を取り上げた一冊だ。 大半は噂の域を出ない。 根拠も説得力も弱い。 が、一方でその噂が確実にウソである保証もないことは知っておいてほしい。 ・バーコードは「反キリスト」の証 ・「ポケモンGO」はCIAによる人類監視システム ・絶対に歌ってはいけない童謡「サッちゃん」の4番 ●新型コロナは人口の生物兵器説は本当にウソなのか? 巷に流れる黒い噂126本 ■目次 ●第1章 身近な迷信 ・IQが高い人は、勉強のできる頭の良い人 ・血圧を下げるには「減塩」が一番 ・「平均寿命」は死亡年令を死亡者数で割ったもの ほか ●第2章 本当は怖い童謡・民謡 ・江戸子守唄 ・かごめかごめ ・ドナドナ ほか ●第3章 怪談伝承 ・電気をつけなくてよかったな ・消えたヒッチハイカー ・ボーイフレンドの死 ほか ●第4章 呪いとジンクス ・六本木ヒルズの呪い ・ジブリの呪い ・11月9日はドイツにとって「運命の日」 ほか ●第5章 名作アニメ・映画の不気味な噂 ・アニメ「ちびまる子ちゃん」さくら家の知られざる悲惨な現実 ・「ワンピース」はフリーメイソンとつながりがある ・「トイ・ストーリー3」の裏テーマはホロコースト ほか ●第6章 戦慄の陰謀論 ・2050年までに財閥支配の「世界統一政府」が誕生する ・花粉症がなくならないのは製薬会社の利権を守るため ・ロシア高層アパート連続爆破はロシア連邦保安庁の自作自演 ほか ●第7章 怖いエトセトラ ・アメリカで目撃される「黒い目の子供たち」の正体 ・東京ディズニーランドで臓器売買目的の子供誘拐話が流れた理由 ・タバコのラッキーストライクは広島への原爆投下を記念して生まれた ほか ■著者 鉄人社編集部
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人は死んだらどこへ行くのか――― 天国、地獄、輪廻転生…? 世界の宗教や死者の書、 霊界を知る達人たちが伝える様々な“死後世界” 生と死を見つめ続ける巨匠が描き下ろした、 古今東西10通りの死生観 あちゃー なにこれ? ヤバイな 臨死体験? まだ心がまえできてないよ ……などという間に自分は流されていき…… 暗闇の中を流れる大きな川の中州に 死後科の病棟はあった 漫画と読み物で繰り広げる古今東西10通りの「死後の世界」。本書の案内役 は、しりあがり寿の漫画『瀕死のエッセイスト』(1996年)や、雑誌『ダ・ヴ ィンチ』(1999~2008年)にて連載していた『オーイ・メメントモリ』などに も登場する、通称・瀕死のエッセイスト。彼は臨死体験のような状態で流れ 着いた“死後病棟”で、「人は死んだらどうなるのか」「死後の世界とはい ったいどういう場所なのか」を知るために、病棟内の無数の部屋を訪ね歩き ます。そこで出会う個性的なキャラクターたちや独自のユーモアは、まさに しりあがりワールド全開! 生と死を見つめ続ける氏ならではといえる作品 であり、ファンのみならず手にしてほしい意欲作です。一方、各コンテンツ に解説のテキストを添えるのは、『辛酸なめ子と寺井広樹のあの世の歩き方』 も話題になった、オカルト研究家の寺井広樹。さらに、宗教学者・島田裕巳 氏の監修による、アカデミックな裏付けも兼備しました。世界の伝統的な宗 教や各地の伝承、霊界の達人などが伝える様々な死生観。そこから自分なり の「死後の世界」も模索できる、新たなガイドブックの誕生です! 【主な内容】 第1章 伝統的宗教の死後の世界 ●仏教の死後の世界 国によって様変わりしてきた仏教の死後の世界。 決め手は善行か、「地獄の沙汰も金次第」か!? ●キリスト教の死後の世界 正しい信仰をもち、善行を積んだ人の魂は天国へ。 罪人や異教徒は、凄まじい地獄で責め苦を受ける。 ●イスラム教の死後の世界 ごくシンプルな死後の世界。火に炙られる地獄と、 酒や乳の川が流れ、望むものが手に入る天国。 ●神道の死後の世界 ガラパゴス宗教である神道では、すべてが曖昧模糊。 天国も地獄も、今いる世界と地続きかもしれない。 第2章 死者の書 ●古代エジプト「死者の書」 ミイラとともに棺に納められた巻物の呪文は、 死後の楽園にたどり着くための必須アイテムだった。 ●チベット仏教「死者の書」 何度も繰り返し現れる光が、死者を解脱に導く。 その好機を逃さぬよう、僧侶がお経を唱え続ける。 ●日本版死者の書『往生要集』 往生を遂げて極楽浄土に行くためのマニュアル本。 現世での罪に応じていく、八大地獄の描写が凄まじい。 第3章 霊界の達人 ●スウェーデンボルグ『天界と地獄』『霊界日記』 天界行きか地獄行きかを自分自身で選ぶ。 ●ワード『死後の世界』 地獄の最下層に行ってもはい上がれるという証言。 ●出口王仁三郎『霊界物語』 トランス状態で口述筆記された壮大なストーリー。 コラム ・琉球に伝わる死後の世界 ・アイヌに伝わる死後の世界 ……etc.
-
4.0第8回ネット小説大賞受賞作! 偏屈でぐうたらな館長と苦労人司書、奇妙な来館者が織りなすビブリオファンタジー! 鬱蒼とした雑木林に囲まれた町はずれの私立図書館・黄昏堂《たそがれどう》。そこで働く新人司書・湊(みなと)は、膨大な蔵書を有するにもかかわらず、少ない来館者数に嘆いていた。しかし、偏屈な若き館長・空汽(うつろぎ)は「この館に余計な客を増やすつもりはない」とまったくやる気を見せない。怠惰な空汽と彼の飼い猫・クロ、そして数少ない常連客たちに囲まれ、湊は仕事にいそしんでいた。そんなある日、常連客の紹介でとある病に苦しむ大学生が訪れた。しかし彼は湊が目を離した僅かな隙に忽然と姿を消してしまう。「――そろそろ新しい仕事を覚えてもらおうと思っていたんだ」空汽に案内されたのは地下の閉鎖書庫・永劫廻廊。そこに足を踏み入れた湊は、書物に纏わる神々や伝承の存在と出逢い……? 謎を秘めた図書館を舞台に繰り広げられる、新たなビブリオファンタジー。
-
-時代と芸を斬る“まくら”隋談 TV・高座で世相と芸界の本質を 批判を恐れず喋る噺家あり。 師匠・立川談志の特異な視線を伝承する 全身落語家が、物事の本質を鋭く“笑い”に変える! スマホで観る 立川志らくの超絶まくら 本文中のQRコードを読み取って、 立川志らく師匠のまくらを堪能する! ひろゆきさんとは仲がいいので、対談したときに、 「もっともっと、落語を広めるには、どうしたらいいですか?」 って言ったら、 「志らくさんが大金持ちになって、それを世間に広めればいいんだ」 と、 「髪を染めて、もの凄いアルマーニの服を着て、それで、外車に乗って女の子をはべらかせて、そうすると皆が憧れる」 って、どういうことなんだ(笑)? そんなもんなんだ、世間の落語に対するイメージなんていうのは。 ――『本当は落語なんか演っている場合ではない』2022年7月日第回立川志らく落語大全集国立演芸場『寝床』のまくらより
-
3.7
-
-徹底取材! 長野県各地で今も起きている怪奇現象の数々を丸山政也が描く! 心霊譚が絶えない長野市のホテル 善光寺に巣食う妖しい怪異の数々 死者に呼ばれる軽井沢大橋 車中に何かが乗り込む碓氷峠 小岩嶽城址の怨霊武士 菅平高原の首なしラガーマン 〈奇譚百物語〉シリーズの丸山政也が地元長野県の怖い話を纏めた実話怪談集! ・松本市のとある住宅におぞましい異形が巣食う…「借家」 ・木曽路にて、不気味な猿に導かれた先で驚愕の光景が…「猿の怪話」 ・断崖で視たこの世の者とは思えぬ存在…「半過岩鼻」 ・天竜川の舟下りで現れた恐ろしい怪異…「南原橋」 ・日本有数のパワースポットで撮れた不可思議な心霊写真…「分杭峠」 ・岡谷市の神社の怪異、その裏に凄惨な事件が…「池に浮かぶもの」 ――など身も凍る恐怖体験談に加え怖い民話も数多く収録! 伝承の宝庫・信濃には恐ろしい場所が数多く存在する…
-
-昭和30年代の東御市の食生活を聞き取りで再現。自給をベースにした時代の日々の基本食、四季の食生活から、子供と食、人の一生と食、食の道具、伝承される知恵、生活改善活動の影響、現在の特産品まで詳述する。
-
-
-
-信州の春を彩る郷土食。小川村のやしょうま名人が教える、すぐに作れる35種のレシピ 信州では、昔から春になると作られている郷土食のひとつに“やしょうま”という食べ物があります。 やしょうまは、お釈迦様の亡くなられた日である涅槃会の2月15日、または月遅れの3月15日に仏壇にお供えする米粉で作った餅菓子のことで、ほんのりと甘くもちもちとした食感のとても素朴な食べ物です。 信州伝統の味をいつまでも伝えていこうと、信州のやしょうま名人がすぐに作れる35種のレシピをやさしく教えます。 【目次】 <基本> やしょうま作りの材料/やしょうま作りの道具/基本の生地のこね方/生地ののばし方/やしょうまの切り方/着色料の作り方/着色の方法 <やしょうまレシピ> 伝統的なやしょうま/うずまき模様/花模様/スイカ/恵方巻き/うめの花/さくら/パンダ/クマ/ライオン/菜の花/ひまわり/ひなまつり ほか <もち菓子> ひしもち/草もち/笹もち/ひと口すあま 【著者】 松本博子 長野県上水内郡中条村(現長野市中条)に生まれる。30年にわたり保育・幼児教育に携わる。平成19年、「工房 食彩」を開設し、農産物直売所、道の駅などでやしょうまの販売をはじめる。現在、小学校、中学校、公民館などでやしょうまの講習会の講師を務めながら、郷土食の伝承にも尽力している。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 江戸版本のなかから、現代人の心の琴線に触れる奇怪譚・滑稽譚・迷宮譚を精選して話題となった『大江戸奇怪草子』(三五館)の復刊本。第一部では「狐狸」、第二部では「不思議話」、第三部では「縁起由来」に焦点を当て、江戸時代の庶民生活の裏側を覗く伝承に迫る。復刊本では筆者のコレクションなどから関連図版を大幅に増補。98タイトル百数十話を収載。一読すると、まるで古老の話を聞いているような余韻が心の中に広がる。「貨幣」「不定時法」「度量衡」など、巻末の資料編も充実。 もくじ 河童/物を言う猫/魔魅/天狗になった男/蛇が蛸になる話/蝦蟇の怪/幽霊の置き土産/大陰因果咄/牛鬼/魍魎/癪のかたまり/山神/生まれ変わり奇談/お菊虫/妖しい少女/地中の亡霊/疱瘡鬼/石像が生まれた/犬嫌いの疫病神/南蛮人の秘術 ほか
-
-
-
-◎実写映画化で話題! 運命を信じる、すべての女性に贈る――あなたの知らないシンデレラ・ストーリー◎あなたの優しさが、愛という名の魔法をかける――不朽の名作に込められた、〈愛〉と〈真実〉! ラブストーリーの原点にして、頂点。世界中の「シンデレラ」ストーリーを収録! 世界中の子供から大人まで愛するラブ・ファンタジーのマスターピース『シンデレラ』。古くから広い地域に伝わる民間伝承をもとに語り継がれてきた“シンデレラ・ストーリー”。誰もが知ってる物語の様々なヴァージョンを収録。◎世界中の女性や子供たちから愛されている物語――『シンデレラ』。これまで数多くの映画やアニメ、ドラマの元となってきた物語の原点とは? 継母とその連れ子によって苛められているシンデレラ。ある日、城で舞踏会が開かれることになるが、彼女には着ていくドレスもなにもない。しかし、不可思議な力によって舞踏会に出席したシンデレラ。しかし、魔法は12時には解けてしまうので、それまでには家に帰ることが条件。シンデレラは舞踏会で注目を浴び、王子に見初められるが、あわてて帰ったために靴を落としてしまう……。◎〈収録作品〉 『シンデレラ』シャルル・ペロー 『灰まみれの少女 アッシェンプッテル』ヤーコブ&ヴィルヘルム・グリム 『バーバ・ヤガー』W・R・S・ロールストン 『キャット・シンデレラ』ジャンバティスタ・バジーレ 『薔薇色の赤い靴の乙女』イソップ 『十二の月たち あるスラヴの伝説』アレクサンダー・コズコ ほか
-
-【名作絵本のデジタル復刻!】日本が元気だった頃、多くの子どもたちに親しまれてきた厚紙の絵本。美しい絵、文章のリズム、ことばの楽しさ、当時活躍した実力派絵本作家の子どもへの熱い思いが伝わってきます。親から子へ語り継ぎたい名作絵本シリーズ!! 継母と姉たちからいじめられてもけなげに生き、最後には王子さまと結婚して幸せをつかむ、誰でも知っている「シンデレラ」は、民間伝承を、ルイ14世時代の作家、ペローがアレンジして「サンドリヨン」というお話にまとめたものがベースになっています。 どんなに厳しい試練にあっても人間らしい心を失わずに耐えていれば、必ず幸せがやってくるという人生肯定物語が、世界中の人の共感を得たのです。同じようなタイプのお話は日本には「鉢かつぎ」「姥皮」、その他世界中にあります。女の子にとっては、試練のときのみすぼらしい服、王子様と出会ったときの美しいドレスなどが印象に残る物語でもあります。 ※この作品はカラー版です。
-
3.8神社や森で突如感じる神々しさや畏怖の念。このような感覚に宿る生命中心主義、自然崇拝こそ神道の本質である。従来、弥生時代に起源を持つとされることが多かった神道。しかし本書は、縄文時代、さらにはそれ以前から人々に宿るアニミズムの感覚に遡る、より大きなスパンで神道を捉え直すことを提唱。その視点から神仏習合、吉田神道の登場、神仏分離令に至る、神道の歴史を読み解く。さらに、「日常に神道は生きているか?」という現在に直結する疑問に答える形で、ディープエコロジーにつながる神道の原像を明らかにしていく。そして、大いなる自然から贈られ続ける生命に驚き、感謝して生きる「かみのみち」こそが、環境破壊・宗教不信など多くの問題を乗り越え、新たな世界を開く、と説くに至る。宗教学者でありながら、神主、祭りの主催者、神道ソングライターとして伝承文化の見直しと調和ある共同社会の創造を実践する著者による、壮大なる神道文明論。
-
-
-
4.5内容紹介 新版 朝鮮カルタ 韓国ことわざ100選 カルタ風イラスト&コラムで知る 朝鮮民族の実態!! 常識を超えた国には、常識を超えたことわざがあった! 韓国のことわざはこんなに酷かった(例) ・乞食同志が袋を引き裂く ・死んだ息子の○○○にさわる ・女は三日殴らないとキツネになる ・嘘もうまくつけば稲田千坪にもまさる ・悪口は祝福の言葉 ・自分の食えない飯なら灰でも入れてやる 本書紹介韓国ことわざの出典元 『朝鮮の俚諺集』高橋亨、日韓書房、1914年 『韓国俚諺集』相場清、日韓親和会発行、1971年 『対訳注解韓国ことわざ選』若松實、高麗書林、1975年 著者からのコメント ことわざを知る事は、その民族を知る事になる。 ことわざは遠い昔から民衆の間で言い交わされ、伝承されてきたもので、その民族的性質をより濃く表現されるものである。 思えば昨今の「反日」「嫌韓」で日韓関係は悪化の一途を辿っている。 だが我々日本人は本当に韓国や北朝鮮の人の性質を、理解出来ているのであろうか? 「馬糞を知らずに、馬の医者になる」という朝鮮のことわざがある。馬を知らない医者が病気の馬を診察しても良くなるわけがないように、その民族の精神や特性を知る事が、今の我々や日韓関係には大切なことではないだろうか? お互いを知る事から、真の友好が始まる。 朝鮮のことわざをカルタ風のイラストと共に楽しく学んで頂き、お互いの理解が少しでも深まれば嬉しく思う。 最後になるが、本書が日韓友好の一助となる事を切に願うものである。 (本書「はじめに」より) 出版社からのコメント ご注意 本書で用いられている用語や表現の中に、現在の日本では差別的表現とされる可能性のあるものが一部含まれていますが、作者及び出版社に差別の意図はまったくありません。 ことわざが生まれた当時の時代背景を鑑み、また朝鮮民族の文化を尊重するため、あえて言い換えなどをせず、そのままにしてあります。 本書は「お互いを知ることから真の日韓友好が始まる」という信念に基づいて執筆されており、私たちがこれを出版いたしますのは、この作品の根底に流れる「日韓友好」「差別反対」などのテーマをより広く社会に訴えることに意義があると考えたからです。 読者のみなさまにもこの問題に対する理解をより深めていただければと考えています。 株式会社 青林堂
-
4.1
-
3.0
-
3.0過酷な断食を繰り返して痩せさらばえた行者が、自らの身を地面に沈め、「土中入定」を果たす。かつて、自らがミイラ化することで、衆生の救済をめざした僧侶たち、すなわち即身仏がいた――。 現在、全国で確認されている即身仏をほぼ網羅する全18体を訪ね歩いた、異色の紀行文。それぞれのミイラ仏にまつわる伝承に加え、即身仏を守り継ぐ人々、信仰する人々の声を丹念に取材した。1996年刊行の『日本のミイラ仏をたずねて』に、宗教学者・山折哲雄氏の「出羽三山即身仏考」を新たに収録。現代即身仏研究の定番書となる一冊。 〈収録寺院・即身仏〉 ◎茨城県岩瀬町妙法寺・舜義上人 ◎福島県浅川町貫秀寺・弘智法印宥貞 ◎宮城県白石市萬蔵稲荷神社・萬蔵 ◎山形県米沢市松本茂方・明海上人 ◎山形県白鷹町蔵高院・光明海上人 ◎山形県朝日村大日坊・真如海上人/注連寺・鉄門海上人 ◎山形県朝日村本明寺・本明海上人 ◎山形県鶴岡市南岳寺・鉄竜海上人 ◎山形県酒田市海向寺・忠海上人/円明海上人 ◎新潟県村上市観音寺・佛海上人 ◎新潟県鹿瀬町観音寺・全海法師 ◎新潟県寺泊町西生寺・弘智法印 ◎新潟県柏崎市真珠院・秀快上人 ◎長野県阿南町新野・心宗行順大行者 ◎岐阜県谷汲村横蔵寺・妙心上人 ◎京都市古知谷阿弥陀寺・弾誓上人
-
4.0
-
-
-
-『ダンマパダ』第1章から第3章までの由来を物語る全32話 初期仏教最古の詩篇のひとつとされ、古来広く伝承されてきた『ダンマパダ(真理のことば)』。 そのパーリ語註釈書に説かれる、これらの詩句にまつわる物語を原典から全訳! ・口論を続ける比丘たちに失望し、象の世話を受け独りで雨安居を過ごしたブッダ ・サーリプッタとモッガッラーナの誕生から出家までと前世の誓願 ・ブッダに敵対して生きながら地獄に落ち、十万劫後に独覚となるデーヴァダッタ ・マハーリに問われて、ブッダが三十三天とその王サッカ(帝釈天)の由来を語る など、ブッダゴーサの珠玉の筆致で語られる、時にウィットに富み時に心が洗われる物語の数々を、ご堪能あれ!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation; DX)は,大量のデジタルデータをAI(Artificial Intelligence, 人工知能)やIoT (Internet of Things)の技術に活かすことで,業務プロセスの改善,製品やサービス,ビジネスモデルそのものを変革するとともに,組織,企業文化,風土を改革し,競争上の優位を確立することを目指しています。そのためにはその変革を成し遂げる人材の育成が最重要課題です。本書では様々な産業活動による排水の処理について取り上げ,DXがもたらす効果を記述しました。 データサイエンスをコンピュータシミュレーション(モデル)と融合することで,新しい技術を創出し大きな変革につなげることができる可能性を,事例とともにお伝えできればと考えています。 物理や数学が苦手な方や人事異動で新しい部署で関わることになった技術者,また今後の活躍を秘めている若手にも,学習意欲を掻き立て,自分たちのアイデアを具現化するための一助となるよう執筆いたしました。
-
-1,100円 (税込)弘法大師空海、御誕生1250年 目次 【巻頭特集】南方熊楠と高野山の土宜法龍 高野山 武将たちが求めた安息の地 【巻頭言】今も昔も多くの人々や魂が集う 高野山への誘い 第一章・平安─鎌倉時代 開基から武士の入山 空海の生涯にみる 高野山成立と弘法大師伝説の誕生 嵯峨天皇の庇護を受け紀州の霊山に伽藍を建立 空海入定し その存在は永遠となる 高野山霊宝館で観る 豊麗な仏教美術の数々 貴族から武士へ 源平時代と高野山 平清盛 弘法大師の化身と会い根本大塔を再建した 北条政子 源頼朝の妻が建てた現存の寺院と宝塔 【高野山ゆかりの人物事典】其の壱 藤原道長・足利義満・平敦盛・熊谷直実 古地図と古写真で訪ねる 高野山 境内・奥之院 第二章・戦国時代 戦乱の中の高野山 【寄稿】調査から探る 高野山の石塔と戦国武将の真の姿 武将たちが信仰せし霊峰 上杉謙信・景勝 世を捨て、高野山に隠棲しようとした 武田信玄・勝頼 その死から3年後、位牌が納められたと伝わる 装化した聖地 覇王・信長と対峙 信長の紀州攻めを受け あわや全山が戦場に 信長に焼かれた比叡山 辛くも免れた高野山 忘れ去られていた信長の墓 妹・お市たちの菩提寺 天下人・秀吉が聖地に刻みし足跡 秀吉の紀州攻めと青巌寺の建立 高野山を舞台にした豊臣親子の確執 奥之院に眠る豊臣一族の魂 【高野山ゆかりの人物事典】其の弐 北条早雲・明智光秀・柴田勝家・黒田官兵衛・筒井順慶 第三章・江戸時代 徳川政権下の高野山 江戸の泰平を築いた徳川家の人々も祀られる 徳川家康 三河の豪族から興り戦乱の世に終止符を打つ 徳川秀忠・家光 家光により高野山に建立された霊廟 徳川家霊台 絢爛豪華な須弥壇と厨子が残る 紀州と尾張の徳川家 高野山を手厚く保護、歴代藩主も眠る 破れし武士たちの御霊を鎮める真田家三代の人物像 真田昌幸・幸村 高野山に蟄居の後、武士の矜持を貫く 【ルポタージュ】真田幸村の足跡とともにたどる 高野山と大坂の陣 石田三成 生前に自らの墓を高野山に建立した 名だたる雄藩の廟所が並ぶ奥之院 佐竹義重 義を貫く志が格調高き霊屋から伝わる 最上義光 東北の雄にふさわしい威厳を放つ石塔 伊達政宗 仙台の本家と宇和島の分家が肩を並べる 前田利家 高野山にふさわしい禅を捉えていた武将 島津家久 累代に渡り「お骨上がり」を続けた島津家 毛利元就 高野聖・勢尊法印と師檀の関係を結んだ武将 【高野山ゆかりの人物事典】其の参 浅野長矩・松尾芭蕉・大岡忠相・井伊直弼・市川團十朗 第四章・空海の伝承 弘法大師・空海の生涯と高野山の開山 【寄稿】空海が到達した最高の境地 密教とは何か? 空海誕生 なぜ、仏の道に目覚めたか? 無名の沙門・空海 ついに海を渡る 34日間の漂流の末、赤岸鎮上陸 長安入京、唐の文化と密教の奥義を学ぶ 帰国した空海、入京の許しを待つ 空海、神の化身に導かれ高野山へ 空海から弘法大師へ……その存在は永遠となる その後の高野山と真言密教の広まり 第五章・宿坊に泊まる 戦国武将と高野山の宿坊 時空旅人 SELECT SHOP 大人が観たい美術展2023 告知 奥付 裏表紙
-
-1,200円 (税込)平清盛や源頼朝、義経たちが繰り広げた諸行無常の物語を紐解く 目次 人形アニメーションの巨匠 川本喜八郎、“平家物語”を創る Special Interview 人形劇団「貝の火」 主宰 伊東万里子 女優 紺野美沙子 大人が読みたい平家物語 川本喜八郎の世界 第一章 平氏の栄華 『平家物語』はなぜ、語り継がれるのか 永久6年-保元元年(1118-1156) 清盛の苦悩と野望 保元元年(1156) 保元の乱 平治元年(1160) 平治の乱 column 源為朝の伝説と武 永暦元年(1160) 源頼朝、伊豆へ配流 清盛と一門の天下 第二章 清盛の死 安元3年(1177) 鹿ヶ谷の陰謀の謎 column 義経・弁慶の出逢い 永暦元年-治承4年(1160-1180) 頼朝と北条一族 治承4年(1180) 頼朝の挙兵 治承4年(1180) 11月9日富士川の戦い column 平清盛の死 column 重衡の南都焼討と東大寺の復興 治承4年-寿永3年(1180-1184) 義仲の天下 信濃源氏の拠点・木曽谷に残る古刹とは 木曾義仲の聖地をゆく 甲府から北へ離れた甲斐源氏の発祥地 武田太郎の郷を訪ねて 国民的作家が愛した吉野村の書斎へ 吉川英治と“新・平家物語” 第三章 源平合戦 寿永3年(1184)2月7日 一ノ谷の戦い 寿永4年(1185)2月19日 屋島の戦い 寿永4年(1185)3月24日 決戦、壇ノ浦 column 腰越の悲劇 文治2年(1186)4月 平家物語 終章 第四章 鎌倉殿と北条氏 文治3年(1187) 義経、奥州へ 文治5年(1189) 頼朝の奥州討伐 Epilogue 『吾妻鏡』空白の謎と御家人らの動静 鎌倉殿の最期。北条政権、誕生へ 富士山麓に宿る平家伝承 重盛と維盛の面影を追う column 『平家物語』年表&相関図 厳選グッズ通販 時空旅人SELECT SHOP ベストシリーズ 日本の城を往く ─現存十二天守と三英傑の城─ 告知 奥付 裏表紙
-
-900円 (税込)歴史、文化を紐解く「時空旅人」は、ひとつのテーマをより掘り下げて特集します。 目次 今だから読みたい大人の昔話 【巻頭コラム】昔話はどのように伝わってきたか?伝承の魅力 巻頭特集 泣ける!笑える!知られざる名作昔話に出会う ゆりわか大臣 石童丸 白菊物語 ねずみの嫁入り、京ノ蛙大阪ノ蛙、クラゲのお使い、人まねじいさん 第1特集 一度は聞いたことがある定番の昔話 五大昔話・続五大昔話 独自の世界観 五大昔話を読み解く 浦島太郎 猿カニ合戦 舌切り雀 花咲か爺 桃太郎 続・五大昔話の世界観 ぶんぶく茶釜 一寸法師 鶴の恩返し 瘤取り爺 かちかち山 COLUMN ”語り“とは何か? 疫病退散と伝承 第2特集 四季と昔話の不思議な関係 春 物事の始まりを告げる季節 夏 異郷との接点が広がる季節 秋 実りの季節に関わる昔話が描かれる 冬 正直に生きる人達が不思議な出来事と遭遇 伝説の御伽衆・曽呂利新左衛門 第3特集 よるのむかしばなし 民間に伝わりし百物語の世界 昔話に秘められた怖いあらすじ 艶笑譚と五穀豊穣 人の一生にも重ねられる普遍的な話の展開 厳選グッズ通販 時空旅人 SELECT SHOP サンエイ新書/時空旅人 告知 奥付 裏表紙
-
4.0「正統竹内文書」の継承者・竹内睦泰氏が一族のルールを破って秘伝を公開。超能力者・秋山眞人氏がシンボル学、霊能の視点で分析。ハーバード大学院出の竹内文書研究者・布施泰和氏が、ジャーナリスティックに解説。 太古の地球/日本の成り立ち/古代ユダヤの叡智/神話・伝承・お伽話......ついに世界の雛型〈ニッポン〉の真相が見えてきた! (本書は2015年7月に刊行された『正統竹内文書 口伝の『秘儀・伝承』をついに大公開!』の新装版です) 秘伝1......「宇宙」は竹の筒の中にあるとしていたから、「筒」は膜宇宙であり、「竹内」とは宇宙そのもの! 秘伝2......八咫烏(やたがらす)は実在の人物オオナムヂの子、アヂスキタカヒコネである! 秘伝3......故郷日本を目指した陸路の〈出雲族〉と海路の〈天孫族〉以外に、のちに富士王朝を設立した草原ルートの「第三の部族」がいた! 秘伝4......「籠の中のとり(イ)」=鳥居=十の理=モーゼの十戒! ◎ 九州と近畿に同じ地名が散見するのは、邪馬台国が二度東遷したから ◎ 『竹取物語』は、天皇家が宇宙人に接触しようとした話 ◎ 『浦島太郎』は、崇神天皇の御代に出雲の巫女が陵辱された報復劇 ◎ 古事記は国内用、日本書紀は海外用の政治文書 ◎ 山の「高み」を結んで三角測量していた古代遺跡群 ◎ 宇宙人は13進法を使っている! ◎ 大相撲を見れば、地震は予知できる! ◎ シンクロニシティ(共時性)は、統計・確率を偏らせる「有り難い」神力 ◎ お金とサービスの代償で成り立つ「経済」こそ、最大の霊的オカルト現象! ◎ これから、奇跡の多発化&超常現象バブルが起きる! ◎ スピリチュアルの論法を、暴走する自我の擁護に使うな
-
-改定保育所保育指針・新保育士養成課程に対応!実践力のある保育士の養成にピッタリ。 2019年度入学生から適用される新保育士養成課程に対応したテキスト。改定保育所保育指針等,保育を取り巻く社会情勢が変化する中において,より実践力のある保育士の養成に向けて,それぞれの科目における関連性が見直され整理された。これを受けて本書では,「資料」・「実践事例」・「コラム」を多く配置した。さまざまな場面の子どもと家庭・保育士・社会の今日的な様子から「子どもと家庭をめぐる状況,保育士養成教育において子育て家庭支援で強化する内容」につながる課題を読み取ることができる。 【発行・発売/ななみ書房】 【目次】 第1章 子ども家庭支援の意義と役割 1 子ども家庭支援の意義と必要性 2 家族・家庭の動向 3 現代の子育て困難 4 これからの子ども家庭支援 第2章 保育士による子ども家庭支援 1 子ども家庭支援の目的 2 子ども家庭支援の対象と内容 3 保育士に求められる基本的態度 4 育児モデルとなる伝承の育児法 第3章 多様な支援の展開と関連機関との連携 1 主な関連機関との連携 2 保育所利用家庭への支援 3 地域の子育て家庭への支援 4 父親の子育てへの支援 5 要保護児童家庭への支援 第4章 子育て家庭に対する支援の体制 1 子育て家庭の福祉を図るための社会資源 2 子育て家庭支援の制度 3 子育て家庭支援の政策動向と課題 第5章 世界の子育て 1 国際比較 2 スウェーデンの子育て家庭支援 3 カナダのファミリーサポート 4 フィンランドのネウボラ 【著者】 松本園子 お茶の水女子大学大学院家政学研究科児童学専攻修了・家政学修士 白梅学園大学名誉教授 著書等 『昭和戦中期の保育問題研究会- 保育者と研究者の共同の軌跡1936 〜 1943』新読書社 2003 『乳児の生活と保育』ななみ書房 2011(編著) 『実践・家庭支援論』ななみ書房 2011(共著) 『子どもと家庭の福祉を学ぶ』ななみ書房 2013(共著) 『証言・戦後改革期の保育運動—民主保育連盟の時代』新読書社 2013 『日本の保育の歴史-子ども観と保育の歴史150 年』萌文書林 2017(共著) 永田陽子 日本女子大学大学院家政学研究科児童心理学専攻修了・家政学修士 東京都北区子ども家庭支援センター・北区男女共同参画センター専門相談員 東洋英和女学院大学大学院非常勤講師 [著書等] 『乳児の保育臨床学』東京教科書出版 1991(共著) 『人育ち唄』エイデル研究所 2006 『子どもと親を幸せにする 保育者・支援者のための保育カウンセリング講座』フレーベル館 2007(共著) 『実践・家庭支援論』ななみ書房 2011(共著) 『0歳児保育革命1』ななみ書房 2017 福川須美 都立大学大学院社会科学研究科社会学専攻修了・社会学修士 駒沢女子短期大学名誉教授 [著書等] 『ここが違うよ,日本の子育て』学陽書房 2002(共著) 『世界に学ぼう!子育て支援』フレーベル館 2003(共著) 『実践・家庭支援論』ななみ書房 2011(共著) 『家庭的保育の基本と実践』福村出版 2017(共著) 森和子 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科発達社会科学専攻修了・教育学修士・社会科学修士 文京学院大学教授 [著書等] 『里親入門-その理解と発展-』ミネルヴァ書房 2005(共著) 『臨床に必要な家庭福祉』弘文堂 2007(共著) 『実践から学ぶ-子どもと家庭の福祉』保育出版 2008(共著) 『子どもと家庭の福祉を学ぶ』ななみ書房 2013(共著)
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 なぜこんなにも世界中に巨人の伝説が残されているのか? 失われた人類の記憶! 神話に込められた巨人伝説。人類の祖先は巨人だった!? 驚くべき伝説・伝承の数々。古今東西世界中に残る巨人にまつわる伝説をイラストと共に解説する!
-
4.1驚くべきことにドイツの学生結社は今日でも、鋭い真剣を用いた決闘が一部の学生の間で普通に行われている。一九八○年代初頭にドイツ留学した著者はふとしたことから学生結社に誘われ、そこで決闘を経験する。文豪ゲーテ、哲学者ニーチェ、政治家ビスマルクらはもちろん、現在の政財界を担うドイツのエリートの多くが決闘経験者という事実。本書は、武士道にも通じるゲルマン騎士の「高貴なる野蛮さ」を具現する決闘文化に迫るドキュメントである。【目次】プロローグ/第一章 ドイツの決闘/第二章 決闘の掟/第三章 学生結社の日常/第四章 伝承と継承 高貴なる野蛮/エピローグ/あとがき
-
4.3底無しの黒い恐怖!! 黒史郎の実話怪談新シリーズ始動! 現代で採集された話と先人の記録(のこ)した譚(はなし)を読み比べる―― 「わたしからサオリを奪った男って…」 何万人ものアカウントから特定し、つきまとう女! 「裏アカ女子」より 「妹の顔の皮を剥いで遺体を雪の下に埋めた…」 そして、兄は家へ入るなり卒倒した! 「皮むき峠」より 奇妙でじわじわ怖い――ホラー作家・黒史郎が紡ぐ実話怪談の新たなシリーズが発動。 ・登山中の若い頃の祖父の写真、妙な違和感を覚える「救助者」 ・母親が描いた怪人の絵を異様に怖がる息子がある夜…「悪魔が来る」 ・自分と合わない客には露骨に不愛想になる飲み屋の女将の理由「寄る辺」 ――など、著者が採集した現代の怪談の数々と、民俗資料や伝承記録から先人が残した怪談を掘り起こして収録。 体験した者がいて記録する者がいるのは今も昔も変わらない――怪談フリークが紡ぐ新たな読み味をお楽しみいただきたい。
-
-古代インドで仏教と同時期に同地域で誕生し、いまなおインドで続くジャイナ教。初期仏典にも多くの記録が残り、祖師マハーヴィーラは六師外道のひとりニガンタ・ナータプッタとされ、主な教義と死亡記事も伝わる。しかも、ジャイナ教聖典と同一の詩句が仏典中に多く見られ、仏教の教えとして伝わっている。 ジャイナ教徒はインド総人口のわずか0.4%ではあるが、19世紀にはインド民族資本の大部分を占めていたといわれ、マハートマ・ガーンディーの非暴力・菜食主義に影響を与え、南方熊楠はその徹底した不殺生を仏教よりも高く評価した。 本書には、ジャイナ教の二大分派である白衣派の聖典から、【第Ⅰ篇】には古層文献を、【第Ⅱ篇】には出家者と在家者との戒律文献を、【第Ⅲ篇】には初期仏典と共通する伝承から作られたパエーシ王の物語を、【第Ⅳ篇】にはジャイナ教の祖師マハーヴィーラの伝記を収めた。 【第1章】『アーヤーランガ』第一篇は、出家修行者が解脱を達成するために遵守すべき禁欲的な修行生活全般を主題とする。なかでも第九章は、マハーヴィーラ出家後の厳しい苦行生活を古風な韻文で描いた、最古の祖師伝である。 【第2章】には、『スーヤガダンガ』第一篇第四章と第五章第一節を収めた。前者は男性出家者が女性との接触を避けるべきことを教示しており、最初期ジャイナ教のジェンダー観に有意な資料を提供する。後者は最初期ジャイナ教の地獄観を表す資料であり、『スッタニパータ』などの初期仏典、ヒンドゥー教の大叙事詩『マハーバーラタ』や法典『マヌ法典』にも類似した観念が見出され、当時の地獄観の共通認識を知るうえで欠かすことができない。 【第3章】には『ウッタラッジャーヤー』から古層に属する第一章から第二〇章、そして第二五章を収めた。出家者の生活への心構え、説話、伝説、対話篇、修行論、解脱論や業論といった教学的議論など、さまざまな内容で構成され、仏典にも並行する詩句が見出される。 【第4章】『ダサヴェーヤーリヤ』(十夜経)は、基本的な教義や出家生活上の規定をまとめた白衣派の古層をなす聖典であり、現在でも出家の儀式を終えた者が最初に学習する派もある。 【第5章】『ウヴァーサガダサーオー』第一章は、白衣派聖典中、もっともまとまって在家信者の宗教生活を説く章であるとともに、後に数多く著された在家信者向けの行動規範マニュアルの祖型ともなり、ジャイナ教の在家信者観をうかがう上で欠かすことのできない資料である。 【第6章】には、来世を信じず霊魂と身体が同一であると主張するパエーシ王と、ジャイナ教僧ケーシの対話である「パエーシ王物語」(『ラーヤパセーニヤ経』後半部)を収めた。訳注には、これに並行するパーリ仏典と3本の漢訳仏典との対応箇所を記した。 【第7章】には、白衣派ジャイナ教在家者にもっともよく知られる『ジナチャリヤ』(ジナたちの伝記)からマハーヴィーラ伝を収録した。 【第8章】『ヴィヤーハパンナッティ』第九篇第三三章「クンダッガーマ」を収めた。前章においてマハーヴィーラは最初にバラモン族の夫人の胎に宿り、胎児のままクシャトリア族の夫人の胎に移った。本章前半では、最初の母であるバラモン族の夫人と夫がマハーヴィーラと再会し、出家して解脱するまでが描かれる。後半部では、最初の教団分裂を引き起こしたジャマーリの出家から死までが記され、仏典におけるデーヴァダッタの破僧事件を彷彿とさせる。 アルダマーガディー語原典から訳出された本書により、マハーヴィーラ在世時の姿が、ここに蘇る。
-
-1巻815円 (税込)参議院議員 和田政宗 アジアで圧倒的1位になれる日本の独自技術 呉善花 韓国の親北姿勢を理解するための「チュチェ思想」 [対談]矢作直樹 並木良和 外国に利用されない意識をひとりひとりが持てば日本は変わる 小川榮太郎 陳腐化した政権批判に終止符を、真の安倍政権応援とは何か ドクタードルフィン 松久正 龍神エネルギー封印解除とドラゴンパワーの覚醒 〈インテリジェンス入門〉戦前の対外情報機関と国際共産主義 江崎道朗 日本の「外国人犯罪」 中編 隠された「在日」犯罪検挙数 坂東忠信 神話と伝承に読み取る〈和の心〉と〈日本の国柄〉 小名木善行 渡邉哲也 イギリスEU離脱で加速、世界は冷戦構造下に逆戻り!? [本誌初登場]森口朗 経営者も労働者も追い詰める危険なユニオン! [本誌初登場]八木龍平 王道の神社参拝 諏訪大社 靖國神社 半井小絵 〈憲法改正〉何もしない憲法調査会ならいらない 赤尾敏が総理大臣ならこうする! 赤尾由美 疑問を持てばライオンに食われる、ただ「愛されている」と信じて! 保江邦夫 中国に狙われた日本のIR利権 安積明子 パワースポットで何を学ぶか 中矢伸一 天宇受売命 自由、創造性、楽しさ、そして情熱を、全身で表現する女神 大野百合子 [特集]中国とのビジネスに要注意 覆面座談会 中国人との取引には落とし穴!? 佐藤守 アメリカによるイラン司令官殺害と金正恩委員長の苦悩? 千葉麗子 チバレイのフォトレポート第13回 『英霊たちの肖像 関行男命 ―前編―』 富田安紀子 『アマテラスの翼』 孫向文 在日特権は存在している、決して都市伝説ではない 後編 井上太郎@kaminoishi 中国に飲み込まれる沖縄! チャイナマネーの破壊力 依田啓示 現役秘書が語る国会と官僚の裏事情15 吉田燈 医療という専門性を最大限に悪用した労災認定乱発 村上 淳一郎 戦場の先輩たちの跡を追って(五) 第十三期海軍甲種飛行予科練習生 森山利秋氏 久野潤 靖國神社崇敬奉賛会青年部『あさなぎ』 パンパカ工務店
-
4.0中国から伝わった十二支、干支(かんし)は、今なお日々の暮らしの中に息づいている。干支とは十干(甲乙丙丁…)と十二支(子丑寅卯…)を組み合わせた六十干支のことで、陰陽五行思想と結びつき、さまざまな伝承や俗信も生まれた。本書では、十二支がどのようにして生まれ、発展・変遷してきたかを中国の歴史からひもとき、年月日・時刻・方位・吉凶など様々な切り口、テーマで丁寧に解説していく。貴重な古図版も多数掲載。
-
3.0“樹木”と聞いて、あなたが思い浮かべるものは、何でしょう?冬、クリスマスにはいわゆるモミが、正月にはマツが、飾られます。季節の終わりには、ウメの花がほころびます。春、スギの花粉が我々を悩ましたかと思えば、サクラが淡い桃色の花を華やかに咲かせます。夏、ヤナギが風にそよぎ、涼を運んでくれます。桃が収穫されるのは、この季節です。秋、カエデやイチョウは鮮やかに紅葉し、林檎・葡萄・栗など、さまざまな実りがもたらされます。本書では、様々な樹木にまつわる、世界各地の伝承や民話に残されたエピソードを紹介します。
-
-古来、人間は、木を伐ることで樹木の無限の恵みを引き出し、利用してきた。英国の沼沢地の萌芽更新による枝を使った石器時代の木道、スペインの12世紀の手入れされたナラの林、16世紀のタラ漁船のための木材づくり、野焼きによって森を育んだ北アメリカの先住民、日本の里山萌芽林。米国を代表する育樹家が、世界各地を旅し、1万年にわたって人の暮らしと文化を支えてきた樹木と人間の伝承を掘り起こし、現代によみがえらせる。
-
-監督就任11年目で 11度の甲子園出場。 冬の3カ月間は室内練習場にこもりきり というハンデをものともせず、 北陸勢初の全国制覇に、 ベスト4二度、ベスト8一度。 チーム全体が高い目標と強い覚悟を持って、 時に理不尽なまでの厳しい練習に取り組む。 代々これを絶やさずに続けていくことで、 そこに「強さの伝承」が生まれる。 「勝てる集団」を作るための、 命を懸けた本気の指導論 著者は、以下のように述べています。 私が監督となった2011年秋以降、敦賀気比は2017年を除くすべての年で春・夏いずれか(もしくは両方)の甲子園に出場している。2015年のセンバツでは、選手たちのがんばりのおかげで北陸勢として初となる全国制覇を成し遂げることもできた。 甲子園に毎年のように出ているからか、周囲からは「敦賀気比は甲子園に出て当たり前」と思われている。みなさんがそのように思ってくれるのはありがたいが、その分プレッシャーも大きい。毎年、夏の大会期間中は眠れぬ夜を過ごす。 また、冬の12~2月にかけて、敦賀は雪に覆われるため、屋外での練習はほぼできない。私たちは3カ月もの間、ふたつある小さな室内練習場にこもり、ひたすら練習を続けるしかない。これは、一年中、屋外で練習できるチームと比べたら相当なハンデである。でも、私たちは春のセンバツで日本一になることができた。 本書では、私たちがいかにして甲子園常連校となり、北陸勢初の全国制覇を成し遂げるまでに成長できたのかを詳しくお話ししていきたい――本文より ■目次 第1章 北陸勢初の全国制覇までの道のり 監督就任早々、北信越大会で優勝してセンバツ出場/北陸勢初の全国制覇~2015年センバツ~ ほか 第2章 やんちゃだった私がなぜ指導者になれたのか? 敦賀気比の監督に就任~なぜ指導者となって早々に結果を残せたのか?~ ほか 第3章 東流「長所を伸ばす」指導法 核となる選手を作り、チームを熟成させていく/技術指導はヒントを与える程度 ほか 第4章 甲子園で勝つための練習 冬は室内練習場で徹底的に体力強化/実戦を意識したピッチング練習 ほか 第5章 北陸勢初の夏の甲子園優勝を目指して 甲子園に出て当たり前の中で戦う過酷さ~妻に感謝~/甲子園には勝ち方がある/北陸勢初の夏の全国制覇に向けて ほか
-
-平安中期の女流歌人和泉式部は、無数といってもいいほどの多くの伝説につつまれている。著者は全国各地にみられる和泉式部にまつわる言い伝えにメスを入れ、そこにかって顧みられなかった大切な日本人の歴史が潜んでいることを発見する。遊行女婦、歌比丘尼、刀自、念仏と物狂いなど、数多くの事例が和泉式部伝説とつながりのあることが明らかにされていく。日本の民間伝承にはじめて学問の光をあてた画期的著作。
-
4.0全国の神社情報を扱うポータルサイト「神社人」主宰である著者が、4年にわたる活動の軌跡と、神社や神道などの日本人が意外と知らない日本の文化・伝承を紹介する。
-
-千所千泊。そうして私は自分の知らない自分を見つけてきた。 今回のテーマは「旅と人生」。日本各地の見知らぬ土地を訪れ、そこで泊まることを志しているという作家・五木寛之。なぜ旅に出かけるのか? 旅に出ると発見がある。自分の目で見て、足で歩き、人々と触れあい、その肉声に学ぶことで、その土地の陰影が生じて旅の面白さが増す。それを味わい、反芻することで、新しい自分を知ることができる。そして、今や「百年人生」と言われる人間の寿命そのものが長い旅でもある。90歳の「生き方の先輩」が贈る人気シリーズ。第6弾! 第1章 日本の旅が示唆してくれるもの 第2章 食の体験を思い返しながら 第3章 人と芸能――山形と秋田の旅 第4章 風景と伝承――鳥取と島根の旅 第5章 宗教と文化――大阪の旅 第6章 「心の武器」が人生を豊かにする
-
4.02020年は『日本書紀』編纂からちょうど1300年の年に当たります。 最近では、古代史ブームの高まりから、初代とされる神武天皇以降の「初期天皇」、葛城氏をはじめとする古代豪族など、教科書には載っていない3~5世紀の時代への関心も高まり、その歴史的重要性が見直されつつあります。 本書では、登場人物を中心に『日本書紀』を扱うことで、個々の登場人物の魅力や「その後」、ほんとうに敗者だったのか、その後どのように伝承されていったのか、など、『日本書紀』をより楽しめます。 「日本書紀の基礎知識」「初代神武天皇から41代持統天皇までの歴代天皇」「皇子、女性、豪族など個性豊かな登場人物」という3つの柱で、総計で150人以上の人物を収録。 関連図版・地図も挿入し、ふだん古代史に触れていない方にもおすすめです。
-
4.2ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』は、多くの音楽ファンの心を烈しく揺さぶる一大傑作である。また『ニーベルンゲンの歌』は古代ゲルマンの英雄伝説を素に、13世紀初頭に成立した一大叙事詩である。両者に共通する「ニーベルング(ゲン)」は地下に住む妖精の名前である。そしてこの侏儒がとてつもない財宝を所有していた。この財宝をめぐってさまざまな闘争が繰り広げられ、壮大な物語へと発展していくのである。この物語の主人公ジークフリートのルーツはどこにあるのか。古代ゲルマンの「竜退治」「財宝獲得」の英雄伝説や北欧の伝承『歌謡エッダ』『サガ』などの系譜を辿り、また、主人公の人間像と楽劇の魅力を徹底的に読み解き、ドイツ文化の特質とその精神の核心に鋭く迫る。 〔文庫書き下ろし〕 第1章 ニーベルンゲン伝説の生成 第2章 北欧への伝承 第3章 ドイツ中世英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』 第4章 新しいタイプの伝承 第5章 ドイツ・ロマン派による伝承 第6章 19世紀における戯曲作品 第7章 ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』4部作 第8章 20世紀のジークフリート伝説 結び ジークフリート伝説の系譜
-
3.5「落人伝説」のある街に赴任してきた不動産営業マンの藤墳は、丘の上で不思議な青年・破金に出会う。破金は、かつて「蘇芳」という一族に追われこの地に逃げてきた氏族の末裔で、今でも「蘇芳」を恐れて生きている。いつかこの街にくる「蘇芳」を破る(=殺す)ために育てられたのが破金だという。藤墳は、伝承に囚われて次第に疲弊していく破金に惹かれ、救いたいと思うようになるが、破金は藤墳が「蘇芳」ではないかと疑いを持ち―――?
-
-
-
-幼少期より様々な霊体験があった著者。 結婚、出産、子育てがひと段落した頃、霊的世界探求がエスカレートして、 著名な聖人たちが密かに学び訪れる陰陽道本拠地ジャワ島奥地にひとり潜入…… Jnana Kundalini Reiki 日本人初の伝承者である著者のスピリチャル修行体験記。 引き寄せ、不思議な出会い、体験はおとぎ話のようですがすべて実話です。 カラー写真掲載、臨場感溢れる体験記にワクワクドキドキ引き込まれていきます。 後半には、心を癒し解放するメッセージを厳選掲載。 何に意識を向け、何を選択していくかはあなた次第。 心を解放し次に羽ばたくのはあなたです。
-
-
-
5.0
-
-※本書は、ぶんか社より2007年に発売された『ズバリ図解 五輪書』を電子書籍化したものです※ 不世出の剣豪・武蔵が晩年に著した地・水・火・風・空の五巻から成る兵法書『五輪書』。 武蔵が幾多の戦いの末に到達した剣の思想が明確に示されており、剣道にたずさわる者だけでなく、一般読者も生きるうえでの指針、智恵、厳しい修行の道というべきものを読み取ることができるに相違ない。本書は武蔵の『五輪書』を現代語( <>山かっこ内)で平易に示し、それをさらに図解で示す方法を取っている。本書が剣聖・宮本武蔵の孤高の精神、厳しい鍛練道を把握するよすがとなれば幸いである。 ■主な内容 ・第一章 宮本武蔵と五輪書 宮本武蔵とは 『五輪書』とは 諸芸に通じた武蔵 出生地と姓の謎 若かりし戦いの日々 吉岡一門との戦い 巌流島の決闘 武蔵の生きた時代 (コラム)武蔵の恋 ・第二章 地の巻 二天一流の概略 ・第三章 水の巻 剣術指南 ・第四章 火の巻 戦術・戦略指南 ・第五章 風の巻 他流派の分析・批判 ・第六章 空の巻 至極の兵法 ほか ■監修者/志村有弘(しむら・くにひろ) 相模女子大名誉教授、県立神奈川近代文学館評議員、日本文藝家協会会員。説話・軍記を軸とした伝承文学を専攻。著書に『宮本武蔵を読む 新訳五輪書』(大法輪閣)、『羅城門の怪』(角川学芸出版)、『信長戦記』(ニュートンプレス)、『役行者のいる風景 ― 寺社伝説探訪 ―』(新典社)、『怪異な話 本朝不思議物語』(河出文庫)など多数。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 おりがみを折ると考え工夫する力がつき図形に強くなる。 おなじみ・人気・あこがれ作品のわかりやすい折り方と遊び方のヒントがいっぱい。 脳を育てるアドバイスも。 5才ぐらいから小学校低学年向けの大型おりがみ本。 おりがみは考える力、工夫する力を鍛えるのに最適。 四角、三角、半分など、図形を理解する力が育ちます。 おりがみつるや風船などのおぼえておきたい伝承作品や、 恐竜、スペースシャトル、ロケット、クジラ、ブレスレット、 花束などのあこがれの作品、ちょっとむずかしい折り方のチャレンジ作品、 遊び方、組み合わせ方をわかりやすいプロセス図でていねいに紹介。 仲間とのコミュニケーションに役立つ花束やカード、 袋や箱などの実用作品も楽しいし、少しむずかしい作品に挑戦する力もつきます。 この年齢のレベルに合わせた構成で、おりがみの技術とともに 知的レベルもぐんぐんアップする、オールカラーの決定版です。
-
3.5◆自己資金ゼロで驚異の月収450万円! ◆最短3年で不労所得生活! ◎区分不動産投資からスタートし、どんな逆境も乗り越えて 11億円の資産を築いた著者が伝授する 年収300万円からできる「脱・社畜」horishin流投資法 新時代の不労所得者のブッとんだ生活実態を公開! 【horishin流の伝承者たち】 ◎既婚者なのに彼女が複数! ◎55歳、クラブDJ! ◎31歳、不労所得1億円! ◎OL兼エステオーナー! ◎コロナショックで給与激減医師! ワンルームマンション、 〇ルガ地方一棟RC、 某シェアハウス、 全部持ってますが、なにか?
-
3.8
-
-
-
-本邦初公開! 一子相伝で伝承されてきた子平推命の源流が詳らかに! 人間の運命・宿命を知るための智慧の集大成! あなたの運命の喜忌にまで迫る決定版! 徐子平、徐大昇の正統を受け継ぎ、一子相伝で口伝されてきた子平推命の源流を日本で初めて本格的に紹介する書です。 秘匿とされてきた「審事」を明らかにし、命式を解読し、的中率抜群の子平理論がこの一冊でマスターできます。 人間の運命、宿命を知るための智慧の集大成である子平推命の具体例を豊富に盛り込み、四柱推命理論しか知らない方にもわかりやすく解説を施していますので、誰もが占った方の運命の喜忌にまで迫ることができます。 既存の四柱推命では物足りないかた、占いを実際に仕事として活用しているかた、これから占いを本格的に学びたいかたには特におすすめです。 四柱推命ではわからない運命の喜忌までがわかる子平推命を学ぶことで、より占いの的中率の精度を高められます。 「子平推命が一般の占いと違う点は、古代中国の伝統的な占術体系に属し、唐宋代の中国の歴史の中で完成していったものであり、本さえ読めばマスターできる占いの類いではないことです。なぜなら、子平推命は秘匿された占いであり、子平推命で行われる「審事」自体が口伝とされ文字として残されていなかったからです」
-
4.0アメリカ先住民のスー族に伝わる祈りの儀式や占術……。神秘的な伝承を貫くものは、大地を敬い、勇気を重んじる「心の文化」であった。比較文明学者がインディアンの精神世界を丁寧に読み解く瞠目の書。
-
-2002年、ガンジー・キング平和賞を受賞した世界的社会慈善活動家、純粋な「愛」そのもののダルシャンを行うインドの女性聖者、アマチ(アンマ)の教えをわかりやすく解説。その教えの基本は、インドの古代聖典ヴェーダの叡智。その主要なものは、心身を癒すアーユルヴェーダ(インド伝承医療)、運命を予知し転換させるジョーティシャ(インド占星術)、病を苦悩を根底から癒し魂を至福へと導く運気転換法とプージャ(儀式)。さらに、アマチ(アンマ)が展開しているホスピスなどの社会慈善活動を紹介。何千人、何万人訪れたとしても最期の一人を抱きしめるまで終わることがない、奇跡をもたらすといわれるダルシャンを世界中で行っている、アマチ(アンマ)の真髄に迫る。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ~「なぜ?」に重きを置き、思索しながら読む西洋音楽の歴史 ~ 西洋音楽史において展開されている音楽史的に重要な点と点を繋ぎ、 ある場面における変化の流れを詳しく、そして多面的に解き明かす。 各章とも、前半は政治的な出来事、文学や他の芸術にも触れながら、 それぞれの時代の音楽の歴史の概略を分かりやすい文章で説明し、 後半は前半で述べた内容を、具体的な音楽の現象の中に固定する構成。 具体的な音楽の例や簡潔な表などを用いながら、 音楽家でなくとも理解できるような言葉による、 分かりやすい分析と語り口のシリーズ第一弾。 第1巻は、起源(古代ギリシャ時代)から 16世紀(ルネサンス人文主義)までを収録し、 第一部は、「語り継ぐ伝承から書き記す伝承へ」、 第1章は、「古代ギリシャの音楽文明」
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 地図の中ならすぐにでも世界に行ける この本では、そらくん、あいちゃん、ビビが世界40カ国を飛び回り、その国のあそびを体験していきます。 世界のお友だちはどんなあそびをしているのでしょう そらくん、あいちゃん、ビビがある日、空を飛んで世界一周あそびの旅に出かけます 【著者紹介】 [絵]平澤 南(ひらさわ・みなみ) イラストレーター。実用書、教材などのイラストを中心に手がける。 挿絵に『この神さまに相談しよう』(飛鳥新社)、『人生が整う 家事の習慣』(西東社)などがある。 [文]ペズル 文筆家。著書に『三国志に学ぶ人間関係の法則120』(プレジデント社)がある。 [監修]寒川 恒夫(そうがわ・つねお) 静岡産業大学特任教授(早稲田大学名誉教授)、日本学術会議連携会員、学術博士。スポーツ人類学が専門。 著書に『遊びの歴史民族学』(明和出版)、『アジア稲作民伝承遊戯の文化史』(明和出版)、『民族遊戯大事典』(大修館書店)など。 【目次抜粋】 1 北アメリカ 中央・南アメリカ どうぞうあそび(アメリカ) イクシンミアク(カナダ) ほか 2 ヨーロッパ あくまのしっぽ(フランス) すずをおえ(イギリス) ほか 3 アフリカ アルハグラ(エジプト) ニワトリとイモムシ(モロッコ) ほか 4 オセアニア コップリレー(オーストラリア) ツバルのゆびずもう(ツバル) ほか 5 アジア 文字読みずもう(中国) サッチギサッチギサッポッポ(韓国) ほか
-
-1巻220円 (税込)世界同時金融緩和がもたらした低金利。ディスインフレが恒常的になったグローバル経済。低金利は一体何を表しているのか。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の共通の教典である「旧約聖書」はかつて金利を禁じ、経済発展の中で容認してきた。聖書と金利の関係が示す驚きの経済の仕組み。 目 次: はじめに ・聖書が禁じ、教会が認めた歴史 神と人の綱引きが定める水準 ・聖書と金利を読み解く7つの基礎知識 モーセはエジプト人? フロイトが唱えた異説 ・旧約聖書の源流 古き洪水伝承「アトラハシース物語」 ハンムラビ法典の金利は年20% 新王の即位で「徳政令」も ・金利の効能 不確実な未来に値段をつける 国家制度を維持するための「出挙」 ・コラム 古代エジプトからあったマイナス金利 ・コラム あせないエンデの「時間泥棒」 ・マイナス金利の必然 経済成長あがめる資本主義の転換点 ・コラム トランプに見る宗教 ・インタビュー 高階秀爾「為替手形を金利にしたメディチ家」 ・インタビュー 伊東俊太郎「西欧が学んだイスラム文明」 ・資本主義で後れを取ったイスラム 「法人」の否定が経済活動の足かせ ・西欧も尊崇 異教徒にも寛容だったイスラムの英雄サラディン ・コラム イスラエルを庇護する宗教国家アメリカ ・金利を肯定した仏教 商人が支えた「都市型宗教」
-
3.0歴史に残る有名な大事件の真相は? 語り継がれる奇蹟と伝説は本当に起きたことなのか? あの重要人物に秘められた疑惑と謎とは? あり得ない現象や未知の生物の正体は解明可能なのか? 古代遺跡と遺物にまつわる新たな仮説とは? ――語り継がれる伝説・伝承と不可思議な事象を現代科学はどう読み解くのか? 思わず誰かに話したくなる、謎と不思議の最新レポート!
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。




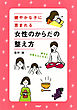




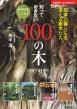



































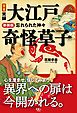



















![次元転換される超古代史 [新装版]正統竹内文書 口伝の《秘儀・伝承》をついに大公開! これが日本精神《心底》の秘密](https://res.booklive.jp/20029062/001/thumbnail/S.jpg)