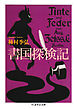筑摩書房作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-重度の障害を背負いつつも、自己への冷徹なまなざしを表現した数々の肖像画で多くの人々を魅了した、メキシコを代表する女性芸術家の生涯。描くことが生きること。キャンバスに心の葛藤を表現し続けた女性芸術家の生涯。
-
-「放射能」の命名者にして、二度のノーベル賞受賞に輝く女性科学者。あくなき探究心と闘志で科学界のみならず世界に影響を与えた生涯を描く。科学者として、他国の支配に苦しむ人として、女性として、母として、常にまっすぐ前を見ていた人。
-
-バレリーナの夢を断たれた少女は、「ローマの休日」で一躍スターの座に駆け上がる。世界を魅了した銀幕の妖精が生涯をかけて追い求めたものとは。「コンプレックスを武器に」スクリーンの“妖精”が輝き続けられた理由。
-
-四川料理が日本の家庭料理のひとつになったのは、この男がいたからだ。料理の確かな腕と好奇心を胸に日本にやってきた中国人青年の波乱万丈の物語。「少しウソのある料理」とは? 麻婆豆腐を日本に広めた男が教える料理の極意。
-
-水に落ちた犬は打つべし。一切の妥協を許さず容赦なく旧社会の儒教道徳や「正人君子」を批判し続けた中国近代文学最大の功労者の生き方を考える。「水に落ちた犬は打て」「私は人をだましたい」あの『故郷』の作家は、私たちに何を突きつけるのか。
-
-まずは、大バカな仲間の作り方、イカサマな金集め作戦など、マヌケ反乱の基本から始まる! そして、最高にマヌケな面白いやつと友達になったり、なんだか知らないけど生きていけたりする空間、金持ちや大企業によって作られた、働きまくって金を使いまくるような消費社会とは無縁な場所を作ろう!!
-
-
-
-
-
-モデルにならないか、とスカウトされ契約書にサイン、いざ撮影となって現場に行ってみたらAVだった。嫌だと訴えても、契約不履行で違約金がかかるぞ、親にバラすぞ、と脅され、仕方なく撮影に応じると、以後、次々に撮影を強要される……。「AV出演を強要された」女性からの生の声を聞き支援するなかで見えてきた、驚くべき実態を報告する。
-
-
-
-
-
-
-
-真言宗の開祖であり、傑出した思想家・芸術家。唐代の新しさを日本へ移入し、「個人」と「自由」を発見した“モダニスト”。それが空海である。9世紀、弘仁時代の先鋭的表現ともいえるこの人物は、生涯にわたり自らの探求心につき動かされていた。高野山が空海にとって特別な地であり続けた理由も、そのことを無視しては理解できない。空海における自己探求とはどのようなものであったのか? 本書では、『性霊集』『三教指帰』『請来目録』など、空海自身の著作の読解と足跡の探訪を通して彼が生きたであろう時空を共有し、その実像に迫る。稀有な個性の魅力と同時代性を深い共感とともに伝える入門書。
-
-
-
-
-
-山登りは絶対安全な管理された場所でのゲームではありません。便利な道具に頼らずに、しっかり準備をして、よく考え、注意深く行動すれば、その先に何ものにも代えがたい体験が……。頂には美しい景色と限りない「自由」が待っています!
-
-ゴミ箱というパンドラの箱を開けると、ツーンとした臭いの先に、都市生活者の事情が見えてくる。風俗嬢、ファストフード店、相撲部屋、不法滞在外国人、極道一家、新々宗教団体……のゴミ袋の中に押し込まれたそれぞれの素顔。本音と建前、虚栄心と劣等感が入り交じる欲望の残滓を捉えた写真ルポ。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-東日本大震災後の原発事故は、世界の原子力政策に大きな影響を及ぼした。欧州を牽引するドイツとフランスも同様。ドイツは二〇二二年までに全原発の停止を決め、フランスは原発依存の低減を目指しながら依然、国策として重視する。廃止を目指すにしても存続するにしても激しい対立と軋轢が起こる。日本ばかりでなく、世界が直面するジレンマである。特派員として両国で取材した記者二人が見た、独仏国内のルポルタージュ。欧州連合(EU)加盟の隣国同士ながら、対応が両極端に分かれたそれぞれの苦悩に迫る。
-
-『中観論』で名高い龍樹が自らの求道過程を綴った『十住毘婆沙論』。第二の釈迦と讃えられながら、自の力で悟りの境地に達することは、人間には不可能だと判断した龍樹は、阿弥陀の名を呼べば救われるという、誰もが実践可能な道=「易行道(いぎょうどう)」を発見する。『中観論』が学問的に仏教と向き合う書であるのに対し、『十住毘婆沙論』は、自らが見つけた易行道に、多くの迷える衆生を導きたいという、慈悲の心に彩られている。多くの浄土思想家たちに影響を与え、法然・親鸞がその教学の根拠とした究極の救いの書を、わかりやすい現代語訳と注釈で読む。
-
-民俗学の祖として知られる柳田国男。しかしその学問は狭義の民俗学にとどまらぬ「柳田学」として、日本近代史上に燦然と輝いている。それは近代化に立ち後れた日本社会が、今後いかにあるべきかを構想し、翻ってその社会の基層にあるものが何かを考え尽くした知の体系だった。農政官僚、新聞人、そして民俗学者としてフィールドワークを積み重ねるなかで、その思想をいかに展開していったのか。その政治・経済・社会構想と氏神信仰論を中心としつつ、その知の全貌を再検討する。
-
-
-
-女は女らしく、男は男らしく──。旧態依然とした価値観だが、どっこい今も生き残っている。どうしてなのだろうか? 性別の「らしさ規範」(女らしさ・男らしさ)が社会から消えないのは、どういう相手を性愛の対象として好きになるかという、人間の「感情」に固く結びつけられているからだ。しかも面倒なことに、性別規範は男女非対称にできている。だから「できる女はモテる」ということにはならない。本書では、社会的な性別機能の身も蓋もない現実を、透徹した視線で分析。男女それぞれの生き難さのカラクリを解剖し、社会構造変化の中でそれがどう変わりうるのかを俯瞰する。
-
-鳩山内閣の時に締結された日ソ共同宣言によってソ連との国交が回復し、シベリア抑留者の返還や日本の国連加盟などが実現した。しかしそれには、ソ連ばかりでなくアメリカの思惑や米ソの確執、それに何よりも自民党内の激しい権力闘争を克服しなければならなかった。同時に、「北方領土問題」はここから始まったのである。一九九〇年代以後に次々に明らかになった新資料を用いながら多くの謎を読み解き、日本外交の原型と可能性をも浮き彫りにする。
-
-
-
-有名芸術家の名作はもとより、版画や挿絵、広告や記念碑に至るまで、美術作品が、何のために、どのように描かれてきたか──それが「イメージの歴史」だ。ここではさまざまな学問領域を自由に往来し、ポスト・コロニアル的かつジェンダー的な視線で従来の美術史を書き換える。絵画と社会のかかわりや画像の解釈方法などの理論を踏まえ、さらに西欧文化が繰り返し描いてきたイメージにメスを入れ、その精神的・社会的な背景を明らかにする。レイプを描き続けたのはなぜか、新しい政治形態はどのような画像を生んだか──人間の想像力に新たな光を当てる美術史の誕生。
-
-
-
-
-
-孔子の生きた時代(前551?‐前479)、世は戦乱にあけくれ、殺戮と陰謀にみちていた。そのような状況下、孔子は、人間にとって重要なのは相互に愛情をもつことだとして「仁」の思想を唱え、政治はその実践であるとした『論語』を生みだす。その後『論語』は儒教の教典として崇拝され、文学的香気にあふれた含蓄深い名句の数々は、人間讃歌、人類永遠の古典として、現代に至るまで多くの人々に読みつがれている。本書は、表題作ほか、孔子と『論語』に関する初心者向けの論考六篇で構成。中国文学最高権威の著者が、人間孔子の精神と『論語』の思想を明らかにした入門書の名著。
-
-政治が乱れ、人の世が荒み果てていた時代、現在の人間に失望しつつも未来の人類に対して期待を抱き、人間の可能性に大きな信頼を持ちつづけた孔子。「論語」全訳・注釈を手がけた中国文学の碩学が二十篇五百章を自在に読みこみ、孔子の生き方と思想をわかりやすく解き明かす。「子曰く、仁遠からんや、我れ仁を欲すれば斯ち仁至る」。伊藤仁斎や荻生徂徠ら江戸の学者をはじめとする人々は「論語」をどのように読んだか。また、孔子が説きたかった仁とは何だったのか。諸国を旅して味わった失望や、弟子や民との対話を通して、孔子を語り、吟味する最上の入門書。
-
-
-
-
-
-人を納得させる議論には「型」がある。「定義」「類似」「譬え」「比較」「因果関係」──たった五つの論法さえきちんと使いこなせれば、誰だって自分の考えを的確に表現できるようになり、一見もっともらしい相手の主張の弱点も見えてくる。教育現場でディスカッションなどを指導する際の手引きとして書かれた本書には、議論に欠かせないこれらの技術の使い方と、それに対する反論の仕方といった、私たちが身につけておくべきイロハが明快に論じられている。豊富な実例を通して論証・反論の技術を磨く、確かな修辞学的知見に裏打ちされた入門書。『議論の技を学ぶ論法集』文庫版。
-
-中国スペシャリストとして、戦前の対中外交を率いた陸軍「支那通」。その代表的人物・佐々木到一は、孫文はじめ中国国民党の要人と深い親交を結び、第二次北伐に際しては国民革命軍にも従軍した。しかし、その後、支那事変(日中戦争)では南京攻略戦に参加して、いわゆる南京「虐殺」の当事者となり、戦後、激しい批判にさらされることになる。革命に共感を寄せ、日中提携を夢見た彼らが、結果としてなぜ泥沼の支那事変へと両国を導くことになったのか。われわれは、どこで道を誤ってしまったのか? 「支那通」の思想と行動を通して、戦前の日中関係の深層に迫る。
-
-赤羽・立石・西荻窪──。古き良き呑み屋街にはそれぞれの歴史がある。アメリカ生まれの著者が酒のグラスの向こうに見たのは、闇市のにぎわう猥雑でエネルギッシュな東京の姿だ。歴史探索とはしご酒という二重の“フィールドワーク”を敢行し、居酒屋文化に頭脳と肝臓で切り込んだ渾身のノンフィクション。
-
-
-
-
-
-
-
-2020年度から大学入試が激変する。従来の知識・技能型、得点重視の一発勝負試験から、主体的・協同的に学ぶアクティブラーニングの導入が前提とされる。塾や予備校は沸き立ち、中学や高校の現場は大混乱。この入試改革は文科省が進める高大接続システム改革の一環。そもそも高大接続とは何だろうか。塾や予備校に通わなければ、大学を目指せなくなるのか……。気鋭の教育ジャーナリストと、「学習学」を提唱し実践的な学びを指導してきた人気大学教授がタッグを組み、これから起こる教育改革の本質を解説。新制度に立ち向かうために、学校や家庭でできる対策を徹底指導する。
-
-
-
-同じ職場で同じ働き方をしていても、賃金に差が生じるのはなぜなのか? 労働者の三人に一人が非正規雇用となり、受け取る生涯賃金にも大きな格差が生まれている。本書はアルバイト・パート・嘱託・派遣社員・契約社員など「働く人の賃金」に焦点を当て、現代日本の労働問題を考察する。賃金というものさしから、いま働く現場で何が起きているのかを読み解き、現代日本の「身分制」を明らかにする、衝撃のノンフィクション。
-
-
-
-大人気アクション小説〈ニンジャスレイヤー〉原作者ブラッドレー・ボンド氏のアメリカン・オタク同人小説コレクションの中から、日本をテーマにした作品を厳選したアンソロジー! ノッペラボウを銃殺する表題作「ハーン・ザ・ラストハンター」をはじめ、SFサスペンスから、ソリッド・ゴア・ホラー、奇跡と感動のカルチャーギャップMMOモノまで、選りすぐりの9編を収録! イラストレーション担当は久正人氏!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-「肘掛椅子の人類学」と断じ去るのは早計だ。ただならぬ博引旁証に怖じる必要もない。典型的な「世紀の書」、「本から出来上がった本」として、あるいはD・H・ロレンス、コンラッド、そして『地獄の黙示録』に霊感を与えた書物として本書を再読することには、今なお充分なアクチュアリティがあろう。ここには、呪術・タブー・供犠・穀霊・植物神・神聖王・王殺し・スケープゴートといった、人類学の基本的な概念に関する世界中の事例が満載されているだけでなく、資料の操作にまつわるバイアスをも含めて、ヨーロッパ人の世界解釈が明瞭に看取できるのだから。巧みなプロットを隠し持った長大な物語の森に、ようこそ。
-
-
-
-少年の凶悪犯罪は減ってるし、少子化になっても日本の社会はなんともない。昔の日本人はちっとも勤勉じゃなかったし、日本のお役人はふれあいが大好きだ……社会学を超えた「反社会学」で見れば、世の中はこんなにおもしろい! 学問とエンターテインメントとお笑いを融合させ、業界を震撼させた奇書が、増補文庫版となって再登場。
-
-
-
-ユダヤ系でありながら熱烈な愛国者にしてゲオルゲ派。迫害と亡命。二十世紀の矛盾そのものを生きたかのような著者の法外な学殖と情熱は、王権表象の冷徹な解剖に向けられた。王は死んでも王位や王冠、王朝は存続する。その自然的身体とは独立して存在するように見える王の政治的身体は、いかにして産出されたのか。王権の政治神学的・象徴的基盤は西欧の歴史の中で、どのように編制されたのか。本書には、問題提起とシェイクスピア『リチャード二世』論に始まり、キリスト論との類比、法学的思考の浸透とその影響、王を神秘体の頭と捉える政体有機体説に説き及ぶ、第五章までを収録する。全二巻。
-
-
-
-日本地図を鑑賞しよう。「ムカツク」地名や人名にしか読めない地名、不思議な飛び地や奇妙な県境など楽しい発見の宝庫だ。その由来を探れば、地形や歴史、あるいは地図制作者の意図が見えてくる。地図の見方や古地図の味わいなど、マニアならではの目のつけどころを、初心者にもわかりやすく紹介する。「机上旅行」を楽しむ地図鑑賞入門。
-
-
-
-英語の学習は趣味にしてしまおう! 本へのアプローチ方法と読み方の基本から英語の文化、ジャンル別小説の読み方とおすすめ本まで。楽しみながら英語力を身につけよう。
-
-イングランド北部の炭鉱町ウィガン。1936年、オーウェルがこの労働者の町を訪れたとき、不景気と失業がひろがっていた。炭鉱夫たちと生活をともにしながらオーウェルは、彼らの顔貌を独特な身体感覚のもと丹念に書きとめていく。ここは、中産階級下層の彼の階級意識が決定的に試される場所となった。たとえば、「労働者階級には悪臭がする」。社会主義への支持を表明しながら、越えられない階級間の「ガラスの間仕切り」。彼はこの違和感を、あえて率直に表明する。声高に語られるドグマではなく、人間らしい生活、すでに中産階級からは失われてしまった生活様式への愛が、未来を考えるひとつの指標として提示される。20世紀ルポルタージュの嚆矢。
-
-
-
-
-
-
-
-紀元前一~四世紀の中国・朝鮮・日本。この時代の東アジアでは、中国の影響を受け、朝鮮・倭など周辺地域において、大小の「渦巻」が発生するごとく社会が階層化し、やがて「王」と呼ばれる支配者が登場する。その状況を最も雄弁に語る考古資料が「墳墓」だ。領域の明確な境界も形成されていなかった時代、ひととものが往来し、漢文化が大量に流入する一方で、東アジア諸地域の「ちがい」はむしろ拡大の方向へと向かった。明白に存在するそのちがいとは? それは何から生まれたのか? 最新考古学の成果に基づき、古代アジアのグローバリゼーションとローカリゼーションに迫る。
-
-歌舞伎を見るのに知識は必要ありません。見れば、難解ではなく、かっこよくて美しいと分かるはず! 贔屓の役者やお気に入りの演目を見つけるまでのドキュメンタリー的入門書。
-
-
-
-
-
-資本主義のメカニズムを明らかにするために、経済学はどこまでも科学的でなければならない──。戦後のマルクス研究を主導した宇野弘蔵。彼は教条的な『資本論』読解を批判し、純粋な科学として再構成することを企てた。本書では、経済学が取り組むべき根本課題から語り起こし、自然科学と社会科学の違い、マルクス理論の核心を踏まえたうえで、三段階論に代表される自らの理論を紹介していく。さらにマルクスの一連の著作をコンパクトにまとめた論考も収録。今日の資本主義を分析するために、マルクスをどう活用できるのか。その可能性がもっとも明快に示された一冊。
-
-
-
-
-
-
-
-現代のさまざまな国家形態、政治思想、さらに哲学、弁論、文学・芸術の諸ジャンルにおける精神活動は、原型をほとんど古代ギリシアに見いだすことができるだろう。この天才的な民族の創造物にあらゆる面から深い考察を加え、文化史家としての力をすべて結集することで、ブルクハルトの『ギリシア文化史』は成立した。その史観の類を見ぬ深刻さ、厳しく率直な人間観、深い洞察力と広い視野により、古今の史家の試みをはるかに凌駕して、この畢生の大著は歴史の真実に肉薄する。第1巻は、ギリシア人とその神話、ポリスとそこで展開された僭主制や民主制を語る。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。