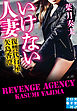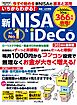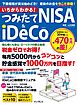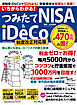金融作品一覧
-
-「で、結局どの金融商品をやればいいの?」の悩みに答える 金融商品にはありとあらゆるものがありますが、いざ自分に適したものを選ぼうとすると、どれもよく見えたりしてよくわからないもの。 本書では、投資家の視点から、様々な商品を解説するとともに、年齢や現在の資産の状況から「こればベスト」な商品を教えます。 著者は、今まで様々な投資を行い、大学の講義から富裕層向けの投資講座まで、投資の手法を教えています。 本書では、様々な投資商品の図鑑だけでなく、資産・年収・年齢などによって最適な「投資の仕方」を説明します。 様々な投資を試した結果お勧めできる内容は、説得力があります。
-
-あなたのセキュリティ対策は、それで本当に大丈夫ですか?! セキュリティ対策なんて面倒だし、難しそうだし、お金もかかりそうだし、できればやりたくないと思われているかもしれません。 しかし、皆さんのまわりでは、日々セキュリティリスクが高まっているのです。 本書の目的は、技術的で難しい表現は極力さけ、皆さんのちょっとした心がけでリスクを下げられることを理解してもらうためですので、気軽な気持ちで是非読んでみてください。 身近で起きているセキュリティ事件・事故の事例からとるべき対策(例えば、SNSを例にとり、「アカウント乗っ取り」の被害事例と乗っ取り対策および乗っ取られてしまった場合の対処法)や、近い将来世の中がどのように変化し、その変化にどのように対応すべきかも紹介しています。 ぜひ、スマホをもっているアナタには、一度読んでいただきたい一冊です。 【購入者様への特典】 「セキュリティ対策チェックリスト」と「セキュリティ関連お役立ちリンク集」 【著者プロフィール】 著者:磯島 裕樹 情報セキュリティスペシャリスト/ネットワークスペシャリスト/中小企業診断士 大手システムインテグレーターに入社して、主に金融機関のシステム基盤の設計/開発/運用に従事しながら、新規システムの提案などに携わる。個人情報保護法施行の際には、セキュリティ対策強化に向けたシステム提案/導入、運用改善提案を実施。2014年に転職し、国内コンサルティング・ファームに入社後、コンサルタントとして数社のCSIRT(コンピュータ・セキュリティ・インシデント・レスポンス・チーム)の構築/運用支援を行った実績を持つ。
-
3.0
-
4.0行き着く先はインフレタックスという究極の増税策! ? 総選挙を経て、再び安倍内閣に託したこの国の経済。 その処方箋が間違っているとすれば、最後にツケを払うのは、われわれ国民なのかもしれない。 ◆異次元緩和は間違った処方箋 5年目に入った「アベノミクス」だが、デフレ脱却には至っていない。それは、アベノミクスの目標及び処方箋が間違っているからではないか? 実は、金融政策依存は、政治的には非常に都合がよい。極論すれば、日銀が物価目標を明示しマネーの供給量を増やすだけで、政治は何もしなくてよいからだ。しかし人口減・高齢化が進む社会では、経済規模は必然的に萎まざるを得ない。量的・質的緩和では、本当の日本経済の構造問題に対処することは不可能なのである。 ◆このままでは金融資産がどんどん目減りする! 人口減対策と雇用制度改革を避けるアベノミクスは、実は意図せざる究極の増税策、すなわち「インフレタックス」である。そして、その潜在的な納税者は、金融資産を保有する企業や高齢者なのだ。 異次元緩和で膨れ上がる日銀の資産と増え続ける国家債務は、いずれ国債の価値下落を通じ日本経済をインフレに導く。その時、国家債務の実質負担は収縮する一方で、企業や国民が持つ金融資産の価値は目減りする。実は、戦前、高橋是清は、世界恐慌からの脱却を図るに当たり、日銀による国債保有を悪性インフレの原因になるとして許さなかった。アベノミクスを高橋財政と同一視し肯定するのは、全くの間違いなのである。 本書は、こうした視点をベースに日本経済の近未来を分析、蓋然性のあるシナリオを提示。インフレタックスが現実となれば、高齢者や企業は蓄積した金融資産の購買力を失い、中若年層は、親もしくは祖父母世代の経済力に依存できなくなる。そうしたリスクに備えるうえで、読者に知っておいてほしい知識を提供する。
-
-第一章 生命保険。知らない人が損をする理由 指切断の大事故!………でも保険金がおりない? あなたは自分の生命保険を説明できますか? 保障の内容を理解していますか? 最大のリスクは無知と無関心 義理人情で500万の損をする! 保険は欲張るほどに損をする! セールストークに騙される? 放置していたら、保険の価値が1/3に まずは「知る」ことから始めよう 自分の資産は自分で守る! 第二章 業界裏事情……生命保険のからくりを知る 生命保険会社はなぜ儲かるのか? 多様化する販売経路 代理店の事情 あなたも身に覚えがありませんか? 商品の価値より売る人の価値? 保険金不払い問題を整理する 保険会社の安全性 裏づけデータの信ぴょう性 消費者ニーズの変化が保険会社に与える影響 巷では保険見直しブーム 第三章 一生使える!保険の見直し10のポイント 保険で何のリスクに備えるかを決める 個人保険の選び方 その1 死亡保障編 個人保険の選び方 その2 医療保障編 個人保険の選び方 その3 生存保障編 個人保険の選び方 その4 介護保障編 「費用対効果」で考える 保険見直しのテクニックと、保険の納品 第四章 知らなきゃ損をする法人リスク対策10の知恵 オーナー社長が保険に加入する目的は4つ オーナー経営者のリスク対策とは? 特徴を踏まえた法人保険戦略 保険は費用で落として利益を圧縮できる装置 4種類の節税方法と、損出し・益出しのコントロール 会社のリスク回避装置としての生命保険 法人保険の活用法 その1 長期平準定期保険 法人保険の活用法 その2 逓増定期保険 法人保険の活用法 その3 法人がん保険 法人保険の活用法 その4 終身保険 法人保険の活用法 その5 ドル建て終身保険 おわりに 著者プロフィール 亀甲 来良 かめこう らいら ● 1979年相模原市生まれ。同志社大学経済学部卒。2002年より日本ユニシス(株)に9年間勤務(金融部門に9年在籍し、生命保険会社向けの企業ITシステム構築事業に従事)。2011年に金融・保険の総合コンサルティングをする「(株)トータス・ウィンズ」に転職。転職後、1年半で個人100人以上、法人100社以上の保険コンサルティングを実践し、様々なリスク回避プランや、相続事業承継プランを提案・策定。2級ファイナンシャルプランニング技能士(厚生労働大臣認定)。
-
3.5シラー教授は2013年に、アカロフ教授は2001年にノーベル経済学賞を受賞。 ともにノーベル賞を受賞した、主流のなかの主流の二人が、主流派経済学のあり方を批判しつつ、「人間」を軸に据えたマクロ経済学が必要だと説いた意欲作。 偉大な経済学者ジョン・メイナード・ケインズが代表作『雇用、利子、お金の一般理論』で提示したアニマルスピリットと、経済学の新しい分野である行動経済学の成果を組み合わせて、危機に陥った現実経済の説明を試みる。 「金融学とは金儲けのための学問ではない。人間行動の研究である」というシラー教授の基本思想どおりに、人間のアニマルスピリット(衝動、血気)を安心、公平さ、腐敗と背信、貨幣錯覚、物語といった要素に分解して、それぞれがアメリカの有名な経済現象にどう関与していたかを紹介していく。 たとえば、 ・1991年ころのS&L危機 ・2001年ころのエンロン問題 ・2007年ころのサブプライムローン問題 などだ。もっと古い経済問題では、1890年代の不況や、1920年代の過熱経済、1930年代の大恐慌も分析の対象となっている。本書自体が、説得力のある一つの物語となっているようだ。 本書が刊行された2009年当時、金融危機で途方に暮れていた当局に対して、本書は独自の分析と鋭い政策提言を行い、注目を集めた。専門家ではない人も読めるタイムリーな経済書として、世界各国で読まれた。 日本でも、週刊ダイヤモンドの2009年ベスト経済書ランキングで、堂々1位に輝いている。 一流の経済学者がどのように経済を見ているかを追体験できる本。 【主な内容】 第I部 アニマルスピリット 第1章 安心とその乗数 第2章 公平さ 第3章 腐敗と背信 第4章 貨幣錯覚 第5章 物語 第II部 八つの質問とその回答 第6章 なぜ経済は不況に陥るのか? 第7章 なぜ中央銀行は経済に対して(持つ場合には)力を持つのか? 第8章 なぜ仕事の見つからない人がいるのか? 第9章 なぜインフレと失業はトレードオフ関係にあるのか? 第10章 なぜ未来のための貯蓄はこれほどいい加減なのか? 第11章 なぜ金融価格と企業投資はこんなに変動が激しいのか? 第12章 なぜ不動産価格には周期性があるのか? 第13章 なぜ黒人には特殊な貧困があるのか? 第14章 結論
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Hな素人娘を金の力でアヘらせました ★出会いカフェの2人組は3Pに応じるのか? ★声優の卵はエッチのときどんな声をだすのか? ★美女とヤリまくる! ●出会いカフェの2人組は3Pに応じるのか? ・10万で3P出来るそうな ・計3万円でまとまったが買う気になれず ・可愛い方が拒否。残念 ・エンコ―するのは片割れのみそんなペアもいるんですね ・ひとり3は高いわ ・イチゴ―ずつで成立! ・こんなことが3万で出来るなんて、ありがたや~ ●トラック運ちゃん、好き放題ワリキリ娘と東京を目指す ●オレだって新潟県知事みたいにハッピーメールで名門女子大生を買いたい! ・4年制の大学に通う子は、パパ活オンナが多い ・名門私立大学で経験人数3人の美少女が ・さあ、どんな体なのかな! よっ 名門!! ●「別れさせ屋」と「ターゲット」の一人二役で美女とヤリまくる! ●相手が好きでタマらなくなる合法媚薬をエンコ―女と一緒に飲んでみる ・どうしよう。めっちゃ幸せなんだけど ・よほどおれのことが好きなようだ ・チンコが膣壁で溶けてしまいそうな ●パパ活手紙を美人店員さんに渡す! 美人店員さんが1万円で ●声優の卵はエッチのとき どんな声をだすのか? ●返済金の3割を上げるから。借金男と金融屋を演じて キャバ嬢と3千円でヤル方法 ●5分5千円のキス援交で 濃厚なベロチューをかましたら なぜか恋人へと発展した話 ●座りんぼスポットにいた3万レベルの美女となぜかタダマンできた奇跡 ●0.1円パチンコを打つ女には 千円が4万円に見えるはずだから 格安エンコーできるんじゃね? ●手コキ千円、愛人契約月3万円、子供の横でハメ撮りも。「ナマポアパート」は安エンコ―天国だ ●練習台になってあげるだけで 金のないネイリスト見習いちゃんと カラオケでプチエンコ―できちゃいます ●格安で泊れる「ネットルーム」の 貧乏家出オンナたちは プチエンコ―に応じるのか? ●超ハイレベル女子だらけの ギャラのみアプリ「パト」で 貧乏男が楽しむための裏ワザ ●エンコ―女の溜まり場 歌舞伎町グランカスタマに 三連泊して実態調査してきました ●「2時間で2回戦4万円」「友人へサプライズプレゼント」まんまと騙されたバカなエンコ―嬢 ■著者 鉄人社編集部 編集部より★本誌掲載記事の中には真似をすると法律に触れるものも含まれています。悪用は厳禁です。 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) ※一部変更して再申請している作品です。お間違いないようお気を付けください。
-
-恋に名前をつけたい。これまでの恋ひとつひとつに。 恋を思い出す時はいつも、ちくりと胸が痛む。 なぜかというとその全てに住む「いつかの私」が、どれも綺麗なものじゃないから。 この本には15編の「恋」が綴られている。 どれもが幸せな物語ではないけれど、きっと、あなた自身のいつかの恋をかすめて、そのぬくもりを蘇らせるはずだ。 あなたがこの本を読み終わる頃には、恋って悪くないな、と思えていますように。 恋をやめられない私たちのことを、どうか愛せていますように。 ※本書はnoteのマガジン「エッセイの花束」から恋愛のエピソードを抜粋し、大幅に加筆・修正を加えたほか、新たに5編のエピソードとイラストを書き下ろしたものです。 ▼著者紹介 みくりや 佐代子(みくりや・さよこ) 微炭酸エッセイスト・ライター。 1988年生まれ、広島県出身。広島大学卒業後、金融機関に就職し、その後は広告代理店に勤務しながらフリーライターとして活動している。 2019年より趣味の一環として、ピースオブケイク社が運営するコンテンツプラットフォーム「note」にて“ちゃこ”名義で執筆活動を開始。 恋愛や生き方など自身の体験や価値観を綴ったエッセイは10ヶ月余りで累計90万PVを記録し、フォロワーは5000人を超える。 “微炭酸系”と称される、甘さと一緒に切なさの残る読後感の文章は「エモい」と話題に。特に20代、30代女性の読者に強く支持されている。 座右の銘は「女の可愛いと男の忙しいは信じるな」。好きな食べ物は汁なし坦々麺。
-
3.5世界中で一番会いたくなかった男性が、いま目の前にいる。モンテベラッテのプリンセス、マリエッタは顔を背けた。ヤニス・マーキデス――辣腕の金融アドバイザーだ。彼に恋をしていたマリエッタは、十六歳のとき、彼の誕生日に純潔を捧げようと彼の寝室に忍びこんだ。だが思わぬ拒絶に遭い、マリエッタはひどく打ちのめされた。それから十三年の月日が経ち、彼女は兄の結婚式で彼と再会、披露宴で二人は付添人の義務としてダンスを踊ることになったのだ。「今夜、僕と愛し合い過去を水に流そう」耳元でヤニスにそうささやかれ、マリエッタの心は揺れ動いた。■1月5日刊『伝説の国のプリンセス』の関連作です。前作のヒーローの妹、マリエッタが初恋の人ヤニスと再会。失われた13年の日々を、二人はどう埋め合わせていくのでしょうか?
-
2.0世界中で1番会いたくなかった男性が今、目の前にいる。モンテベラッテのプリンセス、マリエッタは顔を背けた。ヤニス・マーキデス――辣腕の金融アドバイザーだ。16歳のとき、彼に恋をしていたマリエッタは、純潔を捧げようと彼の誕生日に寝室に忍びこんだ。だが妹のようにしか思えないと言われ、拒絶されてしまった。そんな彼と兄の結婚式で再会し、付添人の義務としてダンスを踊ることになったのだ。彼はマリエッタの耳元にそっとささやいた。「今夜、僕と愛しあおう」
-
-世界中で1番会いたくなかった男性が今、目の前にいる。モンテベラッテのプリンセス、マリエッタは顔を背けた。ヤニス・マーキデス――辣腕の金融アドバイザーだ。16歳のとき、彼に恋をしていたマリエッタは、純潔を捧げようと彼の誕生日に寝室に忍びこんだ。だが妹のようにしか思えないと言われ、拒絶されてしまった。そんな彼と兄の結婚式で再会し、付添人の義務としてダンスを踊ることになったのだ。彼はマリエッタの耳元にそっとささやいた。「今夜、僕と愛しあおう」
-
4.0
-
3.0新型コロナの感染拡大で、不動産市況も大変化。 その動きと、将来の見通しを豊富なデータから解説。 不動産を売る人、買う人、借りる人、必読の1冊 ・アベノミクスによる異次元の金融緩和によって演出された不動産バブルは、すでにピークを過ぎていたものの、2020年の新型コロナウィルスの感染拡大により、まったく違った局面を迎えました。 ・人口減少、デジタル化などによる都心オフィス需要の低下には、ますます拍車がかかり、テレワークの広がりで郊外の住宅需要はかつてないほど活況を呈しています。 ・こうした動きは、今後、どこへ向かうのでしょうか。豊富なデータを駆使して、現状を観察し、将来を見通します。不動産を売る人、買う人、借りる人はぜひとも読んでおきたい1冊です。
-
-人手不足、円安、インフレ……「もう、返済できない!」 コロナ融資倒産を防ぐための資金繰り指南の書。 新型コロナウイルスの扱いが5類となり 一般社会の生活が落ち着きを取り戻りつつある一方、 いま、中小零細企業は未曽有の危機に瀕している。 コロナ禍に受けた「ゼロゼロ融資」の返済が本格化し、 さらに猶予されていた公租公課の支払いも再開。 拍車のかかった人手不足やインフレ、円高によって 日本企業を取り巻く状況は前にも増して厳しく、 公租公課滞納が原因で倒産した企業は コロナ前の20年に比べ23年は3倍にも上る。 (帝国バンクデータ調べ) 日本にある法人の99%は中小零細企業である。 このまま中小零細企業の事業が立ち行かなくなれば、 今以上に経済は逼迫し、破綻することすらあり得る。 「日本の中小零細企業の事業を守る」 本書はその一念によって 中小零細企業再建のスペシャリストたちが集結し、 資金繰りから事業再生のプログラムに至るまで 丁寧に解説していく。 【内容紹介】 第1章 ゼロゼロ融資の「借換保証」をどう活かす? 1.「ゼロゼロ融資」とは何だったのか 2.新たな借換保証制度の創設 第2章 これから中小企業が直面する課題とチャンス 1.いま起こっているのは不連続な変化 2.中小零細企業が直面する課題 3.中小零細企業にとっての可能性 第3章 中小零細の事業再生パターンと手法 1.企業再建に成功する経営者の共通点 2.金融機関との交渉 3.本業の立て直しと磨き上げ 4.会社や事業を譲渡する 5.事業承継は別の視点で 第4章 業種別に考える事業再生ポイント 1.製造業の事業再生ポイント 2.建設業の事業再生ポイント 3.不動産業の事業再生ポイント 4.運輸業の事業再生ポイント 5.人材派遣業の事業再生ポイント 6.商社(卸業)の事業再生ポイント 第5章 元気な中小零細企業が日本を救う 1.中小零細企業の位置づけと役割 2.中小零細企業にとってチャンスの時代 3.賢い経営者になろう
-
3.4
-
3.8日銀出身の決済システムの第一人者が、未来の通貨として注目されるビットコインの崩壊を、その設計と運用の両面からいち早く予測。さらに仮想通貨の中核技術「ブロックチェーン」が、ゴールドマン・サックスや三菱東京UFJ銀行、そして各国の中央銀行を巻き込みながら、金融界に大革命を起こしつつある状況を鮮やかに描く。
-
-国際金融のリセットはすでに始まっている アメリカ“ドル”の支配を覆そうとする中国とロシアの動きとは―― 米ウォール・ストリート・ジャーナル紙でベストセラーとなった話題作を完全邦訳 「言い換えると、実物資産と勤労だけが価値の蓄えになる。株式も債券もすべての会社が潰れてしまえば、無価値になる。債務者は破産し、残された名目的価値はインフレですっかり無くなってしまう。ゲームのスタートオーバーになるかもしれないが、今までいたプレイヤーはすべて吹っ飛ばされてしまっている。」(本文より) 2020年のパンデミックとアメリカ主要都市での暴動を予測した話題の書
-
4.0現代の“新大陸”に潜む莫大なビジネスチャンス いま急速に成長している巨大な市場――アフリカ。本書は、増えつづける9億人の消費者を擁するこの新たな市場の可能性を浮き彫りにする。 衣食住のニーズから金融、通信、メディアに至るまで、あらゆる機会をとらえて市場を開拓する起業家たち。コカ・コーラ、タタ、P&G、ノバルティス、LG電子など、世界各国から続々と進出する企業や投資ファンド。アフリカに急接近する中国・インドはじめ各国政府。さまざまな動きがこの大陸を劇的に変えつつある。社会的・政治的な数々の問題にもかかわらず、ビジネスチャンスは豊富に存在するのだ。これまで見過ごされてきた巨大市場の可能性と、新たなビジネス・経済の姿が見えてくる。
-
-米国や日本における歴史的な株価の上昇を支えているのは、各国の中央銀行が世界にばらまいたマネーだ。だが、その裏にある膨大な債務が、新たな金融危機を引き起こす火種となる。 本書は週刊エコノミスト2017年11月7日号で掲載された特集「危ない世界バブル」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・金融緩和が招いた「債務中毒」 近づく臨界点に打つ手なし ・マネーはどう動く【インタビュー】寺島実郎(日本総合研究所会長) ・官民「2大バブル」 市場への政府介入で膨らむ公的債務 過剰な金融緩和で民間債務も膨張 ・株高・債券高・不動産高の落とし穴 五つのバブル「HIEER(ヒア)」の恐怖 ・米欧の資金循環 欧州勢の米社債投資 ユーロ圏金利上昇で逆流も ・「米ローン3兄弟」 「自動車」「学生」「クレジット」にリスク ・積み立て不足の米年金 州・地方政府の不足額は1.8兆ドル ・「黄信号」のオイルマネー 原油価格低迷に苦しむ産油国 海外資産取り崩しでマネー逆流も ・くすぶる中国リスク 米緩和縮小で人民元安圧力 マネー流出で信用収縮も ・「欧州発」危機 不良債権処理遅れるイタリア 総選挙で「EU離脱」不安も ・カタルーニャ問題 独立強行なら財政悪化や企業流出 【執筆者】 松本 惇、池田 正史、平山 賢一、長谷川 克之、吉川 雅幸、青木 大樹、石原 哲夫、畑中 美樹、宮嵜 浩、安達 誠司、大槻 奈那 【インタビュー】 寺島実郎
-
-「ハッキリ言う、安倍さんが日本を救ったのだ!」(高橋洋一) ・今も続く的外れな「アベノミクス批判」 ・アベガーよ、「安保法制反対!」をウクライナで叫んでみろ! ・「悪い円安論」は無知の極み ・日本は今も全くインフレを心配する必要はない ・岸田総理よ、いま緊縮財政をしてはいけない! ・ウクライナで世界と日本の経済はこうなる ・ロシアの金融破綻の確率は・・・100%だ! ・実は日米同盟は世界基準だと「弱い同盟」である ・日本の戦争確率を確実に減らす方法を教えよう ・「平和ボケ」はお花畑からでて来なさい! ・財務省は防衛省の植民地化を狙っている ・安倍さんほど政策を「世界基準」で考えた政治家はいなかった(著者)
-
5.0尖閣問題/沖縄米軍基地/日米同盟/集団的自衛権/原発問題/憲法改正/景気回復/消費税/TPP問題…… 「日本を取り戻す」ことが、自民党政権はできるのか!? 混迷する日本政治の行方を占う。 歴史的大勝の要因と公明・維新との連携について 尖閣や沖縄基地問題はどう解決する? 日米同盟の強化と対中戦略の構築こそ急務 憲法改正はほんとうに実現できるのか!? 「村山談話、宮澤談話」を変えることはできるか? 日銀の金融緩和によりデフレ脱却へ! 景気動向と消費税増税の関係をどう見きわめる? TPP参加問題についての見解と方針 原発再稼働と活断層の問題をどう考えるか 自民党政権の国策であった原発の必要性を訴えるべき!
-
5.02022年7月8日、日本と世界は偉大なリーダーを喪失した。 ロシアによるウクライナ侵攻、中国による台湾侵攻危機、資源・エネルギー価格高騰によるインフレ、続く新型コロナウイルスの感染拡大…… この多層的未曽有の危機にあって、日本を含む多くの国々が必要としたのが政治家「安倍晋三」だ。 私たちにできることは安倍元総理の遺志を継承し、さらに発展させることである。そのためには「安倍の政治」を理解しなければならない。本書の目的はそれだ。 安倍元総理の「政治」は「外交」と「内政」を連動させ、国民の「生命」を守る国家構造を構築したことにある。それは「戦後」という長大な時間を脱却するという「夢」であり、多くの有権者が、そのダイナミズムに惹かれた。 (「はじめに」より抜粋) 目次より抜粋 特別資料 【その1】 安倍政権 全制定法律 【その2】 「地球俯瞰外交」の全記録 【その3】 歴代安倍内閣全閣僚名簿 第1章 リーダーを喪失した日 国際社会はリーダーを喪失した 自民党と統一教会 安倍元総理と統一教会は無関係 赤いメディアと戦い続けた 憲法と宗教 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 第2章 地球儀を俯瞰した外交 世界から届けられた弔意 日本を中東と国際社会を繫ぐ「ハブ」にした 中東で「一番の親友」争いが起こっている 地政学から見た安倍外交戦略 民主党の愚策で脅威にさらされた列島 戦略概念FOIPを発案 あのアメリカが外交戦略を学んだ 地球儀を俯瞰する外交 戦後を脱却する外交 第3章 盟友の死と復活の日 内政を支えた帝王学 幼少から作られるコミュニティ 集うプリンスたち 売国政党に揺さぶられて 「憲法」こそ「戦後」 「盟友の死」と「大震災」が奮い立たせた 「本来は谷垣」と麻生氏に断られたが 3つの約束のために アベノミクスの原点 金融緩和と財政出動でしか生き残れない アベノミクスの真意 第4章 日本を、取り戻す。 内閣を支えた「戦友」 特定秘密保護法の真意 2022年に周知された安全保障関連法 台湾と与那国島を封鎖した 国際連携こそが安全保障の核 日本を、取り戻す。 第5章 安倍政治は終わらない 逝去直前に持っていたテーマ タブーとされる「核抑止」議論を 岸田政権は「遺志」を継承するのか 継承から発展、展開へ
-
4.0
-
-なぜ安倍首相は憲法改正を目指すのか。 改憲実現を核とする「戦後レジームからの脱却」は安倍政治の根幹をなすテーマである。 「政治家に努力賞はない」を信条としてきた安倍は、宿願の憲法改正への挑戦を 「努力賞」に終わらせるわけにはいかないと思っているはずだ。 改憲実現は在任中の具体的な達成目標と狙いを定め、行動を起こすと見るのが自然だろう。 七十年目の「改憲政戦」の実相を探る――。 【著者紹介】 塩田潮(しおた・うしお) 1946年高知県生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒。 雑誌編集者、記者などを経てノンフィクション作家に。 『霞が関が震えた日』で第5回講談社ノンフィクション賞を受賞。 主な著書に『大いなる影法師』『昭和の教祖 安岡正篤』『金融崩壊』『田中角栄失脚』『憲法政戦』 『権力の握り方』『復活! 自民党の謎』『東京は燃えたか―東京オリンピックと黄金の1960年代』『内閣総理大臣の日本経済』などがある。 【目次】 ◆序章 改憲案発議が可能に ◆第一章 祖父・岸と父・晋太郎 ◆第二章 「改憲が党是」の自民党 ◆第三章 二つの自民党憲法案 ◆第四章 迷走の第一次安倍内閣 ◆第五章 つまずいた改正要件緩和 ◆第六章 憲法解釈変更作戦 ◆第七章 集団的自衛権行使の道 ◆第八章 改憲政党・橋下維新 ◆第九章 幻の衆参同日選挙 ◆終章 七十年目の「憲法戦争」
-
3.0アベノミクス、消費増税、対中外交……、決断の裏側で何が起こっていたのか!? 主要メディアが伝えないインサイドレポート。 第1次政権時の安倍首相は自ら旗振り役となって突き進んだ。だが、現在の安倍氏は常に最終判定者であることを心掛けている。 そのためには、菅官房長官と麻生副総理兼財務相の2人のお膳立てが不可欠である。主要政策すべての判断の際、この二等辺三角形の役割分担が機能して、成功してきた。 アベノミクス(安倍政権の経済政策)の「3本の矢」策定、黒田東彦日本銀行総裁人事(異次元の金融緩和)、 価値観外交による中国包囲網確立とエネルギー資源外交による中東・アフリカ歴訪、国際オリンピック委員会(IOC)総会での2020年五輪の東京招致成功、 消費税率8%への引き上げ(復興特別法人税廃止前倒し)表明、減反決定など農業改革と薬認可自由化など医療改革(岩盤規制改革)――。 このような決断で安倍首相は最終判定者であり続けた。これが、今の安倍スタイルなのだ。(本書「序文」より) 【主な内容】 ●なぜ、安倍1強時代が生まれたのか ●外交分野のお手本は祖父・岸信介元首相の「自主外交」か ●アベノミクスが引き起こす財務省の地殻変動 ●安倍・金正恩会談の布石か!?~飯島勲内閣官房参与の北朝鮮訪問が意味するものとは ●特定秘密保護法案を参院に送った安倍政権には中国の防空識別圏設定は“使える”道具に過ぎなかった!
-
-経済政策を優先してきた第二次安倍政権だが、2013年末に安倍首相が靖国神社に参拝。中国、韓国のみならず、在日米大使館も「米国政府は失望している」との異例の声明を発表した。現在、外交的には厳しい立場に立たされている安倍首相だ。 金融緩和政策、財政出動、成長戦略の「3本の矢」でアベノミクスは構成されている。そのアベノミクスを進める司令塔、財界の安倍親衛隊「さくら会」、ネット右翼との関係、経団連の米倉会長との不仲…安倍首相を取り巻く人脈について詳しく解説。 「限定正社員」という名で解雇自由化は進んでしまうのか? 会社員必読!解雇規制緩和の全内幕。 横浜方式による待機児童解消の実現度は? 憲法改正についての首相の本音は? 安倍首相の秘められた本心と、首相を取り巻く人脈に迫った!
-
4.0安倍政権が実は消費税が上げられない理由とは? 日銀の金融政策、株価、国際、税率、地下などなどの項目が五輪後はどう変わる? そこから、老後破産の根拠を探り、どう逃げ切ればよいのか? 40~50代に向けて、新たな生き方論を提示する書。 第1章 安倍首相が消費税を上げない3つの理由 第2章 消費税は上がらなくても2020年以降に不況の波 第3章 これから危機に直面する「40代・50代」 第4章 家計を救う、この先5年の基本戦術 第5章 家計の“内部留保”はどうやって増やすのか 第6章 10年で天地の差がつく“公的保障活用術” (著者プロフィール) 荻原 博子(おぎわら・ひろこ) 1954年、長野県生まれ。大学卒業後、経済事務所に勤務し、 1982年にフリーの経済ジャーナリストとして独立。 経済の仕組みを平易に解説する家計経済のパイオニアとして テレビや雑誌で活躍。これまでの著書・共著・監修書籍は100冊以上を数える。 近著に『払ってはいけない ~資産を減らす50の悪習慣!』 『投資なんか、おやめなさい』(ともに新潮新書)、『老前破産』(朝日新聞出版)など多数。
-
3.5安倍政権の真の狙いがわかった! アベノミクスは果たして効果があるのか。日本は復活できるのか。独立総合研究所代表取締役社長の青山繁晴氏、ジャーナリストの須田慎一郎氏、経済評論家の三橋貴明氏が“ガチンコ討論”します。 「3本の矢」と言われる大胆な金融緩和、機動的な財政政策、そして成長戦略。 それらに落とし穴はないのか、三氏が徹底検証。 そしてアベノミクスの真の狙いに迫ります。その過程で、第二次安倍政権が掲げる政策が単に強い経済を取り戻すためだけでなく、安全保障と深くリンクしていることが浮き上がってきます。 新聞、テレビが報じないアベノミクスの最終目標を掘り下げて明らかにします。
-
3.6
-
-安倍晋三首相の意を受けて・いままでにない次元・の大胆な金融政策を打ち出した黒田日銀総裁。市場や経済界は大歓迎だが、本当に日本はデフレから抜け出せるのだろうか? また、物価は目標どおり2年で2%上昇するのか? いずれにしても物ごとの本質を捉えた議論なくして予測しようとしてもなかなか難しい。 本書は、現在の円安の本当の理由、デフレの正体など、今回のアベノミクスの効用を、慶應義塾大学准教授の小幡績氏と経済学者池田信夫氏両者が忌憚なく交わした対談録である。非常にわかりやすい言葉で語られているので、現在日本が置かれた状況を簡単に理解できる。 【目次】 第1章 黒田体制で日銀はどうなるか 黒田総裁への評価は意外に高い 相場が信じれば株価は動く 第2章 円安の原因はアベノミクスか 為替はなぜ動いたのか 円安はどこまで行くか 円安は日本経済の実力 デフレもインフレも実体経済の反映 第3章 デフレの正体は賃下げ 日本経済は「デフレ不況」ではない 量的緩和でインフレ予想は起こらない バブルの教訓 物価と資産価格の動きの分離 賃金の引き下げがデフレの原因 本丸は労働市場 第4章 アベノミクスは副作用の強い偽薬 バブルは再来するか 財政ファイナンスのリスク 安倍首相の取るテールリスク 金利上昇で何が起こるか 輸入インフレは起こるか 第5章 停滞から脱却するには 日本はもう「貿易立国」ではない 本丸は労働市場改革だ 世界的に進行する新興国との賃金の「大収斂」 人材の活用が成長の鍵 (アゴラ・シングルシリーズ:A5版で60ページ相当)
-
3.0「いま増税すれば景気が悪くなる」「消費税増税は不公平」「経済成長すれば増税はいらない」これらは「痛みの先送り」の言い訳に使われていないか?金融緩和と財政出動さえすれば、デフレから脱却し、経済成長が実現できる。さらにムダを省けば、財政赤字も解消できる――「アベノミクス」で明るいムードが漂いはじめた日本経済。ここにきて、消費税増税は景気回復に水を差す、時期尚早との声があがりはじめた。「1,500兆円の個人資産があるから国債は大丈夫」「インフレ2%でどうにかなる」。巷で聞かれる楽観論に根拠はあるのか。20、30代は60歳以上より5,000万円損をする? この国の財布がヤバイ理由。【論点】(1)デフレ脱却に向けての処方箋は何か/(2)日本経済は復活できるのか/(3)歳出削減のみで財政健全化はできるのか/(4)「日本の財政は破綻しない」はほんとうか/(5)「経済成長すれば財政再建できる」はほんとうかetc.
-
-参議院選挙で圧勝して勢いがつくかと思ったアベノミクスが、急に失速しています。黒田日銀総裁の「量的・質的緩和」は予告どおり激しくマネタリーベースを増やしましたが、物価(コアコアCPI)はデフレのまま。彼の重視する予想インフレ率(ブレークイーブン・インフレ率)は下がってしまいました。 「2年で2%のインフレ目標が実現できなければ辞任する」と大見得を切った岩田副総裁も、最近の記者会見で「予想インフレ率は下がっている」と追及されて「もう少し長い目で見てほしい」と苦しい言い訳をしています。 おまけに与野党3党で合意して法律で実施が決まった消費税率の引き上げを、土壇場になって見直すとか見直さないとか安倍首相の方針が迷走し、その決断力のなさが露呈して政権の求心力が失われてきました。 「第2の矢」の財政政策は、旧態依然のバラマキ公共事業で、財政を悪化させる以外の効果はありません。「第3の矢」の成長戦略は各官庁の概算要求をホッチキスで綴じただけ、という伝統的な自民党の政策で、中身が何もありません。 GDP(国内総生産)の半分を超える270兆円の日銀券をばらまく「異次元緩和」は、失敗したら金融危機が発生するだけでなく、財政が破綻するリスクもある、史上最大規模のギャンブルです。 何もやらないより新しい政策にチャレンジすべきだ、という意見もありますが、このギャンブルが失敗すると、莫大な損害を負担するのは国民です。この結果がどう出るのか、外資系金融機関でキャリアを歩んできた藤沢数希氏と一緒に考えてみました。池田信夫――プロローグより
-
3.0アベノミクスは今や国民に大きくアピールし、マーケットもそれに反応して円安・株高が続いている。しかし、ちょっと待ってほしい。注目を浴びている「大胆な」金融緩和という政策は、べつに奇手でも妙手でもない。過去、政府が苦しい時に何度もすがってきた手法である。政府は財政が苦しくなると、マネー創出という「打ち出の小槌」に手をかける。そのたびに経済は大混乱し、国民は痛い目にあう。古くは江戸時代の小判改鋳によるインフレ、西南戦争後の大インフレ、大正バブル、1974年の大インフレ、そして1980年代後半のバブル。海外では第1次大戦後のドイツのハイパーインフレなどなど。歴史をたどると、マネーというものがいかに誘惑に満ち、また恐ろしいものであるかがわかる。本書はこうした歴史を振り返ることで、アベノミクスの持つ構造的な危うさを指摘するとともに、期待先行で膨れつつある日本経済に警鐘を鳴らすものである。
-
3.52012年12月、自民党の大勝によって、政権交代が起こった。その後、安倍政権が景気回復のために掲げる「アベノミクス」と呼ばれる経済政策が新聞紙上やニュースを、騒がせている。なかでも最も注目されるのは「デフレ・円高対策」だ。日銀法改正を視野に入れた大胆な金融緩和により、安倍政権は「名目3%以上の経済成長」を達成するとぶち上げた。著者はこの「アベノミクス」に対して、強い不快感を示さざるを得ない。本書では読者に対して、根源的な問いを投げかけたい。日本経済は本当に「成長」することができるのだろうか? そもそも「成長」は、必要なのだろうか?
-
-ついに揺らぎ始めた「アベノミクス」! BLOGOSなどでも人気の著者が、徹底的に裏を取り、アベノミクスのなにが真実でなにが嘘だったのかをわかりやすく解説! 国民は過剰な期待を抱き、有識者たちは根拠の怪しい賛辞と批判を繰り返してきたアベノミクス。 本書では第1章から第5章まで、アベノミクスにまつわり湧き起こっている様々な議論を整理し、 見え難くなってきた「アベノミクスの本質」を浮かび上がらせることで、アベノミクスが導く方向性を明らかにしていきます。 さらに第6章ではどのようにアベノミクス後の社会を生き抜けばいいのかについて考えていきます。 【目次】 ●はじめに ●第1章 必ずしも国民に優しくない「アベノミクス」 ・円高・株高は痛みを和らげる麻酔 ・企業が儲かれば、労働環境は良くなるか? ・円安・株高でももう遅い! 崩壊した厚生年金基金制度 など ●第2章 「大胆な金融緩和」にまつわる「錯覚」と「誤解」 ・実は目標を外していた「黒田バズーカ」 ・「2%の物価安定目標」その根拠はどこに? ・白川元総裁の誤算 ・物価が上がれば、賃金も上がるのか? ・ハイパーインフレは起きるのか? ・デフレが懸念され始めた欧州 など ●第3章 最も人気のない「機動的な財政政策」 ・国民の「不信」に働きかける政策 ・「機動的な財政政策」は「大胆な金融緩和」の重要なパートナー ・「日本国債暴落」は本当に起こるのか? ・「借入先」を無視した片手落ちの議論 ・「日本は借金大国」というのは本当か? ・「サラ金」から資金を借りようと頑張る財務省 など ●第4章 誤解された「成長戦略」が国民に痛みを与える ・勇ましいスローガンでごまかされる「痛み」の説明 ・アジアの参加国が少なすぎるTPP ・中国の経済成長神話 ・進む「一物一価」時代 など ●第5章 アベノミクスの本質と、アベノミクスが導く社会 ・国民全体が「いい思い」をできるわけではない ・成長戦略を練るのは、これまでのルールでの成功者たち ・アベノミクスが葬り去る「一億総中流」 ・証券・運用業界の凋落 ・成果主義で奪い取られた忠誠心とモラル など ●第6章 アベノミクス後の社会をどのように生き抜くか ●最後に
-
3.7
-
3.3もし全国民が国家破産に備えたら、いったい何が起こるのか? 『TVタックル』(テレビ朝日)、『たかじんのそこまで言って委員会』(ytv)で注目の勝間和代の最強ブレーンが、「反リフレ論」のウソを完全論破! 安倍政権の誕生による経済政策の変更で好景気に向かいつつある日本だが、まだまだメディアの世界では「反アベノミクス論」が大勢を占めている。 金融緩和で日本が破産するというウソを平気で垂れ流す奴らを、投資シミュレーションを論拠に一刀両断。
-
4.2◎米amazon 元チーフ・サイエンティスト◎ ジェフ・ベゾスとともに買い物の常識を変えた 科学者が明かす巨大データ企業の秘密。 Facebook,Uber,Google,Airbnb驚愕の戦略! インターネット検索やグーグルマップ、フェイスブックでの「いいね!」や インスタグラムへの写真の投稿など、意識的、無意識的に残すデジタル痕跡を通じて、 あなたがいつ、どこに行ったのか、どんな人とどれくらい親密につきあい、 何に関心を持っているかがデータ会社に把握されている。 ■常識を逆転させたアマゾン 「編集者による製品レビューよりもカスタマーレビューの方が役に立つ」。 フェイスブックやウーバーなど巨大データ企業の秘密。 ■そのつながりが経済を動かす AT&Tによる他者とのつながりを利用したマーケティングでは契約率が5倍。 米国ではソーシャルなメッセージが34万人を追加で投票に向かわせた。 ■1兆個のセンサーがあなたを記録する 全米では毎月1億件のナンバープレート情報が集められ、車がいつどこにいたか特定される。 ■もしフェイスブック・ユーザーが死んだら フェイスブックでは年100万~1000万人が死んでおり、誰がアカウント管理するかという問題が起きている。 ■ウーバーのドライバーは悩んでいる ウーバーで高い評価を確立したドライバーは他の配車アプリにも自らを登録するべきだろうか。 ユーザーがデータ企業に対して主体性を持つ条件とは。 ■データエコノミー フェイスブックの友達リストを見て融資可否を判断する金融機関。 暗記能力を問うのではなく学生同士の議論を促す教育アプリ。
-
4.0コロナ後は、アマゾンが支配する大部分と、 小さな領域をミニ・アマゾンたちが奪い合う過酷な世界 アマゾン一人勝ち時代をハッキングして生き残る方法! 小売り、物流、家電、金融、ヘルスケア、メディア、広告、クラウド、AI・・・ フォーチュン誌のトップ・ジャーナリストが詳細に描く近未来 好むと好まざるとにかかわらず、アマゾンは世界経済においてますます大きなシェアを占め続ける。ベゾノミクスがどのように重要な転換点をもたらすのか、どのように社会を揺るがすのかを知り、ハッキングせよ! アマゾンを動かす3つの哲学「顧客絶対主義」「技術革命」「長期的視野」。ピーター・ドラッカーも提唱したこれらの3本柱ですが、アマゾンは3つの哲学すべてを「同時に、鮮やかに」実践する力が桁違いだといわれます。それらを可能にしているのがCEOのジェフ・ベゾスの発明した「ベゾノミクス」です。 アマゾンのトップであるジェフ・ベゾスは、創業時にレストランのナプキンに、「フライホイール(はずみ車)」として呼ばれるアマゾンのビジネスモデルを書きつけたことが知られています。ベゾノミクスとは、本書の著者が名づけたもので、このビジネスモデルがAIの力によって、巨大化し、しかも大きく高速にまわりだしたことで、1企業の枠、業界の枠を超え、いまや資本主義全体に影響を及ぼすようになってきた現象を指しています。 本書は、AIフライホイールを軸にベゾノミクスを分析しつつ、さまざまな企業がアマゾンの一人勝ちにどう対抗しようとしているのか、将来の起業家や投資家はベゾノミクスから何を学ぶべきなのか、詳しく解説しています。 コロナ禍の後もアマゾンの独り勝ちが続き、もはやその分野は小売り、家電、クラウド、金融、ヘルスケア、メディア、広告など際限がありません。アマゾンの脅威から逃れられる業種はいまや皆無で、しかもアマゾンが見向きもしないような業界では「●●業界のアマゾン」を目指すミニ・アマゾンたちがしのぎを削っています。もはやベゾノミクスを駆使するのはアマゾンだけではないのです。 ベテランジャーナリストが、ベゾスが君臨するアマゾン帝国の特徴や強み、方針や展望などを読み解くとともに、アマゾンを出し抜き成功をおさめたスタートアップの創意工夫や、大手ライバル企業の対抗策を例に挙げ、アマゾンと共存していくための秘策を伝授します。
-
3.7ジェフ・ベゾスが銀行を作るとしたら、何をするだろうか? 次世代金融産業をめぐる戦いの構図と状況を明快に論じた待望の一冊! テクノロジー企業vs既存金融機関の戦いを徹底分析! 三大金融ディスラプター(アマゾン、アリババ、テンセント)は何を目論む? 「世界一のデジタルバンク」と称賛されるシンガポールDBS銀行は何がすごい? 逆襲する米国金融機関ゴールドマン・サックスとJPモルガンはどんな選択をした? 日本型金融ディスラプターとメガバンクとの対決の行方はどうなる? 本書は、次のような重要な問題意識に基づいて、新しい金融のあり方を問います。 1.金融はもはや「Duplicate」(擬似的に創造)できる 2.金融ディスラプター企業が金融を垂直統合してくる(既存金融機関よりも本来の「金融」機能を実現している) 3.金融にも「当たり前」のことが求められてくる 「私は、物事の本質を考える際には、すでに使われている定義を見るのと同時に、大局的に宇宙からその物事が使われている様子を鳥瞰するようなつもりで、超長期かつ地球規模のスケール感で思考するようにしています。(中略)ここで重要なのは、先の項でも述べてきたように、人々の価値観が大きく変化しているなかで、「何が実際にお金として通用するのか」「どのような価値までお金に表象させるべきなのか」が潜在的に問い直されているということなのです」(最終章より)
-
3.0いよいよ米国株の暴落が始まった! 世界同時株安に波及! アメリカ経済は本当に好調なのか? 金融の世界では、何が起きているのか? 黄金律で独自の予測を展開する経済評論家、若林栄四氏が最新経済予測を発表! アメリカや日本、ヨーロッパの経済はいつまで落ち込み、いつから回復するのか? 独自のペンタゴン手法を駆使して、アメリカ経済の“底”(=絶好の投資機会)を、2023年と、大胆に予測! さらに日々、世界を騒がすトランプ大統領をめぐる事件、中国との貿易戦争をはじめ世界景気に影響を与えるアメリカ経済の行方、中国の内部事情……など最新の話題が満載! 投資をする人もしない人も、世界経済の未来を知りたい読者の皆様には必読の一冊。【目次】第1章 確実にアメリカの世紀が終わる/第2章 ついに破裂するアメリカの資産バブル/第3章 堕落するアメリカ/第4章 ふたたび大恐慌に突入……神意の時がおとずれる/第5章 上がり切ったものは下がり、下がり切ったものは上がる/第6章 混沌の欧州、最新の金融事情/第7章 中国の流儀と運命/終章 黄金律が支配する相場の世界
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アメリカの産業・企業の構造、財政・金融システムの現状と政策の役割を、経済学の基礎知識がなくても理解できるように、ミクロ・マクロ経済学の概念から解説するとともに、所得格差、地域発展・都市化、グローバル化の諸問題など応用的トピックスまで網羅した入門書。近年のGAFAに対する規制や財政のデフォルト問題、NAFTA、米中摩擦といった通商政策など新たな動きなどにも注目して解説。
-
-ビジネス作家のなかでも傑出した一人であるジョン・ブルックスが、史上最もよく知られた金融市場のドラマである1929年の世界大恐慌とその後遺症の雰囲気を完璧に伝えているのが本書である。遠い昔々のことと思っている現代の読者にとっても身近で興味深い話題が満載されている。 本書は戦争をはさんだ時代に起きたウォール街の盛衰と痛みを伴う再生を描いた劇的な年代記だ。この時代に生きた最も印象的なトレーダー、銀行家、推進者、詐欺師の人生と運命に焦点を当て、好景気にわいた1920年代の貪欲、残忍さ、見境のない高揚感、1929年の株式市場の大暴落による絶望、そしてそのあとの苦悩を生き生きと描き出している。 具体的には、大相場師のジェシー・リバモア、JFKの父親で仕手筋と有名だったジョセフ・P・ケネディ・シニア、ベンジャミン・ストロング・ニューヨーク連銀総裁、フランクリン・D・ルーズベルト大統領など当時のウォール街を彩ったそうそうたるメンバーや、のちに有罪判決を受けて刑務所に収監されるリチャード・ホイットニー・ニューヨーク証券取引所社長らの活躍や暗躍や暗闘を、映像が浮かぶように活写している。 本書の原題にも使われている「ゴルコンダ(GOLCONDA)」とは、「今ではすっかり廃墟となったが、昔はそこを通過するだけで、だれでもが金持ちになれたというインド南東部の町」のことである。富者は勢いを失い、美しい建物は廃れ果て、その輝ける栄光は失せ、二度と元には戻ることはなかった。株式に関心ある人には知識や常識として知っておきべき史実がいっぱい詰まっている! 再び、ゴルコンダが起こらないように(あるいは、ゴルコンダが起こったときに備えて)!
-
3.7
-
-米国経済の行方は全世界に影響を及ぼす。それだけに目が離せない。米国は2015年12月に利上げを行ったが、次はいつ利上げを行えるのか、それとも当分の間は行えないのか。消費動向はどうか。エネルギー価格の下落はどのような影響を及ぼすのか。トランプ旋風吹き荒れる大統領選の行方も気になる。さまざまな角度から米国経済の実態を検証した。 本書は週刊エコノミスト2016年3月8日号で掲載された特集「アメリカ大失速」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに Part1 経済・金融の綻び ・危うさを増す米国経済 利上げ・原油安で景気後退も ・景気後退はあるか 現地で深まるリセッション議論 ・ニューヨークで聞いた米国経済の行方 ・FRBの悩み 難しい「ほどよい利上げ」判断 ・アンケート FRBは今年、何回利上げできるのか? ・企業業績 業績悪化は明らか 製造業、グローバル企業に打撃 ・個人消費 消費減速、すでにピークアウトの動き ・不穏な金融市場 ハイイールド債に大きなリスク ・激変する住宅事情 若年層は貧困化で持ち家率低下 ・自動車ローン サブプライム層のローン急増 ・逆風のエネルギー業界 中堅・中小の身売りや破綻が現実味 ・シェール危機 国内で厳しい米企業が“脱米国”に活路 ・日本への影響 米国で稼ぐ日本企業は? 1位は船井電機、2位がスバル 米国系投信は大丈夫? エネルギー関連、ハイイールド債 Part2 政治・社会の変容 ・大統領選に見る米国の格差拡大 2大政党にも再編の兆候 ・大統領選の情勢 トランプ台頭は反職業政治家感情 ・外交・安全保障 イラク戦争失敗で内向き志向 【執筆者】 谷口健、石原哲夫、土屋貴裕、藤代宏一 鈴木裕明、福田圭亮、安田一隆、趙玉亮、 津賀田真紀子、吉川涼太、藤原裕之、壁谷洋和、 在原次郎、伊藤桂一、篠田尚子、西川賢、 渡辺将人、渡部恒雄、週刊エコノミスト編集部
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本においても、日本におけるIFRS採用の動向や、日本の会計基準のIFRSへのコンバージェンスの議論などに関連して、アメリカの会計基準の動きが直接的にまたは間接的に日本の会計基準に影響を与えており、その動向には多くの関心が寄せられている。こうした環境下にあって、アメリカの会計基準の動向を理解することは、今後のIFRSおよび日本の会計基準の動向を見極めるうえでも重要であり、直接アメリカの会計基準を適用している企業の経理・財務担当者はもとより、IFRSの導入準備を進めている企業の関係者や日本基準の将来動向に関心を持つ方々にとっても有益であると思われる。 本書は、2011年6月までに公表されたアメリカの会計基準を対象として取扱っており、本書を執筆するにあたっては、以下の点に重点を置いている。 1.実例を豊富に取り入れ、また、説明をできるだけ平易に行い、職業会計人、企業の経理担当者はもちろんのこと、一般ビジネスマン、学生等にも容易に理解できる内容にした。 2.アメリカの会計基準の主たる項目を網羅的に取入れる一方、各項目の会計処理および開示内容については、そのポイントを短時間で理解できるようにした。 3.適宜、会計基準等の原文を参照しやすいよう、主な会計基準等の関連パラグラフを記載した。 4.実務に役立つように、可能な限り充実した解説を加えた。 5.アメリカの会計基準の説明に加え、適宜、日本の会計基準およびIFRSとの比較を織り込んだ。 【主な内容】 第1章 最近のトピックス 第2章 アメリカの会計原則 第3章 連結決算と持分法 第4章 公正価値の測定 第5章 金融商品 第6章 外貨関連事項 第7章 非貨幣取引 第8章 収益の認識 第9章 棚卸資産 第10章 リース会計 第11章 利子費用の資産化 第12章 資産除去債務 第13章 減損会計 第14章 研究開発費 第15章 ソフトウェア 第16章 企業結合 第17章 退職その他の従業員給付 第18章 株式報酬 など。
-
3.5金融教育先進国・アメリカでは、 高校の授業で、「お金」の基本を学びます。 「将来のために貯金しよう」「株ってどんなもの?」などといった、 世の中のお金の本でよく言われるようなことだけではありません。 「破産とはどんなシステムか?」「金融詐欺に騙されないためにどうすべきか?」「老後資産にはいくら必要か?」 ――人生のありとあらゆるライフステージごとに、お金とどう付き合っていくべきかを体形的に学びます。 就職、結婚、マイホーム購入……わたしたちが人生で重要な選択をするとき、 それらすべてが「お金」と切っても切り離せない関係にあります。 お金について考えることは、自分の人生について考えることでもあるのです。 一冊で一生モノのお金の基礎知識が身につく、 世界一やさしい入門書!
-
4.0金融教育の先進国・アメリカでは、高校生からお金の流れと世の中の仕組みについて 学校で勉強する。 アメリカの高校生が学んでいる、 「日本の学校では教えてくれない」一生ものの経済のきほんの授業を一冊に凝縮!
-
3.3■ややこしい金融の概念がカンタンにわかる 金利、インフレ、ローン、株、為替、クレジット……知ってるつもりでも、自分では説明できない金融のややこしい概念。将来お金で困らないために、絶対に知っておきたい金融の基本を小学生でも理解できるレベルの平易な言葉で解説します。 マネーの基礎知識を簡単に学びたいけれど、どの情報もややこしいと感じる大人に向けて、60分で体系的に学べる本です。 ■将来お金に困らないための貯蓄、投資、消費(クレジット、ローン)の知識が身につく この本を読むことで、将来お金に困らないための、お金の使い方、貯め方、増やし方の基本を学ぶことができます。お金にまつわる良いことばかりではなく、お金のリスクも解説します。
-
-日本人は世界の枠組みが大きく変わったことを理解しておらず、眼前の国際情勢を正しく状況判断できずにいる。そんな日本人に、ブッシュ政権要人の肉声を伝え、アメリカが考えているシナリオを的確に描き出した、瞠目の一冊である。もはや冷戦思考の延長では国際政治は語れない。アメリカの新しい戦略はテロリストへの積極的先制攻撃であり、冷戦時代の「抑止力と封じ込め」とは全く異なる。もはやアメリカは、本質的には同盟国すら必要としておらず、自国一国の力ですべてが解決できると考えている。さらにいまのブッシュ政権は、ここしばらくの歴代政権の中では抜群の結束力の強さを誇っている。この力を用いて、まずは中東に決定的な影響力を確立する。そして次は北朝鮮、そして中国。さらに、ドルの立場を守るための日本金融行政とのきわどい対決……。新たな世界の流れを正しく認識し、日本の新しい国家戦略を構築するために必読の書。
-
-なぜユダヤ人はアメリカでビジネスに成功したのか。彼らはアメリカ経済にどれほどの影響力を持っているのか。アメリカにおいても、遅れてきた移民として憎悪されるユダヤ人。しかし、想像を絶する逆境のなかでも彼らは耐え、成功を収め、アメリカ経済の最前線に立って、時代を先取りするビジネスモデルを生み出してきた。本書は、特にユダヤ人の財力・人脈・習慣・人使いの面に注目。金融ビジネスのみならず、情報・通信、メディア、玩具、化粧品、カジノ・観光、不動産業等で大きな影響力を持つ彼らの実像を、最新の情報とともに、それぞれの業界ごとに綿密な調査を行い、明らかにしていく。ユダヤ人企業家の足跡を学ぶことは、とりもなおさず、アメリカ経済の最新の潮流を読み解く鍵となる。同時に、それはまた私たち日本人が進むべき方向性を指し示す指針となろう。巷間囁かれている「陰謀説」を排し、ユダヤ人の実像を丹念に描き出す一冊である。
-
4.0「消費税」という名の非関税障壁に対し、米国はいかなる報復に出るか? 日本製品を米国に輸出する場合、輸出企業は、消費税にあたる金額を輸出還付金として日本政府から受け取ることができる。これが非関税障壁となり、日本企業の競争力を増すことになる。ゆえに米国は、過去にも日本の消費税に対し報復を行なってきた。1989年消費税導入→日米構造協議、1994年消費税増税法案可決→年次改革要望書、1997年消費税増税→金融ビッグバン、2010年消費税10%案→日米経済調和対話、2012年増税法案可決→TPP協議本格化。では、2014年と15年の増税には、米国はどのような報復を画策しているのだろうか――。 「消費税」をはじめとして「TPP」「規制緩和」「為替」等の問題は、日米交渉の歴史という観点から見ると一つの道筋で繋がっていることがわかる。現地で渉猟した米公文書館の資料をもとに解説する「誰も書かなかった日米経済戦争の真相」。これぞ、著者の集大成となる一冊!
-
3.8ユダヤ人はなぜアメリカでビジネスに成功したのか? 彼らはアメリカ経済にどれほどの影響力を持っているのか? 遅れてきた移民として憎悪されたユダヤ人。彼ら自身が自らの経済的成功の存在を否定したため、その実態は今まで知られてこなかった。本書は、彼らの底知れぬ経済力を金融、流通、マスコミ、不動産、建設などの多岐にわたる客観的な調査から明らかにする。 【目次より】●金融支配の神話――大恐慌の時代 ●「経済の暗黒大陸」に固めた地歩――百貨店・新聞・広告業 ●主要産業となった映画産業――東欧系ユダヤ人の出現 ●今日のユダヤ人大富豪――その財力と実像 ●不動産投資こそ富の源泉――ユダヤ移民の天職 ●あらたな事業で富を築く――マスコミ・小売業 ●今日のユダヤ系投資銀行――受け継がれるユダヤ人脈 ●ウォール街のユダヤ人――金融ビジネスの創造者たち。巷間囁かれている〈陰謀説〉を排し、ユダヤ人とその経済力の実像を丹念に描き出す。
-
3.8ジャック・マーの右腕、アリババ前最高戦略責任者が執筆! 中国の巨大IT企業、その想像を絶するビジネス戦略がすべて明かされる。 「われわれは中国版アマゾンではない」 「データ」と「ネットワーク」を融合させたアリババ式「隠陽ビジネスモデル」こそがこれからの世界標準となる。 ◆目次より ・なぜ中国は金融テクノロジーで米国を抜き去れたか ・「奇跡が起きた」--人類最大のショッピングデー「独身の日」を支える舞台裏 ・アマゾンは「データ」は強いが、「ネットワーク」が弱い ・意思決定も自動化される ・C2B(カスタマー・トゥ・ビジネス)へ ・あなたの企業は「線」か「面」か「点」か ・アリババは組織自体が「機械学習」する ・クリエイティビティを生むマネジメント革命とは ・アリババでは、上司が年に5回も変わる ・これからの時代、個人と企業が生き残るための教訓 ◆ジャック・マー序文 「本書は、読者のみなさんが新たなデジタルエコノミーに足を踏み入れる上で、貴重な手引きになるだろう」 ◆米国からも賞賛 グーグル前会長 エリック・シュミット推薦。ペイパル創業者 ピーター・ティール推薦 原書は、米国名門版元ハーバード・ビジネス・レビューより英語にて刊行 ◆日本語版スペシャル・エディション(著者最新インタビュー収録) ・GAFAはアリババのライバルか ・金融分野でアマゾンとの対決はあるか ・AI都市、AI政府は始まっている ・日本企業がIT戦略で成功する方法 ほか
-
-中国の超巨大ネット通販企業・アリババ。年間の商品取扱高は25兆円にも及び、イーベイや楽天を圧倒。利益水準ではアマゾンにも勝つ。 そのアリババが米国への上場計画を発表し、世界の株式市場を揺るがしている。いまや同社は内需拡大や金融改革など中国の経済政策を動かすほどの存在だ。 創業15年でここまで駆け上がった「怪人」馬雲(ジャック・マー)会長の実像、アリババを動かす中核メンバー、創業期を支えたソフトバンクや米ヤフーとの関係など、謎に包まれた企業の正体に迫った。 本誌は『週刊東洋経済』2014年5月24日号緊急特集の20ページ分を抜粋して電子化したものです。 【主な内容】 世界を揺るがすネットの怪人 迫るソフトバンクとの決別 ヤフーがタオバオを“積極学習” 米国投資家の話題独占。アリババのお値段は? 美人社長から学生まで密着取材!「アリババ依存症」を追う 買い物が大好き! でもいい店がない バイト学生も熱中! タオバオにはまる理由 配送先は職場! 忙しい上海人もやはりネット派 偽物も多いけど、何でもあるのが魅力 余額宝のおカネで買い物もしてしまう タオバオで月商100万元のスーパー主婦 タクシー配車アプリが爆発的に普及 アリババの金融大革命 日本企業のアリババ活用術 革命児 馬雲 野望の原点
-
3.0・コーポレート部門は何を拠り所にして最低限何をするのか分かりやすく解説します。 ESG誕生に関与したコフィ・アナン前国連事務総長の想いを企業が実践するためには何をすれば良いのでしょうか? ――世界共通の理念と市場の力を結びつける道を探りましょう。 民間企業のもつ創造力を結集し、弱い立場にある人々の願いや未来世代の必要に応えていこうではありませんか。 ――第7代国連事務総長 コフィー・A・アナン―― ESGという言葉自体は、企業の中長期的成長のために不可欠な要素として、すでに一定の認知度があります。しかしながらビジネスの現場では、金融業界や投資家、経営者が取り組むこととして認識され、ESGに取り組む部門や業務の仕組みが社内にあったとしても、何が本当に求められているのかについて理解されていないように見受けられます。 ▼世の中の物差しが大きく変わった今こそ理解しておきたいESG×リスクマネジメント ・コーポレート戦略・KPI立案、サステナビリティ情報開示、ESGスコア改善に役立ちます。 ESG開示基準をもとにしたサステナビリティ文脈と、セクター/業種の特徴やマテリアリティを理解した上で、全社方針・戦略のもとに事業部門とコーポレート部門が協力し、ESGの取り組みを加速することが求められることは間違いありません。 本書では、企業のコーポレート部門担当者であれば、ぜひ知っておくべき「ESGの必要性と本質」と、その「リスクマネジメント」についてわかりやすく解説します。
-
3.5これからの時代、豊かな暮らしには「投資」は必須です。 これから「投資」を始める人にとって、本当に必要な知識をまとめた1冊! 暗号資産(仮想通貨)の基本をすべて解説しています。 ・仕組みはどうなっているの? ・危なくないの?? ・どうやって買えばいいの?? ・現金とは何が違って、何がいいの???? なかなか聞けない「暗号資産」について確認し、 賢いマネーライフを送りましょう。 ■目次 ●0 知っておきたい「お金」のこと ・お金に必要な3 つの機能 ・お金の発行と流通の仕組み ・お金は「もらう」ものから「増やす」ものへ ほか ●1 新しいお金としての暗号資産 ・暗号資産が生まれた背景 ・暗号資産が持つ4つのリスク ・暗号資産で広がるデジタル経済圏 ほか ●2 暗号資産の運用の仕組みを学ぼう ・暗号資産のウォレットは銀行口座の仕組みと同じ ・取引所のリスク対策① コールドウォレットで資産を管理する ・個人でできるリスク管理 ほか ●3 暗号資産にかかる税金について知っておこう 01 暗号資産は「雑所得」として税金が発生する 02 暗号資産で支払いをした売買でも税金が発生する 03 利益(取得価額)を計算しよう ほか ●4 世の中の動きと連動して暗号資産の価格は変動する ・暗号資産の値動きの特徴 ・ビットコインは金融危機に強い ・世界的大企業の参入を市場は歓迎している ほか ●5 暗号資産投資のこれからを学ぼう ・政府が発行を検討している「CBDC」 ・ゲームして稼ぐことができる「GameFi」 ・メタバースと暗号資産には密接な関係がある ほか ●コラム ・ブロックチェーンとは? ・ビザンチン将軍問題とは? ・スケーラビリティ問題とは? ・マイニングとステーキング ・エアドロップとは? ・ビットコイン相場の歴史 ・イーサリアムの開発計画と技術改善 ・具体的なNFTの活用事例 ※ 本書には解説の都合上、特定の暗号資産銘柄や暗号資産交換業者名などを記載していますが、 あくまでも例として取り上げたもので、その暗号資産の売買や口座開設等を推奨するものではありません。 ■著者 松嶋真倫(まつしま・まさみち) マネックス証券 マネックス・ユニバーシティ 暗号資産アナリスト 大阪大学経済学部卒業。 都市銀行退職後に暗号資産関連スタートアップの立ち上げメンバーとして業界調査や相場分析に従事。 マネックスクリプトバンク株式会社では 業界調査レポート「中国におけるブロックチェーン動向(2020)」や 「Blockchain Data Book 2020」などを執筆し、 現在はweb3ニュースレターや調査レポート「MCB RESEARCH」などを統括。 国内メディアへの寄稿も多数。2021年3月より現職。 本書が初の著書。
-
-ブロックチェーンは社会の繋がり方を根底から変える! ビットコインを代表とする暗号通貨の認知度の高まりと共に、「ブロックチェーン」という言葉にも注目が集まっている昨今。しかし、ブロックチェーンとはいったい何なのか? 今後の社会の在り方を大きく左右するであろうブロックチェーンを十分に活用できないということは、国際社会において致命的といっても過言でない。国家という枠組みをも超越するブロックチェーンの潮流に、正しく乗るための入門書! 【収録トピック(抜粋)】 ・ブロックチェーンとは何か? ・3つのブロックチェーン ・ブロックチェーンの有用性(金融/財務/シェアリングエコノミー/登記/年金/マイナンバー/著作権/公益活動/ネットフリマ/商品管理) ・ブロックチェーンに危険性はあるか ・ビザンチン将軍問題 ・暗号通貨の歴史と現況 ・暗号通貨の市場の動向 ・ビットコイン(BTC)=決済の手段 ・イーサリアム(ETH)=取引と情報の記録 ・リップル(XRP)=価値の送信 ・暗号通貨の使い方 ・DAOとしてのビットコイン ・ビットコインのハードフォーク問題 ・暗号通貨にはなぜ価値があるのか ・ICOの定義 ・ICOのメリット/デメリット/リスク ・ICOのリスク ・ブロックチェーンがもたらす未来 ・企業が変わる〈財務管理〉〈人事評価〉〈人材調達〉 ・人々の生活が変化する〈スピードとコスト〉〈生活上の諸問題〉 ・国家が変わる〈行政プロセス〉〈政治家〉 ・社会が変わる〈日本もキャッシュレスへ〉〈そして金融が変わる〉 他 ※本書は単行本『暗号通貨とブロックチェーンの先に見る世界 ―テクノロジーはどんな夢を見せてくれるのか』(2018年12月梓書院発行)を電子書籍化したものです。
-
4.2『サイロ・エフェクト』著者最新作! なぜ経済学やビッグデータ分析は問題解決に失敗するのか? 社会科学とデータサイエンスの融合で人類学的知見が果たすべき役割とは。 FTのトップジャーナリストが広い視野から事象を分析する人類学の思考フレームワークを解説。 * * * 現代社会の知的ツールが、機能不全に陥っている。経済予測、選挙の世論調査、金融モデルは外れてばかりだ。こうしたツールは、世界はごくわずかな変数で分類・把握できるという前提に基づいて設計されている。視野が狭いのだ。 世界が安定していて、過去が未来の参考になる時代なら、それでもうまくいくかもしれない。だが変化の激しい時代、「極端な不確実性」に直面しているときは、狭い視野は危険だ。 ビッグデータをAI(人工知能)がどれだけ処理しようとも、そこから導き出されるのは「WHAT」だけである。事象の原因、「WHY」にはたどり着けない。 * * * いま求められるのは、広い視野と「WHY」を突き詰める視点である。「未知なるものを身近なものに」「身近なものを未知なるものに」変化させ、隠れたパターンを見いだすツールである。 本書では人類学者のように「虫の目」で世界を視て、「鳥の目」で集めた情報と組み合わせることで「社会的沈黙」に耳を澄ます技術「アンソロ・ビジョン(人類学的視野)」を紹介する。 フィナンシャル・タイムズ紙(FT)のトップジャーナリストが執筆した話題作。
-
4.2
-
4.3急速にキャッシュレス化が進む中国。9億人以上が利用する決済サービス「アリペイ」(支付宝)。1元から資産運用ができるMMF「余額宝」。個人や企業の信用度をスコアリングする「芝麻信用」(ジーマ信用)。一般消費者や零細企業に少額融資を行う、マイクロクレジット専門のインターネット銀行「網商銀行」(マイバンク)。これらすべてを動かすのが、アリババ・グループの金融関連会社「アントフィナンシャル」だ。現在、アントフィナンシャルの業務分野は、決済、融資、資産運用、保険、銀行に及び、テクノロジーによって金融のあり方を大きく変えようとしている。本書では、中国の金融シンクタンク「中国金融40人論壇」(CF40)のメンバーが、2004年の「アリペイ」の誕生から2017年までのアントフィナンシャルの発展史を辿り、その全貌を解明する。アントフィナンシャルが最も重視するのは零細企業や農村、一般消費者へのサービスだ。資金ニーズはあるものの、信用情報がなく、銀行から融資を受けられない人々には、有効な信用情報を蓄積する術を生み出し、適正に与信判断を行うシステムを構築することで融資を実現した(第5章で詳述)。貸付リスクの高さから既存金融機関に見放されてきた農村部でも、実情に即して金融ニーズを腑分けし、インフラを整備して、都市部と同等のサービスを提供しようとしている(第8章で詳述)。この企業の本質は、取引における「信用」の問題を技術力で解決することにある。さらに、その技術を積極的に外部に開放することで、独自の金融エコシステムを世界へ拡げようとしている。KPMG/H2 Venturesが選出する「Fintech100」に3年連続で第1位に選ばれた、世界的フィンテック企業の全貌を解明。金融の最前線を知り、中国の現在を知るための必読書。
-
3.3
-
-金融データ分析を行ったり、モデル駆動のトレード戦略を構築するクオンツやトレーダーたちは、毎日どういったことをやっているのだろうか。 本書では、クオンツ、講演家、高頻度トレーダーとしての著者の経験に基づき、プロのクオンツやトレーダーたちが日々遭遇するさまざまな問題を明らかにし、それを解決するための分かりやすいRコードを紹介する。 プログラミング、数学、金融概念を使って簡単なトレード戦略の構築と分析を行うことに興味のある学生、研究者、実践家たちにとって、本書は素晴らしい入門書になるはずだ。分かりやすく包括的に書かれた本書は、データの調査や戦略の開発を行うにあたり、人気のR言語を使えるようにすることを主眼としたものだ。 本書では、基本的なトレードの概念と、クオンツやトレーダーたちが拠って立つ数学、データ分析、金融、プログラミングを分かりやすく説明していく。各ケーススタディーは、読者の記憶に残りやすいように、細かくモジュールに分けて説明する。各章は数学、金融、プログラミングをバランスよく含み、統計、データ分析、時系列の操作、バックテスト、R言語によるプログラミングといった多岐にわたる題材をカバーしている。 本書は、非常に読みやすいながらも、各題材を徹底的に掘り下げているので、ガイドブックとしても便利に使える。本書を読み終えるころには、クオンツトレード分野の学術研究者や実践家たちが使っているR言語と関連するパッケージに関する知識が身についていることだろう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 生産性100倍も夢ではない! 1人1台、オフィスロボットの時代 ・世界の最新事情に見る「IPA」への進化 ・ヤマトグループ デジタルイノベーションによる経営改革 ・先進事例11に学ぶ! 障害の乗り越え方と成功の秘訣 ・RPAは第2ステージに突入 自動化拡大のカギはAIツールの利用・応用 <注目のインタビュー> 「企業がとるべき3つの道」入山章栄・早稲田大学ビジネススクール准教授 「RPAはAI導入の土壌になる」山田誠二・国立情報学研究所教授 「完全自動化で世界はどうなるか」波頭亮・経営コンサルタント 定型的な業務を、ソフトウエアのロボットで自動化してくれるのがRPA(Robotic Process Automation)。ホワイトカラーがより創造的な業務にあたれるようになり、生産性が劇的に上がります。 様々な業界で導入が進む、注目のITツールです。 RPAとはそもそも何なのか? どのような機能や特徴があり、導入のメリットはどこにあるのか? RPAが向いている業務、あるいは向いていない業務は? RPAを導入する際の注意点は? 本書は、このような疑問に徹底的に答えます。 また、サービス業、製造業、金融業、自治体、病院、大学など様々なタイプ・規模の組織の成功事例11を取材。成功の秘訣や障害の乗り越え方を明らかにします。 さらに、RPAとAIを組み合わせた結果、業務の自動化はどのように拡大していくのか、RPAの最先端を解説しています。
-
-英語を駆使して驚異的営業成績を挙げてきた外資系金融マンが編み出した 海外で活躍できる人材を量産する、実践的英語学習メソッド! 音声ダウンロード、アプリも入手可能! 2020東京オリンピックにも役立つフレーズ満載!! 本書のドリルを行えば、楽しく、確実に英語が身に付く! しかもその方法はとてもシンプル。基本的に「たった2つのこと」だけを行えばよい。 1つ目は「動詞フレーズ」を覚えること、そして2つ目は「言い出し表現」を覚えることだ。 著者はSmart Englishという英会話講座を長年行ない、中学生から80歳代の1000名を超える“話せる”卒業生を輩出している。 世界有数の外資系企業で10年以上英語を駆使して、大きな成果を上げてきた。 とは言っても、大学を出て就職するまでは留学などの海外経験はほとんどない。小学生時代から始めたNHKのラジオ講座だけで英語を極めていった。 本書の方法は海外に住んだり留学したりした経験がなく、自力で英語の達人の域に達した著者が生み出した、誰でもできる最強の英語学習ドリルだ。
-
-イエール大学寄贈基金のCIOが明かす 成功する投資プログラム構築に不可欠のロードマップ 過去30年間で年率12.4%!パッシブ運用と逆張り戦略が成功への近道 名著と名高い本書の初版(2000年)が出版されてからの数年で、世界の投資の景色は劇的に変化した。しかし、スウェンセンの投資戦略がイェール大学寄贈基金にもたらす成果は、変わることなく目を見張るものがある。来る年も来る年もイェールのポートフォリオは、市場に大きく勝ち続け、スウェンセン在職中の23年で、寄贈基金の資産を 200億ドル以上も増やし、イェールの財政に多大な貢献をした。これは米国の大学史上でずば抜けた功績である。(2020年6月時点で312億ドルを運用) スウェンセンは、この全面改訂・拡大版で、イェール大学寄贈基金を支える「投資プロセス」について詳述している。寄贈基金における「資産配分」から「アクティブなファンドマネジメント」 までの分野のさまざまなトピックに光を当てつつ、ファンドマネジメントに関する明快で鋭い洞察を提供。リスクの対処法、外部運用機関の選び方、市場で起こるあらゆる問題の切り抜け方などに取り組むため、実例を用いているが、その多くは自身の経験に基づくものである。また、意識して単刀直入なアドバイスを心がけている――――「伝統的な投資は多くの場合、高く買い、安く売ることにつながる」「信頼は、線香花火的なはかない成功よりもはるかに重要である」等々だ。専門知識、不屈の精神、長期的なものの見方は、秘密の仕掛けやトレンドフォローが利かないような場合でも、有益な成果を生むのである。 ファンドマネジャーをはじめ、市場について学ぶすべての人が活用できる、投資ポートフォリオを積極的に運用するための頼れる一冊。 ※本書は『勝者のポートフォリオ運用』(2003年、金融財政事情研究会)の全面改訂・拡大版です。
-
3.0米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和の終了を決定。リーマン・ショック以降6年間続いた超金融緩和からの脱出を主導するのは、女性初のFRB議長ジャネット・イエレンだ。夫アカロフと師トービンはともにノーベル経済学賞の受賞者、自身も経済学者からセントラルバンカーに転じたイエレンは、どのような経済観の持ち主か。そして出口戦略の舵取りをどのように進めようとしているのか。ワシントンで現地取材にあたった記者が、その実像に迫る力作。 雇用を大事にする「ハト派」セントラルバンカーと見られていたイエレンが出口を主導する真意は?金融正常化に足踏みする日本との違いは?――「テイパーリング」「フォワード・ガイダンス」など出口戦略を読み解くキーワードの解説を交えながら、グローバル・マネー経済のこれからを読み解く。
-
3.0「現代は乱世だ。ウクライナ戦争は、実質的にロシア対米国を中心とした西側連合の戦争になってしまった。この戦争は長期化する可能性が十分ある。」(あとがきより) パンデミックに戦争、元首相暗殺事件、急激なインフレに端を発した金融・経済危機……。正真正銘の乱世を生き抜くために不可欠なのは、正確な情報を得て、自ら判断することだ。そのためには、報道に接するだけでなく、優れた本から知識を吸収する必要がある。 本書は、多い月に500冊以上を読破する作家で宗教家でもある佐藤優氏が、テーマに合わせて今読むべき一冊とその要点を紹介した書評本であると同時に、正しい知識を身につけるための教科書であり、世界と日本、人が抱える問題と正面から向き合って「答え」を提示する人生相談本でもある。 扶桑社『週刊SPA!』の人気連載「佐藤優のインテリジェンス人生相談」のなかから、現在の世界情勢や日本の世相を反映したものを厳選して80本収録。“知の巨人”が人々の悩みにどう向き合い、乱世の世界を生き抜くため方法をいかに読書から見出しているのか? その答えはこの本に。
-
4.0元ゴールドマンサックスのカリスマアナリストとして日本の金融再編に多大な影響力を与えながら、日本の国宝・重要文化財を守る江戸時代より続く老舗企業の経営者へと転身したデービッド・アトキンソン氏が、オックスフォードの日本学とゴールドマンサックスの財務分析を駆使し、「日本」の経済と文化を深く考察。日本人だけが知らない「日本の弱みと強み」をわかりやすく解説する。
-
3.0まもなく国家の財政は破綻します! 出版社の営業・池内貴弘は急な異動で月刊誌の経済担当に。新たな職場に戸惑う最中、叔母から不動産運用に関して相談を受ける。執拗に融資を持ちかける担当者は、なんと仙台の地銀に勤務する池内の元恋人だった。 池内は面会するも、直後に彼女は自殺してしまう。一体なぜ? 周辺取材から見えてきたのは苦境の地銀と、過酷なノルマだった。彼女はその処方箋を求めて、ある男に会っていたという。 古賀遼、人は彼を金融界の掃除屋と呼ぶ。政界の重鎮の命を受け、日銀総裁人事にも関与していたようだ。池内は、古賀の暗躍を白日のもとに晒そうと奔走するが――。 この小説は経済記事よりリアルだ――解説・原真人氏(朝日新聞編集委員)
-
3.8「世界中に火種はあるが、一番ヤバいのは日本だ」! 月刊誌「言論構想」で経済分野を担当することになった元営業マン・池内貴弘は、地方銀行に勤める元・恋人が東京に営業に来ている事情を調べるうち、地方銀行の苦境、さらにこの国が、もはや「ノー・イグジット(出口なし)」とされる未曾有の危機にあることを知る。 金融業界の裏と表を知りつくした金融コンサルタント、古賀遼。バブル崩壊後、不良債権を抱える企業や金融機関の延命に暗躍した男は、今なお、政権の中枢から頼られる存在だった。そして池内の元・恋人もまた、特殊な事情を抱えて古賀の元を訪ねていた。 やがて出会う古賀と池内。日本経済が抱える闇について、池内に明かす古賀。一方で、古賀が伝説のフィクサーだと知った池内は、古賀の取材に動く。そんな中、日銀内の不倫スキャンダルが報道される。その報道はやがて、金融業界はもとより政界をも巻き込んでいく。 テレビ・新聞を見ているだけでは分からない、あまりにも深刻な日本の財政危機。エンタテインメントでありながら、日本の危機がリアルに伝わる、まさに金融業界を取材した著者の本領が存分に発揮された小説。 日経ビジネス連載時から話題となった作品、待望の書籍化。 果たして日本の財政に出口(イグジット)はあるのか! 編集者からのおすすめ:著者の代表作の一つである『不発弾』に登場したダークヒーロー、古賀遼が再び登場。過酷な運命を背負った男の生きざまに、ぜひ、触れてください。
-
-テレビ放送でも話題になった池上彰の愛知学院大学「経済学講義」文庫・全2巻を合本で提供します。 経済の視点で戦後世界の歴史やニュースを読み解く「池上講義」。 「歴史編」では、第2次世界大戦後の世界や日本経済の歩みを振り返ります。戦後の資本主義VS社会主義、東西冷戦の歴史などを学ぶことで、ロシアのウクライナ侵攻の背景や、今の世界経済の問題点が見えてきます。「ニュース編」では、原油価格、リーマン・ショック、為替政策、金融政策、EU、宗教と経済……など、今の世界を理解するために必要なニュースのキーワードをピックアップ。混迷する世界を読み解くにはぴったりの内容となっています。 ※本商品は1冊に全巻を収録した合本形式での配信となります。あらかじめご了承ください。
-
4.0知らない人は基礎の基礎からよくわかる、知ってる人なら頭の整理に役に立つ「ニュースの教室」決定版。 (目次から) (1)アメリカ トランプか、ヒラリーか? 世界を揺るがすパワーゲーム 同性婚と「宗教の自由」が対立?/トランプ「イスラム教徒入国禁止!」/サンダース躍進! 党員集会を取材した/悪夢のシナリオ/FRB、ついに金利引き上げ/原油価格下落で金融危機再来? (2)EU “女帝”メルケルはEU崩壊を防げるか? 中東から難民押し寄せ、EUがパニック/「ギリシャ神話」と地政学/サミットはどうなっている?/地球温暖化防止「パリでの約束」なるか/ベルギー連続テロ (3)中東 ISの力を地政学から考える イランの核開発阻止できる?/トルコ内での対立が日本にまで/シリアめぐり世界は混沌/「第五次中東戦争」は起きるのか/アメリカの心変わりにサウジ激怒 (4)ロシア 逆らう者は許さない“皇帝”プーチン クリミア半島はいま/ヤルタ会談の三巨頭銅像のイメージ操作/「おそロシア」になってしまった/メディアの広告収入絶つという発想 (5)中国 習近平は大人の国にできるのか 南シナ海、波高し/中国株はなぜ暴落したのか/人民元引き下げが世界を揺るがす/中国、「二人っ子政策」へ/香港で反中国書店幹部を「拉致」か (6)日本 祖父・岸信介に並びたい? 安部首相の動機 忖度、忖度、そして忖度……/軽減税率と新聞業界/次々と「内閣改造」をする理由/最近の政治家は劣化したのか?/マイナス金利の衝撃/安倍談話のジレンマ/「ポツダム宣言読んでいない」発言/「南京大虐殺」とは何か エマニュエル・トッド、ミシェル・ヴィヴィオルカ両氏との対談も収録。
-
4.0【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 北京五輪にも象徴される経済成長の一方で、食品問題、台湾との対立、チベット弾圧への抗議活動など多くの問題が噴出する中国、グルジアとの戦争が勃発したロシア、独裁者の君臨や資源を巡る他国の攻防に晒されるアフリカ諸国、情勢悪化の一途を辿る中東、金融不安を抱える中、政権交代したアメリカ……2008年の「激動」の世界情勢について、その原因や歴史的背景、今後の見通しまで、地図や図版も交えて最強ニュースウォッチャー・池上氏がわかりやすく解説。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字サイズだけを拡大・縮小することはできませんので、予めご了承ください。 試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの端末での表示をご確認ください。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 インフレ・デフレとは何か? いくらになれば円高で、どこからが円安? 老後資金はどうなる? 日本は豊かになれるのか、私たちの暮らしはどうなるのか? 池上彰さんが、学生への講義で、お金と経済の不安や疑問についてこたえた。 シリーズ2巻目は、日々のニュースをもとに解説し、より身近なものとしてお金と経済を理解できる。 「この本で取り上げている年金など社会保障の問題は、とりわけ学生の関心が高く、若者たちの危機意識に驚かされました。 と同時に、いまの若者たちが、日本の社会保障制度を知らないまま不安になっていることに気づきました。知らないから不安に思うことは、いくらでもあることです。まずはよく知ることから始めなければなりません。」 〈目次〉 経済学の勉強の続きを――令和新版のための「はじめに」 はじめに Chapter.1 インフレ・デフレとは何か Chapter.2 日銀とはどんな銀行か――財政政策と金融政策 Chapter.3 バブルへGO!――なぜバブルが生まれ、はじけたか? Chapter.4 円高で企業は日本に残るか海外に出るか Chapter.5 君は年金をもらえるか――どうする少子高齢化 Chapter.6 金融危機はなぜ起きるのか?――リーマンショックとは何だったのか Chapter.7 日本はどうして豊かになれたのか?――戦後日本経済史
-
5.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 超ベストセラー『石川晶康日本史B講義の実況中継』に「テーマ史」編が登場です! ●本書の特色● (1) 史学史・女性史・琉球・沖縄史などの必須テーマから、メインの政治史まで、入試頻出テーマに焦点をしぼりました。 (2) 国公立大・難関私大でも出題される、短い「論述問題」を要所要所で紹介しています。 「模範解答・解説」をよく読むようにしてください。 (3) 既刊の通史講義『日本史B講義の実況中継』全4巻で構築した日本史学習に、テーマ史の側面から光をあてる講義で、知識を深化し、不得意分野を一掃します。 ◆本書はしがきより◆ まずは「史学史」「女性史」などのテーマ史の定番から。 そして第12~23回は「政治史」を中心とする総復習とします。そこで、まずは総復習という場合は、最初に第12~23回を熟読してから第1回の「史学史」にとりかかってもかまいません。 第1・2回の「史学史」、第3・4回の「女性史」、第5・6回の「蝦夷地・北海道史」と「琉球・沖縄史」は単なる1テーマというより、日本史学習の基本的な単位です。 入試でも頻出のテーマですから、最低でも3回は熟読してください。 第1・2回の「史学史」は、未見史料問題を解く際の前提ともなる必須の知識です。 未見史料問題でその出展が示されている場合、その史料そのものが書かれた時代、編著者、その目的を知っていれば圧倒的に有利です。 第3・4回の「女性史」も必須のテーマ。各時代の女性の地位、その役割について問う入試問題も増えています。 第5回の「蝦夷地・北海道史」と第6回の「琉球・沖縄史」も古代から現代までしっかり学習しなければならないところです。 「教育史」もテーマ史の定番です。律令制の大学、平安時代の大学別曹から近世の藩校、そして現在の6・3制まで、名称の暗記とともにしっかり学習しましょう。 残るは、経済史分野で「貨幣史・金融史」。この分野は「嫌い」という人が多いですが、やっておけば確実に点を稼げますから、しっかり理解すること。特に、江戸時代の通貨制度と貨幣改鋳、近代の金本位制と通貨政策は重要なテーマです。 なお、各回冒頭には、その回の内容に即した「年表」を掲載しました。 また、入試で論述問題が出題される人向けに、随所に「論述対策」を入れてありますので、参考にして下さい。 直接論述問題対策を行っていない人にとっても、知識の整理に役立ちます。
-
3.0橘川武郎、高村ゆかり、瀬川浩司、平沼光、田辺新一、杉本康太、黒﨑美穂――。 第一人者が集結し、政策を大胆に見直す。 気候変動問題への対応、コロナ禍からの復興、地政学的なエネルギー安全保障への対応、そして、脱炭素経営の必要性など、様々な要素が複雑に絡み合い、我々はこれまでにない異次元のエネルギー危機に直面しています。国産エネルギーの積極活用、再生可能エネルギー政策の注目点、エネルギー高騰時代のクリーンエネルギー技術、住宅・建築分野での徹底した省エネ、投資家・金融家視点でのエネルギー政策など、各分野の第一人者が大胆な改革を提示します。
-
4.3○異次元金融緩和が導入されてから、4年たった。2018年には黒田総裁の任期も来る。いまこそ、総括と展望が必要な時だ。日銀は、2016年9月に、「総括的な検証」を行っているが、とても十分とは言えない。 ○異次元緩和は、日本経済のどこをどのように変えたのか? 基本的には、経済の基本を改善せず、国債市場を歪めただけの結果に終わった。日本銀行が意図したこと、意図の背後にある理論的な枠組みのどこに問題があったのか?そもそも目標や理論が間違っていたのではないか? ○このまま大量の国債購入が続くと、脱却はきわめて困難になる。なぜなら、金融市場の混乱などの問題解決がますます難しくなるからだ。また、仮に目標インフレ率が実現すると、日銀の財務上の問題、財政負担の増加などの問題が深刻になる。 ○いま必要なのは、インフレ目標の達成にこだわることなく、できる限り早く異常な政策から脱却することだ。その際に起こりうる経済と市場の混乱を最小限にとどめるために、何が必要かを早急に検討すべきだ、と著者は説く。
-
-米欧の中央銀行が9月以降、保有資産の圧縮に着手する動きを強める中、日本銀行は物価目標2%達成まで量的緩和政策を続ける。そのリスクを追う。本書は週刊エコノミスト2017年9月19日号で掲載された特集「異次元緩和の賞味期限」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに 量的緩和の限界迫る 買える国債がなくなる時 金融政策転換 日銀も米欧中銀に遅れるな 次の一手は引き締めか、緩和か 危機対応で課題残す日銀 マクロ政策の枠組み変更が必要 日銀は「総括的検証2・0」を示せ マイナス金利再来リスク 【国債】量的緩和の持続性に限界 金融システム安定性自ら損なう 【国債】基礎から学ぶQ&A 【為替】円安の効力失った金融政策 海外発の円高要因が迫る 【為替】基礎から学ぶQ&A 【資産バブル】成長率上回る住宅価格値上がり 緩和長期化すればバブル招く恐れ 【資産バブル】基礎から学ぶQ&A 【執筆者】 後藤 逸郎、花谷 美枝、鈴木 敏之、河野 龍太郎、早川 英男、愛宕 伸康、藤原 裕之、米倉 茂、竹中 正治、大槻 奈那、塚崎 公義
-
4.5●一貫して反対票を投じてきたその根拠 著者の木内氏は、2012年より日銀審議委員を務めてきた。当初は白川総裁のもと、「日銀は過度に金融緩和に慎重」と言われ、木内氏はむしろ積極派とみられていた。 しかし、翌年に黒田総裁に代わると、日銀は「超金融緩和」路線に向かうことに。その中で、積極派を自認していた著者も、相対的には「慎重派」へと変化することになった。 「少数意見を通すには常に自分で考え方やロジックを整理し、議論に臨まなければいけない。それが大変だった」と木内氏は述べているが、この本にはその論理が詰まっている。報道等で伝わっている考えはごく一部であり、この本は5年間の審議委員を全うした男のまさに集大成といえる。 ●副作用を上回る効果を最大化せよ 金融政策は難しい。財政政策のように「財源」などのコストがみえにくく、すぐに効果がみえないからである。それでも目先のことではなく、中長期的に、その効果と、特に「副作用」について考えなければならない。そういう意味では、「何が何でも2%の物価上昇目標」「大量の国債買い」は副作用が大きいと木内氏は言う。異次元緩和においてどのくらい効果を生んでいるかを示す物差しの一つが実質金利だが、14年で底入れしていて、追加的な策は意味をなしていないという。 では木内氏が描く出口戦略とは。(1)長期金利目標の廃止、(2)階層型当座預金制度を廃止したうえで付利金利を+0.1%に、(3)国債買い入れ増加ペースに目標を設定し、それを段階的に縮小。
-
3.0
-
3.8
-
4.0
-
3.0
-
-世界のマーケットを動かすイスラームパワー。 1970年代のオイルブームを契機に成長を続け、その後も原油価格の高騰を背景に、世界の金融市場で関心が高まっている「イスラーム金融」。 いまやイスラーム諸国の人口は約20億人、世界人口に占める割合が26%を占めるに至り、もはや「異端」として片づけられない存在となっている。 さらに近年では、金融の世界的サステナビリティやバブル抑制といった観点からも大きな注目を集めている。 その本質は、「イスラームの教義に従った」金融手法。たとえば、 「利子の授受の禁止」「投機的取引の禁止」「不確実な取引の禁止」「アルコールや豚肉の取引の禁止」など、西欧の伝統的な金融ルールとは大きく異なるスキームを持つ。 それゆえ、これまでわが国でもあまり理解されてこなかったと言える「イスラーム金融」。この独特の金融概念の要諦を、国際経済・金融・通貨などの諸問題に関する調査研究を行なう国際通貨研究所に集った各ジャンルのスペシャリストたちが、徹底解説する。 (底本 2024年2月発売作品)
-
-投資を行いたいと考える社会人の方は多いでしょう。本書では、忙しい社会人のために、金融商品の概略とポイント、そしてその金融商品で投資を行っていくためにはどうしたらいいかの勘所をコンパクトにまとめてみました。「預金」「国債」「株」「投資信託」「RIET」など、初心者でも手が出しやすい金融商品の仕組みと、投資のコツがわかります。忙しいからとこれまで投資に手を出せずにいた方にこそぜひ読んでもらいたい一冊です。
-
-※本書はリフロー型の電子書籍です。 【本当の自由を手に入れていない日本。戦後日本の復興は幻だったのか?】 はたして「日本の貧困化」はどこまで進んでいるのか──。 その実態を掘り下げていき、背景を探っていくと、底流にはひとつのファクト(事実)が見えてくる。 日本の貧困化をもたらしている主たる要因は、新型コロナウイルスやロシアのウクライナ侵攻だけではない。 ましてやGDP(国内総生産)で日本を抜いた中国でもない。 米国に従属してきた日本のスタンスこそが、「貧しい国ニッポン」を加速させているのだ。 取材するユーチューバーの異名も持つ経済ジャーナリスト・須田慎一郎が、政財界から大手行員、銀座のホステス、山谷の住民までを全方位的に取材。 いまある日本の現実と未来に警笛を鳴らす。 〈本書の主な内容〉 まだ本当の「自由」を手に入れていない日本 「コロナ」に「ウクライナ危機」、そして「インフレ」、「円安」などさまざまな出来事が日本を取り巻いている。 そのなかで、時には目に見える形で立ちはだかり、時には目に見えない力を働かせてくる存在に気づく──。「米国」だ。 だとするなら、少なくとも「米国」の動きを見ておけば、これから世界がどう動くのか、自分たちの生活がどう変わろうとしているのか。それも見えてくるはずだ。 それを見なければ、「一億総下流社会」は現実のものとなるかもしれない。 ■二極化のひずみ~極限まで進んだ日本の貧困格差 ■目の前にある日本の金融問題 ■金融とエネルギー問題は表裏一体 ■世界金融戦争勃発~知られざる金融制裁 ■日本の進むべき道 〈著者プロフィール〉 須田慎一郎(すだ・しんいちろう) 経済ジャーナリスト。1961年、東京生まれ。日本大学経済学部卒。経済紙の記者を経て、フリー・ジャーナリストに。『夕刊フジ』『週刊ポスト』『週刊新潮』などで執筆活動を続けるかたわら、テレビ朝日『ビートたけしのTVタックル』、読売テレビ『そこまで言って委員会NP』、DHCテレビ『真相深入り!虎ノ門ニュース』、文化放送『須田慎一郎のこんなことだった!! 誰にもわかる経済学』、YouTubeチャンネル『別冊!ニューソク通信』他、「取材するユーチューバー」としても多方面で活躍中。政界、官界、財界での豊富な人脈を基に、数々のスクープを連発している。また、平成19年から24年まで、内閣府、多重債務者対策本部有識者会議委員を務めた。主な著書に『下流喰い』(ちくま新書)『投信バブルは崩壊する』(ベスト新書)、『コロナ後の日本経済』(MdN新書)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新NISAスタートの今が始めどき! 「公的年金と貯蓄だけでは老後の生活が不安……」 「住宅資金、教育資金なども並行して準備できるか不安……」 「預金だけで大丈夫かな……」 そんな人は「新NISA」と「iDeCo」を利用してお得にお金を作りましょう! 新NISA&iDecoを活用すれば、 住宅資金400万円、教育資金800万円を引き出したとしても、 65歳時点で3800万円の貯蓄も夢ではありません! 新NISAつみたて投資枠とiDeCoは、 毎月コツコツと少額投資で資金を積み立てる制度。 投資で得た運用益は非課税になるなど、税制上の優遇措置も受けられます。 さらに、つみたて投資枠とiDeCoの特徴は「分散投資」と「長期継続」。 これにより、投資への不安「元本割れ」のリスクが減らせるので、 初心者にもおすすめの制度なのです。 2024年スタートの新NISAは、 投資金額・期間が拡大してますます使い勝手が良くなり、やらないのはもったいない! 本誌では、制度の解説はもちろん、金融機関選びや証券口座の開設方法、 商品選びや管理まで、具体的な資産形成の方法をわかりやすくレクチャー。 これを読めば、新NISA&iDecoを始められます!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人生100年時代が目前に迫る今、なにかと話題になるのが老後資金の問題です。「公的年金と貯蓄だけでは老後の生活が不安です」そんな人は国の税制優遇制度である「つみたてNISA」と「iDeCo」を利用してお得にお金を作っていきましょう!つみたてNISA&iDeCoは、毎月コツコツと少額投資で資金を積み立てる制度。投資で得た運用益は非課税になるなど、税制上の優遇措置も受けられます。さらにつみたてNISA&iDeCoの特徴は「分散投資」と「長期継続」。これにより投資への不安「元本割れ」のリスクは、減らせるので初心者にもおすすめなのです。では、つみたてNISAとiDeCo、実際に挑戦すると将来どんなこと待っているのでしょうか?25歳から投資信託(つみたてNISA&iDeCo)と定期預金、合計毎月4万円ずつ積立を開始したところ、40歳で1000万円、60歳で複利運用の効果で、3700万円まで増えるという結果に!さらに月2万円を積み立てたとして、「定期預金」と「つみたてNISA&iDeCo」を比較しても30年後には474万円もの差が出ました!本誌はそんなつみたてNISA&iDeCoの制度やメリットなどを優しく解説しています。見開きで1トピックずつ、右に解説文、左に図解というわかりやすい構成の誌面になっています。さらに金融機関選びや口座の開設方法、さらに投資する商品選びなど、わかりにくいつみたてNISA&iDeCoの始め方も手順を追って紹介。制度の理解から、実際に始めるところまで、しっかりレクチャーしていきます!「新型コロナの影響で景気が不安定な今、始めてもOK?」という疑問にも専門家が丁寧に解説してもらいました。基礎から始め方までがいちからわかるつみたてNISA&iDeCo入門書の決定版です!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人生100年時代が目前に迫る今、なにかと話題になるのが老後資金の問題です。「公的年金と貯蓄だけでは老後の生活が不安です……」そんな人は国の税制優遇制度である「つみたてNISA」と「iDeCo」を利用してお得にお金を作っていきましょう!つみたてNISA&iDeCoは、毎月コツコツと少額投資で資金を積み立てる制度。投資で得た運用益は非課税になるなど、税制上の優遇措置も受けられます。さらにつみたてNISA&iDeCoの特徴は「分散投資」と「長期継続」。これにより投資への不安「元本割れ」のリスクは、減らせるので初心者にもおすすめなのです。2022年はiDeCoの制度改正の年。加入可能年齢が65歳、受取可能年齢が75歳へと引き上げられるので、今まで投資期間の短さににネックがあった50代の人が、今からiDeCoを始めても、利益を出しながら老後資金を準備できます!では、つみたてNISAとiDeCo、実際に挑戦すると将来どんなことが待っているのでしょうか。25歳からコツコツと投資信託(つみたてNISA&iDeCo)と定期預金、合計毎月4万円ずつ積立を開始した場合、40歳で1000万円、60歳で複利運用の効果で、3700万円まで増えるという結果に!50歳から15年間、毎月2.3万円積み立てても、3%の利回りで522万円の老後資金と約80万円の節税効果(※)が得られます!※年収500万円の会社員の場合本誌はそんなつみたてNISA&iDeCoの制度やメリットなどを優しく解説しています。見開きで1トピックずつ、右に解説文、左に図解というわかりやすい構成の誌面になっています。さらに金融機関選びや証券口座の開設方法、さらに投資する商品選びなど、わかりにくいつみたてNISA&iDeCoの始め方も手順を追って紹介。制度の理解から、実際に始めるところまで、しっかりレクチャーしていきます!これからの時代、「投資の必要性」について専門家が丁寧に解説。さらに投資ブロガーに投資のコツと購入銘柄をインタビュー。実践に役立つ情報も満載です。基礎から始め方までがいちからわかるつみたてNISA&iDeCo入門書の決定版です!
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人生100年時代が目前に迫る今、なにかと話題になるのが老後資金の問題です。「公的年金と貯蓄だけでは老後の生活が不安です……」「住宅資金、教育資金なども平行して準備できるか不安です……」そんな人は国の税制優遇制度である「つみたてNISA」と「iDeCo」を利用してお得にお金を作っていきましょう!つみたてNISA&iDeCoは、毎月コツコツと少額投資で資金を積み立てる制度。投資で得た運用益は非課税になるなど、税制上の優遇措置も受けられます。さらにつみたてNISA&iDeCoの特徴は「分散投資」と「長期継続」。これにより投資への不安「元本割れ」のリスクは、減らせるので初心者にもおすすめなのです。では、つみたてNISAとiDeCo、実際に挑戦すると将来どんなことが待っているのでしょうか。コツコツと投資信託(つみたてNISA&iDeCo)と定期預金を毎月2~5万円ずつ積み立てた場合、住宅資金500万円、教育資金1000万円を引き出したとしても、60歳時点で、複利運用の効果で2100万円まで増えるという結果になります!さらに2024年からは新NISAがスタートし、投資金額・期間が拡大し、ますます使い勝手が良くなります。本誌では、新NISAにもいち早く対応した内容で資産形成の方法をレクチャーしています。本誌はそんなつみたてNISA&iDeCoの制度やメリットなどを優しく解説しています。見開きで1トピックずつ、右に解説文、左に図解というわかりやすい構成の誌面になっています。さらに金融機関選びや証券口座の開設方法、さらに投資する商品選びなど、わかりにくいつみたてNISA&iDeCoの始め方も手順を追って紹介。制度の理解から、実際に始めるところまで、しっかりレクチャーしていきます!基礎から始め方までがいちからわかるつみたてNISA&iDeCo入門書の決定版です!
-
-「ビットコイン」によって盛り上がりを見せた仮想通貨。 ビットコインに次ぐ時価総額を持つ仮想通貨「イーサリアム」の入門書が登場しました! 取引所でも取り扱いの多い第2の仮想通貨イーサリアムの知っておきたいコトをわかりやすくお伝えします。 イーサリアムって何? ビットコインとは何がちがうの? 投資はどう始めればいい? イーサリアムの特徴や値動きについて図解付きでわかりやすく解説。 さらに仮想通貨の基本的な投資方法についても紹介しています。 投資の基本は、投資先の価値を知ること。 なぜイーサリアムは人気があるのか? 今後の長期トレンドは? 何をしたら得して、何をすると損する? イーサリアムへの一歩をまずはココから踏み出しましょう! ■こんな方におすすめです ・仮想通貨取引をこれから始めようと考えている人 ・ビットコインの次の仮想通貨投資を検討している人 ・イーサリアムのことが気になっているけれど、よくわからない人 ・仮想通貨やFintechに興味があるけれど、まずは基本をつかんでおきたい人 ・金融機関に勤めていて、仮想通貨について知りたいものの、難しそうと感じている人 ・仮想通貨を使いこなすことでお得な経験をしたい人 ・FXや株式投資の経験はあるものの仮想通貨取引は未経験の人
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。
































































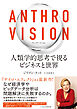

















![池上彰のやさしい経済学[令和新版] 2 ニュースがわかる](https://res.booklive.jp/1471685/001/thumbnail/S.jpg)