国民作品一覧
-
4.5消費税増税は是か、非か。 キーマンが続々証言、その舞台裏がいま明らかに! 国民に重い負担を強いる消費税増税はなぜ決まったのか? 現役朝日新聞記者が増税の舞台裏を解き明かす。 野田佳彦、谷垣禎一、菅直人、与謝野馨など鍵を握った多くの政治家のほか、 鈴木敏文、新浪剛史ら経済人の単独取材にも成功。 キーマンたちの真意に迫った1冊。 【目次より】※肩書きは2013年5月末 【目次より】※肩書きは2013年5月末 ■プロローグ:野田佳彦 前首相~傷はずいぶん負ったが、悔いはない ■第1章:迷走と変遷~変わりゆく増税の目的 ・飛び出した増税宣言[2010年6月17日] ・揺れた発言[2010年6月30日] 【証言】 菅直人 首相[当時]~性急だったな、との反省はある ・「一体改革」の名で包む[2010年12月10日] 【証言】 与謝野馨 社会保障・税一体改革担当相[当時] ・「5%」に当てはめる[2011年6月2日] ・隠した新年金の試算[2012年2月10日] 【証言】 野田毅 自民党税調会長 ■第2章:予行演習~大震災から三党合意へ ・大震災の一日[2011年3月11日] ・定まらぬ復興財源[2011年3月13日] ・ダブル増税へ[2011年4月7日] ・ぼかした増税の時期[2011年6月30日] ・二枚看板へ[2012年1月13日] 【証言】 岡田克也 副総理[当時] ・不揃いの決着[2012年6月15日] 【証言】 石井啓一 公明党政調会長 ・嵐の夜に「学級崩壊」[2012年6月19日] 【消費の現場から・経営者インタビュー】 鈴木敏文 セブン&アイ・ホールディングス会長~増税への手順、全く違っています 新浪剛史 ローソン社長~民の力信じ、経済浮揚、そして増税へ ■第3章:包囲網~追い風も向かい風 ・自公政権の宿題[2011年11月30日] ・経済界の同意[2012年1月5日] 【証言】 前原誠司 民主党政調会長[当時] ・友党の支え[2012年3月30日] ・「戦友」となった日銀総裁[2012年4月27日] ・「小沢切り」の帰結[2012年5月30日] 【証言】 斉藤鉄夫 公明党税調会長 ■第4章:二人三脚~財務省の存在 ・内輪に語った決意表明[2011年1月5日] 【証言】 藤井裕久 民主党税調会長[当時] ・「どじょう」の演説[2011年8月29日] ・心通じた二人の党首[2012年2月29日] 【証言】 安住淳 財務相[当時] ・消えた「再増税」の条文[2012年3月14日] 【証言】 額賀福志郎 元財務相 ・採決日和と「青い札」[2012年6月26日] ・主役交代[2012年8月10日] ■エピローグ:谷垣禎一 前自民党総裁~「税率10%」最初に公約に掲げたのは私 ■年表:消費税増税をめぐる動き
-
4.7
-
3.0「国民栄誉賞」で見る昭和芸能史。 美空ひばり、長谷川一夫、藤山一郎、渥美清、森繁久彌、森光子。昭和・平成の大スターにして国民栄誉賞を受賞した6人。彼らの足跡を辿り、大衆とスターが織りなしてきた芸能史を紡ぎだした意欲作。演出家としてスターたちと直に接してきた著者が、スターがふともらした言葉、仕事に向かう姿勢、演技を離れたときの素顔などを回想し、その芸の本質に迫ります。美空ひばりはなぜ「下品」といわれたのか? 長谷川一夫の「科学的」な演技。知られざる渥美清の素顔。「戦争をしくじった」――森繁久彌が生涯抱えた陰影。等々、同時代の雰囲気を克明に回顧することで、6人の「傑物」が芸能史において、いかなる存在であったかも浮かび上がらせます。
-
4.0未曾有の敗戦、そして占領という危機の時代に対峙したその<大いなる精神>とはいかなるものであったのだろうか? 占領という名の追撃戦――日本人の精神的武装解除に対しては孤独な抵抗を貫き、自らの<つとめ>として靖国神社御親拝、沖縄行幸を果たせなかったことを憂慮され続けた昭和天皇。「雨が続いているが、稲の方はどうか」。最期の病床にありがらも国民に呈する慈愛に満ちた大御心……。御誕生から軍部の独走、大東亜戦争へ、そして一転して復興・高度成長という激動の<昭和の御代>を辿りつつ、常に国民と共にあられた昭和天皇の足跡を明らかにしていく。
-
4.0現在、およそ2210万人の日本人が糖尿病を疑われているという。国民の6人に1人という結果である。がんは命にかかわる病気だけれど、糖尿病は大丈夫だろうと思っているとしたら、大きな誤解である。心筋梗塞や脳卒中など、命に関わる多くの合併症を併発し、網膜症や神経障害、腎症は三大合併症と呼ばれる。腎不全が悪化し透析に至るケースも増加している。また、末梢神経障害や閉塞性動脈硬化症が重症化すると、足の一部が腐る壊疽を起こす。さらに、透析などの医療費負担の急増にも警鐘を鳴らす。本書は、再生医療の専門医が、糖尿病の怖さをわかりやすく解説するとともに、治療に際しての問題点やマゴット(うじ)による最新治療法を紹介する。日本人は糖尿病にかかりやすい国民だという。理由は本文にゆずるとして、子供のころからの清涼飲料水がぶ飲みや栄養過多に注意喚起が必要だ。運動不足の中高年必読の書でもある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 司法修習生(しほうしゅうしゅうせい)……司法試験に合格し、法律実務を修習中の者たち。本書は、弁護士を目指す「茶髪にバスケットシューズの風雲児」若居武蔵、検事を志す「カリスマ弁護士を父にもつサラブレッド」朝倉小次郎、そして裁判長(もしくは玉の輿)になりたい「紅一点・萌え系美少女」大貫小町の3人が中心となって織りなす修習生物語である。そして、なおかつ人間ドラマを楽しんでいるうちに、いつのまにか日本の裁判の実態を理解できてしまう、裁判の入門書でもある。裁判員制度の是非や心構えについて考える前に、日本国民として絶対に知っておかなければならない「裁判に関する基礎知識」を網羅した。漫画の原作と補足解説には、リアル「カリスマ弁護士」荘司雅彦氏を起用。漫画家には、デビュー作『ねこ耳少女の量子論』が大ヒット中の松野時緒氏を起用した。司法修習生の目を通して、日本の裁判の「リアル」を知ろう!
-
4.0
-
4.0
-
3.0「それがしはもと信州上田の城主真田左衛門佐幸村と申す者。ここにあってお首を頂戴いたそうと待っており申した」家康は顔色を変えた。もっとも恐れていた幸村が出たのだ。無言のまま、馬に鞭をくれて逃げ出した。(本文より抜粋)いかなる劣勢にあろうと、神算鬼謀を尽くして数万もの軍勢を翻弄した真田家の智将たち。武田家の興亡から天下分け目の関ヶ原合戦、そして運命の大坂の陣へと続く「昌幸・幸村・大助」三代の活躍は、天下に覇を唱えた信長をはじめ、最終的に江戸幕府を開いた家康など、時の権力者に立ち向かう“国民的英雄”を望んだ民衆により、“華々しい伝説”へと昇華していく。江戸の元禄期以降に書かれ、猿飛佐助・霧隠才蔵・三好青海入道らの奇想天外な活躍で明治から大正期にかけて爆発的な人気を呼んだ「立川文庫」真田編の“種本”となる『真田三代記』が、土橋治重の名訳で現代に甦る! 2016年大河ドラマの世界を愉しむ一冊。
-
-シリーズ70万部突破の「人間学講話」第五集。。 歴代総理、財界重鎮が学んだ「歴史とは何か」 【著者紹介】 安岡正篤(やすおか・まさひろ) 1898(明治31)年、大阪市生まれ。 大阪府立四条畷中学、第一高等学校を経て、1922(大正11)年、東京帝国大学法学部政治学科卒業。東洋政治哲学・人物学を専攻。 同年秋に東洋思想研究所、1927(昭和2)年に(財)金鶏(けい)学院、1931(昭和6)年に日本農士学校を設立。 東洋思想の研究と人物の育成に従事。 戦後、1949(昭和24)年に師友会を設立。 広く国民各層の啓発・教化につとめ1983(昭和58)年12月鬼籍に入る。 【目次より】 ◆干支の意義 癸卯(昭和三十八年)/甲辰(昭和三十九年)/乙巳(昭和四十年)/ 丙午(昭和四十一年)/丁未(昭和四十二年)/戊申(昭和四十三年) 己酉(昭和四十四年)/庚戌(昭和四十五年)/辛亥(昭和四十六年)/壬子(昭和四十七年)/癸丑(昭和四十八年)/甲寅(昭和四十九年) 乙卯(昭和五十年)/丙辰(昭和五十一年)/丁巳(昭和五十二年)/戊午(昭和五十三年)/己未(昭和五十四年)/庚申(昭和五十五年) ◆干支の教訓――河西善三郎 辛酉(昭和五十六年)/壬戌(昭和五十七年)/癸亥(昭和五十八年)/甲子(昭和五十九年) 乙丑(昭和六十年)/丙寅(昭和六十一年)/丁卯(昭和六十二年)/戊辰(昭和六十三年) 己巳(平成元年)/ 庚午(平成二年)/辛未(平成三年)/壬申(平成四年) 癸酉(平成五年)/甲戌(平成六年)/乙亥(平成七年)/丙子(平成八年) ◆干支と安岡先生――山口勝朗
-
3.8シリーズ70万部突破の「人間学講話」第一集。 政財官界の指南役が記した「最高の教養書」が新装版で登場! 【著者紹介】 安岡正篤(やすおか・まさひろ) 1898(明治31)年、大阪市生まれ。 大阪府立四条畷中学、第一高等学校を経て、1922(大正11)年、東京帝国大学法学部政治学科卒業。東洋政治哲学・人物学を専攻。 同年秋に東洋思想研究所、1927(昭和2)年に(財)金〓(けい)学院、1931(昭和6)年に日本農士学校を設立。 東洋思想の研究と人物の育成に従事。 戦後、1949(昭和24)年に師友会を設立。 広く国民各層の啓発・教化につとめ1983(昭和58)年12月鬼籍に入る。 【目次より】 ◆組織盛衰の原理 □近代中国にみる興亡の原理 □明治・大正・昭和三代の盛衰 □兵書に学ぶリーダーの心得―孫子・呉子・六韜三略より ◆東洋思想と人間学 □「万世ノ為二太平ヲ開ク」―終戦の詔勅秘話 □人生の五計―人生観の学問 □見識と胆識 □人間学・人生学の書 ◆運命を創る □運命を創る―若朽老朽を防ぐ道 □次世代を作る人々のために □若さを失わずに大成する秘訣 ◆「気力」を養う養生訓 □敏忙人の身心摂養法 □憤怒と怒気
-
4.0宝島の地図を見つけた少年・ピートは、海へ冒険の旅に出た。戦後漫画界に彗星のごとく現れた幻の名作「新宝島」ついに文庫で登場! ほか、記念すべきデビュー作「マアチャンの日記帳」、貴重な著者によるエッセイ「ぼくのデビュー日記」も同時収録した手塚ファン必備の初期名作集!<手塚治虫漫画全集収録巻数>「新宝島」 MT281『新宝島』収録 /「マアチャンの日記帳」 MT129『マアチャンの日記帳』収録<初出掲載>『新宝島』1947年1月30日 育英出版発行 /『マァチャンの日記帳』1946年1月1日~3月31日 小国民新聞~毎日小学生新聞関西版連載
-
3.6列島を揺るがせた未曾有の震災と、終わりの見えない原発事故への不安。今、この国が立ち直れるか否かは、国民一人ひとりが、人間としてまっとうな物の考え方を取り戻せるかどうかにかかっている。アメリカに追従し、あてがい扶持の平和に甘えつづけた戦後六十五年余、今こそ「平和の毒」と「仮想と虚妄」から脱する時である――深い人間洞察を湛えた痛烈なる「遺書」。
-
-「私の属国理論は、これから先、日本人学者たちからの検証と反論にあっても簡単には滅びないだろう。それは、私が集めた諸事実が、諸外国(外側世界)では当たり前のように通用している諸事実だからである。私が書くことは、日本人にとっては初めて耳にするような驚くべきことが多い。人によっては、まったく聴くに耐えない厭なことばかりだろう。諸外国では高校生でも知っている事実が、日本国内では流通しないようになっている。長年、そのように意図的に日本国民を、外側世界の常識から隔絶し分離する政策が隠然と採用され、長年実行に移されて来たからである」……原本が発刊された2002年当時よりも、さらに深められた思考が、校正ゲラを真っ赤に塗りつぶしたかと思われるほどの大幅な加筆修正を経て表現され、生まれ変わった一冊となった。既読の読者も読み逃せない、気迫あふれる復刊。
-
3.8
-
-難病との壮絶な闘い小さな命を守るためママになりたい・・・ ハイリスク出産を越えて子を持つ親へ、親になろうとする人へおなかの中のちいさな命を守るために難病と闘った、女優・写真作家間下このみ。国民的人気の子役スターから母親へ。その“真実の物語”。2013年、NHKにてドラマ化決定!
-
3.0ゲームクリエイター・まだら牛と異才・手代木正太郎による最凶のエンターテインメント誕生。 〇あらすじ 我々に日本国の主権を譲渡せよ。 二十四時間以内に行わなければ、コトリバコの呪いを全日本国民に向けて解放する。 日本近代以降最悪の呪物と悪名高いコトリバコが、テロリストたちにより強奪された。 コトリバコ奪還のため、島根県沖の洋上に浮かぶ「八八式研究所」へ潜入する、特務部隊「異形厄災霊査課(イヤサカ)」 の隊員たち。 しかしこの事件の奥底には、想像を絶する怪異的陰謀が横たわっていた――。 これは、コトリバコを《新解釈》する物語。 ――そう。この箱は棺なのだ。ああ、憎んでいるのだな…… おまえは私を憎んでいるのだな……。
-
-10分で読めるシリーズとは、読書をしたいが忙しくて時間がない人のために、10分で読める範囲の文量で「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」を基本コンセプトに多くの個性あふれる作家様に執筆いただいたものです。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 まえがき 孫文(1866~1925)は中国において「中国近代資産階級革命先行者」と評される人物である。海外では「逸仙」の号、中国では「中山」の号で知られている。 医学の勉強をするなかで革命を志し、数回の蜂起失敗、亡命を繰り返した後、辛亥革命が起こり、1912年1月、中華民国が成立すると、臨時大総統に就任した。 その後、南北和議を受けて、大総統職を継いだ袁世凱が北京において独裁を強めていくと、南方において袁およびその後を継いだ北洋軍閥に対峙し続け、共和制の基礎、国民党による全国統一の基盤を築いていった。 孫文はどのような人物であったのだろうか。また具体的にはどのようなことをしたのだろうか。 本書では、(1)孫文の生涯、(2)革命指導者としての孫文、(3)孫文と日本との関係に分けて、簡単に解説してみたい。 本書は10分間で読めるようにシンプルにまとまっているので、気軽に読み始めていただきたい。
-
4.0ハイダル王国の若き女王ライラは、複雑な思いを抱えながら婚礼の準備に取りかかっていた。自らを犠牲にしてでも国民を幸せにすること――それが女王としてのつとめだと理解はしている。クセイ王国の国王ザヴィアンとの政略結婚は、十年も前から決められていたことだし、不満はない。でも……。婚礼が済み、ハネムーンでザヴィアンの人柄に触れ、ライラは思いがけず彼に強く惹かれている自分に驚いた。だが、彼の手首にある謎の傷跡を目にしたとたん、妙な胸騒ぎを覚えた。やはり彼には何か秘密があるのかしら?■こちらは昨年好評をいただいた〈ダイヤモンドの迷宮〉の続編です。今作はハーレクインコミックスでも今月同時発売となりますので、是非あわせてお楽しみください!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 今回の東日本大震災の自衛隊の活動記録を陸海空それぞれの自衛隊員自らが写真撮影をしていた。 その貴重な写真を使用することにより、新聞、雑誌などでは伝えきれない、仲間目線から見た現場での隊員の生の活躍ぶり苦労ぶりがリアルに伝わって来る、全国民に勇気を与えるメモリアルブックとなります。 震災発生後、救助、捜索、支援、トモダチ作戦、そして福島原発20km圏内での活動を未公開写真を中心に公開。
-
4.5「三省堂国語辞典」略して「三国(サンコク)」。 そして 「新明解国語辞典」略して「新明解」(赤瀬川原平著『新解さんの謎』でブームとなった辞書である)。 二冊ともに戦後、三省堂から刊行された辞書で、あわせて累計4000万部の知られざる国民的ベストセラーだ。 しかし、この辞書を作った(書いた)二人の人物のことは、ほとんど知られていない。 「三国」を書いたのが、ケンボー先生こと見坊豪紀(けんぼう・ひでとし)。 「新明解」を書いたのは、山田先生こと山田忠雄(やまだ・ただお)。 二人とも国語学者だが、「三国」と「新明解」の性格はまったく異なる。 「三国」が簡潔にして、「現代的」であるとすれば、「新明解」は独断とも思える語釈に満ち、 「規範的」。そこには二人の言語観・辞書が反映されている。 本書は、二人の国語学者がいかにして日本辞書史に屹立する二つの辞書を作り上げたかを 二人の生涯をたどりながら、追いかけたノンフィクション。 著者は同じテーマで「ケンボー先生と山田先生」(NHKBS)という番組を制作したディレクター。 同番組はATP賞最優秀賞、放送文化基金賞最優秀賞を受賞。番組には盛り込めなかった新事実や こぼれおちた興味深いエピソード、取材秘話なども含めて一冊の本にまとめた。 本書で日本エッセイスト・クラブ賞を受賞している。
-
-
-
-二〇一一年四月。日本で行き詰まった編集企画会社社長であるわたしは、自社の3D映像技術に投資してくれる投資家を求めて中国行脚を開始する。舞い込んだのは「もと国民党将軍」による「清朝の民族資産」からの「八〇〇〇億円の投資話」!?東京から重慶、上海、マカオに深セン。追い詰められて香港へ。煮ても焼いても食えない中国人投資家たちとの死闘の旅路。右も左も「アィヤー」な中国との仁義なき戦いが、いま、幕を開ける――。 「中国の人々がしばしば、思わず口にする言葉に「アィヤー」というのがある。突然起こった、自分にとってよくない出来事に驚き、がっかりする心情を表現する場合に、中国の人々が頻繁に使う言葉だ。わたしは、中国の「投資家」と称する奇妙な人々とドップリと付き合い、さんざん振り回され、そのあげく投資契約が実行されず、二三年間営んできた自分の会社を倒産させてしまった。それは、まったく、「アィヤー」なんていってられない深刻な出来事だった。」(本書「プロローグ」より抜粋)
-
4.0アベノミクス、エネルギー政策、国防対策―― 安倍政権を、叱り飛ばしたい。 政府が国民の給料から老後まで管理する―― いまの政治は、何かがおかしい。 現代の経済や社会保障、そして国防戦略の問題点を鋭く指摘。 田中角栄の最大のライバル経済の天才・福田が語る “日本再生の秘策”とは。 ■■ 福田赳夫の人物紹介 ■■ 1905~1995年。政治家。群馬県出身。東京帝国大学法学部を卒業後、大蔵省に入省し、主計局長を務めたのち、政界へ転身。自民党政調会長、幹事長を務めたほか、農林・大蔵・外務大臣等を歴任し、第67代首相となる。なお、学歴・外交・経済政策等、福田と対照的な立場だった田中角栄とは、長年、「角福戦争」と呼ばれる政争を繰り広げた。 目次 まえがき 1 田中角栄のライバル、福田赳夫を招霊する 2 「この霊言、安倍君に聴かせたい」 3 二〇一六年夏の参院選の「争点」は何か 4 安倍首相の「経済政策」をどう見るか 5 日本の「国防」をどう考えるか 6 日本の「エネルギー政策」をどう見るか 7 自民党は「もう終わった」? 8 今の日本の政治、何がおかしいのか 9 福田赳夫が考える「成長産業」とは 10 福田流「日本の富を増やす法」 11 日本は「アジアの警察官」となれ 12 福田赳夫の「過去世」とは? 13 福田赳夫元総理の霊言を終えて あとがき
-
1.0「日本国民に告ぐ…この女を犯せ!!!」平凡なOLだったはずの真美はとある事件をきっかけに"10億円の女"になった。彼女をヤれば10億円が手に入ると報道され、日本中の男たちの目の色が変わる!いつもは紳士な部長に押し倒され、見ず知らずの男たちの標的にされ、逃げ惑う真美。だが、性欲とカネに狂った男たちは容赦なく真美を追い詰めていく…。もうここまで、そう思った矢先に助けに現れたのはイケメンで評判の立花先輩!だけど…何か様子がおかしい?そして泣きじゃくる真美のビリビリに破られたストッキングの隙間から最低鬼畜野郎の欲棒がねじ込まれる!
-
-国民的ヒーローとなった男の凄絶な死 私を見て少し微笑んだように見えた次の瞬間、猪熊は「今ならできる!」という低い叫び声とともに机上の脇差を取り上げ一気に首に突き込んだ。(本文より) 2001年9月28日、東京オリンピック柔道重量級金メダリスト、猪熊功死す。自ら頸動脈をついて自害した壮絶な死の理由とは? その直前二週間、心身ともに最高の状態で死にたいという理由で行われた、美しき死のための合宿の詳細。「まだまだっ、切れてない」最後の瞬間を看取った合気道家、井上斌の証言で綴られる衝撃の真相。 プロローグ 夢 第一章 終わりへの始まり 1 始まり 2 自殺合宿 第二章 猪熊功という男の逆転人生 1 宿命を背負ったデビュー 2 対巨人との戦い 3 若者の考えを変える男 4 柔道新時代の茨の道を告げる大会 第三章 再起不能の病からの帰還 1 フィアンセヘの手紙 2 ヘーシンクという名の巨大黒船襲来 3 ウエイト・トレーニングでの復帰 第四章 美しき死への合宿 1 給料日 2 猪熊の食事 3 合宿二週目 4 傘 5 息子たちと 6 整理 第五章 人生の転換期、柔道から実業へ 1 生い立ち 2 大逆転の夢ならず 3 私(井上斌)と猪熊との出会い 第六章 再々度の延期 1 死に場所 2 時間が止まる 3 遺書のコピー 4 知人たちへの電話 5 時間つぶし 6 周到なドライブ 7 最後の役員会、最後のビール 第七章 哀しき経営者・猪熊功 1 孤独 2 東海建設と東海大学 3 事業拡大路線 4 大学との軋轢 5 中小の建設会社と銀行 6 経営破綻の償い 第八章 最期 1 決行のとき 2 まだまだっ エピローグ 光と陰 ●井上斌(いのうえ・たけし) 1946年中華民国北京市生まれ。1968年慶応大学法学部政治学科卒業。英国合気道協会主席師範を経て、1972年住友不動産入社。ハワイカントリークラブ、泉カントリー倶楽部、新宿住友ビル管理を経て、1987年退社。その後、1989年東海建設入社、社長室長、東海不動産管理常務取締役を経て、2001年東海建設破産により退職。現在株式会社エス・ユウ代表取締役。毎年1回、英国において合気道講習会を開催。師範を務める。 ●神山典士(こうやま・のりお) 1960年埼玉県生まれ。信州大学人文学部卒業。ノンフィクション作家。主な著書に、第3回小学館ノンフィクション賞優秀賞受賞作『ライオンの夢 コンデ・コマ=前田光世伝』(小学館)、『ひとりだちへの旅』(筑摩書房)、『「日本人」はどこにいる~異文化に生きる武士道のこころ』(メディア・ファクトリー)、『アウトロー』(情報センター出版局)など。
-
4.71994年10月8日、優勝をかけたシーズン最終戦。 長嶋監督が「もはや国民的行事」と語ったように、この一戦は、平均視聴率48.8%(プロ野球中継史上最高)。2010年に日本プロ野球機構が現役の監督、コーチ、選手を対象にしたアンケートで「最高の試合」部門1位だった。伝説として語り継がれる「世紀の決戦」を、今中、松井、立浪、桑田、大豊、斎藤……戦った男たちの証言でつづる。 長嶋監督は言う。 「野球のすべての面白さを凝縮した試合だった」
-
-この難事件・怪事件から「昭和」という激動の時代が見えてくる!二・二六、下山事件、三億円事件、ロッキード……国民を震撼させた重要事件の真相と時代背景に迫る本。
-
-
-
3.0日本の皇室と同様、ロイヤルファミリーの動向が国民の注目を集めるイギリス。第二次大戦後から玉座を守り続けてきた、現代史を体現する女王は何をし、何を見てきたのか? いま、王室から歴史の奔流を見つめ直す!!
-
-格差の進む日本。2012年の相対的貧困率は過去最悪を更新して16.1%と、国民の6人に1人が貧困状態。さらに子育て中の一人親世帯では54.6%にも達する。 特に厳しいのが母子家庭だが、若い女性の貧困も問題だ。 元AV女優・日経記者という異色の経歴を持つ著者が書く「セックスワーカーの貧困」、子どもの貧困に取り組む大人たちの取り組み、生活保護の実態など女子の貧困に迫った。 本誌は『週刊東洋経済』2015年4月11日号掲載の22ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 元AV女優・日経記者が歩く女性の貧困最前線 6世帯に1世帯が貧困。困窮する子育て家庭 column「2分の1成人式がえぐる心の傷」 住民の「おせっかい」が子どもを貧困から守る 生活費も家賃もカット。改悪続く生活保護制度 column「カード支給は違法? 揺れる大阪市」 はびこる生活保護への誤解 厚労省が物価を偽装? 揺らぐ保護費削減の根拠 国際比較で見た「生活保護」。日本の特徴は家族まかせ 自立支援法は機能するか Interview 私ならこうする! 慶応義塾大学教授 竹中平蔵/首都大学東京教授 阿部彩/ビッグイシュー日本代表 佐野章二
-
-世に「人権派」と呼ばれる人たちがいる。「人権」という言葉は今日ではヒューマニズムに満ちたという趣きも若干あってか、これに正面から異論を唱える人はそう多くない。しかし多くの人たちは、裏では「人権」にいかがわしさを感じている。何しろ「人権派」が顔を出すのは、死刑廃止論、犯罪加害者の権利、子供の権利、女性の権利、外国人の参政権、国旗・国歌反対、自衛隊違憲、戦争責任、従軍慰安婦、戦後賠償などといった問題が論じられるときであり、その主張の仕方も妙に戦闘的、エキセントリックであって、やはり「人権派」とは「特殊な人たち」だと思われてならないからである。本書は「人権派」の中でもとりわけ法律論を駆使して「人権」を振り回す「人権派弁護士」に焦点を当てて、そのいかがわしさを明らかにしたものである。ここには彼らの甘言に惑わされることなく、国民の常識を信じてほしいという著者の願いもこもっている。
-
3.6多くのエコノミストは、各種の経済指標から未来を予測する。その国のGDP、企業の業績、株価、財政状況などを見て、「ありそうな未来」を導き出す。投資家も、大方が同じようなことをしている。だが著者は、未来予測に関しては、その国の「人口」を見る。増えるのか、減るのか。そして次に、教育のレベルが高いかどうかを見る。それだけで、ほとんど確実な未来が描けるのだという。では、「アベノミクス」「2020年・東京オリンピック」で浮かれる日本の未来どうか。残念ながら、著者は悲観的な未来を描く。「老人の街でやる2020年東京五輪」「ものづくり国家・ニッポンの崩壊」「仕事を機械に奪われ、失業者が増える」「増税で締め上げられ監視される市民生活」……。30年以上のメディア生活で培った視点、情報網を駆使し、多くの日本国民が目を背けたい「現実」を提示しながら、今後のビジネス、投資、生活に役立つ「未来地図」を読者に届ける。
-
-これからの日本は、人口がどんどん減少し、大都市への集中が進み、地方は消滅する……という議論が、現在、巷では優勢である。安倍政権は、「地方創生」を改革の柱として据え、様々な政策案を出してきてはいるが、著者によれば、それらは所詮、経済政策に過ぎず、廃藩置県いらい140年以上も同じ区割りで続けられてきた地方行政の抜本的改革にはなっていない。どんどん国の状態が変わっていっている今、現在の地方行政のやり方は、まったく現状に合わなくなってしまったのである。これを変えてゆくための一私案として、本書では、地域主権型の「日本型州構想」を提案する。地域と地域の間に競争関係を復活させ、かつまた、国全体を元気にしてゆくために、思い切った改革が一刻も早く行われなければならない。日本国民の行くべき道の一つのモデルを示した、地方行政・自治論の第一人者による、渾身の一冊である。
-
3.3「天声」にはパブリックなイメージがあり、ある種の客観をよそおっている。それに対して「人声」はプライベートであり、あくまで個人的な声。だから「人声天語」とは、要するに、反射神経による思考(発言)のことである。 2003(平成15)年から、2008(平成20)年にかけて起きた様々な事象の、おかしさ、うさんくささ、不思議さを、紋切り型ではない「人声」でとらえた世相コラム集。 収録された主な出来事は―― ネット心中/自衛隊イラク派遣議論/「週刊文春」出版差し止め問題/イラク日本人人質事件/国民年金未払い問題/佐世保小六女子殺人事件/ギリシア五輪/プロ野球リーグ再編問題/靖国問題/ライブドア事件/秋田小学生殺害事件/昭和天皇「富田メモ」報道/ハンカチ王子ブーム/朝青龍問題/安倍総理辞任/時津風部屋暴行死事件/「大阪名物くいだおれ」閉店/秋葉原通り魔事件/地下鉄副都心線開通 など
-
4.0昭和36年7月――。敗戦から立ち直り、戦後日本が復興から高度経済成長に進むなかで国民生活は安定し、将来に対する明るい希望や意欲が湧いてきた時代であった。しかし東西冷戦のイデオロギーや戦後民主主義など、思想や教育の混乱により、日本人の誇りや美徳、伝統的価値感は喪失されていく。当時の若者たちにとっては確固たる人生の目標を見失い、決して明るいばかりの世相ではなかった。本書は、東洋学の泰斗として数多くの敬仰者を集めた著者が、前途有為の若者たちに3泊4日の研修会で東洋思想の真髄を直接語りかけた珠玉の講録。「現代文明の堕落」「人生と機」「命は我より作す」「富貴と貧賤」「素行と自得」「日本人の反素的傾向」「人間と環境」「艱難に素しては」「運命と宿命の違いとは」「無心ということ」など、流動の世を生き抜く叡智を学ぶ人生指針の書。我が命はどういうものであるか――。本当に知るとは、創造することなのである。
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 腎臓病と診断されてから病気について必要な知識をわかりやすく伝える。検査と診断、最新の治療まで早期発見、早期治療のための本 腎臓病と診断されてから病気について必要な知識をわかりやすく伝える、腎臓病と診断されてはじめて読む本。 日本では患者が約1,330万人(20歳以上の成人の8人に1人)いると考えられ、新たな国民病ともいわれる慢性腎臓病(CKD)。 腎臓病のなかで患者数がもっとも多い病気です。 慢性腎臓病(chronic kidney disease=CKD)は慢性に経過するすべての腎臓病をさします。CKDの原因は生活習慣病(糖尿病、高血圧など)や慢性腎炎が代表的でメタボリックシンドロームとの関連も深く、誰もがかかる可能性のある病気です。 慢性腎臓病が怖いのは、腎機能が3分の1程度まで低下しないと、自覚症状がほとんどないことです。腎臓学の進歩に伴い早期発見、早期治療が可能になったとはいえ、透析導入になる人も数多く存在します。病気が進んで透析にならないようにするためには、食事療法や運動療法といった生活習慣の改善が欠かせません。必要に応じて薬物療法も併用します。 本書では、専門医が、なぜ腎臓病になるのか、原因や経過、検査と診断、最新の治療までをわかりやすく解説します。体のサインを見逃さず治療に向き合いましょう。 【腎臓病の主な種類】 ●急性腎炎症候群・慢性腎炎症候群 ●急速進行性腎炎症候群 ●ネフローゼ症候群 ●IgA腎症 ●糖尿病性腎症 ●糖尿病性腎臓病 ●肥満関連腎臓病 ●腎不全 ●腎硬化症 ●尿細管間質性腎炎 ●痛風腎と遊走腎 ●尿路感染症 ●腎腫瘍 ●水腎症 ●遺伝性腎疾患 川村 哲也(カワムラテツヤ):虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー健康相談クリニック院長。1979年東京慈恵会医科大学卒業。1988~1991年 アメリカバンダービルト大学小児腎臓科へ留学。2001年東京慈恵会医科大学准教授および附属第三病院腎臓・高血圧内科診療部長。2013年より東京慈恵会医科大学教授。2014年より同大学附属病院臨床研修センター センター長。2020年4月より同大学客員教授。2022年9月より現職。 医学博士。腎臓病の臨床と研究にたずさわるほか、患者のための腎臓病、高血圧に関する知識の啓発に努めている。 湯浅 愛(ユアサアイ):慈恵会医科大学附属柏病院栄養部課長。管理栄養士。1994年、東京慈恵会医科大学附属病院栄養部に入職。腎臓病、糖尿病を中心に、医師と連携したチーム医療活動を行い、患者が実践できるわかりやすい食事療法をめざして活動の場を広げている。
-
-「防ぎたい」「治りたい」「元気で長生きしたい」をかなえます! 日本屈指の名医が教える「健康に生きる」シリーズ、第7弾! (1)重篤な症状にならないための予防法がわかる! (2)たとえ発症しても、あわてず対応できる! (3)あなたの人生が、より意義深いものになる! いまや国民病といってもよいほど急増している慢性腎臓病。 にもかかわらず、世間的によく理解されていないのが実状です。 腎不全にならないよう、腎臓機能を保つには、どうすればいいのか。 最新の透析事情を含め、わかりやすく解説しました。 (著者からのメッセージ) 今、腎臓の機能が健康時の50%だとしたら、何もしなければ、どんどん低下していき、早晩ゼロになります。 しかし、腎臓の機能が50%の段階で治療を始めれば、 その働きを60%に上げることはできませんが、50%を維持し続けることはできます。 腎臓病では、現状維持こそが最大の目標なのです。(本書「プロローグ」より) *目次より ◎腎臓が止まると体の中がゴミだらけになる ◎「急性」と「慢性」の大きな違い ◎透析は「あってよかった」治療法 ◎腎機能を見るには「GFR」を見る ◎過去の健康診断結果は貴重な財産 ◎糖尿病患者の3人に1人が腎臓病に ◎「スイカは腎臓にいい」は大間違い ◎透析を始めるベストタイミングを知る ◎血液透析が合う人、腹膜透析が合う人 etc.
-
4.0明治維新の躍進から日清・日露戦争の勝利を経て、なぜ日本は「敗れる戦争」へと突き進んだのか? 政治の迷走、軍部の独走に翻弄され、なぜ日本の国策は「一元化」できなかったのか?本書は“近代未満の存在”に終わった「日本陸海軍のキーパーソン」25人の理想と挫折をたどり、戦前日本の“失敗の本質”を読み解く――。「文官」と「武官」で教養知識が分断され、総合的な「発想力」が欠如したままの国家戦略。国民の統制は必要不可欠と考え、他者の「自由・独立」を理解できなかった帝国陸軍の「統制派」たち。金科玉条の「対米艦隊決戦」に引きずられ、なぜ文民が軍縮条約を決めるのかと強硬に反対した帝国海軍の「艦隊派」たちなど、最優秀の人材を集めながら、戦前の日本が敗れた理由が見えてくる。今も変わらぬ日本の「パワー・エリート」の限界と陥穽を鋭く衝いた一冊。
-
3.6危うし、年金財政。130兆円の運用資産改革はアベノミクスの救世主にはならない。 2014年4月までGPIFの運用委員を務めていた著者が、知られざる世界最大の機関投資家の全容と、 あるべきGPIF改革について説く、緊急提言の書。 安倍政権が株価引き上げのネタとしてGPIF改革を利用したかどうかは議論しません。そんなことはどうでもいいのです。大事なことは、GPIFというものの存在を、国民が突然意識したのですが、それが何かもどのようなものかもまったく知らない。そして、政権はそのGPIFを大きく変えようとしている。しかも、まさにいますぐに、です。これは危険です。私は4月22日までGPIFの運用委員というものをやっていました。運用委員を運良く退任して、ある分野の守秘義務は依然あるものの、自由に記述できる立場にある私が、いまできることは、GPIFの理解を少しでも幅広く多くの人と共有することだと思うのです。したがって、理解が浅く、誤りもあるかもしれませんが、とにもかくにも、全力でこの本を緊急出版することにしたのです。 (「まえがき」より抜粋) 【主な内容】 第1章 GPIFとは何か 第2章 年金制度とGPIF 第3章 GPIFという組織 第4章 GPIFの運用方針と目標運用利回り 第5章 年金制度と資産市場の断絶 第6章 公的年金のくびき 第7章 国債と分散投資 第8章 低金利革命 第9章 国民によるわな 第10章 GPIFは必要か? 第11章 GPIFのガバナンス改革 第12章 透明性と説明責任 第13章 GPIFの運用とガバナンス 第14章 GPIFは良い運用者か? 第15章 意外と素晴らしい国債とそのリスク 第16章 あるべきポートフォリオ:日本株は買うな 第17章 リスクとは何か 第18章 GPIF改革私案
-
3.6スウェーデンは社会保障が進み男女平等が徹底された福祉国家であると讃美するのも、税金が高く社会主義的な国であると批判するのも、一面しか捉えていない。「伝統的な家族」は崩壊してしまっており、母子家庭・父子家庭や片親の違う兄弟も普通のことだ。ボルボやサーブが破綻しても政府は救済しないなど、米国以上に市場原理主義的な国でもある。その特異な社会・経済を理解するためには、国家を支える理念と、それが生まれた背景を知る必要がある。戦後の高度成長期に必要とされた「国民の家」の理念は、H&Mやイケアの企業戦略、年金制度改革などに、どう実践されているのか。スウェーデンは福祉を経済成長にもつなげている。しかし、それを表面的に真似ても、うまくはいかない。この国から学ぶべきは、個々の政策ではなく、政治・制度に対する国民の信頼という無形の社会資本を形成し、担保するしくみだ。日本がとるべき道を示唆する
-
-粕谷甲一神父の講話からのシリーズ、2冊目のタイトルは「救われるのは誰か」です。ドイツの神学者カール・ラーナーに師事し、青年海外協力隊や海外で働いた経験から、日本での宣教活動への思いをつづっています。最初の講話は、国民的スター水戸黄門にまつわるお話から始まります。黄門さまが悪代官に向かって言う「おまえたちはお天とうさまが見ていたことを知らないのか」ということばから始まります。アッシジの聖フランシスコや、さだまさしさんの「風に立つライオン」などを取り上げながら、身近なことから、日本人が求めている宗教性の深い部分へと入っていきます。
-
-夜間に熟睡できないため、日中眠い。不眠症の悩みは、思わぬ事故やケガにつながります。国民の1%に見られる睡眠時無呼吸症候群の治療や、快適睡眠のためのあの手この手など、あなたを心地よい睡眠に導くガイドブック。イビキ、睡眠中の無呼吸、日中の眠けに悩む人は必読!
-
3.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 怪しい―――――。 でも気になる。 今年初詣をした人は国民の約8割に該当する1億人(重複含む)。携帯占いサイト市場約200億円、ヨガ市場約1600億円。“精神世界”から優しく明るい“スピリチュアル”へとコンセプトをチェンジし、効率的に癒す時代に対応することによって、「スピリチュアル市場」失敗の回避を目標とする若者世代に浸透、急拡大しつつあるように見える。 謎に包まれてきた、怪しいが、でも気になるスピリチュアル市場。その市場に現代人はどれだけの金額を投じているのか。客観的調査に基づいた調査結果を軸に、スピリチュアル市場における有望カテゴリーや今後の市場のゆくえを探る。 誰も語らなかった巨大市場の真相がこの一冊から明らかになる。
-
3.6私たちは本当に「自由が苦手」なのか? 新聞、雑誌、テレビのスポーツ報道は「オヤジ」である。少しセクハラっぽくて、組織を重視。感極まると熱く人生訓を語り始める。それだけではない、彼は周りにいる人たちを〈日本人〉に取り込もうと一生懸命である。スポーツ報道が発するメッセージを丹念に解きほぐし、新たな視点を提示する本。 第1章 本当はこんなに恐いスポーツニュース 第2章 女子選手に向けるオヤジな目線 第3章 スポーツニュースは“人間関係”に細かい 第4章 スポーツニュースは“国”をつくる 第5章 日本人メジャーリーガーが背負わされる“物語” 第6章 世界中で刷り込まれる“国民” 第7章 ワールドカップでつくられた“日本人” 第8章 イビチャ・オシムはなぜ怒ったか―むすびにかえて
-
-記憶を失った私立探偵は病院を抜け出し、自らの足取りを追って調査を開始した 元興信所の冴えない調査員だった相葉潔は女とカネでしくじり、ささやかな探偵事務所を開き細々と生計を立てていた。タフでなければ、残金六百八十円で生きていけない、優しくなければ誰も金を貸してくれない…。しかし、彼はある夜、何者かの襲撃をうけて一時的な記憶喪失(逆行性健忘)に陥る。 「おれが請けた依頼は何だったんだ? 誰と会っていたんだ?」 相葉は彼の担当医となった型破りな美人女医・木村瑤子の協力を得ながら、欲にまみれた“怪事件”の核心へ一歩一歩近づいて行く…。 ●杉元伶一(すぎもと・れいいち) 1963年、埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部中退。大学在学中に『東京不動産キッズ』で小説現代新人賞を受賞。現代を鋭く切りとる才筆で文壇の注目を浴びる。著書に、映画化された『就職戦線異状なし』『スリープ・ウォーカー』(講談社)などの他、漫画原作として『国民クイズ』(太田出版)がある。
-
-
-
-人生とは心の中に道しるべを建てる旅であり、 美しい愛の花を咲かせる旅である。 国民詩人・坂村真民が遺した幻の随筆集・三部作。四半世紀の時を越え、新装版として、ここに完結。 生きることのかなわなかった亡き長女への想い、尊敬してやまない一遍上人の生き様、自身を形成するバックボーンなど。 これまで以上に内面に踏み込んだ話の数々は、多くの人や教えに触れながら流れてゆく著者の人生を、ときに悲しく、ときに美しく描き出す。 *目次より ● もっとも美しかった母 ● お地蔵さまとわたし ● 旅終い ● はまゆうの花 ● つゆくさのつゆが光る時 ● 印度の石 ● 足の人 ● 生きている一遍 ● こんにち、ただいまに立つ人
-
5.0詩作に人生をささげた国民詩人・坂村真民による、 出会いと別れがおりなす人生の悲喜。 国民詩人・坂村真民が遺した渾身の随筆集・三部作。 その第二弾が、装いも新たに復活(旧版『生きてゆく力がなくなる時』)。 今なお私たちを感動させ続ける数々の詩には、 人と人が出会うことの喜び、そしていつかは来る別れへの悲しみが満ちていた。 誰よりも詩のために生き、誰よりも詩の力を信じた著者が「めぐりあい」の美しさを情感豊かに描く。 【本文より】 ――すべて結び合うものが縁なのである。そしてそれは人間だけの世界のものではなくて、木にめぐりあうのも、草にめぐりあうのも、まことに不思議な縁によるものである。――
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「失われた20年」以降の「財政問題」にまつわる 素朴な疑問から最新情報まで 財政とは「数字に凝縮された国民の運命」であり、財政への無関心のツケや負担は最終的に国民に戻ってきます。日本の財政はもともと、右肩上がり経済を前提としていた制度でしたが、「失われた20年」以降には様々な制度の行き詰まりが顕著となっています。 本書は、財政問題にまつわる素朴な疑問から最新情報まで、鳥瞰図的に全体像を理解するための羅針盤の役割を果たす入門書です。 グローバル化を急速に進める金融問題と巨額債務を抱える財政問題の一体化、情報化社会の進展、少子高齢化などによる経済社会構造の変化などはどのように日本の財政問題に影響を及ぼしているのでしょうか? 世代や業種を超えて、素朴な議論から最新知識まで、財政危機の本質と問題点までいっきにわかる入門解説書
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1998年に初版を発行した『図解 年金のしくみ』の第6回目の全面改訂版です。かつて年金は現役世代の人にとっては将来の退職後のことなので、あまり関心が向かなかった方も少なくなかったのではないでしょうか。しかしながら、日本社会の少子高齢化の進行が社会問題となるのに伴い、特に団塊の世代が65歳を迎え年金受給者が増加する一方で、年金制度を支える現役世代が減少していることから、年金制度は持続可能か、将来の年金額は大幅に減額されるのではないか、などの年金制度に対する不安が高まっています。 先述の関心が向かなかった方の中には、理解しようとすると、年金制度の種類が多くて、それぞれのしくみをすべて理解するのはやさしくない、また、何が年金制度の具体的な問題点で、それに対してどのような対策がとられているのか、今後どのような改革が進められるのか、などの全容を把握するのも簡単ではない、といったことが理由でその時期になったら考えようと思っていた方もいるのはないでしょうか。現在、国民の年金制度に対する不安が払拭されない状況も、国がそれらを払拭できるような年金改革が実施できていないという見方もできますが、年金制度・しくみや問題点を理解するのが容易でないということも影響していると思われます。 本書はこうした事情を踏まえ、各年金制度の基本的なしくみや、年金の数理・財政・資産運用のしくみ、年金改革の動向や将来の課題などを40テーマに絞り、図表を多用し、やさしく解説することに努めています。また、客観的な資料をもとに作成し、注目度の高いキーワードを取り上げていることも特徴です。 【主な内容】 はじめに 第1章 年金制度のあらまし 第2章 年金制度のしくみ 第3章 年金運用のしくみ 第4章 年金制度の改革 第5章 年金制度の課題と将来像
-
4.3「このままでは、日本は財政破綻してしまう」「TPPに参加しなければ、日本経済は復活できない」本当にそうなのでしょうか?世の中には、「経済に関する間違った情報が蔓延している」と著者は指摘しています。その原因の代表的なものは以下の3つです。1、用語の定義付けが曖昧で、かつ数値データに基づいていないこと2、国民経済に対する理解が不十分であること3、マクロ経済的視点にミクロ的な視点を取り入れるなど、議論の仕方が間違っていること本書は、マスコミが喧伝する「不要な危機感」「過剰な不安感」に惑わされることなく、日本経済の本質を理解するための一冊です。そのため、まずは前半部分のPART1・2で、「景気とは何か」「GDPとは何か」「国債とは何か」「円高の正体」「ユーロ危機の本質」などの経済の基礎を解説。続けて、PART3・4で「復興プラン」「TPP」について具体的に論じています。
-
-「これだ!」と思える素敵な生き方、考え方を、生活に組み込んで習慣とし、ついでに、いやなクセを解消することができたら、それこそが、生活の質(Quality of Life=クオーリティ・オブ・ライフ)の向上。それを、実行し持続するためのヒントを、ふんだんに提供してくれるのがこの本です。今の自分にピッタリと合うプランを、この本の中に見つけて、すぐに取り組んでみましょう。生活に、明るさと落ち着きが戻ってきます。原書が刊行された1929年と言えば、二つの世界大戦のはざま。しかも、経済恐慌のあらしの中とあって、欧米の人々は、群れの中に逃げ込んで自己を失っていました。先の見通しのつかない、不安に満ちた日々。そこへ出現した本書は、爆発的に広まり、アメリカでは、年間を通してベストセラーの一位を維持しました。二十世紀のアメリカを代表する哲学者・教育学者のジョン・デューイは、本書を「思考のための必需品」と認める小論を書き、さらに推薦文(「訳者のまえがき」に訳文を収録)を書いて本書を推奨しました。いまの人々に必要な、精神の自立と予見の力を教えるのはこの本だ、と確信したのです。本書が興味ぶかく語る、欧米各国の教育事情や国民性の比較は、七十年後の今も、なまなましい現実感を失っていません。世界が、またも、重苦しい雲に被われている今、われわれは、この本を通して過去を思い起こし、それに重ねて現在を考える必要があります。そこで、訳者は、ディムネの心をくみながら、現代日本人を、ディムネ風に考察する三章を書いて巻末に添えています。
-
3.6
-
5.0国民にウソを言わない政治を。 その死から15年―――はじめて消費税を導入した昭和最後の総理は、消費税10%に踏み切ろうとする いまの政治に何を伝えたいのか。 消費税導入後、財政赤字は10倍増! 反省や国民に説明もないまま増税するのは間違い マイナンバー制に潜む危険性とは 民主主義政治の危機と軍事大国化への懸念 なぜマスコミも消費増税を煽るのか? すでに国家権力の一部に!? 軽減税率の密約とは!? いまやDAIGOの祖父として有名な昭和の最後の総理・竹下登。1989年、100兆円の財政赤字を解消するため、初めて消費税を導入したことで知られる。その後、再三の増税にもかかわらず、財政赤字が1000兆円に膨らんだ日本を、どう評価するのか。「気配りの人」だった現職時代とは違い、本書では、安倍政権の危うさを鋭く指摘。増税はもちろん、国家権力の一部となったマスコミ、マイナンバー制の弊害を訴える。国を案じる元総理の本心に、一人でも多くの人に耳を傾けてほしい。 ■■ 竹下登の人物紹介 ■■ 1924~2000年。政治家。島根県出身。早稲田大学商学部卒。郷里の中学校で英語の代用教員をしながら青年団活動に打ち込み、1951年に政界進出。島根県議会議員を二期務め、58年、衆議院議員選挙で初当選。自民党代議士として、内閣官房長官、建設大臣、大蔵大臣等を歴任。党内では主に田中派に所属、後に「経世会」(竹下派)を旗揚げし、最大派閥を形成。87年、第74代内閣総理大臣に就任。ふるさと創生事業や消費税導入等を行うも、リクルート事件で引責辞任した。
-
3.4「自分で決めて選んだ」と実感できれば政治は必ず面白くなる――そう信じる著者が、社会学と政治学の垣根を超え、社会科学者として政治を俯瞰。民主主義の本質と日本型政治の問題を軽快に論じ、独自の改革案を提言する。「原理編」では、ギリシャ・ユダヤ教・キリスト教・儒教などの政治と思想を通して民主主義とはどういうものかを説く。「現実編」では、古代から続く全員一致・連帯責任のムラ原理、明治以来自分たちのものと実感できない憲法、国民に一つの選択肢しか与えなかった戦後政治、質の高い民主主義とはほど遠い現在の選挙制度……日本の政治とは何かを問う。「改革編」では、有権者が政治にリアリズムを感じるための独自の改革案――「党員チケット制」、「次点歳費制」、政治リーダーを養成する学校の創設――を提言。そして有権者が質の高い意思決定をするために情報公開の必要性を訴える。日本の政治をなんとかしたい、そんな市民のための待望の教科書。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2005年9月の総選挙に見る小泉首相の大勝利は、「郵政民営化」を掲げた巧みなメディア戦略によってであろう。そこには、本格的なマニフェスト選挙と期待されながら、不発に終わった感がぬぐいきれない。政治メディアの効果を測るものとして、従来よりいわれる「有権者への争点認知」「評価形成への影響」に「熟慮誘発機能」を加え、国民の知る権利に奉仕するマス・メディアの仕事の理論と実態に迫る。/序章:メディア効果研究の現代的課題 1章:争点を学習したいと思わない世論 2章:効果研究は受け手の何を測定してきたか 3章:マス・メディアの熟慮誘発機能をどう捉えるか 4章:質的議題設定機能としての熟慮誘発効果 5章:熟慮誘発機能の測定調査─原子力発電是非をテーマにして 終章:「認知させ説得するメディアから」から「問いかけるメディア」力の測定へ
-
4.3拡大することを前提につくられてきた近代社会が拡大しない時代に入った21世紀、国家と国民の関係はどうなっていくのか。排外主義や格差の広がりで新たな局面をみせるナショナリズムから考察する。
-
3.0アベノミクスに期待と不安を感じながらも株高・円安で一息ついている日本に対し、逆に不安だらけで日本を見つめている国が韓国だ。 安倍晋三、朴槿恵政権ともに、発足前後から続く外交的対立が経済面でも生じている。「アベノミクスは失敗する」と韓国メディアや有識者が批判すれば、日本も「韓国経済が危ういから日本を批判している」との舌戦が、半年以上続いている。では、そんなに韓国経済は悪いのか。 よく見ると、公約として掲げたが故の財閥規制と、経済成長の主役である企業をどう生かすかで苦心する朴政権の姿が見えてくる。円安が急速に進んだため、対応に手間取る韓国企業や国民の胸の内も垣間見える。 一方で、日本企業の韓国への直接投資がこの数年で急増し、韓国市場は日本企業にとって有望という現実も浮上。韓国がこの半世紀に受け入れた海外投資累計額で日本は2位。それだけ日韓の経済関係は成熟しているのだ。批判ばかりでこの関係を壊してしまうのか。今こそ、冷静に隣国との関係を見つめるときだ。
-
4.0
-
-著者のエハン・デラヴィは、古代文明、地球外生命体、パワーとフォースといった意識や気、宇宙の法則や天変地異、さらには世界を操る闇の勢力や陰謀論まで造詣がある「知の巨人」。そんな彼が自分の半生を振り返りつつ書いた、日本人へのメッセージ本。 高校卒業後、「本当のスピリチュアリティ」を求めて放浪の旅に出たスコットランドの青年。時代はちょうどヒッピー全盛期で「フリーダム」と「ピース」が叫ばれていた。ヨーロッパ、中東、インドと着の身着のままで旅する彼が最後にたどり着いたのが日本だった。鈴木大拙の禅に憧れてほぼ無一文で来日し、ヒッチハイクで京都を訪れた彼はそこで日本文化に触れ、日本文化に惹かれ、そのまま日本で生活することになる。外人(ソトヒト)である彼は日本で何を見て、何を学んだのか。外人だからこそわかる日本のよさ、そして改善すべき点。日本を愛するがゆえに語る真摯な言葉には耳を傾けるべきことが多い。「本当のスピリチュアリティ」を求めていた彼は、日本人は非常にスピリチュアルな心を持つ国民だと言う。しかし日本人はそのことに気づかず、答えを外に求めてばかりだと。スピリチュアリティを求められる現代における日本人の使命とは? 現代に生きる日本人必読の書。
-
4.0今こそ「メザシの土光さん」の言葉に耳を傾けよう――。東芝社長、経団連会長を歴任し、第二次臨調会長として国家再建に命を懸けた男、土光敏夫。当時、つつましい食卓風景が紹介され「メザシの土光さん」と国民的人気を呼びました。「サラブレッドより野ネズミの方が強い」「個人は質素に、社会は豊かに」「ぜいたくは嫌いだ」「社員は3倍、重役は10倍働け」「蛍光灯は半分消せ」。日本が復興に向けて一歩足を踏み出し始めた今だからこそ、土光さんの数々の至言がより輝きを帯びて私たちの胸に迫ってきます。
-
-1,019円 (税込)自分につながる話として歴史を学ぼう!(齋藤武夫) 日本文化の何がすごいか(齋藤武夫) 縄文時代って実はスゴい!(飯島利一) すべて朝鮮半島から伝わったのか?~稲作と前方後円墳(服部剛) 矮小化された弥生時代 (服部剛) 日本の古墳は、どれだけすごいのか (土井郁磨) 渡来人?帰化人?どう違うの? (土井郁磨) 大化の改新はクーデターなのか (服部剛) 消された聖徳太子 (伊勢雅臣) 白村江の戦いと大伴部博麻 (土井郁磨) 尊皇という智恵 (服部剛) 日本の統治は世界に類をみない (久野潤) 特別講義 神話の世界へようこそ (浅野温子) 律令制度は中国の物まねか (服部剛) 貧農と民衆の視点を依然強調 (服部剛) 京都御所が物語ること (相澤正久) 政略話ばかりで悪辣に描かれる (久野潤) 元寇は国難だったんです!(入川智紀) 義満は厚遇、楠木正成は冷遇 (久野潤) 「下剋上」=「何でもアリ」か(服部剛) 信長は傍若無人だったのか (久野潤) 支配者目線の「検地」「刀狩り」(清原弘行) 評価が低い豊臣秀吉 (清原弘行) 武士という存在への誤解の数々(相澤正久) 上杉鷹山を知ろう (服部剛) 明治維新の〝腰骨〟となった武士道 (占部賢志) 歴史人物の歪め方 (久野潤) 幕末のロシアによる対馬占領 (飯島利一) 幕末~維新の奇跡1 国難を救った日本人の進取の気性 (占部賢志) 幕末~維新の奇跡2 日露の国境を画定したタフネゴシエーター (占部賢志) 幕末~維新の奇跡3 日本の無実を晴らしたベルギー公使 (占部賢志) 明治を支えた会津人の気骨 (白駒妃登美) 朝鮮半島はいかに日本にとって大事か (服部剛) 日英同盟の真価を考える (井上和彦) 世界の潮流をつくった日露戦争(土井郁磨) 日本の歩みの凄さを知ろう(齋藤武夫) 神様になった西郷隆盛 (白駒妃登美) ポーランド孤児を救ったシベリア出兵 (井上和彦) 人種差別撤廃を国際会議で初めて提案した日本(皿木喜久) 満州は中国のものか (服部剛) 満州事変から教科書が酷くなる!(土井郁磨) 朝鮮統治の真実① あれは帝国の合併でした (松木國俊) 朝鮮統治の真実② 急成長を遂げた朝鮮(松木國俊) 朝鮮統治の真実③ ハングルを普及させた日本 (松木國俊) 日本の統治は植民地支配か~南洋編(井上和彦) 日本の統治は植民地支配か~台湾編 (井上和彦) 台湾統治の真実 (白駒妃登美) インドネシア独立と日本人(白駒妃登美) アジア解放をもたらした日本の戦い(井上和彦) ユダヤ人を守った日本人(伊勢雅臣) スリランカに助けられた日本(白駒妃登美) 大東亜共同宣言はただの政治宣伝か(服部剛) 硫黄島の戦いの意味(久野潤) 沖縄戦をどう語り継ぐか(仲村覚) 沖縄戦 国民保護の教訓 (仲村覚) 「南京大虐殺」と「従軍慰安婦」という虚構(石川水穂) 通州事件という悲劇(藤岡信勝) 正定事件という新たな虚構(三浦小太郎) 忘れてはならないこと(本誌編集部) 原爆をどう考えるか(齋藤武夫) 東京裁判をどう考えるか(齋藤武夫) GHQの置き土産「社会科」(齋藤武夫) 検閲と公職追放という理不尽(服部剛) 靖国神社はどんな神社か(石川水穂) 英霊は「可哀想な被害者」か(笹峯桜) ウズベキスタンの人々を共鳴させたシベリア抑留者の奮闘(白駒妃登美) 世界は明治天皇をどう報じたか(伊勢雅臣) 世界は大正天皇をどう報じたか(伊勢雅臣) よろこびもかなしみも国民とともに(伊勢雅臣) 特別講義 私の胸に刻まれる英霊の言の葉(伊藤つかさ) 社会主義を総括しない教科書(伊勢雅臣) 知っておきたい領土問題 北方領土編(入川智紀) 知っておきたい領土問題 竹島編(入川智紀) 知っておきたい領土問題 尖閣編(入川智紀) 沖縄はいつから日本だったか(仲村覚) 軍備は「守る」ためにある(井上和彦) 自衛隊を知ろう 徴兵を考える(本誌編集部) 自衛隊を知ろう 自衛隊は国を守れない(本誌編集部) 自衛隊を知ろう カルタゴの教訓(服部剛) 戦争をどう考えるか(齋藤武夫) 学校での国旗国歌めぐる攻防(本誌編集部) 拉致事件を語り継がない学校(入川智紀) 日教組という伏魔殿1 学力テストはダメ!(本誌編集部) 日教組という伏魔殿2校長権限を封じ込める(本誌編集部) 日教組という伏魔殿3 違法確認書の数々(本誌編集部) 日教組という伏魔殿4 今も続く主任制への反対(本誌編集部) 教科書めぐる事件簿1 教科書誤報事件(石川水穂) 教科書めぐる事件簿2 正常化への戦い(石川水穂) 教科書めぐる事件簿3 八重山採択と学び舎教科書(本誌編集部) 価値を語らぬ道徳授業 (本誌編集部) 強制という呪縛(木村貴志) 志を立てよう(木村貴志) 「ゼロ・トレランス」という教育手法(森靖喜) 学校は国家観を育んでいるか(本誌編集部) 戦争犯罪って何だろう(齋藤武夫) 歴史戦とは何か プロパガンダに惑わされるな (齋藤武夫) 反日ネットワークという存在 (江崎道朗) 世界に拡散する慰安婦問題(勝岡寛次) 歴史戦の舞台となったユネスコ(高橋史朗) 再び歴史戦とは何か (西岡力) 国連を利用する人々(西岡力) 朝日新聞の歴史報道はどこに問題があるか プロパガンダとしての慰安婦報道(西岡力) 朝日新聞の歴史報道はどこに問題があるか2 貶められたままの先人の名誉(西岡力) 補習 河野談話の研究(本誌編集部) 歴史見直しの最前線1 (江崎道朗) 歴史見直しの最前線2 アメリカに横たわる二つの流派 (江崎道朗) 歴史見直しの最前線3 コミンテルンの動きを明らかにせよ(江崎道朗) 歴史見直しの最前線4 ヴェノナ文書の破壊力 (江崎道朗) 歴史見直しの最前線5 東京裁判史観の修正進む米国(江崎道朗) 歴史用語を減らす動き① 何が起こったのか(藤岡信勝) 歴史用語を減らす動き② 狙いは何だったのか(藤岡信勝) 歴史の真実にアプローチするために (占部賢志) 歴史は自分を映す鏡(占部賢志) 補講 歴史教育を正し、WGIPの〝洗脳〟を解こう(ケントギルバート) 特別講義 日本の歴史はすばらしいよ!(フィフィ ) 補講 あなたは日本をどこまで語れますか?(産経教育委員会) ゼミナール 世界の中の日本はどう変わるか(江崎道朗) 居残り特訓 戦略的学校生活のススメ(平井基之) ゼミナール 雇用はどう変わるか(鳥潟幸志) ゼミナール グローバル社会のなかで求められるスキル (鳥潟幸志) ゼミナール 日本人を考える私のオススメ(鳥潟幸志) 補講 歴史を知ることはなぜ大事か (室舘勲) 最終講 縦軸を取り戻す歴史教育を (義家弘介) ナビゲーターを終えて (半井小絵) 編集後記
-
3.7
-
-1巻220円 (税込)米国の順調な景気回復を前提に、2015年の世界経済は緩やかな成長を継続する--。こうしたシナリオを大きく崩しかねないリスクが浮上している。原油価格の急落だ。先進国経済にとってはプラスのはずの原油安が、為替市場、株式市場を混乱させている。本書は、週刊エコノミスト2015年1月6日号(合併号)の特集「世界経済2015」を電子書籍化したものです。 世界経済2015 Part1 米国1強の危うさ ・逆オイルショックの衝撃 ・2015年カレンダー 世界経済・政治の注目イベント ・2015年為替・株価大予想 株 為替 ・円安 スーパー円安時代に突入 マネーフローと投資はこう動く ・インタビュー ポール・シェアード ・米国経済 潜在成長率を超える2.7%成長 ・まだ狙える米国株 バイオ、IT、エネルギー… ・インタビュー アダム・ポーゼン ・欧州 欧州を襲うデフレ危機と政治的緊張 ・欧米の対露制裁が招くドル基軸体制のほころび Part2 新興国と資本主義の未来 ・中国 減速中国を襲う4大リスク ・中国株 いまだ割安 2015年に資金流入は拡大 ・ASEAN アジア版EUスタート 関与深める日本と中国 ・TOPIC1 スマホ 凋落するサムスン ・TOPIC2 SNS 「上場」か「買収される」かLINE ・原油安 価格主導権は依然サウジ ・ロシア 原油安直撃で深まるロシア経済危機 ・イスラム国 西側の都合で勢力維持 ・2015世界経済展望 成長しか知らない資本主義が「成長しない時代」に入る ・TOPIC3 水産資源 伸びる世界の漁業 日本だけが衰退 ・TOPIC4 感染症 エボラの次は脳を侵すATCV-1 ・グローバリズムの本質 株式会社が国家を破綻し、国民から搾取する
-
4.0英国のEU離脱は、危機の連鎖の始まるになる! 世界的「価格破壊」の時代/欧州「離脱ドミノ」は不可避/デフレで沈む中国、韓国/世界が頼る日本の資金力/金融、自動車業界大編成/日米が世界を牽引するなど、大激動期の先を読む著者渾身の世界予測、最新版。 英国のユーロからの離脱は今後の成り行きとして、残留に固執していたスコットランドも独立しEUに残ることになりそうである。そしてウェールズも独立することになり、島国イングランドだけが残り孤立する。そうなれば、スペインにも飛び火する。カタロニアが分離独立して、スペインは崩壊する。今後のギリシャ問題の再燃等もあり、EUは、分裂、崩壊の機運を高めることになる。第二次大戦後の強引な国境線の画定によって、強烈な不満を持っている国民はまだ多い。冷戦時代においても既成秩序によって過酷に統制され、各国、各地域の民衆の不平不満が抑圧されてきた経緯がある。確定された国境への異議、戦後処理の不徹底への不満が一気に噴出してくる可能性がある。まさに世界は「パンドラの箱」が開いた状態である。どんな欲求、願望が出てくるか、場合により敵意も、憎悪も噴出してくる可能性もある。(「はしがき」より抜粋)
-
-ウルグアイの第40代大統領を務めた、ホセ・ムヒカ氏をご存知でしょうか。 ムヒカ氏は、その質素な暮らしぶりから「世界で一番貧しい大統領」と言われていますが、国民には「エル・ペペ」の愛称で人気を博しています。 本書では、ムヒカ氏がUNASUR(南米諸国連合)の会長へ就任した際のスピーチのほか、2016年4月に初来日した際に東京外国語大学で行なった講演全文を収録。 本当の豊かさは何なのか、大切にしなくてはいけないものは何なのか、私たちが失いかけている大事なことを思い出させてくれる素晴らしい演説、ムヒカ氏が我々日本人に贈ったメッセージを読み取ってください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 さまざまなデザインの国旗も,その色や形,模様などに注目して見ていくと,その国の歴史,文化,政治,宗教などが見事に概観できます。色ぬりをしながら世界を知る本。120を超える国旗図版を掲載。国名,人口など,最新のデータに直した改訂第6版ができました。 ★★ もくじ ★★ 第1部 似ている国旗・似てない国旗 形から見た世界の国旗 第2部 政府の国旗と国民の国旗 国旗の中の国章 第3部 世界の人々は何色の国旗が好きか 色から見た世界の国旗 第4部 変わる国旗・変わらない国旗 第5部 世界の大国の国旗一覧
-
-「いま世界は」のコメンテーターが語る世界の状況。常識が通用しない時代に、国際的視野から日本の危機と戦略を考える。ビジネスの世界から見ても、この数年、世界が今までにないほど大きく変動し、かつての常識が通じなくなっている。数百年に一度の文明の転換点にあるとも言われる。今まで当然と考えられてきた認識や価値観が劇的に変化するパラダイム・シフトが起きている。中国が台頭し、世界金融危機が起きて以降、政治と経済の境界はなくなってきた。政治がビジネスの現場に土足で入り込んできている。時代が変わり、世界のパラダイムが変わった中で、日本のあり方を考えるためには、今、日本が置かれている状況をできるだけ包括的、総合的に見つめることが第一歩である。現代は細かい現実がわかっていなければ、全体像がわからず、大局的な戦略も立てられない時代だ。本書では、細かい現実の動きと大きな世の中の流れの関連に注目したい。そして、先進国が主導する工業社会、資本主義における経済力や技術力、軍事力が世界を引っ張り、こうした国の豊かさが、国民の豊かさと直結しているという今までのパラダイムが通じなくなっている状況を具体的に探ってみたい。それが、これからの日本が進む道を考える上でも不可欠であろう。
-
-「日本と言えば世界にその名を知られる超大国であるが、ある日私は、現在の日本がどのようにして発展していったかということを知りたくなった」――日本再興の背景となった、アメリカをはじめとした「海外在住国民国家」の凋落、ヨーロッパに誕生した右翼政党「ワンボイス」騒動、中国共産党政権の崩壊……。知識人18人が2041年の世界情勢を徹底分析。分岐点となったのは、2015年。現代日本が今後どのように進むべきかを真摯に問いかける、圧巻の近未来小説。
-
-品格のある国家、気概のある国民、そして夢のある世界のために、古の知恵を知り、新たな世界観を樹立すべきときではないのか―。現役の文部科学大臣が語る日本の「こころ」の素晴らしさと世界に対して「自信を持つ」ことの本当の意味。 【著者「あとがき」より】 世界の共生をなぜ日本から始められるかといえば、日本は一つの物差しで、たとえばある宗教によって全体が染まっているわけではないし、なんとか主義という思想ののもとで、社会がひとつに染まっているわけでもありません。逆に古今東西の思想・哲学・宗教などのいいとこ取りができる国だと言えます。柔軟で抵抗感がないからこそ、新しい文明を切り開くチャンスがあるのです。
-
3.0
-
-接客・販売員の方を対象に、接客の基本とコツ、お客様を満足度をアップするポイントをわかりやすく解説した一冊です。社会人としてのオキテから、「55点が“企業人”の最良点」「“あなたから買ってよかった”と言われなさい」「仲よくなってからクロージングするのです」「3回は下見をさせておきなさい」「やさしくなれる人ほど接客がうまい」アプローチ、クロージング、アフター、達人になれる接客のオキテ77。目からウロコの実践的なアドバイスが満載です。 著者:加納 光(かのうひかる) 1958年福岡市生まれ。百貨店の販売促進部勤務を経て、1998年企業の販売戦略支援会社「コンセプトワーク」設立。船井総合研究所大阪本社コンサルティングチームの事前研修セミナーなどを行う。2001年商品開発コンサルタントの伊吹卓氏が会長をつとめる「商売道・伊吹流」に参加し、企業のヒット商品開発や人材育成などのコンサルティングを担当。2003年「伊吹流・免許相伝」を受け、会長の師範代となる。現在、株式会社フレンテ(湖池屋)、テンプスタッフなどで人材育成を行い、受講生は1000人にのぼる。おもな著作に『あなたから買いたい』(日報出版)、『上司の急所』、『仕事の急所』(ともに自由国民社)などがある。
-
-「いまの自民党なら民主党政権のほうがマシ!?」 「共産党は『ブラック企業』とそっくり!?」 「なぜ野党が『国民いじめ』に走るのか!?」 うんざりするような、この国の政治。しかし、いったい何が本当にダメなのか、その正体を、日本の政治史を明治時代からひもときつつ、すべて明らかにする一冊。もちろん、2014年12月の総選挙以降の直近の政治状況も、世間の通説とはまったく違った角度からズバズバ斬っていく。民主党政権のあまりの酷さにより、現在、日本の政治は「自民党一強VS野党多弱」の「(平成)25年体制」になっているが、しかし、だからといって自民党が立派な政党になったわけでもなければ、野党がしっかりしたわけでもない。この状況下で、いかに各政党が手前勝手な論理で動いているかを、両者が舌鋒鋭く暴いていくのは圧巻のひと言。さらに、現在の中東の状況から、政治にとって何が本当に大切なのかも論考していく。いま、本当は何が起きているのか。本書を読めば、政治のカラクリは丸ごとお見通し!
-
4.3
-
3.9
-
5.0アジアモンスーンの恵みをうけた肥沃な土地、おっとりとした国民性で知られるカンボジアを突然襲った「赤いクメール」の嵐。ポルポト政権下の粛清と強制農村隔離政策は百万人といわれる犠牲者をだし、国土を荒廃に追いこんだ。なぜ悲劇は起きたのか? 現地で外交官の夫とふたりの息子をつぎつぎと喪い、数年におよぶ強制労働に従事した日本女性の体験談から事実を、また、証言を考察可能な距離まで一度切り離したうえで政変の深奥を掘り起すことを試みる。
-
-戦後55年間の年別ヒット商品、音楽、本のベストセラーランキングアルバム。大事件、流行語、人気テレビ番組、ヒット映画などとともに日本国民の需要の変遷を一気に眺める。
-
-2015年8月15日で、第二次世界大戦が終わってから70年。 戦争を体験した人は年々少なくなり、あの悲惨な体験を語り継ぐ人物が減ってきている。 しかし、私たち日本人が当時の状況はどうあれ、アジアの人々に苦痛を与え、国民にも大きな負担を強いることになった、あの戦争を忘れてはいけない。 このところ中国の台頭や北朝鮮の不透明な政治状況など、アジアの緊張が高まっている。またシリア情勢が不安定で中東には火種が燻っている。 いつどこでまた戦火の炎にさらされる人が出てきてもおかしくない危機的状況が世界各地にあるのだ。 本書では時代ごとに日本の政治中枢にいた人間が、第二次大戦をどのように捉えていたのか、過去の談話とともに、先日行われた安倍首相の談話を併せて掲載する。 いまの時代だからこそ決して忘れてはいけない忌まわしい戦争の記憶を再び認識するべきであろう。
-
-戦後、焼け跡のなかで育ち、国民的歌手となった美空ひばりの人生に迫ったノンフィクション。だが、著者が書きたかったのは、ひばりだけではない。著者は、日本人について「敗戦後、お互いに貧しくはあったが、自由で生々としていた。いまは、進行する管理体制の下で不自由をかこち合い、人間性を失ってきている。このような状況でこそ、私たちは『戦後』を見直さなければならない」と指摘。ひばりが生きた戦後こそがテーマなのだ 【解説:後藤正治】
-
-
-
-宗教系ラジオ知識人――高嶋米峰、友松圓諦、高神覚昇といった存在と、“経営の神様”と呼ばれた存在――経営者であり実業思想家でもあった松下幸之助の思想を繋ぐものとは、いったい「なに」か。さらには、松下幸之助が残した数々の言葉、名スピーチは「なに」に影響され、生み出されたのか。本書は、その問題について検証した論考である。これまで渋沢栄一などの実業思想家を研究してきた筆者は、まず戦前のラジオ放送という存在に着目し、戦前の宗教系知識人と松下の間に「声の思想」が形成されたのだという、大胆な推論を立て、その検証を本書で試みている。太平洋戦争敗戦という、日本国民にとって苦渋・悔恨の歴史的事件から逃避することなく現実を直視して死を考える程に悩み苦しんだ結果、生誕した松下幸之助独自の思想であるPHPの実現を、松下は最晩年まで念願してやまなかった。そのPHPという思想の根源(ルーツ)にも、本書は迫るものとなった。
-
-
-
4.3戦争をすることで国民の暮らしがどれほど影響を受けるのか、悲惨な事態になるのか。長年戦時史研究を続ける著者が、コレクションである膨大な戦時史資料をもとに、戦争のバカバカしさを激白!
-
-「戦争画」(戦中記録画)を描いた画家への批判、蔑視を行なっているのは背徳の画家や美術評論家だけではない。本来なら美術品の価値を公正に判断し、国民に広く紹介すべき美術館までがイデオロギーに毒されているのだ。本作は、東京国立近代美術館による藤田嗣治の作品展示に表れた「芸術家の尊厳の破壊」を入り口に、倫理観なき「戦争画批判」の愚昧を正していく。※本コンテンツは月刊誌『Voice』2016年1月号の掲載記事を電子化したものです。
-
-「戦争画」(戦中記録画)を描いた画家への批判、蔑視を行なっているのは背徳の画家や美術評論家だけではない。本来なら美術品の価値を公正に判断し、国民に広く紹介すべき美術館までがイデオロギーに毒されているのだ。本作は、東京国立近代美術館による藤田嗣治の作品展示に表れた「芸術家の尊厳の破壊」を入り口に、倫理観なき「戦争画批判」の愚昧を正していく。※本コンテンツは月刊誌『Voice』2016年2月号の掲載記事を電子化したものです。
-
4.1国民を舐めきった政治家に、激怒せよ! もはや日本に道徳はなく、損得しかないのか!? 今、つくりだすべき倫理とは? 日本は戦争する国になった。これは怒(いか)ることを忘れ、日米安保に甘えた国民の責任だ。安保法制化も、沖縄県民だけに押し付けてきた米軍基地の問題も、当事者以外の意見を封じる福島の原発問題も背景にあるのは、怒りや苦しみによる連帯ができず、すべて他人事(ひとごと)として受け流す日本人の感情の劣化だ。しかし、今度こそ怒らねば、そして怒りつづけねばならない。戦争する現実を直視しつつ、舐めた政治家たちに恐怖を与えねばならない。この危機に、かつて罵り合った小林よしのり氏と宮台真司氏、さらには東浩紀氏という日本を代表する論客三人が集(つど)い怒り合った。暴走する権力を阻止し、共闘することを誓った一冊。 感情を抑えるな! 絶望に囚われるな! 〇日本を変えるにはときには政治家へのテロしかない場合もある 〇国民国家間の戦争は本当にありえるのか 〇インターネットが持っていた連帯の可能性もいまは消えた 〇かつては日本が戦争を仕掛けたという事実を水に流していけない 〇「崩れた民主主義」の行きつく先 〇保守でも革新でもない、新しい日本像をつくる
-
-men(人的戦力)、materials(装備)、money(戦費)――戦争の勝因は、この三点で語ることができる。明治以降の日本の「装備」の研究については進んでいるが、近年の外交、財政の不手際を見ると、実は明治以降の「人」「カネ」に関しても負けるべき要因があったのではないかとの疑問が浮かぶ。現在、「人」「カネ」で世界を仕切っているのはアングロサクソンであり、彼らは戦争でも「常勝」している。彼らの「戦争と経済のカラクリ」がわかれば、日本の弱点と突破口が見えるのではないか。本書は、第一章/戦争できる国づくりを支えるモノづくり、第二章/戦費調達に成功した国が勝者となる、第三章/有事を生きる国民たち、第四章/現代日本の国防はこれでよいのか、という構成で、「人」「カネ」をいかに使えば日本が21世紀に勝ち残れるかを説く。希代の軍学者が自信を喪失した日本人に贈る「日本に競争力がつきすぎて困ってしまう」戦略。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。










![[新装版]真田三代記](https://res.booklive.jp/313923/001/thumbnail/S.jpg)
![[新装版]干支の活学―人間学講話](https://res.booklive.jp/331569/001/thumbnail/S.jpg)
![[新装版]運命を創る―人間学講話](https://res.booklive.jp/315454/001/thumbnail/S.jpg)



![[新版]属国日本論を超えて](https://res.booklive.jp/260743/001/thumbnail/S.jpg)











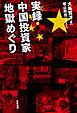






























![[図解]三橋貴明の「日本経済」の真実がよくわかる本](https://res.booklive.jp/153782/001/thumbnail/S.jpg)








































