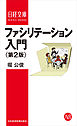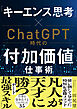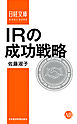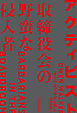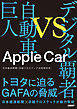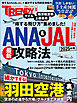ビジネス・経済 - 日経BP作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
3.8シリーズ累計13万部突破! この1冊で、100冊分の重要スキルが身につく エリート・アナウンサー・名経営者・カウンセラー…… みんながみとめた「伝える力」の絶対ルール 雑談、会話、リモート会議、説明、説得、 プレゼン、営業トーク、ほめ方、叱り方…… 「信頼され、好かれる人」の秘訣がわかる! ◆ ◆ ◆ 1位 会話は「相手」を中心に ・「自分の言いたい話」より、「相手の聞きたい話」をする ・人は「自分の話を聞いてくれる人」と話したい 2位「伝える順番」が「伝わり方」を決める ・短時間で誤解なく伝わり、記憶に残るのは「結論」から始まる話し方 ・冒頭で興味をそそり、食いつかせるには? 3位 話し方にメリハリをつける ・「普段よりも、ほんの少し高い声」で印象が劇的に変わる ・聞きやすいスピードは、「1分間に300文字」 ~ 39位 断るときは、きっぱり、はっきりと 40位「あのー」「えっと」を使わない ◆ ◆ ◆ 話し方を変えることは、 自分自身の内面をより良く変えることです。 自分の話し方のクセを見直す作業は、 自分の内面を見つめ直す作業です。 ひとつでもふたつでも、 「これだったらできそう!」というコツを覚え、 「会話を楽しんでいただけたら」 「ビジネスに役立てていただけたら」 「人生を楽しんでいただけたら」。 本書が、言葉と、会話と、内面を磨く ヒントとなることを心より願っています。
-
4.0
-
4.1「儲からない」といわれた個人宅配の市場を切り開き、「宅急便」によって人々の生活の常識を変えた男、小倉昌男。本書は、ヤマト運輸の元社長である小倉が書き下ろした、経営のケーススタディーである。 全体を通して読み取れるのは、「学習する経営者」小倉の謙虚さと、そこからは想像もできないほど強い決断力である。成功した人物にありがちな自慢話ではない。何から発想のヒントを得たか、誰からもらったアイデアか、などがこと細かに記されている。講演会やセミナー、書籍、マンハッタンで見た光景、海外の業者に聞いた話、クロネコマークの由来…。豊富なエピソードから伝わってくるのは、まさに学習し続ける男の偉大さである。
-
4.0営業、企画、システム、制作、人事、経理――すべてのビジネスパーソンにとって磨いておきたいスキルが「提案力」。 役職、業種・業態に関係なく、どんな仕事も、提案なしでは始まらないからだ。 しかし「提案内容に自信が持てない」「人前でプレゼンするのが非常に憂鬱だ」など、誰しもが避けることができない提案業務への苦手意識は根強く、「提案力を高めることができれば、どれだけ仕事がしやすくなるだろうか」と悩む人は決して少なくないだろう。 著者は、日商岩井、ソニー、博報堂で活躍後、電通に移籍したマーケティングプランナー。クライアントへのプレゼンを日々行ってきたが、当初は、なかなかうまく提案ができず、苦労した経験を持つ。しかしある日を境に、提案に対する苦手意識が払拭され、プレゼンに自信が持てるようになったという。その秘訣は、提案の中に「問題解決」があるかどうか。それを「一言」で表現できるかどうかだ。 本書は、著者が経験に基づき体得した提案スキルを体系的に整理。技巧的なものではなく、誰もができる、提案力を本質的に高める手法として提示するもの。クライアントであろうが、自分が所属する組織であろうが、ビジネスのあらゆる現場で抱える様々な問題を特定し、その問題解決シナリオを一言で表現する「シンプル・プレゼンテーション」の極意を伝授する。見せ方の技術などを中心に解説する類書とは一線を画し、幅広く応用ができる「考え方」が身につく一冊。
-
5.0コーチング体験はこれ1冊でOK!レジェンド・コーチの世界的ベストセラーが待望の文庫化。 人間関係を劇的に好転させる「20の悪い癖」の発見・改善テクニック! 2007年に刊行された世界的ベストセラーの文庫化。著者マーシャル・ゴールドスミスは、GEやグーグル、ゴールドマンサックスなどの名経営者たち向けに、1回25万ドル超とも言われた全米指折りのトップ・エグゼクティブコーチ。 米アマゾンによれば、マーシャル・ゴールドスミスの『コーチングの神様』と『トリガー』は、「リーダーシップ本と成功本のトップ100リスト」(古典から現代までの経営本、自己啓発本で構成)に入っており、著者は、そのトップ100リストに2冊もランク入りしている、唯一の存命の作家である。 そんな本書はCEO専門のコーチとして活躍している著者が、いかに自らの悪癖を乗り越え、部下を育て、さらに自分の能力を発揮していくかをステップごとに解説した作品。コーチング体験から得られるステップごとに示され、非常に読みやすく、読みながら自分の悪癖を把握できる。 豊富な事例から、部下を持つ人なら自分ごとに感じられる一方、上司に不満を感じている人にもまた共感を呼ぶ内容となる。ビジネスコーチングにかかわる層から一般ビジネスパーソンまで幅広い読者層が対象となる。
-
4.4高邁なパーパスを掲げても、戦略にはまったく役に立たない。 ミッション・ステートメントは戦略策定の足しにならない。 そんなものに時間と労力を注ぐのは無駄である。 * * * * 戦略策定がうまくいかないのは、戦略とはあらかじめ定められた目標、とくに業績目標を実現する方法のことだ、という経営陣の思い込みにある。 こうした思い込みを打破し、戦略策定を専任者に任せきりにせず、行動計画を各部門責任者に丸投げしない。 * * * * 戦略の策定とは意思決定でも目標設定でもない。 卓越した優位性も長期的ビジョンも他社との比較も要らない。 「戦略の策定」とは克服可能な【最重要ポイント】を見きわめ、それを解決する方法を見つけることである。 「戦略の戦略家」「戦略の大家」でロングセラー『良い戦略、悪い戦略』著者が、戦略をめぐる誤解を解きほぐした新たな名著。
-
-「これさえ守れば、会社や事業は必ずうまくいく」 稲盛氏の経営哲学を12の項目にまとめた集大成。 世界300万部を超える「稲盛経営3部作」の完結作! 稲盛氏が自身の経営体験から導き出した「経営の極意」を12の項目にまとめた『経営12カ条』がついに文庫化。短い言葉のなかに経営の原理原則を込めた集大成にして最後の著書。 「世の複雑に見える現象も、それを動かしている原理原則を解き明かすことができれば、実際には単純明快です。こうした考えの下、『どうすれば会社経営がうまくいくのか』という経営の原理原則を、私自身の経験をもとにわかりやすくまとめたのが、『経営12カ条』です」(まえがきより) 京セラのみならず、KDDIや日本航空などの大企業から中小企業に至るまで、あらゆる業種、業態で実践され、有効性が証明されてきた稲盛経営の要諦を明かす。 解説 岩尾俊兵氏(慶應義塾大学准教授)。 *本書は、2022年9月に日本経済新聞出版から刊行された同名書を文庫化し、新たに解説を加えたものです。 【目次】 第1条 事業の目的、意義を明確にする 第2条 具体的な目標を立てる 第3条 強烈な願望を心に抱く 第4条 誰にも負けない努力をする 第5条 売上を最大限に伸ばし、経費を最小限に抑える 第6条 値決めは経営 第7条 経営は強い意志で決まる 第8条 燃える闘魂 第9条 勇気をもって事に当たる 第10条 常に創造的な仕事をする 第11条 思いやりの心で誠実に 第12条 常に明るく前向きに、夢と希望を抱いて素直な心で 解説 経営は人生の合わせ鏡 慶應義塾大学准教授 岩尾俊兵氏
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 先行きが見えず、将来の予測が困難な現在、「リスキリング」という言葉が注目されています。これまでの“常識”であった終身雇用制度は崩れ、「人生100年時代」と言われるように働く期間も大きく伸びました。 さらに劇的な進化を続けるAIに多くの職業が影響を受け始めているように、今持っているスキルが10年、20年後にも通用するとは限りません。そんな時代を生き抜くために必要なのがリスキリングなのです。 そこで新たなスキルを“武器”として活用できる「資格取得」の最短ルートを解説。さらに、2つ以上の資格を組み合わせれば、より強烈な個性を発揮することも。高年収のハイクラス人材になるための「越境転職」や「タイパ副業」についても紹介します。 ≪主な内容≫ ◎特集 資格・転職・副業の新しい地図 PART1 資格編 「基礎の3資格」を軸に最短コースで資格を極める PART2 転職編 40代・50代が知らずに損する! 転職市場の新常識 PART3 副業編 収入とスキルの両取りが狙える「フロー型」が候補 ◎特集 テレワーク⇔出社 “二刀流”仕事 PART1 仕事ギア&文房具 ハイブリッドワークを快適にする5種の神器 PART2 デジタル仕事術 “分断会議”のよくある悩みを解決するテク PART3 リモート環境整備 オフィス以外でも業務効率を落とさない
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日々、目の前のことに追われてしまい、「自分らしく時間を過ごしていない」と感じている人も多いのでは?自分にとってムダな時間を洗い出し、本当にやりたいことに時間を使うためのヒントを、本書ではたっぷり紹介していきます。 「やるべきこと」よりも「やりたいこと」を優先する時間術や、ひとり時間の過ごし方のコツ、毎日が充実する手帳の書き方、お金が貯まる人の日々の習慣、生成AIなど最新ツールを使った仕事の効率化術など、時間の使い方を見直せる多彩なコンテンツを盛り込みました。 気になることから取り入れるだけで、前向きな変化を実感でき、自分に自信が生まれるはずです。 ≪主な内容≫ PART1 「私らしさ」を取り戻す! 時間の新ルール PART2 人生が好転する! 手帳の使い方 PART3 お金が貯まる人の毎日の習慣 PART4 仕事が速い人の時短のコツ
-
3.0●マーケットデザイン(市場設計)の幅が広がる 1990年半ば以降、日本では翻訳書の出版が相次ぎ、2000年代からは日本の学者による出版も増えてポピュラーになった「ゲーム理論」。相手の利得を探りながら自分の選択を行うという行動は、「戦略論」というタイトルの本にも取り上げられ、経済学を超えて幅広く知られるようになった。 一方で、2012年にアルビン・ロスがノーベル賞を受賞した最大の成果である「マッチング理論」は「自分も選ぶが、相手からも選ばれる」というところに、特徴がある。ロス教授の『Who Gets What』にもあるように、学校選択、就活、臓器移植など、様々な分野で応用が利き、マーケットデザイン(市場設計)の幅が大きく広がった。 ●ベストな決定はこうして導く! 本書は、共にマーケットデザインの分析ツールである「ゲーム理論」と「マッチング理論」を橋渡しする。多くの人が知るゲーム理論は、最新の理論を入れて解説。比較的新興の「マッチング理論」については、著者もかかわる日本の入試制度改革などをはじめ、様々な事例を盛り込む。この分野は日本での浸透は遅れており、啓蒙的な意味合いをもつ。 目次 第1章 なぜゲーム理論の考え方が重要か 第2章 非協力ゲーム理論ーー個人のインセンティブ 第3章 協力ゲーム理論--集団のインセンティブ 第4章 二部マッチング理論 第5章 配分マッチング市場
-
3.9【この「働き損社会」の一因は、組織にはびこる“ジジイの壁”?】 やる気をなくし早々に“窓際族”を目指す30代エリート、 世帯収入3000万じゃないと就職する意味がないと嘯く女子大生、 「普通に暮らせればいいです」が口癖のZ世代会社員、 「今まで頑張ってきたから」を言い訳に会社に寄生する50代、 人生諦めたまま老いていく中年氷河期世代…… 「仕事に意欲を持っている社員は5%しかおらず、世界145位中最下位」 いま、何が日本人から働く意欲を奪っているのか? 健康社会学者である著者が、会社員へのインタビューをもとに 「働かないニッポン」の構造的な問題をひもとく。
-
3.7
-
4.1累計10万部のロングセラー、待望の新版! 本書は2004年7月に刊行した『ファシリテーション入門』の改訂版です。 『ファシリテーション入門』は入門用テキストとして多くの企業や大学で採用され、 当該分野の標準テキストといえるまでになりました。 ファシリテーションとは、 集団による問題解決、アイデア創造、合意形成、教育・学習、変革、自己表現・成長など、 あらゆる知識創造活動を支援し促進していく働きです。 その役割を担う人がファシリテーターであり、 日本語では「協働促進者」または「共創支援者」と呼びます。 ファシリテーションの最大の特徴は、 情報や意見などの内容、コンテンツではなく、 進行や関係といった過程、プロセスを舵取りするところにあります。 改訂版では、多彩なファシリテーションの技法や応用のなかで、 すべての活動の基本となる「話し合い」(会議)のファシリテーションに焦点を当て その理論と実践スキルを紹介していきます。 最新の知見を盛り込み、第一版を全面的にアップデートしました。
-
3.9●価値観はより多様に。「怒る」で解決できることは何もない。 怒ることが、子どもや後輩社員の教育や士気高揚につながり、個人の成長を促してきたという考えは、もう古いものになった。怒られることになれていない子どもも増え、怒る人は職場の雰囲気を悪くし、むしろ感情を抑えられない人としてとらえられる向きもある。 パワハラ防止法が2020年6月から施行され、さらに「アンガーマネジメント」へのニーズは高まるだろう。「怒る」という感情は、「自分の考え(≒常識)と違う」ということが起点となっているが、ダイバーシティが求められる昨今、誰もが常識だと思うことがそもそもなくなってきている。 ●怒りを抑えるトレーニングを盛り込む。怒りに巻き込まれない手法も。 怒りの感情は、自分で生み出しているということをまずは認識する。相手が起点という発想をやめることが大切だ。また、「コアビリーフ」、つまり、自分でこうあるべきだという思い込みが怒りの感情を生むので、その書き換えが必要だ。また、日常の怒りの場面を記録し、ふりかえることで、自分の感情にしっかり向き合うことも効果があるという。 また、本書では、「怒りに巻き込まれない」手法を書いていることも特徴の一つ。怒っている人をみると、自分がその当事者でなくても、嫌な感情が巻き起こって物事に集中できなくなることがある。それを回避するためには、相手の感情を自分で変えることはできないので、あくまで外野のできごとだと割り切ることが必要で、その練習法も盛り込む。
-
4.6インデックスもいいけれど、株式投資の醍醐味はやっぱり個別株選びにあり! リスクをきちんと理解して、大きな利益を手に入れよう。 ○個別株投資についての基本的な手法をコンパクトにまとめました。 「成長株」「割安株」の本質を理解することで、銘柄選びの王道的な知識がひととおり身につきます。 ○個別株投資には「これさえ知れば必ず儲かる」という指標はありません。 どの指標や手法にも一長一短があり、それらを組み合わせる総合判断が重要です。 本書では、指標のしくみと使い方のポイントをわかりやすく説明しました。 ○初心者から経験者まで、幅広い読者にお読みいただけます。 専門家のノウハウについても、難しい数式や専門用語は極力使わず、やさしく紹介しています。 ○『日経マネー』の副編集長が執筆。 目先の情報に踊らされることなく、長期的に伸びる銘柄を見分ける方法を解説しました。 【本書の主な内容】 ・「企業の業績が伸びれば株価は上がる」は嘘 ・「フジテレビの株」急上昇の謎 ・PBR(株価純資産倍率)1倍割れ=「会社をすぐに解散した方がみんな幸せ」 ・「バリュートラップ(割安の罠)」を避けるには ・未来の利益なんてあてにならない ・PER(株価収益率)は「便利だが、単体では使えない」 ・PERに騙されないために ・成長株の危機を避けるコツとは? ・成長株を見極める9つの数字 ほか
-
4.4SEじゃないあなたのための DX推進の教科書! 企業のDX推進でシステムを「作らせる技術」の重要性は増しています。 プログラマーやSEのような専門家だけがシステムについて考えればよいのではなく、「自分では作れなくとも、思い通りのシステムを『作ってもらうノウハウ』」が必須の時代になったということです。 そのためには、 ・「こんなシステムがあればいいのに」を構想し、 ・「A機能とB機能、どちらを優先すべきか」を判断し、 ・これを作るのにいくらまで投資する価値があるか?を見極め、 ・作ってくれる人(社内の情報システム部門、または社外の専門ベンダー)を探し出し適切に依頼し、 ・構築プロジェクトで沸き起こる様々な課題を解決 していかなければなりません。 本書はシステムに詳しくない業務担当者が、新しいビジネスを立ち上げるために、または既存の業務を改革するために、すべきこと/陥りやすい落とし穴を余すことなく書きます。 著者が20年以上にわたり支援してきた多くのプロジェクトでの事例やエピソードを詰め込んだ、実務家のための教科書です。
-
4.1●求められる「アサーティブ」な会話 「アサーティブ」とは「自分を主張する」という意味だが、ここでは、相手を尊重しながらも自分自身の意見を伝えるという意になる。組織の多様性、そして心理的安全性が言われる職場において、誰もが臆することなく、一方で誰もが相手を追いつめることなく、意見を言える環境が求められている。 在宅勤務が増えて、オンラインやメール主体のコミュニケーションが増えると、発言がしにくかったり、顔が見えないことによる攻撃的なコミュニケーションが増える可能性がある。アサーティブ・コミュニケーションの考え方は以前から日本に導入されていたが、いま改めて、そのニーズが増しているといえる。 本書は、『日経文庫 アンガーマネジメント』の著者が、怒りをうまくコントロールした先にあるコミュニケーションとして、アサーティブ・コミュニケーションの考え方と実践法を語る。 ●職場のケースを中心に アサーティブ・コミュニケーションは、アンガーマネジメントの延長戦上にあるとも言える。相手を尊重し、自分の思いを抱え込むことなく語れば、他人への攻撃や自分へのイライラを押さえ込むことができる。アンガーマネジメントでは、「~こうあるべき」という思いが相手を許せないという行動につながっていたが、アサーティブ・コミュニケーションでは「アンコンシャスバイアス」という無意識の思い込みが、相手を必要以上にやっつけたり、必要以上に遠慮してしまったりする原因となる。 本書はビジネスの現場視点から書かれているのが特徴。事例が豊富で、コンパクトに基本がわかる1冊。
-
4.0正確でシンプルな解説が好評!日経電子版連載「キソから! 投資アカデミー」を書籍化しました。 株式、債券、投信で投資をし始めている人はもちろん、 為替や貴金属などの仕組みを理解したい人にも最適な入門書です。 <本書でわかること> ・どのような金融商品があるのか ・それぞれの違いは何か ・商品別に投資を使い分けるコツ ・注目指標から相場を読む分析方法 ・市場が動く要因やニュースの捉え方 日々マーケットの第一線で取材し、市場を知り尽くした日本経済新聞の記者が 中立的な視点から執筆し、豊富な図表とともに よく目や耳にする投資のキーワード、テーマを厳選して解説します。 資産形成に関する基礎知識を余すことなく、一冊にまとめました。
-
4.0マクロ経済学を身近に感じられる1冊。ニュースやケースを交えて解説することで理解がさらに深まる。 ●マクロ経済学の基本の基本書 マクロ経済学はミクロ経済学と並んで、経済学の王道中の王道で、公務員試験で必須のほか、学生、一般の人も含めて読者の多い分野。これからの日本経済を考える上で、必要な知識。GDP(国内総生産)、財政政策、金融政策、為替などを、やさしい事例を用いながら解説。 ●なぜ、いまこれを考えるのか。ニュースなども交えて解説。 著者の塩路氏は、2015年に、経済学研究で名誉ある「日本経済学会・石川賞」を受賞するなど、日本経済学研究の第一人者である。本書では従来の本に多い、頭から理論を押しつける解説ではなく、「なぜ税金が必要なのか」「なぜGDPから考えるのか」など、読者に寄り添う形で解説しています。また、章末にはニュースを題材として取り込んでおり、理解が深まります。「国単位で考える」マクロ経済学はどうしても身近に感じられない場合も多いですが、日々のニュースを理解する上で必要な知識が得られるよう、随所に工夫を凝らしています。
-
3.0イノベーションを生み出すためには、何をすれば良いのだろう。そもそも、イノベーションって何のことなのだろう。本書は、このような素朴な疑問をもつビジネスパーソンや政策担当者、あるいはイノベーションについての基本的なポイントをおさえておきたいと考える人に向けた入門書。「イノベーションが必要だと言うけれど、さて、何から始めれば良いのだろう」という人の手助けをすることが本書の目的。 イノベーションへの注目が大きくなるにつれて、書籍も多く出版されている。イノベーションを生み出した企業家やコンサルタントなどの経験に基づくものや、イノベーションとなった事例の分析、あるいはアイディアの発想法などさまざまだ。その一方で、イノベーションについての研究はおよそ100年前から進められ、さまざまな研究が蓄積されている。本書は、その積み重ねられた発見の上に立って、イノベーションを考えていく。
-
4.0★老後不安を賢く解消!年金だけに頼らない! ★50代からの「無理はしない」副業の考え方と始め方を丁寧に解説 ★早めの準備でほどよいお金とほどよい居場所を手に入れよう ★心身の健康を第一に、ローリスクでのスタートが大事 ★リタイア世代の再スタートにもぴったり 「老後、年金だけではキツそう」…… それならば「月10万円」副業で稼ぐ生活を今から目指そう! 副業評論家として各種メディアで人気の著者が、 40代、50代のビジネスパーソンが、 ローリスクで無理なくスタートできる手法を紹介。 定年退職間近な人、すでに退職した人にもおすすめ。 [考え方] ●“あれもこれも”でやってみる ●今いる会社は「メイン・クライアント」と考える ●自分に合った方法で小さく始める ●「副業」で「本業」も充実 [具体的ノウハウ] ●「仕事仲介サイト」登録のポイント ●会社で見つけた知識・経験・技術を活かす ●趣味や好きなことを活かす ●ネットで短期間の作業を請け負う ●書き手になる ●地方に貢献する ●「昭和なアルバイト」を始める ●ポイ活やアンケートモニターからゆるくスタート ●資格取得と「試運転」のすすめ ●定年のない「ひとり社長」 ●実力を活かして営業代行 ●コンサル、研修講師デビューする [お役立ちヒント] ●公的支援を活用するワザ ●自分をプロデュースする技術 ●写真はプロに撮ってもらう ●通る事業計画書の書き方 ●AIの活用法 ●介護、老親問題、思わぬ出費への対処 ……など、実践的かつ丁寧に解説。 ※2022年11月刊行の『年金にあとプラス10万円を得る方法』(産学社)を文庫化にあたって大幅加筆、再編集、改題したものです。 【目次】 ●第1章:「年金プラ10」生活への準備 ●第2章:「副業・複業」で「年金プラ10」を無理なく実現する11の方法 ●第3章:「ひとり社長」で「年金プラ10」を無理なく実現する方法 ●第4章:小さく始めて確実に稼ぐ! 仕事獲得の最短ルート ●第5章:賢くトクする! 公的支援を活用しよう ●第6章:稼げる自分をつくる! 差別化ポイントと「通る事業計画書」 ●第7章:誰もが直面! 「年金プラ10生活」と介護、老親問題、思わぬ出費
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 11年連続、試験対策書売上ナンバーワン!編者は全国の証券会社・金融機関で「証券外務員」「FP」「コンプライアンス」を教える、研修のプロフェッショナルです。本書は、教え続けているプロだからこそ実現できた、スタンダードな試験対策書です。 <本書の主な特長> ・2025年版『外務員必携』に対応 ・「何が出題されやすいか」「どう備えるべきか」傾向と対策を章ごとに掲載 ・左ページ=問題、右ページ=解答・解説のわかりやすい構成 ・各問に難易度を表示 ・同時発売の『必修テキスト』へのページリンクも充実 ・巻末に本番レベルの模擬試験を収録 ※外務員資格試験には「一種外務員」「二種外務員」「特別会員一種外務員」「特別会員二種外務員」があります。本書は「一種外務員」試験をカバーした問題集です。 【目次】 第1部 科目別問題 1章 株式会社法概論 2章 財務諸表と企業分析 3章 株式業務 4章 取引所定款・諸規則 5章 協会定款・諸規則 6章 金融商品取引法 7章 金融商品の勧誘・販売に関係する法律 8章 付随業務 9章 債券業務 10章 投資信託及び投資法人に関する業務 11章 証券税制 12章 経済・金融・財政の常識 13章 証券市場の基礎知識 14章 セールス業務 15章 信用取引 16章 先物取引 17章 オプション取引 18章 特定店頭デリバティブ取引等 第2部 模擬試験
-
4.0★ベストセラー『怒らないこと』著者で、 仏教の原点を伝えるテーラワーダ仏教の長老が、 ブッダの実学をまっすぐ示す。 ★「半分勝つ。小さく完成させる。よく笑う」…… 日常に効く、ブッダの教えでもう悩まない、苦しまない。 ★「降りかかってくる問題」に目を向けるのではなく、 「受け止め方」に目を向けることが大事。 「働く意味がわからない」 「人間関係に翻弄される」 「怒りや劣等感で苦しい」―― すべて物事を複雑に考えて、悩まなくていいことで悩み、 人生に「つまずいて」いるから。 私たちは、「心の三毒(欲・怒り・無知)」をよく観察して、 与えられた環境に懸命に適応していくしかない。 環境に文句をいうのではなく、 その環境で生きる力を身につけるしかない。 そのためのヒントとは……。 ●苦手な人がいる → 「自分の役柄」を演じ切るだけ ●何のために働いているのかわからない → そもそも働くことに意味はない ●向いていることが見つからない → 「頼まれること」から考える ●他人がうらやましい → 「必要なもの」はすでに持っている ●みんな自分勝手でイヤになる → 他人に厳しいのは「自分を理解していない」から ●劣等感や優越感が強い → それを「発病」させないことを考える ●怒りが抑えられない → 「心の三毒(欲・怒り・無知)」をよく見る ……など、「今を精いっぱい生きる」 「環境に適応して生きる」考え方・実践を伝授。 悩んだり苦しんでいるなんて「損」! 本書で幸せに生きる道をひらきましょう。 ※本書は、著述・法話を精選し、時代に即した加筆・再構成を加え、今日の課題に応える一冊に編んだオリジナル文庫です 【目次】 《第I部 苦しみや悩みから解放される考え方》 ●第1章:「仕事」につまずかないヒント ●第2章:「人間関係」につまずかないヒント ●第3章:「自分」につまずかないヒント ●第4章:「ないものねだり」と賢くつき合うヒント ●第5章:「比較」で心をすり減らさないヒント 《第II部 幸せに生きる、善く生きる考え方》 ●第6章:「わかり合えない」理由を考えるヒント ●第7章:「わかり合えない」を乗り越えるヒント ●第8章:「逆境」に打ち克つヒント ●第9章:迷いを減らす「意味ある生き方」のヒント ●第10章:今日から動ける「意味ある生き方」のヒント
-
-稀代の経営者、稲盛和夫が逝去してから3年が経つ。今なお信奉者が多い稲盛とは何者だったのか。稲盛自身が師と仰いだ江戸時代後期の農政家、二宮尊徳の生き様、思想と重ね合わせ、あらためて検証する。 利他の心で“ど真剣”に生き、働くことが人生の価値を高める唯一無二の道――。この信念こそが稲盛哲学の原点だ。「動機善なりや」「小善は大悪に似たり」「逆境に手を合わせる」といった名言はすべて、ど真剣に働くことで精神性を高めていった稲盛の人生から生まれた。そんな稲盛の考え方は、極貧、一家離散の中で独学刻苦し、飢饉・洪水で荒れた農地を次々に再生した二宮尊徳の思想と見事に重なる。 思想家と呼べるリーダーの不在、ともすると効率だけを追求しがちな今だからこそ、2人のど真剣な生き様から学ぶべきことは少なくない。現代のビジネスパーソンにとっての2人の思想の意義を、楠木建氏が解説。
-
3.9
-
5.0
-
3.9超高収益を生む「キーエンス思考」をChatGPTで"完コピ" 「付加価値」を圧倒的なスピードで創造できる――。 仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版! 「成果に最短距離で突き進む仕事術」を理解し、ChatGPT活用で遂行していく。 日本屈指の高収益企業・キーエンスが成果を生む秘訣である「付加価値」をつくるためのプロセスを、ChatGPTで"完コピ"するための手法を詰め込みました。例えば、情報収集や分析はChatGPTに「仮説」を立てさせることで、新たな観点が生まれ、今手掛けている仕事をブラッシュアップできる。そして付加価値創造が実現し、成果が上がる――。全編を通して、日々の仕事で成果を上げることを念頭に置いたChatGPTのノウハウ本です。 キーエンス出身で、自身も業務にChatGPTを有効活用。コンサルティング業務でも顧客にChatGPT活用を提案し、年10億円の利益改善などを実現している著者が徹底解説します。 さて、ビジネスパーソンには、様々な立場の人がいます。本書は、どんな立場にあっても成果アップに直結させられる一冊です。例えば、こんなことが実現します。 【一般社員のあなた】経験を積む時間を"チート"してみるみる成長 【マネジャー(管理職)のあなた】部下が勝手に育ち、チームの業績もアップ 【経営者のあなた】優秀な社員ばかりになり、組織の生産性が2倍に 「サボっているわけではないのに、上司や同僚に評価されない」「なかなか部下が育たない」「自社、自部署の業績が上がらない」……。そんな悩めるビジネスパーソンにこそ読んで欲しい、AI時代に成果を上げるためのバイブルです。
-
4.5株主との対話による企業価値向上の実際 日本版スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コードにも対応 ロングセラー『IR戦略の実際』の後継本 ・本書は、企業が投資家に対し、投資判断に必要な企業情報を適時に、継続して提供するIR(インベスター・リレーションズ)の基本と実際、課題など包括的に解説します。 ・投資家との積極的な対話をうながす日本版スチュワードシップ・コードや、コーポレートガバナンス・コードの導入をきっかけに、IRの重要性はこれまでになく増しています。 ・企業価値向上の手段としてIRに取り組む企業の実例をふんだんに盛り込みました。 ・著者は、日本IR協議会の事務局長・首席研究員を務める第一人者です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本で唯一の民間非営利団体で「日本のIR活動の情報センター」が集約したIRの現状、動向、データの最新保存版。 大きなトレンドから細かい手順まで、包括的・具体的にIRの姿を浮き彫りにする構成。IRオフィサーが知っておくべき重点課題や法令・制度などの基本情報、IR実態調査結果などによる現況と見通し、実務上の留意点と多様な企業事例、資本市場の評価が高い企業の特徴、IRオフィサーに役立つデータ集を掲載。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 大きなトレンドから細かい手順まで、包括的・具体的にIRの姿を浮き彫りにする構成。IRオフィサーが知っておくべき重点課題や法令・制度などの基本情報、IR実態調査結果などによる現況と見通し、実務上の留意点と多様な企業事例、資本市場の評価が高い企業の特徴、IRオフィサーに役立つデータ集を掲載。 【目次】 ・はじめに ・日本IR協議会 倫理規程 ・IR行動憲章─企業価値の向上と資本市場の発展のために─ ・日本IR協議会の活動内容 ●Focus ・IRの重点課題 ・改善点を探る─「IRカウンセリング」から─ ・IR関連の法令・制度 ●Step1 IRの基本と概論─ IR担当者になったあなたへ─ ・IRの基本と課題 ・IR活動の現状を知る─「IR活動の実態調査結果」から─ ・外国人投資家を知る─その重要性と最新動向─ ●Step2 IR実務情報─ステップアップのためのIR実務情報─ ・IR活動の実行メニュー ・経営を支えるIR実行のポイント─IR行動憲章「実行の手引き」から─ ●Step3 IR優良企業を目指して ・IR優良企業の表彰とその傾向 ●Data IR関連情報のデータ集 ・人気アナリスト調査 ・国内証券会社リスト ・主要リサーチハウスリスト ・主要機関投資家リスト(信託銀行) ・主要機関投資家リスト(損害保険) ・主要機関投資家リスト(生命保険) ・主要機関投資家リスト(投信・投資顧問) ・IR支援会社概要 ・日本IR協議会会員一覧 ・IR用語集
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本で唯一の民間非営利団体で「日本のIR活動の情報センター」が集約したIRの現状、動向、データの最新保存版。 大きなトレンドから細かい手順まで、包括的・具体的にIRの姿を浮き彫りにする構成。IRオフィサーが知っておくべき重点課題や法令・制度などの基本情報、IR実態調査結果などによる現況と見通し、実務上の留意点と多様な企業事例、資本市場の評価が高い企業の特徴、IRオフィサーに役立つデータ集を掲載。
-
3.6IOWNとは何か NTTトップが全貌を明らかに ニュースなどで目にすることが増えた「IOWN(アイオン)」。 日本のみならず世界中で急速に広まりつつあるIOWNとは、一体何なのか――。 生成AIやメタバース、あらゆるモノがネットにつながるIoTの普及を背景として現在、世界の電力使用量は急拡大している。 莫大な電力が必要になっていくことは想像に難くない。 IOWNは、こうした状況の救世主となり得る、NTTが持つ最先端の光技術を使った次世代情報基盤である。 爆発的なデータ量の増加と、それに伴う大量の電力が消費されるであろう近い将来に、電力効率100倍(消費電力1/100)を目標に掲げるIOWNが必要とされることになる。 では、IOWNはどのようにサステナブルな未来を実現していくのか。 その技術的な背景や、我々の生活・社会に与える影響、具体的なユースケースなどをNTTのトップが徹底解説。 IOWNが世界に与えるインパクト、「IOWNの正体」を明かす。
-
3.0「長引く経済的な低迷から脱却するために、日本のビジネスパーソンが今こそ読むべき一冊」 ――ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院マーケティング学名誉教授 フィリップ・コトラー氏 「心でつながる企業の業績は、『ビジョナリー・カンパニー』をも上回るという。経営者の迷いを晴らし、前に進む力を与えてくれる本」 ――星野リゾート代表 星野佳路氏 ―――――― 〔「愛される企業」の7つの特徴〕 ・業界の常識を疑ってかかっている。 ・ステークホルダーの利害関係を調整し、価値を創造している。 ・従来のトレードオフの考え方を解消している。 ・長期的観点で事業をおこなっている。 ・「本業による自律的成長(オーガニック・グロース)」を目指している。 ・仕事と遊びをうまく融合させている。 ・従来型マーケティングモデルを当てにしていない。 多くの経営者にとって、これらの特徴は「当たり前のこと」かもしれない。 しかし、実際には、「高収益をあげている限りは」「業績がいいならば」など 「条件付き」であることがほとんどだ。 わたしたちが実証したのは、まったく逆の成功法則である。 7つの特徴を満たしているから、高収益や好業績につながり、 すべてのステークホルダーが幸せになり、 世の中が大きく変化しても成長し続けることができる。 「愛される企業=世界屈指の高収益企業」72社に共通する経営の本質とは? いまの日本にもっとも必要な経営書の決定版!
-
4.0
-
4.5■悪質なステルスマーケティングや「おとり広告」「しくじり炎上」など、企業の信頼を大きく揺るがす事件がいくつも勃発。マーケターは今、自身が顧客に向き合う姿勢を再点検すべきとき。広告、商品開発、コミュニケーションなど、多岐にわたるマーケ活動の中で、顧客との関係性をどう築くか。専門メディア・日経クロストレンドで反響を呼んだ特集を書籍化。 ■高岡浩三氏、小々馬敦氏、田中信哉氏、音部大輔氏、鹿毛康司氏、嶋浩一郎氏、佐藤尚之(さとなお)氏、並河進氏ら、第一人者たちが登場。
-
3.0
-
-市場規模が80兆円に達するIT業界。その動向・企業・職種・仕事の魅力がこれ一冊でわかります。業界構造の図解や、職種の解説、先輩の体験談はもちろん、社員食堂の紹介など、やりがいを多角的に伝える工夫を凝らしました。スマホに入れて、就活のお供にどうぞ。 ※紙の「IT業界徹底研究 就職ガイド2015年版」から主要記事を抜粋したものです。
-
-市場規模が80兆円に達するIT業界。そのIT業界向けに多くの雑誌を発行してきた日経BP社の取材力を生かし、IT企業は「どのような人材を採りたいと考えているのか」「どんな仕事をして欲しいと考えているのか」が学生に分かりやすく伝わるよう工夫を凝らしました。業界構造の図解や、職種の解説、人事担当者へのインタビュー、先輩の体験談など掲載。独特な用語が多い会社資料を読み解くのに使えるITキーワード集も収録。 2016年版となる本書は、LINE、KDDI、日立製作所の人事担当者に、採りたい人材像をインタビュー。サイバーエージェント、伊藤忠テクノソリューションズ、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)、SCSK、日本オラクルの先輩の体験談も紹介。 ※紙の「IT業界徹底研究 就職ガイド2016年版」から主要記事を抜粋したものです。
-
-ITの現場でロジカルシンキング(論理思考)を使って、相手に納得してもらえる報告や提案を組み立てる手法を解説した1冊。戦略コンサルタントが経験的に使っているノウハウやスキルを整理して体系化した。ITエンジニアがすぐに日々の仕事に生かせるよう具体的な事例を挙げて解説しており、論理思考に基づく場合と基づかない場合の違いを分かりやすく示している。説得力を高めたいITエンジニアは必読。
-
3.0
-
3.0優秀なIT人材を採用したいなら 職場環境を見直すべし ITを活用しない、事務職扱いされる、雑談すらできない、成長機会が得られない―― こうした職場はIT人材に嫌われます。優秀な人ほど、職場環境には敏感です。もし「優秀な人ほど辞めていく」と悩んでいるとしたら、それはきっと職場環境に問題があるはず。 では、どんな職場をつくればいいのか。そのヒントが本書に詰まっています。通常の事務職とIT人材では職場に求めるものが違います。大事なことは、IT人材が嫌がる環境を知ることです。つまり、アンチパターンを押さえることで、初めて「IT人材が働きたくなる」職場になります。 本書では、実例をベースにIT人材が嫌がる職場を多数掲載しています。それらを「なんちゃってIT職場型」「低プレゼンス型」「コミュニケーション不全型」など9タイプに分け、タイプごとに「では、どうすればいいのか」という対策をまとめています。 もし目次を見て「この職場はウチのことだ」と当てはまるなら、早急に改善しないと、どんどんと人が辞めていくかもしれません。企業のデジタル化に欠かせないIT人材は、DX花盛りの今、引っ張りだこの状況です。職場環境の整備で優秀な人材が確保できるなら、実施しない理由はないでしょう。
-
3.0IT×農業で有力な輸出産業に 第一人者が戦略の全貌を語る 農業を「質」で見ると、これほど有望な産業はありません。日本の農作物は世界中で高い評価を受けており、日本の熟練農家の技は“世界一”と言っても過言ではないでしょう。ただ、その多くは本人ですら言葉にできない「暗黙知」であり、スケールさせることが難しく、そこに課題がありました。 しかしここに来て、状況が変わりつつあります。IT技術の進歩により熟練農家の技を「形式知」にできるようになったのです。国内農家の底上げができるだけでなく、熟練農家の技を「知財」として安全に輸出することも視野に入りました。そうした取り組みを「AI農業」と呼びます。 「AI農業」の「AI」とは、人工知能(Artificial Intelligence)の研究をも包含する、農業情報科学(Agri-InfoScience)を指しています。すなわちAI農業とは、人工知能を含めた情報科学の知見を農業分野に適用することで、社会システムの変革を促す一連の取り組みなのです。 最新ITが「農業」を変革する――。その戦略の全貌が本書に書かれています。
-
3.8ITエンジニアをはじめ、ファシリテーションのスキルを身につけたい 全てのビジネスパーソンにおすすめの1冊! 頭で理解していても、なかなか身につかないファシリテーションスキル。 プロマネ経験を持つ著者が講師となり、誌上セミナー形式でノウハウを解説します。 ただ読むのではなく、実際にセミナーに参加する感覚で、スキルがしっかり身につけられます。 「ファシリテーションを身につけることは、例えば、乗れなかった自転車に乗れるようになることと同じです。 本書は、まず自転車でひとこぎするために作りました。そう、読む本ではなく、実際にやってみる本です。 ファシリテーションの本を読んだが使いこなせていない、と悩んでいる方にぜひ手に取ってほしいのです。 さあ、ファシリテーションをあなたの知識ではなく、スキルにするための第1歩を、この本と共に歩み出してください。」 (「はじめに」より) <目次> 【1章】 今すぐ使える!ファシリテーターの口ぐせ 【2章】 知っておこう!ファシリテーションの基本 【3章】 チーム脳の作り方
-
4.0どんな話し下手でも、人見知りでも大丈夫!営業成績が驚くほどアップするシンプルな質問術。お客様の裏ニーズ、上司の本当の考えを聞き出すコミュニケーション力。 著者がリクルートでの広告営業で劇的に営業成績が上がり、ナンバーワンになった秘密を理論化した。 ライバルに比べて売り上げが伸びない営業マン必読!
-
4.0アイスブレイクからクロージングまで4段階で「売れる商談」の組み立て方を紹介。売れている営業マンが無意識に行っている商談フローを体系化、「話術不要」で圧倒的に相手を説得できるテクニックを身に付けよう!
-
3.0みなさん、面白いアイデアって意外と変なところから突然降ってきませんか? これまでの僕の仕事を振り返ると、多くの場合、雑談の中でポロッと出た “どうでもいい話”が「それ! いいね!」となって、 面白いアイデアになっているからです。 アイデアって、関係性がないように見えるものほど、結びつくと面白くなるんですよね。 だから意外な方向、つまり「あさっての方向」が大事なんです。 「あさっての方向」にあるものは、一見すると「ムダ」と思われてしまうものばかり。 でもですね、僕はここで声を大にして言いたい。 「この子たちは、ムダじゃないんです! むしろ、とっても大事。 愛すべき存在であり、役に立つ子たちなんです。ムダはムダじゃないんです!」と。 「あさっての方向」を意識し、ムダを愛してみませんか? そしてムダをたくさん集め、それを生かし、 独創的なアイデアを生み出してみませんか? (本文より)
-
4.2アイデアを出せないという悩みを持つ人の共通点は、「すごいアイデア」を出そうとしてしまっていること。でも、「すごいアイデア」を出している人は、その何倍も「すごくないアイデア」を出している。ピカソは生涯2万点の絵を描いた。エジソンの死後、メモがびっしり書かれた3500冊あまりのノートが発見された。まずは「すごくないアイデア」をたくさん出すところから始めよう!ユニクロをはじめとするウェブ制作で高い評価を得、年間100以上の新サービスを世に送り出す面白法人カヤック。そのクリエイティブな組織づくりの秘訣は、トコトン楽しく働くことにこだわること。ウェブ業界が注目するブレストの達人の極意を解き明かす一冊。
-
3.2アイデアをビジネスで実現していくにはどうすればいいのか? ロジカルな左脳とクリエイティブな右脳、その両方を使いこなすヒントが「建築的思考術」にあった! 建築を学んだ後、企業のブランド開発を数多く手掛ける、ブランディングデザイナー西澤明洋氏が 同じく建築を学び、新領域を開拓、活躍するクリエイターへインタビューを敢行。 インタビューと考察から見えた「建築的思考術」の7つのキーワード 「構造」「コンテクスト」「コンセプト」「場」「考える」「共創」「構想力」から、 企画や交渉などあらゆる仕事でイノベーションを起こし、アイデアを実現させるコツを解き明かします。
-
-「アイデンティティ」の時代、自社ならではの強みで生活者の自分らしさを実現する、 チェンジリーダーのための事業創造・LTV経営の指南書 ・企業と顧客とのアイデンティティの「感応」による事業創造 ・LTV経営を実現するデジタル×新規事業創造の新理論 本書ではアイデンティティを軸にさまざまな企業事例を分類・解説し、これから日本企業が世界で勝ち残っていくための「アイデンティティドリブン(共鳴型)」事業創造モデルを提案。価値観・ライフスタイルに内包される顧客のアイデンティティと、提供価値や顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)に表出する企業のアイデンティティが相互に影響しあうデジタル時代の事業創造のあり方を解説します。 顧客の価値観・ライフスタイルの理解においては、その変化を的確に捉え、顧客との共鳴体験を生み出すためにRidgelinez独自の「Human&Values フレームワーク」を起点にした価値観の分析・洞察の方法と、持続性の高い関係性を生み出す手法を紹介。加えて、著者らが手がけてきた300以上の新規事業開発の事例とノウハウのエッセンスを詰め込んだ、デジタルの時代に求められる事業開発フレームワーク「Identity Driven Approach」を提示しながら、選ばれ続ける差別化された事業創造とLTV経営の実現に向けた実践的なアプローチ方法を解説します。
-
3.7「下町ロケット」神谷弁護士モデル 鮫島正洋氏、推薦! 技術立国・日本の競争力を高めるためには、知財の活用がますます重要となる。 知財を活用する際には、知財を駆使したビジネス的な分析、 すなわち「IPランドスケープ」が前提となる。 ものづくり・サービス業を問わず、すべての企業経営者・事業計画担当者が 「IPランドスケープ」を体得することによって、 次元の異なる新たな一歩が踏み出せるはずだ。 ――内田・鮫島法律事務所 鮫島正洋弁護士 企業の競争力の源泉として知財が注目を集めるようになってから、 20年近くが経とうとしている。しかし多くの日本企業では、 知財部門と経営とが相変わらず分離してしまったままだ。 知財の重要性がますます高まっているにもかかわらず、 グローバルな先進企業との差は縮まっているとは言いがたい状況だ。 そんな現状を覆すキーワードとして、最近注目されているのが IPランドスケープ(Intellectual Property Landscape:IPL)という手法だ。 最も広い意味では知財を中核に据えた経営そのものであり、 最も狭い意味では経営に生かすための知財情報を中心とする分析手法を指す。 本書は、このIPランドスケープを軸に、 日本企業の知財戦略のあり方について提言したものである。 グーグル、アップル、ダイソン、三井化学、ミネベアミツミの 5つのケースを使って実際に分析し、その概要を紹介する。 ◎IPランドスケープの「使いどころ」の例 競合他社の強みと弱みを明らかにし、「次の一手」を予測する M&Aにあたって、技術の側面からその評価を行う 異業種からの参入について、その兆しをつかむ オープン・クローズ戦略を決めるための選別 ――「IPランドスケープ」は、こうした製造業の「羅針盤」として機能する。 ◎本書で取り上げるケース -ケース1 アップルのデザイン戦略を読み解く -ケース2 異業種からの脅威の分析――グーグル自動運転の実力 -ケース3 競合他社の重点分野を読み解く――三井化学の注力先 -ケース4 自社にない技術を探し、補完する――ミネベアとミツミのM&A -ケース5 優等企業の「次の一手」を予測する――ダイソンの意外な参入分野
-
4.0カリスマだけに頼らない! 組織としての優秀企業の強みを徹底解剖 園芸用品→ペット用品→家電→コメ→マスク→法人ビジネスと次々と新分野に参入し、成功してきたアイリスオーヤマ。 その成長は大山健太郎氏の経営力に負うところが大きいのは確かだが、実動部隊としての組織/会社の強みが語られることはほとんどなかった。 本書では「人事の力」「共有の力」「地方の力」「失敗の力」「変化の力」の5つの視点から、経営の秘密を立体的に描き出す。 ◎5つの力とは 1 人事の力……人材を多面的に評価し、力を引き出す人事制度 2 共有の力……部門を超えた全社での情報共有の仕組み 3 地方の力……東日本大震災でさらに強くなった、地域密着の力 4 失敗の力……失敗を恐れず実行し、他社に先駆けて不具合を改善 5 変化の力……常に新しいジャンルに挑戦し続けるチャレンジ精神 ◎本書の主な内容 ・業績や実績だけで社員を評価してはいけない ・評価結果は社内の順位で知らせる ・昇進は「追い越し車線」もある3車線で ・「アイリスグループ内のSNS」の効能 ・アイリスの意思決定「4つの速さ」の仕組みとは? ・ユーザーと顧客は違う ・商品開発は「映画スタイル」 ・管理職の「情報の独占」を防ぐ ・東日本大震災の教訓を生かす ・震災が家電参入のきっかけに ・「被災者特別枠」で人材を採用 ・人材育成道場で若手経営者を育てる ・他社製品を使い倒し、100個の不満を挙げる ・消費者の意表を突く「なるほど」家電 ・アイリスの社内会議で話されていること ・引き算の商品開発 ・なぜ、次々業態を拡大するのか ・成長の理由は「運」ではない ほか
-
4.0日本人の“住み方”を変える「リノベる」の挑戦 海外を回って日本の住宅ビジネスに違和感を覚えた。 勝算もないまま走り続け、周囲を巻き込んで新たな住み方を提案する。 中古マンションを間取りから造り替えてしまうリノベーションが注目を集めている。 ベンチャー企業「リノベる」は、ウェブを使って消費者にワンストップでこのリノベーションを提供するサービスで急成長中だ。 同社を経営する山下智弘社長は元ラガーマンで、何度も挫折と失敗を繰り返しながら、挑戦し続けることで事業を軌道に乗せた。 知ったかぶりをするな、分からないことを周囲の人に教えてもらえる「明るいバカ」であれ――。 この信念を大切にして社内外を巻き込みながら最高のチームを創り上げつつある。
-
3.7DX(デジタルトランスフォーメーション)ブームは既に腐り始めている――。 今、日本企業はこぞってDXに取り組もうとしている。様々な企業によるDX事例がIT系メディアをにぎわし、バラエティー系テレビ番組にさえDXという言葉が登場するようになった。 政府機関や地方自治体でさえDXの必要性が叫ばれる。新型コロナウイルス禍の経済対策などのために導入したシステムが軒並み使い物にならないという失態もあり、政府もデジタル庁の創設などを打ち出し、「行政のDX」を推進する姿勢を明確にした。 しかし、日本で取り組まれているDXの大半は失敗に終わる可能性が高い。本書のタイトルに則して言えば、大半は「アカン!DX」なのだ。DXの主眼はあくまでもトランスフォーメーション、つまり変革である。その本質を理解しようとせず、いたずらに「デジタル」を叫ぶ。そんな例が多すぎる。 本書では、日本企業や行政のDXの「トホホな実態」を徹底的にえぐり出す。DXを叫びながら実行を現場に丸投げする企業の経営者の愚かさ、IT人材の採用・育成策のデタラメぶり、成果を出せないデジタル推進組織やIT部門の惨状、御用聞きでしかないITベンダーの無策など、数々の問題点とその原因を明確に示した。 一読すれば、日本企業や行政機関のDX、そしてそれを支えるIT産業の構造的問題が明確に見えてくるだろう。単なる一般論ではなく、あなたの会社、あなたが所属する組織におけるDXの課題が「見える化」できるはずだ。
-
4.2「オーナー視点から見た現代プロ野球史」が誕生! オリックス・バファローズ前オーナーの宮内義彦氏が34年間のオーナー生活で感じた喜び、悔恨、そして夢……。 強いけど赤字? 黒字だけど弱小? どっちもダメだ! “野球万歳!” オリックス球団のオーナーを34年間にわたって務めたオリックス シニア・チェアマンの宮内義彦氏。野球という競技を愛し、自らも草野球チームでプレーしてきた宮内氏がオーナーとして球団や球界の改革に挑み続けた間、日本のプロ野球史に残る様々な出来事があった。 阪神・淡路大震災による被災やイチロー選手の活躍と渡米、近鉄バファローズとの球団合併に端を発した球界再編、そして長期低迷からのパ・リーグ3連覇につながる復活劇……。オーナーである宮内氏は、絶対に諦めなかった。球団の成績も経営も。 「諦めないオーナー」としての全軌跡と、勇退した今だから言えるプロ野球の発展に向けた私案の数々。プロ野球の「オーナーの視点」が見えてくる1冊です!
-
3.0世間をにぎわせた村上ファンド、スズキやセブン&アイを標的にしたサードポイント、西武と対立したカーライルなど、近年日本でもアクティビスト(「物言う株主」)の存在感が強まっている。 彼らは世界有数の大企業であっても経営陣に立ち向かい、ビジネスの一部に口出しするだけにはとどまらず、取締役会メンバーの一人ともいえる影響力を持つようにまでなっている。 本書は、取締役会における攻防から、放逐される経営陣の悲喜こもごもまで、アクティビストと取締役の間で実際に起こった出来事をストーリー仕立てで描いた一冊。マイクロソフト、ヤフー、ヒューレット・パッカード、デュポン、アラガンなど、近年世界で起こった主要なアクティビスト関連の争いについて、変革推進派、反対派双方の視点を盛り込みながら、そのとき取締役会では一体何が起こっていたのかを浮かび上がらせる。
-
4.0企業価値を高めたいなら経営にアクティビストの視点を入れよ! 具体的事例を基に新しいキャピタル・マネジメントの実践手法を提示。 ■PBR1倍割れは経営者として“恥ずべき”問題である CGコード施行から7年。「形式面」での変革は進んだが、主要KPIと定義されたROEは伸び悩み、上場企業としての究極のKPIともいうべきPBRも1倍割れ企業が続出する異常事態が常態化している。 企業価値の向上はまさに喫緊の課題だ。 ■アクティビズムをヒントに企業価値の創造を目指せ! 本書はこうした問題を、実際の企業ケースを基に、(1)コーポレートガバナンス改革を批判的にレビューする、(2)アクティビズムを企業価値向上の「教科書」として活用する、(3)「バリュー投資の父」ベンジャミン・グレアムに学ぶ、(4)ケースを分析し詳細に紹介する、(5)企業がアクティビストに先んじて処方箋を実践することを提言する――の5つのポイントから整理・分析、課題解決への処方箋を提示するもの。 身売り・MBO、株主還元、最適資本構成、事業売却・スピンオフなど主要アプローチごとに、アクティビズムの主張を活用した「処方箋」を実践し企業価値向上を実現した企業ケースを詳細に分析。アクティビズムの手法を企業価値向上策に取り入れることで究極のアクティビスト対策にもなるという「アクティビズム・インテグレーション」による経営改革の実践を提言する。
-
3.8●「聴く」ことは仕事を推し進めること 相手の話をじっくり聞くことで相互の理解が深まるという「傾聴」。実際、心理的安全性を高めることで相手が話しやすくなるなど、コミュニケーションが改善する効果がある。 そういった「カウンセリング」的傾聴術から、本書では一歩進めて「ビジネスを前に進める」ことを意識する。「聴く」ことによって、話を自分の思う方向に仕向ける「アサーティブ」なコミュニケーションも可能になるという。 著者は数多くのビジネスコミュニケーション研修で、傾聴が仕事に役立つことを説いてきた。本書ではビジネス現場の視点から傾聴の基本を語る。 ●アンガーマネジメントやアサーティブ・コミュニケーションの視点も必要 純粋に「聴く」というのは意外と難しく、様々な感情が巻き起こってきて口を挟みたくなる状況が何度となく生じる。そのときにいかにフラットな気持ちで話を聴けるか。解決策としてアンガーマネジメントで学んだ「6秒待つ」「メモをとる」ということが活きてくるという。また、日頃からバイアスを取り除く訓練も必要だ。 一方で、アクティブに聴くには相手から話を引き出す「質問する力」も必要だ。質問することでコミュニケーションのイニシアティブを取り、仕事を思うようにコントロールすることも可能となる。 本書では、リモートワーク時や集団的コミュニケーションなどのシーンを含めて、様々な事例を盛り込んで解説する。
-
3.7
-
3.0“成功体験”を棄てろ! ! ――缶チューハイ、第3のビール、糖質オフ……怒濤の連続ヒットはいかにして実現したのか? 全社一丸の大変革を、業界に精通したジャーナリストが活写! ! ビール類市場でシェアNo.1を誇るアサヒビール。 言わずと知れた主力商品「スーパードライ」は、1987年の発売以来 ドライビールの先駆けとして30年間不動のトップに君臨してきた。 しかしこれは同時に、アサヒが長らくひとつのヒット商品に 依存し続けてしまったことも意味している。 スーパードライはいつしかアサヒにとっての「聖域」となり、 経営資源の多くはスーパードライに集中してきた。 このためか、競争が激しいビール類市場の首位でありながら、 アサヒは30年近くも目立ったヒット商品がないという事態に陥っていたのである。 ところが、缶チューハイから第3のビール、糖質オフまで ヒット商品や技術面でのイノベーションが、2016年ごろからいくつも重なっている。 アサヒはいかにして成功体験を超え、自ら変革へと動き出したのか。 本書は、マーケティングから研究開発、営業の現場まで、 さまざまな人へのインタビューをもとに、全社一丸のその変革の模様を描き出す。 過去の「成功体験」にとらわれ、「聖域」が存在する企業は多い。 それらとどのように向き合い、どう乗り越えていけばよいのか、 アサヒという一企業を通してそのヒントを提示する。
-
4.0●コロナ禍で変わりゆくコミュニケーション オンラインでの情報のやりとりが格段に増える一方で雑談が減り、本来意図するコミュニケーションが難しくなったという声を聞くことが多くなった。企業側は、出社率を低く抑えつつも、人と人が交流できる場所を作ることに躍起だ。 一方で、AIの発展により、コミュニケーションを「計量する」ことも可能になり、ムダな動きを排除したり、コミュニケーションの「質」に集中することも可能になった。また、人の心理を分析した上での「行動経済学」も大いにプレゼンに役立つ。 本書は日経産業新聞での著者の連載「コミュニケーションのつぼ――人と組織の動かし方」より評判のよいものをピックアップし、加筆・修正して構成している。伝え方・コミュニケーションの最新事情を、著者の体験も踏まえた上で語る1冊である。 ●コミュニケーションの「裏側」には何があるのか ミーティングの「質」を目や口や声質などで判断し、スコアリングする会社、得意なことではなく、苦手なことからアイデアを見つけ出そうとする会社、あるところに注意を集中させ、交渉を優位に進めようとする手法(アンカリング)など、様々な知見からコミュニケーション改善のヒントを提供する。これらを知ることで、自分が戦略に「はめられること」を避けることもでき、交渉を優位に進めることも可能となる。
-
-ステークホルダーの信頼を獲得せよ グローバルでニーズが高まる「アシュアランス」を スペシャリストが徹底解説 生成AIの著作権侵害リスク、サプライチェーンを含めたCO2排出量の正確性、海外のクラウド利用のサイバーリスク、 これらについてうちは大丈夫と言い切れる経営者はどれほどいるでしょうか。ビジネスのブラックボックス化が進み、 経営者がステークホルダーに説明責任を果たすのが難しくなっています。 そこで注目されているのが、第三者からの信頼の付与であるアシュアランスです。
-
-次世代を担うキーパーソンへの独自取材を通じて、アジアのこれからを描き出すドキュメンタリー。 日経の各支局が直接取材し、知られざる素顔を描き出す。 アジアに関心のあるビジネスパーソンは必見だ。 ロドリゴ・ドゥテルテ(フィリピン大統領)~正義か無法か 剛腕ふるう「仕置き人」 蔡英文(台湾総統)~「新・鉄の女」、民主化の旗守り抜けるか ジャック・マー(アリババ集団会長)~ネットの扉 狙うは20億人の経済圏 野村達雄(中国/米ナイアンテックシニアマネジャー)~ポケモンGO開発者は残留邦人3世 藩寧(中国/ファーストリテイリング地域代表)~「安くて良いモノ」日本流買い物観の伝道師 カイラシュ・サトヤルティ(インド/ノーベル平和賞受賞者)~闇と向き合い 児童8万人救済 アローク・ロヒア(タイ/インドラマベンチャーズ グループCEO)~4大陸またぐ「コーラ」の黒子役 ラグラム・ラジャン(インド準備銀行前総裁)~金融危機を予言、祖国思う改革者 シャルミーン・オベイド・チノイ(パキスタン/映画監督)~タブーを直視、2度のアカデミー賞 李娜(中国/元テニス選手)~中国人が憎み、愛した世界王者 マニー・パッキャオ(フィリピン/プロボクサー)~6階級制覇 始まりは260円 馬化騰(中国/騰訊控股=テンセントCEO)~9億人集うSNS、新産業創造担う ケルビン・テオ(マレーシア/ファンディング・ソサエティーズ創業者)~金融に眠る商機 国境越え結ぶ 唐鳳(台湾/プログラマー)~ITの神童 性差超え多様性輝かす グエン・ティ・キム・リエン(ベトナム/農民)~ピュリツァー賞被写体の少女 悲劇語り継ぐ ほか
-
-コロナ禍に見舞われた世界。だが、アジアが世界経済を牽引するトレンドは変わりはありません。2050年には世界の国内総生産(GDP)の約5割を占めるとようされています。ファンド資本主義の繁栄、共産党キャピタリズム、日本の先を行く様々な改革--。成長への期待で多くの企業と投資家を引きつけるこの地域は、さまざまな価値観が交錯する混沌の場でもあります。欧米の経済常識を飲み込み消化するアジアの多様性から、新しい資本主義のかたちが浮かび上がります。それこそがアジア資本主義です。 本書で考える「アジア資本主義」を構成する要素は次の4つです。 I 受容性(市場原理を受け入れる) II 折衷性(伝統・文化と折り合いをつける) III 競争性(個性を主張する) IV 拡張性(多様性が広がる) 「受容性」「折衷性」「競争性」「拡張性」――これらの要素を総合した「アジア資本主義」とは何かの解を明らかにします。 筆者はアジアの価値観や経済の仕組みが、世界均一の尺度という意味でのグローバルスタンダードになるとは考えていません。20世紀が米国の世紀であったのと同じように21世紀がアジアの世紀になる可能性は大きくないでしょう。ソ連崩壊によって世界で唯一の超大国となった米国の覇権が、簡単に消えていくとも思えません。資本主義のかたちも同じで、アングロサクソン型の市場原理主義も消えることはありません。しかし対抗軸は必ずあらわれる。それが「アジア」なのです。
-
-【生き残りをかけた知恵の戦い】 米国主導「戦時」の半導体戦略、中国のデカップリング対応と軍民融合発展戦略、外交孤立の台湾の選択、メガFTA掛け持ちのASEAN、アジア・ゼロエミッション共同体構想――。本書は、東アジアの各国・地域のほか、西側陣営をリードする米国や「グローバルサウス(南半球を中心とした途上国)」の一角として発言力を強めるインドの動向を調査し、戦略物資の半導体をめぐる攻防や地域エネルギー安保の問題も分析。相手に対する脅威認識から始まる安全保障の措置が逆に相手の脅威となり、際限のない軍拡競争を招いてしまうことを「安全保障のジレンマ」という。経済安保の諸政策も取り組み自体が新たなリスクを生じさせるリスクがあり、地域におけるリスク軽減策についても検討した。分断を超えてどのような経済安保戦略を構築すべきかを問う。
-
-■利益でトヨタの利益を上回る韓国のサムスン。7億人の顧客を抱え、株式時価総額をGAFAと争うアリババ。ソニーとパナソニックの合計を上回る鴻海の売上高。半導体世界ビッグ3の台湾企業、TSMCに株式時価総額で対抗できる日本の製造業は一社もない。日本のコンビニの戸棚を開ければサラダチキンなどタイのコングロマリット、CPの商品がずらりと並ぶ――。 ■アジア企業に関する知識は、いまや日本のビジネスパースンにとって必須です。中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、インドなどアジア各地域の強大企業の活動は世界のビジネスの姿を大きく変貌させてきています。そのビジネスモデルは受託生産、ファブレス、垂直統合、タイムマシン経営、国家資本主義など多種多様ですが、半導体で台湾のTSMCの動向が世界から注目されているように、こうしたアジア巨大企業のビジネスモデルの理解なくして、世界の経済は理解できないと言っても過言ではないほどです。そのビジネスモデルを知ることは、グローバル化した世界のいまを理解することに直結します。 ■中国はじめ、アジア各地域の豊富な取材経験をもつ日本経済新聞記者が、世界の貿易・サプライチェーンを支える、日米欧とは異なるアジア独自のビジネスモデルのすべてを、成功・失敗の両面、ライバル企業やアジア各地の制度、政策、文化にも触れ、最新情報をもとにわかりやすく解説します。
-
3.6早く帰れ! そして稼げ! 4年間で年間労働時間を約180時間削減した働き方改革のトップランナー。 残業削減に一定のメドをつけ、収益拡大へ舵を切るまでの全社一丸となった業務改革の全貌を徹底解説。 ■働き方改革を断行し、4年弱で欧米並みの年間労働1800時間を達成した味の素の改革を描いた解説書。年間労働2000時間の日本的働き方では世界のビッグプレーヤーと渡り合えないとして、トップダウンで働き方改革に心血を注ぐ西井孝明社長、逆風にさらされながらも改革を成し遂げた役員、社員らの奮闘を紹介するとともに、短期間で残業削減を実行できた同社のノウハウを余すところなく盛り込む。 ■味の素は、安倍晋三首相が本年3月に視察するなど、働き方改革先進企業として社会的評価が高いが、その全貌を解説した本などはまだない。本書では、社長や幹部から現場まで多くの社員を徹底取材。残業削減を短期に実現した絶好のケーススタディとなっている。取引先が多く、工場などの現業部門を有するメーカーの全社改革は、時短に悩む企業にとって大いに参考になるだろう。改革のプロセスや葛藤を生の声で伝えており、臨場感にあふれるヒューマンストーリーとしても読み応えがある。 ■働き方改革法が2019年4月に本格施行したが、個々の企業は「ノー残業デー」の設定などありきたりの対策を実施している程度で、思うような効果を上げていない。1年間の猶予を与えられた中小企業も2020年4月から規制の対象となるが、対応は遅れている。なぜ働き方改革が必要なのか、どうすれば社員も納得した改革ができるのか――残業削減と業績向上の両立に悩む経営層や管理職、一般社員には課題解決の参考となる具体的なノウハウが満載。 ■本書は、多くのアクセス数を集めた、日経電子版「ストーリー・残業なし奮戦記」の連載(19年5月)を核に加筆してまとめたもの。経営層・管理職から女性、若手と幅広い読者が味の素の働き方改革に関心を寄せた。
-
3.0「人に優しくなければ技術ではない」――。日経BP社が発行する技術系メディアの専門記者200人が選んだ「すごい技術」を分かりやすく解説した一冊。紹介するのは、貼り直せる湿布薬はどうやって実現したのか、コンピュータ将棋はどうやってプロ棋士を破ったのか、といった身近な話題から、超高層ビル「赤プリ」をいつの間にか解体した建築技術や“切らない手術”を実現した治療技術実現法まで55種類におよぶ。電子・機械・医療・建設・ICTの有望技術が1時間強で展望できる。
-
-本書は、中堅中小企業経営層に向け、東南アジア(ASEAN)でのM&Aという「成長戦略」を示すものである。 日本国内市場は、人口減少・高齢化等により縮小の一途にある。この状況下で企業が生き残るためには、世界規模でのビジネス展開が必須となる。とはいえ、東証一部上場企業の約50%が海外進出を果たしているのと比較して、中小企業は約4%。ほとんどが海外進出に目を向けていないのが現状である。 だが、昨今の社会状況でテレワーク化が進み、距離や国境によるハードルは低くなっている。中小企業経営者の目を海外に向けさせるには絶好の機会といえよう。 海外への新規進出は時間がかかるが、M&Aなら海外マーケットにすぐ参入することができる。スピード感ある事業継続・拡大を実現できるのだ。人材やネットワークといった経営資源が限られている中堅中小企業こそ、海外M&Aは有効な手法なのである。 特に本書は対象とするマーケットを、成長・拡大が著しいASEANに絞った。東南アジアは地理的に近く、時差は1~2時間。親日派も多く、人材マネジメントが行いやすいことが利点である。 5カ国(シンガポール・マレーシア・インドネシア・ベトナム・タイ)でのM&A成約事例を紹介しながら、日本M&Aセンター海外事業部ならではの成功に導くノウハウを開示。中堅中小企業にとって、優秀な海外人材やローカルネットワークを獲得する“M&Aによる海外進出”を、より身近なものとする。
-
3.7テレワークで社員の生産性が下がるのはなぜか? 多くの企業では、経営環境が激変し、新しい働き方の模索が続いている。そのなかで、社員の自律やモチベーションの低下に悩む管理職は多い。 「成果目標や役割をわかりやすく示した」「高機能の業務管理システムを導入した」――。社員の自律を促す工夫をしても、多くの企業では期待したほどの効果が出ない。むしろ、上司の指示に真面目に従うだけの社員ばかりが増えていないだろうか。 いまこそ、自立支援の再考が必要なとき。社員がポテンシャルを存分に発揮するのは、仕事の面白さを自覚したときから。いつもの仕事に「遊び」を呼び込み、その面白さを実感してもらおう! いまひとつモチベーションが上がらない社員にとって何が足りないのか、どんなきっかけが社員を動かすのか――。著者自身の企業でのフィールドワークに基づくコンサルティング経験に裏打ちされた事例をとおして、課題の所在と具体的な改善策をわかりやすく解説。 真面目さの向こうに活路を見出す、新しいマネジメントを提示する。 ■目次 第1章 進まない社員の自律 第2章 「真面目さ」を超えよう 第3章 自分に合わせて仕事をクラフトする 第4章 管理者は仕事を面白くできる 第5章 社員が自律していく組織へ
-
3.5
-
4.0Uber(ウーバー)とAirbnb(エアビーアンドビー)――とんでもない破壊者たちの闘争と熱狂の全軌跡! ベストセラー『ジェフ・ベゾス 果てなき野望』著者、ブラッド・ストーンの最新作 2社ともまだ創業から10年未満。しかし、2社合わせた会社評価額は10兆円とシリコンバレーでもまれにみるような成長を遂げている。 UberとAirbnbはいかにして、成功をつかんだのか? 世界各国、各都市での規制との戦い、既得権益を握る企業との闘争、次から次へと現れるライバルたちとの競争、そしてユーザーやコミュニティの熱狂、さらにはUberのカラニックCEO解任。 アメリカのテクノロジー記者として圧倒的な取材力を誇る著者が、その全真相を描く。 ■UPSTARTとは? UPSTART(アップスタート)とは、成功を収めた人物で、経験豊富な年長者や確立された手法をあまり尊重しない者のこと。そう、シリコンバレーの破壊者たちのことだ。 彼らは製品をめちゃくちゃ磨きあげ、大勢のユーザーを味方につける。そしてどんどん成長する。 時として冷徹に。場合によっては倫理を若干犠牲にしながら。 規則を守って慎重になりすぎたら、ライバルに負けてしまうのだ。 ■創業者たちのことば ブライアン・チェスキー(Airbnb創業者兼CEO) 「とにかく早く成長すること。レーダーに引っかからないくらい小さいか、制度として認められなくてはいけないくらい大きいかのどちらかでいたい」 トラビス・カラニック(Uber創業者兼前CEO) 「実際に成功するまでは成功しているふりをするんだ」
-
4.3仕事もプライベートも、大切なのはたったの“20%” 8年間にわたってH&Mジャパンの代表を務め、 数々の日本女性のキャリアを後押ししてきた著者による チャレンジを楽しむための秘密。 著者のクリスティン・エドマンさんは、 日本人の母とアメリカ人の父の間に生まれ、 日本で育ちました。 2007年からのアジア進出に伴い、 H&Mジャパンの立ち上げから2016年まで 代表取締役を務めています。 「将来は専業主婦になる」と思って育ち、 最初は今のようなキャリアを築くことになるとは 全く思っていなかったようです。 著者に初めて会ったのは、 H&Mを退任された直後でした。 20代~40代の女性たちが集まる会の中で、 2児の母でもありながら、 自分の夢を諦めずに働くためにどのような工夫をしているか。 また、そうした考えを社内でどうやって浸透させたか というような話をされていました。 評価基準としての「NEXT ME」、 “20:80”の考え方、 失敗に対する捉え方、 企業文化の見極め方、 「What vs How思考」、 リーダーの責任としてのワークライフバランス……。 H&Mの本社がある スウェーデン流の考え方や発想が非常に面白く、 もっと多くの人に伝えたいと思って作ったのが本書です。 巻末には、著者の夫で早稲田大学商学部准教授のジェスパー・エドマン氏に、 日本の女性が働く環境や家庭内での家事分担についてインタビューも収録しました。 自分の可能性を信じ、家庭や仕事のバランスを掴むためのヒントが詰まっています。 (編集者より)
-
4.3トヨタに迫る GAFAの脅威 アップル、グーグル、アマゾン…。デジタルの覇権を握る巨大企業たちがついに自動車産業に参入してきました。これにより、車そのものが、そして自動車産業が大きく変わろうとしています。 車そのものは、「人を乗せて移動すること」とは別の新たな価値を提供することになるでしょう。例えばアップルなら、アイフォンとアップルウォッチ、そして車がシームレスにつながった形での新たなライフスタイルの提案に期待が膨らみます。既にテスラが提供している、オーバー・ジ・エア(OTA)という遠隔操作が普及すれば、車は買った時点からどんどんと性能が上がっていきます。車のかつての価値は色あせ、全く別次元の価値が備わることになるでしょう。 一方、自動車産業はこれまで、完成車メーカーが車の開発、製造から販売網の構築までを一貫して手掛けてきました。しかし、世界最大の電子機器製造受託サービス(EMS)企業である台湾・鴻海精密工業をはじめ、電気自動車(EV)向けプラットフォームを供給する巨大企業の出現に伴い、完成車メーカーは「企画・開発」と「製造」の分離という「解体」を迫られる可能性が出てきました。 本書は、日本経済新聞と日経クロステックの合同取材班が総力をあげて取材しました。伝統に縛られた殻を破り、新しい産業へと生まれ変わろうとする自動車産業の未来を読み解く一冊です。
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 iWatchは、ロレックスやルイ・ヴィトンを思わせる高級な腕時計端末になる? 本書はiPhone 5以降のアップル製品を分解し、そのデザイン思想を徹底分析。 スティーブ・ジョブズ後のアップルが進めてきたブランド・デザイン戦略は何か。 そして、この先、アップルはどのようなデザインでイノベーションを起こしていくのか。 新型iPhone、そしてiWatchの登場が待たれるなか、その未来予測も含め、アップルのブランド戦略を徹底して解説する1冊。
-
3.0架空の中堅コンビニチェーンを舞台に、人気講師による超実践的研修を再現。具体的な商品・サービス例をもとに、 「欲しい!」「買いたい!」という顧客心理からマーケティングのすべてを分解。売れる商品の秘密を解き明かします。
-
-「会社を経営する覚悟はついたけれど、何をどれくらいやればいいのか分からない」 そんなことを考えているすべての経営者、後継ぎ予定者のために、オーナー企業経営専門誌の記者が、「100点満点ではないけれど十分な、70点の経営」を紹介し、解説する。 <本書の特徴> ●偉人伝やノンフィクションのような、参考にならない経営者ストーリーではない、「参考にできる経営」だけを選りすぐって紹介 ●生産性改善(カイゼン)の専門家でもある筆者が、「セル生産」と呼ばれる手法の本質を具体的な事例を使って解き明かす ●市場縮小、人口減少に直面しても継続していける会社の在り方について、具体的な会社を例に挙げながら明示する <こんな事例をご紹介> ・月次決算の定義と、未導入の会社が最初にすべきこと ・200種以上の資格に手当てを出して人を育てる製造業 ・「選ばれる採用」「短期的な成果に報いない」ことで成長する自動車販売店 ・大ヒット商品を生み出しても不採算品整理を進める超堅実メーカー ・地元のスーパーや介護施設を次々再建するビルメンテナンス会社
-
4.0アトツギが「家業を円滑に引き継ぎ」「新たなビジネスを立ち上げる」ための55のこと 「ベンチャー型事業承継」の提唱者による初の著書が登場! 早稲田大学入山章栄教授 「後継者こそ知の探索を」 深井龍之介氏(歴史を面白く学ぶコテンラジオ) 「ポスト資本主義を担うのはアトツギだ」 本書が取り上げる55のこと(抜粋) 無関係な世界はない、アトツギこそ知の探索を/家業で感じる「違和感」を記録していく/「承認欲求」から始めた事業はうまくいかない/スリーサークルで人間関係を整理する/どんなチームが理想なのか。事例のシャワーを浴びる/同族承継の「カオスと非論理性」と向き合う/金融機関のアポに無理やり同席する/行動だけがチャンスを生む――などアトツギベンチャー思考の数々
-
4.0М&Aの専門家には「両手仲介会社」と「片側アドバイザー」がいます。シンプルに言えば、両手仲介会社は売り手・買い手からの「両手取り」をする「仲介者(ブローカー)」、片側アドバイザーは売り手・買い手どちらかから「片手取り」となる「助言者(アドバイザー)」です。 近年のМ&A業界において、「両手仲介会社」による問題は深刻であると、筆者は指摘します。売り手と買い手の双方と契約し、両者から手数料を受領するのが両手仲介会社です。売り手は「少しでも高く売りたい」、と同時に買い手は「少しでも安く買いたい」と考えるのは、М&Aにおいて極めて自然なことです。しかしながら、その両者の味方をしようというのが両手仲介会社です。これには構造上の無理があり、「利益相反行為」だと言われても仕方がないケースも見受けられ、ここ数年はその弊害が目に余ることもあると筆者は語ります。 本書は、最近よく出版されるような事業承継や、中小企業М&Aに限定したノウハウ本ではありません。専門家の視点で、近年のМ&Aについて知っておくべきことを、網羅的に記しています。そのため、世間の注目を浴びた事例を紹介するとともに、急速に存在感を高めている「投資ファンド」についても詳しく触れました。 М&Aを検討する時、専門家の協力を仰ぐにせよ、事業承継を行おうとしている企業オーナーや、М&Aについての理解が十分ではない一般のビジネスパーソンにとって、必要な知識や理論武装をするために一助となり、示唆に富む一冊です。
-
3.8人生の課題は、すべて対人関係の課題である――。 こう語ったアルフレッド・アドラーの心理学を、ビジネスでのコミュニケーションに応用する手法をわかりやすく、具体的に解説します。 どうすれば、上司、同僚、部下と良好な人間関係を築き、仕事の成果を継続して高めていくことができるのか。 そのキーワードは「距離感」。アドラー心理学を長年研究し、日々の仕事に生かす道を模索してきた筆者は、 「近づきすぎず、遠ざけすぎない」「押しつけず、遠慮しない」コミュニケーションこそが、理想の関係を創り出すと説きます。 悩みを抱える多くのビジネスパーソンに読んでいただきたい1冊です。
-
3.9
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●得に飛ぶANA & JAL完全攻略2025 旅行のコストが高騰する中、強い味方となるのはやはり「マイル」だ。ANAとJALのサービス強化により、電力や光回線などの契約だけで数千マイルが得られる時代になり、キャンペーンを利用すれば国内旅行にはすぐ行ける。ANAの新機材「B787-10」やJALの新たな特典制度「JAL Life Statusプログラム」なども含め、旅がぐっと「安く」「楽しく」なる最新情報をお届けする。 ●細かすぎる羽田空港 裏最新案内 旅行、出張、観光と様々な目的の人が行き交い、混雑する“日本の玄関口”羽田空港(東 京国際空港)。効率的に利用する方法はあるのか。知られざる最強ショートカットから行列 回避術、空港限定グルメまで、歩いて見つけた「細かすぎる最新案内」がこれだ! ≪主な内容≫ パート1:マイレージ パート2:ANA パート3:JAL パート4:格安旅行 ◎細かすぎる羽田空港 裏最新案内 空港攻略マップ 最強アクセス術 得ワザ 観光スポット ビックリ自販機 穴場グルメ
-
3.9「儲からない」にはちゃんと理由がある。 マーケットが好調な時には、身の回りのいたる所に投資に関する情報があふれます。「投資は誰でもできる」「市場が好調なら誰でも儲かる」そんな言葉につられて投資を始めたものの、「期待ほどの結果を得られていない」「思わぬ損をしてしまった」という声は少なくありません。 なぜ、儲からないのか? それは投資の原理原則を理解していないから。情報に踊らされ「自分の頭で考える」投資ができていないからではないでしょうか。 ネットを使えば最近のトレンドからおすすめの銘柄まで様々な情報を得ることができる時代ですが、投資の考え方の基本については誰も教えてくれません。 本書では、証券会社で何万人もの個人投資家をみてきた著者が、その長年の経験から、投資家が陥りがちな落とし穴、そして、成功する投資家が大切にしている考え方の基本について紹介します。
-
4.0★ケンブリッジ大学が800年かけて築いた勉強法を知ろう ★ニュートン、ダーウィンなどの天才、ノーベル賞受賞者、世界的リーダーや大富豪…圧倒的な天才たちの「学び」を知る ★ケンブリッジ大学教授が教える 自分の想像をはるかに超えた知に、早く、遠く到達できる 「学び」という問題を、800年間に渡り考え抜いた組織、それがケンブリッジ大学です。 ケンブリッジ大学は、今も世界にインパクトを与える人材を輩出し続けています。しかし、もともと天才である人たちが入ったからではありません。ケンブリッジが持つ、学びのしくみがあるからです。このしくみを知り、自分のルーチンワークに組み込めば、「学びの奇跡」を起こせます。 この本でいう学びとは、一過性の学びではありません。人生を通じて自分の支えになり、できるだけ遠くに連れて行ってくれる学びのことです。 その学びのキーワードは「コミュニケーション」です。ひとりで机に向かってすることは、学びのサイクルの一部分にしかすぎません。この本で説明する学びのコミュニケーションを身につけましょう。 この本は、人間の本質的な学びとは何かを知り、自分の学びに生かせる本です。 ケンブリッジ学びの掟 〈その1〉:コミュニケーションを学びの中心に据える 〈その2〉:コミュニケーションを通じて、特別な人づきあいを育てる 〈その3〉:学びはひとりでやらない 〈その4〉:学びの真剣勝負をする! 〈その5〉:時間の流れにまどわされず、学び続ける 〈その6〉:日々の生活を学びにする 〈その7〉:奇跡はそこかしこに埋まっていることを忘れない
-
3.0店内で悪ふざけした写真をアップしたり、来店客の個人情報を勝手につぶやいたり。 メニュー表記と異なる食材を使ったり、店を辞める時にレシピや顧客リストを持ち出したり。 お客が話しかけているのに気づかなかったり、仲間内で使うようなタメ口で話しかけたり。 ちょっと前までは考えられなかったような“常識を知らない”スタッフによって、閉店や倒産を招く――そんなトラブルを未然に防ぐためのノウハウをまとめました。 飲食店で起きる50のトラブルシーン別に、すぐに実践できる具体的な取り組み方法を紹介すると同時に、「店がどうあるべきか」「経営者や店長、スタッフがどう考えるべきか」という飲食業の基本についても理解を深めることができる、スタッフ教育に手放せない必読本です。
-
3.7
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日経トップリーダーに掲載され、好評だった特集や連載を再編集。 多くの中小企業経営者から、税務関連だけでなく、新規ビジネスや事業の再構築まで相談を持ち掛けられる税理士が、これからの事業承継のスタイルや事業を承継する経営者の心構えやすべきことを解説する。 <目次> 第1章 激しい変化に適応する新・事業承継 会社を強くするスマートな事業承継を考える 時代の変化に対応するために再構築を柱とした承継を 第2章 後を継ぐ者 先輩経営者が具体的に教える 後を継いだ経営者がやるべきこと、やるべきではないこと 三代目イノベーション「会社の寿命」はこれで決まる 第3章 変革のキーワードは「六方よし」 伸びる会社は「六方よし」若い世代が実現する未来型経営 第4章 親族外承継とM&A 「親族外」への事業承継 経営権と支配権を誰に、どう譲るか 1億円未満のスモールM&A時代 第5章 経営者のための相続対策 会社や社員、家族に迷惑をかけないために 知っておきたい10のこと
-
4.0
-
3.2「おわびのしるし」の裏に何がかくされているのか? 持ち家なら家賃は払わなくてよいのか? なぜ各駅停車ではなく快速列車に乗るのか? なぜ深夜タクシーに割増料金を払うのか? ケチな人は本当にケチなのか? その疑問に、経済学(の考え方の1つ)でお答えします! 「失恋の痛みからの抜け出し方」「接待を成功させるにはどうしたらいいのか」といったことから、金利決定のメカニズム、大規模交通インフラなどの社会資本整備の理解まで、「機会費用」という考え方を切り口にわかりやすく解明。身近なテーマから世の中のカラクリを読み解く知的レッスン!
-
-「優れた仕事をするためには、自分一人でやるよりも、他人の助けを借りたほうがいいと分かったとき、人間は偉大なる成長を遂げる」 「成功の秘訣は、自分で仕事をするのではなく、仕事をさせる適材を見つけることにある」 ――アンドリュー・カーネギー 自分の資源には限界があります。でも、外部には資源が無限に存在しています。ビジネスの世界で爆発的に成長するには、「できる仲間」を集め、その力を借りることが一番の近道です。 いまの自分を正しく知り、仲間づくりを意識することでできる仲間をどんどん増やす。仲間を集めて会社を成長軌道にのせれば、いい仲間=優秀な人材がさらに集まり、成長が加速する―― 本書では、そうした好循環を生み出す考え方を、著者自らの経験を踏まえながら分かりやすく解説します。人口減少で未曾有の人手不足を迎えるなか、「優秀な人材が来てくれない」と悩む堅・中小企業の経営者・管理職の方にぜひおすすめしたい1冊です。
-
3.3
-
4.0行き着く先はインフレタックスという究極の増税策! ? 総選挙を経て、再び安倍内閣に託したこの国の経済。 その処方箋が間違っているとすれば、最後にツケを払うのは、われわれ国民なのかもしれない。 ◆異次元緩和は間違った処方箋 5年目に入った「アベノミクス」だが、デフレ脱却には至っていない。それは、アベノミクスの目標及び処方箋が間違っているからではないか? 実は、金融政策依存は、政治的には非常に都合がよい。極論すれば、日銀が物価目標を明示しマネーの供給量を増やすだけで、政治は何もしなくてよいからだ。しかし人口減・高齢化が進む社会では、経済規模は必然的に萎まざるを得ない。量的・質的緩和では、本当の日本経済の構造問題に対処することは不可能なのである。 ◆このままでは金融資産がどんどん目減りする! 人口減対策と雇用制度改革を避けるアベノミクスは、実は意図せざる究極の増税策、すなわち「インフレタックス」である。そして、その潜在的な納税者は、金融資産を保有する企業や高齢者なのだ。 異次元緩和で膨れ上がる日銀の資産と増え続ける国家債務は、いずれ国債の価値下落を通じ日本経済をインフレに導く。その時、国家債務の実質負担は収縮する一方で、企業や国民が持つ金融資産の価値は目減りする。実は、戦前、高橋是清は、世界恐慌からの脱却を図るに当たり、日銀による国債保有を悪性インフレの原因になるとして許さなかった。アベノミクスを高橋財政と同一視し肯定するのは、全くの間違いなのである。 本書は、こうした視点をベースに日本経済の近未来を分析、蓋然性のあるシナリオを提示。インフレタックスが現実となれば、高齢者や企業は蓄積した金融資産の購買力を失い、中若年層は、親もしくは祖父母世代の経済力に依存できなくなる。そうしたリスクに備えるうえで、読者に知っておいてほしい知識を提供する。
-
5.0
-
-シンプルに考えればファイナンスは難しくない! 多くの企業価値評価を行うアナリストが、実務に最低限必要な基礎知識を凝縮。豊富な実例と演習で、基礎から企業価値評価まで一気に学べる1冊! 企業価値評価やファイナンスへの関心の高まりを背景に多くの書籍が刊行されているが、いざ初心者が読むとハードルが高く、理解しにくいものが多いのが現状です。 そこで、アナリストとして数多くの企業の企業価値評価を行っている著者が、企業の経営企画担当者や、大学・ビジネススクールで学ぶ学生などへ向けて、コーポレート・ファイナンスについて、初心者にもわかりやすくまとめました。 経産省や一般企業で働き、ビジネススクールではファイナンスの修得に苦労した著者が、自らの体験に基づいて書く「シンプルでわかりやすい、ユーザーベースのファイナンステキスト」です。 企業の実例や、株主資本コストやフリー・キャッシュフローを計算する【演習】も多数収録。理解を助けると共に実務にも役立つものとなっています。
-
3.0日経産業新聞の連載、「働き方探検隊」をオリジナル文庫化。働き方改革を進め、生産性向上に成功している国内外企業の先進事例を日経新聞記者が直撃、未来の働き方をひもとく。 ○日本の労働生産性は主要7カ国(G7)のなかで最低水準。時間あたりの労働生産性は46ドル(約5千円)で米国の3分の2にとどまる。一方、人手不足の深刻度が増す中で、就活生は「働き方」を重視して会社を選ぶ傾向が見られる。各企業では働きやすい職場をつくるための自主的な改革が始まっている。完全リモートワークで、オフィスのない会社から、連絡なしに休みをとれる職場、残業ほぼゼロでも12年間増収を続ける会社、約70人が副業を持つ会社まで、その創意工夫ぶりは十社十色だ。
-
3.6某アイドルが広告塔だったアパレル 創業500年の超老舗和菓子店 急成長が仇になった花形ベンチャー企業―― 誰もが知る「あの企業」はなぜ倒産してしまったのか? 「真実は小説よりも奇なり」。破綻の裏側には想像もしないドラマがある! 経理部長の自死、反社会勢力の介入、跡継ぎの背任、複雑な不正取引、警察の手が及ばないグレーゾーン、現存するナニワ金融道の世界など、実際に見てきた企業信用調査マンが明らかにする!
-
3.0成田修造氏(起業家・エンジェル投資家)推薦! 「自社のビジネスに経済学の知見を取り入れてない会社は、オワコン化するかも。未来へのヒントを得たいなら、まずこの本を手に取ろう」 ビジネスの悩みに応える武器としての「経済学」! ○本書で取り上げる先進企業5社 ・サイバーエージェント 経済学で自社サービスを改善。企業価値向上へ [キーワード]因果推論、効果検証、マッチング理論、情報の非対称性の解消 ・AppBrew(LIPS) 経済学に裏付けられた「信頼」と「ユーザー満足度」 [キーワード]データ分析、データ補正、レーティング ・Sansan 業務改善から自社プロダクト開発まで 幅広い活用法 [キーワード]CRM(顧客関係管理)、A/Bテストの効果的使用法 ・デューデリ&ディール 収益最大化・同業他社との差別化に経済学を活用する [キーワード]オークション理論、情報の非対称性の解消、属人的ノウハウからの脱却、CRM ・デロイト トーマツ 顧客との信頼形成、課題の明確化と企業価値向上のための経済学 [キーワード]課題の言語化、EBPM(エビデンスに基づく政策立案)、ESG
-
3.9
-
3.0お家騒動? 身びいき? モラルハザード?―― 旧来のイメージを打ち破る、これがファミリービジネスの強さだ! 「バカ息子の暴走」「親族への身びいき」といった不祥事の代名詞か、「老舗の論理」で語られることがほとんどだった同族企業。本書は経営者や後継者をめぐる「それまで語られなかったリアルなストーリー」と「最新のアカデミズムの知見」によって、同族経営の本当の姿を初めて明らかにします。 星野リゾートの星野代表が父と経営権を争ったハードランディングの事業承継、父が亡くなってから戻った会社で行った清酒「獺祭」の経営改革など、ファミリーの対立すら経営のパワーに変える。そんなスリリングでドラマチックな「情」を描きだします。
-
-成功したければ、「ダメ仕事」から抜け出せ! ある企業の管理職である筆者が、20年以上にわたって実務経験を重ねた中で、「成長する人、成長できない人」「成功する人、成功できない人」「評価される人、評価されない人」を目の当たりにした。そこから得た結論は、世の中には「成功するための考え方」が存在するということ。成功する人と失敗する人の違いを理解し、「成長できないネガティブ特性」と「失敗をもたらすダメ仕事」を排除すれば、あなたも成功に近づくことができる。 本書では、「人はどのように成長するか」「評価を高めるにはどうすればよいか」を、プロジェクトを中心とした上司と部下のやり取りを通じて、ストーリー仕立てでわかりやすく解説する。あらゆるビジネスパーソンの成功に役立つ1冊。 <目次> 読者のみなさまへ 「成長できない10のネガティブ特性」と「失敗をもたらす10のダメ仕事」に注意せよ! 第一章「斬新すぎる企画」はこうして通す 第二章「動かない、頑固な人」は損をする 第三章「人が苦手」は克服できる 第四章「上司の言葉」で浮かぶ部下、沈む部下 第五章「目標・目的・夢」の有無で差がつく 第六章「報酬」なくして人は動かず 第七章「情報不足」では戦えない 第八章「志」は自分自身との約束


![ビジュアル ビジネス・フレームワーク[第2版]](https://res.booklive.jp/1215750/001/thumbnail/S.jpg)