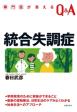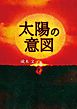精神科医作品一覧
-
4.0人はなぜ自殺するのか? 人はなぜ自殺しないのか? そのあわいをみつめつづけてきた精神科医、春日武彦による 不穏で不謹慎な自殺論考。 自殺は私たちに特別な感情をいだかせる。もちろん、近親者が死を選んだならば、なぜ止められなかったのかと、深い後悔に苛まれ、悲しむことだろう。だが一方、どこかで覗き見的な欲求があることも否定できない。「自殺はよろしくない」「でも自殺せざるを得なかった人の辛さに思い巡らせるのも大切」「あなたの命は決してあなただけのものではない」など、さまざまな意見を持つ人に読んでもらいたい、自殺についての深掘りエッセイ。自殺されたクライアントとの体験や、さまざまな文学作品、遺書、新聞報道記事などを下敷きにした、自らも自殺に近い位置にいる精神科医による、自殺をめぐる集大成。 「強引に言い切ってしまうなら、人間そのものに対する「分からなさ」が身も蓋もない突飛な形で現出しているのがすなわち自殺ということになろう。その突飛さを前にして、動揺した我々は、(情けないことに)つい「ゲスの勘ぐり」やら下品な好奇心至上主義を全開にせねばいられなくことが稀ではない。悼んだり悲しむと同時に、無意識のうちにそんな方向に走ってしまう。だから「その不可解さがもはや珍味と化している事案」と表現してみても、あながち的外れではあるまい。 そんな次第で自殺に関して思うこと、感じること、精神科医としての意見、文学的関心などをだらだらと書き連ねていきたい。もっとも、それが正鵠を射た内容であるのか否かは、自殺を遂げた当人ですらはっきりとはしないであろうけれど。」 (「はじめに」別バージョンより) 目次 はじめに 第1章 胃の粘膜 第2章 石鹸体験 第3章 登場人物を自殺させる 第4章 遺書のリアル 第5章 自殺の七つの型 ①美学・哲学に殉じた自殺。 第6章 自殺の七つの型 ②虚無感の果てに生ずる自殺。 第7章 自殺の七つの型 ③気の迷いや衝動としての自殺。 第8章 自殺の七つの型 ④懊悩の究極としての自殺。 第9章 自殺の七つの型 ⑤命と引き換えのメッセージとしての自殺。 第10章 自殺の七つの型 ⑥完璧な逃亡としての自殺。 第11章 自殺の七つの型 ⑦精神疾患ないしは異常な精神状態による自殺。 第12章 漆黒のコアラ おわりに
-
-本書は,NPO法人メンタルケア協議会で自殺防止事業に取り組み,また精神科医として50年以上患者と向き合ってきた著者による「自殺防止活動のための手引き書」である。 第I部では,「自殺企図直前の状態に陥っていることを示すサイン」(BPSAS)の具体例を示しつつ,BPSASに陥っている人に見られる特徴,またそこに至る三つのプロセス――「悪循環・発展」「精神状態の揺らぎ」「精神病性の症状」――について解説し,自殺企図に至るプロセスの全体像を概観していく。 第II部では,誰もが強力な“ゲートキーパー”(自殺の危険を示すサインに気づき,適切な対応を図ることができる人)になるためにどのように行動すれば良いかを,「対応の工夫」「自殺リスクアセスメント」「ゲートキーパーとしての動き方,支援機関の利用の仕方」の三つのテーマに分けて提案する。 年間約300人もの自殺未遂者・自殺ハイリスク者の支援事業に携わってきた著者の豊富な知見を1冊にまとめたこの「手引き書」は,“ゲートキーパー”として自殺防止に取り組むすべての人のバイブルである。
-
4.3「自分には生きている価値がない」「ブサイクだから異性にモテない」。 極端な言葉で、自分を傷つける人が増えている。 「自分が嫌い」をこじらせてしまった人たちの、自傷行為のように見える言動。 その深層心理にひきこもり専門医である精神科医が迫る。 誰にでも何歳からでも起こり、一度おちいると出られない、徹底的な自己否定。 「ダメな自分」の思い込みを見つめ直し、健全な自己愛を取り戻す方法を探る。
-
3.9
-
4.4私はアンタのATMかっ(涙)! 実家からニートの弟を引きとり、養うことになった駆け出しのマンガ家・沼津マリー。ゲーム三昧の弟を漢気あふれる姉が更生に導くドタバタ・コメディ! 精神科医・斎藤環氏も推薦。
-
-
-
-
-
4.4幸せのコツを習得するほど、お得なことはありません。 ●人によく見られたい、をやめる ●「他人と比べる」思考を抹消する ●自分という最大の味方をうまく使う 著者は精神科医として多くの患者さんをみているが、多くの人たちが「価値のない、つまらない人間だ」と思い込んでいる傾向が気になっているという。いったい、いつからそんなふうに感じるようになってしまったのか。今はSNSで簡単に他人の華やかな生活を垣間見れるため、昨今はますますその傾向が強くなっている。 しかし、一度きりの人生なのに、そうやって他人と自分を比べて落ち込むばかりの毎日でいいはずがない。考え方を切り変えるだけで、人は「自分に生まれてよかった」と心から思える生き物なのだ。 その根拠と方法について現役精神科医がわかりやすく解説します。
-
4.0「整形して人生変えたい。自分を好きになりたい」 幼少期から10年以上、ブサイクな顔に苦しんできた日々。そんな人生を変えるために選んだのが、「整形」だった―― 生きづらい人生の葛藤と解放を描いた、衝撃のノンフィクションマンガ。 ブサイクは整形をするとどうなるのだろうか? ずっと妹とくらべてきた母、女は就職して結婚して子供を産むのが一番と長年言ってきた父、 「寝てるのか~(笑)」とからかってきた同級生の男子、「目、開いてる~?」といじってきた上司。 頭では人は人、自分は自分、とわかっていても心がついて来なくて辛かった日々だった。 ブサイクだった自分が、ブサイクと向き合って、整形して歩んできた人生をありのままに描きます。 『マンガで分かる心療内科』原作者で精神科医のゆうきゆう先生コメント 「外側を変えれば、内側も変わる。美人にも、そうでない人にも読んでほしい」。 「否定され続ける人生に共感して涙」「まるで自分を見ているよう」「生きる勇気をくれてありがとう」など、圧倒的反響を呼んだ7話に50ページ以上の描きおろしを追加。 生きづらさを感じるすべての女子に読んでほしい傑作です。
-
5.0ひきこもり・過食症・閉所恐怖…… 数々の患者の悩みを解決してきた現役精神科医が語るうつ症状の改善方法 幼少期の親子関係から身についた “強迫性”がうつ症状を引き起こす!? ------------------------------------------------------ 強迫性とは他人の顔色をうかがい「ちゃんとしないといけない」という 思いにとらわれ、無理をするといった傾向のことです。 幼少期の親子関係に由来する、うつ症状の要因であるというのが 精神科医として長年多くの患者を診察してきた著者の主張です。 不安うつやパニック症、対人恐怖症など、 うつ症状と言ってもその症状は実にさまざまです。 これらを改善するには強迫性を緩めることが肝心です。 そのために最も大切なのは「自分の好きなこと」に目を向けることです。 自分には好きなことなどないという人でも、 自分の「こうしたい」「こうありたい」という素直な気持ちを明確にすることで、 強迫性は緩まり、心を楽にすることができるようになります。 本書では、著者が豊富な臨床経験から得た知見を基に、 他人の顔色をうかがうことなく「自分の好きなこと」を大事にして、 さまざまなうつ症状を改善する方法をまとめています。 誰にも相談できずに苦しんでいる人にとって希望の光となる一冊です。
-
-人生で起こるすべてのことを、私たちは自分の「思い」で引き寄せています。ですから「奇跡は起きる」と信じている人には、素敵で不思議な出来事が、“特別なこと”ではなく、“当たり前のこと”として何度も起きているのです。あなたにも、たくさんの「奇跡」が起こりますように!――著者より予約のとれない人気精神科医である著者が「過去生療法」やアロマセラピーなどを取り入れたカウンセリング治療、そして自身の経験を通じて明らかになった「奇跡が起こるしくみ」を紹介します。◇私たちは「生まれ変わり」を繰り返している◇「カルマの解消」とは、どういうことか◇なぜ日本には「祈りの場」が十六万カ所もあるのか◇「逆境のとき」こそ運命が動き出す「人生もっと楽しまなくちゃ!」――そんな気持ちが湧いてくるヒントが満載です。
-
-著者は言います。「今の青少年は『自分独自の存在感』が非常に希薄になった。他方で、母親の過保護で自尊心が自分の背丈以上に高まり、些細なことで決定的に傷つく。このため、簡単に『こんな人生(自分)だったら消してしまいたい』となってしまう。いじめられて引きこもってしまったり、自殺してしまったり、犯罪に走って自分の人生を破滅させようとしてしまう」と。序章/青少年の心に何が起きているのか。いじめ、不登校、引きこもり、少年犯罪などに心を痛め、思春期の子どもを持つ親として不安な日々を送る大人たちに、精神科医が豊富な臨床経験に基づいてアドバイスします。
-
4.2『世界一受けたい授業』(日本テレビ系)出演の若手精神科医が伝えたい、心がふっと軽くなるストレスフリーのコツ! 毎日が息苦しく、生きづらさを感じる方が増えています。 でもそれは、あなたの心が弱いわけでも、社会が悪いわけでも、ありません。 大切なのは、世の中も、他人も、そして自分の心だって、自分の思い通りにはならないと知ること。 だから、いい意味で肩の力を抜いて、頑張り過ぎないことが大事なんです。 □自分で自分に「いいね!」をつける □好きな言葉を口に出す □つらかったらすぐ逃げる □落ち込んだらお気に入りの写真を見る □デジタルデトックスの時間を作る たとえばこれくらいのことを実践するだけで、心がふっと軽くなります。 あなたはもう、無意識に十分頑張っています。 何事もほどほどに、“いい加減” で生きることが大事です。 凄まじい速さで“変化”する世界のなか、ありのままの自分を認め、たったひとりしかいない自分を愛して幸せになる思考方法。
-
3.7「わたしはわたしでいい」 そう思えるだけで、人生は輝き始めます。 45万部のベストセラー『感情的にならない本』の著者が、 長年書きたかった究極のテーマ! 「自己肯定感」よりずっとわかりやすい、 「自分を信じるということ」 自分を信じることは、いくつになってからでもできる! 幸せに生きるためには、自分を信じればいい。 私自身、そのことに気づくまでに長い時間がかかりました。 自分を信じることの第一歩は、自分の素直な感覚に従って行動することです。 うまくいかないときでも、「ダメな自分」を信じてあげてください。 そして、「本当はどうなりたいか」という心の声を、聞いてみてほしいのです。 その願望を見つけることが、自分を信じることにつながります。 とくに多いのは、「自分は幸せなんだろうか」という気持ちです。 裕福とは言えなくても生活は安定している。 仕事も人間関係もとくに大きな問題はない。 とりあえず健康だし、家族もみんな元気。 それなら幸せなはずなのに、自分を幸せとは思えない。 いまの暮らしを守れたとしても、これから先、幸せになれるとは思えない。 そういう人に、果たして精神科医のわたしにどんなアドバイスができるのだろうか。 そう思うことがしばしばあり、そしてやっと答えが見つかりました。 短い言葉で十分だと思います。 「もっと自分を信じてください」 とにかく自分を取り巻くさまざまなものに合わせたり振り回されたりしながら暮らしているとき、 自然に備わっていたはずの感覚とか素直な願望を封じ込めてはいないでしょうか。 「わたしはこう感じる」「わたしはこう思う」「わたしはこうしたい」といった、 いわば裸の自分が上げる声や欲求を、無視していることはないでしょうか。 「自分を信じる」というのは、そういう素顔の自分を信じるということです。 自分の声に従うということです。 もちろん、そんな簡単なことではないかもしれませんが、 このことについては自分を信じることにしようというちょっとした決意が、 あなたを変えていく、幸せにしてくれると私は信じています。 今がなんとなく幸せと思えない、自分のことがちょっと嫌で変えてみたいと思う方のお役に少しでも立てたら、 著者としてこのうえない幸せです。
-
4.3仕事や家事、育児などで失敗をして、周囲に迷惑をかけていると思った時。なかなか恋愛の相手が見つからない時。長年連れ添った家族との関係にひびが入った時。練習したのに、スポーツや楽器で結果を出すことができなかった時。そうした時に、一時的に「自分はダメだ」と思ってしまうのは誰にでもあることだ。だが、そうした失敗や困難を後々まで引きずって、自分を責めずにはいられなくなると問題である。一方で、他人のせいで「自分が悪いのだ」と思い込んでいる人もいる。あなたが罪悪感を持っているのは、親の教育の影響かもしれないし、周囲の誰かが巧妙に罪悪感を投げつけているのかもしれない。なかには「道徳的マゾヒズム」といって、いつも一定量の苦悩を持っていないと気がすまない人もいる。こうした罪悪感の深層が明らかになれば、人生が楽になるはずだ。そのためのヒントを、精神科医が自らの体験を踏まえて語る。
-
3.8マスコミを騒がしたショーンK氏、野々村元県議、小保方氏、舛添氏…。 最近急増する自己愛性・演技性人間という存在――。 そういう人に魅了されたり、簡単に騙される私たちやマスコミ。 新たなパーソナリティの諸問題を、現役精神科医がするどく分析! 「普及したSNSで言動をやたら盛りたがる人」 「嘘を積み重ね周りを信じさせるばかりか、自分の嘘を本当だと思い込む人」 「仰々しくやたら演技がかっている人」 「責任を問われると自分が被害者であるかのごとく言いたがる人」… こういった、最近急増する自己愛性・演技性人間という存在――。 そしてそういう人に魅了されたり、簡単に騙されたりしてしまう私たち(個人からマスコミまで)という存在――。 近年増殖するあらたなパーソナリティの諸問題(事例)を、現役精神科医がするどく分析する。
-
-
-
4.5
-
3.6
-
4.2
-
3.8
-
4.2友だち関係、勉強、家族、容姿……ストレスは多いけれど、大丈夫! 君は変われる! □心がざわつくこと、つらいことが多くて、イヤな気分に押しつぶされそう □朝起きると「また一日が始まる」と、どんよりした気分になる □笑うことができなくなっちゃった □自分のことをわかってくれる人がいない、ひとりぼっちだと感じている 気がつけば、こんな状態になってしまっていませんか? でも、大丈夫。 心がパンクしかけていても、自分で自分の心をセルフケアできるようになると、必ずラクになります。生きやすくなります。 大切なのは、知識、心構え(マインド)、行動(技術)、この3つです。 1)まず、「この状態はどういうものか。治す方法があるのか」といったことを知る。 2)次に「よし、治すぞ」という心構えをもつ。 3)そして、治していくために必要な具体的な技術を知り、行動を起こす。 この3ステップです。 どうすることが自分自身をラクにするのか、心の声を聞いて、一歩踏み出せばいいのです。 行動に移せば、状況は変わります。 この本は、「敏感気質(HSP/HSC)」の第一人者でもある児童精神科医・長沼睦雄先生が、これまでの臨床経験を総動員して書きました。 前半は「知識編」、後半は「技術編」。 この本に書いてあることを、小さなことひとつでもいいから、何か実践してみてください。 きっと状況は変わります。 大人ももちろん、とりわけ、多感な思春期を生きる10代の方にこそ、ぜひ読んでほしい本です。
-
4.52020年度から大学入試が変わる。中央教育審議会の答申によると、センター試験は廃止され新テストを導入。すべての国立大学の入試が実質AO入試化される。しかし「従来型の受験学力」を否定し「新しい学力」を求めるこの改革は、格差のさらなる拡大の危険や子供のメンタルヘルスに悪影響をもたらす可能性が非常に高い。そもそも政府が否定する「従来型の学力」は本当に“悪”なのか。子供が受験勉強で身につけるべき能力、これからの時代に必要な力とは何か。精神科医であり、また長きにわたり教育産業に従事してきた視点から多角的かつ詳細に論じる。【目次】プロローグ/第1章 2020年入試改革と受験学力/第2章 受験テクニック再考/第3章 学力と日本の教育について考える/第4章 受験勉強でどんな能力が身につくのか/第5章 受験学力格差はなぜ起こるのか/エピローグ これからの時代を生き抜くために/あとがき
-
3.0「あの大学に絶対合格したい!」と強く願っているはずなのに、なぜか勉強に手がつかない。何をどう勉強すればいいのかわかっているのに、なぜか始まらない……。その原因はきみたちの心が抱える不安にある! それを理解しないで、勉強しないままでは、受験の要領もテクニックも無力になってしまう。不安をコントロールしながら、「勉強に手がつく自分」を作っていくことが、受験に勝つために必要なのである。本書は受験指導のプロであり、精神科医でもある著者が、受験で成功するための「自分作りの指針」を明快に示す。「『将来がダメになる』という不安はヤル気に結びつきやすい」「がんばっている連中を見て、『やればデキる』という感覚を取り戻す」「机の前でグズグズしているときは、“簡単な作業”で不安を散らせ!」など、参考書ではなかなか教えてくれない具体的・実践的なアドバイスが満載。「自分」を理解して、合格を確実に掴み取れ!
-
3.9精神科医が自ら執筆する同名映画の原作小説。 毎年、東京大学に何人もの合格者を送り込み、「受験界のカリスマ」と呼ばれるようになった五十嵐透。富も名声もすべて手に入れ順風満帆の人生だったが、ある日突然がんで余命1年半と宣告される。五十嵐はコンビニで偶然出会った高校中退の貧しい少女・真紀の存在にひかれ、自分の持つすべての受験テクニックを注入して彼女を東京大学に合格させようとする。マスコミでも注目の精神科医・和田秀樹が自らメガホンを取った同名映画を、彼自身の筆で小説化。東大合格の受験テクニックとがん緩和ケアの情報もたっぷり詰った著者渾身の書き下ろし。
-
4.0
-
3.0自分が上機嫌な時は、いろいろなこと に積極的になれます。 いつも「上機嫌な人」には、周りの人 は声をかけやすいので、人づきあいも 円滑にいきます。 そのため人間関係も広がり、好機会も 得やすくなります。 一方、いつも機嫌が悪かったり、自分 は不幸だとすねたりする「不機嫌な人」 には、周囲の人は敬遠しがちで、いい 機会に出会うのも少なくなります。 いつも機嫌が悪いと、当然、人間関係も よくありません。 しかし、「いつも上機嫌でいられる」 「不機嫌になりやすい」というのは、 その人のもともとの性格ではありま せん。 「不機嫌になりやすい」傾向の人も、 ものの見方を少し変えたり、日常生活 の習慣を見直すといった工夫で、気に なることが減ったり、イラつくことが 少なくなります。 生活の中に小さな喜びを見つけられ、 幸せを感じる「機嫌のいい人」になれ ます。 この本では、感情生活を見直し、 「上機嫌でいられる」ためのコツを、 精神科医の和田秀樹先生が、精神科医 としての経験や自らの経験から提案し ます。 ●感情コンディションの整え方 ●やる気が出る「できた感」のつかみ方 ●「いい感情」のつくり方 ●感情を若々しく保つ方法 など、 「イヤなことがあっても、気分を立ち 直せられる」、「平気で明るい心持ち になれる」、「毎日が楽しく、前向き に気持ちで過ごせる」ヒントです。 「上機嫌でいられる」工夫は、毎日 の生活の中でできるので、本書で 提案することで、一つでも「うまく いきそうだ」と思われるものは、 ぜひ試してみてください。 ◎本書は新講社より刊行した『感情革命』 を改題し、再編集した新版です。◎本書は2019/9/17に発売し、2021/3/8に電子化をいたしました
-
4.1上司の暴言、先輩の嫌味、妻の叱責、ご近所トラブル、仲間はずれ、ネットの批判……他人に傷つけられがちなあなたへ。対人関係療法の精神科医が教える、どんな相手でも何があっても、上手に対処するヒント。「会社の人間関係が変わった!」「困った人間への対処法がわかった!」喜びの声、続々。「攻撃してくる人は困っている人として扱う」「相手を安心させればうまくいく」「相手を黙らせるお見舞いの一言」「相手が期待していることを聞き出す」……イヤな相手をするっとかわし、なぜか大事にされてしまう人になれる驚きの秘策とは?(著者紹介)精神科医、元衆議院議員。対人関係療法専門クリニック院長アティテューディナル・ヒーリング・ジャパン(AHJ)代表「対人関係療法」の日本における第一人者。『「怒り」がスーッと消える本』『「本当の自信」を手に入れる9つのステップ』(大和出版)、『女子の人間関係』(サンクチュアリ出版)など著書多数。
-
-
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 最新の薬のこと、病院の選び方、医師とのつきあい方、再発しないための方法まで、うつと診断されてから知りたい情報のすべて 女性の4人から10人に1人は一生のうちに「うつ病」になるといわれるほど多い病気です。女性は、就職、結婚、妊娠・出産、子育て、夫の転勤、自分のキャリアプランに応じて人生の転機が多く訪れます。また、月経周期や妊娠、閉経に伴う女性ホルモンの変動もあり、ストレスを受ける機会も多いといえます。本書では、そうした転機やストレスによって起こりやすい女性のうつ病に焦点を当て、検査、診断、治療、その後の生活までをわかりやすく解説します。最新の薬物療法、認知行動療法など、女性の精神科医が伝える、あなたの病態、病期にあった治療を選ぶために必要な情報のすべて。うつになりやすいのは、もともと真面目で一生懸命な人が多いもの。再発予防のためには、完璧を求めず、ひとりで抱え込まないことも大切です。家族の心がまえも含め、周囲の人役立つ内容です。まずは病気について知ること、理解することから始めましょう。 野田 順子:野の花メンタルクリニック精神科、医師。三重大学医学部卒業。東京医科歯科大学神経精神科、都立松沢病院にて研修後、東京都の産業医、国立公衆衛生院を経て吉祥寺で開業。日本精神神経学会専門医、精神保健指定医。
-
3.5女医が女性を徹底分析 「『女性はいったい何を求めているのか?』というフロイトの問いに対する十分な回答がここにある。ローアン・ブリゼンディーンは、厄介な女性をなんとか理解したいと願うすべての男の望みをかなえてくれた。女性のための小気味よく明快な手引書――男性も必読」――ダニエル・ゴールマン(『SQ生きかたの知能指数』の著者) なぜ女性は男性よりもよくしゃべるのですか? なぜ女性は男性がまったく思い出すことのできない出来事の詳細を覚えているのですか? 女性と男性の違いは、老若男女を問わず悩ませてきました。その問題を解決すべく神経精神科医ローアン・ブリゼンディーン博士は女性の脳機能を研究し本書を執筆しました。 過去の多くの研究が男性のみに焦点を当てていたため、女性に特化した本書は大変な注目を集めています。 生物学的に身体の変化が女性の一生にどのような影響を及ぼしているのかを《幼児期・思春期・恋愛期・セックス・育児期・閉経期とその後》に区分し検証をしています。 「身体の変化=ホルモンの変化」と脳の関係を実例を交えながら、女性だけに見られる思考回路とその理由を解説しました。女性脳で何が起こっているのかを理解すれば、多くの問題は解決することでしょう。 女性ならではの行動をコントロールする術も公開しています。パートナーとのすれ違いも解消できるでしょう。 永遠の悩みと思われていた問題を解決する一歩を踏みだしましょう。 目次 第1章 女性脳の誕生 第2章 10代の女の子の脳 第3章 愛と信頼を求めて 第4章 へその下の脳 第5章 ママの脳 第6章 感情をくみとる 第7章 熟年女性の脳
-
4.5おとなになるまで診断もアセスメントもされなかった自閉スペクトラム症の人たちは、何を知る必要があるのか? そしてどのようなサポートを必要としているのか? 自閉スペクトラム症のアセスメントや診断プロセスのわかりやすい解説、コミュニケーションや感覚に関する自閉特性との上手な付き合い方、自閉スペクトラム症をもつ人たちの年齢別ケースレポート、そして当事者の声を通じて、当事者と家族の知りたい気持ちにしっかり応えていく。どのように自分と家族の「自閉スペクトラム症」を理解していけばよいのかを伝える自己理解ガイド。本田秀夫推薦(信州大学教授・精神科医)!
-
3.7
-
4.3仕事、人間関係、育児、恋愛……人生の鍵は「自己肯定感」が握っている!「自己肯定感とは何か?それは、自分を支える根源的な心の力のことです。そして、この力は、誰でも、いつからでも、何歳であっても高めることができます。これは精神科医として、また禅僧として、さまざまな心の問題と向き合ってきた経験から得た確信です」(著者)序章◎努力より、環境より、才能より大事なもの1章◎自己肯定感の高い人、低い人の差はここに出る2章◎もっと“マインドフル”な人間関係をつくる3章◎「怒り」をどうコントロールするか4章◎だから、この人は仕事がうまくいく5章◎自己肯定感を高める、10のワークもっと明るく、楽しく、そして自分らしく生きるためのヒント
-
3.6「わたしは以前から、考え方も笑いどころも一致するような気の合う人が見当たらず、この世の中にはマトモな人間がいないのかと思っていた。三浦先生と知り合って、やっと気が合う人がいたと思ったら、マトモな人間ではなかった」――。本書はそんな素敵な関係にある、「笑う哲学者」ツチヤ教授と79歳の精神科医三浦医師による夢の(?)対談である。互いに反省と改心を求めるどっちもどっちのやりとりを読んで、あなたは思うだろう。「なんて軽薄でいい加減な人たちなんだろう」。そう思ったあなたは正しい。しかし、そんないい加減な対談だからこそ、あなたの心の重荷が軽くなり、人生が楽になる、かもしれない。<主な内容>「尊敬されない方がいい」「欠点は財産、愛嬌が最高」「心の健康を保つ秘訣」「女とのつきあい方」「プライドを捨てれば楽になる」「成功なんか、しなくていい」他
-
3.0大切な思い出はそのままに、心も部屋もスッキリ!50代から味わえる!最高のご褒美。「人生の意義が見つかる、すごい片づけ法!」と 精神科医 清水研先生大絶賛!「すごいわ! サクサク片づく!」」「元気ハツラツになって、生きがいまで見つかった!」「捨てたくない!」があふれていても大丈夫。本メソッドのすごさは、次の3つが確立しているところにあります。① 何を残せばいいのかパッとわかる「究極の基準」② 頑固な「執着心」を捨てられる4つの思考法③ 大切な思い出を一生残しておける「思い出コンパクト術」究極の基準があるから、迷いゼロ! 挫折ゼロ!しかも、時を重ねた世代だからこそ味わえる素敵なことがあるのです!
-
3.0
-
3.7
-
-定年前に突然「うつ」に陥った50代男性。息子夫婦との同居がきっかけで「うつ」になった60代主婦……。本書では、そんな「初老期うつ」の対処法について、精神科医が症例とともにやさしく解説する。人は年をとるほどに、意欲も希望も失ってしまうもの。だからこそ、心と脳が衰えない生活の智恵が大切である、と説く。その具体的な心構えとして、以下の九つをあげている。(1)ストレスを聞いてもらえる対人関係を確保する (2)自分のポリシーを持つ (3)無意味な疲労をため込まない (4)あるがままを受け入れる (5)恨み、嫉妬、後悔にとらわれない (6)スポーツや趣味を楽しむ (7)ユーモアやダジャレを口にしてみる (8)批判に強くなろう (9)安定した家庭、安定した経済状況を築く。いわば、「初老期うつ」に陥らない秘訣、ということだろう。六十代でリタイアしたとして、あと二十年をどのように生きるのか。人生の先が長いからこそ、「晩年力」を身につける一冊である。
-
5.0大人気精神科医越智啓子氏の代表作『人生のしくみ』から20年。代表作の本作をこの間のエピソードなどをアップデートし、さらに1章分まるまる追加した令和版の決定版。適宜、ワークも掲載。過去生療法など薬を使わない精神科医としての真骨頂としての内容もりだくさん。初めて読む方にとっても、昔読んだことがある人にとっても、新たな気づきのある1冊です。
-
5.0人生の岐路に立ったとき、誰でも進むべき道に悩み、本当にその決断が正しかったのか迷い、後悔することを恐れる。悩んだとき、いかにして進むべき「正しい道」を見つけるべきか。また、後悔や迷いをどのように断ち切るか。人気のスピリチュアル精神科医が、悩み多き現代人に贈る、自分の道の選び方。
-
5.0
-
3.5メディアで話題の精神科医が教える、 「精神医学的に正しく」潜在意識を操る方法。 〈内容紹介〉 ・自分の「限界」は潜在意識でラクに打破できる ・嫌な情報は、「ポイッ!」と捨てられる ・“運がいい人”は、必ず潜在意識を使っている ・豊臣秀吉も潜在意識を使いこなしていた!? ・失敗はハリウッドのゴールデンパターン! ・自分に「タイトル」をつければ生活が変わる ――etc. これは単なる自己啓発書ではなく、 誰にでも奇跡が起こせる、驚異的な医学メソッドです! 【著者情報】 精神科医、ハタイクリニック院長。 弘前大学医学部卒業。 TBSドラマ『ATARU』医療監修も務めていた。 国立国際医療センター勤務、 国立秩父学園医務課医長などを経て、 2009年よりハタイクリニック院長。 テレビドラマ医事監修、メディア出演や雑誌への寄稿も多数。
-
4.0誰でもできる成功の法則とは?大人気メルマガの著者である精神科医・ゆうきゆうがちょっとお疲れのあなた、何となくモヤモヤした思いを抱えるあなたに伝えるシンプルな習慣術! (※本書は2015/8/1に株式会社 海竜社より発売された書籍を電子化したものです)
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人工知能の脳太郎と、精神科医のDr.ナビが、精神医学の世界をご案内。 精神医学の入門書として最適の一冊。 わかりやすい解説とイラストですらすらと読めます。 「精神科」ってどんなとこだろう? 治療ってどういうふうに行われるのかな? 精神科でもらう薬って、どんな作用があるんだろう? 精神科はなんだからわからない、なんとなく怖いと思っている人、 関係ないと思っている人、 本書を読めば、精神医学の概略をやさしく学ぶことができます。 【目次】 プロローグ ある日の精神科 1 脳のしくみとこころ 2 こころの病気とその症状 3 心理療法(精神療法) 4 こころの病気の薬 5 眠りを考える 6 脳の状態を調べる方法 エピローグ 精神医療に携わる人たち ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.4
-
4.0自分の指示通りに部下が動かないと激高する上司、自分の不満を歯に衣着せずにぶつける夫あるいは妻、さらには犯罪を引き起こすような深刻なケースまで。すぐ感情的になる原因として考えられるのは、親の影響、加齢による「脱抑制」、怒りを許容するいい人の存在、さらに人格障害、「間欠爆発症」、そして怒りやルサンチマン(恨み)をかきたてる社会、などなど……。ただし、感情をぶつけられたことで生まれる怒りを抑制することはお勧めできない。無理に抑圧した感情は、必ず何らかの形で表に出てくるからだ。そこで本書では上手に怒るためのヒントも含めた上で、すぐ感情的になる人への的確な対処法を述べる。ベストセラー『他人を攻撃せずにはいられない人』の著者の精神科医が、自分自身の例も挙げて簡潔に解決する。
-
3.0仕事も人生も、悩みのタネは「人間関係が9割」といわれます。そして人間関係で行き詰まると、「周りの人はすべてのことがうまくいっているのに、自分にはいいことが起こらない」と落ち込む場合も少なくないようです。すると、イヤなことがあったり、気分が落ち込んだ際に、よけいに悲観的になり、消極的になるので、いつまでたってもイヤな気分が晴れなかったり、いいことが起こらないということが現実に生じてしまいます。だとすると、落ち込んだり、ひどいことが起こる前から、ものの見方を柔軟にするとか、ツラいときに聞いてもらえる人間関係をつくっておいたほうが賢明でしょうし、気分が落ち込んだときに何をすればいいかを前もって決めておいたほうが、落ち込みのデフレスパイラルにはまり込まないはずです。本書は、明日はいいことがあるように思えるためのテクニックを、長年の精神科医としての経験から書き綴ったものです。(「まえがき」より)
-
3.7
-
5.01巻 仮面――ペルソナ バージルシティ。公園内の全裸の男性像の下で、男の他殺体が見つかった。ワイルドな刑事、スタンレー・ホークは捜査を担当することに。ただでさえ忙しいのに、赴任してきたばかりの内部管理課長、アリスター・ロスフィールド警視の命により、日本人精神科医、ジン・ミサオによるカウンセリングを受けることになり……。スタンレーと、息を呑むほどの美貌と優秀な頭脳を持つ警視・ロスフィールド。ミステリアスで美しい男、ジン。おぞましい事件と、男たちのめくるめく三角関係の扉が、今開く。 2巻 葛藤――アンビヴァレンツ 夏の終わりに上司であるロスフィールドと関係をもったスタンレー。それ以来二度と機会がないままのふたりの前に、強盗殺人事件が立ちはだかり……。 3巻 二重自我――ドッペルイッヒ 遺体の臓器を抜き取る連続殺人事件が発生。スタンレーは難航する捜査だけではなく、美し過ぎる上司・ロスフィールドとの関係にも頭を悩ませて……。 4巻 冥罰――リトリビューション ハンサムな仮面の下におぞましい性癖を隠し持つ画家、ルイス・クウェンティンに囚われたロスフィールドとジン。ルイスは苦悩に歪むロスフィールドの表情を描くことに至上の悦びを感じ、残酷に2人をいたぶっていき……。スタンレーは彼らを救うことができるのか!? めくるめく外伝も収録の完結巻。 ※本電子書籍は、「スタンレー・ホークの事件簿 I 仮面――ペルソナ」「スタンレー・ホークの事件簿II 葛藤──アンビヴァレンツ」「スタンレー・ホークの事件簿III 二重自我──ドッペルイッヒ」「スタンレー・ホークの事件簿IV 冥罰――リトリビューション」を1冊にまとめた合本版です。
-
3.9
-
4.0
-
3.8
-
3.6いつもイライラ、 集中できない……、 それ、スマホのせいです! 「スマホは最強(凶)の依存物です」 国立病院機構久里浜医療センター精神科医長、緊急書き下ろし! 大人も子どもも依存物だと知らずにつきあい、 気づいたときには重症化しているのがスマホ依存症の恐ろしさ。 久里浜医療センター精神科医が警告する、ゲーム依存を中心にしたスマホ依存症とその治療、 「依存症は〈正の強化〉と〈負の強化〉を脳内につくる精神疾患です。まずは、個人も社会もスマホ依存症の正体をよく知ることです」 【目次】 はじめに 第1章 依存物は最高だ! 依存物と同棲している子どもたち 依存症の定義 依存物の条件 オンラインゲームの依存的特性 その依存物が流行るワケ 「依存物は最高だ!」 第2章 脳内借金としてのスマホ依存症 依存症の発症 精神依存における「正の強化」と「負の強化」 精神力で「負の強化」を乗り越える? 「快楽」と「不快」の同時進行 知らないうちに猛獣に食べられている 依存症の正体の見えにくさ 依存症とひきこもり 依存症の複雑な因子 脳内借金としての依存症 依存症からの回復 第3章 依存物との闘いの歴史 覚せい剤の発見と広がり 規制の効果と難しさ アルコールの「性能強化」 アルコールの規制 依存物と人間のつきあい ゲームの発明と黎明期 オンラインゲームの誕生 インターネットメディアの依存的性質 第4章 スマホ依存症の実態 スマホ依存の正体 インターネットとスマホの普及 インターネット依存症の研究 何に依存しているのか? インターネットゲーム障害 ゲーム障害 オンラインゲーム依存の兆候 合併する精神疾患や発達障害 空き時間による依存症の悪化 第5章 スマホ依存症対策の壁 一般的なスポーツとeスポーツの比較 教育や仕事と対決するゲーム 「プロゲーマー」という危ういワード 「聖域」の消失 遊具でもある学習用具? 依存症は「自己責任」か 第6章 スマホ依存症からの回復 「節制しながら」か「全く断つ」か 断ネットか、節ネットか 断ゲームか、節ゲームか スマホ依存症の治療 久里浜医療センターでの取り組み スマホ依存症予防と回復 依存物に触れない自由・依存物から守られる権利 おわりに~スマホ依存症の未来
-
4.0いつでも手にとれ、使えるスマホは、非常に便利な反面、 SNS依存、ゲーム依存など、依存症を起こしやすい道具でもあります。 スマホに振り回されて、現実にある大切な人間関係を壊したり、 生きにくくなったりしないように、 また、自分を見失わず、スマホを賢く使いこなすにはどうしたらいいか。 精神科医・和田秀樹先生が本書で提言します。 ●1対1の人間関係が心を育てます ●「自分」対「みんな」は、心を圧迫しませんか ●なぜ目の前の人より、見えない「みんな」が大事なのですか ●スマホが依存症になりやすいわけ ●脳のソフトが書き換えられていく! ●目に映る世界は、こんなに豊かで面白いのに ●ネットの人間関係が持つ息苦しさ ●「みんなと同じ」は強迫感 ●「炎上」はなぜ起こるのか ●SNSは何を壊すのか ●本来、ネットは議論や共感のためのメディア ●「自分病」はいつの間にか伝染する ●スマホで子どもの学力が落ちる ●2歳児の言語レベルになる! ●「なければ困る」ではなく「あれば便利」と割り切ろう ●まず、自分の感覚を取り戻すこと(他)(※本書は2018/10/25に発売し、2021/3/8に電子化をいたしました)
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※本書は、コンビニ限定書籍「図解 感情的にならない気持ちの整理術」を電子化したものです。 ◎不機嫌でいるとソンをする! 「ついつい怒ってしまう」 「気持ちが落ち込みがち」 「イライラすることが多い」…… 最近、感情をコントロールできず、不機嫌になる人が増えている気がしませんか? 感情に振り回されると、仕事も、人間関係も、うまくいきません。医学的に見てもマイナスです。免疫機能が低下して、病気になりやすいからです。 仕事も、人間関係も、健康も、努力して「自分磨き」するより、まず感情をコントロールして、ごきげんな時間を増やすのが早道。 頭がよくて優秀な人より、いつもごきげんな人がうまくいくのです。 ◎イヤな気分を引きずらないで、毎日ごきげんでいる方法 本書は「実は自分も感情的になりやすい」と語る精神科医・和田秀樹さんが、自分自身でも実践して効果があった考え方をまとめたものです。 「感情的になってしまう理由」から「感情整理のコツ」「感情的になった時の対処法」「毎日ごきげんに過ごす方法」まで、著者の「心のコントロール術」のすべてがわかります。 手軽に実践できる「気持ちの整理術」もたくさん紹介されているので、自分に合ったものから、今日すぐ実践できます。 まずは読み始めてください。気持ちが上向きになっていくことが感じられるはずです。
-
3.0「今日はこんな嫌なことがあった」と部屋の中で一人、もやもやした思いを抱えていても、頭の中は対人関係であふれている。人間の悩み、苦しみ、喜びといった感情はすべて、対人関係の中で起こるといいます。精神科医である著者は、対人関係の悩みを解決するには自分の心と向き合うしか方法はないと語ります。本書では、「心を一瞬で変える技術」と「落ち着いた心の状態を維持するためのエクササイズ」の二つを中心にご紹介。マイナスの感情を断ち切り、深呼吸や瞑想などの方法を習慣化し、心が本来もつ能力を引き出す方法が学べます。今まで『心と向き合う本』というだけで「しんどそう」、「めんどくさそう」と敬遠していた方も、動きのある楽しいイラストが入ったことで、気軽に楽しんでもらえるようになっています。自分の心と向き合うことで、対人関係の問題を解決し、明るく、気分のよい自分らしい自分が見つかる一冊です。
-
-
-
4.0
-
-
-
4.4
-
3.7気楽に始められて、くじけず続けられる「心理テク」と、肉OK、魚OK、マヨネーズOKの「糖質制限ダイエット」を人気精神科医が徹底指南! (目次より)Iメンタル編~食欲をコントロールするための心理テク「口寂しさ」にどう対処する?/食欲を抑える「プチプチ運動」って?/ダイエットを持続させるための心理テク/必ずやせる究極の方法とは?…etc.II 食事編~満腹なのにやせていく、糖質制限ダイエット「糖質制限」の基本/米を食べるのが自然じゃないの?/「糖質制限」って意外に気持ちいい!/くじけそうになったら… etc.(著者紹介)ゆうメンタルクリニック・ゆうスキンクリニックグループ総院長。医師、心理研究家。『マンガで分かる心療内科』(少年画報社)他、著作多数。総発行部数は500万部を超える。メールマガジン「セクシー心理学」サイト「心理学ステーション」http://sinri.net/ を運営。
-
-精神医療改革運動に関わってきた精神科医・看護師・PSW、当事者や福祉関係者による精神医療改革に特化した事典。 精神医療改革の実際を担ってきた多くの精神医療従事者が、日常の実践をとおして、果てしない空白の病棟列島に挑戦する。 ◆精神医学・医療の領域では、すでに多数の辞典や事典が刊行されています。精神医学全般を網羅した大小・新旧の辞典から用語集のような書籍もあれば、精神分析・発達・精神薬理といった専門分野に特化したもの、あるいは歴史・精神看護学・メンタルヘルス・心理学などに焦点をあてたものなどもあり、それらの中には良書も少なくありません。しかし、最も重要であるはずの精神医療改革に特化した事典は、なぜかこれまで刊行されていませんでした。 ◆『精神医療改革事典』は、精神医療にかかわるさまざまな用語や概念の解説を収録したものにとどまりません。一つひとつの項目を読み進めるうちに、日本、あるいは世界的な広がりにまで及ぶ歴史的な事件や犯罪と、精神医療の過去から現在にいたる歴史が、不可分にむすびついていることに気づかされます。精神医療改革の歴史をたどることで、人間の存在、精神の有り様が、言語や文化の違いを超えて普遍性をもっていることに改めて気づかされます。(「刊行にあたって」より)
-
-20年以上にわたり精神医療業界を検証し続けてきた著者の集大成! 過剰診断による発達障害バブル、精神科医と製薬会社の癒着、精神科病院の収容ビジネス、診療報酬の不正取得、訪問診療・訪問看護の悪用など、利益至上主義に走る精神医療業界の実態を暴いた一冊。 【目次】 第1章 作られた精神疾患ブーム 第2章 精神医療ビジネスの構造 第3章 薬に依存する精神医療業界 第4章 大衆を騙す様々なトリック 第5章 どのように精神医療ビジネスに立ち向かうべきか 【著者】 米田倫康 1978年生まれ。私立灘中・高、東京大学工学部卒。市民の人権擁護の会日本支部代表世話役。在学中より、精神医療現場で起きている人権侵害の問題に取り組み、メンタルヘルスの改善を目指す同会の活動に参加する。被害者や内部告発者らの声を拾い上げ、報道機関や行政機関、議員、警察麻薬取締官などとともに、数多くの精神医療機関の不正の摘発に関わる。著書に『発達障害バブルの真相』(萬書房)、『発達障害のウソ』(扶桑社新書)、『児童精神科医は子どもの味方か』(五月書房新社)など。
-
-
-
4.5人々の目に触れることがない、精神科単科病院の「身体合併症病棟」。 ここがどのような場所で、どのような人が生き、そして死んでいくのか 精神医療は、一般にも医療の中でもタブー視されているのではないかと考えます。本書は、少しでも精神医療を知るきっかけにしてほしいと、日経メディカルOnlineで執筆したコラムをまとめました。 ・なぜ、長期間退院できないのか。 ・なぜ、精神科医が身体疾患を診るのか。 ・なぜ、転院を断られるのか。 ・なぜ、家族は治療を拒否するのか。 ・なぜ、精神科病院は人里離れた場所や山の麓に多いのか。 精神科単科病院で亡くなっていった人たちの人生や、家族・友人との人間関係を通して、精神科疾患を有する人の日常や精神科医療の実際を描き出すと同時に、胃瘻造設や延命治療の是非、誤嚥性肺炎、患者家族への説明の難しさなど、終末期医療に共通する医師の悩みも吐露されています。 特別編として、相模原障害者施設殺傷事件についても書き下ろしています。
-
3.0精神鑑定は他人事だと思っている精神科医に、ある日、依頼の電話がかかってくるかもしれない。 精神鑑定が行われる件数は、毎年増加し続けているため、これまで精神鑑定に携わってこなかった医師たちにも精神鑑定の依頼が来る時代になってきた。 本書には、精神鑑定の依頼の受け方から鑑定面接の仕方、鑑定書の書き方まで、精神鑑定を行うための必要十分な知識が分かりやすく解説されている。また、内容も面白く、やさしい記述で、精神鑑定がどのようなものであるかを小説を読むかのように楽しく理解することが出来る。精神鑑定をこれから行う医師にとっても、心理士やPSWなど精神鑑定に携わる方にとっても極めて役立つ心強いガイドブックである。一般の方にとっても、裁判員に選ばれる可能性のある現在、精神鑑定を易しく理解できる最適の書である。
-
-
-
-ロバート・エムディは,世界乳幼児精神保健学会(WAIMH)の創設者で,現在WAIMH理事,乳幼児精神保健研究の第一人者として名高い児童精神科医,精神分析家であり,愛着理論で有名なボウルビーと同時代に活躍し,「3カ月微笑」「1歳半のNo!」の現象を発見したスピッツの正統な直弟子でもある。 本書は,本邦初訳となるエムディの代表的論集である。主要な研究業績である,生物行動学的観察と精神分析理論を用いて,乳児が母親の「情緒応答性」を得ながら,人間存在の中心となる「情動的中核自己」を形成していくプロセスについての論考,また子どもの心の発達には,R=Reciprocity(互恵性)E=Empathy(共感性)V=Value(価値)が大きな影響を及ぼすことを説いた「REV理論」について,詳しく解説されている。 エムディの理論は,日本のいじめ,自殺,無気力,不登校,引きこもり等,現代の日本の子どもたちが持つ多様化し複雑化する問題の本質を考える上で,有効な知見といえよう。 乳幼児精神保健や精神科医,心理士はもとより,広く子育て支援に関わる医療,保育,教育,福祉,司法,行政に携わる専門職必読の書。
-
-
-
3.3
-
2.9もうすぐ三十路の崖っぷち女。親がうるさいため婚活サイトを駆使して絶賛婚活中の夏目。大学病院で精神科医をしていることもあり仕事が理由でお断りされ続ける日々――。ひょんなことから、製薬会社の社長の息子の担当医になる事となる。どんな人か不安を感じつつ、対面すると相手は優しそうな男性で一安心するが……!?
-
4.1
-
5.0
-
-繊細な人、HSPの人が想像以上に時間を費やしている「悩み時間」の短縮方法を、網羅的に紹介・解説! 精神科医として活躍する著者は、医師であるだけでなく、自身がアスペルガーであり、以前はそのことによる自分の繊細さ・敏感さで大いに苦労していました。しかし今では、すっかり快適に暮らしています。その理由は、さまざまな工夫で「悩み時間を減らす」ことに成功したから。 細かいことまで気が回る分、考えすぎてしまったり。イメージ力が豊かな分、悪い想像がはかどってしまったり。記憶力がいいために、自分の失敗を忘れられなかったり。雨が降るだけで気分が落ちたり。 繊細さや敏感さから発生する悩みの数々は、一つひとつは大したものでなくても、積もり積もると結構な時間を奪われているはず。 集中するまでに時間がかかる/興味のあることを行動に移せない/マルチタスクが苦手/チャンスが巡ってきても悩んでいる間に逃してしまう/人のことで悩みすぎて疲れてしまう/理想が高いのに頑張れない/初対面が苦手/頼むのも苦手、断るのも苦手――等、日常のさまざまな悩みに対応した内容です。 私たちは、悩みのまっただなかにいる時、「この悩みは特殊で、複雑で、解決はとても難しいものだ」と感じがちですが、実は「悩みの種類は3つだけ」と聞いたら驚きませんか? さらに、「悩む意味のある悩み」と「悩む意味のない悩み」を分類してみたことはあるでしょうか? ダメ押しで「悩みを効率的に解決するコツ」を知れば、これまで意識せずに膨大な時間をとられていた「悩み時間」を大幅時短できます。 悩み時間を削減して生まれた時間を、あなたの好きなことに使いましょう!
-
5.01960年代後半、ヴェトナム戦争の時代。妄想に取りつかれた合衆国軍の将校たちは、仮病と疑われながら秘密収容所に送りこまれ、治療と研究の対象となっていた。最後の収容所となったセンター18には、元宇宙飛行士のカットショー大尉を始め、様々な強迫観念に囚われた兵士たちが収容されていた。新たに配属された海兵隊の精神科医ハドスン・ケイン大佐は、収容者たちの話を聞き続ける中で、かつての患者が見ていた悪夢に繰り返し苛まれる──館に蔓延する狂気と悪夢。そして“奇蹟”の顕現。『エクソシスト』の鬼才による入魂の傑作。
-
-
-
4.1
-
3.5「もうだめかもしれない」そう思った時に湧いてくる強さがある―― 若者たちは自分の余命とどう向き合い、立ち上がっていったのか。精神科医と見つめる、人間のレジリエンス(復元力)とは。 20年以上、がん医療の現場で患者さんの話を聞いていた精神科医が発見した、人に必ず備わる「レジリエンス(復元力)」とは――。 20代、30代のときに突然がん告知を受け、絶望と向き合いながら今も懸命に生きる6名の若者の物語。決して平たんではない彼らの道のりと、そこに寄り添い話を聞き続けた著者による力強いメッセージから、今日一日を過ごせることへの感謝と、生きるための勇気が心の底から湧いてくるのを感じる一冊。 ◆死を意識することの効能 ◆自分は自分でいいんだと思えること ◆人は死とどう向き合うのか ◆怒りや悲しみなどの負の感情に蓋をしない ◆苦しんでいる人に寄り添うということ ◆不安との向き合い方
-
-
-
4.2だれでも「ソウルメイト(魂の友)」に出会えるしくみになっている。人気精神科医が、ソウルメイトとの運命の絆について解き明かす。人と人との不思議な絆と人生の意味を知る必読の書!
-
4.2不安には「本物の不安」と「ニセモノの不安」があった!――怖れによって作り出され、私達の心を縛り、前向きな行動を阻んでしまう「ニセの不安」。そのメカニズムと、不安に振り回されずに思い通りに生きる方法を、対人関係療法の第一人者が説く。レッスン1 人はなぜ「不安」になるの?/レッスン2 「ニセモノの不安」が湧いてくる理由/レッスン3 ジャッジメントをやめれば、楽になる/レッスン4 「心の姿勢」を整える、ということ/レッスン5 「本当の勇気」とは何か?/レッスン6 「自己効力感」をもてれば、不安は消える【著者紹介】水島広子。精神科医。「対人関係療法」の日本における第一人者。2000年6月~2005年8月、衆議院議員として児童虐待防止法の抜本的改正をはじめ、数々の法案の修正に力を尽くし実現させた。『「怒り」がスーッと消える本』(大和出版)『女子の人間関係』(サンクチュアリ出版)等著書多数。
-
4.2※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “ネガティブ思考クイーン”の漫画家・細川貂々が、精神科医で「対人関係療法」の第一人者・水島広子に会いに行く、等身大の成長物語(コミックエッセイ+コラム)。 ネガティブな性格で生きづらい、自分を“ダメ人間”と思ってしまう、コミュニケーションのとり方がわからない、そもそも人づきあいがニガテ、ネガティブな人を引き寄せてしまう、人に振り回されることが多くて疲れる……etc。 そんな人生をラクにするコツは、「当たり前の気持ち」を受け入れて、自分を認めること。そのヒケツは、対人関係の「ズレ」と「役割期待」にあり。対人関係が健康であれば心も健康であり、対人関係に自信があれば人生にも自信がもてる。生きづらさを克服するための対人関係入門書。
-
-かつて精神疾患は、一般の人々にとって身近なものではなかった。けれども現在では、うつ病、拒食症、統合失調症などの精神疾患の名前はすっかり一般的になり、知人がうつ病で休職したなど、精神疾患を身近に体験している人も多い。 薬物療法が開発され、以前に比べて社会生活と治療を両立させやすくなったこともあり、今後は精神疾患を抱える人とともに生きていくためには、どうすればよいか考えるという、新しい課題に取り組む必要がある。 このような流れの中で、精神疾患は、精神科の医療機関で働く職種だけでなく、さまざまな対人援助職が接するものとなっている。産業医、保健師、教育関係者、スポーツ指導者、そして精神疾患をもつ方が子どもを預ける保育園や幼稚園の保育者などにも、精神医学の基礎知識が必要になっていると言えるだろう。 これらの対人援助職は、精神疾患を「治す」立場ではないが、精神疾患を早期に発見したり不調を察する機会の多い第一線にある職種である。身体の疾患と同じく、精神疾患についても早期発見、早期の治療開始が経過によい影響を与えることは知られており、正しい知識をもった援助者が早めに声をかけ、治療の初動部分がスムーズに開始できることは非常に重要である。さらに初動の部分だけでなく、すでに治療中の人をどのように支え、対応するかも重要な課題である。 精神医学の教科書はすでに数多く出版されているが、精神病理学の用語は難しく、医師であっても精神科医以外にはなじみにくい。やさしく解説した本もあるが、言葉のレベルでやさしく書かれていても、当事者がその症状をどのように体験しているかについては想像しにくい。 本書では「その疾患の当事者がどのような体験をしているか」について、少しでも想像できるよう、事例などを設け、検討することで、精神疾患を身に迫る形で理解できるよう試みた。 さらに、さまざまな職種の人や学生が参加する精神医学講座でのディスカッションという形をとることで、精神疾患に対して、多職種の立場から、立体的に理解できることを目指した。職種によって視点が違うのは当然であり、さまざまな視点があるのは、望ましいことである。 日常的な言葉を使っての多職種による紙上討論を通し、読者はさまざまな視点を取り入れつつ、自分だったらどうするかを考えながら、精神疾患についてイメージを膨らませ、精神疾患についての理解を深め、対応を学ぶことができる。入門者に優しい1冊である。
-
2.0遠い過去の薄明の彼方からよみがえる、恐ろしくもどこか甘美な記憶の断章 精神科医・有坂周平の前に現れた岡元ゆず子は、自分には双子の妹がいて、小さい頃事故で死んだ、と告げて消えた。その後、作家・並木亜砂子の担当編集者となったゆず子に、亜砂子は幼い頃の記憶に触発される奇妙な懐かしさを感じた…。突然ふたりの前に現れたゆず子の奥深くに隠された記憶は、何を告発しようとしているのか。長篇サイコ・サスペンス。 ●新津きよみ(にいつ・きよみ) 1957年、長野県生まれ。青山学院大学卒。旅行会社、商社のOLを経て、88年に作家デビュー。『最後の晩餐』『意地悪な食卓』(角川ホラー文庫)、『手紙を読む女』(徳間文庫)、『記録魔』(祥伝社文庫)など著書多数。『正当防衛』『匿名容疑者』『生死不明』『トライアングル』はテレビドラマ化、『ふたたびの加奈子』は『桜、ふたたびの加奈子』として映画化された。
-
4.5ある患者は違法薬物を用いて仕事への活力を繋ぎ、ある患者はトラウマ的な記憶から自分を守るために、自らの身体に刃を向けた。またある患者は仕事も家族も失ったのち、街の灯りを、人の営みを眺めながら海へ身を投げた。いったい、彼らを救う正しい方法などあったのだろうか? ときに医師として無力感さえ感じながら、著者は患者たちの訴えに秘められた悲哀と苦悩の歴史のなかに、心の傷への寄り添い方を見つけていく。同時に、身を削がれるような臨床の日々に蓄積した嗜癖障害という病いの正しい知識を、著者は発信しつづけた。「何か」に依存する患者を適切に治療し、社会復帰へと導くためには、メディアや社会も変わるべきだ――人びとを孤立から救い、安心して「誰か」に依存できる社会を作ることこそ、嗜癖障害への最大の治療なのだ。読む者は壮絶な筆致に身を委ねるうちに著者の人生を追体験し、患者を通して見える社会の病理に否応なく気づかされるだろう。嗜癖障害臨床の最前線で怒り、挑み、闘いつづけてきた精神科医の半生記。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。












![自分を消したいこの国の子どもたち [傷つきやすい自尊心]の精神分析](https://res.booklive.jp/252499/001/thumbnail/S.jpg)













































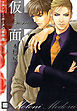










![成功率80%超! [ゆうき式]満腹なのにみるみるやせるダイエット(大和出版)](https://res.booklive.jp/335786/001/thumbnail/S.jpg)