精神科医作品一覧
-
3.8【こちらは無料小冊子版となります】 ★“心の名医”モタさんの今日からできる、『やさしい習慣術』 ★何度も読み直したいとの声続出! 精神科医 斎藤茂太がお届けする心の処方箋 ★なんとなく毎日がうまくいかないと感じるあなたへ。クヨクヨ系がワクワク系に変わる思考法!! ■心配性の原因がわかれば、前向きになれる ■厳しい現実も、「笑い話」にすれば受け容れやすい ■「他人の目」が気にならなくなる5つのレッスン ■「マイナス思考」と上手につき合う3つのステップ ■「人づき合いが不安」な気持ちにサヨウナラ ■すべて「人生80%主義」のすすめ ■心配事をため込まない2つの発想法 ■すぐにできる、心配性を寄せつけない生活術
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ふたたび地球にやってきた星の王子さまと、各界をリードするトップランナー10人。会田誠(芸術家)、上田泰己(生命科学者)、開沼博(社会学者)、金田一秀穂(言語学者)、釈徹宗(宗教学者)、泰羅雅登(脳科学者)、立川志らく(落語家)、名越康文(精神科医)、西内啓(統計家)、村山斉(物理学者)が、ナビゲーターとなった王子さまの素朴な問いに答え、常識や愛など「目に見えない、かんじんなこと」を探求する!
-
4.0「心身のあらゆる不調は、実は『消化力』の低下が原因です」 『相棒』『ATARU』等、数々の大人気ドラマを医療監修し、テレビや雑誌などでも活躍する西脇先生はそう断言します。 本書では、精神科医であり、西洋医学、東洋医学にも通じた西脇先生だからこそわかった「消化力」を高める方法をご紹介。 「朝起きた時」「お風呂場で」など、誰にでも簡単に実践できる方法で「消化力」を高めれば、あらゆる不調は一気に吹き飛びます! ■下記は、「消化力」を高める方法とその効果の一例です ・「情報の消化力」を高め、心理的な緊張をとけば―― →「肩こり」「腰痛」が根本的に治る! ・「白湯」を1日3回飲むだけで―― →内臓温度が1度上がり「冷え性」も解消! ・「潜在意識」をうまく活用すれば―― →風邪などの感染症を寄せ付けない体に! ・「糖質」を摂らなければ―― →「高血圧」「糖尿病」の9割は治る! ・「グッド&ニュー訓練法」を実践すれば―― →みるみるストレスを感じなくなる! など 【著者プロフィール】 西脇俊二(にしわき しゅんじ) ハタイクリニック院長。弘前大学医学部卒業。 1991年~1996年国立国際医療センター精神科。1996年~2007年国立秩父学園医務課医長。 1992年~2007年国立精神・神経センター精神保健研究所研究員。2007年~大石記念病院(足立区)。 2008年~皆藤病院(宇都宮)、金沢大学薬学部非常勤講師。 2009年~ハタイクリニック院長(目黒区)。2010年~European University Viadrina非常勤講師。 『主治医が見つかる診療所』(テレビ東京系列)などメディア出演も多数。 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
4.0新型うつ、アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症、万引き依存症、性依存症、ひきこもり依存症が急増している精神疾患大国・日本。苦しむ患者さんを親身になって治療し、時間がかかっても社会復帰まで寄り添う、患者さん本位の良心的病院は日本には存在しないのか。一人の精神科医が立ち上がった。榎本クリニックの榎本稔理事長その人である。入院しないで通院で治療が受けられるディナイトケア。(1)病態別年代別に細やかな専門的ケア (2)通院を便利にするため都心の一等地にクリニックを設置 (3)ユニークな系術行動療法プログラム (4)サマーフェスタ、海外旅行、大運動会などの多彩なイベント開催など 病気だけを診るのでなく、一人の生きている人間として、その人が背負ってきた生き様をトータルでとらえて、患者さんの心の拠り所となる場所をつくる。画期的なメンタル医療が誕生した!
-
-◎薬を使わずに自分のうつを治した医師の食事術 ◎メンタルが上向くきっかけは小さな食事の変化 ◎ストレスから心を守る食べ方のすべてを公開 なんとなく気分が落ち込みがちな人。 心配や不安がいつもつきまとう人。 疲れてやる気が出ない人。 ストレスをかかえるすべの人の 心を救うのは「食事」です。 私たちの体は、食べたものでできています。 ですから、食べ物が変われば体にも心にも変化があるもの。 本書で紹介するのは、7年間自らのうつに苦しんだ精神科医が実践した食事法です。 ・体に毒を溜めない食事 ・腸内環境を整える食事 ・脳の栄養を補う食事 うつから救ったのは、この3つの視点に基づいた食事法。 実践することで、体も心も変わっていくのを実感し、ついにうつから抜け出すことができました。 自分を変えるのは簡単ではありません。 ストレスの原因になっている職場や学校の環境も、 人間関係もすぐに変えられないでしょう。 そのかわり、食事を少し変えてみませんか? 「変えた」という事実は、大きな自信になります。 メンタルが回復する大事な一歩となる、食事法のすべてをお伝えします。 ※本書は、2017年10月に弊社より刊行された『薬を使わず自分のうつを治した精神科医のうつが消える食事』を改題し、加筆・修正したものです。
-
5.0現在わが国では,メンタル不調で入院・通院している患者は推定50万人と言われ,現在職場復帰できない休業者の割合が3割を超えている企業が半分もあるという事実が確認されている。そしてさまざまな理由から自死を選ぶ人はおよそ年間3万人に達している。 本書には,メンタル不調で休職していた社員が安定した就労ができるように,段階的な復職訓練や休職中の過ごし方,メンタル不調を予防するための知見から医師・会社の管理者との接し方といった実践的な対応の仕方が数多く解説されている。 著者は,「労働衛生コンサルタント」資格を持つ医師であり,精神疾患で休職した労働者が着実に仕事へ復帰できるためのプロフェッショナルサービスを多くの企業で提供した実績を持つ。休職・復職で悩む当事者と家族,企業の人事労務担当者産業カウンセラー,精神科医,心理士,精神保健福祉士等のためのセルフケアガイドブックである。
-
3.4先送り、先延ばし、 いつもギリギリ、やる気が出ない、 すべてのことがめんどくさい…etc. すぐに動けない自分を救う39の技術! 『昨日の疲れが抜けなくなったら読む本』がベストセラーとなった大人気の精神科医・西多昌規氏が、 どうしてもやる気にならない状態からの脱出法を教えます! ・仕事を前にして、心にブレーキがかかってしまうときの簡単な対処法 ・「めんどくさい」と思ったときの対処法 ・いつも「やる気」あふれる人でいるための習慣術 ・「やる気」を生み出す休み方 まで、豊富な具体例とともにわかりやすくアドバイスしていきます。 仕事のパフォーマンスを上げるためのコンディションの整え方指南に定評がある著者が教える、 「やる気が出ない」状態を抜け出し、「すぐやる人になる」ためのコツを教える1冊です。
-
-1日1分、名文を音読すれば 五感が刺激されて活力アップ! 『雨ニモマケズ』『風の又三郎』『檸檬』など 国語の教科書で学び、慣れ親しんだ名文の数々。 この名文を口に出して読むことで脳が活性化され 「ストレスを解消」 「活力アップ」 「認知症予防」 「情緒が豊かになる」 などのメリットがあります。 1日1分の音読で活力をアップしましょう! 精神科医・古賀良彦氏も提唱! 【内容】 第1章 元気になるテンポの音読 第2章 リフレッシュする音読 第3章 心が落ち着く音読 第4章 日本語のリズムを楽しむ音読 今日から読みたくなる名文が満載!
-
4.0
-
3.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ケーススタディで心理的安全性が高まる! 1万人以上のビジネスパーソンを救った精神科医の著者が自分でできる感情コントロールやセルフケアの豊富なレシピを紹介 作り笑いをするのに疲れた……。 上司の機嫌を損ねないようにお世辞を言うのがつらい・・・・・ 職場の同調圧力に耐えられない……。 そうしたあなたの中のネガティブ感情は感情労働のせいなのかもしれません。 感情労働とは、「周囲に不満を感じさせないように自分の感情をコントロールして、ポジティブに振る舞い、賃金を得る働き方」のこと。 感情労働はあなたが気づかないうちに職場の中にそっと溶け込み、徐々に心をむしばんでいきます。 でも、ネガティブ感情自体は決して悪いものではありません。適切な方法でコントロールすることが大切なのです。 本書は、感情労働のストレスを和らげるために効果的な自分でできる感情コントロール術やセルフケアのレシピを、様々な職種のケースタディを交えて豊富なイラストともに分かりやすく解説しています。 また、感情労働の負担を軽減させるために必須となる職場の心理的安全性の高め方のポイントや心身の不調を抱えてしまった時に役立つ「感情労働のおてあて」も紹介。ビジネスパーソンはもちろんのことハードな感情労働を要求される教師やメディカルスタッフにも読んでほしい日本一かんたんな感情労働の入門書が登場!
-
4.0仕事、健康、人間関係、子育て、自分や家族の将来など、自信が持てる人は少ない。ほぼ全員が不安を抱える時代になっている。「コンビニに行きたくても5分は悩む」という「カタツムリ精神科医」が自ら実践中の、不安な時代を少しでもラクに生きられる考え方と習慣を初公開!
-
3.8
-
4.3もしも魔法が使えたら、お母さん、あなたに会いたい!戦争孤児12万3000人。東京で、山形で、神戸で、空襲により孤児となった11人の少年少女たちの生きるための戦い。【解説より】苦しみに耐える子どもの顔は、あまりにも優しい。この絵本の魅力は、残酷な現実にもかかわらず、生き抜く子どもたちの美しい表情との対立にある。野田正彰(ノンフィクション作家・精神科医)
-
3.5他人にわずらわされヘトヘト気味のあなたへ。 「この世に面倒な人が一人もいない世界があったら、どんなにいいことか」 そう思ったことがある人も多いと思います。 でも、残念ながら、面倒な人は存在します。 なにもあなただけが悩んでいるのではなく、多くの人が面倒な人との付き合いに悩みを抱えています。 ではどうしたらいいか。 その悩みの解消法を精神科医で人気Youtuberの著者がわかりやすく解説。 面倒な人、苦手な人、嫌いな人と上手に付き合う方法とは。 ※あなた自身が面倒な人になっている可能性もあるので、「セルフチェック表」も掲載!
-
3.0
-
5.0メディアにセンセーショナルに取り上げられる高齢ドライバーによる重大交通事故。 日頃は慎重かつノロノロ運転という高齢者が、猛スピードで信号を無視して、歩行者をはねてしまう。 あるいは自損事故を起こし自らの命を絶ってしまう。 メディアや世間は、高齢者の運転を危険視し、ひたすら免許の自主返納を促す風潮が続いている。 長年、高齢者医療の現場に身を置いてきた著者は、そんな交通事故の背景には、高齢者が服用している薬による意識障害があるのではと指摘し、免許返納を考える前に、今一度、服用している薬の副作用のリスクを点検する必要性を説く。 我が国に蔓延する、高齢者の多剤服用と、そのことが及ぼす深刻な影響を考える。 【著者プロフィール】 和田秀樹(わだ・ひでき) 1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒。精神科医。 東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。 高齢者専門の精神科医として35年にわたって高齢者医療の現場に携わっている。 著書は、『80歳の壁』(幻冬舎)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社)、『60歳からはやりたい放題』(扶桑社)、『老人入門』『「足し算医療」のススメ』(小社刊)など多数。 発行:ワニ・プラス 発売:ワニブックス
-
-NHK「フランケンシュタインの誘惑」待望の文庫化! 「ドリトル先生」「ジキルとハイド」のモデルになった解剖医。ナチス政権下で断種法を打ち出した人類遺伝学者。大流行した、精神疾患患者の脳を切り取る「ロボトミー」を開発した精神科医。スポーツ選手を薬物漬けにし、国家ドーピング計画を推進した医師。イラク人捕虜を虐待し、心理学実験を行った社会心理学者。5人の科学者たちの希望、そして欲望と闇に迫ります。
-
4.7日本は世界屈指のギャンブル大国だ。パチンコ・スロット、競馬、競輪、競艇、そしてカジノ…ギャンブル症者は、国内推定320万人と目されている。親の貯金や年金、自宅がなくなってもやめられず、さらに借金が増え続けるというギャンブル依存。いかに地獄から這いあがるのか。文庫化に際し、カジノの危険性など最新情報を大幅加筆。現役精神科医の著者が、全国民に警鐘を鳴らす緊急レポート!
-
3.0
-
3.5なぜあなたはリラックスできないのか? 心身共に溜め込んだ疲れは、やる気をなくし、体調も崩し、不安や怒りの元にもなります。このようなハードな状況を乗り越えるのに必要なのは、上手なリラックスによってもたらされる、確かな回復力です。 姉妹本『最強の呼吸法』で紹介したのは応急処置的な方法ですが、本書では、応急処置ではフォローしきれなかった、より根深いストレスを解消していく方法を紹介しています。 いつ終わるとも知れない戦場の日々を生き抜く為のロシア特殊部隊の訓練法「システマ」のテクニックは今やロシアの医療機関や教育機関、サッカーロシア代表チームなどのトップアスリートにも採用されています。 システマ創始者ミカエル・リャブコ特別インタビュー収録 解説 精神科医 名越康文
-
1.0
-
3.8あいつだけは許せない――。 許してしまえばきっとラクなのに、 本当はイライラせず笑って過ごしたいのに、 どうしても、許せない。 なぜ、許せないのか? なぜ、許せない思いに縛られるのか? 呪縛から解き放たれるにはどうしたらよいのか? 気鋭の精神科医が、 他人を許せない心理を分析し、 ラクに生きるための処方箋を示す。
-
3.7最近、NHKの健康番組などの多くのメディアで新たな腰痛治療法として脚光を浴びているのが整形外科医と精神科医、理学療法士らが連携して「認知行動療法」などの新しいアプローチで治療を行う手法。 精神的ストレス、うつ状態、不安感などの心理社会的原因もからみ、整形外科医単独ではスパッと治せなかった腰痛の改善に大きな効果があるようです。 本書の著者は整形外科医でありながら精神科、心療内科を学び、いち早く「心療整形外科」の重要性を提唱してきた第一人者。患者さんの心理面にも詳しい整形外科医だからこそ築ける「患者さんと医者の治療同盟」によって、ウォーキングを推奨し、慢性的な痛みに悩む多くの患者さんを救ってきました。現在はピンピンコロリ運動で有名な長野県の人気整形外科クリニックで、日々多くの患者さんと向き合っています。 コロンブスの卵的手法を具体的な治癒例を交えて明かした一冊です。 「腰痛、肩こり、関節痛は、認知行動療法ほかで患者さんのこころの持ちようを切り替えれば、自分で治せるケースがたくさんあります」「こころを切り替え痛みを軽くするには、自己治癒力を高めるために、まずは少しでもウォーキングを始めることです」「からだは動かさないと痛くなるようにできています。腰痛、肩こり、関節痛は動かさないと治らない。今日から始められることが必ずあります」「原因にこだわらない、未来を考え過ぎない、決めつけない、あせらない、諦めない」「腰痛でしてはいけないことは『してはいけないことを考えること』」「アンチ・エイジングからアジャスト・エイジングへ。ピンピンコロリ運動は前向きな人生を送れるから素晴らしい」 などなど、著者の医者歴30年の経験と理論に裏打ちされた、腰、肩、ヒザなど運動器の痛みを解決する、刺激的でいて優しい、具体的方策と心理的アドバイスが満載です。 現役の整形外科医として、「なぜ医者なのに、すぐ私の痛みの原因がわからないのか? すぐに治せないのか?」「痛み止めの薬を出され様子を見ましょうと言われたけれど、もっと根本的な治療をしてほしい」「ずっと電気治療をやらされているがいつまで続ければ治るのか」「MRIを撮って手術をしたけれどそれでも痛みが消えない」といった患者さんが整形外科に感じる疑問、不信感などについても、しっかり解説しています。 「腰痛は〇〇をやるだけですぐ治る!」といった、今まで話題になった多くの治療法を実践しても、痛みが解決しなかった方。あまり痛みがよくならないのにずっと整形外科に通い続けている方。そしてそんな悩みをかかえているご家族をお持ちの方。是非この本を読んで少し気持ちをラクにして動き出してみてください。 痛みがきっと軽くなっていくハズです。
-
5.0
-
3.5七十二歳の誕生日で引退することを決めた精神科医のもとに、最後の新患が現れる。希死念慮と自殺の衝動に苦しむ彼女とカウンセリングを重ねるなかで、精神科医は自らの人生と老いや死へのおそれを見つめなおす。デンマーク人心理学者が静謐な筆致で描く小説
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 食事療法とがんが嫌がる生活で転移がんが消えた。 実際にがんを消した医師と体験者が教える転移、再発を防ぐ克服術が満載! 余命宣告を受けた医師や患者が実践したがん克服術。 転移、再発を防いで、末期がんから生還を果たした体験者たちが食べた 奇跡の食事や今ある痛みを消して前向きに生きる生活術が満載 今あるがんを小さくし、薬の副作用を半減する【済陽式ジュース&スープ1週間レシピ】 5年生存率0%からがんを克服した現役精神科医が実践した【がんと闘う5カ条】 余命半年と言われた肝臓がんを自宅で治したムラキさんが語る【1日1食のジュース断食と体温上げ法 3cm大の転移がんを10カ月で消した夫婦が語る【がんが消えた食事・生活術】 これで生きる気力が取り戻せる【今あるがんの痛みがスーッと消える生活術】 細菌やウィルス、がん細胞も食べてあらゆる病気を遠ざける【マクロファージ活性術】 白血球、リンパ球を活性化。血行をよくしてがんの痛みをとる【しょうが湿布】ほか
-
4.3ナチス収容所を生き延びた精神科医の152のメッセージ ナチスの強制収容所における体験を綴った名著『夜と霧』の著者であり、 「生きる意味」を見出していく心理療法、実存分析(ロゴセラピー)の創始者である ビクトール・フランクルが読者に熱く語りかける「魂」を鼓舞するメッセージ。 「強制収容所での体験」「愛すること」「生きることの“むなしさ”」「人生の“苦しみ”」 「生きる意味」「仕事」「幸福」「時間と老い」「人間」「神」について、フランクルの言葉を選り抜いて紹介する。
-
-
-
4.0人間の老化は、思考力や体力より、まず「感情」から始まる。40代からは、脳の中でも前頭葉というやる気や感情のコントロールなどを司る部分の萎縮が目立ち始めるからだ。これを「感情の老化」と著者は呼んでいるが、この生理現象に対処することが、40代からの勉強では重要なのである。やる気や集中力が続かず、途中で投げ出してしまうのでは、勉強の成果はいつまでたっても出ないだろう。では、どうやって、この「感情の老化」に対処していけばいいのか。本書では、受験指導のプロであり精神科医でもある著者が「感情の老化」を防ぎ、勉強へのやる気・集中力を高める方法を脳科学、学習心理学、認知心理学をベースに解説する。「枯れた」人間になっていくのか、それともこの知識社会を勝ち抜く「賢い」人間になれるのか、40代は人生のターニングポイントである。
-
3.5
-
3.040代になり、オジサンになりかけている自分にまずい! と思ったら、「雑草を抜く」「家電量販店に行く」など、この本で紹介するアクションをひとつでもやってみてください。澱んだ気持ちがカラッと明るくなり、心身ともにリフレッシュできるはず。本書は、TVでおなじみの精神科医・名越先生が、毎日の生活の中でできる小さな習慣を厳選して紹介。忙しい大人たちがその日常の合間でふとやってみたら、意外なほどリフレッシュできること、新鮮な気持ちや新しいアイディアが浮かんでくるきっかけになりそうなことが意外にたくさんあります。どのページもどの章も、あなたの人生のスタイルありき。それなりにみんな24時間バタバタしていること、疲れていることが前提です。どこから読みはじめていただいてもOK! あなたの小さな隙間時間に、ぜひやってみてください。心を瞬時に切り替えて若々しい気持ちを持ち続けよう!
-
4.3誘拐され父親に見捨てられた息子。虐待を受けた少年を引き取った精神科医。ガールフレンドに捨てられた男、あこがれの舞台女優に拒絶された少年。そんなやりきれない毎日に、寄り添ってくれる誰か――。美しい構図と研ぎ澄まされたセリフでアメリカの孤独を描き出す、多田由美の傑作短編集。
-
4.2ハーバード大学医学部准教授の著者(小児精神科医/脳神経科学者)による、”今よりもきっと楽に生きられる思考法”「リアプレイザル(Reappraisal)」の解説書。 本書で解説する「リアプレイザル(Reappraisal)」は、科学的根拠のある心理療法である「認知行動療法」の中の対処法の一つです。 それは「嫌な感情を覚えた際に、それをできるだけよい感情に変えていく」方法です。 不安・恐怖・緊張・焦燥など、さまざまな感情のコントロールに有効であることが多くの研究からわかっています。 ――――― ★「生きにくい」と感じている、すべての人へ 〇脳はなぜ不安や恐怖を感じるのか 〇感情に支配されないためにできること 〇「認知の歪み」の種類と対処法 〇自己肯定感を高める「内的評価」の育て方 ハーバード大学医学部准教授・脳神経科学者が科学的に解き明かす「脳」の仕組みと「感情」のメカニズム ――――― <本書の内容> 第1章 課題の発見 ・なぜ脳は不安を感じるのか? ・不安の正体とは? ・ポジティブ/ネガティブ思考は生まれつき? ……etc. 第2章 解決の手法 ・再評価とは――感情に支配されない自分を作る ・メタ認知と客観視 ・「認知の歪み」の種類 ……etc. 第3章 レジリエンスを育てるために ・誹謗中傷から心を守る「エンパシー」「昇華」「他愛」「ユーモア」 ・セルフコントロールできない状況での再評価――人間関係に悩んだら ・内的評価を育む――アスリートから学ぶ再評価 ……etc. 第4章 メンタルヘルスが崩れたときに ・ストレス症状や心の病気のサインに気づくことの大切さ ・メンタルヘルスと「孤独」の関係について ・恐れや不安の裏返し?――怒りとメンタルヘルスの関係 ……etc. 第5章 揺れ動く社会と再評価 ・日常に潜む小さな攻撃――マイクロアグレッション ・「元気そうなのに詐病じゃないか」――メンタルヘルスへの無意識の偏見 ・積極的に逃げてもいい――ガスライティングに気づく ……etc.
-
-〝潜在能力を開発したいなら読むべき一冊〟 精神科医 ジュディス・オーロフ(ニューヨーク・タイムズ・ベストセラー『Second Sight』著者) リモート・ビューイングとは、テレパシー、クレアボヤンス、OOB、予知能力など、あらゆる「超能力」の総称です。誰もが秘めているこれらの能力によって、私たち人類には無限の可能性が与えられています。そしてそれらは、誰もがトレーニングできる力なのです。 スタンフォード研究所(SRI)にて超感覚的知覚の研究プロジェクトの共同創立者で、中央情報局(CIA)から資金援助を受けて能力開発のプログラムを開発してきた著者が教える、真のサイキック能力。 スターゲイト計画についての全貌、実際に軍事面で利用された歴史を踏まえ、見えないものが見えるようになるノウハウを語ります。
-
-「〈臨床瑣談〉とは、臨床経験で味わったちょっとした物語というほどの意味である。今のところ、主に精神科以外のことを書こうとしている」本書は、精神科医としての長年の経験をとおして、専門非専門にかかわりなく、日本の医学や病院やその周辺について「これだけは伝えておきたい」という姿勢で書かれている。多方向からの視線ではあるが、病名を告知された患者側ができる有効なことは何かに主眼がある。「現代は容赦なく病名を告知する時代である。告知の時代には、告知しただけの医師の覚悟も必要であり、また、告知された患者も茫然たる傍観者ではなく、積極的に何かを行ないたいだろう。患者もその家族、知己も、いつまでも手をつくねてドアの外で待つだけの存在では済むまい」院内感染を防ぐには患者側はどうすればよいか。脳梗塞の昏睡患者を前にして家族にできることとは。さらにガンを持つ人の日々の過ごし方について、「丸山ワクチン」について――。その実用的な助言は、現代医療批判でもあり、自然回復力の大切さと有限性も視野に入れながら、医学の可能性と限界をくっきりと映しだしている。
-
-1,760~2,640円 (税込)なぜ今,多元主義なのか? 臨床心理学における多元主義とは?―特集にあたって 黒木俊秀 多元主義が臨床の「知」にもたらすもの 村井俊哉 [ダイアローグ×ダイアローグ]臨床における多元主義とは何か?―いかに学び,いかに育てるか 村瀬嘉代子・森岡正芳・黒木俊秀 多元主義の諸相 PTMFとメンタルヘルスケアの社会化 石原孝二 価値における多元主義 榊原英輔 発達支援における多元主義―自閉症の多様な理解を踏まえて 白木孝二 心理臨床の倫理における多元主義― 倫理的転回の立場から 富樫公一 森田療法を支える多元主義的感情観 田所重紀 統合的心理臨床の多元主義 ケースフォーミュレーションの多元的な実践―支援対象者/クライエントへの敬意としての多元主義 三田村仰 統合的心理療法をめぐって―多元主義VS折衷主義 福島哲夫 精神分析的心理療法の多元主義的展開 上田勝久 オープンダイアローグの多元的支援 下平美智代 当事者からみる多元主義 外山 愛 コラム [インタビュー]学派的多元主義と現場的多元主義 東畑開人 学派を超えた実践のスタイル―多元主義と統合 杉原保史 多文化カウンセリングと文化的多様性 岩壁 茂 投稿 原著論文|被虐待事例へのホロニカル・アプローチの特徴―複線径路等至性モデリングによる検討 千賀則史 理論・研究法論文|二枚ぬり絵法からみた慢性統合失調症者とアルツハイマー型認知症者の構成障害―時計描画テストとの関連 五十嵐愛・畦地良平・内田竜人・津川律子・横田正夫 臨床心理学・最新研究レポート シーズン3 第46回「子どもの不安への親の巻き込まれ―巻き込まれの背景による適切な介入への示唆」 藤里紘子 主題と変奏―臨床便り 第66回「セクシュアリティと性行動の心理臨床」 中原由望子 書評 富樫公一 著『社会の中の治療者―対人援助の専門性は誰のためにあるのか』(評者:小川 基) 小森康永ほか 著『ナラティブと情動―身体に根差した会話をもとめて(評者:森 茂起) 中井久夫 著/高 宜良 編『中井久夫 拾遺―対人援助の専門性は誰のためにあるのか』(評者:神田橋宏治) きむらひとみ 著『ステップファミリーの子どもとしての私の物語―親の離婚・再婚でできた「ギクシャク家族」が「ふんわり家族」になるまで』(評者:福丸由佳) 青木省三 著『精神科医という仕事―日常臨床の精神療法』(評者:花房昌美) ステファン・G・ホフマンほか 著『プロセス・ベースド・セラピーをまなぶ―「心の変化のプロセス」をターゲットとした統合的ビジョン』(評者:谷 晋二)
-
4.1日本人論の「古典」として読み継がれる『菊と刀』の著者で、アメリカの文化人類学者、ルース・ベネディクトが、1940年に発表し、今もロングセラーとなっている RACE AND RACISMの新訳。 ヨーロッパではナチスが台頭し、ファシズムが世界に吹き荒れる中で、「人種とは何か」「レイシズム(人種主義)には根拠はあるのか」と鋭く問いかけ、その迷妄を明らかにしていく。「レイシズム」という語は、本書によって広く知られ、現代まで使われるようになった。 「白人」「黒人」「黄色人種」といった「人種」にとどまらず、国家や言語、宗教など、出生地や遺伝、さらに文化による「人間のまとまり」にも優劣があるかのように宣伝するレイシストたちの言説を、一つ一つ論破してみせる本書は、70年以上を経た現在の私たちへの警鐘にもなっている。 訳者は、今年30歳の精神科医で、自らの診療体験などから本書の価値を再発見し、現代の読者に広く読まれるよう、平易な言葉で新たに訳し下ろした。グローバル化が急速に進み、社会の断絶と不寛容がますます深刻になりつつある現在、あらためて読みなおすべきベネディクトの代表作。
-
-――掲載ページより「巻頭言」―― 前号の巻頭言で、大正から昭和初期にかけて出ていた雑誌とからめて、本誌のめざすところを述べてみた。これを読んでいただいての反応かどうかはわからないが、ある読者(高名な精神科医、執筆家)から次のようなお便りをいただいた。 「『旅と伝説』のよみがえりかな、となつかしく思いました。私の少年時代には、こういう雑誌がちらほら残っていました。昔は民俗学も人類学も大学の教科でなく、試験もなかったため、みんなが勝手なことをいっていました。それでおもしろかったのだと思います。昭和の初期は悪い時代だというのが定説らしいですが、独創的、野人的で、おもしろいことをいう人がいました。昔を思うこと切です。」 うれしいお便りであった。今日の「知的情況」の中で本誌の果し得る役割について、若干の自信が得られたような気がしたことであった。なお、鈴木光志氏の「私の古井遍歴 8」も、御ー読いただければと思う。 礫川 全次 男装の怪盗[フォークロア:点描]◎鈴木光志 /銀座・夜店の古本屋[私の古書遍歴]◎越智信義/尾張サンカの研究(4)[回遊竹細工師「オタカラシュウ」の面談・聞き書き・検証調査]◎飯尾恭之/福沢諭吉の異色作『かたわ娘』[ニッポン民俗学外史4]◎礫川全次/鯨は神だった◎下村巳六/菊池山哉小伝(4)◎田中紀子/西国巡礼行者「尼サンド」について(3)◎玉城幸男+小林義孝/幕末期におけるある非人部落の生活と風俗[玄海部落の場合]◎松浦国弘/江戸の人々と「六地蔵石灯篭」[浅草寺「六地蔵石灯篭」考余録]◎武井利通/私の古書遍歴◎鈴木光志/しゃぐじ神信仰覚え書き(1)◎吉村睦志/一石五輪塔は何を語るのか(下)◎横田明+西山昌孝+小林義孝/弥生時代の鉄製工具を用いた石器製作[技術革新か、あるいは消滅していく技術の輝きか]◎栗田 薫/全戸に配布された「岬町の歴史」◎小林義孝/山上の道◎伊藤貞樹/私の古書遍歴◎塩崎幸雄/一人の機知、万人の智恵。ことわざの性質について◎ウォルフガングー・ミーダー著・武田勝昭訳/資料篇 解説◎礫川全次
-
-レムリアからアトランティス、そして「今、ここ」で! 沈んだ文明より転生した魂たちの覚醒をうながす「One truth」 このストーリーのどこかにあなたが潜んでいる! 精神科医エリザベス・キューブラー=ロス博士、推薦の書! アルタザールの伝説はもっと知られるべき物語です。 これは記号言語を用いて語られた、実話です。皆様の、そして私の運命のお話です。ここでは古代文明のレムリアとアトランティスが滅んだ理由が詳細まで描かれています。 長い長い転生の旅からの解放! この惑星上の人生最後の大仕事の始まりを告げる書! 「アトランティスについての史上最高の物語」(COBRA) 神聖な目的を決して諦めなかったあなたに聴こえる帰還命令! 「思い出してください。惑星地球の、真実の歴史を! レムリアの最期、ANの光の塔、アトランティス沈没、エジプト創始やその先の物語。 南米にあった古代の神秘王国ANを目指して旅立つレムリアのいと高き王アルタザール。 真の自由を得るまでの葛藤。愛と感動と追憶の冒険譚!」 今この瞬間も、螺旋周期は廻り続けています。故郷〈ホーム〉への帰還令が聴こえてきたのなら、各自配置につけるように準備を始める時です。古の星天家族〈スター・ファミリー〉が一堂に会する時です。そして共に力を合わせ、二元性を一元性に変化させましょう!
-
3.7あなたの恋愛力はどのくらい?一級?それとも四級? 7人の男女の恋愛模様(ストーリー)を注意深く見守る「恋愛の神様」が、それぞれの主人公たちのランクを判定!小説を読みながら自分の恋愛スキルが確認できる、まったく新しい恋愛エンターテインメントが誕生。ゆうきゆう氏(精神科医・ゆうメンタルクリニック院長)の丁寧な「解説」付き。NHKBSプレミアムでドラマ化された話題作が待望の電子化!
-
4.5
-
4.5老いに対する正しい知識がないことで、過度に不安になったり、老いが加速したり、結果的に不幸な老い方をしている人が多くいます。 そこで本書では、老年医学の専門家による 「これだけは知っておかないともったいない」 という、必須知識をわかりやすくまとめました。 「老いはゆっくりとしか進まない」 「筋肉は日常生活で維持できる」 「脳の機能は自由時間を楽しめば維持できる」 「認知症は過度に心配しなくていい」 「With病気という考え方で穏やかな老後を迎えられる」 「ほかの高齢者はどういう感情で生活を送っているのか?」 「老いは本来、幸せな時間」 「老いてからの人生はどんなに奔放でもいい」 など――。 年齢を重ねるたびに“どんどん楽に、幸せになっていく” 老い方の手引きをご紹介します! 老親をもつ世代にもおすすめです。 【著者プロフィール】 和田秀樹 (わだ・ひでき) 1960年、大阪府生まれ。 精神科医。老年医学の専門家。 東京大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。 高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。 『70歳が老化の分かれ道』(詩想社)、『六十代と七十代 心と体の整え方』(バジリコ)、『80歳の壁』(幻冬舎)など、著書多数。
-
-親子、夫婦、友達、職場、ご近所……、いつの時代も人間関係の悩みは尽きません。多くのシニアから人間関係の悩み相談を受けてきた精神科医が、シニア世代こそ、しんどい関係は手放し(ときには縁を切ることも大切!)、自分に正直に生きることを提案しています。本書では、「和田秀樹流・幸せを引き寄せる人づきあい43のヒント」を解説します。 【本書の内容】●第1章 遠慮をやめれば人間関係は「ちょうどいい加減」になる ●第2章 65歳からは「自分がラクで心地よい」が最優先 ●第3章 つかず離れずが「いい加減」 ●第4章 縁は切った分だけ足せばいい ●第5章 最後まで自分の「いい加減」で生きよう がまんを続けるほど人生は長くありません。自由な時間を得たシニア世代だからこそ、ムリせず、楽しく、ラクに! しがらみや心配事を手放して、自分にとっての「いい加減」を見つけて、いまよりも心地よい、幸せな人生をぜひ手に入れてください。
-
-だるさ、疲れ、不安、「聞こえづらくなった」などの聴覚障害、息苦しさを感じることがある、朝起きるのが憂鬱、気がついたら涙が出ている……など、50代後半からあらわれる心身の不調。精神科医が、臨床の現場で見られる「60歳うつ」を考える。人生100年時代になり、今後40年を「どう生きたらいいのかわからない」。これによって、知らない間に精神的に落ち込んでいく人たちがいる。この場合、じつは「栄養が足りていない」ことが多い。先進国の日本が、質的な栄養失調状態であることは、あまり知られていないのではないか。「藤川メソッド」による分子栄養療法を行なうと、向精神薬の服用やカウンセリングよりもずっと早く、驚異的なスピードで症状を改善していく。本書では、各症例と改善の経緯、なぜ藤川メソッドを実践することになったのか、生活習慣と回復後の生き方についても論じる。最終章では、藤川徳美先生と分子栄養療法について行なった対談を収録!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「日々、ためす、楽しむ」 これこそが、若々しさの秘訣です。 女性は60歳からがチャンス。 それは医学的にも正真正銘の事実です。 更年期を経て閉経を迎えるころ、 ホルモンの変化をきっかけに女性の心と体は活性化。 とても意欲的になります。 それなのに、老い、病気、お金などへの心配事にとらわれ、 せっかくの意欲を、押し殺してしまうのはもったいない! 著者累計1000万部を超えるベストセラー作家であり、 長年高齢者医療の現場に携わる精神科医がすすめるのは、 「60代からは新しいことにチャレンジし、どんどん楽しむこと」 それが、脳の前頭葉を活性化させ、 衰えない心身をキープすることにつながります。 本書は、脳・心・体に自信を持ち続けるために取り入れたいことを 春夏秋冬365日分、提案します。
-
4.5
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 名作『ロダンのココロ』の作者の待望の著作!!気持ちにまつわるエピソードを「いろは」の数え歌にのせた『ロダン』のマンガと著者自身の精神世界の不安との格闘体験が文章で綴られる。監修に精神科医の海老澤先生。『ツレがうつになりまして。』の細川貂々さんの特別寄稿漫画も掲載!内田かずひろさんの、優しい絵本のような「ロダンのココロ」のマンガと、訥々としていながらも心打つ文章。素朴で実直で誠実な著者の人柄が全編ににじんでいます。こんなに心の不安が叫ばれている時代はないと思います。これは“心の不安”と向き合って闘っている一冊です。この本を読んで少しでも気持ちが楽になってもらえたら、少しでも勇気と共感を感じてもらえたら嬉しいなと思います。
-
3.9自閉症スペクトラム(アスペルガー)、ADHD(注意欠如・多動性障害)、LD(学習障害)のトリプル発達障害を持つ作者が、自身の日常をセキララに描くコミックエッセイシリーズ・まだまだやらかす第7弾!! 発達障害研究の第一人者・精神科医 岩波明先生との対談「発達障害のライフハック」も特別収録!!
-
3.0
-
4.3「毒親に殺されないで、よかったね」……?ふざけるな! 義父の性的虐待、母のネグレスト、精神病院閉鎖病棟の闇……。トラウマは一生続くだろう。それでも、明るく笑って前に進みたい! ――SNSで話題の著者・羽馬千恵(はばちえ)が、虐待を受けて育った子どもが、大人になっても多くのトラウマや精神疾患を抱え、社会を渡り歩くことがどれほど困難かを赤裸々に綴った衝撃の問題作。親に殺されなければ、なかなかニュースに取り上げられない「虐待事件」。殺されず生き延びた大人の「未来」にもっと目を向けてほしい。 精神科医の和田秀樹氏との特別対談「虐待サバイバーたちよ、この恐ろしく冷たい国で、熱く生きて行こう!」も必読! 【本書の内容】 こうして「虐待」は始まった。 第2章 「離婚」「貧困」「再婚」「虐待」でぐるぐる。 第3章 愛着障害~精神崩壊へのメルトダウン 第4章 大人になってもトラウマは続く! 第5章 母の物語から見える虐待の連鎖 第6章 解離―虐待がもたらした大きな爪痕対談 和田秀樹×羽馬千恵―虐待サバイバーたちよ、この恐ろしく冷たい国で、熱く生きて行こう!
-
3.0
-
4.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 老年医学の専門家・和田秀樹が初めてこれまでの人生を振り返り、これからの人生を語る和田自身の人生100年時代の設計図。 血糖値600オーバー! 血圧200オーバー! 病気のデパートのわたしが 自由で幸せな生き方を 人体実験中! 人生100年時代が叫ばれ、 平均寿命も毎年、 確実に上がり続けている。 これを手放しで”長生きできてうれしい” と思う高齢者は ひとりもいないのではないか? いや、それどころか、 老後資金の枯渇問題、 健康や認知症といった 老いへの恐怖などなど、 不安を抱えている高齢者が どれだけ多くいることか。 そんな暗雲垂れ込める 人生100年時代を、 30年以上の長きにわたり、 高齢者医療に携わってきた 医師でありベストセラー作家でもある 和田秀樹が、初めて自身の人生を振り返り、 そして、これからの人生を語る 和田自身の人生100歳時代の設計図。 ひとたび読めば、 老後の不安がみるみるうちに消えていき、 人生を幸せで豊かにしてくれる ゴールデンシニア 待望の福音の書である。 *本書・目次より はじめに 【序章】0~60歳までの地図 ~生まれついての変わり者 【第1章】60歳からの地図 ~第2の人生のスタートはまだまだ先 【第2章】70歳からの地図パート1 ~70代で終わらないために 【第3章】70歳からの地図パート2 ~わたしたち高齢者の手で社会を変える 【第4章】 80歳の壁を超えてからの地図 ~死の不安に振り回されないために 【第5章】100歳の地図 ~人生はすごろくゲーム あとがき 和田 秀樹(ワダヒデキ):1960年大阪府生まれ。精神科医。東京大学医学部卒。アメリカ・カールメニンガー精神医学校国際フェロー、浴風会病院精神科医師、東京大学付属病院精神神経科助手などを経て現在、ルネクリニック東京院院長。立命館大学生命科学部特任教授。30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わる。2022年7月より日本大学常務理事。主な著書に『80歳の壁』(幻冬舎)、『70代で死ぬ人、80代でも元気な人』(マガジンハウス)など多数。
-
3.6
-
4.4
-
-生きづらさを抱えながら、みんなで「なんとか生きていく」。 青年期に非行・犯罪行為を繰り返し、現在は薬物・アルコール依存と共に生きる渡邊洋次郎さん。生きづらさを抱えながらみんなで「なんとか生きていく」方法を探るための対談集です。精神医療・若者支援・心理療法・教育・宗教など、多様な領域の実践者・研究者との対話を通して、自らの傷と向き合いながら、誰もが生きやすい社会のあり方を考えます。 【目次】 第1章 対談者―松本俊彦(精神科医) 自己責任社会で弱さを抱えて生きていく 第2章 対談者―村木厚子(元・厚生労働省事務次官) 犯罪は弱さや生きづらさの裏がえし 第3章 対談者―伊藤絵美(公認心理師・臨床心理士) 弱さでつながり、弱さに応える 第4章 対談者―小国喜弘(教育学者) 「しんどい子」をみんなで支える学校 第5章 対談者―高木慶子(心理学者・神学者) グリーフケアとリカバリー 【著者】 渡邊洋次郎 1975年、大阪府生まれ。介護福祉士。現在、依存症回復支援施設の職員。著書『下手くそやけどなんとか生きてるねん。』(現代書館)。
-
5.0仕事でも家庭でもプライベートでも忙しいビジネスマンがどのように時間をつくって、効率よく勉強すればいいのか? また、限られた時間の中でいかにして自分の目標に最短・最速で到達できるのか? 本書では、精神科医でもあり、受験勉強研究家でも定評のある著者が、自らの経験や脳科学、認知心理学などをもとに、人の3倍勉強がはかどる技術を伝授する。「脳のメカニズムを知れば、記憶力を高められる」「『やらざるをえない』状況になると記憶力はよくなる」「賞罰をつけたほうが勉強は面白くなる」「人はアメを用意するとやる気になる」「答えを見て暗記していくほうが効率的」「一週間の目標を五で割って、一日の目標量とする」など、著者が長年磨き上げてきた和田式・大人のための要領勉強術の秘訣をビジュアル図解とともに紹介する。やり方を一つ変えるだけでも、能率は大幅にアップする!
-
-小説投稿サイト〈エブリスタ〉×竹書房が選ぶホラーの頂点 第4回最恐小説大賞受賞作! 脳がザワつく衝撃ラストを見届けよ――。 フリーの編集者・正木和也は妻と五歳の息子・蒼太を連れ、ひと夏を都会の喧騒から離れた避暑地の別荘「カブトムシ荘」で過ごす。 そこは、知人の精神科医が好意で貸してくれた私荘で、妻子が負った列車事故のトラウマを癒すための滞在であった。 時折、失せ物探しや予知など不思議な能力を見せる蒼太。 そして、蒼太にしか見えない友達・コウタ。 正木は別荘のある村の墓地で詩織という少女に出会い、村に伝わる不気味な奇譚、子を攫う妖鬼〈コトリ〉の伝説を知る。 そして始まる村の夏祭り、蒼太が消えた……。 脳を攪乱する衝撃の展開、現実が足元から崩れ去る戦慄のホラーミステリ! *** 寺の掛け軸に記された子をとる鬼【コトリ】の由来—— ある山に鬼がいた。 時折里に下りては子供を攫って食った。母親の嘆き悲しむのを見て己の所業を悔いた鬼は、食った子供に成り代わり、その後母親と共に暮らしたという……。 「ハッピーエンド? これが?」 「母親が鬼と知らなければ。最後まで騙し切れたら、きっとそう――」 世界は、どんな悍ましさも悪も正義になる。
-
-凶悪犯罪が絶えないゴッサムシティ。若き精神科医ハーレイ・クインは、ある夜ルームメイトの遺体を発見する。 そこには謎の連続殺人犯、ジョーカーの痕跡があった。事件は未解決のまま5年の月日が経ち、またしてもジョーカーによる殺人事件が発生してしまう。凶悪犯罪のプロファイラーとしてゴッサム市警に協力するハーレイは、ジョーカーの正体を突き止めようと躍起になり、死屍累々の追走劇が始まる! ●収録作品● 『Joker/Harley: Criminal Sanity』#1-8 『Joker/Harley: Criminal Sanity-Secret Files』 (c) & TM DC.
-
-狂気のヒロインとDCコミックスのナイスガイたちがチームアップ!? スーパーヒーローからアンチヒーロー、はたまたヴィランまで!? ハーレイがDCユニバース中の名物キャラたちを巻き込む(はた迷惑な?)人気シリーズが、ついに邦訳化! 純粋な心とちょっと危険な精神を持った精神科医といえば…… そう我らがハーレイ・クイン! 東西南北いたるところで暴れ回り、ついには銀河系へと飛び出して、宇宙の鼻つまみ者、賞金稼ぎロボともチームアップしてしまう始末。 規格外のキャラクター、ハーレイにとって、やっぱり地球は小さかった? ●収録作品● 『HARLEY’S LITTLE BLACK BOOK』 #1-6 (c) & TM DC.
-
4.5緊急治療を要する精神病患者に24時間取り組む病院の真実! 日本初、救急の精神病患者を専門に受け入れ治療する千葉県精神科医療センターを3年間にわたり密着取材。「精神科救急」と呼ばれる医療の現場をあますところなく精密に活写した。24時間態勢で最前線に立つ医師、看護師たちの闘いと苦悩と喜び、新薬の登場、そして精神科医療の大変革を描く渾身のノンフィクション。
-
3.7「うちの子、理解されにくいかも……」「うちの子、学校になじめないかも……」。言葉としてはよく知られるようになった「発達障害」。ただ、障害の詳しい特性や、望ましい接し方、「療育」など支援の仕方など、肝心なことはまだまだ十分知られているとは言えません。大切なことは、周囲の方が「発達障害」について正しい知識を持ち、早いうちに子どもが抱えている困難感を理解して、その子が持っている伸びる力を発揮できるようサポートしてあげることです。本書は、発達障害を持つ子どもが、すこやかに成長し、将来自立していけるように、発達障害の基礎知識、療育や支援の受け方など、実践的で役立つ情報を児童精神科医師がやさしく解説し家族を応援します。
-
4.0
-
3.310分で読めるミニ書籍です(文章量5000文字程度=紙の書籍の10ページ程度) 10分で読めるシリーズとは、読書をしたいが忙しくて時間がない人のために、10分で読める範囲の文量で「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」を基本コンセプトに多くの個性あふれる作家様に執筆いただいたものです。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 まえがき 精神科医療の中に三大精神病という言葉があります。これは、脳の形や大きさなどの形質に起因するのではなく、脳の中に流れる神経伝達物質等に起因して精神症状が出るものの中で、特に、原因が解明されていなく、再発を繰り返し、完治しにくいということであげられているものです。躁うつ病は統合失調症、癲癇と一緒に、この三大精神病と呼ばれている病です。 簡単にいうならば、ハイテンション(躁状態)と落ち込んでいる状態(うつ状態)が交互に出現する病です。 一般的に、躁状態の時は外出も、グループ活動も可能なので、人と会う機会が多い方は割と良く出くわすかもしれません。ハイテンションは誰にもある状態ですので、社会の中で出会ったとしても、それが病理によるハイテンションと理解されるよりも、もともと性格的にハイテンションな人と理解されることが圧倒的に多いです。
-
3.0
-
-10分で読めるミニ書籍です(文章量5000文字程度=紙の書籍の10ページ程度) 10分で読めるシリーズとは、読書をしたいが忙しくて時間がない人のために、10分で読める範囲の文量で「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」を基本コンセプトに多くの個性あふれる作家様に執筆いただいたものです。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 まえがき 最近は、様々な媒体で統合失調症が取り上げられることも増えてきました。しかし、一部のドラマや映画、本などでは統合失調症が正しく取り上げられておらず、中には誤解を招くような表現のものも少なくありません。 皆さんは統合失調症についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。 実は統合失調症と言っても、その状態像が一つに確定するわけではありません。当然のことですが、患者さんによって出方が異なりますし、予後もかなり変わってきます。統合失調症は精神科医療の中で最も頻繁に研究が行われる病の一つです。現在は有効な抗精神病薬を発売されており、かなりの割合で症状を軽快させられるようになってきました。ある意味、統合失調症と投薬はワンセットなのですがまだまだ投薬に対して偏見も多いのかなと感じています。 この本では統合失調症の典型的な症状や、治療の実態をお伝えすることができればよいかなと感じています。 正しい治療を行うことと同じくらい、周りにいる人がこの病に理解を示すことは重要です。 統合失調症を知るための最初の一冊となるように、なるべくいろいろなことに触れたつもりですので、興味のある方はこの本をきっかけに専門書を読んでいただければと思います。 また、本書に出てくる例や事例はすべて筆者が専門書で解説されている症状を元に作り上げたフィクションの事例です。
-
4.0元気も食欲もなく近寄ってこない/来客があるたびに激しく吠える/家のなかで尿による匂いづけをする/自分のしっぽを追いかけまわすこれは「病気」? たんなる「悩み」? 臨床と基礎の両分野をこなす数少ない研究者として、国内外において双極性障害の研究を牽引している著者が、「うつ」について脳と心の両面から考えた意欲作。動物にも精神疾患はあるのか?――この疑問は、そもそも「心の病」とは何か、私たち人類はどうすればこれを克服できるのかという社会問題そのものである。毎年三万人が自殺で亡くなり、休職者の激増が取り沙汰されながら、じつは根本的な原因も確実な診断法や治療法もわかっていない精神科医療の実情。ただ話を聞いて「とりあえず抗うつ薬」では、真の問題解決にはならない。ひょっとしてうちのイヌ、うつ病!? 何も語らない動物を通して、「悩み」と「病気」の線引きの難しさ、心と脳をつなぐ研究の最新動向を読み解く。
-
4.0才能を潰すことなく、末長く創作活動を続けるためにできること アーティストには付き物の、破天荒なエピソードや空気を読まない奇行、遅刻や細部への異常なこだわり……。周囲からは“ 付き合いづらい”、“ 理解しがたい”と思われるこうした現象は、実は彼らの単なるワガママではなく、自閉症スペクトラムを始めとした生来備え持っている個性的な特徴が現れているのかもしれない。また、彼らの周囲の人もちょっとした固定観念を持っているせいでお互いに理解し合えないのかもしれない。本書では、元バンドマンでマネージメントの経験もある専門学校の新人開発室室長と、現役精神科医師が、そのような観点から“ 個性的すぎる才能”を活かす術を考えていく。アーティストとその周りの人間(家族やスタッフ、バンドメンバー)がお互いを分かり合えば、せっかくの才能を潰すことなく、末長くアーティスト生活を送れるはずなのだ!
-
-
-
-10分で読めるシリーズとは、読書をしたいが忙しくて時間がない人のために、10分で読める範囲の文量で「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」を基本コンセプトに多くの個性あふれる作家様に執筆いただいたものです。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 まえがき 思春期の心理臨床を行なっていると、女の子に多く見られるのが自傷です。それはリストカットをはじめとして、アームカットや広義にはボディピアッシングなども入ってきます。勿論、男性でも自傷される方はいらっしゃるのですが、実際の現場では女性の方がその比率が多いのが事実です。私も様々な、クライアントと出会い、多くの自傷を見てきました。特に、思春期の臨床を行なっていると、女の子の殆どは自傷を体験していると言っても過言ではありません。精神科医療の現場だけでなく、学校などでスクールカウンセリングを行なっていても学年に2~3人いてもおかしくないのではないかと思うほど自傷は身近になってきたといえます。よく、「自傷は構ってほしいだけだから」や「自分を確認するために自傷しているんだよ」という言葉をメディアや噂で聞きますが、果たしてそれは本当なのでしょうか? この本は、リストカットをはじめとした自傷について色々な視点から解説されています。現在自傷をしてしまった人が回りにいる人には是非一読してほしいと思っています。また、自傷をしてしまった本人の人も、「なるほど、こういう考え方もあるのか」と再発見することも少なくないと思います。 また、学校関係者や児童福祉関係者の方は自傷に接する機会も多いと思いますので、是非一度読んでいただければと思っています。 また、本書に登場する事例は筆者が専門書の記述を元に作り上げたフィクションの事例です。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。










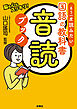







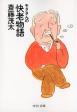










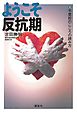
































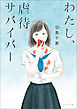


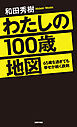



![[和田式]大人のためのハイスピード勉強法](https://res.booklive.jp/119333/001/thumbnail/S.jpg)














