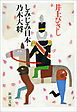天皇作品一覧
-
-明治維新から日清・日露戦争を経て、「世界の一等国」の仲間入りを果たした日本。イギリスとの条約改正を成功させ、三国干渉を素早く収拾するなど、近代日本の外交の礎を創り上げたのが陸奥宗光ならば、日本の存在をさらに押し上げたのは、陸奥宗光に見出された、この小村寿太郎であるといってよいであろう。英米の力を背景にロシアに対抗し、その後、日本独自の大陸進出を目指した小村であったが……。小村が負わされた外交は、必ずしも順風の中での外交ではなかったのである。本書は、興隆期日本の命運を背負った小村の生涯と日本の近代化の過程を、あくまで客観的に描いた、力作評伝であり、近代史の研究書でもある。小村がこの世を去ったのは明治44年11月のこと。翌年、明治天皇は崩御し大正時代を迎える。明治日本の外交を担った男に運命的な何かを感じるのは、著者だけではないだろう。著者のライフワーク「外交官とその時代」シリーズの第二弾。
-
4.0日本とはどんな国なのか、なぜ米が日本の歴史を解く鍵なのか、通史を書く意味は何なのか。きわめて枢要でありながらも、これまであまり語られてこなかった興味深い問題の数々。先鋭的な現代日本史学の泰斗、網野善彦、石井進が、古代律令制から明治時代に至るまでを、エキサイティングに、そして縦横無尽に語りつくす。対談形式のため、高度な内容であるにもかかわらず、読者にも理解しやすく、読み進むにつれ、この日本という国の真の姿が眼前に立ち現われてくる。今までイメージされてきた国家像や、定説とされていた歴史観に根本的な転回を迫る衝撃的な書。
-
-建国記念日はなぜ2月11日なのかご存知だろうか? これは、天武天皇が編纂を命じた『日本書紀』の中で神武天皇の即位年を「辛酉年正月朔(庚辰)=紀元前659年2月11日」としたからだ。しかし、古代の日本には暦がなく、『魏志倭人伝』にも「(倭人は)正月や四季を知らない。ただ春耕秋収を記録して年数を(数えて)いる」と記されている。では、『日本書紀』の編者たちはどのように、神武天皇の即位年を決定したのか? 本書は、5~7世紀に使用された「元嘉暦」「儀鳳暦」を読み解くことで、古代天皇の実像に迫ろうというもの。◎讖緯思想と神武天皇の紀年 ◎天武天皇と天文 ◎武内宿禰の存在 ◎空白の二年間の主役・宇治(菟道)稚郎子太子 ◎最後の「武」は武烈天皇? ◎天皇となった飯豊皇女? 暦から古代史の真実が見えてくる!
-
3.5
-
4.4この1冊で日本の電力問題は決着を見る! 東日本大震災そして原発事故から1年。放射線に汚染された国土は一向に回復の目処が立たない。それどころか汚染は蓄積され、今後百年以上福島第1原発周辺に人は住めないだろう。万が一同様の事故が起きたら、日本は消滅するかもしれない。にもかかわらず、なし崩しに原発再稼働に向けた動きが顕在化している。竹田氏は原発推進派が今も上げるその根拠を徹底検証する。そして原発がいかに日本に合わないか、さらには不必要であるかを明らかにし、原発の10分の1で同出力が得られるガス・コンバインドサイクル発電による代替を提唱する。明治天皇の玄孫である著者が「日本人の感性」や「日本人論」から原発問題の核心に迫った目からウロコの脱原発論。この1冊で日本の電力問題は決着を見る!
-
4.3
-
-1巻330円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 戦後75年、日米安保改定60年に当たる2020年は新型コロナウイルスの感染拡大に始まり、アメリカ大統領選挙に向けて激動を続けている。この特集では、ロングセラー『失敗の本質――日本軍の組織論的研究』にならい、歴史と現代を往還しながらコロナ第1波などから教訓を導き出し、新しい時代のリーダー像を探る。 ※『中央公論』2020年9月号特集の電子化です。 ※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページがございます。 (電子版通巻103号) 【目次】 ⚫内向きの対立を超えて 地方のトップに委ねるべき 小池百合子 ⚫国民を巻き込めなかった憲法論議 九条改正は急ぐ必要はない 石破茂 ⚫合流への挑戦に後悔はなし そして臨む野党再編 前原誠司×〔聞き手〕井手英策 ⚫なぜ安倍政権は支持率が低下したのか データから分析するコロナ禍の各国首脳支持 加藤創太 ⚫【対談】米国は? 日本は? コロナで見えた新たなリーダー像 世界を席巻 リバタリアン的若者と 指導者はどう向き合うか 宇野重規×渡辺靖 ⚫《隣国リーダー解剖学》 ①習近平 土着共産主義者の皇帝化 益尾知佐子 ②文在寅 フォロワーの支持は続くか 浅羽祐樹 ⚫【対談】『沖縄決戦』八原博通と瀬島龍三の発掘資料から読み解く 誰も責任をとらない 日本軍 組織の病 戸部良一×武田知己 ⚫「昭和史の天皇」を次世代に引き継げ 伊藤隆 ⚫「昭和の戦争・軍事史」必読10冊 筒井清忠
-
-橋下徹公式メールマガジン「学者やコンサルでは伝えられない橋下徹の「問題解決の授業」」を号毎に電子書籍化。 <今号の内容> ■なぜ「野党共闘」ではダメなのか? ■野党「予備選」は世論調査を活用すれば実現する ■鍵は「国民からの敬慕の念」。令和時代以降の皇位継承はこの考え方で ■「男系・男子誕生のための女性宮家の創出」という新しい視点 <橋下徹メッセージ> 『独裁者』『民主主義の破壊者』と散々な言われ方をされてきた僕ですが、私人に戻った今だからこそ、皆さんにお話したいことがたくさんあります。府知事、市長在任中に、メディアで報じられたことは全体の中のほんの一部。しかも、いちいち訂正するのが間に合わないほどに好き勝手に報じられました。僕が何を考え、大阪府、大阪市の改革、そして大阪都構想を目指したのか。小さな弁護士事務所の代表から38歳で政治家に転身した僕が、いかにして数万人規模の役所組織をマネジメントしたのか。資金も組織もない中でいかにして政党を作り上げ、マネジメントしたのか。それまでの役所の常識・行動様式とぶつかり合い、いかにして前例のない大胆な改革を実行したのか。そういった本当に価値のある話は、メディアは報じてくれないんです。だから自慢話を織り交ぜながら(笑)、皆さんのビジネスに少しでもお役に立ててもらえればという気持ちで全てを話すためにメールマガジンを始めます。僕を散々に批判してくれた人たちとも、今まで以上に議論を戦わせていきたいと思っていますので、どうぞよろしく。
-
-『日本書紀』の中には、まだ謎と秘密がいっぱい眠っている! 著者の古代史は、大胆な推理、緻密な分析、ユニークな視点が特徴で、多くのファンに親しまれている。本書は、古代史の入門者に向けて、著者独自の謎解きのノウハウを余すところなく解説した古代史エッセイ。内容は、◎なぜ誰もが蘇我氏の地・飛鳥を懐かしんだのか ◎『古事記』だけ読んでも古代史の謎は解けない ◎武烈天皇の非道と継体天皇の出現 ◎『日本書紀』は何のために書かれたのか? ◎纏向遺跡にも確認された東国の存在感 ◎謎がないと信じられている時代に謎がある ◎聖武天皇がなぜ豹変したのか、自分で仮説を立ててみる ◎表裏一体だった「鬼」と「神」 ◎伊勢神宮や新道は本当に「日本的」なのか ◎『日本書紀』には「聖徳太子」は登場しない ◎神社の伝承に記されたヤマト建国直後の政争と結末 ……など、興味が尽きない話題を通覧する一冊。『古代史は知的冒険』を改題し、再編集。
-
-羽生結弦に阿修羅を見出し、BTSに花郎(ファラン)との共通性をあぶり出す。オタマジャクシ型の楽器に、人間と自然の中間領域にある音楽の本質を見出し、ビル・ゲイツの離婚と資本主義精神の根源的な関係を解き明かす。宝塚歌劇団の大階段と巨大古墳に潜む「死と再生」の儀式とは何か? 人間の無意識にあって太古以来不変の動きをする神話的思考を現代の森羅万象に探る。47のエッセイが、この世界と人間の脳の未知の構造に触れる試みです。 【目次】 プロローグ I スケートボードのポエジー ウルトラマンの正義 『野生の思考』を読むウルトラマン オタマトーンの武勲 宇宙犬ライカ ベイブvs.オリンピック 近代オリンピックの終焉 M氏の宇宙飛行 成長のミトロジー 惑星的マルクス II シティ・ポップの底力 氷上の阿修羅 神仙界の羽生結弦 音楽はどこからやってくるのか 花郎(ファラン)とBTS 古墳と宝塚歌劇団 聖なるポルノ アンビエント 非人間性について タトゥーの新時代 III ミニチュアの哲学 乗り鉄の哲学 abc予想 低山歩き復活 第九と日本人 ウクライナの戦争 戦闘女子 『マトリックス』と仏教 IV ポストヒューマンな天皇 フィリップ殿下 シャリヴァリの現在 家族の秘密 キラキラネームの孤独 愛のニルヴァーナ 「人食い(カンニバリズム)」の時代 『孤独のグルメ』の食べる瞑想 自利利他一元論 V サスペンスと言う勿れ 怪談の夏 渋谷のハロウィン 鬼との戦い 丑年を開く 大穴持(オオナモチ)神の復活 気象予報士の時代 エコロジーの神話(1) エコロジーの神話(2) 反抗的人間の現在 謝辞
-
-『学習まんが 日本の歴史』(全20巻)から、歴史人物101人が学べる別巻が登場! 卑弥呼から安倍晋三まで、日本史上の重要人物101人が何をしたのかを9つの時代区分に分け、まんがと解説で説明しています。さらに、101人の生きた時代がひとめでわかるグラフも収録いたしました。試験で深く掘り下げて考える問題が増えた昨今、誰が何をしたのかをしっかりと理解することは、試験にも、教養としても役立ちます。『学習まんが 日本の歴史』(全20巻)と対応しており、合わせて読むことで、いっそう理解が深まり、日本史がより楽しく学べます。 ●弥生~飛鳥時代(1卑弥呼~8持統天皇)/●奈良時代(9藤原不比等~14鑑真)/●平安時代(15桓武天皇~27後白河天皇)/●鎌倉時代(28源頼朝~35北条時宗/●室町時代(36後醍醐天皇~41日野富子)/●安土・桃山時代(42織田信長~46出雲阿国)/●江戸時代(47徳川家康~68徳川慶喜)/●明治・大正時代(69西郷隆盛~84夏目漱石)/●昭和・平成・令和時代(85田中義一~101安倍晋三)
-
4.4
-
3.3アホか、有能かは 言葉のレベルで 評価されてしまう シリーズ17万部突破! 「語彙力ブーム」の第一人者による、 超初心者向けの「語彙力本」。 「拝読(はいどく)」「失念(しつねん)」「言質(げんち)」「所在(しょざい)ない」…など、 使えると便利で、知らないと恥ずかしい 51の言葉をわかりやすく解説。 新人もベテランも、今日から使えて一生役立つ。 あなたの印象がガラリと変わる、語彙力本の決定版。 後輩、部下へのプレゼントにも最適です。 山口謠司(やまぐち・ようじ) 大東文化大学文学部准教授。1963年長崎県佐世保市生まれ。博士。 大東文化大学大学院、フランス国立高等研究院大学院に学ぶ。 ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員を経て現職。専門は、書誌学、音韻学、文献学。 1989年よりイギリス、ケンブリッジ大学東洋学部を本部に置いて行なった『欧州所在日本古典籍総目録』編纂の調査のために渡英。 以後、10年に及んで、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ベルギー、イタリア、 フランスの各国図書館に所蔵される日本の古典籍の調査を行なう。 またその間、フランス国立社会科学高等研究院大学院博士課程に在学し、 中国唐代漢字音韻の研究を行ない、敦煌出土の文献をパリ国立国会図書館で調査する。 文部科学省科学研究費助成を受け、第一次世界大戦後に行われた昭和天皇(当時は皇太子)によるベルギー王国、ルヴァン大学に寄贈された日本古典籍についての研究なども行なっている。 広い視点から、わかりやすく話をするスタイルで、テレビやラジオの出演も多く、 NHK文化センター、朝日カルチャーセンター、中日文化センターなどでも定期的に講演や講座を開いている。『日本語を作った男』(集英社)、『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)など著書多数。
-
3.3
-
4.0「寿命とはこの世で魂を磨く期間である」 ――現役臨床医(2014年当時)が綴る、寿命の本当の意味、今生における私たちのご縁とお役目、そして魂と肉体の磨き方まで。 「寿命というのは、その人がお役目を果たす時間ですが、同時にその人が『魂を磨く期間』でもあるのだと思います」 「自分がやるべきことをしっかりやる。迷わずに行なう。お役目を果たすということは、そういうことではないでしょうか」 「『自分への関心』が、結果としてさまざまな病気の予防につながることを覚えておいてください」 (いずれも本文より) 第一章 寿命とは「魂を磨く期間」でもある 第二章 私たちの魂は死ぬことがない 第三章 健やかに生きる 第四章 社会における私たちのお役目について 【著者プロフィール】 矢作直樹 (やはぎ なおき) 1956年、神奈川県生まれ。1981年、金沢大学医学部卒業。 その後、麻酔科を皮切りに救急・集中治療、内科、手術部などを経験。 1999年、東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻および同大学工学部精密機械工学科教授。 2001年、東京大学大学院医学系研究科救急医学分野教授および同大学医学部附属病院救急部・集中治療部部長。2016年3月に任期満了退官。 主な著書には、『人は死なない』(バジリコ)、『天皇』『日本史の深層』(ともに扶桑社)、『おかげさまで生きる』(幻冬舎)、『天皇の国 譲位に想う』『日本歴史通覧 天皇の日本史』(青林堂)、『自分を休ませる練習』(文響社)など。
-
4.3天皇家の極秘資料を発掘! 「こんな資料は、これまで表に出たことはありません。いや、今後も絶対に出ないでしょう」。資料を目にした宮内庁関係者はこう呟いた。皇室費の中でも、天皇の私的な「財布」である内廷費の内訳は”聖域中の聖域”だ。今回、戦前戦後で大きく変貌を遂げた皇室財産の全容が初めて明らかに。特に驚かされるのは、昭和天皇の真実の暮らしぶりだった。 はじめに 等身大の昭和天皇を伝える二つの極秘文書 第一章 門外不出の資料が明かす戦前の皇室財産 第二章 天皇家の「家計簿」から見た戦後皇室の”聖域” あとがき 超一級史料を残した「ある宮内庁OB」の生涯
-
-昭和20年8月17日、大村基地の海軍343航空隊。隊長の源田実が下令する。「俺は自決する。行動をともにする者は柔剣道場に集まれ」将兵らは最期の杯を交わすうちに減り、残った者は23人。源田は言った。 「死ぬよりも重要な任務がある」 皇統護持作戦。天皇陛下処刑という最悪の事態に備え、皇族の子弟を九州山中に隠匿する極秘作戦をいまから展開する。源田はそう宣言した。作戦は以降36年間にわたり極秘裏に継続された。
-
3.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 賑やかな御朱印が大集結。 著者が実際に足を運んで収集した神社仏閣の御朱印コレクションを一挙紹介。 東京、神奈川を中心とした関東近郊の寺社から、色とりどりで趣向を凝らした希少なものを集めました。 同じ寺社でも、季節の御朱印や令和改元の御朱印、天皇即位の御朱印など、限定版を多数収録しています。 はじめに 第一部 東京・神奈川の御朱印と寺社の由緒 第二部 天皇即位関連 第三部 他 [著者] 石村光市(いしむら・こういち) 群馬県で生まれ、短大卒業後就職で神奈川県に移住。現在は県央地域在住。旅行が趣味で、今までに全国38都道府県を訪れている。平成25年頃から御朱印を集め始めた。北は福島県会津市から西は広島県福山市の御朱印まで約1000種類(1神社で複数枚頂いてる場合もある)以上所有しているが7~8割は関東地域の物です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 両陛下のお暮らしを彩る四季折々の花、自ら丹精された多様性豊かなお庭初公開。天皇陛下喜寿記念写真集。 2年半にわたって御所のお庭を撮影。思い出の地・軽井沢ゆかりの高原植物や、天皇陛下がお好きな野草など、220種以上を紹介。両陛下のお写真やエピソードも満載。
-
-
-
3.6
-
3.0自分はいったい誰の末裔なのか? ヒデミネ流、ルーツ探しの旅が始まる。役所で戸籍にあたり、家紋を調べ、祖先の土地を訪れ、専門家や親戚縁者の話に耳を傾ける。自分似の遠戚と出会ったり、源氏や平氏、さらには天皇家とつながったり……。日本中を東奔西走、「歴史とは?」「過去とは?」「自分って何者?」と問い続ける、じわり感動のノンフィクション。小林秀雄賞受賞。
-
4.0御前会議──天皇の前で開かれるため最高の権威をもつ。が、その天皇は一切の責任の外にあった。昭和十六年、四回の御前会議の結果、日本は勝算なき太平洋戦争に突入した。この会議の経緯を詳細に辿り直し、改めて御前会議のもつ奇怪な本質を抉る迫真のドキュメントが本書である。陸軍と海軍の権力抗争、開戦のために工作される非合理的な数字、参戦を疑問視しながら、しだいに口を閉ざしてゆく重臣たち。著者は言う、“恐るべき傲慢と惰性が日本を破滅させた”と。
-
-
-
3.3
-
3.0承久の変後、孤絶と憂悶の慰めを日々歌に託し、失意の後半生を隠岐に生きた後鳥羽院。同時代の歌人・藤原定家が最初の近代詩人となることによって実は中世を探していたのに対し、後鳥羽院は最後の古代詩人となることによって近代を超えた―歌人であるうえに『新古今和歌集』で批評家としての偉大さも示す後鳥羽院を、自ら作家でもあり批評家でもある著者が論じた秀抜な日本文学史論。宮廷文化=“詩の場”を救うことを夢みた天皇歌人のすがたに迫る。1973年度に読売文学賞を受賞した第一版に三篇を加え、巻末に後鳥羽院年譜と詳細な和歌索引を付した増補決定版。
-
-
-
4.3
-
5.0陛下のご意向を無視する逆臣は誰か。上下巻に分けて配信。 陛下の生前退位のご意向を受けて世に放つ「天皇入門書」決定版! 大ヒットとなった『天皇論』に100ページ超を加筆した総頁数552ページの大作。 陛下は「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ」てご意向を表明された。 皇位を安定的に継承していくには、特措法で一代限りの生前退位を認めるのではなく、皇室典範を改正し、女性・女系天皇、女性宮家を認めなくてはならない。 しかし、多くの国民が「わたしたちの天皇陛下」のお気持ちを大切にしたいと願う一方で、「男系男子しか認めない」と主張する者たちがいる。 天皇に対する「尊崇」を口にしつつも、陛下のご意向を無視する動きに危機感を抱いた著者が放つ問題作。 フィックス型EPUB156MB(校正データ時の数値)。 【ご注意】※レイアウトの関係で、お使いの端末によっては読みづらい場合がございます。タブレット端末、PCで閲覧することを推奨します。
-
5.0あの『ゴーマニズム宣言』が、23年ぶりに『週刊SPA!』に復活!! 小林よしのり、最期の戦いが「より凶暴に」始まる! 1995年、オウム真理教事件への報道姿勢の違いから『週刊SPA!』と決別した小林よしのりさんが、23年のときを経て『ゴーマニズム宣言』の連載を再開し、『週刊SPA!』に復活しました(2018年4月から)。 小林さんは『ゴー宣』を復活させた理由を、次のように語ります。 「再びわしが毎週という過酷なペースで『ゴーマニズム宣言』を描くことにしたのは、怠惰と堕落の底に沈んだ日本を、再浮上させるための最期の戦いが必要だと決意したからである。 未だ皇位の安定的継承もならず、戦後レジームからの脱却もならず、貧富の格差拡大や、少子高齢化における将来不安、女性の地位やLGBT等の問題、先端生殖医療の倫理観など、あらゆる価値が混沌とする状況で、総合的に語る思想漫画を子孫に残しておこうと考えた。」(巻末収録「檄文」より) するどく現在の社会問題に切り込む本作では、 ●安倍改憲には権力の暴走を縛る「立憲的改憲」で対抗せよ! ●オウム13人の死刑を経て、「オウムに殺されかかった漫画家」としてあの事件を総括! といった大テーマのほか、セクハラ問題、日米地位協定、新幹線通り魔殺人事件など、さまざま事象に対し、「ごーまんかましてよかですか!?」と数々の"断言"な問題提起します! 【小林よしのりさんプロフィール】 漫画家。1953年、福岡県生まれ。『東大一直線』でデビュー。『おぼっちゃまくん』などのギャグ漫画が子供たちの間で大ブームに。1992年、『ゴーマニズム宣言』の連載スタート。思想エッセイ漫画という新ジャンルを打ち立て、1998年の『戦争論』も大ヒット。その他、『沖縄論』『台湾論』『天皇論』などヒット作多数。2014年、23年ぶりにかつて決別した『週刊SPA!』で『ゴーマニズム宣言』を復活させる。 【本誌掲載内容】 第1宣言 復活の狼煙を上げる 第2宣言 西部邁、属国に死す 第3宣言 権力忖度システムの愚劣 第4宣言 立憲的改憲という選択がある 第5宣言 女人禁制は伝統ではない 第6宣言 セクハラより人材だ 第7宣言 枝野幸男・コスタリカ・ガンジー主義 第8宣言 長谷部恭男の愚民思想を撃つ 第9宣言 地位協定と憲法9条 第10宣言 安倍「自衛隊明記」の危険 第11宣言 「自衛隊明記」に潜むコンプレックス 第12宣言 君たちはどう生きるか 第13宣言 オウム教祖・幹部、死刑執行 第14宣言 なぜ高学歴の若者がオウムに入ったか 第15宣言 VXガス暗殺団との戦い 第16宣言 吉本隆明らインテリの犯罪 第17宣言 オウムを利する危険なリベラル BEFOR 2nd Season 特別収録 教育勅語で道徳は復活しない 特別収録 憲法と山尾志桜里の真実 檄文 『ゴーマニズム宣言』の復活をここに宣言する!
-
3.0「ごーまんかまして」二十数年、『ゴー宣』の戦歴がこの1冊に! 『ゴーマニズム宣言』の連載が始って以来、言論界に衝撃を与え続けてきた、 戦う漫画家・小林よしのりが自らの戦いの歴史を語りつくした、その名も『ゴーマニズム戦歴』がついに登場。 最初の権威との戦いは漫画賞の審査員。 オウム真理教に命を狙われ、薬害エイズ訴訟、従軍慰安婦問題、最近では改憲問題と、 あらゆる権威と世の中の矛盾と戦い続けた小林よしのりの「戦歴」に刮目せよ! ★『ゴーマニズム宣言』名場面も多数収録!! ◎ゴーマニズムは「権威よ死ね! 」から始まった ◎湾岸戦争のときから「反米」だったわし ◎デモが自己実現の手段になるのは今も昔も同じ ◎一発で言論空間を変えた『戦争論』のインパクト ◎日本人の圧倒的多数は親米ポチも含めて「サヨク」である ◎あえて無知をさらすところから始めた『天皇論』 ◎民主主義イデオロギーが戦争や独裁を生む 他 序章 わしのすべてを教えよう 第1章 「ゴーマニズム」の誕生 ~『東大一直線』から『差別論スペシャル』まで 第2章 「個」から「公」へ ~オウム真理教と薬害エイズ 第3章 自虐史観との戦い ~従軍慰安婦問題から『戦争論』へ 第4章 親米保守との決裂 ~『台湾論』から『戦争論3』まで 第5章 真の保守とは何か ~『沖縄論』から『天皇論』まで 第6章 この国を守るために ~『国防論』から『民主主義という病い』まで
-
5.0強さと脆さが同居し、ファンを魅了してやまなかった暴れん坊は、産駒の活躍によってクラシックウイナーの父となった。 探し、見つけ、守り、紡いできた血の真髄、そして未来につながる名馬への想いとは――。 ウマ娘で大人気! 血統に秘められた意味を知ったら、好きにならずにいられない!? 【内容】 増補版まえがき クラシックウイナーの父として まえがき 決まった種牡馬入り、関係者の期待 第1章 引退の日 ラストランの有馬記念/北海道で見つめた引退式/オーナー小林英一のこれまで/こだわり続けた“スイートフラッグの系統”/ゴールドシップへ注ぎ込んだ“時” 第2章 初めての種牡馬展示会 例年の倍以上もの関係者/思わぬ再会/芦別に訪ねた小林英一オーナー/世界へ羽ばたく志/“幸せの連鎖”を運ぶ馬 第3章 種牡馬としてのゴールドシップ 朝5時半、放牧前の手入れ/競走馬から種牡馬への転換/見学者が心がけるべき注意点とは/血を繋げることの意味 第4章 産駒の誕生 牧場に急いだ節分の日/初めての産駒誕生/人を惹きつける“名馬の持つ力”/備わった“父ゆずりの賢さ” 第5章 種牡馬2年目を迎えて 100頭を超えた種付け/2年目も変わらぬ人気と仕事振り/生まれた産駒への評価 第6章 札幌競馬場でのお披露目 担当者・下村光の思い/札幌競馬場に集結した関係者/珍しい“現役種牡馬のお披露目” 第7章 産駒たちの公開調教 ヴェールを脱ぐ初年度産駒/始まった公開調教/岡田繁幸総帥の思い/名馬の力 【著者】 河村 清明(かわむら・きよあき) 山口県出身。北海道大学文学部国文科専攻を卒業後、株式会社リクルートに入社。1996年に同社を退社したのち、執筆活動を始める。同年、「優駿エッセイ賞」を受賞。 著書『馬産地ビジネス』『JRAディープ・インサイド』『馬産地放浪記』(以上、イースト・プレス)、『三度怒った競馬の神様』(二見書房)、『ウオッカの背中』(東邦出版)、『遙かなる馬産地の記憶』(主婦の友社)、『ウイニング・チケット』(原作、講談社)などがある。 電子書籍『ミスター・ジャパンカップと呼ばれた男 競馬国際化の礎を作り上げた「異端」の挑戦』『競馬 衝撃の敗戦列伝 敗北を糧に頂点を極めた名馬たち』『競馬 衝撃の敗戦列伝2 運命を分けた一戦の知られざる真実』『ウオッカvsダイワスカーレット 天皇賞 運命の15分と二人の厩務員』『JRAディープ・インサイド 主催者が語る日本競馬の未来』『超サバイバル時代の馬産地ビジネス 知られざる競馬業界の「裏側」』、『いのちを繋ぐ馬産地の物語 旅立つサラブレッドの原風景』(共著)など。 競馬関連の著作について業界の内外を問わず高い評価を得ている。
-
-◎ 表の国家経済は破綻していても関係なかった――われわれのまったく知らない《超裏金融》の正体 ◎ サイナー、ゴールドマン・ファミリーズ、フラッグシップ――しくみを実際に動かすシステムがついに白日の下に晒される! ◎ 吉備太秦の肉声をそのままお届けします! 「いわゆるサイナーとは、口座管理人のことです。いわば資金の管理人のような立場です。 私の場合は、フラッグシップで承認する立場であり、サイナーではありません。私が一人ですべてを見ることは出来ないので、口座管理人が何人かいます。 IMFの運用に関わる金の取引と、日本が管理権、運用権、使用権を持っている35%日銀にシェアされるお金は、フラッグシップである私の承認がなければ動かせません。日本政府も日銀総裁も動かす権限はない。 世界銀行の別段預金は、表面上には載らないところにあります。それは、300人の個人委員会が管理しているのです。 ずっと運用していてずっと貯めているので減らない。どんどん増えていっている。 それの管理権、運用権、使用権は、基本的に日本にあります。 なぜかというと、ホストカントリーだからです。厳密には35%が日本のものです。それをどこの国に分配[シェア]するのかを決める人ということです」 「そして、この書類に私がサインを入れます。これが一番重要で、私がサインをすることにより『フラッグシップを立てる』ということになります。 フラッグは、漢字で書くと『旗』だが、実は秦ファミリーの『秦』でもあります。つまり、『この取引をきちんとしますよ』ということを、国連を含めた関連機関に宣言をするのです。 その旗印がフラッグシップであるので、私のサインは『フラッグシップを立てる』ということを意味しています。 つまり、『国連から認められた最終承認者=Special Power of Attorney at Goldman Families Group』が承認したという意味であり、それを宣言している文書ということになります。 世界の金塊は秦ファミリーが支配していると言われているのは、このフラグシップがあるからです」 「I.I.D.Oをつくったのは、英国のケンブリッジ派のドール・ロスチャイルドです。 彼は幕末、まず東インド会社からトーマス・グラバーを日本の長崎に送り込みました。日本という国がどういう国なのかを知ろうとしたのです。 欧州の王族・貴族の人たちは、働くということは奴隷がすることだと思っています。 しかし、日本人はみんな勤勉でよく働く。彼らは一体何を調べに来たかというと、日本の皇室の歴史を調べに来た。 調べてみると、『すごいじゃないか』ということになった。ユダヤより歴史が古い。本当だったら、天皇をさらって植民地にする予定だった。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量25,000文字以上 30,000文字未満(30分で読めるシリーズ)=紙の書籍の50ページ程度) 【書籍説明】 斎王というと、読者の皆さんは、一体どんなイメージをお持ちだろうか? やはり、特に政治に関与したり、華やかな活躍をする訳でもなく、歴史の陰でひっそりと、伊勢で神に仕えて日々を送る、地味な存在、 という印象が強いのではないだろうか? 更に彼女たち斎王は、少女の頃くらいから、年頃の乙女に生い立つまでを、都から遠く離れた伊勢で過ごし、そしてけして恋も許されず、 また帰京できるのは肉親の死か、譲位が行われた時だけという、数々の掟に縛られていた。 こうしたことから、斎王は王権の犠牲者という、かなり否定的なイメージを持つ人々も、いることだろう。 確かに自らが望んで、神に仕える斎王となった訳ではないにせよ、彼女たちは彼女たちに、都から遠く離れた伊勢で、国の平和や、 なるべく天皇の御代が長からんことを懸命に祈り、神に仕える日々を、送っていたのではないだろうか? とにかく何よりも、自分のために生きることが良しとされる、現代人にはなかなか理解しがたい、生き方ではあるかもしれないが。 また、一口に斎王といっても、けして前述のような、一律なイメージだけでは語ることができないところもある。 皆、けして無個性なお姫さまたちばかりではなく、なかなか印象的な斎王たちも時々、存在しているのである。 本書では、そうした、それぞれ印象的な斎王たちを中心に、ピックアップして紹介した。 ただ、これはこれで、読者たちにまた逆の誤解を招いてしまうかもしれない。 基本的には斎王というのは、特筆する程の、大きな喜びや悲しみもなく、ただ静かに自分に与えられた勤めを日々こなし、 また解任後も、ひっそりと平穏に生きた場合の方が、圧倒的に多いということである。 著名な斎王から、ほとんど世にその存在を知られていない斎王たちまでの中から、記録から断片的に垣間見える、 彼女たちの姿を追いかけてみたい。
-
3.0祟るほどパワーが強い!参拝する前に知っておきたい「最強神社」の真の姿、そして謎――『古事記』『日本書紀』に登場する神々を祀る神社。これを、著者は「最強神社」と定義する。最強神社には謎が多い。たとえば伊勢神宮は皇祖神アマテラスを祀りながら、なぜ天皇は明治時代まで参詣しなかったのか。出雲大社の巨大な本殿は実在したのか。大神神社の御神体・三輪山には何があるのか。宗像大社が鎮座する沖ノ島で行われていた謎の祭祀とは。これらを含め、この国の成り立ちにまつわる謎を読み解いていく。また現在、ご利益をもたらすと考えられている神々のなかには、かつては荒々しく祟った神も存在する。最強神社と太古の神々を知れば、参詣・参拝など神社との向き合い方が大きく変わるだろう。
-
4.5「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」とは、ドイツの偉大な政治家オットー・ビスマルクの言葉である。自分の経験だけから学ぼうとすると限界があるが、成功したり偉大な業績を残したりした先人たちからであれば、大いに役立つ教訓を得ることができる。本書では、著者独自の観点から21人の歴史人物を選び、8つのタイプに分けて紹介している。具体的には次の通り。(1)「並はずれた器量の人」=北条泰時・勝海舟・坂本龍馬・渋沢栄一、(2)「正義・大義の人」=行基・和気清麻呂・吉田松陰、(3)「行動力のある人」=北条政子・後醍醐天皇、(4)「我慢・忍耐の人」=吉備真備・徳川家康、(5)「覚悟の人」=大石内蔵助・大久保利通、(6)「進取の精神の人」=市川團十郎・高橋是清、(7)「非情の人」=伊達政宗・土方歳三・細川藤孝/忠興、(8)「奇想天外の人」=三井高利・早川徳次 予備知識ゼロでも一気に読める、最強の自己啓発書! 文庫書き下ろし。
-
4.0坂口征二喜寿(77歳)記念出版 「世界の荒鷲」初の公認バイオグラフィー 「柔道、プロレス、すべての時代の私が詰まっている」──坂口征二 柔道日本一から、鳴り物入りでプロレス界へ転向。ジャイアント馬場・アントニオ猪木とタッグを組んでトップレスラーとなり、新日本プロレスの社長・会長としてプロレス界を支え続けた「世界の荒鷲」のすべて。 「坂口征二──この名前は私の格闘技人生そして人生闘争にとって決して欠かせず消せない4文字です。昭和48年、彼が旗揚げ間もない新日本プロレスに入った時から、私はこの4文字の男に支えられてきたのです」 アントニオ猪木(坂口征二引退記念写真集『黄金の軌跡』より) 第一章 人生のはじまり 第二章 九州に坂口あり 第三章 柔道日本一への道 第四章 天皇杯とプロレス 第五章 日本プロレスの金の卵 第六章 坂口ブームからビッグ・サカへ 第七章 坂口征二の昭和四七年 第八章 猪木とのドッキング 第九章 自ら選んだナンバー2の道 第一〇章 猪木と会社のために 第一一章 世代交代 第一二章 社長就任 第一三章 荒鷲経営 第一四章 坂口会長
-
4.3知られざる「死」の歴史を紐解く! 首切り、切腹、怨霊…なぜ日本には独特の「死に方」が生まれたのか? ●憎き敵に、生首を踏ませて辱めた源義家 ●処刑された首はどこへ行く? ●刀を呑み込む今井四郎、集団自殺の加茂一族……壮絶な武士の死に方 ●なぜ、ペストは日本にやってこなかったのか? ●庶民の遺体があっても、悲しまない? 『明月記』に見る貴族の感覚 ●政治闘争に敗れて左遷され、怨霊となった菅原道真 ●悲惨な死に方をした天皇たちの名前にまつわる不思議 ●日本でも万能薬として売られていたミイラ ●当時と現代における、大きな「死」への価値観の違い
-
4.3【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 古地図と独自資料で迫る、誰も知らない皇居。 江戸城築城から約600年。 徳川将軍家の居城として、江戸文化の中心地として、明治維新の舞台として、太平洋戦争時の大本営として、戦後日本を見守る象徴として、皇居は日本の歴史の中心でした。 深いお濠と神秘的な森に囲まれた「日本最後の秘境」に、歴史探訪家の竹内正浩氏が迫ります。 本書では、皇居を5つの章「皇居東御苑」「皇居外苑(皇居前広場)」「宮殿・宮内庁(西の丸)」「吹上御苑」「北の丸」に分け、それぞれの建築物や遺構が持つ歴史や由来を解き明かします。さらに、まだ誰も目にしたことがない「皇居詳細地図」を収録。いくつかの建築物や遺構の存在や場所は、本邦初公開です。 天守台はもう2m高かった 中雀門の石垣の150年前の本丸火災の跡 徳川家は富士見櫓から花火を見物した 昭和天皇も「うるさい」と頭をかかえた午砲台跡 伏見櫓にあった血染めの畳 田安門と清水門の鬼瓦に残る葵の御紋 「たけ橋」ではなく「みたけ橋」になった深い理由 千鳥ヶ淵のベンチは高射機関砲座だった ――本書には、そんな皇居の秘密が満載です。 ぜひ本書を片手に皇居を歩いてみてください。 歴史の息吹がよりリアルに感じられるはずです。
-
-「継体天皇の王朝交替説に疑問の声あり」「推古天皇は中継ぎではなく強力なリーダーだった」「天皇は藤原摂関家の言いなりではなかった」「南北朝の合一で王朝の分裂が終わったというのはウソ」「織田信長は天皇に敬意を払い、経済的に支援していた」 最新の研究成果を元に、天皇と皇室にまつわる新常識を紹介! 「事件」「政治」「即位・儀礼」「文化・制度」という四つの切り口から、歴代天皇たちの素顔に迫る。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 八〇六~二二年、天台宗の開宗から最澄の死没までを描いたシナリオ風脚本。最澄と空海の二人と関係の深かった泰範をめぐる葛藤を描く表題作をふくむ5編の脚本と小説を収録する。 【目次】 最澄と空海(シナリオ風脚本) 雄略天皇(脚本) 伊乃翁の祝辞(小説) 楽園懐古(小説) 余寒(小説) あと書き 長与 善郎 1888- 1961年。小説家、劇作家、評論家。東京帝国大学文学部英文科中退。白樺派の作家。 著書に、『盲目の川』『求むる心』『彼等の運命』『項羽と劉邦』『結婚の前』『生活の花』『陸奥直次郎』『明るい部屋』『平野』『頼朝』『孔子の帰国』『或る人々』『画家とその弟子』『因陀羅の子』『春乃訪問』『文明主義者』『二週間』『三戯曲』『青銅の基督』『余の宗教への前提』『或る社会主義者』『波』『韓信の死』『エピクロスの快楽』『竹澤先生と云ふ人』『豹』『緑と雨』『生活と芸術』『菜種圃』『一人旅する者』『輝く廃墟』『自然とともに』『この男を見よ』『満支このごろ』『大帝康煕』『少年満洲読本』『日本文化の話』『人世観想』『夕子の旅行記』『幽斎父子』『幽明』『満洲の見学』『乾隆と香妃』『韓非子』『世相と藝文』『東洋の道と美』『見つゝ思ふ』『生活覚え書』『多面の統一』『東洋芸術の諸相』『一夢想家の告白』『銀河に対す』『クールベの娘』『野性の誘惑』『布袋とヴヰーナス』『あたし』『ショーペンハウエルの散歩』『麒麟児』『戸隠』『人間の探求』『人間の教師たち』『わが師わが友』『最澄と空海』など。
-
-戦後混乱期の中、『堕落論』で「生きよ、堕ちよ」と説いて人々の心を捉え、一躍流行作家となった坂口安吾。戦後社会の混乱と退廃を象徴する「無頼派」安吾の傑作評論、随筆を一挙収録した坂口安吾全集。 ●収録内容 諦らめアネゴ/諦めている子供たち/悪妻論/足のない男と首のない男/明日は天気になれ/新らしき性格感情/新らしき文学/阿部定さんの印象/阿部定という女/甘口辛口/哀れなトンマ先生/安吾巷談/安吾史譚/安吾新日本風土記/安吾の新日本地理/安吾下田外史/安吾人生案内/安吾武者修業――馬庭念流訪問記/育児/囲碁修業/意識と時間との関係/一家言を排す/生命拾ひをした話/『異邦人』に就て/意慾的創作文章の形式と方法/インチキ文学ボクメツ雑談/インテリの感傷/エゴイズム小論/遠大なる心構/大井広介といふ男/大阪の反逆/お喋り競争/親が捨てられる世相/温浴/外来語是非/咢堂小論/かげろふ談義/“歌笑”文化/悲しい新風/蟹の泡/感想家の生れでるために/巻頭随筆/観念的その他/気候と郷愁/北と南/教祖の文学――小林秀雄論/後記にかえて〔『教祖の文学』〕/切捨御免/桐生通信/近況報告/金談にからまる詩的要素の神秘性に就て/九段/敬語論/芸道地に堕つ/戯作者文学論/現実主義者/剣術の極意を語る/現代とは?/現代の詐術/講談先生/呉清源/枯淡の風格を排す/碁にも名人戦つくれ/小林さんと私のツキアイ/娯楽奉仕の心構へ/ゴルフと「悪い仲間」/今後の寺院生活に対する私考/今日の感想/坂口流の将棋観/桜枝町その他/酒のあとさき/作家論について/志賀直哉に文学の問題はない/市井閑談/「刺青殺人事件」を評す/思想と文学/思想なき眼/死と鼻唄/島原一揆異聞/邪教問答/集団見合/宿命のCANDIDE/将棋の鬼/勝負師/処女作前後の思ひ出/女性に薦める図書〔アンケート回答〕/白井明先生に捧ぐる言葉/新カナヅカヒの問題/神経衰弱的野球美学論/新作いろは加留多/新春・日本の空を飛ぶ/新人へ/人生三つの愉しみ/真相かくの如し/神童でなかつたラムボオの詩/深夜は睡るに限ること/推理小説について/推理小説論/スタンダアルの文体/砂をかむ/スポーツ・文学・政治/相撲の放送/青春論/清太は百年語るべし/世評と自分/戦後合格者/戦後新人論/戦争論/想片/俗物性と作家/醍醐の里/第二芸術論について/大望をいだく河童/太宰治情死考/ただの文学/谷丹三の静かな小説/愉しい夢の中にて/堕落論/続堕落論/男女の交際について/探偵小説とは/探偵小説を截る/単独犯行に非ず/ちかごろの酒の話/地方文化の確立について/散る日本/茶番に寄せて/長篇小説時評/通俗作家 荷風/通俗と変貌と/月日の話/机と布団と女/D・D・Tと万年床/帝銀事件を論ず/貞操の幅と限界/デカダン文学論/手紙雑談/てのひら自伝/天才になりそこなった男の話/伝統の無産者/天皇小論/天皇陛下にささぐる言葉/当世らくがき帖/ドストエフスキーとバルザック/特攻隊に捧ぐ/長島の死/中村地平著「長耳国漂流記」/夏と人形/新潟の酒/肉体自体が思考する/二合五勺に関する愛国的考察/西荻随筆/日映の思い出/日本人に就て/日本精神/日本の詩人/日本の水を濁らすな/日本の山と文学/日本文化私観/“能筆ジム”/花田清輝論/「花」の確立/反スタイルの記/パンパンガール/ピエロ伝道者/悲願に就て/人の子の親となりて/ヒノエウマの話/百万人の文学/便乗型の暴力/ヒンセザレバドンス/FARCEに就て/風流/フシギな女/不思議な機構/不良少年とキリスト/フロオベエル雑感/文学と国民生活/文学のふるさと/「文芸冊子」について/文章その他/文章の一形式/文章のカラダマ/文人囲碁会/分裂的な感想/僕はもう治っている/本因坊・呉清源十番碁観戦記/本郷の並木道/牧野さんの祭典によせて/牧野さんの死/馬庭念流のこと/未来のために/武者ぶるい論/無題/村のひと騒ぎ/もう軍備はいらない/文字と速力と文学/模範少年に疑義あり/モンアサクサ/矢田津世子宛書簡/山の貴婦人/ヤミ論語/幽霊と文学/由起しげ子よエゴイストになれ/ヨーロッパ的性格 ニッポン的性格/欲望について/予告殺人事件/余はベンメイす/理想の女/流浪の追憶/歴史と事実/恋愛論/老嫗面/わが工夫せるオジヤ/わが思想の息吹/我が人生観/私の碁/私の小説/私の葬式/私の探偵小説/私は誰?
-
-坂口安吾の代表作『堕落論』『続堕落論』『日本文化私観』『ピエロ伝道者』『FARCEに就て』『不良少年とキリスト』『安吾新日本風景』などの傑作評論、エッセイ、紀行文を多数収録した電子全集です。 ■収録内容 諦らめアネゴ 諦めている子供たち 悪妻論 足のない男と首のない男 明日は天気になれ 新らしき性格感情 新らしき文学 阿部定さんの印象 阿部定という女 甘口辛口 哀れなトンマ先生 安吾巷談 安吾史譚 安吾新日本風土記 安吾の新日本地理 安吾下田外史 安吾人生案内 安吾武者修業 育児 囲碁修業 意識と時間との関係 一家言を排す 生命拾ひをした話 『異邦人』に就て 意慾的創作文章の形式と方法 インチキ文学ボクメツ雑談 インテリの感傷 エゴイズム小論 遠大なる心構 大井広介といふ男 大阪の反逆 お喋り競争 親が捨てられる世相 温浴 外来語是非 咢堂小論 かげろふ談義 “歌笑”文化 悲しい新風 蟹の泡 感想家の生れでるために 巻頭随筆 観念的その他 気候と郷愁 北と南 教祖の文学――小林秀雄論 後記にかえて〔『教祖の文学』〕 切捨御免 桐生通信 近況報告 金談にからまる詩的要素の神秘性に就て 九段 敬語論 芸道地に堕つ 戯作者文学論 現実主義者 剣術の極意を語る 現代とは? 現代の詐術 講談先生 呉清源 枯淡の風格を排す 碁にも名人戦つくれ 小林さんと私のツキアイ 娯楽奉仕の心構へ ゴルフと「悪い仲間」 今後の寺院生活に対する私考 今日の感想 坂口流の将棋観 桜枝町その他 酒のあとさき 作家論について 志賀直哉に文学の問題はない 市井閑談 「刺青殺人事件」を評す 思想と文学 思想なき眼 死と鼻唄 島原一揆異聞 邪教問答 集団見合 宿命のCANDIDE 将棋の鬼 勝負師 処女作前後の思ひ出 女性に薦める図書〔アンケート回答〕 白井明先生に捧ぐる言葉 新カナヅカヒの問題 神経衰弱的野球美学論 新作いろは加留多 新春・日本の空を飛ぶ 新人へ 人生三つの愉しみ 真相かくの如し 神童でなかつたラムボオの詩 深夜は睡るに限ること 推理小説について 推理小説論 スタンダアルの文体 砂をかむ スポーツ・文学・政治 相撲の放送 青春論 清太は百年語るべし 世評と自分 戦後合格者 戦後新人論 戦争論 想片 俗物性と作家 醍醐の里 第二芸術論について 大望をいだく河童 太宰治情死考 ただの文学 谷丹三の静かな小説 愉しい夢の中にて 堕落論 続堕落論 男女の交際について 探偵小説とは 探偵小説を截る 単独犯行に非ず ちかごろの酒の話 地方文化の確立について 散る日本 茶番に寄せて 長篇小説時評 通俗作家 荷風 通俗と変貌と 月日の話 机と布団と女 D・D・Tと万年床 帝銀事件を論ず 貞操の幅と限界 デカダン文学論 手紙雑談 てのひら自伝 天才になりそこなった男の話 伝統の無産者 天皇小論 天皇陛下にささぐる言葉 当世らくがき帖 ドストエフスキーとバルザック 特攻隊に捧ぐ 長島の死 中村地平著「長耳国漂流記」 夏と人形 新潟の酒 肉体自体が思考する 二合五勺に関する愛国的考察 西荻随筆 日映の思い出 日本人に就て 日本精神 日本の詩人 日本の水を濁らすな 日本の山と文学 日本文化私観 “能筆ジム” 花田清輝論 「花」の確立 反スタイルの記 パンパンガール ピエロ伝道者 悲願に就て 人の子の親となりて ヒノエウマの話 百万人の文学 便乗型の暴力 ヒンセザレバドンス FARCEに就て 風流 フシギな女 不思議な機構 不良少年とキリスト フロオベエル雑感 文学と国民生活 文学のふるさと 「文芸冊子」について 文章その他 文章の一形式 文章のカラダマ 文人囲碁会 分裂的な感想 僕はもう治っている 本因坊・呉清源十番碁観戦記 本郷の並木道 牧野さんの祭典によせて 牧野さんの死…ほか
-
-1835年、高知の下級武士の家に生まれた坂本龍馬は、青年なって江戸に出ます。そのころの日本は、開国派、攘夷派が争っていました。日本の将来を考える勝海舟の弟子となり、軍事や政治を学びます。やがて 反目し合っていた薩摩藩と長州藩を仲直りさせて、1866年に薩長同盟が成立、翌年、幕府が政治の権力を天皇に返す大政奉還が実現しました。 日本の近代化のきっかけを作った龍馬でしたが、1867年凶刃に倒れます。
-
-
-
3.0南北朝の動乱期、武芸だけでなく連歌や立花など風流に通じ、華美な服装、そして遠慮のない振る舞いで「バサラ大名」と称された佐々木道誉(高氏)。本書は彼の波瀾の生涯を描く長編小説である。鎌倉幕府が弱体化し、次なる政治秩序が模索されていたころ、衆望を集めた後醍醐天皇は、幕府打倒を図る。やがて百数十年続いた武家政権を、いったんは朝廷に取り戻すことに成功するが、加担した武士たちが、恩賞の問題で再び不満を募らせることに。そこに登場してくるのが足利尊氏であり、元弘元年の政変(元弘の変)後、尊氏に従った佐々木道誉である。道誉は尊氏の影の参謀として臨機応変に立ちまわり、尊氏とともに時代を動かしていく。そして、再び京に武家政権を打ちたてるのである。「バサラ」を演ずることを、悪い時代を自由に生き抜くための手段とし、己れの進むべき道を強かに、確かに歩んだ武将の生きざまを、見事に描出する力作である。
-
-
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界と戦うためのキックスキルがここにある! サッカーはボールを蹴る競技なので、キックが重要なのは明白です。 パスをするのもシュートをするのもキックです。 そして、本書の著者である中西哲生氏は「日本が世界で戦うための課題はキックだ」と言います。 軸足をしっかりと地面に固定して、蹴り足を振り抜く。 この、当たり前のように続けてきた蹴り方では世界と戦うことはできません。 キーワードは「軸足抜き蹴り足着地」。 蹴った後、軸足を浮かして蹴った足で着地する―。 とても画期的な蹴り方に聞こえますが、実は世界のトッププレイヤーや世界で活躍する日本人選手は無意識のうちに実践しています。本書ではこの「軸足抜き蹴り足着地」という世界標準のキックを「ストレート」「アウトカーブ」「インカーブ」「ストレートインカーブ」「スワイプインサイド」「ループ」という6のカテゴリーに分けて詳細に解説しています。 さらに、ボールの状態によっても蹴り方は変わります。本書では「離れていくボール」「近づいてくるボール」「ショートバウンドのボール」「止まっているボール」に分けてそれぞれのシチュエーションにおけるキックの思考(=蹴る際の考え方)について解説しています。 また、巻末にはサッカー以上にキックのことを緻密に考えているアメリカンフットボ ール界で活躍する佐藤敏基選手と丸田喬仁コーチとの鼎談を収録。キックについてとことん突き詰めて考える3人の会話は大変興味深く、必読の内容です。 本書で、世界標準のキックとはどんなものかを知っていただければ、日々のサッカー観戦がより楽しくなるはずです。 また、サッカーを指導する立場にある方は「軸足抜き蹴り足着地」を伝えて、世界標準の選手を育ててください。 そして、選手の皆様は本書で改めて自分の蹴り方を見つめ直し、よりレベルの高いキックを身につけていただければ幸いです。 サッカーはボールを蹴る競技なので、キックが重要なのは明白です。 パスをするのもシュートをするのもキックです。 そして、本書の著者である中西哲生氏は「日本が世界で戦うための課題はキックだ」と言います。 軸足をしっかりと地面に固定して、蹴り足を振り抜く。 この、当たり前のように続けてきた蹴り方では世界と戦うことはできません。 キーワードは「軸足抜き蹴り足着地」。 蹴った後、軸足を浮かして蹴った足で着地する―。 とても画期的な蹴り方に聞こえますが、実は世界のトッププレイヤーや世界で活躍する日本人選手は無意識のうちに実践しています。本書ではこの「軸足抜き蹴り足着地」という世界標準のキックを「ストレート」「アウトカーブ」「インカーブ」「ストレートインカーブ」「スワイプインサイド」「ループ」という6のカテゴリーに分けて詳細に解説しています。 さらに、ボールの状態によっても蹴り方は変わります。本書では「離れていくボール」「近づいてくるボール」「ショートバウンドのボール」「止まっているボール」に分けてそれぞれのシチュエーションにおけるキックの思考(=蹴る際の考え方)について解説しています。 また、巻末にはサッカー以上にキックのことを緻密に考えているアメリカンフットボ ール界で活躍する佐藤敏基選手と丸田喬仁コーチとの鼎談を収録。キックについてとことん突き詰めて考える3人の会話は大変興味深く、必読の内容です。 本書で、世界標準のキックとはどんなものかを知っていただければ、日々のサッカー観戦がより楽しくなるはずです。 また、サッカーを指導する立場にある方は「軸足抜き蹴り足着地」を伝えて、世界標準の選手を育ててください。 そして、選手の皆様は本書で改めて自分の蹴り方を見つめ直し、よりレベルの高いキックを身につけていただければ幸いです。 中西 哲生 1969年9月8日 愛知県名古屋市出身。同志社大学を経て、1992年に名古屋グランパスエイトへ入団。 1995年シーズンには、アーセン・ベンゲル監督の下で天皇杯優勝。1997年、当時JFLだった川崎フロンターレへ移籍。1999年には主将としてJ2初優勝、J1昇格に貢献する。2000年末をもって現役を引退。 現在はスポーツジャーナリストとして、テレビ、ラジオ等で活躍中。また、2008年7月には財団法人(現:公益財団法人)日本サッカー協会・特任理事に就任。 サッカー、スポーツの普及に各方面で尽力している。
-
-国家から国民一人ひとりまでの危機管理 「国政」「行政」「自治体」「企業」「団体」「学校」「家庭」、それぞれの集団に対応した危機管理体制が必要です。 国家間においては紛争があり、テロや自然災害などの事件、事故、それぞれの危機に面したとき、どのような行動をとれば良いのか、事前に何を準備すればよいのか、これらのテーマを実例をケーススタディとしてわかりやすく解説されています。 内閣総理大臣官房・内閣安全保障室長も経験した佐々氏の、実体験に基づく説明は、集団のリーダーには非常に役立つ教本となることでしょう。 危機管理問題の第一人者が語る心構えを学んで下さい。 佐々 淳行 初代内閣安全保障室長 1930年生まれ、東大法学部卒業。 1954年に国家地方警察本部(現警察庁)入庁し、警視庁、警察大学校(助教授)、在香港日本国総領事館領事などに赴任。その後、警察庁・警視庁の調査・外事・警備課長、 監察官などを歴任し、三重県警察本部長、警察庁刑事局参事官を経て、防衛庁出向し、防衛審議官、教育参事官、人事教育局長、官房長、防衛施設庁長官を歴任。1986年に内閣総理大臣官房・内閣安全保障室長に就任し、1989年の昭和天皇大喪の礼を最後に退官。 公職退官後は、各省庁委員会の委員、ボランティア活動(JIRAC)、「危機管理」思想の普及・啓蒙活動・政策提言、大学・各省庁研修機関での講師に勤しむ。 受賞歴 ■1975年5月5日 英国C・B・E勲章(Commander of the British Empire) ■1986年9月18日 米軍民間人功労賞(U.S. Military Outstanding Civilian Service Medarl) ■1990年5月16日 ドイツ連邦殊勲十字章 (Das Grosse Verdienst Kreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland) ■カンボジア復興殊勲賞(計5回) ■1992年12月 第54回文藝春秋読者賞 ■2000年12月 第48回菊池寛賞 ■2001年11月 勲二等旭日重光章 ■2007年2月 第22回正論大賞
-
3.5150年目に明かされる真実! 「明治維新」という名の洗脳を解く!! 勝者(薩摩、長州)がでっち上げた通史の誤りを徹底究明。「薩長史観」と「真相」の対比から、幕末維新の真実を明らかにする。 ◆著者の言葉 「薩長史観」とは何か。明治政府がその成立を正当化するために創り上げた歴史である。それは、薩摩や長州が幕末から明治維新にかけて行なった策謀・謀反・反逆・暴虐・殺戮・略奪・強姦など、ありとあらゆる犯罪行為を隠蔽するために創られた欺瞞(ぎまん)に満ちた歴史観であるということである。 ◆主な内容(一部を抜粋) [薩長史観1]幕府は無力・無策のまま開国したために倒幕運動が起こった [真相]幕府は薩長に比べて遥かに開明的で、開国による近代化を進めていた [薩長史観2]吉田松陰は松下村塾で幕末志士を育成した大教育者である [真相]松陰は、暴力革命を礼賛するテロの扇動であった [薩長史観4]西郷隆盛は「無私の心」で明治維新を成しとげた最大の功労者である [真相]西郷は僧侶を殺し、江戸を混乱させ、同調者を見殺しにした策謀家だ [薩長史観17]孝明天皇の病死で、英明な明治天皇が即位して日本は夜明けに向かった [真相]孝明天皇は、薩摩と岩倉具視の陰謀によって毒殺された可能性が高い [薩長史観19]「討幕の密勅」は正式なもので、天皇から幕府討滅の宣旨が下された [真相]討幕の密勅は偽造されたものであり、その真相は文章に示されている [薩長史観20]大政奉還は、その場しのぎの愚かな決断である [真相]大政奉還は「慶応維新」というべき歴史的偉業であり「明治維新」より優れていた
-
-世界を見れば日本が見える 歴史を見れば現代がわかる 世界で起きている最新情報を伝え、埋もれた歴史の真実に光を当てる。それがSAPIOです。気鋭のジャーナリスト、時代を代表する言論人の寄稿による特集記事から見えてくるのは、あなたが知らない「日本」と「日本人」の本当の姿です。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 天皇「秘儀と謎」 目次 第一部 皇室と日本人のこれから 次代の天皇制を読む 天皇は「譲位」によって国体を守ろうとした ひと目でわかる 皇位継承の儀式のすべて ゴーマニズム宣言 新天皇即位を寿ぐ 新天皇 皇太子が胸に刻む訓戒の書『誡太子書』の苛烈な内容を知るべし ご回復 苦難の道を歩まれた雅子妃の「皇后」へのご覚悟 大図解 上皇の生活はどうなるのか 第二部 秘儀と歴史的視点 特別対談 歴史を紐解けば「新天皇像」が見えてくる 検証 大嘗祭で天皇はどんな秘儀をしているのか 完全保存版 宮中祭祀の一年 第三部 天皇と皇室の課題 教えて下さい!天皇と皇室の未来を考えるための「3つの疑問」 激突! 「皇族になる男系男子はいる!」「ならば、連れて来い!」 天皇家の資産 新天皇即位で「三種の神器」の贈与税はどうなる 第四部 天皇・皇后の慈しみ 歩み 国民とともに 御世替わり 今上陛下「30年間のお言葉」に込められた「伝統の継承者」としての覚悟 国母の言葉 美智子皇后「ありがとう」の深き意味 日本の中心 今こそ改めて心に刻みたい「天皇を戴く日本と日本人の幸福」 歴史的瞬間 「昭和の最後」と「平成の最初」を伝えたアナウンサーが明かす「元号越え」秘話 第五部 海外の反応 世界の視点 中韓米英のメディアは天皇「生前退位」をどう報じたのか 中国 中国歴代最高指導者が抱える「天皇コンプレックス」の正体
-
-611円 (税込)朴槿恵氏の弾劾訴追案が可決された韓国。その真の姿を明らかにします。日本ではほとんど知られていない「韓国軍のベトナム戦争での虐殺」「韓国軍の慰安婦」「韓国人の在日差別」「天皇コンプレックス」など多岐にわたって解説した1冊です。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 目次 韓国「破裂」 第1部 韓国軍の蛮行 告発ルポ 韓国軍のベトナム人 強姦 放火 殺戮 虐殺 この戦争犯罪に時効なし! 性暴行 韓国軍兵士は村の女性を輪姦し、ナイフで乳房を切り取った 発掘スクープ 北から連行された若き女性が韓国兵の「性奴隷」にされていた 悲劇ふたたび 韓国男がまたやっている! ベトナム女性を「全裸チェック」で品定め 嫁にした後は殴る、蹴るの暴虐 現地ルポ 韓国軍慰安所では10代のベトナム少女が連夜、乱暴な兵士の相手をさせられていた 特別企画 韓国大激震! 緊急対談 櫻井よしこ×呉善花 朴槿恵後の韓国は北朝鮮と化し、日本に牙を剥く 図解 朴槿恵を窮地に追い込んだ「崔順実ゲート」全関係図 実像 朴槿恵への期待も裏切られた 第2部 反日は止まらない 「日韓合意」のその後 史上最凶の反日映画 『鬼郷』が韓国で公開された! 特別対談 井沢元彦×加藤達也 「それでも、韓国の反日は止まらない」 工作 韓国が世界に広げた「虚言」を暴く! 国際ロビー活動 韓国で盛り上がる「憲法9条にノーベル賞を」運動の目的は“竹島不法占領継続”か 差別 韓国政府はいつまで「福島産水産物」の禁輸を続けるのか 新たな中傷 なぜ韓国の新聞は無罪となった私に文句を言い続けるのか 報道検証 韓国メディアの記事は「日本の不幸は蜜の味」ばかり 侮日 韓国メディアがオバマ広島訪問を絶対に許せない理由 第3部 希望なき「ヘル朝鮮」 現地レポート 韓国の若者たちが「ヘル朝鮮」で苦しんでいる 生活実態 糞尿まみれの共同トイレ、カビ臭い地下倉庫で生活 「漢江の奇跡」の成れの果ては世界一の貧困率だった 経済悪化 サムスンがけっぷちでお先真っ暗 韓国企業8万社が「ゾンビ企業」になっている 観光業界 日本人観光客激減、中国人客激増で韓国の高級ホテルが泣いている 次のリーダー候補 韓国次期大統領を狙う潘基文・国連事務総長を世界のメディアが「無能・無策」と酷評 韓国の苦境 日韓合意の「反日封印」で捌け口を失った不満の矛先が在日に向けられている ロッテ叩き 韓国で血祭り! “在日企業”ロッテに浴びせられた罵詈雑言 第4部 悲しき韓国社会 男尊女卑 20代女性23人が被害! 韓国芸能界の「性接待」はなぜなくならないのか 提言 整形天国を生んだ「容貌差別」に、厳しい「地域差別」…… 日本が韓国社会の歪みから「学ぶべきこと」 整形 KARAになるつもりが常に「アッカンベー」国策で推進する美容整形でトラブル続出 中国嫌悪 韓国人の本音は中国人大嫌い? 「中国人弾圧政策」でチャイナタウンが消滅した 学力 「世界一優れた文字を守れ」ハングル至上主義で漢字を忘れた韓国人は「大韓民國」が書けない 韓国軍 ロッカーは化粧品の山、訓練中にSNS、ゲーム 韓国版“ゆとり世代”兵士では国を守れない 原発ビジネス 品質保証書を偽造、廃棄処分予定の部品を納入“ケンチャナヨ原発”のぞっとする大暴走 皇室 微妙で複雑な韓国人の「天皇コンプレックス」 本音 韓国人女性赤裸々座談会 「私たち日本人男性のほうが 好きなんです」 韓国内の対立 元慰安婦の熊本支援に韓国世論が大反発 韓国人を精神分析するキーワード
-
3.3
-
3.0「めんどくさいやっちゃなあ」と思わせたら勝ち。こういう記者を辞めさせない会社も偉いと思います。――斎藤美奈子推薦 本書の試みを「蛮勇」だとシニカルに冷笑しているジャーナリストたちがいたら、彼らに言いたい。君たち、笑ってる場合じゃないぞ!――井上達夫解説 ■内容 七年八カ月に及んだ安倍政権下、なぜリベラルは敗け続けたのか。問われていたのは、国民を愚民視し、不都合な民意をポピュリズムと断じ続けた自称リベラル勢力の歪んだ認識と底の浅さだった。改憲論争、沖縄の基地移転、脱原発……あらゆる局面で垂れ流された矛盾と欺瞞を、朝日記者が検証する。 ■目次と抜粋 まえがき “朝日新聞の中にいながらして、自社の報道を含めたリベラル勢力の矛盾や問題点を問うという行為には、まだわずかなりといえども意味はあると信じたい” 第一章 正義の暴走――世間とジャーナリズムとの共犯関係 “彼らはまずもって「世間をお騒がせした」と謝罪した。しかし、私たちは「お騒がせ」したのが彼らではないことを知っている。「騒いだ」のはメディアであり、「世間」である” 第二章 フェミニズム――目指すべきは差異か? 普遍か? “意図的か無意識にか、リベラルメディアには「男と女から成り立っている社会」という言い回しが頻繁に登場する。そこに潜む様々な含意を、素通りしないようにしたい” 第三章 憲法九条――リベラルが民主主義を損なうとき “「条文を変えさせていない=九条をまもっている」という我々の意識が、現実から目を背ける効果を持ってしまっていたのではないか” 第四章 原発と科学報道――リベラルメディアが忘れたい過去 “たとえ後追い仕事であっても、原子力平和利用の推進に新聞が果たした役割を検証することは、その看板の下で取材活動をしている者にとっての責任だと認めざるを得ない” 第五章 沖縄と本土――どちらの民意が重いのか “本土のメディアやリベラルがすべきは、沖縄で進行している事態への本土の主権者の責任を突くことだ” 第六章 天皇と戦争責任――戦前から持ち越されたタブー “天皇や皇室に関する自由な言論を許さない構造を作っているのは、リベラル系も含めたジャーナリズムである” 補論 インタビュー 井上達夫 「自称リベラル」は国民を信じていない 原武史 「天皇」という幻想 本間龍 スポンサー企業の新聞社に五輪監視はできない あとがき 記者に「論は要らない」のか 解説 日はまた昇るか(井上達夫) ■著者プロフィール 石川智也〈いしかわ・ともや〉 1998年、朝日新聞社入社。岐阜総局などを経て社会部でメディアや教育、原発など担当したのち、2018年から特別報道部記者、2020年4月から朝日新聞デジタル&副編集長。慶応義塾大学SFC研究所上席所員、明治大学感染症情報分析センターIDIA客員研究員を経る。共著に『それでも日本人は原発を選んだ』(朝日新聞出版)、『住民投票の総て』(「国民投票/住民投票」情報室)など。 Twitter: @Ishikawa_Tomoya
-
-愛の話。子供心の淡い恋。長い同棲に倦み疲れたか、大人の妄執の愛。シャンソンとコラボした新しい小説。 子供心に女教師へ抱いた淡い恋『淡雪の恋』。長い同棲生活に倦み疲れたか、若い女に言い寄られた大人の妄執の愛をシャンソンを交えて語る『「さよなら」はどこへ』。 【目次】 淡雪の恋。「さよなら」はどこへ。 【著者】 畑村達 1926年 山口県生まれ。九州帝大工学部中退。教諭、司書、大学職員を経て日本文芸家協会会員。作家。主な著書に「今日と明日の間で」「昭和天皇と侍医長の死」「海と廃墟の街から」「炎の国、孤島の舞」電子本「オクツキの海」「嗤う瀧」「工場閉鎖」等がある。
-
4.0★緊急出版! 沖縄を守れなければ、日本は米国の支配から永遠に逃れられない! 日本国民に問う問題作!★ 普天間問題をはじめ、レイプ・暴行事件、騒音問題、思いやり予算……さまざまな問題を起こしながらも日本に駐留し、居座り続ける米軍は、本当に日本を守るために存在するものなのか? 鳩山が退陣に追い込まれる元凶となった「普天間問題」の根本的な原因は、日米安保条約の成り立ちにある。しかしそれは、もはや日本をテロに巻き込みかねない悪法と化した。歪みきった日米安保条約の根底原因を暴き、それに代わる完全無欠の国防を実現する、唯一にして最強の「新たなる防衛策」を、元外務官僚の著者が論じる。 【見出し】 ●日米同盟は日本をテロとの戦いに巻き込む ●米国の下請けと化した自衛隊 ●日米安保体制を求めた昭和天皇の「二重外交」 ●対米従属政策は自民党の党是 ●旧日米安保条約は「密約」だった ●最高裁の極秘資料が示す司法の密約 ●米国はどこかで戦争を起こさなければならない ●数人の犠牲と引き換えに千数百人も虐殺した ●「テロとの戦い」の正体 ●戦時の情報工作は正当化される ●米国によって決められた日本の国防政策 ●米国が警戒した樋口レポート
-
-トランプと麻雀の点数棒を使った、誰でも気軽に楽しめる新しいカードゲームのルールブックです。 トランプと麻雀の点数棒を使い、ポーカーの手役に点数を付け、麻雀のように点数を競うゲームですが、3と7のカードが「役札」となって手役のランクが上がる、麻雀のようなドラ札と裏ドラ札がある、役満や振込がある、花札のようなフケ勝ちがある、将棋のようなキャプチャー(駒取り)があるなど、世界中の面白いゲームのルールを加味して作られています。また麻雀卓のような設備も不要で、2人から4人までで気軽に楽しめるゲームです。まさに国境や時間、空間などの制限を超えた究極のワンネス・ゲームと言えるでしょう。 【目次】 はじめに ゲームの種類 ゲームのスタート 手役と基礎点数 手役紹介 3&7雀ポーカー独自の手役とルール 役札の使い方 ドラ札と裏ドラ札 ジョーカーの使い方 リーチ 1ゲームの終了 点数一覧表 ゲームの進め方 3&7雀ポーカーと確率 考えられる追加ルール おわりに 【著者】 河合保弘 司法書士/作家として、現在はオンライン限定で活動中。司法書士としては専門書やビジネス書などを多数出版しており、特に「信託」「一般社団法人」に関しての普及活動に注力、オンラインによる講演活動などにも取り組んでいる。作家としては小説8作を発表、最新作に長編時代小説「カイザリンSAKURA~最後の女性天皇を巡るファンタジー~」がある。FacebookやYouTubeによる情報発信も積極的に進めている。
-
-408円 (税込)長州は、なぜ革命に成功したのか? はじめに 長州は、なぜ革命に成功したのか? 目次 第一章 江戸時代と長州藩の成り立ち 中国地方に覇を唱えた名将 長州藩の始祖・毛利元就の偉業 毛利一族が動かした大決戦の戦局 関ヶ原の戦いと江戸幕府の成立 かろうじて取り潰しを免れた毛利家 長州藩、苦難のなかの誕生 泰平の眠りを謳歌する日本に向けて迫り来る列強国の船団 ついに黒船艦隊が日本上陸 ペリーはなぜ開国を迫ったのか? コラム 徳川将軍家の系譜と役割そして天皇の関わりを知る 第一章「江戸時代と長州藩の成り立ち」の出来事 第二章 幕末の始まりと“志士”の登場 開国に至る最中で沸き立った尊王攘夷とは何か? 幕末日本を動かした大組織徳川幕府の衰退と雄藩の台頭 幕末の長州藩主は名君だったのか? 毛利敬親の人物像 “その頃”の長州城下に暮らした人々 吉田松陰と杉文と家族たち 長州という枠組みから出て活動を始めた吉田松陰の密航計画 多くの長州志士を育む養成機関の誕生 松陰、松下村塾の塾主となる 松陰の門下生がそれぞれに文武を磨く 晋作、小五郎らの江戸修行 取り調べの場で老中暗殺を自供 吉田松陰、江戸に死す コラム 明治維新胎動の地 萩城下・長州路へ 第二章「幕末の始まりと〝志士〟の登場」の出来事 第三章 苦境に立たされた長州藩 幕府の屋台骨を揺るがす戦争にまで発展した生麦事件 有望な人材を留学させる 長州五傑、禁を犯しイギリスへ渡る 外国船への砲撃を開始した長州 八・一八の政変により都を追われる 八方塞がりの状況を打破する強硬策 京都御所を襲った禁門の変 四国艦隊による砲台占拠と幕府軍の来襲 存亡の秋を迎えた長州藩 藩論を倒幕に向けて舵を切らせた高杉晋作による功山寺挙兵 コラム 頑なに、過激に突き進んだ長州藩の戦い 維新回天の足跡 第三章「苦境に立たされた長州藩」の出来事 第四章 勇躍する維新の志士たち 薩長同盟の締結気運の高まりと倒幕のための具体策 寡兵の長州軍に敗北を喫した幕府軍 第二次長州征伐 将軍、天皇の相次ぐ不幸で後ろ盾を失う 瀕死の幕府が打った大博打 薩長の思惑が通り日本最大の内乱、戊辰戦争開戦 議会制による新たな政治体制が樹立 新政府、波乱含みの船出 コラム 幕末から維新まで多くの傑物を輩出長州閥その光と影 第四章「勇躍する維新の志士たち」の出来事 巻末 幕末人物伝 黒船来航時の幕臣と大名 幕末の日本を案じた思想家と学者 夢半ばに散った志士たち 幕末維新を生き抜いた者たち おわりに 激動の時代から150年を経て 奥付 裏表紙
-
-458円 (税込)国生みから天孫降臨、推古天皇まで 神話の歴史旅へ 著者略歴 はじめに 『古事記』のなかの神話 目次 第一章 日本の神と天皇を知る 神話の起源『古事記』とは何か イザナキとイザナミ夫婦の始まりと国生み 天から追放されるスサノオアマテラスとの対峙 オオクニヌシの国造り妨害する兄弟の神々 天孫降臨最初の地は日向 海幸彦と山幸彦の兄弟喧嘩をおさめたトヨタマヒメ 桃太郎伝説を生んだ神武東征 関東から九州まで東奔西走ヤマトタケル 神話と史実の狭間に登場する『古事記』のなかの天皇 天皇家に受け継がれる秘宝三種の神器 第二章 全国の神話の舞台を訪ねて 三貴子の神々が宿る伊勢・熊野 神々の存在を身近に感じる国で「始まりの世界」を逍遥する出雲神話 コラム1 絵図と遺跡が物語る【古代の出雲大社】 コラム2 八百万の神々が出雲に集まる【神在月】 天孫降臨の霊山から黒潮の海へアマテラスから日向三代へ日向神話 コラム3 神の里に伝わる民族文化【高千穂夜神楽】 初代天皇即位の地で神武東征の道筋を辿るヤマト神話 コラム4 神の鎮座する山【三輪山】 日本発祥の地オノコロ島を往く国生み神話 コラム5 ヒルコ神の鎮魂劇【淡路人形浄瑠璃】 数え切れないほど生活に密着した存在八百万の神々 神霊に近しい存在として登場する『古事記』の中の動物 古代人の食生活をうかがい知る『古事記』の中の食べ物 第三章 民話の世界を覗く 神々が住む理想郷と人間との出会い神話と民話 今もこの地に伝わり残る遠野民話と民間信仰 岩手の山麓で聞いた口頭伝承柳田國男と、『遠野物語』の足跡 おわりに ゆかりの地に今なお息づく神話 奥付 裏表紙
-
-日本神界と古代史の謎、ここに極まれり! 山窩(サンカ)とは、天皇家もロスチャイルドさえも足元にも及ばない巨大な財力と権力を持ち、神武以前よりこの国を裏から仕切ってきた謎の龍神一族。その最後の頭領のひ孫がついにその秘密を開示する!本書は、創造主がセットした「岩戸開き」そのもの――あざなえる縄の如き歴史と悟り――「真実」への命懸けの遊覧飛行である! 龍神と共に虚空にて修行した宗源だからこそ、この世に持ち帰ってこれたものとは? ・天皇家は山窩なしに存在・存続し得なかった?! ・戦国時代は実は山窩vs外国勢力の戦いであった?! ・信長も家康も山窩であり、外国勢力を追い払った?! ・秀吉は下級山窩の出身で神国日本の裏切り者だった?! ・山窩の最後の頭領の娘は、外国勢力とつるんだ明治政府要人岩倉具視の里子(人質?!)となっていた! ・山窩は往古からの叡智を結集させて豊国文字(神代文字)で『上記(ウエツフミ)』を遺した。『竹内文書』『九鬼文書』『富士古文献』はこれに連なるもの! ・封印されしウガヤフキアエズ、ニニギノミコト、ニギハヤヒノミコト、役の行者は、本書において、山窩と共に蘇る! 次元の扉が開き、天岩戸が開くと神の再生誕生と共に、悪魔も再生誕生する?! ・龍神が伝えるのは善悪のない虚空へのリセット=往古から聖人賢者が求めた無我の境地! ・釈迦、般若心経、龍神祝詞が伝えてきた真の悟りの意味がこの本に横溢している! ・人類は虚空にあって悟る以外に、道は、微塵もない! ・人間とは実体がないが故に、わからないものであるという以外わかることは一切ない! ・龍神、神々でさえも修行の途上にいる。龍神と人智を超えて虚空に行けば、全てがわかる! ・龍神が伝える岩戸開き、人類が到達すべき道とは、森羅万象を無にする悟りと虚空リセット(解脱)――これ以外に人類の進むべき道は無かった! ・虚空の向こう側の次元が人間界と交わる――これこそが、人類が発祥した目的すなわち、創造主の計画なのである! ・かつて存在したことのない歴史と悟りの本!
-
-ペリー来航から明治元年まで、わずか十五年。この短い間に、全国各地でさまざまな人たちが命を懸けて戦った幕末維新の動乱は、数多くのドラマを生み、それらがからみあいながら日本は新しい時代にたどりついた!しかし、人の立場も藩の動きも「紆余曲折」「二転三転」していて、当時の実態はものすごくわかりにくい。たとえば、ペリーが来た頃、徳川幕府と薩摩藩は仲が良く、また天皇は幕府を信頼していたのに、いつの間にか薩長が連携して天皇を擁し、倒幕の中軸となる。どこで何が変わって、こんな事態に至ったのか?本書は、30のエピソードを通して難解な幕末維新の実像を解説している。「倒幕を正当化する根拠を徳川一門が用意していた」「坂本龍馬は徳川家を守ろうとしていた」「徳川方は錦の御旗に対抗して日の丸の旗印を掲げたことがあった」――教科書には書かれていない話を豊富に盛り込み、幕末維新のストーリーが面白く、すっきりわかる一冊である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2014年10月20日、80歳の誕生日を迎えられた皇后美智子さま。本書はそんな節目の年に美智子さまが天皇陛下とともに歩まれた足跡を多数の写真とともに振り返ります。「皇室は祈りでありたい」――そのお言葉どおり、美智子さまは自然災害が起こるたびに現地へ赴き、被災者を慰め、犠牲者を弔われてきました。その「祈りの旅」や、半世紀前に国民を魅了した、懐かしいミッチースマイルのお写真の数々、渡辺みどりさん、喜多洋子さんによる特別寄稿など、皇室報道で実績のある「週刊女性」ならではの永久保存版です。※電子版には「特別付録 天皇・皇后両陛下2015年カレンダー」は付属しません。
-
-企業が100年間、その歩みを続けるのは容易ではない。激動の時代を生き抜く知恵を100年企業に求めた。 本書は週刊エコノミスト2018年1月16日号で掲載された特集「ザ・100年企業」の記事を電子書籍にしたものです。 第1部 日本的経営の源流 ・持続的な成長への岐路 100年企業に学ぶ知恵 ・インタビュー【パナソニック 津賀一宏社長】「幸之助の教え胸にイノベーション起こす」 ・第一次世界大戦と100年企業 国産化促した輸入途絶と特需 ・100年の転機(1) 関東大震災・昭和恐慌 無審査融資があだに ・安全自動車 中谷宗平社長 輸入車販売から検査・整備機器へ ・【SMBC日興証券 清水喜彦社長】多種多様な人材の集合体 ・【NTN 大久保博司社長】機械に欠かせないベアリング ・100年の転機(2) 敗戦 船舶など国富の25%被害 ・【関西ペイント 石野博社長】自動車・建築・工業の3本柱 ・【グローリー 尾上広和社長】ゼロから硬貨計数機開発 ・【神戸屋 桐山健一社長】米国への憧れを象徴したパン ・100年企業と日本的経営 「合本主義」と「人間主義経営」 ・【GSユアサ 村尾修社長】「天気晴朗ナレドモ…」を打電 ・100年の転機(3) 高度成長とオイルショック 10%成長が20年近く継続 日本的企業システム定着 ・【シチズン時計 戸倉敏夫社長】昭和天皇ご愛用の懐中時計 ・【駿河台学園 山崎良子理事長】根底は変わらぬ「愛情教育」 ・【象印マホービン 市川典男社長】割れない魔法瓶が大ヒット 第2部 長寿企業の強さ ・データで見る「100年企業」7つの秘密 ・100年の転機(4) バブル経済と崩壊 「リスクマネー」が消失 内部留保蓄積の悪循環 ・【帝人 鈴木純社長】鈴木商店源流の化繊から素材・医療の2本柱へ ・【東洋電機製造 寺島憲造社長】鉄道を幅広い電機品で支える ・【日本板硝子 森重樹社長】ガラスの進化で需要が拡大 ・【日本精化 矢野進社長】樟脳から化粧品原料にシフト ・100年の転機(5) リーマン・ショック ドル枯渇で設備投資抑制 円高で競争力に揺らぎ ・【ハナマルキ 花岡俊夫社長】100年でもまだ若い ・【ホーチキ 山形明夫社長】火災犠牲者ゼロ目指して「非戦」貫かせた企業理念 ・【松井証券 松井道夫社長】独立保った堅実経営 ・【守山乳業 大塚直人社長】日本で初めてコーヒー牛乳販売 ・これから100周年を迎える主な企業
-
-100余年前、明治天皇の暗殺を企てたと、幸徳秋水ら12人が刑場の露と消えた「大逆事件」。身に覚えのない罪を着せられ、被告26人の「最後の一人」となって戦前・戦後を生き抜き、無実と再審を訴え続けた坂本清馬。しかし、一徹で一刻、高知の「いごっそう」坂本は、23年もの獄中生活に耐えつつ、何度も何度も上申書を提出し、ひたすら無実を訴える。大逆事件は、治安警察法ができ、軍事大国に向かう時代のフレームアップだった。秘密保護法と集団的自衛権行使容認で、当時と似た空気を纏いはじめた今、坂本の生涯は我々の道標(みちしるべ)として強い輝きを放つ! 事件をでっちあげて、時代の風潮を変える「国策捜査」はこのとき始まった。検察腐敗の原点を抉る! ヒューマン・ドキュメンタリー。
-
-愛する家族やペットとの別れ、心身をむしばむ突然の病気や事故、そしていつか来る自然災害…… 「どうすれば死を恐れずに生きていけるか――」 人類の永遠のテーマに“魂”を磨く習慣で向き合う。 「肉体が滅んでも、魂は生き続けます。 平凡な毎日を大切にしてください。 後悔や心配を少しでも減らして心地よく生きていきましょう。 私たちは魂を成長させるためにこの世に来たのですから」(著者より) Q.私は80代後半ですが、家族や友人が鬼籍に入りました。 あの世へ行ったら、会いたい人全ての人に会えるのでしょうか? A.あなたが会いたい人が、あなたに会いたがっていれば会えます。 Q.今、地震や台風などの災害が増えています。 私は災害のことを考えると、とても怖くなります。どうしたら安心できますか? A.「備え」をして、「恐れ」を手放してください。自分なりに備えると、覚悟が定まるものです。 【出版社からのコメント】 東京大学名誉教授でもある矢作先生が、初めてのQ&A方式で死を恐れずに生きていくための思考術を提案します。 【著者プロフィール】 矢作直樹 (やはぎ なおき) 東京大学名誉教授/医学博士。 1956年、神奈川県生まれ。1981年、金沢大学医学部卒業。 その後、麻酔科を皮切りに救急・集中治療、内科、手術部などを経験。 1999年、東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻および同大学工学部精密機械工学科教授。 2001年、東京大学大学院医学系研究科救急医学分野教授および同大学医学部附属病院救急部・集中治療部部長。 2016年3月に任期満了退官。 主な著書に、『人は死なない』(バジリコ)、『天皇』『安心して、死ぬために』(ともに扶桑社)、『おかげさまで生きる』(幻冬舎)、『自分を休ませる練習』(文響社)など。
-
-
-
-7つの新しい「見方」が古代史学習の最強の「味方」になる! 天皇の存在意義とは? 新元号「令和」出典の『万葉集』の謎…にも言及! 日本史、特に古代に真実を知らずにいる日本人は不幸である。たとえば、千数百年間、日本人は天皇を推戴してきた。 しかし、天皇とはいったい何者なのか、教科書では教えてくれない。宗教についても同様で、神道とはどのような信仰なのか、なぜ仏教とごちゃ混ぜになってしまったのかを説明できない。本書は、7つのテーマから謎めく古代の真実を解き明そうと試みる野心作である。古代史は「ミカタ」しだいでいっきにわかる! 【主な内容】 第一章 「古墳」から読み解く古代の真実 第二章 「縄文」から読み解く 第三章 「天皇」から読み解く 第四章 「女性」から読み解く 第五章 「記紀」から読み解く 第六章 「神社」から読み解く 第七章 「事件」から読み解く
-
-反逆の罪に問われて死罪となった吉田松陰は、明治になって甦り靖国神社に祀られ、教育者としても賞揚されている。西郷隆盛も、時代によって、人によって評価がわかれる。幕末に尊王攘夷を掲げた志士たちの実像は、為政者や時代の空気によって書き換えられる。 そもそも尊王攘夷とは、中国の儒教から出てきた考え方で、君主の権威を擁護して異民族を国外に排斥することである。幕末の志士たちは、列強の脅威をはらい天皇を担ぎ出して維新を遂行した。やがて彼ら自身が英霊として担がれ、1945年まで生き続ける。志士から英霊へ――継続あるいは転換はどのようにおきたのだろうか。『儒教が支えた明治維新』に続く新・維新論。
-
3.0
-
4.0なぜキーンさんは英語で書き、私に翻訳させたのか ドナルド・キーンは生前、日本の新聞社・出版社の求めに応じて自伝を3冊刊行したが、まとまった評伝はこれまで書かれてこなかった。『日本文学史』をはじめ、長年のキーンの日本文学研究についての本格的な批評・研究もあまり見られないのではないか。数々の文学賞や文化勲章を受け、晩年に帰化してからは多くのメディアに登場したが、「学者ドナルド・キーンは、こうした受賞も含めて世間で持て囃されるか、あるいは無視されるか、そのどちらかの扱いしか受けてこなかったような気がする」と、40年来の友人で、『明治天皇』『日本人の戦争』などを翻訳した著者は指摘する。 ドナルド・キーン生誕101年、ユーモアと本物の知性を兼ね備えた文人の生涯をたどり、その豊かな仕事に光をあてる1冊。
-
3.5
-
-「生まれて、すいません」「待つ身が辛いかね、待たせる身が辛いかね」「恥の多い生涯を送ってきました」 いくつかの盗作があり、薬物中毒者でもあり、心中事件を繰り返し、最後は妻子を残して愛人と38歳で入水心中を遂げた作家は、今なお多くの読者を惹きつけています。 三島由紀夫に毛嫌いされて、檀一雄を激怒させたが、それでも無視できない魅力を感じていました。 太宰は、ダメな人間であり、ダメな作家であったからこそ、その輝きが永続するのだと、著者は言います。また、現代だからこそ、読まれるべき作家なのだとも。 太宰の作品が持っている、弱者に寄り添う独特な視線、未来志向とはほど遠い、退嬰的なあり方、自堕落なあり方は、私たちが弱々しく生きる自由があり、弱々しくしか生きられない私たちに寄り添う力があるのです。 弱い立場にあった(今なおある)「女」という存在を太宰はどう表現しているのかを、女言葉を使った作品の解読から読み解く「第一章 言語的異装趣味 「女」は文学に何をもたらしたのか」。 戦前・戦後を挟んで、人間でなかった天皇は、「人間」となりました。第一章の議論を受けて、多くの周りの人々を喪失した経験を生き残り(サバイバー)として、生きながらえる時の罪悪感(ギルト)をどう捉えるのかという視点から、作品を読み解く「第二章 人間失格と人間宣言 二人のサバイバース・ギルト」。 そして、「第三章 治りたがらない病人 太宰と三島」では、第二章の議論を受けて、二人の対照的な作家のあり方から、戦後日本における、生き方の困難への立ち向かい方を読み解いていきます。 作家太宰治の魅力を根本から問いなおす一冊です。 【目次より】 序 章 ふたつの失格 第一章 言語的異性装趣味 女生徒の見た世界 第二章 人間失格と人間宣言 太宰治と天皇 第三章 戦後作家のサバイバル 太宰と三島 終 章 私的太宰治論あるいはすこし長いあとがき ほんとうのおわりに 註 主要参考文献 初出一覧
-
4.8北条氏はなぜ将軍にならなかったのか。なぜ鎌倉武士たちはあれほどに抗争を繰り返したのか。執権政治、得宗専制を成立せしめた論理と政治構造とは。承久の乱を制し、執権への権力集中を成し遂げた義時と、蒙古侵略による危機の中、得宗による独裁体制を築いた時宗。この二人を軸にして、これまでになく明快に鎌倉幕府の政治史を見通す画期的論考!【本書より】・鎌倉北条氏は、そもそもどのような家であったのか。・「得宗」とは、いったいどういう意味なのか。・これは事実自体がほとんど知られていないが、鎌倉将軍には実は四人目の源氏将軍が存在した。第七代将軍源惟康がその人である。鎌倉幕府が空前の強敵蒙古帝国と対峙したこの時期、なぜ鎌倉幕府は源氏の将軍を戴いていたのであろうか。―これらの問題を追究するためには、どのような方法が有効なのであろうか。まず、鎌倉幕府の通史や北条氏歴代の伝記を書くつもりはない。なぜならば、この本は北条氏という「一族の物語」ではなく、「一族の物語」の底を流れる「基調低音」を書くことが目的だと思うからである。表面的に幕府や北条氏の歴史をなぞっても、我々が求める答には辿り着けないはずである。そこで私は鎌倉北条氏歴代のなかからキー・マンとして二人の「執権」を選んだ。承久の乱で仲恭天皇を廃位し後鳥羽・土御門・順徳の三上皇を配流(流刑)した「究極の朝敵」、第二代執権北条義時と、蒙古帝国の侵略を撃退した「救国の英雄」第八代執権、北条時宗である。世間一般の評価に極端な隔りのあるこの高祖父(ひいひいおじいさん)と玄孫(ひいひいまご)の人生に注目することにより、答に迫りたいと考える。この試みが成功し、見事、解答に至れるかどうかは、わからない。「とりあえず付き合ってやるか?」と思った読者と共に旅に出るとしよう。【本書の内容】はじめに―素朴な疑問 第一章 北条氏という家 二章 江間小四郎義時の軌跡―伝説が意味するもの 第三章 相模太郎時宗の自画像―内戦が意味するもの 第四章 辺境の独裁者―四人目の源氏将軍が意味するもの 第五章 カリスマ去って後 おわりに―胎蔵せしもの
-
3.5■「鎌倉殿」とは鎌倉幕府将軍のことであり、頼朝の周囲を13人の側近(御家人)が支えていた。頼朝の死後、彼らは激しい内部抗争を繰り広げるが、その中で最後まで生き残り、将軍にかわる「執権」として権力を手中に収めたのが、13人中もっとも若かった北条義時である。戦前は、ライバルをはじめ、実父、源氏将軍、上皇・天皇を排した所業から「暴君」とされたこともあったが見方を変えれば、数々の闘争に勝ち続け、最高権力者として君臨できた日本史上でも稀な人物でもある。鎌倉初期から承久の乱までを駆けぬいた2代執権・義時が勝ち続けた理由はなにか?なぜライバルは義時に歯が立たなかったのか?敗者として歴史の闇に消された13人の歴史人物に焦点をあて、執権義時の黒すぎる生涯を見ていく。 [目次] 序 章 「鎌倉殿の十三人」と合議制 第1章 頼朝側近・有力御家人を次々排した北条氏 第2章 合議制で台頭し実父を排した義時 第3章 三代将軍を排し執権政治を確立した義時 第4章 倒幕勢力をねじ伏せ幕府を盤石にした執権義時 終 章 執権義時を消したのは誰か <著者略歴> 榎本 秋 (えのもとあき) 1977年東京生まれ。文芸評論家。歴史解説書や新書、評論や解説などを数多く手がける。代表作は『世界を見た幕臣たち』(洋泉社)、『殿様の左遷・栄転物語』(朝日新書)、『歴代征夷大将軍総覧』『外様大名40家』『戦国軍師入門』『戦国坊主列伝』(幻冬舎新書)、『将軍の日本史』 (MdN新書)など。福原俊彦名義で時代小説も執筆している。 ※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『執権義時に消された13人 闘争と粛清で読む「承久の乱」前史』(2021年11月17日 第1刷)に基づいて制作されました。 ※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
-
4.0「天皇・皇族に戸籍はあるの?」「国事行為ってどんなことをするの?」など硬めの疑問から「天皇・皇后はお互いになんと呼んでいる?」「お召し列車は有料?」など柔らかめの疑問まで。皇室の素朴な疑問に答えます。
-
3.4「アマテラスの岩戸隠れ」「因幡の白兎」「ヤマトタケルのオロチ退治」など、日本人なら誰でも知っている神話を天地創造神話・古代天皇に関する神話・神社創祀などに分類し、神話の世界が現代語訳ですっきりわかる。
-
4.5
-
-聖書のもつダイナミズムを解き放ち、人間の救済を志向する。 理性への信頼に基づく近代主義、あるいは人間中心主義を根底とした自由主義神学の内部から、それを打ち破るかのように登場したカール・バルト。神学を人間学へと解消する潮流に抗し、キリストと行動をともにした使徒によるドキュメントとして聖書をとらえ、神の言葉と啓示がもつ直接性の復活を果たす。使徒という存在に近代の超克を読みとり、来るべき人間として思想と文学の起点にすえる、画期的な長篇評論。 佐藤優 使徒は、人間を救済するという自覚を持つ人間だ。この救済は、個別具体的である。救済の一般理論は存在しない。(略)神の存在が生成において人間に理解されることに対応し、富岡氏の思想的営為も常に生成過程にある。イエス・キリストという名に徹底的に固執することによって、日本人の歴史物語、特に天皇と救済の関係について、いつか適切な言葉が見つかることを信じながら、富岡氏は評論活動を展開しているのだと私は見ている。――<「解説」より> ※本書は、講談社刊『使徒的人間――カール・バルト』(1999年5月)を底本として使用しました。
-
3.5
-
5.0
-
3.0先日、渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎が新紙幣(2024年度~)の肖像に選ばれ、話題となった。 だが実は、肖像のセレクトには「時代背景」や「印刷技術の制約」が絡んでいる。 「時代背景」の観点では、戦前は皇国思想の影響で、天皇と国に尽くした人物(藤原鎌足など)が採用された。 「印刷技術」の観点では、福沢諭吉が起用されるまでは偽造防止の印刷技術が未熟で、偽造しにくいヒゲの人物が優先で選ばれている。 さらに、新旧紙幣の肖像は、実は互いに関連性を持ちつつも、その人物像に「対照的な違い」があることも面白い。 例えば現五千円札の樋口一葉は、貧困のなか活躍した女性作家だが、実は“女”を利用するしたたかさもあったとされ、 新紙幣では、女性の高等教育に尽くした清廉な津田梅子が採用された。 以上、本書では「紙幣の肖像の背景」を検証し、そこにある“知の発見”を読者に提供していく。
-
5.0
-
-連隊旗を奪われた若き日の事件から、明治天皇のあとを追って殉死するまで、英雄伝説はいかにして作られたか……。乃木大将の愛馬たちの脚から眺めた滑稽なる近代日本とは? 辛辣なパロディの礫で迫る軍神一代記「しみじみ日本・乃木大将」(読売文学賞受賞)に、若旦那とたいこもちが、流離の悲運のなかで繰りひろげられる爆笑みちのく道中記「たいこどんどん」を併録する傑作戯曲集。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 社会学の泰斗による、「社会学」の諸主題(意味関連、競争、共同社会、社会構造など)についての、考察をまとめた論考集です。社会学の初学者から専門家まで役に立つ論文集です。 【目次】 まえがき 一 社会学の対象と方法 二 意味連関と現実態 三 社会心理学的相互作用の過程 四 他我の了解 五 親和関係考 六 競争考 七 共同社会考 八 利益社会考 九 社会発展の論理 一〇 社会構造と人間形成 一一 未開社会考 一二 村落 一三 日本家族の推移 一四 女性の特質とその社会的基礎 一五 民族 一六 社会と個人 あとがき 索引 臼井 二尚 1900~1991年。社会学者。京都大学名誉教授。京都帝国大学文学部社会学科卒。文学博士。 著書に、『国家国民の象徴としての天皇』『社会学論集』『臼井二尚論攷抄』『社会と民族』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.7・内容紹介 「いま私たちはどんな時代を生きているのか」「これからの時代で何を大切にして生きていくべきなのか」。 社会学者・宮台真司が日々のニュースや事件、社会現象をネタに、 「そもそもなぜそれが起こったのか」を解説しながら、 現代という社会、また、より良い生き方のスタンスについて詳しく丁寧に説いているラジオ番組 「デイキャッチャーズ・ボイス宮台真司」。 「天皇と安倍総理」「民主主義と独裁」「沖縄問題のゆくえ」「ブラック企業」……。 この社会の本当の「問題の本質」を解き明かす。 宮台真司の「本質を見抜くニュースの読み方・考え方」が学べる書。 社会学的知見に基づいたフィールドワークを通して論考した宮台の現代批評は、 不透明な時代の見晴らしを良くする武器となるはずだ。 ・著者 宮台真司(みやだい・しんじ) 1959年生まれ。社会学者、映画批評家。首都大学東京教授。 東京大学文学部卒、東京大学大学院社会学研究科博士課程満期退学。 社会学博士。東京大学教養学部助手、東京外国語大学専任講師、東京都立大学助教授を経て現在に。 社会システム理論を専門分野とする一方、テレクラ・コギャル・援助交際など、 サブカルチャー研究でも第一人者に。 著書に「権力の予期理論」「制服少女たちの選択」「終わりなき日常を生きろ」「日本の難点」 「民主主義が一度もなかった国・日本」「絶望時代の希望の恋愛学」など多数。
-
-最大のミッションは世継ぎを残すこと 将軍が幼いころから受ける性の作法とは――。 奥御殿での「性の作法(テクニック)」を門外不出の秘伝として、 江戸時代初期に記された『秘事作法』を種本に、薬子が宣旨(せんじ)、内侍(ないしのかみ)として後宮に奉職した頃、立派なお世継ぎを産んでもらうために、幼少から若君の男性器をたくましいものに鍛える「養宝作法(ようほうさほう)」。女官たち自らの身体を駆使して若殿に実践の手ほどきをする「奉礼作法(ほうれいさほう)」など様々な秘め事を集約した一冊。 【目次】 前之章 秘事作法 第一章 強腕・藤原百川の策略(白龍となった井上皇后の怨霊) 第二章 藤原薬子と安殿親王(薬子、安殿の養育係として東宮に入る) 作法1「養宝作法」(若殿のお宝を強靭にする方法) 作法2「奉礼作法」(若殿に女性への手ほどきを指南する) 作法3「養宮作法」(奥方に交合の作法をお側でお手伝いする) 第三章 薬子が尚侍に任命される(薬子、女官たちへ秘事作法を指南) 作法4「房中術難所の心得」(我慢のための還精の術を学ぶ) 作法5「女官たちの礼法と健康指導」(奥女中の欲求不満解消法) 第四章 平城太上天皇の変(薬子の最期と平城の悲しみ) 終之章 余禄 1)医心方房内篇(性医学書の集大成で春本にあらず) 2)藤原一族(朝廷をも牛耳る神代からの名門) 3)水鏡(神武から仁明天皇まで1,500年間の仮名国史) 4)弓削道鏡(道鏡は坐ると膝が三つでき) 5)臨御之章(初夜はとりあえず、男性は右に女性は左に) 6)断鬼交之章(鬼とのセックスの満足感は人間以上なり) 7)態位九法之章(黄帝が石室に残した秘中の性交九態位) 8)四ツ目屋のこと(江戸のアダルトショップ秘聞) 【著者プロフィール】 昭和17年生まれ石川県白山市在住。「歴史は同じことの繰り返し、その検証は我が将来への道標(みちしるべ)となる」を命題に、東四柳史明氏(金沢学院大学名誉教授)に師事し、郷土の中世・戦国社会を研究。著書に『悪女万華鏡』(幻冬舎2022年)。
-
-日本を代表する歌人が、珠玉の名歌を季節ごとに精選した究極のアンソロジー。初心者にもわかりやすくその魅力を解説する、極上の短歌体験! 柿本人麿、藤原定家、良寛、正岡子規、石川啄木など、八〇人以上に及ぶ古今の歌人から一五〇首以上の歌を選り出し、その魅力を解説し、初心者にもわかりやすく読んでいく。いつの世も変わらぬ人生の愉悦、悲哀、そして無常をも心ゆくまで堪能する、贅沢なひとときがここに。 【本書の扱う歌人(一部)】 天智天皇 額田王 持統天皇 山上憶長 大伴旅人 柿本人麿 大海人皇子 山部赤人 小野小町 在原業平 西行法師 藤原定家 和泉式部 式子内親王 源実朝 良寛 正岡子規 北原白秋 与謝野鉄幹 与謝野晶子 窪田空穂 伊藤左千夫 前田夕暮 斎藤茂吉 若山牧水 土岐善麿 土屋文明 石川啄木 島木赤彦 釈迢空 川田順 佐佐木信綱(ほか多数) 【目次】 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 あとがき
-
-【目次】 ・賢い相続と不動産活用 ・世界史に学ぶ経済、2、3 ・宗教と経済1、2 ・税務調査がやって来る ・とことん学ぶ通貨と為替 ・あなたの土地の相続増税 ・強い大学 ・終の住みかを考える 上下 ・地図で学ぶ世界経済 ・資本主義をとことん考えよう ・水素・シェール・藻 ・とことん考える 人口減 ・ランキングで見える世界経済 ・もめない遺産分割 ・人工知能が拓く未来 ・世界低成長の「異常」 ・水素車・リニア・MRJ 水素4兆円市場の「ミライ」 ・実家の後始末 年末年始親と子で考える ・競争激烈!税理士・会計士・弁護士 ・読書会ブームが来た ・自動運転・AI・ロボット ・危ういROEブーム ・ピケティにもの申す ・宇宙・深海・地底 ・とことん分かる低金利 ・相場は歴史に学べ ・キーワードで知る経済リスク ・日本人が知らない 中東&イスラム教 ・水素と電池 世界はこれでリードだ ・土地投資の極意 ・相場を見抜く経済指標 ・農業改革の化けの皮 ・いま古本屋が熱い ・アジアインフラ争奪 ・徴税強化 ・地銀再編前夜 ・世界史を動かす 聖書と金利 ・世界を変えるiPS産業 ・商社の下克上 ・今そこにある財政危機 ・AEC 期待と不安の発足 ・日本を守る情報戦の極意 ・東芝の闇 ・軽き日本国憲法 ・戦後70年 歴史と未来 ・よみがえる絶版本 ・オワハラ時代の大学と就活 ・本当は怖い 物価大停滞 ・歴史に学ぶ 通貨と為替 ・これだ人工知能自動運転 ・大解剖 日本郵政株 ・韓国の限界 ・インドびっくり経済 ・生保の正念場 ・知って驚く コーヒー革命 ・保存版 相続増税の新常識 ・そうだったのかTPP ・銀行の破壊者フィンテック ・これじゃ食えない会計士、税理士、弁護士 ・地図でわかった原油恐慌 ・コンビニ経済圏 ・丸分かり激震中国 ・農業がヤバい ・投資が恐い人の資産防衛大綱 ・マイナス金利 ・暴れる通貨 ・ネットスーパー戦国時代 ・ここが変だよ電力自由化 ・農協猶予5年 ・商社の憂鬱 ・世界を変えるIoT ・直撃マイナス金利 ・会社で役立つ経済学 ・悩む仏教 ・世界史に学ぶ金融政策 ・どん詰まり中国 ・検証なき日銀 ・マイナス金利に勝つ資産運用 ・新聞に載らない経済&投資 ・人工知能AIの破壊と創造 ・パナマ文書ずるい税金逃れ ・経済は物理でわかる ・もう乗れるぞ自動運転・EV ・英国離脱EUの衝撃 ・ヤバイ 投信 保険 外債 ・ヘリコプターマネーの正体 ・世界の危機 ・天皇と憲法 ・韓国の騒動 ・中国ゾンビと政争 ・ぶらり日本経済 ・人口でみる世界経済 ・踊る経済統計 ・さまよう石油再編
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ヤクザ顔負けの抗争、裏切り、怪死。戦後の日本を駆け抜けた異色の政治家たちと、その側にいたフィクサーや名物財界人。独自証言と貴重な写真満載の決定版。 登場人物はこの16人 中曽根康弘 安岡正篤 小佐野賢治 池田勇人 大野伴睦 佐藤栄作 中川一郎 竹下登 本田宗一郎 盛田昭夫 永田雅一 金丸信 渡辺美智雄 安倍晋太郎 浜田幸一 昭和天皇 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。