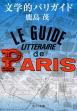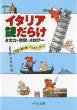雑学・エンタメ - 中央公論新社作品一覧
-
4.2古関裕而(一九〇九~八九)は忘れられた名作曲家である。日中戦争中、軍歌「露営の歌」で一世を風靡、アジア・太平洋戦争下のニュース歌謡や戦時歌謡を多く手がけ、慰問先でも作曲に勤しんだ。戦後は鎮魂歌「長崎の鐘」、東京五輪行進曲「オリンピック・マーチ」、映画「モスラ」劇伴音楽と、流行歌からスポーツ音楽まで数々の名曲を残す。戦争、そしてテレビの普及まで、昭和史を彩った彼の生涯をたどる。
-
4.2小説を書くときにもっとも大切なこととは?実践的なテーマを満載しながら、既成の創作教室では教えてくれない、新しい小説を書くために必要なことをていねいに追う。読めば書きたくなる、実作者が教える〈小説の書き方〉の本。 著者の小説が生まれるまでを紹介する、貴重な「創作ノート」を付した決定版。
-
5.0戦後の「正義」に抗い、自身の「私情」に忠実であることを表明した「戦後と私」、三島由紀夫、石原慎太郎、大江健三郎を論じた卓越した批評「神話の克服」。「私」三部作ほか、癒えることのない敗戦による喪失感と悲しみを文学へと昇華した批評・随想集。自作回想「批評家のノート」初収録。 〈解説〉「江藤淳と『私』」平山周吉 【目次】 Ⅰ 文学と私/戦後と私/場所と私/文反古と分別ざかり/批評家のノート Ⅱ 伊東静雄『反響』/三島由紀夫の家/大江健三郎の問題/神話の克服 Ⅲ 現代と漱石と私/小林秀雄と私 解説 江藤淳と「私」(平山周吉)
-
3.3イベント好きな日本人に 商業主義も忍び寄る…… ●神社の「二礼二拍手一礼」は伝統的な作法なんかじゃない! ●除夜の鐘を全国に広めたのはNHKだった!? ●初詣は鉄道会社の営業戦略だった! ●郊外の墓参りはバブルが生んだ年中行事! ●結婚式のご祝儀もお葬式の半返しも伝統なんかじゃない! ●そもそも、クリスマスはキリスト教と関係がない! 日本人が「しきたり」と思っている行事には、ごく最近生み出されたものが少なくない。私たちは「しきたり」とどう向き合えばいいのか。 神社に掲げられる「二礼二拍手一礼」は伝統的な作法なんかじゃない! 初詣は鉄道会社の営業戦略だった! 郊外の墓参りはバブルが生んだ年中行事! 結婚式のご祝儀もお葬式の半返しも伝統なんかじゃない! そもそも、クリスマスはキリスト教に関係がない! 日本人が「しきたり」と思っている行事には、ごく最近生み出されたものが少なくない。私たちは「しきたり」とどう向き合えばいいのか。「しきたり」の概念を根底から覆す一冊。
-
-民俗学とは何か。表題作ほか「国史と民俗学」「実験の史学」など学問実践の体系化を目指した論考によって「方法としての民俗学」を浮き彫りにする文庫オリジナル論集。折口信夫との対談、生涯と学問について語った「村の信仰」を併せて収める、柳田学入門の決定版。〈解説〉佐藤健二 【目次】 I 日本の民俗学 郷土研究ということ/日本の民俗学/Ethnologyとは何か/日本の民俗学/ 郷土研究の将来 /国史と民俗学/実験の史学/ 現代科学ということ/日本を知るために Ⅱ 柳田国男・折口信夫対談 日本人の神と霊魂の観念そのほか 民俗学から民族学へ――日本民俗学の足跡を顧みて Ⅲ 村の信仰――私の哲学
-
-著作活動六〇年、生涯に刊行した一〇一冊の自著に寄せた序跋文と解説を年代順に初集成。全業績を一望のもとにおさめるオリジナル自著解題集。第Ⅰ巻には『最新産業組合通解』(明治三五年)から『居住習俗語彙』(昭和一四年)までを収録する。全二巻。 〈解説〉「柳田國男による柳田國男」佐藤健二
-
-『最新産業組合通解』(明治三五年)から『海上の道』(昭和三六年)まで、著作活動六〇年。生涯に刊行した一〇一冊の自著に寄せた序跋文と解説を年代順に初集成。全業績を一望のもとにおさめるオリジナル自著解題集。 〈解説〉「柳田國男による柳田國男」佐藤健二
-
4.5発火、料理、消毒、肥料、発酵、製紙、染料、陶芸のほか香道や茶道にも道具や材料として、灰は日本人の生活を支えてきた。また童話の中には「灰かぶり姫(シンデレラ姫)」に似た話が世界にあることを見出す。食生活、社会、風俗、宗教、芸術に分け入り、身近な生活必需品=灰の科学と神秘性を解き明かす。灰の負のイメージを払拭する画期的な作品。 目次 Ⅰ 灰の生いたち 灰の誕生と埋火(うずみび)のこと 灰の成分と用途、そして灰屋のこと Ⅱ 灰と食 食べものと灰 酒と灰 醤油・味噌と木灰 海藻と灰 料理と灰汁(あく) Ⅲ 灰の恵み 和紙・織物と木灰 染料・染色と木灰 やきものと灰 Ⅳ 灰の効能 薬と灰 「秘術伝書」と灰 Ⅴ 灰の恐怖 火山と灰 死の灰 Ⅵ 灰と高貴 茶道・香道と木灰 習俗・宗教と灰 文学と灰
-
5.0高齢化社会での親と子の複雑な関係を分析した「親のトリセツ(取り扱い説明書)」です。ニュースでは、高齢の親の実家を片づけること、親の老後の不安、オレオレ詐欺の犯罪までがテーマとなっています。実家問題や墓じまい、相続に関すること、あるいは親の老後生活や介護など、親と子の問題はたくさんあります。ところが、親は子の提案に耳を傾けないことが多く、それどころか、反発したり泣かれたりもして収拾がつきません。そこには、「子に迷惑をかけたくない」という心理、また、「老い先が心配」「喪失感が大きい」などの気持ちの葛藤が隠されているようです。親も子も、もめたくないし誰もが親の幸せを願っています。本書では、高齢の親との話し方、接し方を含め、具体例を交えながら、わかりやすく事例を紹介する親のトリセツ(取り扱い説明書)の決定版です。高齢化社会の問題を解決するバイブルの一冊です。
-
4.0二十八日ノ船デ暑イ所ヘ行ツテ来マス――。一九四一年に南洋庁の官吏としてパラオに赴任した中島敦。その目に映った「南洋」とは。小品『南島譚』『環礁』に加え、南洋群島(ミクロネシア)から妻子に宛てて毎日のように綴られた多くの書簡を収録。 〈巻末エッセイ〉土方久功 【目次】 南島譚 幸福 夫婦 雞 環礁――ミクロネシヤ巡島記抄―― 寂しい島 夾竹桃の家の女 ナポレオン 真昼 マリヤン 風物抄 書簡 昭和十六年六月―昭和十七年三月 巻末エッセイ トン 土方久功
-
-二十世紀を代表する歴史家ホイジンガが、フランスとネーデルラントにおける十四、五世紀の人々の実証的調査から、中世から近代にかけての思考と感受性の構造を、絶望と歓喜、残虐と敬虔の対極的な激情としてとらえ、歴史の感動に身をおく楽しみを教える。中世人の意識と中世文化の全像を精細に描きあげた不朽の名著。 【目次】 第一版緒言 Ⅰ はげしい生活の基調 Ⅱ 美しい生活を求める願い Ⅲ 身分社会という考えかた Ⅳ 騎士の理念 Ⅴ 恋する英雄の夢 Ⅵ 騎士団と騎士誓約 Ⅶ 戦争と政治における騎士道理想の意義 Ⅷ 愛の様式化 Ⅸ 愛の作法 Ⅹ 牧歌ふうの生のイメージ ⅩⅠ 死のイメージ ⅩⅡ すべて聖なるものをイメージにあらわすこと 史料解題
-
3.6「いつもオタク現場にいるあの人、一体なんの仕事をしているんだろう?」 ソシャゲに延々お金を注いだり、推しているアイドルのツアーに合わせて全国を飛び回ったり……。すべてを惜しみなく推しに注いでいる彼女たちはいったいどんなお仕事をして、時間とお金をやりくりしているの? そんなリアル女子のおしごと事情をインタビューでひもとくWeb連載「オタ女子おしごと百科」が本になりました! ベストセラー『浪費図鑑』でおなじみの劇団雌猫が、日々趣味と仕事の両方にいそしむオタク女子たちにインタビュー。「仕事とオタ活の両立」の工夫や、知られざる「オタ活に向いた仕事」も徹底取材。 さらに、本書ならではのオリジナル要素として、悪友たちが実践している働き方のアンケート調査結果や、悩める悪友のためのキャリアコンサルタント・西尾理子先生のお話も収録。 仕事とシュミ、どっちも頑張る女子のための、新しい働き方指南本です! ■内容紹介 ◇仕事は仕事、シュミはシュミ! 「切り替え」オタク女子インタビュー ◇仕事でもシュミを強みに! 「公私混同」オタク女子インタビュー ◇私たちのキャリア、どうすれば? 「お仕事選び」のプロに聞いてみた ◇オタク女子が幸せに働いていくには? 劇団雌猫座談会 ◇悪友たちの"おしごと"事情 ◇あなたのお仕事と推し事の両立のコツを教えて!
-
-1987年4月にスタートした「朝まで生テレビ!」。著者は、ときに強引すぎるとの批判を受けつつも、その独特の司会ぶりで、原発、天皇、右翼など“日本のタブー”に挑み、30年間にわたって番組を牽引してきた。野坂昭如氏、大島渚氏など放送開始時から存在感を示した出演者から、堀江貴文氏ら最近の若手論客まで、多彩なパネリストたちによる“論戦”を一挙に振り返る。 目次 第一章 「公平でない」「発言しすぎる」は、私にとっての褒め言葉 第二章 手応えを感じた原発論争 反対派と推進派が直接対決 第三章 自粛ムードの中、あえて天皇と天皇制を論じる 第四章 野坂昭如抜きには成り立たなかった差別問題論争 第五章 野村秋介との対話で確信、右翼とも議論はできる 第六章 ときには同志、ときには好敵手 野坂、大島、西部……素顔の論客たち 第七章 本物っぽく見えた麻原彰晃 宗教を扱う難しさを実感 第八章 対米従属か、自立か 安全保障をめぐり意見は真っ二つ 第九章 これからは彼らが主役 若手論客に教えられること
-
4.0デーモン閣下「吾輩の場合は、一見、力技のように見える、正統派の押し相撲を取る力士がもっと評価されていいと思う。突き押しにもテクニックがあるのだから。」 やくみつる「横綱には横綱の勝負の格というものがあるよね、横綱らしい相撲が見たいなあ、場所を通じて。」 ――自他ともに認める好角家・やくみつるとデーモン閣下の両氏が、神事から興行への歴史、相撲との出会い、思い出の取組、技巧派と力相撲の変遷、四股名のあれこれ、引退後の白鵬問題などを語り尽くした激論沸騰の熱血対談!
-
3.0会社をリタイアしても、人生は終わってはいない。還暦になろうが古稀になろうがそれがどうしたというのだ。やりたいことがある。やり残したことがある。このまま終わりたくない。社会のために生きていきたい……そんな気持ちが少しでもあるのなら、思い切って新しい一歩を踏み出して欲しい。人生に最後の花を咲かせたいと思っているすべての大人たちに捧げる応援の書。「定年後」を楽しく生き抜くヒントに溢れた一冊。 ◎内容紹介 ★第一章 同世代はこんなことをしている 隠れ家のすすめ 遊べ男たち/タクシードライバーのLINE/「ポケモンGO」への好奇心 / イクジイは楽しい/歯医者さんは全力疾走/ライフ・シフト/70代が作った「世直し結社」/ めざすは「荒野」から京都へ/クールに地球に恩返し→男のアンチ・エイジング ★第二章 心機一転! 残間の日々 花咲かオバサン/バーゲンへ行こうよ/百恵さんのキルト/社外取締役になってみた! /英語をはじめようかな/私が主宰している「クラブ・ウィルビー」のこと /ときには、退路を断って/泣かない時代をつくりたい/病院の玄関で年末の儀式/ 入院中に「喝」を入れる/ つくり笑いでリハビリを/元気なうちは、「起きたきりでいよう」 ★第三章 気を付けよう、同世代、あるある! 葛藤と嫉妬を乗り越えて/「鏡よ鏡!」、年齢同一性障害の恐怖/気が付けばオバサン服。わび・さび色の罪と罰?/怒りやすくなってませんか?/鬼婆はいても鬼爺はいない/今、再びのシュプレヒコール/「してはいけないこと」を考える/うるさいシニア女性たち /世のスピードに乗れてますか/80歳でも油断禁物 /同世代男性のシモネタを一喝 /褒められ下手な女たち/病気の問屋/愚痴は鍋の中に溶けて…… ★第四章 始まれば終わる、未練を捨てよう。 髪を切る/息子目線でダウンサイジング /断捨離 第2弾 が必要/免許返納を意識する日々/始まれば、おわる/再び考えた「閉じる幸せ」/空の巣症候群 くよくよするな! /100歳からはあるがままに/シニアファッションは鈍感力で!/「尊厳死宣言公正証書」はまだ書かない/平凡 非凡も大海の粒 /年賀状を諦める /すべては恩讐の彼方に 記憶の「確かめ電話」/恋は「暗闇」専門 に ★第五章 お独りさまは 寂しくなんてない 増える一人旅/ 大人の一人旅は代理店を活用しよう/一人の闘病に備えて/ 落ち込んだ日には/ エンタメは心の栄養剤 !/漬物とご飯があれば/もやしのヒゲ/お独りさまライフの醍醐味/最後まで仲間と過ごしたい/孤独な運動よりおしゃべり/仲間に会える店があれば/お独りさまの道連れ/古い友人たちは「原点」 ほか。
-
3.5孤独に怯えることはない 豊かさを愉しめばいい 人は本来孤独を恐れるべきものだろうか。あるいは、孤独はただ避けるほうがいいのか。 私は孤独の中にも、何か見いだすべきものがあるのではないかと思うのです。(中略)孤独の持っている可能性というものをいま、私たちは冷静に見つめ直すときにさしかかっているようにも感じるのです。(本文より) 30万部のベストセラー『孤独のすすめ』、待望の続編! 世に流布する「孤独論」を退け、真の「孤独論」がここに完成した。 第一章 孤独に怯える人びと 第二章 「和して同ぜず」という思想 第三章 生物としての孤独とは 第四章 老いるヒントについて 第五章 孤独を愉しむ 終 章 孤独は永遠の荒野ではない 【対談】 × 下重暁子 歳をとるにつれて ひとりの時間が味わい深くなる
-
3.0『機動戦士ガンダム』の生みの親の一人であり、マンガ家として歴史や神話を題材にした傑作を世に問うてきた安彦良和。『宮崎駿論』などで注目される気鋭の批評家が20時間にわたって聞き取った、『機動戦士ガンダム』の神髄とマンガに込められたメッセージとは? 2019年は『機動戦士ガンダム』テレビ放送開始から40周年。戦争・歴史マンガの多彩で豊饒な作品世界、日本の歴史、あの戦争、いまの社会――。40年を超える、過去から未来への白熱討論!
-
3.9「非」フィクションとして出発したノンフィクション。本書は戦中の記録文学から、戦後の社会派ルポルタージュ、週刊誌ジャーナリズム、『世界ノンフィクション全集』を経て、七〇年代に沢木耕太郎の登場で自立した日本のノンフィクション史を通観。八〇年代以降、全盛期の雑誌ジャーナリズムを支えた職業ライターに代わるアカデミシャンの活躍をも追って、「物語るジャーナリズム」のゆくえと可能性をさぐる。
-
4.0未曽有の大事件から我々は何を学ぶべきか。自身の評論活動から、一時「オウムシンパ」との批判を受け、以来、オウム事件の解明に取り組んできた筆者が、いまこそ事件の教訓を問う。信念なき「普通の人」たちが凶悪犯罪を起こしたのはなぜか。それは、オウムが日本組織に特有な奇妙な構造を持っていたからだ。日本組織の特殊さを理解せずにオウム事件は終わらない。
-
-元政上人は、法華宗の僧侶としてだけでなく、漢詩、和歌、文筆に秀でた江戸時代有数の文化人として知られていた。 元政上人の名前を知る人は、今となってはほとんどいないかもしれない。まさに“忘れられた詩人・文学者”である。けれども、松尾芭蕉や、井原西鶴、北村季吟、小林一茶、宝井其角、与謝蕪村といった江戸時代を代表する文化人たちがこぞって元政上人を仰ぎ、讃嘆していた人であり、宮沢賢治の「雨ニモマケズ手帳」にも「元政」の名前を挙げて上人の短歌がメモされていたことなどを知れば、没後三百五十年の歳月を経た今、元政上人を改めて見直すことも、日本文化の源流を知る上で重要なことであろう。――「はしがき」より
-
3.0「戦略」については、古今多くの論考がなされ、広く注目を集めてきた。しかし現在、欧米の軍事専門家が最重要視しているのは「戦略(strategy)」と「戦術(tactics)」を架橋する「作戦(operation)」の考え方である。日本ではもともと作戦という言葉が幅広い使われ方をしていることもあり、この概念はいまだ理解が進んでいないが、戦争を取り巻く状況が変化した現代にあって、その役割を学ぶのは喫緊の課題であろう。本書では「作戦」の歴史的経緯をふまえたうえで、現在論議されている具体的な事例を検討する。 目次 序論 ポスト冷戦時代における作戦の特色―「軍隊行動の三レベル」 第一部 作戦の起源 第1章 作戦のない軍隊運用―絶対君主時代の戦闘回避主義 第2章 「大戦術」の開発とナポレオン戦争 第3章 ジョミニとアメリカ南北戦争 第4章 クラウゼヴィッツの「戦略」とモルトケの作戦 第二部 冷戦期までの作戦 第5章 米軍の消耗戦方式―封印された作戦の概念 第6章 ソ連軍の縦深作戦 第7章 フラーとハートの士気喪失作戦 第三部 ポスト冷戦時代の作戦 第8章 「緊要で、脆弱な『重心』」の追求 第9章 「影響」重視の考え方 第10章 複雑な「問題」と「システミック作戦デザイン」 おわりに
-
4.7星の文人・野尻抱影が三十余年の歳月をかけ蒐集した、星の和名七百種の集大成。各地に埋もれた星の方言をまとめ、四季の夜空をいろどる星の生い立ちを、農山漁村に生きてきた人々の生活のなかに探る。日本の夜空に輝く珠玉の星名が、該博な知識と透徹した詩人の直観力とをもって紡がれていく。 〈解説〉石田五郎
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1982年に創刊された『新潮45』が2018年10月号をもって休刊した。8月号の杉田水脈・衆議院議員による論文「『LGBT』支援の度が過ぎる」、並びに10月号での杉田論文の検証企画が強い反発を受けたためだ。これからの言論空間はどうなっていくのか―― (『中央公論』2018年12月号同名特集より) 「休刊誌でたどる『編集』の困難 分断された読者を、雑誌は『総合』しうるか」武田徹・専修大学教授/「くだらない企画に内包されたLGBTと国家の大きな問題」千葉雅也・立命館大学准教授/「元『論座』編集長が語る論壇史」薬師寺克行・東洋大学教授
-
4.1すべての人は笑う前に驚いている――。数々のヒットCMで知られる広告クリエイティブの第一人者が、「起承転結のワナ」「オムニバス禁止令」「ポストイット脚本術」など、豊富な事例を挙げながら、映像や脚本づくりのテクニックを公開。クリエイターのみならず、「伝わる」表現とは何か知りたいあらゆる人に役立つ本。〈解説〉佐渡島庸平
-
3.5◆ベストセラー『服を買うなら、捨てなさい』のスタイリストと、ハリウッド女優のファッションにも詳しい映画ジャーナリストによる激辛放談。30年来の仲の二人は、おしゃれも恋愛も人生も、映画から学んだと断言します。 ◆「映画は、ちょっと先の未来を見せてくれる」という二人が、今こそ観てほしい映画をピックアップ。ファッションと映画という華やかな世界で活躍し続けてきた二人が語る、オシャレ観、恋愛観、人生観は、これからを生きる女性たちに、勇気と希望を与えてくれます。 ◆トレンドの最前線にいるハリウッド女優の話や、リアル女子の手本となったファッションアイテムについてなど、女性が気になるポイントも登場。映画通の人はもちろん、仕事や子育てで映画を観ることから離れてしまった人、今まで映画を観ることの少なかった人も、「もう一度映画を観てみたい」と思える1冊
-
4.0噺を残すのは、噺家の使命。あたしたちの代で噺の数を減らしたら先人に申し訳ない――。小学四年生で噺家になると決心、「笑点」出演で一躍人気者になるとともに、古典落語の掘り起こしに取り組み続けた生涯をたどる、粋なひとり語り。持ちネタの舞台裏を語る「あたしのネタ帳」と口演速記『ねずみ』も収録。『恩返し 不死鳥ひとり語り』を改題。
-
3.0好き嫌いがキッパリ分かれるパクチーの爆発的なブームとともに、 いま日本には第二のアジア飯ブームが到来している。 ガパオ、パッタイ、カオマンガイ……。 いつから日本人はこれほどまでにスパイスとハーブの香りの虜になったのか。 『Hanako』『きょうの料理』『オレンジページ』『dancyu』など時代を鮮やかに映しだしてきた雑誌や、アジアを舞台にした映画、小説、日本に急増する移民が広めた食文化を丹念に紐解きながら、日本人をとりこにしたパクチーとアジア飯の喜びの謎に迫る。 のびゆくアジア、どこか懐かしいアジアを愛し、旅し、食べ歩いている すべてのニッポンの女子に贈る。アジア飯の魅力の源泉をさぐる一冊。
-
4.5ニューヨークの古書店で『源氏物語』に魅了されて以来、日本の文化を追究しているキーンさん。法話や執筆によって日本を鼓舞しつづけている瀬戸内さん。日本の美や文学に造詣の深い二人が、今こそ「日本の心」について熱く語り合う。 世界中で日本の古典が愛読されている理由、親交のあった文豪たちとの貴重な思い出、戦争や震災後の日本への思い、そして、時代の中で変わっていく言葉、変わらない心……。 ともに96歳、いつまでも夢と希望を忘れない偉人たちからのメッセージがつまった“日本への贈り物”対論集。 ◆瀬戸内寂聴 1922年、徳島県生まれ。東京女子大学卒業。63年「夏の終り」で女流文学賞受賞。73年、中尊寺にて得度。92年『花に問え』で谷崎潤一郎賞、96年『白道』で芸術選奨文部大臣賞、2001年『場所』で野間文芸賞、11年『風景』で泉鏡花文学賞を受賞。06年に文化勲章受章。『美は乱調にあり』『現代語訳源氏物語』『秘花』『奇縁まんだら』など著訳書多数。徳島県立文学書道館館長、宇治市源氏物語ミュージアム名誉館長。近著に『いのち』『句集 ひとり』など。 ◆ドナルド・キーン 1922年、アメリカ・ニューヨーク生まれ。日本文学研究者。コロンビア大学、同大学院、ハーバード大学、ケンブリッジ大学を経て、53年に京都大学大学院に留学。コロンビア大学名誉教授、アメリカン・アカデミー会員、日本学士院客員。菊池寛賞、読売文学賞、毎日出版文化賞など受賞多数。2008年文化勲章受章。2012年日本国籍取得。主な著書に『日本人の西洋発見』『日本との出会い』『百代の過客』『日本文学史』『明治天皇』『ドナルド・キーン自伝』など。近著に評伝『石川啄木』がある。
-
4.0あなたの運命は選んだ楽器が決めていた! まさかと思ったホルン奏者のあなたは山奥育ちですね。チェロを始めたあなたは、最近お人好しになっていませんか。楽器と性格の関係を、N響首席オーボエ奏者が爆笑的にプロファイリングする禁断の音楽書。演奏者必携の名著を大幅リニューアル。指揮者、ソリスト、声楽家などを考察した「オーケストラ周辺の人々学」、「アマチュア・オーケストラ専門用語集」などを増補した決定版。 〈巻末マンガ〉二ノ宮知子
-
4.5太宰治から「会ってくれなければ自殺する」という手紙を受けとってから、師として友として、親しくつきあってきた井伏鱒二。井伏による、二十年ちかくにわたる交遊の思い出や、太宰の作品解説を精選集成。「あとがき」を小沼丹が寄せる。中公文庫版では井伏の没後に節代夫人が語った「太宰さんのこと」を増補。 目 次 I 太宰治の死 亡 友――鎌滝のころ 十年前頃――太宰治に関する雑用事 点 滴 おんなごころ 太宰治のこと 太宰と料亭「おもだか屋」 琴の記 太宰治と文治さん II あの頃の太宰君 「ダス・ゲマイネ」の頃 御坂峠にいた頃のこと 「懶惰の歌留多」について 余 談 戦争初期の頃 甲府にいた頃 報告的雑記 太宰君の仕事部屋 御坂峠の碑 蟹田の碑 III あとがき〔『富嶽百景・走れメロス』〕 解 説〔『太宰治集上』 あとがき(小沼丹) 太宰さんのこと(井伏節代)
-
-ルトワック、クレフェルトと並ぶ現代三大戦略思想家の主著、待望の全訳 古今東西の戦争と戦略論を検証しつつ、陸・海・空・宇宙・サイバー空間を俯瞰しながら、戦争の本質や戦略の普遍性について論じる イントロダクション 拡大し続ける戦略の宇宙 第一章 戦略の次元 第二章 戦略、政治、倫理 第三章 戦略家の道具:クラウゼヴィッツの遺産 第四章 現代の戦略思想の貧困さ 第五章 コンテクストとしての戦略文化 第六章 戦争の「窓」 第七章 戦略経験に見られるパターン 第八章 戦略の文法 その一:陸と海 第九章 戦略の文法その2:空、宇宙、そして電子 第一〇章 小規模戦争とその他の野蛮な暴力 第一一章 核兵器を再び考える 第一二章 戦略史における核兵器 第一三章 永遠なる戦略 現代の戦略MODERN STRATEGY
-
3.6【目次】 ●プロローグ 人生は後半戦が勝負 経済的な余裕だけでは足りない/終わりよければすべてよし……ほか ●第1章 全員が合格点 定年退職日は一大イベント/定年退職か、雇用延長か/隠居と定年の相違点……ほか ●第2章 イキイキした人は2割未満? 名前を呼ばれるのは病院だけ/クレーマーは元管理職が多い?/米国の定年退職者も大変……ほか ●第3章 亭主元気で留守がいい 日本人男性は世界一孤独?/名刺の重み/主人在宅ストレス症候群……ほか ●第4章 「黄金の15年」を輝かせるために 会社員人生の2つの通過儀礼/8万時間の自由、不自由/一区切りつくまで3年……ほか ●第5章 社会とどうつながるか ハローワークで相談すると/得意なことに軸足を移す/100歳を越えても現役……ほか ●第6章 居場所を探す 自ら会合を立ち上げる/同窓会の効用/家族はつらいよ?……ほか ●第7章 「死」から逆算してみる お金だけでは解決できない/死者を想うエネルギー/「良い顔」で死ぬために生きている……ほか
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 25万部突破のベストセラー新書『定年後』、待望のまんが化! 自営業などを除けば誰もがいつか迎える定年。シニア社員、定年退職者などさまざまな人たちへの取材で、定年後の「現実」を明らかにした著者監修のもと、人生の後半戦を真に豊かに生きるための「黄金の7法則」を伝授します。 まんがを読むだけで、名著『定年後』のエッセンスが身につきます。 <あらすじ> 大手商社に勤める進一(40歳)は、日々真面目に仕事をこなしていた。 ある日、会社の辞令で子会社に出向することに。 自分が中軸から外されたことにとまどいを隠せない進一。 そんな中、大学時代の先輩で今はフリーカウンセラーとして 活躍する奈々と出会い、悩みを打ち明ける。 奈々から「人生の後半戦を幸せにする方法」を教えてもらうことで、 日々の生活を見直し、好転させていくストーリー。
-
3.716歳でデビューしたバンドは4年で解散。天国から一転、堕ちた地獄から、ノーギャラライブや15年に亘るアルバイト生活を経て、今頂に立つ、アニソン界のパイオニア・影山ヒロノブ。苦難の先で出会った「聖闘士神話~ソルジャー・ドリーム~」「CHA-LA HEAD-CHA-LA」、アニソンレジェンドたち、そしてJAM Project。なぜ諦めなかったのか? なぜファンは、そして世界は彼を愛するのか? だからもっと熱くなれ! その手で夢をつかみとれ!
-
4.0「諦めきれぬをどうあきらめた 諦めきれぬとあきらめた」──人の心のありようをうたった都々逸から、「箪笥屋は離れ座敷を嫁の部屋」など、ちょっとエロティックな川柳、破礼句(ばれく)、「世の中ね顔かお金かなのよ」といった回文まで、三五〇余りの句や歌を通して、日本人の心の機微、男女の情愛や性愛の世界を読み解くエッセイ集。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『中央公論』12月号に毎年収録している総目次のうち2013~2017年の5年分をまとめてデジタル化。特集はもちろん、連載小説、連載コラム、カラーグラビアなどの見出し、著者名が一目瞭然。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 落語家立川吉笑が雑誌『中央公論』に連載中の人気コラムをまとめた電子書籍。各回タイトル:(1)芸名変更ニモマケズ(2)明日は昨日の風が吹く(3)SMAPこわい(4)疑わしきは、我にあり?(5)散り際は、潔くなく(6)“ベタ”力(7)コンプライアンスの功名(8)アラ出汁はいつでも美味い(9)応援してしまう夏(10)不倫よりも抜きたいスクープ(11)お金の重み(12)人気稼業は大変だ。
-
3.4人は食べなければ生きていくことはできない。人類の歴史は、糖質とタンパク質のセットをどうやって確保するかという闘いだった。今では、西洋では「小麦とミルク」、東洋では「コメと魚」のセットとして摂取されることが多いが、山菜を多食し、採集文化が色濃く残る日本のように、食の営みは多様である。本書は、ユーラシア全土で繰り広げられてきた、さまざまな生業の変遷と集団間の駆け引きを巨細に解読する。
-
3.7世界が認める巨匠がおくる7つの幸福論。ネットが隆盛し、フェイクニュースが世界を覆う時代、何が虚構で何が真実か、その境界線は曖昧である。こういう時代だからこそ、与えられた情報をひとまず信じずに、自らの頭で考えることの重要さを著者は説く。幸せになるために成すべきこと、社会の中でポジションを得て生き抜く方法、現代日本が抱える問題についても論じた、押井哲学の集大成とも言える一冊。
-
4.2不思議な学生寮「ともきんす」に暮らす〈科学する人たち〉朝永振一郎、牧野富太郎、中谷宇吉郎、湯川秀樹……彼らが遺した文章と一組の母娘の出会いを描く、高野文子11年ぶりの新作コミック。
-
3.3悪用禁止! タックスヘイブンだけじゃない。なぜ「金(ゴールド)」を買うのか? なぜ高層階に住むのか? 租税回避商品とは? 相続の裏技とは? プライベート・カンパニーとは何か? 税務署も気づいていない裏技のカラクリ。累計46万部突破「元国税調査官の裏情報シリーズ」最新刊。
-
-夏目漱石『三四郎』冒頭の名古屋駅、「勝負に打って出る玄関の駅」と言った升田幸三の大阪駅、出征・帰還の軍用列車が発着した品川駅……。明治初年の岩倉使節団で久米邦武が見出したように、「駅」は近代文明の本質を表わす場となった。大衆化・大量化する鉄道とともに変貌していく駅の姿を辿り、鉄道史から近代をとらえ直す。 〈解説〉老川慶喜
-
4.0李光洙は韓国の夏目漱石である。近代文学の祖とされ、知らぬ者はいない。韓国併合前後に明治学院、早大で学び、文筆活動を始めた李は、3・1独立運動に積極関与するが挫折。『東亜日報』編集局長などを務め、多くの小説を著した。だが日中戦争下、治安維持法で逮捕。以後「香山光郎」と創氏改名し日本語小説を発表。終戦後は、「親日」と糾弾を受け、朝鮮戦争で北に連行され消息を絶つ。本書は、過去の日本を見つめつつ、彼の生涯を辿る。
-
3.5知りたい? 知りたくない?ほんとうの素顔。元メイドがお店の舞台裏や、「ご主人様」の実態を衝撃レポート! 老人から「男の娘」まで、あらゆる職種・性癖が集う秋葉原には、危険も少なくない。この街で繰り広げられる過酷な生き残り競争から、リフレ、JKビジネスなど次々生まれる新業態。過激化する「裏オプション」。セクハラ、ストーカー被害と背中合わせでも、「癒し」を与え続ける彼女たちは何を思うのか。
-
3.8人生で最も有意義なスキル、それが「同性にモテる技術」だ! 1万人を対象に調査した結果、「人間関係の能力」こそが成功するかどうかの85%を決定付けていたという(本文より)。この本ではその技術を徹底指導。あなたの同性モテを実現する。想像して欲しい、上司や後輩からは慕われ、ご近所さんからチヤホヤされるところを。「人付き合いが苦手」な人こそこの本を読もう。同性にモテるだけで、あなたの人生はバラ色に輝くのだから!
-
-卓抜な着想。緻密な論理。大胆な展開。地球時代の日本が生んだ独創的思想家の知的構築。 <目次> 探検隊の見習士官/山と旅/探検の時代/探検記をよむ
-
-草津では小林一茶が江戸との往復時にたちより、俳句を詠んだ。一茶自身湯治が好きで覚え書きや感想を残している。また熱海を訪れた中級武士たちは新鮮な海の幸に感激してグルメ三昧、弁当を持って寺社詣でに出かけた。道後・有馬などの大歓楽地では、小金のある連中が名産・名物を買い漁り……。古代の湯浴みに始まり、江戸期に急速に広がった温泉文化の有り様や魅力を語る。
-
3.719世紀半ば、日本へ輸入された写真。日露戦争を経て新聞・出版メディアが拡大するなか報道写真が成長。第二次世界大戦時にはプロパガンダに利用され、また敗戦直後には「マッカーサーと天皇」の写真のように、社会に大きな影響力を持つようになった。戦後は戦禍や公害問題を追及するリアリズム写真が隆盛を誇ったが、経済成長とともに私的テーマ、広告へと多彩化する。本書は1974年まで120年に及ぶ歴史を描く。
-
-江戸庶民のほとんどが住んでいた長屋。大家は親も同然といわれ、入居希望者の人柄の見極めに始まり、夫婦喧嘩の仲裁冠婚葬祭の仕切りまで、店子たちの世話を焼いていた。一方、店子は年に一度の井戸浚いや、煤払いなど、季節の行事の取り決めを守りつつ貧しくも長閑に暮らしていた。そんな江戸っ子の日常を小咄、落語に絡めて活写する一冊。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 誕生日をズバリ的中させる速算術、賭けゲームの必勝法…マジックの背景には算数があった! 数の面白さと奥深さ、美しさに満ちた、古今の名作マジック&パズルから厳選。コイン、電卓、トランプなど身近な小道具で、いつでもどこででも。手順、演じ方のポイントは初心者向けに写真・イラスト付きで解説。子供の探求心をくすぐるきっかけを、お父さんの手で! 酒席にも使えます。
-
3.0大リーグでの日本人選手の活躍、WBCでの連続優勝…。日本の野球は世界の頂点を極めつつあるように見える。ただ、その歴史に暗黒の時代が刻まれていることを知る人は少ない。昭和七年、学業軽視、選手獲得に金銭が動くことを懸念した文部省は「野球統制令」を公布。さらに、泥沼化する戦況のもと、野球部排撃の動きが全国に広がった。粛正、弾圧を潜り抜け、物資窮乏の中、焦土の上に復活する苦難の日々を史料と証言で辿る。
-
4.0フランスが世界に誇る「花の都」パリ、そしてヴェルサイユ宮殿。これらを形作ったのは、ルイ十四世の治世に花開いた「グランド・デザイン」の思想だった。当時のフランスは、世界を席巻していたバロックに背を向け、徹底した計画志向の下でニュータウンを建設し、パリの街並みを整備し、ついにはヴェルサイユ宮殿を造営した。駆け引きに満ちた宮廷政治と、個性豊かな建築家たちの物語を通して、近代都市の源流に迫る。
-
4.0ハーフは皆「かわいい」「バイリンガル」「お金持ち」と思っているあなた。それは妄想です。実際には、不美人・日本語しか話せない・貧乏なハーフも大勢いる。日・独ハーフ(三十路、独身)が、日本社会でハーフが巻き込まれる「怒るに怒れない話」を多数挙げ、おもしろおかしく、時に真面目に「純ジャパ」との共生を考える。
-
3.0アントニ・ガウディが活躍した十九世紀のバルセロナとはどんな都市だったのか。奴隷貿易が生んだ「黒い金」を元手にガウディのパトロンとなった新興富裕層、チャンスをもたらした建築ラッシュ、経済力が生んだナショナリズムと独自文化の再評価…これらのどれ一つが欠けてもガウディの建築群は誕生しなかった。知られざる作品も紹介しながら、その異能がどのように誕生し、発揮されていったかを、同時代史の中に位置づける。
-
3.7カカオは原産地の中米では飲み物であると同時に薬品であり、貨幣にもなった。ヨーロッパに到来したときも、この珍貴な実の食用について激論が交わされたが、一九世紀にはココアパウダーや固形チョコレートが発明・改良され、爆発的に普及する。イギリスの小さな食料品店だったロウントリー家もまた、近代的なチョコレート工場を作り、キットカットを開発、世界に販路を拡大するが…。ヨーロッパ近代を支えたお菓子の通史。
-
3.5毒にしても薬にしても、人類との関わりは、きわめて長く深い。古くから人類は毒を避け、効能のある物質は活用してきた。そして、それらを合成することが可能になってからは、良きにつけ悪しきにつけ、その使用法は無限に拡大している。しかし、実は、同じものが毒にもなれば薬にもなる。本書は、ソクラテスの飲まされた毒から、錬金術、ドーピングにいたるまで、古今東西の毒や薬をめぐる秘話・逸話を紹介するものである。
-
3.7南米生まれのジャガイモは、インカ帝国滅亡のころ、スペインに渡った。その後、フランスやドイツの啓蒙君主たちも普及につとめ、わずか五百年の間に全世界に広がった。赤道直下から北極圏まで、これほど各地で栽培されている食物もない。痩せた土地でも育ち、栄養価の高いジャガイモは「貧者のパン」として歴史の転機で大きな役割を演じた。アイルランドの大飢饉、北海道開拓、ソ連崩壊まで、ジャガイモと人々をめぐるドラマ。
-
4.4映画はいったいどこで見るべきものなのだろうか。ホームヴィデオの普及以降一般的になった、個人的な鑑賞は、はたして映画の本来的な姿から遠ざかってしまったものなのだろうか。本書は、黎明期から今日までの一一〇年間の上映形態を入念にたどりながら、映画の見かたが、じつは本来、きわめて多様なものだったことを明らかにする。作品論、監督論、俳優論からは到達し得ない映画の本質に迫る試みである。
-
3.8長く人類はまずいものを繰り返し食べてきた。「美味しいものをお腹いっぱい食べたい」という欲求が強いのも無理はない。美味、珍味の探求は世界の人々の日常行為となっており、たべものへの関心は高まり続けている。本書は、食材、調理法、食事のしきたり、さらに各地各時代の食文化などを広く紹介するものである。味覚の満足、心躍る会食、そして健康増進のために、たべものについての正確な知識は欠かせない。図版多数。
-
4.1馬は、人間社会のなかで、多種多様な役割を担わされてきた。太古には狩猟の対象になり、やがて車を引き、人を乗せ、人間の世界に深く入りこんだ。人が馬を乗りこなさなかったら、歴史はもっと緩やかに流れていただろう。戦争、交易、世界帝国……、馬から歴史を捉え直す。JRA賞馬事文化賞受賞作
-
4.2魔女裁判は近代の夜明けである16―17世紀、ヨーロッパ各地を吹き荒れ、多数の人々を無実の罪で処刑した。その背後にはヨーロッパに根強い魔女信仰があった。愛する子どもの死、インポテンツや作物の不作といった身の回りの不幸や不安を魔女のせいにするという、呪術的思考の存在は、科学的知識がいきわたった現代社会とも無関係ではない。本書は英語圏の魔女幻想を中心に、歴史上の事実と文化的なうねりをエピソード豊かに検証する。
-
3.6地政学的にもイデオロギー的にも揺るぎない超大国アメリカ。しかし、イラク攻撃の口実だった大量破壊兵器は存在しないことが確実、パレスチナ問題での露骨なイスラエル寄りの政策など、傲慢で独善的な外交姿勢は国際社会の批判の的となっている。同時にアメリカは内政でも、深刻な人種差別、異様な銃社会、肥満大国など数多くの問題を抱えている。アメリカの病根は深い。内憂外患の唯一の超大国を揶揄した傑作ジョークに的確な解説を交えて「病めるアメリカ」の核心を衝く。
-
3.6紛争、圧政、貧困の地で生まれる無数の悲劇。そこで民衆の心を絶望、怒り、憎しみから解放してきたのは、笑いだった。援助物資や深遠な哲学よりも、一つのジョークの方が民衆の力になることがある。決して誇張ではなく、笑いには世界を救い、戦争にも独裁にも負けない強靭な精神を養う力がある。本書には、イラク、パレスチナ、北朝鮮を始めとする、逆境下の民衆が生み出した秀逸なジョークを多数収録した。もちろん日本人のストレス解消にも役立つ。
-
3.8今こそ平成の笑いの力を! 腹の底から笑って、不安な気持ちを吹き飛ばそう。累計100万部突破のジョーク・シリーズ。6冊の中から、珠玉のジョークをセレクト。笑いは社会の潤滑油となり、生きる力となる。「変に難しい理屈の本よりも、明るさがあって素直に心に届くようなものを今は読みたい」という読者の声から生まれた一冊。「〈笑い〉こそが、人類が絶望の歴史の末に見出した、最大の生きる術なのだ」(おわりに)
-
3.5世界から憧憬の眼差しが注がれる経済大国? それとも、物真似上手のエコノミック・アニマル? 地球各地で収集したジョークの数々を紹介しながら、適材適所に付された解説により、異国から見た真の日本人像を描き出していきます。『世界の紛争地ジョーク集』『世界反米ジョーク集』に続く、同著者入魂の第三弾は、読者からも問い合わせの多かった「日本人をネタにしたもの」を満載しました。笑って知って、また笑う。一冊で二度おいしい本の誕生です。知的なスパイスの効いた爆笑ネタを、ぜひご賞味あれ!
-
4.0シャン=ゼリゼあるいはプルースト、パレ=ロワイヤルあるいはバルザック、モンパルナスあるいはボーヴォワール……24の名所・旧跡と24人の文学者をつないで描く、パリの文学的トポグラフィ。文学のエピソードから新しいパリが見つかる、鹿島流パリの歩き方。
-
3.0『東京物語』を初めて見た著者は、紀子役を演じた原節子に魅せられる。『晩春』『麦秋』を含めた紀子三部作を中心に、彼女が主演した戦後映画十一本を精細に論じて、「クリエイティブな能力を無限に持った」原節子の魅力と、それを引き出した小津安二郎監督の卓越した演出を分析した異色の映画論。
-
4.0欧米人は、なぜ動物をと畜して食う一方、動物を愛護するのか? 本書は、ヨーロッパ思想の原型を、歴史的・地理的条件に由来する食生活の伝統に求め、それに基づき形成された思想的伝統を明らかにし、日本とも比較しながら平易に説く。食という新しい視点で西洋の歴史を見直す、西洋史学究の問題作。
-
4.0家族、食生活、ファッションと美容、教育、政治・経済、習慣といまどき事情、男と女の恋模様などの不思議を、古代ローマから現代までの格言・諺を紹介しながら解き明かす。
-
3.0前の副将軍水戸光圀――日本人なら誰しらぬものもない史実と巷説に縁どられたこの人物の生きた時代は、泰平の世を謳歌する町人文化が華麗繚乱に絢を競ったときであった。なかでも食の世界は象徴的な展開をみせ、その奔流はあらゆる階層の人々を巻き込んでいく。光圀とても例外ではない。起伏に富んだ生涯のなかで、こよなく酒を愛し、味覚へのこだわりさえ感じさせる光圀の日々の暮らしは、近世食文化の黎明を如実に物語っている。
-
3.7一九六〇年代に、新劇を否定するかたちで現れた小劇場運動があったか、その後、つかこうへいを嚆矢として奔出した新しい小劇場運動は、より多くの若い観衆に熱狂的に迎えられ、それらは社会現象としても大きな動きとなった。そして今や、そうした小劇場出身者が商業演劇や、映画、TVへと進出している。本書は、つかこうへい、野田秀樹、鴻上尚史の三人を中心に、七〇年代から八〇年代にかけての演劇とは何だったのかを探る。
-
3.8日本人のイスラム観はかなり偏っている。礼拝、ラマダン、一夫多妻制……。最近ではそれにテロが加わり、「恐い」というイメージも定着しつつある。本書においてはそれら「イスラムに対する偏見」を取り除くために、彼らが大好きなジョークを通じてイスラムの日常生活を紹介した。
-
3.0草の根交流から国家的プロジェクトまで、様々な分野で国際交流が広がっている。しかし明治以来続いてきた、「先進国」を上「途上国」を下と見る価値観に基づく「差別型交流」は跡を絶たない。文化はそれぞれの国に固有の価値観に根ざした体系であり、相対的なものである。無意識にまで染み透った西洋文化至上主義を脱却し、文化相対主義に基づく「誠実型交流」を進めるために今なにをなすべきか。世界文化への貢献を展望する、現場からの提言。
-
-一八五一年の第一回ロンドン万博を契機に、十九世紀後半は、ヨーロッパで空前の日本ブームが沸き起こった。時を同じくしてアメリカでも同様の流行を見るが、その場合、際立っていたのは、日本趣味の及んだ範囲が、美術や文学といったハイ・カルチャーにとどまらず、服飾、造園、装飾品といった生活に密着した品々にも広がったことである。本書は多岐に亘る実例を示して、短いながらも広く深かった日本趣味流行の軌跡を辿るものである。
-
-日中双方のふところの中で育ち、自ら現地を視察し事業展開する著者が、繁栄に向けて離陸した中国の知られざる素顔と、両国人の気質の差異を実務・文化の両面からわかりやすく解説する。アジアの時代をむかえた今、巨大な隣国とどうつきあうか……。
-
4.1バーの重い扉の向こうには、非日常の空間が待っている。そこは、酒だけを売っている場所ではない。客のひとりひとりが、バーテンダーと対面し、一期一会の時間を購い、空間に戯れる町の“秘境”である。そこには、シキタリもあれば、オキテもある。しかしそれらは、居心地をよくするものでこそあれ、がんじがらめの規則ではない。これから出かける人の背中をそっと押し、行き慣れた人をさらなる一軒へ向かわせる、体験的バー案内。
-
3.3ヴィクトリア文化は性を抑圧する文化であり、性に対するとりすました淑女ぶり、お上品主義である――このような考え方は、今世紀のみならず、当時からすでにあった。「中流階級の女たちは不感症に育てられる」「娼婦に落ちたら死ぬまで娼婦」「避妊を知らない」「未婚の母は召使に多い」など、本書は現在まで多くの人が受け入れている「神話」を26とりあげ、その虚構性を当時の日記や書簡、新聞の投書や漫画などの資料を通して検証する。
-
-豊かな国オーストラリアに、迫害を受けつづけてきている先住民、アボリジニーがいる。日本人では初めて、彼らに友人として受けいれられた著者は、五百以上の部族、三百以上の言語をもつアボリジニーの内奥に入りこんで調査を続けてきた。最下層にあえぐ都市のアボリジニー、地方で酒を追放して繁栄するセツルメント、日本人との交流。複合民族国家の中で、伝統文化の復興をはかりつつ共存と自立をめざすアボリジニーの実態を紹介する。
-
3.8父の役割は家族を統合し、理念を掲げ、文化を伝え、社会のルールを教えることにある。この役割が失われると子どもは判断の基準、行動の原理を身につける機会を逸してしまう。いじめや不登校が起こり、利己的な人間、無気力な人間が増えるのもこの延長線上にある。独善的な権威を持って君臨する家父長ではなく、健全な権威を備えた父が必要だ。父性の誕生とその役割を家族の発生と社会の形成との関連から検証し、父性の条件を探る。
-
-江戸前鮨が今のような姿を取り始めたのはいつ頃のことなのか? 大阪と江戸前の鮨の違いは? すし屋でのマナーとは? 私たちの風土と文化が育てた日本人のもっとも愛す鮨の素顔に迫る一冊。すし業界に長く関わってきた著者ならではの視点で鮨の歴史と食文化を辿る。『小僧の神様』の屋台の鮨から現在のあの名店の握り鮨まで、食べて美味しく読んで楽しいすしの世界と歴史。元来、庶民の食べ物であったすしの魅力を、その誕生に遡りながら、なぜすしが人々に愛されてやまないかを豊富な写真を交えながら解説した。
-
4.5日本人の美的世界・倫理的世界を善意な眼差しで概観しながらも、「慇懃と粗暴」「礼儀正しさとモラル破壊」「思慮深さと見栄っ張り」「同情心と冷淡」「慎み深さと思い上がり」といった相反する要素が両立する謎について、言語・風土・社会的要因から解明する。一九七〇年代にベストセラーとなった稀有な日本人論を初文庫化。
-
3.8世の多くの人達は日常を退屈と見なし、さまざまな形でロマンティックな世界に憧憬を抱く。ところがここにロマン主義の弱点を見抜き、持前の機智とユーモアと皮肉と諷刺で平凡な日常を非凡な喜劇的世界に転じた作家がいる。漱石が「平凡の大功徳」を心得た写実の大家と絶讃し、山本健吉が「世界で一番平凡な大作家の一人」と評した、英国の天才女流ユーモリスト、ジェイン・オースティンである。その生涯と作品の全貌を描く。
-
-どじょう、牛鍋、すし、和菓子……日本の食文化を支えてきた職人が守ってきた道とは何か。風土に根付く食文化に、いろいろな角度から迫る、食の職人の世界。
-
3.7幽冥界には妖しい力があって絶えず人間界に災厄を加えんと恐ろしい糸を操っている…そう信じて、鬼に食われ、狐狸に誑かされ、幽霊に悩まされてきた日本人。多くの文献から収集した記事をもとに、妖怪変化の正体を多面的に明らかにし、古来の風俗に人間の妄執の移り変わりを見る。大正十二年に発表された表題論文ほか、「文芸上に表われたる鬼」「火の玉」を収録。中公文庫版に図版を追加し、本文の補訂をおこなった新版。
-
-「なまめける歌舞妓びとすら ころされて、いよ 敗れし悔いぞ 身に沁む」(昭和二十一年)と詠んだ折口信夫は、戦中から戦後、歌舞伎について度々論ずるようになる。防空壕の中で死んだ中村魁車、上方歌舞伎の美の結晶実川延若、そして六代目尾上菊五郎。役者論を軸に、豊穣な知とするどい感性で生き生きと描く独特な劇評集。
-
-活気あふれる明治から大正へ三十余年、新聞人のとらえた庶民の文化と世相の歩み。下町の風俗文化、演芸娯楽に名物、書画骨董、もろもろ見聞の宝庫。
-
3.0ありもしない怪異がなぜ起り、居もしない幽霊がなぜ出没するのか。昔なつかしいお化けのエピソードも豊かな民俗学者の幽霊研究。〈解説〉矢代静一
-
3.6「花鳥風月」に代表される日本文化の重要な十のキーワードをとりあげ、歴史・文学・科学などさまざまな角度から分析、その底流にひそむ「日本的なるもの」の姿を抉出させる。著者一流の切り口が冴えわたる、卓抜の日本文化論。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。