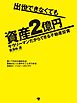所得作品一覧
-
4.0
-
5.0効かない景気対策、積み上がる不良債権、人民元国際化をめぐる矛盾……。中国経済に何が起きている? これからどうなる? 新興国ブームの終焉を予言したエコノミストが冷徹に読み解く! 長年、危ぶまれてきた「中国経済崩壊」は、いまや議論の前提となったようにも思える。いったい中国経済はここから「どこまで悪化していく」のか。しかし、信頼できる数字が表に出てこないなかで、その行方を予測するのは簡単ではない。本書では、近代経済学の知見を有し、歴史にも精通した気鋭のエコノミストが、数々のマクロ指標、中国人の経済観、アメリカなど他国の政策動向も踏まえつつ、中国経済の現在と未来を徹底分析。その先にあるのは長期停滞か、ハードランディングか、それとも体制崩壊か? さらには中国がほんとうに「バブルリレー」の最終走者であり、そこでバトンが途切れたとき、日本・世界経済の命運はどうなるのか? ヒステリックな「崩壊論」でも無条件の「礼賛論」でもない、いま日本人がどうしても知っておかねばならない、中国経済の真実。内容例:リレーに譬えられる「バブルの発生と崩壊」のサイクル/中国はいま「中所得国の罠」にはまるかどうかの瀬戸際/中国はアンカーか、次の走者にバトンを渡すのか/金融緩和を講じつつ、人民元買い支えを行なう矛盾/「ゴーストタウン」のような不良債権はどれだけあるのか/場合によってはマイナス成長に陥る可能性も/財政出動は機能しないどころか、無駄に終わる ……ほか。
-
3.6
-
4.8
-
3.7
-
4.4夢の不労所得を手にするため0歳児は立ち上がる――!!!! 辺境の新生児セフィリアは、 前世で過労死したOLプログラマー。 今世では絶対に同じ轍は踏まず、 楽してお金を稼ぎたい……!! そんな強固な信念を胸に、 前世の知識を活かした魔法を編み出すことに成功! 絶対に働きたくない乳児の ドキドキ異世界ライフ、開幕♪ ★単行本カバー下画像収録★
-
3.5持てる国が停滞し、持たざる国が発展しつつあるという今日の世界経済の流れのなかで、我々はグローバルビジネスをどう捉え、どう実践していけばよいのだろうか。日本人の多くは誤解している。現代のグローバルビジネスは、もはや先進国のマルチナショナルなビジネス(≒多国籍企業)を意味するものではなく、従来は経済活動の主体となりえなかったBOP層(年間所得3,000ドル未満の途上国の低所得者層)をも含む、新たな広域分業のステージに突入しているのである。いまやグローバルビジネスは、マクロとミクロの社会的文脈のなかで理解しなければならなくなったのだ。そこで、日本が否応なく巻き込まれていくグローバル化の流れとその本質を、豊富な事例や体験談を交えながら、歴史的経緯、構造論、制度論、社会インフラおよび最新の経営課題(イノベーションやCSRなど)を踏まえつつ、多角的な視点から包括的に考察する。
-
3.8
-
3.6
-
4.9シリーズ累計10万部突破のベストセラーが待望の文庫化!! 人気YouTubeチャンネル「学識サロン」激賞! ごく普通の青年が体験した成"幸"の物語、『CHANCE』から2年......。 人生の師に学び、成功者の入り口に立ったあの日から6年後、主人公の卓也は信じていたビジネスパートナーからの予期せぬ裏切りに遭う。 傷ついた卓也に手を差し伸べてきたのは2人のメンター。1人は優れたバランス感覚で「不労所得」を築く方法を教える師。もう1人は圧倒的なビジネスセンスでお金を生み出す方法を教える師。 卓也は2人に学びながら、ビジネスと資産形成を両立させていく。しかし、待ち受けていたものは衝撃的な出来事だった。 圧倒的な感動と不思議な安らぎに包まれる、作者自身の体験をもとに描く「成功者シリーズ」の第2弾!!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 所得も年金受給額も減っている、混乱の時代で 巷にはお金にまつわる本や雑誌、番組があふれています。 「とにかく節約!」「支出を減らそう!」「まだまだ削れる!」 確かに支出を減らすのは大事。 特に、一度見直せば効果が長続きする固定費カットは貯蓄の第一歩です。 でも、無理して削ることばかりを考えていると心が疲れて、頑張れなくなることも。 そんなときに読んで欲しいのがocanemoです! 本書は1冊で今、大事なお金のトピックを抑えつつ 家計を整え、貯まる・増える仕組みづくりができるところまでナビゲート。 それは、削ってばかりの苦しい世界とは違って 収支をコントロールしているという満足感を持ったうえでお金を使うことを楽しめる状態です。 テストする女性誌『LDK』から生まれた ホントに使えるお金の本 第7弾!
-
3.4
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※THE21電子版は、紙の雑誌とは一部内容が異なります。表紙・目次に書かれていても、収録されていないページや記事、写真などがあります。あらかじめご了承ください。】年金支給開始年齢の引き上げにともない、60歳以降も働き続ける人が増えています。一方で、60代以降はお金のために働くのではなく、好きなことに時間を使いたいという人も少なくありません。そこで、60歳前後までに「仕事を辞めても困らない経済的自由」を手にする方法を、お金のプロに取材しました。 【目次より】●総力特集:普通のサラリーマンが60歳までに「お金の自由」を手に入れる方法 〈第1部〉60歳でお金の不安なくリタイアできる資産形成術 〈第2部〉お金が自動的に入ってくる!「高配当株投資&不労所得」入門 〈第3部〉「不動産投資」の失敗しない堅実な始め方
-
3.3
-
3.7
-
-書籍説明文 本書は以下のような方々のために書きました。 ・稼いでもお金が手元に残らない。 ・社会保険料の負担が大きい。 ・もっと節税できるのではないか? ・なにか手取りを増やす方法はないのか? ・増やしたお金を守りたい、家族に残したい。 社長には守るべきものがたくさんあります。 愛するご家族はもちろん、社員様、お客様にお取引先、背負うものは一般のサラリーマンの比ではありません。 それらの方々をお守りするには、きれいごと抜きでお金が必要です。 社長がお金を増やして貯めておくことは、会社の財務戦略と一体で、ある意味「義務」といっても過言ではないのです(公私混同という意味ではありません)。 そんな社長のお役に少しでも立てればと、本書を執筆させていただきました。 この本は、金融知識の解説本でもなければ、株やFX、仮想通貨のような増えるかどうかわかならい投資ノウハウでもありません。 実際にお金を増やして守る実践的ノウハウです。 わかりやすいように、本書は4つのテーマに分けて構成しております。 ・第一章 お金を増やす方法 具体的には、役員報酬の見直しです。役員報酬とは別の受け取り方をし、節税と社会保険料削減を実現する方法です。「稼いでもお金が残らない」悩みの解決策です。 ・第二章 お金の運用方法 そのお金をさらに増やすための運用方法について解説します。投資でお金を増やす鉄板ルールです。 ・第三章 社長個人へお金を移す方法 節税で会社に残したお金を社長個人へ移す方法です。これを知らないと、移転時に高い税率で課税されてしまいます。 節税と個人への所得移転方法はセットとお考え下さい。 ・第四章 増やしたお金を守る方法 節税だけでは不十分です。 苦労して増やしたお金も、そのままにしておけば相続税をドカンと課税されます。 社長の財産を守るには、相続税対策まで必要です。 本書の特徴はこれだけではありません。 実際に行動に移していただけるよう、最後にチェックリストも付けております。 本書を読んでいただけるとわかりますが、はじめるのは早ければ早いほど効果的です。 社長は何かと忙しいとは思いますが、どうぞこの機会に本書をご活用くださいませ。
-
4.0どう見たって……君は抱かれる方に向いてるだろう 資産、才能、容姿…すべてに恵まれている評論家・谷町胡太郎。9年間片想いしている先輩の駆け落ちと俺様議員秘書との出会いがセットで訪れて!? 親の遺産の不労所得で何ひとつ不自由ない生活環境を持ち、年に一冊本を書くことで人気評論家の身分を有する谷町胡太郎。だがその私生活は9年に及ぶ片想いと、肩書きばかりが立派な三人の居候に支配されていた。そんな胡太郎の運命の分かれ道、某日お台場のホテル――「誰ともつき合ったことがないって言うんじゃないだろうな?」弱点を抉る痛烈な一言を浴びせてきたのは、財務省の出世頭から議員秘書へ謎の転身を遂げ、官僚たちの間で伝説と化している男・小早川秀峰で……。
-
4.1
-
3.8
-
3.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 No.1経済誌「日経ビジネス」が2021年を徹底予測! アフターコロナの世界はどうなるのか? 2021年の展望を200ページ以上にわたって徹底予測する! 激変する世界の動きを米国、欧州、中国、日本の4賢人が先読み。 2021年の数々のイベントや企業の動きに関する詳細なスケジュールと注目の10大トピックスも紹介する。混迷の時代だからこそ、多様なシナリオを知っておくことが助けになる。 ビジネスパーソンの様々な疑問に答える2021年予測の決定版! 《主な内容》 ◆コロナ後の世界を読み解く 世界の4賢人 特別インタビュー 《米国》 イアン・ブレマー氏 [国際政治学者] 《欧州》 ビル・エモット氏 [国際ジャーナリスト] 《中国》 チョウ イーリン氏 [伊藤忠総研 主任研究員] 《日本》 榊原英資氏 [元財務官] ◆Part1 2021年は何がある? 2021年10大トピックス&スケジュール (1) 東京五輪・パラリンピックは開催できるか? (2) バイデン大統領就任で米国はどう変わるか (3) 新型コロナウイルスの感染拡大は止まるか (4) 中国共産党設立100周年 ほか ◆Part2 専門記者が総力取材!主要30業種予測 自動車 /電機 /自動車部品 /機械/精密機械 ほか ◆Part3 コロナ危機を乗り越える! 新時代テクノロジー ◆Part4 アフターコロナの世界をどう生きる? ・所得崩壊 年収2割減も現実に ・変われるか? 日本型雇用 働き方ニューノーマル ◆Part5 日本への提言 ・柳井 正氏 変わらねば日本は潰れる ・出口治明氏 学ばない大人が衰退招
-
3.5知りたい基本が一気にわかる。Q&A付で読みやすい。 この本を読めば、ピケティと『21世紀の資本』のポイントが60分でわかる! サブテキストとして最適の「超」入門書が、日本初登場! ピケティについて知りたい人、『21世紀の資本』を読みこなしたい人全員におすすめ! この1冊で、ざっと「基本」を身につけよう! 【第1章「ピケティQ&A」より】 Q すごい厚さですが、要するに何が書いてあるんですか? Q それだけのことに、なぜ700ページも必要なんですか? Q 19世紀の所得や資本をどうやって測定したんですか? Q その結果、どういうことがわかったんですか? Q この不等式はどういう意味ですか? Q 資本主義で格差はずっと拡大してきたんですか? Q 『21世紀の資本』の何が画期的だったんですか? Q こんな専門的な本が、どうしてアマゾン・ドットコムのベストセラー第1位になったんですか? Q ピケティってどういう人ですか? Q アカデミックな評価はどうなんですか? Qこの本はマルクスの『資本論』とはどういう関係があるんですか? Q 大学で学ぶ普通の経済学とまったく違う感じですが、どう理解すればいいんですか? Q ピケティはどういう政策を提言しているんですか? Q 日本とはどういう関係があるんですか? 【主な内容】 第1章 ピケティQ&A 第2章 ピケティをどう読むか 第3章 『21世紀の資本』の3つのポイント
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 月10万円稼げる「副業」ガイド 【目次抜粋】 PART1「貯める」編 1億円へのファーストステップは貯めることからスタート! お金、人付き合い、仕事……同じ年収で貯まらない人とはどう違う? 明日から実践! ミリオネア女性たちの小さな習慣 年収別1000人アンケート! コツコツ貯まる人vs.貯まらない人の意外な法則 人生100年時代の貯め方&増やし方 なぜ今、お金を増やすなら「積み立て」なの? これからはじめる人必見! 口座開設から商品選びまで全部解説 「つみたてNISA、iDeCo」スタートアップ 忙しくてもズボラでもほったらかしで「貯まる仕組み」をつくろう! 年収・役職・幸福度・部屋の片づけ……自然に貯まる人vs.貯まらない人「暮らしと幸せ」大分析! PART2「稼ぐ」編 人生100年時代、60歳、70歳でも稼ぐ力を身につけよう コロナショックで大転換の時代、しなやかに稼げる後半戦の準備を! 40代から考える、アラフィフからの「逆転キャリア」計画 緊急調査! 年収800万以上「稼ぐ女性」の仕事&お金&プライベートその1 キャリア&年収アップの軌跡から、資産ポートフォリオまで大公開! 「アラフォーから所得が大幅アップ」した4人の法則 緊急調査! 年収800万以上「稼ぐ女性」の仕事&お金&プライベートその2 料理教室月30万円、就職面接指導月15万円…… 続々解禁! 月10万円稼げる「副業&ダブルワーク」 同じアラフォーでも“お金観”はここまで違う 6カ国座談会 お国別「マネーの常識vs.非常識」 女性の多くが最後はひとりの時代。シングルも既婚者も必読! 「おひとりさまの老後」にかかるお金のリアル ポストコロナの世界を知るのに役立つ「経済&マネー」本10選 ※紙版と一部内容が異なる場合があります。
-
-私たちは皆、幸せになりたいと願っています。 しかし、異なる文化のレンズを通して観察すると、 多くの理論家が最も普遍的な感情と考えている幸福でさえ、 独自のニュアンスを持っていることに気づきます。 幸せは十人十色、つまり個人によります。 それと同時に住む文化によって、異なる可能性があるのではないか――。 ある国(文化)の中で生きていると、それが「あたりまえ」となり、 実は「世界的に見るとかなり変わっている」ということが、少なくありません。 いわゆる「カルチャーショック」ともいわれるものですが、 日本は古くからその筆頭格ともいわれる国であり、 その文化やそれにもとづく国民性について、 かなりの研究がされてきました。 わかりやすい例でいえば、 ・本音と建前 ・察する(空気を読む/暗黙の了解) ・周りと合わせる ・極端に人の目を気にする などですが、 優れた社会スキルとして機能している反面、 日々診療(カウンセリング)をしていると、それらがしがらみとなり、 心の不調となってしまっている日本人が多いことに気づかされます。 日々、日本で診療をしている、イタリアで生まれ育った精神科医が、 カウンセリングを通じて見えてきた「日本人の心の特性」「日本文化の特有性」 そして「日本社会で暮らしながら、どうすれば日本人はもっと幸せになれるのか」について、 外国人・精神科医の視点からまとめた1冊。 ■目次 ・プロローグ どうしたら「しあわせ」になれるのか ●Ⅰ部 イタリア人精神科医パントー先生の診療室 ・「眠れない」「食欲がない」――原因は自分より他人を優先させたい? ・「本当はどうしたい?」――しっかり自分を尊重しよう ・「〇〇だから、こうするべき」――決めつけが自分を苦しめる ほか ●Ⅱ部 パントー先生は考えた 日本人がしあわせになるために 日本社会の文化・慣習と「うまく付き合う」コツ ・「我慢」という怪物に遭遇したら ・「同調圧力」の罠にかかりそうになったら ・「恋愛」をもっと楽しむために ほか ●Ⅲ部 同じ? 違う? 日本の「しあわせ」他国の「しあわせ」 ・エピローグ 日本人がもっと、さらに「しあわせ」になるために ■著者 パントー・フランチェスコ 1989年イタリア・シチリア島生まれ。 幼少期に『美少女戦士セーラームーン』に感銘をうけ、 多くのアニメ・マンガ文化に触れるうちに、将来日本に住むことを決意。 医学部の勉強と並行して、『名探偵コナン』全話(当時)を見て独学で日本語を学び、 日本語能力試験で最も難易度が高いN1に一発合格。 イタリアの医師免許を取得後、ローマ最大であり、イタリア国内では2番目の規模を誇る、 ローマ教皇御用達のジェメッリ総合病院勤務を経て、日本政府(文部科学省)の奨学金留学生に選ばれ来日。 イタリア人で初めての日本医師免許所得者となる一方で、筑波大学大学院博士号取得(医学)。 慶應義塾大学病院にて初期研修医として研鑽を積んだのち、 同大学病院精神神経科教室に入局し、精神科専門医となる。 現在は複数の医療機関にて精神科医として勤務する傍ら、日々ヲタ活に励んでいる。
-
3.2
-
3.8待機児童ゼロ、結婚した女性の離職率の低さ、 貧困の少なさ、公教育の水準の高さ……日本型「北欧社会」が保守王国で生まれていた! 富山県は県民総生産が全国31位の小さな自治体だが、一人当たりの所得では6位、勤労者世帯の実収入では4位に浮上する。背景にあるのは、ワークシェアリング的な雇用環境と女性が働きやすい仕組みだ。さらに、公教育への高い信頼、独居老人の少なさなど、まるでリベラルの理想が実現しているかのようだ。しかし、北陸は個人よりも共同体の秩序を重視する保守的な土地柄とされる。富山も例外ではない。つまり、保守王国の中から「日本的な北欧型社会」に向けた大きなうねりが起きているのだ。10年間にわたって富山でのフィールドワークを続けてきた財政学者が問う、左右の思想を架橋する一冊。 【目次】はじめに/序章 保守と革新、右と左を超えていくために/第一章 富山の「ゆたかさ」はどこから来るのか/第二章 どのように富山県の「ゆたかさ」は形づくられたのか?/第三章 家族のように支え合い、地域で学び、生きていく/第四章 危機を乗り越えるために「富山らしさ」を考える/終章 富山から透視する「歴史を動かす地域の力」/おわりに/参考文献
-
3.6
-
3.7
-
3.2絶望の老人社会を告発する、硬骨の社会派ノンフィクション! 近い将来3人に1人が高齢者となる日本では、老人をめぐる状況が凄まじい勢いで悪化している。それも貧困層ばかりか、中流層も「地獄」へ引き込まれようとしているのだ。 たとえば…… ・全国各地に「無届け老人ホーム」が増加。古い空き家で、同じ部屋に男女を雑魚寝させる「お泊りデイ」施設も。排泄物の臭気が充満する不衛生な環境で、ノロウイルスが蔓延したり、転んでケガするケースが続出。それでも「安い料金」が魅力となり、入居させたい家族は後を絶たない。 ・北海道には「老人下宿」なるものが増えている。狭い部屋が与えられ食事が出るが、経営者が逃げてしまい、入居者が突然放り出される例も。 ・特別養護老人ホーム(特養)を経営する社会福祉法人のなかには、濡れ手で粟のボロ儲けをし、まさに「老人食い」で肥え太っているものもある。政治家の介在が見え隠れするケースも。 ・介護計画を立てるのはケアマネージャー(ケアマネ)。ところが、ケアマネが特定の施設にカネが落ちるよう誘導し、入居者が無意味に高い料金を払わされるケースも多発。 ・未婚率の上昇とシングルマザーの増加により、低所得の独居高齢者は激増。年金をきちんと払っていても、年金基金が破綻し、実質無収入となる老人も増えている。 ・国民健康保険が払えない低所得の老人たちから、無慈悲な「強制徴収」に踏み切っている自治体も 団塊世代が後期高齢者入りする2025年以降は、もっと悲惨な現実が待ち受けている。はたしてわれわれは自分を守るためにどうすべきか? そのヒントが本書にある。
-
3.5重税国家ニッポンのブラックすぎる収奪システム! あなたの給与明細を見てほしい。所得税、住民税、健康保険税、復興特別所得税……年収や家族構成にもよるが、おおむね3割~4割を「取られ」ている人がほとんどだ。 これに加えて、買い物をすれば消費税8%。家を持てば固定資産税が毎年かかる。さらには酒、自動車、たばこ等に税金がかかる。親族が死ねば相続税もかかる。 すでに日本は世界有数の重税国家だが、財政悪化と超高齢化社会によって、ますます私たちの税負担は大きくなる。 一方、節税ノウハウをもつ富裕層は巧みに税逃れをし、資産の海外流出は止まらない。現金取引が主体の自営業者も税金を払わない。結果的に「中~下層のサラリーマン」が狙い撃ちにされ、中・低所得者層の税負担率も高まっている。まさに税金地獄である。 本書には、以下のような驚くべき実態が赤裸々に描かれる。 ・タワーマンションやペーパーカンパニーを用いた富裕層たちの驚愕の節税テクニック ・税滞納ですぐに差し押さえをする自治体 ・固定資産税の過大請求発覚が急増中(持ち家の人は絶対に要チェック!) ・しかも自治体は、余分に徴収した税金の返金にはなかなか応じない ・ある日突然、とうの昔に死んだ親戚の所有地の固定資産税の請求書があなたに届く ・「ふるさと納税」が富裕層たちの税逃れツールと化している実態 ・バブル時代のリゾートマンションが“老人ホーム”化し、1万円で売られている ・大企業が優遇され、中小企業が損をする税制決定の舞台裏 ……税金で損しないため、泣かないために、必読の作品だ。
-
4.1子どもの6人に1人が貧困という日本社会。放置すれば43兆円が失われ、政府負担も16兆円増! 日本では衣食住に困るような絶対的貧困は少ない。しかしギリギリの生活で教育へお金をかけられない家庭の子どもは将来の選択肢がせばまり、大人になってから得られる所得が減るだろう。となると回りまわって国の税収は減少。彼らが職を失うことになれば、生活保護や失業保険といった形で支出は増大する。子どもの貧困は「かわいそう」などという感情的な問題だけではなく、私たち一人ひとりの生活を直撃する重大な社会問題なのだ。 本書では、データ分析、国内外での取り組み事例紹介に加え、生活保護世帯、児童擁護施設、ひとり親家庭の当事者たちへインタビューを収録。 【おもな目次】 <第1章 子どもの貧困大国・日本> 貧困は「連鎖」する/子どもの貧困問題は「ジブンゴト」 <第2章 子どもの貧困がもたらす社会的損失> 子どもの貧困は何をもたらすのか?/社会的損失を防ぐために何が必要か?/子どもの貧困が閉ざす日本の未来 <第3章 当事者が語る「貧困の現場」> ケース1(女性・二十代・自立援助ホーム出身)/ケース2(男性・十代・ひとり親家庭)など <第4章 貧困から抜け出すために> 貧困の連鎖の正体とは/「社会的相続」への注目/ライフサイクル論 <第5章 貧困対策で子どもはどう変わるのか> 子どもの貧困対策に効果はあるのか?/幼児教育は生涯にわたって大きなインパクトをもたらす <第6章 子どもの貧困問題解決に向けて> 「子どもの貧困対策プロジェクト」始動/家でも学校でもない第三の居場所を目指して
-
4.0●こんな人にオススメ ・難しそうだから、お金の話は興味あるけど学んでこなかった ・真面目に働いているけど、お金に恵まれてこなかった ・大金持ちにはならなくてもいいけど、お金で悩みたくない ホームレス寸前だった著者が、お金に困らなくなったのは必然だった? 謎多き著者がはじめて語る「意識低い系」の人のための等身大のお金の哲学。 第1章 会社ですりへらないための「働き方のルール」 ・なぜ暮らしがこんなにキツいのか ・弱肉強食の世界に「タダ働き」はあり得ない ・「時給900円」なのはそれだけの価値しかないから 第2章 「蛍光灯おじさん」にならないための“生きがい”の考え方 ・社畜から脱出するための「副業のすすめ」 ・「仕事をしなくても給料をもらえる」がダメな理由 ・仕事にやりがいを求めても無駄 第3章 「金持ち奴隷」と「貧乏貴族」 ・貧乏人は「価値のないもの」にお金を使う ・国民が節税しても政府は困らない ・「1本128円のきゅうり」ってどうよ? 第4章 「ほぼオート」でお金が入ってくる生活 ・「死ぬまで働く」以外に方法はないのか ・やるなら「不労所得」一択 ・絶対に手を出してはいけない商売3つ 第5章 「朝ゆっくりココアを飲める生活」のために今やるべきこと ・お金から自由になるためにお金を稼ぐ ・日本人は「量産型ザク」のように働かされる ・「金持ち=成功者」ではない ★(日本で一番長い)あとがき★ ・誰かの決めたルールに従うのが苦手だった ・社員になるか、自由を選ぶか ・お店を閉め、無一文に ・どん底の「ほぼホームレス」時代 ・YouTubeとの出会い
-
-筆者の願いは、自分と同じく1人でも多くの人が大切な人と過ごす時間を持ち経済的に豊かに暮らせること。 この本は、サラリーマンだった著者が、6年間でFIREを達成するまでのストーリーを、インタビュー形式で赤裸々に綴ったものである。新型コロナウイルスの影響で、投資やFIREに興味を持つ人が増えている今、不労所得を得る為の虎の巻となる1冊であり、著者が経験したFIREまでの道のりは、これからFIREを目指す人にとっての良きシミュレーションとなり、サラリーマンで稼ぐことの限界、投資を始めたことによる変化、安定に至るまでをすべて公開している。 【目次】 はじめに 第一章 FIREまでの道のり 不動産投資家カワベ敦資 ブラック企業のサラリーマン 1回目のFIRE(専業ネットトレーダー) FIRE失敗で再びサラリーマンに 株から不動産投資へ 再就職を繰り返す日々 不動産投資を始めるには 物件購入は誰に相談する? 所有不動産について 第二章 不動産投資 物件購入のポイント 裏技とメリット 心がけておくこと 営業マンとの連携 第三章 投資資金の貯め方 株式投資 株を買うタイミング 損切りをするタイミング ドルコスト平均法 副業あれこれ 第四章 FIRE そしてその先へ 不動産投資のリスク 大学 生の息子 1回目のFIREと2回目のFIREの違い FIREして変わったこと 資格の取得 今後の展開 FIREを目指す方へのメッセージ おわりに 【著者】 カワベ 敦資 1968年生まれ 54歳 1986年 工業高校卒業、就職 2006年 1社目(勤続約20年)退職、1回目のFIRE 専業ネットトレーダースタート 2008年 再就職 2015年 1棟目アパート購入 2016年 2棟目アパート購入 2017年 3、4棟目アパート購入 2021年 会社員を辞め、2回目のFIRE 2022年 5棟目アパート建築中
-
3.5
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 お金に困らない生き方 最短で2000万円貯めるほったらかし投資術 ※紙版と一部内容が異なる場合があります。 【目次抜粋】 インフレ時代に貯金は大損! 老後資金はこう増やす! 難しいことはわかりませんが、「元手0円で、老後資金2000万円」つくる錬金術を教えてください! ●横山光昭 勘違いしやすい「ドルコスト平均法」の真実を大公開! 8割がやらずに大損している! 最新版「ほったらかし積立投資術」 ●星野泰平 賢い人はもう準備している! 人生100年時代も安心! 大節税でトクする「新NISA」投資術 ●深野康彦 なぜ米国株より日本株のほうが得なのか 月23万円の配当金が入ってくる!「オートモード高配当投資」入門 ●長期株式投資 ▼おすすめ「永久保有銘柄」17選 有望9銘柄も大公開! 会社四季報の達人が直伝! 10倍株が見つかる7つの法則 ●渡部清二 コラム▼クレジットカード投資で最大5%還元! 最強「積立クレカ」リスト なぜ今、日本株に投資すべきなのか? 世界三大投資家ジム・ロジャーズ特別取材「歴史が証明! ロシア株の急騰に備えよ」 日本の5大商社に追加投資! 投資の神様「ウォーレン・バフェット」最新投資戦略ガイド ●桑原晃弥 コラム▼お金持ちになりたかったら、ユダヤ人の大富豪に学びなさい ●石角完爾 なぜ米国株より「PBR1倍割れ」の日本株なのか? 大人気の個人投資家に誌上相談! 単刀直入に、良い株の見つけ方を教えてください ●テスタ、弐億貯男、馬渕磨理子 今どきはスリッパではなくて○○を見なさい! 人気急上昇中のプロ投資家が明かす伸びる会社、ダメな会社 ●奥野一成 5分でわかる「テクニカル投資術」を伝授! チャート分析のプロが図解! 絶対に投資してはいけない株、投資すべき株 ●阿部 隆 コラム▼脱サラ起業家直伝「金持ち老後を実現したいなら、小さな起業を目指しなさい」 山を買って電柱敷地料で稼ぐ! サラリーマンでも、グズでもできる! 株より手堅い「ズルい不動産投資」3選 繰り上げたとき、繰り下げたときの損得 7タイプ別◎徹底シミュレーション 何歳から年金をもらうべきか? ●山崎俊輔 ▼共働き正社員型 ▼妻が専業主婦型 ▼妻がパート型 ▼夫婦とも自営業型 ▼おひとりさま型▼稼ぐ夫・公務員夫婦型 ▼番外編=離婚・死別型 「受給繰り下げ」だけじゃない! 2023年、今すぐ「年金」を増やす具体策 ●内藤眞弓、加谷珪一、吉川英一 ▼公的年金の増やし方 制度改定。65歳以上で働くと翌年年金アップ ▼私的年金の増やし方 「お宝個人年金」を持っていたら、掛け金増額交渉 ▼じぶん年金の増やし方 タイプ別「不労所得」をつくる8つの方法 世界最大級の機関投資家と同じ作戦 経済アナリストの結論「投資初心者の成功法は1つだけ」 ●森永康平
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本の都道府県としては、北海道に次ぐ2番目に広い総面積を誇るのですが、可住居面積の割合は約24%(全国40位)と低く、内陸部と沿岸部に人口が集中し、あとはだだっぴろい平地と山があるだけ! 県内全体が豪雪地帯に指定されており(特に藪川は真冬に-30度を記録することもある)、本州最寒地としても有名です。 また、南北の所得格差に代表される、典型的な「南北問題」も起こっており(北上市など県南部では著しい経済発展により所得水準も大きく向上しているが県北の中心都市である二戸市や久慈市では所得水準が低いまま)、 県は今も根本的な解決策を見い出せない状況です。 近年では、NHKの朝ドラ「あまちゃん」のロケ地として、久慈市が一瞬だけ注目を集めましたが、 そのブームも終わり元の寂しい姿に戻ってしまいました。そんな現状を、故郷を「イーハトーブ(理想郷)」と称した宮沢賢治が見たらどう思うでしょう……。 東北を代表する理想郷(?)、岩手の現状とこれから進むべき未来を、様々な角度から熱く語り尽くす一冊です!
-
-中国の都市部の世帯は、持ち家を平均1.5軒持っており、北京市の平均世帯資産は1億3392万円に上る。なぜ、彼らは「お金持ち」になったのか? 本書では急激に豊かになった(たとえば上海市の大卒初任給は30年前の190倍)中国人の資産の増やし方や消費傾向を紹介し、彼らのライフスタイルや価値観の変化を浮き彫りにする。 ●「Z世代」といわれる若者は従来の中国人とは異なり、商品の箱の中身を確かめないでモノを買う ●若者が憧れるKOL(キー・オピニオン・リーダー)――「ライブ・コマース」で商品を巧みに紹介する人たち ●ホワイトカラーよりブルーカラーのほうが可処分所得が多い ●農村住民や都市の非就労者が加入する年金の受給額は、月平均125元(約1875円) ●介護に関しては在宅介護が全体の9割を占めており、「子どもが老親の介護を負担するのは当たり前」という従来の考え方は今でも根強い ●コロナ禍の武漢での食生活は……
-
3.8
-
4.0税務署員もやっている手取り増額術を公開! ビジネスパーソンなら、毎月必ずもらっている給与明細。しかし、実際には、総支給額と振込金額だけ確認してあとはポイッ、としている人の方が多いはず。それぞれの数字の意味を理解している人は少ない。その内容を知らないということは、実はそれだけで大損しているのだ。 給与明細には、収入だけでなく、貯蓄、税金、社会保障に関する情報が満載だ。この情報をうまく生かすことができれば、収入を増やしたり、支出を減らしたり、試算を大きくすることも可能なのだ。 実際に支給されている額から、様々なものが天引きされている。税金や社会保険料がその代表だ。その天引きされているものを減らせば、手取りは増えるのだ。 多くのビジネスパーソンは「会社がすべてをやってくれる」と思い込んでいることだろう。しかし、そうではない。会社は「最低限度のこと」しかやってくれない。ビジネスパーソンが使える所得控除13種類のうち、会社がやってくれるのは3~4種類に過ぎない。会社は税務署の代わりに、税務署の指示通りに社員から税金を取り立てているに過ぎないのだ。 自分の給料をきちんとマネージメントするだけで、汲々とした生活が一新できるのだ。 【ご注意】※この作品は図表が含まれるため、お使いの端末によっては読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。
-
-
-
3.3「ピケティが示した不平等の歴史的な展開を、さらに歴史的に俯瞰する。格差論の未来のために!」 ――『21世紀の資本』共訳者・山形浩生氏 推薦 フランスの経済学者トマ・ピケティによる大著『21世紀の資本』が公刊されたのは2013年。その後、ノーベル経済学受賞者のスティグリッツやクルーグマンらの推薦もあって英訳から火がつき、またたく間に世界的にベストセラーになりました。 どうして大ブームになったのでしょうか? 実は下地ができていました。高度成長を終えた先進国のなかで、ピケティしかり、日本の「格差社会」「大衆的貧困」ブームしかり、明らかに「不平等ルネサンス」とでもいうべき学問的潮流が起きていたのでした。 それでは一体いつ、経済学者たちの「不平等との闘い」は始まったのでしょうか? 本書では、ピケティ的な意味での「市場経済の中での不平等(所得や資産の格差)」に焦点を絞り、その歴史を紐解きます。 18世紀にフランス革命の思想的後ろ盾となった、ジャン=ジャック・ルソーと、そして“神の見えざる手”で知られるアダム・スミスから議論を始め、マルクス経済学、近代経済学、不平等論議の新しいステージ「不平等ルネサンス」、そして現代のピケティにいたるまでの学問的軌跡を追っていきます。
-
3.8どうして日本の国力は 30年以上も低下し続けているのか? 低所得・低物価・低金利・低成長の 「4低」=「日本病」に喘ぐニッポンを、 気鋭のエコノミストが分析! <本書の主な内容> ・「4低」現象は「日本化(Japanification)」と呼ばれ、世界で研究対象に ・今や日本の賃金は、アメリカの半分強、韓国の約9割 ・失業率が高い国ほど、賃金上昇率も高い不思議 ・「物価上昇率がマイナス」は、OECD諸国で日本だけ ・異次元の金融緩和でも、物価が上がらない理由 ・日本は家計も企業も過剰貯蓄、はびこるデフレマインド ・アメリカはリーマン・ショック後、すごい勢いで量的緩和と利下げを行い、「日本化」回避に成功 ・日本の政府債務の増加ペースはG7の中で最低、財政赤字を気にしすぎ ・ここ30年で、アメリカのGDPは2倍、日本は1.2倍 ・日本では、年収200万円未満の世帯が増加、年収1500万円以上の世帯は減少⇒1億総貧困化へ ・「日本の年金・社会保障制度は危機的状況」の間違い ・大きな可能性を秘めている日本の第一次産業
-
4.0給与所得者ほど税金を取りやすく、そして実際に取られている人はいません。そのような実感のない人も多くいますが、源泉徴収制度などの巧妙な徴税システムでその実態が庶民にはわからなくなっており、また、所得税や相続税、贈与税などの増税は、閣議決定などで「いつの間にか」決められています。こうして、日本はいつの間にか“重税国家”になってしまったのです。重税国家というと、収入の半分以上を税金で持っていかれるスウェーデン、デンマークなどの北欧諸国を想像しますが、これらの国はいずれも高福祉国家で、国民は納税した分のしっかりした行政サービスを受けています。それに対して、人口減少時代に入った日本では、これからますます福祉が削減されるだけでなく、今後は「支出税」「資産税」「死亡消費税」などの新税が現実のものになるかもしれません。そして最終的には、国は膨大な債務を帳消しにするために大きなインフレを起こし、国民の資産を吹き飛ばしてしまう可能性すらあります。われわれはそのとき、国に対してどのようなスタンスで向き合い、各個人はどのような対策をとれるのか? これから持つべき税についての知識を明快に示していきます。
-
4.0◆官製相場、株高、格差拡大……歴史が物語る「資本主義のカラクリ」! ◆「経済史」をひもとくことで見えてくる日本経済の行く末、世界経済の向かうところ。 ケインズやマネタリストなど時代を先導したさまざまな経済思想から、最近のピケティ「21世紀の資本」まで、博覧強記の著者がひも解く! ◆ピケティ「21世紀の資本」が巷間話題となっているが、所得・資本格差の拡大は資本主義においてとくに目新しい課題ではない。 ではなぜこんなにも注目を浴びたのか? それは、もともと日本が欧米型パワーエリートが住む社会とは別種の、資本格差も知的格差も世界一小さい国であり、つい最近までそうだったからだ。 ◆20世紀の日本経済はどのように推移し、現代へと至ったか。バブル経済、規制緩和とグローバリズム、増税など、過去の事例を照らし合わせれば、21世紀の経済の流れはおのずからわかる! ・小泉改革とアベノミクスはまるきり違う ・地方創生会議は、経済効率が悪いからこそ企業が逃げていく場所に強引に人と資源を縛り付ける愚策 ・たとえインフレ率を上回る実質成長率があったところで、それは4~5%という威勢のよい水準に戻ることは土台無理 ・デフレを是とした着実な経済運営は可能だった…… など、目からウロコの着眼点で、アベノミクスのその先の日本経済がむかえる状況まで大胆に見通す!
-
-黄金の1960年代はいかに達成されたか── 東京オリンピック、新幹線に象徴される高度成長の驀進時代を活写! 2020年、2回目の夏季東京オリンピック開催に向けて、今その熱気を振り返る。 東京オリンピックの開幕を10日後に控えた昭和39年10月1日、 そのオリンピックと並んで「黄金の1960年代」を象徴するモニュメントとなった 東海道新幹線が、開業の朝を迎えた。 午前6時、発車のベルが鳴り終わると同時に、下り「ひかり1号」がゆっくり動き始めた。 「あの時代の熱気を生み出したものはいったい何だったのか、 日本人はどんなエネルギーをどのように結集して「黄金の1960年代」を生み出したのか。 何が日本と東京に『大変貌』をもたらしたのか。」 「『燃える』とは、東京がオリンピックで燃えていることを指すのだろうか。 新幹線の発着ということもあるだろう。 しかし、私は結局、燃えたのは池田勇人の所得倍増計画だったし、日本経済そのものだったと思う。<中略> この見地からいえば、東京オリンピックと交通体系は別のものではない。一つのものである。 そういう意味では、東京は今も燃えているといっていい。」 《電子書籍版あとがきより抜粋》 2020年、夏季東京オリンピック開催に向けて、日本は、東京はどこへ向かうのか。 【目次より抜粋】 ◆序章 黄金の‘60年代 「黄金時代」前夜/開幕/戦後史なかの東京オリンピック ◆第1章 東京への3000日 紀元2600年のオリンピック/ムッソリーニとヒトラー/「東京、遂に勝てり」/開催返上 ◆第2章 オリンピック、再び 国破れて夢あり/「いったいいくら金がかかるかね」/一万日の聖戦 ◆第3章 「所得倍増」の誕生 「黄金時代」がやってくる/死の淵から蘇った男/積極財政派への道/二人のブレーン ◆第4章 高度成長の演出者たち 戦後最大のコピー/二つの数字をめぐる攻防/投資が投資を呼ぶ/池田政治の光と影 ◆第5章 二人の都知事 「復興した東京をPRしたい」/保守都政の帽子/「オリンピック知事」の誕生 ◆第6章 東京大改造 東京を蘇生させたい/道と水/「陰の知事」の陰の任務 ◆第7章 1兆円オリンピック 「私生児」新幹線/開催準備/官製オリンピック ◆終章 「世紀の祭典」の遺産 さまざまな思惑/神の見えざる手/「高度成長」の夢の跡
-
-終身雇用の崩壊した現代日本社会を生き抜くため サラリーマンにしかできない不動産投資を実践しよう! 若いうちから始めれば、資産はもっと増やすことができる! 昇格はたったの1回…。50歳・主任サラリーマンに襲いかかった突然のリストラ。 しかし、不動産投資によって食べるに困らない生活は保障されていた。 不動産投資とは何か?どうすればいいのか?など…… 著者の経験からこの1冊を読めば不動産投資がわかる! これを読んで目指せ!ハッピーリタイア! 東海林満(とうかいりん・みつる) 1962年山形県生まれ。山形大学工学部機械工学科卒業。85年に大学からの推薦によって大手メーカーに就職。 システムメンテナンスなどの業務に従事しながら、アフィリエイトや株式投資を試みる。 その後、『金持ち父さん、貧乏父さん』(筑摩書房)と出会い、不労所得の重要性を再認識して不動産投資を始める。 2012年、会社の早期退職制度を利用して退社、これまでの実績と培った経験を元にした投資コンサルティングなどフリーエージェントとして第二の人生を歩み始めている。
-
-ロングセラーである本書が、 インボイス・電帳法など最新制度に対応してリニューアル。 設立、申告などの各種手続きから、経理、相続対策まで、 法人化 & 経営に必要な実務をすっきりマスター。 手間をかけずに高利回りを実現する効率経営も解説。 投資ビギナーにも、 すでに個人で不動産投資をはじめている人にも わかりやすい1冊です。 ■目次 ●プロローグ ・アパート・マンション経営なら、手堅く儲けられます ・アパート・マンション経営を始めるときの注意点 ・どんなマンションに需要がある? 市場調査はしっかり ●第1章 アパート・マンション経営を個人から法人に アパート・マンション経営を会社経営しましょう ・アパート・マンション経営を会社経営にするメリット・デメリット ●第2章 アパート・マンション経営を個人から法人に 会社設立でこんなに節税できます! ・法人と個人事業の違いは「税金」 ・所得税と法人税、税率はどのくらい違う? ・会社の設立や維持のための費用はどのくらい? ・会社設立で相続税も節税に! ・使える経費の幅が広がるので、法人がダンゼン有利 ・旅費・交通費や交際費の取り扱いも、法人が有利 ・退職金が損金になるため有利 ・会社で生命保険に加入すると保険料が損金になる ・損益通算・繰越控除でも法人税が有利 ・相続税・贈与税の節税効果も! ●第3章 なるほど! 不動産会社のしくみ 不動産管理会社には4つの形態があります ●第4章 なるほど! 不動産管理会社のしくみ 【ケーススタディ】最適な会社形態を選びましょう ●第5章 なるほど! 不動産管理会社のしくみ 【小資本で不動産投資】ワンルームマンション投資 ●第6章 なるほど! 不動産管理会社のしくみ 【もっと高度に不動産経営】建物所有会社でアパート・マンション経営 ●第7章 なるほど! 不動産管理会社のしくみ 自宅や社員の住居を会社所有にしましょう ●第8章 なるほど! 不動産管理会社のしくみ 会社といってもいろいろな形があります ●第9章 しっかり知っておきたい! 税金の話 消費税の取り扱いに注意しましょう ●第10章 しっかり知っておきたい! 税金の話 不動産の相続税評価と節税のポイント、教えます ●第11章 しっかり知っておきたい! 税金の話 不動産管理会社の税務調査ではここをみられます ●第12章 しっかり知っておきたい! 税金の話 相続時精算課税の特例を使って節税できます ■編集 山端康幸 税理士法人東京シティ税理士事務所所長。 土地活用や相続税対策に関する不動産税務を専門とする。 不動産税務専門税理士として40年の経験を有する。 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
3.4タワマンに住んで外車に乗る人まで国が支援するのか――所得制限撤廃の話になると、きまってこんな批判がわき起きる。だが、当事者の実感は今やこの言葉とはかけ離れている。かつて“勝ち組”の代名詞でもあった「年収1000万円」世帯は、不動産価格の高騰、実質賃金の低下、共働きで子育てに追われる夫婦の増加などによって、ギリギリの生活設計を迫られているのだ。様変わりした中流上位層のリアルを徹底分析。
-
-誰でも簡単にできる確定申告書の書き方を徹底解説! 年金や退職金を受け取った場合など、さまざまなケースに対応した申告書の書き方を紹介します。 実際の申告書をサンプルに解説するので、確定申告が初めての方でも誌面をマネするだけで迷わず書き進めることができます。 ■大きな文字でわかりやすい 大判(A4サイズ)、オールカラーで文字が大きく読みやすいのが特徴。難しい用語を可能な限り減らし、初心者の方でも理解しやすい内容になっています。 申告のポイント(1)インターネットを使った申告書の作成・提出が便利! 申告のポイント(2)申告書Aが廃止され新たな書式の申告書に 申告のポイント(3)「新型コロナ」による影響は? ●項目別早見表から該当するページを読めばOK! 【年金受給者、退職者の場合】※申告すればお金が戻ってくることも! 1 公的年金等を受け取った 2 個人年金を受け取った 3 退職後に再就職しない 4 退職金を受け取った 5 所得控除 6 税金の計算 7 復興特別所得税 8 源泉徴収税額 9 納付金額・還付金額 【個人事業主】※自宅と事業はどう分ける? 1 事業所得 2 所得控除 3 税金の計算 4 復興特別所得税 5 納付金額・還付金額
-
-誰でも簡単にできる確定申告書の書き方を徹底解説! 年金や退職金を受け取った場合など、さまざまなケースに対応した申告書の書き方を紹介。実際の申告書をサンプルに解説するので、確定申告が初めての方でも誌面をマネするだけで迷わず書き進めることができます。 ●項目別早見表から該当するページを読めばOK! 【年金受給者、退職者の場合】※申告すればお金が戻ってくることも! 1 公的年金等を受け取った 2 個人年金を受け取った 3 退職後に再就職しない 4 退職金を受け取った 5 所得控除 6 税金の計算 7 復興特別所得税 8 源泉徴収税額 9 納付金額・還付金額 【個人事業主】※自宅と事業はどう分ける? 1 事業所得 2 所得控除 3 税金の計算 4 復興特別所得税 5 納付金額・還付金額
-
4.0
-
3.92021年10月、第100代総理大臣に就任した著者の、はじめての著書を新書改訂版として緊急発売! 「聞く力」を備えた新しいタイプのリーダーの登場。 新自由主義を脱し、「新しい日本型資本主義」の構築を目指す。 コロナウイルスの感染拡大によって国民の生活は大きな痛手を受け、格差拡大、「勝ち組」と「負け組」、中間層の没落などが顕著になりつつある。 日本だけでなく、欧米やアジアなど、世界的に「格差拡大」が広がり、さらに国同士の分断も進む。 この「分断の時代」に、求められていることこそ「協調の精神」ではないか。 具体的には、高額の金融所得に対する課税率の見直し、中間層の教育、住宅費に対する支援、社会人に対する再教育支援、中小企業、小規模事業者に対する支援などである。 さらにIоTなどの普及によって、地方にあっても都会と同じレベルの仕事ができる環境ができつつある。 宏池会の大先輩・大平正芳元首相が唱えた「田園都市構想」を再生し、「デジタル田園都市構想」を推進する。 外交面でも、「分断から協調へ」がキーワードになる。4年7ヵ月の外相経験を通して、アメリカ、イギリス、ロシア、中国をはじめ世界の首脳と築いてきた人間関係を生かし、孤立化、分断化が進む世界で「協調」をテーマとした外交を展開する。 さらに広島出身の政治家として、「核兵器なき世界」への取り組みは最大のテーマである。2016年に実現したアメリカ・オバマ大統領(当時)の広島訪問は、核軍縮という観点で非常に大きな出来事だった。 核軍縮交渉の根底には、やはり協調というベールが求められる。 なぜ政治家を志したのか。 差別を憎み、理不尽を疑う心はどこから芽生えたのか。 日本政治にいまも内在する悪弊とは何か。 その一方で、長く守り抜いていかなければいけない価値とは。 政治家人生を懸けた、渾身の一冊。
-
-『繁栄は通過する』松下幸之助の危惧は的中し日本は衰退への端に。夢を託された政経塾2期生の悔恨の思い。 1980年、84歳の松下幸之助は私塾を開き国づくりの思いを託す。日本礼讃の罠からの奈落のゆでガエル30年、危惧は的中。今COVID-19が世界をリセットする。①『竈に煙が戻るまで』所得税減税、②透明・可視化される生産性の高いデジタル民主主義、③地球規模のインフラ・データ活用産業振興、④つながりの世界経済を魅了する都市づくり、⑤セーフティーネット化した学校現場の活用強化で多様な人材育成、など国内外に知見を求め衆知を集めて日本再生を図り未来を次世代に託す。著者は直接薫陶を受けた松下政経塾第2期生。 【目次】 希望をつなぐ「日本改造試案」目次(抜粋) 序章 COVID-19禍は日本のチャンス 〇陰謀説から天譴説まで 〇資本主義経済の流れは変わらない ほか Ⅰ.やることは決まっている 行財政改革、インフラ投資と産業振興、人材育成 Ⅱ.所得税減税の提案 〇竈(かまど)に煙が戻るまで 〇松下幸之助の無税国家論 〇リリース&フィードバック ほか Ⅲ.インフラ投資と産業振興 〇宇沢弘文の慧眼「社会的共通資本」 〇中国の台頭 〇覇権争いはどこまでも ほか Ⅳ.人材育成 一気に「1945年に戻った」2020年 〇「コロナ世代」と呼ばせない 〇セーフテイネット化する学校 〇学び直しは当たり前に ほか 【著者】 高橋秀明 1956年埼玉県生まれ。埼玉県立浦和高校、慶應義塾大学法学部法律学科卒業の後財団法人松下政経塾第2期生。株式会社バンダイ勤務を経て参議院参事・議長秘書、埼玉県知事特別秘書、松下政経塾政経研究所研究員、日本BS放送社長室長を務める。現在一般財団法人日本おもちゃ図書館財団事務局長、一般社団法人日本くにづくり研究所政策顧問など。
-
4.2日本の相対的貧困率は15.7%(2015年。相対的貧困とは、2015年現在では手取りの年間所得が一人暮らしの世帯で122万円以下、4人世帯で244万円以下の世帯を指す)。人数で言えば1900万人以上にも上るが、日本には本当の貧困なんてないと言う人もいる。そんな人にこそ伝えたい現実がある。一時的にせよ「飢えた」状態に置かれてしまい、万引きをしなければ食べ物にありつけない貧困家庭の子どもは少なくないのだ。本書では貧困問題のリアルと本質について、社会調査とデータのエキスパートと、貧困家庭の現場を徹底して見聞きしてきたライターが語り合う。貧困への無理解に対抗するための本音対談。 ●欧州はなぜ社会福祉が整備されているのか ●新築の家などの『強制出費』は罪が重い ●貧困家庭の冷蔵庫はものでいっぱい。ただし、賞味期限切れの食べ物ばかり ●地方の若者の刹那主義 ●なぜ貧困を放置してはいけないのか ●貧困対策を徹底的に考える ●政治家も官僚も、世論を恐れている
-
3.9
-
3.0
-
4.0
-
-<本書の特徴> 1.弁護士、税理士、社会保険労務士、セキュリティーの幅広い専門家が執筆 すでにマイナンバー制度の解説本はかなりたくさん出ています。ただ、これら解説本は、1人の筆者がその専門分野の見地からしか書くことができません。今回の本書では、様々な分野の専門家に原稿を書いてもらっており、多様な関心に応えています。 2.マイナンバー制度を分かりやすく、かつ批判的に検討 他のマイナンバー関連本は、法律家やシンクタンク研究者などのものが多いですが、用語そのものが非常に難解です。また、シンクタンク自体が特需の恩恵を受けているため、制度そのものを批判的に検討することが難しいのが実情です。本書ではシンクタンクの研究者は起用せず、マイナンバー制度の礼賛にならないように注意しました。 3.一利用者の立場に立って、素朴な疑問に応える本書だけの情報が満載! ! マイナンバーを受け取らないと罰則はあるのか、副業や無申告はバレてしまうのか、情報漏えい時に民事賠償額はどれぐらい......といった、素朴な疑問を出発点にしています。本書だけしか載っていない情報が満載です! <構成> ・生活、仕事は激変 前代未聞のプロジェクト■桐山友一/酒井雅浩 ・インタビュー 福田峰之 内閣府特命担当相補佐官 「便乗商売はやめてほしい」 ・隣り合う「利便」「危険」、漏えい不安根強く■日下部聡/青島顕 ・個人を襲うマイナンバーのリスク■鈴木敦子 ・マイナンバーの基礎知識 Q&A ■エコノミスト編集部 ・所得、資産は丸はだか? 預金口座と個人番号ひも付け 申告漏れの捕捉・徴税強化 ■村田顕吉朗/高山弥生 ・不自然な預金情報を把握 税務調査の対象容易に ■松嶋 洋 ・徹底シミュレーション 社会保険の適用逃れ大問題 過去2年分を一度に徴収 ■松本 祐徳 ・際限ない利用拡大 戸籍、医療情報、社員証... プライバシーへの重大な脅威 ■坂本 団 ・難しい収集・廃棄 「本人確認」「利用目的の特定」...■松本 祐徳 ・ 「誤解」していない? 年内の一斉収集は必要なし 実際には来年の年末調整から ■松本 祐徳 ・大丈夫かセキュリティー 対策が甘いマイナンバーの情報漏えい問題 ■山崎 文明 ・これほど重い! 法的リスク 民事賠償、刑事罰、行政処分... ■渡邉 雅之 ・個人情報保護法改正に要注意! 中小事業者向け特例が無実化 ■渡邉 雅之 ・自社に合ったシステムを探そう 9社のサービスと価格 ■エコノミスト編集部
-
-●※裏情報満載※●行政書士×キャバクラ嬢! 法律が学べるエンタメノベル! 全3巻すべてをまとめた完全版が登場! 六本木の実在“人気キャバクラ嬢”でありながら、 “現役行政書士”のサキが送る、「夜のお店と行政書士の仕事」の裏事情。 今日も指名を取りまくる。行政書士でキャバクラ嬢のサキ。 “慰謝料請求”“債務整理”“無店舗型性風俗特殊営業”“遺言作成と新規店舗開業” などなど、夜のトラブルをズバッと解決! ◆こんな人におすすめ ・風俗特殊営業の裏側を知りたい ・行政書士×キャバクラ嬢という肩書が気になる ・楽しく法律を学びたい 【著者情報】 杉沢志乃(スギサワシノ) 1981年6月6日、東京都生まれ。中卒。ホステスのかたわら様々な資格を所得し、21歳の時、3回目のチャレンジで行政書士に合格。現在は六本木にあるバー「LIV」のママをしている 浅野幸惠(アサノサチエ) 香川県高松市出身。中央大学法学部法律学科卒業。1993年9月行政書士事務所開業後、共同事務所時代を経て2001年独立し、事務所を構える。主に風俗営業、運送業関係の業務を手がける。現在、東京都行政書士会理事、風俗営業部長。東京都行政書士会港支部副支部長 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 【目次】 「キャバクラ嬢」 行政書士の事件簿1 第1話 調子に乗った若手お笑い芸人と憤怒の嬢王 第2話 恋人の連帯保証人になってしまった新人キャバ嬢 第3話 芸能プロダクション社長、涙のデリヘル開業 第4話 父の死、そして、ナンバー1キャバクラ嬢の旅立ち 「キャバクラ嬢」 行政書士の事件簿2 第1話 「オタク系ストーカー」と「キャバクラ性うつ病」 第2話 「セックスレス」元キャバ嬢の離婚問題 第3話 キャバ嬢に口止め料を送りつけた「プロ野球選手」 第4話 「党首候補」と「癒し系ヤクザ」と「拉致・監禁」 「キャバクラ嬢」 行政書士の事件簿3 第1話 労働基準法なんておかまいなしの「パワハラ店長」 第2話 賃金不払い「キャバクラ」とのらくら「行政書士」 第3話 学歴なんか関係ない! 独学で行政書士になる方法 第4話 キャバクラ愛好同盟による外国人ホステス救出作戦
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 賢く確実に節税して、総額500万円以上得する! 本書は、節税に関するあらゆるテクニックをまとめた1冊です。 [目次] 所得税と住民税について知っておくべきこと サラリーマンもやらなきゃぜったい損する確定申告 確定申告を実践してみよう! 第1章 節税対策 基本のき 第2章 節税テク 会社員編 第3章 節税テク 個人事業主編 第4章 知っておくべき節税テク 第5章 節税テク 資産運用編 第6章 お金がもらえる&得する制度 第7章 節税対策用語一覧 会社員や個人事業主、年金受給者も、賢く節税すればお金がもどってきて得します! そのために、節税に関するテクニックを基礎から応用までとことん解説。 たとえば、 「マイナポイント」「ふるさと納税」など、知っておきたい節税の鉄板テク、 「子どもの扶養を夫婦で分散したほうがお得」「産休・育休中は社会保険料が免除される」 「副業すると家賃などを経費として計上できる」といったサラリーマン向けの節税対策、 「収入の浮き沈みが激しい業種のための『変動所得の特例』という特別減税制度」 「税務調査と脱税疑いは似ているようでまったくの別物」など 個人事業主なら押さえておくべき節税のワザ、 「暦年課税を使えば贈与税なしで贈与できる」 「特定の団体に寄付をして所得控除を受ける」など、知らないと損する節税情報、 iDeCoやNISAなど資産運用の活用術、 直接利益を得たり、お金がもらえる制度の紹介etc…… あらゆるケースを徹底的に説明しています。 全ページカラーで、読みやすさも抜群です。 これを機に、自分の税金対策を見直しましょう!
-
4.0
-
4.0現在、我々は世界的な社会経済構造の大変革期に直面している。その結果、戦後作り上げてきた様々な社会保障制度、再分配システムが壊れ、所得格差が世界的規模で拡大してきた。社会保障制度の歴史的背景を見ると、産業革命後のイギリスで成立した救済制度が最初の社会保障制度であることがわかる。当時のイギリスは貧困が蔓延し、大きな社会問題になっていた。また、「貧困=怠惰」と考える社会風潮があり、その制度の中身はかなり貧困者に厳しいものであった。これは今の生活保護受給についての批判と重なる。しかしさまざまな研究により、貧困は不運であり、貧乏人の一発逆転はないことが明らかになった今、私たちはどんな選択をするべきなのか。富の集中は仕方がないこととあきらめるのか。それとも、時代に合った新しい社会保障制度を構築していくのか。世界に類を見ない超高齢社会に突入した日本の行く末を世界は注目している。本書では、不安定な雇用環境が少子化の大きな原因の一つであることを明らかにし、団塊の世代が75歳を迎える2025年までに取り組まなければならない課題と、その解決のための処方箋を提示した。国が中間層を守れない時代がくる前に、将来について真剣に考えるきっかけとなる一冊である。 駒村康平 1964年千葉県生まれ。慶應義塾大学経済学部教授。経済学博士。1995年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。社会保障研究所、国立社会保障・人口問題研究所研究員、駿河台大学、東洋大学を経て、2007年より現職。2009~2012年厚生労働省顧問。2010年社会保障改革に関する有識者検討会委員。2010年~社会保障審議会委員。2012年~2013年社会保障制度改革国民会議委員。著書に『大貧困社会』(KADOKAWA)など。
-
3.7
-
4.3
-
3.5高齢単身者の老後は夫婦世帯より厳しい! 生涯未婚率は年々上がり続け、2015年の国勢調査ではおおよそ男性の4人に1人、女性の7人に1人が生涯結婚することなく人生を終わる計算だ。2020年度の同調査ではさらに上回ることが確実視されている。所得減や非正規雇用といった経済的要因が主な原因とされているが、「おひとりさま」となるのは彼ら彼女らだけではない。離別、死別などで独身者になる人たちも含まれる。 つまり、夫婦同時に死ぬことがない限り、子どもがいない場合、いても同居していない場合は誰もが高齢単身者となるのだ。 しかし、日本の年金制度は夫婦単位で設計されており、しかも持ち家が前提だ。さらに2019年に物議を醸した「老後2000万円不足問題」では、老後重要となってくる介護費やリフォーム代といった項目がすっぽりと抜け落ちている。つまり、ぼんやりしていたら2000万円では足りないというわけだ。高齢単身者は恵まれた一部を除き、困窮する運命にある。実際、生活保護受給者の過半数が65歳以上の高齢世帯で、そのうちの9割以上が高齢単身者なのだ。 元国税調査官が悲惨な老後にならないための「裏ワザ」をあらゆる角度から伝授する。
-
-国から3000万円を返してもらい、所得を倍増させる方法とは? 政治家、官僚、マスコミ、経済学者のウソを暴く! 日本は「赤字国家」でなく、世界一の「黒字国家」である―。 それなのに、なぜ景気が回復しないのか……。 工学博士が整理する、給料を2倍にするためのホントの経済書。 ■ 日本政府は“赤字”ではない ■ 日本は世界で一番のお金持ちの国 ■ 国民一人あたりの貯金は、3106万円!? ■ 「税金を増やしたい」―政治家と官僚の本音 ■ 給料が2倍になるための「2つの条件」 ■ 「温暖化対策」をしているのは日本だけ!? ■ 「資本主義」が「共産主義」の勝った理由 ■ 増税で「財政健全化」は無理 ■ 「経済」は人々の生活を良くしていく社会活動 etc.
-
4.0ドイツ人の平均可処分所得(手取り)は年290万円と意外に低い。しかも、消費税(付加価値税)は19%と高い。にもかかわらず、多くのドイツ人が「生活に満足している」と答えているのはなぜか? いっぽう、サービスが行き届いた世界一便利な国・日本で、日本人の多くが生活に「ゆとり」を感じられないのはなぜか?ドイツ在住29年の日本人ジャーナリストが肌で感じた「ドイツ流・お金に振り回されない」生き方・働き方を明らかにした一冊。
-
4.5
-
3.6
-
4.0国家の行く末を左右するのは「税金」だった! 本書では、「海賊税」「農民税」などの歴史を大きく動かした税金から、現代日本の「ワンルームマンション税」まで、70の「ヤバい税金」を解説します。 【目次】 第1章 歴史を変えた「ヤバい税金」~フランス革命も独立戦争も「税金」のせい!?~ 第2章 世界は「ヤバい税金」であふれている ~乳房税・子ども税・独身税!?~ 第3章 日本にもあった「ヤバい税金」 ~税率300%の「遊興飲食税」とは!?~ 第4章 一見ヤバいけど、実は合理的な税金 ~古代ローマの脱税密告制度とは!?~ 第5章 皆が知らない「ヤバい税金」事情 ~犯罪の収益にも所得税がかかる!?~
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 「老後に1億円」を叶える! これ1冊ですべてがわかる!家計・不動産・株式投資 ※紙版と一部内容が異なる場合があります。 【目次抜粋】 Chapter1 家計アドバイス 凄腕FP 田中香津奈が診断 所得税に注目で目指せ「老後に1億円」! 世帯タイプ別「資産形成」メニュー A家 典型的高収入専業主婦ファミリー 年収1000万でも老後は厳しい…… B家 中小企業お勤めのDINKs 中小でも共働きの底力で老後に1億円達成! C家 中小企業勤めのおひとりさま 税負担が大きくなりがち、さてどうする? Chapter2 株式投資 日本最強アナリスト 馬渕磨理子が解説 「NISAだけ」から一歩踏み込む! 手堅く勝ち抜く「黒字転換2倍株」投資術 STEP1 投資テーマ 知らないで損をしないために! STEP2 IR情報 信頼できる企業を見極める! STEP3 米国株・海外ETF 次は海の向こうに目を向けよ! 今さら恥ずかしくて聞けない 投資Q&A Chapter3 不動産投資 不動産投資コンサルタント 姫野秀喜が指南 絶対に失敗できない会社員が ゼロから始める「不動産投資」虎の巻 不動産専門税理士 萱谷有香が講義 ポイントは「損益通算」と「減価償却」! 会社員大家さん「節税」バイブル Chapter4 富裕層の投資 富裕層研究のプロ 米村敏康が解説 野村総合研究所・最新データから読み解く 「日本のお金持ち」その思考と行動
-
4.5世界のどこかで有事が起きれば最初に飢えるのは日本、そして東京、大阪が壊滅する。気骨の農業学者と経済学者がこの国の危機を撃つ! アメリカの日本支配に加担する財務省、そしてその矛盾は「知ってはいけない農政の闇」となって私たちの生活を直撃する! (目次より抜粋) 第一章 世界経済はあと数年で崩壊する/世界のどこかで核戦争が起きれば日本人は飢え死に/「一億総農民」になれば飢えない/農地を買えなくしてしまった農水省/ビル・ゲイツの「デジタル農業」で東京がスラム化/資本主義は人間の命を大事にしない/「虫が食わないキャベツ」は逆に危険/一番インフレに強いのは米/富裕層は庶民の一万倍も環境を汚染している/地球環境はあと五年で壊れる/「五公五民」の時代がやってきた 第二章 絶対に知ってはいけない「農政の闇」 財務省という「カルト教団」の怖さ/農業政策はお友達企業に牛耳られている/「エブリシング・バブル」は崩壊する/ 「バカ高い不動産」は買うべきではない/「キラキラした都会人」が真っ先に飢え死にする/もともと増税反対の岸田首相が寝返った理由/米食中心に戻せば食料自給率が劇的に改善 第三章 アメリカの「日本搾取」に加担する財務省 「米を食うとバカになる」と洗脳された/少子化対策は高所得世帯を助けているだけ/貧困と格差をなくすための「ガンディーの原理」/中国はツケを世界に回そうとしている/都合のいい日本人/アメリカは有事に援助してくれない/漁業の衰退が尖閣問題を招いた/遺伝子組み換え作物を一番食べているのは日本人/二酸化炭素以上に危険な「窒素・リン濃度」 第四章 最後に生き残るためにすべきこと 鈴木宣弘 インドの輸出規制が与えたインパクト/最初に飢えるのは東京と大阪/酪農家を追い込む「七重苦」/「牛乳不足」と「牛乳余り」を繰り返す理由/「鶏卵不足」に「米不足」が追い打ち/農業を潰し国民を飢えさせる「ザイム真理教」/台湾有事になれば日本人の九割が餓死する/本当は恐ろしい「コオロギ食」/地方で続々と誕生する「生産」と「消費」の新たなシステム
-
3.9「日本の初任給はスイスの3分の1以下」 「日本のディズニーの入園料は、世界でもっとも安い水準」 「港区の平均所得1200万円はサンフランシスコでは『低所得』」 「日本の30歳代IT人材の年収はアメリカの半額以下」 …… 物価も人材もいつしか「安い」国となりつつある日本の現状について、 ダイソー、くら寿司、京都、ニセコ、西川口など、記者がその現場を取材。 コロナ禍を経てこのまま少しずつ貧しい国になるしかないのか。脱却の出口はあるか。 取材と調査から現状を伝え、識者の意見にその解決の糸口を探る。 2019年末から2020年にかけて日経本紙および電子版で公開され、 SNSで大きな話題をよんだ記事をベースに取材を重ね、大幅加筆のうえ新書化。
-
4.0世界のトヨタを擁し、県民所得は全国2位。若者が多く、外国人も多い。日本列島のど真ん中で、東京からも関西からもアクセスの良い場所。名古屋城をはじめ史跡が多く、観光資源だって豊富。 ひつまぶしやきしめん、小倉トースト、味噌カツなどご当地グルメもたくさんある。 なのに、「魅力の薄い土地」と一部でささやかれる。外国人観光客は「トヨタ」は知っていても「アイチ」に興味なし。新幹線で東京→大阪に直行し、「名古屋飛ばし」をされてしまう・・・・・・ そんな、ちょっと残念な名古屋の知られざる魅力を、本書では、日経の転勤族記者が取材とデータで紹介。 「名古屋港の貨物取扱量は全国1位」「税収1000億円増!自治体の稼ぐ力が半端ない」「製造品出荷額は41年間、ダントツ1位」と名古屋の地域経済の強さの秘密をあますことなく伝えるほか、「公立高校2回受験の独自ルールはどうして生まれたか? 」 「大都市圏なのに、広い家に住めるのはなぜか」「料理がみそ仕立てになった理由」など独自文化をまじめに分析。 転勤や出張で名古屋を訪れる人の入門書としてもぴったりな一冊です。 Q台湾の空港で100杯売れる「名古屋ラーメン」ってどんなの? Q名物「ひつまぶし」茶碗ではなくおひつに入れた理由は? Q 100歳祝いに100万円!日本一裕福な○○村 Q夏暑くて冬寒い・・・・・・独特の気候はいったいどうして? Q農業王国なのに、野菜摂取量はどうして最下位?
-
3.5「親リッチ」とは、日本で急増している富裕層の子どもや孫たちのこと。彼らは何にお金を使い、どんな暮らしているのか――。今や隠れた消費の主役とも言える「親リッチ」の実像、多様なライフスタイルに迫る。 日本では近年、富裕層世帯数が急増している。景気低迷が続くなか、所得階層の二極化は確実に進んでおり、野村総合研究所の推計では、2017年には純金融資産保有額が1億円超の世帯が126.7万世帯、2011年比で56.4%もの大幅増加となった。富裕層の大幅な増加は、その子ども・孫世代である「親リッチ」の大幅な増加を意味する。しかし、その実像は専門家にも意外なほど知られていない。 親リッチは、一般に思われているような浪費家ではなく、蓄財に励むばかりの倹約家とも一線を画す。確立されたブランドを好む親世代の保守的な価値観とは異なるイノベーターの一群が静かに台頭しつつある。富裕層マーケットは実態が正確に伝わりにくいと言われるが、本書はさらに情報が少ない「親リッチ」に焦点を合わせ、彼らの消費やお金に関する意識・行動の実態、さらには独特の価値観やライフスタイルを、確かなデータの裏付けや個別インタビューによる興味深い実例とともに深堀りする。
-
4.5「観光立国論」を提唱して訪日外国人観光客激増のきっかけをつくり、「所得倍増論」で最低賃金引き上げによる日本経済再生をとき、「生産性革命」によって日本企業と日本人の働き方の非合理性を指摘した論客が、ついに日本経済低迷の「主犯」に行きついた!その正体は、「中小企業」!これまで、日本経済の強みとされてきた零細、中小企業が、いかに生産性を下げているか、完璧なまでに論証する。そこから導かれる日本再生の道筋とは――。ついに出た、アトキンソン日本論の決定版。
-
4.5マイホームを「廃墟」にしないために、今やるべきこと ○全国に650万戸弱あるマンションのうち、築30年のマンションは約200万戸、2031年には400万戸を超えます。住人が年を重ねて所得が減っていく一方で、当初予定していた修繕積立金が不足し、管理がおろそかになっていきます。その結果、資産価値が下がり、スラム化が進行。住民合意のもと、建て替えを計画しようにも、大半のマンションの建て替えは事実上不可能です。 ○ 資産としてマンションを買うこと、マンションをずっと所有し続けることは、果たして合理的なのか、不安を覚える人も少なくありません。 ○本書は「マンションの長寿命化の道」を提言、「マンション危機」の解決法を示します。欧米では100年、200年の物件が普通に取引されており、価格が下がらないどころか上昇するマンションもたくさんあります。かたや、日本のマンションの管理・修繕の事情はお寒い限りです。所有者の多数派はマンションの資産価値には関心があっても、管理組合運営には無関心です。 ○マンションの所有者と購入予定者は、マンションの管理状況のどこを、どのようにチェックすべきか、管理組合にどう関与していくべきか、「マンションという運命共同体」とつきあうための必須教養を伝授します。
-
3.8私たちは不健康・不摂生な人々に対して安易に「自己責任論」を振りかざしてしまいがちですが、現在ひそかに進行しているのは、所得や家庭環境などにより自らの健康を維持する最低限の条件すら蝕まれつつあるという異常事態です。まさに《命の格差》とも言うべき「健康格差」の危機的な実態に、NHKスペシャル取材班が総力を挙げて迫ります。
-
3.0税理士である著者のもとに寄せられた一件の相続税申告の依頼。 そこで目にとまった一通の「年金支払通知証明書」には、源泉徴収税額22万800円の記載があった。 年金払い形式の死亡保険金に対し、なぜ相続税・所得税の両税が課税されているのか…。 これまで見過ごされてきた二重課税の実態を見抜いた著者は、税理士としての使命を胸に国と争うことを決意した。 相続税・所得税の二重課税処分をめぐり、国を相手に最高裁まで続く長い道のりを戦い抜いた“無骨な税理士”自らが綴った裁判ドキュメント。 勝訴率10%未満と言われる税務訴訟で逆転勝訴を勝ち取り、2010年に大きく話題となった事件の全容を完全収録。
-
-累計70万部突破! 韓国人の若者の夢 「マンションを買えば貴族になれる!」 金融、ハウス・プア問題、青年貧困…、 能力値を超えた「借金」にハマる韓国の社会心理を抉る! ・「家計債務」の総額は、IIF(国際金融協会)データで世界1位 ・韓国国内外の専門家が「1年以内に金融危機が来る」と警告 ・他国には見られないマンション購入の熾烈な戦い ・年間所得の98%が借金の返済で飛んでいく354万世帯 ・「霊魂」まで搔き集めて借金して投資する「ヨンクル」 ・韓国人にとって「家」とは、身分上昇の手段 ・韓国の20代、30代の「生活保護受給者」は、日本の4倍 ・映画『パラサイト』で有名になった「半地下」が高くて住めない理由…… 【目次】 序 章 たとえば、マンションを買うとしたら? 第一章 韓国人いわく「借金は資産である」 第二章 韓国の社会問題「ヨンクル」の末路 第三章 歴代最低の出生率と「半地下」の因果関係 第四章 韓国人の消費を促す「謎の自信」 第五章 韓国 薄氷の「企業債務」 第六章「中国依存」経済の限界 第七章 韓国は「政府債務」もやばい 第八章 韓国特有の賃貸システム 終 章 そのお金はどこから来たのか?
-
3.7なぜ「日本は崩壊する」と言い続けるのか? 財務省の事務次官が「このままでは国家財政は破綻する」という論考を某雑誌に寄稿した。「バラマキ合戦のような政策論を聞いていて、黙っているわけにはいかない」という彼の主張には賛否両論の議論がある。 この論考に対して、筆者は、「会計学でゼロ点、金融工学でもゼロ点」と切って捨てる。 なぜ財務省は、「日本経済が破綻する」と言い続けるのか? なぜ「緊縮財政」「増税」を言い続けるのか? データを重視した数量理論を展開する髙橋洋一氏が、得意の理詰めの論法で財務省の主張を論破する! 【内容】 歪められた「統合政府バランスシート」/コロナの混乱に乗じた増税論/緊縮財政は、国民生活を悪化させる/ レベニュー・ニュートラルではない炭素税はおかしい/MMTとリフレ派の混同/「プライマリーバランス黒字化」の大ウソ/労働者のためではない「賃上げ促進税制」と「金融所得課税強化」/消費増税は経済にマイナスを及ぼす/高齢化で上昇する「国民負担率」は歳入庁で解決/ベールに包まれた財務省の内部構造/財務省とつながりの深い岸田政権/財務省に餌付けされるマスコミ/年金破綻の可能性が極めて低い理由・・・・・・等々 【もくじ】 序 章 矢野論文の評価はゼロ点 第1章 岸田政権下でのZの暗躍 第2章 ケチでがめつい天下り集団 第3章 省益を優先する功罪 第4章 財政破綻を煽る手口 第5章 Zを解体する方法
-
3.3●第一章 満員電車にさようなら 過疎地の定住促進住宅が満室に/政府の移住支援金100万円をあてに/条件は「新幹線が停まる場所」/23区の若者の約4割が地方移住に関心 ●第二章 コロナで人はどこに動くのか 移住希望者の窓口「ふるさと回帰支援センター」/移住相談者の7割は40代以下/コロナ下の移住相談増加トップは茨城県/パソナ本社移転報道で注目の淡路島/リモートワーク移住でも100万円 ●第三章 コロナ移住 人気自治体を歩く 移住者集める過疎の町「みなかみ」/役場の移住担当者が町をアテンド/岡山県の小さな町に続々と関東圏の移住者が/地震と放射線リスクが低い町/移住のきっかけは東日本大震災 ●第四章 「地域おこし協力隊」という移住法 40歳になりますけど間に合いますか/約6割の隊員が退任後に定住/年間報酬は上限280万円に/退任後の起業・事業継承に100万円の補助 ●第五章 半農半エックスのリアル 農業所得の平均値は109万円/400万円の所得確保を目指し支援/半農半Xの先駆け島根県/国から年間150万円の交付金/半農半蔵人で生計を立てる ●第六章 都会人が知らない田舎暮らしのトリセツ 1 住居 空き家バンクとは何か/空き家の改修に1000万円以上/下水道普及率が5割以下の県も 2 生活費 プロパンガスは都市ガスの1・8倍/同じ県内でも5倍以上違う水道代/中古車は予算30万円で十分 3 生活インフラ 4分の1の市町村に高校はない/リモートワークなら実測30Mbps 以上を ●終章 第三の日本
-
3.5
-
4.4はっきり言って始めないと損! 老後資金を940万円上積みも。隠れた優遇税制をフル活用し、「老後貧乏」を防ぐ! 制度の徹底活用法をコンパクトに解説する入門書。 確定拠出年金は、自分で投資商品を選んで年金資産を運用する制度。掛け金全額が所得税・住民税から控除されるほか、運用で得た利益も非課税になります。2017年1月から対象者が大幅に拡大し、現役世代なら誰でも入れるように。会社員はもちろん、主婦や公務員の方も、本書で学んでぜひご活用ください。加入方法といった制度の基本を押さえながら、カギとなる金融機関の選び方や節税効果を最大限に活かす運用術、お得な受給方法などをわかりやすく解説。さらに、企業型確定拠出年金の有利な活用法も紹介します。
-
3.0●この30年で平均所得は100万円下落……なぜ賃金は上がらない? ●理由は国民が平等に貧しくなる「未熟な資本主義」にあった! ●元IMFエコノミストがデータで示す「日本の歪みと処方箋」 物価の高騰、賃金の低迷が続く日本経済。未曾有の物価高にもかかわらず、賃金が「ほぼ横ばい」という異常事態。日本の平均賃金は韓国にも追い抜かされ、同時に歴史的な円安も進行している。かつてIMF(国際通貨基金)に勤め、現在は東京都立大学教授の著者は、「日本経済停滞の要因は、日本特有の構造、いうなれば“未熟な資本主義”にある」と喝破し、そのためには物価と賃金、さらにはそれらの土台となる「企業経営=労働・雇用のメカニズム」を知る必要があると説く。各種国際統計・データから、日本の経済構造の歪みを徹底分析し、日本再生の処方箋を示す1冊。
-
-本物のプロから学ぶ失敗しない方法 税理士の大半は法人税や所得税が専門で、実は相続に詳しい税理士は少ない。その道のスペシャリストだけが知っている攻略法を大公開!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 オトナとして知っておきたい「常識」、あなたは英語で言えますか? 「とりあえず、ビール」、「ありえない!」、「ワリカンにしよう」といった日常の言葉から、「所得格差」「地球温暖化」など社会情勢に関する言葉まで。学校では習わなかった身近な英語を、クイズでマスターしましょう! 「生きた英語」を身につければ、お勉強もぐっと楽しくなります。「アメリカ人小学生と勝負!」のコーナーでは、ネイティブの小学4~5年生の語彙力とあなたの英語力を比較できます。
-
-1.結局、将来受け取れる年金は、所得代替率で何%? A.50% B.40% C.30% 2.年金の受給資格は現在の25年から何年になる予定? A.7年 B.10年 C.15年 はたしてこの問題を正答できる人はどの程度いるのだろうか? 本書は、年金、介護、消費増税などの仕組みについて解説するとともに、詳しく説明されていないがゆえに多くの人が知らない社会保障の真実をクイズ形式で学べる一冊。内容例を挙げると、クイズ1「貧困・格差」のリアル/クイズ2「年金」のリアル/クイズ3「老後のお金」のリアル/クイズ4「転職・起業」のリアル/クイズ5「女性」のリアル/クイズ6「消費税」のリアル/クイズ7「介護保険」のリアル なまじ希望を見出すよりも現実を知ることでしか見えてこない未来がある。自らの頭で社会保障について学ぶことこそが、「老後破産」を免れる唯一の手段なのだから。
-
3.3かつて「一億総中流社会」と言われた日本。戦後、日本の経済成長を支えたのは、企業で猛烈に働き、消費意欲も旺盛な中間層の人たちだった。しかし、バブル崩壊から30年が経ったいま、その形は大きく崩れている。 2022年7月内閣府が発表したデータでは、1994年に日本の所得中間層の505万円だった中央値が2019年には374万円と、25年間で実に約130万円も減少した。もはや日本はかつてのような「豊かな国」ではなく先進国の平均以下の国になってしまった。なぜ日本の中流階層は急激に貧しくなってしまったのか。「中流危機」ともいえる閉塞環境を打ち破るために、国、企業、労働者は何ができるのか。その処方箋を探った。 【プロローグ】稼げなくなった中間層 第1部 中流危機の衝撃 第1章 幻想だった中流の生活 第2章 夢を失い始めた若者たち 第3章 追い詰められる日本企業 第4章 非正規雇用 負のスパイラルはなぜ始まったのか 第2部 中流再生のための処方箋 第5章 デジタルイノベーションを生み出せ 第6章 リスキリングのすすめ 第7章 リスキリング先進国ドイツに学ぶ 第8章 試行錯誤 日本のリスキリング最新事情 第9章 同一労働同一賃金 オランダパートタイム経済に学ぶ 【エピローグ】ミドルクラス 150年の課題
-
3.7税金や社会保険料で所得の半分近くを持っていかれている! 2021年度の負担を見ると、「租税負担28.7%」、「社会保障費負担19.3%」で、合計負担率は、48%まで増えている。しかし、庶民を救うべき政府は増税路線をひた走る。さらなる増税地獄がやってくる。国民全員が死ぬまで働き続けて、税金と社会保険料を支払い続ける納税マシンになる社会。われわれは、暮らしの発想の転換を急がなくてはならない。 本書では、現在の税金、社会保険制度を徹底的に検証。増税地獄の実態を明らかにする。そして、「家計大苦難」時代のサバイバル術をモリタクが伝授する。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 身内が亡くなった際のさまざま届出や手続き等を1冊にまとめたムックです。 「図解」でわかりやすく解説していきます。 01 いつまでに何をする? フローチャートで見る 02 看取りのあとのことをイメージしてみましょう 03 忌引期間5日間でやっておく 04 相続の手続きはプロにまかせてスムーズに! 05 身内が亡くなったあとにする 【第1章】 通夜・葬儀・告別式にまつわる手続き 《弔いの基本を知る》葬儀の基礎知識と準備 《死亡診断書と死亡届》死亡診断書と死亡届の受け取りと提出 《埋火葬許可書の申請》埋火葬許可申請書の提出と許可証の交付 《葬儀社を決める》葬儀社選びのポイント 《葬儀費用》 葬儀にかかる費用の目安 《葬儀社との打ち合わせ》葬儀社との打ち合わせと交渉のコツ 《葬儀後のこと》葬儀後のあいさつや事務処理 【第2章】 葬儀後にするさまざまな手続き 《届出・手続きの確認》期限と優先順位を確認しよう 《健康保険》健康保険の届出と手続き 《年金の受給停止》年金の受給停止と未支給分の請求申請 《世帯主の変更》世帯主変更届の提出 《準確定申告》故人の所得税の申告 《給付金の申請》葬祭費と埋葬料の申請 《給付金の申請》高額療養費の払い戻しを受ける手続き 《遺族年金の受給》受給できる遺族年金の確認 《遺族年金の請求》遺族年金の請求手続き 《寡婦年金と死亡一時金》寡婦年金と死亡一時金の請求手続き 《変更・解約手続き》各種契約の名義変更と解約の手続き 【第3章】遺言・相続にまつわる知識と手続き 《改正相続法と相続の流れ》相続手続きの流れを把握する 《遺言書の確認》遺言書を確認する 《相続人の確定》相続人を確定する 《財産の特定》遺産の種類と調査 《相続放棄》相続放棄と限定承認 《遺産分割》遺産分割と遺産分割協議書の作成 《不動産の相続》不動産の分割方法と相続手続き 《金融機関の手続き》銀行や証券会社での手続き 《自動車の相続》自動車の相続手続き 《そのほかの財産》そのほかの相続に該当する遺産 《相続税の申告と納税》相続税の申告と納付手続き 《相続税控除と特例》相続税のさまざまな控除と特例 【第4章】 お墓と法要 四十九日法要と納骨、その後の供養 《法要・納骨》忌明け(四十九日法要)から喪明け(一周忌法要)まで 《お墓と供養》さまざまなお墓のタイプと供養のカタチ 《お墓の購入》 新たにお墓を建てる 《墓じまい》墓じまいの手続き 巻末付録① 巻末付録②
-
-トランプ政権発足で、アメリカの変質は決定的になりました。自由や民主、多様性を尊び、戦後の国際秩序を主導してきた超大国の約70年ぶりの内向き宣言。「米国第一」の旗を振り、保護貿易、移民制限、孤立主義にまい進するトランプ氏は、米国を世界の火薬庫に変えてしまいました。我々が知っていたアメリカはもう存在しないのです。 米国民がこの異端児に未来を託したのはなぜか。そこには建国から240年以上を経た人工国家の機能不全と、それに対する民衆の失望やいら立ちがあります。 (1)上位1%の富裕層が富全体の4割を握る (2)白人の比率が今後30年間で5割を割る (3)0.01%の大口献金者が政治を牛耳る (4)実質200兆ドルの借金を次世代に残す 米国では経済、人種、政治、世代の上記の「4つの分断」が深刻化し、多くの低中所得層、白人層、被支配層、若年層が置き去りにされているのです。そんな国の形に絶望した中年白人の死亡率が上昇し、先進国でも異例の夢を持てぬ社会になりつつあります。 いまの米国はもはや「無限の未来」を謳歌できない。そんな置き去りにされた人々の怒りが爆発し、未曽有のポピュリズム旋風を吹かせたのです。 ギリシャ神話のパンドラの箱は、あらゆる災厄を解き放ちました。その最後には「エルピス(希望)」が残ったといいます。トランプという劇薬を投じた後の米国にエルピスは残るのでしょうか。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 知らなきゃ損! 節約と節税のワザをマスターしてお金を貯める! 本書は、誰でもすぐにできる節約&節税のテクニックを余すことなく解説した1冊です。 節約というと、「ケチケチ生活はストレスになりそう」「結局、そんなに貯まらないでしょ?」、 節税に関しては、「専門知識が要るのでは?」「手続きなどが面倒くさそう」といったイメージがあります。 でも、本書があれば大丈夫! 無理なく節約できるさまざまなテクニックや、賢く節税するワザを丁寧に紹介。 「そんな仕組みだったんだ!」「私にもできる!」と 気づきが得られるので、日々の生活やお金に対する意識が変わります。 全ページカラーで、写真や表を多用しているため読みやすさ抜群です。 【目次】 「賢く節税する最強のマル得テクニック集」 所得税と住民税について知っておくべきこと サラリーマンもやらなきゃぜったい損する確定申告 確定申告を実践してみよう! 第1章 節税対策 基本のき 第2章 節税テク 会社員編 第3章 節税テク 個人事業主編 第4章 知っておくべき節税テク 第5章 節税テク 資産運用編 第6章 お金がもらえる&得する制度 第7章 節税対策用語一覧 「苦労せずに毎月5万円!?お金が貯まる節約術!30代から備える、安心な老後のための節約ライフ」 1 日常生活編 2 お買い物編 3 行楽編 4 補助金・投資編 5 掃除編 6 低コスパ・アイテム編 7 お料理編 ※本書は 「賢く節税する最強のマル得テクニック集」(2022年1月)と 「苦労せずに毎月5万円!?お金が貯まる節約術!30代から備える、安心な老後のための節約ライフ」(2019年6月)を 合本化した作品です。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。