無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
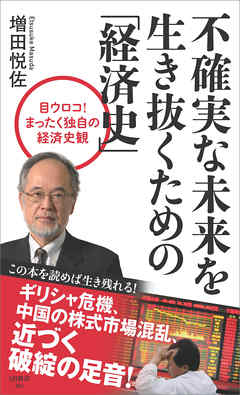
◆官製相場、株高、格差拡大……歴史が物語る「資本主義のカラクリ」!
◆「経済史」をひもとくことで見えてくる日本経済の行く末、世界経済の向かうところ。
ケインズやマネタリストなど時代を先導したさまざまな経済思想から、最近のピケティ「21世紀の資本」まで、博覧強記の著者がひも解く!
◆ピケティ「21世紀の資本」が巷間話題となっているが、所得・資本格差の拡大は資本主義においてとくに目新しい課題ではない。
ではなぜこんなにも注目を浴びたのか?
それは、もともと日本が欧米型パワーエリートが住む社会とは別種の、資本格差も知的格差も世界一小さい国であり、つい最近までそうだったからだ。
◆20世紀の日本経済はどのように推移し、現代へと至ったか。バブル経済、規制緩和とグローバリズム、増税など、過去の事例を照らし合わせれば、21世紀の経済の流れはおのずからわかる!
・小泉改革とアベノミクスはまるきり違う
・地方創生会議は、経済効率が悪いからこそ企業が逃げていく場所に強引に人と資源を縛り付ける愚策
・たとえインフレ率を上回る実質成長率があったところで、それは4~5%という威勢のよい水準に戻ることは土台無理
・デフレを是とした着実な経済運営は可能だった……
など、目からウロコの着眼点で、アベノミクスのその先の日本経済がむかえる状況まで大胆に見通す!
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。