分断作品一覧
-
-1998年から始まる民主化以降もなお残るインドネシアの非自由主義的な性質の解明に向け、スハルト体制が強固に作り上げた統治理念(「パンチャシラ」(=5つの国家原理))を明らかにし、一貫して窺える暴力の実態に迫る。未解明とされる過去の惨事の詳細な分析を通じて、現在のインドネシア政治との連続性を浮き彫りにする。 【主要目次】 第一章 無法の暴力が支える調和 一 問題設定 二 既存研究における位置づけ 三 本書の構成 第二章 パンチャシラ――変動する体制、変わらない国家原則 一 はじめに 二 パンチャシラの誕生――独立準備調査会 三 国軍とパンチャシラ 四 パンチャシラの変遷 五 反政党とパンチャシラ 六 スハルトのパンチャシラ 七 スカルノとスハルト――その違いと連続性 第三章 九・三〇事件 一 はじめに 二 スハルト体制が描く「大衆の自発的行動」 三 地方における虐殺 四 一体化する国家と民衆の暴力 第四章 タンジュンプリオク事件 一 はじめに 二 事件の経緯 三 スハルトのパンチャシラとイスラーム知識人 四 タンジュンプリオクにおけるイスラーム・シンボル 五 情報統制 六 対イスラーム作戦としてのタンジュンプリオク事件 七 統治手段としての「暴徒」 第五章 「謎の銃殺」事件 一 はじめに 二 ペトルス事件の経過 三 ペトルスに対する反応 四 ペトルスに見るスハルト体制の国家と社会 第六章 一九九八年五月暴動――体制崩壊と残された分断 一 はじめに 二 背景――激化する抗議運動 三 暴動の発生 四 陸軍における権力闘争 五 暴動と体制崩壊 終章 統治理念と暴力 一 調和を支える暴力 二 一九九八年五月暴動被害者のその後 三 スハルト体制の遺産 ロシアによるウクライナへの侵攻から、1年半以上が経過した。この間、この戦争にもっとも影響を受けたヨーロッパはどのように戦争に対処してきたのか。各国・各地域の研究を牽引する気鋭の研究者が、これまでを振り返り現況を再確認するとともに今後のゆくえについても言及する。 【主要目次】 序 ウクライナ戦争はヨーロッパをどう変えたのか(細谷雄一) I ウクライナ戦争が変えたヨーロッパ 1 ロシアによるウクライナ侵略がEU拡大に及ぼした変化(東野篤子) 2 NATOはどう変わったのか――新たな対露・対中戦略(鶴岡路人) 3 ウクライナ「難民」危機とEU――難民保護のための国際協力は変わるのか?(岡部みどり) II ヨーロッパ各国にとってのウクライナ戦争 4 ウクライナ戦争とイギリス――「三つの衝撃」の間の相互作用と国内政治との連関(小川浩之) 5 ロシア・ウクライナ戦争とフランス(宮下雄一郎) 6 ドイツにとってのロシア・ウクライナ戦争――時代の転換(Zeitenwende)をめぐって(板橋拓己) 7 ウクライナ戦争とロシア人(廣瀬陽子) 8 ロシア・ウクライナ戦争とウクライナの人々――世論調査から見る抵抗の意思(合六 強) 9 NATOの東翼の結束と分裂(広瀬佳一) あとがき
-
-「20世紀最後の巨人」の脱神話化を試みる決定版 世界を牽引した指導者、「最後の偉大なフランス人」シャルル・ドゴール。彼は巧みな戦略家であり、ひとつの政策に固執する反面、融通無碍な政治家でもあった。派手さを嫌う性格でありながら、ショーマンシップも発揮した。悲観と楽観のあいだを揺れ動き、自信を喪失したかと思うと、自己をフランスと一体化させ、君主であるかのように振る舞った。人びとの心にほとんど宗教的な崇敬の念を吹きこんだ。国民の統一を希求したが、その手法や政策はフランス社会に分断と対立を生み、ドゴールが憎悪の対象ともなった。 従来のドゴール伝が礼賛か批判かに偏りがちだったのに対して、本書は時代ごとの世界情勢や政治的状況、経済的環境のなかにドゴールを位置づけ、著作、書翰、発言、さまざまな同時代人の証言、新公開されたフランス国立文書館収蔵のドゴール文書など膨大な資料を駆使して、その全体像を中立かつ客観的な視点から記述する。さらに本書の大きな魅力は、資料の綿密な分析に基づいて、「人間ドゴール」の複雑な性格を浮びあがらせている点にある。英国の世界的権威による、ドゴールを主役にした「20世紀フランス史」。
-
-「20世紀最後の巨人」の脱神話化を試みる決定版 世界を牽引した指導者、「最後の偉大なフランス人」シャルル・ドゴール。彼は巧みな戦略家であり、ひとつの政策に固執する反面、融通無碍な政治家でもあった。派手さを嫌う性格でありながら、ショーマンシップも発揮した。悲観と楽観のあいだを揺れ動き、自信を喪失したかと思うと、自己をフランスと一体化させ、君主であるかのように振る舞った。人びとの心にほとんど宗教的な崇敬の念を吹きこんだ。国民の統一を希求したが、その手法や政策はフランス社会に分断と対立を生み、ドゴールが憎悪の対象ともなった。 従来のドゴール伝が礼賛か批判かに偏りがちだったのに対して、本書は時代ごとの世界情勢や政治的状況、経済的環境のなかにドゴールを位置づけ、著作、書翰、発言、さまざまな同時代人の証言、新公開されたフランス国立文書館収蔵のドゴール文書など膨大な資料を駆使して、その全体像を中立かつ客観的な視点から記述する。さらに本書の大きな魅力は、資料の綿密な分析に基づいて、「人間ドゴール」の複雑な性格を浮びあがらせている点にある。英国の世界的権威による、ドゴールを主役にした「20世紀フランス史」。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 今なお傑出した外交家として歴史に名を刻む仏大統領ドゴールの、政権復帰から退陣までのヨーロッパ秩序再編構想とその国際的反応を分析する本書は、欧州統合と大西洋同盟の二つの国際秩序において「ヨーロッパ」が立ち上がる様子を活写する。膨大な量の仏・独・米・欧州共同体等の一次史料から見えてくるのは、冷戦と分断という秩序を書き換え、組み直し、そして突き破ろうとしたアデナウアー、ケネディ、ブラントなどの思惑の交錯・衝突と、冷戦・欧州統合・脱植民地化・独仏関係が連関しながら展開される多国間外交の姿である。その外交の末に我々が目にするのは、冷戦構造を侵食する重層的なメカニズムの形成であった。従来の外交史研究では捉えきれなかった、国民国家を超える政治空間の構築を解明する、「ヨーロッパ構築史」の画期的な試み。第25回渋沢・クローデル賞本賞受賞。 【目次より】 序章 戦後ヨーロッパ国際関係史の再構築 第一部 「大構想」の実現を目指して 一九五八─一九六三:ドゴール=アデナウアー時代のヨーロッパ国際政治 第一章 アングロサクソン、アルジェリア、世界政策 一九五八─一九六〇:ドゴール政権復帰後のフランス外交 第二章 政治同盟交渉 一九五九─一九六二 第三章 米仏二つの大構想と西ドイツ外交 一九六一─一九六二 第四章 エリゼ条約の成立一九六二─一九六三 第二部 「大構想」後のヨーロッパ国際政治の危機とその克服 一九六三─一九六九:デタントと共同市場 第五章 ドゴール外交の「頂点」 一九六三─一九六六:自主外交とデタントヘの転回 第六章 ヨーロッパ・デタント 一九六三─一九六八:西ドイツによる東西関係変革の模索 第七章 ヨーロッパ統合の危機 一九六三─一九六五 第八章 ヨーロッパ共同体の定着 一九六五─一九六九 終章 統合されたヨーロッパと多極化された世界 あとがき 註 史料・参考文献一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 川嶋 周一 1972年生まれ。政治学者、明治大学政治経済学部政治学科教授。北海道大学法学部卒業、同大学院法学研究科修士課程修了。パリ第4大学DEA(Diplome d'Etudes Approfondies)取得。北海道大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学。専門は政治学、国際政治史、ヨーロッパ政治外交史(EU研究含)。 著書に、『独仏関係と戦後ヨーロッパ国際秩序――ドゴール外交とヨーロッパの構築 1958-1969』(渋沢・クローデル賞)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1955年の夏、シカゴからミシシッピにやってきた黒人少年は、地元 白人女性に「狼の口笛(ウルフ・ホイッスル)」を吹いたとして「私刑(リンチ)」によって裁かれ殺害された。 事件から半世紀以上を経過して沈黙を破った白人女性当人による告白を基に、著者 タイソンンはエメット・ティル殺害事件の真相を追求していく。 「黒獣姦魔」から「南部のユリ(白人女性)」を守る」という白人至上主義の神話に込められ、人々の心を縛ってきた南部の歴史と閉鎖社会の欺瞞を炙り出す。 アメリカの根深い人種差別のみならず、事件の背景にある南部の白人男性が黒人から白人女性を守るというエゴイスティックな騎士道精神がどのようにして生み出されてきたのか。「人種」という概念は、白人支配を正当化するために作り出された「虚構」に過ぎず、女性もまた男性のもとで抑圧された生活を強いられた。この南部の歴史と神話がどのように人々の心を縛ってきたのかを考えることで、今日の混迷するアメリカの分断にたいする理解を深めることができる。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 戦後アジアにおいて日本とは何であったのか?―アジアへの関与が「経済進出」として語られることの多いなか、冷戦や革命、脱植民地化といった国際政治の潮流に占める日本の位置づけを探る本書は、1950年代から60年代中盤のインドネシアをめぐる攻防にその答えの鍵を見出す。巨大な国家規模と豊富な資源に加え、地政学的観点からも海域アジアの「要」であるインドネシア。そのインドネシアが、急進的ナショナリズムを掲げたスカルノ時代からスハルト体制下の開発の時代へと大きく転換した軌跡は、戦後アジアの政治潮流と国家建設模索のひとつの典型であった。ベトナム戦争へと収斂していくアメリカの冷戦政策、東南アジアにおけるイギリス帝国の解体、中国の急進化、そしてナショナリズムや革命から開発の時代へというアジアを覆った巨大な変容のなかで、日本は何を目指し、どのように振舞ったのか、各国の思惑と駆け引きが渦巻く多国間関係史を立体的に描き出す。海によって分断されているように見えて、実は何よりも海でつながれた「海のアジア」。本書は、従来の東アジア国際政治史では解明されることのなかった、いわば「海のアジア」の戦後史なのである。 【目次】 序──戦後アジアにおける日本とは何だったのか 第一章 インドネシア賠償をめぐる国際政治 一 「アジア復帰」の模索 二 インドネシア賠償交渉経緯 三 インドネシア内戦とアメリカの介 四 賠償交渉の妥結──両国の思惑 五 米英の対応 六 欧米とアジアの間で 第二章 マレーシア紛争仲介工作(一)──日本の関与の端緒 一 アジア関与の深化 二 マレーシア紛争 三 インドネシアの国内事情 四 紛争の本格化 五 池田首相の和平工作 六 和平工作の行方 第三章 マレーシア紛争仲介工作(二)──アメリカとの連携 一 ロバート・ケネディの仲介工作 二 イギリスのいらだち 三 日米の説得 四 ベトナム情勢とアメリカの強硬化 第四章 マレーシア紛争仲介工作(三)──中国との「綱引き」 一 インドネシアの国連脱退 二 川島正次郎の仲介工作 三 中国との「綱引き」 四 シンガポールの分離独立とイギリスの方向転換 第五章 九・三〇事件とスカルノ体制の崩壊 一 九・三〇事件 二重のクーデター 二 日本の対応 三 スカルノか、スハルトか 四 米英の対応 五 大量殺戮の進行 第六章 開発体制の構築と日本 一 積極的関与の検討 二 経済危機の到来と権力闘争の決着 三 イギリス主導策の模索とマレーシア紛争の終結 四 インドネシア債権国会議と開発体制の構築 終章 戦後アジアの変容と日本──冷戦・革命・脱植民地化・開発 注 あとがき 宮城 大蔵 1968年生まれ。政治学者。上智大学総合グローバル学部教授。1立教大学法学部卒業、一橋大学大学院法学研究科公法・国際関係専攻修士課程修了、同大学院法学研究科国際関係専攻博士後期課程修了。一橋大学博士(法学)。専門は、アジア国際政治史。 著書に、『バンドン会議と日本のアジア復帰』『戦後アジア秩序の模索と日本』『「海洋国家」日本の戦後史』『現代日本外交史』『橋本龍太郎外交回顧録』(五百旗頭真共編)『戦後アジアの形成と日本 歴史のなかの日本政治5』(北岡伸一監修。編著)戦後日本のアジア外交』(編著)『普天間・辺野古歪められた二〇年』(渡辺豪共著)などがある。
-
-1巻6,050円 (税込)分断と圧力に直面する冷戦期東アジアにおける制限の下で表現の自由が許された特別な空間、日本。核や米軍基地、アジア諸国との関係、高度経済成長に伴う様々な矛盾をめぐって、アメリカの従属的パートナーを前提とするのではない別のあり方=対抗文化を目指す表現者が生まれた。文学・絵画・映画・演劇といった多彩な対抗的表現はいかに生み出されたのか。表現と想像力の豊かな可能性をたどる--。 敗戦後の日本の歩みは米軍占領下から始まった。すでに始まっていた冷戦に規定されて、対日占領政策の基調は、非軍事化・民主化から、経済復興・反共防波堤建設へと変化していく。日本が独立を回復したのは冷戦下の局地的熱戦としての朝鮮戦争のもと、アメリカの同盟国としてであり、以後、対米従属のもとでの経済復興・経済成長が政治的・経済的基調となり、社会や文化の動向もそれに強く規定されることになった。 しかし、冷戦期の日本においては、基地や核やアジア諸国との関係をめぐって、あるいは同時期に進行した高度経済成長にともなう諸矛盾をめぐって、この基調にそって発想することを自明の前提とせず、別のあり方を構想しようとする想像力をそなえた人々が数多く存在していた。本書はそのような人々の遺した多様な表現を「対抗文化」と捉え、表現と社会の関わりを重視しつつ、文学・思想史・歴史学・社会学などの人文社会科学から実像に迫る。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「国家の物語」から「ディアスポラの物語」へ 資本主義の高度な発達によるグローバル化が加速した現代社会。猛烈に肥大化したハリウッド映画に代表された「映画理論」からも、グローバル化の陰で第三世界の国々に飛び火しつつある「ナショナリズムの論理」からも解放された、もうひとつの《空間》を作り出すことへの積極的な参画。本書の「映画読解行為」は新たな《闘いの場》を創造する。 (1)ナショナル・シネマとジェンダー(2)インディペンデント・トランスナショナル・シネマの可能性(3)植民地映画の系譜(4)フランス映画のアイデンティティ危機(5)植民地映画『望郷』分析(6)ベトナム革命映画の成立過程(7)南北分断のジェンダー化(8)革命映画とジェンダー(9)『インディア・ソング』アンヌ・マリー=ストレッテルの死(10)アイデンティティと政治性(11)白人植民ブルジョワ社会の終焉(12)声の導く時空間(13)『姓はヴェト、名はナム』政治的映画の製作(14)「ベトナム女性の声」の構築過程(15)国家とジェンダーの関係(16)声の中の「ホームランド」(17)ナショナル・シネマにおける国家/国民とジェンダー(18)新しい女性表象の創造。図版資料多数収載。
-
-ヘイトスピーチ、分断と対立、新たな全体主義……。誰もが表現者になれる一方で「言論の自由」の価値が揺らぐ現代。古代ギリシアから啓蒙主義、反ファシズム、インターネットの時代まで、言論の自由が果たしてきた役割を追い、その意義を問い直す。解説/森村進
-
-エミール・デュルケムの集合意識論を批判的に継承し、フランス社会学派第2世代の中心を担ったアルヴァックス。近年、海外でも再評価が進むアルヴァックスが1925年に執筆した「記憶の社会学」の嚆矢が本書である。 社会のメンバーがみずからの過去を想起するとき、「記憶の社会的枠組み」がいかに機能するのか、過去の出来事の記憶を社会のメンバーはどう組織化し、「集合的記憶」を形成するのか、「集合的記億」は社会にどのような影響を及ぼすのか――。 アルヴァックスは本書でまず、個々人の夢や記憶などを論じるベルクソンやフロイトなどの哲学や心理学を緻密に検証する。そのうえで、「家族」「宗教」「社会階級」などを切り口に、社会集団にとって記憶が、人々を統合するばかりでなく、ときに分断もするというその社会的な機能を析出する。 記憶をどう継承するのか、歴史と社会の関係をどう考えていくのかが様々な局面で問われる今日にも、集合的記憶という視点から問題提起を差し向けるアクチュアルな古典的名著。
-
-【『ブループリント』上下巻を1冊にまとめた電子書籍オリジナル合本版!】 分断と格差の時代に、「ファクトフルな希望」を示してみせよう。 経営者から科学者まで各界トップ絶賛の全米最新ベストセラー人類史、待望の邦訳! 「これほどの『希望』を感じて本書を読み終えるとは、予想もしなかった」 ——ビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者) 「いま世界にはびこっている排外主義は、必ず克服できる。私は本書で『何をすべきか』『何ができるか』を教わった」 ——エリック・シュミット(Google元CEO) 「人類の進化論的な本質は『善』であり、共感的な文明を生み出せる。これほどタイムリーかつ見事な本はない」 ——スティーブン・ピンカー(ハーバード大学教授『/21世紀の啓蒙』) 「進化の設計図(ブループリント)」を知れば、「分断」を乗り越えられる。 経済格差、人種、国家間対立……。今ほど「分断」が強調される時代はない。だがちょっと待ってほしい。こうした分断はなぜ起こるのだろう? それは進化の過程で、私たちが「仲間」を愛し、尊重する能力を身につけたからだ。この能力こそが、世界の命運を握る最大のカギである。 そこで本書は、南極探検隊の遭難者コミュニティからアメリカのユートピア運動、果てはAmazon.comのスタッフコミュニティまで、古今東西のあらゆる「人間社会」を徹底検証する。さらにはサルやクジラなどの「動物社会」をも。 繁栄するのはいかなる社会か? そこには驚くべき共通点があった――。科学界からビジネス界まで、全方面から絶賛されたニューヨークタイムズ・ベストセラー、待望の日本語版。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 20カ国語に翻訳されたグラフィックノベルのベストセラー。 完成に22年をかけた歴史大作。 街は静かに破滅へと向かう――。 人びとはいかにしてナチスに傾倒していったのか。 共和国は人びとになにをもたらしたのか? リベラルな大都市からファシズムの拠点へ。 ジェイソン・リューツは、1920年代のドイツの大都市を、住民の目を通して複雑に描きだしている。彼らの人生は、優しさと残酷さ、愛と憎しみ、セックスと死の十字路で交差する。煙草のけむりが充満するサロン、崩れかけた歩道、にぎやかな駅、華やかなカバレットなど、街そのものが活気づいていた。 ワイマール共和国時代、ベルリンはヨーロッパの最先端であり、創造性、政治思想、性的自由が、忍び寄るファシズムの足音にもみ消される前に明るく輝いていた――このような時代背景を見事に表現した傑作。 2019年、グラフィック文学賞優秀賞受賞。 2019年、バーモント・ブック・アワード受賞。 示唆に富み、現在の社会問題を映しだすグラフィックノベル 1928年、マルテ・ミュラーは引き寄せられるように脈動する首都ベルリンへ向かった。芸術アカデミーに通いはじめたマルテは、それからの数年間、時代のあふれる豊かさと悲惨さを経験する。カバレットやサロンで米国のジャズが流れ、性の解放が進むいっぽうで、経済危機と過激な政治活動が路上をすでに埋めつくしていた。矛盾する世界が並存し、交錯する1930年代初頭の街で、マルテはみずからのアイデンティティをたしかめようとする。しかし、ドイツという国がそうであったように、未来への選択を迫られていき……。 ジェイソン・リューツは、崩壊が進むワイマール共和国を舞台に、マルテの運命とほかの人物たちの人生を結びつけ、この時代の複雑なスペクタクルをつくりあげていく。言論の力への信頼を失ったジャーナリスト、クルト・ゼフェリング、政治のうねりのために家族がバラバラになった労働者グートルン・ブラウン。はびこっていく反ユダヤ主義の標的にされたユダヤ人の少年ダーヴィト・シュヴァルツ……ベルリンの街角で彼らの運命が交錯する。 「『ベルリン』のマジックは、リューツが古い新聞や写真から、時空間的に自分から遠く離れた都市を呼び起こす方法にある。本書の結末は息を呑むほど衝撃的である」――エド・パーク(ニューヨーク・タイムズ書評) 「ナショナリズムと反ユダヤ主義がふたたび頭をもたげるなか、 本書は政治がいかに早く毒に変わるかについての教訓をあたえてくれる」――レイチェル・クック、ガーディアン紙 「圧倒的なストリート シーンと、この街に住む多くの人びとの内面を掘り下げることで、本書は私たちが知っている物語を新しい方法で語っている。それは私たちが昨日を見つめなおし、今日との比較を可能にしてくれる」――ニナ・マクラフリン、ボストン・グローブ 「職人技と忍耐の驚くべき偉業。ワイマール時代の最後の数年間を描いた本書は、ファシズムが家族を分断し、友情を終わらせる過程を考察していることで、かつてないほど切迫している。リューツは、ディケンズ規模のキャストを丁寧かつ一貫した筆致で描き、登場人物たちは、政治的忠誠、闘争・同化の選択を余儀なくされる」――サム・シールマン(この10年間のベストコミック)、ガーディアン 「狭い心と気まぐれな心があり、街全体を焼き尽くすほどの怒りがある。しかし、そこには愛情、利他主義、勇気、他者を助けようとする意欲、物事を改善しようと続ける努力もある。読者は期せずしてベルリンに親しみを感じている自分に気づくだろう。リューツの慎重で精巧なこの作品は、すべての人の心に響く」――ケイトリン・ロズベルグ 、The A.V.Club
-
-“ブラザー”・ホリスが語る 貧困、暴力、人種差別、投票権、文化の闘い! 本書は、アメリカ公民権闘争に関する研究で 見落とされがちだった地道な草の根の活動を、 ミシシッピ州の活動家ホリス・ワトキンズが語る 貴重な証言である。 そこには黒人たちの長い日常的な闘争、 多様な活動の歴史が語られ、読み手の注意を引く。 著書ホリス・ワトキンズは、 1960年代の若い黒人たちを主な構成員とする 学生非暴力調整委員会(SNCC)の複雑な内情、 白人学生ボランティアの導入をめぐる指針の変容などを、 他組織や社会とのかかわりをもたせながら赤裸々に語る。 さらに「公民権運動」という言葉は メディアの作った言葉として1960年代に限定して 使いつつ、それよりも長期にわたる諸々の活動の実態を、 公民権の新たな指導者育成組織サザーン・エコー創設と その今に至る活動なども射程に入れて、 人が人として生きる生活感覚から深く詳らかに語る。 21世紀の今も ミシシッピ州で公民権の活動を続けるホリス・ワトキンズは、 実践経験から知恵を練り上げる。 その語りは、現代社会の差別や分断の諸問題を 「自分で考えて新しい扉を開いてほしい」 という、若者への強いメッセージである。
-
5.01巻4,400円 (税込)北米で発売初日89万部! 空前の売れ行きを達成したベストセラー 信念に燃え、あらゆる難局に全力で立ち向かった日々が再現される 「短所もあるけれど、才能にあふれる思想家たちが考え抜いてつくり上げた、ゆるぎない、それでいて変化も受け入れる体制。それが私の納得できるアメリカなのだ」(本書より) 2009年。ハワイ州で生まれ育ち、父は黒人、政治家としてのキャリアは浅く、若干47歳と異例尽くめのアメリカ合衆国大統領が誕生した。「YES WE CAN」をキャッチフレーズに世界中で大フィーバーを巻き起こし、人種、民族、政治的分断に橋を架けようと、困難に立ち向かい続けた日々を、オバマ自身が詳細なディテール、関係者の発言とともに、生き生きと描く。
-
-世界の分断と対立を乗り越えるために―― コネクティビティと信頼を鍵として、イスラーム文明の知を可視化する シリーズ刊行開始! 「イスラーム的コネクティビティに基づいた信頼構築」とはいかなるものなのか。国家体系や経済、境域における翻訳と規範の変容、思想と戦略知の展開、移民が形成するコミュニティ、紛争地域での平和構築、人文情報学の可能性といった切り口から全8巻のシリーズのねらいを総合的に論じる。 【主要目次】 序章 イスラームから考える「つながりづくり」と「信頼」――今後の世界を見通す鍵として(黒木英充) 第1章 瀬戸内から世界に広がるつながり――ある日本人ムスリムの足跡をたどる(岡井宏文) essay1 他者を理解するために必要なこと――幕末の「日本人」のイスラーム経験から(黒田賢治) 第2章 多様なひとびとをつなぐ翻訳――イスラームの各地への展開と知の伝達(野田 仁) 第3章 異なることばをつなぐ言語――インド洋世界におけるウルドゥー語の役割(須永恵美子) 第4章 未来を拓くイスラーム経済のつなぐ力――その思想と歴史から学ぶ(長岡慎介) 第5章 イスラームで国をつくる――宗教・国家・共同体(近藤信彰) essay2 宗教がひしめきあう都市で人がつながる――18世紀イスタンブルの公衆浴場から(守田まどか) 第6章 不信から生まれる信頼――モロッコ、ベルベル人の「寛容」を中心に(池田昭光) essay3 信頼と不信が垣間見えるとき――シリアで見聞きしたこと(黒木英充) 第7章 信頼のためのイスラーム思想と戦略――現代南アジアにおける政治運動の正当化(山根 聡) essay4 中東で政治的な信頼をはかる――イラクでの世論調査から考える(山尾 大) 第8章 神の教えの実践とヴェール――信頼から信仰を読み解く(後藤絵美) 第9章 「テロリスト」に対する暴力による解決と信頼のゆくえ――フィリピンからの問い(石井正子) 第10章 見えないつながりを描き出す――デジタル人文学の可能性(熊倉和歌子) essay5 保育園で「つながり」を考えてみた――双方向的探究から広がる新しい世界(太田(塚田)絵里奈) 付録 文献リストとサイト案内(荒井悠太)
-
4.0第一次大戦下、相対論完成の最後のピースを探し求めるアインシュタインに立ちはだかった、あらゆる試練――平和主義者の弾圧、妻との確執、食糧難、病、そして協力者たちとの分断。ドイツに閉じ込められた「世紀の理論」はいかにして世界に羽ばたいたのか。憎しみあう大国のはざまで揺れ動いた科学者たちの群像。
-
4.7「ありそうもない、稀有な、不可思議な、奇跡的な」ルーツこそが本物だった。植物や、翅のない昆虫、塩水に弱い両生類やサルなど、“海越えができない”はずの生きものたちが、大海原を渡って分布を広げた歴史が明らかになりつつある。地理的な障壁によって生物の分布域が分断されてきたとする「分断分布」偏重のパラダイムに、変革が起き始めていると著者は指摘する。新たに浮上してきたのは、動植物があちらの陸塊からこちらの陸塊へと奇跡の航海を遂げた、躍動感とサプライズに満ちた自然史である。歴史生物地理学の世界を覗き込めば、多彩な生きものたちの姿はもちろん、プレートテクトニクスや気候変動、化石記録に分子時計といった幅広い知見がひしめき合っている。個性豊かな研究者たちが、生物の来歴をめぐって激しく論争した経緯も、本書は臨場感たっぷりに映しとっている。第III部では、読み進むにつれてますます「ありそうもない度合い」の高い海越えの事例が登場するので、その頂点までどうかお見逃しなく。それらはいずれも、著者が最後に語る「私たちの世界は、なぜ今このような姿をしているのか?」という大きな描像の大切なピースなのだ。
-
-「機械で読む」ことで何ができるのか? デジタル・ヒューマニティーズ×日本文学研究から生まれた驚くべき成果とは? デジタル時代の文学リテラシーがこの一冊でつかめる、最前線の研究をいち早く翻訳! 本書では、数字と文学のあいだの概念上の分断を超えて、批評理論と統計学・計量的読解を融合した新たなアプローチから、 言語やテキストにひそむ人間の認識の問題にせまり、日本文学の読み直しを通して世界文学へと接続する。 データ・サイエンスの影響をうけた北米発の〈デジタル・ヒューマニティーズ〉の手法をつまびらかにする、入門書にして文学研究に量的革命を巻きおこす挑戦の書である。 デジタル情報化とAI革命が猛スピードで進行しつつある現在、人文学においてもデジタル技術を研究に用いた〈デジタル・ヒューマニティーズ〉が注目されている。文学研究における〈デジタル・ヒューマニティーズ〉は北米で独自の発展をとげ、膨大なデータをコンピュータで処理し、ジャンルや文体といった大きな対象にアプローチする手法が確立されつつある。 日本文学に対して初めて本格的にこの手法を適用した本書は、夏目漱石の文学論にさかのぼりながら日本におけるデジタル思考の文芸史を概観し、青空文庫を例にテキストのアーカイヴとサンプルの意味を分析する。 さらに「私小説」というジャンルの謎や、ジェイムズ・ジョイスで広く知られる「意識の流れ」の技法と日本の近代文学の関係、そして大日本帝国の時代の日本語小説における人種の表象がどのような記述によって生み出されてきたのかを、テクノロジーを駆使して膨大なテキストを解析することで明らかにする。 数字で文学を読み解き、文学研究における数字の値打ちを吟味する、グローバル情報化時代の文学研究を実践する必読の一冊である。 日本文学者・翻訳家 カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授マイケル・エメリック氏推薦! 「明晰かつ雄弁で、主張には細心の注意が払われた『数の値打ち』は文学研究へのコンピュータ・アプローチの歴史と現況をめぐる魅力的な案内であり、ケース・スタディそれ自体も豊富かつ説得的、しばしば驚きである。この本を長年待ち望んでいたのは私ひとりではないはずだ。」
-
4.0『サピエンス全史』のユヴァル・ノア・ハラリ大絶賛! 「国家がいかに危機を乗り越えたか? 明快な筆致に引き込まれる。本書は、地球規模の危機に直面する全人類を救うかもしれない」 遠くない過去の人類史から 何を学び、どう将来の危機に備えるか? ペリー来航で開国を迫られた日本、ソ連に侵攻されたフィンランド、軍事クーデターとピノチェトの独裁政権に苦しんだチリ、クーデター失敗と大量虐殺を経験したインドネシア、東西分断とナチスの負の遺産に向き合ったドイツ、白豪主義の放棄とナショナル・アイデンティティの危機に直面したオーストラリア、そして現在進行中の危機に直面するアメリカと日本・・・。 国家的危機に直面した各国国民は、いかにして変革を選び取り、繁栄への道を進むことができたのか『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』『昨日までの世界』で知られるジャレド・ダイアモンド博士が、世界7カ国の事例から、次の劇的変化を乗り越えるための叡智を解き明かす!
-
-■感染症リスクにどう向き合い、回復を軌道に乗せるか。国際経済、デジタル、貧困と格差、途上国など、各領域の専門家が最新データと緻密な分析をもとに、課題と展望を多面的に読み解く。 ■コロナ危機が襲い、国際協調が弱体化するなかでの新興国経済の状況を分析し、日本がとるべき道を探る。コロナ危機が明らかにした格差、世界経済の行方、国際関係の再構築といった課題に対し、貿易、国際金融、技術、格差、多国籍企業、国際秩序・協調などの地域横断的なテーマ視点からの分析と、中国、韓国、インド、ブラジル、南アフリカなど個別地域に焦点を当てた分析の両方から立体的なアプローチを試みる。ジェトロ・アジア経済研究所の専門家たちが分担執筆。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、「高野切」の全文字を、かなの単体、二字連綿、連綿、漢字の順に分類、収録した字典です。「高野切」は、その一部が高野山にあったことから、「高野切」の名で親しまれてきました。もとは巻子本でしたが、後に分断されたために「切」の名称で呼ばれています。古今和歌集の写本のなかでは最も古いものですが、かなの完成された姿を見ることができ、「かなの原点」「古筆の王者」と賞賛されてきました。美しい書は数多くありますが、「高野切」ほど見る者の心を落ち着かせ、また襟を正させるような古筆はありません。書も技法中心の現代にあって、改めて見直されてよい至高の古筆といっていいでしょう。「高野切」は、三人の能書家の寄合書で、それぞれ第一種、第二種、第三種と呼ばれていますが、本書には第一種と第三種を収録しています。第一種は墨づきが美しく、温雅で、気品に満ちています。第三種は若々しく清らかな書風が、見る者を魅了します。この字典が、「高野切」との新たな出会いの場になってくれれば幸いです。
-
4.0【 推薦!】ピーター・バラカン氏 デトロイトやメンフィスより語られないシカゴのソウル・ミュージックを支えたコミュニティが目に浮かびます。 共同体あってこその音楽シーン、そのことを痛感しました。 * * * 音楽産業とブラック・パワー、そして公民権運動の結びつきを、 膨大な当事者インタビューと資料から解き明かす、決定的ノンフィクション! --------- ◆カーティス・メイフィールド ◆ジェリー・バトラー ◆ダニー・ハサウェイ ◆アース・ウィンド&ファイアー ◆ミニー・リパートン ◆チャカ・カーン ◆テリー・キャリアー……。 ──ソウル界に燦然と輝く星々は、音楽とともに、世界を変革しようとした。 * * * 〈 音楽の変革 × 社会の変革 〉 人種隔離の時代に、シカゴのソウル・ミュージシャンが行った変革とは何だったのか? 自主レーベルの設立、黒人経営企業の立ち上げ、地元コミュニティ、メディアとの協働、独自の流通網の開拓……。 シカゴ・ソウルの生成を中心に、ファンク、ハウス、Hip hopの時代まで駆け抜ける、唯一無二の音楽/社会のドキュメント! --------- 【目次】 ■はじめに 第1章・廊下とラジオ ──コミュニティの変化と新しいメディアが音楽を変えた 第2章・アイム・ア・テリング・ユー ──新興のアーティストと起業家が拓いた新時代 第3章・ウィアー・ア・ウィナー ──ミュージシャン、活動家、教育者たちが音楽業界を築き、発展させた 第4章・サイケデリック・ソウル ──シカゴの一九六〇年代のカウンター・カルチャーが社会運動と音楽の方向を変えた 第5章・ア・ニュー・デイ ──一九六〇年代の闘いの答えとなったアフリカ中心主義と明確な政治的声明 第6章・リズムがすべてではない ──企業の力が一九七〇年代のブラック・ミュージック、商業、政治を動かした 第7章・サウンド・パワー ──ファンク、ディスコと結束、分断、希望 第8章・未来予想 ──リイシュー、サンプリング、若いアーティストたちが再考するソウルの歴史 ■謝辞 ■訳者あとがき ■原注 ■ディスコグラフィー ■参考資料
-
5.0ニューヨークの街角から、現代都市の「分断」を学びほぐし、「共生」の可能性をさぐる 今世紀初頭以降、ニューヨーク・ブルックリンで拡大してきたジェントリフィケーション。その過程とメカニズムを考察し、人種やジェンダー、階級による「分断」が錯綜する時代に生きる住民たちの日常生活と闘争、そして「共生」への試みを、精彩に富む筆致で描き出す。 【主要目次】 序章 なぜブルックリンに注目するのか――ポスト・コロナ都市の実験室 I ブルックリンの都市変容と住民コミュニティの再編――ジェントリフィケーションが引き起こす「身体的共存」 1章 現代都市を変える力学――ローカルな都市空間とトランスナショナルな不動産・金融複合体 2章 複数のブルックリンと予期せぬ共存 Ⅱ 対立の争点としてのジェントリフィケーション 3章 「立ち退き」というパンデミックな感覚 4章 地元で「部外者」になる――その場にいながらの排除 5章 地域の新たなアクターたち――ジェントリファイヤー論再考 6章 空間にひもづけられた「差異のるつぼ」――ミクロな差異の可視化と空間的共存の帰結 Ⅲ ジェントリフィケーションの再解釈と「共生」 7章 反ジェントリフィケーションの多様な実践 8章 人種横断的な共生の実践――再解釈されるジェントリフィケーション 9章 パンデミック時代の共生 終章 「分断」を学びほぐす
-
-貴族、公民権運動家、IT起業家、ラッパー、YouTuber… 私たちの思考と行動は「服装」で決まっていた。 14世紀の宮廷、フランス革命、公民権運動、ジェンダー、人種、宗教問題まで、 姿を変えながら人びとに影響を与えてきた「ドレスコード」とは何か? 法律家にして文化評論家、スタンフォード・ロースクール教授の意欲作 17世紀、ルイ14世は自分と廷臣以外の赤いソールの靴着用を禁止し、21世紀、クリスチャン・ルブタンは赤いソールの商標を独占した。彼らは赤い靴底ではなく「権力と特別感」を守ろうとしていた。なぜなら「服装」にはそれだけの効き目があると知っていたからだ。 宮廷と修道院、革命と公民権運動、娼婦と淑女、ギャングとセレブ。「階級・性差・貧富」を表し、固定するものとしてドレスコードは機能していた。そしてフランス革命後の「国家と個人の誕生」とともに、服装は自由と平等を実現し、一人ひとりの個性を表し、格差を破壊するものになる――はずだった。 それにもかかわらず、アメリカの高校は現在も服装規定を増やし、レストランは髪型を理由に従業員を解雇する。「流行なんてどうでもいい」とTシャツを好むIT起業家たちは、「ファッションに無関心という最新の流行」に夢中になっている。ドレスコードに隠されたメッセージは形を変え、今なお生きているのだ。 ジャンヌ・ダルクは異性装でパワーを手にするもタブーに倒され、おしゃれをした黒人は「身のほど知らず」だとリンチにあい、現代の女性はメイクをしてもしなくても批判される。イタリア人の無造作なネクタイは絶賛され、スコッチテープでネクタイを固定したトランプは馬鹿にされる。服装は女性の趣味ではない。人類がパワーゲームのために用いてきた暗号であり、今でも社会と個人に密接に関わる重要な要素だ。 私たちがドレスコードに縛られるのはなぜだろう? 服装が取り決め、ルールや法、裁判所命令の対象になるほど絶対的になるのはどんなときか? ドレスコードが、平等や個人の自由に関する社会規範の変化と衝突したら何が起きるのか? ドレスコードが役立つのはどんなときで、必要以上に抑圧的になったり、不当なものになったりするのはどんなときか? 歴史をひもとけば人は服につくられてきた。それなら服装は本当に個人が選択しているのか? 時代の流れに知らぬ間に同調し、周囲に好印象を与える――あるいは人の気を引くためにその服を着ているのだろうか? 本書は、歴史を通したファッションの法則を探り、服装――自己表現の最も私的かつ公的な媒体――が持つ個人的、社会的、政治的な意味を明らかにしていく。階級、性差を表す「暗号」だった歴史的なドレスコードを読み解くとともに、人種、ジェンダーの平等をめぐる戦いの中で、服装がどのような役割を果たしてきたのかを考察する。そしてこのテレワークの時代、消えない分断の世界で、「これからのドレスコード」を問う。
-
4.0既得権をなくす! 独占を壊す! 自由な社会をどうつくるか? 若き天才経済学者が描く、資本主義と民主主義の未来! 支配なき公正な世界のデザインとは? 富裕層による富の独占、膠着した民主主義、巨大企業によるデータ搾取…… 21世紀初頭の難題を解決する、まったく新しいビジョン! 「私はずっと、テクノロジーと市場の力を用いて平等な社会を実現する方法を探してきた。本書こそが、その方法を示している」――サティア・ナデラ(第3代マイクロソフトCEO) 「深淵かつオリジナルな本書の分析は、あなたの世界観を根底から覆すだろう」――ジャン・ティロール(2014年ノーベル経済学賞受賞者) 経済の停滞、政治の腐敗、格差の拡大。この状況を是正するには、発想を自由にして抜本的な再設計を行わなくてはならない。社会を成立させるための最良の方法は市場と考えるが、最も重要な市場が今は独占されているか、存在していない。 だが、真の競争が可能な、開放的で自由な市場を創出することによって、格差を縮小し、繁栄をもたらし、社会の分断を解消できるはずだ。すなわち、オークションを要とするラディカル・マーケット(競争原理によって誰もが参加できる自由な取引市場)である。 本書は、移住の自由化への反感、機関投資家による市場の独占、巨大なプラットフォーム企業によるデータ労働の搾取といった、21世紀のさまざまな問題を解決し、繁栄と進歩を可能にするために、古い真理を疑い、物事を根底まで突き詰め、新しいアイデアを提案する「ラディカル」な提案の書である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 貧困や格差の拡大、テロ/人種差別といった剥き出しの暴力と排外主義の台頭、他者へのバッシング……グローバル化を背景に国境を越えて再編される現代の越境社会は、いま様々な場面で分断を抱えた危機的状況にある。 移民、難民、テロ、犯罪、ヘイトスピーチ、多文化共生、福祉財政、災害被災地――国内外の具体的事例と現場を「越境」と「想像力」に着目しながら読み解き、そこに潜む問題性を浮き彫りにする。他者と対話し理解しようと努める人びとの営みを「越境的想像力」と位置づけ、他者の経験を想像力によって自身のリアリティーに取り込む重要性を指摘する。社会的分断を乗り越えるために、私たちの想像力をバージョンアップするアクチュアルな成果。
-
-
-
4.6※収録作品(単行本に収録したインタビューや文庫解説等は含みません) レイテ海戦の大戦果はソ連軍の北海道侵攻を招き、日本は南北分断国家となった……。激動の時代を戦艦〈大和〉そして超大型護衛艦〈やまと〉として戦った一隻の艦と、歴史に翻弄されながらも未来へと歩み続ける軍人一族・藤堂家を軸に、日本の戦争と戦後を描く戦記巨篇。 急逝した著者の初期代表作三巻を合本、初期短篇「晴れた日はイーグルにのって」を併録。 ※収録作品(単行本に収録したインタビューや文庫解説等は含みません) 征途 I 衰亡の国 II アイアン・フィスト作戦 III ヴィクトリー・ロード 晴れた日はイーグルにのって
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2021年7月から9月にかけて東京オペラシティアートギャラリーにて開催され、大きな注目を集めた、加藤翼の美術館での初個展「縄張りと島」のカタログであり自身初の作品集。 人々が知恵を出し合い、ロープと人力だけで巨大な構造体を引き倒したり、引き起こしたりする作品の原点とは何か? 「引き倒し」から「引き興し」への展開点は何だったのか? 東日本大震災の年に福島県いわき市で行なった《The Lighthouses – 11.3 PROJECT》(地域のシンボルである灯台を模した構造体を被災者や住民とともに引き起こした)、トランプ大統領誕生の年にアメリカのシアトルで制作した《Woodstock 2017》(4人の白人男性が互いに縛られながらアメリカ国家を演奏)といった代表作をはじめ、他にもマレーシア、メキシコ、ベトナム、香港など、世界各地で制作してきたこの15年間ほどの作品の数々を最新作まで網羅。 作品画像だけでなく、制作時のスケッチ、制作現場の写真、アイデアメモや図面など、資料も多数収録。作品解説ともなる対談2本と論考2本がそれらの間を有機的に縫って展開することで、作品理解にさらなる奥行きが生まれるつくり。もちろん「縄張りと島」展の展示風景も現場の雰囲気そのままに紙面で再現。 自然災害、都市開発、環境破壊などで地域のコミュニティが解体の危機に瀕するなか、人々が自発的に参画し、一体となって何かを実践することの意義を照らし出す。そして、ロープにみなぎる緊張そのままに、「ともに引っ張る」ことの原初的衝動を探りながら、分断や対立を超えた「協働」の可能性を見据える。ブックデザインは吉岡秀典(セプテンバーカウボーイ)。 「縄張りや境界線のない大空を自由に飛翔するすぐれた洞察力と批評性こそ、加藤翼というアーティストのたぐい稀な作家性に違いない」……堀 元彰(本書より)
-
-今、もっとも求められる世界的権威による最高の知見、ついに翻訳版刊行! 【ノーベル経済学賞受賞 ウイリアム・ノードハウス激賞】 「新型コロナウイルスの科学的・社会的問題を真っ直ぐに射る一冊。生物学、医学、疫学、社会学のバックグラウンドをもつクリスタキスは、この複雑な問題を解き明かすための高最高の方程式をもっている。神々は、この本を書くために彼を創ったと考えたくなるほど、賢明で鮮明で魅力的だ」 【米ベンチャー投資家・京都大学特任准教授 山本康正絶賛】 「すべてのリーダー必読! 同じ構造の悲劇を繰り返してはいけない。感染症があぶりだした世界レベルでの社会の『不都合な真実』の検証。科学は都合のいいところだけを利用され、伝えられ、メディアの監視は機能していない。自称専門家の意見がメディアの都合によって増幅されてしまう。次の感染症に限らない危機も必ずやってくる。その前に今回の教訓を真摯に受け止め対策につなげなければならない」 新型コロナウイルスの問題は、「科学VS.経済」の対立構造があるとされ、格差、貧困、差別など、秘められた問題を白日の下に晒す。この問題を論じられる人物こそ、著者ニコラス・クリスタキス。医師であり公衆衛生学の研究者であり、社会的つながりを解き明かしたネットワーク科学の先駆者である知の巨人が、ここ100年間の疫病研究と最新の科学的エビデンスをもとに、疫病と”人類知”の攻防を描く。 病原体という「昔なじみの小さな敵」は、どのようにやってきて世界を変えたのか? パンデミック期、パンデミック余波期を科学と社会の両面で丹念に解き明かすとともに、ポスト・パンデミック期に言及。 人類は数々の疫病と戦って歴史を紡いできた。わたしたちは「希望」を必ず見いだせる! 【目次より】 第1章 小さな大敵との出会い ウイルスのゲノムが描く感染地図 第2章 昔なじみの敵が戻って来る 隔離と追跡とプライバシー/ウイルス検査のしくじり 第3章 引き離すこと 感染症にはワクチンより経済発展が効く/政治化するロックダウン 第4章 悲嘆と恐怖と嘘 年収と性別で悲しみの度合いが異なる?/「つながり」の多い人がスーパー・スプレッダーになる? 第5章 わたしたちと「彼ら」の分断 病原体は無差別だが人は差別をする 第6章 一致団結する 利己的な遺伝子をもつ「ヒト」はなぜ助け合うのか? 第7章 深遠かつ永続的な変化 新しい自律と自主の誕生/サウンドバイト時代の科学の役割 第8章 疫病はどのように収束するか 脅威の測定基準は「失われた人生の年数」/疫病と希望は人類の一部
-
3.0格差と分断が広がる社会のリアルな人間模様を通し、「正義とはなにか」「正義の執行とはどうあるべきか」を読者に真摯に問いかけ、ともに考える。オバマに任命され、トランプと闘い罷免されたNY連邦検事が在職期間7年半の法廷秘話を明かす現代の「罪と罰」。
-
4.5分断と対立を克服するための処方箋 各国の社会は今、ナショナリズムやマルクス主義といった古びたイデオロギーやポピュリズムに流される低所得・低学歴層と、グローバル化する世界で利益を追求して豊かな暮らしを謳歌する高学歴エリート層とに分裂し、対立している―。そんな溝を埋め、資本主義をふたたび多くの人びとに豊かさと希望をもたらすものへと軌道修正していくにはどうすればよいのか。著者は、資本主義が本来もっていた責任感と義務感に基づく「助け合いの精神」の復興を説く。そして、そのためにはデジタル化の進展で希薄になり、価値観の相異から内部に対立さえ抱えるようになった国家や地域社会といったコミュニティの住人としての、アイデンティティーの回復が重要だと指摘する。 開発経済学の分野を牽引してきた第一人者ならではの深い洞察をベースに、かつて鉄鋼業で栄えながら深刻な状況に陥って回復の途上にある英国シェフィールドの労働者の家庭に育った個人的な体験も交じえながら、資本主義の倫理的・道徳的側面に着想を得た方策の数々を平易な言葉で述べる。グローバル社会を生きるあらゆる世代に向けて、未来への指針を具体的に提示した野心作。
-
5.0「肉体は他人である」という気づきが、すべてを変える。 感謝と喜びで、生と死を超えるーー 死生観論争に終止符を打つ、壮大な宇宙法則の全貌が明らかに! AIが人間を滅ぼす時代に必読。 第1章 「肉体は他人」という真理 第2章 人類最大の悲劇とは 第3章 「心魂一如の愛」と「心魂分断の恩讐」 第4章 「肉体は他人」革命 第5章 物質世界と意識世界 第6章 「ZEROの法則」と「COSMOSの法則」 第7章 コスモスの意識に基づくコスモスの世界 第8章 COSMOSの法則に基づく生命原理 第9章 「COSMOSの法則」に基づく生命原理の検証 第10 章 「COSMOSの法則」と「CHAOSの法則」の検証 第11 章 コスモスの意識と私の意識の相関性 第12 章 「COSMOSの法則」の結論と確信 関連特集
-
-各自がそれぞれの属するコミュニティの論理に従って「正しい」と信じて疑わないことを行っているだけなのに、それがコンフリクトを生み、解決が難しい状況となる。このような<話の合わない>事例は、社会にあふれている。 本書は、このようなコンフリクトが引き起こされる状況を「制度複雑性」と解釈し、解決の糸口を探る。題材にするのは、科学と事業の関係であり、その連携が複雑化する中、いかに科学の論理と事業の論理の対立をマネジメントし、イノベーションを生み出していくのか、その方策を追究する。 協働に伴って、必然的に顕在化する複数の論理の錯綜とコンフリクト。これを分断ではなく、新たな創造性を生み出す機会へと昇華させるための、「制度ロジック」の視点からのアプローチである。 イノベーションを生み出すべく、科学と事業の関係に関与する実務家や、さらには、<話の合わなさ>に直面し、苦悩する人々にも、多くの示唆を与える研究成果をまとめている。加えて主要な章には「ノンテクニカルサマリー」を収録し、一般の方にも読みやすく工夫され、好評を得ている。
-
-インターネットの影響を技術、ビジネス、社会と多角的に報告するデジタル業界定番の年鑑『インターネット白書』。1996年の発行以来、27年目を迎えた2023年版では、世界を席巻するジェネレーティブAIの進展、Web3の重要概念であるDAOの政策面からの考察、ステルスマーケティング規制や欧州のデータ流通に関する法制度の進行など、ビジネスに直結するインターネットの最前線を38人の専門家が解説しています。また、この一年はロシアによるウクライナ侵攻に関連したサイバー攻撃やフェイクニュースによる情報戦も展開されました。この分断の時代に私たちのインターネットはどうあるべきか。原点となる「インターネットガバナンス」の視点に着目しています。
-
-安全保障とビジネスの間で選択を迫られる日本。だが、米中のデカップリング(分断)は言葉が独り歩きしているところもあります。米ソ冷戦時代と違って、今の米中は経済面で相互依存が進んでおり、切り離そうにも簡単に断ち切れない関係ができあがっているからです。どの分野でデカップリングが進み、どの領域では進まないのか。デカップリングが予想される分野は実際にはどんな形で、どの程度、分断が進むのか。冷静な議論と慎重な見極めが必要です。米中のデカップリングの実像と背景、今後の展望を、宮本雄二、鈴木一人、土屋大洋、詫摩佳代、関山健、戸堂康之ら各分野の第一人者が結集し、多角的に分析。波乱の時代の座標軸を提供します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、「三色紙」の全文字を、かなの単体、二字連綿、連綿、漢字の順に分類、整理したものです。「三色紙」の名称で親しまれている「継色紙」「寸松庵色紙」「升色紙」は、古来より古筆の最高峰として称賛されてきました。継色紙の品格の高さ、寸松庵色紙の強靭な線とリズム、升色紙はふくよかで清らかな線、散らしの斬新さが日本人の心に迫ってきます。これら三つの色紙は、いずれももともとは十数センチ四方の冊子本であったことが知られています。平安時代の姫君の手のひらに納まる、まことに愛らしいものであったようです。後世にバラバラに分断され、色紙として珍重されるようになったのは、数ある古筆の中でもさん然と輝くこれら名筆の運命だったのかもしれません。しかし、今日その大半が失われてしまったのは残念な限りです。「三色紙」の字書を編纂するにあたって、現存する資料は可能な限り参照したつもりですが、もはや行方知れずとなってしまったものもあります。しかしその逆に、近年新たに発見されたものも少なくありません。本書を改訂する機会があれば、時代の移り変わりとともに、より充実した字書に育ててゆきたいと思います。字書に整理分類された文字からは、一首一葉の形で見るのとはまた違った顔を発見できます。臨書、倣書の勉強では、その古典にどれほど肉薄できるかが重要ですが、この字書がその一助となってくれれば幸甚です。
-
-
-
-《 シカゴ大学の緊急救命医が告発する[人種差別×医療格差 ]の実態 》 「差別と貧困」が医療ケアに爪を立てる日常に挑み続けた、あるシカゴER医師の葛藤と前進、そして憤懣と挑戦に満ちた熱きドキュメント。 --------- 〈 格差が分断する、医療という名の戦場 〉 通院するカネがなくて病状を悪化させた者、銃撃事件に巻き込まれた者、麻薬中毒者……。 救命救急室に担ぎ込まれるのは、社会構造と医療保険制度から取りこぼされた貧困層の黒人ばかり。 ──アメリカ型資本主義の価値観は医療システムの中に勝者と敗者を生み続け、“敗者のいのち” は常に軽んじられてしまう。 社会で正義がおこなわれないかぎり、医療もまた、正当に人を救えるものにはなりえない。 これは、私たち日本人にとっても対岸の火事ではない。 --------- 〈序文寄稿〉タナハシ・コーツ(2016年タイム誌『世界で最も影響力のある100人』選出) 「本書は、パンデミックさなかのERの1年を描いているのみならず、複雑な医療システム全体、そしてそれを捻じ曲げる分配の不平等について果敢に検証する。思い出してほしいのは、新型コロナウイルスの流行が始まったばかりの頃、ウイルスには〝肌の色は無関係〞と言われていたことだ。たぶん、本物の危機にあっては、人間誰もが共有する弱さを克服するため、誰もが立場を超えて力を合わせることになる、そう信じたかったのだろう。 しかし、それから3年が経過した今、黒人とラテン系の人々はこのパンデミックのあいだに平均寿命が3年も短くなった。これは白人の3倍に当たる。あの時点で予想してしかるべきだったのだ。そして今こそ、利口になるべきだ」 --------- 〈訳者〉宮﨑真紀(「訳者あとがき」より) 「全編を通して、ドラマ『ER』さながら救急医療現場に緊張感と切迫感がみなぎり、黒人コミュニティを少しでも癒そうとする著者の情熱と不平等への怒りが満ちあふれていて、読む者を圧倒する。そして、格差構造の根深さをあらためて思い知らされる。いや、日本でも、貧困層の無保険問題、地方と都市部の医療格差など、医療環境に確かに深い溝が存在していることを忘れてはならないだろう」 --------- 【目次】 ■序文……タナハシ・コーツ ■1………2020年2月 ■2………2020年3月 ■3………ジャネットへの手紙 ■4………2019年11月(パンデミックの前) ■5………ニコールへの手紙 ■6………2020年5月 ■7………ロバートへの手紙 ■8………2020年7月4日 ■9………ダニアへの手紙 ■10………2020年8月 ■11………リチャードへの手紙 ■12………2020年9月 ■13………フェイヴァースさんへの手紙 ■14………2020年11月 ■15………母への手紙 ■謝辞 ■訳者あとがき
-
3.0《 民主主義の危機から、戦争は現れる 》 格差、移民、差別、陰謀論……分断社会に解決策を示せないリベラル諸国。 渦巻く不安と不信、露わになるナチズムの脅威。 アメリカを代表する歴史家が描く、緊迫の第二次大戦前夜。 --------- 「他国が脅威として現れたとき、民主主義はどう対応すればいいのか」 「自国のリーダーが無謀で危険、あるいは無能とわかったとき、私たちはどう行動すべきか」 平和を望む民意を背景に、ヒトラーに譲歩を重ねる英首相チェンバレン。 ナチの脅威を一人訴え続けるチャーチル。 孤立主義の立場から機を窺う米大統領ローズヴェルト。 国内で粛清の嵐を吹き荒らすソ連のスターリン。 様々な思惑が交錯しながら、世界は戦争への道を進んでいく──。 --------- アメリカを代表する歴史家が、1930年代から40年代初頭における民主主義の危機と覚醒を鮮やかに描く。 〈 『ドイツ人はなぜヒトラーを選んだのか──民主主義が死ぬ日』続編 〉 --------- 【目次】 ■主な登場人物 ■プロローグ……民主主義の危機 〈 PARTI・危機 〉 ■1……首相の野望──「生存圏」の拡大 ■2……グライヴィッツ市で何があったのか──ポーランド侵攻のきっかけ ■3……「同罪」──赤軍将校の命運 ■4……「計画は模索中」──チャーチル、チェンバレン、ローズヴェルト ■5……「王は、ここでは理解していらっしゃる」──スキャンダル ■6……「将来がとても心配だ」──イギリス空軍戦闘機、スピットファイア ■7……鉄格子をこすり続ける──移民受け入れ 〈 PARTII・ミュンヘン 〉 ■8……「これだ、私が求めていたのは!」──将官たちの企て ■9……「この危険という茨のなかから」──ミュンヘン会談 ■10……銃口を突きつけられて──民主主義の苦難 ■11……「不和の種を蒔く」──分断と差別 〈 PARTIII・戦争 〉 ■12……「国民のみなさんに申し上げねばなりません......」──宣戦布告 ■13……「これがプロイセンの将校か!」──指導者への抵抗 ■14……「力を合わせて、ともに進もうではありませんか」──就任演説 ■エピローグ……「始まりの終わり」──大西洋憲章 ■訳者あとがき ■参考文献 ■主な出来事
-
-【生き残りをかけた知恵の戦い】 米国主導「戦時」の半導体戦略、中国のデカップリング対応と軍民融合発展戦略、外交孤立の台湾の選択、メガFTA掛け持ちのASEAN、アジア・ゼロエミッション共同体構想――。本書は、東アジアの各国・地域のほか、西側陣営をリードする米国や「グローバルサウス(南半球を中心とした途上国)」の一角として発言力を強めるインドの動向を調査し、戦略物資の半導体をめぐる攻防や地域エネルギー安保の問題も分析。相手に対する脅威認識から始まる安全保障の措置が逆に相手の脅威となり、際限のない軍拡競争を招いてしまうことを「安全保障のジレンマ」という。経済安保の諸政策も取り組み自体が新たなリスクを生じさせるリスクがあり、地域におけるリスク軽減策についても検討した。分断を超えてどのような経済安保戦略を構築すべきかを問う。
-
4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2000年に入る頃、数十年にわたる社会主義の失敗により、出版や流通、 書籍販売が疲弊しきっていたエジプト。書店を開くことなど不可能だと 思われた時代に、彼女は小さな書店「Diwan(ディーワーン)」を始めました。女性店主はあらゆる困難に直面しますが、それでもエジプトを代表する独立系書店チェーンへと成長を遂げます。 西欧と中東が出合うカイロで、それぞれの文化を共存させ、後世に伝えるということ、読書家や女性たちの心安らぐ場所であるということ。書店としての使命をまっとうすべく、彼女は闘います。分断されたこの世界を変え、希望をつなぐために。 これは、一冊分ず つ、世界を変えていこうとした、カイロの革新的な書店主の実話の物語です。
-
3.6ウクライナ侵攻前史、米露75年間の覇権争い 諜報の分野では帝政時代以来の歴史を持つソ連・ロシアと、第二次大戦後にCIAを設立した諜報の素人の米国。ソ連は冷戦時代、東欧を支配し、その勢力を全世界に広げようとしていた。一方、米国はソ連を封じ込めるために、さまざまな諜報戦(政治戦)をくりひろげた。 冷戦に勝利した米国は、その後の戦略をあやまり、NATOをいたずらに拡大させたことで、ロシアは危機感を抱く。それをもっとも切実に感じていたのが、冷戦崩壊を現場で見ていたKGBのプーチンだった。彼は権力を握るや、ただちに反撃に出る。インターネットとソーシャルメディアを駆使した彼の政治戦は、前例のないものだった。米国はいつの間にか世論の分断で民主主義の危機にさらされ、民主主義のプロセスを無視するトランプに率いられることになった。しかも、トランプはロシアの影響下にあるという……。 ウクライナ戦争の前史、戦後75年間の諜報活動と外交の深層からサイバー攻撃の脅威まで、『CIA秘録』のピュリツァー賞受賞作家が機密解除文書を徹底検証! 国際情勢に関心がある読者のみならず、民主主義の未来を真剣に考える方々にもご一読いただきたい。
-
4.2※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 私たちの背中を押してくれる、10の英知 どんなに行き詰まっているように見えても 社会をよくする解決策は、まだまだ世界中で生まれている。 ビジネス・非営利・行政の枠を越えて活躍する第一人者たちが これからのリーダーシップ、コラボレーション、 事業創造、資本主義のあり方を示す、珠玉の傑作選。 1人の個人、1つの組織、1つのアイデアでは解決できないほど、現代の社会課題はますます複雑になっています。だからこそ、多くの人が組織やセクターの壁を越えてつながり、小さなアクションをともに積み重ねることで、大きなインパクトを生み出そうと挑戦しています。より幅広いコラボレーションに求められるのが、「共通言語」となるコンセプトと実践的な知見です。 『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー』(SSIR)は、2003年にスタンフォード大学で創刊された、世界最大級の「ソーシャルイノベーション」専門のメディア。社会の新しいビジョンの実現に向けて活動する人々が集い、それぞれの知見と学びを共有するコミュニティとして世界各地に広がっています。 日本版創刊に先立つ本書は、SSIRでこれまで発表された論文から、セクターや分断を越えて人々が協働して、よりよい社会をつくるときに求められるアイデアや方法論を厳選した一冊です。 さらに巻末にはスペシャル対談「日本の『社会の変え方』をどう変えていくか」(入山章栄×篠田真貴子)を収録。日本でのソーシャルイノベーションの実践に役立つ事例や知恵を共有します。
-
4.61976年生まれの著者は、植木屋を営む夫と独立開業の地を求めて福島県いわき市の山間部に移り住む。震災と原発事故直後、分断と喪失の中で、現状把握と回復を模索する。放射線の勉強会や放射線量の測定を続けるうちに、国際放射線防護委員会(ICRP)の声明に出会う。著者はこう思う。「自分でも驚くくらいに感情を動かされた。そして、初めて気づいた。これが、私がいちばん欲しいと願っていた言葉なんだ、と。『我々の思いは、彼らと共にある』という簡潔な文言は、我々はあなたたちの存在を忘れていない、と明確に伝えているように思えた。」以後、地元の有志と活動を始め、SNSやメディア、国内外の場で発信し、対話集会の運営に参画してきた。「原子力災害後の人と土地の回復とは何か」を掴むために。事故に対する関心の退潮は著しい。復興・帰還は進んでいるが、「状況はコントロールされている」という宣言が覆い隠す、避難している人びと、被災地に住まう人びとの葛藤と苦境を、私たちは知らない。地震と津波、それに続いた原発事故は巨大であり、全体を語りうる人はどこにもいない。代弁もできない。ここにあるのは、いわき市の山間に暮らすひとりの女性の幻視的なまなざしがとらえた、事故後7年半の福島に走る亀裂と断層の記録である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 建築・土木に関わるすべての方必携!! 「震度7の連鎖」がもたらした教訓とは? 4月14日夜の「前震」、16日未明の「本震」と、2度の大地震が熊本を襲った。震度7クラスの揺れが短期間に連発するという“想定外”の現象により、木造住宅やマンションは崩れ、交通インフラやライフラインも分断された。 市民を守るはずの庁舎や学校なども多くが使用不能となった。 「本震」を現地で体験した3人の記者のリポートを軸に、日経グループの専門3誌のネットワークで地震や建築の専門家を取材。 阪神大震災や東日本大震災など、過去の大地震との比較を交えつつ、前例のない「波状的地震」が突き付けた都市と建築の課題を明らかにする。 写真で見る街の傷跡 建築編 あえなく機能停止した災害拠点 住宅編 「新耐震基準」以降でも明暗分かれる 土木編 阿蘇大橋はなぜ落ちたのか? 今こそ過去の大地震に学べ! 阪神・淡路大震災(1995)、新潟県中越地震(2004)、福岡県西方沖地震(2005)、東日本大震災(2011)、台湾集集地震(1999)、台湾南部地震(2016)
-
-コロナ・パンデミックをはじめとする災禍の時代。露わになる格差の拡大、社会の分断、民主主義の危機などに、私たちはどのように立ち向かうのか。社会学理論の知見やデータをもとに、第一線の社会学者たちが未来へ向けて発信する市民へのメッセージ。 【主要目次】 まえがき I 災禍が拡大した格差と孤立 1.コロナ・パンデミックと雇用格差(有田 伸) 2.コロナ・パンデミックとジェンダー格差(筒井淳也) 3.コロナ・パンデミックと教育政策(中村高康) 4.コロナ・パンデミックと住宅問題(村上あかね) 5.コロナ・パンデミックと日本の自殺(江頭太蔵) Ⅱ 民主主義社会のゆらぎと危機 6.コロナ禍は民主主義国への評価を低下させたか(園田茂人) 7.新しい介入主義に市民社会はどう対峙するか(町村敬志) 8.危機に瀕する民主主義:ヴァイマル共和国の歴史から考える(友枝敏雄) 9.民主主義の二つのかたちと日本の選択:教育から考える価値観と市民像(渡邉雅子) 10.社会のゆらぎと社会理論のゆくえ(山田真茂留) 11.文化戦争と文系学問の危機(盛山和夫) Ⅲ 未来をどのように創るか 12.〈生〉を包摂する社会へ:ケアとジェンダーの視点から(落合恵美子) 13.モビリティーズと〈共〉の社会理論(吉原直樹) 14.持続可能な民主主義へ向けて(今田高俊) 15.ウィズコロナ、ウィズAI時代の民主主義と社会学5.0(佐藤嘉倫) 16.災禍の時代を超えて:孤立から語り合う世界へ(遠藤 薫) あとがき
-
3.0トランプ政権の外交基盤となり、アメリカ保守主義再編や欧州ポピュリズムに大きな影響を与えた問題作! 自由と民主主義を守るのは国民国家であるとして、誤解されがちなナショナリズムの価値観を問い直していく。 その一方で、リベラリズムのパラダイムは、専制や帝国主義と同じだと警鐘を鳴らす。 ナショナリズムと国民国家400年の歴史を再評価する括目に値する1冊。 中野剛志、施光恒の両氏によるダブル解説付。 <「解説」より> ★政治秩序とは、本質的に、非リベラルなのである。しかし、すべてのリベラルな統治形態は、非リベラルな政治秩序を基礎としている。そして、そのリベラルな統治形態を成立させる非リベラルな政治秩序こそ、ハゾニーが擁護する「国民国家」にほかならない。ーーーーーー中野剛志氏(評論家) ★本書の意義は数多くある。欧米の新しい保守主義を理解するのに資するであろうし、先進各国で進む国民の分断現象を考察する際にも有益な視角を与える。とくに指摘したいのは、本書の議論が、現行のグローバル化の問題点を認識し、それを克服しうる「ポスト・グローバル化」(グローバル化以後)の世界の在り方を考えるうえで必要な認識の枠組みを与えるという点だ。-----施 光恒氏(政治学者) <本書の特徴> ◎「無政府状態」と「帝国主義」を両極に置き、その中間的なものとして「国民国家」を置いている。 ◎無政府状態と帝国主義との比較で、国民国家がもっとも、個人の自由や多様性を擁護し、発展させることができる政治体制であるとしている。 ◎文化や起源、宗教を共有しているという連帯意識があってはじめて、近代的な自由民主主義の政治制度や市場経済も機能させられるとしている。 ◎「リベラリズムは自由な秩序をつくるどころか帝国主義に近い」とはっきり述べている。 ◎「トランプ以後」の米国保守主義勢力が目指している姿。
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 なぜコラボレーションはかくも困難なのか? 伝説の論文「コレクティブ・インパクト」が書き直されなければならなかった理由とは何だったのか? 複雑な社会課題の解決には、異なるセクターのコラボレーションが必要である。この「あたりまえ」のことが実行に落とし込めないために、善意、人、お金をいくらつぎ込んでも社会システムの根本的な変化を起こすことができなかった。そこに新しい協働の思想と技法をもたらした2011年の「コレクティブ・インパクト」の論文は、世界で熱狂的に受け入れられた。それから10年。実践者と成功事例が増えたのと同時に、批判と失敗事例も集まった。それらを踏まえて、より「包括的(誰も取り残さない)」で「公正(特定のグループが支配しない)」なコラボレーションのあり方が問われている。本号では、「エクイティ」を中心に据えた「コレクティブ・インパクト」の最新の流れと、コラボレーションをめぐるさまざまな課題をとりあげる。 <目次> Editor’s Note ・コレクティブ・インパクトの試練と深化 COMMENTARY ・ソーシャルイノベーションの2つの系譜とコレクティブ・インパクト FEATURE ・コレクティブ・インパクトの北極星はエクイティの実現である ・なぜ「地域の声を聞く」だけではインパクトが生まれないのか ・横断型コラボレーションを襲う5つの岐路とその乗り越え方 CLASSICS ・コレクティブ・インパクトの実装に向けて CASE STUDY ・エシカル・テクノロジーで音楽業界の常識を変える OUR IDEAS ・「やっかいな問題」の解き方としてのネットワークーー災害復興の鍵を握る「ハブ」は何をしているのか OUR CHALLENGE ・30人から始めるスローイノベーションーー地域の社会課題に取り組む実践共同体のつくり方 DIFFICULT QUESTIONS REGARDING COLLABORATION 社会を変えるコラボレーションをめぐる「問い」 ・決定権限がある側と一般市民の「パワーの差」をいかに解消するか(鎌田華乃子) ・当事者の声を守り「対等な連携」を進めるために何が必要か(吉岡マコ) ・「奪い合う関係」を「与え合う関係」に変える仕組みとは(新井和宏) ・リスキリングにおいて官民連携の核になるものは何か(後藤宗明) ・コラボレーションで生じる「わかりあえなさ」とどう向き合うか(鬼澤秀昌) ・セクターを越えて社会を変えていけるのはどんな人か(濱川知宏) ・70~80点の短期的な成果を長期的なシステム変化につなぐには(小田理一郎) ・「チャレンジの総量」を増やす際の障壁をどうやって取り除くか(齋藤潤一) ・なぜ日本では企業とNPO・NGOの連携が進まないのか(羽生田慶介) FACTS & FIGURES ・世界の人権意識の高まりとビジネス上の人権リスク VIEWPOINTS ・気候変動対策がジェンダー不平等を拡大する危険性 ・「不安の解消」がコラボレーションを加速する RESEARCH ・企業がBコープ認証を求める2つの理由 ・雇用における差別はなぜなくならないのか ・時間の寄付か、お金の寄付か BOOKS ・人に見せたくないものを覗き見られない権利をいかにして守るか ・「規模の拡大」の教科書が見落としていること ・分断を超えたなめらかで豊かな未来創造 Thoughts for Tomorrow ・ビル・ストックランドの冒険
-
-地球規模の銀行詐欺の暴露と 人類繁栄のためのブループリント 世界140カ国以上に広がる 人類解放の「ウブントゥムーヴメント」がついに日本上陸! お金のない世界はできる! そして、それが人類を最大に幸せにする! 私たちが種族として歩んできた道のりは、 想像を絶するほどの嘘や欺瞞に満ちている。 何千年も前から人類の支配は続いてきた。 すべては、お金による支配だ。 マイケル・テリンジャーは、 お金が物々交換から進化したものではなく、 悪意を持って、絶対的な支配と奴隷のツールとして 人類に導入されたことを指摘する。 彼は、私たちの現在の状況は、 人類の運命を変えるまたとない機会であると述べる。 グローバルな金融システムによって、 種として奴隷にされていることを理解することは、 覚醒の道を発見するためにも非常に重要なのだ。 本書では、地球規模の銀行詐欺の実態を暴くとともに、 古代アフリカ人の哲学「ウブントゥ」をもとに、 分断されたお金で動く社会から、 人々が生きる情熱、神から与えられた才能を原動力とする 団結したコミュニティへとスムーズに移行していく 具体的な方法を解説している。 「ウブントゥ貢献主義」は、金融的な暴虐から 真に自由な新しい時代へと私たちを連れ出してくれる、 揺るがない社会構造の基盤となる実践的イズムなのである。 ウブンツ貢献主義のシステムとは ・誰もが絶対的に自由で平等な新しい社会構造の設計図である。 ・貨幣の概念やいかなる形態の取引も存在せず、 物質的なものに価値を付与しない社会である。 ・一人ひとりが情熱を持って行動し、 生まれ持った才能や身につけた技術をもって、 コミュニティの人々により大きな恩恵をもたらすために 貢献することが奨励される文化である。 ・人々のニーズに基づいた新しい法律があり、 見返りを求めない自発的な取り組みによって、 すべての人にすべてが提供される社会である。 ・誰もがどこに住むかを選択でき、 自分の意志に反することを強制されることはない。 ・芸術や文化の爆発的な発展を通じて人々が精神的に成長することによって、 調和という概念を完全に受け入れる意識が急速に高まる社会である。 ・資本主義的な消費者主導の環境にいる人々には思いも寄らないような、 あらゆるレベルにおいて想像を超える豊かさを提供するシステムである。 (本文より抜粋) お金がまったくいらず、豊かに繁栄していく社会を あなたは想像できるだろうか。 これは夢物語ではない。 すでに世界各国で、ウブントゥ運動に参加している 多くの人の手によって実現しはじまっているのだ。 世界11カ国で読み継がれる名著、待望の刊行! 人類が思い出すべき美しい世界がここにある!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 今、「分断」に揺れるアメリカだが、本書の登場人物の語りから、「分断」ということ以前に、アメリカ人であることの基層にアメリカ人が共有している価値が息づいていることが見えてくる。 分断や個人主義に振れるアメリカ社会に失望し、抗議し、憤る人たちもアメリカ人の一つの姿である。彼らの人生の語りの中には、誠実なアメリカ人の精神、すなわちアメリカの良心が、そこここに立ち現れている。本書を読んで、是非このようにアメリカ人を見つけてほしい。 「よく知らないもの」には偏見や差別意識が生まれやすい。対峙するものとつながりが生まれ、そこに理解できる関係の友人や知り合いや親しい人がいて、その人たちの生活の様子を想像することができるようになると、意識は変わっていくだろう。
-
-ロンドン下町出身の優柔不断な中年男・アーチーと、バングラデシュ出身の誇り高きムスリム・サマード。第二次大戦で親友になったふたりは、ロンドンで新たな人生を模索する。 成長したアーチーの娘・アイリーとサマードの双子の息子・ミラトとマジドは、遺伝子工学者のチャルフェン一家と関わり、生命倫理にふれる研究をめぐる問題の渦中へ……。 移民家族が直面する悲喜劇を知的でユーモラスに描く、ジャマイカ系イギリス人作家の衝撃作。カリブ海やインド亜大陸からヨーロッパにわたる壮大な家族の物語を背景に、歴史、信条、遺伝子などさまざまな差異を抱えて混沌の街ロンドンで生きる人々を描く。分断と混沌の深まる時代に希望の光を放つ、21世紀の必読書 ブレイディみかこさん推薦! 「この本、いちおう社会派で、すでに古典と呼ばれているんです。 こんなにヤバくて笑えてぶっ飛んでるのに。 繚乱と咲く、移民たちのサーガ! ストリートの歴史はなんと猥雑でカオスなことか。 多文化共生の諸問題をごった煮にしておおらかに笑い飛ばす、才気煥発な本である。」 西加奈子さん推薦! 「これはすべての呪われた、そして祝福された人間の物語だ。 きっと100年後も、200年後も読み継がれるだろう。 人間がどうしようもなく、抗い難く、救い難く、人間でしかないことを、こんなに面白おかしく、鮮やかに、完璧に書かれた小説がこの世界に存在することに感謝したい。 20年前に誕生したこの傑作を、これから初めて読むことが出来る人に嫉妬する。そう思っていたけれど、何度目だって衝撃は変わらなかった。いや、増した。著者が描いたこの世界に、私たちは近づけているのだろうか。」
-
-非婚/未婚/既婚、正規労働/非正規労働、性差別的な売春か/セックスワークか、女性の保護か/男女平等か――。フェミニズムは分断と連帯にどう向き合えばいいのか。 フェミニズムの議論を骨格に、現場の声にふれた経験に基づき、女性たちが簡単にはつながれない現実を見据えたうえで、シスターフッドとは何かを問いかける。 女性たちが差別に抗い、不満に共感しあいながらも、ともに声を上げられない現実を、ジェンダーに基づく権力構造による分断だけではなく、考え方や生き方、事情や立場が異なる個人の関係性などの視点から読み解く。 「分断」を乗り越えることを模索し、「ほどほどに、誰かとつながり、生き延びる」ための女性のこれからを提案して、長年のフェミニズムの場での活動と思索に基づいて女性のつながりのあり方の再考を求める評論。
-
-船橋 洋一/鈴木 一人/細谷 雄一/神保 謙/村井 純/柴田 なるみ/相良 祥之/大矢 伸/尾上 定正/富樫 真理子/越野 結花。 各分野における第一人者・気鋭の研究者を結集! 新冷戦下における米中・日米・日中関係、 デジタル・サイバー、エネルギー、健康・医療、生産・技術基盤。 そのベースとなる「経済安全保障」のかたちとは。 論点を整理し、日本がとるべき国家戦略について分析・提言。 東洋経済オンライン連載をもとに大幅改稿・加筆。 経済安全保障の“黒字”/“赤字”ということで言えば、日本は戦後、米国が主導し、構築した国際秩序とルールという大きな“黒字”を享受してきた。米国が内向きになり、ポピュリズムと分断の政治が広がり、中国が相互依存を武器化し、勢力圏を拡大するにつれてその“黒字”構造が“赤字”体質に変質しつつある。それをもう一度、“黒字”構造に作り替えることが日本の経済安全保障戦略には求められる。経済力を国際秩序とルール再構築のために戦略的に使うことを学ぶ必要がある。言い換えれば、「守る」だけでなく「攻める」ことが大切だということである。さらには、それを持続的に行うには日本の経済と産業の生産性と国際競争力の不断の向上、未来を実装するビジョンとイノベーション、そしてそのための人材と投資が不可欠である。「育てる」ということである。経済安全保障の最大の要諦は、「育てる」ことにほかならない。【序章(船橋洋一)より】
-
-ジェンダー視点で見る新しい世界史通史 現代のグローバルな課題を捉え直す 現代性の歴史的文脈をたどり、暴力・環境・災害・疫病・最新科学に切り込む! 今ここから見えている「世界」は、他の人たちが別の場所から見ている「世界」と同じだろうか。「世界」を問い、「世界を問う私」を問う―この双方向性のなかに身を置くとき、私たちは「世界」が決して自明のものでないことを再認識させられる。だとしたら、「世界」の歴史、「世界史」とは何だろうと、西洋中心、成人男性中心に描かれてきた従来の「世界史」を見直さざるをえなくなる。時間軸と空間軸とを交差させ、比較と関係性を考えるジェンダー史の視点で考察していく。 本巻のもう一つの目的は、現代的諸課題と向き合うことである。私たちは今、地球規模で考え、協力して取り組まねばならない問題を数多く抱えている。新型コロナウィルス・パンデミックを経験し、ロシア・ウクライナ戦争やイスラエルのガザ侵攻といった20世紀の分断を引きずりながら、私たちは、ビッグデータやIoT、生成AIといったデジタル技術が人間の諸関係を左右する21世紀を生きている。そのなかで、諸課題の解決に向かう端緒を開くためには、適切な問いを発し、その問いを根拠(史料/ 資料)に基づいて多角的・多層的に掘り下げていかなければならない。 本巻では、シリーズ全体を貫くジェンダー史の視点から現代世界に斬り込み、その「現代性」の本質を熟考する。換言すれば、それは、20世紀という時代をジェンダー史の視点で「歴史化」し、「相対化」する作業にほかならない。
-
4.0《円安は止まるのか? 金利のある世界が再来!》 しつこい物価高で国民は疲弊、資産価格の高騰で富裕層は潤う──。 持続困難な財政、低金利政策の継続が、問題をいっそう深刻にする。 本書は、中長期的視点から日本経済の課題と選択肢を提示するとともに、 金融政策の課題と今後の見通しをわかりやすく解説。 マイナス金利解除後の動向を見定めたい投資家、金融関係者必読! ■2013年4月、日本銀行は長らく続いたデフレ経済からの脱却を目指し、量的・質的金融緩和を導入した。黒田東彦日本銀行総裁(当時)は、大規模な金融緩和策によって2%の「物価安定の目標」を2年で実現すると表明。インフレ目標の導入により期待に働きかけ、デフレ脱却を目指した。 ■日本がデフレと格闘する中、2020年には新型コロナウイルスの感染が世界的規模で流行(パンデミック)、その2年後にはロシアがウクライナへ侵攻した。経済の分断は深まり、欧米諸国を中心に激しいインフレに見舞われた。日銀は2024年3月、マイナス金利政策を解除したが、依然として緩和的な環境を維持。政府は歳出改革に手つかずのまま。その陰で経済の歪みは拡大、重要課題は置き去りにされている。 ■本書は、人口動態やエネルギー政策、社会インフラなど日本が直面する困難を見据えつつ、粘着的な物価高の構造的な要因を説き、政策運営全般の矛盾を鋭く指摘。具体的な課題を提示するとともに、政府・日銀に決断を迫る。 ■政策関係者や金融関係者のほか、今後の金利やドル円の動きなどを見定め、運用を検討したい投資家が読んでおきたい注目の一冊。
-
4.0有意義な対話のためのレベル別・超実践ガイド 分断と二極化の時代、考えが極端に異なる人とも礼節と共感を保って会話・対話をするにはどうしたらよいか? 友人や家族との会話、ビジネスでの交渉、SNSでの議論……よい会話のための入門級の基礎知識から、強硬派・過激派に対処するための達人級のテクニックまで、すべてを網羅した実践的マニュアル。 リチャード・ドーキンス氏推薦 「すべての人がこの本を読めば、世界はもっとよい場所になるだろう」 戸田山和久氏推薦 「著者たちの思想も行動も気に入らない。なのに、本書には学ぶべき価値あることがギッシリつまっている。というわけで、私は、極端に考えが違う人たちから「根本的に異なった考えをもつ人と語り合うスキル」を教えてもらったのだ。稀有な読書体験を与えてくれた本書に感謝。分断のあっち側にいる人もこっち側にいる人もぜひ読みましょう」 【目次】 第1章 会話が不可能に思えるとき 第2章 入門:よい会話のための9つの基礎 ──通りすがりの他人から囚人まで、誰とでも会話する方法 第3章 初級:人の考えを変えるための9つの方法 ──人の認知に介入する方法 第4章 中級:介入スキルを向上させる7つの方法 ──(自分を含む)人の考えを変えるための効果的スキル 第5章 上級:揉める会話のための5つのスキル ──会話の習慣の見直し方 第6章 超上級:心を閉ざした人と対話するための6つのスキル ──会話のバリアを突破すること 第7章 達人:イデオローグと会話するための2つの鍵 ──動かざる人を動かす 第8章 結論 謝辞 原注 監訳者解題 参考文献 索引 【著者・訳者】 ピーター・ボゴジアン(Peter Boghossian) 1966年生まれ。アメリカ合衆国出身の哲学者。主たる関心は、批判的思考や道徳的推論の教育に関する理論とその実践。ソクラテス式問答法を活用した囚人教育プログラムの研究によってポートランド州立大学から博士号を取得し、2021年まで同大学哲学科で教員を務めた。意見を異にする人びとが 互いの信念や意見の根拠について理性的に話し合うためのテクニックである「路上の認識論」(Street Epistemology)を提唱。著書に、『無神論者養成マニュアル』(A Manual for Creating Atheists , 2013)など。 ジェームズ・リンゼイ(James Lindsay) 1979年生まれ。アメリカ合衆国出身の文筆家、批評家。テネシー大学ノックスビル校で数学の博士号を取得。宗教やポストモダン思想の問題を分析・考察する論考を多数発表している。著書に、『「社会正義」はいつも正しい――人種、ジェンダー、アイデンティティにまつわる捏造のすべて』(ヘレン・プラックローズ共著、山形浩生+森本正史訳、早川書房、2022年)など。 藤井翔太(ふじい・しょうた) 1987年東京都生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了、テンプル大学大学院教育学研究科修士課程修了。関心領域は応用哲学、教育哲学。現在、テンプル大学ジャパンキャンパス アカデミック・アドバイザー/講師。訳書に、ナンシー・スタンリック『アメリカ哲学入門』(勁草書房、2023年)、ドナルド・ロバートソン『認知行動療法の哲学――ストア派と哲学的治療の系譜』(共監訳、金剛出版、2022年)など。 遠藤進平(えんどう・しんぺい) 三重県津市生まれ、愛知県名古屋市育ち。慶應義塾大学文学部人文社会学科哲学専攻卒、アムステルダム大学論理学修士課程修了(Master of Logic)。現在、シドニー大学博士課程(Philosophy, PhD)。曖昧さや様相といった伝統的な哲学のトピックから、冗談や脅迫、挨拶のようなコミュニケーションの(ときに哲学分野では非標準的なありかたとして放置されがちな)諸相に関心がある。業績など:https://researchmap.jp/shimpei_endo
-
3.0映画のように書き、小説のように撮る…… のちに世界有数の映像作家となった 映画監督イ・チャンドンによる傑作小説集 待望の日本語訳刊行! 映画監督として世界中にファンを持つ韓国の作家イ・チャンドンが、かつて小説家として発表し、「映像の世界への転換点となった」と自ら振り返る小説集、『鹿川は糞に塗れて』(原題『??? ??? ???? ?? ??』)(1992)の邦訳。 収録される5作品はそれぞれ、朝鮮半島の南北分断、そこに生まれた独裁政治下の暴力、その後の経済発展がもたらした産業化や都市化に伴う諸問題などを背景にしている。すべての登場人物は、分断や社会矛盾の犠牲になって生きる「ごく普通の人びと」。膨大な量のゴミで埋め立てられた地盤と労働者たちの排泄物の上に輝く経済発展、そしてそこに生まれた中間層の生活の構造を、作家イ・チャンドンは「糞に塗れている」と看破し、そこに生きる市民たちの悲喜交々の生を問う極上の物語を紡ぎ出す。
-
-アメリカ型新自由主義の成立・変容・危機 ITや知的財産に基づく新しい資本蓄積、経済の「金融化」とバブルの反復、米中「新冷戦」と軍事産業のゆくえ、政治の分断とポピュリズムの台頭……。ダイナミックに変貌するアメリカ資本主義の姿をトータルに把握する共同研究。 ※本書は、大月書店刊『21世紀のアメリカ資本主義――グローバル蓄積構造の変容』の電子書籍版です。 【目次】 序章 本書の対象と課題 第1篇 景気循環とマクロ経済構造 第2篇 グローバリゼーションと通商政策 第3篇 金融とバブル 第4篇 デジタル化・無形化と新しい資本蓄積 第5篇 労働、貧困、社会運動 第6篇 政治と政策 【著者】 河音琢郎 立命館大学経済学部教授 豊福裕二 三重大学人文学部教授 野口義直 摂南大学経営学部准教授 平野健 中央大学商学部教授
-
-アユのことがここまでわかった! 天然アユを増やし、今より釣れるように、 これから先もアユ釣りを楽しめるようにするには、どうしたらいいのか。 川と海が分断され、現在、アユを取りまく環境はいいとは言えないが、 釣り人、漁協関係者、地元住民が一丸となって取り組めば、 天然アユの海からの遡上数向上は決して夢ではない。 アユとアユ釣りをこよなく愛する3人の研究者が、 日本列島の川で生まれ、海に下り、 また川に上って1年間で生涯を終える愛すべきアユの生態から、 アユが遡上する川作り、放流種苗ごとの特徴、 釣果が上がるテクニック、アユ増殖の成功事例まで、 アユに関する最新知見をあますことなく綴った、最強のアユ本。
-
3.6「WOKE」という切り口で、企業が社会問題に取り組むことそのものが本音レベルで利益に直結する現代資本主義の構造と裏側を読み解く。 ■「WOKE」とは:「WAKE=目を覚ます」という動詞から派生した言葉。公民権運動時代から使われていた言葉だが、近年は「社会正義」を実践しようとする人びとの合言葉になっている。 ■「WOKE CAPITALISM」とは:企業が気候変動対策、銃規制、人種平等、LGBTQなど性的平等実現などに取り組む様子。 【「WOKE CAPITALISM」のチャート図】 リベラルな「WOKE CAPITALISM」の実践で企業イメージ&株主価値が向上 ⇒翻って保守層は「意識高い系」に反発し、選挙では保守党派に投票 ⇒保守党派の伸長は、「WOKE」な企業にとっても実はプラス。むしろ「減税」政策の恩恵を受けチート化。さらなる利益がもたらされる。 ⇒この構造が継続し続けることで、社会階層は固定化。民主主義の破壊につながり社会はディストピア化。しかし、企業はどちらに転んでもユートピア化。 ⇒繰り返し 近年「WOKE」という言葉がよく使われている。「wake=目を覚ます」という動詞から派生したこの言葉は「社会正義」を実践しようとする人びとの合言葉になっている。 たとえば、一般消費者向け企業が、気候変動、銃規制、人種平等、LGBTQなど性的平等、性的暴力廃絶などに参加する様子は「Woke Capitalism」と呼ばれる。 Woke Capitalismの実践で成功した企業は「社会正義」に取り組むことで、株主価値向上にも顧客の開拓・維持にもつながる。 一方で、リベラルなWokeの実践は保守層の反動を煽り、その反動による投票行動で政治は企業に優しい保守党に委ねられる。トランプ現象はその象徴だ。あまつさえ伝統的に企業に優しい保守党派により減税にも与れる。「Woke」を糧にしたキャピタリズムというわけだ。 ある意味で企業にとっては無敵である。ただし、社会には深刻な分断がもたらされ固定化し、民主主義が破壊されることにもつながってしまう。 「WOKE」という切り口で、企業が社会問題に取り組むことそのものが本音レベルで利益に直結する現代資本主義の構造と裏側を読み解く、オリジナルかつユニークな論考。
-
-確認申請でポイントとなる面積、高さ、階数などの算定ポイントが 写真・イラストで一目瞭然! 条文から通達まで、算定における押さえどころを すべて図解して解説しています。 本書は、2015年2月に刊行した『確認申請[面積・高さ]算定ガイド』の改訂版です。2018年の宅配ボックス設置部分が容積率算定床面積の対象外になったことについても加筆・修正しています。 ■もくじ はじめに 第1章 面積 建築面積と床面積の違いがすぐに分かる対照表 敷地面積の算定方法 吹きさらしバルコニーでも構造により算入・不算入が分かれる建築面積 築造面積は工作物の水平投影面積 算定方法に個別解釈がまだまだ多い床面積 など 第2章高さ 建築物の高さの起点と屋上部分の除外早見表 地盤面の算定は斜面地やからぼりの有無に注意 建築物の高さは12(5)mまで不算入となる屋上部分に注意 絶対高さと軒高は地盤面から算定する 道路斜線、高さは前面道路の路面の中心の高さから算定 など 第3章長さ 建築物と境界線との距離の規定は4 つある 接道長は原則2m だが条例で厳しくできる 道路幅員は側溝は含むが法敷は含まない 容積率算定における最大幅員のとり方 特定道路からの延長による容積率緩和 など 第4章階・階数 階数に不算入でも階に該当すれば延べ面積に算入される 床面の地中埋設率で地階の可否を判定 階に係る主な制限の早見表 Column 建蔽率制限の緩和規定 水路等で分断されても「一団の土地」 敷地面積を正確に算定するための注意点 建築物に該当する工作物 木3 共同住宅にかかる避難上有効なバルコニーの規定 隣地または前面道路の反対側に高速道路・鉄道の高架橋がある場合 地区計画で定められる建築物等に対する規制 避難安全検証法により安全性能が確かめられた場合の緩和規定
-
4.0『フィナンシャル・タイムズ』『サンデー・タイムズ』『エスクァイア』などの2022年ベストブックに輝いた話題作、待望の邦訳。 トランプの大統領選再出馬は2度目の南北戦争を招くのか。 アメリカを代表する政治学者による20年に及ぶ徹底調査と歴史的な分析。 世界中で「内戦」が急増している現状とその原因、アメリカでも内戦が勃発する潜在性が高まっている状況を読み解き、警告する。 アメリカ、そして世界に衝撃を与えた「Qアノン」扇動による2021年1月に発生した前代未聞の連邦議会襲撃事件。トランプ政権時に進行していた市民分断の最終章とも言えるようなこの事件は、今後の本格的な党派闘争の序章になるのだろうか。 内戦を専門とする政治学者が、過去の内戦に関するデータから、イラク・北アイルランド・インド・フィリピンなどを具体事例として、紛争が発生する契機と紛争が起きる条件と心理についてのパターンを分析。 また、現代の紛争を拡大・激化させるソーシャルメディアというツールについて考察することで、アメリカの内戦の危機接近度を明らかにしていく。
-
3.5ヤンキーという言葉から、どのようなイメージをもつだろうか。時代遅れというイメージがある一方で、近年では「マイルドヤンキー」のようにマーケティングの対象として注目されたりもしている。しかし、ヤンキーと呼ばれる若者が何を考え、どのように生活をしているのか、十分な調査に基づいた書物は少ない。 大阪府の高校で3年間、〈ヤンチャな子ら〉と過ごしフィールドワークして、対立だけではない教師との関係、〈インキャラ〉とみずからの集団の線引き、家族との距離感を丁寧にすくい上げる。そして、高校を中退/卒業したあとの生活も調査し、大人への移行期に社会関係を駆使して生き抜く実際の姿を活写する。 集団の内部の亀裂、地域・学校・家族との軋轢、貧困や孤立――折り重なる社会的亀裂を抱える若者の「現場」から、分断や排除に傾かない社会関係の重要性を指し示す。
-
3.5
-
4.3中流という生き方はまだ死んでいない。 万人を豊かにする進歩的資本主義とは? 上流エリートか、貧困層か……。未来の選択肢は、この二つだけではない。 今こそ、分断なき世界について語ろう! 「スティグリッツはとてつもなく偉大な経済学者だ」――ポール・クルーグマン(ノーベル経済学賞受賞経済学者) 「クルーグマン、ピケティと並び、21世紀のグローバル資本主義論争をリードしてきた偉人」――アンドリュー・アンソニー(ガーディアン紙) ノーベル経済学賞受賞経済学者が、市場原理主義に異議を唱え、経済の再生を提言する! いまや経済や政治は、一部の富裕層や大企業だけのためのものになってしまった。 さまざまな産業を、わずかばかりの企業が独占的に支配するようになった結果、格差が急激に拡大し、成長が鈍化している。 だが、我々が直面しているこのような状況に対し、打つ手がないわけでは決してない。 スティグリッツによれば、富や生活水準の向上を真にもたらすのは、学習、科学やテクノロジーの進歩、法の支配だという。本書で示される政策改革に賛同する人が多数派を占めれば、いまからでも、豊かさが万人にいきわたる進歩的資本主義を構築することは可能だ。そしてそれは、誰もが中流階級の生活を実現できる社会である。 市場原理主義から予想される危機と、進歩的資本主義の基盤を提示する本書は、現代社会の危機的状況を明らかにすると同時に、困難な時代を乗り越えるための、正しい資本主義のあり方、すなわち「それでも資本主義にできること」を示すものである。
-
5.0世界トップレベルの自動車メーカー・ゼネラルモーターズ。その生産工場が閉鎖したとき、企業城下町ジェインズヴィルの分断は始まった。元工員と家族、教育者や政治家、財界人にいたるまで、異なる立場の人々に行った緻密なインタビューが、事実のみならず心理まで克明に描写する小説さながらのストーリーテリングに結実。「住民のパーソナルな物語」を通して「二分した全アメリカの物語」を浮彫りにした、衝撃のノンフィクション!
-
4.5「わたしの政治への関心は、ぜんぶ託児所からはじまった。」英国の地べたを肌感覚で知り、貧困問題や欧州の政治情勢へのユニークな鑑識眼をもつ書き手として注目を集めた著者が、保育の現場から格差と分断の情景をミクロスコピックに描き出す。2008年に著者が保育士として飛び込んだのは、英国で「平均収入、失業率、疾病率が全国最悪の水準」と言われる地区にある無料の託児所。「底辺託児所」とあだ名されたそこは、貧しいけれど混沌としたエネルギーに溢れ、社会のアナキーな底力を体現していた。この託児所に集まる子どもたちや大人たちの生が輝く瞬間、そして彼らの生活が陰鬱に軋む瞬間を、著者の目は鋭敏に捉える。ときにそれをカラリとしたユーモアで包み、ときに深く問いかける筆に心を揺さぶられる。著者が二度目に同じ託児所に勤めた2015-2016年のスケッチは、経済主義一色の政策が子どもの暮らしを侵蝕している光景であり、グローバルに進む「上と下」「自己と他者」の分断の様相の顕微描写である。移民問題をはじめ、英国とEU圏が抱える重層的な課題が背景に浮かぶ。地べたのポリティクスとは生きることであり、暮らすことだ──在英20年余の保育士ライターが放つ、渾身の一冊。
-
3.0朝鮮半島統一への第一歩を踏み出すために 悲しみと苦悩に満ちた分断の歴史を改めて検証する。 ------------------------------------------ 1948年第二次世界大戦後の冷戦を背景に、 朝鮮半島は北の朝鮮民主主義人民共和国と南の大韓民国に分割された。 以降現在に至るまで、同一民族がふたつの国家に所属するという不自然な状態が継続している。 両国の統一は、朝鮮民族にとってアイデンティティーに関わる悲願であり、 国際的にも、北朝鮮の世界的孤立や南北の経済格差などは看過できない重要な懸案事項だ。 その平和解決は、朝鮮半島のみならず、世界平和を実現するための第一歩となると著者は語る。 本書では、国際的NGO活動を通じて長く世界平和に貢献してきた著者が、 統一コリアに向けたビジョンとロードマップ、および歴史的背景について解説する。 朝鮮人だけではなく日本人にも著者の思想を共有することで、 日本と朝鮮半島における新しい調和と平和を築くための礎となる一冊である。 2015年の発行から8年が過ぎ、内容に一部変更を加えるとともに、 新たに推薦者記事紹介を加えた形で改訂版として出版する。
-
3.9DXをいかにして活用するかをリテール業界を中心に説いた前作『リテール4.0』の法則と実践をマーケティング全般にまで広げアップデートさせた最新刊。深まる分断と高まる反消費の機運にいかにして立ち向かうか。マーケター必読書。
-
4.5DXへ挑む、マネジメント、現場、すべての人へ 本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるためのガイドブックです。 DX推進を担うビジネス部門・情報シス、現場・チームの人たちに向けて、 仮説検証とアジャイル開発を中心とした、DXを進めるために必要な基本的な知識を解説します。 また、DX推進にあたって組織として「戦略(経営側)と現場活動の一致」を高める必要があり、 そのための体制や進め方を提示します(どこから始めるか? どのような体制で臨むか?)。 DXという名の組織変革を推し進める4つの段階を解説。 1.業務のデジタル化 2.スキルのトランスフォーメーション 3.ビジネスのトランスフォーメーション 4.組織のトランスフォーメーション 【本書で扱うDX推進のキーワード】 分断/適応課題/協働/アジャイルブリゲード/アップデートとアライアンス コミュニケーションのストリーミング化/変革推進クライテリア/仮説検証型アジャイル開発 など 【本書の構成】 ■第1部 デジタルトランスフォーメーション・ジャーニーを始める前に 第1章 DX1周目の終わりに 第2章 デジタルトランスフォーメーション・ジャーニーを描く ■第2部 業務のデジタル化 第3章 コミュニケーションのトランスフォーメーション 第4章 デジタル化の定着と展開 ■第3部 スキルのトランスフォーメーション 第5章 探索のケイパビリティの獲得 ■第4部 ビジネスのトランスフォーメーション 第6章 仮説検証とアジャイル開発 第7章 垂直上の分断を越境する ■第5部 組織のトランスフォーメーション 第8章 水平上の分断を越境する 第9章 組織のジャーニーを続ける ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.7「何気なく使っているFacebookだけど…それで、本当に大丈夫?」 ソーシャルメディアを長年研究し、自身もユーザーである著者による啓発書。 「コンピューターテクノロジーが人間の問題すべてを解決する」かのように考えるFacebookの使命感(善意)と自信過剰こそが、逆効果をもたらしまっていることを、文化的・歴史的・哲学的に振り返りつつ、明らかにする。 わたしたちは今後、どのように関わっていけばよいのか? 便利さとスピードを追い求める現代人よ、今こそ立ち止まって考えよう。 ◎本書のポイント フェイスブックには、以下のような、さまざまな危険性が引き起こす構造的な問題がある。 これらを、実際に起こった事例を取り上げながら、文化的・歴史的・哲学的に分析している。 ❶記事の信頼性 記事の出典を特定・評価する機能がないので、虚偽や誤解を招く情報が拡散されやすい ❷エンゲージメント エンゲージメント率の測定により、感情に強く訴えかけるコンテンツが蔓延しやすい ❸フィルターバブル ユーザーの興味・関心に基づくものばかり表示されるため、ユーザーの視野が狭まる もくじ はじめに フェイスブックの問題とは何か 1.喜びを生むマシンー私たちを虜にするフェイスブック【ニコマコス倫理学】 2.監視するマシンー完全監視社会の到来【プライバシーと監視】 3.関心を引くマシンーアテンション・エコノミー時代で勝つのは誰か【アテンション・エコノミー】 4.善意のマシンー善意がもたらす数々の失敗【CSRと企業価値】 5.抗議するマシンーフェイスブックは世界を変えるか【ソーシャルメディアが革命を起こすのか?】 6.政治のマシンーフェイスブックは政治も動かすのか【ソーシャルメディア(ビッグデータ)と政治の関連性】 7.偽情報のマシンーフェイスブックが吐きだすフェイクニュース【偽情報が何をもたらしたか】 おわりに ナンセンスのマシン
-
-
-
-駐在、留学、ロングステイ……海外に住むという環境の変化をうけて、こころには何が起こりうるのでしょうか。新しい環境にうまく適応する人がいる一方で、不適応や精神不調に陥る人がいます。その違いはどこから起こるのでしょうか。 また、海外ではこころの危機に瀕しても、日本語と日本文化を理解し、そのこころに寄り添えるメンタルヘルス専門家に出会える可能性は極めて低いです。多くの海外邦人が、精神医療過疎地に住んでいると言えます。では、身を守るためにどうしたらいいのでしょうか。 新型コロナパンデミックを経験して、海外に住むことの意味合いとそのライフスタイルが変わったように感じます。本書では、下記「海外生活ストレス症候群」22症候群を挙げながら、海外でのこころのリスクマネジメントについて解説します。 【駐在員本人の場合】 慢性過重労働症候群 抱え込み症候群 小規模事業所症候群 赴任延長症候群 ワークライフバランス葛藤症候群 マルチスタンダード混乱症候群 サンドイッチ症候群 依存助長症候群 再適応困難症候群 愛憎は倍増症候群 やむをえず単身赴任症候群 【帯同家族の場合】 ムラ社会症候群 夫婦間葛藤顕在化症候群 配偶者のキャリア分断症候群 アイデンティティ混乱症候群 発達障害見のがし症候群 【青年期の一時渡航の場合】 根拠なき楽観症候群 海外モラトリアム症候群 転地療法症候群 海外発症の精神科救急症候群 【高齢者のリタイア後長期滞在の場合】 フレイル海外発症症候群 老いらくの恋症候群
-
3.0大学で政治学とグローバリゼーションを講じながら子育てをするイタリア系女性ブルーナは、自立心が強く進歩的だ。しかし医師でもある夫もその両親も保守的で差別と偏見に満ちている。両親に逆らえない夫、性同一性障害の幼い息子……。仕事と家庭の板挟みに苦しむブルーナの人生が教え子のムスリム青年の出現で覆る。そして彼の突然のISISへの出立。人種差別、性差別、移民問題……分断化が進む現代アメリカ社会で生きる彼女の人生が、今を生きる私たちすべての人生に重なり、訴えかけてくる。本書は著者のデビュー作で、イタリアの著名なジャーナリスト(イタリアの表現の自由・報道の自由のシンボル的存在で、『死都ゴモラ』や『コカイン ゼロゼロゼロ』といったノンフィクションで日本でも知られる)ロベルト・サヴィアーノ監修のフィクション&ノンフィクションのシリーズ「弾薬庫(ムニツィオーニ)」叢書の第一弾として刊行された作品である。
-
3.9分断と格差の時代に、「ファクトフルな希望」を示してみせよう。 経営者から科学者まで各界トップ絶賛の全米最新ベストセラー人類史、待望の邦訳! 「これほどの『希望』を感じて本書を読み終えるとは、予想もしなかった」 ——ビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者) 「いま世界にはびこっている排外主義は、必ず克服できる。私は本書で『何をすべきか』『何ができるか』を教わった」 ——エリック・シュミット(Google元CEO) 「人類の進化論的な本質は『善』であり、共感的な文明を生み出せる。これほどタイムリーかつ見事な本はない」 ——スティーブン・ピンカー(ハーバード大学教授『/21世紀の啓蒙』) 「進化の設計図(ブループリント)」を知れば、「分断」を乗り越えられる。 経済格差、人種、国家間対立……。今ほど「分断」が強調される時代はない。だがちょっと待ってほしい。こうした分断はなぜ起こるのだろう? それは進化の過程で、私たちが「仲間」を愛し、尊重する能力を身につけたからだ。この能力こそが、世界の命運を握る最大のカギである。 そこで本書は、南極探検隊の遭難者コミュニティからアメリカのユートピア運動、果てはAmazon.comのスタッフコミュニティまで、古今東西のあらゆる「人間社会」を徹底検証する。さらにはサルやクジラなどの「動物社会」をも。 繁栄するのはいかなる社会か? そこには驚くべき共通点があった――。科学界からビジネス界まで、全方面から絶賛されたニューヨークタイムズ・ベストセラー、待望の日本語版。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 最高峰の知性が読み解く 世界情勢の現在と未来 世界を俯瞰する100の地図を収録! ✔巨大企業は世界を支配しうるか? ✔移民問題はコントロールできるか? ✔中国は世界の主導権を握れるか? ❖目次 イントロダクション グローバリゼーションとはなにか│6 国際秩序│10 │第1部│世界 第1章│歴史的視点 1945年の世界秩序│20 ヨーロッパの分断│24 冷戦と雪どけ│28 非植民地化と第三世界の出現│32 ソビエト帝国の崩壊│36 1989年の戦略的状況│40 第三世界の終焉と、西側による力の独占の終焉│44 第2章│国際関係のプレイヤー 要となるプレイヤー、国家│50 国連は世界を統治できるか?│54 国際機関は脇役か?│58 NGOは新たなプレイヤーか?│62 多国籍企業は世界の新たな支配者か?│66 力を増す世論│70 第3章│地球規模の課題 国際統治とは?│76 経済発展│80 気候温暖化:戦略上の重大な脅威│83 人口増加は抑制できるか?│86 移民の動きは制御不能か?│90 テロリズムは生存にかかわる脅威か?│94 核拡散は避けられないか?│98 組織犯罪とマフィア│102 スポーツ外交│106 国際的司法機関は夢物語にすぎない?│111 民主主義と人権は広まっているか?│114 文明の衝突へ?│117 第4章│歴史上の重大な危機と戦争 ドイツの分断とベルリン危機│122 朝鮮戦争│125 スエズ戦争(第二次中東戦争)│128 キューバ危機│131 ベトナム戦争│134 アフガニスタン紛争(ソ連)│137 アフガニスタン紛争(NATO)│140 湾岸戦争│143 ルワンダ虐殺│146 バルカン半島の紛争│149 コソボ紛争│153 イラン、アメリカ、イスラエル│156 イスラエル・アラブ紛争│159 イラク戦争│163 第5章│現代の危機と紛争 ロシアとウクライナは和解不能か?│168 奈落の底に落ちたシリア│171 イスラム国(IS)は国家並みのテロ組織か?│174 イランとサウジアラビアの対決│178 イスラエルとパレスチナ:果てしない紛争?│181 イラクは再建に向かっているか?│185 東・南シナ海における緊張│188 朝鮮半島:紛争は凍結?│191 米中関係:協調か敵対か?│194 │第2部│各地域 ヨーロッパ フランス:主要な大国│202 ドイツ:復活した大国│206 イギリス:ヨーロッパの大国?│210 イタリア:役割の見直し│213 イベリア半島│217 中央・東ヨーロッパ諸国:均質ではない地域│221 北欧:多様な特色を持つ地域│225 ヨーロッパの再建│228 紛争後のバルカン諸国│232 再確認されたロシアの強さ│235 トルコよ、どこへ行く?│240 南北アメリカ アメリカを再び偉大にする?│246 カリブ海地域:アメリカの裏庭?│252 中央アメリカ:安定を求めて│256 アンデス諸国:新たな出発│260 コノ・スール(南の円錐):力を秘めた極地?│264 アラブ世界 マグレブ地域の統合は不可能か?│270 マシュリクは混沌とした地域か?│274 安定が脅かされるアラブ・ペルシャ湾│278 アフリカ 西アフリカ:民主化と人口問題の間で│284 中部アフリカは立ち往生?│288 東アフリカとアフリカの角:開発と専制政治の間で│292 南部アフリカの大きな存在感│296 アジア インド:将来の大国?│302 東南アジア:地域統合と経済発展│308 朝鮮半島:分断の固定か、克服か?│312 日本:不安な大国│316 中国は世界一の大国か?│320 地図一覧│326
-
-35歳でオックスフォード大学正教授に就任した、いま最注目の政治学者が、分断と格 差の起源と解決という難題に鮮やかに答える! ―対立軸を組み変え、民主主義・福祉・繁栄した社会を持続可能にする、ほとんど唯 一の狭い道。 政治はなぜ常に私たちを失望させるのか? 古代ギリシャから気候変動条約、ブレグ ジットまで、私たちが集まると近視眼的選択の「罠」に落ちてしまう。それを回避す べく、直感に反する最近の研究成果、例えば政治・社会的平等の増加が大きな不平等 をもたらし、不平等の高まりが民主主義を促す逆説などを活用して、現実政治の罠か ら脱出する方法を生き生きと説明する。
-
-心理学的、神経学的に全てを研究し尽くした集団が、その成果を逆手にとって人間を追い詰める―いまその過程の真っ只中で、何ができるのか?! 心理学者と反骨のジャーナリストが放つ、最後の一撃!あなたがいかに防衛機制のカラクリで心を守ろうとしても無駄です! AINO 16世紀、モンテーニュの友人であったラ・ボエシの「自発的隷属論」というものがあります。権力者のおこぼれにあずかりたい「とりまきたち」は、喜んで自分から奴隷のように従う。そして、支配されることの中に喜びを見出しているようにさえ見える。臆病と呼ばれるにも値しない、それに相応しい卑しい呼び方が見当たらない悪徳を「自発的隷属」とラ・ボエシは呼んでいます。 船瀬 全ての洗脳のルーツは集団主義だと思います。集団による、同調圧力だ。あなたがおっしゃった「美徳」と「キズナ」というのは、全て集団からもたらされる圧力。 AINO 最近話題になっているのがポリヴェーガル理論です。みなさんがご存知の「戦うか、逃げるか」の反応、そこからもう一段複雑な神経系の働きを、「安全と繋がり」を求めるメカニズムとして説明します。どんな人も、無意識的に、つまり自律神経の働きとして安心と絆を求めている!私たちは自動的に、そのように反応する仕組みを神様から授かっている! 船瀬 あなたの言った、防衛機制。これは、キーワードだ。そこで「合理化」っていうのもある。「攻撃」というのもある。「逃避」もあるじゃないですか。だから真実から目をつぶって逃げる。もう防衛機制の一つだったんだと思う。だけど、それは一時的には自分を救うよ。だけど、長い目で見たらワクチンの行列に並んでるわけだ。 AINO だから短期的には、救われても長期的には殺される。そういうケースです。進んで喜んで奴隷になっている人達がどれだけ多いことでしょう。 生まれつき、自由を求めるはずの人間が、なぜ自ら進んで自由を放棄してしまうのか。そこには何か快感があるに違いありません。皆、安心したいのです。ポリヴェーガル理論で説明したように、誰もが、生き残るために人と繋がっていたいのです。分断されてしまうことに耐えられる人は多くはいないのが実情です。
-
-日本三大清流に数えられる長良川は、本州の大河で唯一本流にダムと堰のない川と言われ、山・川・海の連続した生物圏の上に豊かな水文化が育まれてきた。アユをはじめ海と川を回遊する生き物、汽水域で生活する生き物は長良川の大切な恵みであり、川の生物圏の連続性、持続可能性の指標だが、河口堰はその営みを分断した。2015年、長良川の天然アユは岐阜市で準絶滅危惧種に指定(後に削除)、「清流長良川の鮎」が世界農業遺産に認定された。本書は、生物多様性の喪失が地球の限界を超えている時代に、川の生物圏を再生し、社会や経済の基盤として復権させ、川と人の関係を結びなおす可能性を探る。
-
-「ハンガー・ゲーム」(飢えた民の殺し合い)を楽しむ1%の大富豪たちは、全人類の囚人化・AI奴隷化を狙う! 第6章 なぜ私たちはわからないのか? 第7章 私たちはどのように操られているのか? 第8章 なぜ生命のガスを悪魔化するのか? 第9章 なぜ「気候変動」が担がれてきたか? 第10章 あなたはニューウォーク? ・カルトによる「教育」は、ハートチャクラを閉じ、右脳を抑圧し、若者を生涯にわたってボディーマインドのシャボン玉(孤立した自己認識)に閉じこめることが目的 ・生まれたときから知覚プログラミングを受けた「ニューウォーク」は、資本主義ではなく「カルテル主義」=「共産/社会主義」(カルトが目指すエリート支配体制)を望み、みずからの首を絞める規制や検閲を要求。大いなるワンネスを思いださぬよう、小さく小さく細分化されたアイデンティティに閉じこもるようしむけられている ・映画『ハンガー・ゲーム』は現実を描いている。都市に人を詰めこんで、AIによる徹底管理を行なう。それが「スマートシティ」だ ・欧米の国境を開放し、異文化を流入させ、社会を変容させる。異を唱えれば、ポリコレ警察が「レイシスト」と糾弾する。「国」意識が薄れ、「世界政府」への道が開かれる ・陸上資源、海洋資源、淡水資源などすべてを世界政府が計画・管理 ・グレタ・トゥーンベリは、若者を結集させ、大人に対して反乱を起こさせるためにかつぎ出された。世代間に分断をつくりだし、完全に知覚プログラミングされた若者に天下をとらせ、プログラム不足の大人を排除するのが目的 ・気候科学者の97%が唱える「人類が気候変動の主な原因」説はでっちあげ。気候変動デマは、幻想を信じさせるための知覚操作。カルトは生命に必要である二酸化炭素を悪魔のガスとし、逆転した真実を常識として売りこんだ。行き着くところは、人間の存在自体が地球にとって害であるという「アンチヒューマン(反人間)」アジェンダだ ・SDGsは、「ハンガー・ゲーム」社会を押しつけるため
-
3.0コロナ禍で、とりわけ若年層や女性たち、非正規雇用の困窮層が急増し、 私たちは深刻な貧困問題、格差拡大に直面している。市場競争、経済成長、 効率性に最大の価値を置く新自由主義がもともとはらんでいた危機が、 コロナ禍で顕在化した。 その中で、市民社会の中からNPO、協同組合、社会的企業などの 多様な実践が生まれ、共的な空間を築きあげ、新しいつながりの経済を 生み出している。 孤立や分断の社会を乗り越えるための世界と日本の具体的とりくみとは? 【目次】 序章 なぜ社会的連帯経済なのか (藤井敦史・立教大学コミュニティ福祉学部教授) 第1章 社会的連帯経済とは何か(藤井敦史) 第2章 イタリアにおける社会的企業の展開過程 (田中夏子・都留文科大学教養学部教員) 第3章 社会的連帯経済を推進する世界の運動 (田中滋・アジア太平洋資料センター事務局長・理事) 第4章 不安定社会の編み直しを求めて―社会的企業研究会の展開から 浮かびあがるサード・セクターの新しい実践潮流 (菰田レエ也・鳥取大学地域学部教員) 第5章 労働者協同組合の社会化戦略―協同労働を軸に明日が希望と思える 社会変革へ(相良孝雄・協同総合研究所事務局長(理事)) 第6章 地域再生政策における連帯的な経済の可能性と課題 (原田晃樹・立教大学コミュニティ福祉学部教授) 第7章 公的サービスの外部化と非営利組織の評価(原田晃樹) 第8章 私たちが韓国社会的経済から学んできたことは何か(藤井敦史)
-
4.2戦争、パンデミック、資源争奪、サイバーテロ…… 人類の存亡を脅かす危機の正体と解決策を、地政学の世界的な大家が語る! 「世界は日本のリーダーシップを必要としている」(本文より) 【人類の存亡を脅かす「3つの危機」】 現在、我々は3つの危機に直面している。 1つはパンデミックだ。世界は今も、新型コロナウイルスの経済的、政治的、社会的影響を払拭できずにいるばかりか、今後も危険なウイルスが世界を苦しめるのは間違いない。 2つ目は気候変動で、何十億もの人々の暮らしを一変させ、地政学的なリスクを高める要因となる。 3つ目は破壊的な新技術だ。我々の生き方、考え方、他人とのかかわり方を変え、それが思わぬ悪影響を人類におよぼし、未来を決めるだろう。 分断が進むこの世界で、人類は果たして危機を乗り越えられるのか……。 だが、希望はある。 歴史を見ても、人類の存亡に関わる危機、世界的な戦乱が起こりかねない断絶が起こると、それを避けるために協調の動きが起こる。 逆説的だが、分断を乗り越えるために「危機の力」が必要なのである。 本書は、地政学の第一人者による「警告の書」であると同時に「希望の書」でもある。 【本書の主な内容】 ・新たな冷戦の正体とは? ・台湾、そして東アジアの火種 ・コロナが明らかにした地政学的停滞 ・次の危険なパンデミックは、確実にやってくる ・ロシアのウクライナ侵攻が意味するもの ・弾圧の道具を売る強権国家 ・気候アパルトヘイトというリスク ・気候難民の権利は守られるか ・下がる戦争へのハードル ・偽情報と暴力行為の扇動 ・「監視資本主義」の台頭 ・自律型兵器の恐怖 ほか
-
3.8【内容紹介】 ディストピア禍の新・幸福論 パンデミック、気候変動、格差拡大、侵略と戦争…… 混迷と分断の“ディストピア禍”に問う 心とは、生きるとは、幸せとはなにか? 慶應義塾大学大学院教授の「幸福学者」が書き尽くした入魂の書! コロナショック、大規模な気候変動、苛烈さを増す自然災害、経済的な格差の拡大など、不幸の連鎖が止まらない。そのうえ、人類は21世紀になっても戦禍の中にいる。 そんな時代に、わたしたちは幸せに生きることができるのか? そもそも幸せとはなにか? どうすればあらゆる人が幸せに生きる世界をつくれるのか? 「幸福学」の第一人者である著者・前野隆司氏が、それらの問いに正面から取り組んだのが本書である。 科学と宗教、洋の東西、人間とロボット……一見相反する領域をダイナミックに架橋しながら、力強く本質を掘り下げていく。 思索の果てに辿り着いた「幸せの正体」は、「いま」を生きるすべての人の希望となるだろう。 ――本書では、脳神経科学・心理学・統計学・工学を中心とした様々な科学的研究の結果として、その結論を導いていく。 【著者紹介】 [著]前野 隆司(まえの・たかし) 1962年、山口県生まれ。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)教授。1984年、東京工業大学工学部機械工学科卒業。1986年、東京工業大学大学院理工学研究科機械工学専攻修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、慶應義塾大学理工学部教授、ハーバード大学客員教授等を経て、2008年より現職。2017年より慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼任。認知心理学、脳神経科学、倫理学、統計学、工学などの研究を統合した「幸福学」を提唱し、個人と人類の幸せ(well-being)について研究している。主な著書に『脳はなぜ「心」を作ったのか 「私」の謎を解く受動意識仮説』(筑摩書房)、『幸せのメカニズム 実践・幸福学入門』(講談社)、『ウェルビーイング』(共著、日本経済新聞出版)などがある。 【目次抜粋】 第1章 前提条件:心はない パンデミックという人類滅亡リスク/資本主義は限界を迎えたのか?/日本というガラスの城/「ウェルビーイング産業」への転換を/自殺を「悪」と切り捨てていいのか?/日本人が見落としがちな「無意識」の利他性/心はすべて、幻想である/意識は「記憶のための劇場」である/「脱人間」という不安の超克 etc. 第2章 必要条件:死を想う 心がなくて本当によかった/いま死んでも、あとで死んでもたいした違いはない/ふたつの本能――「怒り」と「共感」/他者を「許す」ことはなぜこんなに難しいのか?/一生の長さはたったの0.1ミリ/人間には、過去も未来もない/わたしたちには「いましかない」し「いまはない」/主観的には死は存在しない/あなたは本当に「あなた」なのか? etc. 第3章 幸せの連立方程式 生きてよし、死してよし/幸福学――幸せは原因にも結果にもなる/「ありのままに!」――他人と自分を比べない/「やってみよう!」――主体的に生きる/「なんとかなる!」――未来を信じる/「ありがとう!」――ともに生きる/戦いのエンジンから愛のモーターへ/「ルールに従う」という思考停止/サイエンスとしての倫理学 etc. 第4章 解:わたしは、地球であり宇宙である わたしは地球の一部以外の何者でもない/蔓延しているのはウイルスか、それとも人間か?/人類は「安心安全」かつ「不幸」になった/「一番大切なこと」を一番大切にしよう/中心に無がある国、日本/近代科学が見つけた、近代的価値観の限界/そして、東まわりと西まわりが出会うとき/すべてを包摂する「ウェルビーイング資本」主義 etc. 第5章 分岐点:愛するか、滅びるか 心の地動説/「世界中の生きとし生けるものを愛す」ことは可能か?/人間という合体動物/世界はあなたである/世界を100パーセント愛することをイメージしよう/敵は消え去る/「自利利他円満」というひとつの円/あなたが幸せでありますように etc.
-
-亡命チベット人医師が遺したチベット愛と苦難の長編歴史小説 1925年、若きアメリカ人宣教師スティーブンス夫妻は幾多の困難を乗り越え、チベット、ニャロン入りを果たした。現実は厳しく布教は一向に進まなかったが、夫妻は献身的な医療活動を通じて人びとに受け入れられていく。やがて生まれた息子ポールと領主の息子テンガは深い友情で結ばれる。だが、穏やかな日々も長くは続かない。悲劇が引き起こす怨恨。怨恨が引き起こす復讐劇。1950年、新たな支配者の侵攻により、人びとは分断され、緊迫した日々が始まる。ポールもテンガもその荒波の中、人間の尊厳を賭けた戦いに身を投じてゆく。 【目次】 この本について 第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 訳者解説 【著者】 ツェワン・イシェ・ペンバ チベットのギャンツェ生まれ。医師であり作家。1941年にインドのイギリス式学校に入学して英語を身につけ、1949年にロンドン大学に留学。医学を学び卒業後はブータン、インドなどで外科医として活躍。1957年にチベットで過ごした日々をエッセイに綴った『少年時代のチベット』をロンドンで出版。1966年にはチベット人として初めての長編小説『道中の菩薩たち』を出版。その後創作活動から離れていたが、晩年ようやく実現したチベット旅行をきっかけに『白い鶴よ、翼を貸しておくれ』を執筆後病没。享年79歳。 星泉 1967年千葉県生まれ。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授。チベット語研究のかたわら、チベットの文学や映画の紹介活動を行っている。訳書にラシャムジャ『雪を待つ』、共訳書にトンドゥプジャ『ここにも躍動する生きた心臓がある』、ペマ・ツェテン『ティメー・クンデンを探して』、タクブンジャ『ハバ犬を育てる話』、ツェラン・トンドゥプ『黒狐の谷』などがある。『チベット文学と映画制作の現在 SERNYA』編集長。
-
-闇の歴史に終止符を打つための切り札! それが『日本の大麻』であることを今こそ深く理解するとき――。 古代日本の叡智である大麻と意識進化の秘儀、その実践法がいま解かれる。 GHQは大麻草を分断、禁止することで何を封じ込めようとしたのか。 祓い清め産靈(むすひ)の叡智に精通し、日本の大麻復古に尽力する著者が、 現象化を引き起こす「大麻、言靈、祈り(意宣り)」の秘儀三法を紐解いていく。 クローズアップすべきは、大麻の祓いの、リセットさせて進化させていく力! さまざまな穢れがあふれる現代において、 多くの人が陥っている「憑かれからの疲れのループ」を断つ秘訣がここにある。 「戦いから調和へ価値観のシフトを促すのが大麻である」 と伝える大祓祝詞に示された予言を読み解きながら、 ひふみ祝詞、言靈、神々のエネルギーと大麻の秘密を詳らかにしていく。 <第1章 呪術の限界> 裏密教大阿闍梨との出会い/不動明王開眼の術法/密教のエクソシスト的降伏法の限界 <第2章 分断された大麻> 罪か祈りか/医療大麻/内因性カンナビノイド/和方―祈りと生薬 <第3章 大麻と祓い清め> 神道における大麻/精麻の霊力「水に流す」威力/祓いとは、邪を転じて生かす道 <第4章 大麻と言靈~『荒の言靈図』から『麻の言靈図』へ> 大祓祝詞は予言メッセージ/争いから調和へ大転換期/ 『あたかまはらなやさわ』の音靈/ひふみ祝詞と神々のエネルギー <第5章 大麻と祈り~闇の歴史に終止符を打つ切り札!> 大麻・言靈・祈りの三位一体は、現象を発現させる秘儀中の秘儀/ 八百万神は一人ひとりのこと―肚の意(祓い)で岩戸を開く <第6章 実践! 精麻を使った日々の祓い清め> 結界の張り方/日々の祓い清め 日々生じてしまう重い感情を水に流せていますか。 対立から生まれる何かしらが体の負担、ストレスになっていませんか。 陰(女性性)陽(男性性)のバランスは保たれていますか。 体の中の水は穢されていませんか。 現代の私たちは、なぜ調子が悪くなりやすいのか。 私たちが内なる神にアクセスすることができないように、 ここ何百年かの内に、形而上の領域で 《魔の仕掛け》がなされていることは明白です。 私たちはその仕掛けに動かされているのです。 これを《大麻》で切ることができます。 直き力に変えることができます。 大麻は、目に見えない形而上の世界に 純なる意図を到達させることができる唯一の、しかも強力な植物です。 だから、ある人たちからすると日本の大麻は恐ろしい。 彼らが最も恐れるのは、 私たちが<本来の祈りの形>を思い出すこと――― 祓い清め、真釣り合わせて、本望(肚の意=祓い)で生きる!
-
3.0ゲーム、ソフトウェア、モバイル、資本、ジェンダー、観光、軍事まで…… 現在/過去の技術や概念を体系的に一望できる、メディア論の新しい教科書! 2020年代を迎えた現在、グローバル資本主義と政治的分断の加速を背景に、インターネット以降のテクノロジーやスマートフォン、SNSの一般化はさらに進み、メディアを取り巻く社会や文化、私たち人間の状況は、かつてないほどの大きな変化にさらされ、メディアの在り方も大きく変容し続けています。 そのような状況において「メディア論」は常にアップデートされ続ける研究領域であり、現代社会のあらゆる局面を考える上でますます重要な分野になっていると言えるでしょう。本書は、人文社会研究におけるメディア論の新たな動向や、メディア理論の歴史的な系譜を現代の視点で整理し直し、さらにメディアの実践を横断的にとらえて論じることを試みた、理論編・系譜編・歴史編の三部からなるメディア哲学の入門書です。 ◆シリーズ[クリティカル・ワード]とは 現代社会や文化および芸術に関わるさまざまな領域を、[重要用語]から読み解き学ぶことを目指したコンパクトな入門シリーズです。 基本的かつ重要な事項や人物、思想と理論を網羅的に取り上げ、歴史的な文脈と現在的な論点を整理します。もっと深く理解し、もっと面白く学ぶために必要な基礎知識を養い、自分の力で論じ言葉にしていくためのヒントを提供します。
-
-本書は、明治維新から現在に至る日本の建築史を一筆書きで描き出す試みである。日本の建築史については、これまで幾多の著作が書かれてきたが、1970年までで終わるものがほとんどで、その後の時代を包含するものはない。バブル経済に沸き立った1980年代を経て、長い不景気の時代を迎えた日本は大きな変化を受けている。ならば、21世紀の今、本当に必要なのは、この150年の歴史を通覧することにほかならない。 本書は全二部で構成される。第一部では、従来の建築史が扱ってきた明治維新から1970年代までの時期を取り上げる。そこでは、「国家のための建築」という特殊な役割を負わされる中で、明治期に導入された西洋の建築様式との格闘を続けながら、大正期、戦時期、そして戦後の復興から高度経済成長期までの激動の歴史が描き出される。続く第二部は、その「国家のための建築」という役割から解放された建築が、いかに拡散し、現在見られるような複雑な様相を呈するに至ったのかを見る。 自宅にいても、街に出ても、常に私たちは建築に囲まれている。にもかかわらず、建築について、その歴史について、手軽に基本的な知識を得られる書籍がない、というのは不思議なことである。本書は、そんな状況に終止符を打つべく、専門的な知識を必要とせず、ただ歴史的な建築物を羅列するのではなく、それぞれの時代に何が求められ、何が考えられたのか、その背景には何があったのかを明快に描くことを主眼としている。 本書を読めば、日本の建築について知悉できるばかりか、建築とは何か、そして建築物とともに生きるとはどういうことなのか、という重要な問題について明確なイメージをもつことができるだろう。 建築家として活躍するだけでなく、建築批評でも定評ある地位を確立してきた著者が手がけた壮大なドラマ、ついに完成。 [本書の内容] 第一部 国家的段階 第一章 明治維新と体系的な西洋式建築の導入/第二章 非体系的な西洋式建築導入/第三章 国家と建築家/第四章 明治期における西洋式建築受容の到達点/第五章 直訳的受容から日本固有の建築へ/第六章 近代化の進行と下からの近代化の立ち上がり/第七章 近代建築の受容と建築家の指向の分岐/第八章 総動員体制とテクノクラシー/第九章 戦災復興と近代建築の隆盛/第一〇章 建築生産の産業化と建築家のマイノリティ化/第一一章 国家的段階の終わり 第二部 ポスト国家的段階 第一章 ポスト国家的段階の初期設定/第二章 発散的な多様化と分断の露呈/第三章 新世代の建築家のリアリティと磯崎新/第四章 定着した分断とそれをまたぐもの/第五章 バブルの時代/第六章 一九九◯年代以降の展開と日本人建築家の国際的な活躍/第七章 ポスト国家的段階の中間決算
-
3.7分断、移民、グローバリズム、フェイクニュース…… 独裁者は見慣れた場所から生まれる。 ナチ党の活動は、第一次大戦後に英米が押し進める国際協調、経済的にはグローバリゼーションに対する抵抗だった。 戦後賠償だけがドイツを追い詰めたわけではない。 ロシア革命などによる東方からの難民、共産主義への保守層の拒否感、社会の激しい分断、正規軍と準軍事組織の割拠、世界恐慌、「ヒトラーはコントロールできる」とするエリートたちの傲慢と誤算……アメリカを代表する研究者が描くヒトラーがドイツを掌握するまで。 ——現代は1930年代の再来? 【目次】 イントロダクション 1 八月と一一月 2 「信じてはいけない、彼が本当のことを言っていると」 3 血のメーデーと忍び寄る影 4 飢餓宰相と世界恐慌 5 国家非常事態と陰謀 6 ボヘミア上等兵と貴族騎手 7 強制的同質化と授権法 8 「あの男を追い落とさねばならない」 訳者 あとがき ナチ党が政権をとるまでの主な出来事
-
-デモクラシーにこそ、「野蛮」を生み出す危険性が潜んでいる。文明の極まりに生じる自由と平等の葛藤をいかに乗り越えるか。デモクラシーの在り方を問い直す試み。 はじめに 第Ⅰ部 デモクラシーと市場の選択 第1章 高齢社会のデモクラシー 第2章 ナショナリズムと経済政策 第3章 メディアの役割と読者の責任 第Ⅱ部 教育と学問が向かうところ―高等教育を中心に 第4章 社会研究における人文知の役割 第5章 大学の理念とシステム 第6章 「大学改革」をめぐって 第Ⅲ部 文明から野蛮へ? 第7章 歴史に学ぶとは 第8章 格差と分断 第9章 文明から野蛮へ
-
3.8ホモ・サピエンス誕生からトランプ登場までの全人類史を「家族」という視点から書き換える革命の書! 人類は、「産業革命」よりも「新石器革命」に匹敵する「人類学的な革命」の時代を生きている。「通常の人類学」は、「途上国」を対象とするが、「トッド人類学」は「先進国」を対象としている。世界史の趨勢を決定づけているのは、米国、欧州、日本という「トリアード(三極)」であり、「現在の世界的危機」と「我々の生きづらさ」の正体は、政治学、経済学ではなく、人類学によってこそ捉えられるからだ。 下巻では、「民主制」が元来、「野蛮」で「排外的」なものであることが明らかにされ、「家族」から主要国の現状とありうる未来が分析される。 「核家族」――高学歴エリートの「左派」が「体制順応派」となり、先進国の社会は分断されているが、英国のEU離脱、米国のトランプ政権誕生のように、「民主主義」の失地回復は、学歴社会から取り残された「右派」において生じている。 「共同体家族」――西側諸国は自らの利害から中国経済を過大評価し、ロシア経済を過小評価しているが、人口学的に見れば、少子高齢化が急速に進む中国の未来は暗く、ロシアの未来は明るい。 「直系家族」――「経済」を優先して「人口」を犠牲にしている日本とドイツ。東欧から人口を吸収し、国力増強を図かるドイツに対し、少子化を放置して移民も拒む日本は、国力の維持を諦め、世界から引きこもろうとしている。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。












![[グラフィックノベル] ベルリン 1928-1933](https://res.booklive.jp/1421561/001/thumbnail/S.jpg)























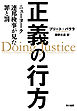
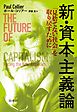































![最新改訂版 確認申請[面積・高さ]算定ガイド](https://res.booklive.jp/20057161/001/thumbnail/S.jpg)




















![答え 第3巻[偽の社会正義編]](https://res.booklive.jp/20058658/001/thumbnail/S.jpg)









