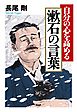司馬遼太郎作品一覧
-
4.4
-
4.5
-
-
-
5.02018年、NHK大河ドラマ「西郷どん」放送! 生誕190年&没後140年、そして明治維新150年! 本当の「西郷どん」とはどういう人間だったのか? なぜ、一薩摩藩士が討幕という偉業を成し遂げられたのか? 「征韓論」とは、一体何だったのか? そして、無謀とも思える「西南戦争」に打って出た理由は何だったのか? 今こそ知っておきたい西郷隆盛の生き方と熱い名言が、 “齋藤流人生読解術”で面白いほどよくわかる!! <名言の一例> 自ら精神を養うて人を咎めず 訳 他人のことは言うまい。ただ自分の精神を鍛えよう 夢幻の利名なんぞ争うに足らん 訳 名声などはしょせん夢幻みたいなものだから、わざわざ追うほどのものではない やっぱり西郷隆盛はすごかった! キーワード「智仁勇」でわかる日本人的リーダーシップの秘けつ!! 強いチームには、その中心に「絶対にやり遂げるぞ」という気力、 活力の源泉になる人物というのが必ずいるものです。 経営学の父として知られるドラッカーは、そうした人のことを「エグゼクティブ」と呼びました。 ギリギリのところで戦争を回避した江戸城無血開城、あるいは、武士の既得権益にかかわるので、 誰もが手をつけるのを嫌った廃藩置県を成功に導いた西郷隆盛という人物は、 まさに史上最高峰のエグゼクティブだったといっていいのではないでしょうか。――「はじめに」より 西郷の心事は天下の人にはわかるまい、 わかるのはおれだけだ。 ――大久保利通(参議・内務卿)158ページより 日本的美質を結晶させたという点ではほとんど奇跡的な人格を持つ男 ――司馬遼太郎(作家)169ページより
-
4.2
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1925(大正14)年。本書の主人公、藤井富太郎は木曜島へ移民として渡り、真珠貝採取の仕事に就いた。 戦前、オーストラリアに移民した日本人の多くが真珠貝採取業という危険を伴う海での職業を生業とした。 中には潜水病で命を落とす人も少なくなかった。司馬遼太郎著『木曜島の夜会』では、その仕事ぶりや生活が紹介されている。 和歌山・串本から真珠貝ダイバーとして移民した藤井富太郎氏の生涯を通じて、オーストラリアにおける戦前の日本人移民の歴史とその生活の一端を垣間見る。
-
-
-
3.0原作のストーリーを追いながら、厖大な資料を駆使して、その背後にある数多くの新事実を発掘!司馬遼太郎の名作『坂の上の雲』をさらに面白くする著者渾身の作! (※本書は2009/11/1に発売し、2022/2/10に電子化をいたしました)
-
3.0
-
-
-
4.0
-
-「大破局」を描いた作家小松左京は、夢の大阪万博に何を見たのか。 モンゴルの草原に憧れた司馬遼太郎のロマンと、本質的悲劇とは。笠智衆を選んだ名匠小津安二郎。その静かなる戦いと、いつかくる「最後の五分」に込めた知られざる覚悟とは……。鮮やかな着眼で巨匠たちの思考を読み解きつつ、日本の過去・現在・未来を浮かび上がらせていく。この国の大きな断面を明らかにする画期的評論!(解説・先崎彰容)
-
4.5幕末維新期きっての剣客「人斬り半次郎」として知られる桐野利秋とは、果たして何者だったのか。司馬遼太郎が描いた人物像の検証から、幕府と雄藩の間で繰り広げられた情報戦の内実、維新後に陸軍少将に大出世できた本当の理由、西南戦争での壮絶な最期まで。激動の時代に暗躍した西郷隆盛の懐刀の実像に迫る、初の本格評伝。
-
-私立探偵の須藤は自分の事務所で依頼人に自殺されてしまい、それが一連の連続自殺事件と関連があると考え、インターネット上で人格データとしてのみ存在している元相棒に相談に行く。やがて捜査をするうちに自殺した依頼人について不審な点を見つけ、現実世界に戻るが、そこで自身の体を操られる事態に至る。そして、危機を脱した須藤は再び元相棒の下を訪れる。 ■著者コメント サイバーパンク風のハードボイルド探偵もので、主人公と元相棒との友情とその齟齬の結末を描いており、軽く読める。本好きな人間にはにやりとできるディティールがいくつかあります。 ■著者プロフィール 1990年、北関東とも時には南東北とも言われる栃木県にて生まれる。哲学を学びつつ、如何にして社会にもぐりこんで金銭を得るかを模索する。亀を二匹飼っており、ペンネームの「たあとおる」は「タートル」をもじってつけた。酒と寿司が好物であり、たまに魚を買ってきて卸したりする。またよくウイスキーを好み、ほぼ毎日飲酒浸りの日々。好きな作家は、レイモンド・チャンドラー、ヘルマン・ヘッセ、司馬遼太郎など。
-
4.0日本の言論はなぜ分断したのか ◎北京の特等席に座り続ける新聞と追放された新聞 ◎「あえて書かない」新聞と言論裁判に苦しめられた新聞 ◎GHQに屈した新聞とGHQと闘った新聞 ◎護憲しか考えてはいけない新聞と改憲に理想を求める新聞 ◎戦前から大東亜共栄圏を理想とする新聞と脱亜入欧を訴える新聞 ◎平和だけを目的とした新聞と平和の維持を考える新聞 ◎日本を敵視する国から「友好的」と褒められる新聞と「極右」と蔑まれる新聞 だから我々はGHQ、中国共産党、日本共産党、青瓦台、金政権、 そして朝日新聞と闘った! 「極左も極右も排す」真の自由主義を説いた戦前の思想家、河合栄治郎。 「強い日本」づくりを目指した明治の思想家、福澤諭吉。 産経新聞に2人の遺志が脈々と受け継がれていることは意外に知られていない。 一つの言論しか許されない社会は独裁社会であり、暗黒社会である。 産経の存在と主張、さらに言えばその魂をもっと広く知ってほしい。 本書は戦後マスコミ界の裏面史である! 《おもな内容》 第一章 二つの「中国」に向き合う 第二章 言論裁判に勝つ 第三章 福澤諭吉と河合栄治郎 第四章 司馬遼太郎の遺言 第五章 朝日が目指す「大東亜共栄圏」 第六章 追い込まれるメディア
-
3.0歴史はふりかえってみるものではない。すすんでいって、みるものである。「特別随想 ふりかえること」より 『三国志』をはじめ長年、中国歴史小説を書き続ける著者が、みずからの歴史観、世界観、小説観をあますところなく開陳した。 自作解説や作家、経済人、学者など多彩なメンバーとの対談などを収録。 <目次> 【ロングインタビュー】私の「歴史小説」 【自作解説】三国志の世界 ・『三国志』の沃野に挑む--大歴史絵巻の豊穣なる世界 ・曹操と劉備、三国志の世界--正史からみえてくる英雄たちの素顔 ・『三国志』の可能性--歴史は多面体だからこそおもしろい ・『三国志』歴史に何を学ぶのか--構想十年、執筆十二年の大長編を終えて 【対談】歴史小説を語る ・水上勉--歴史と小説が出会うところ ・井上ひさし--歴史小説の沃野 時代小説の滋味 ・宮部みゆき--「言葉」の生まれる場所 ・吉川晃司--我々が中国史に辿り着くまで ・江夏豊--司馬遼太郎真剣勝負 ・五木寛之--乱世を生きるということ 【講義&対談】中国古代史の魅力 ・中国古代史入門--どこから学べばいいのか ・白川静--日本人が忘れたもうひとつの教養 ・平岩外四--逆風の中の指導者論 ・藤原正彦--英語より『論語』を ・秋山駿--春秋時代から戦国時代へ ・マイケル・レドモンド--碁盤上に宇宙が見える ・項羽と劉邦、激動の時代--ふたりを動かした英雄たちと歴史的必然 ・『三国志』をより深く楽しむための本 ・宮城谷昌光 中国歴史作品の年代一覧 ・特別随想 ふりかえること ・宮城谷昌光 出版年譜
-
-日本近代を動かした英傑(おとこ) 吉田松陰、久坂玄瑞、楫取(かとり)素彦の生涯を見届けた、知られざる「女の一生」とは。 2015年NHK大河ドラマ『花燃ゆ』のヒロイン・杉文。 なぜ今、まったく無名といっていい文を主役にしたのか。 歴代の大河ドラマで時代考証を務めた著者が、文の人生を通り過ぎた男たち、吉田松陰、久坂玄瑞、楫取素彦との関わり合いから「名もなき女の一生」に迫る。 【内容抜粋】 ●大河ドラマ『花燃ゆ』の題名に秘められた意味 ●「篤姫」「新島八重」と同時代を生きながらどう違うか ●「女性登用」時代にあえて問う「名もなき女たちの偉大さ」 ●文の子ども時代が偲ばれる姉・芳子の談話 ●司馬遼太郎が「維新史の奇蹟」と呼んだ松陰の存在 ●兄・松陰の早すぎる死を、文はどう受け止めたか ●久坂玄瑞が最初、文との縁談を渋った理由とは ●20通の手紙が語る玄瑞と文の、短いながら細やかな夫婦愛 ●楫取、男爵となり華族に列せられ、美和子は男爵夫人となる ●楫取素彦は、なぜ歴史上の主役にならなかったのか
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 維新途上で倒れていった志士たちの行動原理はなんだったのか? 生き残った明治の元勲たちはどうしてヒーローになりえたのか? 司馬遼太郎が描いた英雄たちは、本当は何者だったのか? つくられた「ヒーロー伝説」の真実を追究した「思想劇画」シリーズの第1弾。 幕末ファン、司馬遼太郎ファンに大きな衝撃を与えた2004年刊行の問題作を、加筆修正して復刊。 第1章 文久2年の巨大な謎 第2章 外国は、日本を支配しにやってきた! 第3章 坂本龍馬と秘密のインナー・サークル 第4章 幕末ゲバゲバ・尊皇攘夷事件クロニクル! 第5章 幕末に英雄はいない!
-
5.02023年は司馬遼太郎生誕100年! 司馬さんが好きだった花に由来する〈菜の花忌〉。 司馬作品にちなんだテーマで、パネリストたちが自由に意見交換をする シンポジウムは、司馬作品のさらなる魅力を見出す場として、定着している。 過去25回の中から17回分のシンポジウム、3本の講演を編んだ、 文春文庫オリジナル。新たな気づきを与えてくれる貴重な記録。 (目次抜粋) 「竜馬と司馬遼太郎」井上ひさし・檀ふみ・永井路子・松本健一/「二十一世紀に生きる君たちへ」安藤忠雄・井上ひさし・養老孟司/「司馬作品の輝く女性たち」田辺聖子・出久根達郎・岸本葉子/「『坂の上の雲』と日露戦争」篠田正浩・黒鉄ヒロシ・松本健一・加藤陽子/「3・11後の『この国のかたち』佐野眞一・高橋克彦・赤坂憲雄・玄侑宗久/「『関ケ原』――司馬遼太郎の視点」原田眞人・葉室麟・伊東潤・千田嘉博/「土方歳三と河井継之助――『燃えよ剣』『峠』より」小泉堯史・黒川博行・星野知子・磯田道史/「『胡蝶の夢』――新型コロナ禍を考える」澤田瞳子・澤芳樹・村上もとか・磯田道史 (講演)福田みどり・養老孟司・沢木耕太郎
-
3.0「日清・日露だけを美化し戦前・戦中の昭和を断罪した司馬遼太郎の感覚がわからない。なぜ昭和の戦争だけを負ける戦争、無謀な戦争と決めつけるのか。清国、ロシアという大国を一国で相手にした戦争も無謀であった。あのまま戦争が続いていれば負けていた可能性が濃厚であった。日清・日露こそ僥倖の勝利であり、大東亜戦争にも勝機はあった。」日清・日露戦争だけを美化し、戦前・戦中の昭和を断罪した司馬遼太郎の歴史観が、戦後の日本人に与えた影響は計り知れない――。護憲派は大戦を「侵略戦争」と称し、保守派は彼らの歴史認識を「東京裁判史観」と批判する。我々にとってかけがえのない過去は、左右両派のイデオロギーによって書き換えられてしまった。一方で、朝日新聞と読売新聞は“共闘”して「戦争責任」を追及。しかし、罪を問う資格のある日本人などいるのだろうか? 我々は昭和の歴史をどう振り返るべきか。先の戦争をあらためて問う。
-
4.5全国民 必読! 天国からのメッセージ この国には“英雄”が必要だ。 習近平、金正恩、プーチン…… 独裁者たちの「世界史を変える戦い」がはじまっていた――。 国際社会から置き去りにされる日本に、司馬遼太郎は何を語ったのか。 日本人へ、伝えたかったこと。 ▽大局観なき“週刊誌政治”への警告 ▽北の延命戦略と韓国ファシズムの危険性 ▽2050年までに地球の半分を支配へ 中国が目論む「天下二分の計」 ■■ 司馬遼太郎の人物紹介 ■■ 1923~1996年。日本の小説家、評論家。大阪市生まれ。大阪外国語学校(現在の大阪大学外国語学部)蒙古語学科卒。産経新聞の記者を経て作家となる。『梟の城』で直木賞受賞。代表作に『竜馬がゆく』『坂の上の雲』『街道をゆく』等がある。 ◇◇ 霊言・守護霊霊言とは ◇◇ 「霊言現象」とは、あの世の霊存在の言葉を語り下ろす現象のことをいう。これは高度な悟りを開いた者に特有のものであり、「霊媒現象」(トランス状態になって意識を失い、霊が一方的にしゃべる現象)とは異なる。外国人霊の霊言の場合には、霊言現象を行う者の言語中枢から、必要な言葉を選び出し、日本語で語ることも可能である。 また、人間の魂は原則として六人のグループからなり、あの世に残っている「魂のきょうだい」の一人が守護霊を務めている。つまり、守護霊は、実は自分自身の魂の一部である。したがって、「守護霊の霊言」とは、いわば本人の潜在意識にアクセスしたものであり、その内容は、その人が潜在意識で考えていること(本心)と考えてよい。
-
3.7国民的作家として読み継がれている司馬遼太郎。そのあまりの偉大さゆえに、司馬が書いた小説を史実であるかのように受け取る人も少なくない。しかし、ある程度の史実を踏まえているとはいえ、小説には当然ながら大胆な虚構も含まれている。司馬の作品は、どこまでが史実であり、何が創作なのか? 吉田松陰、坂本龍馬、高杉晋作が活躍する司馬遼太郎の名作をひもときながら、幕末・維新史の真相に迫る。【目次】はじめに/第一章 吉田松陰と開国/第二章 晋作と龍馬の出会い/第三章 高杉晋作と騎兵隊/第四章 坂本竜馬と亀山社中/第五章 描かれなかった終末/おわりに
-
-
-
4.2
-
-難解な幕末・維新を、今こそ紐解こう! 同書は、幕末・維新を舞台とした司馬遼太郎の小説・評論等を通して、幕末・維新を改めて考える一冊である。 登場人物の多さ、複雑な人間関係、そして人々を突き動かした思想。 「幕末・維新は、難解だ」――。こう感じている読者はぜひ読んで欲しい。 比較文学者・小谷野敦氏が、この難解さを、現在の繋がりの中で考え、鮮やかに紐解いていく。 私にはむしろ、今の日本にはすでに尊王攘夷思想が瀰漫していると思える。 「攘夷」とはこの場合、「反米」であり「護憲」である。 地政学的に西側に北朝鮮、中華人民共和国、ロシヤのような危険な国々を控えている日本は、 憲法九条を改正して米国と連携するのがベストだが、それを理解しない精神論が、反米護憲である。(「あとがき」より)
-
-
-
5.0
-
4.1
-
3.0死してなお多くの人々の心を捉えて離さない司馬作品の数々。グローバル化する現代社会において、私たち日本人が誇りを持って生きるために、今こそ日本と日本人を励ます司馬文学にその指針を求めることができるのではないか。本書は、「司馬文学は、日本人が“一人前の大人”になるための最良のテキストである」と力説する著者が、司馬作品の“読みどころ”をわかりやすく解説、その魅力を浮き彫りにした好著である。敵にさえも愛される資質とは何かを教えてくれる『竜馬がゆく』、一身立ち一国立つ(個人の独立があり、そして国家の独立がある)ことを謳った『坂の上の雲』、日本の近代的な合理精神を気づかせてくれる『国盗り物語』、才能ある人間が世に出て認められることの難しさを説いた『新史太閤記』、ビジネス社会の倫理とは何かがわかる『菜の花の沖』……。人間、社会、歴史について、知見と洞察に溢れた作品群のエッセンスを堪能できる一冊。
-
-『坂の上の雲』『竜馬がゆく』など大衆的な歴史小説家としての司馬遼太郎はよく知られているところ。また、独特の史観で書かれた数々の評論、随筆も物故後の今も多くの読者を得ている。だが、初期の作品群『ペルシャの幻術師』『戈壁の匈奴』等を読むと、司馬は卓越した幻想小説家であったことがわかる。大衆歴史小説家のイメージとは異なる、司馬のもう一つの作家性に秘められたものとは何だったのか。本書は、司馬遼太郎が遺した爛熟の幻想世界の秘密に初めて迫る評論である。【目次】はじめに/第一章 司馬遼太郎の人と文学の原風景・竹内街道(大道)/第二章 “辺境史観”によって、遠い祖先のルーツをさぐる/第三章 幻想小説(一)―雑密(雑部密教)と役行者/第四章 幻想小説(二)―純密の世界と雑密の世界を映し出す司馬文学の真骨頂/第五章 幻想小説(三)―山伏、忍者、幻術師の関連/第六章 幻想小説(四)―散楽雑伎(戯)と幻想小説のおもしろさ/あとがき/本書関連の司馬遼太郎略年譜
-
4.2
-
-司馬遼太郎は、日本の近代のルーツを鎌倉幕府の誕生に求めた。封建制は進歩の力を内包し、西欧近代へも親和的な統治システムだったからだ。こうした中世を経験しなかったアジアの国々は立ち遅れた。一方で、日本人が長く育んできた道徳観や規範意識は、進歩と安定を調和させ、近代化を支えた。我々がそうした伝統の下にあることは、現代の日本が、世界中でも稀に見る、豊かで秩序ある社会を実現させていることからも明らかである。 しかし、その良き伝統は一時期失われ、太平洋戦争に向かう異胎の時代を生んだ。世界の動きに耳目を塞ぎ、合理的に考えることを怠れば、国は容易に危機に瀕する、それが、司馬のもう一方のメッセージでもあった。世界の組合員としての振る舞い、イデオロギーの対立の克服、歴史認識問題など、司馬の声を聞きながら、日本のこれから歩むべき道について考えてみる。
-
3.0ここには人間のドラマがある。眼光紙背に徹すれば、たった十数行の記事でも、その一語一語が奥深い――。夏目漱石から司馬遼太郎まで、文学者の死はいかに報じられてきたか。芸能人はなぜバカでかい記事になるのか。経済人や野球選手の扱いは業績に比して小さい。名前の右に傍線が引かれる由来は。軟派の社会面は見出しで勝負。……誰もが毎日目にしながら、実は知られていないその読み方。
-
3.0【無料ガイドブック】このガイドは、2014年刊行された集英社新書のベストタイトルを、10編紹介しています。各タイトルの著者のプロフィールと冒頭の一部を収録。集英社新書の魅力ある世界を、少しでも知っていただければ幸いです。収録タイトルは以下10編です。『一神教と国家 イスラーム、キリスト教、ユダヤ教』内田 樹・中田 考/『行動分析学入門―ヒトの行動の思いがけない理由』杉山尚子/『心の力』姜尚中/『司馬遼太郎が描かなかった幕末――松陰、龍馬、晋作の実像』一坂太郎/『資本主義の終焉と歴史の危機』水野和夫/『世界と闘う「読書術」 思想を鍛える一〇〇〇冊 』佐高 信・佐藤 優/『自由をつくる 自在に生きる』森 博嗣/『成長から成熟へ――さよなら経済大国』天野祐吉/『はじめての憲法教室――立憲主義の基本から考える』水島朝穂
-
-
-
4.1第15回(2011年)司馬遼太郎賞受賞作。 日本の命運を若くして背負わざるをえなかった君主はいかに歩んだのか。昭和天皇の苦悩と試行錯誤、そして円熟の日々――。我々は後年の円熟味を増した姿で昭和天皇についてイメージし語ってしまいがちだが、昭和天皇が即位したのは25歳。世間では天皇の神聖さが説かれていても、右翼や保守派の重臣たちは天皇をかなり手厳しく見ていた。本書は側近や実力者たちが残した膨大な日記など、一級の史料を丁寧に掘り起こし、生真面目で気負いのある若かりし頃から晩年にいたるまでの多面的な昭和天皇の姿を描く。「昭和」という時代を理解するために必読の評伝!
-
5.0「日本という国の森に、大正末年、昭和元年ぐらいから敗戦まで、魔法使いが杖をポンとたたいたのではないでしょうか。その森全体を魔法の森にしてしまった。発想された政策、戦略、あるいは国内の締めつけ、これらは全部変な、いびつなものでした。魔法の森からノモンハンが現れ、中国侵略も現れ、太平洋戦争も現れた。」 なぜ「昭和」は、滅亡に向ってころがっていったのか」。「昭和への道」「戦後日本という下司国家」のことなどが、いささかの諦念と鬱懐を抱きながら語られる。この国の行く末を案じた巨匠のもう一つの遺言である。 <注>電子版には巻頭カラーは収載されていません。
-
5.0「昭和」が終わり二十年が経とうとしている。その六十余年の歴史には、目まぐるしい思想変遷があった。戦前―戦後という大きな断絶、六〇年安保、七〇年大学闘争、オイルショック、ポストモダン、バブル経済……。時代意識の転換はいかに起き、作家や学者たちはどのような発言をしたのか。マルクス主義の人間学を樹立しようとした三木清、大衆の肉体主義を批判した丸山真男、大衆の自立こそが変革の出発点だとした吉本隆明をはじめ、芥川龍之介、柳田国男、福田恆存、三島由紀夫など、彼らの功罪を含めて果敢に批評。ベトナム戦争をめぐって開高健をやり玉にあげた吉本隆明や、丸谷才一の「国家論」に噛み付いた江藤淳などのエピソードも印象深い。また、八〇年代以降、西部邁や小室直樹、浅田彰が登場してきた必然性を考察。司馬遼太郎、長谷川慶太郎といった思想家の範疇におさまらない人物が登場するのも斬新である。豊饒な昭和思想史を総括した記念碑的労作。
-
-458円 (税込)空海が今も瞑想している高野山200年の史実 はじめに なぜ高野山なのか? 目次 第一章平安─鎌倉時代 空海による開基から武士の入山 空海の生涯にみる高野山成立と弘法大師伝説の誕生 空海と高野山の年表(平安時代まで) 空海と真言密教 密教とはいかなるものかを知る 密教の思想を描き表している曼荼羅を知る 貴族から武士へ。源平時代と高野山 高野山ゆかりの人物事典 1 藤原道長 2 足利義満 3 平敦盛・熊谷直実 第二章戦国時代 戦乱の中の高野山 上杉謙信・景勝越後の軍神も悩み多く二度にわたり高野山へ登った 武田信玄・勝頼 比叡山を焼き討ちした信長に怒りの書状を送りつけた コラム 武田二十四将の一人馬場美濃守の墓 織田信長 武装化した聖地、覇王・信長と対峙 コラム 寺院に根付いた僧兵なる存在 豊臣秀吉 天下人・秀吉が聖地に刻みし足跡 高野山ゆかりの人物事典 4 北条早雲 5 明智光秀 6 柴田勝家 7 黒田官兵衛 6 筒井順慶 コラム 日本各地で誕生し、今も語り継がれる弘法大師伝説 コラム 弘法大師伝説マップ 真田昌幸・幸村 コラム 真田幸村の足跡とともにたどる高野山と大坂の陣 石田三成 第三章江戸時代 徳川政権下の高野山 徳川家康 戦国乱世に終止符を打ち、泰平の世を作り上げた 徳川秀忠・家光 徳川家霊台を造営。さらに空海の持仏堂を寄進 御三家 蓮花院と御三家と言われる尾張、紀州、水戸の徳川家との関係 佐竹義重 佐竹氏の全盛時代を築いた猛将 最上義光 上杉景勝の参謀、直江兼続の軍を破った 伊達政宗 政宗はもちろん仙台藩主であった代々の伊達氏の供養塔があり 前田利家 勝家に仕え、その後豊臣政権の中枢を担う存在 島津家久 「高麗陣敵味方戦死者供養塔」を建立 毛利元就 歴代当主による建牌や石塔の建立は数十に 高野山ゆかりの人物事典 9 浅野長矩 10 松尾芭蕉 11 大岡忠相 12 井伊直弼 13 市川團十朗 第四章近代 激動の世界情勢と高野山 明治初期の廃仏毀釈によりかつてない試練を経験 時代も宗派も超越した弘法大師の威徳に包まれる 女人禁制の聖地に赤ん坊の産声が響く コラム 主な日本の女人禁制地 高野山ゆかりの人物事典 14 陸奥宗光 15 高浜虚子 16 与謝野晶子 17 司馬遼太郎 巻末 古地図で訪ねる高野山境内 巻末 古地図で訪ねる高野山奥之院 おわりに 一度は体験してみたい密教の真髄 奥付 裏表紙
-
-
-
5.0
-
4.4あなたの知っている坂本龍馬、フィクションではありませんか? 龍馬の名は、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』など伝記小説から広まったため、実像と離れた「伝説」が生まれ、今なおそれが通説となっている。歴史学者が丹念に史料を読み解くことでわかった龍馬の実像とは!? 龍馬は薩摩藩士? 薩長同盟に龍馬は無関係? 亀山社中はあったのか? 大政奉還は龍馬のアイディア? など、新知見が満載。「英雄フィルター」を外してみれば、龍馬の真価が見えてくる。――(本書「プロローグ」より)私は、明治維新史を専門としているが、その主な対象は幕末政治史であり、さらに絞り込めば、薩摩藩を中心に研究を行っている。その他にも、攘夷といった対外認識論(外国に対する考え方、世界観)にもアプローチしている。そうした中で、とくに前者の研究において、龍馬の存在はきわめて重要である。しかし、史料にあたっていくと通説と違った龍馬の動向が散見され、過大評価された部分も少なくないと感じる。一方で、過小評価されていた部分も発見した。これは、龍馬の価値を高めることとなるだろう。こうした新しい龍馬を提示したい。
-
4.0維新前夜の京都の治安維持を任務として結成された新選組。「誠」の旗印に参集した剣士たちの生と死を描いた司馬遼太郎の連作短篇集を、『墨攻』や『ムカデ戦旗』で知られる時代劇画の第一人者・森秀樹が激烈コミカライズ! 第1巻に収録するのは、「芹沢鴨の暗殺」「沖田総司の恋」「菊一文字」「長州の間者」の4編。 「芹沢鴨の暗殺」は、新選組の筆頭局長となった剣豪・芹沢鴨が、その粗暴で傍若無人な振る舞いが災いして、近藤勇や土方歳三らによって謀殺されるまでを描く。芹沢の死によって、近藤・土方体制が確立された。 「沖田総司の恋」は、若き天才剣士・沖田総司を主役とした物語。労咳を患った沖田は、かかりつけの医者の娘、お悠に淡い恋心を抱く。しかし、お悠も沖田と同じ不治の病に侵されていた……。 「菊一文字」も、沖田を主役とした一篇。名刀「菊一文字」を入手した沖田だが、その刀を実戦で使用するのをためらったため、部下を勤皇派の剣士に斬り殺されてしまう。復讐に燃える沖田は……。 「長州の間者」は、長州藩の間者(スパイ)として新選組に加わった京都浪人深町新作が、二つの組織の狭間で苦悩する逸話。 『新選組血風録』は、週刊文春において2018年3月から2020年2月まで2年間にわたって連載され、動乱の京都を彩った剣客集団の群像描写と、緊迫感溢れる殺陣シーンが大きな反響を呼んだ。 司馬遼太郎・森秀樹コンビによる「文春 時代コミックス」シリーズとして、6月刊の『幕末』を皮切りに、7月に『新選組血風録 一』、8月に『新選組血風録 二』、9月に『新選組血風録 三』を連続刊行する予定。
-
3.9
-
4.0
-
3.8
-
4.2
-
4.0
-
3.9
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “旬”“作法”“味わう順”を知れば 回転だって鮨はもっともっと美味しくなる! 一貫目 白身 二貫目 貝 三貫目 烏賊・蛸 四貫目 赤身 五貫目 海老・蟹 六貫目 光りもの 七貫目以降の正しい順、わかりますか? [味わう順]別 鮨ダネ大図鑑 全86ネタを完全解説! [昆布締め][煮る][漬ける] 江戸前鮨、職人の仕事を知る 鮨の王様! マグロ徹底解剖 池波正太郎、司馬遼太郎… 作家が通った 鮨の名店 料理評論家・山本益博さんが教える 恥ずかしくない 鮨屋の作法 超入門
-
-550円 (税込)戦国武将が眠る霊峰 目次 高野山 空海が求めた密教の聖地 〈巻頭特集〉鎌倉殿と北条政子 頼朝を弔った政子の想いとは? 金剛三昧院 上杉謙信ゆかりの古刹に高野山文化歴史研究所がオープン 清浄心院 偉人たちの魂が集う超世の存在 なぜ高野山なのか? 高野山1200年、悠久の時を越えて、今──。 第一章・平安─鎌倉時代 開基から武士の入山 空海の生涯にみる 高野山成立と弘法大師伝説の誕生 嵯峨天皇の庇護を受け 紀州の霊山に伽藍を建立 空海入定し その存在は永遠となる 高野山霊宝館で観る 豊麗な仏教美術の数々 貴族から武士へ 源平時代と高野山 平清盛 弘法大師の化身と会い 根本大塔を再建した 北条政子 源頼朝の妻が建てた 現存の寺院と宝塔 【高野山ゆかりの人物事典】 其の壱 藤原道長・足利義満・平敦盛・熊谷直実 古地図と古写真で訪ねる 高野山 境内・奥之院 第二章・戦国時代 戦乱の中の高野山 武将たちが信仰せし霊峰 上杉謙信・景勝 世を捨て、高野山に隠棲しようとした 武田信玄・勝頼 その死から3年後、位牌が納められたと伝わる 武装化した聖地 覇王・信長と対峙 信長の紀州攻めを受けあわや全山が戦場に 信長に焼かれた比叡山 辛くも免れた高野山 忘れ去られていた信長の墓 妹・お市たちの菩提寺 天下人・秀吉が聖地に刻みし足跡 秀吉の紀州攻めと 根来寺の焼き討ち 秀吉、高野山を再興し 青巌寺を建立する 高野山を舞台にした 豊臣親子の確執 奥之院に眠る 豊臣一族の魂 【高野山ゆかりの人物事典】 其の弐 北条早雲・明智光秀・柴田勝家・黒田官兵衛・筒井順慶 第三章・江戸時代 徳川政権下の高野山 真田家三代の人物像 高野山に蟄居の後、武士の矜持を貫く 破れし武士たちの御霊を鎮める 真田幸村の足跡と共にたどる 高野山と大坂の陣 石田三成 生前に自らの墓を高野山に建立した 江戸の泰平を築いた徳川家の人々 徳川家康 三河の豪族から興り戦乱の世に終止符を打つ 徳川秀忠・家光 家光により高野山に建立された霊廟 徳川家霊台 絢爛豪華な須弥壇と厨子が残る 紀州と尾張の徳川家 高野山を手厚く保護、歴代藩主も眠る 名だたる雄藩の廟所が並ぶ奥之院 佐竹義重 義を貫く志が格調高き霊屋から伝わる 最上義光 東北の雄にふさわしい威厳を放つ石塔 伊達政宗 仙台の本家と宇和島の分家が肩を並べる 前田利家 高野山にふさわしい禅を捉えていた武将 島津家久 累代に渡り「お骨上がり」を続けた島津家 毛利元就 高野聖・勢尊法印と師壇の関係を結んだ武将 【高野山ゆかりの人物事典】 其の参 浅野長矩・松尾芭蕉・大岡忠相・井伊直弼・市川團十朗 第四章・近代 激動の世界情勢と高野山 世界へと船出した日本と高野山が受けた試練 女人禁制の聖地に赤ん坊の産声が響く 【高野山ゆかりの人物事典】 其の四 陸奥宗光・高浜虚子・与謝野晶子・司馬遼太郎 第五章 戦国武将と高野山の宿坊 無量光院 持明院 恵光院 光臺院 蓮華定院 蓮花院 時空旅人 SELECT SHOP バックナンバー 奥付 裏表紙
-
-平安時代から多くの絵師が描き、歌人が詠んだ夕映えの空。江戸時代、人々が愛した浄瑠璃の義理人情劇、子守歌が奏でる、哀しい短調のメロディ・・・・・・。 かつて日本人が持ちえた<共感の場>が消え、確たる死生観すら見えなくなった昨今、私たちは人生をどうまとめたたらいいのか。宗教学者が、来し方を振り返りつつ、次世代に伝える、いのちの作法集。 *本書は、第一章から第七章までを、『こころの作法――生への構え、死への構え』(中公新書 2000年刊)を底本に、終章をこの文庫のために書き足したものである。 目次) はしがき 学術文庫版 はしがき 第一章 こころの原風景 消えゆく短調のメロディー/夕焼け信仰/山のお寺の鐘/二羽の「夕鶴」 第二章「語り」の力 歌のリズムと生命のリズム/語ること・聞くこと/フェアプレイか無私か/友情の語り方 第三章 人間、この未知なるもの 子どもの犯罪にどう立ち向かうか/放っておくと、子どもは野性化する!/犠牲と奉仕/全身運動と数学的1 第四章 私の死の作法 どのように死ぬべきか/現代の無常物語/臓器移植ははたして布施の精神の発露か/断食死こそ死の作法の出発点 第五章 精神性について 人間批評の尺度/任きょう道〈長谷川伸〉/浄瑠璃と町人道〈司馬遼太郎〉/武士道の「仁」〈新渡戸稲造〉 第六章 伝統のこころ、近代のこころ チャンバラ映画/人間を信じる/遠景のなかの仏教/身もだえの話/人情の極致 第七章 眼差しの記憶 司馬さんの鋭い眼差し/丸山政治学と司馬文学/日本人の中の日本人/『燃えよ剣』の夕日 終章 辞世の作法 挽歌の作法/一期一会の歌/自然葬の行方 「あとがき」に代えて 辞世の弁「若き魂たちよ」 内容紹介) 日本の子守唄が、遠くなってしまった。もうどこからもきこえてこない。(中略) 悲哀の旋律を忘れた社会というのは、ひょっとすると他人のこころの痛みや悲しみに鈍感になっている社会なのではないか。われわれはいつのまにか短調排除の時代を生きて、感性の大切な部分を失いつつあるのかもしれないのである。(本書「第1章」より)
-
4.5
-
4.3金融に関する予測本での活躍が最近は目立つ著者であるが、もともとは、日本とアメリカの政治思想を専門とする、右に出る者のない碩学である。著者は、常々、「本当は、日本人はどのような思想のもとに生きてゆくべきなのか」を考えてきた。そのヒントは、これまで日本という国、日本人という人種が歩んできた、「歴史」のなかにこそ存在する。そこで、著者の知力を総動員して、描かれたのが、本書である。この本は、美しい人間絵巻である、司馬遼太郎が描いたような歴史観には基づかない。過去の人々が、なるべく一般庶民のまえに出すまいとしてきたであろう事実を表に出し、本当に起きていたことは何なのかを抉り出すことに全力を注いでいる。読者は、戸惑いと驚きの中で、今まで誰も教えてくれなかった、真の歴史考察と直面するであろう。日本人必読の一冊である。
-
3.0「すみれほどな 小さき人に 生まれたし」。この夏目漱石の俳句を故・司馬遼太郎は大好きだったという。エッセイや講演などでよく引用しては、「この句に漱石の基本的な悲しみが読めるんです」と語ったという。漱石は苦悩の人生を歩んだと言えるだろう。日本人や日本社会への憤り、英国留学で味わった劣等感、慢性的なうつ症状、我が子の病死……。華やかな作家生活を送ったと見られがちな漱石だが、その内面は実に深刻だった。その漱石が最後にたどりついた境地が「則天去私」だった。“天に則って私を去る”まさに己れのエゴを捨て、天の命ずるままに生きるのが悩みを解脱する道である、と漱石は悟ったのであろう。本書は、そんな漱石が自ら語ったメッセージを小説、書簡、日記、講演などから選んで解説を加えたものである。自分自身が悩める人だっただけに、その言葉は慈愛にあふれ、説得力がある。日本人にとってなつかしく、また心強い人生の書である。
-
4.7
-
-行き当たりばったりの好奇心で、あらゆるジャンルの本を読む――それが私の読書です。 今回のテーマは「本」。小説はもちろん、歴史、エッセイ、音楽、車、鍼灸に関するものなどなど、少年時代から続けてきた「ごった煮読書」が、作家としての自身の仕事ぶりを形成したと語る五木さん。「読書をすれば優れた人間になるわけではないし、ましてや努力や義務で読むものではありません。本は、私のよき友であり、おもしろいから読むのです」。91歳になった「生き方の先輩」が贈る、人生百年時代を豊かにする必読ガイド、第7弾! 【内容】 第1章 ごった煮読書のすすめ 第2章 古典の読み方、楽しみ方 第3章 活字文化は消えてしまうのか 第4章 作家として「書く」ということ 第5章 忘れえぬ三人の作家――松本清張、司馬遼太郎、井上ひさし 第6章 本を友としてさびしさを癒す
-
-運のいい人と悪い人、その差は“ちょっとしたコツ”にあった! 本書のポイントをマスターすれば、あなたも「運」に愛される! 「禍福はあざなえる縄のごとし」と言うように、わたしたちは幸運によって何かをつかみ、 不運によって何かを失うと同時に、幸運によって何かを失い、不運によって何かをつかんでいます。 幸運は、特別な人だけに訪れるものではありません。 誰にでもできるちょっとした意識の変革で、グンと引き寄せることができるのです。 本書では、人生、仕事に効く「運を引き寄せる」44のポイントを紹介。 不運を食い止め、幸運へとシフトする方法を、具体的な事例で丁寧に解説します。 意識が変われば行動が変わる。行動が変われば性格が変わる。 性格が変わると運が変わり、そして結果が大きく変わります! この1冊であなたの運は確実によくなる! 人生を切りひらくヒントが満載の一冊。 【目次】 はじめに 第一章 いちばん強いのは運がいい人! □同窓会で遭遇した驚愕の風景! □人生いろいろ、運命もいろいろ! □女性の運命は男次第? □運を呼び込む資質がある! □ある文豪が決断したこと □松下幸之助がいちばん重視したこと □「いちばん偉いのは運の強い人」という回答! □もう一人の自分に聞いてみる! □「運のいいこと」と「運の強いこと」は違う! 第二章 運を引き寄せる七つの性格 □何度失敗してもめげないタフなヤツ □男の顔は履歴書だ! □顔相が9割! □困難に見えても意外と運が味方してくれる! □「ほっとけない!」というキャラクター □続けること □好きで好きでたまらない □運の女神もストーカーが大嫌い! □味方を増やす! 第三章 不運と悪運は伝染病! こんなタイプには絶対に近づいてはいけない! □味方のいない人 □不幸依存症のヤツには近づくな! □貧乏はOK! 貧乏性はNG! □絶対不安と絶対不満はつらい! □史上最強のストーカー! □見栄っ張りの人はダメ! □「邪魔するのはいつも自分である」と自覚すること □「いい人=甘い人」ではダメ! □実は、厳しい人のほうが尊敬される! □アルバート・エリスの論理療法で不運、悪運から脱出する! □アドラー心理学で不運と悪運から抜け出す! 第四章 こうすれば良くなる! 金運、男運、女運! □安月給だから貯金できる! □若いから貯金できる! □蓄財は氏より育ち □金運、商運、勝運は信頼で築け! □見切り千両、損切り万両! 第五章 「運のいい人」「運の強い人」に変わる7つの習慣! □優れた人に弟子入りすること □理屈やデータに足をすくわれないこと □ゴールを見失わないこと □偶然ではなく必然だと心得ること □司馬遼太郎の「必然主義」 □顕在意識は潜在意識の奴隷にすぎないこと □好きになること □好きだからここまでできる! □心の切り替えスイッチを持つこと □一〇〇%運で決まる!
-
-関西が熱い! プロ野球関西ダービーで注目 関西人とはどういう人なのか ◆関西人とは、訛りを残した世界人である。日本書紀、源氏物語も、徒然草、そして風姿花伝、芭蕉も、司馬遼太郎、谷崎潤一郎も関西産、「世界」標準であり、「不易流行」である。 ◆18歳から関西で23年間過ごした著者が、23人の関西人を取り上げ、その本質に迫る。 ▼開高健、長谷川慶太郎、嵐寛寿郎、松下幸之助、南方熊楠、出口王仁三郎、梅棹忠夫、松田道雄、林達夫、淀川長治、横溝正史、福沢諭吉、三木清、栄陽子、谷沢永一、阪本勝、堺屋太一 他 ◆併せて「社長の哲学」「社長の読書」で、古今東西の人物名鑑を展開。 ▼石橋湛山、ケインズ、ドラッカー、チャーチル、世阿彌、アリストテレス、古田織部正、カーネギー 他 ◆さらにプルタルコス『英雄伝』の人間哲学に学ぶ――東に史記、西に英雄伝 ▼アレクサンドロス、カエサル、キケロ、ブルートゥス、クレオパトラ、スパルタクス、プルタルコスと日本 他
-
4.4
-
3.0
-
3.9妄説、打破! 信長は戦前まで人気がなかった。秀吉は人たらしでなく邪悪だった!? 時代ごとに人物像は変化していた。最新研究による実像に加え、虚像の変遷から日本人の歴史認識の特徴まで解析した画期的論考! 画期的に見える人物像も、100年前の焼き直しにすぎないものが多い。 織田信長は革命児、豊臣秀吉は人たらしで徳川家康は狸親父。明智光秀は常識人で、斎藤道三は革新者、石田三成は君側の奸で、真田信繁は名軍師。 このようなイメージは、わずか数十年前にできたものが実は多い。 彼らの虚像と実像を通して、江戸、明治、大正、昭和と、時代ごとの価値観まで浮き彫りにする! ■光秀=「温厚な常識人」は一つのベストセラーがつくった。 ■油売りでも革新者でもなかった道三 ■信長は将軍も天皇も尊重していた ■秀吉の評価ポイントは勤王と海外進出 ■江戸時代にも三成肯定論はあった ■幸村は「軍師」ではなく「現場指揮官」だった ■司馬遼太郎の家康論は徳富蘇峰の受け売り!? ■歴史小説・ドラマの源流は“蘇峰史観”にあり! ■「野心家・光秀」はなぜ定着しなかったのか? ■信長の「勤王」は「革命」だった? ■徳川政権への不満が生んだ秀吉人気 ■三成忠臣/奸臣論が見落としてきたもの ■超人化していった真田幸村 ■賞賛されていた家康の謀略 【目次】 はじめに 第一章 明智光秀――常識人だったのか? 第二章 斎藤道三――「美濃のマムシ」は本当か? 第三章 織田信長――革命児だったのか? 第四章 豊臣秀吉――人たらしだったのか? 第五章 石田三成――君側の奸だったのか? 第六章 真田信繁――名軍師だったのか? 第七章 徳川家康――狸親父だったのか? 終 章 大衆的歴史観の変遷 あとがき 参考文献
-
3.0
-
4.0※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【北海道の機甲科部隊・第71戦車連隊の連隊長までつとめた 戦車戦闘のプロフェッショナル・木元寛明氏(元・陸将補)が、 「戦車の戦う技術」を1冊にまとめました!】 「戦車」の存在を知らない人は、ほとんどいないと思います。 しかし、戦車が「どういう場合に実戦に投入されるのか」、 投入された戦車が「どのように戦うのか」まで正確に知っている人は少ないでしょう。 そこで本書では、「戦いとはなにか」という基本から、 「陸の王者」ともいえる戦車が「どのように運用され、どう戦うのか」を 豊富な写真とイラストで解説していきます。 【この本の内容(一部)】 ●戦車を撃破する最適の兵器は戦車 ●戦車は進歩発展しても乗員の役割は不変 ●戦車戦力の発揮は戦車と乗員のコラボ ●敵戦車はマッハ5の刺客を放つ ●司馬遼太郎は戦車小隊長教育を受けた ●戦車小隊長の「呪文」METT(メッツ) ●車長は砲塔から顔を出して指揮する ●先制射撃で撃破される前に撃破する ●ときには射撃の原点に戻れ ●敵戦車の撃破 ●照準具の規正は正確な射撃の原点 ●Mモードで2目標を同時照準 ●目標をロック・オンして走りながら射撃 ●熱線映像装置(サーマルセンサ)による夜間の昼間化 ●演習弾を使用して実戦感覚を身につける ●高温・高速ガスで装甲版を焼く ●日本の地形を活かした稜線射撃 ●火力発揮に最適な場所へ最速で移動せよ ●潜水深度は予想戦場の河川を想定して決まる ●戦車と機動戦闘車は役割を分担する ……など。
-
-
-
-未完の戦争を追い続けるジャーナリストが、今こそ知らせたい戦争の真実―― 勝てないと分かっていた太平洋戦争を、なぜ日本は始めたのか。 80年前と同じことが、今ウクライナでも起きている。 敗戦から今日まで続く屈辱の日露外交を検証する 【第1章】為政者は間違える~開戦決定まで 国家の「主権戦」と「利益線」/「大東亜共栄圏」とは/自己中心的歴史観 ロシアと大日本帝国/ロシアのウクライナ侵攻と「核シェア」/仮想敵国アメリカに頼っていた石油 etc. 【第2章】大日本帝国の「終戦構想」 開戦の理由 司馬遼太郎の指摘/希望的観測+空想の「終戦構想」/ロシアのウクライナ侵攻と「成功体験」/「国史」は「終戦構想」を無視/昭和天皇の戦争責任 etc. 【第3章】必然の敗戦 的中した山本五十六の予言/「天才」石原完爾が敗戦を予言/補給戦でも惨敗/自らへの批判を許さない権力者の行き先/戦略上、致命的なミス/国辱的な対ソ交渉 etc. 【第4章】 「聖断」=「英断」? 「大元帥」が把握していなかった軍の実情/開戦2年で勝利の見込みを失った天皇/「決められる政治」は正しいか/ロシアに裏切られる歴史/大事なのは国益より組織の秩序 etc. 【第5章】為政者は間違える 市民の責任 新聞の戦争責任/ロシアのウクライナ侵攻報道/政治家を選んだ国民にも責任がある?/戦争被害受忍論/為政者は常に後世に審判される/本当の「国民の責任」 etc.
-
-10分で読めるミニ書籍です(文章量12,000文字程度=紙の書籍の22ページ程度) 【書籍説明】 私が吉田松陰という人物を知ったのは、司馬遼太郎の「世に棲む日日」だった。 大好きな司馬作品の中でも殊に偏愛している作品である。 長州を中心に幕末の動乱期を生き生きと描きだす名作で、好んで何度も読み返しているが、それにしても、一人物を中心に、若い連中が集まって何やら活発に議論している姿がひっかかる。 どうもどこかで見た風景であるような気がする……。最近になってようやく気付いた。 プラトンが描写したソクラテスの姿によく似ているのだ。 無論そう感じるのは私だけかもしれないが、自然発生的な議論の場としての機能、そしてその中心にいる卓越した人物、という点で、このふたつはよく似ているような気がするのである。 そして最終的には刑死し、その後弟子たちの中から歴史に残る人物が現れたという点でも、二人は共通している。 この非常に興味深い二人の思想家を、並べて見比べてみたら面白いのではないか? そして遠く離れた時代、遠く離れた場所でも同じように権力に屈しない知性の輝きを見ることができたら、それが「いついかなる場所にも存在する普遍的な理性」の存在を証明することになるのではないか。 人と比較することで、個性はより鮮明になる。 後世に多大な影響を残した思想家を知るうえでも、この比較検討の試みは無駄ではあるまい、と思う次第である。 それでは、古代ギリシャと幕末期の萩、ふたつの世界に生きた二人の大人物を比較する試みを始めてみよう。 そこに人類不変の何かを見つけ出せるかどうか、それはまだわからない。 どんな答が出るのか、読者諸賢にもぜひ最後までお付き合いいただき、ご自分の目で見届けていただきたい。 【目次】 その生涯 彼らは何と戦ったのか 萩とアテナイの学生たち 「弁明」と「留魂録」 教育者としてのソクラテスと松陰 二つの謎 【著者紹介】 大畠美紀(オオハタミキ) 猫とドイツ観念論をこよなく愛する40代。 大方の例にもれず大河ドラマから幕末史に興味をもつにいたる。 プラトンとは学生時代からの腐れ縁。
-
-故・司馬遼太郎が「よき江戸時代人の末裔」と称賛した市井の研究者によって体系化された、「蕎麦」に関する膨大な知見。江戸時代の文芸や大衆文化に登場する蕎麦、全国各地に根付いたさまざまな食し方、植物としてのソバと製粉の過程、蕎麦打ちの用語、そば店の隠語、蕎麦をめぐる史跡・習俗・諺など、あらゆる資料を博捜し、探究した1155項目。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-徳川光圀、藤田東湖、横山大観…… なぜ水戸藩・茨城から名だたる英傑が生まれたのか。 なぜ数多くの「日本初」「日本一」を誇るのか。そして、なぜ岐阜県民の筆者が茨城愛を著したのか――。 その歴史と風土に隠された、知られざるパワーを語り尽くす! ・渋沢栄一も心酔した「水戸学」とは? ・「日」本列島屹「立」の地・日立 ・ヤンキーも博士も日本一? 歴史、経済、文化、パワースポット、グルメ……etc. 「都道府県魅力度ランキング」で 2019 年まで 7 年連続最下位という不名誉に甘んじた茨城県を、さまざまな角度から徹底分析。 “最下位なんてとんでもない”真の魅力に迫る決定版! 〈目次〉 第1章 イバラの道は志士の道 第2章 本当に最下位? 茨城に隠された真の実力とは 第3章 未来に残したい茨城の心 〈著者紹介〉 昭和46 年(1971 年)岐阜県岐阜市生まれ。 高校時代に司馬遼太郎の『燃えよ剣』に出会い作家を夢見る。高校卒業後、松下電工の関連会社をはじめ多くの会社を渡り歩き(長続きせず)世の常、人の常に触れる。現在は誰もが知る大手運送会社に就業中。令和2年、子供たちに素晴らしい日本を残すことを本願とした教育、慈善団体「令和天狗党」を(独り寂しく)結党。党員番号は4989 番。 座右の銘は「夢なき者に成功なし」(吉田松陰)。
-
-
-
4.0
-
-
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。