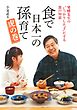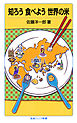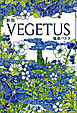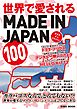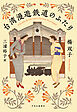食文化作品一覧
-
5.0日本各地の地魚料理約500例を収録。日本の豊かな魚食文化を担ってきた全国各地の料理法を魚種ごとに集大成。巻頭には「旬の地魚マップ」、巻末にはうまい地魚と出会える宿、全国の魚市場マップガイド、各地の魚介や加工食品の取り寄せ情報を掲載。魚に関するうんちくもいっぱい。豪快、簡単、美味!※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 カップヌードルを発明した男の執念の人生! 「平成最後の朝ドラ」となり、平均視聴率21.4%の好成績を残した『まんぷく』。実際のインスタントラーメンの生みの親として注目が集まっている安藤百福が学習まんがで登場します! 百福はなぜインスタントラーメンを発明したのでしょう? きっかけは若い頃に空腹で死にかけた経験でした。その後生涯を通じて「食」で人々を幸せにしたいと願うようになり、数々の事業を興しては失敗し、何度失敗を重ねても前を向いて進み続けました。 そして辿り着いたラーメンという答え。妻の揚げる天ぷらがきっかけで、世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」が誕生しました。 その後百福はインスタントラーメンのグローバル化を目指して「カップヌードル」を発明します。今ではインスタントラーメンは、世界で年間1000億食以上が消費されており、20世紀最大の発明ともいわれています。 人生の後半に数々の偉大な発明をした百福は、「転んでもただでは起きるな」「人生に遅すぎるということはない」などの名言を残しています。 考えて考えて、考え抜け――!食文化の革命に執念を燃やした男の哲学は、現代を生きる我々に前向きな希望をもたらしてくれます。
-
4.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 食の人類学の視点から東西の食法を考察し,箸の食文化と三点セット(スプーン,フォーク,ナイフ)の食文化の違いを人間の自然へのかかわり方の違いとして捉える。
-
4.0
-
-
-
-
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 鯖や塩などの海産物から醤油や唐辛子などの調味料まで、さまざまな食品・食材が伝わってきた道をたどり、日本の食文化の流れを俯瞰する。
-
4.0【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 食文化への深い造詣と食に対する果敢な行動力で人気の、小泉教授の辛口痛快エッセイ。納豆、干物、漬け物、日本酒など日本の伝統食に込められた深い智恵や工夫、健康への効果を見直す。また、現代日本人の食の堕落を嘆き、食の堕落は国を堕落させると警鐘を鳴らす。コンビニにたむろする若者よ、ダイエットに励む女性よ、疲れきったサラリーマンよ、今こそ日本の伝統食を食べて元気を取り戻せ! 永六輔氏も大絶賛、現代人必読の書。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字サイズだけを拡大・縮小することはできませんので、予めご了承ください。 試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの端末での表示をご確認ください。
-
4.3
-
3.3【内容紹介】 「人類の幸福の源は、食にある」とジャック・アタリ氏はいいます。 衣食住は、昔から人の生活に欠かせない3要素です。地球の誕生から過去、現在、未来に至るまで、人類はどのように食べるという行為と関わってきたのか。アタリ氏は、これらを綿密な資料から分析します。 特に食には、生命を維持する以上の役割があり、政治・経済・文化・産業・性・哲学・環境・芸術などあらゆることが結びついてきました歴史があると指摘するのです。 たとえば、イタリアやフランスは食文化の宝庫であり、フランス王ルイ14世などは料理を戦略的な外交の手段として活用してきました。また、高級ホテルや加工食品の歴史も食なしには語ることができません。 同時に現在のアメリカの繁栄にも食が大きく関連しています。コーンフレークやファストフードは、いかに人を効率よく働かせるかという目的で作られたものです。これら栄養学がアメリカの国家戦略に強く影響しています。 富裕層は何を食べているのかといった世俗的な話題から貧困層の食事は何か、世界の飢餓はどうして起こるのかなど、世界的な課題に関しても鋭い分析は留まりません。 2050年に世界の人口が50億に達し、AI社会が到来しているとすれば、人類は何を食べていくのか。アタリ氏は、昆虫食に関する未来も予言するのです。 実は、アタリ氏は自称健康オタクで、食べる物に関して最大限の注意を払っています。現在、78歳にして輝かしい知性を放ち続けるために必要な巻末の「食の科学的基礎知識」は必読です。 【著者紹介】 [著]ジャック・アタリ(Jacques Attali) 1943年アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院(ENA)卒業、81年フランソワ・ミッテラン大統領顧問、91年欧州復興開発銀行の初代総裁などの、要職を歴任。政治・経済・文化に精通することから、ソ連の崩壊、金融危機の勃発やテロの脅威などを予測し、2016年の米大統領選挙におけるトランプの勝利など的中させた。林昌宏氏の翻訳で、『2030年ジャック・アタリの未来予測』(小社刊)、『新世界秩序』『21世紀の歴史』、『金融危機後の世界』、『国家債務危機─ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか?』、『危機とサバイバルー21世紀を生き抜くための〈7つの原則〉』(いずれも作品社)、『アタリの文明論講義:未来は予測できるか』(筑摩書房)など、著書は多数ある。 [翻訳]林 昌宏(はやし・まさひろ) 1965年名古屋市生まれ。翻訳家。 立命館大学経済学部卒業。訳書にジャック・アタリ『2030年ジャック・アタリの未来予測』『海の歴史』(小社刊)、『21世紀の歴史』、ダニエル・コーエン『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』、ボリス・シリュルニク『憎むのでもなく、許すのでもなく』他多数。 【目次抜粋】 はじめに 第一章さまよい歩きながら暮らす 第二章 自然を食らうために自然を手なずける 第三章 ヨーロッパの食文化の誕生と栄光(一世紀から一七世紀中ごろまで) 第四章 フランスの食の栄光と飢饉(一七世紀中ごろから一八世紀まで) 第五章 超高級ホテルの美食術と加工食品(一九世紀) 第六章 食産業を支える栄養学(二〇世紀) 第七章 富裕層、貧困層、世界の飢餓(現在) 第八章 昆虫、ロボット、人間(三〇年後の世界) 第九章 監視された沈黙のなかでの個食 第十章 食べることは重要なのか 付属文書 食の科学的な基礎知識 謝辞 訳者あとがき
-
4.0
-
3.9「お好み焼き発祥の地は大阪でも広島でもない」「鶏を使わない焼き鳥?」「九州でうどんにかけるのは胡椒?」など、食に隠された意外でおもしろい歴史をひもときながら、世界に類を見ない複雑で多様性に富んだ日本の食文化を紹介。 「マグロを最も買っている市は?」「ソースを最も好んで使う市は?」など、最新の家計調査から見る、リアルな今の日本の食事情もレポート。あなたの常識をくつがえす、ニッポン食文化地図! 【もくじ】 はじめに ~食文化は、「ケンミン」単位では語れない! 第一章 「藩」がつくった食文化 第二章 豚に追われた牛、王国守った鶏 第三章 歴史が語る食の「産業遺産」 第四章 「関西=うどん 関東=蕎麦」と思っていないか? 第五章 海の幸が教えてくれる食物地図 第六章 家計調査からみるケンミン食 第七章 地域によって変わる呼称 第八章 食の多様性の代表格「雑煮」を検証する
-
-食の安全を科学の目で見る力を養い、より安全な食文化の創造に寄与する人材を育成するために発足した「食品安全検定」の公式テキスト。中級は、食の安全を脅かす要因の理解、安全・衛生管理の知識、法制度等を学ぶ。新たな知見や制度改正等をアップデートした第3版。 ※本電子書籍は同名出版物(紙版)を底本として作成しました。記載内容は、印刷出版当時のものです。 ※紙版とは異なる表記・表現の場合があります。また、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
-
-最も注目される歴史学者の新基軸!人類中心主義をこえる試み。 人間の内なる植物性にむけて―― はたして人間は植物より高等なのか? 植物のふるまいに目をとめ、歴史学、文学、哲学、芸術を横断しながら人間観を一新する、スリリングな思考の探検。 【目次】 第1章 植物性 第2章 植物的な組織 第3章 大気のクリエーター 第4章 植物の舞踏―ブロースフェルトの『芸術の原形』に寄せて 第5章 根について 第6章 花について 第7章 葉について 第8章 種について 第9章 「植物を考える」とはどういうことか あとがき 【著者】 藤原辰史 1976年生まれ。京都大学人文科学研究所准教授。農業史、食の思想史。2006年、『ナチス・ドイツの有機農業』で日本ドイツ学会奨励賞、2013年、『ナチスのキッチン』で河合隼雄学芸賞、2019年、日本学術振興会賞、『給食の歴史』で辻静雄食文化賞、『分解の哲学』でサントリー学芸賞を受賞。著書に『カブラの冬』『稲の大東亜共栄圏』『食べること考えること』『トラクターの世界史』『農の原理の史的研究』『歴史の屑拾い』ほか。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「食」に対して、産地・成分表示の偽装や遺伝子組み換え食品などで不安が高まり、多様なメディアがそれを増幅している。また「食」は、孤食・個食などのように家族問題として取り上げられることも多い。それに対抗するかのように、「健康」「自然」というイメージによってスローフードや郷土食が注目され、食育が見直されている―。「コメ志向」の再考、食育の歴史、調理とジェンダー、スローフード、一家団欒イメージなど、食文化やそれを取り巻くイメージを多様な視点から読み解き、社会的・歴史的文脈によって「食」に対する人々の感性やイメージが全く異なってきたことを描き出す。食文化をとおしてさまざまな社会状況や歴史を、そして現代を照らす論考集。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 220ヵ国・地域それぞれを代表する食材を使った「国旗」のお弁当で、世界の食文化と郷土料理を楽しく学べる一冊。 郷土料理、伝統料理、家庭料理だけでなく、時にはかわいい動物や花などのキャラクターを加えてその国らしさをお弁当箱にぎゅっと詰め込んだ、言わば世界の国旗の「キャラ弁」レシピ図鑑です。 お弁当だけはでなく、一皿メニューとしても使えるレシピも掲載します。 見た目でわかりやすいビジュアルとともに、実際に手を動かして作ってみることで、世界の多様な食文化を幅広い世代により親しみやすく理解していただくことを目指しています。 各ページには日本の家庭でも作りやすいレシピに加えて、奥深い国旗や国名の意味、各国の切手に描かれたその国の食材・農業などについて解説しています。 「日の丸弁当」を生んだ日本は、いわば国旗弁当の発祥国。 インターネット時代のグローバル化の流れの中で"Bento"や"Kyaraben"は今や世界に誇れる日本の文化であり、食を通じた国際的な相互理解にも役立てていただけるはずです。 著者は、世界の料理 総合情報ウェブサイト e-food.jp代表の青木ゆり子。 サイトの創設20周年を記念して発表した『世界の郷土料理辞典』(2020)に続き、世界各国の料理レシピ、食文化を紹介する、集大成本の第二弾です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 私たちの「食をめぐる環境」とその「問題点」とは? 日本の食料・農業問題を多角的・体系的にまとめ、 「SDGs」、「TPP」、企業の農業参入、食品表示、 食料自給力、エンゲル係数の上昇、「中食」のさらなる拡大など、 新たな動向についてデータとともにわかりやすく解説。 農学系・栄養学系・経済学系の大学・短大・専門学校1・2 年生、 公務員をめざす農学系の学生、「食の将来」に関心のある社会人に最適。 ※本書は2016年7月発行『食料経済(第5版)-フードシステムからみた食料問題』の改訂第6版です。 prologue 食料経済で何を学ぶか ─食卓からさかのぼってそのフードシステムのしくみをたずねる─ 1 “豊かな食卓”から思い浮かべるもの 2 “ご飯”,“米”,“稲” 3 ひろがる“食”と“農”の距離 4 フードシステムとその基本数値 1編 “豊かな食卓”を解析すれば 1章 食生活の変遷と特徴 1 わが国の食生活小史 2 第二次世界大戦後の食生活の変化 3 食生活変化の背景および現代食生活の特徴と問題点 4 食の外部化と簡便化 5 “食”の国際比較─日本食文化の特徴─ 2章 成熟期にきた食の需給 1 食料の需給システム 2 食料の供給市場構造 3 成熟期にきたわが国の食料需要 4 日本人の食品購買行動の特徴 2編 農場から食卓を結ぶ食料・食品産業 3章 農畜水産物の生産 1 フードシステムの“川上”:農業 2 農業生産をめぐる環境の変化 3 SDGsと漁業 4章 食品企業の役割と食品製造業の展開 1 食品企業の目的 2 フードシステムにおける食品製造業の位置 3 食品製造業の国民経済の中での役割 4 食品製造業の構造的特徴 5 食品製造業の原料調達とフードバリューチェーン構築 5章 食品流通とマーケティング 1 卸売市場流通を中心とした生鮮食品の流通経路 2 加工食品の流通経路 3 食品流通業における構造変化の諸形態 4 商品のライフサイクルと食品小売業のマーケティング 6章 外食・中食産業の展開 1 飲食業と外食産業・中食産業 2 外食産業の経営戦略の特徴 3 中食産業の多様性 4 外食・中食産業の食材調達─農産物の需要者としての食品産業─ 7章 貿易自由化の進展と食料・食品の輸出入 1 グローバル化と食料貿易の転換点 2 高度化・多様化する食料・食品輸入 3 世界規模での食料の需要増大と食料貿易の将来 3編 国民食料の安定確保 8章 世界の食料問題 1 “過剰”と“不足”の併存 2 地球規模の食料需要の増大 3 成長の限界が懸念される食料供給 4 世界食料の需給バランスと新たな要因 5 世界の食料需給の展望 9章 日本の食料政策 1 食料政策の課題 2 「主食」政策─おもに米政策を対象として─ 3 食料をめぐる貿易政策 4 食料産業政策 5 食料自給の確保─食料安全保障の確立に向けて─ 10章 食品の安全政策と消費者対応 1 食料に求められる基本的な性格─安定供給と安全性─ 2 なぜ食の安全・安心が保たれないか 3 安全性確保のための政策対応 4 環境問題から食料問題へ 5 安全な食料共有と安心な食生活のためのフードシステムの構築 epilogue 日本の食料問題を考える─真の豊かさを求めて─ 1 他国に例をみない食料自給率の低さ 2 基本は“風土に見合った食生活” 3 真の豊かさを求めて,21世紀の食生活を展望する 参考文献/索引
-
3.0発酵学の権威、小泉武夫さんが日本の食への熱い思いを孫の食育に託す、心がしっかりした子、からだがしっかりした子に育てるための食読本。 醸造学・発酵学・食文化論を専門とする農学博士、小泉武夫さんがこれまで培われてきた、膨大な食にまつわる知識、知恵を、孫の食育といった視点で、孫育て世代のおじいちゃん、おばあちゃんに向けて伝授します。健康的ですばらしい和食、昔ながらの日本の食の叡智、もっともっと伝えたい、そんな願いをこめて。 子どもが食への関心と理解を深めるというだけでなく、親世代、祖父母世代にとっても、あらためて日本の食、長く受け継がれてきた食の知恵を見直す、いいきっかけとなるために。日本人が日本人を今一度自覚する、そんな時間を孫と一緒に共有したい。小泉武夫さんの伝えておきたい、残したい、日本の食の知恵語りです。 *食べ物を大切にする心を育てる。 *「いただきます」は食べ物に対する感謝の言葉。 *きちんとした箸の作法を早くから教える。 *食べ物を捨てない工夫。 *姿勢を正して食べる習慣をつける。 *噛むことで、頭がよくなる。 *健康なウンコとは何かを孫に教えよう。 *元気になりたければ納豆豆腐汁に限る。 *食物繊維豊富な和食が免疫力を高める。 *日本の出汁は世界一。 *おむすびは丸くないといけない。 *粥には十の徳がある。 *鰹節がカチンコチンなのはカビのおかげ。 *梅干しは日本人の元気の素、心の安定にも寄与。 *からだの維持になくてはならない塩の力。 *朝のお茶は戻ってでも飲め。 *腐敗を知って発酵を尊ぶ。 *がんの予防にもつながる味噌。 *祖母の肌をツルツルにした「美人水」。 *孫を美人に育てる十カ条。 など、97にも及ぶ項目で食の知恵を伝授します。
-
4.5
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ― 日常はこんなにも美しい ― 保存食を中心とした長野の食文化を研究している料理家・横山タカ子さんの暮らしとレシピ 「さあ、今一番おいしい野沢菜漬けと、手作り甘酒を召し上がってください」 四季折々その一瞬一瞬の輝きに、日々寄り添い続ける料理研究家・横山タカ子さんの暮らしを 庭、着物、台所道具や、素材を生かすシンプルなレシピ63品を美しい写真とともにご紹介する 第一章 春から初夏へ 春の庭 / 庭と一体の台所 / 着物の愉しみ / 私の台所 / 春から夏の保存食 / 文箱 / 愛しの台所道具 / 杏のさしす漬け / 手仕事の愉しみ1 手作りようじ、すりこ木 第二章 盛夏 夏の庭 / 部屋の模様替え / 葉使いの料理 / 使い切る暮らし / 夏の保存食と常備菜 / 私の遊び相手1 ガーゼと裁縫 / 私の遊び相手2 糸と糸巻き / 手仕事の愉しみ2 ふきんの縫い方 第三章 秋 秋の庭 / 秋の慶びごはん / お茶のおもてなし / 果実酒の愉しみ / 蜂蜜 / 秋の保存食と常備菜 第四章 冬 冬の庭 / 薪ストーブの愉しみ / 夫とのコーヒータイム / 豆を煮る / 鍋 / 冬の保存食 / 正月を迎える / 手仕事の愉しみ3 布を染める
-
-新宿が最も輝いていた頃の愛と情熱の物語。 本格的インドカリーで全国的にも有名な新宿中村屋。2014年10月、リニューアルした同社新ビル内に美術館がオープンした。 明治時代末期から大正、昭和初期にかけて、同社の創業者である相馬愛蔵・黒光夫妻のもとには多くの芸術家が集い、サロンとして文化を発信。ロダンに影響を受け日本の彫刻界に大きな足跡を残した荻原碌山や詩人の高村光太郎、書家の會津八一らが出入りし活況を呈していた。そしてインドの独立運動家をかくまい、ロシアの詩人を援助し、それらがきっかけでインドカリーやボルシチなど名物料理が生まれていく。 この「中村屋サロン」を中心に花開いた芸術と食文化を、愛と情熱に溢れた人間模様とともに描いた、知られざる新宿ヒストリー。 ※【ご注意】お使いの端末によっては文字が読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立読みファイルをご確認いただくことをお勧めいたします。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 伝説のベストセラー自然派料理本が、30年のときを経て復活。 1984年に刊行され、カントリーライフを提唱した料理本の名著を新装版として再刊。 現代だからこそ読み直したい、自然で奥深い食文化とレシピの提案。 Lesson1 大地を耕す 自然の摂理/作物を栽培する Lesson2 食物を保存する アリスの保存食作り/果物を加工する/大豆を加工する Lesson3 乳製品・ワイン・スモーク ミルクを加工する/チーズを作る/ワインをつくる/スモーク製品 Lesson4 アリスファーム流クッキング パンを焼く/スープを作る/スパイスとインド風料理/ 夏野菜を使って/豆を使って/ジャガイモを使って/レタス包みとオムレツ/ ふだんの和風料理/豆腐を使って/米を使って/おいしいサラダ/楽しいデザート 宇土巻子(うど・まきこ) 1950年、東京生まれ。東京外国語大学イタリア科卒。大学在学中、インドでパートナーの藤門弘と出会い1973年、アリスファーム設立(飛彈)。 1983年、飛彈での10年間の活動を機に北海道に移住。 現在は北海道余市郡赤井川村在住。広大な農場でベリーの栽培と加工に携わり、田園生活を楽しんでいる。 著書に『ファブリック・ワーク』(1983年 山と渓谷社)『ハーブ・レシピ』『フルーツ・レシピ』(1993年文化出版局)、「シェーカークッキング」(1994年柴田書店)『田園の食卓』(1995年山と溪谷社)「農的生活12ヶ月」(2001年世界文化社)ほか多数。訳書に『完全版自給自足の本』(1983年 文化出版局)などがある。
-
3.0
-
-根強い人気を誇る韓国時代劇で描かれる朝鮮王朝は、どこに魅力があるのか? 本書はその謎に迫る一冊だ。1392年に成立して約520年間続いた朝鮮王朝は、日本史の年表でいうと、室町時代から明治時代までの長期にわたった。文化や習慣、生活様式などさまざまな面で現在の韓国社会へと脈々と受け継がれている。また、日本から見ても食文化、礼儀作法、儒教の教え、身分制度などの共通点が多く、他の外国の歴史に比べ親しみやすい。 そんな朝鮮王朝を彩った初代王の太祖(李成桂)から歴代27人の王の治世やエピソードを「朝鮮王朝実録」をもとにひも解く。 ※本書は2011年に刊行された「知れば知るほど面白い 朝鮮王朝の歴史と人物」(実業之日本社刊)を一部改稿し、再刊行したものです。改稿の際に、専門ウェブメディア「韓ドラ時代劇.com」に著者が執筆した原稿も生かされています。 【目次】 第1章 傑作時代劇が謎めいた歴史を面白く見せてくれる 「ヘチ」は英祖の若き日の歴史騒動を描いた傑作! 「カンテク」では王妃選びの過程が興味深くわかる 立派な世子が哀れなダメ亭主になってしまう「100日の郎君様」 国王と道化師が巧みに入れ替わる「王になった男」 王子同士の葛藤を歴史絵巻として描いた「不滅の恋人」 「チャングム」は女性を勇気づける成功物語! 果たしてチャングムは本当に実在したのか 苦労した名君をスーパースターに仕立てた「イ・サン」 歴史に残る悪女「張禧嬪」は時代劇にひっぱりだこ どん底から頂上へ! 究極のシンデレラを描いた「トンイ」 実在のファン・ジニは若者が恋に殉じるほどの美女だった 「成均館スキャンダル」が昔の受験地獄を愉快に再現! 孤高の王の苦悩がよくわかるドラマ「大王世宗」 胸がすくような勧善懲悪ストーリー「春香伝」 「オクニョ」は実在した悪人だらけの歴史ドラマ! 「仮面の王 イ・ソン」では世子の権限の絶大さが描かれている 朝鮮王朝なるほどQ&A(1) 第2章 王になるとこんな人間になってしまうのか 王はスーパーマンなみに働いていた 王の名にある「祖」と「宗」はどう違う? 朝鮮王朝をつくったやりすぎの創業者「李成桂」 クーデターで王権を奪取した武闘派「太宗」 今も尊敬を集める王朝最高の名君「世宗」 甥から王位を奪った非情の野心家「世祖」
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ラーメンの誕生からご当地ラーメンの特色まで世界的グルメガイド本への掲載、ヨーロッパでのラーメンイベント開催、中国や東南アジアで爆発的に広がる豚骨ラーメン……。今や日本の「ラーメン」は世界食としてはばたいている。日本固有の調味料である醤油。それよりも歴史の古い味噌。また世界共通で調味料の原点である塩。これらを駆使してスープを調理し、中華麺と合わせる日本のラーメン。戦前から変わらぬ味で続く老舗から、流行の味を追い求める新しいお店まで、数多くのラーメン店が日本に存在し、世界進出を果たしたラーメン店も数多く出てきているのだ。本書は、ラーメンの誕生から、ジャンルの形成、ご当地ラーメンの特色までを総括し、ジャパンクオリティで発展したラーメンの魅力を、日本語と英語で解説する。スープの種類から調味料、麺の解説やトッピング、サイドメニューの紹介までを網羅。さらにはラーメンの歴史、食べ方、マナー、注文のしかたやラーメンにまつわる用語の解説など、まさにラーメンに関するあらゆる情報を、日本語と英語でわかりやすく掲載。日本を代表する食文化のひとつとなった「ラーメン」について、日本語と英語で、一から学べる一冊である。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。
-
-地元の魚、近海で獲れた魚という意味をもつ「地魚」は、大量流通の規格品にはない魅力と美味を秘めている。本書は、そんな知る人ぞ知る存在の地魚について、漁獲・加工・流通・料理というすべての過程を、地域の商慣習や歴史とともに探究。卸売市場勤務のかたわら、魚食文化と食育の普及活動に精力を注いできた著者が、漁業や市場関係者、料理人のほか、産地と都市をつないできた行商人の聞き書きもまじえ描き出す文化誌。
-
-新宿名産の「八房唐辛子」が平成の世に復活。 江戸時代に、現在の新宿御苑とその周辺約二十万坪を領地として治めていた内藤家。「内藤新宿」と呼ばれた宿場の一角では屋敷で栽培した野菜が売られ、中でもとうがらしが評判となり……。 江戸の食文化を支えた「江戸野菜」のひとつ『内藤とうがらし』の発祥と盛衰、そして復活にいたるまでのストーリーや関係者のエピソード、 『内藤とうがらし』を使ったレシピなど、あらたな新宿名物のマニュアルとも言える一冊。
-
4.0※電子版は書き下ろしショートストーリー『食文化の不思議』の特別付録つきです。 男であると勘違いされ 連れてこられたのは…後宮!? 男装の女性騎士・コーラルは、 外交先の「華烈」で主人を冤罪から庇い、 死ぬまで後宮で働く「宮刑」を言い渡されてしまった。 後宮での監視役を務めるのは、 かつて“鬼神“と噂された男・汪紘宇。 おまけに二人が仕える妃の星貴妃は後宮一気位が高く、 女官も手を焼く人物だという。 そんな殺伐とした環境の中でも、 次第に惹かれ合っていくコーラルと紘宇。 ただ、コーラルが女性であるということに、 紘宇は全く気付いていなかった…。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 イギリスのティータイムに欠かせない定番のお菓子、スコーン。 各家庭やティールーム、ホテルなどそれぞれの味があります。 本書では、今日本で注目を集めているティールームや、予約が取れない人気のお菓子教室など15名の、とっておきのレシピ集です。 つくり方はもちろん、スコーンへのこだわりや、材料を決めるポイント、レシピ開発の裏側など、お菓子づくりに役立つテクニックがもりだくさん。 スコーンをおいしく仕上げる「コツ」も惜しみなく公開。 スコーンだけでなく、各ティールーム・お菓子研究家が得意とするイギリス菓子のレシピも充実。 スコーンにあわせる紅茶の楽しみ方、著者ならではのイギリスの食文化についても理解が深まる一冊です。
-
-日本が誇る食文化、寿司。 保存法として生まれたといわれる寿司は、食事という次元を超えて文化として発展してきました。 握り寿司の基礎を築いた江戸の技を継承する名店を支持する寿司通が多い一方で、 伝統に縛られることなく独自のスタイルを表現する寿司屋へ予約が殺到しています。 現代はまさに、寿司の成熟期と言えるでしょう。 本書では、日本各地で名を馳せる雲上級の名店を訪ね、店主の想いから熟練の仕事までを披露していただきました。 ※デジタル版には、表紙画像や目次に掲載している記事、画像、広告、付録が含まれない場合があります。また、掲載情報は原則として奥付に表記している発行時のものです。 ※本書の内容は、2018年発行『寿司大全』、『寿司屋が教える魚のさばき方』、『#日本酒部』、2017年発行『Wine Complete』の記事を再構成・加筆・修正したものを含みます。
-
4.0もとをたどれば塩辛やナレズシといった古代アジアの保存食。それが日本に伝来し、律令時代には〈すし〉として日本に根付く。江戸期に酢や醤油と出会い、江戸前スタイルの〈寿司〉が誕生。現代では回転ズシの普及で〈SUSHI〉は世界の食文化を劇的に変えた。一方でフナズシのようなスローフードとしても現存するスシが、如何にして世界のファーストフードにまで広がることができたのか? その背景にはより新鮮な生の状態を味わいたいという日本人のこだわりがあったのでは……。本書は、フォト・ジャーナリストであり、世界の食文化に精通する著者が、数千年間、変容し広がり続けるスシの魅力に迫る。【目次より】スシを巡る旅は如何にしてはじまったか/保存食としてのスシ/オールアバウト・スシ―ナレズシから江戸前までの変容について/握りズシの完成―醤油と刺身とスシ/そして、スシはインターナショナルな料理となった/何故、スシはこれだけ受け入れられたのか
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 高級店から回転寿司まで、代表的なおすし約320貫とネタ元の魚を写真で解説する、おすしの図鑑です。著者は、『からだにおいしい魚の便利帳』の著者のぼうずコンニャク 藤原昌高さん。二千種にも届こうとしている著者のおすしのデータベースから、比較的ポピュラーなもの、日本各地で実際に使われているものを選びました。同じ魚でも、皮霜、一般の握りなど、複数のすしダネを掲載しているものもあります。さらに、すしダネには「超高」「高」「並」「安」というアイコンがつけているので、本書を片手におすし屋さんで安心して注文しやすくなっています。本書はすしダネが321貫掲載してあるものの、バッグの中にいれてもっていけるハンディサイズになっています。ぜひ、本書と一緒にお寿司を召し上がってください。 ■CONTENTS 赤身/サーモン/魚卵/光りもの/長もの/白身/白身/イカ・タコ/貝/エビ・カニ/その他 ■著者 ぼうずコンニャク(藤原昌高) 1956 年、徳島県美馬郡貞光町(現つるぎ町)生まれ。子供の頃から川魚を捕ることが好き、魚を食べることは嫌いだった。ある日突然、魚好きに。人間と関わる生物すべて、食文化を調べ始めて30年以上。すしの写真を撮り始めて15年。魚介類関連写真は50万点以上、すしの写真は2万点以上を保有。現在、島根県水産アドバイザー、釣り雑誌などにエッセイを書いている。※著者略歴は書籍刊行時のものを表示しています。
-
3.6日本料理の基礎が出来上がった江戸時代。後期に入り経済事情が安定すると、ふだんの食事にも胃袋を満たす以上のものが求められるようになる。こうした中で生まれ、洗練されていったのがすし、天ぷら、蕎麦、うなぎだ。腕利きの料理人が現れると、食べ手にも粋人が現れる。この両者が出会い、食の世界に変革がもたらされていった。たとえば、日本橋南詰の天ぷら屋台の名店「吉兵衛」の客が、隣り合わせた屋台のかけ蕎麦に天ぷらを浮かべることを思いつく、といった具合に──。膨大な史料を読み解き、江戸四大名物食誕生の知られざる歴史に迫る、江戸食文化史の決定版!
-
4.0寿司、天ぷら、とんかつ、懐石料理から、お好み焼き、立ち食いそば、おみやげ、コンビニまで、アメリカ人ビジネスマンのスティーブが体験する、おいしくて不思議でクールなニッポン。日本の料理と食文化について、英語で読みたい・聴きたい・話したい人、外国人と食事をする機会のあるビジネスピープル・留学志望者などに最適の本です。外国人との食事で使える知識&表現がいっぱいあります! ※この電子書籍には、紙の書籍の付属CDに収録された音声データは含まれておりません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 空前のスパイスブームの今、料理好き、飲食業界の方にスパイスとハーブの知識と活用法を指南。スパイス&ハーブ検定公式テキスト 今、関心の高いスパイス料理とハーブ。美味しいだけでなく様々な健康効果も注目されている。お店で出てくるスパイスに詳しくなり、家庭でも楽しみたい人のためのわかりやすい入門書。全80種の基礎知識と使いこなし術を紹介。歴史、主な働き、使うタイミングと使用量、世界の食文化との関わり、料理レシピ、手作り調味料レシピ、ハーブティーレシピ、アロマテラピーやクラフト作り、ハーブの栽培などを掲載。●スパイス&ハーブ検定事務局(山崎香辛料振興財団)認定の1級、2級、3級の唯一の公式検定テキストなので受験者は必携。予想問題集も掲載。●2009年発行のテキストの改訂新版で、料理レシピやレイアウトは一新したが、検定内容は従来どおりで変更なし。●掲載品種はオールスパイス、オレガノ、ガーリック、クミン、クローブ、ペッパー、コリアンダー、シナモン、ジンジャー、ターメリック、タイム、バジル、ミント、ローズマリーなど
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ご利用前に必ずお読みください】 ■本書は「Fielder」に掲載された「図解サバイバル読本」に加筆・修正し、纏めた合本です。 ■誌面内の目次やページ表記などは紙版のものです。一部の記事は、電子版では掲載されていない場合がございます。 ■一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 ■電子版からは応募できないプレゼントやアンケート、クーポンなどがございます。以上をご理解のうえ、ご購入、ご利用ください。 フィールドで役立つ知恵と技術をイラストでわかりやすく解説 自然をもっと身近に感じるための現代版アウトドアマンズバイブル 本格アウトドア雑誌「Fielder」が蓄積したフィールドで役立つ知恵と技術をイラスト化し、誰にでもわかりやすく解説した一冊。 本書ではかつてホモ・サピエンスが持ち得ていた自然界を生き抜く知恵や技術を現代の環境に合わせて解説しているので、日頃のアウトドアレジャーから万が一の災害時まで、読むだけではなく様々な場面で実践することができる。 ■収録内容 Part.01 火熾し 生き抜くための火熾し/火とは何か?/火熾しとは何か?/現代的な火熾し/火口と焚き付け/メタルマッチで火を熾す/メタルマッチに向いた火口とは?/チャークロスを作ってみよう COLUMN 火花には2種類ある Part.02 焚火の基本 焚火のメカニズムを理解する/焚火の大原則「ファイヤートライアングル」/焚火の一生を理解する/基本のロングファイヤー/ロングファイヤー型焚火の組み方/ロングファイヤー派生型の焚火/3つの実用焚火/用途特化型の焚火/炎を楽しむ定番焚火型 COLUMN 燃えているのは薪ではない? Part.03 焚火の応用 焚火をより実用的にする/焚火台を自作する/焚火を活かす周辺工作 COLUMN 野外炊飯の極意 Part.04 シェルター構築の基本 命を守るシェルター/サバイバル「3」の法則/タープ設営の基礎技術/タープ設営の基本/タープ設営の応用技術/ブルーシートでシェルターを作る/定番ロープワークを習得する Part.05 シェルター構築の応用 最小限の道具で築く実践的シェルター/大定番の「デブリハット」/ 伝統的な「ティーピー型シェルター」/工夫次第で冬も快適「防寒寝床」/ブルーシートと現地素材で作る「高床式寝床」 COLUMN 自然物で作るシェルターのリスク Part.06 野食の知識 食料を調達するということ/食材候補の判断基準/身近で簡単な食料調達 COLUMN 寄生虫は移動する Part.07 野食の実践 動物として、動物を食べる/手軽に動物性タンパク質が得られる入門的野食3選/田舎の味の山菜レシピ/野食上級者が好む美味い食材/ 美味いヘビランキング/河川大国・日本の伝統魚食文化 COLUMN 昆虫食は世界的文化 Part.08 狩猟 ハンターになるために/2つの狩猟方法を知る/銃の所持許可を取得する/狩猟免許の取得と狩猟者登録/わな免許とわなの種類/日本の狩猟鳥獣/猟銃の種類を知る/散弾銃の弾を選ぶ/単独しのび猟/ヌートリアのエアライフル猟 COLUMN 素手猟の勧め EX. 非常時のサバイバル 火熾し/飲料水の確保/河川敷でのサバイバル術 COLUMN ナイフの携行について知る 巻末資料 実用生物図鑑(カラー) 身近な優良食材図鑑〈野草/木の実/虫〉 危険生物図鑑〈動物・虫/キノコ・植物〉
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界でイスラム教徒が増えている理由 ~じつは楽しく、優しい宗教だから?~ イスラム教徒の暮らしと文化、その教えから経済事情まで。 最新情報を起源とともに徹底解説。 14歳から読める!わかる!カラー図版満載!! 図解でわかる「世界の宗教と文化」シリーズ! 【目次より】 世界で19億の信者/拡大するイスラム経済/信じる神はユダヤ教・キリスト教と同じ/「ジハード」の本当の意味は「努力」/イスラム教の2大宗派 スンナ派とシーア派/ラマダン月の断食で心身をリセット/イスラム独自の社会福祉 喜捨によって弱者を支援/豚肉やお酒は禁止でも豊かなイスラムの食文化/利子をとらないイスラム金融の仕組み/世界最先端の学問の粋を集めたイスラム文明800年の輝き/十字軍との戦い キリスト教徒との確執の始まり/キリスト教とユダヤ教の確執がパレスチナに戦争を/イスラエルを支援する欧米にアラブ諸国は石油で戦いを挑んだ/西欧社会との対立のなかで混迷するイスラム社会 ●Part1 データで見るイスラム教 ●Part2 イスラム教の基礎知識 ●Part3 イスラム教徒の暮らしと文化 ●Part4 イスラム世界1400年の歩み
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界中で今なお愛され続けているMADE IN JAPAN=日本製品や、日本発の技術、食、文化を一挙紹介!日本では当たり前の製品が海外では絶大な支持を集めていたり、日本のメーカーが現地のために作り上げた製品などなど、世界で愛されるMADE IN JAPANから100点を厳選。外国人が見た、日本人の知らない日本がここにある!
-
4.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 料理で知る、料理がつなぐ 文化や宗教の多様性。 世界各国・300地域を網羅した家庭料理、伝統料理を、各々の料理の歴史や食文化などの背景とともに楽しめる1冊です。 ネット時代はグローバル化を推し進め、世界各国の食文化にも関心が集まっています。 「その国を知るには料理から」ということで、世界各国・300地域の伝統料理、郷土料理を再現、紹介し、日本の家庭でも作りやすいレシピでご紹介します。 併せて、その国の食文化の概観、また宗教の食規定などもわかりやすく説明し、多様な文化を理解し合うための一冊を目指します。 著者は、世界の料理、日本で楽しめる各国レストラン情報をいち早く提供する総合情報ウェブサイト、e-food.jp の青木ゆり子。 設立20周年を迎える2020年、満を持して、今までフィールドワーク、研究を続けてきた世界各国の料理レシピ、食文化を紹介する、集大成的1冊です。
-
4.5世界各地の家庭に滞在し、その家の人とその土地の食材で料理をして食卓を囲むと、 それまで気づかなった疑問が湧いてくる―― ・どうしてここのほうれん草は日本のより味が強いんだろう ・肉とチーズを一緒に食べることが宗教的にだめってどういう理屈だろう ・なぜアボカド産地なのにいいアボカドが買えないのだろう ・ブルガリアの人って本当にヨーグルトをたくさん食べるんだろうか そんな疑問から、食べ物と政治、宗教、環境、教育、気候、民族などとのつながりを解き明かしていく。 台所探検家・岡根谷実里が探る「おいしい/おいしくない」を超えた料理の向こう側の話。 第1章■食と政治 ブルガリア ヨーグルトは本当に「伝統食」か? メキシコ アメリカナイズされるタコス ベトナム 元技能実習生たちが作る精進料理 スーダン パンの普及が生活を揺るがす ★コラム1 おみやげに喜ばれる日本のお菓子は? 第2章■食と宗教 イスラエル マクドナルドにチーズバーガーがない――食べ合わせの謎に迫る インド 世界一厳しい? ジャイナ教の菜食と生命観 ★コラム2 機内食に見るフード・ダイバーシティ 第3章■食と地球環境 ボツワナ アフリカの大地で出会った、タンパク質危機を救う最強の魚 メキシコ アボカド人気が大地を渇かす ★コラム3 世界のサバ缶30種を食べ比べてみた 第4章■食の創造性 フィンランド パンケーキ作りに透けてみえる子ども中心教育 ベトナム 代替肉のルーツを探して寺の台所へ 第5章■食料生産 キューバ 食料配給制が残るオーガニック農業先進国 中国・上海 安心して食べられる野菜を求めて ボツワナ 牛肉大国でなぜ虫を食べるのか? ★コラム4 卵大国の日本、なぜ卵はずっと安いのか? 第6章■伝統食と課題 モルドバ 自家製ワイン文化とアルコール問題 中華文化圏 進化する月餅と増える廃棄 ★コラム5 ラマダンの時期、世界の食欲は増す 第7章■食と気候 ウズベキスタン 日本の野菜は水っぽい? コロンビア 豊富な気候帯が生み出す一杯のスープ ★コラム6 世界の家庭の朝食はパンとシリアル化が進む 第8章■食と民族 パレスチナ 国境よりも堅いオリーブの木と自家製オリーブ漬けの誇り ヨルダン シリア難民がもたらした食文化
-
-
-
5.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シャン州のインレという湖の上。ここで、10才のスミンミャがくらしています。水上にたてられた家から舟で市場へでかけたり、湖で浮き輪をつけて水浴びをしたり。湖上でくらす知恵が脈々と受けつがれてきたこの場所で、スミンミャは、湖の上の学校へ通い、放課後は塾で勉強をしています。スミンミャの将来の夢は、学校の先生。でも、お父さんは、「スミンミャは勉強がよくできるから、ヤンゴンのような都会にあるいい大学に入って、外国にでていけるような仕事についてほしい」と思っています。ミャンマーの独特な服装や食文化も面白い1冊です。将来友だちになるかもしれない、だれかの毎日。世界36か国で写真家が撮り下ろした、「世界のともだち」シリーズの26巻目。
-
-世界各地で、農畜水産物を長期に保存したり、うま味を醸し出す発酵食を調味料として利用したり、栄養豊かな発酵食を主食としたりする人間の営みにフォーカスを当て、地域の食文化における発酵食の位置づけ、発酵食と社会との関係を明らかにする。取り上げる地域は、日本、モンゴル、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマー、ネパール、エチオピア、そしてアフロ・ユーラシアの乳加工品をつくる地域とし、インジェラ、エンセーテ、納豆、ナレズシ、塩辛、魚醤、後発酵茶、馬乳酒、チーズ、バター、醸造酒、餅麹などの発酵食を論じる。
-
3.3約4万人の人生を変えてきた人気テーブルマナー研究家が「世界のビジネスエリートの食べ方とふるまい」を通して、「マナーからにじみ出る教養」について説く本。 各国の大使や国内外の要人らとの多くの会食から、著者が得た知見は「食べ方は生き方の鏡である」「マナー(美しさ)とは、単なる形式ではなく、まわりへの配慮である」というもの。 ・世界のビジネスエリートの食事風景とは、どんなものか? ・世界のビジネスエリートは、マナーの何を大事にしているのか? ・世界のビジネスエリートがマナーよりも大事にしていることとは? 和洋中から手食のインド料理、ハラルフード、ファストフードやブッフェまで、世界各国の料理のマナーに触れつつ、「なぜその形式に至ったのか」、文化や民族性から考える「相手への心遣い」や「他国の食文化への敬意」、「世界を変える食の本当の大切さ」についてひも解きます。 「マナーとは人をジャッジするものではない。まわりの人を幸せにする技術である」と語る著者の言葉は、マナーによって知識をひけらかすのではなく、マナーを知ったうえでマナーにとらわれない姿勢こそが真の教養であることを示しています。世界レベルのビジネスエリートに求められるのは「正しさではなく敬意」です。 ※カバー画像が異なる場合があります。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 豆は、穀物と並ぶ最も古い農作物です。 エジプトのツタンカーメン王の墓からはえんどう豆が、紀元前5500年頃のトルコの遺跡からはレンズ豆が見つかっています。 中東では、紀元前7000~6000年頃からえんどう豆、レンズ豆、ひよこ豆が、紀元前3500年頃にはそら豆が作られ、地中海地域を中心に広まりました。 モロッコやスペイン、ポルトガルの豆料理には、アラブ料理を源とするものが多くあります。 メキシコではいんげん豆が紀元前5000~4500年頃から作られ、大航海時代にコロンブスたちによってスペインに渡り、そのおいしさからヨーロッパをはじめ世界各国へと広がりました。 アフリカを起源とするささげ種の黒目豆は、大航海時代以前はヨーロッパで食され、大航海時代には奴隷貿易とともに新大陸に渡りました。大航海時代は、アフリカ、ヨーロッパ、新大陸の豆料理が影響を与え合った時代でもありました。 中国を起源とする大豆は、主に発酵食品の原料として利用され、アジア各国で独自の発酵食文化を育んできました。 本書では、東京近郊で人気の各国料理店や専門店のシェフによる各国の豆料理のレシピを美しい写真とともに掲載。 今まで紹介されることの少なかった中東の料理も網羅した、豆を使った料理全108レシピを紹介します。 現地の味そのままの本格的な料理から、簡単に作れる家庭料理まで、バラエティに富んだ豆料理が満載。 いずれも乾燥豆を使った料理のため、季節を問わず、通販や各国の食材店で現地の豆を入手して、旅する気分で料理を作ることができます。 料理の他にも、豆の伝播の歴史や豆図鑑など豆に関するさまざまな情報を網羅。 古今東西の豆にまつわるこぼれ話や、メキシコ、イタリア、インド、ミャンマーなど“豆食い”の国の現地レポートも充実。 知られざる豆大国ミャンマーのトーフ村や、その場で豆を豆粉に挽いてくれるインドの豆事情まで、豆にまつわる各国の食文化を紹介します。
-
-
-
-日本の失われた1カ月とは?! 西暦は実は二の次?! 世界から7年遅れてる国がある?! 宗教・アート・食文化・仕事…… カレンダーから見える意外な事実! 普段生活するなかで当たり前のように使っている暦。ですが、歴史を勉強してみたり、海外へ旅行してみると、はじめて知る暦の不思議がたくさん出てきます。暦にまつわる不思議を知れば、日本と世界の文化・暮らしの違いや共通点に気づき、異文化理解も深まります。世界中のカレンダーを収集し、そのカレンダーが使われる地域の社会・文化・暮らしを理解するための研究を長年行ってきた著者が、さまざまな角度から暦の話をわかりやすく語ります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 分かる&使える&活かせる! やっぱりすごい!!二千年の叡智 約1万人以上のクライアントと関わり、4千人以上の生徒に中医学を伝授! 日本在住歴30年&セラピスト歴20年以上、本場の中医師が教える、分かりやすくてと~っても深い中医学の世界! 「知りたいけど難しそう」 「学んだけれどよく分からなかった」 「もっと本場の知識に触れたい」 「中医学を暮らしや仕事に取り入れたい」etc…という方におすすめ! 中医学を活かすための基礎を、徹底的に分かりやすくお伝えします。 〈この本で分かること↓〉 ◉陰陽論 ◉五行学説 ◉気血津液 ◉虚と実 ◉経絡と経穴 ◉蔵象学説 ◉外因と内因 ◉望診 ◉10種の体質 ◉養生法 ◉刮痧療法 ◉人をどう診るか? ◉中医学 歴史上の大医達 読むと、「そうだったんだ!」「中医学って面白い、すごい!」「自分や家族、クライアントさん達に活かしていきたい!」ときっと感じるはずです。 【中医学とは?】 古代中国伝統医学の略称で、二千年の歴史がある。東洋医学をはじめ、様々な伝統医学の元になったといわれている。中医学の大前提は「陰陽バランスの医学」。「陰」と「陽」という相反するエネルギーがひとつになることで生命は確立し、そのバランスを整えることが中医学の目的。 【中医学を知ると…】 •「陰」と「陽」の概念が分かると、身体だけでなく心のバランスもとりやすくなる •世界の成り立ちや、人間を形づくっているものを感じることができる •臓器と感情の関係や、身体の内側の状態が外側にあらわれることなどが理解できる •10種の体質を知り、食や暮らし方などの養生法が分かるようになる •五行学説、虚と実、望診などでクライアントに必要な施術や養生法が分かるようになる •慈愛の心や志を育ててくれる 他多数 これからさらに必要とされるであろう、“人”のすべてを診る「中医学」。 本書でその叡智と二千年の歴史、先人達の慈愛をぜひ感じてください! CONTENTS 【第1章 中医学とは何か?】 盲目の師匠から教わった心で感じる施術 東洋医学は中医学が根源 陽=交感神経 陰=副交感神経 バランスがとれている安心感 耳の凍傷回復のために誕生した餃子 医者仁心(いしゃじんしん) [コラム]鳥肌が立つくらい凄い『黄帝内経(こうていだいけい)』 【第2章 陰陽五行(いんようごぎょう)を感じてみよう!】 季節や気候と関係する陰陽五行学説 偉大な先人達の自然界観察 春夏秋冬と陰陽の気 更年期症状は陰血(いんけつ)が減ることが原因 日常生活に欠かせない木火土金水 中医学は完全オーダーメイド [コラム]竹に書かれた物事の本質 【第3章 生命の通り道 経絡(けいらく)学説①】 秋冬養陰(しゅうとうよういん)には杏仁ミルクがおすすめ! 全身に張り巡らされた生命の通り道 経絡 六臓六腑(ろくぞうろっぷ)とつながる「十二経脈(じゅうにけいみゃく)」 任脈(にんみゃく)とを合わせた「十四正経(じゅうよんせいけい)」 経絡にも陰陽がある 二時間ごとの当番制「十二経脈当令(じゅうにけいみゃくとうれい)」 中医学は天人合一(てんじんごういつ)が大前提 [コラム]人は宇宙とつながっている 【第4章 全身をつなぐ命の道 経絡学説②】 変化を止めることは誰にもできない 人間は身体に病院と薬局を提携している 押さえておきたい各経絡のツボ 円形脱毛症と経絡の関係 体質を見極め強弱を決めよう [コラム]塗る漢方『五行』シリーズ 【第5章 内と外のつながり「蔵象(ぞうしょう)学説」】 羊肉とミルクティーで新年のお祝いを! 「細胞」を診るか「気」を診るか 「肝(かん)」は目と爪に症状があらわれる 舌に異常が出やすい「心(しん)」 湿気が増える長夏(ちょうか)は脾胃(ひい)の状態に注意 秋は肺の季節 白い食べ物で養生を 腎(じん)の症状は耳と髪にあらわれる [コラム]五臓と六腑は陰陽表裏関係 【第6章 〝気・血・津液(しんえき)〟の働きを知ろう】 陰から陽へ巡る季節 自然界から酸素 食べ物から栄養を 気が少なくなる「気虚(ききょ)」 ストレスで滞る「気滞(きたい)」 〝血〟は身体の精神と深く関わる 瘀血(おけつ)は痛みを引き起こす セルライトや原因不明の病には 気・血・津液は健康の源 [コラム]西太后(せいたいごう)も愛飲した漢方薬膳茶 【第7章 病気の原因〝外因(がいいん)と内因(ないいん)〟】 緑の力強い生命を感じられる喜びの初夏 病気や不調の一番の原因〝外因〟 春夏秋冬それぞれの病 感情と病気の関係性 遺伝や怪我は不内外因(ふないがいいん) 病気を未然に防ぐためには? [コラム]自然界の変化に応じた養生法 【第8章 中医診断学 「望診(ぼうしん)」の基礎】 夏の伸びやかな陽気を感じて過ごす 中医学の醍醐味 望診でさらに深く診る 青・赤•黄・白•黒 顔色が教えてくれる 顔の反射区 望五官(ぼうごかん) 健康や病気の状態をあらわす舌 舌の質や色が教えてくれること [コラム]動物のための中医学 【第9章 10種類の体質判断】 真の〝美しさ〟とは健康である 健康的な平和体質と気の生成不足 気虚体質 冷えを感じる陽虚(ようきょ)体質と血が足りない血虚(けっきょ)体質 乾燥する陰虚体質と気分が塞ぐ気うつ体質 痛みがある血瘀(けつお)体質と肥満体型の痰湿(たんしつ)体質 吹出ものができる湿熱(しつねつ)体質 特別な特異体質 深めていけば的確なアドバイスが可能 [コラム]土地に合わせた「異法方宜論(いほうほうぎろん)」 【第10章 体質別の養生法】 朝は一杯の白湯から始まる 気虚体質には卵や牛肉がおすすめ! 女性は血を補うことが大切 気持ちを上げるハーブを取り入れよう! 清熱作用のある食材を 食べることが養生につながる [コラム]心・身体・精神をつくる薬膳 【第11章 刮痧(かっさ)のすごい力!】 食文化を楽しむ! 日本の食の魅力 留学生時代を救ってくれた刮痧 二千年の歴史を持つ伝統医術 15㎏体重が減り薬も手放した! 道具ひとつにも解熱や鎮静の意味がある [コラム]頭部刮痧でスッキリ! 【第12章 〝人〟をどう診るか?】 これからさらに必要とされる中医学 人を診て人を理解する医学 エネルギー過剰な実証(じっしょう) 不足している虚証(きょしょう) 食事、便通、月経 生活習慣からの判断 肝・心・脾・肺・腎 五臓を診る 初心を思い出すことが悩みや迷いの指針になる [コラム]やっぱり施術は楽しい! 【番外編 中医学 歴史上の大医達】 中医学を知ると陰陽バランスが整う 中医学の蒼生大医(そうせいたいい) 多くの伝説を残す炎帝神農(えんていしんのう) 中医学三大経典の一つ『傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)』を編纂 医聖 =張仲景(ちょうちゅうけい) 滋陰潤肺(じいんじゅんぱい)の『百合鶏子湯(びゃくごうけいしとう)』 『本草網目(ほんぞうこうもく)』を著した李時珍(りじちん) 鍼を使って二人を生き返らせた 時を超えて伝わる志
-
4.0
-
3.3胃弱だった漱石が作品にちりばめた食のかくし味!――『吾輩は猫である』の牛鍋屋、『坊っちゃん』で清がくれた金鍔(きんつば)。 作品の中に出てくる洋食と日本の家庭食の意味は? 明治から始まる日本人の激動期を、食文化の視点から考察する! ●『吾輩は猫である』の家庭食 ●胃弱な漱石と苦沙彌(くしゃみ)先生 ●『坊っちゃん』と天麩羅蕎麦 ●博覧会と『虞美人草』 ●三四郎が行かなかった食堂車 ●明治家庭のカレーレシピ ●本格仏料理店、精養軒 ●『明暗』のりんごは何県産か ●サンドイッチとビスケット ●漱石は最期に何を食べたのか 「漱石といえば胃が悪く、酒も弱い。ろくなもの、食べていなかったんじゃないのか?」 そんな疑問を抱かれる向きもあろう。 しかし、漱石だってやはり人間。食べてきたのである。彼が生まれたのは、まさに日本の夜明け。詳しくは本編と年譜を見ていただきたいのだが、江戸から東京に変化し、日本が西洋の料理をどんどん取り入れていく過渡期に彼は生きていた。そして小説のなかに、彼自身がつぎつぎと出合っていったさまざまな食べ物を書き込んでいったのである。 漱石を読むと、新しい食べ物を前にして、ときに驚き、喜び、ときに懐疑的に対峙した明治の日本人がみえてくる。それは、とても新鮮である。
-
-日本が誇る伝統食にして健康食、そば。しかし、植物であると同時に作物でもあるソバの文化は、日本だけのものではない。ソバの本場・信州で研究を積んだ農学者が、世界のソバ食文化を探訪して日本のそばの魅力を再発見する。さらにその栄養と味覚、健康食品としての機能や、品種改良についても解説。 江戸の農書に表れる「ソバめくそ」「めくそ飯」とは何か? 「普通種」よりも収量が多くて安定しているダッタンソバ、ニガソバは、なぜ日本で栽培されなかったのか? なぜ「手打ちそば」が上等なのか? 朝鮮半島のシミョン、カルクッス、中国の「猫の耳たぶ」マオアルドウ、ネパールのソバの腸詰、ウクライナのソバカーシャ、スロベニアのソバ団子、フランスのガレットに、イタリアのポレンタ・・・各地のソバ食レシピをみれば、日本の「そば切り」を本流とする麺食ばかりがソバではない。縄文時代から親しまれる、ソバをもっと楽しむ本。〔原本:平凡社、2002年刊〕
-
-肉料理に合うワイン、魚料理に合うワイン――。ワインと料理の組み合わせにはある一定のルールがあることはよく知られていて、これはペアリングと呼ばれるものです。ソムリエの石田博さんは、世界のワインの産地を巡り、郷土料理とともに出されるワインを味わいます。すると、時としてこれまでの常識を覆すような、極上の組み合わせと出会うのでした。なぜこの料理にはこのワインが合うのでしょうか。そこには、その地で長年育まれてきた「絶対の組み合わせ」の秘密がありました――。本書では教科書的な知識ではなく、ワインを育むその地の歴史・文化、自然環境、食文化にまで言及し、ワインと食を深く楽しみ、味わうコツが描かれます。それは日々の食卓でも応用できるものです。ワインを本当に楽しみ、味わうためにぜひ知っていただきたいエピソードと情報が満載の一冊です。
-
3.3
-
-ソロタビ(=ひとり旅)向けガイドブックのシリーズに、金沢・北陸版が登場! ひとりだからこその楽しみ方はもちろん、 出発前から滞在中に役立つ、旅のテクニックまで盛りだくさんにお届けします。 【巻頭特集】 ★ひとりだから楽しい9つのこと! In 金沢・北陸】 1. まずはフォトジェニック茶屋街へ! 2. 21世紀美術館で現代アートに浸る 3. 兼六園でじっくり名園鑑賞 4. 店もネタ選びも妥協なし!極上寿司を味わう 5. 全店はしごでお気入りの器探し 6. ひとくちの口福を求めて~金沢和菓子 7. 美食の宝庫、加賀の食文化堪能 8. レンタサイクルで城下町ひとめぐり 9. 至福のスイーツタイム♪ 【エリアプロフィール&ソロタビグルメ】 エリアページでは、エリアの位置関係を把握しやすい地図&モデルコース、 ひとりでも気兼ねなく楽しめるグルメスポットをご紹介。 グルメスポットのデータには、ひとりで利用しやすいカウンター席の有無も掲載。 【金沢発 1dayトリップ】 ◆輪島 活気ある朝市でパワーをもらう ◆七尾 レトロな商店街をぶらり散策 ◆珠洲 自然とアートを訪ねて能登半島の先端へ ◆白山鶴来 「しらやまさん」で良縁祈願 ◆山代温泉 ノスタルジックな温泉街と九谷焼 ◆富山 最旬モダンアートに出会う 【ソロタビ流! 旅のテクニック】 ・交通手段&宿の賢い選び方 ・現地での移動手段 ・身軽なパッキング術&あると便利な持ち物 ・ひとりで困らない行動術 ~ひとりごはんから、情報収集まで~ ・観光に便利なアプリ ・旅をより深める ゆかりの映画、アニメ、小説 ソロタビデビューに欠かせない、超充実の内容を詰め込みました! 初めての金沢・北陸ひとり旅に欠かせない、便利なMAPと路線図付きです。 ※この電子書籍は2019年3月にJTBパブリッシングから発行された図書を画像化したものです。電子書籍化にあたり、一部内容を変更している場合があります
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 微笑みの国の住人たちを育てた、タイ全土かあさんの味巡り 東京都内だけでも数百軒ものタイ料理店がひしめき、毎年代々木公園で開催されるタイフェスティバルには、2日間で約30万人が来場。「タイ料理を食べるためだけにタイに行く」という人も多いほど、日本人を魅了しているタイ料理。ガパオ炒めやトムヤムクン、グリーンカレーなどに代表されるように、日本では濃厚かつガツンと刺激的でスパイシーな印象ばかりが強調されがちなタイ料理ですが、現地の家庭で食べられているタイ料理には、まだ日本では知られていないメニューも実はたくさんあるんです。また、おなじみのトムヤムクンひとつ取っても、かあさんの出身地や家族の背景によって味も見ためも材料もまったく違うことだって珍しくなかったり。そんなタイ家庭料理の“いろいろ”をご紹介したくて、北から南までタイ全土を周り、各地の料理上手なかあさんたちにいつものおうちごはんを作ってもらいました!テーマは「ファミリーの背景」から生まれた「家族を結ぶかあさんの味」華僑の夫と結婚したタイかあさんが作る、中華系タイ料理の味。バンコクで生まれ育った後、海外で長く暮らしたかあさんを支えた母直伝の味。3軒先までの庭先を訪ねれば新鮮な食材が手に入るタイ北部、自然豊かなチェンマイの味。恵まれた土地ならではの豊富な魚介とマレーシアの影響を受けた独特の食文化が交差する、南タイかあさんの個性豊かな味。かあさんたちが毎日家族に作っている豪快かつちょっと大雑把な家庭料理をそのまま教えてもらったので、通常のレシピ本とは少し使い勝手が異なります。「これで合ってるの?」と不安に感じる瞬間もあるかもしれませんが、自分だけの“おいしい”を発見できればそれで成功なのが、家庭料理のいいところ。計量はしない、入れる材料も日によって少しずつ変わるけど「いつもとちょっと違っても、家族のために作ればそれがウチの味でしょ」と、笑顔で語るタイかあさんを見習って自分流にアレンジしながら楽しんでいただけたらと思います。そして、それぞれのかあさんとその家族の物語を通して、タイの文化も感じていただけたら。タイのかあさんたちが家族に注ぐどこまでも深い愛情に触れることでタイという国の一面を知り、タイにより近づくきっかけになれば嬉しい。そんな思いも込めて、この一冊を作りました。
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界三大スープの一つに数えられる「トムヤム・クン」をはじめ、辛味、酸味、甘味にハーブやスパイスの香りが絡み合い、複雑で個性的な味わいを持つタイ料理に、日本のみならず世界の人たちが魅了されています。 本書は、タイで広く食べられている家庭料理や定番料理から宮廷料理まで、日本で再現可能な100の料理を厳選し、レシピとともに掲載しています。 地方料理にスポットを当て、一般的によく知られているバンコク周辺の中部の料理とともに、最近人気を集める東北部のイサーン料理や、北部・南部の料理の紹介にも力を入れました。 「トムヤム・クン」は、中部のココナツミルク入りと、南部のクリアスープの2種類を掲載。 東北部発祥の青パパイヤのサラダ「ソムタム」は、中部で食べられる一般的なものに加え、カニの塩漬け入りのものやカノムチン(米麺の一種)入りのものも紹介しています。 北部のハーブ入りソーセージ「サイウア」や、東北部の発酵ソーセージ「ネーム」や米入りソーセージ「サイコーク・イサーン」などのレシピも載っています。 特徴ある各地方料理を知ることで、タイ料理の魅力を再発見できます。 監修は、株式会社スパイスロードの料理顧問であり日本にタイ料理を広めてきた第一人者、味澤ペンシーと、同社が展開する「サイアムヘリテイジ東京」料理長ヴィチアン・リアムテッド、「サイアムセラドン銀座店」前菜・カービングスペシャリスト、ナルナート・スクサワン。 タイ料理の歴史や北部・東北部・南部の各地方料理、バンコクの外食事情、タイのコーヒー事情やアルコール事情などに関する読み物も充実。 食材や調味料、発酵食品の情報や、カービングや飾り切り、フルーツの食べ方、ワインのマリアージュなど、プロの料理人にも参考になる情報も載っています。
-
4.0台湾は小さい島ながら、変化に富んだ美しい風景、多様な民族、バラエティー豊かな食文化がぎゅっと詰まっている。台北、高雄などの大都市を起点に、活気ある下町やレトロな市場、最北端の離島、南国リゾート、映画『KANO』の街、深山の温泉へショートトリップ。人々のあたたかいおもてなしに感動し、食堂や屋台の絶品グルメと大衆酒を味わい尽くす、台湾ディープ紀行エッセイガイド。大好評『台湾一周! 安旨食堂の旅』に続く、台湾紀行エッセイガイド第二弾!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 眺めて楽しい台湾醤(ジャン)の本 「眺めて楽しい台湾食文化の本」第二弾です。 テーマは中華系料理に欠かせない ペースト状の調味料である「醤(ジャン)」。 30個の食材をもとに、醤を手作りする方法や 醤を使ったレシピをグラフィカルに解説。 台湾食文化のエッセンスを暮らしに取り入れれば、 おうち時間が少しだけ充実するはず。 台湾の食べ物に興味があるすべての方に! 台湾発「種籽設計」によるイラストを多様した紙面をお楽しみください。 ★著者プロフィール イラスト/種籽設計 台湾のデザイン事務所。 グラフィックデザイン、WEBデザイン、 プロダクトデザインなどを手掛けるほか、 体験をデザインする「ストーリーテリングデザイン」を提供。 ★翻訳者プロフィール 光瀬憲子 1972年、横浜市生まれ。紀行作家、英中日翻訳家、通訳者。 米国ウエスタン・ワシントン大学卒業後、台北の英字新聞社チャイナニュース勤務。 台湾人と結婚し、台北で7年、上海で2年生活。現在は台湾と日本を往復している。 著書に『台湾一周‼ 途中下車、美味しい旅』『台湾一周! 安旨食堂の旅』 『台湾縦断! 人情食堂と美景のの旅』『台湾の人情食堂 こだわりグルメ旅』 『美味しい台湾 食べ歩きの達人』『台湾で暮らしてわかった律儀で勤勉な「本当の日本」』『ビジネス指さし会話帳 台湾華語』など。 『タビリスタ』『ウレぴあ総研』や朝日新聞社のwebサイトでコラム連載中。 カルチャーセンターで台湾旅行講座の講師も務める。株式会社キーワード所属。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.4炒米粉、魯肉飯、冬瓜茶……あなたとなら何十杯でも――。 結婚から逃げる日本人作家・千鶴子と、お仕着せの許婚をもつ台湾人通訳・千鶴。 ふたりは底知れぬ食欲と“秘めた傷”をお供に、昭和十三年、台湾縦貫鉄道の旅に出る。 「私はこの作品を過去の物語ではなく、現在こそ必要な物語として読んだ。 そして、ラストの仕掛けの巧妙さ。ああ、うまい。ただ甘いだけではない、苦みと切なさを伴う、極上の味わいだ。」 古内一絵さん大満足 1938年、五月の台湾。 作家・青山千鶴子は講演旅行に招かれ、台湾人通訳・王千鶴と出会う。 現地の食文化や歴史に通じるのみならず、料理の腕まで天才的な千鶴とともに、 台湾縦貫鉄道に乗りこみ、つぎつぎ台湾の味に魅了されていく。 しかし、いつまでも心の奥を見せない千鶴に、千鶴子は焦燥感を募らせる。 国家の争い、女性への抑圧、植民地をめぐる立場の差――― あらゆる壁に阻まれ、傷つきながら、ふたりの旅はどこへ行く。
-
4.8おいしい野鳥が食べたい!――幕府の権力をもってしても、江戸のグルマンの食欲を抑え込むことはできなかった。失われた食文化の全体像を、初めて描き出す異色作! 江戸時代の人々は、多くの「野鳥」を多彩な調理法で食していた。鶴、白鳥、鴨、雁、雉子、雲雀、鷺、雀、鳩・・・それらは、食のみならず政治や経済、儀礼などをめぐって、魚やほかの動物たちには見られない、複雑で高度な文化の複合体を形作っていた。鳥は、日本文化そのものを理解するうえで欠かせない重要な動物だったのである。 歴代の徳川将軍は、鷹狩で野鳥を狩り、鶴を天皇に献上し、また大名や家臣に獲物を分け与えた。中・下級の武士たちは雁鍋や鴨鍋を楽しみ、裕福な町人は料亭で野鳥料理に舌鼓をうち、庶民は鴨南蛮や雀焼といった素朴なファストフードを頬ばった。幕府によって野鳥流通が厳しく統制され、日本橋の水鳥市場は活況を呈し、その大きな利権を狙ってアウトローたちがうごめいていた。しかし、江戸時代に隆盛を極めたこの食文化は、明治以降、衰退してしまう。そして今、数千年の歴史をもつ野鳥を食べる伝統文化が、日本から消滅しようとしている。 さまざまな野鳥料理のレシピ、江戸に鳥を送っていた村のフィールドワークなどから、語られざる食文化を総合的にとらえたガストロノミー(美食学)の誕生。 目次 序章 鳥の味にとりつかれた美食家たち 第一章 鳥料理の源流――京料理から江戸の料理へ 1 日本人はいつから鳥を食べていたのか? 2 中世の鳥料理 第二章 江戸時代の鳥料理と庖丁人――鶴の味噌汁、白鳥のゆで鳥、鷺の串焼き 1 江戸の町から出てきた大量の鳥の骨 2 『料理物語』のレシピ 3 庖丁人――一流シェフの伝統と技術 第三章 大衆化する江戸の鳥料理――富商、貧乏武士、町人の味覚 1 鶏鍋、雁鍋、鴨鍋――中級・下級武士の食卓 2 料亭・名店の味――富裕層、文人墨客の贅沢 3 鴨南蛮と雀焼――庶民の素朴なファストフード 第四章 闇の鳥商売と取り締まり――せめぎあう幕府と密売人 1 「生類憐れみの令」による危機 2 アウトローたちの鳥商売の手口 3 鳥商売と大岡裁き 第五章 侠客の鳥商人 ――東国屋伊兵衛の武勇伝 1 日本橋・水鳥市場の男伊達 2 幕臣と侠客との親密な関係 第六章 将軍様の贈り物――王権の威光を支える鳥たち 1 鷹狩と贈答による秩序維持 2 「美物」の使い回し――中世の主従関係 3 「饗応料理」の鳥の意味 第七章 江戸に鳥を送る村――ある野鳥供給地の盛衰 1 手賀沼の水鳥猟 2 西洋的狩猟の浸食 3 カモが米に負けた 終章 野鳥の味を忘れた日本人
-
-沖縄で味わう世界のおいしい料理 今日はどこの国へグルメトリップ!? 沖縄にいながら世界各国の料理を楽しむ!国際色豊かな沖縄だからこそ集結した多種多様な食文化、見知らぬ土地の見知らぬ味、いざ各国をめぐる食の旅へ出発!南米や欧米諸国、中近東から東南アジアなどおいしいものが沢山、さまざまな味が楽しめる嬉しい1冊です。
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本の2018年度の食料自給率はカロリーベースで約37%。先進国の中でもかなり低い。私たちは「持たざる国」に住んでいることを自覚せねばならない。しかし、米と大豆さえあればこの国は何とかやっていける。米は主食「ご飯」、大豆はみそ、しょうゆなど「汁物」の原料。 本書では、四月は胚芽米ご飯とあさりのみそ汁、五月はたけのこご飯と鶏のすっぽん仕立て、六月は梅干しご飯とえんどうのけんちん汁、十月はかやくご飯と天ぷらのみそ汁、十一月は麦ご飯ととろろ汁、三月は五目ずしとはまぐりの吸い物など、季節ごとに食べたいご飯と汁物を紹介し、その大切さを説く。 著者は、脳血栓で倒れて言語障害を伴う半身不随の父親の8年におよぶ介護を通じ、スープの重要性に気づくことになる。その代表的なスープである「玄米スープ」と「干ししいたけのスープ」も掲載している。 また、著者と親交のあるヒゲタ醤油株式会社・取締役相談役の濱口敏行氏が「しょうゆについて」を、合資会社八丁味噌(屋号カクキュー)・代表社員の早川久右衛門氏が「八丁味噌について」を寄稿し、しょうゆやみそが日本の食文化に欠かせない調味料であることを力説している。 ご飯と汁物のレシピだけでなく、米と大豆との向き合い方を考えさせる一冊である。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 京料理にお茶、おやつ……。バラエティー豊かで奥深い京都の食文化を、12カ月ごとのテーマに沿ってたのしく紹介。読むだけでも面白く、京都グルメを味わいに出かけたくなる一冊。(文・甲斐みのり/イラスト・ぱんとたまねぎ)
-
-教育と授業を根本からたのしく考え直す教育雑誌 今月は,生活の中で見つけることができる科学の原理に焦点を当てて特集を組んでみました。そういう視点を持って身の回りを見渡してみると,生活の中にはたのしく,そして親しみと感動をもって見ることができる科学のタネがたくさん転がっています。今月号がそんなタネを見つける手助けになればうれしいです。もちろん,自由研究や自由工作にぴったりの内容もたくさんあります。どうかお楽しみください。 【目次】 (今月のものづくり)共振ってたのしい! 福嶋昭雄 穴あけパンチでおりぞめ花火 西岡明信 ねこパチンコ 中西 康 〔あぶらのかんの話〕をたのしもう! 伊勢革観 自転車反射板で虹色を1つずつ見る 佐藤重範 バスボムづくりはいかが? 高畠 謙 キンキンのジョッキの秘密 郡 進 (板倉聖宣アーカイブズ鉛筆やクレヨンも磁石にすいつく! 板倉聖宣 (いたずら博士のオモチャ箱)番外編 ハッカ舟の発見 市原千明 編集委員会ニュース 私がタブレットで《空気と水》をするなんて! 亀川純子 食文化で見る世界史 堀江晴美 2学期は〈爆発〉でどっか〜んとスタート 滝本 恵 予想が外れるからイヤ 佐竹重泰 「救世主」になった道徳プラン 原田尚賢 女の先生・男の先生 村西正良 (手描きのページ)風だより 藤原詔子 サークル&研究会案内 市販の実験キット,どう扱う? 東垣 淳 おたよりのページ 本の紹介『生命とは何か』 萠出 浩 仮説社のページ 編集後記 【著者】 「たのしい授業」編集委員会 「このたのしさを伝えたい」という思いから自主的に書かれた授業の実践記録のうち多くの人に喜んでもらえそうなものを厳選して紹介しています。
-
5.0鮨職人たちが選ぶ最も尊敬する鮨職人のアンケート一位に選ばれ、多くの食通たちを心酔させてきた四ツ谷『すし匠』の中澤圭二氏。国内の評価を不動のものとしていたにもかかわらず、中澤氏は2016年、53歳でハワイのリッツ・カールトンに進出する。築地からネタを空輸するのではなく、地元ハワイやアメリカ大陸沿岸の魚をつかって、一流の鮨を握るという前途多難な試みに挑んだのだ。それを可能にしたのは、素材の魅力を極限まで引き出す、200年の歴史をもつ江戸前鮨の技法だった――。 中澤氏に出会って以来、その人柄と仕事に惚れ込んだノンフィクション作家の一志治夫氏が15年以上にわたる取材の蓄積から描き出す、熱き男の物語である。江戸時代に握り鮨を考案した華屋與兵衛の時代から、戦前戦後の鮨文化、ここ数十年の海外での展開まで、ダイナミックな変遷を浮き彫りにしつつ、江戸前鮨という食文化の奇跡を浮き彫りにした、鮨ファン垂涎の一冊。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■「もっと、南へ」 いま一番熱い台湾がここにある。 台湾リピーターの日本人にもまだあまり知られていない屏東。人、食、文化、様々な側面で「台湾らしさ」を感じられる場所である。そんな屏東に魅せられた作家たちが語り尽くす貴重な旅エッセイ&ガイド。読めば必ず屏東を訪れたくなるはず! [目次] 第1部 屏東に息づく日本 一青妙 第1章 懐古の街を訪ねて 第2章 何者かになりたくて 第3章 屏東のなかの「日本」 第4章 歴史を知り、未来を考える 第2部 屏東の食を訪ねて 山脇りこ 第5章 屏東で食べる 第6章 屏東の味を支える調味料 第7章 大地と海からの恵み 第3部 異文化に出会う 大洞敦史 第8章 海を愛する人々 第9章 山に生きる人々 第10章 土地に深く根差すアート 第11章 客家の文化に親しむ 【著者略歴】 一青妙 (ひとと・たえ) 作家・女優・歯科医。台湾人の父と日本人の母との間に生まれ、幼少期を台湾で過ごし、11歳から日本で暮らし始める。家族や台湾をテーマにした執筆活動では『私の箱子』(講談社)『わたしの台南』(新潮社)『環島 ぐるっと台湾一周の旅』(東洋経済新報社)など著書多数。日台をつなぐ交流活動に力を入れている。 山脇りこ(やまわき・りこ) 料理家・文筆家。屏東が故郷の友を得て、彼女にいつも癒され、大切なものが何か教えられました。彼女を育んだ魅力ある土地、行けば納得です。『食べて笑って歩いて好きになる 大人のごほうび台湾』(ぴあ)など台湾3部作のほか、ひとり旅先として台北を推す『50歳からのごきげんひとり旅』(大和書房)など著書多数。 大洞敦史(だいどう・あつし) 文筆家、三線奏者、蕎麦職人、台湾政府認定観光ガイド、法廷通訳、台南市日本人協会副理事長。1984年東京生まれ。2012年台南市に移住、レストラン「洞蕎麦」を5年間経営し、現在「鶴恩翻訳社」代表。著書『台湾環島 南風のスケッチ』(書肆侃侃房)など。 この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『旅する台湾・屏東 あなたが知らない人・食・文化に出会う場所』(2023年11月20日 第1刷)に基づいて制作されました。 ※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
-
-食事をデザインするための調理学の基礎テキスト。日本の食文化を新たに加え、食べ物のおいしさから食事の設計、食品の特性をふまえた調理科学、基礎調理、食の安全までを扱う。イラストや資料データを数多く掲載。 目次:調理学とは/日本の食文化と調理/食べ物のおいしさとは/食事をデザインしよう/基本的な調理操作/食品の特性を知って調理する/安全な食事を供するには※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0ジャガイモをめぐる知的冒険 「ポテトチップスはクレームから生まれた?」 「フレンチフライは戦争とマックで世界に広がった?」 「ジョエル・ロブションの、世界一のマッシュポテトの作り方とは?」 ジャガイモの起源から歴史、食文化、料理法など、ユーモアあふれる文章で、徹底的に思考した一冊。 美しいイラストレーションで繰り広げられる、レシピ本でも、エッセイ集でもない、読んで美味しい、見て楽しい、まるごとポテトブック! 【目次】 はじめに 伊丹十三さんの思い出 ポテトをめぐる物語 夜のカフェで/ミスター・リーズのサンドイッチ/新大陸の贈りもの/不謹慎な植物/ 戦乱と飢饉のヨーロッパ/タラとジャガイモの出会い/ジャガイモの食べ方/郷愁のブランダード/ 海を泳ぐ黄金/ニューファンドランド/スープの語源/失われたパン/土のないジャガイモ畑/ イモに月が出ている/アイリッシュ・シチュー/ジャガイモ掘り ジャガイモという不思議な植物 コモンポテト/ノアの箱舟/ジャガイモ博士に聞く/インカ帝国の知恵 ポテトの料理法 ポテトチップス/フレンチフライ/ベークドポテト/ローストポテト/ハッシュブラウン/ マッシュポテト/ポテトサラダ ―― コラム <ミスター・リーズのサンドイッチ><夜のカフェで><ジャガイモ掘り> <料理の四面体><和食とジャガイモ> おわりに 家庭菜園からの報告
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 わかりやすい【マンガ】と本格【解説】のハイブリッド! 主人公と一緒に世界旅行へ出かけよう! 国ごとのキャラクターが自分たちの国を紹介してくれるから、スラスラ読めて頭に残る! 〈地誌〉と〈系統地理〉の大事なところがスッキリわかる、最高の入門書! 【本書の内容】 プロローグ 1 東アジア/東南アジア/南アジア(韓国/中国/ベトナム/タイ/フィリピン/シンガポール/インドネシア/インドなど) 2 西アジア/アフリカ(イラン/イラク/サウジアラビア/トルコ/エジプト/ケニア/ナイジェリア/南アフリカ共和国など) 3 ヨーロッパ(イギリス/フランス/スペイン/ドイツ/イタリア/スウェーデン/ロシアなど) 4 アメリカ大陸/オセアニア(アメリカ合衆国/カナダ/メキシコ/ブラジル/ペルー/ボリビア/オーストラリアなど) 5 日本(地形/気候/農業/食文化/交通/貿易/工業/観光/世界遺産など) 付録 系統地理(プレートテクトニクス/外的営力/内的営力/平野地形/海岸地形/気候/農業/工業など)
-
3.3名古屋の人はなぜ小倉トーストが好きなのか? カレーの元祖が大阪に多いのはなぜ?…… 〈”県民食”に風土と歴史あり〉 日本全国の土地土地で人々のおなかを満たしてきた22の食べものを深掘り。 ”あの美味しいもの”への理解と愛が深まる、食文化・教養エッセイ。 ---------------------- 【もくじ】 ◆はじめに 01……道東ではなぜ牛乳豆腐が生まれたのか? 02……岩手ソウルフードにはなぜ、三つも麺類があるのか? 03……忘れられない、十和田湖のきりたんぽ 04……山形の食文化は、なぜ特別なのか? 05……信州蕎麦は冷たいのが正解? 06……金沢の醬油はなぜ甘い? 07……東京人はなぜ讃岐うどんを愛するのか? 08……東京と紅茶は相性が悪いのか? 09……浦和はなぜウナギが名物なのか? 10……名古屋人はなぜ小倉トーストが好きなのか? 11……なぜ、名古屋の喫茶店は特別なのか? 12……大阪人はなぜミックスジュース好きなのか? 13……歴史の中心地、関西を物語る淡口醬油 14……カレーの元祖が大阪に多いのはなぜ? 15……神戸っ子のハード系パン好き 16……広島市にはなぜパン屋が多いのか? 17……広島のお好み焼きはなぜおいしいのか? 18……博多ラーメンの出汁はなぜ、豚骨なのか? 19……カステラはなぜ、江戸時代の日本に根づいたのか? 20……長崎に和菓子屋が多いのはなぜか? 21……海に囲まれて暮らす沖縄ケンミンは肉ラバー 22……沖縄のおやつ。ポーポーとサーターアンダギー ◆あとがき ----------------------
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2015年に実施された第7回「なにわなんでも大阪検定」の公式問題集。1級・2級・3級全298問の完全解答・解説をハンディな1冊に収録。ことば、歴史、地理、産業をはじめ、食文化やスポーツ、娯楽、まち歩き、さらに「今年のテーマ」問題の「大阪城と大坂の陣400年」まで、幅広い分野からの出題にチャレンジ。要点をおさえた解説を読めば正解だけでなく周辺知識まで得られ、楽しみながら大阪力が身につく本。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2014年に実施された第6回「なにわなんでも大阪検定」の公式問題集。1級・2級・3級全298問の完全解答・解説をハンディな1冊に収録。ことば、歴史、地理、産業をはじめ、食文化やスポーツ、娯楽、まち歩き、さらに「今年のテーマ」問題の「商都大阪の軌跡~誇るべき大阪の企業と企業家」まで、幅広い分野からの出題にチャレンジ。要点をおさえた解説を読めば正解だけでなく周辺知識まで得られ、楽しみながら大阪力が身につく本。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 奥深すぎる中華料理を、中国と世界を歩き続けてきた地球の歩き方が徹底解説。本場中国の多彩な料理から、世界に広がった中華ルーツのメニューまで一挙紹介。現地の食文化を掘り下げる雑学や、取材先で知り得た旅コラム、国内のガチ中華レストラン情報も!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※電子版では、紙のガイドブックと内容が一部異なります。掲載されない写真や図版、収録されないページがある場合があります。あらかじめご了承下さい。 ※この商品は、「チェコ ポーランド スロヴァキア」編の分冊です。「チェコ ポーランド スロヴァキア」編3冊がパックとなった合本も販売しています。詳しくは『地球の歩き方 チェコ ポーランド スロヴァキア』で検索ください。石畳、堅牢な教会、豪華な宮殿、古城。中世ヨーロッパの町並みが残っているチェコ。神聖ローマ帝国時代の首都プラハや世界一美しいと称されるチェスキー・クルムロフ、カラフルな建物が並ぶテルチ以外にも個性豊かな美都が揃っています。またチェコビールをはじめとした食文化や伝統文化でも注目を集めている国です。 ●特集 01 チェコ ポーランド スロヴァキア ビジュアルガイド 02 チェコ ポーランド スロヴァキア 世界遺産案内 03 世界一おいしい! チェコビールを極める7つのスペシャル体験 ビールだけじゃない! 実はワインもおいしいチェコ 04 絶対食べたい! チェコ&ポーランド伝統料理ベスト5 指さしオーダーOK! 3ヵ国のローカル料理カタログ 05 かわいいアイテムがたくさん! 定番みやげをリサーチ 各都市の気になるおみやげ 06 ローカルグルメをゲットしにスーパーマーケットへGO! 07 ちょっと違った旅をしよう 芸術家と旅するチェコ まだまだいます! チェコ&ポーランドの偉人・有名人 ●本書に掲載されているおもな都市・観光地 【チェコ】プラハ、カルルシュテイン城、コノピシュチェ城、チェスキー・シュテルンベルク城、ボタニクス・クラフト・センター、テレジーン、フルシッツェ、クトナー・ホラ、カルロヴィ・ヴァリ、マリアーンスケー・ラーズニェ、ヘプ、プルゼニュ、チェスケー・ブディェヨヴィツェ、ホラショヴィツェ、フルボカー城、チェスキー・クルムロフ、ターボル、リトミシュル、テルチ、トゥシェビーチ、ブルノ、ゼレナー・ホラ、レドニツェ城、ヴァルチツェ城、オロモウツ、クロムニェジーシュ ●旅の準備と技術 シーズン/情報収集/モデルルート/予算とお金/出発前の手続き/航空券の手配/持物/出入国の手続き/3ヵ国間の交通/ホテル/電話/インターネット/トラブルと安全対策/イエローページ ※本商品は過去にダイヤモンド社から発行されていた商品になります。収録内容に変更はありませんので、重複購入にご注意ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※電子版では、紙のガイドブックと内容が一部異なります。掲載されない写真や図版、収録されないページがある場合があります。あらかじめご了承下さい。 ヨーロッパ、アジアが交差する位置にあるジョージアは、言語や宗教、生活習慣など独特の文化をもつ国です。発祥の地とされているワインやハチャプリやヒンカリなどの豊かな食文化、世界で2番目に国教化したキリスト教文化やハイキングや海水浴など大自然を楽しむことができます。そんなジョージアを満喫するならこの一冊。 ※本書には以下の内容が収録されています。 ジョージアでおすすめ見どころを詳しく紹介する「TO DO LIST」を見れば、訪れるべき場所がどんな場所でどこにあるかがぱっとわかります。本書は予習なしでも使えるガイドブックです。 ●ジョージア早わかりナビ ●ジョージアモデルプラン ●11 THINGS TO DO IN GEORGIA 01.トビリシ旧市街を空中散歩! 02.トビリシ旧市街で温泉浴! 03.「ジョージア正教会」の教会、修道院を訪ねる 04. 伝説の画家ピロスマニを知る 05. ジョージアの多声合唱を聴く 06. 絶景のジョージア軍用道路を行く 07. カヘティのワイナリーを訪ねる 08. 鉱泉リゾート ボルジョミを訪ねる 09. 秘境スヴァネティで氷河ハイキング 10. 黒海のビーチリゾート バトゥミで泳ごう! 11. エレヴァンへウイークエンドトリップ ●GOURMET & SHOPPING ジョージアのグルメ/ジョージア料理を味わおう/ジョージアのワイン&ドリンク/ジョージアで手に入れたいおみやげ/スーパーへ行こう ●AREA GUIDE 【トビリシ】 トビリシ早わかりナビ 新市街:ルスタヴェリ大通りから自由広場へ/旧市街/その他エリア/トビリシのレストラン/トビリシのショップ/トビリシのホテル 【クタイシ】 クタイシ中心部/クタイシからのエクスカーション(プロメテウス洞窟、マルトヴィリ渓谷、オカツェ峡谷)/クタイシのホテルとレストラン ●TRAVEL INFORMATION ジョージアの基本情報/ジョージア入出国/空港から市内へ ジョージア国内の交通案内/現地の旅行会社の活用法/旅の安全情報/INDEX ●巻末MAP ジョージア全図/トビリシ市街図/トビリシ中心部/トビリシ新市街/トビリシ旧市街 クタイシ市街図/アルメニア・エレヴァン中心部 ●Column ジョージアの歴史/ジョージアからアゼルバイジャンへ ●ジョージア語 あいさつと単語/ジョージア語 ミニ会話 ※予告なく一部内容が変更される可能性もあります。予めご了承ください。 ※本商品は過去にダイヤモンド社から発行されていた商品になります。収録内容に変更はありませんので、重複購入にご注意ください。
-
4.0
-
-麹菌は私たちの食文化に欠かせない存在で、醸造では「国菌」に指定され、多くの研究が進み、栄養・健康作用も広く知られるようになりました。体にすっと染みゆく滋味は、そのままいただくのはもちろん、野菜や果物を組み合わせれば軽やかにボリュームアップした一杯となり、料理にうまみを加え、お菓子をおだやかな甘みに仕上げてくれます。本書でご紹介するレシピは簡単でつくりやすい物ばかりです。懐かしい味の一杯を、新しい味の一皿を、ぜひお試しください。 <もくじ> PART1 美と健康に効果あり! 甘酒の秘密を知ろう PART2 毎日の健康習慣に! 甘酒をつくって、おいしく飲もう PART3 ヘルシーで簡単! 甘酒のスイーツ PART4 1工程プラスで簡単! 甘酒で定番料理をおいしく
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本で一番早く初日の出があがる町 銚子への旅 関東最東端にある千葉県銚子市は、日本で一番早く初日の出を見ることができる町。年末年始には多くの人々で賑わい、「銚子はね込み太鼓」などイベントも盛りだくさんです。銚子はまた、魚の水揚げ量が日本一、温暖な気候で野菜や果物も豊富な町。江戸の食文化を支えた醤油の醸造地としても知られ、祭りが盛んなのも特徴です。そんな銚子に足を延ばしてみませんか? 地域の魅力を、地域の人たちが伝える旅のガイドブック。
-
3.0
-
3.0
-
3.5
-
-【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 1月のお節は伝統としきたりの心を大切に、2月には寒さの中に春の訪れを待つ心で、3月雛の節句には春の華やいだ気分を盛り込み、4月花見の膳は春の寿ぎ。5月の膳では季節を五感で感じ、6月には涼感をポイントにし、7月は冷たさと温かさの取り合わせを考え、8月にはご先祖を迎える精進料理。9月の膳で暑さに疲れた心身をいやして、10月には実りの秋の滋味を味わい、11月の膳で冬を迎え、12月師走の膳に1年の感謝をこめる。季節を彩る12か月の行事を中心に、おもてなしの心をこめた料理の作り方。食文化の真髄を伝える書き下ろし。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 みそ、だし、具材を混ぜて丸める…たったこれだけで、いつでもどこでも本格的なみそ汁が味わえる「みそまる」がいま、大注目! 作りおきもできるので、忙しい朝や、疲れて料理が面倒なときはもちろん、ランチタイムやスポーツ、アウトドアのシーンでも重宝します。 さらにトッピングやコーティング、ラッピングも楽しめてパーティーやサプライズギフトとしてもおすすめ! みそまるをコロコロ丸めれば、大人も子供も笑顔があふれます。 日々の生活にすぐに取り入れられるみそまるで、暮らしを食事から健やかに。充実した毎日をスタートさせましょう。 【内容】 ・コロコロかわいいだけじゃない、「みそまる」ってなに? ・「みそまる」の栄養&効能・使い方・基本の作り方 PART1|「みそまる」パワーレシピ 美肌レシピ/ダイエットレシピ/疲労回復レシピ/生活習慣病予防レシピ/アンチエイジングレシピ PART2|「みそまる」アレンジレシピ 山椒風味のみそから揚げ/ピリ辛みそ鍋/和風みそまるハンバーグ/ビーンズみそキーマカレー など 【著者紹介】 藤本智子(ふじもと ともこ) アパレル販売員、読者モデル、ファッション雑貨店マネージャーを経て、2011年ミソガールとして「365日味噌活宣言」をし、みその普及啓蒙活動を開始。2012年「みそソムリエ」取得。2014年「ジャパン味噌プレス」創刊。2015年「ミラノ国際博覧会日本館サポーター」に就任。「朱鷺米応援大使2015」(佐渡市)に就任。フード・アクション・ニッポンアワード2015「食文化・普及啓発部門」最優秀賞受賞。「東久邇宮文化褒賞」受賞。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。






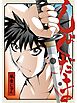
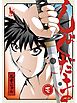


![食の堕落と日本人 新版[プレミア健康選書]―伝統的な日本食がニッポンを救う!](https://res.booklive.jp/1022678/001/thumbnail/S.jpg)