経営・企業作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-
-
5.0
-
4.0DX時代の顧客データ基盤「CDP」の考え方と導入方法を紹介 カスタマーデータプラットフォーム(CDP)はデジタル時代の重要なビジネスインフラ。 その導入の方法と顧客体験の向上のためのデータの管理・活用の考え方を解説。 著者の2名は、米国セールスフォース・ドットコムの有識者。 米国のデジタルビジネスの最先端の経験と知見に基づき B2Bの顧客、オンライン顧客、リアル店舗からEC、アプリ、ソーシャルなど 複雑なチャネルを通じて得られる顧客データを適切にマネジメントする方法を紹介。 DXへの取り組みを考えるビジネスリーダー、 デジタル・マーケティングを推進するマーケター 顧客データ管理のシステムに携わるIT関係者にお薦め。 【内容】(一部) ・顧客データに関する課題 ・CDPとは何か ・顧客の同意を得た上でのファーストパーティデータの管理と活用 ・顧客主導型のマーケティングシステムの構築 ・機械学習とAIとCDPの関係 ・カスタマージャーニーのオーケストレーション ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.1『サイロ・エフェクト』著者最新作! なぜ経済学やビッグデータ分析は問題解決に失敗するのか? 社会科学とデータサイエンスの融合で人類学的知見が果たすべき役割とは。 FTのトップジャーナリストが広い視野から事象を分析する人類学の思考フレームワークを解説。 * * * 現代社会の知的ツールが、機能不全に陥っている。経済予測、選挙の世論調査、金融モデルは外れてばかりだ。こうしたツールは、世界はごくわずかな変数で分類・把握できるという前提に基づいて設計されている。視野が狭いのだ。 世界が安定していて、過去が未来の参考になる時代なら、それでもうまくいくかもしれない。だが変化の激しい時代、「極端な不確実性」に直面しているときは、狭い視野は危険だ。 ビッグデータをAI(人工知能)がどれだけ処理しようとも、そこから導き出されるのは「WHAT」だけである。事象の原因、「WHY」にはたどり着けない。 * * * いま求められるのは、広い視野と「WHY」を突き詰める視点である。「未知なるものを身近なものに」「身近なものを未知なるものに」変化させ、隠れたパターンを見いだすツールである。 本書では人類学者のように「虫の目」で世界を視て、「鳥の目」で集めた情報と組み合わせることで「社会的沈黙」に耳を澄ます技術「アンソロ・ビジョン(人類学的視野)」を紹介する。 フィナンシャル・タイムズ紙(FT)のトップジャーナリストが執筆した話題作。
-
-電力王と呼ばれた明治・大正期の実業家、福沢桃介。埼玉の貧農の次男として生まれた桃介は金持ちになることを夢見て慶應義塾に通い、福沢諭吉の娘婿となる。念願の米国留学も果たし、一流企業に就職、すべては順調にいくかと思いきや、行く手を病魔が立ちふさぎ、長期入院を与儀なくされる。ところが病床で株を覚え、大金持ちになる。その金を元手に自分の会社をつくるものの、義父である諭吉の裏切りに遭い、会社を畳む。そこから一転、相場の世界にはまり、兜町の風雲児となるが、相場師という虚業に嫌気がさし、電力事業という実業に目覚める。弟分の松永安左エ門、日本最初の世界的女優、川上貞というパートナーの助けも借り、木曾川に東洋一のダムを築く。 桃介は直感や感性の人で、物事を論理からのみ考えない。「二と二が合わさって四になるんじゃない、時には五にもゼロにもなるんだ」と言うのが口癖。水力発電を主戦場と決めたのも、事業の将来性はもちろんだが、生き物を殺さず、土や岩を苛め抜くだけで済む、という理由からであった。本書は、桃介の稀代の事業家、イノベーターとしての機略縦横の活躍ぶりにスポットをあて、その生涯を描く。
-
3.8小売り企業は、どう動くのか 明暗を分ける決定因は何か ダイエー、イトーヨーカ堂、ジャスコ。業界大手3社の明暗はどこで分かれたのか? その決定要因は何だったのか? 企業の企画部による入念な解析が、現状の改善・改良をもたらし、その蓄積が業績の向上につながると考える戦略のミクロ解釈。経営者に宿る事業観が企業の「立地」や「構え」の選択に現れ、それが業績のトレンドを決めるという戦略のマクロ解釈。 本書では戦略のマクロ解釈の立ち位置が有効であることを明らかにする。この立場に立つとするならば、企業の明るい未来のためには、透徹した事業観を培った人物に経営を任せることが肝要である。神戸大学三品ゼミが徹底分析した経営戦略の要諦。
-
4.4プライム市場で生き残り、企業価値を上げるコーポレートガバナンスとは? そんな疑問に答える最強の指南書。 ガバナンス改革は、経営改革だ! 企業でガバナンスに携わる人のバイブル、「これならわかる コーポレートガバナンスの教科書」、 「ESG経営を強くする コーポレートガバナンスの実践」の筆者、松田千恵子氏のシリーズ第3弾です。 2021年6月に再改訂されたコーポレートガバナンス・コードに完全対応。 新たに盛り込まれた原則の意味や背景を紹介し、サステナブル経営のポイントを指南します。 2022年4月に東京証券取引所の市場区分が変更され、企業にESGが不可欠なものになります。 特に最上位の「プライム市場」には、より高度なガバナンスが求められます。 企業価値を高める取締役会の運営とは? 近年、日本で力を増すアクティビストへの対策は? など、日本企業が直面するガバナンスやサステナブル経営の課題について、分かりやすく解説します。 「ガバナンスにどう対応するか」という解説はもとより、そこから一歩踏み込んで、 「マネジメントとしてこれからどうするか」という解説も充実させました。 「サステナビリティやガバナンスは専門的で難しいかも」という人でも大丈夫です。 今回も「難しいことは言わない」「綺麗ごとも言わない」「何かあればイチから説明する」の三原則を貫きました。 コーポレートガバナンスの本質的な事柄について、「腹落ち」できることを目指しています。 企業の経営者やガバナンス関係者だけでなく、企業におけるマネジメントをどう考えるか・どう変えていくかを考えるビジネスパーソンにも役立つ、経営指南書の「決定版」です。
-
4.0経営における意思決定の精度向上を目指す 世界中で気候変動のリスクは年々高まっており、日本でも豪雨や酷暑等が毎年甚大な被害をもたらすようになりました。これらを背景にグローバル企業は気候変動時代における競争力の確保に向け、業態転換を含めたダイナミックな対応を始めています。 日本企業もようやく重い腰をあげ、気候リスクを経営リスクとして捉え、RE100(再生可能エネルギーの使用を進める国際企業連合「RE100」が主宰する温暖化防止の企業表彰)などに本腰を入れ始めました。しかし、日本の取り組みは欧米諸国にかなりの後れを取っており、グローバルスタンダードから引き離されているのが実情です。 本書は、実際に国内外で動き出している政策・企業事例(ケース)を紹介。日本企業に対し、気候変動に対する経営アクションを起こす際の「きっかけ」と、実際に脱炭素経営を進める上での「羅針盤」を提供する、脱炭素「経営」の初めての解説書です。
-
-本書を推薦します! 『1分で話せ』著者・伊藤羊一氏 経営理論を幅広くカバーし、ニューノーマルに引き寄せて解釈する。 だから実践的なスキルになる。 『経営戦略4.0図鑑』著者・田中道昭氏 ミッションから戦略、組織、ファイナンスに至るまで、 経営で実践するための世界最先端の経営理論解説書 世界の知を新時代の経営に活用する 新型コロナウイルスの感染症拡大は、 ビジネスの根底を大きく覆そうとしている。 対面で顔を合わせて業務を進めていくという 従来の日本型のプロセスが崩壊し、 企業は非接触ビジネス、DX、 サブスクリプション、SDGsなど、 「ニューノーマルの時代」に対応した ビジネスのあり方が求められるようになってきた。 また、これまで行ってきた事業が急速に落ち込んでしまった業界では、 どのように新規事業を創出するのかが 求められるようになっている。 このような急激なビジネス環境の変化が起こることで、 企業運営の前提であった法則や理論を見直す必要に迫られている。 本書では、ニューノーマル時代に通用する世界最先端の経営学の理論と その背景について広く共有することで、 これからどのような経営をしていかなければならないのか、 何がニューノーマル時代に役に立つのかという視点から、 新しい理論から古典的な理論までを網羅的にかつ体系的に整理し直す。 【本書の特徴】 ・世界最先端の経営論の中から、アフターコロナでも使える有用な理論を平易に解説 ・理論の紹介だけで無味乾燥とならないように、 論文の執筆背景や対象企業の事例、研究者の経歴なども解説 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.2世界1000万部超ベストセラーシリーズ『ビジョナリー・カンパニー』の原点で最新刊! 本書『ビジョナリー・カンパニーZERO』は、『ビジョナリー・カンパニー』シリーズが発行される前の1992年にジム・コリンズが記し、日本語訳されずにいた名著『Beyond Entrepreneurship』の改訂版。まさに、ビジョナリー・カンパニーの原点だ。 ◆リード・ヘイスティングスNETFLIX共同創業者兼CEOも大絶賛! 「本書は誰よりもどの本よりも、私のリーダシップを一変させてくれた。10年以上この本を読み返した。起業家なら、86ページ分を暗記せよ」 ◆スタートアップや中小企業が「偉大な企業」になるために必要なことを解説 偉大で永続的な企業になるために必要ことを1冊に凝縮してまとめた。誰と一緒に仕事をするか、リーダーシップ・スタイル、戦略、戦術をどうつくるか、パーパスやミッションなどをどう決めて実行するか重要になる。「偉大な企業」とそうでない企業との違い、規模が小さいうちから考えておくべきことなど、時代を超えて重要な内容が理解できる。 ◆ジム・コリンズとビル・ラジアーの教えの例 ・偉大な企業という目的地があるわけではない。ひたすら成長と改善を積み重ねていく、長く困難で苦しい道のりだ。高みに上り詰めると、新たな課題、リスク、冒険、さらに高い基準を探す。 ・企業が追跡すべきもっとも重要な指標は、売上高や利益、資本収益率やキャッシュフローではない。バスの重要な座席のうち、そこにふさわしい人材で埋まっている割合だ。適切な人材を確保できるかにすべてがかかっている。
-
3.01巻2,420円 (税込)真のDX化とは、 新規事業の創出である デジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)の 成功率はたったの16%だと言われています。 多くの企業がDX成功の糸口を見つけられずにいるのです。 DXを成功させるには、既存事業の「強化」と破壊を 両立する必要があり、成功要因が大きく異なる この2つを取り持つ「ジレンマ」が存在するのです。 本書は、DXを成功させるためのロードマップです。 多くのDX関連書籍が「なぜ行うのか?」を中心に書かれているのに対し、 「どのように実行するのか?」を中心に解説しています。 ミシュラン、ドイツ鉄道、ネスレ、世界経済フォーラムなど 100件以上のインタビューをもとに生まれた 独自のフレームワークと、多数のケーススタディを掲載。 真のDX企業になるための方法を伝授します。 【対象読者】 ●DXで自社を変革したい人。 経営者、役員、企業内アントレプレナー、製品責任者など。 経営/ITコンサルタントなど、DX化を指示する人。 ●プロジェクトとして担当する人。 システム開発会社の経営者、営業、PM、SEなど。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-
-
4.5
-
3.0
-
4.5【内容紹介】 リアル店舗は、感動する体験を提供せよ――グーグル、ウォルマート、IKEA、BMW、エスティローダーなどのグローバルブランドの戦略策定に関わった世界的な小売コンサルタントの最新作。アフターコロナに生き残る店舗経営とは? 「アフターコロナ時代はますますアマゾンやアリババなどのメガ小売の独壇場となっていくだろう」 「その中で小売業者が生き残る方法は、消費者からの『10の問いかけ』に基づく『10のリテールタイプ』を追求することだ」 「『自分たちはどのタイプで戦うのか』を正しく知る小売業者だけが生き残る」 と本書の著者ダグ・スティーブンス氏は説きます。 小売業界がパンデミックに打ち勝ち、さらに繁栄するための最新情報と戦略、そしてリーダーシップについて語った、次世代小売のロードマップです。 【本書で展開される10の「リテールタイプと消費者の問いかけ」】 1「ストーリーテラー」型→自分を奮い立たせてくれるブランドはどれ? 2「活動家」型→自分の価値観と一致するブランドはどれ? 3「流行仕掛け人」型→新しくてクールなものは、どこに行けば手に入る? 4「アーティスト」型→一番充実した体験が味わえるのはどこ? 5「透視能力者」型→自分のことを一番理解してくれているのは誰? 6「コンシェルジュ」型→最高水準のサービスはどこで受けられるの? 7「賢者」型→一番いい助言がもらえるのはどこ? 8「エンジニア」型→最高に作り込まれた商品はどこで手に入るの? 9「門番」型→必要な商品はどこで手に入るの? 10「背教者」型→この商品が欲しいけれど、もっと買いやすくしてくれるのは誰? 【著者紹介】 [著]ダグ・スティーブンス(Doug Stephens) 世界的に知られる小売コンサルタント。リテール・プロジェクト社の創業社長。人口動態、テクノロジー、経済、消費者動向、メディアなどにおけるメガトレンドを踏まえた未来予測は、ウォルマート、グーグル、セールスフォース、ジョンソン&ジョンソン、ホームデポ、ディズニー、BMW、インテルなどのグローバルブランドに影響を与えている。著書に『小売再生 リアル店舗はメディアになる』(プレジデント社)など。 [訳]斎藤 栄一郎(さいとう・えいいちろう) 翻訳家・ジャーナリスト。山梨県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。主な訳書に『ビッグデータの正体 情報の産業革命が世界のすべてを変える』『1日1つ、なしとげる! 米海軍特殊部隊SEALsの教え』『イーロン・マスク 未来を創る男』(以上、講談社)、『小売再生 リアル店舗はメディアになる』『センスメイキング』『イノセントマン ビリー・ジョエル100時間インタヴューズ』『TOOLS and WEAPONs テクノロジーの暴走を止めるのは誰か』(以上、プレジデント社)、『データ資本主義 ビッグデータがもたらす新しい経済』(NTT出版)などがある。 【目次抜粋】 序章 握手とハグが当たり前だった日々 第1章 “基礎疾患”のあるブランド 第2章 異世界へのタイムトンネル 第3章 食物連鎖の頂点に立つ怪物たち 第4章 大きな獲物が狙われている 第5章 新しい時代を生き抜くリテールタイプ 第6章 小売りの技を極める 第7章 ショッピングモールの再生 第8章 小売の未来
-
-本書は、山田コンサルティンググループがコンサルティングの実務を通じて得られた知見に基づき、医療・介護業界にかかわる人を対象として、経営課題へのアプローチを解説したテキストです。医療・介護業界向けの支援実績を豊富に有するコンサルタントが日々の案件実務を通じて得られた経営課題に関するアプローチを解説しています。本書で解説しているテーマは、多くの医療・介護事業者に共通する経営課題であり、多くの経営者や事務長、財務・経理の責任者のご参考になるテーマを取り上げました。さらに、医療・介護業界と取引しているが業界のことがよくわかっていない方、新規に取引することになり業界のことを理解する必要がある方等、これから業界のことを学ぶ方を対象とした基礎的な論点を解説した項目も設けています。Q&A形式ですので興味があるテーマからご覧いただけます。 医療・介護業界は一般になじみの少ない専門用語が多くあふれています。また、医療・介護事業者を取り巻く制度環境は複雑であり、加えて、定期的に改正・改定があります。更に、医師をはじめとして、患者の生命に直結するサービスであることによる職業倫理という事業特性もあります。そこで、山田コンサルティンググループでは、業界に精通したコンサルタントが必要と考え、医療・介護業界向けの専門組織を立ち上げました。事業部創設当時の自民党政権下において、診療報酬改定は大幅なマイナス改定が続いていました。多くの病院は経営悪化の一途であり、事業再生や業務改善等の相談が多く寄せられました。それから15年間、医療・介護業界に特化して多くのクライアントへのご支援を続けてきました。これらの実務から得られた経験が、少しでも皆様のご参考になれば幸いです。
-
3.5◎日本の人事部「HRアワード2020」書籍部門 最優秀賞受賞!『他社と働く』 著者の最新刊。 ◎今、最も注目されている学者が、職場のモヤモヤを解消する、新しい対話の方法「2 on 2」を初公開。 ◎本書の効能はズバリ「7つ」ある。★1.自分も相手も見えている風景が変わる★2.自分でしょいこんでいた荷物をおろす方法がわかる★3.人の力を借りられるようになる★4.ひとりで悩まなくなる★5.4人1組の「2 on 2」で言語化できないモヤモヤの正体が現れる★6.上司と部下が協力し合える★7.組織が変わる ◎ターゲット読者は自分で仕事を抱え込んで苦しんでいるミドル・マネージャー。『他社と働く』 を読んだ多数の読者から「考え方はとても腑に落ちた。だが現場でどう実践したらいいかわかりらない」という声があった。そこで本書は現場で具体的にどんな手順でどう進めたらいいか。やってはいけない「6つの罠」や体験者・共同開発者の声を交えながら、現場で使える本となる。・職場に活気がない・会議で発言が出てこない・職場ギスギスしている・仕事のミスが多い・忙しいのに数字が上がらない・病欠が増えている・離職者が多い……。著者はこれらの現象を「組織の慢性疾患」と呼び、セルフケアの方法を紹介する。業績不振、新規事業低迷、企業再生等はすぐに対策がとられる。だが、組織の慢性疾患は放置され、少しずつ組織を蝕んでいく。著者は、行き詰まりを見せる階層型組織に代わる新しいイノベーティブな組織の形を研究する異色の経営学者。専門は経営戦略論、組織論。カウンセリングや心理療法のケアの手法を経営学に取り入れている第一人者。文体も何か読者に寄り添いつつ、語りかけるような口調なので、妙な説得力があるのが特徴。特に、言語化できないモヤモヤの正体が現れる衝撃の“反転の問いかけ”は、こんな方法があったのかと非常に面白く使える内容になっている。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■新版によせて 2018年12月に初版を発行してから、2 年以上経過しましたが、その間様々な環境変化がありました。 最初にあげられるのは、2020年1 月に日本で初めて感染が確認された新型コロナウィルスにより、日常生活、会社での勤務形態、経済活動が一変したことです。そして、リモートワークによって採用の仕方も評価も育成も働き方も全て変わってきました。これらニューノーマルを見据えた人財マネジメント改革の重要性を改めて認識する必要があります。 2019年8月、米企業の規範である「株主第一主義」の修正が行われ、ステークホルダー主義の経営が宣言されました。このことはわが国でもESG やSDGs への取り組みを一層促進させるきっかけになっています。 2021年3月施行の改正会社法・同施行規則では、役員報酬決定方針の開示が拡充されています。 そしてデジタルトランスフォーメーションDX も話題を呼びました。DX は、IT を活用したビジネスモデルの変革や、それに伴う業務、組織などの変革をいい、デジタル化によりあらゆるものがネットにつながるIOT やAI(人工知能)を使って生産性の向上を目指すことでもあります。一方で、経済のデジタル化は、模倣が容易になることでもあります。このような時代では、模倣や破壊されないために、他社がなしえない独自性の追求・確立が重要課題となります。 以上をふまえ、新版では、下記の項目を追加しました。 ・独自性の追求・確立 ・ニューノーマルを見据えた人財マネジメント改革 ・デジタルトランスフォーメーションDX の本書における取扱い ・ニューノーマル下の経営 ・ステークホルダー主義 ・ESG
-
4.3組織・チームを真の効率化へと 導くにはどうすればよいか? 全14か国で翻訳された世界的ベストセラー、待望の邦訳! > 本書では「フロー効率」という画期的な視点を導入することで、 組織とチームを圧倒的に「リーン」にする方法を紹介している。 多くの経営者やマネジメントがリーンのことを コスト削減だと考えているが、それは誤っている。 顧客志向になることが、リーンの本筋であり、 真の効率化へと至る結論である。 デジタルトランスフォーメーションに代表されるような 組織・チームの効率化が求められる中、 本書はその王道を歩む方法を提示している。 とくに ・新規事業開発担当者 ・既存事業を立て直したいマネージャー ・DX担当者 ・スタートアップのリーダー ・組織の新陳代謝を促したい経営者 にとっては組織で実践できるリーンのエッセンスが 凝縮された、目から鱗の必読の一冊。 【目次】 プロローグ 五〇〇倍のスピード 第一章 リソース重視から顧客重視へ 第二章 フロー効率を左右するプロセス 第三章 プロセスにフローをもたらす要素 第四章 効率性のパラドックス 第五章 むかしむかし……トヨタは顧客重視を通じてどのようにナンバーワンになることができたのか 第六章 西の荒野へようこそ……君のことはリーンと呼ぼう 第七章 リーンではないもの 第八章 効率性のマトリックス 第九章 これがリーンだ! 第一〇章 リーンオペレーション戦略の実現 第一一章 あなたはリーン?釣り方を学ぼう! エピローグ 無駄のない装いを! ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-
-
-
-
4.0余計なプライドを捨て「キャッシュ創出マシーン」になりきれるか? 経営をお金の視点から見ることではじめてわかる企業価値創造のプロセス。 本書は「キャッシュ創出マシーン」への変身プロセスを「経営者こそ投資家である」という視点に立ち、特にキャピタルアロケーションにフォーカスを当て、国内外の事例とともに解説する。キャピタルアロケーションは、バフェット氏がその重要性を説いた影響もあり、一部関係者の間では既に関心が高い。日本でもコーポレートガバナンスコードに関連する記述があり、経営資源としてのお金の配分(=キャピタルアロケーション)への関心も高まりつつある。また、事業ポートフォリオの見直しによるキャピタルアロケーションの変更への投資家の関心も高まり、アクティビストを中心に、再投資ではなく資本還元へのキャピタルアロケーションの引き上げへの要求も増えている。ファイナンス研究の第一人者が、ESGを含む最新動向にまで目配りをしながら、そうした状況を踏まえ解説する最新の実践の書である。
-
-クリエイティビティを阻害せずにベクトルを合わせる! 異能集団をまとめ収益と社会性を両立させてきたリーダーに学ぶ組織運営の真髄 「リーダーシップとは、答えを与えることではなく、その答えを導き出すための問いを考えることだ」 「お金がなければ文化も社会貢献もない!」 「チェリストとしての自分は、オーケストラのなかで日々同じことの繰り返しだった。しかしビジネスは今日と明日で状況が変わり、違うことをしなければならない。なんとクリエイティブな世界だ!と申し上げたい」 本書は、我が儘なアーチストたちで構成される世界的な芸術・文化的組織を率い、市民の支持を得ると同時に収益も上げてきたリーダーが、その実践するマネジメント哲学、リーダーシップのあり方を幅広く語るもの。カーネギーホールのエグゼクティブ・ディレクター兼芸術担当として組織の運営に携わるクライブ・ギリンソンに、Arch Street Pressの編集主幹ロバート・リムがインタビューをする形式となっています。 ここで語られる内容は、決して文化の話でもなければ、クラシック音楽の話でもない。組織運営を考える時、またリーダーシップを考える上で、非常に大きな示唆に飛んだものになっている。アメリカでは、ビジネスのクラスのテキストとして採用されている大学が複数ある。個々のクリエイティビティを殺すことなくいかに全体を一つの方向にまとめ上げるか?よき企業市民としての組織、つまり社会から支持される組織のあり方とは?など多くの企業が直面する課題に論及しており、マネジメントにとって大いに参考になる内容が満載である。
-
4.2
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●日本で働く外国人材が 日本のビジネスコミュニケーションの特徴を理解したいときに ●明日から外国人材と一緒に働くことになったら…? 日本人の「あるある」お悩みをもとに、本質的な相互理解へ 【おもな特徴】 ・12のリアルなケース(事例)を掲載 実際の職場で起きるリアルなトラブルや悩みから学び合うことで、 実践的なコミュニケーションスキルの獲得につなげられる。 ケースの前後には「チェックポイント」や「ウォーミングアップ」「深掘りしてみよう」などを設け、読者のスムーズな学習と、事例の背景まで含めた本質的な理解の手助けとなるよう工夫した。 ・「新しい働き方」にも対応 ケースは、「在宅勤務」「オンライン会議」といった、 これからの時代に不可欠な「新しい働き方」にも対応できる。 ・「タスク」で多様な価値観・考え方に気付ける 他者の視点に立った「タスク(ワーク)」を通して多様な考え方に気付き、 本質的な相互理解へ! ■目次 テーマ1 業務中のコンフリクト CASE 1 せっかく日本語を勉強したのに CASE 2 それって指示ですか CASE 3 表情が見えない会議なんて CASE 4 業務の効率化につながっていますか CASE 5 ビジネスメールには必要ないのですか CASE 6 理屈って何を書けばいいんですか CASE 7 どうして仕事が進まないの テーマ2 社内で戸惑うルールや文化の違い CASE 8 家賃は教えてくれないのですか CASE 9 私のことを不幸だなんて CASE 10 飲みニケーションに行きたいのに CASE 11 個人評価を見せ合いますか CASE 12 わたしが信用されないのは
-
-本書の売りは、一言で言えば、「一粒で3つ美味しい」を実現することです。 一、独自性経営のエッセンスが短時間で理解できる 一、経営幹部に必要な「結果を残す会計力」が理解できる 一、Amazon、Apple、IKEAのビジネスモデルと利益の源泉が理解できる 1997年、ジェフ・ベゾスCEOは株式上場を果たしました。その時の株主への手紙は、今でも毎年の年次報告の末尾に添付され、「顧客への執着」と「長期志向」を柱にした揺るぎない経営方針・経営哲学が連綿と受け継がれています。これは毎日が「Day One」、初心忘れるべからず のAmazonの基本精神です。 1997年、スティーブ・ジョブズは倒産寸前のAppleに復帰しました。製品や販売チャネルの大胆なリストラを行い、量から質へ、「最高のもの」を「ジャストインタイム」で顧客に提供する体制へと、ビジネスモデルを大変革しました。この時、今日のAppleへの長期成長の礎が築かれました。 1999年、IKEAのCEOに就任したアンダッシュ・ダルヴィッグは、それまでのジェットコースターのようアップダウンの激しい成長過程を踏まえ、安定性と新しい方向性を示すために、「10年計画」を打ち立てました。この計画では、ビジネス理念と価値観をより具現化するために、「10年間で20%の値下げを実現する」という明確な目標が設定されました。今でもデザイン性に優れ機能的で品質の良い製品の値下げが続けられています。 以上が、本書で取り上げる独自性の代表的企業、Amazon、Apple、IKEAの象徴的イベントです。 20世紀が終わりかけ次世紀に向かうこの原点とも言えるべきイベントが起点となって、21世紀の今、その業界で圧倒的な存在感を誇り、飛躍的・持続的な成長を遂げています。 現代は、経済のデジタル化とグローバル化の時代です。簡単に模倣されてしまう時代であり、強みを磨き上げ独自性を確立して維持していかなければ生き残っていけない時代だと言えます。だからこそAmazon、Apple、IKEAという独自性の代表的な企業の事例を深く分析し、そこから得られる教訓を今後の経営に活かすことはとても重要です。 本書の最終的なゴールは、読者の皆様の企業が、強みを磨き上げ自社ならではの独自性を確立すること、そして、「結果を残す会計力」を活用して、持続的な売上・利益成長を実現する独自経営デルを確立することです。特に、経営参画される皆様には、新たな視点・ゼロベースでの視点で経営にあたることが期待されていますので、本書を通じて、自社の戦略・ビジネスモデルを検証し見直すきっかけにしていただきたいと思います。 本書を執筆することによって、少しでも会計士としての使命を果たすことができれば幸いです。
-
4.2●Netflixはどうやって190カ国で2億人を獲得できたのか? ●共同創業者が初めて明かすNetflixビジネスとカルチャーの真髄。 ■Netflixの「脱ルール」カルチャー *ルールが必要になる人材を雇わない *社員の意思決定を尊重する *不要な社内規定を全部捨てよ *承認プロセスは全廃していい *引き留めたくない社員は辞めさせる *社員の休暇日数は指定しない *上司を喜ばせようとするな *とことん率直に意見を言い合う ――新常態の働き方とマネジメントが凝縮
-
4.0「飛び道具トラップ」「激動期トラップ」「遠近歪曲トラップ」 経営を惑わす3つの「同時代性の罠」を回避せよ! 近過去の歴史を検証すれば、変わらない本質が浮かび上がる。 戦略思考と経営センスを磨く、「古くて新しい方法論」。 「ストーリーとしての競争戦略」の著者らの最新作! これまで多くの企業が、日本より先を行く米国などのビジネスモデルを輸入する「タイムマシン経営」に活路を見いだしてきた。だが、それで経営の本質を磨き、本当に強い企業になれるのだろうか。むしろ、大切なのは技術革新への対応など過去の経営判断を振り返り、今の経営に生かす「逆・タイムマシン経営」だ。 そんな問題意識から、日本を代表する競争戦略研究の第一人者、一橋ビジネススクールの楠木建教授と、社史研究家の杉浦泰氏が手を組んだ。経営判断を惑わす様々な罠(わな=トラップ)はどこに潜んでいるのか。様々な企業の経営判断を当時のメディアの流布していた言説などと共に分析することで、世間の風潮に流されない本物の価値判断力を養う教科書「逆・タイムマシン経営論」を提供する。 経営判断を惑わす罠には、AIやIoT(モノのインターネット)といった「飛び道具トラップ」、今こそ社会が激変する時代だという「激動期トラップ」、遠い世界が良く見え、自分がいる近くの世界が悪く見える「遠近歪曲トラップ」の3つがある。こうした「同時代性の罠」に陥らないために、何が大事なのか──。近過去の歴史を検証し、「新しい経営知」を得るための方法論を提示する。
-
4.2営業職員3万人が使用するタブレットを更新せよ! ビッグプロジェクトの全容を追体験しながら学べる 業務改革の新しい教科書! 本書は、住友生命で行われた営業職員が使用している3万台のタブレットを更新するビッグプロジェクトを通し、自律自走型プロジェクトとは何かを学べる新しいタイプのテキストです。 自分たちの仕事はどうあるべきで、それを支える営業端末はどう形作られるべきなのか。メンバーの関係は完全にフラットで、それぞれの担当が自分で考え周りを巻き込みながらも最後は自分で決める「進化する変革プロジェクト」として実行し、成功を収めた事例を紹介しています。 特徴的なのは、支援していたコンサルティング会社の社員と、支援を受けながらプロジェクトを進めた2人の社員が、それぞれの異なる立場から立体的に描いている点。 内部と外部の視点からプロジェクトをどう捉えていたのか、なぜこのような進め方をしたのか、そこにどんな悩みや決断があったのか。プロジェクトの状況を追体験しながら、組織の運営や、業務改革、システム構築のノウハウを学べます。
-
-情報銀行は2020年から本格的にはじまる! 業界・業種別! 情報銀行を利活用したビジネスや 情報銀行への事業参入手法がわかる! 【情報銀行とは】 情報銀行は、預かった個人情報を本人に代わって企業など第三者に提供する事業です。 利用者は、個人情報の利用を許諾しデータを提供することにより、ポイントやサービス提供などの便益を受け取れます。 欧米の基本理念を取り入れつつ、企業が個人情報を利活用しやすいように配慮して枠組みが作られた、日本独自のビジネスモデルです。 【本書の概要】 本書はこれから情報銀行を利活用したビジネスや情報銀行への事業参入を考えている方に向けて、 パーソナルデータ活用や情報銀行が求められている背景、 参入に必要な知識(情報銀行認定制度、利用されているテクノロジーや法令等)、 事例などについて、 各分野ごとに図解で解説した書籍です。 【本書の対象読者】 情報銀行のビジネスでの利活用もしくは事業参入を考えている企業のプロジェクトマネージャーや経営層 【参入が先行する5つの業界・分野】 ・観光・エンターテインメント ・ヘルスケア ・金融 ・人材サービス ・地域支援 【活用機会が多い7つの業界・分野】 ・医療サービス関連 ・流通関係 ・食品 ・マーケティング ・日用品 ・化粧品 ・交通インフラ 【著者プロフィール】 森田 弘昭 株式会社マイデータ・インテリジェンス取締役執行役員COO。 総務省、経済産業省「情報信託機能の認定スキームに関する検討会」委員、 「情報信託機能普及協議会」理事。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.3
-
-●メンタル不調社員の管理が急務に 2017年の労働安全調査によると、「現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスになっていると感じる事柄がある労働者」の割合は59.5%と、16年調査より3.8%増加。ここ5年ぐらい増加傾向が続いている。 一方で、精神障害の労災認定件数も増加傾向にあり、これを抑制するため、19年4月からは改正労働安全衛生法が、20年6月からはパワハラ防止関連法が、企業に対してメンタルヘルス対策の強化を求めている。 本書は、法律により、対策が急務になったメンタルヘルスについて、パワハラ防止関連法の具体的指針も踏まえて出版するものである。 ●メンタルヘルスの見分け方から対処法まで、産業医・弁護士・社労士が一体となって解説 実効性あるメンタルヘルス対策を進めるためには、まずは管理職層を含め、メンタル不調の疾病状況やその見分け方を確認しておくことが重要である。その上でメンタル不調の原因として、職場環境および労働者本人の個体側要因を把握し、原因ごとの対応検討が求められる。 さらに、今回の種々の法改正では、1過重労働防止、2ハラスメント防止、そして3個人の健康情報管理の適正化、を強く求めており、法改正内容を正確に把握した上で新たな実務対応策の立案が必要となる。 一方で、産業医の役割が拡大。自らが労働者に自分の業務を告知しなければならないほか、労働者ひとりひとりの健康状態を把握することも求められるようになり、権限と負担が増しているが、その具体的手法についても執筆する。 本書は上記問題に対し、産業保健実務に長く取り組み、これまで数多くの業績をあげてきた鈴木安名産業医、主に労働問題に取り組んできた峰隆之弁護士、そして日経文庫で執筆実績のある北岡大介社労士が、三位一体となって解説をする。
-
-
-
-近年、シェアリングエコノミーの高まりを背景として、日本国内でも「シェアオフィス」を筆頭に「コワーキングオフィス」「サービスオフィス」など、様々な形態のオフィスが登場しています。 本書は、長年オフィスビル開発やオフィス賃貸業を営む著者が、これらの新しい形態を「スモールオフィス」を総称し、各々の機能の違いや、使用例を解説。また一般の賃貸オフィスと比較しながら、コストや活用にあたってのメリット・デメリットを詳説。著者独自の調査による豊富な使用事例も紹介しています。 スモールオフィスは、「専用の執務室があるもの」と「執務スペースもシェアするもの」に大別され、その多くは駅から徒歩数分というアクセスの良い立地にあります。一般の賃貸オフィスと比較して、最大のメリットは初期費用の少なさと、入居・退去が楽であること。 当初はスタートアップ企業や独立したての士業のビジネスパーソンなどに支持されてきましたが、ここ数年で大手企業もその使い勝手の良さに着目し、プロジェクトオフィスやサテライトオフィスとして、また地方企業が大都市圏へ進出する際にも活用されています。 オフィスの大きな特長として、エントランスや受付、会議室などが共用化されています。会議室や打ち合わせスペースは「使った分だけ」のコストで済み、スペースの有効活用につながります。また複数企業が同じフロアに入居しており、会社を越えた交流会も頻繁に行われているため、オフィス内で新たなビジネスが生まれたり、取引先を紹介し合うなど、一般の賃貸オフィスにはない「コミュニティの形成場所」としても注目されています。 企業の経営者や経営戦略、経営企画、総務に携わるビジネスパーソンにとって、示唆に富む内容となっています。
-
4.0amazon、Netflix、ティンバーランド、アップル、ナイキ、鴻海シャープ、ファイザー、バイオジェン、ハイネケン、デル、IBM、HP・・・ 最先端企業の財務データからファイナンスの論理を学ぶ 2020年代の基礎ファイナンス教科書 ウォール街に多大な影響を与える人気教授による ハーバード・ビジネス・スクール・オンライン講座初のテキスト化! 本書は、ハーバード・ビジネス・スクールのオンライン講義(MOOC)をもとに、つくられたファイナンスの教科書です。(https://online.hbs.edu/courses/leading-with-finance/) ハーバード・ビジネス・スクールの人気教授が長年温めたアイデアをもとに書かれた企画ですが、本書はMBAのための分厚く難解な専門書ではありません。MBAのようなファイナンスのプロを目指す人のためのというよりは、入門者でもなんとか読める内容になっているところが特徴といえます。 アマゾン、ネットフリックス、アップル、ナイキなどをはじめ、読者が関心を持てる有名企業のファイナンスの事例が豊富になっているところが最大の魅力です(たいていの教科書の財務データは、架空の起業のものになっています)。各社の折々の意思決定の動きと、実際の財務データを検討し、そこから見えてくるファイナンスの論理を読み解いていきます。 関心をもって読み進めていくうちに、ファイナンスの基本的知識が身につく、というのが著者の狙いで、横開きに大小100点近いチャートやコラムがちりばめられ、本文は比較的シンプルなので、わかりやすく読み進められます。
-
3.5本書を推薦します! 魚谷雅彦氏(資生堂社長) 伊藤邦雄氏(一橋大学経営管理研究科特任教授) 『PEOPLE FIRST』こそ、日本企業がグローバル市場で勝つための戦略だ。 ――魚谷雅彦氏(資生堂社長) 21世紀に勝ち残る条件は戦略ではなく人材経営だ。CEOとCFOとCHROの協働を唱えた衝撃の書。 ――伊藤邦雄氏(一橋大学経営管理研究科特任教授) ★ ★ ★ CEOがなすべき仕事は 人材の総責任者として 会社の命運を握る〈2%人材〉の ポテンシャルを引き出し 人材ファースト企業への移行を 完遂することだ! 今日の経営幹部の大半は、人材こそが競争優位を生みだすことを理解しているが、企業が使っている人事制度は一世代前の遺産である。それらは、将来が予測可能な環境、伝統的な仕事のやり方、レポートラインと部門で人を管理する組織のために設計されたものである。近年、仕事も組織もどんどん流動的になるにつれ、事業戦略は予測可能な向こう数年間の計画を練ることではなく、絶えず変わりつづける環境のなかで新たな機会を察知し獲得することを意味するようになった――企業は新たな手法で人材を活用しなければならない。人材が戦略を主導しなければならないのだ。 ★ ★ ★ 世界的ビジネス・アドバイザー、マッキンゼー・アンド・カンパニー前グローバル・マネージング・パートナー、コーン・フェリー副会長の3人がタッグを組んだ21世紀企業のための人材戦略ブック。
-
3.5「人事のあり方」を刷新しようとする動きが本格的に加速し始めた。人、組織、企業そして社会を変えていく人事とは。 世界で勝つ企業の人事になるために、どのようなコンセプトと戦略を持ち、どのような組織体制やシステムでサービスを提供していくべきなのだろうか。そして、そうしたこれからの世界と時代に必要とされる人事にどの様に生まれ変わることができるのか。 人事そのものを変革していくための考え方とアプローチを図表などを多く用いて丁寧に解説した、これまでにない一冊。 <本書で取り扱う問いの例> SDGsやESGといった社会からの要請の中で人事に求められるものは? 現在の人事がオペレーション業務に追われ、戦略貢献出来ない理由は? 真の意味で経営に貢献する人事とは? イノベーションやデジタル化の領域で人事が貢献すべきことは? これから人事部員はどの様に育てていくべきか? など <本書の構成> 〇第1章 人事が影響を与える“3つの領域” 〇第2章 人事の実態と陥りがちな“4つの症状” 〇第3章 これからの世界で勝つ“最強の人事”とは 〇第4章 最強の人事に変革するための“6つのステップ” 〇第5章 最強人事を担う“人事プロフェッショナル”
-
4.5世界中の最先端企業を知り尽くす男が、「ニセのイノベーション」にブチ切れた! 『Wired UK』創刊編集長が、6大陸、10か国、世界中の「真のイノベーション」を総力取材。「シリコンバレー後」の16の新戦略を全網羅!
-
-
-
-
-
3.5【内容紹介】 LEAP〈跳躍〉かFALL〈凋落〉か。それを決めるのはテクノロジーではなくストラテジーだ! LEAPは絶え間ない市場の変化と、ほぼ時間差のない競合からの追い上げという過酷な環境のなかで企業が繁栄し続けるための戦略と実践の書。どんなテクノロジーもイノベーションも、すぐに真似をされ、コモディティ化を免れない。消耗戦を避けるには、成功体験をゼロリセットし、追い上げてくる競合と異次元のレベルにLEAP〈跳躍〉する必要がある。それができる企業には、共通する5つの基本原則がある。 「これらの原則はすべてのビジネスリーダーの 心を揺さぶるだろう」(クレイトン・クリステンセン) 【著者紹介】 [著]ハワード・ユー(Howard Yu) 世界トップクラスのビジネススクールIMD(スイス・ローザンヌ)教授。同スクールのエグゼクティブ向けコース、AMP(Advanced Management Program )ディレクター。2011年にハーバード・ビジネス・スクールにて博士号を取得。専門は戦略とイノベーション。洞察に富むケーススタディーには定評がある。 [訳]東方雅美 (Masami Toho) 翻訳者、ライター。 慶應義塾大学法学部卒業。米バブソン大学経営大学院修士課程修了(MBA)。日経BPやグロービスなどでの勤務を経て独立。 【目次抜粋】 イントロダクション 競争の仕組み 第1部 歴史から学ぶ 第1章 「日米ピアノ戦争」の教訓――強みが弱みに変わるとき 第2章 新たな知識分野へ跳躍する――準備できている者が生き残る 第3章 セルフ・カニバリゼーションを恐れるな――どうせ滅ぼされるのなら… 第2部 未来を見据える 第4章 ユビキタスな環境を味方につける――一人の天才から集団の知恵へ 第5章 人工知能を味方につける――直感からアルゴリズムへ 第6章 マネジメントにクリエイティビティを――ビッグデータから人間としての強みへ 第3部 いまやるべきこと 第7章 知識を行動に変えるために エピローグ 謝辞
-
4.2●本質シリーズの最終巻 圧倒的に不利な条件から勝利を導き出した独ソ戦のスターリン、英独戦のチャーチル、ベトナム戦争のホー・チ・ミン、対イラク戦圧勝もつかの間、非正規戦という泥沼の打破を迫られた米国――。 本書は、日本陸軍の敗北のメカニズムを組織論の切り口から解明した『失敗の本質』(中公文庫)、海外の戦史を題材に成功の本質を解明した『戦略の本質』、国家指導者に焦点を当てた『国家経営の本質』につづく本質シリーズの最終巻。勝利を実現するメカニズムの解明は、『失敗の本質』とは裏表の関係となります。また『戦略の本質』は逆転を生み出した要因を現場の指揮官レベルで解明しましたが、本書は国家の指導者レベルとリンクさせて、機動戦と消耗戦を臨機応変に使い分ける知略戦略こそが勝利を生み出したというストーリーで解説します。 知略戦略とは、「知略=知的機動力」で賢く戦う哲学であり、過去-現在-未来の時間軸で、組織メンバーの共感を得、一丸とさせる共通善のために「何を守り、何を変革するか」の動的平衡を追い求めながら、行動し続ける戦い方を指す。これを実現できたリーダーが、本書で取り上げる、スターリン、チャーチル、ホー・チ・ミンです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「多くの企業が、ESGとSDGsを別箇の課題として捉えています。 しかし、両方をうまく活かせば、成功するビジネスを開拓できるのです」 ESGとSDGsを正しく理解し、社会と自社の両方にとって良い仕組みを構築することが、これからの時代に求められる会社のかたちです。本書では、専門用語に触れたことのない人から目の前の課題として取り組む人まで使えるものを目指し、用語解説から実践例まで網羅しました。経営者、企業担当者必読の1冊です。 第1章 基礎編その1 登場する言葉を理解しよう 第2章 基礎編その2 企業に求められるESG/SDGs対応とは何か 第3章 実践編その1 ESG/SDGs対応の好事例を見てみよう 第4章 実践編その2 あなたの会社でESG/SDGs経営をするには
-
4.0新元号「令和」がスタートし、2020年という節目は目前、 足元の業績も好調ないまこそ、次の成長に向けての長期ビジョンをつくろう! という経営者は多い。 とはいえ、だいたいは社長およびその周辺だけが乗り気になっており、 経営企画や現場は当惑する、というケースも少なくないようだ。 だいたい、こんなパターンだ。 ―10年後の話なんて、どこから手をつけていいかわからない ―そもそも、そのころどんなテクノロジーが出てきているかもわからないし、予想するだけ時間の無駄だ ―この忙しい時期に、悠長にそんなものをつくっているヒマはない ―2010年ごろもそういうのをつくったが、役に立っていないし、みんなもう覚えてないよ ……などなど。 いずれも、ごもっともである。 しかし、では未来のことを考えなくてもいいかと問われると、 もちろんその必要性はみんなが認識している。 本書は、意味のある「中長期ビジョン」を作り上げ、 実行にまで落とし込んでいく手法を解説するものである。 ◆本書の特徴。 -実際に企業の未来ビジョン策定を手伝ってきた著者が、具体的な事例をもとに展開する -陥りやすいワナ、ありがちな失敗をとりあげ、それらを防ぐ方法を紹介する ―線形予測(少子高齢化、デジタル化など、誰もが予測できる未来)と 非線形予測(非連続的で、業界構造を破壊してしまうインパクトを持つ変化)のかけ算で、 自らつくるべき未来を描く「未来洞察」の手法を説明 ―実践的な9つのステップを解説。長期ビジョン作成から現場に浸透させ、 実行計画にまで落とし込む段階までをフォローする。
-
3.0VRブームはこの本から始まった! 進化を続ける「もうひとつの現実」を読み解く 【豪華鼎談収録】 廣瀬通孝(東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター長) GOROman(株式会社エクシヴィ代表取締役社長) 【内容紹介】 Google、Apple、Facebook、Amazonなど、 名だたる企業がVRに参入している。 VRが普及した未来の世界はどうなるのだろうか。 実用化が進むVRだが、その多くの コンセプトは研究初期と変わっていない。 当時を振り返りながら今後の発展を見据えることで、 「VRが本当に目指していること」を理解できるだろう。 本書では、VRを取り巻く技術革新の系譜をまとめ、 大きな全体像の中にVRを位置づけることで、 テクノロジーとしての文脈を明確にする。 日本のVR研究者、開発者、ビジネス関係者に 読み継がれてきた史上初のVRの本『人工現実感の世界』(工業調査会)。 大幅な加筆を行い、待望の再版。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0なぜ日本企業は不当に低く評価されているのか? 「見えない資産」を活かせ! 上場企業(金融除く)のバランスシートには依然として200兆円近い広義の現金(現金+有価証券)が積み上がり、上場企業の1割以上で広義の現金の方が時価総額より大きい。アベノミクス前後で株価もROEもほぼ倍増したが、企業価値の創造は十分ではない。一方、ESG(環境、社会、統治)ブームの中、ROEを忌み嫌う一部の経営者も非財務情報のアピールには熱心であるが、日本企業のPBR(株価純資産倍率)はほぼ1倍で推移しており、非財務資本の価値が付加価値として市場から認識されていない。 その背景には、日本市場の長期的低迷、「資本の価値」の低評価、企業と投資家の認識ギャップ、低いROEとコーポレートガバナンスの問題等があり、歴史的文化的要因も含めてきわめて根が深い。近年アベノミクスのガバナンス改革、「伊藤レポート」などでROEは向上してきたが、いまだ道半ばであり、その質が問われている。皮相的なROE経営ではなく長期的持続的な価値創造に貢献することが重要である。 わが国企業には資本コストやROEが十分に理解されていないのではないだろうか。あるいは当局のリードに盲目的に追従して皮相的なROE経営や横並びの配当政策に陥っていないだろうか。一部の投資家のショートターミズムも悪影響を及ぼしてはいないだろうか。 そして究極的には、企業価値は非財務資本から財務資本に転換されて生成されると考えられるが、いかにしてそれを具現化して資本市場の理解を得ていくのか。潜在的には非財務資本の価値がきわめて高いはずの日本企業が過小評価される事態に陥っている現状を打破し、コーポレートガバナンスや財務リテラシー、ESGとそのIR(説明責任の履行)を改善することで、大きな企業価値の向上が図れるのではないか。ESGが救世主になる可能性があるのではないだろうか。 こうした思いでわれわれ3人はそれぞれ啓蒙活動をしてきたが、本書は3人の長年の日本企業の企業価値向上への思いを伝える集大成と言って良い。 ――「はじめに」より抜粋
-
-
-
-
-
3.8不確実性の高いビジネス環境に“計画”はいらない! 世界最強組織のアメリカ海兵隊が行動の基本原則とするOODAループが、 いまアメリカの優良企業に広がっている。 OODAループとは何か? PDCAサイクルと何が違うのか? OODAループの提唱者であるジョン・ボイドの愛弟子である著者が、 ビジネスを事例にOODAループを解説した古典的名著、待望の翻訳! *** ◆OODAループとは? 観察→情勢判断→意思決定→行動という4つのフェーズを サイクルではなく、ループさせることで、 目の前で起こっている環境に合わせた判断を現場レベルで下し、 組織で目的を達成するための意思決定スキルです。 ◆AI時代に求められるスキル! ここ数年、急速に発展している、 AI、IOT、ビックデータ、ソーシャルメディアという流れのなかで、 リアルタイムにデータを収集し、即座に判断して行動に移すという OODAループが競争優位を築くための鍵になります。 ◆勝つべくして勝つ組織に変わる! OODAループを高速で回すためには、組織文化が基礎となります。 チームメンバーが同じゴールを目指す組織が共通して持つ組織文化です。 ・相互信頼を醸成している ・直観的能力を活用している ・リーダーシップ契約を実行している ・焦点と方向性を与えている OODAループを取り入れることで、 この組織文化を生み出すことにつながります。 ◆不確実性の高い環境で活躍する変革型リーダーになれる! OODAループは変革を求めるリーダーに必須のスキルです。 変革型リーダーは、目標達成のために権限を現場に委譲します。 ◆日本語版オリジナル! 充実した訳者解説!
-
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5キッシンジャーの「戦略的交渉術」を徹底分析した初の本 「世界最高のネゴシエーターは誰か?」 この質問を1375大学の国際関係学に携わる1615人の学者にしたところ、最も多くの支持を集めたのがヘンリー・キッシンジャーでした。 辛口の作家のウォルター・アイザックソンでさえ、キッシンジャーを「20世紀で最も重要なアメリカの交渉者」と評価しています。 ネゴシエーターとしてのキッシンジャーの輝かしい実績は、誰も否定できません。東西冷戦下、世界が憎悪に満ちあふれ、一触即発だった時代、 キッシンジャーは中国、中東、ソビエトと、一見不可能に思えるような交渉をいくつもまとめてきました。 90歳代の今でも、キッシンジャーは外交の重鎮として活躍し、バラク・オバマからドナルド・トランプ、ウラジーミル・プーチン、アンゲラ・メルケル、習近平まで、 多岐にわたる世界の指導者から意見を求められています。 キッシンジャーがどんな活動をしてきたかは自身の伝記や他の研究者・作家が、これまで数々の作品を世に送り出しています。 ところが驚くべきことに、キッシンジャーの交渉術に関しては、これまで詳しく分析されてきませんでした。 著者3人は、ハーバード・ビジネススクール、ハーバード・ケネディスクール、ハーバード・ロースクールの教授で、交渉の専門家・研究者。 ハーバードを代表する三つの大学院の英知を結集して、キッシンジャーの交渉を徹底分析し、エッセンスを抽出したのが本書です。
-
-
-
-介護業界・障害福祉業界で大注目「新しい仕組み」! 福祉には「介護保険優先」の原則があります。 障害を持つ方が65歳になると、介護保険の被保険者となって 使い慣れた障害福祉サービス事業所が利用できなくなる、 というケースがありました。 しかし、2018年4月の介護保険法と障害者総合支援法、 両改正により「共生型サービス」が新設! 介護保険、障害福祉いずれかの指定を受けている事業所は 制度の枠を超えて子供から高齢者まで同じ空間で過ごす 「共生型のサービス」を提供しやすい仕組みが導入されました。 本書は、この新しい「共生型サービス」について、 制度の仕組みの概要や、先行して行われているサービスの事例紹介、 施設開設方法や運営のポイントなどを解説します。 共生型サービスについて考え始めたとき、 最初に読んでいただきたい本です! ■■■読者対象は…■■■ ・共生型サービスの概要を知りたい方 ・小規模の共生型サービスの立ち上げを考えている方 ・介護業界や障害者福祉業界で働いていて、 将来的に起業にも興味をお持ちの方 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.4数字のウラに隠された、驚くべき人間ドラマ。 誰にも書けなかった 「会計エンタテインメント」爆誕! 【本書の特徴】 その1 ダ・ヴィンチ、レンブラント、スティーブンソン、フォード、 ケネディ、エジソン、マッキンゼー、プレスリー、ビートルズ ……意外な「有名人」たちが続々登場! その2 冒険、成功、対立、陰謀、裏切り、愛情、喜びと悲しみ、 栄光と挫折、芸術、発明、起業と買収 ……波乱万丈、たくさんの「知られざる物語」が展開します その3 簿記、決算書、財務会計、管理会計、ファイナンス、IFRS ……物語を楽しく読み進めるだけで、これらの仕組みが驚くほどよくわかります その4 イラストと写真、ひと目でわかるイメージ図が満載。 会計の本なのに、細かい数字はいっさい出てきません! 「私はこれまで数々のビジネススクールや企業研修で 会計分野の講師を務めてきました。 会計を『大局的に・楽しく』学んでもらうのはとても難しい作業ですが、 講義で『歴史』をもちいる手法はかなり効果的でした。 会計ルールの誕生エピソードや人物秘話を少々大げさな講談調で語ると、 受講者たちが身を乗り出してきます。 本書はそんな経験をもとにしています。 皆さんにも『好奇心とともに会計を理解する』経験をしてもらえれば 嬉しいです。」 ──「旅のはじめに」より 【「9つの革命」で全体像がわかる】 第1部 簿記と会社の誕生 「3枚の絵画」 15世紀イタリアから17世紀オランダへ 銀行革命/簿記革命/会社革命 第2部 財務会計の歴史 「3つの発明」 19世紀イギリスから20世紀アメリカ、21世紀グローバルへ 利益革命/投資家革命/国際革命 第3部 管理会計とファイナンス 「3つの名曲」 19世紀から21世紀・アメリカ 標準革命/管理革命/価値革命
-
5.0
-
3.6これからは、想像力を超えた「構想力」へ 不正相次ぐ大企業、掛け声だけの働き方改革、かみ合わないデジタル化… 日本の問題は、想像力の欠如に起因する構想力の欠乏にある。 これからの時代、目先の課題より 世界的な視野で社会全体の在り方を見据え、 方向性を考えるべきだ-- 野中郁次郎氏、紺野登氏が贈る新世代へのメッセージ。 「この本は知識創造理論を基礎にして、いかに構想力を「次代の知力」として 身に付けられるか。その方法論がテーマです。 構想力を高めるヒントやメソッド、儲け方などについて書かれた ノウハウ本ではありません。構想事例(ケース)集でもありません。 それらを期待する読者をがっかりさせるかもしれません。 経営の世界だけでなく、社会的活動や研究活動など何らかの構想や 構想力を求められる読者も想定しています。本書が構想力について 関心を持ち、実践していくための「知的資源」となれば幸いです。」 (「はじめに」より)
-
3.31958年に発表された本書は、終身雇用・年功序列・企業内労働組合の三本柱を軸とする「日本的経営」の特徴や利点を欧米に初めて紹介し、その後の海外の日本研究者にとってバイブル的存在となった。また、本文中のLifetime Commitmentの訳語として、「終身雇用」という言葉が初めて用いられたことでも知られている。日本の企業経営を考えるうえで基本文献となる名著、待望の復刊。
-
4.3『星野リゾートの教科書』で紹介された、星野佳路社長が会社経営を学んだバイブル 「コモディティ化と資源の有限性という企業の課題に対してわかりやすいアプローチを提案しており、“教科書”通りに試してみる価値がある」(星野佳路) マーケティングの神様・コトラーも推薦し、多くの優良企業が採用する実践的経営理論 ファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略とは、あらゆるビジネスに共通する5つの要素―価格・商品・アクセス・サービス・経験価値―から自社を見つめ直し、市場において独自のポジションを築く戦略です。 この戦略では、5つのうち1つで市場支配を、別の1つで差別化を、残り3つで業界水準を達成することが理想とされています。
-
4.5企業の情報システム担当者(責任者)、経営者向けのIT活用の最新実務書。「デジタル時代」に欠かせないIT戦略、マネジメント手法などを見開き2ページの図解で実践的かつ体系的に解説しています。 2000年版、2005年版、2009年版、2012年版に続くシリーズ5冊目で、デジタル化への対応を中心に内容を大幅に刷新しました。IT実務の担当者がデスクに常備しておきたい1冊です。
-
4.0
-
-
-
4.4自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ 稀代の起業家「江副浩正の仕事と生涯」正伝 江副浩正の名前は、一般にはリクルート事件と併せて語られることが多い。ロッキード事件にも比肩する一大事件の主人公として昭和史に、そして人々の記憶に深く刻まれることになった。この鮮烈な記憶が、起業家としての江副浩正の実像を覆い隠しているのかもしれない。いまだに、強烈な逆光によって江副浩正の正体は眩まされ、「東大が生んだ戦後最大の起業家」「財界のあばれ馬」と讃えられた江副の凄みを本当に理解する者は数少ない。 1989年、リクルート事件で江副は会長職を退任する。その3年後にはリクルート株を売却、完全にリクルートを離れた。それ以来、裁判報道を例外として、江副の名前はマスコミから消えた。2013年2月8日享年76歳で亡くなるその日まで、江副が何を考えどう生きたのか、それを知る人はほとんどいない。実は、彼はその死の日まで、事業での再びの成功を願いもがいていた。新たな目標を定め、組織をつくり、果敢に挑んでいたのである。起業家の血はたぎり続けていたのだ。 その、江副浩正の実像を明らかにすることが本書の目的である。彼だけが見ていた世界、目指したもの、そこに挑む彼の思考と行動。その中に、私たちを鼓舞し、思考と行動に駆り立てる何かが準備されていると信じるからである。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 デザインがブランドとビジネスを強くする。 デザインを原動力にしてブランド価値を上げ、躍進するマツダ 今なお進化を続ける同社のブランド戦略の全容に迫る 「デザインがブランドを、会社を変える」――マツダのブランド戦略が加速している。 デザインをテコにしてブランド価値を上げたい、会社を変えたいと考える企業は多いが、それは容易ではない。デザインをどうレベルアップさせればよいのか。社内の意識改革をどう進めるべきかなど、様々な課題がある。 マツダはなぜ変わることができたのか。 本書では、マツダのデザインに対するこだわりが次第に他部門まで伝播していく様子を徹底取材。これまでの進化の過程をたどりながら、今なお進化を続けるマツダのブランド戦略の全容に迫る。 巻末には「K360」から「コスモスポーツ」、そして「ロードスター」まで マツダの傑作を一挙に振り返る「マツダデザインヒストリー」を収録。
-
4.0リーン・スタートアップの次の段階である「成長」に向けての6つのステップを詳述した経営戦略の解説書です。 ベストセラー『リーン・スタートアップ』の著者エリック・リースがシリーズ・エディターをつとめたオライリーの「The Lean Series」第1弾『Running LEAN』の著者による続編です。 エリック・リースは本書の推薦に当たり、「関心ある企業に組み込むための実践的なアプローチ」と評しています。120点近い2色刷の図によって、理解しやすい図解の構成になっています。 本書の6ステップを、著者はGO-LEAN(Goal→Observe and Orient→Learn, Leverage, or Lift→Experiment→Analyze→Next Actions)[目標→観察と方向付け→学習・利用・強化→実験→分析→次のアクション]と名づけています。 本書では、うまく成長できないのは「局所最適化の罠」であると位置づけ、ゴールドラットの制約理論を引用しながら、全体最適化の方向へと読者を導きます。 また、本書では拡大の規模の目安となる「10倍ルール」を設定し、ステージごとの目標値を定めています。これがもう1つの新しいツールとなる「トラクションモデル」です。 これらのツールなどを使い、リーンの「継続的改善」を用いながら、「目の前のニーズに完璧に応えつつ、グローバルな拡大を実現する」ことを目指すのが、本書です。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 国連のSDGs(持続可能な開発目標)や東京五輪が話題になる中、地球の自然資源を枯渇させない持続可能な経営として、「生物多様性・自然資本経営」に注目が集まってきた。 持続可能な調達や街づくりの観点からも重要になっている。 ESG(環境・社会・ガバナンス)投資家も、企業が自然資本経営をしているかを投資判断に入れる傾向が強まってきた。本書籍はSDGsやESG投資、五輪と結び付けて生物多様性経営や自然資本経営を解説するとともに、最先端の企業事例を60以上も盛り込んで具体的な取り組みを紹介している点が特徴だ。 ユニリーバやネスレなど海外企業の事例も盛り込んでいる。 既に取り組んでいる企業や、これから着手する企業だけでなく、大学生や自治体の担当者にも分かりやすい内容となっている。 <主な内容> 【第1部】 「生物多様性と自然資本の世界動向」 【第2部】 「先進企業の自然資本経営から学ぶ」 【第3部】 「海外の巨人から学ぶ」 【第4部】 「自然資本の定量評価とESG情報開示」 【第5部】 「押さえておきたい基礎知識」
-
-近年急速に注目を集めるESG(環境・社会・ガバナンス)経営 先進20社の事例に基づき、ESGへの取り組みがビジネスに役立つ具体例を詳しく解説 いま「環境経営」は「ESG経営」へと大きく進化しようとしています。 グローバル企業は従来の環境対策に加えて、 世界が抱える社会課題の解決や生物多様性に配慮した経営を強化しています。 投資家や金融機関も、ESGに優れた企業に投融資する動きを加速させています。 今後、日本企業もESG経営が求められるでしょう。 従来の環境対策やCSR活動に加えて、より一層の温暖化対策の推進、貧困や人口減少などの 社会課題解決、天然資源の持続可能性に配慮した調達などを進めなくてはなりません。 本書では、ESG経営のヒントになるケーススタディー集です。 環境・CSRの専門誌『日経エコロジー』の好評連載「ケーススタディ環境経営」から、 特に読者の反響が大きかった先進企業20社を紹介しています。 全事例とも、専門記者が経営者や環境・CSRの担当役員などの幹部取材と、 事業の現場に足を運んで取材して執筆しました。 巻末には「ESG経営を理解する最新キーワード15」を収録。 ≪掲載企業一覧≫ コニカミノルタ/大日本印刷/デンソー/TOTO/大和ハウス工業 川崎重工業/積水ハウス/竹中工務店/清水建設/リコー 佐川急便/コマツ/積水化学工業/イオン/サントリーホールディングス 住友林業/三菱地所/日立造船/東レ/ヤマハ発動機
-
3.9プロジェクトマネジメントの能力がある人材が、どの業界でも求められています。 「プロジェクト」とは、「独自の目的・目標を設定し、それを期限までに達成させる一連の活動」のこと。「独自の目的・目標」とは「過去に経験したことのない要素が1つでも含まれている目的や目標」のことです。名称に「プロジェクト」という単語が入っていなくても、「独自の目的・目標」と「期限」が入った仕事や活動であれば、それはプロジェクトなのです。 「プロジェクトマネジメント」とは、端的に言うと「プロジェクトの目的・目標を期限までに達成させるために“やりくり”する手法」のこと。具体的には、「どのような技術を使うのか」「体制はどうするのか」「どのようにスケジュールを立てるのか」「どの程度のコストがかかるのか」など、幅広い範囲を含むものです。 プロジェクト実行に際し、知識が不足していたり、適切な方法・体制を用いなければ、円滑な活動ができず、最終的には目的・目標達成が困難になります。そうした事態を避けるため、「プロジェクトマネジメント」を学ぶ必要があるのです。 本書は、プロジェクトマネジメントの具体的知識とツールを、「目標設定」「計画」「実行」という3つの視点を中心に解説。プロジェクトの進捗に沿って、豊富な図を使って説明しています。 また著者の会社は、約2000名のプロジェクトマネージャーを育てた実績もあり、本書は現場の声を反映。ビジネスストーリーのケーススタディも掲載しています。 多くの仕事や活動がプロジェクトである、と言っても過言ではありません。ビジネスマンをはじめ、プロジェクトを成功させたいすべての人、必読の一冊です! ISO21500:2012(プロジェクトマネジメント国際規格)に準拠。
-
3.8
-
-宇宙ビジネス革命はここから始まった! 少年時代からの夢に向かって、宇宙飛行ビジネスの実現を目指すピーター・ディアマンディス。天才航空機設計者で民間宇宙機の開発に人生を捧げるバート・ルータン。 難病を克服し、偉大な祖父のように横断飛行に挑戦するエリック・リンドバーグ。 不可能に立ち向かい、新たな時代を切り拓いた男たちの驚異のストーリー、斬新なアイデアにあふれたイノベーション。国際賞金レース、Xプライズの誕生から成功までの大いなる野望に満ちたドラマ。 著名人も絶賛! 「本書を読めば、歴史を変えた瞬間を知ることができる。大きな考えと常識はずれの夢を持った人々の物語は、面白いと同時にやる気を与えてくれる」――リチャード・ブランソン(ヴァージン・グループ創業者) 「人類の挑戦に限界はないというのが本書のメッセージだ」――スティーヴン・ホーキング(理論物理学者) 「最後まで夢をあきらめない姿は、情熱と忍耐が持つ力を教えてくれる」――アリアナ・ハフィントン(〈ハフィントンポスト〉共同創設者、作家) 宇宙への夢を追う大物たちが多数登場 イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、リチャード・ブランソン、ポール・アレンなどライバル同士でも切磋琢磨し、世界をよりよい場所にするためにベストを尽くす。
-
-1巻2,420円 (税込)意図的な異物汚染を防ぐため、すぐに使える73の対策を紹介します。1つの対策は1ページで完結し、イラストや写真でやさしく説明。製造工程だけでなく工場全体でリスク管理を考える時の具体的ポイントがわかります。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-●優れたビジネスモデルの真実を解明! 環境の変化に上手く対応し、自らを変化させることが出来るようなビジネスモデルは、稼働するなかで徐々にビジネスモデルの様相が変化していく。多くの本では当初の設計ばかりに目が向き、より重要であるはずの変革し、自走し続ける仕組みの解明がなされていない。本書では、ビジネスモデルづくりのプロセスを「設計」「駆動」「変革」「自走」の4段階に分け、それぞれどんな状態なのか、実現させるためにどのような工夫がなされているのかを説明する。設計ばかりに注力し、後工程を軽視する企業のビジネスモデルは決してうまくいかない。 本書の解説に織り込まれる事例は、エフピコ、宅急便、セブン-イレブン、セブン銀行、俺のフレンチ、東レ、Amazon、テレビ通販、デル、ホンハイ、ブックオフ、グーグル、良品計画、ニトリ、サンリオ、ヒロセ電機、ミスミ、しまむら、ウォルマート、コマツ、江崎グリコ、ユニクロ、ライフネット生命、アスクル、など多岐にわたり、説得力が高い。
-
4.1ヒトの動きとモノの流れが、 いま、変わりはじめた―― 気鋭のピューリッツァー賞ジャーナリストが描く交通(トランス)・(ポーテ)物流(ーション)の「見たくない現実」と「見えてきた希望」。 ネットで注文した商品がその日に届く。そんな「当たり前」を実現するために、世界中の交通・物流システムは悲鳴をあげ、崩壊の危機に直面している――。気鋭のピューリッツァー賞作家が、誰もが目をそらしたくなるような不都合な事実を詳らかにするとともに、自動運転車やAI(人工知能)、IoTなどに後押しされて始動しつつある「移動革命」の姿を展望する。
-
4.3
-
-
-
4.2
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 国内市場が停滞するなか、日本の中堅企業は海外戦略を再構築しなければならない時期に来ている。 さらに海外現地法人の規模や機能が拡大しており、コンプライアンス・ガバナンスの必要性の高まりから現地法人の経営高度化が求められている。 これに伴い、多くの企業が現地の文化や商習慣、規制などの対応に苦労している。 本書ではグローバル展開する「中堅企業」の、とくに中国・ASEAN・インドなどアジア新興国での重要な経営課題を厳選。 課題解決の視点や解決するためのポイントを、数多くの事例とコンサルティング経験をふまえて提案する。
-
3.5「パターン・ランゲージ」をビジネスに活かす! 「企画」を考えるすべての人のためのヒントとなる「32」のパターンを紹介。 本書は、パターン・ランゲージの研究者として世界的に活躍する慶応義塾大学総合政策学部(以下慶應SFC)准教授 井庭崇 氏と建築家・デザイナー 梶原文生氏による共著です。日本初とも言われるデザインホテル「クラスカ」などを手がけるUDS株式会社を牽引してきた梶原文生氏が長年プロジェクトを通して培ってきた「企画のコツ」を、井庭崇氏の専門である「パターン・ランゲージ」の手法にもとづき32のパターンに分類し、具体的な事例とともにわかりやすく紹介したものです。 パターン・ランゲージとは、一言で言うと「良いデザインや良い実践の秘訣を共有するための方法」のことです。建築家クリストファー・アレグザンダーが考案したこの方法論は、建築分野だけでなく、ソフトウェア、デザイン、ビジネスプロジェクトの多くに適用されています。 企画の携わるすべての方にとって、現場で役立つ「画期的な企画」のコツを言語化してまとめています。何十から何百にのぼるプロジェクトの経験則を言語化し、その共通パターンをあぶり出して名前を付けるパターン・ランゲージの手法を用い、企画を立てる際に意識すべきポイントを32個のパターンにまとめ紹介しています。「企画のコツ」をまとめるのはパターン・ランゲージの世界でも初めての取り組みとなります。 また井庭崇氏による、パターン・ランゲージの解説と、井庭・梶原両氏による対談、梶原氏によるパターン適用のストーリについても紹介しています。 本書の対象は、企画・プロデュース、新規事業にたずさわる方々になります。企画・アイデアを練るとき、ビジネスを考えるとき、参照することで、きっと新たな知見とヒントが得られるでしょう。※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0最新装備の精鋭部隊がなぜ、寄せ集めのイラクのアルカイダに苦戦したのか?不確実性の高い環境のなかで、勝ち残る組織の条件とは? 著者が率いる特任部隊は確かにイラクで苦戦したが、それは敵が一流の組織であるため力が及ばなかったからではない。イラクのアルカイダは強くて柔軟性がありへこたれないが、たいてい訓練不足で装備も貧弱だった。彼らの強さと能力は、たまたま運よく21世紀的なファクターの相乗効果によって強化されたにすぎない。これはシリコンバレーの起業家のなかに、アイデアや製品の秀逸さよりも、タイミングがよかったというだけで桁はずれに儲けた者がいるのとよく似ている。こうしたファクターはイラクや戦争時に限ったことではなく、我々の日常の暮らしや組織のあり方にも関係してくる。これらのファクターを理解して適応していくことは必要不可欠であり、それが数年後の成否を分ける。本書は、こうしたファクターを理解するためのレンズを提供し、企業をはじめとする組織が新たな適応の必要性に迫られたとき、それにいかにアプローチしていくかの要諦をまとめたものである。
-
-
-
-
-
4.1IOT、インダストリー4.0を徹底解説&デジタル時代の日本企業の戦略を大胆に提言&最新論考と図版を大幅に追加! 「ものづくり」や「匠の技」だけでは、もはや勝てない。市場撤退を繰り返し、長らく停滞してきた日本の製造業をはじめとする産業の再生の方途はあるのか? アップル、サムスン、インテル、クアルコム。これらの企業は利益を生み出す自社のコア領域をクローズに独占し、市場との境界にオープン領域を設定し、多くの企業を巻き込みビジネスエコシステムを築き上げている。 本書は欧米企業が生み出した周到な知財マネジメントとビジネスモデルの構造を分析し、実証研究に基づき、日本企業の本質的な課題を克服し、再び活力を与え再成長のための戦略を大胆に提起する。また進行しつつある「IoT/インダストリー4.0」が日本に及ぼす影響、日本企業のとるべき方策についても新たな考察を踏まえ、最新の論稿を追加した。 【推薦のことば】 「重厚な実証と洞察!この金字塔的労作は次世代ビジネスの共通言語だ」――妹尾堅一郎(特定非営利法人 産学連携推進機構理事長) ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 なぜイケアは愛されるのか。本書はその秘密をデザインの視点から解き明かします。 イケアが掲げるのは、一人でも多くの人に豊かな生活を提供しようとする「デモクラティックデザイン」と呼ばれる考え方。 一般的なデザインの概念である「形」は、その要素のひとつに過ぎません。同社にとってデザインとは、より良い暮らしをより多くの人に提供するための手段です。価格も機能も品質も、そして最近はサステナビリティー(持続可能性)も、デザインの大切な要素なのです。 そのデモクラティックデザインを支えるさまざまな取り組みを紹介。 例えば徹底した家庭訪問調査。「ホームビジット」と呼ばれる調査は、デザイナーや技術者、企画担当者はもちろん、カタログや広告を作るディレクターやコピーライター、店舗のインテリアデザイナーも物流担当者も全員が実施して、今の生活者が抱える暮らしの問題点を本気で考える点が特徴です。 そんなホームビジットから生まれる製品やコミュニケーションが、消費者の心を捉える秘訣。 豊富な写真で、世界一の家具・雑貨メーカーの成長の秘密が分かる1冊です。
-
3.6ダートマス大学の経営学の俊英が、経営者、企業への膨大な聞き取り調査をもとに、「なぜ名経営者がいたのにあの企業は失敗したのか?」 という大命題の解を明かす、目からウロコの本格的経営学の書。アップルコンピュータ、モトローラ、サムソン自動車、そして雪印など。 日米欧韓の一流企業が、「名経営者」が指揮していたのに犯してしまった「失敗のケーススタディ」を、当事者に徹底的にインタビュー調査。 緻密な分析で、「名経営者だからこそ」犯しやすい「失敗の原因」を明かす。具体事例と、明晰な分析、そして鮮やかな処方箋をセットにした 「経営者、失敗の研究」の集大成。




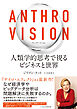


























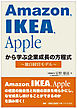
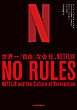









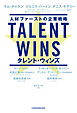










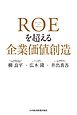
![ES[社員満足]経営の鉄則](https://res.booklive.jp/488050/001/thumbnail/S.jpg)

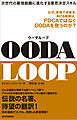



















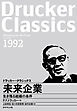
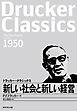












![アルバイト・パート[採用・育成]入門](https://res.booklive.jp/406832/001/thumbnail/S.jpg)









