無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
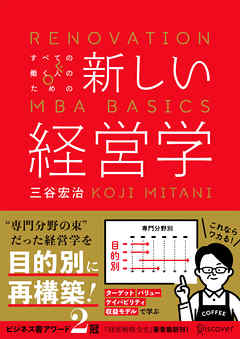
あらゆるビジネスの見え方が変わる!
“専門分野の寄せ集め”だった経営学を
ビジネスの目的別に再構築した画期的入門書
■経営学をビジネスモデルで理解する「常識破り」の入門書
そもそも「経営学」という学問は、「経営戦略」や「マーケティング」「アカウンティング」「ファイナンス」「人・組織」「オペレーション」といった専門分野の集合体です。
それゆえ、経営学の「入門」をうたっている本はどれも、各分野の寄せ集めでしかなく、経営学がわかりにくい原因となっていました。
本書は、そうした経営学“入門書”の「常識」を打ち破るもの。
「ターゲット」「バリュー」「ケイパビリティ」「収益モデル」という、
現実のビジネスを構成する4つの要素から経営学を「目的別」に理解してしまおうという
前代未聞の試みが結実したものです。
この4要素が組み合わさることで、「ビジネスモデル」が成立します。
ビジネスモデルは、事業を統合的に運営していくために欠かせない「経営視点」。
事業運営を任されたビジネスパーソンも、アルバイトをする学生も、会社そのものを経営する経営者も、
誰にとってもためになる、面白く学べて実践できる
画期的な一冊が、ここに誕生しました。
■独自企業・事業のビジネスモデルを解き明かすオリジナル演習収録!
本書では、ビジネスモデルのフレームワークを机上の空論に終わらせず
読者に実際に身につけてもらうことを考え、22題の演習を収録しました。
Google、Amazon、Apple、スターバックス、エプソンといった
独自のビジネスモデルを有する企業や事業を題材に取り上げ、
読者自らが実際にビジネスモデル図に描きだすのです。
このビジネスモデル図を一発で描ききるのは至難の業。
自ら調べ、考え、整理するという過程が必要です。
しかし、その繰り返しを経ることによって初めて、
真に「経営視点」を身につけることが可能になるのです。
■ビジネス書アワード2冠『経営戦略全史』著者渾身の一作!
本書のもう一つの特徴は、その圧倒的な読みやすさにあります。
文字数18万字超、ページ数360ページという大ボリュームながら、
平易でスピード感のある文体と189点にも及ぶ図表によって
「一気読み」することが可能になっています。
同じく「経営戦略100年の発展史を一気読み」する本として
大きな話題を呼び、ビジネス書アワード2冠を獲得した
『経営戦略全史』の著者・三谷宏治氏による、
かつてない読書体験を約束する渾身の一作です。
■目次
序章 経営学の全体像とこの本での学び方
1章 ターゲット:誰を狙う?
2章 バリュー:提供価値は何?
3章 ケイパビリティ:どうやって価値を提供する?
4章 収益モデル:どうお金を回す?
5章 あと3つ:事業目標、共通言語、IT・AI
補章 ミクロ経済学基礎と経営戦略史
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。