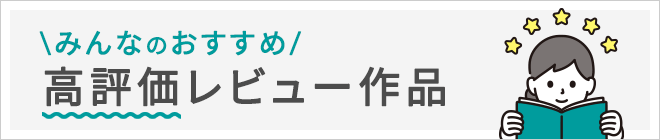小説・文芸の高評価レビュー
-
Posted by ブクログ
データを駆使して、この混沌とした、複雑な世界を、どのように生きるべきか、を考えたさせられる本。簡単に言うと、もっとシンプルに、大切な物に目を向けていこよ、って事かなって思う。
人は誰しもが死に向かって生きているのは本当にそうで。だからこそどう生きるかが大切で。
きっとどうしたって後悔はある。それはそれを通して学びがあるから、振り返った時に「あーすればよかった」って出てくる。けどそーいうもんだって思ってると、どうだろ。
結果なんかわからない。だからこそ、自分の大切にしたい人、物、事を、その時その時で考えて、感じて、生きていくことが大事。
時には他の人のことを優先しなきゃって時があるかもだけど、 -
-
Posted by ブクログ
ネタバレ
流れ石
破魔矢↔︎翔のミスリードも良かった
1時間寝ていたと言われ「そんなに」と答えた量子に笑う破魔矢や
斗真のシーンに切り替わる時に「2人が量子を覚してから2年前』という書き方など、2週目にして分かることがたくさんあった
「息子さん有能」
ひまわりの花言葉
中国語の部屋
おかえりを言わなければいけない
→翔くんがおかえりを言うの、すごい良いシーンだった
バイバイブラックバードと作品名似てるな
田中徹は別作品で出てきたのかな?
凍朗、天狗、燕など特徴的な名前だったのは、不思議の国のアリスからくる「童謡」を連想させるためなのか??
最後「何かに取り憑かれたんですか?」と斗真が言うのも -
Posted by ブクログ
ネタバレ辛い、辛すぎる12巻。
高槻の物語は加速を止めない。
真相に少しずつ、歩みを止めずに近づいていると感じる。
今回は鍵を握る祖父嘉克が亡くなり、彰良と家族との関係性の輪郭がくっきりと描かれる。祖母の佐奈子の存在も明らかになり、また山路も再び現れ、異捜との関係性も深くなっていく。
そんな中、高槻自身の異界との繋がりは、あの行方不明以前からあったのでは…という疑惑とともに、高槻が消える…。
EXの彰良の父と母の出会いのエピソードでほっこりさせるのかと思いきや、そこで匂わされる「彰良は智彰の子ではなく、清花と異界のものの血を引く子供」であるという事実。
おそらく引き金は祖父嘉克なのだろうが…。
思って -
Posted by ブクログ
この間「ジヴェルニーの朝食」を読み終わってとても良かったから、また続けて原田マハさんの作品を読みたくて偶然見つけた一冊。
先日金沢に旅行に行って、すっかり旅熱が上がっている私にとって興味をそそられた本作は旅の代行業のお話。
本書も原田マハさんらしく、心が暖まる話だった。
主人公の丘えりかを始め、事務所の仲間が個性豊かで面白い。
本書は前作「旅屋おかえり」未収録の北海道編。
読んでいて、本当に北海道を旅しているかのような気分になれた。
依頼人の女性から頼まれた北海道でしてほしいことは、結構重い内容ではあるのだけど、とにかく主人公丘えりかの天真爛漫な明るさがそれを必要以上に重くさせない。
人と人の
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。