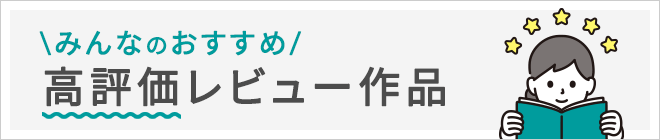小説・文芸の高評価レビュー
-
Posted by ブクログ
梨木さんの日常を語るエッセイ。家の周りで咲く小さな花や人とのつながりを、優しく鋭い目で見つめ、温かい言葉でつづる、何気ない暮らしの羅針盤。
梨木さんはふと歩いてみた隣との細い境、手入れのされていない庭で一綸やっと花をつけて咲いている貝母を見つける。
この花は束にして活けるとお互いの巻きひげでまるで縛りあって立っているかのように見える、そういう生き方から無理をしない、寄りかかれるものがあれば寄りかかってみる、状況に合わせて生きていく姿勢を感じる。
そしてサステナビリティー(持続可能性)という言葉に気が付く、よく見かけるようになったその言葉はやがて時代の波に流されていくだろう、生きていく間にはさ -
Posted by ブクログ
ネタバレどうしようもない父親から、母子が逃げ出す。
よくある設定で、父と息子の確執が物語の主軸というのもあるあるです。
それなのに、父・哲治が死亡したという連絡が、警察から届いたことから、主人公の嘉人の、父親の見る角度が変わっていく過程が、違和感なく描かれています。
それも単純に「実はいい人だった」というドンデン返しでもなく、次元と超えた二人の和解というファンタジーに走るでもない。
主人公の進路を方向づけた、恩師とのまさかの再会や、その恩師と哲治の意外な接点、貸本屋が存続し続けたことは(そんなことあるかなぁ)でしたが、総じて人の見方を今よりも多角的に変えていこうと思われるには、十分過ぎるほどの感動 -
Posted by ブクログ
ネタバレ主人公の名前が最後まで分からない連作短編。名前がなくても、この人のやわらかいまなざしは一貫していて居心地が良かった。
一話ずつご近所さんたちが登場して、ちょうどよい距離感でそれぞれ交流して、だんだん季節が巡っていくのが良かった。こんな風に付かず離れず穏やかに周囲と関わって生きていけたら、幸福な人生と言えると思う。少し寂しい別れもあるところが良い。
人間社会で暮らす熊、梨の妖精、叔父の幽霊、河童、壺の魔人、鬼、人魚。色んな存在が世界を共有していることが不思議で可愛くておおらかで、少し怖い。
生きることに疲れたらこんな本を読みたいと思わせてくれる、どこかあたたかい作品だった。 -
-
Posted by ブクログ
感動しました。
タイムカプセル=未来への手紙どんな話なんだろう?と思いと、喜多川泰さんの本と言う理由で選びました。
タイムカプセルに憧れていたので、私も書きたいと思いました。
相手が思っていること、自分が思っていることが違うとすれ違ってしまい、上手くいかないこともあるから気をつけないといけないと教えてもらえました。
届け先不明になった未来の自分への手紙の配達してくれる話なんですが、その人達の話を知ることが出来て、感動や素敵な話やこんな時はどうしたら良かったのかな?など考えさせられることもありました。
あとがきも印象強いです。
これからも本を読んでいきたいと思いました。 -
Posted by ブクログ
寺地はるなさんの『いつか月夜』を読み終えた。ページを閉じた後も、心の中で余韻が静かに波紋を広げている。そんな読後感に包まれる作品だった。
タイトルに込められた意味
『いつか月夜』──このタイトルは「いつも月夜に米の飯」という諺から来ている。月明かりに照らされた夜、温かい米の飯。何不自由ない生活、満足のいく暮らし。しかし、人生はそう上手くは行かない。そんな現実への洞察が、このタイトルには込められている。
美しくも切ない、この諺の響き。寺地さんが選んだこのタイトルは、物語の本質を見事に言い表している。
深夜のウォーキングが導く「人生の旅」
主人公の實成が歩くのは、深夜の街。
静寂に包ま -
Posted by ブクログ
以前、「サコ学長、日本を語る」という本を読んでとても共感したので、こちらも読んでみました。
まだ空気が読めないそうです笑。日本の、空気を読まなきゃいけない感じについて、論じてあります。日本の文化・風習について、「なんでやねん」と突っ込みたくなることがたくさん書かれていて、日本人でも「そう、それな!」と共感します。不思議やね。そこをちゃんと、疑問に思って「なんでやねん」と言うべきじゃないですか、というのがサコ学長の考え。本当に、ごもっともです。
最近は「コミュニケーション能力」がどうのこうのと言われますが(もうそれも古くなったのかな?)、サコ学長の主張を読んでいると、私たちがよく使う「コミュニケ
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。