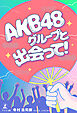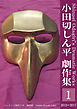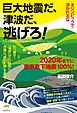東日本大震災作品一覧
-
4.2二宮和也主演!「家族」を撮りつづけた写真家と、彼を支えつづけた「家族」の笑いと涙あふれる感動実話。映画『浅田家!』10月2日(金)全国公開に先がけ、小説版8月7日(金)発売! 「一生にあと一枚しか、写真と撮れないとしたら?」 彼が選んだのは、“家族”だった――。 消防士、レーサー、ヒーロー、バンドマン……家族全員を巻き込んで、それぞれが“やってみたかったこと”をテーマにコスプレし、その姿を撮影したユニークすぎる《家族写真》で、写真界の芥川賞・木村伊兵衛写真賞を受賞した、写真家・浅田政志(二宮和也)。受賞をきっかけに各地の家族から撮影依頼を受け、《家族写真家》としてようやく軌道に乗り始めたとき、東日本大震災が起こる――。かつて撮影した家族の安否を確かめる為に向かった被災地で、政志が目にしたのは、家族も家も全てを失った人々の姿だった。 「家族ってなんだろう?」 「写真家の自分にできることは何か?」 シャッターを切ることが出来ず、自問自答を繰り返す政志。津波で泥だらけになった写真を一枚一枚洗浄して、家族の元に返す《写真洗浄》の活動に参加し、そこで写真を見つけ嬉しそうに帰っていく人々の笑顔に触れることで、再び《写真の持つチカラ》を信じられるようになる。そんな時、一人の少女が現れる。「私も家族写真を撮って欲しい!」。それは津波で父親を失った少女の願いだった――。
-
4.1「吉田調書事件」の当事者となった元エース記者が目にした、崩壊する大新聞の中枢 登場人物すべて実名の内部告発ノンフィクション 地方支局から本社政治部に異動した日、政治部長が言った言葉は「権力と付き合え」だった。 経世会、宏池会と清和会の自民党内覇権争い、政権交代などを通して永田町と政治家の裏側を目の当たりにする。 東日本大震災と原発事故で、「新聞報道の限界」をつくづく思い知らされた。 2014年、朝日新聞を次々と大トラブルが襲う。 「慰安婦報道取り消し」が炎上し、福島原発事故の吉田調書を入手・公開したスクープが大バッシングを浴びる。 そして「池上コラム掲載拒否」騒動が勃発。 ネット世論に加え、時の安倍政権も「朝日新聞バッシング」に加担し、とどめを刺された。 著者は「吉田調書報道」の担当デスクとして、スクープの栄誉から「捏造の当事者」にまっさかさまに転落する。 吉田調書報道は、けっして捏造などではなかった。 しかし会社は「記事取り消し」を決め、捏造だとするバッシングをむしろ追認してしまう。 そして、待っていたのは「現場の記者の処分」。 このときに「朝日新聞は死んだ」と、著者は書く。 戦後、日本の政治報道やオピニオンを先導し続けてきた朝日新聞政治部。 その最後の栄光と滅びゆく日々が、登場人物すべて実名で生々しく描かれる。 【目次】(抜粋) ◆第一章 新聞記者とは? 記者人生を決める「サツ回り」 刑事ドラマ好きの県警本部長 ◆第二章 政治部で見た権力の裏側 政治記者は「権力者と付き合え」 清和会のコンプレックス 小渕恵三首相の「沈黙の10秒」 古賀誠の番記者掌握術 朝日新聞政治部の「両雄」 ◆第三章 調査報道への挑戦 虚偽メモ事件 社会部とは違う「調査報道」を生み出せ! 社会部出身デスクとの対立 ◆第四章 政権交代と東日本大震災 内閣官房長官の絶大な権力 小沢一郎はなぜ総理になれなかったのか 原発事故が突きつけた政治部の限界 ◆第五章 躍進する特別報道部 福島原発の「被曝隠し」 「手抜き除染」報道と特別報道部の全盛期 ◆第六章「吉田調書」で間違えたこと 吉田調書取材班の結成 吉田調書報道の「小さなほころび」 危機管理の失敗 動き始めた安倍政権 「池上コラム問題」はなぜ起きたのか 衝撃の木村社長会見 ◆第七章 終わりのはじまり バッシングの嵐と記者処分 ツイッター騒動と「言論弾圧」 東京五輪スポンサー
-
-2004年10月12日、埼玉県皆野町の山中で男女7人がレンタカーの中で死亡しているのが発見された。死因は練炭による一酸化炭素中毒だった。北は青森から南は佐賀まで、全国各地から集まった7人の接点は、インターネット。いわゆる「ネット心中」である。連鎖的に、いわば流行のように広がった自殺の手段だった。「過去最高の人数」の自殺者を出したこの事件は、世間の注目を浴び、この集団自殺の呼びかけ人「マリア」から計画を知らされていた著者に、マスコミは殺到した……。 マリアはなぜ死を選んだのか? 事件が浮き彫りにする若者たちの「生きづらさ」とは? 実行にふみきれず、死を免れた参加者への取材も収録。自殺が跡を絶たない現代に、改めて命の価値を問うノンフィクション。 ●渋井哲也(しぶい・てつや) フリーライター。ノンフィクション作家。中央⼤学⾮常勤講師。 栃⽊県⽣まれ。東洋⼤学法学部卒。東洋⼤学⼤学院⽂学研究科教育学専攻博⼠前期課程修了。教育学修⼠。家出、援助交際、摂⾷障害の取材の過程で「⽣きづらさ」という⾔葉を聞いて以来、子ども・若者の⽣きづらさ、⾃殺、⾃傷⾏為、依存症などに関⼼を持つ。そのほか、いじめや不適切指導による自殺(指導死)などの教育問題、ネット・コミュニケーション、ネット犯罪、ネット自殺、東⽇本⼤震災やそれに伴う原発事故・避難⽣活の取材を重ねる。週刊女性の取材班として「グッドプレス賞」(依存症問題の正しい報道を求めるネットワーク主催、雑誌部門、2020年度)受賞、『ルポ自殺 生きづらさの先にあるのか』(河出新書)で「貧困ジャーナリズム賞」(反貧困ネットワーク主催、2022)を受賞。
-
-特集 今、何が問題か われわれは絶え間なく「問題」について語っている。 少し考えてみても東日本大震災からの復興、原子力とエネルギー、 雇用や財政、TPP参加の是非といった具合に、 およそ「問題」には事欠くことがない。 だが、一〇年、二〇年はもちろん 一年もするとすっかり忘れ去られてしまった「問題」も数多い。 「今」という時の重みは小さくなり、 「問題」も大量に生産され大量に消費されている。 『アステイオン』は創刊以来の四半世紀、本質的な「問題」を正面から語り、 時代の大きな流れの中で「今」を問う試みを続けてきた。 この基本的な姿勢にはいささかの変更もないが、 新しい編集体制で臨んだ本号の特集では、 各編集委員が「今、何が問題か」について自問することで、 われわれの知的姿勢を改めて明らかにしておきたい。 あえて時間的にも地域的にも限定を設けず、 それぞれ専門を異にする編集委員が「今」と「問題」を自由に語った論考から、 何が見えてくるだろうか。 現代の諸問題を「鋭く感じ、柔らかく考える」本誌の挑戦に対する 読者諸氏のかわらぬご支援を期待しつつ、 リニューアル後の最初の特集をお届けしたい。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 東日本大震災から復興へと歩み始めた被災地の様子を記録。 岩手日報紙面に連載した「明日への一歩」、大きな反響を呼んだ延べ5万人に上る避難者名簿の紙面掲載の経緯、震災直後に取材した記者が3カ月を経て再度現地を訪れて変わりつつある被災地の様子を書いた「被災地を歩く」など、一連の企画をまとめた。 【目次】 震災から半年 空撮2011.8.26 明日への一歩 コラム 希望のニュース 空撮 5.16 5万人の安否を伝えた避難者名簿報道 今被災者に必要なものは コラム 希望のニュース 被災地を歩く 東日本大震災 避難者アンケート 記者の証言 検証 平成の三陸大津波 東日本大震災 ドキュメント岩手 地震発生から6カ月 いわてのテとテ
-
5.0
-
-
-
-「生きづらい」と感じることは弱さではない……ネットを浮遊している若者たちの心の裡 不登校、援助交際、自殺、リストカット、摂食障害、家出、虐待、過干渉、抑圧……。学校や家族や友達、現実の世界では、うまく自分の思いを表現できない「生きづらさ系」の若者たち。彼らは「名前」から逃れて、何を想い、何を求めているのか。ネットでの3年に及ぶフィールドワークをまとめたノンフィクション。 ●渋井哲也(しぶい・てつや) フリーライター。ノンフィクション作家。中央⼤学⾮常勤講師。 栃⽊県⽣まれ。東洋⼤学法学部卒。東洋⼤学⼤学院⽂学研究科教育学専攻博⼠前期課程修了。教育学修⼠。家出、援助交際、摂⾷障害の取材の過程で「⽣きづらさ」という⾔葉を聞いて以来、子ども・若者の⽣きづらさ、⾃殺、⾃傷⾏為、依存症などに関⼼を持つ。そのほか、いじめや不適切指導による自殺(指導死)などの教育問題、ネット・コミュニケーション、ネット犯罪、ネット自殺、東⽇本⼤震災やそれに伴う原発事故・避難⽣活の取材を重ねる。週刊女性の取材班として「グッドプレス賞」(依存症問題の正しい報道を求めるネットワーク主催、雑誌部門、2020年度)受賞、『ルポ自殺 生きづらさの先にあるのか』(河出新書)で「貧困ジャーナリズム賞」(反貧困ネットワーク主催、2022)を受賞。
-
3.9東日本大震災後、被災地に大量に設営された仮設住宅は、共同体を排除した「個」の風景そのものである。著者は、岩手県釜石市の復興プロジェクトに携わるなかで、すべてを失った被災地にこそ、近代主義に因らない自然に溶け込む建築やまちを実現できる可能性があると考え、住民相互が心を通わせ、集う場所「みんなの家」を各地で建設している。本書では、国内外で活躍する建築家として、親自然的な減災方法や集合住宅のあり方など震災復興の具体的な提案を明示する。【目次】はじめに/第一章 あの日からの「建築」/第二章 釜石復興プロジェクト/第三章 心のよりどころとしての「みんなの家」/第四章 「伊東建築塾」について/第五章 私の歩んできた道/第六章 これからの建築を考える/おわりに
-
-岩手県陸前高田市では、東日本大震災の教訓を後世に残すために、桜ライン311という団体によって、市内の津波最高到達点に桜を植える活動が行われている。 「同じ悲しみを繰り返して欲しくない」という想いで桜を植える彼らの姿を通して、全国の人々に対する防災意識の喚起ができないか。 そんな想いから制作されたドキュメンタリー映画『あの街に桜が咲けば』を、全国上映の日々の記録とミックスして今回書籍化。 ただ悲しみを切り取っただけの記録じゃない。 家族や大切な人と読んで欲しい、暖かい気持ちで防災がしたくなる命の物語。 【著者プロフィール】 著者:小川光一 1987年5月29日東京生まれ。 多数のNPOおよびNGOに所属し、国際協力や東北支援を中心に活動中。 「他人の痛みを想像できる人間であれ」を信条に掲げている。 日本防災士機構認定防災士/陸前高田まち・ひと・しごと総合戦略策定会議 委員/ウガンダ支援NPO法人MUKWANOサポートメンバー/認定NPO法人 桜ライン311理事/陸前高田ドキュメンタリー『あの街に桜が咲けば』監督/カンボジアエイズドキュメンタリー『それでも運命にイエスという。』監督
-
-東日本大震災が起きた時、若手社会人、もしくは これから社会に出ようとしていた学生たちだった「after3.11世代」。 本書は、after3.11世代がどのように東日本大震災を受け止め、どのように捉えたのか。 そして、彼らの考え方、働き方にどんな影響があったのを追いかけた一冊です。 リブセンスの村上太一さん、フィッシャーマン・ジャパン 鈴木真悟さんを含む5人が登場します。 ※デジタル版には、表紙画像や目次に掲載している記事、画像、広告、付録が含まれない場合があります。また、掲載情報は原則として奥付に表記している発行時のものです。
-
4.3コロナ禍の今、日本は東日本大震災と東京電力福島第一原発事故以来の国家的危機に直面している。この歴史的な国難に対して、当時首相であった安倍晋三と菅直人はどのように対処したのだろうか。危機に際して国民に何を語り、国民をどう守るかは政治家の最優先事項であり、時の政府の姿勢は、国民に対する本音を浮き彫りにする。安倍元首相は常々、民主党政権を「悪夢」と呼んでいたが、はたして安倍政権は菅直人政権をこんなに非難できるほど優れていたのか。そこで、両者の「危機の認識力」「国民への言葉」「権力の使い方」「補償」など個々の対応を徹底比較し、危機における、あるべきリーダーシップを考察。最後に安倍政権を引き継いだ菅(すが)政権のコロナ対応も評価する。10年前の記憶・記録を掘り起こすことで、今の自民党政権の“実態”が明らかになる!
-
5.0どなたでも簡単に中国輸入Amazon販売を行い、『短時間』で『給料以外の収入』を得られる方法の解説書です。 一般的な中国輸入ノウハウとは全く異なり、現地の中国人パートナを活用して、中国人パートナーに儲かる商品のリサーチから販売店への価格交渉、商品の検品、不良品の返品、商品包装、日本への発送まで多くの作業を中国人パートナーに依頼する事で『中国ビジネスの一番難しい部分を自動化』し、日本では『Amazonのサービスを最大限活用』して受注から、入金確認、発送、クレーム対応までを自動化することでリサーチから販売まで多くの作業を自動化できます。 忙しいサラリーマンの方でも『隙間時間』で中国輸入Amazon販売を行うことができ、年金問題、老後破綻など将来不安を感じる方が多い中で、自分の力で給料以外の収入を得るため方法を簡単に解説しています。 著者自ら数年前ままで会社員で限られた時間でビジネスに取り組んで来たため本書の内容は、非常にシンプルでどなたでも実践でき英語も中国語も不要、難しいパソコンスキルも長時間の作業も不要なビジネスモデルです。 多くの方が、中国輸入Amazon販売で自分の力で収入を手に入れてもらいたいと願っています。 【著者プロフィール】 山田 野武男 2011年3月11日 東日本大震災により当時勤めていた会社の業績が大幅にダウン会社命令で始めたヤフーオークションでたった3ヶ月で1年分の商品販売に成功、ネット販売のパワーを感じ独立を決意、その後副業で、国内転売、せどり、欧米輸入、欧米輸出、様々なネット転売に挑戦して結果を残しより効率化を求めて中国人パートナーを活用した中国輸入Amazon販売に行き着く、時間の無いサラリーマンの方でも短時間で結果の出し易い中国輸入を広めたいと中国輸入スクールや個別コンサルで今まで何をやっても結果の出なかった方でも結果出る転売ビジネスを広めている。
-
-完全描き下ろしデジタルコミックマガジン『いぬまみれ』に収録されたあやせりう氏が綴る実体験に基づいた物語。 東日本大震災からしばらくして一時預かり犬としてやってきたのは10歳になるラブラドールのアランだった。 幾度となく訪問してくれる飼い主さんとの面会に「おうちに帰れる!」と期待するも叶わず、期待するも叶わず……福島まで続く空の下、やがて「ウチの子」になろうとしてなのか、アランにも小さな変化が訪れる。 季節は巡り、期待、反抗、諦めを繰り返し、それでもやっぱりアランは飼い主さんが大好き!その一途な思いが心を打つ。 やがて時は流れ、15歳になろうとしていたアラン! 彼がもたらしてくれた眩しくって愛おしい日々を、温かな色合いのフルカラーで綴った感動作。
-
3.92011年3月11日に突然日本を襲った東日本大震災。そんな未曾有の事態が発生した直後から、被災地でまさしく命を賭してさまざまな救援活動を続ける自衛隊。テレビや新聞では報じきれていない現地におけるその活躍と、自衛隊員への感謝のメッセージを佐藤正久議員が綴る。 さらに自衛隊OBでもある“ヒゲの隊長”だからこそ知りうる自衛隊員の心身の驚異的な強さの秘密や、ベールに包まれた訓練内容、さらには自衛隊がもっと好きになる知られざる彼らの素顔まで完全網羅。自衛隊への感謝の気持ちと親近感が増す1冊です。
-
4.4子育ては何もかも期間限定のいとおしい時間。 東日本大震災を機に、仙台から移り住んだ石垣島。都会の生活から一変した島の暮らしが親子に与えてくれた豊かな時間が、短歌と共に綴られます。 「たくみん」は中学2年生に成長し、親がしてやれることもだんだんと少なくなってきたことを実感する日々。 『ありがとうのかんづめ』というタイトルには、俵さんの、子育ての日々の中で授けられた感謝の思いを閉じ込めた「この缶詰一個あれば、母は充分」という意味が込められています。 「子育て」は「親育て」であることを実感するハートウォーミングなエッセイです。
-
-
-
-
-
4.1異端経営者はなぜ生まれたのか。 今から一世紀前。韓国・大邱で食い詰め、命からがら難破船で対馬海峡を渡った一族は、豚の糞尿と密造酒の臭いが充満する佐賀・鳥栖駅前の朝鮮部落に、一人の異端児を産み落とした。 ノンフィクション作家・佐野眞一が、全4回の本人インタビューや、ルーツである朝鮮半島の現地取材によって、うさんくさく、いかがわしく、ずる狡く……時代をひっかき回し続ける男の正体に迫る。 在日三世として生をうけ、泥水をすするような「貧しさ」を体験した孫正義氏はいかにして身を起こしたのか。そして事あるごとに民族差別を受けてきたにも関わらず、なぜ国を愛するようになったのか。そしてなぜ東日本大震災以降、「脱原発」に固執し、成功者となったいま、再び全米の通信業界に喧嘩を売りにいこうとするのか――。飽くなき「経営」の原点が本書で明らかになる。
-
-温室効果ガスによる気温上昇、新型インフルエンザウイルスなど感染症の脅威、2011年東日本大震災・・・ 環境問題は国内外問わず、喫緊の課題として認識され始め、環境・衛生の国際的な規格としてHACCP、FSSC、ISO、TPPなど徐々に整ってきている。本書は食品安全の基準となるHACCPを中心に、いかに環境衛生基準に則るための準備をしておく必要性を説いている。現在の環境・衛生問題を網羅的に理解し、「エコマインド」を身につけなければ、じきに到来するエコ重視の時代に取り残されてしまうだろう。経済ありきの考えから脱却し、新たなグローバルスタンダードを生き抜いていくための「エコ」入門の決定版。
-
-2011年3月、東日本大震災に伴い福島第一原発で事故が起きた。火災、放射能漏れ、情報収集の遅れなど後手に回った東電の対応など、2007年7月の新潟・柏崎刈羽原発事故で指摘された教訓はなぜ生かされなかったのか--。正確なデータにもとづき、朝日新聞が総力を結集した検証ルポ『「震度6強」が原発を襲った』に福島原発事故を大幅加筆。
-
4.0喪失の時代、私たちを支える「他者」との邂逅 古今東西の哲学者、宗教家、詩人、作家、そして無名の人々の言葉を引用し、「生きがい」とは何かを論じた神谷美恵子の『生きがいについて』。刊行から50年以上読み継がれるこの一冊は、神谷美恵子の生涯や他の作品に照らすとき、作家自身の精神的自叙伝としての姿を現す。誰かのために、何かのために必要とされることこそが「生きがい」であると考えた神谷は、一度は見失った「生きがい」をいかにしてふたたび見いだしたのか――。東日本大震災という「大きな喪失」を経験し、新型コロナウイルス禍という試練のなかにあって、わたしたちが「生きがい」を回復する方法について考える。
-
4.0私たちは、スピリチュアルな現象をどのように理解し、その疑問に答えれば良いのか――。30年前の奇跡的な出来事から自らの能力を発見した著者は、その後の臨死体験を経て、いかなる困難な悩みにもカウンセリングをほどこす「光の学校」を設立した。本書は、悩み苦しむ人々の「魂の救済活動」を続けてきたスピリチュアル・カウンセリングの事例の一端を各界の切実な要望を受けて紹介したものである。未曽有の試練となった東日本大震災における魂の対話をはじめ、「先立った夫からのメッセージ」「運命の赤い糸」「死後の生命」「幽霊の正体」「神様の証明」「病気になる理由」「うつ状態からの脱出」など、生きがいを失った人々に、なぜ困難に出合うのか、生きる意味と価値、自らの使命とは何であるかといった人生の“根源的な問い”に対して分かりやすく答えた渾身の一冊。
-
4.3かしこくて、こわがりな動物、馬。その命を守る活動をしているのが、NPO法人『引退馬協会』代表の沼田恭子さんです。東日本大震災のときには、福島県南相馬市に入り、津波の被害にあった多くの馬を救いました。子どものころ動物が苦手だった沼田さんが、なぜ馬にかかわる仕事をするようになったのでしょう? 沼田さんと馬たちの交流と、馬を守る活動をえがくノンフィクション!<すべての漢字にふりがなつき・小学校上級以上>
-
4.3
-
4.5品質・作業効率が向上 離職率・人件費が減少 好きな日に働く、嫌いな仕事はやらない…… 人に優しい働き方の先にあったのは 想像を超えたプラスの循環だった 「出退勤時間は自由」「嫌いな作業はやらなくてよい」など、非常識とも思える数々の取り組みが、いま大きな共感を呼んでいる。そして、その先にはあったのは思いもしなかった利益を生むプラスの循環だった。 2011年3月11日14時46分、東日本大震災。石巻のエビ工場と店舗は津波ですべて流された。追い打ちをかけるような福島第一原発事故。ジレンマのなか工場の大阪移転を決意する。債務総額1億4000万円からの再起。 人の生死を目の前にして考えたのは、「生きる」「死ぬ」「育てる」などシンプルなこと。そしてそれを支える「働く」ということ。自分も従業員も生きるための職場で苦しんではいないだろうか。 そんななかで考え出したのが「フリースケジュール」という自分の生活を大事にした働き方。好きな日に出勤でき、欠勤を会社へ連絡する必要もない。そもそも当日欠勤という概念すらない。 これは、「縛り」「疑い」「争う」ことに抗い始めた小さなエビ工場の新しい働き方への挑戦の記録である。
-
-大ヒットTVドラマの原点! 漫画『監察医朝顔』監修者、初の著書! 人気漫画「監察医朝顔」の監修者であり、杏林大学医学部名誉教授である著者の初の著書。 「法医学者」の仕事の裏側だけでなく、重大事件や大規模災害、感染症、子ども虐待など、 1万体以上を検死し5000体以上を解剖してきた経験と、ご遺体から届いたメッセージを、今を生きる人々へ伝える。 長年取り組んでいる児童虐待の防止、感染症対策で注目されるエンバーミング(死体衛生保全)など、現代社会の課題解決につながる知見も紹介する。 序章 ようこそ法医学教室へ 第一章 検死・解剖でわかった真実 (火葬が24時間後なのはなぜ?/死亡推定時刻を見極める3つのポイント/死後経過時間をずらすトリック/“におい”に気づき司法解剖へ/「検視」と「検死」/無理心中が一転、殺人事件/解剖前の儀式と手順/葬儀直前、棺に入った状態で検死/単なる偶然か。それとも完全犯罪か/「バイトマーク」から犯人逮捕/人間はなぜ死臭を発生するのか?/「法医昆虫学」死臭を察知する虫の特性) 第二章 世間を震撼させた重大事件 (トリカブト保険金殺人事件/東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件/坂本堤弁護士一家殺害事件/東村山警察署旭が丘派出所警察官殺害事件/井の頭公園バラバラ殺人事件/新宿歌舞伎町ビル火災) 第三章 悲嘆のケア ご遺族と向き合う (父が家族に残した最期のメッセージ/「心不全」は死因ではない!?/山本五十六海軍大将「空白の1日」/悲嘆のケアにつながる「聞き役」) 第四章 身近に潜む命の危険 (昔は常識、今は非常識/脳梗塞は3時間以内が肝/ヒートショックにつながる危険な組み合わせ/死亡事故増加が危惧される乗り物/睡眠時無呼吸症候群は「突然死」の怖れあり/魚や貝が凶器に!?) 第五章 大規模災害における法医学 (「阪神・淡路大震災」最期に立ち会った者の願い/「東日本大震災」歯科所見による身元確認/心に寄り添ってこその「トリアージ」/異常気象により白骨が?) 第六章 感染症と向き合う法医学 (恐怖!「人食いバクテリア」/一類感染症に対する解剖/致死率100%「狂犬病危険キャリア動物」/「医療崩壊」の先にある「葬儀崩壊」/熱型から「腸チフス」の疑い) 第七章 3つの役割を果たすエンバーミング (エンバーミングが持つ3つの役割/古代エジプト文明のミイラが起源/「整える」による最期のお別れ/東京五輪開催に備えた「最期のおもてなし」/娘を導いてくれたダライ・ラマ法王の言葉) 第八章 子ども虐待と臨床法医学 (法医学者が子ども虐待に取り組む理由/25年間、検視官に伝え続けてきたこと/子ども虐待の“SOSサイン”/世界に学ぶ「見守りシステム」/未来を救う「こうのとりのゆりかご」)
-
3.0後悔しない本当の幸せとは何か、といった人生論から、東日本大震災や放射能に関すること、誰でも実践できる健康法、フリーラジカル、アンチエイジング、最新医療まで幅広く、とことん話し合いました。目次――第1章 くじけずに、しなやかに生きる/第2章 「温かな社会」をつくるために/第3章 科学と自然の中で生きる/第4章 健康長寿のためにすべきこと、できること/第5章 医療はどうあるべきか。悔いのない人生のために ◎無理なことは長続きしない/◎試練を乗り越えたら、その分、強い人間になる/◎人生の禍福は、どうなるかわからない/◎「病院はNPO」ドラッカーに教わったこと/◎日本人の“いい加減さ”を大切にしたい/◎イラクやチェルノブイリで感じること/◎ウンコは軽いほうがいい/◎老化を食い止める六種類の食べ物/◎鉄分の摂りすぎは危険!/◎余命は平均的な寿命。治る可能性はある/◎存分に生きた人の最期はサッパリしている……
-
-東日本大震災を乗り越えた老学者が、病床で書き綴った渾身のメッセージ 長年、海藻の研究に取り組んできた著者。 「なぜ昆布は死んでからダシが出るのか」という素朴な疑問をはじめ、光合成のために様々な色をもつ、海藻が地球環境に果たす役割、陸上植物との意外な関係など、身近な食材でありながら、あまり知られていない「海の森」、海藻の世界を解き明かします。 そして、海藻もヒトも自然のサイクルの中で生きる、同じ生物としてとらえたとき、 「生きるとはどういうことか」「ヒトとは何か」「ヒトの欲望の愚かさ」を、深く考えさせられることになります。 震災前の南三陸町の海岸で撮った、貴重な写真も収録。
-
3.0
-
3.5プロゴルファー石川遼は若くして賞金王を獲得し、ゴルフの最高峰マスターズでの成績も飛躍しました。東日本大震災では2011年の獲得賞金全額を被災地へ贈ることを決め、ゴルフのみならずその言動が注目を集めています。若くして人格者とも言われ、老若男女問わず好感を持たれています。過去、これほどのゴルファーはいません。その石川遼はどのように育ったのか? 子どもを持つ親なら関心のあるところです。遼が育った石川家は首都圏郊外の典型的なサラリーマン家庭です。父である著者はアマチュアのゴルフ好きで、プロではありません。では、なぜ遼は若くして一流のゴルフ選手になれたのか? それは親が遼にゴルフのみを教えたわけではないからです。ゴルフについては遼が幼稚園児のころからいつも導いてきました。ただ、ゴルフよりも親として遼に伝えていった大事なものが遼の人間性や向上心を高めたといってもいいでしょう。本書では、石川遼の人間性を育てた父親が、独自の「石川式子育て論」を語ります。石川家の子育て法は、子どもを持つ親や教育関係者のみならず、人材育成の立場にある方にも大きなヒントになるでしょう。
-
4.8この医療活動は日本の底力だ。 簡易ベッドで埋め尽くされた待合室、廊下にあふれる被災者、家族の安否もわからないまま不眠不休の極限状態で働く医療従事者の姿――東日本大震災で災害医療の最前線となった石巻赤十字病院での全記録です。 約20万人が居住する石巻圏の医療施設がほぼ壊滅状態となり、唯一、水没を免れ、自家発電機を所有していたこの病院に人々が殺到。また、石巻市役所が浸水のため孤立、一時は300か所以上に膨れあがった避難所への医療提供やアセスメント(評価付け)も医師自らが担いました。結果的に救えない命も少なくはありませんでしたが、それを最小限に留める努力を、赤十字の組織力と機動力をもって全力で行ったこの病院の取り組みは、今後の災害医療のモデルケースになるともいわれています。 かつてない規模で行われた過酷なトリアージ、津波被害特有の“低体温症”患者への対応、避難所の劣悪な環境が引き起こした肺炎――石巻赤十字病院が体験した死闘の100日間を追い、そこで生まれた様々な人間ドラマと交差させながら描くノンフィクションです。 ロングセラー単行本を、増補(5年後の石巻赤十字病院・約1万8000字)した文庫化版を電子化! 【ご注意】※この作品はカラ―写真が含まれます。
-
4.0
-
-1995年に生まれた少年少女たちは、社会や自然のうねりに巻き込まれながら生きる方法を模索してきた。ゆとり教育、東日本大震災、消費税増税など現代のピリオドとなるできごとが、たびたび試練として降りかかってくるためだ。 多感な中学・高校時代には震災が与えたショックに打ちひしがれ、大学時代にはゆとり教育の影響や、SNSで相互監視的になったインターネットを意識せざるを得なくなった。 本書では、そんな不遇に見舞われてきた23歳の著者陣が、実話をもとにした短編小説、漫画、エッセイなどさまざまな表現方法で自らのエピソードを語る。 新社会人を迎える世代が感じているリアルを伝え残す1冊として、興味を持っていただければと思う。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 <ねえ ねえ かあさん。 一生ぶんの だっこって どのくらい?> 2011年東日本大震災以降、東北、熊本など被災地に向けての絵本の読み聞かせを続けている南 果歩。 本書は、コロナ禍でのリモート朗読が話題になった詩を絵本にしたものです。 読んでもらう子どもたちはもちろん、 読み聞かせする大人もいやされてほしいという気持ちがこもった、 やさしく包み込むような詩に 世界で活躍する話題のアーティスト、ダンクウェルがカラフルで躍動感のある絵をつけました。 何度でも読み返したい、新しい癒やしの絵本です。 *読んであげるなら3才くらいから *こどもから大人まで ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-
-
-1969年高校生も政治の季節を生きていた。 6年ぶりに連絡をとった冨士真生子は、ニューヨークでの生活を引き払い、3週間前に帰国したばかりだった。中南米を舞台に報道写真を撮り続けてきた彼女だったが、折から東日本大震災が起きると、旧交を暖める間も無く、現地に飛んだ。9か月にわたる取材成果を披露する会場に現れた彼女はすっかり痩せて、人生の重大な局面に立たされていることを感じさせるのだった。 真生子とは、いまから40年以上も前、高校生の時に出会った。当時学生運動の波は高校にまで押し寄せてきており、彼女は市内の女子高に通う1学年上の活動家だった。そして、15歳のぼくは、彼女に淡い恋心を抱いていた。 ぼくは綴る、彼女の命を見つめながら、悲しみと痛みにみちた青春の日々を、そして輝ける人生の瞬間を。
-
-2014年、稲川会高田一家総長の座を二代目に譲り、長年のヤクザ人生に区切りを付けた著者。稲川会のため、高田一家のために、体を張ってきたからこそ知り得る業界の真実がある。ヤクザとは、シノギとは、博徒とは――その波乱に満ちた半生とともに書きつくした珠玉の一冊。また、東日本大震災の発生時に行ったボランティア、金、物品、シノギについても詳しく述べられている。
-
5.0空前のペットブームと言われるなか日本ではいまだ年間6万匹もの犬や猫が殺処分されているという現実がある。 この悲惨な状況を少しでも変えていこうと精力的に活動を続ける女性―― それがNPO法人・犬猫みなしご救援隊の代表・中谷百里さんそのひとだった。中谷百里さんの活動を追いつつ犬と猫、さらにはその向こうにいる「人間」の問題により深く迫る! 多頭飼育崩壊の現場では大量に増えた犬や猫だけでなく飼い主である人間の社会からの孤立も問題に。 東日本大震災で被災した犬や猫が飼い主から離れて暮らす現実。少しでも大切な命を救うために中谷さんがとった行動。 本書では、番組で紹介された内容をさらに深く掘り下げて紹介!
-
-【戦後日本社会の抱えてきた問題、実に大きい問題が、たとえば天皇の戦争責任が問いかけられている――大江健三郎】【東日本大震災で私たち劇作家が何より痛感したのは、井上ひさしさんの不在なんです――平田オリザ】【井上ひさしが生きていたら、その目には、この日本の状況がどう映っていただろう。――没後10年。いまこそ読み直したい、井上ひさしの文学。】大人気テレビ番組「ひょっこりひょうたん島」の脚本をはじめ、岸田國士戯曲賞を受賞した『道元の冒険』、直木賞受賞作となった『手鎖心中』、さらには日本SF大賞や読売文学賞に輝いたベストセラー小説『吉里吉里人』など、多彩な活躍を見せた作家・井上ひさし。本書は、井上に共鳴する人々が、生前の交流を明かしながら、その作品を論じる初の論考集。井上に刺激を受けながら創作活動を行ってきたと明かす作家・大江健三郎をはじめ、国内外から評価の高い劇作家・平田オリザなど、錚々たる創作者がそのメッセージを読み解く。
-
3.7ふと気付くと、涙がぼろぼろとほおをつたっていく。 「あれ、俺、なんで泣いてんだろ」 自分でもわけがわからなかった。 「東日本大震災以来の、とんでもないことが起きていると思って」ーー 2020年1月、横浜を出港した豪華客船、ダイヤモンド・プリンセス号は、香港、ベトナム、台湾をめぐっていた。 沖縄・那覇を経て、2月4日に横浜に戻る予定だったが、その直前、香港で下船した中国人乗客が発症したことが判明する。船内でも発熱した乗客が次々に医務室を訪れていた。 しかし、そのとき、多くの乗客はまだ「異変」に気付いてはいなかった。 正装のディナー、外国人歌手によるエンターテインメント、絵画展、マージャン、有志による合唱発表会などが行われ、旅のフィナーレを目前にしていた。 日本政府には、衝撃的な情報がもたらされる。発熱した31人の乗客のうち、10人が「新型コロナウイルス陽性」だったのだ。 横浜で下船予定だった乗客たちは、船内に足止めされることになり、まず厚労省の医系審議官と、横浜検疫所の検疫官らが乗船。その後、災害派遣医療チーム=DMATの面々が乗船した。 DMATは震災や水害など、災害時に発生する病人の救護にあたるボランティア医師たちである。事務局が片っ端から電話してかき集めたメンバーだった。当然、感染リスクはある。家族は反対する。活動の法的裏付けさえ満足になかった。 「俺たちがやらなければ」という使命感だけがよりどころだった。 連日、乗客・乗員数十人の感染が判明。2月17日、陽性者は99人にのぼった。 ある外国人女性は、感染が判明したものの下船することを嫌がり、駄々っ子のように床を転がった。部屋で暴れたイタリア人男性もいた。 混乱をきわめた船内で、医師たちは感染と隣あわせになりながら、困難なミッションにあたっていた。 「薬を」「情報を」焦燥を募らせる乗客の気持ちに、どう向き合えばいいのか。 やがて迎えた、大切な人との別れーー。 医師、乗客への重厚な取材で描きだす、感涙のノンフィクション。
-
-巨大地震の直後、「レスキュー機能ゼロ」という状況が訪れることを、私たちは覚悟しなければならない。行政との通信手段が断たれたとき、あるいは行政そのものが動けなくなった時に、一体誰が市民を救うのか?それは一大テーマである。荒野で、弱者、貧者に手を差し伸べられるのは誰なのか。根源的な問いを東日本大震災は突きつけた。本書が追跡したのは、そこだった。そして「レスキュー機能ゼロ」地帯に、果敢に挑んだのが一般社団法人 釜石医師会のドクターたちだった。本書はその記録である。(序章より)
-
5.0過去の風景が未来を語る。 流転の日々をその土地と人々の記憶から紡ぎ出す、 <極私的日本史>。 どうしても読んでみたかった本が目の前にある興奮。 最も誠実なインタビュアーとしてあらゆる人生の細部に光を投げかけてきた著者が とうとう語り始める、自らの人生。 在日韓国人三世として呼吸したこの国の、風と土の変遷。 ――七尾旅人(シンガーソングライター)、推薦 高度成長期に生まれ、多感な時期にバブルとその崩壊を体験し、 阪神大震災・東日本大震災という二つの巨大な天災をへて、いま 未知のウイルスに浸食されている「私たち」。 その姿がたった一人の視点と経験が浮かび上がらせる。 神戸・京都・大阪、東京を経由して、福岡・鹿児島、そして宮古島へ。 すでに行き去りし人々の息遣いと熱をまとった「私の物語」から明らかになる もう一つの日本史。 【本文より】 そこでしか語られない言葉があり、そこに吹き渡る風がある。 風土を記すとは、表に現れないところを感じることではないか。 ――そんな想像を手掛かりに私が暮らした、歩いた土地について記してみたい。 【目次】 第1章……神戸編 1:神戸、1975年 2:あちらとこちら、1975年 3:阪神間モダニズム 4:モロゾフとコスモポリタン、1984年 5:震災、1995年 第2章……京都編 1:洛中洛外 2:路地 3:ソウル 4:巫祝 第3章……大阪編 1:大阪との邂逅、1989年 2:鶴橋 3:彼女の口の達者さ 第4章……東京編 1:東京、1994年 2:大山ハッピーロード 3:別離、1995年 4:歌舞伎町、2002年 5:千駄木、感情教育の始まり 6:2011年3月11日 第5章……福岡そして鹿児島 1:福岡、2013年 2:メゾンプールサイド 3:本当に本当の記憶 4:鹿児島、2017年 5:永遠の今を生きる人たち 第6章……宮古島 1:宮古、2015年 2:ミャークとヤマト 3:淫蕩 終わりに
-
4.53.11からの10年、福島の詩人が詩作と対話と日々の随筆から求めたカタストロフとの対峙の記録。 東日本大震災で被災した福島の詩人は破壊への恐怖と、不条理への怒りに言葉で抗った。ツイッターから放たれた言葉は「詩の礫」と名付けられ、多くの共感を得た。あれから10年――。現在も福島に暮らし、高校教師の職と並行しながら詩人として活動する和合亮一氏はこの歳月を克明に言葉に刻んでいる。本書はその十年記の書である。2011年3月11日から10年となる今年。和合氏は1月1日から犠牲になられた方々にとって最初の祥月命日となる1月11日まで祈りのように連日の詩作を試みた。第一章の「貝殻詩篇」はその結実である。10年の歳月を、その折々の出来事と思いの変遷を綴ったエッセイ集成「十記」。ASIAN KUN-FU GENERATIONの後藤正文氏批評家の若松英輔氏と共に『詩の礫』がこの歳月に何をもたらしたのかを語る「対話篇」。そして「おわりに」のかわりに書き下ろされた新作詩「OVER」を収録。和合氏の言葉は、被災したまち、そしてこの世界の未だ来たらぬ未来に向けて放たれた光の矢となる――。 <目次> はじめに 第一章 貝殻詩篇 第二章 対話篇 後藤正文氏(ASIAN KUN-FU GENERATION) 時代の異常な速度感から外れてみる 第三章 十年記 第四章 対話篇 若松英輔氏(批評家) 死者と共に在ることが未来をつくる OVER (「おわりに」にかえて)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 第2号 地震・噴火と防災 最先端のテーマを深掘りし、科学的な思考力を身につける「今解き教室サイエンス」。 今号のテーマは「地震・噴火と防災」です。 日本は大きな地震や噴火に繰り返し見舞われてきた災害列島ともいえる国です。 地震や噴火が起こるメカニズムについて報道写真や豊富なビジュアルを使って解説します。 災害から身を守る防災知識についても学びます。 <目次> ●最新トピックス 東日本大震災から9年/ 【緊急ニュース特集】日本でも感染拡大 新型コロナウイルスの脅威/人間を脅かす様々な感染症/ ついに証明された 数学の超難問「ABC予想」/アメリカ 9年ぶりの有人宇宙飛行 スペースX新型機で/地球サイズの系外惑星発見 水も存在か?/富士山大噴火で首都圏は?/スカイツリーの上と下 時間の流れが違います!/KAGRAで重力波の観測開始/アメリカ国防総省が「UFO映像?」を公開 ●報道写真 災害列島に生きる ●MANGAdeSCIENCE まずは日常備蓄から ●記者の視点 繰り返されてきた噴火と地震 ●図解でなぞとき! 日本列島付近の地震のしくみ 噴火はこうして起こる ●サイエンス英傑伝 第2回 杉田玄白 ●ノーベルの遺言 第2回 核をめぐるノーベル賞 ●ミュージアムガイド 災害の特徴と防災技術を学ぼう! ●親子で実験工作教室 もしもの時に役立つ防災グッズを作ろう! ●JSEC OB・OG紹介 発光バクテリアを研究 ●キーワード 地震・噴火・防災に関する重要語句 ●今解きサイエンス検定 学んだことを振り返って、答えてみよう
-
4.0■ネガティブな思いに囚われた、すべての人の処方箋 本書は2012年に刊行され、東日本大震災(2011年3月11日)で傷ついた多くの人々の心を救った 5万部超のロングセラー『「イヤな気持ち」を消す技術』のポケット版です 現在、新型コロナウイルスが引き起こした世界規模のパンデミックによる社会不安、 それに伴う経済的な不況、社会の混乱、人心の分断、 フェイクニュース、陰謀論…われわれを取り巻く世界はさまざまなネガティブな事象によって、日々不安が絶えません。 ■そんな今こそ求められているのが、科学的エビデンスに基づいた冷静な判断 過去の記憶に囚われることのない自由な生き方です。 本書『「イヤな記憶」を消す技術』はそんな生き方を実現するための最強のガイドといえます。 本書は、最先端の科学的知見をもとに「悩み・不安の正体」を記憶と脳の関係で解き明かします。 さらには、脳の仕組みとその特性を利用して、 「どうすればイヤな記憶を忘れることが出来るのか」について具体的に示した画期的な書です。 これを読めば、ネガティブな情動に囚われずに生きていくことができるようになります。 ■本書の内容 ・再版にあたって ・はじめに ・第1章 なぜイヤな記憶ばかりが甦るのか ・第2章 記憶とは何か。それとどうつき合っていくか ・第3章 その「自我」があなたを不幸にする ・第4章 悲惨な体験をトラウマにしない ・第5章 うつ病は一瞬で治る ・第6章 イヤな気持ちから自分を解放するために
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書で推奨する副業は、「幅業」「副業」「複業」ですが本書では一般的な表現として「副業」と表現しています。 筆者は、作業療法士ですが、新卒で就職した直後から、副業を始めました。筆者が作業療法士になったのは1998 年で、当時は作業療法士が絶対的に不足していた時代でした。最初は、病院勤務をしながら非常勤で他の病院や介護施設で働いていました。さらに、養成校の教員として転職してからは、週4 日勤務であったため、平日の1 日と土日を使って、同じように非常勤として働いていました。そして、経験を重ねるうちに、徐々に非常勤先では、仕事の役割が、現場のマンパワーから指導的立場に変わり、最初は、リハビリ部門のみの指導でしたが、徐々に、全病院、全施設への指導や管理職への指導を依頼されるようになり、最終的にその経験をいかして、経営コンサルタントとして34 歳で起業しました。 本格的に経営コンサルティングを始めたのは30 歳の時で、この時に個人事業主として届け出ました。専門学校の教員が本業で、非常勤先で「副業」を行い、その「副業」が徐々にパラレル・キャリアとしての「複業」へと変化しました。 本書では、筆者の経験やそのなかでの思考軸、判断軸の元となった基礎知識を多く入れています。ただし、読者の皆さんに、「副業をするべきだ」と押し付けるつもりはありません。今の病院や介護施設でそのまま働く、もしくは、独立起業するなど働き方は自由であり、これらすべて優劣をつけるものではありません。一番、重要なのは、どの立場においても「自分らしく働くこと」です。 ここ数年、大手企業は、すごいスピードで副業を認めるようになってきました。これは、まさに終身雇用制度の終焉です。医療・介護業界も別の話ではありません。特に医療・介護業界は、病院数、介護施設数ともに効率化、適正化の政策のもとに、徐々に淘汰が進んでいます さらに、2020 年から始まったコロナ禍です。私たちの生き方、働き方は大きく変化しました。新型コロナウイルス感染症患者対応で医療機関がひっ迫する一方で、多くの医療機関では、病床稼働率や外来患者が大幅に減少しました。また、介護施設も同様に入所・通所・訪問ともに減少しました。なかには、新型コロナウイルスの影響で赤字倒産したところもあります。 「すでに医療・介護業界は、一生安泰な業界はない」ということです。これから数年はウィズコロナ時代が継続するでしょう。その間にもリーマンショックのような大不況、東日本大震災のような自然災害、そして、新型コロナウイルス以外の新たな感染症も出てくるかも知れません。そうなった時、あなたはどうしますか。自分の働き方を考えず、ただ、業界や組織のなかで、びくびくしながら働くのか、もしくは、自分でキャリア・デザイン戦略を持ち、自分らしく働くのか。筆者は、このような時代だからこそ、本書のようなキャリア・デザインに関する考え方が重要であると考えています。 本書は、シリーズの第1 弾としてキャリア・デザインのなかでも「副業」をテーマにしました。副業を「する・しない」に限らず、副業という働き方を知ることはこれからのキャリア・デザインによっては非常に大切なことです。また、今回は、副業を成功させるためのワークもたくさん用意しています。ぜひ、楽しみながらワークに取り組んでください。 本書によって、副業にチャレンジし、素晴らしい働き方を実践するが1 人でもいれば幸いです。
-
-世界支配を目論む闇の秘密結社イルミナティの正体とは、いったい何者なのか。彼らは聖書の預言を利用して、さまざまな陰謀を仕掛けてくる。東日本大震災や福島第一原発事故の裏には何があったのか。ふたりが独自に入手した情報と証言をもとに真相を暴露する。
-
-1975年以降に生まれてきた多くの若者たちは、インディゴブルーの魂を持ち、古く、使いものにならなくなった既存の概念や社会通念、社会常識、社会システムを破壊し、愛と喜び、調和を基盤にした新しい社会を創造する使命を持って生まれてきています。 彼らはインディゴチルドレンと呼ばれ、今までの社会にない、まったく新しい視点や発想を携えています。 この本は、インディゴの一人である著者が、新しい視点とユニークな発想で、日常と世界をつぶやいたエッセイ集で、18編のエッセイが収録されており、2011年に出版されたエッセイ集『インディゴのつぶやき』(日本文学館)の新装版です。 今では古くなってしまった時事的なエッセイを削除し、加筆・修正を加え、新たに未発表エッセイ1編を追加しました。 世界と社会と日常に、彩りと希望を見出すことのできるエッセイ集です。 ●本の内容 初代若乃花 花田勝治さんの言葉 / UFO(未確認飛行物体)と黒船 / 戦争と平和について / お金と人類の意識について / 民主主義と自立について / アラーキーの写真に生と死、光と闇の完全性をみる / 学校教育について / 「知っている」ということについて / 東日本大震災と新しい社会 / 東日本大震災と人災 / 新卒一括採用について / 好きなことを仕事にする / 競争について / 信じることについて / 客観はありえない / 発達障害を排除するな / 遊びについて / 戦うということ
-
-ブログ、SNSなどの浸透にしたがって、これまでとまったく異なったコミュニケーションをしている人が増えている。インターネットを通じて知り合い、意気投合し、恋愛関係にいたる。こうした行動は現実の人間関係の希薄さの表れなのか。また、匿名メディアである電脳空間は危険な犯罪の温床なのか。ウェブを介した恋愛の実際やネット発の純愛ブームの背景を取材。同時に、新ツールがもたらした新時代の恋愛観の本質に迫るルポルタージュ。 プロローグ 本当の恋を探して 第1章 ウェブで出会うということ 第2章 恋愛日記を綴る 第3章 生きにくさからの解放 エピローグ ウェブのアドバンテージ ●渋井哲也(しぶい・てつや) フリーライター。ノンフィクション作家。中央⼤学⾮常勤講師。 栃⽊県⽣まれ。東洋⼤学法学部卒。東洋⼤学⼤学院⽂学研究科教育学専攻博⼠前期課程修了。教育学修⼠。家出、援助交際、摂⾷障害の取材の過程で「⽣きづらさ」という⾔葉を聞いて以来、子ども・若者の⽣きづらさ、⾃殺、⾃傷⾏為、依存症などに関⼼を持つ。そのほか、いじめや不適切指導による自殺(指導死)などの教育問題、ネット・コミュニケーション、ネット犯罪、ネット自殺、東⽇本⼤震災やそれに伴う原発事故・避難⽣活の取材を重ねる。週刊女性の取材班として「グッドプレス賞」(依存症問題の正しい報道を求めるネットワーク主催、雑誌部門、2020年度)受賞、『ルポ自殺 生きづらさの先にあるのか』(河出新書)で「貧困ジャーナリズム賞」(反貧困ネットワーク主催、2022)を受賞。
-
4.0【第37回講談社ノンフィクション賞、第58回日本ジャーナリスト会議賞(JCJ賞)受賞作】東日本大震災、福島第一原発事故で被曝地となった福島。警戒区域内の家畜を殺処分するよう政府は指示を出した。しかし、自らの賠償金や慰謝料をつぎ込んでまで、被曝した牛たちの「生きる意味」を見出し、抗い続けた牛飼いたちがいた。牛たちの営みはやがて大地を癒していく―。そう信じた彼らの闘いに光を当てる、忘れてはならない真実の記録。
-
-宇宙人はずっとあなたと繋がる日を待っています! 「同じ使命の宇宙人をチェック」「宇宙人とコンタクトする方法」「UFOに乗り込むワーク」など、新しい時代に願いを叶えて、幸せに生きる方法を解説! あなたは、どの宇宙人? 色でわかる! あなたと同じソウルグループの宇宙人 ・ピンク→マリゼアンの宇宙人 ・紫色→プレアデスの宇宙人 ・シルバー→ヘンデリックの宇宙人 ・レインボーカラー→アンジュリミナルの宇宙人 ・エメラルドグリーン→アークトゥルスの宇宙人……etc. 服部エリー(浮舟エリー)アカシックリーダー 大学卒業後、OLや派遣社員など職を転々としていたが、2011年の東日本大震災後に突然「宇宙の図書館」といわれるアカシックレコードと繋がり、個人セッションやセミナーを開催し始める。また、宇宙人からのメッセージを伝えるなどの活動も通して、誰もが思いどおりの人生を生き、願いをかなえることができると発信している。
-
4.0もうこれ以上、原発に頼ることはできない!――東日本大震災により福島第一原子力発電所が起こした事故の深刻さは、これまでの原子力に依存したエネルギー政策に大転換を迫ることになった。 もはや地球レベルの問題になりつつあるエネルギー不足の問題は、宇宙に太陽光発電所(SPS)を建設することで解決できる。 SPSとは、宇宙空間に超大型の太陽電池パネルを広げ、太陽光発電によって得られる電力をマイクロ波に変換して地球に届けるもので、将来的には人類の生存に向けた道を宇宙に模索するというもの。 ――そして日本は、このSPSの分野で、今こそ世界をリードすべきなのだ。 本書では、長年、国内外の多くのプロジェクトを導いてきたSPS研究の第一人者が、その可能性と希望にあふれる未来について語る。 日本が力強く立ち直り、生き残りを賭けて宇宙という新領域に大きな一歩を踏み出すために、いま必読の書!【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
-今の「不安感」を解くカギは、100年前の「言葉」にあった! 新型コロナウイルスの流行、東日本大震災、ウクライナ侵攻…など、人々を「鬱屈」とさせる未曾有の混乱に見舞われている現代。 我々は、内面に生じるモヤモヤした感情とどう付き合うべきか。 そのヒントは、100年前にあった! 本書では、スペイン風邪や関東大震災、そして第一次世界大戦の時代における、「災後」の言語空間に着目。 夏目漱石や太宰治、芥川龍之介、田山花袋などの有名文学作品をはじめ、雑誌、辞書、詩といった膨大な資料を引きながら、「鬱屈」の時代を読み解く。
-
3.0
-
-昨日の自分と今日の自分も違うのに「人と違ってたらどうしよう…」とか悩む必要なくない? ポジティブ論が止まらない19歳・総フォロワー60万人(2020年12月時点)の佐藤そるとの初エッセイ。 【本文より】 わいの地元は福島県郡山市。小学3年生の頃、東日本大震災があって世間は大変な騒ぎ。住んでいた場所が流されることもなく、身近にいる人が亡くなることもなかった。でも、そのあと福島県では原発の問題が発生。健康被害を心配する友だちの両親は引っ越しという選択をする人も少なくなくて、仲良くしてた友だちは見事に福島からいなくなってしまった。 違うグループに入ってみようと思ったこともあったけど、「なんでコイツ話しかけてくんの?」みたいな空気感が漂ってきてその瞬間から、自分のためにも友だちの輪は広げておこうって思ったんだよね。いじめられたわけじゃないし、単純に「あなたは違うグループの人ね」って思われていただけ。それでもね、やっぱりひとりは辛かった。 【構成】 第1章 生まれたことすら、自分の気まぐれ 第2章 みんなと違う時代を切り抜いて生きてる 第3章 お金に自分の幸せを振り回されてたまるか 第4章 思い出のマンゴータピオカに救われて 第5章 生きてる以上嫌われるのが当たり前
-
3.0海から来た謎の男が、奇跡と愛をもたらしてゆく 『淵に立つ』でカンヌ映画祭ほか内外の絶賛を浴びた深田晃司監督が、ディーン・フジオカ主演の最新映画(5月公開)を自ら小説化! インドネシア、バンダ・アチェの浜辺に打ち上げられた、日本人らしき謎の男。 彼の正体を探る周りの人間たちの間に、波紋が広がっていく……。 2004年のスマトラ島大津波と、2011年の東日本大震災。 そして、第二次大戦中は日本の軍政下に置かれ、オランダからの独立戦争においては日本人義勇兵が支援した、インドネシアと日本の歴史上の因縁。さまざまな要素が織り込まれ、映画のストーリーをさらに発展させた力作です。
-
4.0「裏日本」の魅力満載、酒井版『陰翳礼讚』。 常に時代を先取りする話題作を刊行してきた酒井順子氏が、“控え目だけれども鋭い光を放つ”日本海側の魅力を存分に伝えるエッセイ。 経済発展=幸福と、太平洋側を「表」として走ってきた日本ですが、とくに東日本大震災以降、その構図はくずれつつあります。経済至上主義によって、私たちは、日本人にとって大切なものをたくさん失ってきたのではないかということに、多くの人が気づき始めています。 そして、その開発の手を逃れて、ひっそりとマイペースで生きてきた日本海側=「裏」には、裏だからこその日本の大切なもの=「幸せ」が、たくさん詰まっていることに、日本中を何度も旅してきた著者は魅了されました。 都道府県別幸福度ランキングでは、トップ3は福井、富山、石川の北陸三県。富山にある世界一のスタバ、日本海が必須の演歌、美人が多い秘密、谷崎潤一郎、水上勉、泉鏡花、川端康成が描いた「裏」、顔を隠す盆踊り、金箔のほとんどを生産する金沢…などなど 「裏日本」の宝ものが次々と紹介されます。「裏の幸せ」を求めて旅に出たくなるエッセイです。
-
3.5
-
-福島県南相馬市にある円明院は、 海岸からわずか500メートルほどの位置にありながら、 東日本大震災の津波が避けて無傷で残った「奇跡の寺」。 世界一のパワースポットといわれるセドナと同等か それ以上のパワーを秘めたエネルギー聖地と話題。 泉 智教住職の「運気好転講話」は、 生きて幸せになるための宗教を超越した教え。 異端児住職による、超楽しんで、超笑える「生き方指南」。 本書を読めば、エネルギーチャージできる。 円明院の奥の院で写る話題の「奇跡の光の写真」も本書に掲載。 写真を見るだけで不思議と運気が上がった、病が治った、 宝くじが当たった、奇跡が起きた、などのお礼の報告が後を絶たない。 本書を持っているだけで、運気好転、幸せになれる! 【電子特別特典付き】 電子書籍版には、本書未収録の運気好転の強力パワー入り「奇跡の光の写真」と「泉智教ご住職 直筆の護符」付き!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 19世紀の英米に生きた5人の女性詩集の再版です。初版時はフェミニズムと東日本大震災の被害者追悼がテーマとなりましたが、初版の好評を迎え、今回の再版版はより広範・世界的なロマン主義の復興祈願と重なります。 初版で試行された日本語翻訳文の七五調での翻訳はいまだに一般には受容・評価されておりませんが、ここに再版を重ね、繰り返し日本の詩歌文化の国際化を問います。
-
-東日本大震災から10年、今こそ子どもたちや多くの人に読み継がれていってほしい命と感動の実話 2011年3月11日、の日本大震災、地震と大津波が襲う中、仙台市中野栄あしぐろ保育所では保育士が必死で子どもたちを守り抜いた。マニュアルにあった園庭避難では危険と判断し2階に全員を避難させた主任、胸まで水に浸かりながら外出先から戻り、子どもたちや保育士を元気づけた所長、子どもたちを不安がらせないように必死で笑顔を作り続けた保育士たち。寒さと暗闇の中で一晩を過ごし、子どもたちは全員けが人もなく保護者のもとに戻った。日本テレビ系人気報道番組「News every.」でも特集された話題の絵本。 【著者】 あいはらひろゆき 累計発行部数220万の大人気絵本シリーズ「くまのがっこう」(ブロンズ新社)の作者であり、絵本ユニット「たあ先生」として2020年に発表した「はっはっはくしょーん」シリーズ(カドカワ)や「てあらいまんとうがいひめ」(サニーサイド)も大ヒット中。
-
5.0専門記者が解説する業界入門の決定版。 電力、ガス、石油業界の全体像が1冊でわかる!! ・国内外の最新情勢、ビジネスの仕組みがすぐにわかる! ・市場の自由化はこれからどうなる? ・主要企業25社の特徴・経営戦略を徹底分析! ・就職・転職はもちろん、市場調査などに必読の1冊! 【内容構成】 Chapter1 最新エネルギー情勢 激化するエネルギーの大競争時代/東日本大震災と原子力政策/2030年、50年に向けたエネルギー戦略 ほか Chapter2 電力業界の基礎知識 電気が家庭に届くまで/期待高まる再生可能エネルギー/コスト低減が急務/電気使用量の動向 ほか Chapter3 電力業界の主要企業 東京電力ホールディングス/関西電力/中部電力/東北電力/九州電力/中国電力/北海道電力/四国電力/北陸電力/沖縄電力 ほか Chapter4 ガス業界の基礎知識 暮らしを支えるガス/多様化するガスの使い道/局所集中の都市ガス導管網 ほか Chapter5 ガス業界の主要企業 東京ガス/大阪ガス/東邦ガス、西部ガス Chapter6 石油業界の基礎知識 生活に浸透する石油/地下に眠る重要資源/増加が続く埋蔵量と生産量 ほか Chapter7 石油業界の主要企業 JXTGエネルギー(JXTGホールディングス)/出光興産/コスモ石油/昭和シェル石油/国際石油開発帝石/石油資源開発 Chapter8 世界の最新エネルギー動向 アメリカ/中国/インド/ロシア/欧州諸国/東南アジア・東アジア/中東諸国
-
-元 山形大学長・医学部長の回想録。 児童養護施設「光の子どもの家」の広報誌『光の子』に2007年から2022年まで掲載された連載を基にまとめたエッセイ。現在は、老健施設の理事長を務めながら、自らの老いや施設での看取りなど、日々の気付きや自己や社会へのまなざしが丁寧につづられる。 2007年に山形大学学長を辞した後、70歳の時に研究等で交流があった南米の国、パラグアイに国際協力事業団(JICA)シニアボランティアとして参加。かの国の人たちと心を通い合わせた様子を丁寧に描写。また、インターネットにどっぷりとつかり、東日本大震災後はフェイスブックを活用して子ども支援プロジェクトを立ち上げたことなど、さまざまな活動に取り組んできた著者の軌跡。
-
-今後、海外産の液化天然ガス(LNG)を乗せたタンカーが続々と日本にやって来る。電力・ガス会社が東日本大震災後に先を争って調達したものだ。しかし、米国からの本格輸入が始まったばかりだというのに、早くもLNG貯蔵量の余剰が懸念されている。電力・ガス業界を襲うLNGパニックの真相に切り込んだ。 『週刊ダイヤモンド』(2018年6月2日号)の特集2を電子書籍化したものです。 雑誌のほかのコンテンツは含まれません。 *本誌の電子版も販売しています(最新号は毎週月曜日配信)。 詳しくは「週刊ダイヤモンド」で検索ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2011年3月の東日本大震災発生の3カ月後に発行された『LPガス販売事業者の危機管理入門』を、その後の国内で多発した大規模な風水害や今回のコロナ・パンデミックを踏まえ、改定版を発行しました。LPガス販売事業者のBCPマニュアル作成資料も掲載。
-
5.0「震災→恐慌→五輪→戦争」繰り返す悪夢のシナリオ 世界は「90年×2=180年」サイクルで動く! 「大東亜戦争=日本の属国化」の歴史が、再び始まる! 「関東大震災→1940年東京五輪中止→太平洋戦争」と「東日本大震災→2020年東京五輪→北朝鮮危機」の驚くべき符合とは。 「英国のEU離脱」と「米国のトランプ勝利」をたんなるポピュリズムとして捉えるのは間違いだ。なぜなら、「欧州ロスチャイルド家」と「米国ロックフェラー家」が、それぞれの背後でまったく異なる動きを見せているからだ。 そして近年、不気味さが際立つロシアの目的とは。「世界の奥の院」に操られた2020年東京五輪をめぐる暗闘を透視する。
-
-2011年の東日本大震災から、早いもので10年が経過している。 災害大国である日本は、今も予報技術の開発や防災設備の建設に巨額の予算を投じているが、天災はそうした努力を易々と凌駕する規模で人間をいつも圧倒するのだ。 ハードの力で災害に対抗するには限界がある。ならば、情報の力でその脅威に対抗できないか。それが私の考え方である。 (「はじめに」より抜粋) -------------------------------- 日本は元来、自然災害の多い国であるが、近年は気候変動の影響と思われる災害がこれまで以上に頻発するようになってきた。 また、それに備える防災という分野は、長らく土木や建設業が大部分を担ってきた。しかし、想定外の被害を減らすために今後より重要になってくるのは、リアルタイムに状況を見える化し予測することである。 そんな新しい防災のカタチをAIによって実現しようとしているのが、スタートアップ、スペクティだ。SNSの投稿などからAIが情報を精査・解析し、「予測する防災」を可能にしたサービスを提供している。それは現在、全国47都道府県の防災部門の8割で導入され、民間企業でも約500社が採用するまでにいたっている。 本書では、「防災」という珍しい領域で事業を成長させてきた企業の取り組みを描くとともに、「防災×AI」で何ができるのか、何をするべきなのか、その現状と未来の防災の可能性について展望する。
-
-
-
4.0
-
-1994年にノーベル文学賞を受賞した大江健三郎は、その受賞後に数々の傑作・問題作を書きつづけた、世界的に稀有な小説家だが、とくに2000年の『取り替え子』から東日本大震災を経て2013年に完成した『晩年様式集』へと至る「晩年の仕事」(レイト・ワーク)は、透徹した知性で時代を見据えた予言的で豊饒な作品群である。この、さまざまな文学的技巧やたくらみに満ちた難解な作品群を、ときにセルバンテス、フローベール、プルースト、ジョイス、エリオット、ナボコフ、渡辺一夫、埴谷雄高、大岡昇平らの作品や言葉に触発され、ときに大江の盟友サイードとの友情と文学に導かれながら繙いていく。大江健三郎の真の偉大さを明かす、力作評論。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 メディアでは触れられない復興現場の「今」を住民目線で記録した写真集 ◆概要 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で甚大な被害を受けた大槌町。 その大槌町の中心部である町方地区の復興過程を390枚の写真で記録した写真集です。 ◆こんな人にお勧め ・東日本大震災の復興の「今」を知りたい人に ・大槌町や三陸に住んでいた人に、大槌町に関わった人に ・まちづくりを知りたい人に ◆収録内容 2015年度の写真を中心に構成しています。 写真そのものは2014年1月から2016年3月までを収録していますが、2014年1月から2015年3月までの写真は多くはありません。 ※本作は盛り土工事中心ですが、同シリーズの2016年度版は宅地整備が中心になっています ・町方地区(上町、本町、末広町、大町および周辺)の復興現場写真…390枚 そのうち2014年1月~2015年3月の写真…62枚 ・現場のスナップ写真、大槌町の風景写真…34枚 ・すべての写真にキャプションつき
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 メディアでは触れられない復興現場の「今」を住民目線で記録した写真集 ◆概要 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で甚大な被害を受けた大槌町。 その大槌町の中心部である町方地区の復興過程を754枚の写真で記録した写真集です。 ◆こんな人にお勧め ・東日本大震災の復興の「今」を知りたい人に ・大槌町に住んでいた人に、大槌町に関わった人に ・まちづくりを知りたい人に ◆収録内容 2017年度中に撮影した写真から537枚を選出し、収録しています。 残りの217枚については、JR山田線の復旧工事の様子、おしゃっちの上棟式、2015年からの定点観測などの写真です。 ◆注意 これは紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。 文字だけを拡大する、引用することなどはできません。 また見開きでの閲覧を前提としているページが含まれるため、タブレット、PCブラウザなどでの閲覧を推奨しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 メディアでは触れられない復興現場の「今」を住民目線で記録した写真集 ◆概要 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で甚大な被害を受けた大槌町。 その大槌町の中心部である町方地区の復興過程を460枚の写真で記録した写真集です。 ◆こんな人にお勧め ・東日本大震災の復興の「今」を知りたい人に ・大槌町に住んでいた人に、大槌町に関わった人に ・まちづくりを知りたい人に ◆収録内容 2016年度中に撮影したおよそ4000枚の写真から460枚を選出し、収録しています。 「今を伝える」というコンセプトで作成しているため、2015年度以前の写真は掲載していません。 同シリーズの「2015」をお求めください。 ※2015年度は盛り土工事中心、2016年度は宅地整備が中心の写真になっています ・町方地区(上町、本町、末広町、大町および周辺)の復興現場写真…458枚 ・現場のスナップ写真、大槌町の風景写真…25枚 ・すべての写真にキャプションつき ◆注意 これは紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。 文字だけを拡大する、引用することなどはできません。 また見開きでの閲覧を前提としているページが含まれるため、タブレット、PCブラウザなどでの閲覧を推奨しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆概要 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で甚大な被害を受けた大槌町。 その大槌町の中心部である町方地区の復興過程を128枚の写真で記録した写真集です。 ◆こんな人にお勧め ・東日本大震災の復興の「今」を知りたい人に ・大槌町に住んでいた人に、大槌町に関わった人に ・まちづくりを知りたい人に ◆収録内容 2018年度の末、2019年1月から3月までの出来事、大槌ICの開通、大槌駅開業、三陸鉄道リアス線の開業(旧JR山田線の復旧)、2019年4月の大槌町町方地区の景色、計128枚。 岩手県沿岸南部、宮古市から陸前高田市までの名勝や景色を51枚。 ◆注意 これは紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。 文字だけを拡大する、引用することなどはできません。 また見開きでの閲覧を前提としているページが含まれるため、タブレット、PCブラウザなどでの閲覧を推奨しています。
-
5.0
-
4.3沖縄の戦後65年余を知らずに現代日本は語れない。歴史的な政権交代と鳩山民主党による普天間飛行場移設問題の裏切り、「琉球処分」後に王朝尚家を見舞った数奇な運命、尖閣諸島の秘められた歴史、沖縄の戦後そのものの人生を生きたヒットマンの悲しい最期など……東日本大震災後の沖縄の今日を視座に入れながら、大幅加筆200枚。沖縄戦後史を抉る渾身のルポルタージュ。
-
-歌舞伎台本、オペラ台本、映画台本、そして小説。コンテンツの面白さを満喫する多彩な台本を集めて 歌舞伎台本で、東日本大震災に取材した「陸奥下絡繰白波」、同じく未解決の東電女子社員殺人事件に取材した「紅地蔵夜鷹絵暦」。シャカ族殲滅という釈尊晩年の悲劇をオペラ化した「ビルーダカ〜シャカ国を滅ぼした哀しみの王」。防衛大学校に落語部を、と奮闘する防衛大女子学生を描く映画台本「武人娘あすか〜噺版・防衛大学校物語」。国際法を無視した中国の海洋最前線基地へ果敢に殴り込むアニメキャラの水着美少女たちを描く短編小説「南シナ海マリン・エンジェル作戦」。以上、ギリギリのテーマ設定で上演が危ぶまれる5篇を収録。 【目次】 劇作集刊行にあたって 陸奥下絡繰白浪 ビルーダカ〜シャカ国を滅ぼした 哀しみの王 武人娘あすか〜噺版・防衛大学校物語〜 紅地蔵夜鷹絵暦 怪談・東電女子社員殺人事件 南シナ海マリン・エンジェル作戦 【著者】 小田切しん平 1955年愛知県生。私大の文学部仏文科卒。卒論は後にノーベル賞受賞のル・クレジオ。広告会社、テレビ番組制作会社、クラシック音楽事務所を経て、21世紀からライター業。著書「東京パルチザン」「世界街頭広告図鑑」「老犬コロが教えてくれた幸福」、翻訳各種(英、仏、伊)。
-
4.4【スーパーボランティア 尾畠さんがすべて語った!】 日本を元気にする82歳の人生とことば 2018年、行方不明だった2歳児を発見し、一躍時の人となった尾畠さん。「スーパーボランティア」はその年の流行語大賞にもなった。尾畠さんとは一体どんな人物なのか。著者が3年にわたる交流を重ねると、意外な素顔が明らかに。毎朝8キロ走り、家の庭に生えた雑草を食べ、ここ十数年は病気知らず、全国の災害地を飛び回り、毎月年金5万5千円で暮らす――超元気な尾畠さんの知られざる人生と胸に残ることば。100枚近くのフルカラー写真も掲載! 目次 はじめに 序章 奇妙な生活 第1章 最後のイワシ(幼少期編) 第2章 包丁と足袋(修業と独立編) 第3章 抱き合ってな泣いた日(第二の人生編) 第4章 奮闘500日(東日本大震災編) 第5章 守り抜いた約束(2歳救出編) 第6章 土嚢とスコップ(広島・呉ボランティア編) 第7章 眠れない日々(東海道大騒動編) 第8章 愛しき由布岳(山岳ボランティア編) 終章 母なる太陽 おわりに
-
-400件のトピックで30年分の人やモノ、出来事をまとめて総決算! 目次 永久保存版 【徹底図解】平成大合併日本地図 図解で振り返る 激動の平成史 平成元年 (1989) 楽しい(?)世紀末がやってきた 平成が幕開け! 平成2年 (1990) 春よ来い! 第1回大学入試センター試験始まる 平成3年 (1991) 湾岸戦争、バブル崩壊…… 混迷の時代が始まった? 平成4年 (1992) PKO協力法成立! 自衛隊、災害派遣はOKなの? 平成5年 (1993) Jリーグ開幕に日本列島沸く! そしてドーハの悲劇へ 平成6年 (1994) 就職氷河期に突入! 向井千秋さん、アジア初の女性宇宙飛行士に 平成7年 (1995) 阪神・淡路大震災発生、“がんばろうKOBE”で日本がひとつに 【コラム】1 エコカーの変遷 平成8年 (1996) 有森裕子2大会連続メダル&メークドラマに沸いた日本列島 平成9年 (1997) 山一證券自主廃業、援助交際…… 光と影が交錯する時代 平成10年 (1998) 日本列島総不況のなか、日の丸飛行隊に日本中が感動した 平成11年 (1999) 東海村で国内初の臨界事故、金融業界再編とリストラの波 平成12年 (2000) あけましてミレニアム! 新時代は混迷の船出となるのか? 【コラム】2 どうする? “老老介護”“認認介護” 平成13年 (2001) 小泉旋風とアメリカ同時多発テロ事件 激動の一年間を駆け抜けた 平成14年 (2002) 拉致問題に光明 平成15年 (2003) 大義なき戦い? 混迷するイラク戦争と自衛隊派遣 平成16年 (2004) 暑いぞ! 熊谷 全国的猛暑で日本列島、夏バテ気味? 平成17年 (2005) 郵政解散から日本列島選挙一色へ! 変革の時を迎える 平成18年 (2006) 世界中が注目した! ワールドベースボールクラシック第1回大会 平成19年 (2007) 年金記録問題発覚! 自民党歴史的大敗で政局が動く 平成20年 (2008) リーマン・ショック 米国過去最大の破綻に世界が揺れた 【コラム】3 情報社会を超える“Society 5.0” 平成21年 (2009) 民主党の圧勝で政権交代! 波乱の2010年代へ向けて前進 平成22年 (2010) おかえりなさい、はやぶさ 宇宙の神秘に思いを馳せて 平成23年 (2011) 東日本大震災、激動の世界情勢を読み解く 平成24年 (2012) 安倍首相、再登板! 「アベノミクス」3本の矢でデフレ脱却? 平成25年 (2013) 秘密保護法案に反対続出! 希望と不安が交錯した波乱の年 平成26年 (2014) 集団的自衛権、消費税8%…… 「強い日本」とは何か、模索の時代へ 平成27年 (2015) 北陸新幹線開業、ラグビー日本代表…… 安保法制を巡って列島紛糾 平成28年 (2016) 熊本地震、米大統領広島訪問…… 天皇陛下「生前退位」へ 平成29年 (2017) 北朝鮮の核実験、トランプ大統領来日…… 大転換期の世界情勢に注目 平成30年 (2018) 北海道胆振東部地震、噴火、豪雨…… 自然災害への対応が迫られた 奥付 裏表紙
-
-日本中が歓喜に沸き立った東京オリンピックの開催。でも、熱に浮かれたようなオリンピック報道の影で、それまで新聞紙面をにぎわしていた東京直下地震の話も、南海トラフの報道もいっさいが消えてしまった。状況は何も変わっていないのに!だが、安倍内閣の参与・藤井聡京都大学名誉教授自身が警告するように2020年までに首都直下地震の起きる可能性は100%なのだ!! 我々はどうすればいいのか?座して死を待つな! 本書は「海岸」から「森林」への文明転回を提示する警告と希望の書である。 M7級の首都直下地震が、今後7年以内に起きる! ◎ 東京はロスの7倍強、ニューヨークの17倍、パリの28倍も危険な都市なのだ。 ◎ 東京は、直下型地震に加えて、首都周辺地域を震源とする巨大地震に重層的に直撃される運命にある ◎ 「震度7」で確実に崩壊するのが「首都高」だ。 ◎ 都心を南北に3本の活断層が発見された。 ◎ 山手線が走る場所は、震度6強エリアに、まるごと包まれる ◎ 震度7で、トンネルが裂断する。外堀から大量に水が怒濤のように流入する。 ◎ 海抜ゼロメートルの地下鉄駅は、入口に「止水板」を設置している。しかし、数メートルの津波にはまったく無力だ。 ◎ 東京は利根川などの砂が滞積した沖積平野に位置する。“液体化”した地盤が、横向きに流れ出す。1964年、新潟地震では地盤が最大7メートルも動いた記録がある。 ◎ 「1メートルの津波でも死者が出る」さらに、ベイエリア、都心部は人口密度がけたはずれ。危険度は東北沿岸の比ではない。 ◎ 葛飾区、江東区など下町のほとんどは海抜ゼロメートル地帯どころか海抜マイナス地帯なのだ。 ◎ 「日本のビル鉄骨溶接の9割以上が手抜き」と言うから唖然。「手抜き疑惑のビルは東京だけで9万棟にも上る ◎ 最新研究では「M10超巨大地震もありうる」。地球上でありえる最大級地震M10とは、東日本大震災M9の32倍のエネルギーをもつ。 ◎ 東京下町では「震度六強」で木造93%倒壊! 周辺は一瞬にして瓦礫と化す。 ◎ 大震災では街全体が燃えるのだ。立ち上がる煙は、致死量の青酸ガスやホスゲンを含む。 ◎ 関東大震災では被服廠広場だけで3万8000人も命を落した。火災旋風の炎熱地獄で焼け死んだのだ。…etc
-
4.3新しい光に満ちた第五歌集。 「電信柱抜けそうなほど揺れていた」震度7とはそういうことか 空腹を訴える子と手をつなぐ百円あれどおにぎりあらず 子を連れて西へ西へと逃げてゆく愚かな母と言うならば言え 東日本大震災発生当時、東京にいた著者が仙台の家に帰れたのは、4日後だった。余震と原発事故が落ち着くまでと思い、翌朝息子の手をひいて、西へ向かう。 醤油さし買おうと思うこの部屋にもう少し長く住む予感して 第三者的には「軟禁」とも言える車を持たぬ離島の暮らし 「オレが今マリオなんだよ」島に来て子はゲーム機に触れなくなりぬ 紆余曲折ののち、沖縄の石垣島に住むことになった親子。豊かな自然、地域の人々との密な触れ合いは、様々な変化をもたらした。 愛、発見、出会い――。かけがえのない石垣島の日々から生まれた第五歌集。 解説・松村由利子(歌人)
-
3.6
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2016年、ソロ・デビュー40周年を迎えた浜田省吾。1983年の『ON THE ROAD ’83』から、2016年の『ON THE ROAD 2016 “Journey of a Songwriter” since 1976』まで、彼のツアーを彩ってきた歴代のオフィシャル・ツアー・パンフレットが電子書籍となって完全復刻。デジタル・リマスタリングによって美しくなった写真の数々が、あなたの手元で鮮やかによみがえります。 2010年に発売されたベスト盤「The Best of Shogo Hamada vol.3 The Last Weekend」にちなみ命名された『ON THE ROAD 2011 “The Last Weekend”』。当初ソロ・デビュー35周年を記念したツアーという位置づけでもあったが、同年3月に発生した東日本大震災によりその意味合いは特別なものに。チャリティ公演も含めて総動員数約35万人という過去最大規模のツアーとなった。本書はツアーに先駆けて北の地で撮り下ろされた写真のほか、田家秀樹氏による楽曲解説等も掲載。ツアーパンフレットとしてだけでなく、詩集のようにも楽しめる大ボリュームの全105ページ。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2016年、ソロ・デビュー40周年を迎えた浜田省吾。1983年の『ON THE ROAD ’83』から、2016年の『ON THE ROAD 2016 “Journey of a Songwriter” since 1976』まで、彼のツアーを彩ってきた歴代のオフィシャル・ツアー・パンフレットが電子書籍となって完全復刻。デジタル・リマスタリングによって美しくなった写真の数々が、あなたの手元で鮮やかによみがえります。 東日本大震災に見舞われた2011年に決行された全国ツアー『ON THE ROAD 2011 “The Last Weekend”』の模様を中心に構成され、インターネット限定で販売されたツアー・ドキュメント・ブック。リハーサル風景やステージ写真だけでなく、ツアーで流された映像の撮影現場の様子や被災地を訪れた際のオフショットなども多数掲載。また当時ツアー・サイトにアップされた各公演ごとの浜田省吾からのメッセージも収録。史実としても持っておきたい1冊(全109ページ)。
-
-“呪い”シリーズ書き下ろし最新刊! 話題沸騰!「呪い面」の後日談も収録。怨念、祟り、神隠し、妖怪…。異界へと通じる扉はあなたのすぐ横で口を開けている――。 【内容紹介】徳島のある通りを深夜、黒い影が横切り…「通るもの」。東日本大震災の直後、前方から歩いてきた女の顔には…「牛女、東北に現る」。自衛隊のある基地に深夜響きわたる足音の正体は…「自衛隊の娯楽室」。心霊スポット・犬鳴峠に向かった人気力士の身に異変が…「力士と林檎と犬鳴峠」。怨霊、英霊、先祖の霊…あらゆる霊が蠢く恐怖譚全47編を、不思議研究の第一人者・山口敏太郎が厳選! 日常のすぐ横にある異界にようこそ。
-
3.0地球の2/3を占める海の底に広がる世界――海底。そこに穴を掘って暮らすのがゴカイやユムシ、シャコなどの底生生物だ。彼らは常に海底下に潜って隠れているうえ、多くは体が柔らかく、化石として残りにくいため、近年までその生態は謎につつまれてきた。そこで生痕、つまり「巣穴」を解析するアプローチで彼らの“隠された行動”を明らかにしてきたのが、産業技術総合研究所地質調査総合センターの清家研究員だ。サーフィンのごとく波乗りして移動する底生生物とは? 水深1000mを超える海底の巣穴に樹脂を流し込んで判明した事実とは? 東日本大震災前後で三陸沖海底の生態系に起きた激変とは? 世界初となる発見を重ね、文部科学大臣表彰・若手科学者賞を受賞した氏が驚くべき、そしてどこかユーモラスな底生生物の生態と海底の神秘を綴る。この世界は、彼らの巣穴で満ちている!
-
-中国輸入を始めるのなら最初に読むべき本 ■ローン地獄の会社員が、起業してわずか3年で1億円を手にしたノウハウを大公開。 ■現在の世界情勢は非常に不安定で楽観視できない状況です。 ■そんな今、この「改訂版」を出版して伝えたいこと。 【目次】 第1章 なぜ中国輸入ビジネスは「金のタマゴ」を産むのか 第2章 中国輸入ビジネスほど稼ぎやすいビジネスはない 第3章 商品リサーチで「金のタマゴ」を産む商品を見つけよう 第4章 まずはこれだけ! 誰でもできる自分ブランドのつくり方 第5章 輸入代行業者に初めての発注をしよう! 第6章 自分ブランド商品をAmazonに出品しよう! 第7章 中国輸入ビジネス成功の10か条 【著者】 根宜正貴 1979年愛知県生まれ。年商1億円の中国輸入ビジネス・メーカーオーナー。東日本大震災を機にビジネスを学び、2012年、パソコン1台で仕事のあとの空き時間(1日1~3時間)のみで中国輸入ビジネスを開始。1年目から自分ブランドでの販売を始め、年商1億円を達成。確実に売れるブランドを生み出すための法則を体系化し、売れるブランドのリサーチツール「あまログ」を自社開発。コンサルティングを通じて延べ1,000名以上の指導実績がある
-
3.0芥川賞受賞の鮮烈デビュー作、待望の文庫化。 あの日行方不明となった彼が、ドイツの私の元を現れる。 忘却に抗う言語芸術の傑作にして、鮮烈なるデビュー小説。 第165回芥川賞受賞作 第64回群像新人文学賞受賞作 ドイツの学術都市ゲッティンゲンに暮らす私の元に、東日本大震災で行方不明になった彼が現れる。 陽に透けないほどの存在感を持つその訪問者に私は安堵するが、死者との邂逅はその街と人の様相を重層的な記憶を掘り起こすように変容させてゆく。 群像新人文学賞と芥川賞をダブル受賞した著者のデビュー作。 解説=松永美穂(ドイツ文学者、翻訳家)
-
-「逃げろ! 転んだ年寄りにかまわず逃げろ!」 東日本大震災…その時、その場には驚くべき「真実」があった――! 2011年3月11日、岩手県陸前高田市を大地震と、そして大津波が襲った――! 海から5キロも離れた街が壊滅してしまうということ、地震から数日経っても家族の安否も分からないということ…いつもの安全で便利な暮らしからは想像もできない現実に襲われた時、人間はどうなってしまうのか!? 岩手在住の作家だからこそ描ける、テレビやニュースでは分からない「異常な光景」と「本当にあったこと」!
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。
























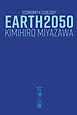


![生きがいの創造[実践編] 悩み苦しむ人をどのように導くのか](https://res.booklive.jp/317844/001/thumbnail/S.jpg)