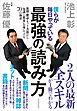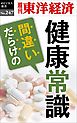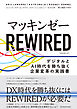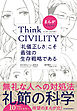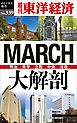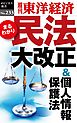東洋経済新報社作品一覧
-
3.8【遂に出た!2人が毎日やっている「最強の読み方」最新の全スキルが1冊に!】 【予約殺到!事前注文多数!発売前から、もう7万部突破!】 ★池上彰氏、佐藤優氏は毎日「何を」「どう」読んでいるのか? ★どうすれば、彼らのように「自分の力で世の中を読み解ける」のか? ★「新聞1紙5分」「月平均300冊の読書」はどうすれば可能か? ★「スマホ」「アイパッド」「新聞電子版」「dマガジン」はどう使いこなすか? ■2人の「アイフォン&アイパッド画面」もカラー写真で公開(巻頭カラー16ページ) ■「研究室」「仕事場の本棚」「仕事アイテム」「愛用グッズ」の写真も完全公開 「新聞」「雑誌」「ネット」「書籍」をどう読めばいいのか? そこから「知識と教養」をいっきに身につける秘訣とは? みんなが知りたかった「2人の知の源泉」が、いま明らかに! 《本書の5大特色》 【1】2人の「読み方の最新全スキル」が1冊に ■これだけ読めば、全ノウハウがわかる 【2】「普通の人ができる方法」をやさしく具体的に解説 ■今日からできる!これなら続けられる!「超実践的な技法」を紹介 【3】「重要ポイント」がひと目でわかり、読みやすく、記憶にも残る ■「70の極意+総まとめ」「重要箇所は色付き」だから、わかりやすく、読んだら忘れない 【4】とにかく内容が具体的――「おすすめサイト全一覧」から「新聞・雑誌リスト」「おすすめ本」まで紹介 ■「何を、どう読めばいいの?」知りたい情報・答えが、すべてこの1冊に 【5】2人の仕事グッズも完全公開!見るだけで参考になる! ■「巻末カラー」16ページ!「特別付録」は3つも収録! 巻末では「人から情報を得る技法」まで解説! ここだけでも面白すぎる! 「知の源泉」をここまで公開したのは本書が初! 2人の「共通点」と「違い」が面白い! この本で、自分なりの「最強の読み方」を身につけよう!
-
4.6【ついに出た! 稀代のヒットメーカー・つんく さんの”頭の中”が全部わかる! 超画期的なビジネス書!】 【自分の中の「眠れる才能」を見つけ、とことん大きく伸ばす方法、「時代を超えて愛されるヒット」の作り方、全ビジネスパーソンに今最も必要な「プロデュース力」の磨き方……全部この1冊でわかる!】 【「僕も含め、99%の人は凡人。だからこそ「大逆転」できる」そう断言するつんく さんが見つけた「普通の人が”小さな才能”を見つけ劇的に伸ばす45のルール」とは?】 【本書で紹介する「黄金ルール」の内容の一部】 ■僕も凡人、君も凡人。では、僕ら凡人が輝くためには? ★まず、自分が「天才じゃない」ことを認めよう ★凡人の勝機は「好き」をとことん追求すること、その「大事なポイント」がある! ★何が「好き」がわからない……大丈夫!「好きを見つけるコツ」もある! ★生まれもった素質や「親ガチャ論」を乗り越えられる! ★人間、じつは誰しも「元・天才」だった、その理由は? ★結局、僕ら凡人は、では「何を」「どう」すればいい? ■凡人が「小さな才能」を伸ばし、天才に勝つためには? ★天才に勝つには「行動」あるのみ!「根拠のない自信」を”行動力”につなげるコツは? ★「当たって砕ける」精神で、とにかく「数」をこなそう! ★とにかく打席に立って、どんどんアウトプットすれば、「凡人集団の先頭」には立てる! ★「実践」と「分析」を繰り返す!「自分の好きをデータ化」し、「好き」の要素・要因を徹底的に分析しよう! ★「理不尽を味方につける」くらいのメンタルが最強!「折れない心」を作る超簡単なコツは? ■「モーニング娘。」を世に生み出したプロデューサー、つんく が考える「プロ論」とは? ★これから求められるつんく 流「令和の10大能力」はこれだ! ★発想が無限に湧いてくる「アイデア出し3つの法則」がある! ★9人の「まあ、ええんちゃう?」より、1人の「めっちゃ、ええやん!」をつくるのが大事 普通の人が「自分の長所を極限まで伸ばし」「自分らしく輝く」ための最高の1冊! 誰でも自分に自信がつき、一歩踏み出す勇気をもらえる! この1冊で、これまで見えなかった本当のチャンスがつかめる! 着実に、人生を好転させよう!
-
3.3ポイント・会員制サービスの運営コンサルの第一人者による、初の入門書。 成熟社会になって、ポイント・会員制サービスの運用の成否がビジネスの成否を決める時代のノウハウを紹介する。 大企業のポイントや会員制サービスを紹介するだけでなく、これまで消費者向けのビジネスを行っていたが顧客情報を取得していなかった業種(例:出版業)や、中小企業(例:街の飲食店)が新たに会員制サービス(例:メルマガ配信)を行う場合の手順や方法論を詳しく解説する。 また、既に会員制サービスを提供している企業においては、会員情報の「ビッグデータ」の山から、データ分析ノウハウ・技術によって、”プラチナデータ”を抜き出すことで、会員をセグメント化し、ある層にターゲティングすることで、次の施策を効率的に打つ方法を紹介する。 【主な内容】 第1章 ポイント・会員制サービスの魅力 第2章 ポイントプログラムの特徴と最新事情 第3章 会員制サービスの特徴と最新事情 第4章 会員制サービスを新たに始める場合はどうする? 第5章 会員制サービスをすでに提供している場合はどうする? 第6章 ポイント・会員制サービスの課題と新たなビジネスの可能性
-
4.7世界41カ国で実践! SDGs時代の問題解決バイブル、待望の翻訳! ポジティブデビアンス(PD)とは、同じコミュニティや組織などで、問題が発生している悪条件の現場のなかで良い結果を出している「逸脱者」です。このPDが成果を出したプロセスを問題解決につなげるのがPDアプローチです。 PDアプローチは、世界41ヶ国で、複雑で解決が困難な問題、たとえば子どもの栄養不良、学校の退学率、ウイルスの院内感染、新生児や母子保健、少女の人身売買などを解決するための手法として長年使われています。 最近では、本書でも、製薬メーカーのメルク、投資銀行のゴールドマン・サックスが事例として扱われているように、PDアプローチの導入で、現場主導で問題を解決し、現場がさらに自ら考える組織に進化することから、ビジネスの世界でも注目されています。 本書は、最難関課題を、予算をかけずに、短期間に解決に導いたさまざまな事例を取り上げ、PDアプローチについて解説しています。社会起業家、イノベーター、企業リーダー、政策立案者など、喫緊に解決するべき社会的問題やビジネスの問題を解決したいチェンジメーカーをワクワクさせる一冊です! 【付録】 ・PDアプローチを実践するためのフィールドガイド ・日本語版オリジナルのビジネス視点の訳者解説
-
3.4英国のトップジャーナリストによるベストセラー、待望の邦訳。 人類史上初のチャンスをもたらす「プロジェクト・ゼロ」=資本主義以後の世界を探る。 【本書への賛辞】 たとえ、あなたが現在の資本主義システムを愛しているとしても、本書を無視するのは間違っている。 本書の主張は、右派と左派も分け隔てなく幅広い読者層を得るだろう。 ――ジリアン・テット(ジャーナリスト・元フィナンシャル・タイムズ アメリカ版編集長) これまでとは違う真の選択肢を導き出す独創的、魅力的、刺激的かつ活気ある明確なビジョンである。 ――ナオミ・クライン(ジャーナリスト、『ショック・ドクトリン』著者) ポストモダニズムなど、さまざまな『ポスト○○論』の流行が去った後、 メイソンは、唯一本物のポスト論である『ポスト資本主義』と恐れることなく向き合った。 ――スラヴォイ・ジジェク(哲学者、精神分析家) 【「プロジェクト・ゼロ」=資本主義以後の世界とは?】 ●機械や製品の製造コストはゼロ、労働時間も限りなくゼロに ●生活必需品や公共サービスも無料に ●民営化をやめ、国有化へ。公共インフラを低コストで提供し、単なる賃金上昇よりも公平な財の再分配へ ●ベーシック・インカムで、劣悪な仕事は姿を消す ●並行通貨や時間銀行、協同組合、自己管理型のオンライン空間などが出現 ●経済活動に信用貸しや貨幣そのものが占める役割がずっと小さくなる etc
-
-ベストセラー『達者でポックリ。』の実践編。 「これぞポックリ名人だ」と著者が感動した人々の生き様、死に様を紹介。いい生き方をして、いいリタイアをして、いい死に方をする――その一連の過程を見ることにより「生き方、死に方」を学び、安心して生をまっとうする指針を示します。 併せて、「ポックリ名人に学ぶ食養生」「ポックリ名人の呼吸法」など、最期まで元気に生きるための実践方法も解説。家族や周りの人に遺す巻末付録「帯津式{書置きノート}」は、死への心の準備としても最適です。 (前著で大好評だった、大きな活字の本文組みもさらに読みやすくリニューアルしました)
-
4.0Q なぜ『競争の戦略』を実務で使いこなすのは難しいのか? Q なぜ差別化の賞味期間はわずか3カ月なのか? Q どうすれば差別化を次から次へと実現できるのか? 低価格競争というチキンレースを続ける牛丼3社に未来はない? 「粉」で突き抜けたハッピーターン、亀田製菓は7年連続売上拡大。 親の肌感覚で顧客ニーズを顕在化、ターゲット児童693万人に600万足売った「瞬足」…… ポーターの基本戦略を使いこなして、日本企業が競争力を高める方法が豊富な事例から学べる 多くの日本企業で現状を打破する経営戦略が描けていないのはなぜなのか。 経営戦略なる代物は、そもそも役に立たないものなのか。 この問いに答え、多くの日本企業が経営戦略策定のどこで躓き、どうすれば経営戦略を機能させ、競争力を高められるのかを明らかにすることが、本書の目的である。
-
4.2マイクロファイナンスは貧困者の自立を促すための少額無担保融資をいう。国内の貧困問題解決策として、この手法の可能性や具体的な導入方法を考察。貧困・格差の現状分析も詳しい。 【主な内容】 第1章 マイクロファイナンスのビジネスモデル 第2章 そもそもなぜ貧困対策が必要なのか? 第3章 企業にマイクロファイナンスは可能か? 第4章 金融機関及び一般企業へのマイクロファイナンスのすすめ 第5章 市民へのマイクロファイナンスのすすめ 第6章 政府へのマイクロファイナンスのすすめ 第7章 マイクロファイナンスの普及、そしてマイクロファイナンスを超えて
-
-2016年1月29日に、日本銀行が「マイナス金利付量的・質的金融緩和政策」の導入を決定し、従来の「量」、「質」に「金利」を加えた三次元の金融緩和手段がとられた。 さらに同年9月21日には、金融緩和の効果をいっそう強化するため、日本銀行は「長短金利操作付量的・質的金融緩和政策」と称した新たな枠組みの金融政策を実施に移した。 超金利緩和政策の継続・推進は、不動産向け融資のさらなる増大を通じて既成市街地での都市再生や良質な住宅ストックの形成に寄与するとの評価がある一方、資産価格の行きすぎた上昇をもたらし、資産価格の下落の引き金になることはないのかという意見や不動産向けの融資拡大が他産業の設備投資・ベンチャー融資を阻害し、産業の新陳代謝の足を引っぱることにはならないかという懸念もある。 本書では、金融・不動産市場を巡る諸問題について、斯界の研究者、エコノミストが様々な知見をもとに市場への影響を読み解くものである。
-
-2016年1月29日、日銀は電撃的なマイナス金利導入を決定した。2014年10月の量的・質的金融緩和発表に勝るとも劣らない黒田総裁一流の奇襲といえる。 マイナス金利導入の真の目的な何か? 副作用はないのか? 円相場や株価への影響は?、国債はどうなる? そして個人の預金は・・・? さまざまな疑問に対し、専門家がその「功罪」をズバリ!解説する。 本誌は『週刊東洋経済』2016年2月13日号掲載の12ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● マイナス金利の「功罪」 疑問にズバリ! マイナス金利とは何か? 銀行収益に大打撃! 欧州のマイナス金利政策 手探りで効果は不透明 マイナス金利下で株が「買い」の理由 マイナス金利導入でも円安効果は限定的
-
3.8
-
4.0●「マイナンバー法案」(2012年2月国会に上程、同11月廃案)の問題点を洗い出し、国民本位のマイナンバー制度を作るにはどうすべきかを提言。 1) 検討されてきた「マイナンバー制度」を「社会保障・税の番号制度」「国民ID制度」「身元証明書制度」「プライバシー保護制度」の4つに分解して、目的を明確にしたうえで制度設計をし直す 2) マイナンバーの共通化は、プライバシー保護の観点から必要最小限に留めるべきであり、無暗に番号を共通化すべきではない 3) 喫緊の社会保障・税の一体改革のためならば、マイナンバーは「納税者番号」兼「社会保障番号」に限って導入し、まずは、このテーマにしぼっていかに早く・安く・安全に実現するかの議論に徹する 4) そして、同時に「プライバシー保護制度」の構築を急ぐ 5) 逆に、これまで検討されてきたマイナンバー制度の中で、ICカード、マイ・ポータル、社会保障と税分野以外での情報連携基盤は必要ない 6) その後、「国民ID制度」と「身元証明書制度」については、時間をかけながらじっくり制度設計を行う 7) すべての制度設計は、民間企業や国際標準のICT技術の知恵を十分に活用した制度設計を心掛ける ●やがてくる「マイナンバー」時代を、便利・公平・安全なものにするための方策が見えてくる!
-
3.3フェイスブック14万人、ツイッター12万人、メルマガ15万人! ネット界のカリスマが、毎日90分で終わらせている「ネット・メール・SNSのすごい使い方」を初公開! ネットは1日90分にまとめれば、「効率」「情報」「人脈」が一気に手に入る! しかも、「上手なネット断ち」で、自由な時間が毎日2時間も増える! 【1】メールは30分にまとめる────「効率」を最大化する秘訣 ●メールチェックは1日4回、返信は10通まとめて書く ●お願いとお礼は必ず「電話」にする、だらだら長文メールを書かない etc. 【2】ネットも30分だけ見る────簡単&勝手に「情報」が届く仕組みのつくり方 ●「○○とは」で検索すると、速く目的情報にたどり着ける ●情報が自動的に集まるおすすめアプリはこれだ! etc. 【3】SNSは30分だけ使う────デジタルとアナログを上手につなげて「人脈」に変える ●SNSは「情報発信」と「交流」の2つの目的に使う ●リアルで会った人とだけ「友達」になる、意味のない「いいね!」やコメントは百害あって一利なし etc. 今日から誰でもできる簡単な99のコツを一挙紹介! 「メールチェックのしすぎで、仕事がよく中断して効率が悪い…」 「用もないのに、ついスマホやニュースを見てしまう…」 「スマホの入力にイライラする、SNSにちょっと疲れ気味…」 心当たりがある人は、ぜひ読んでください! 読めば、仕事も人生も面白くなること間違いなしです! 【主な内容】 【第I部 デジタルツールの最適な使い方】 第1章 なぜ私はスマホを使わないのか?────「パソコン&モバイル」の正しい使い方をまず知ろう! 第2章 たったこれだけで作業効率が10倍高まる「パソコンの環境設定」超入門 【第II部 デジタルテクニックを極める】 第3章 1日30分で見事に終わる「メール&メッセージ」のすごい使い方 第4章 1日30分で必要な情報をチェックする「ネットの見方」はこれだけでOK! 第5章 1日30分で本物の情報と交流を得る「SNS」の正しい使い方 【第III部 デジタルとアナログを上手につなげる】 第6章 デジタル時代でも「あえてアナログ」にすべきもの 第7章 ネットとリアル社会をつなげるイベント参加術&交流術
-
3.93万部突破『ホウレンソウ禁止で1日7時間15分しか働かないから仕事が面白くなる』の第2弾は実践版! 山田式「先憂後楽」ワークスタイルを新提案! つまらない「常識」を捨てるから、仕事も人生も面白くなる! 【日本一“社員”が幸せな会社の「反常識」仕事術を初公開!】 ★営業マンは携帯、パソコン禁止! ★効率性を考えて、現場訪問は事前にアポをとらない! ★言い訳防止のため、出社時に今日の退社時間を決める ★部下にはきっかけだけつくって、あとは丸投げする ★「管理職ががんばられない仕組み」をあえてつくる ★3つの方法で、職場の「段取り力」を上げる ★「声かけ雑談」で部下の相談にのり、「ランチ雑談」で上司のフォローを引き出す ★「営業職にとってIT機器は「あ痛てぇ」と心得
-
-
-
3.8政・官の抵抗勢力を向こうに回し、電力会社分割を成し遂げるなど戦後日本の屋台骨をつくった松永安左エ門。昭和の激動期を勝ちぬいた九十余年の痛快人生を描く。 松永安左エ門は、明治8年に九州の壱岐で生まれ、上京後、慶應義塾に入塾し福沢諭吉の教えを受けた。しかし、人間の真価は学歴ではないと慶應義塾を中退。福沢の紹介で日本銀行に勤務するもサラリーマンが合わず退職。石炭販売業を始めて、芸者遊び、相場……とムチャクチャな生活を送りながら、大成功を収めたかにみえたが、株暴落ですべてを失い隠遁。読書三昧の2年間の浪人生活の後に再起し、会社をおこして徐々に成功を収め、九州水力電気を設立。「電力界の松永」といわれるまでに電力業界に君臨し、電力独占化の時代に東邦電力を一人できりもりし5大電力の一角にのしあげた。 しかし軍国化の時代に、「官僚は人間のクズである」と放言し、役人たちと大ゲンカし、一切の職を引退してふたたび隠遁生活へ……。完全に過去の人物になったかと思われたが、戦後、不死鳥のように復活。電力業界再編の中心的人物となり、電力事業の分割民営化を成し遂げた。その後、昭和46年に亡くなるまで、95年の人生を生涯現役でまっとうしている――。 ※本書は2003年7月に東洋経済新報社より刊行された『まかり通る 電力の鬼・松永安左エ門』を電子書籍化したものです。
-
3.6
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 信用創造、貨幣創造を組み込んだ、整合的なマクロモデルを提案した本。金融危機分析に欠かせない著者独自の新たなモデルを提示する。 【主な内容】 序論 第1章 ケインジアン・モデルおよび「マネタリスト・モデル」と利子率政策 第2章 貨幣錯覚、名目政府支出と利子率政策 第3章 信用と貨幣の創造を含んだマクロ経済モデルの本質 第4章 為替相場決定理論の再構成について 第5章 開放経済におけるマクロ不均衡調整モデル 第6章 市場の均衡および不均衡における信用創造と貨幣供給 第7章 貸出市場の不完全性による信用割当とマクロ信用創造モデル 補遺および数学注
-
3.5「1勝9分け」の働き方が仕事の質を変える! 1勝9分けの働き方の「1勝9分け」とは、現実の勝敗のことではありません。 1勝というのは、少なくとも自分には克つということであり、残りの9分けは、とにかく負けないようにする、仮に勝負に負けたとしても自分の心まで折れないようにするということです。 どんなにがんばっても、自分が置かれている環境が悪ければ結果は出ませんし、その時々の社会状況や運もあります。だからこそ、不遇をかこっているときには内面を磨き、将来のための種まきをして、捲土重来に備えるべきなのです。最後に成功する人、一流の仕事ができる人は、他人との勝負に「勝つ」こと以上に、自分に「克つ」ことに強く執着しているものです。 なぜなら、他人との勝負は、時の運や相手との力関係があるので必ず勝てるとは限りませんが、自分との勝負は、 その気になれば100パーセント勝てます。 やるかやらないか、続けるか続けないかを選ぶのは、ほかの誰でもなく自分自身です。
-
-
-
4.1ぼくはいかにして天皇主義者になったのか。 立憲デモクラシーとの共生を考える待望のウチダ流天皇論。 【ウチダ流「天皇論」の見立て】 ◆天皇の「象徴的行為」とは死者たち、傷ついた人たちと「共苦すること」である。 ◆「今」の天皇制システムの存在は政権の暴走を抑止し、国民を統合する貴重な機能を果たしている。 ◆国家には、宗教や文化を歴史的に継承する超越的で霊的な「中心」がある。日本の場合、それは天皇である。 ◆安倍首相が背負っている死者は祖父・岸信介など選択された血縁者のみだが、今上陛下はすべての死者を背負っている。 ◆日本のリベラル・左派勢力は未来=生者を重視するが、過去=死者を軽視するがゆえに負け続けている。 【本書の概要】 2016年の「おことば」から生前退位特例法案までの動きや、これまでの今上天皇について「死者」をキーワードとしてウチダ流に解釈。 今上天皇による「象徴的行為」を、死者たち、傷ついた人たちのかたわらにあること、つまり「共苦すること(コンパッション)」であると定義。 安倍首相が背負っている死者は祖父・岸信介など選択された血縁者のみだが、今上陛下はすべての死者を背負っていると指摘する(「民の原像」と「死者の国」)。 さらに日本のリベラル・左派勢力は生者=現在・未来を重視するが、過去=死者を軽視するがゆえに負け続けていると喝破。 同時に日本は「天皇制」と「立憲デモクラシー」という対立する二つの統治原理が拮抗しているがゆえに、「一枚岩」のロシアや中国、二大政党によって頻繁に政権交代する米仏のような政体にくらべて補正・復元力が強いとも論じる。 天皇主義者・内田樹による待望の天皇論。
-
4.3疫病と戦争で再強化される「国民国家」はどこへ向かうのか。 拮抗する「民主主義と権威主義」のゆくえは。 希代の思想家が覇権国「アメリカ」と「中国」の比較統治論から読み解く。 アメリカにはアメリカの趨向性(あるいは戦略)があり、中国には中国の趨向性(あるいは戦略)がある。それを見分けることができれば、彼らが「なぜ、こんなことをするのか?」、「これからどんなことをしそうか?」について妥当性の高い仮説を立てることができる。それがこれからこの本の中で僕が試みようとしていることです。(第1章より) アメリカと中国というプレイヤーがどうふるまうかによって、これからの世界の行方は決まってきます。僕たち日本人にできることは限られています。直接、両国に外交的に働きかけて彼らの世界戦略に影響を及ぼすということは日本人にはできません。日本自体が固有の世界戦略を持っていないのですからできるはずがない。できるのは、両国の間に立って、なんとか外交的な架橋として対話のチャンネルを維持し、両国の利害を調整するくらいです。それができたら上等です。 とりあえず僕たちにできるのは観察と予測くらいです。この二つの超大国がどういう統治原理によって存立しているのか、短期的な政策よりも、基本的にどのような趨向性を持っているのか、それをよく観察して、世界がこれからどういう方向に向かうのか、どのような分岐点が未来に待ち受けているのか。(第1章より)
-
4.2大胆な戦略を立案し 成功確率を高める 戦略策定のニューモデル! 2393社・15年分のデータから導き出した マッキンゼーの科学的アプローチを公開!
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『地方のデポチプ(マッコルリ酒場)で飲んでいると、酒そのものよりも、酒母(女将)やお客さんの人柄、町の空気が、何よりもごちそうだ。朝は夜勤明けの道路工事のおじさんと、昼は市場の仕事を終えたおばさんと、そして夜は農家のおじさんと次がれコンドゥレマンドゥレ(へべれけ)。歌や踊りまで飛び出した。10年近く日本の仕事をしているため、個人主義が身についてきた私だが、今回の取材では久しぶりに暑苦しいほどの情の海に身をゆだねた。』 上記はまえがきにあたる『まずは一杯』よりの抜粋。本書は韓国の大衆酒であるマッコルリそのものよりも、著者が江原道の束草から全羅南道の海南まで、各地のマッコリを飲み歩き、酒場や酔客の熱気、町や醸造場の歴史ドラマなどを伝えることに重きを置いた紀行文である。韓国の魅力を再発見すること間違いなしの一冊である。
-
3.6全米ベストセラー! 頭がいい人は、 地図を描くように情報を見きわめ、 スマートな「最適解」を導いている! * * * 「判断力が優れている人」とは、どういう人のことを指すのだろう? ぱっと思い浮かぶのは「知的である」「頭の回転がいい」 「勇気がある」「忍耐力がある」などではないだろうか。 なかでも特に重要なのが、本書のテーマ「マッピング思考」、 「物事をまるで地図を描くように“俯瞰的に”とらえようとすること」だ。 たとえば…、 ●自分の間違いに気づき、死角を探し、仮定を検証し、軌道修正ができる。 ●「あの議論では私が間違っていなかっただろうか?」 「このリスクを取ることに価値はあるのか?」といったことについて目をつぶらず、率直に自問できる。 ●思い込みではなく、事実とデータにもとづき、曇りのない目で物事を判断する力がある。 あなたはこういったことが、自然とできているだろうか? 物理学者の故リチャード・ファインマンいわく―― 「自分に嘘をつかないことは、なによりも重要だ。だが、自分ほどだましやすい人間はいない」。 そう、私たちの判断力を妨げているものは「知識」ではなく「態度」なのだ。 近年、認知科学の研究から明らかになっていることは、 人間は自分の欠点やミスを認めるのがおそろしく下手だという事実である。 人はすぐに希望的観測に逃げ込み、 偏見や信条を肯定するような証拠だけを見つけようとする。 しかし、自分の思い込みから脱出し、真実に向き合って行動するときに何が起こるか、 その成功から何を学べるか――これが、本書のテーマである。
-
-史上最高の経営者に学ぶ最強のリーダー論 元側近の著者が成功の秘密を解き明かす決定版! 能力は60点でいい。大事なことは、熱意。「熱意のない人の能力は増すことはないが、熱意のある人の能力は、その熱意に比例して増していく」。それが、松下さんの人材観でした。ですから、他社の経営者から見れば、無謀とも思えるほど、社員に、部下に、どんどんと大きな仕事を任せました。 権限を委譲して、責任を待たせて仕事をやらせる。そうすれば、「立場が人を育てることになる」ということでしょう。「60点の能力と滾る熱意」が、権限を委譲する時の目安だということです。(本文「能力は60点でいい」より抜粋)
-
-
-
4.0わたしは、個人が喜んで株式や投資信託などを買う環境を創れれば、日本経済の風景を一気に変えられると考えています。 多くの国民が株式や投資信託を持つ国では、株価が上がれば、個人の資産価値が上がり、生活にゆとりが出ます。ローンや奨学金の返済も楽になります。年金のリターンも高まり、老後不安も減ります。企業活動が活発になり、経済全体が底上げされます。国民にとっても、企業にとっても、ハッピーなことばかりです。 資本主義の総本山ともいうべき米国には、株価の上昇が広く社会全体に恩恵をもたらすような仕組みが、ビルトインされています。 それと同じことができるのは、個人が2000兆円もの金融資産を持っている日本です。人口が減少し続ける日本でGDPを増やすことは非常に大変ですが、個人金融資産をはじめとする国富を2倍にするのは案外簡単なことだと思うのです。 いまほど、資本市場を活用して日本を復活させるグランドデザインが求められている時代はないと思います。
-
-リスキリングやリカレントという言葉に代表されるように「学び直し」が注目されている。では、40~50代のビジネスパーソンは、今後どんな学びをすれば、「これからも社会で活躍する人材」「稼げる人材」になれるのか? Webマーケティングやデータ分析といったデジタル人材に必要なスキルから、MBA、中小企業診断士といった経営者にプラスとなる資格、そして歴史や宗教、文化人類学、美術、数学、物理学といった人生に厚みを持たせる教養まで、その学習法を紹介していく。 本誌は『週刊東洋経済』2022年10月22日号掲載の34ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
-
-
-学習指導要領が改訂され、2022年度から高校で「歴史総合」という新しい必修科目が新設された。18世紀後半以降の日本史と世界史を融合させたものだ。日本史と世界史を融合させると、欧米列強と東アジア諸国との関係、日本や中国などの近代化など、複合的な視点から歴史を学ぶことができる。私たちが今生きている現代社会が抱えている課題は、そのほとんどが近現代の歴史と密接に関わっている。こうした視点はグローバル化が進む現代で、誰もが身に付けたいもの。最新の知見から近現代史を学ぼう! 本誌は『週刊東洋経済』2021年11月20日号掲載の32ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
3.8◆40万部突破シリーズ、最新作!◆ 仕事にも勉強にも趣味にも効果絶大! これが【偏差値35からの東大合格】を支えた「学びの王道」だ! マネするだけで、誰でも、どんなことでも! ・「最速・最短」で学べる ・「自由自在に応用」できる ・「自分に最適」なやり方がわかる ◆最小の努力で最大の効果!「東大独学」の4大特徴◆ 1:単なる知識を「応用可能」にする極意を徹底解説! 2:弱点を見つけ、成長につなげる東大流「復習の作法」を初公開! 3:「より速く」「より深く」学ぶための9種の「東大独学シート」付き! 4:独学に役立つ本・アプリ・YouTubeチャンネルを厳選紹介! ◆「6つの独学法」で、どんなことでも最速マスター!◆ 基礎を「最短・最速で」身につける……「ゲームづくり」独学法 知識を「自由自在に応用」できる………「質問づくり」独学法 弱点を「抜け漏れなく」見つける………「目標づくり」独学法 「次に学ぶべきこと」がわかる…………「言い訳づくり」独学法 「自分だけの成功法則」を導く…………「教訓づくり」独学法 「どんなときでも成功」できる…………「説明づくり」独学法 ◆東大生は「才能」ではなく「独学のやり方」が優れていた!◆ 多くの東大生が、受験の中で得た「独学のやり方」を、受験勉強以外のことにも応用していたのです。 彼らは受験勉強と同じように授業の勉強をし、複数の外国語やプログラミングをマスターし、 公認会計士試験や司法試験などの超難関の資格試験を突破しています。 勉強だけでなくスポーツや音楽などの趣味にも、この「独学のやり方」を応用しているのです。――「はじめに」より
-
4.019世紀を産業化の時代と呼ぶのなら、20世紀はまさにマネジメントの時代であったといえるだろう。 本書は、20世紀のマネジメントを構成するさまざまな要素を集め、その理論と実践がどのように発展してきたのかを、深い洞察を交えながら振り返る。 偉大な経営思想家、実業家の人生や時代背景、そして彼らが創造した組織の輪郭を改めて見つめ直すことで、明日につながる何かが見えてくることだろう。 テイラー、フォード、メイヨーからポーター、ウェルチ、デルまで。20世紀のマネジメントを構成するさまざまな要素を集め、その理論と実践がどのように発展してきたかを洞察を交えて振り返る。経営の100年史。
-
-
-
3.5カイゼンを徹底しながら イノベーションを起こす! 事業のライフサイクルを考えてみると、誕生から成長、成熟を経て衰退を迎える。 誕生から成長の期間が「攻め」であり、その代表がイノベーションである。成熟から 衰退を「守り」と考えると、その代表がカイゼンである。 事業のライフサイクルは、創業期・成長期は攻めるという行動をとり、成熟期・衰退期は 守るという行動をとるのが普通であり、攻守の切り替えは急にはできない。しかし、 事業のライフサイクル・マネジメントの視点に立つならば、各事業のライフサイクルを 理解したうえで、いかに円滑に攻めから守りにシフトしていくか、そして、いかに 革新的に守りから攻めに転換するかが要諦となる。 本書では、事業のライフサイクルを時間軸でマネジメントする方法を示し、各企業が 「攻めつつ守り、守りつつ攻める」ことができる優良企業になるための方法が明かされる。 成長期・成熟期も終わり、衰退期の真っ只中にいる日本企業は多い。そうした企業に 向けては、「次の攻めの準備」についてが解説されている。成長期にある事業・企業に 「どのようにして守るのか」が解説されている。
-
-時代は大乱世に突入した。貧富の格差拡大や気候変動に代表される環境破壊、AI(人工知能)など制御困難なテクノロジーの脅威が資本主義を揺さぶる。同時に米国の民主主義が混沌とし、「一党独裁」の中国が台頭する中で、国家と社会、個人のあり方が今後根本から問われてくる。戦後社会の信念とイデオロギーが崩れ落ちる今、私たちに必要なのは、危機の根本を知り、それを乗り越えるための道を示す思想を手に入れることだ。脱経済成長を旗印に支持を広げる新マルクス主義と新型コロナで完全復活したケインズ主義を軸に、大思想家が残した知恵を学び直そう。 本誌は『週刊東洋経済』2021年4月10日号掲載の28ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
3.8●世界記憶力グランドマスター・記憶力日本一を6度獲った専門家が伝授する、 覚えるのが楽しくラクになる、独自メソッド。 ●【英単語】【難読漢字】【専門用語】【年号】【クレジットカードの数字】 【文章】【人の顔と名前】 魔法のシートに一度書くだけ! 一瞬で「ドラえもんひみつ道具」のような記憶力を手に入れる。 ●ありとあらゆる脳力が1枚のシートで上がる! 記憶力UP、集中力UP、思考力UP、想像力UP、言語力UP、非認知能力UP、行動力UP etc ●年齢は関係なし! 小学生から高齢者まで、大量に覚えて、絶対に忘れない! ●資格試験、大学入試、語学学習、リスキリング、教養を深める、ビジネスに活かす、物忘れ防止に。 NHK『あさイチ』、TBS『マツコの知らない世界』など メディアで人気の「記憶の専門家」が、 たった1年で記憶力日本一になった、 超簡単・独自メソッドを初公開! 以下の勉強法をしている人は注意!! もっと効率的な勉強法があります! ・試験前の一夜漬け × ・マーカー箇所を下敷きでかくして丸暗記 × ・ブツブツ唱える暗唱法 × ・他人の考えた語呂合わせで強引に覚える × 【池田式】絶対に忘れない技法 ①自由に描いて脳にすり込む 【落書き式】 ②キャッチコピーを考える 【ワンフレーズ式】 ③似ている部分を探す 【類似式】 ④気になることにツッコミを入れる 【ツッコミ式】 ⑤複雑なモノは分ければ簡単 【分解式】 etc 【超簡単!】魔法のシートに書くとこんなに良いことが! ・大量に覚えられて、緊張してても忘れない。 ・アイディアが次から次へ出てくる。 ・会話がよどみなく話せ、言葉が出てくる ・多くの仕事が立て込んでも、優先順位を考え対処できる ・何時間でも同じことに集中して取り込める ・一つのことをあらゆる視点で考えることができる ・物事の本質を見極め、抽象化し、他分野でも活かせる ・EQ(非認知能力)を上げ、生きる力、人間力がつく ・三日坊主にさようなら。目標実現の力がつく。
-
4.0「ゴルゴ13」「美味しんぼ」「釣りバカ日誌」「ザ・シェフ」「あしたのジョー」「DEATH NOTE(デスノート)」……。いずれもコミックスが1000万部を超えるベストセラー漫画です。共通する点は、原作者がストーリーを書いている原作付き漫画です。ヒット作の3~4割が原作付き漫画と言われています。 1000万部売れると、どれくらい印税が入るのでしょうか? コミックスの値段を500円とすると、1部当たりの印税は10%の50円。漫画原作者の取り分は漫画家と折半が基本なので25円です。25円×1000万部=2億5000万円。これが漫画原作者に入る印税です。 小説なら5000部を売るのも至難の業ですが、人気漫画は必ずシリーズ化されるので、夢の数字ではありません。さらにアニメ化、映画化、キャラクターグッズの販売などされれば、ロイヤリティが入ってきます。 漫画原作者になるのに、特別な資格や知識は必要ありません。年齢も関係なし。ビジネスマンだろうとОLだろうと、学生だろうと主婦だろうと、リタイアしたシニアだろうと、老若男女誰でもなれます。初期資金も必要なし。アフター5や休日を利用して、気軽にチャレンジできます。 小説家と違って筆力や文学的センスも二の次。漫画原作者にとって一番大切なのは、ストーリーやキャラクター設定を考えることです。仕事や趣味、恋愛体験、打ち込んだスポーツ、ギャンブルなど、あなたが人生で積み重ねてきた経験やエピソードが、漫画原作づくりに大いに役立ちます。 本書では、どうすれば漫画原作者になれるのか、また、どうすればヒット作を生み出すことができるのか、そのコツやヒントをわかりやすく解説します。ぜひあなたも、漫画原作者となって話題作を世に送り出し、一攫千金を狙ってください! 【主な内容】 第1章 目指せ!「漫画原作」で印税1億円! 第2章 「漫画原作」の基本を押さえよう 第3章 人気漫画に学ぶヒットのコツ 第4章 ノウハウ大公開!ヒット作を生み出す授業 第5章 「漫画原作」でデビューする方法
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、第55代内閣総理大臣で、東洋経済新報社の社長を務めた石橋湛山の生涯を漫画化した市村章氏の作品です。 第1回 「若き日の湛山」 第2回 「運命を決めた出会い」 第3回 「我が行くべき道は」 第4回 「無知と高慢」 第5回 「ほのかなデモクラシー」 第6回 「繰り返えされる醜態」 第7回 「閉じ込められる民意」 第8回 「行き場のない失望」 第9回 「ムキ出される白い牙」 第10回 「基本は家族にあり」 第11回 「増幅する不安」 第12回 「せまり来る暗雲」 第13回 「論旨堂々、信念を表白」 第14回 「政界への道」 第15回 「決断と選択」 第16回 「四面楚歌の就任」 第17回 「歪められた真実」 第18回 「のしかかる苦難」 第19回 「権力の選択」 第20回 「曲げる意地、曲らぬ信念」 第21回 「逆転とその運命」 第22回 「運命は過酷」 第23回 「イデオロギーは人間に奉仕するもの」 第24回 「その気概、大国を動かす」 第25回 「人間の幸福と平和」
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 10万部のベストセラー『ThinkCIVILITY「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である』待望のまんが化! MBAで「職場の無礼さ」を研究する著者、20年間の集大成をまんが1冊に凝縮! あなたの周りにいませんか? ■突然キレる理不尽な上司 ■人を小ばかにする傲慢な同僚 ■いつも無愛想で不機嫌な部下 ■人を見下し協力し合わないチームメンバー 無礼な人が「仕事」も「人間関係」もダメにする! 【あらすじ】 大手ネット広告代理店で働く主人公。営業成績がトップクラスの彼女は、課長に抜擢される。しかし、「理不尽な上司」「周りを見下す部下」「協力的じゃないチームメンバー」に振り回され、思うように結果が出せずストレスが溜まる日々。 この物語は、そんな主人公が「礼節」を身につけて、自分とチームの問題を解決していくストーリー。 「礼節の科学」で仕事も人生もきっとうまくいく!
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本書の魅力①20万部突破のベストセラー『13歳からの地政学』待望のまんが化!】 高校生・中学生の兄妹と年齢不詳の男「カイゾク」との会話を通して「地政学」がわかりやすく楽しく学べる本『13歳からの地政学』をさらにパワーアップさせてまんが化。 【本書の魅力②いま世界で起っていることの「なぜ?」がわかる!】 約2年たっても続くロシアとウクライナの戦争、南シナ海をほしがる中国の狙い、宇宙をめぐるアメリカと中国の対立……、いま世界で起きていること、その裏側・本質が理解できるようになります。 【本書の魅力③大人も子どもも一緒になって学べる!】 「日本は大国なのか」「なぜ多民族の国が豊かになりにくいのか」「国際法に意味はあるのか」「日本が核爆弾を持つ日は来るのか」……なんとなくでわかっていたつもりになっていた大人もこれから0から知っていく子どもも一緒に楽しんで学べる本になっています。
-
4.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シリーズ27万部ベストセラー『東大読書』、待望のマンガ化! これは偏差値35から“奇跡の東大合格”を支えた 「読書術」を伝える、笑いと感動の物語である! 「本を読めないヤツは、読み方を知らねぇだけだ」 美人書店員に誘われ「読書会」への参加を決めた東君、実は「大の読書嫌い」で… 「読書の神様」と「ドS女神たち」のしごきに堪え、読書嫌いを克服する! 【本書で身につく読書術】 学校では教えてくれない!一生使える「5つの読み方」 ・スラスラ読めるようになる! 装丁読み ・深く理解できるようになる! 取材読み ・内容を一言でまとめられる! 整理読み ・多面的に理解できる! 検証読み ・ずっと記憶しておける! 議論読み
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 いま、日本は100年に1度の大きな転換期を迎えています。 子どもの数が減り、寿命が伸び、テクノロジーの進化で 私たちの働き方が大きく変わろうとしている―― この時代における「新しい生き方」のロードマップを示したのが、 社会現象にもなった「ライフシフト」です。 「ライフシフト」のシリーズは、 「人生100年時代(多くの人が100歳まで生きることを想定した時代)」を提唱し、 多くの日本人に「ワクワクするような新しい選択肢」を示してきました。 本書は、「ライフシフト」の大事なエッセンスを 「1時間で読める」ストーリーにまとめました。 【あらすじ】 主人公「平野くん」は、働き盛り35歳のビジネスパーソン。 転勤族だけど、まじめに会社に貢献してきたおかげで、 上司からの評価も上々。 一方で、妻と幼い娘には 「俺の仕事人生のせいで我慢を強いているのではないか…」 という罪悪感も。 しかし、あるとき「大きなニュース」が飛び込んできて……。 「本当に、俺も家族みんなも幸せになれるのかな…?」
-
3.8今こそ、自分の人生を生きよう! 「100年人生」の一大ムーブメントを巻き起こした30万部のベストセラー、待望のまんが化。 長生きなんてしたくない。今が楽しければよく、将来に漠然とした不安を抱く大学生の美咲。 真面目に仕事ばかりし、遊ぶことは罪だと思っている父。 お金を稼ぐことが男の価値とイコールだと思い、家庭のことまで気が回らない兄。 「ライフシフト」を実践し、自分らしく生きる留学生のエルザに出会った日から、 美咲の家族を巻きこんで、美咲の日常が、人生が、少しずつ変わり始める。 長生きなんてしたくない、が 「200年でも生きたい」に変わる。 あなたらしい人生を生きるヒントが見つかる、勇気の書。
-
4.1※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 何の武器も持たずにビジネスの世界に飛び込んで数年。 何をどれだけ頑張ったら、あの人と仕事したいと思ってもらえるのだろう。 転職を試みても「よくて現状維持」、自分の市場価値を思い知る…… そんなイケてないOL・かんべみのりが、脳に汗かいてMBAに挑戦! 勇気を持って一歩踏み出せば、世界は変わる。 クリティカルシンキング、マーケティング、会計、リーダーシップ他、 今日から使えるMBAのフレームワークが、まんがで1時間で読める! 【主な内容】 第1章 クリティカルシンキング 第2章 マーケティング 第3章 会計・ファイナンス 第4章 ビジネス定量分析 第5章 リーダーシップ 第6章 志 もっと勉強したい人のためのおすすめ本 すべてはこのノートから始まった。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 みなさんは、経済学についてどのようなイメージをもっているでしょうか。経済学は、金儲け理論と思われがちです。でも、実はそうではありません。経済学は、みなさんが毎日行っている取引にスポットを当て、どうすればベストな取引ができるかを考えていくものなのです。では、なぜ難しくなってしまうのでしょうか? 経済学が難しく感じる点は、大きく分けて3つあります。 1つ目は、経済学の目的がわからないまま話が進んでいくという点です。なぜこの理論が重要で、今後の話にどう関連していくのかがわからないまま、理論の詳細を説明されている感じがするので、理解が難しいのです。 2つ目は、専門用語が多すぎて、そもそも説明されている日本語がよくわらないという点です。 実際、多くの教科書では、経済学専用の言葉で解説してあります。そのため、書いてある内容を理解することに時間を取られてしまうのです。 3つ目は、グラフと数式のイメージがつかみづらいという点です。経済学では、頻繁にグラフと数式が登場します。しかし、グラフや数学が苦手な方からすれば、グラフと式は暗号やパズルに見え、内容が把握できません。 この3つが経済学を難しく見せています。ということは、この3つさえクリアーすれば、経済学は、誰にでも理解することができます。 経済学を初めて勉強される人はもちろん、苦手意識をお持ちの人にも読んでいただけるよう、「今までになかった」「今までで一番わかりやすい」経済学の教科書を目指して書きました。この本で少しでも経済学に対して興味を持っていただけたら嬉しく思います。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 いま世界で一番で読まれている大ベストセラーテキストのミクロ編、最新改訂版(原書第8版)。豊富な図や例を用いて、ミクロ経済学の基礎の基礎から、情報の経済学、政治経済学、行動経済学といったフロンティアまで扱う。丁寧な解説でテキストにはもちろん、ビジネスマンがもう一度ミクロ経済学をおさらいするのにも最適。全7部、22章構成。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 いま世界で一番読まれている、経済学の入門テキストの改訂版。ハーバード大学、シカゴ大学のグローバルエリート候補生もテキストとして学ぶほどしっかりしたレベルながら、高校生にもわかるように懇切丁寧に解説している。 ミクロ、マクロの主要な章に加えて、失業や税、為替などもの付論もあり、これ1冊で経済学のエッセンスをすべて学ぶことができるようになった。 内容は、マンキュー経済学Ⅰ、Ⅱの第4版に対応。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マクロ経済学における超スタンダードなロングセラー・テキストの第Ⅰ巻の最新改訂版(原著第11版)。トランプ大統領の貿易政策の帰結や新型コロナ不況時の失業保険制度などといった最新のトピックスについて新たにケース・スタディでとりあげるほか、「富裕層と貧困層の格差の拡大」を詳しく分析する補論を追加。新型コロナ不況については新たに節を設けて深く分析するなど、マクロ経済理論を実際の経済に照らしあわせながら学ぶには絶好の書。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マクロ経済学における超スタンダードなロングセラー・テキスト。第II巻では成長理論のほか、マクロ経済理論のトピックス、そしてマクロ経済政策のトピックスを収録。第I巻で学んださまざまなモデルを使って、マクロ経済学を適用して現実世界のデータや経済政策を自分の頭で考えられるように構成されており、第I巻を学んだあとの応用コースとしてふさわしいテキストになっている。また、原著のアメリカの図表に対応して日本の図表もほぼ完備した。 さらに、この第4版(原書第9版)では、経営手法の変化による生産性への影響や、経済政策の不確実性に関する最新の研究成果をテキストに盛り込むとともに、2008~2009年の金融危機後の金融機関規制にマクロ経済学的な観点が導入されるようになったことについても新たに1章を設けて詳しく説明している。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マクロ経済学における超スタンダードなロングセラー・テキスト 第Ⅱ巻の最新改訂版(原著第11版) 今回の原著第11版では、大きく2つの改編を行った。1つ目は超長期の経済成長のパートを再編したことである。超長期の経済成長に関する3つの章を第1部に集めることで、成長理論を詳しくみるとともに、成長に長期的な影響を与える公共政策という重要なトピックスについても扱う。2つ目は、マクロ動学モデルとミクロ的基礎を含むマクロ経済理論の2章と、マクロ経済政策に関する3つの章を、すべて第2部に集めたことである。マクロ経済理論とマクロ経済政策においては、学界の最新の研究結果も紹介している。 上級者向けのトピックスとして、第Ⅱ巻ではマクロ経済学が明らかにできていることと、できていないことに関する終章も加えている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マクロ経済学における超スタンダードなロングセラー・テキスト。「長期から短期へ」という原著の方針に従いつつも、第I巻では短期分析のウエイトを大きくし、かつ開放経済モデルを重視した形で編成し、1学期間の入門コースの簡潔したテキストとして使えるようになっている。また、原著のアメリカの図表に対応して日本の図表もほぼ完備した。 さらに、この第4版(原書第9版)では、ビットコインに関するコラムや、最近のアメリカ労働市場の参加率の大幅な低下など、最新の経済状況を反映した内容がふんだんに盛り込まれている。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ホームインスペクション、地震・水害、マンションの老朽化、そして、空き住戸の増加など、 最新のマンション管理のコツとポイントを一気に解説する企画です。 建物も住民も高齢化する日本の分譲マンションの管理は、難題山積み。なによりも一番の問題点は、住民の無関心さと知識不足です。「他人任せ」の住民たちがたどる末路は、大規模修繕を放置、管理組合への無関心、管理会社への丸投げ…といった、「マンションの資産価値を落とすこと」。 本書は、こんな負のスパイラルを断ち切り、マンションの資産価値をUPさせる知識を、9名ものマンション管理のエキスパートから伝授いただきます。また、大震災以後に注目を集めている「マンション内コミュニティの形成」についても豊富な事例を掲載。住民同士の絆が、理事会の参加率UPにもつながり、マンションの資産価値を高めていくのです。 知らないと損する「マンション管理」のキホン知識、今さら聞けない「管理組合のしくみ」、意外と大事な「管理会社との上手な付き合いかた」など、マンション管理&修繕に関連する基礎情報を1冊にまとめました。 理事会の幹事になった方、修繕積立委員会のメンバーに選ばれた方など、マンションの管理と修繕に関わるすべての方は、必読です。
-
-新築分譲マンションの売れ行きがおかしい。そんな話があちこちで聞こえ始めてきた。未発売の「潜在在庫」増加からも、こうした傾向が見てとれる。土地代や建設費用が上昇し平成バブル期並みに価格がハネ上がった結果、購入者層の需要価格とのバランスが崩れたのではないか。さらに、KYB問題や羽田新飛行ルート、五輪選手村跡地の巨大開発や金利上昇への懸念など時限爆弾とも言える要因も気にかかる。一方、住民の高齢化、空き家増加、管理不全で既存マンションにも課題は山積し、問題は今後一層加速すると見られている。 これから何が起きて、どう対応するべきか。「絶望未来」に立ち向かう知恵を探る。 本誌は『週刊東洋経済』2018年12月8日号掲載の30ページ分を電子化したものです。
-
-マンションの資産価値を維持するために最も大事なのが大規模修繕。最初はピカピカでも、時間が経てば劣化します。中古マンションを購入する際も、大規模修繕が適切に行われているか、修繕計画がしっかりしているかは重要なチェック項目です! いつやる、何をする、いくらかかる? 疑問だらけの大事業を、住民目線で解明! また、「買ってはいけない」管理組合マンション、修繕問題に立ち向かう管理組合の実例など、マンション購入検討中の方もすでに購入された方も必読です! 本誌は『週刊東洋経済』2013年8月10・17日合併号の第1特集の30ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。 【主な内容】 大規模修繕ABC 修繕工事でどこを直すのか 実際の工事はこう進む! どこに発注すればいいのか Column大規模修繕工事に新ブランド 修繕工事、いくらかかるのか Column国内マンションの3棟に2棟が「修繕適齢期」 分譲時の計画は「ウソ」。一刻も早い見直しが必要 これが長期修繕計画だ(例) 長期修繕計画の大ピンチ! 理事たちはこう乗り切る 計画を自力で50年へ延長/プリズム東京スクエア(船橋市) 先手必勝の修繕積立金値上げ/イニシア千住曙町(足立区) 修繕方針をルール化し住民と共有/パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー(川崎市) 段階式値上げを決定/リバーフェイス(足立区) 華麗なる共用施設どうやって維持?/ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン(江東区) Column「いびつな管理組合」物件には近寄るべからず Column修繕積立金が一定! 野村不「OHANA」の衝撃 Column立ち上がれ! マンション理事長
-
-
-
-新型コロナの影響で2020年2月下旬の3連休からモデルルーム来場者が急減した。だが、建築費の上昇や立地の厳選が進み、かつ大手の寡占が高まっていることから、「値下がりは限定的だ」とデベロッパー各社は口をそろえる。 今がマンションの買い時かと聞かれれば、そうではないかもしれない。それでも、家賃がもったいない、資産を持ちたいなどの理由から今持ち家が欲しい人もいる。情報洪水の中だからこそ、質の低いマンションを掴まされないよう、買う側も目利き力を養っておきたい。そこで、マンション開発・販売のリアルを明らかにし、売り手と買い手の間に横たわる情報の非対称性を埋めるべく徹底取材した。なお、新型コロナウイルス感染症による経済や社会への影響は不確実な要素もあり、掲載の情報は取材時点であることを、おことわりしておく。 本誌は『週刊東洋経済』2020年3月14日号掲載の30ページ分を電子化したものです。
-
3.8【「何者でもない自分」が最強の武器になる生き方】 「やりたいこと」なんてなくていい。 「相手がしてほしいこと」をしよう。ただし、とことん、徹底的に――。 マーケティングの英知が生んだ【4ステップ】で 「仕事」「キャリア」「副業」「プライベート」…すべてで「求められる人」になれ! STEP1 「自分がもっとも輝く場所」が見つかる…………市場を定義する STEP2 「相手が本当に欲するもの」がわかる……………価値を定義する STEP3 「自分がやるべきこと」がわかる…………………価値をつくりだす STEP4 「自分を必要とする相手」に見つけてもらう……価値を伝える 【本書の効能】 ①あなたが「本当に輝ける場所と方法」が見つかる 自分からではなく「相手からスタート」するマーケターのような生き方で、 どんな人でも「必要とされる場所」と「そこで輝く方法」が見つかる! ②「マーケティング」の本質がわかる さまざまな場面で価値観が激変する世界では、 「市場を定義し、価値を定義し、つくりだし、伝える」マーケティングの知識は すべてのビジネスパーソンに不可欠なスキルになった。 その本質を、マーケティング実務のカリスマが余すところなく解説! 【著者からのメッセージ】 自分に特別な才能がないことは自覚しています。 もしあったとしたら、あの「暗黒時代」はなかったはずです。 私が「人から必要としてもらえる」ようになったのは、 そんな暗黒時代から現在に至る20年で体得した、 「生きる知恵」としてのマーケティングのおかげです。 私はマーケティングを理解することを通じて、 仕事の幅を大きく広げることができました。 そして、キャリアプランを見直すこともできました。 のみならず、それを生き方のレベルにまで広げることで、 個人としての情報発信や趣味も充実させることができました。 本書ではそんな「生きる知恵」としてのマーケティングを、余すところなくお伝えします。
-
4.1日本人よ、これが世界最強の米国人の投資術だ! 月間120万PV!の人気サイト運営人が初めて明かす 投資大国の全ノウハウ アメリカの有力投資家はこんなノウハウで株を買っている! 日本人も徹底的にロジカルな投資手法を学んで、よりスマートな投資家になろう! 「Market Hack流投資術10カ条」 1.営業キャッシュフローのよい会社を買え 2.保有銘柄の四半期決算のチェックを怠るな 3.業績・株価の動きが荒々しい銘柄と、おとなしい銘柄を上手く使い分けろ 4.分散投資を心がけろ 5.投資スタイルをきちんと使い分けろ 6.長期投資と短期投資のルールを守れ 7.マクロ経済がわかれば、投資家としての洗練度が格段に上がる 8.市場のセンチメントを軽視する奴は、儲けの効率が悪い 9.安全の糊代(のりしろ)をもて 10.謙虚であれ(投資の勉強に終わりはない) この10カ条さえ励行すれば、投資で大失敗はしません。 【主な内容】 序章 1990年代のシリコンバレーとMarket Hack流投資術が編み出されるまで 第1章 Market Hack流投資術 第2章 ポスト団塊ジュニア世代のネストエッグ戦略 第3章 デイトレーダーへの道 第4章 長期投資のコツ 第5章 2014年の投資機会
-
4.0最近10年間で約10万人にのぼる消費者からマーケティングリサーチをおこなってきている著者が消費者の意識を「聞き出す技術」を余すことなく解説。読めばあなたも名マーケッター。
-
-練習問題を解くワークブックスタイルでマーケティングを学ぶ。「自分は最近何を買ったか」「最近、気になる広告は?」といった身の回りの事柄から基礎と実践を学ぶスタイルを採用。 【主な内容】 第1章 マーケティングの思考 第2章 消費行動の理論――「演習I 自分の買い物」から学ぶ 第3章 日本の市場環境の変化 第4章 消費環境の変化――「演習II タウンウォッチング」から学ぶ 第5章 メディアとコミュニケーションの変化 第6章 マーケティング戦略の分析――「演習III コミュニケーション読解」から学ぶ 第7章 社会の構造変化とマーケティング――「演習IV 仮説構築と課題発見」から学ぶ 終 章 マーケティングの素養とは
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ビジネススクールでは教えないマーケティングの発想力と思考力を身につけるための1冊。観察から、発想、企画立案、プレゼンまで、実務担当者に必要な基本プロセスが独習できる! 【主な内容】 第1部 現状を分析する技術 第1章 するべきことを見通す 第2章 生活者と社会を知る 第2部 針路を選ぶ技術 第3章 課題を発見する 第4章 ターゲットを描く 第5章 ポジショニングを定める 第6章 コンセプトを築く 第7章 コミュニケーションプランまでのストーリー 第3部 考えを表現する技術 第8章 企画を決める 第9章 プレゼンテーションを組み立てる
-
3.6「もし、あなたが○○○のマーケティング担当者になったら?」 こうした問いかけを本書では行なっている。家電メーカーの業界シェアトップの自動炊飯器、日産自動車のマーチ、独立系レコードレーベル、化粧品会社のナチュラルコスメ事業立ち上げといったケースを扱いながら、「もし、あなたがそのマーケティング担当者になったら、どう考え、どう行動するか」を解説している。 具体的な商品、企業名は出てくるものの、マーケティング担当者は架空の人物であり、いずれも経験豊富なマーケッターではなく、もともとは研究開発者、営業マン、IT部門マネジャーながら、マーケティング担当者になったという設定になっている。これらの担当者になったつもり、自分ならどうするかを考えることで、実践で活用できる知識と知恵が身につくようになっている。 もちろん、こうしたケースの前に、マーケティングの理論、概念、考え方、事例を解説している。ただし、解説の仕方は他のマーケティング関連書とは大きく違う。マーケティングの実践の中で役立てる、あるいは、その後に掲載されているケースに対して「どう分析するか?」「その結果、どのようなアクションを起こすか?」を検討するための解説である。教科書的な説明ではなく、筆者自身の経験や優秀な経験豊富なマーケッターたちからの情報・知見をベースし、実践に役立つ解説になっている。
-
3.8マーケティングマインドとは、顧客に「買う理由」を提供すること。顧客に喜んでもらいたい、驚いてもらいたいという気持ち、すなわちマーケティングマインドを常に忘れないようにすれば、顧客に「買う理由」を提供できるようになる。 例えば、BMWのチーフデザイナーは「どんな車に乗りたいですか」と聞くのではなく、7シリーズのような高級車に乗るのはどういう人なのかを徹底的に考え、その人たちが求めているデザインを想定する。 「BMWは顧客の声を聞かない」「ユニクロのターゲットは広くて狭い」「経済危機で売上を伸ばしたウォルマート」……。 豊富な事例、エピソードから、マーケティングの重要なテーマ、キーワード、そして新たなトレンドを学ぶ「教科書」。
-
-明治、青学、立教、中央、法政の5大学は「MARCH」と称され大きな存在となっている。少子化、グローバル化、定員厳格化などで変革を迫られる今、伝統とブランド力を武器に名声を高めている。5大学とも国際系などの新学部を設け、時代の要請に応えようと、グローバル人材の育成に力を入れる。さらに文理融合やAI(人工知能)、リーダーシップといった先端教育にも着手。改革に遅れる国公立大学を尻目に、私立大学ならではの独自性を確立している。 その結果、受験生からの人気は上昇。少子化にもかかわらず、志願者数は右肩上がりだ。改革を進める有力私大の今に迫る。 本誌は『週刊東洋経済』2019年12月21日号掲載の32ページ分を電子化したものです。
-
3.8
-
-スマホゲームの「モンスターストライク(モンスト)」は、ミクシィにモンスターな利益をもたらし、利用者は累計3000万人超に達した。しかし、過去の「一本足経営」の苦い経験から、その脱却と危機感を強調する。M&Aを通じて事業領域を拡大する中で、次に見据えるのはチケットアプリ「チケットキャンプ」。絶好調のミクシィが描くこれからを笠原会長、森田社長に聞いた。 本誌は『週刊東洋経済』2016年4月30日・5月7日合併号掲載の6ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● ミクシィの焦燥 モンストで一気に逆転 スマホゲームの穴埋めをゲーム以外ができるのか 【INTERVIEW】ミクシィ会長・笠原健治 【INTERVIEW】ミクシィ社長・森田仁基
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本が直面している現実の経済政策問題を評価する方法を学ぶための、ミクロ経済学の入門テキスト。 基礎理論と、「市場の失敗」「政府の失敗」の分析をとおして基本的な考え方を学ぶ。 ○本書の特徴 (1) 加減乗除以外の数学を用いず、需要・供給分析の応用により経済学の基本的な考え方を学ぶ。 (2) 日本の現実の経済政策問題を数多く分析。 (3) 理論トピックは、日本の経済政策問題に役立つものを選択。 (4) 独学者にとっても、自分の興味あるトピックに最短時間で到達できる。 (5) 経済学的な政策判断の基本的な考え方の背景にある暗黙の前提を、掘り下げて解説。 本書は、従来の日本のミクロ経済学の教科書と異なる目的を持っています。 従来の日本のミクロ経済学の教科書の多くは、より高級な経済学を分析するための基礎を作ることを目的としています。このため、経済学を専攻する人のためには役立つが、それだけを読んでも現実の日本の政策問題に対する判断はできません。 それに対して、本書は、現実の経済政策問題を数多く分析することを通じて、経済学を初めて学ぶ人が、日本が直面している広範な経済政策問題に関する対応策を自分自身で考えられるようになることを目的としています。 そのような教科書は、大学生だけでなく、経済学を独習したいと考えている社会人にも、大学で経済学を専攻するかどうか判断しようとしている高校生にも、役立つでしょう。 序章 市場と政府の役割分担 1章 市場 2章 供給 3章 余剰と参入規制 4章 市場介入 5章 弾力性・限界収入 6章 規模の経済:独占 7章 外部経済と不経済 8章 減産補助金と環境権 9章 情報の非対称性 10章 公共財 11章 権利の売買
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プログレッシブ経済学シリーズの八田達夫著『ミクロ経済学I』『ミクロ経済学II』の2冊の幹の部分のみを1冊にまとめたもの。単純に「章」を抜き出したのではなく、章ごとに再構成が行われ、大幅に加筆作業が行われた「最新要約版」となっている。多量の図のすべてに「説明」が加えられ、それを追っていくだけでも復習が可能になりました。ミクロ経済学の最重要な部分の展望を与えるとともに、独習書として読み終えた後では、さまざまな経済政策問題への対応策を自分自身で考えられるようになることができる。 本書の特色は、以下の点に要約されます。 第1に、加減乗除以外の数学を用いていない。 第2に、現実の日本の経済政策問題を数多く分析している。 第3に、需要曲線と供給曲線と余剰の概念を用いて分析を貫いている。 第4に、独学者が部分的に読んだ知識でも現実に活用することができる。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、経済学を初めて学ぶ人が、さまざまな経済政策問題への対応策を自分自身で考えられるようになることを目的としたミクロ経済学の入門テキストです。 上巻(I)では,市場と政府の役割分担を明らかにしたうえで、市場の失敗と政府の失敗への対策を論じました。 本巻(II)では、労働・土地・資本市場をくわしく分析し、それを土台に、格差是正政策と効率化政策との関連を明確にします。さらに、その視点から現在日本の経済政策を評価します。 ○本書で扱う課題 【格差是正】 家計が得る所得(賃金,地代,家賃など)が市場でどのように決まるかを分析し,所得格差の原因を探り,格差是正策を論じます。 【効率化】 まず,労働・土地・資本市場の余剰分析を行います。つぎに,社会的機会費用の概念を用いて,独占や外部不経済などの非効率を示します。さらに厚生経済学の基本定理を証明します。 【格差是正と効率化の両立】 格差是正政策が効率化政策と両立可能であることを示し,そのうえで,日本では効率化政策も格差是正政策も実行する余地がきわめて大きいことを示します。けでなく、経済学を独習したいと考えている社会人にも、大学で経済学を専攻するかどうか判断しようとしている高校生にも、役立つでしょう。 <I巻-市場の失敗と政府の失敗への対策>に続く 12章 フローとストック 13章 労働 14章 生産要素の総量市場と帰属所得 15章 供給者による自家消費 16章 混雑 17章 長期と最長期 18章 生産と消費の基礎理論 19章 厚生経済学の基本定理 20章 社会的厚生 21章 効率化政策 22章 格差是正政策 終 章 効率化政策と格差是正政策の両立
-
3.0親、子、配偶者、兄弟、親族、内縁関係、友人…… 身近な人が亡くなった後のトラブルを避けるために、いま何をしておくべきか? 終活に必要な心構え・手続き・お金のすべてがこの一冊でわかる! 突然やってくる身内の死―― 本人が“元気なうちに”知識を備えておくことで、いざというときあわてず、トラブル防止にもつながります。 「ああしておけばよかった……」と思ったときにはもう遅いのです。 「親が寝たきりになったら仕事を辞めないといけないの?」 「介護に必要な手続きやかかる費用がわからない」 「身内が亡くなったとき、どんな手順で葬儀を出したらいい?」 「相続の申告モレをして損をするのではないか?」…… 多くの人が持つそんな漠然とした不安。 それらを解消するため、お金のエキスパートであり人気ファイナンシャルプランナーの著者が、自らの体験をもとに「いまやっておくべきこと」「事後にしなければならないこと」をわかりやすく時系列で解説します。 「だれが、どこへ、いつまでに、なにを」提出するのかが一目でわかる「手続きチェックリスト」付き。 ●本書の5大特色 <元気なうちに> (1)事前に読んでおくことで、いざというとき慌てず、親族とのトラブル防止に (2)実例をもとに具体的な状況をイメージしながら、対処法やノウハウを学べる <亡くなってから> (3)実際に使用する書類を見ながら手順を確認できるので、頭に入りやすい (4)煩雑な各種手続きや時間に追われる葬儀の流れが一目で分かる (5)「手続きチェックリスト」を活用して、申告モレなし!
-
-2002年と2011年に2度の大規模障害を経験している「みずほ」。21年に入ってからも頻発している障害。なぜ、こんなに頻度が多いのか。インフラとしての役割も持っている銀行のシステムでは安定稼働が第一。そこにはコストをかけるのが基本。ところが、みずほはコストカットの圧力が強く、お金も人も不足しているようだ。3行統合から20年。みずほ誕生時からの歴史も振り返えり、今後のみずほはどうなっていくのか、最新の戦略や企業向けのメインバンク調査を基に分析する。 本誌は『週刊東洋経済』2021年10月23日号掲載の33ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
4.3いつも結果を出す人と、 努力だけで終わってしまう人は何が違うのでしょうか。 この違いは、自律神経のバランスで説明できます。 最近の環境の厳しいビジネスの世界では ストレス要因に事欠きません。 ストレスなどで緊張が高まると、 どうしても交感神経が優位な状態になります。 つまり、多くのビジネスマンが、 副交感神経が下がったままの状態でいるのです。 これが、努力しても結果に結びつかない要因になっています。 スポーツであろうと、ビジネスであろうと、 交感神経と副交感神経という2つの自律神経のバランスが、 パフォーマンスに大きな影響を及ぼしていています。 100パーセントの実力を発揮するには、 自律神経のバランスをよくする必要があるのです。 自律神経を意識することで、 あなたの仕事のやり方はまったく違うものになります。 それによって導き出される結果も大きく変わります。
-
-
-
3.9霞ヶ関からの緊急提言! 電機・情報通信産業の5つの環が切れている! つなげば日本は浮上できる!! 5つの失われたピース(ミッシングリンク)を埋めることでパズルは完成し、デジタルエコシステムが機能しはじめ、好循環の上昇スパイラルが生まれる。 日本の電機・情報通信産業はデジタルエコシステムにうまく対応できていない。結ばれるべき環が欠けていてデジタルエコシステムが築けていないのだ。つまり、ミッシングリンク(失われた環)が存在している。 ミッシングリンクとは、生物の進化に関する議論に登場する用語だ。ある種が進化する過程で、進化の途中段階を証明する化石が発掘されない場合、それをミッシングリンクと呼ぶ。時間の流れに合わせたパズルの中で、真ん中のピースが埋まらない状態であり、ここを埋めることでパズルは完成する。 日本の電機・通信情報産業におけるミッシングリンクが5つある。 1:「機器」と「サービス」をつなぐ環 / 2:「供給者」と「利用者」をつなぐ環 / 3:「情報通信産業」と「他産業」をつなぐ環 / 4:「国内」と「海外」をつなぐ環 / 5:「官」と「民」をつなぐ環 5つの失われたピース(ミッシングリンク)を埋めることでパズルは完成し、デジタルエコシステムが機能しはじめ、好循環の上昇スパイラルが生まれる。
-
-1870年(明治3年)の創業から2020年で150周年を迎えた名門財閥。三菱は幅広い事業分野に根を張る日本を代表する企業集団だ。グループの企業数は4521社。3大財閥グループの中でも群を抜く。資産、負債・純資産計は約433兆円にも上り、その額は国の資産が約670兆円であるのと比べると圧倒的だ。歴史の流れとともに、最強集団としての地位を強固にしてきた三菱。かつてないグローバル化やデジタル化という令和の荒波を前に、150年目という節目に立った名門財閥はどこへ向かうのか。その「潜在力」と「山積する課題」を追った。 本誌は『週刊東洋経済』2020年3月21日号掲載の34ページ分を電子化したものです。
-
4.1〈著者メッセージ〉「ほめる」より「認める」ことでヤル気を引き出すビジネススキル ほめ方、しかり方について書いた本が書店にあふれています。しかし、はたしてそれでほんとうに自信がついたり、やる気がでたりするでしょうか? 最近、上司が部下をほめるたびにシラけた空気が職場に漂いはじめるといわれます。ほめるのが逆効果となり、社員がやる気を失ったり離職したりするケースもみられます。それらは、ほめるという行為が、実は欺瞞(ぎまん)や作為と隣り合わせだということを示しています。 相手をイルカやアシカのような「動物」レベルではなく、人格と意志を備えた「人間」として尊重するなら、ほめるより「認める」ことのほうが大切なのです。認めることで長期的な有能感、自己効力感を高めれば、人は自ら努力し、成長していきます。 本書では、どのように認めるか、かりにほめたりしかったりする場合にはどこに気をつけなければならないか、そして「認める制度」である表彰のポイントはどこにあるかについて、最新の研究成果、国内外の先進的な企業の事例、職場のエピソードをたくさん盛り込みながら、ハンドブック風に仕上げています。
-
-近年、持続可能性を意味する「サステナビリティ」、あるいは2015年9月の国連サミットで採択された国際目標である「持続可能な開発目標(SDGs)」という言葉を目にする機会が増えつつある。また、サステナビリティ・SDGsの実現においては、国家という枠組みにとどまらず、企業が果たすべき役割が大きいことも指摘されている。 現実として、投資家や顧客が企業によるサステナビリティの取り組みを評価し、社員が企業のサステナビリティ、SDGsについての関心度合いで会社を選ぶ状況も明らかになってきている。 そのような状況下で、SDGsに明示されるサステナビリティと利潤の同時追求は、企業にとって新しいテーマであると同時に、むしろ積極的に目指すべきテーマである。サステナビリティやSDGsを理解しないまま、利潤の追求に走る企業は、淘汰されかねない時代に突入している。 本書は、次世代産業の中核要因を社会課題の解決に置き、それらを産業・市場として捉え、さらに具体的なビジネスにつなげていくために、「インプルーブ」「エネーブル」「アドボケート」という3つの視点を提示し、これらを通して社会課題の解決と企業としての利潤を同時に追求していくことが肝要と指摘する。 今なお、サステナブルな社会の実現には課題も多く、急務となっている取り組みも存在する。その中で、本書は、ともすれば日本企業の対応は遅れがちともされるなか、日本企業が日本の強みを活かす余地はあると主張する。 そして、グローバルな市場で日本企業が存在感を発揮していくための方法を提案する。これからサステナビリティをビジネスチャンス、収益の柱としていく上で、不可欠な情報を網羅する。
-
3.9今の政府は、40年前のOSで動いているコンピュータのようなものだ。 遅くて、処理できる問題の範囲もせまい。 こんなに世界がつながっているのに、誰も政府とつながろうとは思わない。 では、どうするか。 シリコンバレーを擁するカリフォルニア州の副知事であり、 自らも起業家としてビジネスを手がける著者が、起業のビジョナリー たちとの対話を通じて、未来の政府の姿を描く。 ●もし、お役所にシリコンバレーのアイデアとツールを取り入れたら? 市民の熱狂的参加を促す、オズボーン=ゲーブラーの「行政革命」を 超える、新しい「行革バイブル」 ●新しいツールとアイデアで、市民による本当の自治を実践! スマホ、アプリ、ソーシャルデータ、ビッグデータ、ゲーミフィケーション。 新しいツールを活用してコミュニティを改善したアメリカの事例を多数紹介。 成功例だけでなく、失敗例も紹介。 ●政府はプラットフォームとなれ! 政府、行政は、みずからすべてを解決しようとしてはいけない。 持てる情報を公開して、課題の発見と解決は、市民の力(アプリ)に 委ねればいい。 ●起業のビジョナリーたちの知見が満載。 J・ストッペルマン(イェルプ共同創業者) A・ハフィントン(新時代のメディア王) P・ディアマンディス(Xプライズ創設者) E・ウィリアムズ(ツイッター共同創業者) S・ブランド(『ホール・アース・カタログ』創刊者)など
-
5.0「未来構想力」「実践知」「突破力」「パイ(Π)型ベース」「場づくり力」 次世代リーダーに不可欠な5つの力を身につける MBA理論を学んでも変革リーダーにはなれない 野中郁次郎氏推薦 「スケールの大きな正しい野心を持ったリーダーの資質、いわば未来創造の起業家精神を持つリーダー像、それがイノベーターシップというコンセプトなのである」 「イノベーターシップ」とは、「マネジメント+リーダーシップ」を超えて、「高い志で未来の社会を創造していく力」。 本書ではイノベーターシップに必要な5つの力と、それらを身につけるためのトレーニング方法について詳述している。 また、自らの信念を打ち立て、イノベーションを実践している5人のイノベーターを紹介している。 5人のストーリー、インタビューから、5つの力をどのように身につけ、イノベーターシップをどのように発揮して、自分の思いを実現していったらいいのか、リアルにイメージできる。
-
-\SDGsについての知識を深めるだけでなく、就職活動にも役立つ企業情報が満載です!/ “持続可能な”社会づくりで、“持続可能な”企業に。 国際課題解決のために定められたSDGsに、日本はどのように取り組んでいくべきでしょうか。 各国の取り組みに注目が集まるなか、長野県では企業側のSDGsの取り組みを支援する制度を先進的に制定しました。本書はそんな長野県に焦点を当て、各企業の工夫を本書でたっぷりと紹介します。 SDGsに関する本は沢山ありますが、その多くは企業の取り組みの紹介で留まります。本書では、取り組みはもちろん、企業理念、製品開発、人材育成など、事業の根幹に関わる点まで深堀りしていきます。
-
4.4大人が学んでおきたい「政治のしくみ」基礎のキソ。 民主主義の根幹を、サントリー学芸賞受賞・新進気鋭の政治学者が一からわかりやすく解説する。 日本政治をリアルに理解するための新常識が、この1冊に凝縮! ・そもそも選挙で「いちばんいい候補」を選べるの? ・自民党はなぜ強いのか?これからも強いのか?? ・なぜ、町村議会議員は「無所属」ばかりなのか? ・18歳が選挙権を持つってどういうこと? ・ダメ党首を辞めさせるには? ・参議院っていらなくない? ・どうして「高齢者」と「農村」が優先されるのか? ・「AKB総選挙」とふつうの選挙の共通点は? ・「統一地方選挙」って何の意味があるの? 読めば、こんなソボクな疑問もスッキリ解けて、 明日からニュースの見方が変わる!
-
4.4
-
-親、兄弟・姉妹、配偶者、子ども。今、ペットはこうした血縁者に次ぐ「第5の家族」と呼ばれる。犬・猫を飼っている家庭は全国に1300万世帯。これら家庭の少なからずが、ペットの病と老いに悩んでいる。高齢期を迎えたペットの身に起こることは、人間の高齢者とほとんど変わらない。しかも小動物医療が人間の医療と遜色のないほど高度化している。選択肢も豊富だ。ただ、その医療費は安くはなく不安と疑問もいっぱいだ。やがて終末期を迎え、ペットを失う悲しみも人と同じだ。一方で殺処分問題や生体展示販売などに目を向ければ、「うちの子じゃない子」のためにもできることもある。女優・杉本彩さんと作家・佐藤優さんの異色対談を通じて、人とペットのこれからを見つめたい。 本誌は『週刊東洋経済』2016年9月10日号掲載の28ページ分を電子化したものです。
-
3.5米国型株主重視経営は企業や社会をダメにする! いまこそ経営者が真剣に考えるべき国民を幸福にする「公益資本主義」について提言する。 最近の世の中を見てみると、どうもそういった本来の存在意義が薄れ、どれだけ最終利益を上げることができたか、どれだけ株価を上げることができたか、そんなことだけが企業価値であるという風潮が高まっており、強く危惧の念を抱いております。日本では古来より、数々の素晴らしい教えが伝えられてきました。自分も相手も満足し、そして社会全体にとっても貢献できるのが良い商売であるという「三方良し」の精神。あるいは、不正なやり方はせず、一所懸命、額に汗して働く「浮利を追わず」の精神。そして、上手くいっていても、時には一歩踏み留まって、振り返る謙虚さ、「足るを知る」という精神。こうした精神をしっかりと持ち会社を運営していくことこそが、私は企業の本来のあるべき姿ではないかと考え、今回この書籍を出版する決意をさせていただいた次第です。(「まえがき」より)
-
-2017年に成立した民法の一部改正が、2020年4月から施行された。1896(明治29)年に制定され120年間にわたり専門家の解釈や判例の蓄積により補われてきた。法律の条文を見てもわかりづらく、ビジネスの現実には適用しづらいものになっていた。そこで、契約に関する「債権法」を大幅に見直し、これまでの解釈や判例によるルールを明確化したのである。そのほか、同じ民法において、国民的な関心を集める改正相続法のほか、企業活動や私たちの日々の働き方に直結する労働法についても、法律の専門家に詳しく解説してもらう。 本誌は『週刊東洋経済』2020年4月4日号掲載の28ページ分を電子化したものです。
-
-
-
3.5GAFAが台頭する中、無形投資の増大は生産性や格差にどのような影響をもたらすのか? 企業・投資家・銀行・政府はどのように対応すべきか? 有形資産とは異なる無形資産の4つの特徴とは何か? これまで計測できなかった無形資産の全貌を、初めて包括的に分析した画期的名著 『フィナンシャル・タイムズ』ベスト経済書 【推薦の言葉】 「世界経済最大のトレンド『無形資産』を理解したければ、本書を読むべきだ」――ビル・ゲイツ 【無形資産の一例】 ・スターバックスの店舗マニュアル ・アップルのデザインとソフトウェア ・コカ・コーラの製法とブランド ・マイクロソフトの研究開発と研修 ・グーグルのアルゴリズム ・ウーバーの運転手ネットワーク
-
4.0「無形資産」の全貌を明らかにした著者による最新作! 成長、格差解消、イノベーションを加速させるために必要なこと 経済のフロンティアで何が起きているのか? 無形資産が経済を支配する中で発生した、「経済停滞、格差拡大、機能不全の競争、脆弱性、正統性欠如」という5つの大問題にどう立ち向かえばいいのか? 金融と経済政策立案の最前線で活躍する著者がその経験を生かし、処方箋を提示する。 『無形資産が経済を支配する』 (『フィナンシャル・タイムズ』ベスト経済書) 著者による続編! Haskel &Westlake著Restarting the Future: How to Fix the Intangible Economy、待望の邦訳
-
-
-
-
-
4.2新型コロナウイルスの出現、大規模災害をもたらす気候の激変と温暖化、グローバル資本主義による格差と分断・・・ 人類は「拡大・成長」と「不老不死」の夢を未来永劫、追い続けるのか。 地球規模での「第三の定常化」時代に向かう現在、人類が「無」をどう捉えてきたかを遡りつつ、私たちの世界観、生命観、死生観の在り方を壮大なスケールで問いなおす。 人口減少・定常型社会の社会保障、コミュニティ、死生観、哲学等、ジャンル横断の研究・発言を続けてきた第一人者による人類史への気宇壮大なアプローチ。 [第一の定常化]ホモ・サピエンスの増大 →転換1「心のビックバン」 [第二の定常化]農耕と都市の拡大 →転換2「枢軸時代/精神革命」 [第三の定常化]近代の進歩 →転換3「地球倫理」へ 人類は新たな「生存」の道への転換を図れるのか? 「狩猟採集社会や農耕社会それぞれの拡大的発展において、それが資源・環境的な制約にぶつかった際、人間はそれぞれ『心のビッグバン』『精神革命』という大きな意識転換あるいは従来になかった思想ないし観念を生み出し、…新たな『生存』そして『創造』の道を見出していったのだ」(本文より)