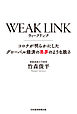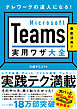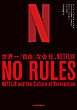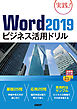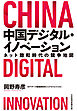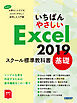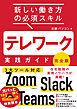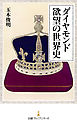日経BP作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.0知的興奮を呼ぶ、まったく新しい日本論! 文系・理系両極のキャリアを重ねた麻布卒の同期生による、この国の閉塞感の原因を問い、その解決策を考える対談集。 このままで日本は本当に大丈夫なのか、必要な改革がなかなか進まない原因はどこにあるのか、我々が皆、自身の属する閉鎖的な組織(タコ壺)にどっぷりつかり、内輪のルールや「空気」に従うのが当然だと思っていることに原因があるのではないか――。 文系・理系の無意味な「区別」への疑問を端緒に、タテ割りを排し、既得権に切り込み、現状を打開するための方策を考える。
-
3.8同じ仕事をしている限り、給与は「ずっとそのまま」の時代!? これからやってくる“ジョブ型”時代を僕たちはどう生きるか―― “そうはいっても、日本はまだまだ年功序列でしょ”“?なんだかんだ言って終身雇用は続くよね‥” コロナショックは、そんなこれまでの日本の常識を根底から変えつつあります。 ジョブ型雇用に、テレワークの普及……会社員の働き方と雇用や給与の在り方が激変するいま、どうすれば、新しい仕組みの中で、自分のキャリアと生活を保っていけるのでしょうか。 人事のプロフェッショナルが、テレワークで評価されるためのヒント、転職先の見極め方から住居の探し方まで、クライシスを生き延びるためのヒントを授けます。
-
4.5〇新型コロナウイルスはいつ、どのようにして収束するのか――。本書は、世界中の人々が抱くこの問いに答える書。COVID-19というウイルスの特性、治療薬やワクチン実用化の見通し、経済社会や医療・ヘルスケア業界に及ぼす影響まで分析する。 〇「日経バイオテク」への緊急寄稿、「新型コロナの収束シナリオとその後の世界」をベースに、最新情勢を加筆。
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「超図解」をうたい、全60点のインフォグラフィックスを収録した、最新メソッドまで身に付けられるマーケティング入門書の決定版。全20テーマについて、各テーマを5分で学習できる。博報堂の現役トップマーケター21人が総力を挙げて、新人マーケターに向けて初歩の初歩を手ほどき。マーケティング理論を最新版にアップデートしているので、中堅マーケターにとっても基本を振り返りつつ、読後すぐにも現場の業務に役立つ最新メソッドを身に付けられる。 ●そもそもマーケティングがどんな役割を果たす存在か、ちゃんと理解したい ●スピーディーな現代、どこが自社の強みなのか改めて浮き彫りにしたい ●生活者の心をつかむようなブランドは、どう定義すればよいのか ●D2Cなどが登場した今、チャネルはどう再設計をするとよいのか ●マーケティングプロセスが適切かKPIを設定したいが、うまくできない ●せっかく集めたビッグデータを使って、効率的に顧客へアプローチしたい ●国・地域ごとの特徴に合わせてデジタルマーケティングはどう実践すべきか こうした新人マーケターが抱えがちな数々の悩みに答えるべく、博報堂マーケティングスクールでも教える総勢21人のトップマーケターが書き下ろし。この1冊ですべての疑問が氷解します!
-
3.9※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ベストセラー『ファンベース』著者の佐藤尚之(さとなお、ファンベースカンパニー会長)と、ネスレ日本でコーヒーのオフィス向け定期宅配サービス「ネスカフェ アンバサダー」を大成功に導いた津田匡保(ファンベースカンパニー代表)の共著による待望の書。漫画と対談でファンベースの実践ポイントを解説します。 人口急減や超高齢化、超成熟市場といった消費環境の一大変化に加え、相次ぐ自然災害の発生などで「先が見えない時代」。あなたの会社や事業の逆境を支えてくれるのは、まだ見ぬ新規顧客ではなく、熱烈に愛してくれている「ファン」の存在です。 さとなおが提唱するファンベースとは、「自社のサービスやブランドを愛してくれるファンを大切にし、ファンをベースにして、中長期的に売り上げや事業価値を高める」考え方。 ともすれば、顧客を囲い込む、無理に増やすといった発想に陥りがちな「ファンマーケティング」や「コミュニティービジネス」とは一線を画すものです。 みなさん、頭では理解したつもりでも、「実際どうやってファンベースを実践すれば良いのか分からない」というのが本音でしょう。それに100%応えるのが本書です。 本書では、さとなおによる漫画版ファンベース最新解説に加えて、ファンベースに試行錯誤しながら取り組んでいる「ファンベースなひとたち」の実践例を漫画と対談形式で紹介していきます。 「中の人」はどんな思いで、どんな苦労を積み重ねながらファンと共に成長の道を歩んでいるのか――。漫画と対談で分かりやすくひも解いていきます。 楽しいファンベースの世界へ、ようこそ!
-
3.9建設投資60兆円 眠れる巨大産業が覚醒する!! 「アナログ産業」の代表格とみなされてきた建設産業は、いかにDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組むべきか。2018年10月発行の前作「建設テック革命 アナログな建設産業が最新テクノロジーで生まれ変わる」で深掘りした土木分野のその後と、建築・都市分野の動向を、専門記者が豊富な事例を基に描く ■主な内容 はじめに コロナ・ショックが迫る建設DX 第1章 ゼネコン研究開発2.0 第2章 リモートコンストラクション 第3章 BIMこそが建設DXの基盤である 第4章 創造性を解き放つ建設3Dプリンター 第5章 モジュール化の世紀、舞台は現場から工場へ 第6章 「建設×AI」で単純作業を爆速化 第7章 建設テック系スタートアップ戦記 第8章 全てはスマートシティーにつながる
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 インターネットに代表されるTCP/IPのネットワークでデータがどのように相手に伝わるかきちんと説明できますか? VPNがどうして安全なのか理解していますか? IT分野のエンジニアでも意外とネットワークのことはしっかりと分かっていないもの。「苦手」とか「難しい」といった意識を持っている人も多くいます。ネットの活用はしていても技術としては理解していない人が多いのは残念なことです。 本書は日経NETWORKの人気連載「インター博士とネット君のスッキリわかる!ネットワーク技術解説」をまとめたもの。ていねいな図解で基礎から分かりやすく、しかもしっかり理解できるように説明しています。 TCP/IPの基礎から、UDPやマルチキャスト、QoSといった技術、ファイアウオールやアクセスコントロールなどのセキュリティの技術、HTTPSやVPN、IPsecといった暗号化の技術、Webやメールなどの様々なサービス、さらにはネット障害への対処法といった広範囲の内容を含んでいます。教養としてネットワークの技術を知りたい人にも、企業のネットワーク担当になって勉強が必要な人にも役に立つ内容となっています。
-
-■世界最大の震源地でリーダーシップを発揮し、賞賛を集めたアンドリュー・クオモ州知事を主人公に、コロナ渦に見舞われ、復活を遂げようとしているニューヨークを描く。クオモ州知事については、その英雄的な行動や記者会見が全米の注目を集め、大きな感動を呼んだことは知られている。本書では111日間に何が起きていたか、現地の目線で回顧する。 ■2020年、新型コロナウイルスは中国・武漢を発生源としてアジアや欧州へと感染が広がった。米国最大の商業都市ニューヨークを襲うのは時間の問題だった。3月1日に初めて感染者が確認されて以降、感染者はニューヨーク州だけで40万人近く、中核のニューヨーク市だけで20万人を超え、世界最大の震源地(エピセンター)となった。死者は州全体で2万人を大きく上回った。 感染被害を防ぎ、医療システムの崩壊を避けるため、厳しい外出制限が課され、街はロックダウン(封鎖)された。その後、感染被害がようやく落ち着き始めた5月から州の一部で経済活動が再開。もっとも被害が深刻だったニューヨーク市も6月に、経済再開の第2段階へと移った。経済活動の正常化は進みつつある。 ■クオモ氏は3月2日から土日も休むことなく記者会見を重ね、その数は110回に及んだ。感染者を確認した3月1日から111日。クオモ知事は何を考え、どう動いたか。ニューヨークの街がどのように変遷していったのか。なぜニューヨークでもっともウイルスが伝染したのか。そしてどのように事態は好転へと向かったのか。客観的な「事実」や「科学」を最重視し、データに基づいて意思決定するクオモ氏のやり方は光を放つ。
-
4.0●2019年12月に日本経済新聞に連載して好評だった澤部肇TDK元会長の「私の履歴書」を単行本化。 ●著者は大学を卒業した1964年、東京電気化学工業(現TDK)に入社。同社は、東京工業大学の電気化学科が発明したフェライトという磁性材の技術に鐘淵紡績(現カネボウ)が資金を投じて1935年に創業した、いわば大学発ベンチャーの走りのような会社。当時、東京・神田の6階建てのビルを間借りしていたTDKはその後、世界的な優良企業へと業容を拡大していく。同社の歩みと自身の半生を振り返る一冊。 ●著者は、工場や経理部などで厳しい上司の薫陶を受け、若くして社長室(のちの経営企画部)に配属される。ここで、同社の中核的な創業メンバーである3代目社長の素野福次郎氏、4代目社長の大歳寛氏の謦咳に接し、仕事や人生の諸々をじかに教わる幸運に恵まれる。中小企業だった同社は、音楽用カセットテープが大ヒットしたのを機に時ならぬ急成長企業となり、ニューヨーク証券取引所の上場を果たす。この間、著者は社長室の一員として経営を支え、貴重な経験を重ねた。その後、テープ事業を立て直し、磁気ヘッド事業では辣腕を振るい、社長に就任。ITバブル崩壊を乗り越え、新興のATLを買収して世界的な電池メーカーの礎を築いた。 ●書籍としてまとめるにあたっては、好評だった新聞連載と同様に紙幅の多くを経営中枢での興味深いやりとりに割いている。著者の人柄を反映した率直な心情の吐露が、本書をいっそう魅力的なものとしている。
-
4.4※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「今日、何つくろう?」の悩みがなくなる! 伝説の家政婦・志麻さんのとっておきレシピ&料理上手になれるワザ ゆるっと覚えて、毎日組み合わせを考えるだけ! 「子育て15年間」を乗り切るおいしい魔法、教えます! ◆実は簡単・手間いらず!フランスの家庭料理は子育て家庭の味方 ◆あなたも志麻さんになれる!調理・片づけを効率よく進める「プロの手際」を公開 ◆調理の「面倒くさい」が「楽しい」に!覚えたい「志麻さんテク」 ◆志麻さんの「しないワザ」も満載! 「下ごしらえしない」 肉&魚に塩を振るだけのフランス流メソッド 「特別な材料・調味料・道具は使わない」野菜はじゃがいも、にんじん、玉ねぎがあればいい 「手間をかけない」 基本はほったらかし!“暇な時間”の洗い物で効率アップ ◆フランス流の子育てアドバイス、夫・ロマンさんの子育てコラムも掲載! PART1 メイン10品/定番ハンバーグから15分で完成できるごちそうまで PART2 付け合わせ10品/作り置き×パパッと調理で、もう悩まない! PART3 スープ5品/脱・味噌汁! おしゃれなスープで野菜をいっぱい食べる PART4 離乳食&移行期3品/赤ちゃんも子どもも“大人と同じもの”で手間を省く PART5 とっておき5品/休日の豪華メインで食べる喜びを満喫する
-
4.0「観客には『自分が抱えている不安を、具体化、形象化してほしい』という気持ちがどこかに必ずある」 押井守監督はそう指摘します。 その時代に生きる人々の「無意識の不安」を探り当てて、エンターテインメントにするのが映画監督の仕事。不安の影を捉えればヒット作になるし、ビジネスにもつなげることができる、と。 この本で語られるのは、「宇宙大戦争」から「007 ロシアより愛をこめて」「仁義なき戦い」さらには「キャプテン・アメリカ」「ゲーム・オブ・スローンズ」まで、それぞれの時代をタイムカプセルのように封じ込め、大ヒット(中には渋いヒット)につながった映画とドラマ。第二次世界大戦から令和の世の中に至るまでを、エンターテインメントとして楽しみながら、その作品が作られた時代の背景を学ぶ、押井守監督による「現代史講義」、開幕です。ひと味違う映画ガイドとしても役立ちます。 いつもの押井節に乗って、自らの作品「THE NEXT GENERATION パトレイバー」についても解題していただきました。押井ファンには「オシイヌ」でおなじみ、西尾鉄也氏のイラストもたくさん収録しております。 エンタメ作品で時代を読み解く398ページ、押井節をたっぷりお楽しみください。
-
-◆The chain is only as strong as its weakest link ――鎖の強さはその最も弱い輪によって決まる (イギリスの格言。今回のコロナ禍の本質を突く言葉として本書では用いる) ◆パンデミックが起き、世界全体に拡大し、未曽有の経済災害となったのは、グローバル経済のエコシステムにウィーク・リンクがあったのではないか。世界的な供給体制、都市への集中、人やモノの移動速度と複雑な混じり合い、政治や宗教による対立や断絶が、パンデミックを起点とした世界的な経済危機にどのようにつながったかをダイナミックに描く。 ◆取り上げるテーマは日本よりも、世界に焦点を当てる。コロナウイルス危機のクロノロジーを描き、グローバル・エコシステムの最弱点に問題が起こり、それが弱いリンクを通していかに破壊的な力をもっていったかを解説する。 ◆著者は日本経済の長期停滞やリーマン・ショック、ユーロ危機などについて、内外の情勢をすばやく集め、ノンフィクション的な筆致やアカデミックな知見を織り交ぜながら数々の名著を執筆してきた経済学者。2019年からは経済財政諮問会議の民間議員も務めている。
-
3.2本書は古代エジプトの「第I部:会社以前」から「第II部:大航海時代と会社の誕生」「第III部:英国――産業革命の成立・発展・衰退」「第IV部:ドイツ――大企業と重工業の誕生」「第V部:米国――マネジメントと経営者の創出」そして現代の「第VI部:個人によるイノベーションと非営利組織の時代」という順番で進んでいきます。 第I部では古代エジプトのピラミッド建設から説き起こし、アテネやスパルタといった都市国家群、ハンザ同盟、十字軍を経てルネサンス期の商業都市ヴェネツィアに到着します。 第II部はなぜか2012年のロンドン五輪のエピソードから始まります。コロンブス、マゼラン、東インド会社を経て会社の誕生の軌跡を追い、辺鄙な英国がインドに植民地を築いた謎を解き明かします。 第III部の舞台は英国。なぜこの地で産業革命が成立したのか、成功したはずなのにドイツやアメリカと違って後世に生き残った会社はなぜないのかを解説します。英国は金融に向かっていったのですが、それは植民地と大きく関係しています。 第IV部では、そんなイギリスを凌駕し大企業と重工業を生み出したドイツに迫ります。同族企業が多く、本社は分散し、多くの巨大科学工業の発祥は染料工場であるなど意外な素顔が明らかになります。 第V部の舞台は米国です。主役はフォード、デュポン、GMなど今でも有名な企業です。意外なことに米国企業はイノベーションに強い訳ではなく、共通性部品、事業部制、フランチャイズ制などの知恵で大きくなっていったことが明らかになります。第VI部は現代です。米国大企業の黄昏と非営利組織の時代の到来を描きます。
-
3.8私の人生、何があっても大丈夫 ! どんぶり勘定、ズボラさんでもできる 毎日を心地よく過ごしながら家計と暮らしの軸を整えるTO DOリスト 新型コロナで世の中が激変したことをきっかけに、収入が減ったり、支出が予想外に上下したりと、お金の出入りがブレやすくなっていませんか ?先が見えない不安から、モノを買い込んだり、ストレスでつい散財してしまったり。これまで、「とにかくお金を貯めなければ」と貯蓄に励んでいた人も、不安ばかりが募りつつ家計管理ができていなかった人も、「本当に幸せな使い方、貯め方とは」?を考えるようになったのではないでしょうか。 本書はそんな人に向けて、毎日を幸せに過ごしながら家計や暮らしの軸を整えていく習慣を、実践しやすい「TO DO」としてまとめた本です。「お金のことは難しくて分からない…」という初心者でも、日々の暮らしのルーティンを変えるだけで、いつのまにか家計が整い、気持ちも前向きになってくるはず。新時代の「自分らしいお金との付き合い方」のバイブルとして、ぜひ手元に置いてください。 第1章 見つめる 価値観が変わる時代。お金を何と交換しますか ? 第2章 つかむ 「分からない」をなくせば不安は消えます 第3章 仕組化する 安定した家計の流れをキープします 第4章 焦らない 余裕のある毎日が、お金の乱れを防ぎます 第5章 増やす 今あるお金で、将来の自分の安心を育てます
-
-問題意識があるからグチが出る! 「デキる社員」よりも「グチる社員」を大切にすることから始める 生産性向上の秘策。 「グチを言ってはいけない」――多くの人がそう言われてきた。「グチグチうるさいんだよ」――仲間からも上司からも疎まれ、組織の足を引っ張るネガティブな存在として扱われてきた人は少なくないはずだ。しかし実は、グチの中にこそ、会社を変え、収益を上げる秘策のタネが隠されている。グチは経営改革を推進するエンジンでありエネルギーでもある「宝の山」なのだ。 本書は、グチに着目したユニークな経営改革を実践してきた筆者が、実際のクライアント先でのケースを織り込みながら解説する、上司と部下双方にとっての意識改革の本である。 令和時代、リモートワークの時代の上司に必要な能力は、グチという今まで誰も考えもつかなかったネガティブな感情の裏側にあるホンネを汲み取り、会社の生産性を上げること。これによって会社の上司と部下の関係がまったく違うものになる。自社や部門の運営に悩むトップやマネジャーはもとより、上司や会社に不満を感じているビジネスピープルにも支持されることが期待できる。
-
3.8〇資本主義は歴史上、最も成功した経済システムです。だが、いまやそれが、資本主義そのもの、そして世界を破壊する危機に直面しています。大規模な環境破壊、経済格差、信頼できる社会的な仕組みの崩壊という現代社会の大問題の解決のために、企業や個人はどのような役割を果たせるのか。 〇著者は、株主価値最大化のみを追求することそのものが問題を生み出していると指摘、共有価値の創造、共通の価値観に根差した目的・存在意義(パーパス)主導によるマネジメント、会計・金融・投資の仕組みの変革、個々の企業の枠を越えた業界横断的な自主規制、政府や国との協力が必要不可欠であることを説き、こうした行動には企業に利益をもたらす経済合理性があることを明らかにします。また、政府と市場は互いを必要とし、企業は民主的で自由な社会を支える包摂的な仕組みを強化するために積極的な役割を果たすべきだと提唱します。 〇15年にわたり強い危機感をもって問題解決に取り組んできた著者が、資本主義を創り直すための体系的な枠組みを提示します。
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 幼保無償化&私立高校の実質無償化を踏まえデータを刷新 ! 教育費の準備方法も時代とともに変わっています。 子育てを始める人&子育て中のすべての人に伝えたい親世代とは違う、教育費の「本当の」話 ! 子どもを育てるにはお金がかかると、心配しすぎていませんか ? パパやママの収入ごとに家族に合う教育費は変わります。 子どもの人数や習い事、進学コースによって最高の「お金の貯め方・使い方」があるのです ! 保育園、習い事、小学校、中学受験、高校、大学、留学…と、 成長ごとに必要なお金を知って、楽しく子育てをするためのポイントを、 マンガやイラストを交えながらやさしく、わかりやすく解説します。 ★教育費は「月額4万円」で赤ちゃんから大学までOK! ★え!?ずっと公立&ずっと私立で1400万円の大差 ★きょうだい1~4歳差で教育費負担はどう変わる ? ★ウィズコロナ時代に収入を増やす副業・起業、お金の注意点 ★子育て中、3回やってくる「貯めどき」を逃さないで ! ほか 第1章 子育てって、ざっくりどのくらいお金がかかるの? 第2章 ウチはどう貯める?どこまでお金をかけられる? 第3章 ママとパパどう働く?収入に合った幸せな生活スタイル 第4章 「親世代」とは全然違う!「私世代」のお金の新ルール
-
-「嘆きの人生から、喜びの人生へ」 「集金より支払いに気を遣え」 「天地自然の法則は厳しいものである」 千葉県成田市の建設会社4代目が「老舗の知恵」をひもとく 「われわれには100年が長いとは少しも思わない。 120年前の創業者の息吹がありありと感じられる」 幼少時から家訓をたたき込む、平山一族の「早期隔世教育」! 【目次】 第一部 徳の隔世教育 「我家の五箇条」大家族主義と玄松の集い 第二部 人生の指針となる言葉 第一章 良き習慣を作る 第二章 お金について 第三章 積徳の方法 第四章 より良き人生を生きるために 第五章 商売のコツ あとがきに代えて 「創業の精神」を受け継ぐ
-
4.0企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが加速する中、システムやサービスにおけるUX(ユーザーエクスペリエンス)の重要性は高まっています。システム開発において、質の高いUXデザインが強く求められるようになっているのです。 しかしシステム開発を手掛けるITエンジニアの中には、UXデザインを見栄えを良くすることだと限定的に捉えている人が少なからずいます。ユーザーにとって価値のある使いやすいシステムをつくるには、見栄え以外にも改善すべき項目がたくさんあります。 またUXデザインに取り組みたくても、その方法がわからないという声も少なくありません。本書は、ITエンジニアがシステム開発の中でより良いUXデザインを実現するための知識やノウハウを、基本と実践の2部構成で解説した一冊です。 基本編となる第1章では、UXデザインのプロセスをシステム開発と同様に上流から「戦略」「要件」「構造」「骨格」「表層」の5 つのフェーズに分け、各フェーズで取り組むことや進め方、よく利用されるメソッドやつまずきポイントなどをわかりやすく解説します。 実践編となる第2章では、基本編で紹介した5つのフェーズの実践に必要な体制や仕組み、実際に取り組んだ事例などを、具体的な勘どころも交えて解説しています。UXデザインに取り組んでいくうえで組織的に準備しておきたいことや、UXデザインの活用方法など、実践を支えるヒントや心構えなどにも触れています。 著者が実際のシステム開発現場で積み重ねた豊富な経験を基に、UXデザインの実践的なノウハウをITエンジニアの目線で整理し、解説しています。ぜひご活用ください。
-
3.8ボトルネックと技術的負債はどうすれば解消できるのか、 DXを実現する組織・システムの作り方とは――。 「速いものが遅いものに勝つ」痛快IT物語。 3000人規模の自動車部品製造販売会社パーツ・アンリミテッド社の凄腕プログラマー、マキシン・チェンバース。彼女は理不尽な理由から、デスマーチに陥っていた「フェニックス・プロジェクト」に配置転換されてしまった。 ビルドすらできない絶望的な環境で苦しみながらも、システムのボトルネック解消に努めるマキシン。運用や品質保証など他部署を巻き込みながら本番環境に迅速にデプロイできる体制を整えたあとには、技術的負債を払拭するためにクリーンコードで開発される「ユニコーン・プロジェクト」が待ち構えていた……。
-
4.2オンライン商談も怖くない、コロナ禍の「新常態」を味方に顧客と二人三脚で「知的創造活動」する「4つの要点」を説く4万部突破の前著「無敗営業」に続く、チーム戦略の指南書 需要の喪失や先送り、客先訪問もままならない営業活動──。コロナショックを経て、多くの企業が岐路に立たされています。 今、必要なのは、個人の技量に過度に頼らない「強いチーム」で営業活動に臨むことではないでしょうか。 東京大学経済学部を卒業し、外資系戦略コンサルティング会社を経て25歳で起業した筆者は、これまで一部上場企業を中心として、 3万人以上の営業パーソンに対して、コンサルティングや研修、講演を実施してきました。リピート需要や客先からの紹介による依頼が一年中、全国から寄せられています。 このほど、たくさんの試行錯誤や挫折を乗り越えてきた自分自身の経験と、顧客と共有しながら蓄えてきたノウハウを「強いチームづくり」の指南書としてまとめ上げました。 この本は、ポイントを「勝ちパターンをつくる」「活動の実態を『見える化』する」「人が育つ仕組みをつくる」「コミュニケーションのバランスを整える」の4つの要点に整理して章建てして、図表を多用しながら解説しています。 また本書は特に、対面営業の機会を絶たれてオンライン商談を余儀なくされている状況に対して、具体的なソリューション、勝ちパターンを提示しています。 ぜひ、組織に属するみなさんでお読みいただき、強い営業チームづくりに役立ててください。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ビデオ会議、チャット、ファイル共有、プレゼン・・・ わかれば簡単!サクサク操作で、もう戸惑わない ! 在宅勤務・テレワークの必須ツール、Microsoft Teamsの実践テクニックを徹底解説 よりスマートに、賢く使いこなすノウハウが満載! 新型コロナによる在宅勤務やテレワークの推進に伴い多くの企業が活用し始めたTeamsですが、なじみのないツールでマニュアル類も整備されておらず、現場で戸惑う人も多いようです。 そこで本書では、Teamsを活用するうえで知っておきたい操作の基本から実用ワザまでを、エンドユーザーの視点で徹底解説。「ここは戸惑いがち」という操作や、「これは便利!」というテクニックを網羅しました。 ◆外部の人を会議に招くには ? ◆名刺交換ってどうする ? ◆資料を画面に映す際のコツ ◆投稿したチャットを修正する ◆回線が遅い時の対処法 ◆余計な通知を止めるには ?
-
3.3
-
4.1●Netflixはどうやって190カ国で2億人を獲得できたのか? ●共同創業者が初めて明かすNetflixビジネスとカルチャーの真髄。 ■Netflixの「脱ルール」カルチャー *ルールが必要になる人材を雇わない *社員の意思決定を尊重する *不要な社内規定を全部捨てよ *承認プロセスは全廃していい *引き留めたくない社員は辞めさせる *社員の休暇日数は指定しない *上司を喜ばせようとするな *とことん率直に意見を言い合う ――新常態の働き方とマネジメントが凝縮
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 最難関を突破するための必須知識を解説! コロナ禍が受験に与える影響は? 関連情報も充実 巻頭インタビューで、新型コロナ治療で著名な忽那賢志医師が登場! コロナ危機で、医師の社会的地位がますます上がっています。医師を目指す受験生は、難関を突破するため、他学部の受験生以上に情報収集に注力し、勉強しなければなりません。 本書では、医師になるための道のりを初心者にもわかりやすく解説。何をどれくらい勉強すればよいのか、大学のタイプ別攻略法、各科目の効果的な勉強法など医学部合格に必須の知識に加えて、医学部の診療科や履修プロセス、高額の学費のまかない方など大学入学後に医師になるまでのノウハウを解説します。 コロナ禍が入試、勉強方法などに与える影響など関連情報も充実。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 巨大マーケットの最先端を徹底解説! 巻頭対談に、落合陽一氏(メディアアーティスト)が登場! 高速・大容量で多数の端末に同時接続が可能な第5世代通信システム、「5G」。自動運転、医療・介護、工場、スポーツ観戦などの分野で革新的なビジネスの誕生が期待されています。2020年春から携帯キャリア各社の商用サービスがスタートし、今、最も関心を集めているビジネステーマです。 本書では、5Gの技術の特徴といった基本から始まり、5Gによって生まれる巨大なマーケット、様々な革新的なビジネスを解説。コネクティッド・カー、遠隔医療、音楽ライブの進化、工場内の機械の制御、インフラの保守・点検など、ビジネスの最先端を事例を交えながら明らかにする。また、携帯キャリア各社の戦略や5Gビジネスの課題も取り上げ、1冊で5Gビジネスの全体像が理解できるようにする。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 東洋医学の知恵とヨガを融合した新メソッドで 巡りのいいからだと心の快適さを実感 ! 予約殺到「ヨガの解剖学」主宰の鍼灸師が初心者にもわかりやすく解説します。 ★各章ごとに【お悩み・不調別INDEX】つき★ 肩こりや首こり、頭痛、冷え、むくみ、目の疲れなど、悩みや不調別に必要なポーズがすぐわかります ! Part1 オフィスでツボ押しヨガ 東洋医学×ヨガの効果を、まずは座ってできる簡単ポーズで実感! からだを流れる「経絡」でも特にエネルギーが集中するとされる特効ツボを使うことで、さらなる巡り改善効果を狙っています。仕事中の凝りや疲れ、モヤモヤ不調を感じたときにもその場で実行されば、単なるストレッチとは異なる、すっきりした爽快感を得られるはず。 Part2 経絡ヨガ 東洋医学の叡智と、ヨガの効果を融合して生まれたのが「経絡ヨガ」。滞った経絡に“気”を流し、その巡りを改善することを目的とします。大きな特徴は、心と体の健康を左右する「五臓六腑」をれぞれに対応する経絡を8つのゾーンに分け、これを深い呼吸とともに伸ばすこと。自分の体質や体調、目的に合わせてポーズを選べるのもポイントです。 Part3 お灸ヨガ お灸は、古代中国において二千年以上も前にその理論が確立された東洋医学の伝統的な施術法。ツボ刺激が急性の症状に有効であるのに対し、慢性的な症状に、より効果があるとされています。温熱による刺激が経絡にスーッと浸透し、体がじんわりゆるんで温まる、その心地よさは格別。目的に応じたリラックスポーズで、疲れたからだと心を解き放ちましょう。
-
3.2【コロナショック後の自動車産業を徹底分析! 】 ■100年に一度の大変革に直面する世界の自動車産業は、モビリティ産業への変革を迫られている。電動化をはじめとする「CASE革命」の大激変、MaaSへの対応を進めるべく、世界の自動車産業は次々と手を打ってきた。そのさなか、新型コロナウイルスが突如として猛威を振るい、世界は一変した。本書は、業界を代表する人気アナリストが、コロナショック後の自動車産業への影響をいち早く分析し、中長期的な展望を示す注目の書。 ■ 世界の自動車市場は、コロナショック後の短期的な需要急減を乗り越え、驚くほどの急回復を見せつつある。しかし、人々の行動は地域によっては大きく変容し、ディーラーを含めた自動車産業全体に、質的にも量的にも多大な影響を及ぼしつつある。 ■本書は、ウィズコロナ時代の自動車産業における新常態(ニューノーマル)――世界の移動ニーズと消費行動、市場特性の変化を読み解き、説得力のある数字に基づいて先行きを展望する。とりわけ、2022年以降と見られるアフターコロナ時代に向けた構造変化を解説。画一的な世界ではなく、地域の特性により、より多様な状況が現出すると見通す。大きな影響を受ける部品メーカーへの影響も取り上げる。終章では、ハードウェアからソフトウェアへと価値が移行する大きなトレンドの中で、自動車産業に関わる主要産業(OEM、サプライヤー、ディーラー)への指針を示す。 ■各社の2020年第一四半期決算など最新動向を踏まえた展望は、業界関係者や投資家必読。日経ビジネス人文庫『CASE革命』との併読で、自動車産業の将来像が掴める。
-
-決済業界のイノベーションの波に乗れずに衰退していく企業、企業としては生き残るが、大きくビジネスモデルを変革するものが出てくる時代がやってきました。一方で、大きなチャンスを手にする新規参入企業が登場するのかもしれません。今後、決済の世界で覇者となるのは、従来のカード会社か? 小売や通信などの異業種のプレーヤーか? やはりGAFAなのか? それとも、これまで以上に国際ブランドが力をつけてくるのか? あるいは、いまは誰も想像もしていないプレーヤーが勝者となるのか? 生き残りを賭けた戦いはすでに始まっています。 本書では、ともすると供給者側の論理に終始してしまうことも懸念される、昨今の消費者不在のキャッシュレス推進に一石を投じ、日本であるべきキャッシュレスと、キャッシュレス社会で勝ち抜くための要諦を、決済事業者と加盟店それぞれの経営戦略の観点から論じます。日本におけるキャッシュレスは、加盟店と決済事業者がWin-Winの関係を構築し、キャッシュレスを通じて企業の売上成長に貢献し、消費者も自らが気づいてすらいなかったニーズが満たされるような形で進展すべきです。いまは残念ながらそうはなっていません。真のキャッシュレス時代到来へ向けたアクションを本書では考えます。
-
-実際の事例から導き出された「変革成功モデル」。 「どの企業にもあてはまる」手法を解説! ◆昨今の企業活動は、従来の改善・コスト削減といった積み上げ式の活動から、改革・イノベーションのようなより複合的なテーマに変革の課題が変化してきている。企業の変革を維持するために、著者は4つの力を提案する。 1未来志向力:未来に向けた価値を作る活動をし続ける 2式年遷宮力:会社の仕組みの刷新を日常的に織り込む 3換装自在力:会社の組織・業務をモジュール化し、環境に合わせて適合させる 4全社運動力:分散的かつ演出的に一人ひとりの従業員を巻き込む ◆また、「4つの力」をより日常的に実行にうつすために、著者は7つのメゾットを提案する。具体的なステップを本書で提案することで、読者が継続的に社内で変革をおこせるようになることを目的としている。 1未来年表化:未来のメガトレンド、危機感、会社の価値・本質を共有すること 2可視化:事業ポートフォリオ、人材マップ、等の会社の“今”が適切にわかるようにすること 3ロードマップ化:人材、技術、設備・IT、等、日常的に実行するべきことは将来向けたロードマップを整備・更新すること 4アジェンダ化:ロードマップに基づいた議論・意思決定を適切に行うための会議体の整備およびアジェンダを設定すること 5アクションプラン化:誰が、いつまでに、どのようにやるのか、をアクションプラン・予算に落とし込み、実行管理をすること 6標準化:イレギュラー、属人的な業務とせず、会社としてのスタンダードは何かを決め、維持すること 7ダイアログ化:将来にむけた計画と実行を従業員に絶えず伝えていく方法を確立する
-
3.0一時的な感染対策にとどまらず、恒常的な働き方として、多くの企業で導入が進むテレワーク。 「在宅で生産性を高く保つためには」といった大きな課題に始まり、 「労務管理をどうするか」「人事評価を適切に行うためには」 「部署による不平等をどうするか」「手当などが必要か」「サボる社員、連絡の取れなくなる社員をどうするか」 「情報漏洩などのリスクを避けるためには」「新人研修をどうするか」といった所まで、 企業にとってまだまだ課題は多く残され、現場の管理職や、労務担当を悩ませている。 本書では、10年以上も企業のテレワーク相談を受ける2人の社労士が、 法律に基づく適切な制度策定の方法を示すとともに、 現場から寄せられる悩みや、各社の失敗事例・成功事例をもとに、実践的な知識を授ける。
-
4.0世界最大のコンソーシアム「MOBI」のトップが執筆。 これがニューノーマル/ポストコロナの切り札だ! いま、モビリティ業界が注目するのがブロックチェーン。 MaaSやCASEを本当に「儲かる」ものにするためのラストピースとして、 そしてスマートシティ構築の基盤技術として期待を寄せられている。 本書は、ブロックチェーンの基礎技術から最先端の活用事例までを解説。 国内外のトップランナーたちの動向も踏まえて展開する。
-
4.0◆デジタル・ネイティブではない従来型企業が、デジタル技術を活用してデジタル変革を進めるためのステップを解説する。 ◆5年におよぶ、40社の企業トップとのインタビュー、27社のケーススタディー、171社の企業経営幹部への調査を実施した成果を解説します。技術解説がメインではなく、デジタル変革を構想する非IT部門(戦略企画、オペレーション、財務、人事など)向けに変革の進め方を解説。 ◆デジタル経済では技術とそれを使いこなす能力、さらには顧客ニーズも急速に変化するため、企業戦略は流動的にならざるを得ない。経営者にとっては効果的な企業デザインにより、新たな競争上の脅威や機会に対応して、迅速に対応することが求められる。企業デザインのデジタル化対応を成功させている企業では、従業員、業務プロセス、データ取得と活用、技術導入をどのように調和させ、革新的な顧客向けソリューションを見出しているかを探る。 ◆ケースとしてはレゴ、フィリップス、アマゾンなど日本でもなじみのある企業の他、DXの成功事例としてMITでの研究が進められているシュナイダー・エレクトリックやDBS銀行などを取り上げています。著者はDX研究の世界的な拠点であるMITCISRの研究者たち。2018年に刊行した『デジタル・ビジネスモデル』(Peter Weill他)の続編とも言える一冊です。
-
3.0第2次世界大戦後の保守本流の流れを汲み、また、被爆から75年という節目を迎えた広島出身の政治家として、「核兵器のない世界」へ、未来に向けてどう取り組むか―――これからの日本が目指すべき姿を、岸田文雄氏が自ら書き下ろした渾身の1冊。 ロナルド・レーガン、ミハイル・ゴルバチョフ、そしてバラク・オバマといった指導者たちがこれまで幾度となく、「核全廃」という名の松明を掲げ、挑戦してきた。しかし、その勇気ある行動は常に国際政治の厳しい現実に翻弄され続けている。その松明が細っている今、「この手にしっかりと引き継ぎたい」という政治家としての信念をつづる。同時に、政治家を志した理由。理想と現実の間で、政治家が迫られる決断の難しさ。政治家として夢を、その半生を通して語る。 2016年に外務大臣として実現させた米オバマ大統領(当時)の広島訪問はじめ、4年7ヵ月の外相経験を通して、米国、英国、ロシア、中国をはじめ世界の首脳と築いてきた人間関係。数々の具体的な交渉エピソードを題材にして、孤立、分断化が進む世界で、なぜ「協調」をテーマとした政治、外交が肝要かを、改めてひもとく。 吉田茂以来、脈々と受け継がれてきた、戦後保守本流の流れを汲み、近年の日本の政治、外交の現場を知る著者の証言は、歴史の記録としても貴重な1冊である。
-
3.02030年の自動車産業を取り巻く環境変化を定量的に予測した「モビリティー革命2030 自動車産業の破壊と創造」の出版から4年が経過した。100年に1度といわれる大変革期の只中にある自動車産業は、当時の見立てをはるかに超えるスピードで変化している。CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)やMaaS(Mobility as a Service)といった既存の概念だけでは、この荒波を乗り切ることは難しい。デロイト トーマツ コンサルティングは今回、CASEやMaaSの背景となる社会変化に立脚した新概念「MX(Mobility Transformation)」「EX(Energy Transformation)」「DX(Digital Transformation)」に着目する。もはや、“クルマ”だけに閉じた戦略は通用しない。モビリティー、エネルギー、デジタルの3大メガトレンドに対応した新戦略が求められている。自動車メーカー、部品メーカー、カーディーラーの各プレーヤーが激動の時代を生き抜く新戦略を考察する大ヒット“革命本”の第2弾。
-
3.7日本にもデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が到来しました。2020年はその波が大波になり、新型コロナウイルスの感染拡大によって、あらゆる仕事やサービスが強制的にデジタル化されました。 ではそれがDXかと聞かれれば、「DXの一歩目であり、本質はその先にある」というのが私の見解です。 コロナ禍がもたらしたアナログからデジタルの置き換えは、会社がどうにかして通常業務を維持していくために行ったものにすぎません。いわば、商品やサービスを供給する側のDXです。 しかし、顧客や消費者はどうでしょうか。供給側では、あちこちからDXという単語が聞こえてきますが、DXのメリットを享受するはずの市場からは「便利になった」「楽しくなった」といった声がほとんど聞こえてこないのが実態だと思うのです。 では、どうすれば市場が喜ぶDXを実現できるのでしょうか。重要なのは、市場の声を聞き、市場の課題を解決することです。 そのためには、従来のように「ITの人」だけが技術面からDXにアプローチするのではなく、市場の消費者に近く、市場を最も理解しているマーケティング部門の人やマーケターが積極的にDXに関わる必要があります。 マーケティング視点を持ってDXを推進していくことを、本書では「DX2.0」と呼んでいます。マーケティング視点を持つことによってDXの価値はさらに高まります。 コロナ禍で強制的にDX1.0が実現している今こそ、その勢いに乗りながら、DX2.0を推進し、実現する絶好のタイミングです。ぜひ市場を魅了し、ユーザーの心をつかむDXを実現してください。
-
3.9「データ分析」はビジネスの基本スキル 文系・理系は関係ない 「データ分析はデータサイエンティストの仕事」というのは、もはや古い考え方です。最近では「ビジネストランスレーター」という役割も重要視されています。「データサイエンティスト」でなければできない高度な分析はありますが、ビジネスで役立てるには、必ずしも高度な分析は必要ありません。しかも、最近ではGUIを備えた「データ分析ツール」が充実し、プログラミングなどできなくてもデータ分析は可能です。 だからといって、「ツールさえあれば、誰もがビジネスで役立つデータ分析ができる」というわけではありません。AI技術を活用し、データさえあれば自動で高度な分析をしてくれるツールもありますが、やみくもに使うとトラブルを起こしかねません。 データ分析を“うまく”進めるには、身に付けないといけない方法論があります。本書では、著者らが成功と失敗を繰り返して見つけ出した独自の「5Dフレームワーク」という方法論を解説しています。いくら高度なデータ分析手法をマスターしたとしても、本書で説明しているような方法論を知らなければ、ビジネスで役立たせることはできません。 本書を読むのに、データ分析の前知識は必要ありません。文系も理系も関係ありません。「データ分析はビジネスパーソンの基本スキル」となるのはもうすぐそこまで来ていると思います。「データ分析人材になる。」との決意を持って本書を読めば、ビジネスで役立つデータ分析の進め方が分かります。
-
4.0コロナ禍の経験を通して、デジタル・トランスフォーメーション(DX)を 推進している企業の優位性が明らかになった。 3密を避けた状況下でも、いつも通りにビジネスを進められる企業へと、 既にトランスフォーメーション(変革)していたからだ。 だが日本企業のDXは、海外企業に比べ、総じて遅れている。 IT(情報技術)活用のレベルが低いわけではなく、 新規事業アイデアが無いわけでもないが、日本企業はとにかく 「変革が苦手」なためにDXがうまくいっていない。 なぜ日本企業は変革できないのか。それは日本企業が無敵だった バブル期までの成功体験をいまだに引きずっており、 この古い仕組みや企業文化が新しい時代への適応を阻む 「習慣病」となって社内にはびこっているからだ。 DXの成否を分けるのは、実はデジタル技術の活用方法ではなく、 この習慣病の克服とその先にある企業変革にある。 業務・組織・ITにはびこる習慣病にスポットを当て、 変革を遂げた6社のCxOインタビューや豊富な事例を通して、 DXを成功に導くための道を解説する。
-
4.3ポーター、コトラー、ミンツバーグ、 「ダイナミック・ケーパビリティ」のデビッド・ティースに、 「両利きの経営」のチャールズ・オライリー ……。 「世界標準の経営学者」たちは、今、何を考えているのか? 入山章栄、興奮。 まさにドリームチーム。 ありえないほど豪華な17人。 【世界トップのスター研究者による全17講】 ポーター教授のCEO論/ダイナミック・ケーパビリティ/両利きの経営/オープンイノベーション/コトラー教授から、ニューノーマルのマーケティング論/社会的インパクト投資/ステークホルダー理論/パーパス経営/リーダーシップの経営心理学/マーケットデザインで読み解く起業マネジメント/ネットワーク効果で読み解くプラットフォーマー/デジタルトランスフォーメーション(DX)/AIと雇用の未来/AIとアルゴリズムの進化論/日本のイノベーション力/デジタルマーケティング/ミンツバーグ教授の資本主義論
-
4.5経済再起動、カギは日本にあった! MBAホルダーである著者が、ハーバードの白熱授業と教材に取り上げられた日本企業を徹底取材。 海外企業に「柿の種」の工場見学が人気の理由 トヨタウェイは「両利きの経営」の模範だった ソニーとアップル、復活劇の共通点は……? 16万部突破 『ハーバードでいちばん人気の国・日本』 待望の続編! 世界一「長寿企業」が多い日本には、企業が長く存続し、成長していくための知恵が蓄積されているという。イノベーションを起こし続ける仕組み、社会貢献を重んじる経営、人を大切にするリーダーシップ……。 なぜ激動の時代の中で、ハーバードは日本企業がずっと大事にしてきた「基本」に注目しているのか。ベストセラー著者がハーバードの白熱授業を徹底取材し、その理由に迫る。 【本書の内容】 テッセイ、楽天、 トヨタ、が定番教材に/日本企業が起こした破壊的イノベーション/学生が驚いたホンダの「長期的視点」/ハーバードの研究対象となってきたコマツ/優れたプラットフォームを生んだ日本型組織/ミクロンの世界にイノベーションを起こす/世界的なベストセラー教材『日本:奇跡の年月』/松下電器の社歌に象徴される復興への情熱/日本企業の創業者が伝える「遅咲きの人生」/リクルートの本質はドリームマシン/ 「個の尊重」に大きな影響を与えたドラッカー/AKB48は「体験型エンターテインメント」/「柿の種」を試食する授業が大人気/米のお菓子でアメリカに挑んだ亀田製菓/ソニー株式会社が初めて教材に/学生の記憶に強く残るトヨタの事例/トヨタはなぜ街をつくるのか/国のブランドランキングで1位/経済複雑性指標が示す日本の潜在能力……
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 企業などで実際に使われている様々なビジネス文書を作成する能力を身に付けるための問題集です。Excel 2019を使用し、請求書、見積書、売上報告書、名簿などを作成する問題を解くことで、これらのビジネス文書を作る能力が身に付きます(Excel 2016でもほとんどの問題を解くことができます)。 「計算」、「集計」、「グラフ作成」、「自動化・マクロ」、「データベース」、「文書作成」の5つのカテゴリーに分かれており、はじめにカテゴリーごとに作成のポイントを解説しています。そして、入力例や完成例を参照しながら手順に沿って問題を解く基礎問題と、文章から求められている指示を読み取り、自分で考えて問題を解いていく応用問題が出題されます。問題数は、基礎25問、応用25問の全50問です。 問題ファイル、入力例ファイル、完成例ファイルを「実習用データ」として用意しました。完成例は、そのままビジネスの現場で使うこともできます。 「Excelの機能や操作は理解したけれど、実際の仕事にどう生かせるのかよくわからない」、「Excelを活用して実践に役立つビジネス文書の作成法を身に付けたい」といった方にお薦めです。 ※実習用データはダウンロードしてご使用ください
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 企業などで実際に使われている様々なビジネス文書を作成する能力を身に付けるための問題集です。Word 2019を使用し、案内状、連絡書、報告書、申請書などを作成する問題を解くことで、これらのビジネス文書を作る能力が身に付きます(Word 2016でもほとんどの問題を解くことができます)。 「【社外】社交儀礼」「【社外】業務・取引」「【社内】報連相」「【社内外】企画・提案」「【社内外】パンフレット・ポスター」の5つのカテゴリーに分かれており、はじめにカテゴリーごとに文書作成のポイントを解説しています。そして、入力例や完成例を参照しながら手順に沿って問題を解く基礎問題と、文章から求められている指示を読み取り、自分で考えて問題を解いていく応用問題が出題されます。問題数は、基礎25問、応用25問の全50問です。 問題ファイル、入力例ファイル、完成例ファイルを「実習用データ」として用意しました。完成例は、そのままビジネスの現場で使うこともできます。 「Wordの機能や操作は理解したけれど、実際の仕事にどう生かせるのかよくわからない」、「Wordを活用して実践に役立つビジネス文書の作成法を身に付けたい」といった方にお薦めです。 ※実習用データはダウンロードしてご使用ください
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Windows 10を初めて使用される方が、起動と終了、文字の入力、ファイルとフォルダーの管理などの基本操作に加え、アプリケーションの使い方、ユーザーアカウントやパスワードの管理、インターネットや周辺機器を利用するための操作などを、実習しながら学習できるテキストです。「May 2020 Update」および新しいMicrosoft Edgeに対応しています。 ワードパッドやペイントなどの基本的なアプリケーションの使い方、インターネットの活用、写真の取り込みと編集など、パソコンを快適に使うためのさまざまな機能をわかりやすく説明しているので、楽しくパソコンが使えるようになります。
-
-外に出られなくなった若者 “コロナ”問題でさらに増えるプチひきこもり 心配ご無用! 彼らこそ貴重な人財なのです! いまや大人のひきこもりだけで100万人もいるといわれる。不登校とその予備軍は中学生で8人に1人。そのうち8割が、そのまま大人の「ひきこもり」になるとも。 しかし、こうした現象をネガティブに捉える必要はない。彼・彼女らの多くはPC技能に長け、インターネットやSNSを駆使し、アニメやイラストの世界にも長じている。ユーチューバーやプロのゲーマーとして、あるいはインフルエンサーとして、マーケティングなどの世界で影響力を持つ存在も増え、下手な会社員よりよほど高収入を得ている。 あるいは自らの経験を活かし、ひきこもり達が安心して学べ、かつ地域社会と交流しながら少しずつ収入を得られるフリースクールを運営したり、農業体験を勧めることで過疎地の頼れる存在として輝きを取り戻した元ひきこもりもいる。 学校や会社に行かなくても、組織に所属しなくても、自らやりたいことを見つけ、立派に生きていける時代になったのだ。 本書は生活経済ジャーナリストとして活躍する著者が、自身の子も不登校、親戚にも不登校児がいたことから不登校専門訪問員の資格を取得、キャリアカウンセラーの資格も活かし、ひきこもり問題の現場を取材、彼・彼女らが活躍する様々な実例を紹介し、この問題を明るくとらえ、未来を展望する。
-
3.3誰も出社しないオフィスなんて、必要なのか──。 テレワークが浸透するなか、オフィス撤廃や縮小が相次いでいる。本社機能をバーチャル空間に移す企業も登場。働き方が一変し、「オフィス不要論」も飛び出した。オフィスってどうなる? ジョブ型雇用って何? オフィスの価値って何? 10の疑問を専門記者が徹底取材し、働き方ニューノーマルを解き明かす。 ◆オフィス完全撤廃「ブレスト? 必要ないですね」の真意 ◆必要な面積が「現状の3分の1」だったベンチャー企業 ◆「解約やっぱりやめた」僕らがオフィスに戻るワケ ◆あえてオフィスを3倍に拡大するベンチャーが考えていること ◆続々と登場する「オフィス縮少コンサルタント」の正体 ◆今、はやりの「ジョブ型雇用」って何? メリットは? 何が変わる ? ◆テレワークの労務管理ってどうしてる ? ◆富士通「オフィス面積半減」の皮算用 ◆日立「半分在宅」が大企業の方向性を決定付けた ◆パソナが淡路島に本社機能を移す理由 ◆本社機能をバーチャル空間に移転させるベンチャーが登場 ◆パルコがシェアオフィス参入、なぜ ? ◆勃興する「オフィステック」 新しい市場が生まれる ◆「総合職で世界一周しながら働く」という挑戦 ◆それでもオフィスに残る3つの価値を独自解説 ◆「オフィス不要論」の真偽 これからの働き方、働く場所に悩んでいるビジネスパーソン、オフィスのリニューアルに携わる総務、経営企画、人事の担当者、オフィスをデザインに関わる設計者や実務担当者、必読。 さよならオフィス──。あなたは明日からどこで働きますか ?
-
3.6「食品ロス問題」の専門家が教える、 SDGS時代の必携暮らし読本。 捨てない幸せ、使い切る満足。 食も暮らしも生き方も。 “新しいスタンダード"にすっきりシフト。 第二回食生活ジャーナリスト大賞食文化部門 Yahoo!ニュース個人オーサーアワード2018受賞の著者! あなたのまわりはまだ食べられる、もっと使えるものであふれている! 食べ物もモノも限りある資源。 再利用したり、リメイクしたり、長持ちするように工夫することで、 そこに新たな命が宿ります。 □「賞味期限」はおいしさの目安 □冷蔵庫にあるもので調理する「おうちサルベージ」 □“あぶること"“寝かせること"でおいしくなるもの □ごみ処理機には助成金も。生ごみは乾燥させて捨てる □ペットボトル水は賞味期限切れでもOK。品質ではなく内容量の問題 □切り方ひとつで野菜の無駄が減る □調味料を上手に使い切るコツ □野菜を長持ちさせるなら「超カンタン乾物」 □「残りそうならこれに使う」のお決まりを用意 □マンション住まいでもできる「コンポスト(堆肥化)」 □シーツも本も。修理・修繕で「またあたらしいいのち」 □Gパンをスカートに。「アップサイクル術」 □日本の伝統「金継ぎ」で器がよみがえる □人も野菜も規格外…… すがすがしく生きるヒントにあふれた一冊です
-
4.0菅首相の目玉政策「携帯値下げ」、変わらない市場の奥底に呪縛がある! 「携帯料金は四割程度引き下げる余地がある」--。 菅義偉新首相が官房長官時代から力を入れる携帯の値下げ。しかし国民の多くは値下げを実感するに至っていません。 13年ぶりの新規事業者となった楽天の携帯参入、大幅な減益覚悟で値下げを決断したNTTドコモ、今度こそ市場を変えようと 劇薬の「完全分離」導入に踏み切った総務省、ソフトバンクとKDDIによる瀬戸際の攻防。 それでもなぜ市場は変わらなかったのでしょうか。 本書は、そんな官邸と携帯大手の過去1000日の攻防を最前線で取材した著者がその裏側に迫り、 携帯電話市場の課題を浮き彫りにしました。国民が納得するような携帯料金を実現するにはどうすればよいのか。 著者は、市場を取り巻く「大手三社体制」「囲い込み」そして「月額収入」という三つの呪縛を解くことで、 初めて実現すると語ります。本書の内容は菅新政権の次の一手を探る上でも欠かせないでしょう。
-
4.0「飛び道具トラップ」「激動期トラップ」「遠近歪曲トラップ」 経営を惑わす3つの「同時代性の罠」を回避せよ! 近過去の歴史を検証すれば、変わらない本質が浮かび上がる。 戦略思考と経営センスを磨く、「古くて新しい方法論」。 「ストーリーとしての競争戦略」の著者らの最新作! これまで多くの企業が、日本より先を行く米国などのビジネスモデルを輸入する「タイムマシン経営」に活路を見いだしてきた。だが、それで経営の本質を磨き、本当に強い企業になれるのだろうか。むしろ、大切なのは技術革新への対応など過去の経営判断を振り返り、今の経営に生かす「逆・タイムマシン経営」だ。 そんな問題意識から、日本を代表する競争戦略研究の第一人者、一橋ビジネススクールの楠木建教授と、社史研究家の杉浦泰氏が手を組んだ。経営判断を惑わす様々な罠(わな=トラップ)はどこに潜んでいるのか。様々な企業の経営判断を当時のメディアの流布していた言説などと共に分析することで、世間の風潮に流されない本物の価値判断力を養う教科書「逆・タイムマシン経営論」を提供する。 経営判断を惑わす罠には、AIやIoT(モノのインターネット)といった「飛び道具トラップ」、今こそ社会が激変する時代だという「激動期トラップ」、遠い世界が良く見え、自分がいる近くの世界が悪く見える「遠近歪曲トラップ」の3つがある。こうした「同時代性の罠」に陥らないために、何が大事なのか──。近過去の歴史を検証し、「新しい経営知」を得るための方法論を提示する。
-
3.0新型コロナに立ち向かう医療技術から、共生するためのものづくり、IT、流通・サービス、建築の技術まで、知っておくべき100のテクノロジーを解説します。 ビジネスパーソン800人に聞いた「今重要な技術」「五年後重要になる技術」のリストも収録! 日経BP専門誌の編集長30人が、テクノロジーを100件厳選。わかりやすく解説します。 次のように医療、生活、仕事、移動、場所、基盤という6分野に分け、それぞれ重要な技術を説明していきます。新型コロナの危機を乗り越え、新しいビジネスを生む濃いヒントが詰まった一冊です。 ・医療:急ピッチで開発が進む治療薬、ワクチン ・生活:買い物の決済、エンターテインメントの技術 ・仕事:建設や製造の遠隔操作、自動化の最新技術 ・移動:接触確認アプリや感染拡大の分析など、人の移動にまつわる対策 ・場所:オフィスや住宅を安全に保つための技術 ・基盤:非接触で体温や五感を測る技術、拡張現実に必要なテクノロジー 紹介する技術の例 Covid-19ワクチン/Covid-19抗ウイルス薬/PCR検査/AI問診/オンライン診療/インシリコ創薬/介護ロボット/コンテナ診療所/オンライン婚活/遠隔パーティ/オンラインメンタルヘルス/ネット接続体温計/感染拡大リアルタイム分析/ドローン配送/自動運転/IoT住宅/Covid-19スマートシティ/都市OS/Beyond 5G・6G/EDR/ハプティクス通信/デジタルツイン/人工光合成/再エネマイクログリッド
-
4.0
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 これからプログラミングを始めるときに選ぶ言語として注目されているPython。 人工知能(AI)、機械学習、データサイエンスなど、今最もニーズの高い分野で利用されているプログラミング言語です。 そうした分野のソフトウェア開発に数学の知識は必須と言われています。 ならばPythonプログラミングと数学を同時に学んではどうでしょう。 数学というと「自分は文系だから数学は苦手で……」という人も多いでしょう。だったら、最初からやり直してみませんか?本書は徹底して直線だけを学び直します。数学としてはまさに一歩目。中学一年生に戻ったつもりで、“わかるところ”からやり直しましょう。数学が苦手ならなおさら「急がば回れ」がお薦めです。 傾き、切片、垂直、交点、連立方程式、垂直二等分線など、「確かに昔やったよな」とおぼろげに覚えているところを、もう一度しっかり理解できます。これならごくシンプルな数式ばかりなので、「数学は苦手だったのに、なぜ今ならわかるんだろう?」と意外なほど理解できます。 理論で確かめたら、実際に計算して確かめてみましょう。そこはPythonにおまかせ。最初はごくシンプルな数式をプログラムにすることで、プログラミングとPythonに自然に慣れて、ソフトウェア開発の基礎を身に付けていくことができます。 「直線だけじゃ何もできないのでは?」――。直線を舐めてはいけません。直線だけでも、ビッグデータを分析し、将来の予測をすることができます。どうやってそのためのモデル(数式)を作り、分析や予測に役立てるのか。機械学習の一歩目に踏み込むことまでできるのです。入門レベルだからと遠慮せずに、本書でそこまで行ってみましょう!
-
5.0日本が大好きで日本でぜひ働きたい──。そんな外国人が増えている。日本で学ぶ外国人留学生は今や約30万人に達した。その中には、東京大学をはじめとする有名大学や大学院で学ぶエリート人材も目立っている。 だが、彼らが日本でいざ働こうとすると、さまざまな壁が立ちはだかる。日本独特の新卒一括採用のシステム、日本語以外の言語での情報発信の少なさ、自分の意見を言いづらい日本的な「空気を読む」カルチャー……。 せっかく日本に強い関心を持ち、就職を希望する“金の卵”を活かすために、日本企業は何をすればいいのか? 知られざる外国人留学生の本音、日本企業が抱える様々な課題と、それらを解決するために何が必要なのかを提示する。 本書は、東京大学公共政策大学院の外国人留学生向け講義「日本産業論」を通じて、エリート留学生が日本の企業について何を学び、働く際に何を期待し、何が課題だと思っているのかに迫る。 実は日本企業の人材育成システムや日本の技術力に魅力を感じている外国人留学生は多い。日本の魅力も日本人が思っているよりも高く、外国人材を獲得することは企業のイノベーション力を高め、競争力の向上にもつながる。 しかし、日本全体で30万人を超える留学生がいて、卒業生の6割以上が就職を希望するが、現実にはその半分しか就職できない。運よく就職できたとしても、完璧な日本語や日本人社員化を求められ、 「日本が好きなのにね…」と言って、日本企業を辞めたり日本を離れたりする多くの優秀な外国人材が目立つ。このような課題を乗り越えるためには必要な処方箋とは。
-
4.3累計15万部突破! 「やりたいことを全部やる!」シリーズ最新刊! 書下ろし! 人間関係、仕事、人生…… たったひと言ですべてがうまく回り出す。 『やりたいことを全部やる!時間術』 『やりたいことを全部やる!メモ術』に続くシリーズ第3弾。 今回のテーマは「言葉術」。 「やりたいことを全部やる!」ためには、 周囲を巻き込み、味方をつくることが必須。 本書では、最短で味方を増やし、 望む結果を手に入れるための「ひと言」をエピソードと共に紹介。 ●むずかしい課題には→「まずはやってみます」 ●うまくいかない状況では→「ゴタゴタは成功の前触れ」 ●共感を伝えるには→「たしかに」 ●厳しい状況には→「楽しみですね」 ●うまく話を本筋に戻すには→「なるほど。ところで」 ●優位に交渉を進めるには→「仮に」 ●“残念な人”のやる気を引き出すには→「惜しい!」 ●お願い事でYESをもらうには→「○○さんを見込んで」 ●無茶ぶりの問いかけには→「今、思いついたのですが」 ●オンとオフの切り替えには→「また週明けに!」 ●次につながる断り方は→「今回は」 対面からオンライン、メール、SNSまで…… ビジネスでも日常でも役立つ「ひと言」の玉手箱。
-
3.3〇13年9月に文庫オリジナルで刊行した同名書の増補改訂版。本書は、株式市場が乱高下する度によく動き、ロングセラーとなっている。 〇相場全体が右肩上がりに上がり続ける時代は終わった。今後も新型コロナショック級の危機、マーケットの波乱場面は何度でも到来する。上昇相場でも下落相場でも、確固たる投資ルールを保てた投資家だけが生き残る。個人投資家のための実践的なリスク管理術を教える。 ○主な改訂・増補箇所は以下の通り。「あなたの投資家レベルを判定--乱高下相場にどう対応するか」(序章)「新興銘柄のリスク管理はこうしよう(第2章)「株価が上がる理由、下がる理由を知ろう」(第3章)「個別銘柄に自信がなければ株価指数型ETFでOK」「NISAと確定拠出年金を活用しよう」(第7章)
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「疾病の基礎知識を学びながら、日経DIクイズを解く」というコンセプトで、書籍化したシリーズ「日経DIクイズ疾患篇」。循環器疾患、精神・神経疾患、皮膚疾患、呼吸器疾患に続き、第5弾として用量換算や服薬指導に手間がかかる「小児疾患篇」を書籍化しました。 気管支喘息やアトピー性皮膚炎、中耳炎、便秘症、注意欠如・多動症(ADHD)など、小児でみられる代表的な10疾患の病態生理と治療指針の「基本」、服薬指導のコツを臨床医の解説で学びます。 小児の服薬指導に精通した三浦哲也氏、松本康弘氏の監修の下、過去に出題した日経DIクイズから小児の疾患に関する様々なクイズ45題を厳選。ガイドラインの改訂や現在の標準治療、薬剤の適応追加、後発医薬品の情報など、現状に則してアップデートを行っています。 現場で働く薬局薬剤師が、小児の服薬指導のための基礎学習から知識のレベルアップまで、無理なく学べる一冊です。
-
4.0なぜ米国一流メディアは偏向報道を続けるのか? ニューヨーク・タイムズやCNNをうのみにしてはいけない! 現代のメディアでは、報道に携わる人々自らが「報道の自由」を踏みにじっている。 報道の自由が失われているのは、政府による弾圧や抑圧があるからでも、 ドナルド・トランプ大統領がメディアを非難しているからでもない。 原因は、放送局や新聞社、そこで働くジャーナリストたちにある。 かつて、ニュースといえば客観的な事実を集めたものだったが、 いまは特定の意見やプロパガンダをニュースとしてまことしやかに流し、 メディアがつくった「偽物」の出来事をあたかも事実のように報道し、 ときにあえて事実を報道しないという選択をする。(本書「はじめに」より)
-
3.0新たな時代のR&Dを推進する博報堂DYホールディングスが体系化した、事業開発者のための先進的ビジネス戦略! 欲求は、「個々の生活者の内部」から生じているのではない。 「生活者・物・情報のつながり」から生じている。 つながり方は変化しており、生活者自身も欲求に気づいていない。 従来、生活者の気づいていない欲求といえば、属性や趣味嗜好、日常生活における価値観といった、「個々の生活者の属性」に影響を受けて生じるものだった。それは、しばしば生活者の「インサイト」と呼ばれ、それに着目することが重要であると言われてきた。 しかし、5G、IoT、AI、AR/VRといった「つながるテクノロジー」の発展によって、欲求は、「個々の生活者の属性」だけでなく、「生活者・物・情報のつながり」にも影響を受けて生じるようになった。 本書では、このような「生活者・物・情報のつながり」に影響を受けて生じる欲求のうち、生活者自身も気づいていないものを、「生活者モード」と定義し、生活者モードを捕えるための事業やマーケティングの戦略策定の方法論を提示している。
-
3.0優秀なIT人材を採用したいなら 職場環境を見直すべし ITを活用しない、事務職扱いされる、雑談すらできない、成長機会が得られない―― こうした職場はIT人材に嫌われます。優秀な人ほど、職場環境には敏感です。もし「優秀な人ほど辞めていく」と悩んでいるとしたら、それはきっと職場環境に問題があるはず。 では、どんな職場をつくればいいのか。そのヒントが本書に詰まっています。通常の事務職とIT人材では職場に求めるものが違います。大事なことは、IT人材が嫌がる環境を知ることです。つまり、アンチパターンを押さえることで、初めて「IT人材が働きたくなる」職場になります。 本書では、実例をベースにIT人材が嫌がる職場を多数掲載しています。それらを「なんちゃってIT職場型」「低プレゼンス型」「コミュニケーション不全型」など9タイプに分け、タイプごとに「では、どうすればいいのか」という対策をまとめています。 もし目次を見て「この職場はウチのことだ」と当てはまるなら、早急に改善しないと、どんどんと人が辞めていくかもしれません。企業のデジタル化に欠かせないIT人材は、DX花盛りの今、引っ張りだこの状況です。職場環境の整備で優秀な人材が確保できるなら、実施しない理由はないでしょう。
-
4.0「社会を作り変えたいなら、コードを書くのが一番だ」 フェイスブックやツイッター、ウーバー、ペイパル、インスタグラムといった各種サービスを開発・提供する「ソフトウェア開発者」の多彩かつ具体的なエピソードを通じて、彼ら・彼女らはどのように考え、行動し、デジタル世界に大きな影響を与えるソフトウェア/サービスを生み出しているのかを解き明かした読み物です。 デジタル世界、およびソフトウェア・ファーストが浸透するにつれて、社会におけるプログラマーの重要性はますます高まっています。彼ら・彼女らの役割と実態を、IT分野で活躍したい方々はもとより、彼ら・彼女らと接するビジネスパーソンも知ることで、生産性を高め、よりよいサービスを生み出す大きなヒントが得られるでしょう。 ――――――――――――――― ソフトウェアにより世の中が変わりつつあることが明白ないま、企業は、企業の管理職は、コーダーをどのように活用するかを考えなければならない。本書はそのようなコーダーを活用することが必要となった管理職にとって必読の書だろう。 本書の原題は「Coders The Making of a New Tribe and the Remaking of the World 」だ。世界のリメイク。自分の周りや組織、会社など、すでにできあがっているようなものも、いまの混沌とした社会状況の中、再構築が必要だ。コーダーが世界をリメイクする人種であるのだが、あえて逆説的に言うと、世界をリメイクするのがコーダーなのだ。世界をリメイクするために、あなたも本書を指南書として、コーダーになろう。 及川 卓也、「ソフトウェア・ファースト」著者
-
3.0コロナ後の我々はどうなる! 日経記者がズバッと解説。 「コロナで業績が大きく変化した業界は何ですか」 「コロナ対策のお金はどこから出ているのですか」 「中国の立ち位置はどうなる」 ●「いまさら聞けない…でも、わからない」そんな悩みをサクッと解決。各分野に詳しい日経記者が、Q&A形式で疑問にズバッとお答えします。 ●経済がまったくわからない人でも容易に読めるように、目線を下げて解説。難しそうな単語は、用語解説をいれるという工夫を凝らしています。 ●この一冊で、日本経済の主要な課題を把握できます。豊富なグラフで、何がどう変わったのかを一目で理解することができます。ビジネスで、就活で、話題についていくための必携書です。 ●一項目完結のスタイルなので、知りたい項目だけを拾い読みできます。 ●巻末に、別途「ニュースを読み解く重要キーワード」を掲載しました。実際の日経新聞の過去記事を使用しながら、重点的にキーワードの解説をします。
-
4.0製造業の頂上決戦! 巨額投資で市場を席巻する中国、韓国企業。世界をリードしてた日本企業は勝機を見出せるか--。 パナソニック、GSユアサ、村田製作所、ATL、 サムスンSDI、LG化学、CATL、BYD……。 次世代革新電池を視野に入れた競争の最前線を徹底解説。 1887年に屋井先蔵が世界に先駆けて乾電池を発明して以来、日本の電池産業は長く世界をリードしてきた。とりわけ1960年代以降は隆盛期を迎え、次々と新たな電池を開発、生産を開始した。さらに1983年には旭化成の吉野彰氏らが経済社会を大きく変えることとなるリチウムイオン電池の原型を確立。1991年にソニーが世界初の製品化を実現した。 日本電池産業の輝かしい歴史も、21世紀に入ると様相が変わる。韓国企業が日本勢を追い上げ、2010年にはサムスンSDIがモバイル用リチウムイオン電池で世界シェアトップに立った。近年は、さらに高い性能を要求される自動車搭載用の大型リチウムイオン電池の世界で、中国勢が急速にシェアを伸ばしている。高性能電池の開発、製造の行方は、製造業の頂点に立つ自動車産業の未来をも左右する。世界の環境規制、中国の産業政策などもあいまって、日本の牙城だった電池産業が大きく変貌しようとしている。
-
3.5『古事記』現代語訳から6年、待望の小説が紡がれた! 神話から歴史へのあわいの時代に 森羅万象を纏った、若く猛る大王が出現した 暴君であると同時に、偉大な国家建設者。 実在した天皇とされる21代雄略の御代は、形のないものが、形あるものに変わった時代。 私たち日本人の心性は、このころ始まった。 時代の転換点の今こそ、読まれるべき傑作長編! ! 時は5世紀、言葉は鳥や獣、草木たちにも通じていた。歯向かう豪族たちや魑魅魍魎を力でねじふせ、國を束ねるワカタケル大王(雄略天皇)。樹々の合間から神が囁き、女たちは夢の予言で荒ぶる王を制御する。書き言葉の用意のない時代、思いを伝える歌と不思議な伝説、そして残された古墳の遺物や中国の史書……。作家は言葉の魂に揺さぶりをかけ、古代から現在に繋がる、「日本語」という文体の根幹に接近する―― 令和改元をまたいで日経新聞朝刊に連載された小説がさらにパワーアップして単行本化。
-
4.2「経済が成長すれば資源の消費量が増えるに決まっている」 「資本主義と技術が進歩し、社会が豊かになれば、自然環境はダメージを受ける」 ――産業革命以降、人間が繁栄すればするほど、地球を壊してしまうという予想が無批判に信じられてきた。 * * * だが、実際にはどうであったのか。予想とはまったく逆のことが起きたのだ。 資本主義は発展し続け、世界中に勢力を拡大し続けているが、同時にテクノロジーが資源を使わない方向に進歩した。 人類はコンピュータ、インターネットを始めとして多様なデジタル技術を開発し、消費の脱物質化を実現させた。 消費量はますます増加しているものの、地球から取り出す資源は減少している。デジタル技術の進歩により、物理的なモノがデジタルのビットに取って代わられた。かつて複数機器を必要とした作業は、いまやスマホ一つで事足りる。 なぜ経済成長と資源の消費を切り離すことができたのか? 脱物質化へと切り替えられたのはなぜか? このすばらしい現象について、なぜそれが可能となったのかを解き明かし、どんな可能性を秘めているのかを記していこう。 * * * テクノロジーの進歩、資本主義、市民の自覚、反応する政府――「希望の四騎士」が揃った先進国では、人間と自然の両方が、よりよい状況となりつつある。この先の人類が繁栄し続ける道がここにある。
-
4.5■世界の注目を集めた中国プラットフォーマーのビジネスモデルには限界が見えてきた。アリババもテンセントも、これまでの手法では先がない。ネット展開はすでに飽和。中国のプラットフォーマーたちはリアルとの融合に戦略転換し始めた。 ■消費者の安全性、信頼性への要求が高まり、競争の焦点が消費者接点から、商品やサービスそのものへとシフトしつつある。その中で、主要なプレーヤーのBAT(百度、アリババ、テンセント)に加え、TMD(バイトダンス、美団点評、滴々出行)が新たな主役として登場してきている。 ■この変化は、リアルに強い日本企業にとっても有利になる時代がやってくることを意味する。第二幕に入った中国デジタル革命の実態を、「コロナ後」の展望も含め、中国ITビジネス・経営に精通する専門家が詳細に解説する。
-
-環境への悪影響を抑えつつ、 いかに生産と消費を拡大するか。 サーキュラー(循環)型イノベーションで、 繁栄を続けるための具体策を提示する。 前作『サーキュラー・エコノミー デジタル時代の成長戦略』では、 サーキュラー・エコノミーによって、 競争優位性が獲得できるという新たな事実が提示された。 続く本書では、競争優位性を速やかに獲得して、 大規模に展開していく方法を、 10業界の考察、豊富な事例と共に解き明かす。 「取って、作って、捨てる」という、 従来の一方通行型生産・消費モデルはもはや持続不可能。 全く新たな手段「サーキュラー・エコノミー」を選択することで、 企業は、気候変動に前向きに取り組み、 生産と消費の拡大を可能にすると同時に、 活発なイノベーションと競争力を手にできる。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1日仕事が5分で終わる! 基本操作からプロの裏ワザまで、 仕事が速い人が実践している即効&効率化ノウハウを全解説! 創刊から20年以上にわたりエクセルの機能や実用テクニックを 研究・解説し続けてきた「日経PC21」の エクセル「時短」ノウハウを凝縮した1冊です。 ●何百回を1回で済ます入力の秘策 ●セル選択とコピペを究めて劇速編集 ●数式も関数も使わないラクラク集計ワザ ●サッと作れて一目瞭然 グラフ作成の実用テク ●もう失敗しない! 印刷&PDF化のツボ 第1章 ラクして高速化!入力の時短ワザ 第2章 二度手間を防ぐ最速コピペ術 第3章 数式&便利機能で集計作業を効率化 第4章 面倒な計算や判定は「関数」にお任せ 第5章 たまったデータを手早く整理&集計 第6章 見やすい表を短時間で作るコツ 第7章 修正の手際がグラフ時短のカギ 第8章 伝票、名簿、予定表…実例で学ぶ即効ワザ 第9章 印刷の時間と紙の無駄を削減 ★時短によく効くショートカットキー集つき ★解説に使用したサンプルファイルがWebからダウンロードできます ★最新Excel 2019/Microsoft 365にも対応
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「スクール標準教科書」は初心者でもつまずかないように“とにかくやさしく”、そして“本当に必要なことだけ”を、大きな文字と画面を使用してカラー誌面でわかりやすく解説した学習書です。Webサイトでダウンロード提供している実習用データを操作しながら学習するため、表の作成手順とExcelの操作手順の理解度もアップします。また、一つのCHAPTERで学んだことを確認するための「章末練習問題」と、一冊全体の内容を振り返ることができる「総合練習問題」によって学習の振り返りと記憶の定着ができるため、セミナーや講習などの集合学習のテキストとしてはもちろん、個人での学習や自習書としても利用できます。 基礎、応用の2冊構成で、「基礎」は、Excel 2019を利用してシンプルな表を作るために最低必要な基本的な機能を解説しています。主な内容は、Excelの起動・終了と基本的な操作、数式や関数を使って表を作成、絶対参照の活用、罫線や書式の設定、行や列の挿入データの移動・コピー、グラフの作成などです。
-
4.3「ビル・ゲイツは2012年に『イノベーションがこれまでにないペースで次々に出現しているというのに‥…アメリカ人は将来についてますます悲観的になっている』と指摘し、これは現代のパラドックスだと語った。(本書序章から) 「仕事の半分が消える」――2013年、オックスフォード大学の同僚マイケル・オズボーンとの共同論文「雇用の未来ーー仕事はどこまでコンピュータ化の影響を受けるのか」で世界的な議論を巻き起こしたカール・B・フレイによるテクノロジー文明史。 フレイによるテクノロジーの観点から見た人類の歴史はこうだ。新石器時代から長く続いた「大停滞」の時代を経て、アジアなど他地域に先駆けて、蒸気機関の発明を転機としてイギリスで産業革命が起きる。「大分岐」の時代である。労働分配率が低下する労働者受難時代であり、機械打ち毀しのラッダイト運動が起きる。 その後、電気の発明によるアメリカを中心とした第二次産業革命が起き、労働者の暮らしが劇的に良くなる格差縮小の「大平等」の時代がやってきた。テクノロジーと人間の蜜月時代だ。 ところが工場やオフィスへのコンピュータの導入を契機に、格差が拡大する「大反転」の時代に入る。さらにAIによる自動化が人間の労働に取って換わることが予想される今後、人類の運命はどうなってしまうのか。著者フレイは膨大なテクノロジーと人間に関する歴史研究を渉猟し、「ラッダイト運動」再来の可能性もある、と警告する。
-
4.3“Fランク”とレッテルを張られた組織をどう変えたのか、 社会や企業で活躍する若者を育てるために何が必要か――。 本書は、日本電産を1代で世界トップの総合モーターメーカーに育て上げた経営者・永守重信氏が、 50年計画で挑む「大学改革」から、組織改革・人材育成の本質を探り出した書籍です。 改革の舞台は、京都市内に本部を置く「京都先端科学大学」。 19年3月までは京都学園大学という名称で、受験界では偏差値が低く“Fランク”と呼ばれていました。 永守氏は私費130億円以上を投じたうえに、自ら大学に足しげく通い、改革を断行。 同大学は、永守氏の理事長就任からわずか2年で、大きな変貌を遂げつつあります。 今回は、永守氏本人に加え、彼の薫陶を受けた5人の改革実行者に直撃。改革の全貌に迫りました。 本書は、大学改革を追った書籍であると同時に、永守氏の組織論、人材育成論を学べる書籍です。 そして、カリスマ経営者の人間像に迫った書籍でもあります。 会社という組織の中で自分がどう動き、人を動かすために何をすべきか。 そして、これから世界で戦っていくうえで必要な人材とは何か、 若者にどう接するべきかといった視点でも、ビジネスパーソンに役立つはずです。
-
3.5新型コロナウィルスの影響により、テレワークをはじめ、オンラインでの研修や会議、打ち合わせ、商談などがもはや当たり前になりました。ところが、です。対面からオンラインに切り替わった途端、コミュニケーションがうまく取れないと悩む人が急増しています。オンライン講座を担当した講師は、「受講者に熱量が伝わらない」「受講者の反応が見えない」と戸惑いを隠しません。社員を前に訓示を述べようとした経営者は、「対面のときとは違って、どうも調子が出ない」とぼやいています。こうした方々の多くに共通するのは、オンラインでも、対面で積み上げてきたこれまでのやり方を変えていないという点。実は、オンラインでメッセージを発信する際には、対面のときとは少し違うノウハウやコツが求められるのです。 本書では、オンライン講座を実施する講師の例を中心に、オンライン・コミュニケーションの極意をまとめました。その一つに、例えば照明があります。自宅でも会社でも、パソコンだけで講義をすると、どうしても暗くなりがちで受講者に対してあまり良い印象を与えません。ところが、学習スタンドを持ってきて自分に光を当てるだけで一転、明るく好印象に変わるのです。他にも、アイコンタクトの取り方や受講者が飽きない話し方などオンライン講座ならではのノウハウや、顧客との距離感の取り方や雑談の仕方などオンライン営業などに活用できるコツも満載しました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「信用失墜」「コスト圧迫」・・・落とし穴を回避せよ! 建て主の“本音”に学ぶ、もめない家づくり 家づくりのプロと顧客のすれ違いはどこから生まれるか。 住宅会社が建て主から受けたクレームの実例50ケースから考えます。 ■目次 Part1 資金計画や契約内容を巡るトラブル Part2 設計や見積もりを巡るすれ違い Part3 施工を巡るトラブル Part4 建材・設備を巡るトラブル Part5 途中変更を巡るトラブル Part6 建て主支給や自主施工を巡るトラブル Part7 建て主への説明・対応を巡るトラブル Part8 「イメージ」の違いを巡るトラブル Part9 「感覚」の違いを巡るトラブル Part10 「住まい方」から生まれたトラブル
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 厳選30事例を大解剖! ◎ CLT、製材、集成材の攻略法 ◎「構造」や「防耐火」の知識も 隈研吾氏や原田真宏・麻魚氏ら、名手のテクニックを徹底解説 2020年3月に発行し好評を得た「ディテールの教科書」の第2弾。 今回は、特に動きが大きいCLT(直交集成板)や地元の流通製材の活用事例を中心に、中大規模木造にスポットを当てました。 この5年間に完成した同木造の代表事例の詳細図を集め、デザインや構造までを解説しました。
-
3.2新型コロナウイルスが働き方に及ぼした影響で最も大きいのが在宅勤務を中心としたテレワークです。これまでテレワークを全く行っていなかった企業もテレワークを始め、さらにはテレワークを常態化した企業も続々登場してきています。 著者の成瀬氏は、10年近く前から100%テレワークの組織で管理者を務めてきました。テレワークのメリットもデメリットも知り尽くし、様々な試行錯誤を重ねてきました。それだけでなく、国や自治体のテレワーク事業の企画・プロジェクト運営を多数担当し、総務省委嘱のテレワークマネージャーとして全国の企業から相談を受けてきたまさにテレワークのエキスパート。 本書はその知識と経験に基づいて、テレワークの組織を運営する方法を実践的に解き明かします。中でも肝になるのが、管理者が部下の一挙手一投足を監視するような「マイクロ・マネジメント」から、部下の行動を「支援する」管理への転換です。そのためには部下が自分で動く「自律自走」する組織を作っていく必要があります。 本書ではそういった組織を築く方法をその土台から解説しています。本格化するテレワーク時代の組織運営のバイブルになるでしょう。
-
4.3危機のときに必ず業績が飛躍的に伸びるのはなぜか? 「15の選択」で会社は根本から変わる ■新製品の売り上げ比率は50%以上 ■設備稼働率は70%以下にとどめる ■「選択と集中」「選択と分散」をバランス 【目次】 序章 効率偏重経営の終わり CHOICE 1 「環境変化に対応する」か「環境を自ら変革する」か 1章 製品開発力 売れる製品を最速で大量に生む仕組み CHOICE 2 フォーカスするのは「買う人」か「使う人」か CHOICE 3 KPIの目的は「業績向上」か「新陳代謝」か CHOICE 4 開発は「リレー型」か「伴走型」か 2章 市場創造力 流通を主導し、顧客と結びつく仕組み CHOICE 5 「自社の強みに絞る」か「自社の強みを絞らない」か CHOICE 6 強みは「固有の技術」か「固有の仕組み」か 3章 瞬発対応力 急な外的変化を成長に取り込む仕組み CHOICE 7 上げたいのは「稼働率」か「瞬発力」か CHOICE 8 瞬発力があるのは「身軽な外注」か「柔軟な内製」か CHOICE 9 「選択と集中」か「選択と分散」か CHOICE 10 「短期の効率」か「中期の効率」か 4章 組織活性力 仕事の属人化を徹底的に排する仕組み CHOICE 11 社長にとって「いい会社」か社員にとって「いい会社」か CHOICE 12 経営情報を「独占する」か「共有する」か CHOICE 13 組織内に「ヌシがいる」か「ヌシがいない」か 5章 利益管理力 高速のPDCAで赤字製品を潰す仕組み CHOICE 14 PDCAの要所は「PLAN」か「ACTION」か 6章 仕組みの横展開 7章 ニューノーマル時代の経営 CHOICE15 業界は「守るべきもの」か「壊すべきもの」か
-
3.3あなたより賢い頭脳を持った機械をコントロールできる? ユナイテッド航空3411便のオーバーブッキングによる乗客の強制退去事件を覚えているだろうか。航空会社が座席数より多めの予約を受けるのは日常的で、「便変更に協力いただければ1万円を差し上げます」などというアナウンスを聞いたことがあるだろう。当の3411便も4名に便の変更が必要となり、誰に降りてもらうかは、複雑なデータセットとアルゴリズムに基づきAIが特定した。しかし、1人だけ頑なに拒否。強制的にひきずり降ろされる映像が、SNSで世界中に拡散する。彼は医師で、患者との約束があった。その結果、航空会社は批判に晒され、最終的にはトップの辞任にまで追い込まれた。 技術の進化、AIの深化によって機械は飛躍的に賢くなっていき、我々の日常業務を代替する範囲は着実に広がっていく。その機械はどんどん複雑化するアルゴリズムのもとで動く。では、日常生活のあらゆる側面を変革するこれらの進化が、仕事、リーダーシップ、および創造性の未来にとって何を意味するのかを理解できているだろうか? 機械知能の急速な進歩のもと、21世紀における人間の知能の真の可能性は何なのか? 本書は、未来を読むことで世界的に高い評価を受ける著者が、長年にわたる研究と最先端の専門家、経営者たちへのインタビューをもとに、アルゴリズム時代に成功するために必要な10の原則を提示するもの。前例のない変化を続けるこの時代に生き残り、繁栄するために、あらゆる規模の組織とリーダーに希望的で実用的なガイドを提供する。
-
5.0顧客に会えなくても、成果を出す。 マイクロソフト、グーグルで活躍した著者が解説! リモート営業は、単純にミーティングをTeamsやZoomでやればいい、というわけではない。 顧客の興味付けからキーパーソンとの対話、クロージングまで、 営業プロセスそのものを見直す必要がある。 また、ウェブ、電話、メールなど、各種ツールの組み合わせ方や プレゼン資料の見せ方なども、対面による説明を前提としたものとは違うものになってくる。 本書では、こうした「営業プロセス」についての考え方から、 オンラインミーティングにおけるツールの概要や活用のポイントまでをわかりやすく、 コンパクトにまとめた入門書だ。 著者の水嶋氏は、デル、マイクロソフト、グーグルなど外資系IT企業で 訪問しない「インサイド・セールス」の仕組み作りに携わってきた。 こうした豊富な経験を生かして、リモート営業への転換の仕方を具体的に語る。
-
-30年にわたる経済の停滞と、それに対して的確な対処が出来なかった一つの理由は、日本経済の急速な構造変化を経済統計が的確に捉えていなかったことだ。1990年代以降に統計を通じた十分な構造変化の把握をしてこなかったために起こった第2の「敗戦」が、現在の停滞であるとも言える。 本書は、GDPの精度改善、統計カバレッジの向上から「毎月勤労統計」問題、統計作成技術の改善まで、日本の統計の課題とその問題解決のための統計改革について、改革の司令塔の前統計委員会委員長を中心に解説。エビデンスにもとづく政策を実現するために不可欠な改革策を具体的に示す待望の統計改革ガイド。 ●日本の統計の5つの問題点 1.景気判断のもととなるGDP(四半期GDP速報<QE>)や景気関連統計のブレ(ノイズ)が大きい 2.統計のカバレッジが十分ではない: GDPが経済活動を十分に捕捉できていない 3.インフレ率の推計精度が十分ではない 4.日本経済の成長力(潜在成長率・生産性)を正確に評価できていない 5.統計作成プロセスが、日本の社会経済の構造変化に対応していない
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新しい防災の心得 新型コロナは、「防災」に対する考え方を一変させました。 例えば「避難」。「3密」の避難所に避難することは、 感染という別のリスクを生み出します。 そこで、考えたいのが「在宅避難」です。 自宅で避難生活をするための ノウハウを徹底調査しました。 台風や地震に強い家はDIYや片付けだけでも作れます。 非常食の備えは普段の買い物を工夫するだけ。 アウトドアグッズは最高の防災グッズに。 災害対策は意外と簡単にできることがたくさんあります。 災害シーズンを万全の状態で迎える準備は、いつからでも遅くありません。 ◎台風の前に確認するチェックリスト ◎「ハザードマップ」には2種類ある ◎養生テープでは窓は守れない ◎100円ショップのランタンはお役立ち ◎「防災セット」の中身は全然足りていない! ◎アウトドアグッズは最強の防災ソリューション ◎非常食は「ローリングストック」が新常識 ◎広げるだけで使える断熱性マット ◎2泊3日の「おうち避難訓練」で、足りないものが分かる ◎食器や家具が飛んでくる!身を守る「防災片付け」 ◎コロナ時代は在宅避難がカギ ◆日常生活で備える台風&水害 対策のアイデア満載 ◆警視庁災害対策課Twitterに学ぶ 防災の最新アイデア
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ゲームやロボット製作で身に付く 工作基本ワザ30、Pi 4/カメラ新版検証 「積み木ができる小さなロボットアーム」 「人が近づくと回り出す卓上扇風機」ーー。 そんな作って楽しい9種類の作品を製作しながら、 30種類の電子工作の基本ワザを身に付けます。 ハードワザとソフトワザを15種類ずつ紹介します。 ラズパイ4の8GB版、64ビットOS、新高精細公式カメラの実力はどの程度か。 性能や使い勝手をしっかり検証します。 Webのコロナ情報を調べて警告するマシン、 抵抗16本をベースに自作するADコンバーターも併せて作りましょう。 特集1 ゲームやロボット工作で分かる! 電子工作基本ワザ30 特集2 メモリーは8Gバイト&OSは64ビット対応 ラズパイ最新版の実力を徹底検証 特集3 高解像度でレンズ交換が可能になった! 新公式カメラモジュールの使い勝手をレビュー 特集4 AD変換器を自分で作ってみよう 抵抗の「分圧」で細かく測れる 特集5 音楽・動画専用OS「LibreELEC」で遊ぼう! インターネットラジオやYouTubeをラズパイで再生 特集6 自治体のWebページと連携、新型コロナ信号機を作ろう 特集7 「Ubuntu 20.04 LTS」+「ラズパイ4」で構築! ハイレゾ対応の音楽配信サーバー 特集8 ラズパイをBluetooth経由で操作できるようにしよう 講座 実験して分かる電子パーツの動かし方 講座 ハード&ソフトをちょい足し?新しいラズパイの遊び方 講座 ラズパイとPC両対応! ゆっくり学ぶLinuxの使い方 講座 電子工作にも役立つ! 基礎からわかるLinuxコマンド マンガ 女子高生とラズベリーパイ 【付録冊子】アキバの人気パーツ配線図ベスト17
-
-新型コロナウイルスは社会の姿を一変させた。 このウイルスに感染すると、風邪のような症状だけで済むこともあれば、 肺炎を発症し、命を落とすこともある。 症状が全くない人からもうつることが分かり、不安は募るばかり。 こうした状況で一番大切なのは、この感染症を正しく理解し、正しく恐れること。 「肺炎」については、誰もがその名前を知っているが、実態を理解している人は少ない。 そもそも肺炎はどのような病気か、なぜ肺炎で亡くなる人が多いのか。 新型コロナウイルスによる肺炎は、これまでとは何が違うのか。 なぜ、一気に悪化してあっという間に亡くなる人がいるのか。 肺炎を避け、予防するにはどうすればいいのか――。 呼吸器内科医として肺炎と向き合って30年、 実際に新型コロナの肺炎患者も診察し、テレビにもたびたび出演する、 池袋大谷クリニック院長の大谷義夫さんが解説する。 肺炎は、新型コロナウイルスに関わらず、日本人にとって身近な怖い病気だ。 現在、日本では年間で13万人を超える人が肺炎で亡くなっている。 新型コロナウイルスによる肺炎を正しく恐れることができれば、 将来の肺炎対策につながり、日本人の健康長寿に貢献できるのだ。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Zoom、Slack、Teamsの3大ツール対応! 今日から業務に役立つ実践・活用ノウハウ満載 在宅勤務やテレワークを実践する職場が急増し、 ビデオ会議やビジネスチャットを利用した情報共有など オンラインでのコミュニケーションが当たり前になりつつあります。 そこで本書では、ビデオ会議やビジネスチャットなどを利用した 「テレワーク」の導入から実践までを、実務に即して分かりやすく解説します。 ZoomやMicrosoft Teams、Slackなど代表的なツールを紹介しながら、 文書のデジタル化(ペーパーレス化)やファイルのやり取り 効率的な共同作業の仕方など、「デジタルワークスタイル」全体を 見通した働き方のノウハウをお届けします。 ●導入編 第1章 テレワークで仕事を進化させる 第2章 話題のツールで何ができ、どう変わる? ●実践編 第3章 Zoomで手軽にオンラインミーティング 第4章 Slackでビジネスをスピードアップ 第5章 Teamsで始める本格オンラインワーク ●応用編 第6章 デジタル時代の新しい働き方とは 第7章 在宅勤務を快適にする便利グッズ ●資料編 テレワークを理解するための用語集
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、日経NETWORKに掲載したネットワークプロトコルに関連する主要な記事をまとめた1冊です。ネットワークプロトコルを網羅的かつ分かりやすく解説します。 文章を読むだけでは難解なネットワークプロトコルを、豊富なイラストや図を使って解説していることが特徴。「TCP/IPを学ぶ」編では、インターネットの通信で使われている主要プロトコルであるTCP/IPやその関連技術を豊富な図で解説します。「イーサネットを学ぶ」編では、有線通信の代表的なプロトコルのイーサネットやMACアドレス、ARPなどの基礎を初心者にも分かりやすいように説明します。「通信制御のプロトコルを学ぶ」編では、インターネットの通信に不可欠なDNSやIPアドレスなどを配布するDHCPなどを徹底図解。「データ送受信のプロトコルを学ぶ」編では、WebのプロトコルであるHTTPやデータ送受信のプロトコルFTPを豊富な図とイラストで解説します。HTTPの最新バージョンであるHTTP/3や安全性を高めたHTTPSについても詳述します。 ●目次 【第1部 TCP/IPを学ぶ】 第1章 マンガでわかるTCP/IP 第2章 ネットワーク技術解説 IPアドレスって何だろう? 第3章 図解で学ぶネットワークの基礎 IPアドレス など 【第2部 イーサネットを学ぶ】 第1章 今こそ知りたいイーサネット 第2章 ネットワーク技術解説 イーサネットって何だろう? など 【第3部 通信制御のプロトコルを学ぶ】 第1章 安全DNSの極意 第2章 ネットワーク技術解説 DNSって何ですか? など 【第4部 データ送受信のプロトコルを学ぶ】 第1章 HTTP/3登場 第2章 ネットワーク技術解説 Webアクセスってどんなの? など
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Linuxの心臓部であるカーネルの動作を 実験用プログラムで自ら試し、体感することで 仕組みを基礎から理解できる入門書の決定版 サーバーOSとしてデファクトのLinux。 その中核となるカーネルの仕組みを分かりやすく丁寧に解説します。 OSとしてのLinuxがどのように動いているのかが分かります。 1章と2章ではカーネルの全体像をつかめるよう 基礎となる部分を大きくページを割いて紹介。 3章ではLinuxカーネルのソースコードから 実際に動く状態に組み立てる「ビルド」と呼ばれる操作を、 手順を追って紹介します。 4章以降では、3章までに学んだ知識や手法に基づき、 Linuxカーネルの仕組みを章ごとに解説していきます。 機能解説の章には、実験用のプログラムを用意し、 それを実際に動かすことで理解を深められるよう工夫しました。 第1章 Linuxカーネルの基礎 第2章 Linuxカーネルのモジュール管理 第3章 Linuxカーネルのビルド方法 第4章 タスクスケジューラの仕組み 第5章 仮想メモリーを実現する仕組み 第6章 コンテキストスイッチの仕組み 第7章 物理メモリー管理の仕組み 第8章 ファイルシステムの仕組み
-
4.0ダイヤモンドの歴史とは、人々の欲望の歴史です。「ダイヤモンドは永遠の輝き」とは、ダイヤモンドのシンジゲートを牛耳るデビアスが、一九四八年に考案したキャッチコピー。このキャッチコピーにより、世の男性は、結婚指輪として、ダイヤモンドを女性に渡すようになっていったのです。人は、指にはめたダイヤモンドを見せびらかします。それは、優越の証。それが、他の人よりも良いものであれば、優越感に浸り、満足するのです。 本書は、古代ギリシャから覇者デビアスの誕生と凋落、紛争ダイヤ、合成ダイヤまで人々の欲望をめぐって成長してきたダイヤモンドビジネスの歴史をたどるユニークな世界史です。
-
3.2○本書は、私たちが暮らす場所の地形にはどのような特性があって、どう変化してきたのかについての見方を紹介する歴史地理学入門。近年各地で発生している水害や地形災害は、単に地球温暖化や異常気象だけで説明できない。どこで、どのように災害が発生しているのかについて理解を進めるために、地歴、地形環境やその歴史的改変の知識が欠かせない。 〇日本人の大半は平野に居住している。そもそも平野は川によってつくられた。平野は、扇状地・自然堤防・後背湿地・氾濫平野・三角州などに分類でき、後背湿地や氾濫平野は、主に水田に利用され、集落は自然堤防沿いにつくられてきた。 〇近年相次ぐ大型台風による洪水や山崩れは、地形的に災害の発生しやすい低地や地盤の弱いエリアに集中して発生している。本書は過去の日本人の土地との付き合い方、地形環境の改変の歴史を豊富な事例とともに紹介、大災害時代の必携教養として伝えたい。
-
3.3
-
4.3★白Tシャツ、ボーダー、デニム、カシミアニットの4つが最高におしゃれに着まわしまくれる! ★アメブロ3万8千人! 人気ブロガーが教える ★ユニクロ、楽天、ZARAほかプチプラ服で120コーデ 白いTシャツ、ボーダー、ジーンズ、黒カシミアニット。この4つ、みなさん、持っていますか? 特に、「白いTシャツ」「ボーダー」「ジーンズ」の3つを着たことのない人はいないでしょう。黒カシミアニットを持っていない人も、黒のニットなら持っている人は多いと思います。 この4つは、とにかく便利です。とても着やすい服です。ただ、着やすいがゆえに「とりあえず着る」服にもなりがちです。この4つが、何も考えずにおしゃれに着られたらとてもいいと思いませんか? この本では、猫のみにゃこが、この4つのどれかを着た街ゆくおしゃれな人たちに「なんでそんなにおしゃれに着られてるの?」とインタビューしています。本人が、自分がなぜおしゃれなのかを教えてくれるから、とってもわかりやすいです。 イラスト全部描きおろし! 各アイテム30ずつ、計120コーデが掲載されています。これでもう一生コーデに困りません!
-
4.1大人気投資ブログ「エナフンさんの梨の木」筆者として知られる会社員投資家が、 年率30%リターンで勝ち続ける、最強のバリュー投資法を実践的に解説。 コロナショック時の逆転勝利、10倍高をゲットした成功例など、 独自に編み出した新しい株式必勝ノウハウを大公開。 ◎「はじめに」より バリューエンジニアリングとは、 「より優れた製品をより安くつくる方法」の研究から発展したビジネスの手法である。 私は仕事で出会ったこの手法が株式投資にも応用できると直感し、独自にその体系化を進めてきた。 バリューエンジニアリングでは、「価値」という概念を体系的に分析する手法に加えて、 インプットである「情報」という概念を厳密に扱う。 この2つは株式投資において最も重要な要素であり、その応用範囲は広い。 ◎主な内容 バリュー発生の5パターン/VE投資の方程式/VE投資の3つのキーワード 本質的価値の算定方法/個別株の評価のための情報整理/「あるべきPER」の基準表 『会社四季報』を丹念に読み込む/投資ストーリーを書き残す VE投資の5原則/7つのバリュー原理/「市場は間違う」という観点から攻める VE投資の成功と失敗/10倍高をゲットした成功例/VE投資法の売却ルール 未来予測の4パターン/鳥の目、虫の目、魚の目/株式投資はキノコ狩りと同じ
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2020年9月1日から「マイナポイント」が始まった。マイナポイントとはキャッシュレス決済サービスの利用者1人当たりに政府が最大25%のポイント5000円分を付与するキャンペーンだ。ただし、この政府の大盤振る舞いを受けるには条件がある。マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていることだ。本書はマイナポイントをもらう手続きの解説に始まり、マイナポイントに必須のマイナンバーカードがデジタル社会に欠かせない役割を担うことを説明。マイナンバーカードが「デジタルの実印と身分証」になるといった知られざる機能などを解説する。さらにマイナンバーカードを持っているとアクセスできる個人情報の管理基盤「マイナポータル」についてその活用法を伝授。これからの新しい生活様式に欠かせないマイナンバーカードとマイナポータルを完全理解するための1冊です。 ≪目次≫ 第1章 マイナポイントをゲットしよう 「マイナポイント」って何? もらう手続き方法一挙解説 マイナンバーカードとは? みんなの疑問を徹底解明 知られざるマイナンバーカード 3つの機能を大解説 マイナンバーカードが健康保険証に 医療機関の窓口はこう変わる マイナンバーカードで実現 いつどこからでもインターネット投票 第2章 マイナポータル徹底活用 マイナポータルって何? 自分の情報を管理する基盤に 健康管理や引っ越し、起業も マイナポータル活用サービス 第3章 デジタル未来図[インタビュー] デジタル社会への変革につなげる マイナンバーカードは給付インフラ PINなし認証で健康保険証
-
4.0「スタッフが育つ褒め方、叱り方を知っている」「労務問題に発展させない空気をつくる」「お金をかけずに売上を増やす」「原価・粗利に常に目を光らせている」――。 店長や店長候補、スタッフのために、「プロ店長」が実践している仕事術を豊富な事例とともに紹介する。 ■1店舗の運営、そのすべてを任される店長の仕事は、非常に多岐にわたります。スタッフの採用から育成、シフトの組み立て、離職防止のための個別フォローといった人材に関すること、お客様満足度を高めるための工夫やリピーター獲得といった店舗づくりに関すること、日々の現金管理をはじめ売上・利益に関すること、さらには店舗の安全・防犯に関することと、実に幅広いことがわかります。 ■そんな多岐にわたる仕事を日々的確に行っている“プロ店長”がいます。お客様との信頼関係を築き、売上をアップさせ、スタッフを育てる――、成功している“プロ店長”はどんなふうに店舗運営=店舗マネジメントをしているのか、なかなかうまくいかない“ダメ店長”と何が違うのか、“プロ店長”が実践している仕事術を豊富な事例とともに紹介します。 ■現在店長の方、店長候補の方、店舗で働くスタッフ、初めて店長になった方、さらに成長したい方、うまくいかないと悩んでいる方は必見です。また、介護、保育園・幼稚園、塾・予備校といった施設運営を必要とする業種の方でも、現場で使える、役に立つヒントが満載です。
-
3.8気が散る本当の原因は、スマホやSNSではない 集中は目標の達成を助け、注意散漫は人を目標から遠ざける。気が散る原因とよく挙げられるのがスマホ、SNS、テレビ、タバコ、ゲーム、友人とのおしゃべり……。しかし、これらは表面的原因にすぎない。注意散漫を跳ね返すには、根本原因を見つけ、戦略的に対処しなければならない。本書が掲げる戦略テクニックを実行すれば、「集中力を保つ」というスーパーパワーを身につけられる。 魅力のある製品やサービスには、使っているうちに「やみつき」になる魅力が備わっている。それは、たまたまそうなっているのではなく、企業が心理学を駆使し、ユーザーが「ハマる」ように設計しているからだ。著者ニールは、この「秘密の心理学」を、スタンフォード経営大学院とハッソ・プラットナー・デザイン研究所(Dスクール)で、未来の企業のエグゼクティブたちに長年教えている。いわば、舞台裏を知り尽くしている「ハマる心理学」の達人が、企業側の仕掛けたトラップに陥らないで、自分が本当にやりたいことに集中力を振り向けるための戦略と実践テクニックを公開する。
-
3.3反響を呼んだ前作から5年、待望の第2弾。 最新の環境データからエコハウス実践術まで、変わる常識と変わらない真実を解き明かす。 東京大学で省エネ住宅を研究する気鋭の研究者が、実証データやシミュレーション結果をもとに、一般ユーザーや住宅関係者が信じて疑わない“エコハウスの誤解”をバサバサと切っていきます。前半の「変わる常識ー基本編」では、地球環境問題やエネルギー問題をめぐり、これからの家づくりに求められる「変革」について最新のデータから解説。後半の「変わらない真実ー対策編」では、実際の家づくりで実践すべき工夫を独自の検証データをもとに提案します。ユーザーにとってもプロにとっても、「本当のエコハウス」をつくるために必読の1冊です。 ■主な内容 ◎PART1:変わる常識-基本編 第1章 環境・エネルギー 第2章 健康 第3章 家電 第4章 太陽光発電 第5章 エコハウスの目標 ◎PART2:変わらない真実-対策編 第6章 冬の備え 第7章 夏の備え 第8章 空気とお湯
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 コロナ危機の今こそ、業種を超えた変革の好機。 各界の識者が、14業界の活路を示す! 巻頭対談は、柳川範之氏(東京大学経済学部教授)。 そのほか、翁百合氏(日本総合研究所理事長)、平野正雄氏(早稲田大学ビジネススクール教授)、岩下直行氏(京都大学公共政策大学院教授)、三浦瑠麗氏(国際政治学者)、石川温氏(ジャーナリスト)など第一線で活躍する識者や、TDK、ヤフー、UBS証券、T&Dホールディングス、オリックス自動車、ローソン、経済産業省、関西電力といった業界のキープレーヤーが多数登場! 新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界経済が危機に瀕しています。どのように危機から脱け出し、立て直していけばよいのか。 日本経済を14の業界に分けて網羅。業界ごとにアクセンチュアの専門家がコロナ危機を踏まえた現状の課題と展望を明らかにした上で、キーパーソンと対談。解説と対談を合わせて展開し、各業界が向かうべき道を浮き彫りにします。
-
4.1
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 コロナ危機で医療、健康の進化が加速する! ・オンライン診療、AI創薬、個別化医療、医療・健康データ活用、予防サービスetc――.持続可能・成果ベースに変革する最先端の動き ・医療機関、製薬会社、保険会社、行政のキーパーソンが続々登場! ・新型コロナワクチン開発の最前線 ・体内病院、再生医療、中分子薬――革命を起こす研究者たち 世界を揺るがしている新型コロナウイルスの感染拡大によって、医療や健康に対する考え方が変化し始めています。コロナ危機を乗り越え、ヘルスケアはどのような姿を目指すべきなのか。様々な角度から最先端の動きを捉え、ヘルスケアの未来を描きます。 まず、ポスト・コロナ時代のヘルスケアの全体像を示した上で、医療、医療行政、製薬、保険の各パートで変革のポイントを解説。対コロナ治療薬・ワクチンの展望やAIによる創薬、オンラインによる遠隔診療、予防型医療、保険会社の健康維持ビジネスなど、注目の最新事例を多数紹介します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆新聞連載の病院ガイド「日経実力病院調査」をムック化 本書は新聞の連載企画「日経実力病院調査」を再録したムックの最新版です。日経実力病院調査は、手術数や施設・運営体制などから全国の病院を毎年評価する取り組み。胃がんや肺がんといった疾病ごとの調査だけでなく、病院の「総合力」も分析する点が特徴で、新聞では2019年6月から20年1月にかけて連載しました。 本書では新聞に掲載した調査結果を大幅に拡大して、のべ約4000の実力病院を公表します。 巻頭特集では日経の編集委員が病院の選び方について解説。さまざまな情報の中から自分に合った病院を探すためのヒントを紹介しています。 解説ページでは患者数が増加している「がん」と「認知症」の最新医療を解説するほか、患者の負担を軽くする在宅医療の現状も紹介。病気で悩む読者に役立つ情報をまとめています。 ◆病院選びもニューノーマルに! 新型コロナウイルスの影響により、病院と患者の関係が急速に変わりつつあります。第2特集ではコロナ関連の特集を組み、コロナ下の病気との向き合い方を紹介します。日経の編集委員による書き下ろしの解説記事も収録します。
-
4.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日経新聞の精鋭記者による取材の成果が一冊に! 信頼度No.1の決定版 業界ごとに、企業の提携・勢力関係、今後の見通し、キーワードをビジュアルに解説! 巻頭では、20年4月以降の環境激変後、業界勢力がどう変わるかを徹底解説。 日経オリジナルの「世界シェア調査74品目」も掲載。 本編とあわせて、今後の業界の勢力関係を多面的に把握できます。
-
3.7●待望の農業戦略白書 日本農業が高齢化、農地荒廃に直面しているのは事実ですが、これから先どのような戦略を立てるべきなのでしょうか。世界の食糧事情・食習慣の変化、農業手法の革新、プレーヤーの状況の理解無しには、これからの日本農業の戦略は立てられません。本書は、世界的なコンサルティング企業マッキンゼーによる大局観が得られる農業戦略白書。 マッキンゼーというと日本では戦略立案のプロというイメージが圧倒的に強いのですが、その顧客に多くの世界的な農業関係企業を抱えていることもあり、食糧・農業動向の分析には実績があります。また、ここ数年の日本農業への法人参入を受けて農業ビジネス改革のレポートも公開してきました。本書は、これまで蓄積されてきたマッキンゼーの内外の食糧・農業関連の知見を初めて書籍としてまとめるもの。単に世界動向をまとめるのではなく、各動向が日本に及ぼす衝撃も解説する内容となります。 本書は、食と農のグローバル・メガトレンドを1大状況の変化、2アグリテックなどの抜本的な技術革新、3政策・規制の変化、4食習慣・ソーシャルファクターの影響、5農薬・種子・肥料など上流プレイヤーの変化、6消費者ニーズの変化、7代替品・代替手法の進化、8新規参入プレイヤーの8つのポイントで整理し、各々が日本農業にどのような影響を及ぼすのかを解説し、日本農業の生産性向上に何が必要か、進むべき方向と解決策は何かを提言します。マクロからミクロまでバランスの取れた内容になります。
-
4.2営業職員3万人が使用するタブレットを更新せよ! ビッグプロジェクトの全容を追体験しながら学べる 業務改革の新しい教科書! 本書は、住友生命で行われた営業職員が使用している3万台のタブレットを更新するビッグプロジェクトを通し、自律自走型プロジェクトとは何かを学べる新しいタイプのテキストです。 自分たちの仕事はどうあるべきで、それを支える営業端末はどう形作られるべきなのか。メンバーの関係は完全にフラットで、それぞれの担当が自分で考え周りを巻き込みながらも最後は自分で決める「進化する変革プロジェクト」として実行し、成功を収めた事例を紹介しています。 特徴的なのは、支援していたコンサルティング会社の社員と、支援を受けながらプロジェクトを進めた2人の社員が、それぞれの異なる立場から立体的に描いている点。 内部と外部の視点からプロジェクトをどう捉えていたのか、なぜこのような進め方をしたのか、そこにどんな悩みや決断があったのか。プロジェクトの状況を追体験しながら、組織の運営や、業務改革、システム構築のノウハウを学べます。