統治作品一覧
-
-リベラル・アーツの多様性と現代への問題提起 文学、言語学、外国語教育学から 経済学、メディア論、教育工学まで── 『異文化のクロスロード』(2007)、『ポスト/コロニアルの諸相』(2010)、『ことばのプリズム』(2014)、『リベラル・アーツの挑戦』(2018)に続く、岐阜聖徳学園大学外国語学部の研究成果。 【目次内容】 ▼ ジェンダーからみる太平洋戦争の記憶 ――環太平洋文学の描く日本植民統治(河原﨑やす子) ▼ ペーター・ハントケの『雀蜂』について ――「盲目性」の意味(熊沢秀哉) ▼ 病と不調の経験から他者としての女性の経験へ ――病者と労働者階級へのヴァージニア・ウルフの(非)共感性(四戸 慶介) ▼ 英語教育における批判的思考力の育成 ――クリティカル・リーディングの指導(伊佐地恒久) ▼ 談話研究とその日本語教育への応用 ――「のだ」疑問文を中心に(大塚容子) ▼ 恩師の取材とレジリエンス形成 ──教職課程のアクションリサーチ(冨田福代) ▼ マインドセットと学習環境 ──外国語を学ぶ学生たちを成功へと導く学習スペースの構築(テイラー・クレア/長尾 純) ▼ 教育における ICT(情報通信技術)の活用と考え方(長谷川 信) ▼ 分裂と統合のTwitter ──コロナ禍におけるトレンドの特性(宮原 淳) ▼ 功利主義と義務論 ──社会科学の視点を進化理論から考える(蔵 研也) ▼ 現代アメリカ英語における whom に関する一考察(丹羽都美) ▼ 中国語の自由会話におけるメタ言語否定のストラテジー(李 嘉)
-
3.7代々の紋章王が統治するゼルティバッソ紋章国の東端、ニルイースト。そこは脛に傷持つ犯罪者たちや、一攫千金を夢見る荒くれ者たちが集い、暴力と欲望が支配する街。そんな蛮都の風紀を守るべき王国直下の常駐治安騎士団だったが、しかし彼らこそが一番危険で邪悪な存在であった。――人呼んで、悪逆騎士団。誰もが目を奪われる美貌と、誰もが畏れる暴威を振りまく女エルフの団長アリシア。彼女に捕らわれて、新たな団員として暮らすことになった元暗殺者の少年コルナルド。そして拷問騎士、淫蕩騎士、醜悪騎士という出鱈目な団員たちによって繰り広げられる狂乱の事件とは――。「まったく私達はとんでもない悪党だな」悪によって悪を裁く、退廃のダークファンタジー登場!
-
3.7
-
4.3文武兼ね備えたエリート武将は、いかに本能寺の変へと追い詰められていったのか。牢人医師としての出発点から、延暦寺焼き討ちで見せる冷酷さ、織田家中における異例のスピード出世、武官としての比類なき実力まで。近年急速に進む光秀研究の成果を踏まえ、謎多き素顔に英雄史観・陰謀論を排し、実証的に迫る。気鋭の中世史家による、渾身の一作! 序章 新時代の子供たち 第一部 明智光秀の原点 第一章 足利義昭の足軽衆となる 第二章 称念寺門前の牢人医師 第三章 行政官として頭角を現す 第四章 延暦寺焼き討ちと坂本城 第二部 文官から武官へ 第五章 織田家中における活躍 第六章 信長の推挙で惟任日向守へ 第七章 丹波攻めでの挫折 第八章 興福寺僧が見た光秀 第三部 謀反人への道 第十章 領国統治レースの実態 第十一章 本能寺の変へ 終章 明智光秀と豊臣秀吉
-
3.3
-
3.0急激な経済成長により、中国のエネルギー事情は逼迫。衰退していく北部都市を抱えた中国は、南沙諸島の領有に死命を賭け、海軍艦艇を展開した。南沙の共同統治を主張するASEAN諸国との高まる緊張を緩和させるため、日本政府は国連軍活動に踏み切った。先んじて派遣された潜水艦「あさしお」は中国軍の対潜作戦の標的に!? 地下資源と交易拠点をめぐりアジア各国の思惑と戦略は交錯する。シミュレーション巨篇新シリーズ、堂々誕生。
-
4.0
-
4.0第二次大戦以前、日本の植民地だったパラオ。そこには「南洋庁」という役所があり、日本からの移民と現地島民が織りなす「暮らし」がたしかにあった――。当時パラオに赴任した作家・中島敦の小説をきっかけに、著者が当時の南洋諸島に興味を持ち、実際にパラオへ赴き、日本統治時代を知るお年寄りを訪ねて、当時のエピソードを収集した歴史ルポルタージュ。著者はパラオだけでなく、パラオからの帰国者が集団で移住した宮城県蔵王町の北原尾や、宮崎県小林市の環野にも赴いて、当時の証言を集めた。戦中派が世を去って歴史の記憶が薄れる今こそ、広い世代に読まれるべき貴重なエピソードが詰まった一冊。
-
5.0「朝鮮の人たちが朝鮮語を話して何が悪いんだ」 終戦間近、日本統治下の朝鮮の学校で、日本人の少年Aが叫んだ言葉が、朝鮮の少年Bの脳裏から離れない。 戦争末期の朝鮮半島、二人の少年はともに地元の旧制中学に通い、学んだ。日本統治下の朝鮮半島の実情、参戦してきたソ連の横暴、終戦後の悲惨な脱出行、41年後の劇的な再会など、二人の知識人の交流はそのまま日本と韓国の歴史を物語る。
-
4.0国際社会を震撼させた「カブール陥落」から2年――タリバン統治の実態は? 女性の権利は? 和平実現への道筋は? そして日本が果たすべき役割は――? アフガニスタン政権崩壊が、ロシアによるウクライナ侵攻を間接的に招いたとの見方もある。文明が交錯する場所であるが故に不安定なアフガニスタンは、ユーラシア大陸の連結性のミッシング・リンクとなる。激変するアフガニスタン社会を、中東政治の研究者が詳細にレポート。
-
4.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「英米法」と総称されるイングランド法とアメリカ法はきわめて近い関係にありながら、様々な分野で大きく異なる側面を持つ。本書は「比較歴史学」の方法を駆使してアメリカ法のイングランド法からの継受・分離・独立過程を解明、あわせてアメリカ本国およびわが国における「研究史」を調査、整理、評価した初の本格的研究。「アメリカ法制史学不在の現状」を打破すべく書かれた著者二十年の苦闘の成果。第7回天野和夫賞受賞。 【目次より】 序:わが国におけるアメリカ法制史研究不在の現状 第一 法形成の主体 アメリカ型法曹の醸成に関する歴史学的考察 第1篇 独立前夜マサチューセッツの法曹制度 I はじめに 問題の所在 II 予備的説明 III 「法律家団体」 IV 法学教育 V 「イングランド化」の阻害・限界要因 VI むすびにかえて 第2篇 独立前ヴァジニアの法曹制度 I はじめに 問題の設定 II 研究史の概略 III ヴァジニアの統治・権力構造における司法機構 IV 法曹資格試験及び法曹関係立法 V 一般管轄裁判所のアトーニ(GCA)の実態及び性格 VI むすび マサチューセッツ法曹との比較におけるヴァジニア法曹の特徴 第3篇 連合規約時代における「アメリカ型法曹」醸成過程 I 序 アメリカ法制史学不在の現状 II アメリカ法制史学に対するWarrenテーゼの意義 III 独立宣言当時における法曹制度 IV 連合規約時代マサチューセッツの法曹 V 連合規約時代ヴァジニアの法曹 VI 「アメリカ型法曹」醸成過程に関する理論的考察 第二 アメリカ的法制度の形成過程断片 第4篇 奴隷が行使する I聖職者の特権」 独立前ヴァジニアにおける「イングランド法継受」の一例 I 本篇の問題 II 奴隷が行使する聖職者の特権の実例 III 聖職者の特権制度の導入と奴隷への拡大 IV 聖職者の特権の実態と機能 V むすびにかえて 第5篇 独立前夜における陪審裁判の歴史的位置 マサチューセッツに見るその実像 I 本篇の問題 II 歴史的事実の文脈 独立前夜マサチュ ーセッツにおける「陪審裁判」のある実態 III 法制史上の文脈 IV むすびにかえて 第三 アメリカ法制史研究批判 第6篇 アメリカ法制史研究の回顧と展望 「アメリカ法制史学不在の現状」の根本問題 I 序 第1部 II アメリカ本国におけるアメリカ法制史研究概観 III わが国におけるアメリカ法制史研究概観 第2部 IV 本国におけるアメリカ法制史研究の批判的検討 V わが国におけるアメリカ法制史研究のあり方に関する批判的検討 VI アメリカ法制史研究 VII 跋 文献一覧 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 大内 孝 法制史学者。東北大学教授。東北大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士課程修了。 著書に、『アメリカ法制史学序説』『西洋法制史学の現在』(編著)などがある。
-
1.0織田信長の一代記をいっきに読む! 織田信長の家臣だった太田牛一が実際に見聞きした事柄をもとに著した、信長の一代記「信長公記」。信長の生涯を知る上で、もっとも信頼できる史料として評価されている。そんな「信長公記」の首巻・巻一~十五の全十六巻から、主要なエピソードを凝縮! 信長の合戦・城・道楽、そしてその生涯をたどる。 第1章 尾張統一 第2章 信長と足利義昭 第3章 浅井・朝倉攻め 第4章 石山合戦 第5章 武田征伐 第6章 諸勢力との戦い 第7章 本能寺の変 第8章 領国統治と外交 第9章 信長の道楽 巻 末 『信長公記』首巻・巻一~十五 全文段要約
-
3.8
-
-本書は、マリア・テレジア女帝とヴィクトリア女王を戴いた通貨の流通 という視点からみた、日本ではあまり馴染みのないアラビア半島の近代史 かつ国際関係史である。 貿易通貨のマリア・テレジア銀貨が内陸部、法貨のインド・ルピーが英国の 勢力圏で流通したのは国際政治の反映であった。「偶像禁止」のイスラム教義 に反するマリア・テレジア銀貨がなぜアラブ人に選好されたのか、 また、統治者がイスラム君主の条件を満たさずに外国の君主の肖像入り通貨を 認めるという、通常では考えられない現象の理由が何であったかを解き明かす。 「イスラムの教えの理解なくして中東は理解できない」との主張に反し、 外国の元首であるマリア・テレジアを戴く銀貨を使い続けたアラブ人が、 イスラム以前からの銀の純度と重さを重視する慣習に従っていたこと、及び、 インド洋とペルシャ湾での覇権を求めた英国とフランスの外交戦が与えた、 アラブ人の英仏に対する感情の違いから、反英感情の裏返しとしての マリア・テレジア銀貨への「リヤル・ファランシ(仏リヤル)」呼称使用が 生まれたことなどを、当時のアラビアで活躍した欧州商人、インド商人の 具体的な活動と共に描いていく。 【目次】(第1章)マリア・テレジア銀貨(第2章)レヴァント(東地中海) 貿易 (第3章)モカコーヒー(第4章)「リヤル・ファランシ(仏リヤル)」の呼称 (第5章)インド洋経済圏のオマーン(第6章)独立尚武の国イエメン (第7章)マリア・テレジア銀貨の廃止(第8章)英領インドの「飛び地」アデン (第9章)英国の湾岸進出とネジド(サウド家) への関与 (第10章)法貨でない通貨の流通理由 (第11章)イエメンとオマーンにマリア・テレジア銀貨が残った理由
-
4.5三十歳の時に、異世界に勇者として召喚された祈里(女)。服装が悪かったのか、彼女はそこで男に間違われ、魔王を倒した後もそのまま勇者王として国を統治することに。そして十年間、真面目に王様業をこなしていたのだが、最近、美少女との見合いが殺到!? いくらなんでも女の子との結婚は無理と、やさぐれて酒と一緒にとある薬を飲んだところ、なんと祈里は銀髪碧眼美少女になってしまう。……この顔なら、勇者王だと気付かれないのでは? そう考えた彼女は、溜まりまくった休暇と称して城を抜けだし旅に出た! 見た目は美少女、心はアラフォーの勇者王による、異世界満喫お忍び旅。 ※電子版は単行本をもとに編集しています。
-
4.8*:;:*:;:*:;:* 新たな大河ロマン、ここに開幕! *:;:*:;:*:;:* 後の世に伝説として語られる妃、ライラーは、元々和国の姫君。謀略で捕われダリル帝国の後宮(ハレム)に入れられた。しかしこの後宮では子を産まず数年経てば解放される道が! 彼女は希望を得て、皇帝(スルタン)に近づかず、年季明けを目指すと決意する。 だがさっそく皇后に試されたり、高慢な妃候補に挑発されたり。ライラーはいくつもの窮地を両親に鍛えられた聡明さと生来の明るさを発揮して乗り越えていく。しだいに周囲から慕われ、賢明な統治者としての片鱗すら垣間見せ……。 けれどその結果ーーなんで逆に成り上がって寵姫扱いされてるの!? *:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:* 「わが家は幽世の貸本屋さん」シリーズ(マイクロマガジン社)、「異世界おもてなしご飯」シリーズ(KADOKAWA)の著者・忍丸氏、書き下ろし小説! *:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:* 担当編集コメント *:;:*:;:*:;:*:;:*:;:*:;:* 主人公のライラーの聡明さ、機転は必見!!! 痛快でスピード感あふれる展開に引き込まれること、間違いありません! とくに自分が好きなシーンは、敵視してくる妃候補から仕掛けられたある戦いに、思いがけない形でライラーが対応したあの場面。 ほかにも見所となる華やかな後宮文化、異国情緒あふれる描写、登場人物達の魅力…… どれをとっても、この作品を読まないなんて、もったいないです!
-
3.0空手部で練習に励みながら当たり前の学園生活を過ごしていた少女・アリサ。だが、その日常は16歳の誕生日の前夜、突如終わりを遂げる。黒ずくめの男たちの集団が家に押し入り、両親を殺害したのだ。襲い掛かる男たちからアリサを救い出したのは、大型の拳銃を手にした近所のタバコ屋の主人だった――。タバコ屋の主人はこの世界でのアリサの護衛役で、実はアリサは、複雑に重なり合う多重世界≪パラレルワールド≫を統治する能力を持つ「第一執政官アウラ」の娘だという。そして、その血族の最後の一人だと…。「ソロン」と呼ばれる追っ手から逃れるため、導かれるがままに別の世界へと逃れたアリサ。目を覚ましたのは慣れ親しんだ自分の街。すべては悪い夢だったと思おうとするが…家には見ず知らずの他人が住み、学校の友人たちも誰もアリサを覚えていない…。この時から、多重次元を股にかけたアリサのたった一人の戦いが始まった…!『週刊少年チャンピオン』で人気を博したSFアクション巨編!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 前4Cの古代ギリシア哲学の巨人は、自然学、論理学、形而上学そして政治学についても物した。その著作の深い洞察を改めて読み解く。 【目次より】 はじめに 序章 アリストテレス政治哲学研究の諸前提 伝記的素描、『政治学』の構成、研究の方法 一 伝記的素描 二 『政治学』の構成 三 研究の方法 分節・統合的言分析 第一章 「統治(アルケー)」の二重性 E・バーカー、H・アレントの「アルケー(統治)」理解との対比において 一 はじめに 二 E・バーカーのアリストテレス理解 三 H・アレントのアルケー理解 四 アリストテレスにおけるアルケー把握 五 結びにかえて 第二章 「公的なるもの(ト・コイノン)」の重層性 一 問題の所在 二 「コイノン」の用例の検討 三 国家と家 四 市民規定の二重性 五 結びにかえて 第三章 「正(ディカイオン)」の重層性 一 問題の所在 二 訳語の問題 三 「正」の構造 タクシス(整序づけ)論の視角から 四 「正」の構造 エートス論の視角から 五 「正」の二重性 倫理学から政治学へ 六 拡張的転用としてのディカイオン 奴隷に対して 七 結びにかえて 第四章 所有論の位相 一 問題の所在 二 所有、富、規定の二重性 三 財産の獲得をめぐる方法の二重性 四 蓄財術への実用的対応 五 理想的国家体制における所有の原理 六 結びにかえて いわゆる人間中心主義をめぐって 第五章 知慮(フロネーシス)の重層性 一 問題の所在 二 『政治学』における知慮(フロネーシス)、観想知(テオーリアー)、直知(ヌース) 三 『政治学』『ニコマコス倫理学』における哲学と政治 四 直知(ヌース)の四つの位相 五 知慮の構造 六 知慮の定義と知慮が働く場 七 実践概念の新たな地平 八 結びにかえて 第六章 国家論の構造 一 問題の所在 二 いわゆる自然的国家論について 三 アリストテレスにおける国家の定義 四 現実的国家体制論 五 理想的国家体制論 六 結びにかえて 第七章 アリストテレス政治学における国内的・国際的秩序観について 一 序 二つのアリストテレス観 二 アリストテレス政治学における秩序 三 アリストテレス政治学における個人と共同 四 アリストテレスにおける国家 五 アリストテレス政治学における国際的秩序観 六 結びにかえて 終章 展望あるいはアリストテレス政治哲学の現代的意義 一 直知論 二 意志論と感性論 三 音楽教育論と直知 補論一 アリストテレス政治学における「コイノーニアー 」と家と王の統治 補論二 アリストテレス政治学の基本用語「ポリーテウマ」について 註 あとがき 文献一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 荒木 勝 1949年生まれ。岡山大学副学長。専門は、西洋政治史。名古屋大学法学部卒業、名古屋大学大学院法学研究科博士課程単位修得退学。国際基督教大学博士(学術)取得。 著書に、『アリストテレス政治哲学の重層性』『現代公共政策のフロンティア』『ポーランド年代記と国家伝承』など、 訳書に、アリストテレス『政治学』『匿名のガル年代記―中世ポーランドの年代記』などがある。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量24000文字以上 32,000文字未満(30分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 私の名はヘンリー。65歳。 日系二世の父と日本人の母の下、沖縄にて生を受けた。 当時の沖縄は未だアメリカ統治下であった為、当然私はアメリカ人として生を受け、ヘンリーと命名された。 人に言わせると波乱万丈な人生に感じるらしいが、私本人はごくありふれた平凡な生活を送っていたイメージしか持ち合わせていなかった。 元来、穏やかな性格なのか単なる鈍感な人間なのか自分でもよく解らない。 若いころから一般的なアルコールの飲み方をしてきたつもりだったが、アルコールは確実に徐々に私の肉体と精神に影響を及ぼしていたみたいだ。 ある事件をきっかけに私はアルコール依存症者と診断され、精神的な療法を受けるために精神科病棟での入院生活を余儀なくされた。 この告白文がストーリーテーラーとしての単なる戯言か? アルコール依存症者の真の告白か?あなたはその最初の判断者になるだろう。 私を含め、世間一般でも、アルコール依存症という精神的疾患を、単なる言葉としてしか認識していない現実がある。 今回は自分自身が経験したことをもとにお話しさせていただいたが、アルコール依存症のことをどれくらい理解してもらえるかわからない。 アルコール依存症と診断された本人と、その家族や友人の本音が少しでもわかっていただけるように、敢えて筆を選ばず語らせていただいた。 特にお伝えしたいのは『アルコホリック』いわゆる、アルコール中毒患者に対しての偏った認識により、 患者の家族が特別視されてしまうという悲しい現実がついてまわっていることである。 アルコール中毒患者は暴力的で身勝手、手に負えないほど『意味もなく酔っている厄介な人間』という概念がついてまわるのは、いたしかたないことだが、 罪のない家族にも患者本人に向けられる視線と同じような視線が注がれる状態の社会は理解しがたく、怒りすら覚える。 ご家族、社会全体を含めて、アルコール中毒患者の精神状態、肉体状態を理解し、私たちに何ができるか共に考えていただければ幸いである。
-
3.01918年、日本統治下の朝鮮。山間の小さな村で育った18歳のポドゥルは、ハワイで暮らす朝鮮人男性のもとへ嫁ぐため故郷をあとにした。結婚相手とはお見合い写真を交換しただけで一度も会ったことはなく、ハワイがどこにあるかもわからない。けれど、楽園と呼ばれるその島へ行けば、何不自由ない生活が送れるうえに、女性でも勉強ができると聞いたのだ。一枚の写真だけを頼りに、同じく「写真花嫁」となる同郷のホンジュとソンファと共に海を渡る。だが三人を待っていたのは、波のように押し寄せる試練の連続で……。激動の時代に痛みを背負いながらも明日を信じた彼女たちの、勇気と愛情に満ちた半生とは。国際アンデルセン賞・韓国候補作家が贈る、希望を捨てない女たちの愛と連帯を描いた傑作長編小説。
-
3.5
-
4.5いまや新自由主義は、民主主義を内側から破壊している。新自由主義は政治と市場の区別を取り払っただけでなく、あらゆる人間活動を経済の言葉に置き換えた。主体は人的資本に、交換は競争に、公共は格付けに。だが、そこで目指されているのは経済合理性ではない。新自由主義は、経済の見かけをもちながら、統治理性として機能しているのだ。その矛盾がもっとも顕著に現れるのが大学教育である。学生を人的資本とし、知識を市場価値で評価し、格付けに駆り立てられるとき、大学は階級流動の場であることをやめるだろう。民主主義は黙っていても維持できるものではない。民主主義を支える理念、民主主義を保障する制度、民主主義を育む文化はいかにして失われていくのか。新自由主義が民主主義の言葉をつくりかえることによって、民主主義そのものを解体していく過程を明らかにする。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 20世紀に入り、インド独立の機運が高まってから、イギリスの統治が終わるまでの歴史を、イギリス側の重要人物の動きを基に読み直す。 1858年、インド大反乱を経て、イギリス東インド会社を解散、ムガル帝国の君主を排除して、直轄植民地とした。 本書は、植民地経営の終盤に焦点を絞り、20世紀に入り、インド独立の機運が高まってから、イギリスの統治が終わるまでの歴史を、イギリス側の重要人物の動きを基に読み直す。 第13代副王ハーディング卿の時代に、英国王ジョージ5世とメアリー王妃の初訪問から、第一次世界大戦、第二次世界大戦を経て、独立運動の高揚、インド内の宗教対立を経て、1947年ネルー首相による独立宣言までの歴史を丹念に描く。 【目次】 はしがき 第一章 インド担当相エドウィン・モンタギュー 一九一〇年~一九二二年 一 意識の創出 (一) 情報の受容(イギリス) (二) 情報の受容(インド) 二 政策の形成 (一) 『対インド宣言』 (二) 『モンタギュー・チェルムスファド報告』 三 政策の破綻 (一) カーゾンの反対 (二) ガンディーの反対 (三) モンタギューの錯誤 むすび 命運 第二章 総督アーウィン卿 一九二六年~一九三一年 一 アーウィンのインド像 二 宥和と反発 (一) サイモン委員会 (二) 『アーウィン声明』 (三) ガンディーの反応 三 むすび 『ガンディー・アーウィン協定』 第三章 チャーチル 一九二九年~一九三五年 一 基調 二 宣伝 三 組織 四 暴露 五 弔鐘 むすびにかえて 第四章 総督リンリスゴウ卿 一九三六年~一九四二年 一 性格 二 「分割統治」 (一) 州自治 (二) インド連邦 三 失策 (一) 宣戦 (二) 反応 四 むすび 想像力と洞察力の欠如 第五章 サー・スタフォード・クリップス 一九四二年 一 状況 二 派遣の決定 三 説得の行使 四 調停の失敗 五 余波 第六章 総督ウェーヴェル卿 一九四三年~一九四七年 一 統合 二 崩壊 三 亀裂 四 むすび 投影 第七章 クレメント・アトリーと総督マウントバットン卿 一九四七年 一 去来 二 『複数分割計画』 三 『二分割計画』 四 虹と旗 あとがき 参考文献 索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-十五世紀、室町幕府より関東の統治を任されていた足利家は、鎌倉に拠点を置いていたものの将軍家の部下でいることを嫌い、いつのまにか「公方」と名乗り、自らの勢力を築こうとしていた。そのため、足利家を補佐していた上杉家が関東管領として鎌倉公方と対立する事態となっていた。 上杉家は山ノ内・扇ガ谷家ともに鎌倉公方と対立し、争うことになる。そうした時代にあって、扇ガ谷上杉家の家宰である太田家はよく主家を助け、なかでも資長(道灌)の才と力量は群を抜いていた。やがて鎌倉公方・足利成氏は下総・古河に逃れ、資長は切望していた江戸城を手にいれる。そして鎌倉奪回を図る成氏たちを相手に、他の武将たちとともに戦い抜いていった。 一方、成氏の動きに危機感を抱いた京都の将軍・義政は、異母兄を関東公方として京都から下向させる行動に出る。加えて、山ノ内上杉の家宰相職を求めて長尾景春が乱を起こし、関東はさらに混迷を極めることに……。 関東の戦国初期、東国武士たちの動きを太田道灌中心に描いた力作。
-
3.8徴用工問題にレーダー照射問題……。 なぜ、日本と韓国はいつもこじれているのか? 日本は、これからどう付き合っていけばいいのか。 池上彰が現地を歩き、丹念に取材してわかった 韓国の頭の中。 今さら聞けない朝鮮半島の複雑な歴史背景から 北朝鮮やアメリカとの関係まで、時事問題もやさしく解説。 第1章 韓国と北朝鮮の歴史を変えた一日 レーダー問題とは何だったのか? 北朝鮮の融和姿勢の鍵 穴だらけだった経済制裁 北朝鮮が核兵器を完成させた本当の理由 外交の勝者はどっち? 韓国と北朝鮮の歴史的な会談 平和協定をめぐる複雑な思惑 板門店宣言の画期的な文言 うやむやになる可能性も? 文在寅大統領の北朝鮮へのシンパシー ルポ・燃える韓国、矛先を間違えては 第2章 駆けひきに揺れる朝鮮半島 翻弄されたトランプ大統領 「リビア方式」という禁じ手 「非核化」の工程表は? ハノイ会談の決裂はなぜ? 北朝鮮、約束破りの歴史 韓国と北朝鮮、統一はあるか? 「強い朝鮮」への願望 金委員長と文大統領はベンチで何を話したか? 強硬路線の日本は置いてきぼり? 安倍政権だからこそできること ルポ・「美女軍団」、韓国で感じたもの美女軍団」、韓国で感じたもの 第3章 朝鮮戦争とは何だったのか ルポ・軍事境界線にて―北朝鮮の虚勢に振り回される世界 二つの国はなぜ分断されたのか 日本人が知らない朝鮮戦争の実態 戦争はどちらが仕掛けた? 連軍の介入 北朝鮮が掘った南侵トンネル 潜水艦でやってきた北朝鮮兵士 戦争はまだ続いている ルポ・南北隔てる非武装地帯に咲く花 第4章 なぜ韓国の政治は感情的に見えるのか? なぜ韓国の大統領は決まって罰せられるのか 感情で法律が動く? 民主化運動の成功体験 軍事クーデターはなぜ起きたか 軍事政権時の空気 ルポ・五輪の風、韓国をどこへ運ぶ 第5章 日本と韓国はなぜ仲が悪いのか? ルポ・少女と徴用工、像からのぞく変化 憲法前文に見える「日本嫌い」 統治時代に対する認識のズレ 日本は被害者? 加害者? 慰安婦像を守る女性のホンネ 竹島は、どちらの国のものなのか? 関係を悪化させた韓国の竹島上陸 データで見る、関係改善のために必要なこと それでも「日本に行きたい」 慰安婦問題の解決法にみる韓国の情緒 第6章 韓国の厳しい格差社会 ルポ・生きづらい、悩む韓国の若者 生きづらいのは若者だけではない 財閥がつくる格差の実情 「ナッツリターン」「水かけ姫」騒動は何を表すか ルポ・めぐる聖火、熱気は起きるか 第7章 韓国と日本の未来――どう付き合っていくべきか ルポ・平昌高校、日の丸を作る理由 「日本の統治時代はよかった」? 「昼は反日、夜は親日」 徴用工問題にみる韓国のホンネ 統治時代を肯定することの危うさ 歴史を知ることから始めよう 韓国人に望むこと ルポ・ボランティアの学生も「日本代表」 ルポ・おもてなし、東京への教訓
-
4.3神の啓示の言葉を集めたコーランによれば、異教徒は抹殺すべき対象である。彼らを奴隷化することも間違っていない。ジハードは最高の倫理的振る舞いである。その意味で、カリフ制を宣言し、イスラム法によって統治し、ジハードに邁進する「イスラム国」は、イスラム教の論理で見れば「正しい」のだ──。気鋭のイスラム思想研究者が、コーランを典拠に西側の倫理とはかけ離れた「イスラム教の本当の姿」を描き出す。
-
-
-
4.0『君主論』は“西洋の『孫子の兵法』”とも呼ばれ、リーダーのための教科書として知られています。 中世イタリアの官僚ニッコロ・マキャベリが、自らの経験を基に「成功する組織の作り方」「統治の技術」「人間の本質」などについて著しています。 ※『君主論』とは? ……権謀術数の書として物議を醸し、現代では帝王学として切り貼りされがち。 しかし、それが政庁への再雇用を求めて権力者に献呈された論文だったことはあまり知られていない。 ルネサンス期のフィレンツェで書かれた、乱世を生き抜く政治哲学。 本書は、その『君主論』を現代のビジネスマンが読んでも分り易いように“ビジネス語訳”し再構成、理解の助けとなる事例を加えています。 リーダーシップは先天的な素質ではなく、訓練して身に付けるもの。「人を思いのままに動かす方法」を会得できるヒントにもなります。 「厳しい世の中をサバイブする知恵がここにある」「慎重であるより、果断であれ」というメッセージを打ち出します。
-
-
-
3.4『呪怨』の清水崇監督が映画化! あなたは日本最恐の心霊スポット〝犬鳴村〟を知っていますか? 「この村の名は検索しないほうがいいよ」 「“午前二時に鳴る公衆電話”」 「トンネルを抜けた先に村があって、そこで××を見た……」 「もう会えない」 「わんこがねぇやにふたしちゃろ~♪」 午前二時、YouTuberがトンネルに入ったことから始まった不可解な事件。 全ての謎は[犬鳴トンネル]にあり。 常に恐怖体験で名が上がるほどの最凶スポットでもある「犬鳴村」。 福岡県の「旧犬鳴トンネル」の先に位置するとされ、 「近くの小屋には骸が山積みにされている」 「全ての携帯電話が圏外になる」など、 日本地図から存在が抹消された村である。 単なる都市伝説なのか、すべて真実なのか…!? 決して触れてはいけない〝犬鳴村〟が、ホラー映画の第一人者・清水崇によって禁断の映画化! 身も凍る恐怖と戦慄、古より続く血の祝祭からあなたは逃げられない。 本書は、監督の清水崇・脚本家の保坂大輔と共に、恐怖実話の第一人者で九州在住の久田樹生によって書かれた、もう一つの『犬鳴村』である。 ★巻末には、清水崇[監督・脚本]×保坂大輔[脚本]×紀伊宗之[プロデューサー]による特別鼎談も収録 映画『犬鳴村』2020年2月7日(金)公開 主演:三吉彩花 監督:清水 崇 脚本:保坂大輔 清水 崇 音楽:海田庄吾 滝澤俊輔 主題歌:Ms.OOJA「HIKARI」(UNIVERSAL SIGMA) 制作プロダクション:ブースタープロジェクト 配給:東映 (C)2020 「犬鳴村」製作委員会 〈あらすじ〉 日本には、行ってはならない場所がある―― 臨床心理士の森田奏の周りで突如、奇妙な出来事が起こり始める。 「わんこごねぇやに ふたしちゃろ~♪」 奇妙のわらべ歌を口ずさみ、おかしくなった女性、行方不明になった兄弟、そして繰り返される変死……。 それらの共通点は心霊スポット【犬鳴トンネル】だった。 「トンネルを抜けた先に村があって、そこで××を見た……」 突然死した女性が死の直前に残したこの言葉は、一体どんな意味なのか? 全ての謎を突き止めるために、奏は犬鳴トンネルに向かう。 しかしその先には、決っして踏み込んではいけない、驚愕の真相があった……! ◆犬鳴村とは? 九州に実在する最恐の心霊スポット・犬鳴トンネル。 その近くには日本政府の統治が及ばない集落“犬鳴村”があり、そこに立ち入った者は決して戻れない、という都市伝説がある。 村の入口には「この先、日本国憲法は通用せず」と書かれた看板が立てられており、犬鳴トンネル、及び周辺では、過去に事件が起きているという。またネット掲示板やSNSには村周辺を訪れた人たちの恐怖体験が今も数多く寄せられている。 犬鳴村は、犬鳴トンネルの先にあると言われているが、現在はダムが建設され、日本地図にその痕跡は残っていない。 これは単なる都市伝説なのか、現実なのか?"" 著者について 作家。 徹底した取材に基づくルポルタージュ系怪談を得意とするガチ怖の申し子。代表作に『「超」怖い話 怪怨』、『「超」怖い話ベストセレクション 怪業』、『怪談実話 刀剣奇譚』(竹書房文庫)など。
-
3.8権力はあらゆる関係に遍在し、私たちの生を規定する。そうした権力が織りなす現実を耐えがたいと感じたとき、状況を批判的に捉え、いまとは違った社会を、自分を、実現する道はどこにあるのか。 私たちはなぜこのような状況に置かれているのか? 何に我慢がならないのか? こんなふうに統治されないためにはどうすればよいのか? [本書のおもな内容] ●権力は誘惑し、行為を促す ●学校・会社・病院は、人を「最適化」する装置である ●完全競争実現のため、新自由主義は社会に介入する ●私たち「ひとり企業家」の能力(スペック)向上の努力に終わりはない ●政治とは、自他の統治が入り乱れる「ゲーム」である ●主体には、つねに別の振る舞いをする力が備わっている ●批判とは、「このようには統治されない技術」である ●哲学的に生きるとは、社会を批判的に捉え、真実を言い、自分自身を変えること ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100ページで教養をイッキ読み! 現代新書の新シリーズ「現代新書100(ハンドレッド)」刊行開始!! 1:それは、どんな思想なのか(概論) 2:なぜ、その思想が生まれたのか(時代背景) 3:なぜ、その思想が今こそ読まれるべきなのか(現在への応用) テーマを上記の3点に絞り、本文100ページ+αでコンパクトにまとめた、 「一気に読める教養新書」です! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 イギリス法制史学の創始者のケンブリッジ大学での講義。今なお憲法史・現行制度理解のための最高の入門書である。 【目次より】 凡例 序 分析 第一期 エドワード一世死亡当時のイングランド公法 A イングランド法の一般的特質と立法の概観 B 土地制度 C 王国の区画と地方統治 D 中央統治 E 司法 F 封建制の回顧 第二期 ヘンリー七世死亡当時の公法 A 議会 I その構成 II 議会の頻度と存続期間 III 議会の仕事 B 国王と国王評議会 C 司法 D イングランド法の一般的特質 第三期 ジェイムズ一世死亡当時の公法の素描 A 議会 1 議会の構成 2 議会の特権 3 議会の裁判権 4 金銭を譲与する庶民院の機能 5 争いのある選挙を決定する権利 6 議会手続 7 議会の頻度と存続期間 B 国王の議会に対する関係 C 軍隊の歴史 第四期 ウィリアム三世死亡当時の公法の素描 A 王位の制度 B 議会の構成 C 議会の頻度と存続期間 D 主権の問題 E 立法 F 課税と財政に対する統制 G 司法 H 議会の特権 I 軍事 第五期 現在(一八八七ー八年)における公法の素描 緒言 A 主権機関 I 王位 II 貴族院 III 庶民院 IV 議会の頻度と存続期間 V 議会の特権 VI 議会の仕事 B 「国王」と「政府」 C 国王権能の分類 D 財政制度 E 軍制 F 司法 G 警察制度 H 社会問題と地方統治 〔I は欠如〕 J 教会 K 憲法の定義 付録 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 メイトランド,F・W 1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。 著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。
-
4.0天皇はなぜ「武士の時代」といわれる中世を生き延びたのか――その答えは「院政」にある、と著者・岡野氏はいう。「院政」とはたんに、皇位をしりぞいたのちも前天皇が影響力を保ちつづけたといった単純な政治的事件ではない。それは律令体制が完全に崩壊した中世にあって、国家財政を支えた唯一の経済基盤である「荘園」を、「家産」として「領有」した天皇家の家長「治天の君(ちてんのきみ)」が、日本最大の実力者として国政を牛耳った統治システムだった。本書は、摂関家・将軍家・寺社勢力とも対抗し、「権門勢家」のひとつとしてたくましく時代を生き延びた中世皇室の姿を、実証的かつ論争的に明らかにした、著者渾身の力作。中世政治史、経済史、そして皇室史に興味のある読者にとって、本書は間違いなく「目から鱗」の斬新な視点を与えてくれる好著である。
-
4.0
-
-ヨーロッパ全体に匹敵する、広大な大地、ばく大な人口、多様な文化や言語を有するインド亜大陸。20世紀以前、この亜大陸には英領インドと別に、500を超す半独立状態の藩王国があった。 それらの国を統治するのは「マハラジャ」や「ナワーブ」と呼ばれた絶対君主(王)たち。泥酔の挙句、舞姫と領土半分の賭けに興ずる「王」。イギリス渡航にあたって六か月分のガンジス河の水を携行する「王」。領土にダイヤモンドの産地をもち、あふれんばかりの富で知られた「王」。 イギリス植民の進む近代インドにあって、昔ながらの生活に固執する王族、イギリス紳士とマハラジャの交流、近代化、世界大戦など、時代はうねりを見せながら、やがてガンジー、ネルーらの登場を迎える。 1947年のインド・パキスタン分離独立にいたる以前の、インド各地にあった国々や王たち(Princes of India)の様子を生き生きと描いた『印度藩王国』。1934年に出版され、長らく衆目にふれることのなかった希少本が、現代仮名遣いで読みやすくなって登場です。 【印度藩王国】目次 序 第一章 インド人のインド 第二章 諸藩王国とインドにおける英国勢力の発展 第三章 諸藩王国における生活 第四章 諸藩王国における政治 第五章 ラージプタナ地方、中部インドおよびカティアワール地方におけるラージプート族の藩王国 第六章 カシミール地方―ヒマラヤ山脈地帯のラージプート族藩王国およびシーク教徒の藩王国について 第七章 マイソールおよびトラヴァンコール藩王国 第八章 マラータ族の藩王国 第九章 ハイデラバード藩王国 第十章 回教徒藩王国 第十一章 ネパール王国 第十二章 従属同盟政策 第十三章 インド王侯と政治部 第十四章 インド藩王侯とインド連邦 第十五章 インドの将来 「付」 インド藩王国について
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ESGとは「Environment」(環境)、「Social」(社会)、「Governance」(企業統治)のことです。これら3つの軸で企業を評価し投資することを「ESG投資」と呼び、日本では2017年に年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がESG投資を開始したことで、主に投資家の注目を集めてきました。言い換えれば、ESGに取り組むことがこれからの企業には求められるのです。ESGと近い文脈で語られるSDGsが国や社会全体が目指す目標であるのに対し、ESGは企業が行う具体的な手段といえます。株主の利益だけを追求するのではなく、社会や環境の利益となるような事業を行うことで、企業の価値が上がり、結果としてSDGsの達成にもつながる取り組みがESGです。昨今はSDGsの浸透に後押しされるような形でESGに取り組む企業も増えており、ESGに取り組むことが「投資家」「就活生」「顧客」などから企業が選ばれる条件、言い換えれば企業が持続する条件といっても過言ではない状況になりつつあります。本書は、ESGによってステークホルダーから「選ばれるビジネス」を行うための入門&実践書です。具体的な事例を紹介しながら、本書オリジナルのフレームワークで読者自らESGの推進度を自己評価できる仕組みになっています。ESGってなに?という人から、実際どうとりくめばいいの?という人まで、多くの場面で本当に役に立つESGのバイブルです。
-
4.4もう「E<環境>S<社会>G<企業統治>」を知らずに仕事はできません! ワシントンポスト、CNN、エコノミストほか世界注目の第一人者による、 不況期こそ重要なESG入門決定版。 世界の巨大投資家が気づいている史上最大の破綻リスクとは何か? 世界の勝ち組企業がやっていて日本企業がやっていない唯一のことは何か? そして、新型コロナ不況をサバイブするESG思考とは? 2019年9月に開催された国連行動サミットでは、グレタ・トゥンベリの演説が注目を浴びた。欧米での積極的な反応にくらべ、日本国内では批判的な論調が強かった。しかし日本人に見えていない現実がある。世界の投資マネーはESG(環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance))に向かって怒濤の勢いで流れているのだ。その額はおよそ3000兆円! 製造業やIT系グローバル企業もぞくぞくとCO2削減目標を行動方針に掲げていることからわかるように、もはやESGとサステナビリティは世界の勝ち組企業の常識。これに対し、日本の取り組みは遅れが際立っている。 日本人が今ひとつ理解できていないESGの教科書として、ビジネスパーソン必携!
-
5.0ESGによる企業の選別が始まる! 世界の新しい潮流を第一人者が解説。 ◆日本でも本格化するESG 2017年初の日経ヴェリタスの巻頭は「ESG投資の号砲」でした。投資家の間でE(環境)、S(社会)、G(企業統治)を通じて社会的存在としての企業の価値を探り投資先を選別する動きが強まり、収益一辺倒の企業はやがて市場からの退場を求められることになるという新しい時代の始まりを、投資家、企業、それぞれの動きから探ったものでした。 ESG(投資)は、既に欧米の資産運用会社や機関投資家の間では「洗練された株主価値」として投資における重要な指標となっています。日本でも2015年9月、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が責任投資原則(PRI)に署名、2017年には、多くの機関投資家も重視する指標としてあげ、一方の上場企業でも、ESGを専門にする部署の設置が急増。まさに「ESG元年」を迎えました。 ◆第一人者が全貌を解説するはじめての一冊 ESG投資は、コーポレートガバナンス改革の柱でもあるエンゲージメントを通して、世界の持続的・安定的な成長に寄与できるかで企業を選別、それによって将来の世界全体の繁栄を守るという新しい社会システム(資本主義)を生み出そうとするグローバルな動きで、単に「ESGを考慮して投資すれば儲かる」ということではありません。そういう企業に投資して支えることで、社会全体が豊かになっていき、その富が自分たちにも返ってくるという、格差や資源の問題を抱えた世界全体のことを長期的に考える、誰もが求めるきわめて合理的な行動という点で、支持が急速に広がっているのです。 本書は、欧州など海外での研究も重ねてきた第一人者が、これまで断片的にしか伝えられてこなかったESGをめぐる様々な動きを整理、上場企業、機関投資家双方に必須の知識を提供するものです。
-
3.0現在最も注目されている「ESG投資」をわかりやすく解説! 少子高齢化への歯止めが効かず、年金の減額が進む現代日本。この流れはこの先も改善される見通しはなく、老後の備えに関する不安は私たちに常につきまとう大きな問題です。公による年金だけに頼ることができない今、私たちはこれまで以上に自助努力、自ら資産を管理し、殖やしていくことが必要になってきています。 では、老後のために安定し、かつ「持続可能」な投資とは何でしょうか。現在世界的に最も注目されているのは、ESG投資です。 ESGとは、環境:Environment、社会:Society、企業統治:Governanceの略語で、ESGの観点で企業を分析し、優れた経営を行っている企業に投資する手法をESG投資と呼びます。持続可能な社会を創っていく上でSDGsとともに注目され、世界最大の年金基金であるGPIFがESG投資を開始したことも大きな話題となりました。 本書では、そもそもESGとは何か、注目される理由などを見た上で、ESG投資を行う方法、見るべき指標など運用の実践を解説しています。 持続可能性の高い取り組みをしている企業への投資だからこそ、長期的な運用に適しているESG投資。老後の資産管理を考える上で一読いただきたい一冊です。
-
4.0責任投資のパイオニアが実践 経済と環境・社会をつなぎ、持続可能な世界に導く戦略 欧州No.1の資産運用会社が、ESG投資の豊富な蓄積に基づいて解説 地球温暖化対策でカーボンニュートラルを目指す潮流、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)達成などのため、ESG(環境・社会・企業統治)に対する関心が高まっています。 機関投資家の間ではESGに配慮して投資先を選定することが当たり前となっており、投資を呼び込みたい事業会社にとっても経営で不可欠な要素です。 本書は、「E」「S」「G」それぞれが表すもの、ESGの歴史といった基本から、投資での実践、企業経営での取り組みまで深掘りして解説。 ESG投資で利益があがるのか、という重要な点についても、株式、債券、それぞれのデータに基づいて分析しています。
-
-世界的潮流が日本に与えるインパクトを 最前線からリポート! ◆ESGを巡る世界的潮流 ESG(環境・社会・企業統治)はビジネスの世界でも1丁目1番地。いまや機関投資家の間ではESGを考慮して投資先を選定することが主流となっており、投資を呼び込みたい企業にとっても経営戦略上不可欠な要素になっています。その背景には、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)の達成や、気候変動対策でカーボンニュートラル(脱炭素)を目指す潮流などがあります。 ◆日経新聞記者による多面的な報道を1冊に 上場企業、機関投資家などあらゆる層が対応を迫られる一方、現時点ではESGのプレーヤーはまだまだ有象無象で、日進月歩で市場が形成されているところ。 本書は、ESGを意識した企業経営や国際基準を巡る攻防、ESG関連の金融商品など、金融の最前線で多面的な取材してきた記者たちが現場のリアルな状況を伝える1冊です。
-
4.1メディアには日々、「ESG(環境・社会・企業統治)」があふれています。この言葉を抜きには企業経営や財務戦略、株式投資は語れなくなっていますが、成り立ちや意味するところがきちんと理解されているとは言えません。単なる欧米の流行言葉ではなく、世界的なビジネスの常識となっているESGをきちんと理解しなくては後悔することになります。ESGによって企業の情報開示や経営戦略、投資家の顔ぶれなど、資本市場のエコシステム(生態系)ががらりと変わることになるのです。またバイデン次期米大統領は環境問題を重視するスタンスを示していますので、ESG重視のトレンドは加速するばかりです。 本書は、 (1)ESGの盛り上がりに「乗り遅れた」と思っている人向けの基礎的かつ包括的な解説 (2)「ESG=市場のエコシステムの変革」の切り口を提示。解説本を超えた未来予測も行う 既刊書では(2)017年刊行の『ESG投資』(日経出版刊)が信頼できる本としてロングセラーになっていますが、この数年でESGをめぐる環境は激変しています。このテーマはどうしても環境に偏った記述が多くなりがちですが、本書は投資家、ビジネスパーソン目線で、最新事情を踏まえて、バランス良くそのインパクトを解説します。
-
-Environment(環境)、Social(社会)、Governance(統治)の観点から評価する「ESG不動産投資」。 収益性、融資、資産価値などでメリットのあるESG不動産投資について解説した初の書籍! ------------------------------------------ 長期的に資産価値を保つために、不動産にもESGによる評価が導入され出しています。 すでに株式投資においては、PL(損益計算書)やBS(貸借対照表)といった財務情報だけでなく、 企業経営におけるサステナビリティ(持続可能性)に着目する機運が高まり、気候変動などを踏まえた 長期的なリスクマネジメントや新たな収益機会創出へのチャレンジを評価するため E(環境)・S(社会)・G(統治)に着目した「ESG投資」が当たり前となっています。 E(環境)では、二酸化炭素の排出量や廃棄物をどう削減するか、大気や水の汚染対策をどうするか、 原材料やエネルギーなど資源の利用方法、生物多様性への配慮などがあげられます。 S(社会)はかなり広い概念であり、地域コミュニティからグローバルまでさまざまなテーマがあります。 最近では、コロナ感染症対策や「人的資本経営」などが当てはまります。 G(統治)は、直接的には企業経営におけるコンプライアンス(法令遵守)や情報公開のことです。 「ESG不動産投資」とは、こうした「ESG投資」の考え方を不動産投資の分野に適用したものです。 不動産投資においてもこれまでは、インカムゲインやキャピタルゲインというリターンを いかに最大化するかが重要視されてきました。 しかし、近年は20年後、30年後も安定して収益を上げ、市場価値が維持される物件をどのように選べば よいのかについて考えたときに、E(環境)・S(社会)・G(統治)の視点が重要になると考えられているのです。 こうした動きはすでに金融機関で、融資の際の重要な評価ポイントの一つになりつつあります。 不動産投資におけるE(環境)では、建物の省エネ性がまず挙げられます。省エネ性の高い建物は 二酸化炭素の排出を抑えるだけでなく、居住環境、執務環境としても優れています。 不動産投資におけるS(社会)では、地域コミュニティとの関わりが重要です。 例えば地域の景観への配慮や地域の伝統文化との関わりが考えられます。 不動産投資におけるG(統治)では、法令遵守は当然のこととして、顧客をはじめ関係者への説明責任が問われます。 こうした取り組みを意識することで不確実性の高まるこれからの時代において、 不動産投資で長期的に安定したリターンを確保できるのです。 著者は京都を中心に、ワンルームマンションなどの投資用不動産を開発しているデベロッパーです。 京都エリアではワンルームマンションの供給数トップを長年維持しています。 京都は1000年以上の歴史を持つ日本の古都であり歴史の宝庫です。 また、日本一厳しい景観保護のための建築規制があります。さらに、世界全体で取り組みが進む 気候変動対策の原点となったCOP3京都議定書が締結された環境都市でもあります。 こうした京都で活動する不動産企業として、著者はいちはやくESG不動産投資の意義と可能性に着目してきました。 具体的な物件開発にESGの視点を取り入れるとともに、個人投資家、仲介不動産会社など 関係者にESG不動産投資の重要性を伝えています。 本書はESG不動産投資の入門書となっており、ESG不動産投資とは何かから始まり、 他の不動産投資に比べてどのようなメリット・デメリットがあるのかを解説しています。 ESG不動産投資の重要性と可能性について理解を深め、長期的に安定した資産形成を実現したい人は必読の一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 超低コストで、世界に分散投資して稼ぐ! ・巻頭対談に松島花さん(モデル)が登場! 「長期の資産形成はETFではじめよう」 ・全251銘柄の主要データを一挙掲載! ・プロ6人が選ぶ注目銘柄 ・成果を出している人に学べ! 「私の投資術」 ・ロボット、ESG――話題のETFが登場! ・マーケットメイク制度、ロボアドバイザーなど最新トピックを解説 ・市場や経済の“ものさし” 指数を完全解説 いざ投資を始めよう、と思っても、どの金融商品を買えばいいのか、迷ってしまうのではないでしょうか? そんなときに有力なのが、ETF(上場投資信託)です。 ETFとは、日経平均株価、TOPIX(東証株価指数)、ニューヨークダウなど様々な指数と連動する投資信託の一種です。「日経平均を買える」というわかりやすさがあり、最低投資金額も全銘柄の70%超が2万円以下。初心者にも向いています。 投資で重要なのは、投資先を分散してリスクを減らすこと。ETFは、日本株、海外株、日本債券、海外債券、金・原油などの商品といった様々な対象に投資する銘柄がそろっており、少額から、手軽に分散投資が可能です。 ESG(環境、社会、企業統治を重視する経営)関連指数やロボット関連指数などに連動するユニークなETFも登場しています。 本書では、こうしたETFの基本や投資する際の注意点、資産運用に活かす方法などを丁寧に解説。また、プロによる注目銘柄や、全銘柄の主要データも掲載し、銘柄選びに役立つ実践的な内容です。
-
-フランスが誇るダークファンタジーの帝王オリヴィエ・ルドロワ見参! 目眩く人工楽園で繰り広げられる真夏の夜の“悪”夢。機械仕掛けの暗黒妖精譚。妖精物語×スチームパンク。三浦建太郎氏絶賛! 「さすがネイティブ・ファンタジー。勉強になります!」(三浦建太郎『ベルセルク』) 遠い昔、人間たちの世界から遥か遠く離れた妖精王国。美しき妖精女王タイタニアは、妖精王国を統べるオーディンの息子オベロンに憎まれ、夫である公爵クレイモア・グリムとともに命を狙われる。2人の間にはウィカという名の娘がいた。彼女もまた狼女ロウェナに襲われるが、忠臣ハギスの働きで、一命を取りとめ、強力な妖精の力を封印したまま、ある農夫に育てられることになる。やがて、妖精王国は、オベロンの統治のもと、狂気と闇の時代に突入することになる。13年後、成長したウィカが、王都アヴァロンに辿りつく。その地で、彼女は自らの生い立ちを知り、運命に翻弄されるまま、オベロンの軍勢と立ち向かうことになる――。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 アメリカ合衆国大統領ウッドロウ・ウィルソン(1913-1921)に淵源する世界平和の実現のための外交方針。1918年1月には、「十四か条の平和原則」を発表された。侵略戦争を終わらせるための機関として、「国際連盟」を提唱した。 ウィルソン外交の最たる特徴は、「自由主義的・民主主義的・国際主義」を標榜し、国内外の政治体制の変革を追求することがアメリカの使命であると見なすことであり、今日では一般に「ウィルソン主義」と呼ばれている。本書は、日米英の外交史料を駆使して、20世紀アメリカ外交に理念的裏づけを与えたウッドロー・ウィルソン政権による対日政策を、アメリカの東アジア政策史の系譜に位置づけながら、4つの重要問題の再検証を通じて、その特質と実態を明らかにしたものである。ウィルソンの対日外交の分析を通じて、現代アメリカ外交の理念的原点である「ウィルソン主義」の可能性と限界を描き出す。 【目次】 目次 序論 研究動向と問題提起 「ウィルソン主義」をめぐる諸見解 第一節 先行研究の整理 第二節 本書の課題 第三節 アメリカの東アジア政策の伝統 第四節 二〇世紀初頭のアメリカの東アジア政策――ウィルソン政権期に至る歴史的背景 第一章 対華二一箇条要求への対応 第一節 対華二一箇条要求とアメリカ政府内政策方針の相違 第二節 ブライアンの対日宥和的方針 第三節 対日イメージの悪化とウィルソンの対日強硬方針 第二章 石井・ランシング協定への対応 第一節 前史 第二節 交渉の開始とその展開 第三節 石井・ランシング協定の成立 第三章 シベリア出兵への対応 第一節 日米共同出兵への道程 第二節 アメリカ政府の対日抗議と共同出兵の有名無実化 第三節 シベリア撤兵をめぐる諸問題 第四章 パリ講和会議をめぐる日米関係――ウィルソン構想の展開と挫折 第一節 アメリカによる戦後東アジア・太平洋秩序構想 第二節 ウィルソン整形と山東問題 第三節 ウィルソン政権と旧ドイツ領南洋諸島委任統治問題 第四節 ウィルソン政権と人種差別撤廃問題 結論 ウィルソンの対日政策――アメリカの東アジアの政策の中で 第一節 ウィルソン政権の対日政策に見られる振幅の実体 第二節 ウィルソン政権内部における政策潮流 第三節 対外政策における三つの基本要素との関係 第四節 ウィルソンの対日政策に見られる特質 第五節 ウィルソン外交の現代的意義とその東アジアへの適用に見られる限界 あとがき 注 参考文献 人名・事項索引 高原 秀介 1968年生まれ。政治学者。京都産業大学教授。関西学院大学文学部卒業、神戸大学大学院法学研究科博士前期課程修了。神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(政治学)。 著書に、『ウィルソン外交と日本 理想と現実の間 1913-1921』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-1853年、浦賀に黒船が来寇した。しかし、それはペリーの艦隊ではなく仏艦隊だった。日本列島はいつの間にか英が位置するはずの北大西洋に転移していた!仏の統治下におかれてから約80年後の1939年、欧州大戦が勃発!日本を待ち受ける運命とは!?
-
-政治に〈嘘〉がつきものなのはなぜか。絶対の権力というものがあるとすれば、嘘はいらない。それなりの反対勢力野党や異議申し立てがあるからこそ、それを迂回するために嘘が必要となり、反対する野党や異議申し立ての側も、権力と闘うために嘘を武器にするのだ。もちろん嘘には害があり、特に危険な嘘もある。世界中に嘘が横行する今、近現代の日本の経験は、嘘を減らし、嘘を生き延びるための教訓への対応策と対抗策の格好の素材となるはずだ。複数政党政治が成立するための条件と地域社会のあるべき未来像も、そこから見えてくる。 目次 はじめに Ⅰ 〈嘘〉の起源――生真面目な社会 歴史をとらえる 第1章 職分から政党への五〇〇年 Ⅱ レトリックの効用――〈嘘〉の明治史 横着な〈嘘〉への対処法 第2章 福地櫻痴の挑戦 第3章 循環の観念 第4章 五/七/五で嘘を切る Ⅲ 野党 存続の条件 政党の〈嘘〉の功罪 第5章 複数政党政治を支える嘘 Ⅳ 地方統治の作法 〈嘘〉のある号令と、呼応する人々 第6章 人類を鼓舞してきたもの 第7章 受益と負担の均衡を求めて――近現代日本の地域社会 補章 昆虫化日本 越冬始末
-
4.0自称《天才》な高校生・郡武人。巨大学園を統治する《生徒会》入りを目論む彼は、転校初日に《会長》を名乗る少女・天音ミコから「我が生徒会に入らないか?」と誘われる。だが、彼女は本物の生徒会と対立する《裏生徒会》の会長だった!! ミコの想いに突き動かされた武人は、圧倒的な力を持つ生徒会の敵となり、熱いバトルを繰り広げることに!?
-
-銀河の片隅に忘れ去られていたノンディル星系。だが、ここでも人類はたくましく生きていた…。万能自動宇宙服マルチ・ムーバーのダイザッパーを愛用するバン・リディム。彼は怪我で入院した父親に代わり、高速貨物宇宙船シェラIIIを駆ってノンディル星系を飛び回っていた。そこに突然現われた純白の巨大宇宙船エターナル・ハリハクスとそれを追う漆黒の宇宙戦艦ワルキューレ。これこそは銀河系中央政府を1000年に渡って統治してきたルルマ家を揺るがさんとする陰謀の一端だった!! スペース・オペラ・コメディ第1弾。ぶらじま太郎による解説を収録。 ●とまとあき 音楽その他もろもろディレクター。エネルギー源/ヱビスビール。 ●塚本裕美子(つかもと・ゆみこ) 蟹座。B型。趣味/千羽鶴に乗馬。好物/おいしいもの。
-
4.2▼第1話/入隊▼第2話/訓練開始[-3週]▼第3話/ネスト[-2週]▼第4話/移植[0週]▼第5話/拒絶反応[3週]▼第6話/座標空間[3週]▼第7話/犬の日[6週]▼第8話/出撃[8週] ●主な登場人物/マナ・オーガ(徴兵され特別転送隊に配属された新兵。故郷に家族と恋人を残してきた) ●あらすじ/歪な月に照らされる惑星・碧王星。漂流の末たどり着き土地を開拓してきたファースト(第一次移民)と、後からやってきて正規移民を名乗るセカンド(第二次移民)との間で激しい戦争が続いていた。ファーストの一国・ハストに暮らすマナ・オーガは、徴兵され特別転送隊に配属される。いまだその実態がつかめぬ“転送兵”として、過酷な軍隊生活が幕を開けた(第1話)。 ●本巻の特徴/碧王星の統治権を巡り、戦争を続けるファーストとセカンド。卑劣な攻撃を繰り返すセカンドに対し、ファーストたちは大いなる森の主“ニーバス”の体組織を子宮に入れた女性の“転送兵”が活躍する。碧王星の至る所に瞬間移動が出来る“転送隊”に入隊したマナ・オーガの運命は…!? 圧倒的な画力で見るものを引き込む、白井弓子渾身のSFストーリー!! ●その他の登場人物/アルメア軍曹(特別転送隊の特技一等軍曹。現役の転送兵であり、新兵の指導教官も務める)、サウラ中佐(マナとアルメア軍曹が所属している第一特別転送隊の隊長)、ニコルズ軍医(転送隊員の検査や“転送器官”の移植などを担当する)
-
-■毎夜見る夢と同じだわ――端整な顔だちも、飢えたような瞳も。■ローレルは夢を見ていた。毎夜繰り返される黒い馬に乗った男の夢。「あなたは誰なの? なぜここに来たの?」彼女の問いかけに、鎧で身を固めた馬上の男が振り返る。「すべてを手に入れるためだ。おまえのすべてを」やめて!目が覚めたあともローレルの動揺はおさまらなかった。あのすみれ色の暗い瞳は、忘れたくても忘れられない。彼女の祖父が統治するエデンの谷は、近隣の賊たちに狙われている。あの夢の男は、賊の一人なのだろうか?やがてその男の正体が明らかになった。キアラン・サザーランド――この地を守るために雇われた傭兵、そしてローレルの夫となるはずの人物だった。夢が現実となると知って、ローレルは愕然とした。そうよ、彼はエデンの谷を乗っ取ろうとしているんだわ!■十四世紀のスコットランドを舞台にした愛と冒険の一大叙事詩〈サザーランドの獅子〉も、いよいよ最終話! 今月はライオンの忘れ形見キアランが放浪の末、本当の自分の居場所を見つけます。
-
3.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 まず近世土地法の生成の歴史を叙述、ついで土地に関する法律用語の意義を明らかにし、合わせて難解な江戸時代土地法を解明。 【目次より】 序文 目次 第一 地租改正と土地所有権の近代化 第二七回東洋学者会議における報告 第二 江戸時代土地法の体系 第三 江戸時代土地法の生成 第四 統轄、領知、所持、進退および支配 江戸時代土地法の基礎構造 一 統轄(将軍による大名の統轄) 二 大名の領知 三 (庶民による)土地の所持 総説 A 田畑永代売の禁令 B 江戸時代における用水路の所有権 C 江戸の町屋敷 (i) 江戸の町屋敷 (ii) 江戸の町屋敷の売買 四 進退と入会権 A 江戸時代の入会権と地租改正 (i) 江戸時代の入会権 (ii) 地租改正 B 「江戸時代の入会権と地租改正」続考 C 安政五午年三月山田村秣場一件留 江戸時代入会権の性質をよく示す史料 D 山梨県山中部落の入会権 第一章 法制史的研究 五 江戸時代における土地の「支配」 物権の行使として 初出一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 石井 良助 1907-1993年。東京帝国大学法学部法律学科卒業。東京大学教授を務めたのち、東京大学名誉教授。専門は日本法制史。 著書に、『中世武家不動産訴訟法の研究』『日本法制史概説』『日本不動産占有論』『天皇 天皇統治の史的解明』『日本史概説』『大化改新と鎌倉幕府の成立』『江戸の刑罰』『江戸の離婚 三行り半と縁切寺』『吉原 江戸の遊廓の実態』『江戸町方の制度』『略説日本国家史』『日本婚姻法史』『日本団体法史』『近世関東の被差別部落』『民法典の編纂』『日本相続法史』『近世取引法史』『天皇』『近世民事訴訟法史 正続』『日本刑事法史』など多数ある。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 北米における<会社の仕組み><経済の仕組み>の解説から、<財務諸表と会社責任・企業統治><貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書>そして<財務諸表分析>までの会計、財務の知識と英語を、実際にカナダで企業に在籍し、実務に携わる著者がわかりやすく解説する本書。MBA取得を視野に入れた人も、ビジネスでこうした知識が必要な人も、まさに必携の1冊です。
-
5.0「ユマニストの王者」として君臨したエラスムス。ヘンリー八世の統治下で大逆罪に問われて刑死したトマス・モア。その固い友情が、のちに伝説化されるまでになった二人の往復書簡全五〇通に、一六世紀ヨーロッパにおける知識人たちの知的活動、政局、文化交流の様子を読む。宗教改革の舞台裏を赤裸に語る資料としても貴重。
-
3.4
-
3.6
-
3.8【内容紹介】 緊迫するウクライナ情勢と今後の世界の行く末を考えるヒントが満載! 2時間でわかる! 世界の政治・経済・産業動向の決定版。 世界を震撼させている、ロシアによるウクライナ侵攻。 国際世論の大半を敵に回したり、厳しい経済制裁を受けているにもかかわらず、なぜプーチン大統領は、ウクライナ攻撃の手を緩めないのか。 今年の『大前研一 世界の潮流2022-23』は、ロシアウォッチング歴50年を誇る大前研一氏が、日本のメディアが報じないウクライナ危機の真相を約50ページにわたって徹底分析するスペシャルエディションです。 ◎累計10万部超『世界の潮流』シリーズ最新作 ◎2022~23年の世界情勢を分析した渾身作 ◎40点もの図版を使ってわかりやすく解説 ◎現代を俯瞰できる用語解説付き ◎就職・転職にも役立つ 「マッキンゼー伝説のコンサルタント」として名を馳せた大前研一氏の1日は、毎朝4時に始まります。膨大な世界のニュースを収集し、分析し、アウトプットとして残します。 大前氏の緻密に分析された情報は、雑誌や書籍、WEB等で発信されていますが、これらのエッセンスが詰まったのが、本書です。 今年、主に論じるテーマは以下の通りです。 ロシア→日本のメディアが報じないウクライナ侵攻の背景と行く末 中国→台湾への武力侵攻の可能性は低く、香港方式での実質統治戦略にシフト アメリカ→根深いトランプ前大統領の後遺症 EU→「イギリスなきEU、メルケルなきEU」新時代に突入 日本→コロナが浮き彫りにした“没落国家日本” 【著者紹介】 [著]大前 研一 Kenichi Ohmae 早稲田大学卒業後、東京工業大学で修士号を、マサチューセッツ工科大学(MIT)で博士号 を取得。日立製作所、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、現在、(株)ビジネス・ブレークスルー代表取締役会長、ビジネス・ブレークスルー大学学長。著書に、『「0から1」の発想術』『低欲望社会「大志なき時代」の新・国富論』『「国家の衰退」からいかに脱するか』(共に小学館)、『大前研一 稼ぐ力をつける「リカレント教育」』、「日本の論点」シリーズ(小社刊)など多数ある。 「ボーダレス経済学と地域国家論」提唱者。マッキンゼー時代にはウォール・ストリート・ジャーナル紙のコントリビューティング・エディターとして、また、ハーバード・ビジネス・レビュー誌では経済のボーダレス化に伴う企業の国際化の問題、都市の発展を中心として広がっていく新しい地域国家の概念などについて継続的に論文を発表していた。この功績により1987年にイタリア大統領よりピオマンズ賞を、1995年にはアメリカのノートルダム大学で名誉法学博士号を授与された。英国エコノミスト誌は、現代世界の思想的リーダーとしてアメリカにはピーター・ドラッカー(故人)やトム・ピーターズが、アジアには大前研一がいるが、ヨーロッパ大陸にはそれに匹敵するグールー(思想的指導者)がいない、と書いた。同誌の1993年グールー特集では世界のグールー17人の1人に、また1994年の特集では5人の中の1人として選ばれている。2005年の「Thi nkers50」でも、アジア人として唯一、トップに名を連ねている。 2005年、『The Next Global Stage』がWharton School Publishingから出版される。発売当初から評判を呼び、すでに13カ国以上の国で翻訳され、ベストセラーとなっている。経営コンサルタントとしても各国で活躍しながら、日本の疲弊した政治システムの改革と真の生活者主権国家実現のために、新しい提案・コンセプトを提供し続けている。経営や経済に関する多くの著書が世界各地で読まれている。 趣味はスキューバダイビング、スキー、オフロードバイク、スノーモービル、クラリネット。ジャネット夫人との間に二男。 【目次抜粋】 まえがき 序章 ウクライナ情勢が物語る、これからの時代の読み解き方 第1章 新型コロナウイルスからの回復と成長を模索する世界 第2章 コロナ化が加速させるビジネスの新潮流 第3章 国民国家の終焉と新しい世界の視点 第4章 コロナが浮き彫りにした“没落国家日本” 第5章 2022年、日本はどうすればいいのか
-
3.6【内容紹介】 「アフターコロナ」「ウィズコロナ」……正解のない時代は、革新的なアイデアと企業ガバナンスでフロンティアを切り拓け! 大前研一、安藤忠雄、松尾豊をはじめ、豪華執筆陣たちが語る、0から1を生み出す方法! 【著者紹介】 [著]大前 研一 (Kenichi Ohmae) 早稲田大学卒業後、東京工業大学で修士号を、マサチューセッツ工科大学(MIT)で博士を取得。日立製作所、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、現在、(株)ビジネス・ブレークスルー代表取締役会長、ビジネス・ブレークスルー大学学長。著書に、『「0から1」の発想術』『低欲望社会「大志なき時代」の新・国富論』『「国家の衰退」からいかに脱するか』(共に小学館)、『大前研一 稼ぐ力をつける「リカレント教育」』、「日本の論点」シリーズ(小社刊)など多数ある。 「ボーダレス経済学と地域国家論」提唱者。マッキンゼー時代にはウォール・ストリート・ジャーナル紙のコントリビューティング・エディターとして、また、ハーバード・ビジネス・レビュー誌では経済のボーダレス化に伴う企業の国際化の問題、都市の発展を中心として広がっていく新しい地域国家の概念などについて継続的に論文を発表していた。この功績により1987年にイタリア大統領よりピオマンズ賞を、1995年にはアメリカのノートルダム大学で名誉法学博士号を授与された。 英国エコノミスト誌は、現代世界の思想的リーダーとしてアメリカにはピーター・ドラッカー(故人)やトム・ピーターズが、アジアには大前研一がいるが、ヨーロッパ大陸にはそれに匹敵するグールー(思想的指導者)がいない、と書いた。 同誌の1993年グールー特集では世界のグールー17人の1人に、また1994年の特集では5人の中の1人として選ばれている。2005年の「Thinkers50」でも、アジア人として唯一、トップに名を連ねている。 2005年、『The Next Global Stage』がWharton School Publishingから出版される。発売当初から評判をよび、すでに13カ国以上の国で翻訳され、ベストセラーとなっている。経営コンサルタントとしても各国で活躍しながら、日本の疲弊した政治システムの改革と真の生活者主権国家実現のために、新しい提案・コンセプトを提供し続けている。経営や経済に関する多くの著書が世界各地で読まれている。 趣味はスキューバダイビング、スキー、オフロードバイク、スノーモービル、クラリネット。 ジャネット夫人との間に二男。 【目次抜粋】 【パート1】企業統治編 第一章 21世紀に通用する企業のつくり方 大前研一 第二章 低迷を続ける日本企業の分析 斉藤 惇(日本野球機構 会長) 第三章 AIを活用した次世代経営 松尾 豊(東京大学大学院工学系研究科 教授) 第四章 花王のコーポレートガバナンスにおける絶えざる革新 杉山忠昭(花王株式会社 執行役員 法務・コンプライアンス部門統括)*講演当時 【パート2】構想力編 第一章 構想力 AI時代に活躍できる人の条件 大前研一 第二章 私の考える「構想力」 安藤忠雄(建築家) 第三章 衰退した熱海のリノベーションまちづくり 市来広一郎(machimori代表取締役)
-
4.2
-
4.5ベトナム戦争への出撃基地となったアメリカ統治下の沖縄。1960年代末の返還運動、ベトナム反戦闘争が激化する時代、夜の風俗街に生きた人々。沖縄地上戦の傷痕、米軍最優先社会、生死隣合わせの米兵たち……。それらの矛盾を一身に背負った女たち。その姿をヒリヒリと肌を刺すような筆致で描く。今に続く沖縄が抱える問題の原点を激しく問いかける歴史的名著。
-
5.0
-
-戦後75年――。 62の言葉が、この国の実像を照らし出す。 沖縄には言葉がある。もう少し正確に言えば、沖縄という地に関わった人たちの言葉は深く、重い。こんな場所は日本中どこをめぐってもないだろう。それは沖縄の歴史が人に考えることを促すからだ。 ――「はじめに」より 日本で唯一の地上戦が繰り広げられた沖縄。戦後末期から、終戦につづく米統治時代、さらに本土復帰を経て昭和、平成、そして令和の現代へ。沖縄をめぐって、どんな言葉が生まれたのだろうか? 62の言葉をとりあげ、その背景や意味をさぐって時代を読み解く。 ※こちらの作品は過去に他出版社より配信していた内容と同様となります。重複購入にはお気を付けください
-
-今日も座席が決まらない……! 「この桜吹雪をよもや見忘れたとは言わせねえ」「これにて一件落着」――。決め台詞でおなじみの「江戸のお裁き」の現場は、本当はどうなっていたのか? 100年以上にわたって書き継がれた“役人用マニュアル”を読み解き、近世社会に貫徹していた「秩序感」をリアルに描き出す。 江戸時代、訴えを持ち込んでくる人々に対し、奉行所が開廷初日、真っ先に取り組んだのは、3段ある座席に出廷人を割り振る作業であった。無限にある「格式」の上下を見極めようとする熱意の背後に、幕府が守ろうとしていた正義のあり方――統治の正当性――を見出す。「身分制度」への思い込みが覆される快作!
-
4.4
-
-「戦国の風雲児」と形容されるように、旧秩序の破壊者・改革者という印象が強い織田信長。しかし、その統治政策には、既存のシステムや先人の知恵も、うまく取り入れられているという。模倣者か? 変革者か? 統治者として信長の実像に迫る!
-
-900円 (税込)戦国から令和へと受け継がれる勇姿 AD 目次 【巻頭グラビア】数百年の時を超える12の天守受け継がれる勇姿よ、永遠に 日本の名城を訪ねて 【巻頭言】現存十二天守はなぜ残ったのか? 第一章守り継がれた名城現存十二天守 【巻頭特集】現存天守を巡る旅四国四城を訪ねて 高知城(高知県高知市) 本丸建築群が現存する南海道の名城 丸亀城(香川県丸亀市) 築城の名手が築いた日本一の高石垣 松山城(愛媛県松山市) 登城者を圧倒する巨大迷宮 宇和島城(愛媛県宇和島市) 伊達氏が仕上げた端正な海城 知っておきたい、城の豆知識 弘前城(青森県弘前市) 津軽家十二代の歴史を物語る名城 松本城(長野県松本市) 実戦を見据えた質実剛健なつくり 犬山城(愛知県犬山市) 木曽川のほとりで美濃をにらむ城 丸岡城(福井県坂井市) 越前平定の要となった最古級の現存天守 彦根城(滋賀県彦根市) 琵琶湖を見下ろす彦根山頂にそびえる 姫路城(兵庫県姫路市) 生まれ変わった白亜の連立式天守 備中松山城(岡山県高梁市) 備中国を統治する難攻不落の天空の城 松江城(島根県松江市) 山陰地方唯一の現存天守 往時の姿を再建した名城木造復元天守5 第二章古写真で見る失われた名城 岡山城燦然と金箔瓦が輝く5重6 階の城 松前城松前氏悲願の城 会津若松城瓦解の手前で持ちこたえた城 新発田城 3階櫓の3匹の鯱 大垣城秀吉亡き後の要所 福山城西国の守り家康の従兄弟が築いた城 福井城白亜の城郭建造物 津山城 77棟もの櫓を有する 大洲城最も完成された名城 今治城海水を引き入れる構造 岡崎城/広島城/高島城/尼崎城/萩城 琉球王国グスク物語 第三章覇権をかけて争った両雄と城明智光秀VS豊臣秀吉 築城術から見る二人の才覚 光秀の出発点越前で過ごした十年とは?(一乗谷城) 信長が作らせた琵琶湖の城郭網(坂本城、長浜城) 丹波平定で新拠点とした名城(亀山城、福知山城) 光秀討伐へ秀吉転進(姫路城、備中高松城) 両雄の命運を握った城(安土城、勝龍寺城、山崎城) 厳選グッズ通販男の隠れ家SELECT SHOP 男の隠れ家本誌/大人が観たい美術展告知 奥付 裏表紙
-
-917円 (税込)男の隠れ家「城」シリーズの決定版 目次 日本の名城を往く 過ぎ去りし時に想いを馳せて──。 【巻頭特集】御城印集めでもっと楽しむ、城巡り 御城印のある城を訪ねて 岐阜の名城を巡る 郡上八幡城(郡上八幡市) 岐阜城(岐阜市) 大垣城(大垣市) 御城印のある東美濃の山城(苗木城・美濃金山城・岩村城) 日本の名城 厳選御城印15 第一章 現存十二天守 松本城(長野県松本市) 実戦を見据えた質実剛健なつくり 弘前城(青森県弘前市) 津軽家十二代の歴史を物語る名城 犬山城(愛知県犬山市) 木曽川のほとりで美濃をにらむ城 丸岡城(福井県坂井市) 越前平定の要となった最古級の天守 彦根城(滋賀県彦根市) 琵琶湖を見下ろす彦根山頂にそびえる 姫路城(兵庫県姫路市) 生まれ変わった白亜の連立式天守 丸亀城(香川県丸亀市) 日本一の高さを誇る巨大な石垣と最小天守 高知城(高知県高知市) 堅い防御を誇る南国土佐の名城 松山城(愛媛県松山市) 実践さながらの城構えと比類なき美 宇和島城(愛媛県宇和島市) 海を望みつつ静かに佇む孤高の城 備中松山城(岡山県高梁市) 備中国を統治する難攻不落の天空の城 松江城(島根県松江市) 山陰地方唯一の現存天守 COLUMN 今なお残る、戦国の山城を歩く 知っておきたい! 山城のいろは 縄張り図の読み方 岩村城(岐阜県恵那市) 高取城(奈良県) 金山城(群馬県) 第二章 発掘調査で読み解く三英傑と戦国大名の素顔 徳川家康 × 駿府城(静岡県静岡市) 浜松城(静岡県浜松市) 夢を膨らませた出世城 織田信長 × 小牧山城(愛知県小牧市) 岐阜城(岐阜県岐阜市) 安土城(滋賀県近江八幡市) 豊臣秀吉 × 大坂城(大阪府大阪市) 伏見城(指月城・京都府京都市) 隠居屋敷から本格城郭へ 明智光秀 × 坂本城(滋賀県大津市) 北条早雲 × 小田原城(神奈川県小田原市) 石田三成 × 佐和山城(滋賀県彦根市) 第三章 築城名人が造った城を知る 藤堂高虎 黒田官兵衛 加藤清正 震災から3年 熊本城 復興への歩み 男の隠れ家SELECT SHOP 奥付 裏表紙
-
-815円 (税込)城と城下町が物語る悠久の歴史 目次 日本の名城を巡る 城と城下町が物語る悠久の歴史 【巻頭特集】 熊本城(熊本県) 古地図で読み解く! 熊本城と城下町の秘密 第一章 現存十二天守の城 姫路城(兵庫県) 生まれ変わった白亜の連立式天守 松本城(長野県) 質実剛健な美を有する城 弘前城(青森県) 津軽家十二代の歴史を物語る名城 犬山城(愛知県) 木曽川のほとりで美濃をにらむ城 彦根城(滋賀県) 琵琶湖を見下ろす彦根山頂にそびえる 松江城(島根県) 山陰地方唯 一 の現存天守 COLUMN 1 知っておきたい城の豆知識 高知城(高知県) 堅い防御を誇る南国土佐の名城 松山城(愛媛県) 実践さながらの城構えと比類なき美 丸岡城(福井県) 越前平定の要となった最古級の現存天守 備中松山城(岡山城) 備中国を統治する難攻不落の天空の城 丸亀城(香川県) 日本 一 の高さを誇る巨大な石垣と最小天守 宇和島城(愛媛県) 海を望みつつ静かに佇む孤高の城 COLUMN 2 古地図で楽しむ!ぶらり城下町散歩 第二章 三英傑の城と城下町 天武の才によって新しい国づくりを目指した風雲児 織田信長 岐阜城 岐阜(岐阜県) 安土城 安土(滋賀県) 足軽から天下人へと駆け上がった戦国の英雄 豊臣秀吉 長浜城 長浜(滋賀県) 伏見城 伏見(京都府) 数々の辛苦の末に天下を手中にした大将軍 徳川家康 岡崎城 岡崎(愛知県) 駿府城 静岡(静岡県) COLUMN 3 名古屋城の本丸御殿復元工事 男の隠れ家SELECT SHOP 男の隠れ家 本誌/別冊 告知 時空旅人 告知 奥付 裏表紙
-
4.2※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ▼サエない会社員が、謎の宇宙人に「交渉学」を学ぶ!?▲ 「なんでうまくいかないんだろ……」 「それは、キミの交渉がヘタだからだよ」 サエない会社員、久地米太(くち・べいた)の前に突如あらわれたのは、 交渉で統治された「ネゴ星」からやってきた、アボットとコステロの2人組。 地球人の交渉力を底上げするため、久地くんを鍛えるという。 かくして、異色の「おとしどころ探し」の物語がはじまる……! ▼話をまとめるには、あなたの知らないコツがある▲ ・話が通じない相手との打ち合わせで、時間をムダにしている…… ・会議が平行線をたどって、いつまでも結論が出ない…… ・家族や恋人とのやりとりで、つい感情的になってしまう…… ・業者のいいなりになってしまい、なんだか損をしている気がする…… こういったお悩みはすべて「交渉学」で解決できます。 ▼交渉学・合意形成論の専門家が教える、毎日使える"話し合いの技術"▲ 交渉とは、複数の人間が未来のことがらについて話し合い、協力して行動する取り決めをすることです。 つまり、私たちが毎日行っている話し合いのすべてが交渉にあたるのです。 この本では、交渉のプロである「交渉学・合意形成論」の専門家が、 ポップなイラストとストーリーをまじえて、毎日の交渉に役立つ実用的なメソッドを紹介します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ●本電子書籍は、固定レイアウト型(フィックス型)で作成されております。 ●本書は、同名の紙媒体の出版物(紙書籍版)を底本として作成しているため、内容は、原則、紙書籍版印刷当時のものとなります。 ●ご購入前に必ず、当説明文末尾の【電子書籍版ご購入に際しての注意事項】をご確認ください。 北国で感じる異国情緒 ロマン溢れる夜景、生まれ変わる歴史的建造物 心洗われる坂の上の教会も改修完了 函館は元町周辺、ベイエリア、駅周辺、五稜郭、少し足をのばして大沼、北斗、木古内、松前、江差、津軽は弘前、五所川原、金木、さらには青森、白神山地、巻末では十和田湖・奥入瀬までフォローする「歩く・観る」「買う」「食べる」「泊まる」の最新情報をアップデートした’24-’25年版。 巻頭では「光が紡ぐ物語」と題して幻想的な函館の夜景をプレビュー。函館はモダンな街を縫うようにのびる坂道、豪奢な洋館、異国情緒溢れる教会、箱根山の絶景など元町周辺の紹介が続きます。 また、函館空港のリニューアル、函館ハリストス正教会の改修完了、ホテルのオープンなどをニュースとして取り上げています。 五稜郭は幕末の軌跡とともにスポットを紹介。津軽は多彩な四季の表情が感じられる自然の景観をピックアップ、弘前城を中心とする弘前公園と城下町のさんぽ、岩木山ドライブ。世界遺産・白神山地は世界最大級のブナ林と十二湖をウォーキングするコースを案内します。 青森は青森県立美術館や三内丸山遺跡、奥津軽、奥入瀬渓流までのルートを解説します。 「食べる」は、朝市から寿司の名店、リノベーションカフェ、北のスイーツ、港町の洋食、函館の夜景を楽しめる大人のバーまで。さらに弘前の郷土料理(津軽そば、じゅっぱ汁、けの汁)、青森のご当地グルメ(のっけ丼、塩ラーメン)はもちろん、弘前フレンチ、洋館カフェ、りんごの街のおみやげもご紹介します。 歴史特集は函館をはじめとする道南地域の歴史を、縄文文化の発展から松前藩による統治時代、ロシアとの接近、函館戦争の勃発へと辿り、津軽については城下町・弘前の繁栄、伝統工芸品やねぶた(ねぷた)祭の由来、津軽が生んだ文豪・太宰治、津軽三味線のゆかりの地を案内。 詳細な別冊地図で安心ナビゲート。 トラベルカレンダーで1年を通した気温、降水量、気候、開花情報、イベント開催、旬の食材などが一望。 【電子書籍版ご購入に際しての注意事項】 ●特典がある場合の利用期限は、紙書籍版の利用期限が適用されます。 ●構成および一部の表記について、紙書籍版と異なる場合があります。 ●紙書籍版のような、「別冊があり、取り外して別冊ごとに使用すること」はできません。 ●紙書籍版とは色味が異なる可能性があります。また、フルカラーページや網掛けページがある場合には、モノクロ端末では見づらくなる可能性があります。ご購入前に、必ず、電子書籍版のサンプルにて表示状態をご確認ください。
-
3.6
-
4.0珪素生物と彼らの「円卓政府」が統治する地上で「運び屋」をしている人間リュウは、ある夜、騒動に巻き込まれる。荷物の届け先だったはずの相手は殺され、リュウ自身も謎の敵に襲撃され、おまけに運んでいた荷物から出て来たのは、珪素生物の少女――!? 「ほら私おとーさんの娘で、相棒で、将来的にはお嫁さんでしょっ?」「娘ではないし、お父さんでは断じてない。そして、そんなろくでもない将来の計画を立てた覚えもない!」「これから立てさせてみせるもん!」 なぜか自分のことをを父親呼ばわりし、懐いてくる少女ルーに困惑するリュウ。奇妙な同居生活が始まるが――? 第3回GA文庫大賞奨励賞受賞作登場! ※電子版は文庫版と一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください
-
-食べたい“お肉”が食べられる ししじょーぐー待望の一冊! 琉球料理に深く根ざした豚肉や米軍統治下のAサインステーキ、お祝いに欠かせないヤギ肉にチキン、ブランド肉も続々登場し、沖縄の食肉文化は多彩に進化。ししじょーぐー(お肉大好き)の胃袋をがっつり満足させる充実の一冊!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1930年日本統治下の台湾でおきたタイヤル族の蜂起を追う。このときオビン・タダオは17歳、父親は殺され、夫は自殺。妊娠中のオビンは、夫の言葉に従い生き延びる。
-
3.3総面積は地球の5000倍にもおよぶ巨大惑星オマル。そこではヒト族、シレ族、ホドキン族の3種族が暮らしていた。何世紀にもおよぶ壮絶な抗争の末、65年前に結ばれたロプラッド和平条約により、いまはかろうじて平和が保たれていた。そんな3種族共同統治区プラットフォームジャンクションの大港に停泊中の巨大飛行帆船イャルテル号をめざし、今、種族も年齢も出自もまったく異なる6名の男女が向かっていた。彼らが手にするのは謎めいた卵の殻と22年も前に購入された乗船券(チケツト)。彼らの目的は? そしてイャルテル号の行く手には? フランス有数のSF賞、ロニー兄賞受賞に輝く壮大なSF叙事詩!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 東南アジアにおいて経済の中心として存在感のあるシンガポールとコロニアルな街並みが残るマレーシア。近接している両国は、もとは同じ国でした。マレー系、中国系、インド系、イスラム系の文化が混在しながら、近未来的な建物が建ち並ぶ都市を持ち、ヨーロッパによる統治の面影を残すなど共通点が多くあります。 本書ではシンガポールとマレーシアの基本情報、観光地、スマホユーザーが海外でスマホを使用するために役立つ内容をご紹介しています。その他、お得なレンタルWi-FiのグローバルWi-Fi情報、Wi-Fiで通信速度のストレスなくスマホとタブレットの両方を使う方法、海外でのスマホ利用での高額請求回避について、海外旅行に役立つアプリなどの情報も掲載! スマホユーザー必読の一冊です!
-
1.0急発展を遂げるアジアの新興国・シンガポールとマレーシア。近接している両国は、マレー系、中国系、インド系、イスラム系の文化が混在しながら、近未来的な建物が建ち並ぶ都市を持ち、ヨーロッパによる統治の面影を残す、など共通点が多いですが、やはりそれぞれ異なった趣があります。 その違いは街を歩けば一目瞭然! 東京のような高層ビル街にビジネスマン……というシンガポールに対し、マレーシアは街中にモスクが点在し、イスラムの衣装を身に纏った女性をみかけることも多いでしょう。時間とお金に余裕があれば、ぜひ同時期に訪れてみたいものです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 急発展を遂げるアジアの新興国・シンガポールとマレーシア。近接している両国は、マレー系、中国系、インド系、イスラム系の文化が混在しながら、近未来的な建物が建ち並ぶ都市を持ち、ヨーロッパによる統治の面影を残す、など共通点が多いですが、やはりそれぞれ異なった趣があります。 その違いは街を歩けば一目瞭然! 東京のような高層ビル街にビジネスマン……というシンガポールに対し、マレーシアは街中にモスクが点在し、イスラムの衣装を身に纏った女性をみかけることも多いでしょう。時間とお金に余裕があれば、ぜひ同時期に訪れてみたいものです。 本書では、生活必需品であるスマホを、お得に、日本にいるときと同じように海外でも使える裏技を掲載しました。 そちらもお楽しみに!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 会社を始めとする多くの組織で発生する様々な不正が、毎日のように新聞やテレビで報じられています。 不正をはたらく動機もしくは不正をはたらかなければならないほどのプレッシャーがあり、不正をはたらいても発見されにくい組織体制であり、かつ不正をはたらいても許されるはずだと考えられる素地が組織内にある場合に不正は起きやすいと言われます。 不正には様々なものがありますが、①資産の流用、②不正な報告、③汚職の3 つに類型化した場合、①資産の流用が8 割を超えるといわれます。 資産の流用は、いかなる理由があるにせよ、流用をはたらいた本人はもとより、組織、組織の従業員、社会に損失をもたらします。 資産の流用により、組織は財務的な損失を被るし、従業員が流用をはたらいたことの報道等による組織のイメージダウンによって業績の低迷を招きかねません。 流用をはたらいた従業員が所属する組織の他の従業員は、組織が財務的損失を被ったことにより昇給や賞与の面て抑制を強いられ、世評の悪化により肩身の狭い思いをします。 社会も無縁ではありません。国民の相互信頼の度合いが低下し、組織の新たな統治体制の構築などの社会的費用を負担しなければならない恐れがあります。 本書は資産の流用の事例を取り上げ、それが組織の経営、特に財務面に与える影響を会計思考で見える化したものです。同時にその背景を探り、再発防止の仕組みを提案しています。 本書では資産の流用を、窃盗・横領、不正使用、経費の水増し、不正な財務報告の4 つのカテゴリーに分類しています。不正な財務報告は直接的に資産を流用するものではありませんが、自分の報酬や地位、待遇などを維持するために行うものであり、間接的に資産の流出に結び付くと思われることから、1 つのカテゴリーとしました。 本書が、管理職の皆様方が資産の流用の事例と影響を知り、その再発防止の仕組み作りに必要な知識を習得するきっかけになれば幸いです。
-
-
-
3.0
-
-海賊党という「あやしい政党」が21世紀のヨーロッパを徘徊している! これは、かつて海上で船を襲って金品を強奪していた直接的な意味における海賊ではなく、海外や自国の書籍・DVD・CD等を無断でコピーする場合の比喩的表現である「海賊版」という言葉にちなんで名づけられた。スウェーデンが発祥の地で、現在ドイツ各地で猛威をふるっていると聞けば、北欧ゲルマンの神話やヴァイキング、ハンザ同盟の歴史も連想されるだろう。逆説的パロディーで「ふざけた名前」を党名に掲げているわけだが、反社会的な海賊行為を推奨している政党ではない。むしろこれまで自明とされてきた著作権や知的所有権の本質を問い、ACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)に反旗を翻し、デジタル時代の現状に即した見直しを要求している。本書は、個人使用のダウンロードの合法化&特許システム廃止という主張や液体民主主義という制度設計など、海賊党が提唱する新しい統治(透明性あるガバナンス)のあり方について紹介した日本初の概説書。津田大介氏推薦! 海賊党の思想が実装された、ウェブで政治を動かすヨーロッパの方法論をレポート。ネット選挙解禁に際しての基礎知識。
-
5.0戦前日本の海外鉄道を徹底ガイドした名著が新版で復活! 時空を超えた鉄道の旅にようこそ 第41回 交通図書賞 奨励賞受賞作の改訂新版! 巻頭に伝説の超特急「あじあ」の最新写真収録! *当時統治下にあった「台湾」「朝鮮」「関東州」「樺太」「南洋諸島」そして「満洲」に日本が敷設した外地の鉄道を詳細に解説。 *当時の時刻表や観光案内、膨大な文献を駆使し、運賃や旅客の取り扱い、内地からのアクセス、豪華列車の案内などを展開した、戦前版『地球の歩き方』的書籍。 *旧版では2頁だったカラー口絵を大幅増の16頁とし、貴重な写真を多数(62点)掲載。 *新たに入手した当時の写真や絵はがき、パンフレット、使用済み乗車券や駅の記念スタンプなどの稀少資料の掲載を、旧版より大幅追加。 もともと旅行ガイドブックとは、歳月を経て版が改まるたびに情報が少しずつ更新され、写真や地図が充実していく発展途上型の読み物とも言える。今回、初めて本書を手に取ってくださった方も、旧版をお読みいただいた方も、大幅に増やした新掲載の写真や資料、そしてところどころ更新した本文を通して、時空を超えた東アジアの空想鉄道旅行による新しい景色を楽しんでいただければ幸いである。……「改訂新版の刊行にあたって」より
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。


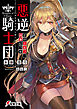
































![犬鳴村 [小説版]](https://res.booklive.jp/692721/001/thumbnail/S.jpg)
































































